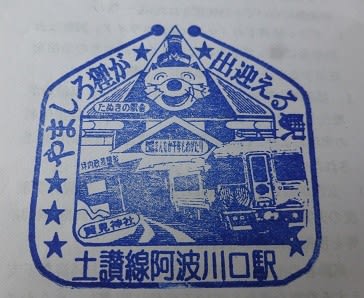岡山県瀬戸内市牛窓町は、”日本のエーゲ海”と称し観光業によって町の活性化を図っている岡山県東部にある町です。この町は古くから内海航路の風待ち、潮待ちの港として知られており、江戸時代には将軍の代替わりに来日し、江戸に向かった朝鮮通信使の寄港地としても知られていました。写真は、朝鮮通信使の資料を展示している海遊文化館と、朝鮮通信使が4度宿泊した本蓮寺です。前回は、海遊文化館でいただいた「しおまち唐琴通り散策まっぷ(以下「マップ」)」を手に、岡山藩が整備した、岡山城下町と牛窓をつなぐ牛窓往来(唐琴通り)を、本蓮寺から関町まで歩いて来ました。

マップの左上から町並みの間を抜ける、緑で示された通りが唐琴通りです。前回は、4つ目のオレンジ印の右(東)のミニ広場のあたりまで歩き、石段を上って菅原道真を祀る「天神社」まで行ってきました。

マップに「関町ミニ公園」と書かれている広場です。道端に、牛窓往来の往来の説明板が白く見えています。

その手前にあった「フードショップ ナカニワヤ」のお店の脇を右折して進みます。

港の手前に乗車してきた東備バスの終点、牛窓バス停がありました。右側には、「仕出し料理寿司 寿司勝」のお店がありました。通りがかった人は「ここは以前3階建てだったよ」と、相手の方に話しておられました。

海岸沿いの道を右折して、海遊文化館方面に向かって引き返します。前島フェリーの”第七からこと”が入港するところでした。フェリーは、目の前にある前島と牛窓とを結び、1日20便が運行されています。

フェリー乗り場にあった観光センター「せとうちキラリ館」です。観光案内とおみやげの販売も行っています。

唐琴通りに戻ります。「関町だんじり」の収納庫の向こうに「写真のマサモト」のお店。その先に和風の建物が見えました。丘の上の白い建物は「あいの光病院・牛窓」ですが、以前はここに牛窓東小学校があったそうです。

和風の豪壮なお宅は”牛窓・備中屋・高祖の酒「千寿」”のブランドで知られる高祖酒造の発祥の地です。天保元年(1830)年創業。木造2階建て本瓦葺きの主屋は、正面1階は出格子で、2階はなまこ壁と黒漆喰でつくられており、明治25(1892)年頃に改装されたそうです。裏には赤煉瓦の煙突と白壁の土蔵が残っています。高祖酒造は、現在は瀬戸内市牛窓支所の前に移転して、醸造を続けておられます。

裏に回りました。かつては板塀で敷地を囲んでいたそうですが、現在は取り壊されていました。赤レンガで、長い面と短い面を交互に積んでいくイギリス積みの煙突は、昭和7(1932)年頃につくられたといわれています。基底部は1.2m、高さは15mあるそうです。見えにくいのですが、東面と西面には「千壽」の文字も残っています。”牛窓港の赤煙突”として親しまれてきました。主屋や煙突、蔵座敷、井戸洗い場は、平成19(2007)年、国の登録有形文化財に登録されています。

高祖酒造の前からあいの光病院・牛窓に向かう通りがあります。その脇に、白壁の建物と屋根のついた井戸がありました。白い建物は下見板張りの壁が白く塗られています。「関町だんじり」の収蔵庫の並びにあった「写真のマサモト」の以前のお店だそうです。明治20(1887)年、初代の正本平吉氏創業のお店です。

高祖酒造の建物の向かいにあった「学校の井戸」です。気候温暖で雨も少なく、大きな河川もなかった牛窓では、昭和34(1959)年に上水道が完成するまで、各所に共同井戸がつくられ活用されていました。この井戸は、昭和43(1968)年までこの丘の上にあった牛窓東小学校も使用していたため、このような名前がついたといわれています。

関町ミニ公園に戻りました。唐琴通りを東に向かって歩きます。

高祖鮮魚店、割烹旅館川源の裏を過ぎると左側に空き地があり、通りの脇に「中屋発祥の地」「高祖保生誕地」の石碑がありました。中屋という屋号の高祖家があったところで、戦後は洋品店を営んでいたそうです。戦前、詩人として活躍した高祖保は、ここで生まれました。そして、8歳のときに父金次郎が亡くなったため、母の実家のある彦根に移り、18歳までを彦根で過ごしました。その後、詩人として活躍していましたが、昭和19(1944)年、陸軍中尉として応召され、翌年34歳のとき、ミャンマーで戦死しました。今は閉館していますが、高祖保の資料を集めた「私設手づくりミニ資料館 なかなか庵」があり、彼を慕う人たちが訪れていたそうです。

その先の左側に、伏見稲荷を連想させる、小さな鳥居の並ぶ参道がありました。その先に拝殿と銅板葺きの本殿がありました。最一(さいいち)稲荷神社です。マップには「『由来記』によれば、明治4(1871)年、北側の山にいた老狐がここで天寿を迎えました。霊狐は神のように人の願いをかなえるようになり、明治7(1874)年京都伏見稲荷から神璽(しんじ)を賜った」といわれています。残念ながら「近日、撤去予定」と、マップに書かれていました。

西町を歩いています。左側に、地元西町の保存会の人々によってつくらえた「金刀比羅宮・荒神社」の道標がありました。

牛窓は神社・仏閣は山の上に建てられているようです。金刀比羅宮の境内に来ました。正面の海には、元禄8(1695)年、岡山藩主池田綱政が津田永忠に命じてつくらせたまっすぐな波止め、「一文字波止」が見えました。岡山藩の新田開発や土木事業に大きな功績を挙げた津田永忠は、近くの犬島から運んだ花崗岩を使って、10ヶ月という短期間に完成させた、堅牢な波止でした。この完成によって、牛窓は北前船の寄港地になるなど、物資の集散地として発展していくことになりました。

こちらは、東方向です。遠くの甍は、妙福寺(東寺)の観音院。目の前には、ドイツ製のレンガが鮮やかな「街角ミュゼ牛窓文化館」(以下「街角ミュゼ」)が見えました。

唐琴通りに降りてきました。さらに歩きます。すぐに、街角ミュゼが見えてきました。この建物は、大正4(1915)年、旧牛窓銀行本店として、建設されました。牛窓銀行は、地元の豪商の人たちが、明治10(1877)年、貯蓄と利殖のために、株式会社集成社を結成したことに始まります。明治16(1883)年から金融業を始め、明治26(1893)年に、銀行条例に準じて「牛窓銀行」と改称しました。

本店を建設してからは、金融合併を繰り返し、昭和5(1930)年、中国銀行牛窓支店になりました。その後、昭和55(1980)年に中国銀行は新店舗に移ることになり、牛窓町に寄贈されることになりました。そして、平成9(1997)年、現在の街角ミュゼ牛窓文化館になりました。また、同年、国の登録有形文化財に登録されました。牛窓町で最初の登録でした。

内部です。吹き抜けになっており、白い漆喰で仕上げられています。上の窓を開閉するためにキャットウオークもつくられています。現在は牛窓の歴史や文化を伝える展示場として使われています。

町角ミュゼの手前の道に「御茶屋井戸」(マップには「通信使ゆかりの井戸」と書かれています)への案内板がありました。行ってみることにしました。

御茶屋井戸です。近くにあった「井戸枠」には、「御茶屋で通信使を迎えるために、承応3(1654)年6月、岡山藩によって掘られた井戸」と書かれているそうです。井戸枠はこれまで何回か取り替えられており、現在の井戸枠は、明治10(1877)年に取り替えられたものだといわれています。残念ながら、私には井戸枠の文字を読むことはできませんでした。

朝鮮通信使の宿泊などの接待のためにつくられた御茶屋は、寛文9(1669)年に岡山藩主の別邸があったところに接待所を増築して整備されたそうです。マップを見ると、御茶屋は、街角ミュゼの向かい側、今はレストランになっている長屋門のあるお宅のあることろにあったようです。

海側から見た御茶屋跡の光景です。広々とした敷地に、御茶屋がつくられていたことがわかります。

御茶屋跡から見た港のようすです。マップには、海に突き出した突堤の付け根のあたりに、港を管理する岡山藩の「港在番所」があり、その先には、そこに仕えていた人たちの「足軽屋敷跡」があったと書かれていました。

さらに進みます。通りには、かつての雰囲気を残す景色が残っています。右側のお宅は、木崎商店です。前回、関町の旧牛窓町役場の跡地付近に、「和洋船舶用品店 木崎商店」という宣伝広告があったのを思い出しました。今は、閉店されているようです。通りの右側は、足軽屋敷が並んでいたところのようです。

その向かいにある空き地には、かつてバスターミナルがありました。大正7(1918)年に、牛窓・尾張間と牛窓・西大寺間で乗り合いバスの運行が始まったとき、ここがバスターミナルになっていました。「5、6人乗りの乗合バスが2~3台、ここに発着していた」と、当時を知る人のお話が紹介されていました。乗合バスの会社は大正15(1926)年に邑久自動車と改称され、昭和30(1955)年に両備バスに併合されたそうです。その先に海が見えるようになりました。

マップに、「番所跡」と書かれた広場に着きました。正面に灯籠堂が見えました。灯籠堂の手前には「恵比須宮・竜王宮」が、左側の石段の先には、航海の神として尊崇されている五香宮が祀られています。

五香宮の境内から見た灯籠堂です。江戸時代の延宝(1673~1681)年間、航行する船舶が増えてきたのに対応するため、、岡山藩主池田綱政が夜間の航行の目印(灯台)として設置しました。出崎の突端の岩盤の上に、割石積みの基壇を築き、その上に木製の灯籠台を建てていました。明治になって取り壊されていましたが、昭和63(1988)年に復元されたそうです。基壇の下部は東西、南北ともに4.9m。上部は東西、南北ともに4.3m、高さは2.2m。岡山藩がこのとき建設した4ヶ所の灯籠台のうち、完全に残っているのはここと大漂(大多府)の2ヶ所だけだといわれています。灯籠堂の向こうは前島です。

五香宮の境内から見た東町の光景です。牛窓は、木造船をつくる船大工の人々が多数居住していたところです。そのため、船材を扱う木材問屋で財を成した商人も多かったといわれています。その町をめざして歩きます。

灯籠堂の基壇にあった「これより造船の町 東町」の案内にしたがって、さらに海岸沿いの通りを進みます。

通りの右側にあった建物です。入口の上にある白い看板には「岡本造船」と書かれていました。このあたりは東町字新町です。「文政(1818~1829)年間には、船大工頭の平兵衛という人がおり、その配下には150名の船大工と300人を超す木挽きがいました。岡山藩主から五香宮付近の東町字新町に屋敷地を賜り名字帯刀も許されており、灯籠堂の管理も任されていた」(「牛窓みなと文化」による)そうです。

通りの左側の空き地の上に、妙福寺の観音院が見えました。創建は天平勝宝(749~756)年間。現在の建物は、鬼瓦の銘から、江戸時代の延享3(1746)年に再建されたものだといわれています。入母屋造りの本瓦葺きで、江戸時代中期の密教寺院の本堂の様式を残している建物だそうです。左側には五香宮があるはずです。

東町に近づいてきました。たくさんの船が停泊しています。その向こうに草木造船の工場が見えます。

海岸沿いの通りが、左右の通りにぶつかります。そこにあった道標です。右折して東町に入ります。造船の町である東町は、江戸時代の前期に開発された町で、寛文11(1671)年頃から、東に広がった町に材木問屋や棟大工の人たちが集まってできた町だそうです。

通りの右側の海岸沿いの空き地には多くの船舶が並んでいます。造船の町らしい光景が続きます。

通りの左側に食事処「潮菜」の入口がありました。ギャラリーで雑貨などを見ながら食事を楽しむお店だそうです。ここから東に向かって、広大な敷地の邸宅がありました。若葉屋の東服部邸です。文政元(1818)年、梶屋の木材部門が分家してできた店でしたが、材木問屋として発展しました。また、名主をつとめるなど、この地で大きな影響力を持っていた商家でした。

明治時代になると、「牛窓は、阪神地方に近いという地の利を活かし、港湾の艀(はしけ)を大量に受注するようになり、造船業が発展して行きました。それに伴って、牛窓では材木商が造船業に進出し大規模な造船所を設立するようになりました。若葉屋は、大正6(1917)年東服部合資会社を設立し、造船部(後に牛窓造船所になる)をつくり、機帆船時代の造船業界をリード」(「牛窓みなと文化」)していたそうです。

写真は、若葉屋の土蔵です。現在の東服部邸は、明治43(1910)年から15年をかけて完成させたもので、750坪の敷地に茶屋、裏屋敷、土蔵などが配置されているそうです。
二回に分けて、朝鮮通信使の寄港地、瀬戸内市牛窓町を「しおまち 唐琴通り 散策まっぷ」を手に歩いてきました。
朝鮮通信使が宿泊した本蓮寺、牛窓の赤煙突が残る高祖酒造の発祥の地、旧牛窓銀行に始まる街角ミュゼ、岡山藩が築いた灯籠堂、そして、若葉屋の邸宅など、牛窓の豊かな歴史を伝えているたくさんの文化遺産が残る美しい町でした。