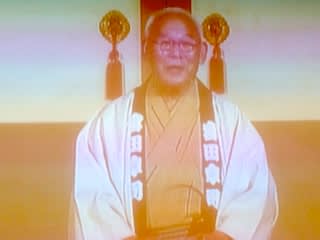およそそう呼べる代物かは別にして、小説らしきものを書いている
書くようになって変わったことといえば、読書への主体的な取り組みだったり、論理性、倫理性への追求だったり、知らずプロットの構築を巡らしたりするようになったことか。この作者はこれをどのように取材をしたのか、参考文献の選び方、研鑽の先にたどり着いたモノへの嫉妬だったりいろんなものを抱える病にかかったとも云える。
圧倒されるそれらにいつまでも臆しては書けやしないし、そんな程度のものでしかないのなら、 そもそも筆を持つ必要もないのだ。
師と仰ぐ小説家も、かつてカミュやサルトルをまえに、己の書くべき余地などもう残されていないのではないかと自問、葛藤していた。物書きのみならず、クリエーターとはそうしたものを大なり小なり感じて通過するものなのかもしれない。
こと知見に関して云えば、 遅れを取ったものは先人の知識に一度は呆然を憶えるはずだ。だが、小説とは一筋縄にはいかず、その圧倒的な知識をそのまま転写したような文章に、反吐を憶える瞬間も訪れる。如何にはやる気持ちを抑えられるか、ひけらかしと見られたらこれほどの恥辱はない。物書きとしての資質に関わることなのだ。並べた小説群には本物と偽物がある。いまこの段階でそれを愉しみ、眺め、見極めている。
西加奈子の[舞台]を読んだ。
太宰の人間失格になぞらえる冒頭は挑戦的だが陳腐に思えた。だが、私小説に通ずるような自己憐憫、自意識への嫌悪の描写に知らずハマっていった。舞台はニューヨークとはいえ、じつに狭いブロックの中で起こる出来事を淡々と綴っただけ。ラストに向けて疾走をはじめる主人公葉太の憤悶、そして解放感は圧巻だった。人を描く。読後至極考えさせられる。久しぶりに、純粋に読むことを愉しめた一冊だ。
「自意識や梅雨の干ぬ間に汗かけり」哲露





先日、物書きの先輩ふたりと飲んだ。
生肉を喰らい、マッコリを飲み、創作の辛みを味わう。
忌憚のない遠慮で、言いたいことを言い合った。常に眼前にある小説をネタに、愉しい時間があっという間に過ぎる。
ロックで飲む韓国と石垣島の原酒は、理性を飛び越え、本能を呼び覚ます。
心地よい時間。けだし、祭りの後は、自意識への過敏な瞬間でもある。
作家などというもの、元々自意識の塊なのだ。文章に紡ぐその自意識で満足しろ。実生活においての自意識を極度に畏れる。西加奈子、おそるべし。
地元民に配られる台東区の区報。
享保に始まり、昭和に復活した両国の花火。
昨年は天候の急変に中止を余儀なくされた。
今年も7月26日(土)に開催予定。
不穏な空気を吹き飛ばす、江戸の大輪を今年こそ観たいものである