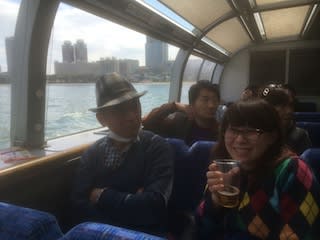【カフェ・デ・キリコ】
佐藤まどか 著 中島梨絵 画
2013年4月25日第一刷 講談社刊
古い石畳、赤錆びた鍵穴、高い天井、日の差すバルコニー、ツタの絡まる建物
公証人の末裔の家、堅牢な門を風が抜ける。
重厚な歴史を積んだミラノのもう一つの顔は大都市の慌ただしさ。
時間に追われるミラネーゼに、カフェは必須なのだ。
ジーンズ姿、ショートカットの似合う霧子は母と二人、父の故郷のミラノに降り立つ。
日本人の母と相容れない祖父から、勘当された父を亡くしたばかり。この地この家で母と再出発する。

「カフェすすり苦いと笑い更衣(ころもがえ)」哲露
隣人であり良家のアンドレア、ダヴィデに助けられながら少しずつ町にとけ込む霧子。
蜘蛛の巣だらけの空間を、居心地の良いカフェに生まれ変わらせる。
母に対する複雑な感情を抑えながら。
母のインテリアセンスは抜群で、そこに霧子の思いつきと工夫が物語に色を添える。
日本語に渇望する環境だから、母に話しかけてしまうという部分は異国で暮らす作者の人間観察の賜物だろう。

異国での再生、編入先の学校のこと、気になる金髪の男の子、材料は揃いすぎているがゆえ、これらを一作にまとめるのは容易ではない。
坂の町の彩り、クラシックの調べ、ミラノの季節感、カプチーノの香り、一癖も二癖のあるミラネーゼ、国や出生の異なる人々と、作者はじつに丁寧に、飽きさせることなく描写していく。
まるで紙上ギャラリーのように。
不安と期待、一途で真摯な霧子の言葉が全篇を心地よく締めてくれる。
年老いた常連たちはアンティークの椅子で居眠りし、木のテーブルで執筆し、カノーヴァのパンナコッタやダヴィンチのクッキーで癒されていく。 

日本人特有の気持ちを察して寄り添う安心感も大切だと思う。
だが、ときに泣いたり、思いの丈をぶつけ合うことなくして、関係は修復しないし深まらない。みんな生身なのだから。霧子の家族と、隣人のバジリコ家にそれを教わった。
本郷のカフェで、まどかさんが話していた異国でのエピソードも、この本にあった。
読みはじめを机に置いてランチを作っていたら、滅多に単行本を手にしない次男が熱中している。
おかげで一日遅れの読書になった。
霧子の苗字が、デ・キリコで、キリコ・デ・キリコ。
作者はイタリア在住でお父さんの知人だよ、と言ったら息子たちにびっくりされた。
はじめて読んだまどかさんの本。
初夏の気候にぴったりの瑞々しさ、肌の色や性格の違い、思春期の多感、宗教、階級、様々な題材のグラデーションが、ラテンの哲学と爽快を運んでくれた。
ヒトの内面の吐露、ひとつ一つの丁寧な描写の大切さ、擬音の使い途など、まどかさん、たくさんいただきました。
ああ、ドゥオーモのある町へ旅に出たくなっちまった