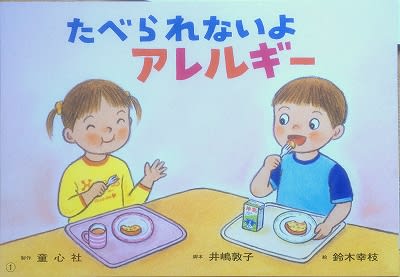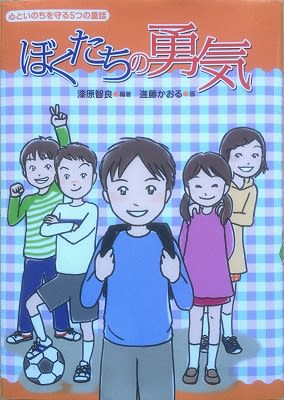森川別館鳳明館
澄み渡る碧さも眩しい秋の週末
今年も本郷の台地に仲間が集まった。
緑に覆われた門をくぐった。
水を打たれた石畳に気が引き締まる。
同人誌季節風の泊りがけの合宿がはじまる。
大広間の総会、ぼんやりと聴いていた。
あさのあつこ代表が立ちあがる。
地下に響く、凛と発した言葉が、私を現実に引き戻す。
そうだ、漠然と生きるのではなく、何を成すかがもっとも大切なのだ。
私は【愛の物語分科会】に参加。
昨年に続いて、越水利江子、土山優両師匠にお世話になる。
参加者は12名。創作10篇、評論1篇。
ひと月かけて読み込んだ生原稿を元に、一筋縄でいかない御仁たちがあーだこーだ。
どの言葉も作品をよりよくするための真摯な助言に満ちている。
私と小西大兄の作品は初日に終える。
それぞれに抱える思いを癒すため、日の落ちた本郷の町に出た。
おでん「呑喜」
言問通りを渡った先に、老舗のおでん屋がある。
その名も「呑喜」。
明治20年の創業だという。
なんと。。
店に入るとラッキーなことにカウンターが空いていた。
横には東大生と思しき若者たちが味の滲みた芋を頬張っていた。
大振りのそれは、カラメル色に染まっている。
東京でも珍しくなった醤油たっぷりの関東炊きだ。
私はツミレ、筋、ガンモ、はんぺんなど頼み、サッポロラガーをぐびり。
緊張感の張りつめた合評で強張った肩が、解されていく。
【呑気にもぬる燗飲みつ筆は持ち】哲露
燗酒に切り替え、今日を振り返る。
年輪を重ねた琥珀は、何千、何万の呑んべの肘を支えてきたカウンター。
辛口がしみる夜。
大根が煮えるにはまだ時間がかかるとのこと。
残念だ。
代わりに頼んだお新香が素朴でいい。
東大のおひざ元、歴代の首相経験者やら各界の大物が通った暖簾。
同人と杯を交わすため、早々に店を出た。
20代に憶えたMac。「日曜日のiMac」の著者、山川健一さん親子が飛び入りの参加。
脱原発の急先鋒で、名うてのロッカーであり、プロデューサーであり、プロフェッサーであり、書き手である。越水師匠に紹介してもらう。
若き日の憧れの方と話せて、思わぬ収穫だ。
山川さんとお嬢様で若き作家でもある山川沙登美さんはその場で同人に入会されたとか。なんとも不思議なご縁である。
そして、毎年、天水を差し入れてくださる奇特な先輩ご夫婦。
磨きに磨いた天の酒精は、微かな色をまとい、米粒の深みを残している。この珠玉は、この地下でしか飲めない。
フレッシュな果実をそのまま含んだようなモノ、湖の底に沈殿させた宝石のようなモノ、ワインの名品もいくつか飲ませていただく。
同部屋の高田さんからも佐渡、新潟の地酒を振る舞われる。そして、櫻井さんからも。
なんという贅沢。
グラスや茶碗に満たされた、虚栄と慢心、率直と反省、宣誓と失望。
交わす言葉の鋭さと重みこそ、現代の寺子屋。
安酒に慣れた内臓の襞が各地の銘酒に洗われ、 勇み尖った気持ちを溶かしていく。
ただ、呑気に飲んでるわけじゃない。
はしゃいだ宴は2時まで。タハッ。
井嶋さん、今年も御馳走さま。
高田さん、櫻井さん、呑んべに名水をありがとう。
二日間に渡る、合評を終えた。
バブル全盛のゴールデン街に迷い込んだような濃密な気配が充満した小部屋。
推薦作は、越智さんの「キタキバシリ」に決まった。越水師匠の的確を胸に、きっと名作が完成することだろう。
発表した安田さんがひとこと、
「疲れた!」
場内がどっと湧いた。
だが、みんな知っている。この疲労はただの虚脱ではないと。
薄い木枠の窓ガラス、そろりと歩くと軋む廊下、清潔な洗面所、紅い座布団、染みのついたフスマ、窓からみえる洗濯物、赤門に佇む学生たち、陽に輝く銀杏並木。
どれもが私の秋の風物詩となった。
こうして文字を書いていることがかぎりなく幸せだ。
あれも書きたい、これも書きたい。
私を推してくださったありがたい同人たちに感謝。
今日の一票が背中を押してくれる。
脱力のなかに僅かに芽生えた光の粒が、やがて誰かを燈す日が来ますように
追記
近江屋さん、大会委員長という大役はホンマ大変やったと思う。本当にお疲れさま。
幹事会、関係者、同人の皆様、今年も何かをいただきました。どうもありがとうございました。
【お知らせ】

11月15日(土)、子どもたちのことを考える、フォーラムが開催される。
詳しくは、 http://www.jpic.or.jp/event/jpic/2014/10/09161959.html へ。