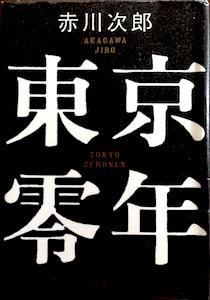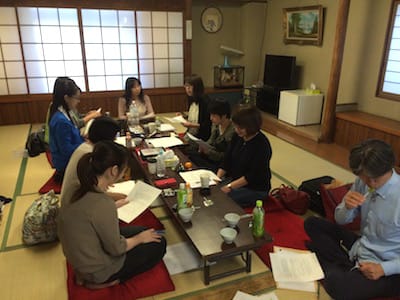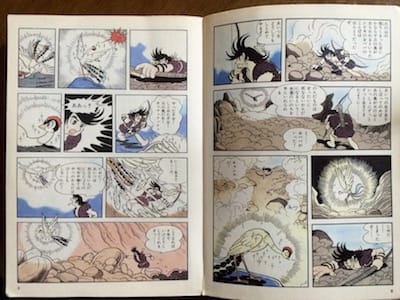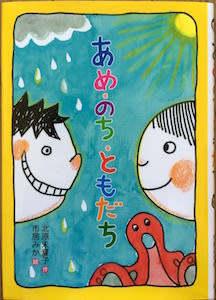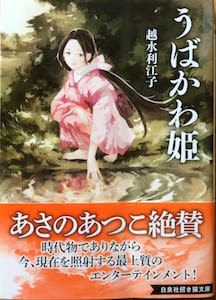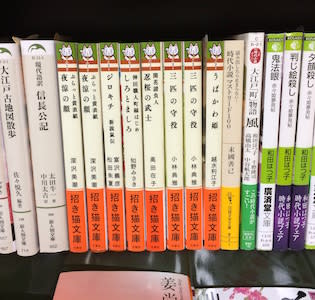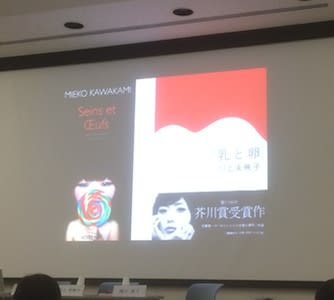【車夫】
著:いとうみく
冒頭の一文から本の世界へ引きずり込まれた。
ミュールの靴擦れに悪態つく女の子の独白が生々しい。
どうやらその原因が父親の再婚問題に絡んでいるらしいと判る。
その父親と再婚相手を一緒に追っかけてくれたのが車夫の吉瀬走だ。
浅草の町に人力車が復活したのはいつの頃だったろう。
あの頃、ローカルは人力車なんて流行らないと決めつけていたように思う。

【紫陽花や笑顔が滑る足袋の音】哲露
いまでは六区の町の灯が消えかけたのが嘘のように、観光地として息を吹き返した。
それと呼応するように勢力を増した人力車。
住人として今では当たり前の風景だが、それを動かすのは生身の人間の力だ。
そして観光客を口説き、乗せるのが商売だから、
見てくれ、風采がいいに越したことはない。
まさに体育会系の若者にはうってつけの職だろう。
陸上出身の主人公とはよく思いついたものだ。
人力車が行き交う辻の風景や描写、町の空気感。
作者は実際、よくよく取材されてのことに違いない。
「この仕事をはじめてから、季節の変化に敏感になった気がする。」
お気に入りの一文だ。
欲を言えば、喰い物のシーンにシズル感と香り立つ匂いがもっとあればと思った。
野暮かもしれないが、一読者として、
ここを削ったらもっと余韻が残るのにと残念に思ったとこは内緒で伝えたい。
過酷な運命に翻弄され、ストイックでニヒルになった主人公が、
浅草の町人と共生することで、この町を訪れる人と触れ合うことで自然と明るく再生していく。
予定調和の結論を急がない運びがいい。
もっとこの先を読んでみたいと思った。
仕事の合間に本を開きながら、神保町の老舗で元祖冷やし中華を食う。
くらげも椎茸もたっぷりとさっぱりと酸味の効いたタレが沁みている。
胡瓜はあくまで潔い食感で、老舗の焼き豚とハムは口に含むと柔らかく滋味深い。
頬が緩むほど肉肉しいシュウマイを噛み、冷えた麦酒で流し込んだ。

揚子江飯店の冷やし中華は、おいらの中でいちばんの味。
車夫はいとう作品でいちばん気に入った本。
一度、人力車に乗ってみたくなった。
いとうさん、続編はいつ!?