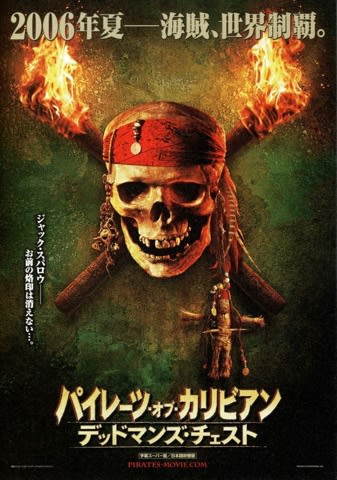◼️「フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊/The French Dispatch」(2021年・アメリカ)
監督=ウェス・アンダーソン
主演=ビル・マーレイ ベネチオ・デル・トロ エイドリアン・ブロディ フランシス・マクドーマンド レア・セドゥ
(注意・嫌いな理由を散々書いてます)
ウェス・アンダーソン監督作がどうも好きになれない。初めて観た「ロイヤル・テネンバウムス」は楽しめた。世間がオシャレ映画とキャーキャー言ってるグランドなんちゃらも、ちゃんと映画館で観た。申し訳ないけど、好かん。キャスティング以外の好きなところを挙げる自信がないので、グランドなんちゃらはレビューを放棄している。色彩と独特な構図でなーんかごまかされたような気持ちになったのだ。個人の感想です。ファンの皆さま、ごめんなさい。
「フレンチ・ディスパッチ…(以下略)」は、活字文化に対するリスペクトあふれる作品と聞いて、文系男子としてちょっと心惹かれた。監督と相性悪い気がするけど、この題材ならイケるかも。かなり期待していた。
映画冒頭、この雑誌「フレンチ・ディスパッチ」が出版業界でどんな位置付けのものか、現在に至る沿革が早口で語られる。編集長が急死したことで、現在編集中のものが最終号となる。掲載される4つの記事をコミカルに描くオムニバス形式だ。
雑誌「ニューヨーカー」からインスパイアされたと聞く。確かに洗練されたハイセンスな雑誌のコラムや記事を読んでるような"外観"(ここ大事ね)で出来あがっている。各エピソードの最初に映し出されるイラスト、ちょっと好き。最初は街を走ってリポートする「自転車レポート」。ところどころに寒いギャグを挟みつつ、淡々と街の様子が描かれる。
続く「確固たる(コンクリートの)名作」では、刑務所に収監されている男が描いた前衛芸術の秘話。鉄格子が映り込む映像だけに、ウェス・アンダーソン監督が好きな縦と横の線、正面から顔を見据えるショットが冴え渡る。というか、この監督これしかできないでしょ。撮影現場で大工が使う直角定規差し金やら水準器でも使ってんじゃないの?と思えるくらいに、真正面から見据えたシンメトリーぽい映像が続く。顔認証かよ。この無機質で淡々とストーリーだけ追ってく作風が、アンダーソン監督作の特徴であり、僕が嫌いなところ。愛しのレアたんや芸達者なエイドリアン・ブロディがいなかったら投げ出してたかも。
やっと映像に躍動感が出てくるのは「宣誓書の改訂」。学生運動のリーダーと記者自身の関係を告白するようなエピソード。やっと人間らしい話が出てきた。この微妙な三角関係や世代ギャップは話としては面白いのに、また舞台劇のような背景チェンジや色彩を突然変える演出で、話に浸らせてくれない。中年女性記者が最終号で秘め事を告白する感じがいいのに、アンダーソン監督はそれを茶化してるように思えて仕方ない。
最後の「警察署長の食事室」は、美食家署長が抱える天才シェフを取材していた記者が遭遇した事件の顛末。お話としては面白い。だが、雑誌社が苦境の記者を救ってくれたエピソードが語られていい感じで進んでいたのに、だんだんと記者目線なのか、署長目線なのか、シェフの活躍物語なのか、話の視点が定まらなくなってくる。ここでもやっぱり縦横に線が引かれる構図は健在。方眼紙の中でもの考えてんじゃないの?これを最後まで貫くかと思ったら、唐突にアニメーション化。ここで初めて画面から直線が消える。結局ビジュアルで驚かせたいんじゃない。
そして編集長の死をスタッフと記者が迎えるクライマックス。デスクの上に横たわる死体の横で記事書きますか。死体を囲んで思い出話しますか。しかも編集長がどこまでみんなに慕われていたのかが、ほぼ語られずに迎えるこの場面。申し訳ない。上っ面の話じゃん。人懐っこい笑顔のビル・マーレイ編集長だから慕われてたんだろうなって含みがあるのかもしれないけど、それってストーリー語ることを放棄して、キャスティングに頼ってるだけでしょ。だからパブリックイメージが強いキャストだらけにしてるんじゃないの。映像ばっかり凝って、喜怒哀楽が伝わってこないのが残念で仕方ない。「ロイヤル・テネンバウムス」は、ちゃんと情が感じられたぞ。活字文化へのリスペクト?、だったらそれを支える編集者や記者こそ讃えるべきでしょ。
ふぅ。言いたいことは言わせていただきました。やっぱりウェス・アンダーソン監督は僕には向かないみたい😞。
VIDEO