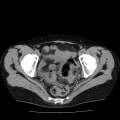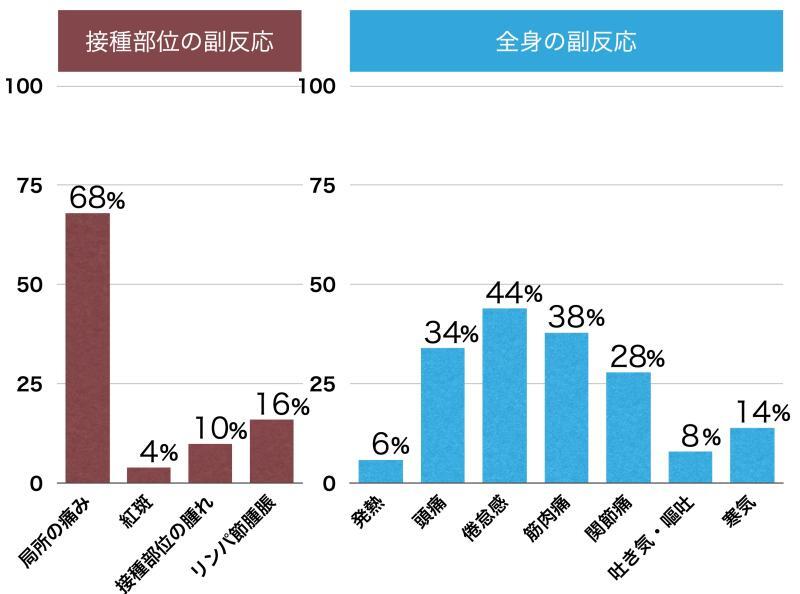11月6日(月)の午後に前日当直だった先生が、急性胆嚢炎で入院した81歳男性を救急搬送していた。地域の基幹病院は受け入れ不可で、消化器センターのある専門病院への搬送だった。
この患者さんは心窩部痛で11月1日の夜間に救急外来を受診した。当直の腎臓内科の若い先生が診て、CT(単純)で目立った所見がなく、胃痙攣として(?)帰宅としていた。
症状が続いて、11月2日に内科外来を受診した。現在は内科をしている先生(もともとは消化器外科)が診て、前日のCTで所見に乏しいことから、血液検査だけ行った。
白血球15500・CRP3.0と炎症反応の上昇を認めたが、それ以外はLDHが248(124~222)と若干の高値だが、それ以外の肝機能は正常域だった。アセトアミノフェン投与で帰宅とした。
11月3日・4日はいったん治まっていたらしいが、11月5日にまた心窩部痛が出現して救急外来を受診した。日直は大学病院から来ている外科医だった。
腹部CTを行うと、胆嚢の壁肥厚と腫大を認めた。(胆管も若干拡張?)急性胆嚢炎で入院として、受診したのが夕方だったので、当直の内科医に申し送っていた。連休明けの6日月曜に手術可能な病院は転送予定となった。
11月6日の血液検査では、白血球8800・CRP14.5となり、AST 293・ALT 316・LDH 283・ALP 355・γ-GTP 397・総ビリルビン4.6と肝機能障害を認めた。
総胆管結石疑いでMRCPも追加したので、午後になってしまったようだ。総胆管の拡張はあまり見られなかった。
腹部エコーをしていないので、胆嚢結石はよくわからない。こんな経過で進行するということがわかる症例?となった。