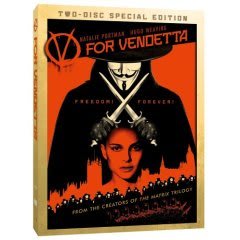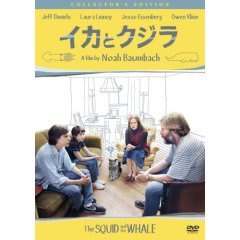監督:コスタ・ガブラス
脚本:ホルヘ・センブルン/コスタ・ガブラス
音楽:ミキス・テオドラキス
製作:ジャック・ペラン/ハメッド・ラシュディ
出演:イヴ・モンタン/イレーネ・パパス/ジャン=ルイ・トランティニャン
ジャック・ペラン/レナート・サルバトーリ/フランソワ・ペルエ
マガリ・ノエル
《あらすじ》
地中海に面した架空の国では、軍事政権に反対する勢力が日増しに大きくなっていた。反対党の指導者的存在であった大学教授・医学博士のZ氏が演説会場で、暴漢に襲われ変死する。しかし、警察と憲兵隊はこれを交通事故死と発表した。Z氏の死を悲しみ、若者たちは激昂し、暴徒と化す。予審判事と新聞記者が真相究明に乗り出し、政治的な計画的殺人容疑が浮かぶ。警察署長、憲兵隊長、将軍を共犯容疑で告訴するが、判事側の証人が次々と姿を消していく……
ギリシャで実際に起こった「ランブラキズ事件」をモデルに作られた、鬼才コスタ・ガブラスが贈る衝撃の問題作。
《この一言》
“ わたしは殴られた
理由は?
なぜ我々の思想を
暴力で封じ込めるのか ”
衝撃の問題作でした。たしかに。
共産主義とは何か。
軍事政権とは何か。
独裁者とは。
こういうことに、私は興味と関心を持っているので、この映画もまた私には非常に興味深いものでありました。
私は長らく「共産主義=軍事政権=独裁者の存在」というように3つの項目を結び付けた認識が世間にはあるのではないか(といっても私に認識できる程度のごく狭い範囲にすぎませんが)と感じながらも、深く考えることもなくなんとなく過ごしてきました。ところが行き当たりばったりに、色々な時代の色々な国の人々の歴史的事実を述べようとした文章や映像などに触れるうちに、「なんでそんなふうに思っていたのだろうか?」という疑問が膨れ上がったわけです。
いい歳をした社会人がこんなふうに無知であることや、それを曝してしまうということは実に恥ずかしいのですが、恥ずかしがってはいられません。
共産主義、これは経済の話ですよね。
軍事政権、これは社会体制の話ですよね。
独裁者、これはいったい何者ですか。どういう基準で認定されるものなのか。その国の国民から圧倒的な支持を受け、投票によって民主的に選出された人物でさえも時として「独裁者」呼ばわりされるのは何故なのか。
それが知りたい。
いずれの言葉にもどういうわけかネガティブな印象がまとわりついている気がしてならないのですが、それはどうしてなのか知りたい。
そういうことを思いながら、この『Z』という作品を観ました。
それでどうだったかと言えば、少なくとも、共産主義と軍事政権は必ずしもイコールでは結べないという事実があるということですね。それはガルシア=マルケスの『戒厳令下 チリ潜入記』を読んだ時にも思ったのですが、どちらかと言うと「軍事政権の影には巨大な資本主義国家の存在が…」という構図が見えて仕方ない。少なくとも、そう見られても仕方のない状況はあったらしい。
しかし、経済と社会体制の問題は分けて考えるべきかもしれません。たとえ経済活動あってこその社会であるとしても、今のところの私の能力でもってひとくくりに判断をしてしまうのは浅薄かつ危険でしょうから、ひきつづきの課題としておきたいところです。
映画では、軍事政権の幹部たちによって謀殺される指導者の大学教授は平和を訴え(作品中では第三者によって何度か「彼は共産主義者ではない」と説明される場面があるが、軍部では「彼は共産主義者である」と認識されているらしい場面もたびたびある)、軍事政権に反対する集会を開こうとしますが、妨害に合い集会所をなかなか借りることができず、しかも彼の暗殺計画があるという噂までが囁かれます。そして結局それはその通りに実行されるのでした。
さらにその後の世間への発表のなかには「暗殺事件」などはなく、単に「交通事故」があっただけとされるのでした。
しかし事実は違っていたのではないかと気付いた予審判事(この人の格好良さについては、それだけでひとつの記事が書けそうなくらいです)と新聞記者(「国民には知る権利があるのです!」といってずかずかと部屋に入っては断りもなく写真を撮りまくる新聞記者の姿に、どの時代にも新聞記者とはこんなに鬱陶しいものだったのか…と一瞬憂鬱になりましたが、だかしかし絶対に必要な存在であることは否定できません)が、確固たる信念と情熱、そして知性を働かせて事件の真相に迫っていきます。そのあたりはとても素晴らしい。結果として、事実に到達した予審判事は、上司の脅しにも屈せず、実行犯およびそれを操作していた軍の幹部たちを起訴します。
ところが、その結果は………。
さあ、恐ろしいものは、憎むべきものは何か。
私はそれは、あらゆる「主義」そのものそれ自体ではなく、「私の主義と違うお前の主義」を認めることができず暴力でしか解決しようとしない態度であろうかと思います。暴力は手っ取り早くて簡単な方法かもしれませんが、それがつまり最良・最善の方法と言えるでしょうか。
ではどうすれば良いのか、暴力で訴えてくる相手の言うことを聞くために、されるがままになっても黙っていろというのかと問われれば、私には今のところ何も良い考えがないのでなんとも答えられません。でも暴力に対して暴力でこたえていたのでは、人間には滅びという未来しかないような気はします。最後のひとりになったら、それはたしかに平和だろうなとは思いますが。(それがエレンブルグの『トラストD・E』という物語だったかもしれません)
映画をみて、やりきれないと感じたところには、実行犯となった男たちを含む庶民の姿でしょうか。彼等は「生きるために、自分にとってより利用価値のある権力の側につく」わけであって、必ずしも「主義」を掲げているわけでもない。仕事や生活の安定のために便宜をはかってくれるなら、もしかしたら相手は誰でもいいのかもしれない。そこを、権力者たちに利用されている。
上に引用した言葉のほかにもうひとつ、印象に残った言葉。
棺職人は、暗殺計画を事前に聞いていたので、証人になろうと自ら名乗り出ます。が、役人の夫を持ち、仕事を得るために極右団体に所属したという妹からは「ロバのように頑固で、家族のことなど何も考えていない! 父が死んだあとも、妹である私のために何もしれくれなかった!」と罵られます。そこで、
「いいかい、よくお聞き。
もし、お前が暗殺の話を聞いて
本当に人が殺されたら
黙ってるか?」
黙っていられない時に、無理矢理黙らされることのないような社会を、どのように作ったら良いのでしょう。私にはまったく見当も付かないですが、この映画の最後に込められたメッセージに、希望を見いだしたい。
“ Z。
それは古代ギリシャ語での、
その意味は
「彼は生きている」 ”
けっこう最近まで軍事政権の国だったというギリシャについてはこちら。
Wikipedia : ギリシャ
 『ツルバミ』YUKIDOKE vol.2 始めました /【詳しくはこちらからどうぞ!】→→*『ツルバミ』参加者募集のお知らせ(9/13) / *業務連絡用 掲示板をつくりました(9/21)→→ yukidoke_BBS/
『ツルバミ』YUKIDOKE vol.2 始めました /【詳しくはこちらからどうぞ!】→→*『ツルバミ』参加者募集のお知らせ(9/13) / *業務連絡用 掲示板をつくりました(9/21)→→ yukidoke_BBS/ 『ツルバミ』YUKIDOKE vol.2 始めました /【詳しくはこちらからどうぞ!】→→*『ツルバミ』参加者募集のお知らせ(9/13) / *業務連絡用 掲示板をつくりました(9/21)→→ yukidoke_BBS/
『ツルバミ』YUKIDOKE vol.2 始めました /【詳しくはこちらからどうぞ!】→→*『ツルバミ』参加者募集のお知らせ(9/13) / *業務連絡用 掲示板をつくりました(9/21)→→ yukidoke_BBS/