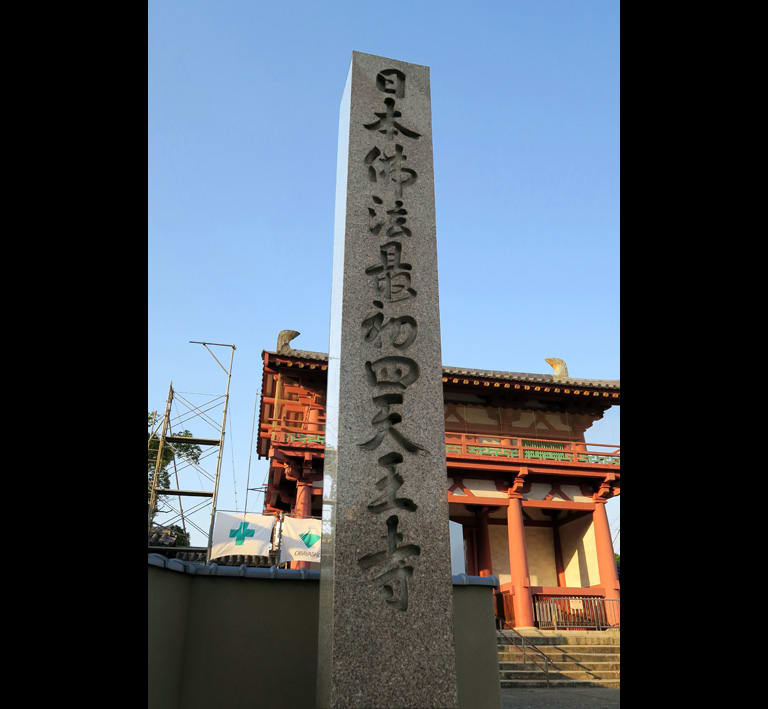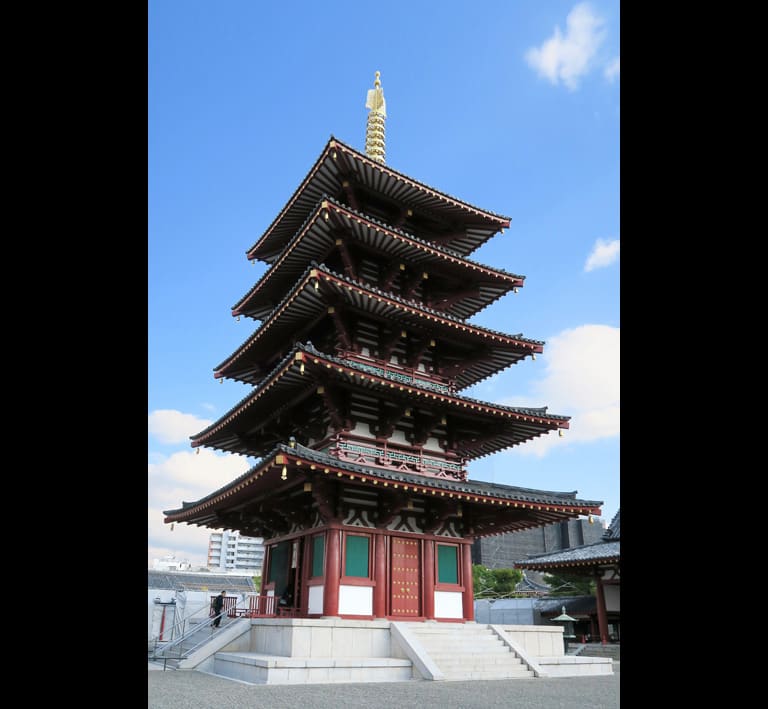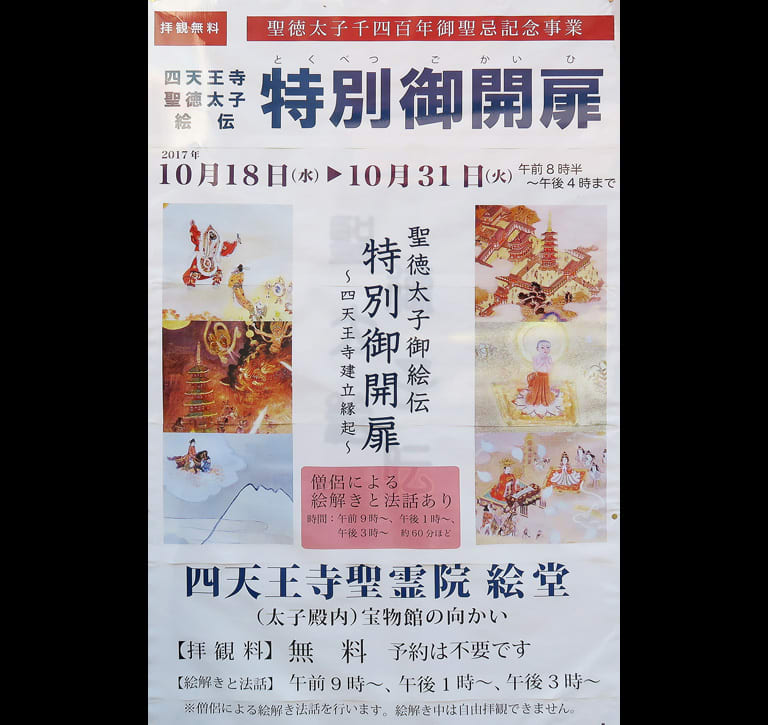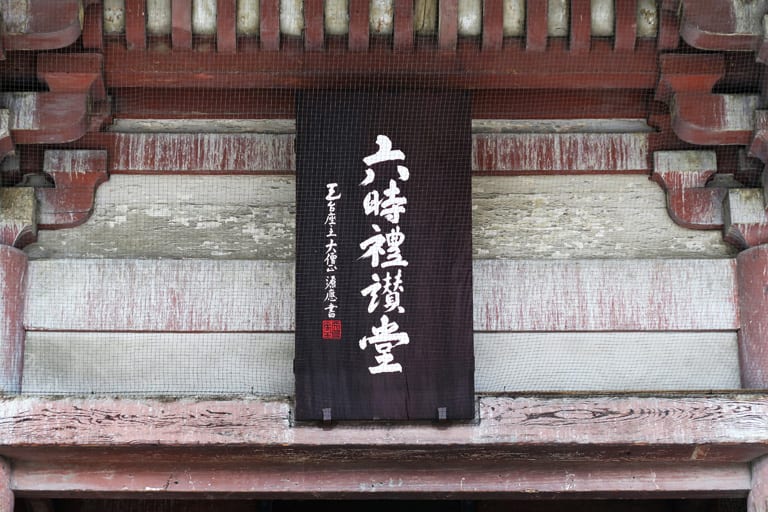(2016.11.04訪問)
極楽寺から県道30号を南へしばらく走り、国道24号五條市街を通り本陣交差点をR168号に入ります。
あの有名な谷瀬の吊橋、日本一広い十津川村、熊野本宮大社を通りやがて新宮市に至る国道です。R168号は変化に富んだ山岳道路で
冬期はともかく、春夏秋それぞれのシーズンの顔を見せてくれ、かなりワイルドなドライブを楽しめるワインディングロードですヨ。
そうそう吉祥寺に向かうのでしたネ、R168号の吉野川を渡り少し行って丹原町を右折、開運坂と呼ばれる小道を1キロほど登ったと
ころに建つ毘沙門さんのお寺、吉祥寺に到着です。
▼参道入口に山門はありません、シンプルな石柱が両サイドに建てられています。
この参道を少し進むと広場に出ます。

[ 吉祥寺 ]
●山号 柴水山 (しばしざん)
●院号 宝塔院 (ほうとういん)
●寺号 吉祥寺 (きっしょうじ)
●宗派 高野山真言宗 (こうやさんしんごんしゅう)
●開基 弘法大師空海 (こうぼうだいしくうかい)
●開創 弘仁七年 (816年)
●本尊 毘沙門天立像
▲拝観 境内自由 朱印300円
▲時間 9:00~17:00
▲奈良県五條市丹原町914 Tel.0747-22-0332
▲https://ameblo.jp/kissyouji/
▲JR和歌山線「五条駅」から十津川温泉または城戸または西吉野温泉行きバス「丹原」下車、徒歩約10分
南阪奈道路「葛城IC」から県道30号、国道24号経由、約22km約45分
▼到着です。奥に見えるのが山門、提灯が見えますネ。

吉祥寺縁起 (吉祥寺パンフレットから抄出)
弘法大師は高野山開創にあたり、高野山の丑寅に鬼門除けの毘沙門天を安置し堂宇の建立に着手。しかし当地に水が無かったため
「柴手水の法」でもって身を清め開眼供養を終えた。この秘法の縁起にちなみ、大師は「柴手水の法」の手の一字を除き「柴水山」
と号し、毘沙門天の宝塔を院号とし、脇立ちの吉祥天女の名をとり「柴水山宝塔院吉祥寺」とし、現在に至る。
▼オシャレな料亭ではないんです、お寺なんですよ。しかし古刹の山門には見えませんよネ。
崩れかけた袖塀がいい雰囲気を醸しています。

▼やはり文字は勘亭流崩しですか。

▼スグ左手に鐘楼が。

▼そして右手に手水鉢。

▼正面を見ますと来てます来てます紅葉の始まり。

▼広場右に目を転じますと右手に本堂、正面庫裡。

▼そして左手に大師堂。
吉祥寺境内の建物は実はこれだけ、大師堂は新しい建物でお堂の雰囲気感じる事は出来ませんし、入堂も出来ません。

▼本堂横のお庭には山茶花や、

▼楓に、

▼宝篋印塔がヒッソリと建っています。

▼本堂。方六間、宝形造、本瓦葺、一間向拝付。

▼本堂前面はすべて中央一間三枚格子戸と格子蔀戸になってます。

▼本堂扁額。

▼本堂内陣の様子。

▼中央お厨子前のお前立ち毘沙門天立像。
像高約1mの小さなお前立ち像ですが、江戸期の作という事で、彩色と文様の細かさが綺麗に残っています。お前立ち像がこれだけの
素晴らしさ、さてお厨子の中のご本尊は果たして……。

写真は堂外小窓からのショットです。
▼本堂横のお庭。

▼山門を出ると……、

▼お寺の周辺は柿畑が広がっています。御所から五條にかけては有数の柿の産地で、途中柿畑があちこちに広がっています。
チョット手を伸ばせば……、そんな事はしてませんヨ、ボクは。

▼御朱印は毘沙門天王です。

庫裡にお声掛けをするとご住職が本堂内を案内して下さり、本尊お前立ちの毘沙門さんには目の前でお目にかかり、レクチャー頂き
ましたがお厨子の中はクエッション、本尊はもう少し大きい像との事。ついでに寺院経営のしんどさも。国指定でない限り仏像や堂
宇の維持修復は総て持ち出しらしく、これがまたお金のかかる事、お寺の悲哀を嘆いておられたのには、こちらも身に詰まされた思
いです。大寺院を除いて何処のお寺も地方へ行くほど、こう云った嘆きがお寺の現状を表しているようです。
吉祥寺これにて オ シ マ イ
↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。