京都の神社仏閣でまだ訪れたことのないところ、そして少し早いが桜を求めて回っている。 その途上で「石清水八幡宮」に参ったところ、その本殿への参道に目新しい植物を見かけたので、集めてみた。 この参道は緩やかではあるが、足の弱った私には厳しく、格好の足安めとなるので片っ端から撮りまくった。
その中には、私の「花写真館」にまだ登録のない花(以下“新種”という)を見つけたので、心して見て歩いた結果、大きな収穫があったので特記する。 我が家の周辺では、野原を詳細に見ても、“新種“に出会うことは、極めて稀であるが、ここは”新種“の宝庫にも見えてきて、足腰の痛み忘れる瞬間もあり狂喜したしだい。
ここ「石清水八幡宮」は「男山(別名:鳩ヶ峰)」という、標高143mの山上にあり、ケーブルカーもあるが、山の周りを半周するように、表参道があり、その道すがら野草を撮りながら、足を休めたのである。 ここの自然保護には地元でも取り組みがあるようだし、独特の自然環境があるやも知れない。
それでは“新種”から紹介しよう。
「キケマン (黄華鬘)」 「花写真館」“新種”登録 第1264号
「ケマンソウ」or「タイツリソウ」の仲間であり、何度かお目にかかっているが、花が萎れていたりして、私の「花写真館」には未登録であったが、こんなにきれいにきちんと咲いてるのは初めて目にし感動したものだ。

「マメヅタ (豆蔦)」 「花写真館」“新種”登録 第1267号
シダの仲間であるが、石や木に寄生して生える。丸いのが葉であり、細長いのは「胞子葉」であり、茶色いのは「胞子」であり、これを飛ばして子孫繁栄を図るのだそうな。 であるから、ここでは花扱いだ!。


「ヤマネコノメ (山猫目草)」 「花写真館」“新種”登録 第1266号
まだ咲はじめではあるが、これでも立派な花である。

少々見難いが薄い黄色のが「シベ」であり、包まれた中に見える黒いのが「実」であり、これが猫の目に似るというが・・・・・・?。

「セントウソウ (仙洞草)」 花写真館」“新種”登録 第1265号
花も葉も「セリ」に似るが別らしい。

以上4種を“新種”として登録した。 ちなみにここまでの登録種類は 1267種となった。
「姓名不詳」 2種
花の咲き方、葉の様子は「ヒトリシズカ」または「フタリシズカ」とよく似るが、「ヒトリシズカ」はその名の通り“ヒトリ”に限定されるから異なるし、また、「フタリシズカ」は“フタリ”どころか“ヨニン”も“ゴニン”もあるので少し近いが、「フタリシズカ」は花びらがくるりと巻くので、これも違う。 よって今の所は姓名不詳である。

これは葉も花も「ウルシ」とそっくりさんではあるが、「ウルシ」は花がもっと多く、花が下向く点が違うように思う。 もう少し日が経つと花が増えて、下向くやも知れないが、今の時点では同種とは言いきれないので不詳とした。

ここからは登録済の花を紹介する。


もう少し日が経つと新芽の赤が濃くなってより美しくなるのだが・・・・

昔は“おでき”に効く薬草だったらしい。

何故かわからないが、ここは固有の自然環境があるようだ。 例えば伊吹山のような固有種は見られないが、ほかで見られない植物が自生しているので、 出来れば日を改めて何度か訪れたいと思う。 さすれば必ずや“新種”と巡り合えると確信を持った。
i以上













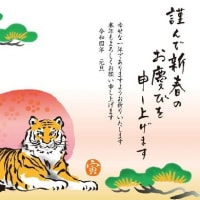






男山だけでこれだけブログのネタ量になったのはホクホクじゃないですか。
地形からすると、三つの川が近いという以外に、特別なものを感じませんが、土質か何かちょっと普通じゃないのかもしれません。
生えてる植物が、特殊な環境に育つものではなく、ただ、我が家の近くではお目に係れないので、何か特別なように感じるだけの事なののです。
一度地元の環境保護団体の方に尋ねてみたいところです。
お陰で、”新種”が4種も見つかり、ブログの一ページを飾るこが出来ました。