2017.05.23(火)、一年二ヶ月ぶりに京都に来て、大谷粗廟にて納骨をすませたので、 体力の続く限り、その近辺を見て回ろうと、歩き始めたのであった。 大谷粗廟の北門を出てすぐに右に折れると・・・・。
黄台山 長楽寺 (ちょうらくじ)
京都市東山区八坂鳥居前東入る円山町626 (拝観料 ¥500)

ウイキペディアによれば・・・
円山公園の東南方に位置する。かつての境内地は円山公園の大部分や大谷祖廟(東大谷)の境内地を含む広大なものであった。長楽寺は、一説によれば805年(延暦24年)勅命により最澄が延暦寺の別院として創建したのに始まるという。『平家物語』「灌頂巻」によると、1185年(文治元年)には高倉天皇の中宮で安徳天皇の生母である建礼門院(平徳子)が壇ノ浦の戦いの後、この寺で出家したと伝えられる。法然の弟子、隆寛はこの寺に居住して多念義を唱えた。隆寛の系譜は寺院名をとって後に長楽寺流・長楽寺派といわれた。1385年(至徳2年)時宗の僧国阿がこの寺に入り、時宗の寺に改められた。1908年(明治41年)には、時宗の道場が置かれ七条道場と称された金光寺がこの寺に統合されている。長楽寺が所蔵する時宗祖師像7躯(慶派仏師の作)は、金光寺から移されたものである。

「本堂」



「建礼門院塔」

「鐘楼」

「収蔵庫」

「平安の滝」
滝と言っても、今は少量の水が高さ3mくらいの所に突き出たパイプから、流れ落ちている。

ここを入る・・・





京都のお寺や神社の主なところは既に訪れているが、この寺は今回がはじめてである。
この後、近くにある「いそべ」と言う、京料理を食べさせる店で、昼食を取り、大谷祖廟の前を通り、南の方角に向かったが、そこらは次回にしたい。













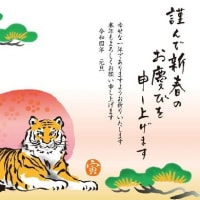






長楽寺は地図で見ると円山公園の一番奥にありますね。写真を見る限り全体的に侘しい印象をもちました。
円山公園はよく来たものですが気が付きませんでした。
やはり京都では東山区が一番京都らしく母も此処に住むのが夢だったと聞いていました。
最後の写真を見ると池が見られますが私の庭には長い間池水も空っぽで荒れ果てています。メンテナイスをする元気がないからです。
2年後の新名神でなくてもバスなど利用も出来ます。「お逢いするのももう無理かも」なんて寂しいことを言わないで下さい。
体全体に老化は着実に進んでいますが、足腰だけは特別にへたっているように感じます。 日常生活において、最も重要であり、よく使うものですが、それだけに老朽化が激しいのかも知れません。 安静にしていれば治るはずなんですが、治る前に動き出すから、治る暇が無いのです。 それだけ回復にかかる時間が長くなったということでしょうか?。
長楽寺は一番奥ですが、大谷祖廟の北門の前が入り口で近かったのですが、それからが長かった。 その途中で食事場所を見付け、足が休めると、一息ついたのでした。
あとで詳しく(?)書くつもりですが、京都の街は全体的に私は好みますが、なかでも、東山それも祇園周辺は特別に好きです。 京都を代表する地と言えると思います。 ここに住むなんぞは、私には思いもよらないことですが、そのお気持ちも分かる様な気がします。
二年なんて、すぎてしまえばあっという間でしょうが、これからの二年は段々と長くなってるように思えてきます。 新名神に自分がハンドル握って進むのは、もう一つ遠い先のことです。 誠に悲しいことですが、これは現実の問題です。