今年の紅葉はもう終盤戦になるが、まだ、谷汲の華厳寺と養老公園を見ただけなので、少し物足りない気分であった。2012.11.28(水)は1月並みの気温とかで少し寒いが、天気が良さそうなので、出掛けることにした。
奈良の五条、吉野方面をかなり前から狙っていたが、紅葉情報を漁っていると、京都方面で、宿題(まだ訪れていない寺)となっている、「実相院」などのある岩倉方面のお寺などが、”まだ見頃”との記述があったので、この周辺を廻ることにした。
少々早起きをして、メダカ達の餌もちゃんとやり、午前8時に我が家を出発。新名神など高速道路は順調に走れたが、京都市内に入ると通勤時間なのか、混雑に巻き込まれ、最初の訪問予定地に着いたのは10時を過ぎていた。
「実相院」
京都市左京区岩倉上蔵町121
拝観料 ¥500、 駐車無料
 d92677
d92677
相院(じっそういん)は、京都市左京区岩倉にある仏教寺院。宗派は単立(元天台宗寺門派)、開基(創建者)は、静基(じょうき)、本尊は不動明王(鎌倉時代作の木像)。門跡寺院の1つである。岩倉実相院門跡とも呼ばれる。
鎌倉時代の寛喜元年(1229年)、静基僧正により開基された。当初は現在の京都市北区紫野にあったが、応仁の乱を逃れるため現在地に移転したとされる。
室町時代末期までに多くの伽藍等が戦火で焼失し、江戸時代初期に足利義昭の孫義尋が入寺。母古市胤子が後陽成天皇の後宮となった関係で皇室と将軍徳川家光より援助を受けて実相院を再建した。
門跡寺院であり、代々の住職は天皇家と繋がりのある人物が務めた。本堂は東山天皇の中宮、承秋門院の女院御所を移築したものであり、四脚門・車寄せも御所より移築されたものである。老朽化が進み主な建物は多数のつっかい棒が施されてようやく倒壊を免れているのが現状であり、修理のための資金集めが課題となっている。
幕末には岩倉具視も一時ここに住んでおり、当時の密談の記録などが残されている。
庭園は池泉回遊式庭園と枯山水の石庭の2つがある。前者の池にはモリアオガエルが生息している。新緑、紅葉の頃とも見所となっており、特に部屋の黒い床に木々が反射する光景は「床緑」「床紅葉」と呼ばれ知られている。
 d92628
d92628
紅葉はやや遅めではあるが、間に合った感じにほっとする。
 d92635
d92635
入りざま、カメラによる撮影は何故か厳しく注意を受ける。なぜ、そんなに仇のように思われるのか?、きっと、前にエチケットを心得ないやつが来たに違いない。
 d92639
d92639
 d92665
d92665
 d92666
d92666
 d92669
d92669
 d92633
d92633
建物の”つっかい棒”があちこちにやたら目に着く。
 d92644
d92644
 d92662
d92662
 d92656
d92656
 d92658
d92658
 d92675
d92675
 d92674
d92674
この後は、少し南に下がった所、宝ヶ池の北西に位置する、「妙満寺」に向ったが、その記録は次回に載せたいと思っている。
<< 続く >>
現在「ネパール紀行」の連載中であるが、季節性のある記事を7編ほど作ったので、少しの間交互に公開してゆきたい。
 d92831
d92831 d92833
d92833 d92834
d92834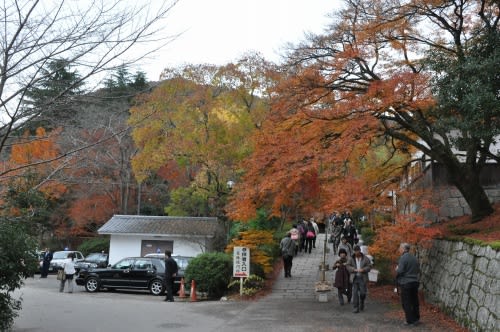 d92836
d92836 d92837
d92837 d92838
d92838 d92841
d92841 d92845
d92845 d92846
d92846 d92847
d92847 d92849
d92849 d92828
d92828









 d92931
d92931 d92935
d92935 d92813
d92813 d92814
d92814 d92949
d92949 d92952
d92952 d92815
d92815 d92945
d92945 d92954
d92954 d92816
d92816 d92817
d92817 d92927
d92927 d92789
d92789 d92793
d92793 d92794
d92794 d92795
d92795 d92775
d92775 d92776
d92776 d92779
d92779 d92780
d92780 d92782
d92782 d92783
d92783 d92798
d92798 d92802
d92802 d92805
d92805 d92738
d92738 d92740
d92740 d92742
d92742 d92751
d92751 d92760
d92760 d92761
d92761 d92762
d92762 d92763
d92763 d92768
d92768 d92766
d92766 d92743
d92743 d92765
d92765 d92684
d92684 d92689
d92689 d92696
d92696 d92717
d92717 d92721
d92721 d92709
d92709 d92700
d92700 d92731
d92731 d92719
d92719 d92725
d92725 d92728
d92728 d92690
d92690 d92677
d92677 d92628
d92628 d92635
d92635 d92639
d92639 d92665
d92665 d92666
d92666 d92669
d92669 d92633
d92633 d92644
d92644 d92662
d92662 d92656
d92656 d92658
d92658 d92675
d92675 d92674
d92674






















