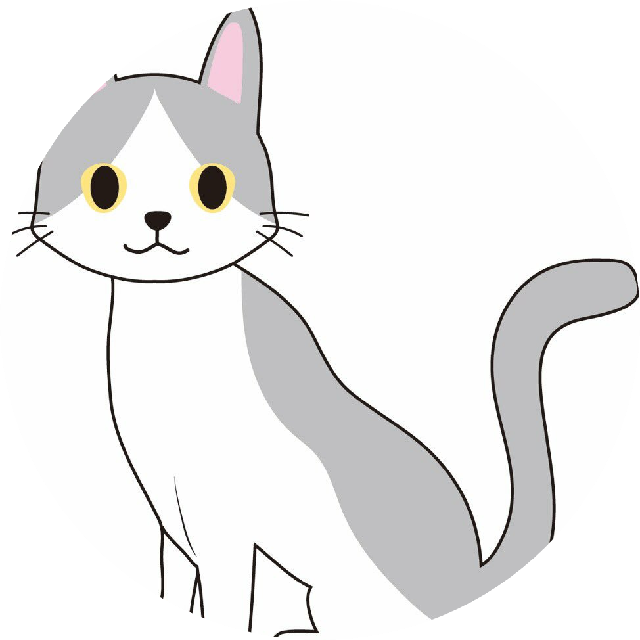橋本胖三郎『治罪法講義録 』・第五回講義
第五回講義(明治18年5月6日)
本日は前回に引き続いて、私訴を行うべき者について説明致しましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
私訴を起すことができるのはどのような者でしょうか。
一 被害者
二 被害者の相続人
相続人は先人の権利義務を継ぐ者ですので、起訴の権利もまた相続人に移転します。有形の財産だけでなく、無形財産も相続するからです。
権利は無形財産の一種ですから、先人が損害を受け、その者が私訴権を有していた場合には、相続人が先人の権利を継承して起訴することができるのです。ただし、相続人が起訴する際には、犯罪の時期によって多少の違いがあります。被害者の死亡時期の前後に分けて説明致しょう。
1. 被害者の死去前に係る犯罪
2. 被害者死去の原因となった犯罪
3. 被害者死去後に係る犯罪
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第一の場合:被害者の死去前に係る犯罪について説明しましょう。
被害者が生存中に他人の犯罪によって財産に損害を受けた場合、要償の権利(私訴権)を持つことは当然です。
被害者が死亡した場合、相続人はその財産を引き継ぐため、損害を受けた者は先人に代わって損害賠償請求をすることができるのです。
例えば、先人が生存中に他人に土地を横奪されたとします。横奪がなければ、相続人はその土地を引き継いでいたはずです。しかし、相続人は横奪されたことで土地を引き継げなくなったのですから、相続人に起訴権が与えられなければなりません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
身体の安全や自由などに対して損害を受けた場合にも相続人は起訴権を有します。
なぜなら、訴権は無形財産の一種であり、先人が起訴せずに死亡した場合、その訴訟権は相続人に移転するからです。さらに、自由や安全が侵害されたことは、道義上の損害であり、間接的には財産にも損害を及ぼす性質を持っているので、相続人が起訴権を持つのは当然のことだと言えるでしょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
名誉毀損の場合
損害を受けたのが、財産でも身体の安全・自由でもなく、名誉であった場合、相続人に起訴権があるでしょうか。
これは前の二つの場合と大きく異なります。
前の二つの場合における損害は有形のものであり、目で見ることができるものでした。しかし、名誉毀損の場合は無形損害に属するものなので、目で見分けることができないのです。この点については少し詳しく説明する必要があります。
名誉毀損罪は被害者の告訴がなければ成立しません。そのため、被害者である先人が起訴せずに死亡した場合、相続人に訴権がないといわなければなりません。
もともと、名誉毀損罪を訴えるかどうかは被害者自身の選択に委ねられるべきものです。
よって、被害者が起訴せずに死亡した場合、被害者には起訴する意思がなかったと考えざるをえません。
被害者に起訴する意思があった場合には、自ら訴えるか、又は事故などで自らが訴えられない場合は、他人へ委託するか、又は生前に子孫へ起訴を遺言するといった方法で意思を示すことができたはずだからです。これらの方法を何もせずに死亡した場合は、被害者には起訴する意思がなかったと考えるのです。
先人に起訴する意思がなかったのに、相続人が勝手に起訴した場合、先人の意思に反する結果になります。
本人の意思に反する行為は、法律の趣旨にも反することになります。
先人が起訴せずに死亡した場合、相続人に訴権を持たせないのは以上の理由によります。
名誉の損害は、人の立場や感覚によって大きく異なるだけでなく、被害者の気持ちによっては訴えることでさらに名誉を損なうと考える場合もあります。
しかし、この訴権を他人に委ねた場合は、他人が訴訟を起こすことで、かえって被害者の心情に苦痛を増す可能性があります。
そのため、この訴権は検察官にも委託させていないのです。
先人が起訴せずに死亡した場合、相続人に起訴権がないのはおわかりいただけたかと思います。
一方、先人がすでに訴訟を起こして死亡した場合、相続人はその訴権を引き継ぐことができます。この場合には、先人の意思に反する心配はないからです。
このように、被害者である先人が起訴したかどうかによって、相続人の訴権の有無が変わってくるのです。これが名誉の損害と他の損害との違いです。
我が国のように新法が制定されて間もない国では、これらの区別は実際には必要ないかもしれません。しかし、条理上はこうであるべきして、実際にフランスではこのような判決例が存在しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第二の場合:被害者の死因となった犯罪の場合には、相続人に私訴権があるのは当然です。
既に述べたように、親子や夫婦は直接の被害者として、相続人としての名義ではなく、相続人固有の名義で起訴することができます。しかし、このような犯罪に関する起訴は、多くは公益に関わるため、検察官に属すべきものです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第三の場合:被害者死亡後の犯罪の場合
第三のケースは、被害者が死亡した後の犯罪に関係するものです。
「人は一度死んでしまえば、もう二度と害を受けることはないのではないか」 と疑問を抱く人もいるでしょう。
しかし、死者に害を加える可能性がないわけではありません。具体的には死者の名誉が毀損される場合です。
そして、この場合には、死者も依然として人として扱われるべきです。そもそも、死者を人として扱うべきかどうかについては、古くから議論されてきました。
しかし、私は場合によっては死者も人として認めるべきだと考えています。実際に、我が国の法律もこの説を取っています。例えば、刑法第359条には「死者を誹毀した者は誣罔に出たるに非ざれば、前条の例に従って処断することを得ず」と規定されています。
この規定を見ると、死者を一個人として認め、これを保護する精神に基づいていることが分かります。法律の美徳と言ってよいでしょう。
刑法第264条や第265条のように、死者を人と同視して、保護する法条も存在します。このように、死者を人と見なす場合があることを知っておいていただきたいのです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
死者の名誉を誹毀する犯罪について、4点に分けて説明致しましょう。
(第一) 直接に相続人自身の害となるべき場合
この場合においては、相続人として訴える必要はありません。直接、自分名義で起訴することができます。例えば、ここに一人の富豪がいて、その父親が死去した後、ある人がそれを誹謗して、「某は、かつて不正な行為によって富を得た者である。今は富豪と呼ばれ、人から尊敬されているけれども、その当初の不正な行為によって富を得た者だから、今日の富は不正な富である。何を以てこれを誉れとするに足るだろうか」と言ったとしますな。
この誹謗は死者に対する罪です。
しかし、この誹謗が世間に広まれば、相続人の信用が地に落ち、仕事や人間関係に大きな影響を及ぼすでしょう。このような損害は相続人にの直接の損害として、相続人本人の名義で起訴することができます。もし、事実の如何によって刑事裁判所に訴えることができない場合は、民事裁判所に損害賠償請求をすることができます。|
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(第二)相続人の損害とならない場合
相続人は起訴の権利を有しません。
通常、相続人が先人の権利を相続するときは、その相続を受けた時点に現存するもの以上のものを受け取ることはできません。しかし、相続人が損害を受けていないのですから、その権利は相続の時点で異なるところがありません。
訴権が相続人に移転される理由がないのですり。
刑法を適用する上で、死者に対する誹毀罪は、その誹毀が誣罔に出るか否かによって、即ち事実の存否によって罪を問うか否かを決定します。このように事実の有無に基づいて罪の有無を定めることは、公益の観点から定められたものです。
死者に対する中傷を生者に対する場合と同様に、事実の有無を問わないとすると、歴史を編纂する者は、刑罰に触れることを恐れ、筆を燃やしてその仕事を廃することになるでしょう。歴史叙述は讃美のみとなり、批判することがなくなり、世に正史の一篇のみ残ることとなります。このような結果は、公益を害します。
日本の刑法では、このように明文があるのですが、フランス刑法には明文の規定がなく、この点に関しては説が分かれており、議論がなされています。
死者に対する誹毀の罪では、相続人は告訴権のみを持ちますが、この告訴は、犯罪があったことを裁判官に報告することにとどまりますので、告発と同じです。相続人は私訴権を持ちません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(第三) 被害者の債権者は起訴権を有する
被害者の債権者が起訴権を持つ理由を詳細に説明すると長くなるので、ここでは要点のみ説明します。
被害者が窃盗などの被害に遭い、財産を失った場合、被害者は債務を弁済できなくなる可能性があり、その結果、債権者も直接的な損害を受けることになります。
「義務者の財産はすべて権利者の抵当である」というのは民法一般の原則です。この原則は、フランス民法2092条及び2093条に存在し、日本の民法草案でもこの点が規定されています。
この原則は、債務者が支払いを怠った場合、債権者は債務者の財産を売却して弁済を受けられることを黙示的に承諾したことを意味します。
よって、上記の原則に基づき、被害者の財産が損害を受けた場合、債権者は自らの権利を守るために私訴を行うことができるというべきです。
もし債権者に私訴権がないとすると、どのようなことになるでしょうか。
一人の富豪に金銭を貸していた人がいるとしましょう。賊が富豪宅に忍び込んで大金を盗んだとします。富豪は、残りの財産を全て売却しても債務を支払えなくなったとしましょう。この場合、債権者は加害者である盗賊に対して直ちに起訴をする権利があります。そのように考えなければ、債権者は債務者をして加害者に対する賠償請求をさせるしかありませんが、何かの理由でこの請求をしなかった場合、債権者は損害を回復することができません。
債権者がただちに加害者に対して賠償の訴えを起こすことができるならば、何ら不都合はありません。
刑法上の観点からいうと、その当否につき問題もありますが、民法上の観点からは全く疑いのないところです。
債務者が身代限りとなった場合に、債権者が直ちにこの権利を行使するのは、我が国で現に実施されていますから、私訴においても同様であるべきです。
被害者の債権者が、私訴を行うのは、財産上の損害に関する場合に限ります。身体や名誉など損害の場合には私訴権はありません。身体や名誉などの場合にまで私訴権があるとすると、適用範囲が際限なくなってしまいます。したがって、私は財産上の場合に限るものと考えております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(第四) 私訴の権利の譲渡を受けた者は起訴をすることができる
訴権は一種の財産とみることができ、被害者がそれを有しているので、その処分は被害者の意思次第です。訴権の譲渡が法律で禁じられていない以上、有形物と同様、譲渡できるということになります。即ち、わが国においては、私訴の売買は禁じられていないので、理論上、譲渡はできるものと解するほかありません。
この点、裁判官が最も注意すべきことは、賠償の金額を定めるにあたっては、寧ろ少額になりすぎても過大になりすぎないようにすることにあります。賠償の金額が常に売買の金額を超える点で決めるようなことになれば、これによってますます濫訴の風潮を招くようになりかねないからです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
小括
私訴を行うことができる人は、次のとおりです:
1. 被害者
2. 被害者の相続人
3. 被害者の債権者
4. 私訴権の譲渡を受けた人
私訴を行うことができる人については、治罪法で明文化しておらず、民法に委ねられています(治罪法第2条には、民法に従い、被害者に属するものとされています)。
以上で、公訴を行うことができる人と私訴を行うことができる人を説明しました。次回からは公訴と私訴を受くべき人について説明します。