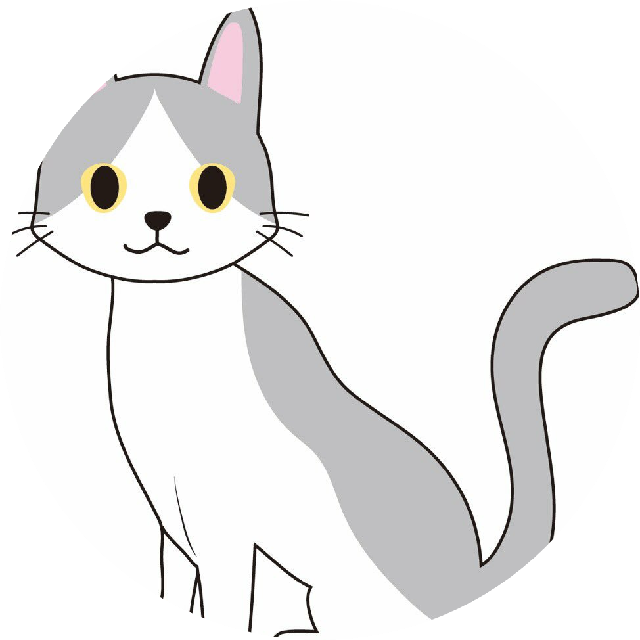橋本胖三郎『治罪法講義録 』・第13回講義
第13回講義(明治18年6月5日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第二款 公訴の抹殺
(緒言)
公訴の抹殺とは、犯罪は成立していても、裁判権を奪却して公訴を許さないことをいいます。
大別すると二種あり、一つは治外法権、もう一つは不問令です。以下、二つの節に分け、第一節では治外法権について説明し(今回)、第二節では不問令について論じます(次回)。
━━━━
第一節 治外法権
今回取り上げる治外法権は、万国で一般的に認められている、欧米諸国で一般的に行われている普通の治外法権です。現在、東洋諸国で行われている不正不当な治外法権についてではありません。
━━━━
(治外法権の種類)
治外法権には二つの種類があります。
第一に外交官の犯罪、第二に内海や港内で起きた犯罪及び軍旗の下にある外国兵士の犯罪です。
━━━━
(治外法権の根拠)
治外法権がどの範囲まで及ぶかについては、各国で違いがありますが、治外法権それ自体は全ての国で認められています。
公訴は、刑罰を科すことを目的としており、刑罰は、一国の安寧(平和)を守るために設けられているものです。よって、犯罪を犯した者には公訴を行う必要があります。
たとえ外国人であっても他国に滞在している間は、その国の法律の保護を受けます。保護を受ける以上、その国の法律を遵守する義務も当然に生じます。一方で利益(保護)を受けるならば、もう一方では羈束(義務)を負うというのが自然の道理です。
そうであるならば、法律上外国人と自国民を区別する必要はありません。「外国人だから法律を守らせる必要はない」とするならば、その国の安寧と秩序を維持することができなくなってしまうでしょう。安寧と秩序を維持することができなくなれば、その国は滅亡するでしょう。
そうならないためには、外国人であってもその国の法律を守らせなければなりません。これが、法律は土地(領域)を支配するという原則です。
この原則は自然の道理に基づくものなので、万国すべてがこれを認めています。古代ローマの時代から世に行われており、欧米の各国もすべて、自国の安寧を守るための法律を外国人にも適用してきました。
これは今日に始まったことではなく、遠い昔から行われてきたことです。
━━━━
(治外法権を論じる理由)
犯罪を罰するには、犯罪が起きた場所で行うことが必要があり、かつ正当です。なぜなら、犯罪が行われれば、多かれ少なかれその地の安寧や秩序が害されるものだからです。その土地で安寧や秩序が損なわれた以上、それを回復する権利はその土地に属します。
犯人が犯罪地を離れ、遠く数千里も離れた場所にいるような場合、その場所で罰する必要はありません。例えば、アフリカのある孤島で罪を犯した者が日本に逃れてきたとしても、日本はその犯罪によって何ら被害を受けておらず、その人物を罰する必要がありません犯罪地であるアフリカの孤島こそが、犯罪を罰する必要性を持ち、またその罰が正当であるとされるべき場所なのです。
以上の理由からは、今日、欧米諸国が東洋諸国に対して治外法権を持つことは、極めて正理に反するものであると言わざるを得ません。
しかし、さまざまな事情から、この不当な治外法権を受け入れざるを得なくなったことは、我が国をはじめとする東洋諸国にとって、深く嘆息せざるを得ない事態です。
この不正で不当な治外法権は、いずれその廃止の日が訪れるでしょう。私はそう信じています。
不正で不当な治外法権については、このくらいとし、一般的な治外法権について説明を進めます。
━━━━
(外交官の不可侵)
まず、外交官の不可侵についてです。
外交官の不可侵(アンビオラビリティ)とは、外交官が他国に駐在している場合でも、自国の法律の保護を受け、駐在国の法律の保護を受けないことを指します。
まるで自国にいるかのように、他国に滞在している間もその国の裁判を受けず、またその国に対して租税を納めないのです。
欧米の学者の間では治外法権それ自体を認めることは一致していますが、「不可侵」の権限がどの範囲に及ぶかについては議論があります。
これは万国公法(国際法)の問題です。万国公法は慣例と道理に基づくものであって、強制力を持ちません。そのため、この「不可侵」のような問題においても、具体的な範囲がいまだ確定していない部分があるのです。
外交官に対して治外法権という特例を設けるのは、各国の相互利益に基づくものです。
使臣を外国に派遣する際に、独立した立場に置かなければ、その使命を全うすることができません。
使臣の役割は、他国に駐在し、自国の主権を代表して、両国間の交際に関する諸般の応接と談判を行うものです。時には駐在国政府の意に反して、自国の意見を主張しなければならない場合もあります。
したがって、使臣を保護し、独立を維持させなければ、その使命を果たさせません。使節が駐在国の干渉や制約を受けるようなことがあれば、自国の主権を代理することは到底できません。
このような理由から、各国は互いにその使臣に治外法権を認めるに至ったのです。
━━━━
(外交官の不可侵の及ぶ範囲)
外交官の治外法権がどこまで及ぶのか、その範囲については議論があります。フランスで説かれている三つの説を簡単に説明します。
第一説は「外交官はすべて駐在国の裁判権から免除され、自国の君主と同等の待遇を受けなければならない」とするものです。
この説では、外交官がどのような行為をしたとしても、駐在国の政府はその行為に干渉せず、ただ傍観するほかありません。行為を黙認することができない場合に、最終的に取れる対応は、その外交官を国外に退去させるだけです。
しかし、この説は極端すぎます。
この説では外交官が駐在国の内部で徒党を組み、国の秩序を乱そうとしたとしても、その本国に対して処分を求めることになってしまいます。このような行為であっても放置すべきだというのは、極端としか言いようがありません。
第二説は「外交官は治外法権に属する。しかし、駐在国に対する内乱の陰謀に加担したり、兵器を扱ってその国の安寧を害する場合には、治外法権の範囲外である」というものです。
これは第一説に例外を加えたものといえます。駐在国に対する内乱の陰謀やその国に対する兵器の使用といった行為については、外交官の特権を放棄したとみなし、その者を外交官として扱わず、外寇(外部からの侵略)とみるべきだとする考えです。
外交官が駐在国に対して罪を犯した場合には、その国は正当防衛権を行使して国の安寧を守ることができる、ともいえます。
第三説は、前の二つの説とは趣旨を異にします。国家に対する犯罪だけでなく、殺人、放火、強姦等にかかる現行犯の場合には、治外法権として扱わないとする説です。こうした場合には外交官としての資格を失ったものとみなし、通常の外国人と同じように扱うべきだという考え方です。
私は第三説が最も正当であると信じています。たとえ外交官であっても、人を殺し、あるいは強姦というような暴行を行う場合には、それは国家の安寧を損なうものであり、ただちに逮捕して処罰するのは当然です。
しかし、この説にも弱点があります。処罰をどこまで及ぼすべきか、その範囲を定めるのが極めて難しいからです。
━━━━
(外交官の治外法権の及ぶ人的範囲)
外交官とは特派全権大使、全権大使、全権公使、弁理公使など、国の政府を代表するすべての使節を総称したものです。これらの者はすべて治外法権に属し、特別な待遇を受けるべきです。
公使館附書記官や外交官の家族、その使用人や従者も治外法権の特例の対象とすべきです。その理由は、たとえ外交官に特例があったとしても、その付属者に特例の適用がなければ、外交官自身が独立性を保つことができなくなるからです。
━━━━
(外交官の使用人について)
以上が、使用人に至るまで治外法権の特例を及ぼすべき理由ですが、使用人が内国人(国内の人間)であるか外国人であるかによって、区別する必要があります。
使用人が内国人(国内の人間)である場合には、その国の裁判権が及ぶべきであることは当然です。外国の公使に雇われているという理由だけで治外法権が与えられる道理はないからです。もっとも、内国人の使用人を処分する場合には、必ず公使の同意を得る必要があります。これは一般的な慣例です。
使用人が外国人である場合には、その国の裁判権を適用しないのが慣例です。
もっとも、外国人であってもその国の裁判権を適用すべきだとする見解もあります。この説では、使用人が殺人、放火、強姦などの重大な罪を犯した場合、公使はこれを黙認することはできず、処分を受けさせるために、その使用人を本国に送還する手続きを行わなければならなくなりますが、使用人を本国へ送還するには費用がかかり、逃亡などの懸念もあるため、むしろ駐在国の裁判所に処理を委ねるほうがよいとも説かれています。
━━━━
(領事について)
領事は公使と同じように扱うべきでしょうか。この問題に関してはさまざまな議論があり、いまだ結論は定まっていません。
著名なファースターンエリー氏は、「領事は外国に滞在する自国民やその商業活動を保護する役割を持つ者であり、公使のように自国を代表する者とは大きく異なる。したがって、裁判における扱いも異なるべきである。たとえば、軽罪を犯した場合に直ちに逮捕や未決勾留を行うべきではないが、重罪を犯した場合には、一般の人々と同様に処分すべきだ」と説いています。
「領事は重大な犯罪を犯した場合を除いて、すべて公使と同等の待遇を受けるべきである」との説もあります。この説は、1814年にフランス外務省が「領事は重大な犯罪を除き、公使と同等の待遇を受けるべきである」と通達したことを根拠としています。
外国公使に関する事項については、日本にも規程があります。明治7年9月の第128号公達第1条には「外国公使は我が国憲に拘束されるべきではないのが原則であり、この原則を拡張し、公使の家族および公使館職員、その家族、さらには車馬に至るまで同様と考えられるべきである」と規定されています。
━━━━
(内海および港内における犯罪〜内海の意味)
以上、外交官の不可侵について述べました。次いで、内海および港内における犯罪について説明を進めます。
内海とは、陸地と同じく領土の一部を構成するものであり、これには二つの種類があります。
一つは、陸地から弾丸が届く最遠距離に至る海岸線であり、もう一つは通常の内海です。この二種類の内海はいずれも国家の所有権が及ぶ範囲とされます。内海および港内は、十分に取締りを行うことが可能であり、必要に応じてこれを閉鎖したり、砲台を築いたり、軍艦を配置して守ることができます。
しかしながら、これを領土とするためには、取締りできる実力を有することを要します。万国公法では「封鎖がもし実力を伴わないときは、効力を持たない」といわれており、実力が必要であることを指摘しています。
かつてあるロシア人が、「横浜港には十分にこれを取り締まるための兵備、すなわち実力が備わっていない。したがって、この港は日本の領土外と言うべきである」といったということです。この発言の妥当性については、ここでは論じませんが、このことからも、取り締まりの実力が必要であることを知るべきです。
━━━━
(大洋の中で犯罪が発生した場合)
大洋の中で犯罪が発生した場合は、すべて船舶の所属国の法律によってこれを処理するのが原則です。例えば、フランスの便船に乗り、大平洋を航行中に、船内で犯罪を犯した者がいた場合、その者はフランスの法律に基づいて処罰されることになります。
もっとも、船内での犯罪に関しては、各国がほぼ例外なく別個の法律によってその処罰方法を定めているようです。
━━━━
(内海での犯罪が発生した場合)
内海で犯罪が発生した場合はどうなるのでしょうか。フランスの法律では、フランス港内に停泊している外国商船内で起きた犯罪を処理する際、次のように処理されます。
犯罪が港内の安寧を害さない限り、その処理は船内の規律に委ねられ、フランスの法律を適用しません。例えば、マルセイユ港内に停泊しているイギリス船の中で暴行等の犯罪が起きた場合でも、フランスの司法官はこれに干渉することはありません。船内においては船長が司法権を有していますし、その港にイギリス領事がいれば、その領事がこれらの問題の処理を行うことになっているからです。
しかしながら、重大な犯罪であり、かつ港内の安寧を害する場合は、フランスの法律が適用されます。
もっとも、その裁判権がどこまで及ぶべきかについては明確な規定がなく、港内の安寧を害する程度の大小によってどちらの国の法律を適用するかが判断されます。
要するに、港内での犯罪は基本的にその国の法律によって処理されるべきですが、些細な事件については干渉しない、ということです。
━━━━
(軍艦の犯罪)
軍艦は商船とは異なり、その所属国の法律の適用を受けるものであって、外国の法律を適用すべきものではありまそん。軍艦というものは、その本国の国権の一部であり、艦内には官署が備えられています。
軍艦にその停泊地の法律を適用すべきとすれば、他国の主権を支配するという結果を生じてしまいます。これは国家間の主権の原則に反します。
このように、軍艦は完全に治外法権の対象とされていますが、しかし、軍艦による暴力的な行為があった場合には、処分をしないわけにはいきません。
検疫規則を破って航行した場合がその例としてあげられるでしょう。その外にも、軍艦が敵対的な行動を取る場合には、こちらもそれに対抗すべきことは当然のこととされています。
━━━━
(軍艦の乗組員の犯罪)
軍艦内で外国人が罪を犯した場合、軍艦の所属国の法律が適用されて処分が行われます。これが軍艦と商船との大きな違いです。
もっとも、その乗組員が上陸してから罪を犯した場合には、その土地の法律によって処罰されるべきであることは言うまでもありません。
━━━━
(外国軍旗の下にある兵士の犯罪)
外国軍旗の下にある兵士の犯罪については、軍艦が治外法権を有する理由とほぼ同じですので、繰り返しません。
━━━━
(終わりに)
以上で治外法権についての説明を終えます。
次回は「不問令」について説明を行います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━