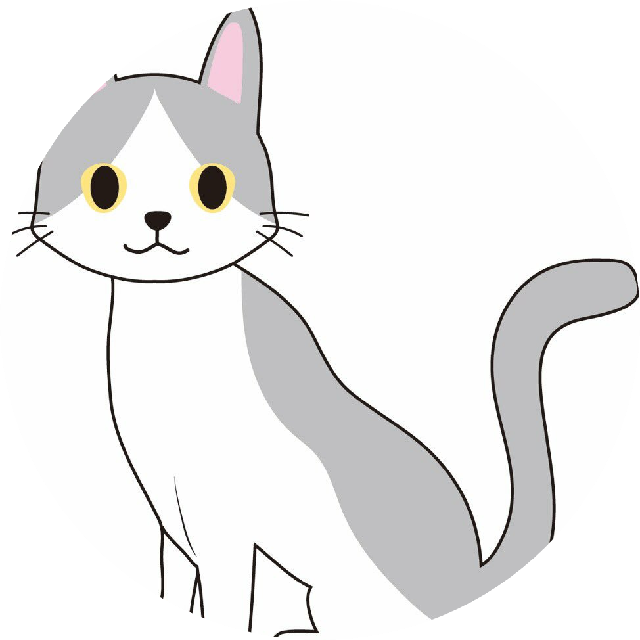橋本胖三郎『治罪法講義録 』・第八回講義
(明治18年5月15日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(はじめに)
本日は第二款「私訴の施行に関する規則」から説明致しましょう。
━━
第二款「私訴の施行に関する規則」
(付帯私訴が許される理由)
判決を行う権限は民事裁判所及び刑事裁判所に属します。民事事件は民事裁判所で担当し、刑事事件は刑事裁判所で担当します。
このように民刑という二個の裁判所があるのですから、刑事事件の公訴は刑事裁判所に行い、私訴は刑事事件を契機として起こった場合でも、民=民の争いですから、民事裁判所に提起することになるはずです。
しかし、法律上特に私訴 を刑事裁判所に提起することが許されています。その理由は次のとおりです。
①公訴と私訴の証拠を共通とすることができる
②公訴と私訴を同じ裁判所で裁判することで、事務が簡便となり、公訴と私訴の裁判に齟齬がなくなる
③民事の原告人を保護するという観点からも、公訴に付帯して私訴を行うことを認めた方が良い。
民事と刑事の2つの訴えが同時に別の裁判所に提起された場合、民事裁判所では刑事裁判が終わるまで裁判を中止せざるをえません。そのため、民事の原告人は刑事判決があるまで待たされることになります。被害者に一日でも早く損害を回復させるためには、公訴に付帯して私訴を行うことを認めた方が良いのです。
さらに、④私訴を刑事裁判所に提起することを認めると、民事の原告人は検察官を助けて証拠を提出し、それによって犯罪を証明し確実なものとすることができるという利点もあります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次に、私訴の施行に関する規則を三節に分けて説明しましょう。
第一節 民事原告人は裁判所選択権があること
犯罪によって損害を受けた者は、民事裁判所と刑事裁判所のどちらかを選んで訴える権利があります。このような選択権があることは、民事原告人にとって利益ですが、民事原告人が刑事裁判所で訴えを起こす際には、一定の制約があります。それは公訴に付帯させる必要があるということです。
民事原告人が刑事裁判所に私訴を行うには公訴と分離独立してこれを行うことはできず、公訴に付帯してしなければなりません。
━━
(付帯私訴の方法)
付帯私訴を行うには2つ方法があります。1つは検察官の起訴がある時に、私訴の申立て行う方法、もう1つは予審判事に対して私訴の申し立てをすることです。
民事原告人が刑事裁判所に私訴を行うときは、通常民事裁判所の事物管轄に制約されません。治罪法第4条に「私訴はその金額の多寡に拘わらず公訴に附帯して刑事裁判所にこれを為すことを得」との規定があるからです。
━━
(民事裁判所の事物管轄と付帯私訴)
民事裁判所の事物管轄は次の規定があります(明治14年12月第83号布告)。
第2条「治安裁判所は請求の金額及び価額100円未滿の訴訟に付き始審の裁判を為す」
第4条「始審裁判所は請求の金額及び価額100円以上並びに第3条に揭げる治安裁判所権外の訴訟につき始審の裁判を為す」
以上のように、民事訴訟では金額100円以上となると、治安裁判所に訴えを提起できません。
しかし、刑事事件での付帯私訴ではこの制限を受けず、損害の金額100円以上であっても違警罪裁判所(治安裁判所)に提起できます。また民事訴訟では金額100円未満のものは始審裁判所に訴えを提起することができませんが、刑事事件では損害額が100円未満であっても、軽罪裁判所(始審裁判所)に提起できます。
このように刑事裁判所に付帯私訴を提起する場合は、通常民事裁判所の事物管轄の制限を受けません。
━━
(付帯私訴ができない刑事裁判所)
もっとも、例外はあります。治罪法第4条但書が「法律においてその裁判所に私訴を為すことを許さない場合はこの限りにあらず」と規定されめいるとおりです。「私訴を為すことを許さない場合」とは、次のものです。
①陸軍治罪法第1条第2項「軍法会議は刑事付帯の民事を受理せず」
②海軍治罪法第1条「海軍軍人の犯した重罪・軽罪は軍法会議においてこれを審判す。軍法会議は刑事付帯の民事を受理せず」
現行法では例外はこの2つですが、治罪法第4条に「私訴を為すことを許さざる場合はこの限りにあらず」とあり、後日法律で規定されることが予定されていると見ることができます。
━━
(フランスにおける例外)
フランスでは、これ以外にも私訴ができないものがあります。会計官吏の犯罪です。
日本では会計官吏の犯罪は、他の犯罪と同様に通常裁判所で審判しますが、フランスでは会計検査院が審判し、通常裁判所には管轄がありません。
━━
(軍事裁判所で付帯私訴を認めない理由)
陸海軍裁判所が付帯私訴を許さないのは、軍事裁判所が厳格を主とすることから、私訴の審判に適さないからです。また、軍人が裁判官を務めることからは、民間の争論を判決するに適さないのです。
━━
(高等法院で付帯私訴を受理すべきか)
高等法院では、付帯私訴を受理すべきでしょうか。このような問題が起こることは稀有ではありますが、法的には重要な問題です。
治罪法第91条には、「高等法院の訴訟手続きは、通常の規則に従う」と規定され、また、同法第4条には「その裁判所に私訴をなすことを許さない場合はこの限りではない」と規定されており、高等法院に私訴を許さないとの規定は存在しません。そうしますと、条文上からは高等法院でも私訴を受理することは可能なように見えます。
しかし、私は法理論上の理由から、高等法院での私訴は許されないと考えます。高等法院は、通常裁判所とは異なります。審判事項は皇族・貴顕の犯罪及び国事犯であり、いずれも一国の大事件です。また、高等法院では大審院判事及び元老院議官が裁判官となります。このように高等法院は特殊であり、皇族・大臣の犯罪及び国事犯のような大事件を審判するのは通常裁判所の適任ではないので、一種特別の裁判所を設けたといえるでしょう。
このような裁判所で、一私人の争論に過ぎない私訴を審判するのは当を得ないものと考えます。それだけでなく、私訴の審判をなすことは、高等法院の尊厳を冒涜するものともいえます。高等法院を設けた趣旨からして、一私人の争論の審判といったような瑣事を任せるべき機関ではありません。よって、条文上は高等法院に私訴を提起することが禁止されていなくても、法理論上の理由から高等法院には私訴を提起できないと考えざるを得ません。
この点フランスはどうかといいますと、日本と同じく治罪法中には明文の規定はなく、通常裁判所の原則を適用するか否か解決がついておらません。この点の裁判例もありません。
━━
(私訴移転ができるか)
私訴は、民事刑事どちらの裁判所を選んで提起してもよいのですが、一度どちらかの裁判所を選んで提起した場合に、他の裁判所に私訴を提起することができるかという問題があります。
ローマ時代には、一度どちらかの裁判所を選んで提起した場合には、他の裁判所に訴えの提起をすることは許されませんでした。
フランス法では、この点についての明文がなく、どのように解すべきか問題となっています。
我が国では、この点明文をもって規定していますが、その規定の趣旨について知るためには、往古に遡って検討する必要があります。
━━
(ローマ法及びフランスでの考え方)
ローマ法では「ひとたびある道を選んだときは、他の道は閉ざされてしまう」との格言に基づき、一度どちらかの裁判所を選んで提起した場合には、他の裁判所に変えることはでき混ぜんでした。
フランスでは、法学者の間で説が分かれています。
第一説はローマ法と同様、 一度どちらかの裁判所を選んで提起した場合には変更はできないとするものです。
第二説は、当初民事裁判所に訴えを提起したときは、刑事裁判所に訴えを提起することはできないが、先に刑事裁判所に訴えを提起した場合は、改めて民事裁判所に訴えることができるとしています。
第一説は次のように考えるものです。
「もともと人には選択の自由があり、法律がこれを禁じてない以上は、人がその欲するところに従い、変更することは自由である。しかし、法律手続きにおいてはこのような自由を許すべきではない。よって、一度ある裁判所に訴えを提起したときは、他の裁判所に訴えを提起することはできない」
第二説は次のように考えるものです。
「刑事裁判所は厳格な性質をもっているが、民事裁判所は緩容な性質をもっている。被告人の立場からみて、緩から厳に移るのであれば、被告人の権利を害することはないが、厳から緩に移るのであれば、被告人の権利を害するおそれがない。よって、刑事裁判所から民事裁判所に移すことは許されるが、民事裁判所から刑事裁判所に移すことを許されない。」
━━
(日本の治罪法の規定)
我が国の治罪法は次のように規定しています。
第7条第1項「民事裁判所に私訴を行ったときは、検察官の起訴があるときでなければ、願下げを行って、刑事裁判所にその訴えを提起することができない」
第2項「刑事裁判所に私訴を提起したときは、被告人の承諾を得て願下げをなして、民事裁判所にその訴えを提起することができる」
このような規定としたのは妥当と考えられます。
━━
(民事裁判所から刑事裁判所への私訴移転)
裁判所から刑事裁判所に訴えを移すことができるのは、検察官が起訴を行った場合に限ると規定されていますが、これは被告人の利益のためです。なぜなら、民事裁判所で訴えが提起されている途中で、刑事訴訟が開始されると、民事訴訟は中止となり、刑事裁判の終了を待たなければならないからです。
これを刑事裁判所に移すことができるとすれば、原告と被告の双方がその権利を保護できるのはもちろんのこと、同時に付帯する事件を裁判することができますので、被告人にとって利益は少なくありません。
━━
(刑事裁判所への私訴移転の利点)
さらに、検察官が起訴を行ったことで、刑事裁判所に私訴を移すことができる利点としては次の3点があります。
①被告人は少なくとも一度は法廷に出ざるを得ず、出廷回数を減らすことができること
②検察官が犯罪を証明するのに、原告人の援助を得ることができること
③同一の事件を同一の裁判所で審判することにより迅速かつ簡便な処理ができること
━━
(刑事裁判所から民事裁判所への付帯私訴の移転)
また、一度刑事裁判所に私訴を行ったときは、
被告人の承諾がなければ、私訴を民事裁判所に移すことはできません。これは、民事原告人の意向だけで、被告人に不利益を与えることを防ぐためです。
原告人が当初刑事裁判所に付帯私訴を提起したのに、これを民事裁判所に移すというのは、刑事裁判所の審判が自分に不利だと判断するからでしょう。このようなことを許すと、被告人の不利益となるため、一旦刑事裁判所で私訴を提起した場合は、被告人の承諾がなければ、民事裁判所に訴訟を移すことはできないと規定したのです。
被告人が移転を承諾する例としては、刑事裁判の審理が遅延する等、刑事裁判所での審理が不適当だという被告人が考える場合には、民事裁判所に移すこと場合が考えられます。
以上、原告人がその訴訟を民事裁判所から刑事裁判所に移す場合、また刑事裁判所から民事裁判所に移す場合の詳細について説明しましたので、諸君も理解されたことでしょう。
━━
(治罪法第7条の適用要件)
このことから考えるに、治罪法第7条は私訴移転の制限法ということになります。原告人の立場からみると、権利を制約することになります。
原告人に治罪法第7条を適用するのは次の三要件が必要です。
①訴訟の目的が同一であること
②訴訟の原因が同一であること
③訴訟人が同一であること
以上の三つの要件を満たさない場合、原告人には治罪法第7条を適用することができません。以下例を示します。
━━
(第一の例 離婚と損害賠償請求)
第一の例として、犯姦罪(姦通罪)のケースをとりあげます。
夫が姦婦(妻)に対して賠償を求め、その後離婚を請求した場合はどうでしょうか。この場合、原因と訴訟人は同一ですが、目的が大きく異なります。つまり、一方は離婚を求め、もう一方は損害賠償を求めているのです。このように目的が異なる場合は、治罪法第7条を適用する要件を満たしていません。よって、離婚請求を民事裁判所に訴えることは、被告人の承諾を必要としません。
民事裁判所で離婚を訴えた後に、刑事裁判所で損害賠償を求めた場合はどうでしょうか。
この場合は、検察官が起訴していなくても、原告人は公訴を提起することができます。訴訟の原因と訴訟人は同一ですが、その目的が異なるため、治罪法第7条を適用することはできないからです。
━━
(第二の例 委託物返還請求と財産犯)
第二の例として、民事裁判所で委託物の返還を求める訴訟を行っており、その審理中に詐欺による財産取得や寄託財産に関する犯罪であることが分かった場合について考えてみます。
この場合も、検察官が起訴するのを待たずに、公訴を提起することができます。
訴訟の目的と訴訟人は同一ですが、その原因が異なり、治罪法第7条を適用することができないからです。
━━
(第三の例 民事担当人への請求と本人への請求)
第三の例として、民事裁判所で民事担当人に対して損害賠償を求め、刑事裁判所で犯人に対して私訴を提起する場合を考えてみます。この場合、訴訟の目的と原因は同一ですが、訴訟人が異なるため、治罪法第7条を適用することはできません。
━━
(まとめ)
このように、治罪法第7条を適用するためには、訴訟の目的、原因、および訴訟人すべてが同一である必要があります。この三つの要件のいずれかが異なる場合には、同条を適用することはできません。
治罪法第7条についての説明は以上です。
民事原告人が刑事裁判所で私訴を提起することの可否については、次回お話し致します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━