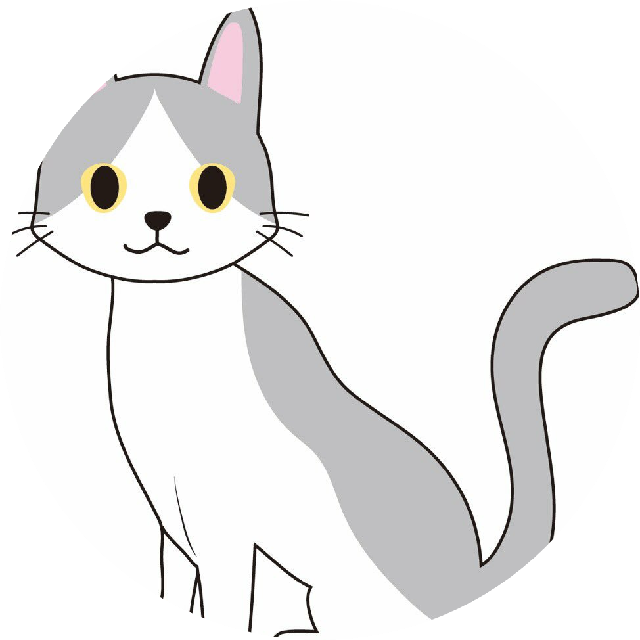子どもの虐待関係での実務的な解説書として、「子どもの虐待防止・法的実務マニュアル」(明石書店;日本弁護士連合会子どもの権利委員会編)という本があることを知りました。改訂を重ねて、第6版まででております(2017年)。
弁護士という視点からだと、この本、児童相談所のインハウスローヤーには大変役立つだろうなあと思うのですが、例えば、児童相談所から虐待をされたと疑われている親からの依頼にはそのままは使えないと感じました。
・子どもの権利委員会が編集者なので、現に起きている虐待からいかに防止するかという視点が主体です。
親は虐待の加害者として描かれているといって良いでしょう。
そのため、親を依頼者とする場合は、この本の目線で対応することは不適切になってくるかと思います。
・この点をもう少し詳しく述べますと、本書は「はじめに」で次のように書いています。
「子どもたちを虐待被害から守るとともに、虐待被害を受けた子どもの回復や自立を支援するためには、児童相談所を中心にしながら、弁護士を含む法律家、自治体職員やNPOなど、さまざまな職種の大人がそれぞれの役割を従前に果たすことが、ますます求められているといえるでしょう。」
「児童相談所を中心にしながら」というのは法制度上はそのとおりです。
しかし、児童相談所も人が運営する組織である限り、過誤が紛れ込む可能性は十分あり、批判的視点が必要なはずですが、本書には児童相談所への批判的な視点が見受けられません。
親が依頼者となる場合は、なんかの形で児童相談所に不満を有していると思われます。
その不満をいかに掬い取って依頼者の正当な利益に結びつけるかが弁護士にとって求められるものですが、本書を読むだけではそのような発想はほとんど得られないものと思われます。
・本書は親についての記述がないわけではなく、例えば、「再統合」という表題で親へのアプローチが述べられてはいます。
しかし、その視線は、親によりそったものとは言えないように感じられます。
例えば、本書では、再統合に向けた取組について、家族が支援を受けることの動機づけをあげ、「虐待を行った親に対する援助の効果をあげ、虐待の再発を防ぐためには、親が虐待の事実を認知しかつ児童相談所の援助を受ける動機づけが必要である」との記述をしております。正論ではありますが、これをそのまま弁護士が依頼者である親に述べたとしても、ほとんど何の効果も得られないでしょう。否、下手をすると、弁護士に対して反感を持たれかねません。
親が虐待の事実を認めること、児童相談所の援助を受けようという気になるためには、場合によってはかなりの時間と忍耐が必要となります。
そのためには、親が抱える問題点への洞察が必要です。
しかし、本書ではこの点は驚くほどクールに書かれているだけです。
「虐待が発生する要因、親の抱えている問題にはさまざまなものがあるところ、それらの問題を理解し、解決するため、他機関と連携して、福祉サービスの提供、治療期間等の紹介などの必要な手立てを講じ、親が経済的、社会的、心理的にもゆとりを取り戻せるようにしなければならない。」
本書の立場はこの記載に集約されているように思われます。
ここでも正論ではありますが、そこに至るプロセスや親がそのような問題を抱えるに至ったことへの配慮は何らされておりません。
・翻って考えてみれば、これが弁護士の書いた「マニュアル本」主義というものの弊害なのかもしれません。
世にいう弁護士向けのマニュアルは、法律上の制度を実務的に解説したものをいいます。
法律上の制度を述べていくため、問題がもつ法律上の意味以外を捨象していくきらいがあります。
ビジネス法務であれば、それもまた良いかもしれません。
しかし、児童虐待でいえば、なぜ虐待が起こるのかという点についての社会学的問題はカットされ、その点への洞察を得られるような記載もないことで良いのでしょうか。
これが「マニュアル」本の弊害でもありますので、この点についてはくれぐれも注意する必要があるような気がしました。
弁護士という視点からだと、この本、児童相談所のインハウスローヤーには大変役立つだろうなあと思うのですが、例えば、児童相談所から虐待をされたと疑われている親からの依頼にはそのままは使えないと感じました。
・子どもの権利委員会が編集者なので、現に起きている虐待からいかに防止するかという視点が主体です。
親は虐待の加害者として描かれているといって良いでしょう。
そのため、親を依頼者とする場合は、この本の目線で対応することは不適切になってくるかと思います。
・この点をもう少し詳しく述べますと、本書は「はじめに」で次のように書いています。
「子どもたちを虐待被害から守るとともに、虐待被害を受けた子どもの回復や自立を支援するためには、児童相談所を中心にしながら、弁護士を含む法律家、自治体職員やNPOなど、さまざまな職種の大人がそれぞれの役割を従前に果たすことが、ますます求められているといえるでしょう。」
「児童相談所を中心にしながら」というのは法制度上はそのとおりです。
しかし、児童相談所も人が運営する組織である限り、過誤が紛れ込む可能性は十分あり、批判的視点が必要なはずですが、本書には児童相談所への批判的な視点が見受けられません。
親が依頼者となる場合は、なんかの形で児童相談所に不満を有していると思われます。
その不満をいかに掬い取って依頼者の正当な利益に結びつけるかが弁護士にとって求められるものですが、本書を読むだけではそのような発想はほとんど得られないものと思われます。
・本書は親についての記述がないわけではなく、例えば、「再統合」という表題で親へのアプローチが述べられてはいます。
しかし、その視線は、親によりそったものとは言えないように感じられます。
例えば、本書では、再統合に向けた取組について、家族が支援を受けることの動機づけをあげ、「虐待を行った親に対する援助の効果をあげ、虐待の再発を防ぐためには、親が虐待の事実を認知しかつ児童相談所の援助を受ける動機づけが必要である」との記述をしております。正論ではありますが、これをそのまま弁護士が依頼者である親に述べたとしても、ほとんど何の効果も得られないでしょう。否、下手をすると、弁護士に対して反感を持たれかねません。
親が虐待の事実を認めること、児童相談所の援助を受けようという気になるためには、場合によってはかなりの時間と忍耐が必要となります。
そのためには、親が抱える問題点への洞察が必要です。
しかし、本書ではこの点は驚くほどクールに書かれているだけです。
「虐待が発生する要因、親の抱えている問題にはさまざまなものがあるところ、それらの問題を理解し、解決するため、他機関と連携して、福祉サービスの提供、治療期間等の紹介などの必要な手立てを講じ、親が経済的、社会的、心理的にもゆとりを取り戻せるようにしなければならない。」
本書の立場はこの記載に集約されているように思われます。
ここでも正論ではありますが、そこに至るプロセスや親がそのような問題を抱えるに至ったことへの配慮は何らされておりません。
・翻って考えてみれば、これが弁護士の書いた「マニュアル本」主義というものの弊害なのかもしれません。
世にいう弁護士向けのマニュアルは、法律上の制度を実務的に解説したものをいいます。
法律上の制度を述べていくため、問題がもつ法律上の意味以外を捨象していくきらいがあります。
ビジネス法務であれば、それもまた良いかもしれません。
しかし、児童虐待でいえば、なぜ虐待が起こるのかという点についての社会学的問題はカットされ、その点への洞察を得られるような記載もないことで良いのでしょうか。
これが「マニュアル」本の弊害でもありますので、この点についてはくれぐれも注意する必要があるような気がしました。