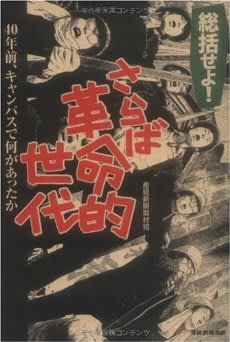 大学1年生の秋、学内でひとりの大学生が内ゲバで襲われた。現場を目撃したサークルの先輩情報だったので詳細は不明だったが、大学という学び舎で白昼堂々と暴力行為が多くの学生がいる中で行われたということに衝撃を受けた。しかも、被害者は友人だったかも知れない同じ大学生。私が入学した時は、学生運動はとっくに衰退していたが、授業料値上げでロックアウトにより試験がレポート提出となったり、ヘルメットをかぶった人がビラを配り、タテカン、某政党に所属するカオも頭も育ちもよい学生が授業がはじまる前にやってきて話をするオルグ活動もあった。またそういう大学でもあった。昔のよど号ハイジャック事件、あさま山荘事件、内ゲバ、何も知らなかったが、何も知らないだけに学生運動に対して恐怖心と嫌悪感が残されたのが、60年代以降の三無主義のシラケ世代。考えてみれば、催涙ガスをあびることもなくまともに授業を受けられて運がよかったのか、全共闘世代の負の遺産に去勢されながらも残り香をかいだために、次の個人主義的な享楽を求める世代とも価値観があわず、私たちって不運な谷間の世代なのだろうか。
大学1年生の秋、学内でひとりの大学生が内ゲバで襲われた。現場を目撃したサークルの先輩情報だったので詳細は不明だったが、大学という学び舎で白昼堂々と暴力行為が多くの学生がいる中で行われたということに衝撃を受けた。しかも、被害者は友人だったかも知れない同じ大学生。私が入学した時は、学生運動はとっくに衰退していたが、授業料値上げでロックアウトにより試験がレポート提出となったり、ヘルメットをかぶった人がビラを配り、タテカン、某政党に所属するカオも頭も育ちもよい学生が授業がはじまる前にやってきて話をするオルグ活動もあった。またそういう大学でもあった。昔のよど号ハイジャック事件、あさま山荘事件、内ゲバ、何も知らなかったが、何も知らないだけに学生運動に対して恐怖心と嫌悪感が残されたのが、60年代以降の三無主義のシラケ世代。考えてみれば、催涙ガスをあびることもなくまともに授業を受けられて運がよかったのか、全共闘世代の負の遺産に去勢されながらも残り香をかいだために、次の個人主義的な享楽を求める世代とも価値観があわず、私たちって不運な谷間の世代なのだろうか。しかし、そもそもあの時代、40年前のキャンパスで何が起こったのか。時代をゆるがすような盛り上がりをみせた運動が急に沈静化していった理由は。本書は、全共闘運動を知らない30代の産経新聞記者による時代の証言者のインタビューを集めた一冊である。
革命家・重信房子、元日大全共闘議長の秋田明大、赤軍派議長だった塩見孝也、作家の三田誠広や立花隆、西部邁、あさま山荘事件で広報担当幕僚長だった佐々淳行、数多くの発言が並ぶが、所謂著名人でない市井の人になった方は、ほぼ全員匿名希望だったのが印象に残る。
バリケードの外から見ても本当に革命が起こるのではないかという盛り上がりに命がけだったと語る人もいれば、女にもてたかったと語るものがいる。課長、島耕作だったらファッションとして関わるだけ。どちらも正直な感想であり、だから盛り上がりもあったのだろう。無責任にノスタルジックにひたれるのはつつがなく社会生活にスライドできたからであろうか、トップレベルの国立大学に進学しながらずっと社会的には不遇な暮らしを送りつつも、今でも無血革命の理想を追い求める老いた戦士も登場する。ただ、様々な証言からうかんできたのは、当初の学生運動の動機は、誰もが共感できるしごくまっとうなものだったということだ。インテリが集まる東大で大学解体を掲げる賢い学生の反乱だとしたら、日大闘争は間違ったことにおかしいと言っただけの百姓一揆。実際、安田講堂攻防戦を指揮した佐々淳行さんは、68年に日大使途不明金問題の捜査でロッカーから一杯に積まれた2億円もの札束!を発見するという事件に遭遇した。日大価格は、学生に1点1万円、裏口入学の相場が800万円だったそうだ。警察側の佐々さんですら、日大で、秋田明大の演説に心を打たれ、「言っているとおりだったんだよ。彼らの怒りは当たり前だった」と百姓一揆のそれなりの理由に同調している。労働者をはじめとした、社会市民の理解をえられたのも初期の頃だった。
間違ったことに疑義を唱え、改善を要求した学生による大学改革が、いつのまにか一部の尖鋭部隊によって世界革命という大層なことに向かい、またきわめて残酷なる内ゲバ闘争に向かっていたのか。映画監督で『実録・連合赤軍』を撮った若松孝ニさんによると「集団があると権力者が生まれ、権力を握った者はそれを守ろうと内向きに攻撃をはじめる。相撲部屋のリンチが起きたように、どんな組織でもおこりうる」そうだ。一般的なノンセクトの活動家だったが、理系の知識を頼られかかわるうるに実行犯になったHさん(本書では実名)の、周囲がより厳しい状態に追い込むことで本人が成長できる発想は、社員教育や体育会にもそうした風潮があり、あの時は制裁ではなく教育のためという考え方に陥っていたという証言は、いかにも日本的で印象に残る。
その一方で、多くの学生はヘルメットを捨て、長髪を切り、Gパンからダークスーツの資本主義の企業戦士へと転向していった。(そういえば、内ゲバ事件を目撃した先輩の好きな歌がユーミンの「いちご白書をもう一度」だった。)長年、彼らの変わり身の早さと合理的な考えが謎だったのだが、哲学者ヘルベルト・マルクーゼの「体制の外側からの革命ではなく、体制に身を置いて理想を実現せよ」とうダブルスタンダードの高等戦術でわりきれることを理解した。なるほど、この理論だったら私だって革命家として企業に潜伏していると考えることができる。しかし、ノンポリの立場を貫きこだわった大塚将司さんによるとその後動きだした気配もなく、実は体現すべき自己がなかったのではないかという厳しい批判も伴う。組織の中で闘う学生運動の構図に慣れた人たちにとって、むしろそのままカイシャという組織の中に所属することは何ら違和感がなかったのではないかとも想像する。
本書は予想外におもしろかったのは、取材した人は100人以上というそれぞれの人のそれぞれの総括?に考えさせられるものがあったからだろうか。それでもいまだに総体としてひとことではとらえることができないのもあの時代だ。
「おいしいところだけもっていった彼らは、時代の熱狂と自分たちの青春時代が偶然にも一致した幸福かつ不幸な世代」(鴻上尚史)
「誰もが他者のことを考えるかけがえのない”われらの時代”」(川本三郎)
あらためて私も問いたい、彼らが社会から引退してしまう前に、総括せよ!











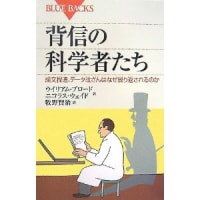

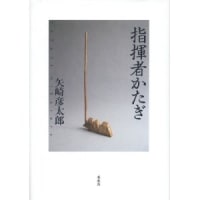
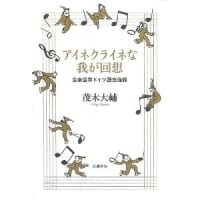
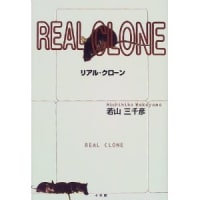
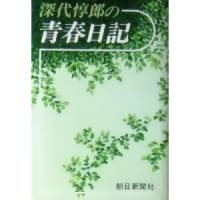
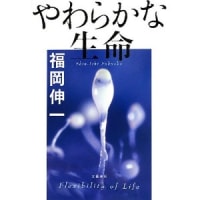
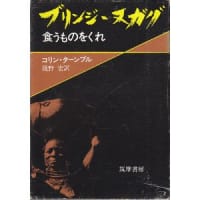
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます