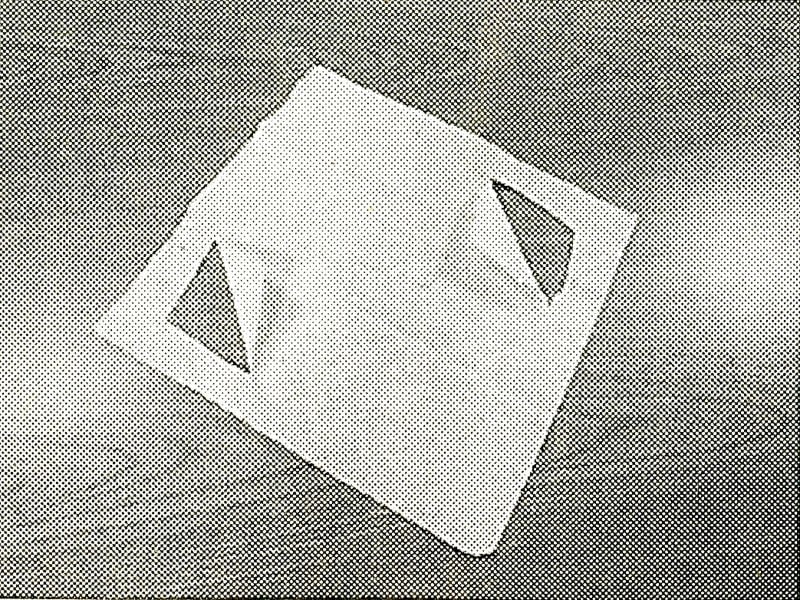東日本大震災・福島原発事故9年 教訓なき原子力政策
東京電力福島第1原発事故から9年。いまだ収束の道筋も見えないなか、政府は原発再稼働を進めています。「事故の教訓が原子力政策に生かされていない。このまま無責任体制が続けば“第二の福島事故”が起こるに違いない」と警鐘を鳴らす、核・エネルギー問題情報センターの舘野淳事務局長(核燃料化学)に聞きました。(中村秀生)
核・エネルギー問題情報センター事務局長 舘野淳さん
すでに10年近くがたつというのに、事故の教訓を現実の原子力政策にどう反映させるのかーという総合的な検討がされていません。
事故現場は、1~3号機の溶け落ちた核燃料デブリが取り出せず四苦八苦しています。当然、重大な事故が発生した場合、万一の炉心溶融に備えなければいけません。
溶けたものが原子炉格納容器の底に落下するとコンクリートと反応してガスが発生し、爆発を起こす可能性が指摘されています。大量の水の中に落ちた場合には水蒸気爆発の可能性があります。
たとえ炉心が溶けても、耐熱性の材料で受けとめる設備「コアキャッチャー」を設置すれば、ある程度は制御できます。これを設置した原発が、欧州などで開発されています。
しかし日本では、これだけ福島の事故で苦労しているのに、規制基準でコアキャッチャーは必要ないということになっています。

原子力規制委員会が再稼働の前提となる審査でOKを出した東海第2原発。自治体が避難計画を策定することになっている30キロ圏内には約96万人が居住=2月19日、茨城県東海村(本紙チャーター機から山形将史撮影)
【妥協】
原子力規制委員会では個々の原発の技術的検討は行っています。ただ実現可能な工事は求める一方、本格的改造を伴う困難な工事やコストが高い工事については口をつぐんでいます。局所的な安全性だけに帰着させた「現実妥協的な審査」で、再稼働が進められているのが現状です。
事故時の避難計画も規制対象外だとして、目をつぶっています。福島では、お年寄りや入院患者が避難のときに亡くなりました。事故の最大の教訓の一つですが、生かされていません。周辺の人口が多い東海第2原発(茨城県)では、事故時の避難などとても不可能ですが、再稼働に“OK”を出しています。
【幻想】
過去の原子力政策の問題点が次々と明らかになっています。
核燃料サイクル、プルサーマル、高レベル放射性廃棄物の地層処分など、政府は幻想を振りまいてきました。
しかし高速増殖炉もんじゅは安全に運転できず、計画はつぶれました。再処理工場は先がみえず、蓄積するプルトニウムをどうするのかという問題もあります。核燃料サイクル計画のお粗末さは明らかになっています。
福島の事故をみれば汚染土さえどこにも受け入れてもらえないのが現実です。各原発から出る使用済み核燃料はどうするつもりなのか…。当面は「中間貯蔵施設」に置くとしても、問題の先送り以外の何でもありません。全国で廃炉が進みますが廃棄物の後始末問題は残されたままです。
ところが、政府のエネルギー政策をみると「原子力はべースロード」という位置づけは変わっていません。再稼働や輸出など、原子力の体制や産業を維持することしか考えていない。エネルギー政策をどうするか、国民合意をどうつくるか、事故の教訓を踏まえた全面的な見直しが必要で、す。現在の原発システム(軽水炉)そのものの欠陥も、ほとんど議論されていません。
こうした総合的な検討がされずに、無責任状態で再稼働が進んでいます。いつか来た道を歩いているのではないでしょうか。
「しんぶん赤旗」日刊紙 2020年3月23日付掲載
原子力規制委員会は、実現可能な工事は求める一方、本格的改造を伴う困難な工事やコストが高い工事は求めていない。
東海第2原発などは、事故時の避難などとても無理なのに再稼働OKだとか。
日本のエネルギー政策を抜本的に改めるときです。
東京電力福島第1原発事故から9年。いまだ収束の道筋も見えないなか、政府は原発再稼働を進めています。「事故の教訓が原子力政策に生かされていない。このまま無責任体制が続けば“第二の福島事故”が起こるに違いない」と警鐘を鳴らす、核・エネルギー問題情報センターの舘野淳事務局長(核燃料化学)に聞きました。(中村秀生)
核・エネルギー問題情報センター事務局長 舘野淳さん
すでに10年近くがたつというのに、事故の教訓を現実の原子力政策にどう反映させるのかーという総合的な検討がされていません。
事故現場は、1~3号機の溶け落ちた核燃料デブリが取り出せず四苦八苦しています。当然、重大な事故が発生した場合、万一の炉心溶融に備えなければいけません。
溶けたものが原子炉格納容器の底に落下するとコンクリートと反応してガスが発生し、爆発を起こす可能性が指摘されています。大量の水の中に落ちた場合には水蒸気爆発の可能性があります。
たとえ炉心が溶けても、耐熱性の材料で受けとめる設備「コアキャッチャー」を設置すれば、ある程度は制御できます。これを設置した原発が、欧州などで開発されています。
しかし日本では、これだけ福島の事故で苦労しているのに、規制基準でコアキャッチャーは必要ないということになっています。

原子力規制委員会が再稼働の前提となる審査でOKを出した東海第2原発。自治体が避難計画を策定することになっている30キロ圏内には約96万人が居住=2月19日、茨城県東海村(本紙チャーター機から山形将史撮影)
【妥協】
原子力規制委員会では個々の原発の技術的検討は行っています。ただ実現可能な工事は求める一方、本格的改造を伴う困難な工事やコストが高い工事については口をつぐんでいます。局所的な安全性だけに帰着させた「現実妥協的な審査」で、再稼働が進められているのが現状です。
事故時の避難計画も規制対象外だとして、目をつぶっています。福島では、お年寄りや入院患者が避難のときに亡くなりました。事故の最大の教訓の一つですが、生かされていません。周辺の人口が多い東海第2原発(茨城県)では、事故時の避難などとても不可能ですが、再稼働に“OK”を出しています。
【幻想】
過去の原子力政策の問題点が次々と明らかになっています。
核燃料サイクル、プルサーマル、高レベル放射性廃棄物の地層処分など、政府は幻想を振りまいてきました。
しかし高速増殖炉もんじゅは安全に運転できず、計画はつぶれました。再処理工場は先がみえず、蓄積するプルトニウムをどうするのかという問題もあります。核燃料サイクル計画のお粗末さは明らかになっています。
福島の事故をみれば汚染土さえどこにも受け入れてもらえないのが現実です。各原発から出る使用済み核燃料はどうするつもりなのか…。当面は「中間貯蔵施設」に置くとしても、問題の先送り以外の何でもありません。全国で廃炉が進みますが廃棄物の後始末問題は残されたままです。
ところが、政府のエネルギー政策をみると「原子力はべースロード」という位置づけは変わっていません。再稼働や輸出など、原子力の体制や産業を維持することしか考えていない。エネルギー政策をどうするか、国民合意をどうつくるか、事故の教訓を踏まえた全面的な見直しが必要で、す。現在の原発システム(軽水炉)そのものの欠陥も、ほとんど議論されていません。
こうした総合的な検討がされずに、無責任状態で再稼働が進んでいます。いつか来た道を歩いているのではないでしょうか。
「しんぶん赤旗」日刊紙 2020年3月23日付掲載
原子力規制委員会は、実現可能な工事は求める一方、本格的改造を伴う困難な工事やコストが高い工事は求めていない。
東海第2原発などは、事故時の避難などとても無理なのに再稼働OKだとか。
日本のエネルギー政策を抜本的に改めるときです。