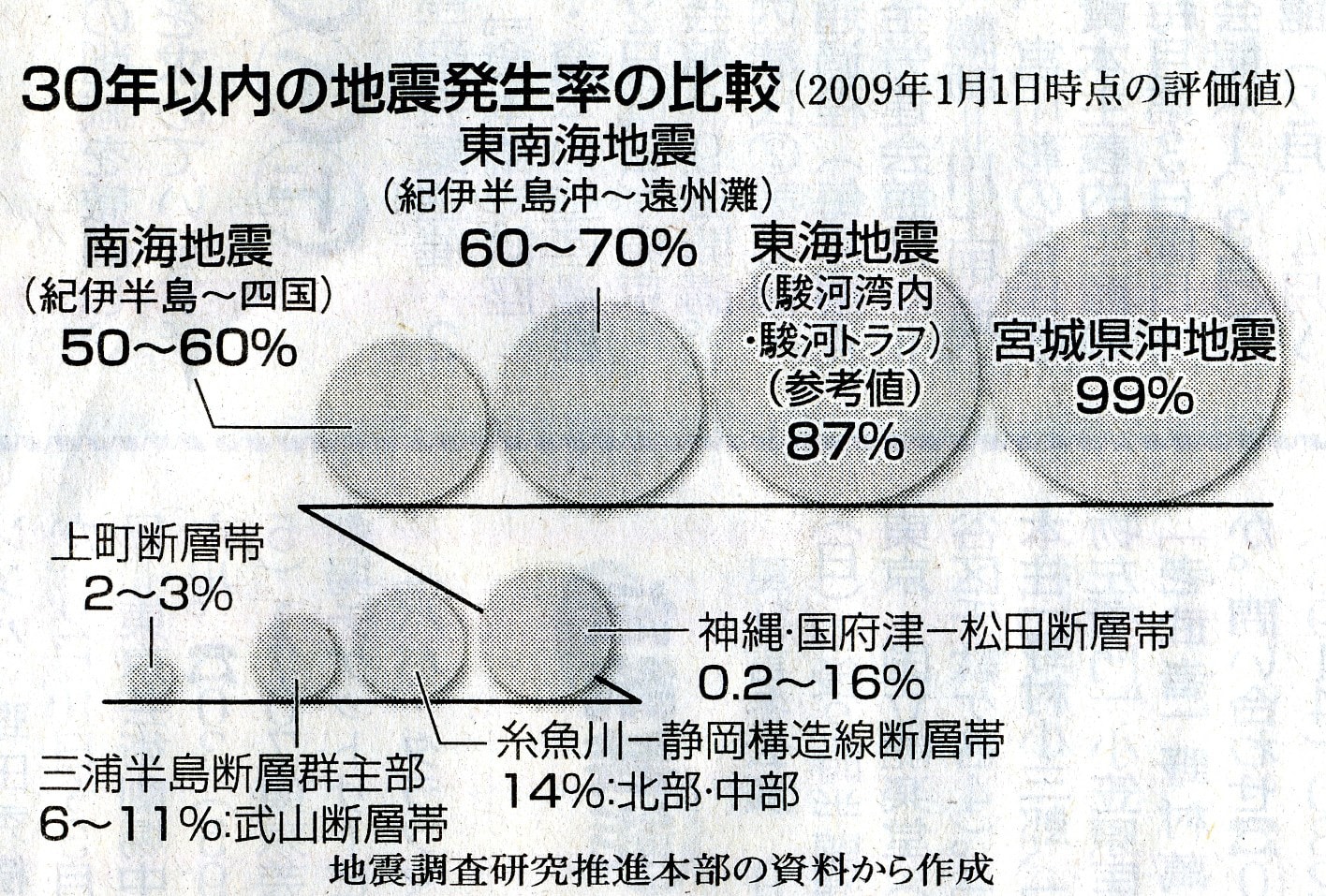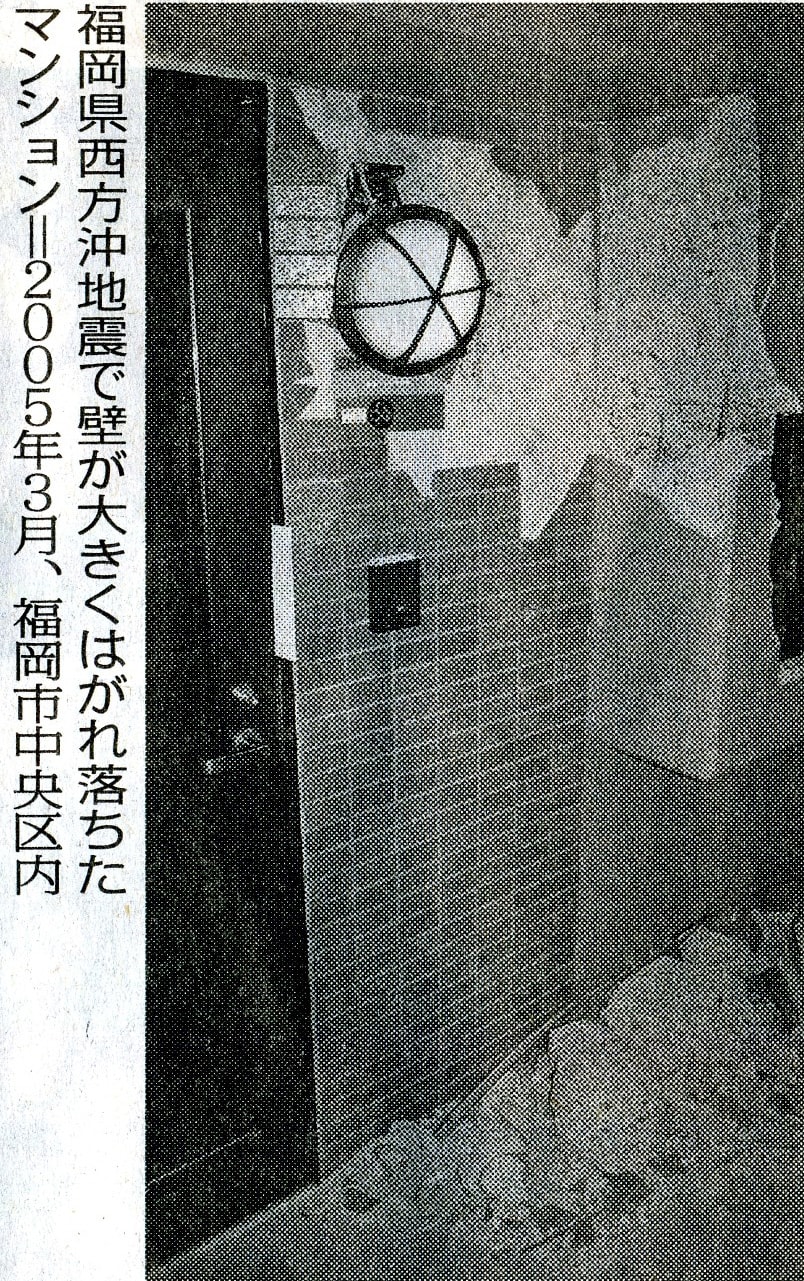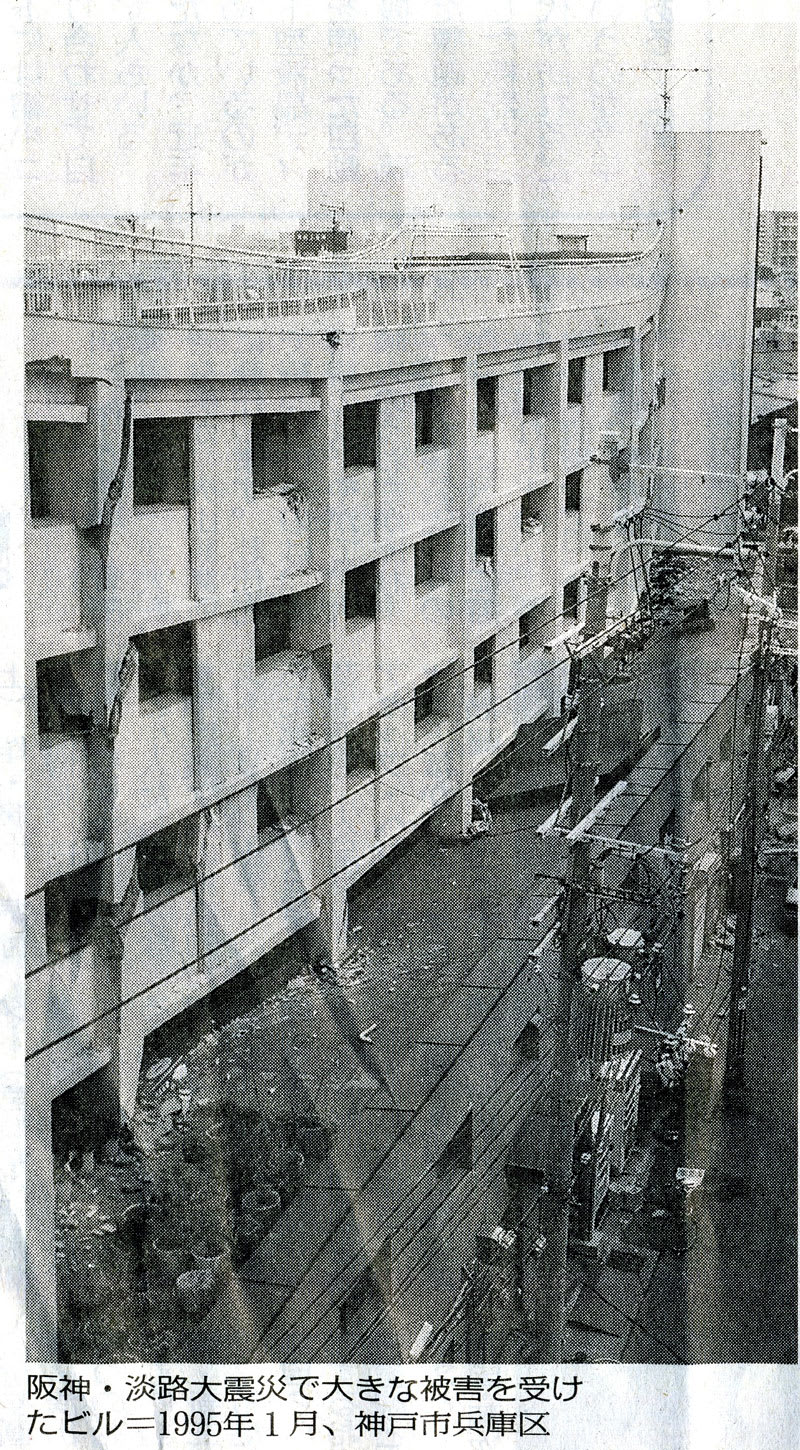マンション 地震防災② 事前対策が命・財産まもる
大きな揺れでマンションの部屋はどのような被害になるのでしょうか。
防災科学技術研究所と兵庫県は、E-ディフェンス(実物大3次元震動台)を用いて南海地震の長周期の揺れが発生したときに、30階相当の建物がどのような被害を受けるかについて実験しました(写真)。居室には、家具の動きだけでなくそこに居る人々がどのような危険にさらされるかを、人体模型を用いて表現しています。



壁に強度必要
実験では揺れは3分以上、揺れ幅は片側1・5メートル、両側3メートルもあり、人や家具に大きな被害がでました。ビデオ映像は音響も含めてインターネットを通じて簡単にダウンロードできるようになっています。映像をご覧いただくとおわかりのように、「大地震が起きたらすぐに動けない」ことや、戸建と比べて避難経路が限られているマンションでは“事前対策こそが人命と財産を守るすべて”であることを一層強く意識していただきたいと思います。
室内の安全対策で重要なポイントは、いかに重い家具を減らせるかです。家具の固定は、万全ではありません。マンションにおける家具固定には法律の改正を含んだ大きな問題があります。設置面の壁には十分な強度が必要で、強度があるコンクリート壁の戸境壁(隣戸との間にある壁)は、共有物なので管理組合の承認が必要となりボルトを使用した固定は現状では困難です。室内の部屋を仕切る間仕切り壁なら、穴は開けられますが家具を支える強度が不十分です。冷蔵庫やタンスなど重量物を置く場所にあらかじめ壁に補強下地を設置して十分な強度にしているマンションはほとんどありません。
家具減らして
高層・超高層建物の歴史は浅く巨大地震の被害経験に乏しいため、家具固定を含めた対策は全般にわたり研究途上です。マンションにおける家具固定の難しさを踏まえれば、現状では家具を減らすことが最も有効な策です。必要な家具については、就寝中や避難時にできるだけ影響の少ない適切な配置で固定をすること、できるだけ造り付け家臭にすること、一つの家具に二カ所の固定、を固定する前に意識しましょう。固定して安心せず、緩みがないか定期的に確認することも大切です。
ところで、家具をがっちりと固定すると、かえって中の収納物が飛び出しやすくなります。家具を固定するなら、棚板に滑り止めシートを敷き、扉にストッパー(扉開き防止器具)を取り付けることも忘れないようにしましょう。
照明器具は、つり下げタイプでなく、天井じか付けタイプをお勧めします。キャビネットの扉、花瓶、写真フレーム、額縁などの装飾品を含めて、案外ガラス製品は室内にあるものです。ガラス製品は割れて飛び散ると厄介な存在になりますから、できるだけ強化ガラスの製品を選ぶか、ガラス飛散フィルムを貼りましょう。ガラス製品や陶器の破片、倒れた家具が高速で床を移動してご自身や家族に衝突する様子をイメージしながら、室内の安全対策に取り組んでください。(金曜掲載)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年1月14日付掲載
こう言われると、家具の固定はほとんどできていないのが現状です。家具を減らすってことは難しいですから、すくなくとも睡眠する時は家具から離れて寝るようにするしかないですね。
大きな揺れでマンションの部屋はどのような被害になるのでしょうか。
防災科学技術研究所と兵庫県は、E-ディフェンス(実物大3次元震動台)を用いて南海地震の長周期の揺れが発生したときに、30階相当の建物がどのような被害を受けるかについて実験しました(写真)。居室には、家具の動きだけでなくそこに居る人々がどのような危険にさらされるかを、人体模型を用いて表現しています。



壁に強度必要
実験では揺れは3分以上、揺れ幅は片側1・5メートル、両側3メートルもあり、人や家具に大きな被害がでました。ビデオ映像は音響も含めてインターネットを通じて簡単にダウンロードできるようになっています。映像をご覧いただくとおわかりのように、「大地震が起きたらすぐに動けない」ことや、戸建と比べて避難経路が限られているマンションでは“事前対策こそが人命と財産を守るすべて”であることを一層強く意識していただきたいと思います。
室内の安全対策で重要なポイントは、いかに重い家具を減らせるかです。家具の固定は、万全ではありません。マンションにおける家具固定には法律の改正を含んだ大きな問題があります。設置面の壁には十分な強度が必要で、強度があるコンクリート壁の戸境壁(隣戸との間にある壁)は、共有物なので管理組合の承認が必要となりボルトを使用した固定は現状では困難です。室内の部屋を仕切る間仕切り壁なら、穴は開けられますが家具を支える強度が不十分です。冷蔵庫やタンスなど重量物を置く場所にあらかじめ壁に補強下地を設置して十分な強度にしているマンションはほとんどありません。
家具減らして
高層・超高層建物の歴史は浅く巨大地震の被害経験に乏しいため、家具固定を含めた対策は全般にわたり研究途上です。マンションにおける家具固定の難しさを踏まえれば、現状では家具を減らすことが最も有効な策です。必要な家具については、就寝中や避難時にできるだけ影響の少ない適切な配置で固定をすること、できるだけ造り付け家臭にすること、一つの家具に二カ所の固定、を固定する前に意識しましょう。固定して安心せず、緩みがないか定期的に確認することも大切です。
ところで、家具をがっちりと固定すると、かえって中の収納物が飛び出しやすくなります。家具を固定するなら、棚板に滑り止めシートを敷き、扉にストッパー(扉開き防止器具)を取り付けることも忘れないようにしましょう。
照明器具は、つり下げタイプでなく、天井じか付けタイプをお勧めします。キャビネットの扉、花瓶、写真フレーム、額縁などの装飾品を含めて、案外ガラス製品は室内にあるものです。ガラス製品は割れて飛び散ると厄介な存在になりますから、できるだけ強化ガラスの製品を選ぶか、ガラス飛散フィルムを貼りましょう。ガラス製品や陶器の破片、倒れた家具が高速で床を移動してご自身や家族に衝突する様子をイメージしながら、室内の安全対策に取り組んでください。(金曜掲載)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年1月14日付掲載
こう言われると、家具の固定はほとんどできていないのが現状です。家具を減らすってことは難しいですから、すくなくとも睡眠する時は家具から離れて寝るようにするしかないですね。