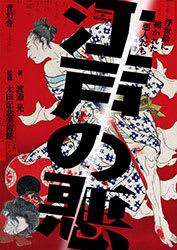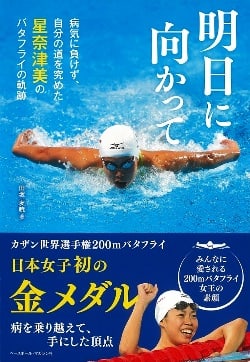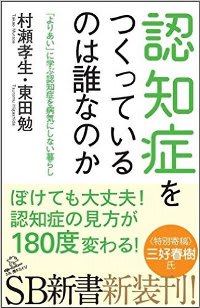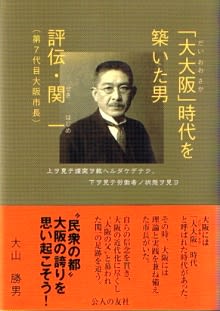【村松友視著、文芸春秋発行】
北の富士(勝昭さん)は幕内優勝回数10回を誇る第52代横綱。現役引退後は九重部屋の親方として名横綱千代の富士と北勝海(現日本相撲協会理事長)を育て上げた。2人の優勝回数は合計39回(千代の富士31回、北勝海8回)。1985~87年には九重部屋10連覇という黄金時代を築いた。まさに名伯楽である。日本相撲協会退職後の1998年からはNHK専属の相撲解説者としてお馴染み。テレビ中継での粋な着物姿と、歯に衣着せぬ辛口の解説が評判を呼ぶ。この3月28日には75歳の誕生日を迎えるが、歳を感じさせない若々しさだ。

著者の村松氏は出版社勤務を経てフリーとなり『時代屋の女房』で直木賞を受賞。北の富士と初めて顔を合わせたのは同じ直木賞作家で作詞家の山口洋子さんが経営する銀座のクラブ「姫」だった。北の富士の人間味に魅せられた村松氏は店に行くたび、常連の北の富士向けにコースターに「北天祐は横綱になれますでしょうか」といった質問やメッセージを書いて店の人に託した。次回行くと必ず北の富士が返事を書いたコースターを店から渡された。それが数年続いた。初対面から30年後、知人を介して北の富士との初めての食事会が開かれた。床の間に白い紙が納まったガラス張りの額があった。その白い紙は村松氏が「姫」で北の富士宛てに書いたコースターだった!
村松氏は北の富士を〝謎の生命体〟と形容する。北の富士が北海道から上京して入門したのは中学卒業直後。力士最高峰の横綱まで昇りつめ、2人の横綱を育て、今なお相撲解説者として人気を博す。「自身の魅力や努力もさることながら、その個性の輝きを評価する存在にも折々に恵まれなければ、かくも長く〝現役〟が持続するはずもない……〝魅力〟〝人気〟〝運〟というものをくるみ込んだ北の富士流が、いかなる絵柄の彩りによって構成され、どのようなものがたりを紡いできたのだろうか」(「前書のようなもの」から)。北の富士の友人、力士仲間、弟子などへの幅広い取材を通じて、「比類ない華、粋、男気、そして色気などをキーワードとして」(「後書のようなもの」から)北の富士流の〝謎〟を探った。
入門後、同じ出羽海部屋の若手力士だった松前山(渡辺貞夫さん)によると、北の富士は「いつ横綱になっても困らないように」と、いつも土俵入りの真似をしていたという。「その真似事が現実化したというわけで、〝夢〟は〝見る〟ものではなく〝手にする〟ものであるという証しを身をもって示して見せた」。北の富士は歌がうまく、大関時代には『ネオン無情』というレコードも出している。マスコミからは〝夜の帝王〟というニックネームを献じられた。村松氏は「北の富士本来のセンスが、遊びの場で出会う人々によって、さらに肥やされ、磨かれ、洗練され、醸成されていった」とみる。2人の名横綱を育てた手腕については「他の名伯楽とのちがいは、その〝人間味満開の男道〟による指導スタイルの師匠というところにあるのではなかろうか」。そして「派手な〝求心力〟と、その裏側にある求心的な〝実〟との一体化によって、北の富士流は成り立っているにちがいない」。
【追記】1月8日から始まった2017年初場所、初日のテレビ解説者は北の富士とともにNHK専属解説者の舞の海秀平さんだった。ということは2日目の9日は北の富士? そう思いながら9日の朝刊スポーツ面を開いたところ片隅に「北の富士さんが心臓を手術」という小さな記事。それによると、12月末に心臓手術を受け現在療養中のため初場所の出演は見合わせることになったとのこと。今場所でも味のある名解説を期待していただけに残念。3月大阪場所ではまた元気な着物姿を見せてほしいものだ。