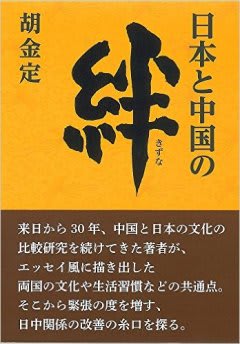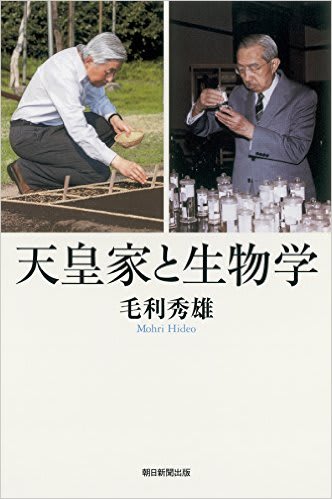【「ツタンカーメンのエンドウ」は捏造! 王墓副葬品にエンドウはなかった】
市販中の「ツタンカーメンのエンドウ豆」の売り文句はエジプト王家のツタンカーメンの墓から豪華な副葬品とともに発見され3000年の時を経て発芽! なかなか夢とロマンのあふれた話で、一時は小学校で栽培ブームが起きるほど。ところが実際には王墓の副葬品の中にエンドウマメはなかったといわれる。本書は昨年11月30日に初版が発行されたばかり。第9章「虚構の主役になったマメ―エンドウ」で22ページを割いて「ツタンカーメンのエンドウ」の誕生やブームの背景を詳細に論じている。(写真㊨は昨年自家栽培した「ツタンカーメンのエンドウ豆」の花)


著者がこのエンドウマメの由来について研究を始めたのは今から約30年前の1987年。内外の多くの文献に当たった結果「9世紀ごろの欧州における『ミイラのコムギ』や『ミイラのオオムギ』の話の『書き替え』であることを確認できた」という。「ツタンカーメンのエンドウ」は「科学的根拠のない虚構」だったわけだ。
元となった「ミイラのコムギ」はエジプトの墳墓から見つかった種子が時を超えて発芽したというもの。だが古植物学者らによると、その種子は炭化し胚が壊れて発芽は全く不可能で、まさに根も葉もない作り話とか。種子の寿命は貯蔵の条件にもよるが、それでも数百年ということは決してあり得ないという。普通コムギ(パンコムギ)とは別種のコムギの種子を「奇跡のコムギ」「ミイラのコムギ」と称して売った業者もいたそうだ。捏造話の裏には一儲けしようという欲があった。
「ツタンカーメンのエンドウ」が捏造された背景について、著者は「エンドウの種子が3000年も生きていた」ことを信じた植物や作物の専門家とともに、ブームの火付け役となったマスメディアに大きな責任があると指摘する。農林水産省のホームページ「消費者の部屋」(2006年)でさえ「ツタンカーメンのエンドウ」を「えんどう豆は発芽能力の維持が難しいといわれていますが、発見されたものは約3000年の年月を超えて発芽しました」と紹介していたという。著者は「専門家や国が科学的根拠を示さずに『事実』として、いわば『お墨付き』を与えている『ツタンカーメンのエンドウ』の話が、今もなお生き続けている」ことに警鐘を鳴らす。