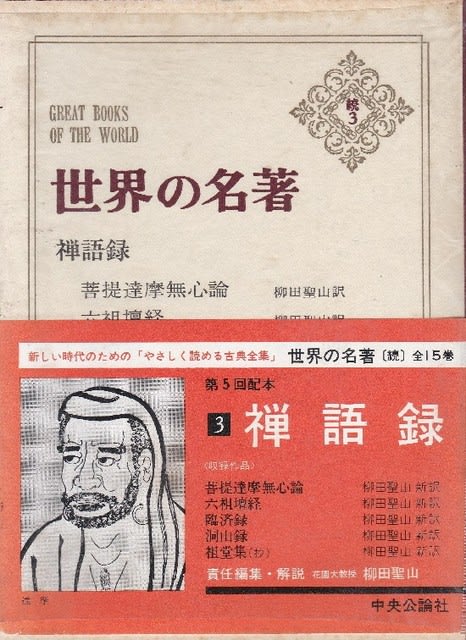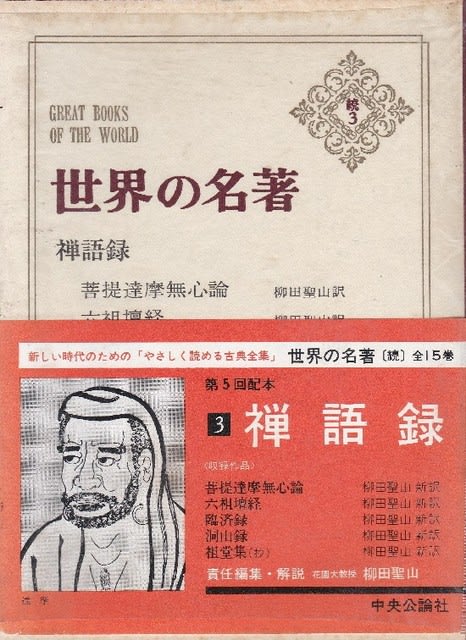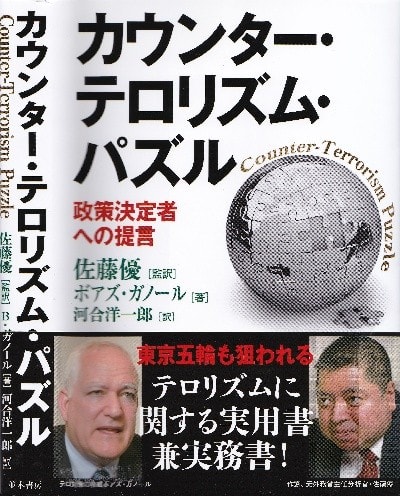(1)ABC理論
金太郎(かねたろう) さあ、今日はいよいよ本題の「ストレス対処法」だね!
得子(とくこ) では、まず質問。一言でストレスっていっても、とらえ方次第で変化するって、知ってた?
金 いや、知らなかった。
得 それじゃあ、ストレスとうまくつき合うための「ABC理論」から説明するわね。
金 ABC?
得 そう。Aは「Activating event(出来事)」。Bは「Belief(信念・価値観)」で、その人なりの物事のとらえ方のことを指すわ。難しい言葉で、「認知」というのよ。最後のCは「Consequence(結果)」。出来事の結果として表れる感情や体調の変化のことをいうの。
金 ABCの意味はわかったけど、どう関係しているの?
得 ストレスの原因となる出来事(A)を受けた結果として、今の心身の状態(C)が決まると思いがちだけど、違うの。AとCの間には、Bというフィルターがあるのよ。
(2)「ストレス日記」
金 難しくなってきたな。
得 簡単よ。例えば、「プレゼン資料の内容について、上司から厳しく叱責(しっせき)された」という出来事があった、と仮定しましょう。金ちゃんなら、どう感じる?
金 そりゃ落ち込むに決まってるでしょ。
得 でも、例えば「僕の将来のことを考えて叱ってくれた」「人前ではなく、個室に呼んで叱ってくれた」と考えてみたらどう?
金 ちょっと気が楽になるかな。
得 でしょ? これは「認知を変える」というのよ。精神療法の一種「認知療法」を応用した考え方よ。
金 でも、今の上司のことを考えると、そう簡単に前向きにはなれないなあ。
得 うん、わかるよ。そこで一つの方法として、日記をつけることをお勧めするわ。その日のストレスの元になった出来事を書き出すの。そのときの怒りや落ち込みなど、浮かんだ感情のキーワードを点数化してみて。何日か経って、少し客観的に日記を読み返すと、その点数が下がっていると思うわ。新しい点数は、赤字で「上書き」してね。
金 日記をつけるコツはある?
得 数日後に日記を読み返すとき、「こうあるべきだ、と決めつけていないか」「悪いことを、針小棒大にとらえていないか」「完璧主義に陥っていないか」などを意識するの。これを繰り返していくと、自分の「考え方の悪い癖」がわかって、少しずつ前向きな考え方ができるようになるはずよ。
(3)「四つのR」と「GNN」
金 よし、やってみよう! あとは、どんな対処法があるの?
得 「四つのR」と「GNN」ね。
金 何かアルファベットの頭文字が多いなあ(笑)。
得 覚えやすいからね。四つのRは、(1)Rest(休息)、(2)Recreation(遊び・気晴らし)、(3)Relaxation(神経を休める)、(4)Retreatment(転地療法)のことよ。(1)は睡眠やマッサージ、(2)はスポーツやカラオケとかね。(3)は、例えば呼吸法やアロマセラピー、(4)は旅行とか森林浴など、非日常の場に身を置いてリフレッシュすることね。
金 GNNは?
得 それゃ、決まってるじゃん。義理、人情、浪花節だよ、人生は! 成果主義の導入などで、今の日本の会社には、そういう人間的な温かさが減ったのよ。無駄話の多い職場はメンタルの健全度が高い、ともいわれてるわ。実は、GNNが職場のストレス改善に一番大事かもね。
取材協力・渡部卓さん(帝京平成大学現代ライフ学部教授、ライフバランスマネジメント研究所代表)
(構成・佐藤陽)=全4回
【職場のストレス対処法は?】
●ABC理論→同じストレスの元になる出来事でも、物事のとらえ方次第で、不快な感情は減らせる
●物事のとらえ方をポジティブに変えるため、「ストレス日記」をつける。怒りや落ち込みを点数化し、数日後に見直すことを繰り返す
●休息(レスト)や気晴らし(レクリエーション)など「四つのR」も重要
●義理、人情、浪花節の「GNN」も大切に
□「(知っ得 なっ得)ストレスとつき合う:2 どう対処すればいい?」(朝日新聞デジタル 2018年4月14日)を引用、かつ、小見出し追記
「
(知っ得 なっ得)ストレスとつき合う:2 どう対処すればいい?」