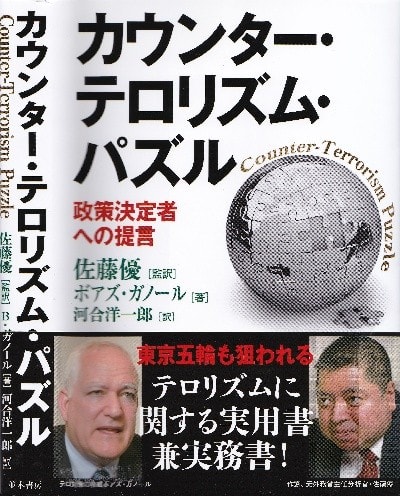大雅は、多くの旅を重ねた画家だった。26歳の時、江戸に遊んだ大雅は、そこから塩竃、松島にまで足を延ばし、その美しい景色に目を奪われる。翌年には北陸地方を遊歴したほか、20歳代後半から30歳にかけて、伊勢や出雲など各地を旅したことが知られている。なかでも、38歳の時に友人の高芙蓉、韓天寿とともに白山・立山・富士山の三霊山を踏破した長途の旅行は特に有名なもので、豊富なスケッチを含む「三岳紀行図屏風」(作品番号111)によってその詳細を知ることができる。そしてこの旅の成果は、「浅間山真景図」(作品番号108)という江戸時代絵画史においても傑出した風景表現へと見事に結晶した。
大雅の旅は、万巻の書を読み万里の道を行かねば偉大な画家にはなれないという、中国の文人画家の考え方に触発されたものだろう。旅を重ね、自然を肌で感じることこそが、優れた山水画を描くために必要だと考えたのである。旅先で目にした自然の実感にもとづく風景表現(真景図)は、大雅の画業を特徴付ける主要テーマとなっていく。のみならず、40歳代以降に顕著となる広やかな空間表現など、自らの表現様式の確立にも多大な影響を及ぼすことになるのである。
□京都国立博物館、読売新聞社『池大雅 天衣無縫の旅の画家』(読売新聞社、2018)の「第5章 旅する画家--日本の風景を描く」の冒頭を引用

★池大雅「比叡山真景図」

大雅の旅は、万巻の書を読み万里の道を行かねば偉大な画家にはなれないという、中国の文人画家の考え方に触発されたものだろう。旅を重ね、自然を肌で感じることこそが、優れた山水画を描くために必要だと考えたのである。旅先で目にした自然の実感にもとづく風景表現(真景図)は、大雅の画業を特徴付ける主要テーマとなっていく。のみならず、40歳代以降に顕著となる広やかな空間表現など、自らの表現様式の確立にも多大な影響を及ぼすことになるのである。
□京都国立博物館、読売新聞社『池大雅 天衣無縫の旅の画家』(読売新聞社、2018)の「第5章 旅する画家--日本の風景を描く」の冒頭を引用

★池大雅「比叡山真景図」