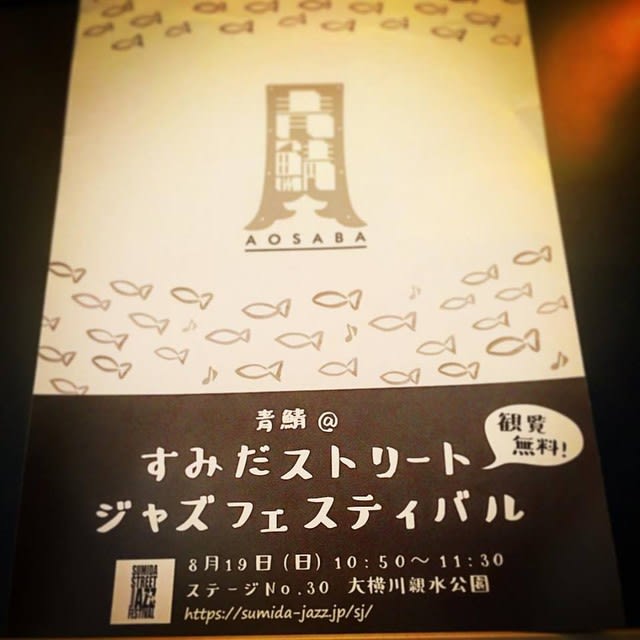怪我や病気などで右手が使えなくなってしまったピアニストが集って競い合う
左手のピアノコンクールのテレビ番組を見て泣いてしまった。
そこには、どうしても音楽をやりたいというひたむきな意志があるからだろう。
これは音楽を愛するものにとって感動的だ。
ただ「コンテスト」「コンクール」には思うところがある。
ここ2年ほど、中学や高校の吹奏楽を取材する機会があって、そこでも思ったんだが、
「音楽」と「勝ち負け」がどうしても馴染まない気がするのだ。
たとえばピッチ、リズムを揃える。シンセサイザーやメトロノームの音を流しながらやったり、
ものすごく不機嫌なふりをした先生が、怯えを利用して生徒を掌握する。
あるいは審査員のための対策をする、とか。
でも、勝つための演奏なんてないし、勝つための演奏には決してミューズは微笑まない。

私自身、長年音楽をやってきて、最近やっと到達したのが、
「とにかく落ちついて演奏する、そしてその時、誰よりも音楽を味わい演奏を楽しむ」
というものだ。
コンクールやコンテストでは、それはたぶん不可能だろう。