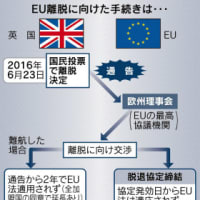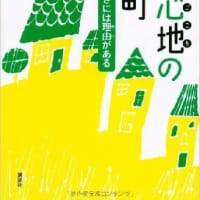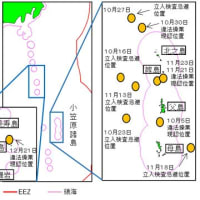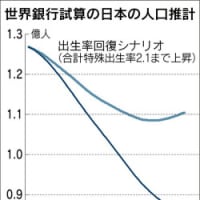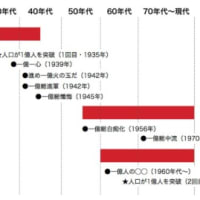『防衛とは自国のためだけでは決してないのだ。隣人のためなのである。』
『日本の安全保障の問題で、多くの論者がまったく視野の外においている盲点は、米国に対する防衛の問題である。』
『憲法9条の規定は、そのままでは、かならずしも「真理」でも「理想」でもなく、戦争と平和の基本的見方において、「軍備コントロール」の問題を妨げるものである。』
『本書に一貫している議論の基調は、この世で美しいもの、価値あるものも、なんらかの代償なしには何も得られないという素朴な日常的英知の再確認にほかならない。』
「平和の代償」中央公論社(1967) 所収、上から順に、
『米国の戦争観と毛沢東の挑戦』P65,(初出1965)
『日本外交の拘束と選択』P117(初出1966)
『国家目標としての安全と独立』P164(初出1966)
『あとがき』P224
「筆者コメント」
40年以上も前、大学2年生の時に読んだ。その時は、日本の政治、防衛等について、それほど知識があったわけではない。それでも、
「防衛とは自国を守ること」
「米国は民主主義の手本で仲間」
「憲法9条は理想の表現」
と何となく、疑わずに、そう思っていたのは確かだった。それをひっくり返された。これらが既成概念であって、いつの頃からか、自らの政治的思考を制約していたわけだ。最初の言葉には『若い女性が身だしなみを整えるのは、彼女のためだけではない』と付け加えてあったので、おう!そうか、と納得した。
以下の言葉は入学したての頃、新入生向きの本に書かれていた。固定観念から、自己を解放する学問として「永井政治学」は偶然にも自分の前に姿を現した。これを読んでいなければ、おそらく、「平和の代償」も読まなかったのではないか?
『われわれが深い自己観察の能力と誠実さを失わない人であればあるほど、自己の内面に無意識的に蓄積、滲透している“時代風潮”とか、“イデオロギー”や“偏見”の拘束を見出さざるを得ないであろう。その固定観念からの自己解放の知的努力の軌跡こそが政治学的認識そのものといっていいだろう。』
『政治的認識の構造』「学問と読書」(大河内一男編・東大出版会)
『日本の安全保障の問題で、多くの論者がまったく視野の外においている盲点は、米国に対する防衛の問題である。』
『憲法9条の規定は、そのままでは、かならずしも「真理」でも「理想」でもなく、戦争と平和の基本的見方において、「軍備コントロール」の問題を妨げるものである。』
『本書に一貫している議論の基調は、この世で美しいもの、価値あるものも、なんらかの代償なしには何も得られないという素朴な日常的英知の再確認にほかならない。』
「平和の代償」中央公論社(1967) 所収、上から順に、
『米国の戦争観と毛沢東の挑戦』P65,(初出1965)
『日本外交の拘束と選択』P117(初出1966)
『国家目標としての安全と独立』P164(初出1966)
『あとがき』P224
「筆者コメント」
40年以上も前、大学2年生の時に読んだ。その時は、日本の政治、防衛等について、それほど知識があったわけではない。それでも、
「防衛とは自国を守ること」
「米国は民主主義の手本で仲間」
「憲法9条は理想の表現」
と何となく、疑わずに、そう思っていたのは確かだった。それをひっくり返された。これらが既成概念であって、いつの頃からか、自らの政治的思考を制約していたわけだ。最初の言葉には『若い女性が身だしなみを整えるのは、彼女のためだけではない』と付け加えてあったので、おう!そうか、と納得した。
以下の言葉は入学したての頃、新入生向きの本に書かれていた。固定観念から、自己を解放する学問として「永井政治学」は偶然にも自分の前に姿を現した。これを読んでいなければ、おそらく、「平和の代償」も読まなかったのではないか?
『われわれが深い自己観察の能力と誠実さを失わない人であればあるほど、自己の内面に無意識的に蓄積、滲透している“時代風潮”とか、“イデオロギー”や“偏見”の拘束を見出さざるを得ないであろう。その固定観念からの自己解放の知的努力の軌跡こそが政治学的認識そのものといっていいだろう。』
『政治的認識の構造』「学問と読書」(大河内一男編・東大出版会)