
8月5日(火)雷、雨【總持寺の蔵】
この写真の蔵は、明治の大火から免れたそうです。やはり蔵の造りは違うのですね。そして火事のあとすぐに開けなかったのでしょうね。建物が焼け残っても、すぐに開けるとせっかく焼け残ったとしても、また燃えてしまうそうですが、多くの書類やら宝物などが助かったのは、きっとそのような知識のある人がいたのでしょう。
「開けるな、開けるな、まだ開けては駄目だ」と、叫んだ人がいたような情景を、この蔵の写真を見ていて、思い描きました。
なお總持寺祖院に関しての記事は「つらつら日暮らし」のtenjin和尚さんのWikiをご覧ください。http://wiki.livedoor.jp/turatura/d/%e5%c1%bb%fd%bb%fb%c1%c4%b1%a1
この写真の蔵は、明治の大火から免れたそうです。やはり蔵の造りは違うのですね。そして火事のあとすぐに開けなかったのでしょうね。建物が焼け残っても、すぐに開けるとせっかく焼け残ったとしても、また燃えてしまうそうですが、多くの書類やら宝物などが助かったのは、きっとそのような知識のある人がいたのでしょう。
「開けるな、開けるな、まだ開けては駄目だ」と、叫んだ人がいたような情景を、この蔵の写真を見ていて、思い描きました。
なお總持寺祖院に関しての記事は「つらつら日暮らし」のtenjin和尚さんのWikiをご覧ください。http://wiki.livedoor.jp/turatura/d/%e5%c1%bb%fd%bb%fb%c1%c4%b1%a1















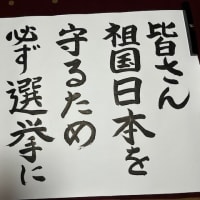




ところで、最後のほうで大阪空襲で船場が焼けます。ぼんちもせめて蔵の一つも残そうと、商い倉に水桶を沢山運び込んで、扉を閉めます。本宅と他の蔵は皆焼夷弾で焼かれてしまいますが、この蔵だけは残りました。水桶が蔵の中の温度を上げなかったのでしょう。
やはり蔵は特殊な造りなのでしょう。おそらく壁の造りが違うのではないでしょうか。しかし明治31年の大火では總持寺はほとんど焼けてしまったのです。惜しいことをしました。その後、鶴見のほうに總持寺を建てて移転することになったのです。