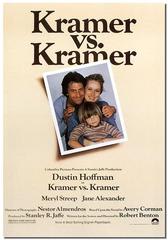DENONの新型プリメインアンプPMA-2000REの試聴会に行ってみた。DENONはかつては日本コロムビアのオーディオ・ブランドであり、2001年に同社の経営再建策により分社化したが、元々は日本電氣音響という戦前に発足したメーカーであった(60年代に日本コロムビアと一度合併)。昨今のオーディオ不況にあっても昔とほぼ変わらず機器のフルラインナップを揃え、その製品は家電量販店でもよく見かける。
PMA-2000はDENONのプリメインアンプの中堅機種で、96年にシリーズ第一作がリリースされ、今回の2000REで7代目になる。とはいえ、以前の製品は私にとって満足出来るものではなかった。押しの強い中低域と寸詰まりの高域。恰幅の良い音だが、質感はそれほどでもない。何より音場表現については他メーカー品の後塵を拝している印象が強かった。

それでも前作の2000SEは幾分フラットに振っているようにも思えたが、諸手を挙げての評価は出来なかった。ならばこの新作はどのような展開を示すのか、決して小さくはない関心を持って試聴会に臨んだ次第だ。しかも、今回は2000SEとの聴き比べも企画されており、なおかつ繋げるスピーカーはアンプの違いをリスナーが認識出来るようにと、モニター調の音質を持つ英国PMC社の製品を用意してくれたのは有り難い。
実際に聴いてみると、PMA-2000REはとても良い製品であることが分かる。前作の2000SEと比べると、低域の押し出し感が幾分気にならなくなった代わりに、中高域がかなり充実してきた。特に中域の聴感上でのS/N比の改善は目覚ましく、音場の見通しが格段に良い。高域も詰まった感じや妙な強調感が伴うこともなく、しなやかに響く。また適度な力感があり、決して音像がやせることはない。
解像度や情報量といった音のクォリティでは、同クラスのMARANTZのPM-15S2を確実にリードしている。同じMARANTZならば上位クラスのPM-13S2といい勝負だ。またONKYOのA-9070との比較では、クリアネスやヌケの良さならばONKYOに分があるが、音のコクや温度感では勝っている。電源ケーブルの交換により、全域に渡って少し“引き締まった”テイストを演出することも可能だろう。

おそらくこのアンプの音が嫌いな人は、あまりいないのではないだろうか。決して高忠実度再生を目指したような音作りではなく、独自の色付けが施されているが、鳴りっぷりがよく長時間聴いても疲れない。繋ぐスピーカーもあまり選ばないと思う。万人向けのモデルである。
ただし、この図体と重量のデカさはいただけない。もちろん“オーディオ機器は大きくて重い方がイイのだ!”と思っている昔ながらのマニアは気にならないかもしれないが、家庭に入れると一般ピープルは“引いて”しまうほどの威圧感がある。それと、10万円を優に超える製品だけに、ツマミはアルミ無垢を採用して高級感を出して欲しかった。
なお、CDプレーヤーは本機とペアになるDCD-1650REと共に、前作のDCD-1650SEとも聴き比べることが出来た。個人的な印象としては、両者の差はあまりないと思う。店のスタッフも“今回のモデルチェンジはCDプレーヤーよりもアンプの方が音の変化が大きい”と言っていた。
いずれにしろ、PMA-2000REはこのクラスのベストバイのひとつであり、(重量とサイズの問題をクリアすれば)買って損するような製品ではないと思う。機会があれば、SOULNOTEのsa3.0やNmodeのX-PM2Fといったスクエアな音作りのアンプとも聴き比べてみたい。
PMA-2000はDENONのプリメインアンプの中堅機種で、96年にシリーズ第一作がリリースされ、今回の2000REで7代目になる。とはいえ、以前の製品は私にとって満足出来るものではなかった。押しの強い中低域と寸詰まりの高域。恰幅の良い音だが、質感はそれほどでもない。何より音場表現については他メーカー品の後塵を拝している印象が強かった。

それでも前作の2000SEは幾分フラットに振っているようにも思えたが、諸手を挙げての評価は出来なかった。ならばこの新作はどのような展開を示すのか、決して小さくはない関心を持って試聴会に臨んだ次第だ。しかも、今回は2000SEとの聴き比べも企画されており、なおかつ繋げるスピーカーはアンプの違いをリスナーが認識出来るようにと、モニター調の音質を持つ英国PMC社の製品を用意してくれたのは有り難い。
実際に聴いてみると、PMA-2000REはとても良い製品であることが分かる。前作の2000SEと比べると、低域の押し出し感が幾分気にならなくなった代わりに、中高域がかなり充実してきた。特に中域の聴感上でのS/N比の改善は目覚ましく、音場の見通しが格段に良い。高域も詰まった感じや妙な強調感が伴うこともなく、しなやかに響く。また適度な力感があり、決して音像がやせることはない。
解像度や情報量といった音のクォリティでは、同クラスのMARANTZのPM-15S2を確実にリードしている。同じMARANTZならば上位クラスのPM-13S2といい勝負だ。またONKYOのA-9070との比較では、クリアネスやヌケの良さならばONKYOに分があるが、音のコクや温度感では勝っている。電源ケーブルの交換により、全域に渡って少し“引き締まった”テイストを演出することも可能だろう。

おそらくこのアンプの音が嫌いな人は、あまりいないのではないだろうか。決して高忠実度再生を目指したような音作りではなく、独自の色付けが施されているが、鳴りっぷりがよく長時間聴いても疲れない。繋ぐスピーカーもあまり選ばないと思う。万人向けのモデルである。
ただし、この図体と重量のデカさはいただけない。もちろん“オーディオ機器は大きくて重い方がイイのだ!”と思っている昔ながらのマニアは気にならないかもしれないが、家庭に入れると一般ピープルは“引いて”しまうほどの威圧感がある。それと、10万円を優に超える製品だけに、ツマミはアルミ無垢を採用して高級感を出して欲しかった。
なお、CDプレーヤーは本機とペアになるDCD-1650REと共に、前作のDCD-1650SEとも聴き比べることが出来た。個人的な印象としては、両者の差はあまりないと思う。店のスタッフも“今回のモデルチェンジはCDプレーヤーよりもアンプの方が音の変化が大きい”と言っていた。
いずれにしろ、PMA-2000REはこのクラスのベストバイのひとつであり、(重量とサイズの問題をクリアすれば)買って損するような製品ではないと思う。機会があれば、SOULNOTEのsa3.0やNmodeのX-PM2Fといったスクエアな音作りのアンプとも聴き比べてみたい。