今回は交響曲三題。今年(2011年)はグスタフ・マーラーの没後百年に当たる。だから・・・・というわけでもないのだが(^_^;)、久々にマーラーの作品のディスクを買ってみた。交響曲第10番である。演奏はダニエル・ハーディング指揮のウィーン・フィル。2008年の録音だ。
クラシックファンには説明するまでもないが、この曲はマーラーが完成させることなく終わった作品である。完成された部分のみ(第一楽章のアダージョ)の録音が多いが、補筆による全曲完成版のレコーディングもけっこうある。補筆版の中ではイギリスの音楽学者デリック・クックによるものが有名で、当ディスクもそれを採用している。

正直言って私は補筆版の交響曲第10番は今までディスクを買ったことがなく、曲自体もラジオで数回聴いたのみ。実演に接したこともない。だからこのCDが交響曲第10番の全ディスコグラフィの中でどれほどのレベルに位置しているのか分からないが、聴いた限りではかなり上質の出来映えだと思う。とにかく音が滑らかだ。晩年のマーラーの激しい情念のテイストこそ希薄だと感じるが、純音楽的に目覚ましい響きの美しさを獲得していると言って良い。
ハーディングは75年生まれの、若手と言って良い年代の指揮者だが、しなやかで強靱な曲の運び方には感心した。ウィーン・フィルの美音にもほれぼれする。清涼で、それでいて薄口ではなく、スコアの美しさを存分に堪能できるディスクだと思う。録音も、このレーベル(独グラモフォン)にしては良好だ。
エリアフ・インバル指揮のフランクフルト放響によるマーラーの第5番が、廉価版それもBlu-specCD仕様で再発されていたので、思わず買ってしまった。86年の録音である。この曲はマーラーの交響曲の中でもよく知られており、特に第四楽章のアダージェットはヴィスコンティの「ベニスに死す」や市川崑の「おはん」といった映画にも採用されているので、クラシックファン以外でも聴いたことがある人は多いだろう。
インバルの指揮は明晰そのもので、決して感情的に没入しない。レナード・バーンスタイン&ウィーン・フィルのような濃厚な演奏が好きな人にはあまり受け入れられないだろうが、本作の精緻な構築力には大きな説得力がある。だが、このディスクの最大のセールスポイントは録音の良さだ。

マイクを多数立てて主に編集によってサウンド・デザインを決める通常のマルチ録音とは違い、マイクの数を最小限に抑えて音場の再現性を狙うというワンポイント録音方式を採用している。この方式はヘタをするとボケた音になることもあるが、本作は大成功した部類だろう。深々とした広大な音場がリスニングルームに展開、楽器の定位が明確で、音像も鮮明だ。当初リリースされた際はオーディオマニアの間で随分と話題になったものだが、今聴いても素晴らしい音質である。クラシック入門者にとっても必携盤だと思う。
セルジュ・チェリビダッケ指揮のチャイコフスキー交響曲第5番が安い価格で再発されていたので購入した。オーケストラは手兵のミュンヘン・フィルで、91年のライヴ録音である。チェリビダッケは生前録音媒体の発売を嫌っていた(晩年近くにはビデオソフトはいくつかリリースされていたが)。そのため一般の音楽ファンにとって実演以外には彼の演奏に接することはほとんど出来なかったのだ。没後にようやく演奏会のレコーディング音源などがディスク化されてきた。このCDはその中でも彼の代表作と言われるものである。
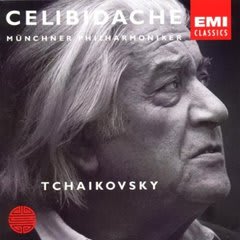
私はチャイコフスキーの作品はそれほど好きではない。何というか、情緒過多で長く聴いていると胃にもたれてくるのだ(笑)。この交響曲第5番も同様で、第6番「悲愴」に次ぐ知名度がありながら今までCDやレコードの一枚も買ったことがなかった。ただし、このディスクは評論家筋も絶賛しており、また伝説の指揮者チェリビダッケの実相を少しでも知りたいという思いもあり、今回入手した次第。
実際聴いてみると、なるほど実に聴き応えのある演奏だ。情緒を廃した、純音楽的なアプローチ。テンポは遅めだが、音の厚みは格別。まさに屹立した音の壁がグッと迫ってくるようだ。チェリビダッケの指揮は鋼のように強靱で、最後までテンションが落ちることはない。ミュンヘン・フィルの演奏能力も端倪すべからざるもので、レベルとしてはベルリン・フィルなど他のドイツの一流オーケストラとタメを張れるほど。とにかくこの曲の代表盤であることは間違いない。録音もライヴ盤としては水準をクリアしている。
クラシックファンには説明するまでもないが、この曲はマーラーが完成させることなく終わった作品である。完成された部分のみ(第一楽章のアダージョ)の録音が多いが、補筆による全曲完成版のレコーディングもけっこうある。補筆版の中ではイギリスの音楽学者デリック・クックによるものが有名で、当ディスクもそれを採用している。

正直言って私は補筆版の交響曲第10番は今までディスクを買ったことがなく、曲自体もラジオで数回聴いたのみ。実演に接したこともない。だからこのCDが交響曲第10番の全ディスコグラフィの中でどれほどのレベルに位置しているのか分からないが、聴いた限りではかなり上質の出来映えだと思う。とにかく音が滑らかだ。晩年のマーラーの激しい情念のテイストこそ希薄だと感じるが、純音楽的に目覚ましい響きの美しさを獲得していると言って良い。
ハーディングは75年生まれの、若手と言って良い年代の指揮者だが、しなやかで強靱な曲の運び方には感心した。ウィーン・フィルの美音にもほれぼれする。清涼で、それでいて薄口ではなく、スコアの美しさを存分に堪能できるディスクだと思う。録音も、このレーベル(独グラモフォン)にしては良好だ。
エリアフ・インバル指揮のフランクフルト放響によるマーラーの第5番が、廉価版それもBlu-specCD仕様で再発されていたので、思わず買ってしまった。86年の録音である。この曲はマーラーの交響曲の中でもよく知られており、特に第四楽章のアダージェットはヴィスコンティの「ベニスに死す」や市川崑の「おはん」といった映画にも採用されているので、クラシックファン以外でも聴いたことがある人は多いだろう。
インバルの指揮は明晰そのもので、決して感情的に没入しない。レナード・バーンスタイン&ウィーン・フィルのような濃厚な演奏が好きな人にはあまり受け入れられないだろうが、本作の精緻な構築力には大きな説得力がある。だが、このディスクの最大のセールスポイントは録音の良さだ。

マイクを多数立てて主に編集によってサウンド・デザインを決める通常のマルチ録音とは違い、マイクの数を最小限に抑えて音場の再現性を狙うというワンポイント録音方式を採用している。この方式はヘタをするとボケた音になることもあるが、本作は大成功した部類だろう。深々とした広大な音場がリスニングルームに展開、楽器の定位が明確で、音像も鮮明だ。当初リリースされた際はオーディオマニアの間で随分と話題になったものだが、今聴いても素晴らしい音質である。クラシック入門者にとっても必携盤だと思う。
セルジュ・チェリビダッケ指揮のチャイコフスキー交響曲第5番が安い価格で再発されていたので購入した。オーケストラは手兵のミュンヘン・フィルで、91年のライヴ録音である。チェリビダッケは生前録音媒体の発売を嫌っていた(晩年近くにはビデオソフトはいくつかリリースされていたが)。そのため一般の音楽ファンにとって実演以外には彼の演奏に接することはほとんど出来なかったのだ。没後にようやく演奏会のレコーディング音源などがディスク化されてきた。このCDはその中でも彼の代表作と言われるものである。
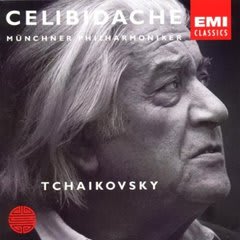
私はチャイコフスキーの作品はそれほど好きではない。何というか、情緒過多で長く聴いていると胃にもたれてくるのだ(笑)。この交響曲第5番も同様で、第6番「悲愴」に次ぐ知名度がありながら今までCDやレコードの一枚も買ったことがなかった。ただし、このディスクは評論家筋も絶賛しており、また伝説の指揮者チェリビダッケの実相を少しでも知りたいという思いもあり、今回入手した次第。
実際聴いてみると、なるほど実に聴き応えのある演奏だ。情緒を廃した、純音楽的なアプローチ。テンポは遅めだが、音の厚みは格別。まさに屹立した音の壁がグッと迫ってくるようだ。チェリビダッケの指揮は鋼のように強靱で、最後までテンションが落ちることはない。ミュンヘン・フィルの演奏能力も端倪すべからざるもので、レベルとしてはベルリン・フィルなど他のドイツの一流オーケストラとタメを張れるほど。とにかくこの曲の代表盤であることは間違いない。録音もライヴ盤としては水準をクリアしている。














