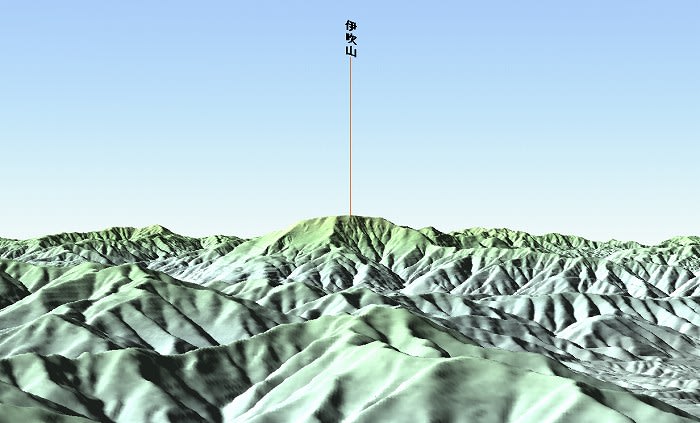8月の最後の日になりました。ここのところ、さすがの猛暑も遠のき、秋雨前線のお陰で、涼しく過ごせています。
何よりも朝の涼しさときたら、散々暑さにもてあそばれてきただけに、”宝物”のように思えます。
しかし、雨の日が続きますと、洗濯物が乾きにくいとか、それなりの不平も出てきてしまいます。
でも、今のところは、「天の配剤」などと言って、人の力では何とも出来ないうちが華でしょうね。
これが人為的に操ることができるようになると、紛争の火種になりかねないのではないでしょうか。
ドライブウェイを目指す ↓

樹林帯を抜けてから草の道をつづら折れに登っていましたが、一つの尾根に出たので、その尾根を使ってドライブウェイに直登するようにします。
キヌタソウ ↓

今度は日当たりの良い場所で咲いています。
はるか下に自車 ↓

眼下に自分の車を置いた場所が見えています。(白線内)
ドライブウェイに出た ↓

ドライブウェイに出ると、そこには年配の男性が歩いていました。聞くところによると、ドライブウェイの途中まで車に乗せてきてもらい、下ろされた場所から歩いてきているとのことでした。
ツリガネニンジン ↓

車道にはみ出さないように細心の注意をして、本来ご法度の車道歩きをすることにしました。
日当たりのよい道端に、早速ツリガネニンジンが出てきます。
カワラナデシコ ↓

こんな美花も出てきます。
クサボタン ↓

花の咲いたものが、やっと出てきました。
テンニンソウ ↓

花の咲いたテンニンソウもやっと出てきました。この山ではこのテンニンソウと、フジテンニンソウの二種類が生育しているそうです。
人だかり ↓

ちょっとした人だかりに近づきます。そこはドライブウェイと北尾根の合流点となります。
そこに居た彼らは、イヌワシに特化したバードウォッチャーたちです。
静馬ヶ原 ↓

目の前の大きな盛り上がりは、北尾根を歩くときの最初のピークで、これを静馬ヶ原と言うようです。
合流点の標高 ↓

ここの高さは、歩き始めから500m弱上がったことになります。山頂まで高さにして、あと250mほど残っています。
琵琶湖が見えた ↓

この場所から、この日初めて琵琶湖を見ます。今回はお天気に恵まれた雨男ですね。
ドライブウェイ ↓

北尾根の合流点から、山上の終点(スカイテラス駐車場というらしい)まで、2kmほど有ります。
サラシナショウマ ↓

サラシナショウマの、ボトルブラシのような花穂が見えました。
コオニユリ ↓

近づけないので、クルマユリとの区別がはっきりと分かりませんが、この山にそれの生育はないようですから、消去法ですが、コオニユリで良さそうです。
アカソ ↓

山側斜面にアカソが盛んに出てきます。
アケボノソウ ↓

今度は、咲いているアケボノソウに遭えましたが、花数は僅かです。
ヨツバヒヨドリ ↓

ヨツバヒヨドリももう終局ですね。今回は、この花に寄るアサギマダラを見ませんでした。
北尾根 ↓

距離が離れたので、北尾根コースがまとまってよく見えてきました。
アキノキリンソウ ↓

やっと、この花の、咲いた姿を見るようになって来ました。
山上の駐車場 ↓

ドライブウェイの終点に着きました。ここの標高は1245mほどのようですから、皆さんが等しく残りの130mほどの高度差を自分の足で稼ぐことになります。
何よりも朝の涼しさときたら、散々暑さにもてあそばれてきただけに、”宝物”のように思えます。
しかし、雨の日が続きますと、洗濯物が乾きにくいとか、それなりの不平も出てきてしまいます。
でも、今のところは、「天の配剤」などと言って、人の力では何とも出来ないうちが華でしょうね。
これが人為的に操ることができるようになると、紛争の火種になりかねないのではないでしょうか。
ドライブウェイを目指す ↓

樹林帯を抜けてから草の道をつづら折れに登っていましたが、一つの尾根に出たので、その尾根を使ってドライブウェイに直登するようにします。
キヌタソウ ↓

今度は日当たりの良い場所で咲いています。
はるか下に自車 ↓

眼下に自分の車を置いた場所が見えています。(白線内)
ドライブウェイに出た ↓

ドライブウェイに出ると、そこには年配の男性が歩いていました。聞くところによると、ドライブウェイの途中まで車に乗せてきてもらい、下ろされた場所から歩いてきているとのことでした。
ツリガネニンジン ↓

車道にはみ出さないように細心の注意をして、本来ご法度の車道歩きをすることにしました。
日当たりのよい道端に、早速ツリガネニンジンが出てきます。
カワラナデシコ ↓

こんな美花も出てきます。
クサボタン ↓

花の咲いたものが、やっと出てきました。
テンニンソウ ↓

花の咲いたテンニンソウもやっと出てきました。この山ではこのテンニンソウと、フジテンニンソウの二種類が生育しているそうです。
人だかり ↓

ちょっとした人だかりに近づきます。そこはドライブウェイと北尾根の合流点となります。
そこに居た彼らは、イヌワシに特化したバードウォッチャーたちです。
静馬ヶ原 ↓

目の前の大きな盛り上がりは、北尾根を歩くときの最初のピークで、これを静馬ヶ原と言うようです。
合流点の標高 ↓

ここの高さは、歩き始めから500m弱上がったことになります。山頂まで高さにして、あと250mほど残っています。
琵琶湖が見えた ↓

この場所から、この日初めて琵琶湖を見ます。今回はお天気に恵まれた雨男ですね。
ドライブウェイ ↓

北尾根の合流点から、山上の終点(スカイテラス駐車場というらしい)まで、2kmほど有ります。
サラシナショウマ ↓

サラシナショウマの、ボトルブラシのような花穂が見えました。
コオニユリ ↓

近づけないので、クルマユリとの区別がはっきりと分かりませんが、この山にそれの生育はないようですから、消去法ですが、コオニユリで良さそうです。
アカソ ↓

山側斜面にアカソが盛んに出てきます。
アケボノソウ ↓

今度は、咲いているアケボノソウに遭えましたが、花数は僅かです。
ヨツバヒヨドリ ↓

ヨツバヒヨドリももう終局ですね。今回は、この花に寄るアサギマダラを見ませんでした。
北尾根 ↓

距離が離れたので、北尾根コースがまとまってよく見えてきました。
アキノキリンソウ ↓

やっと、この花の、咲いた姿を見るようになって来ました。
山上の駐車場 ↓

ドライブウェイの終点に着きました。ここの標高は1245mほどのようですから、皆さんが等しく残りの130mほどの高度差を自分の足で稼ぐことになります。