削ろう会の案内戴きました。
川越大会の案内をプロショップ・ホクトさんから戴きました。
久しぶりに阿保氏の胸の透くあの削りが見られるのかも。
第27回 全国削ろう会 川越大会 のご案内
全国から集まった競技者がそれぞれの自慢の鉋で木材を薄く削り、鉋屑の薄さ・均一さ・
美しさで競い合う”鉋薄削り競技”がメインイベント。
薄く削ることを通して、手道具を使う精密で高度な日本の伝統的木工技術の根幹を修練し、
日本特有の木に対する感性を共感し、古来からの優れた木材文化と資源を守り、これらの
素晴らしい文化を次世代に伝えるものとして行います。
川越は単なる蔵造りのまちのみならず、職人文化の残るまちであり、それがまちの発展に
大きく寄与してきました。
本大会を機に、さらなる職人文化の啓発、未来に向けた輝きある川越を創造いたします。
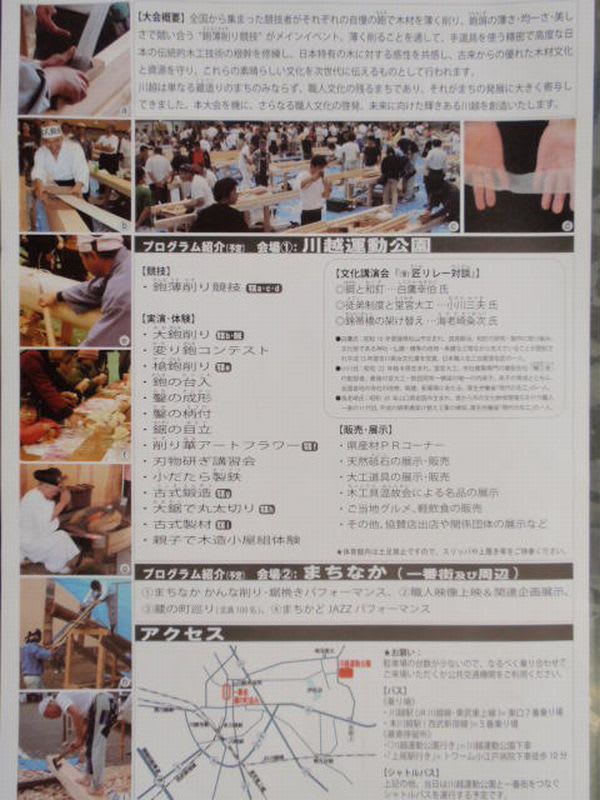
開催日 :平成23年9月10日(土)・11日(日)
メイン会場:廿川越運動公園総合体育館及び公園内
サテライト会場:一番街及びその周辺
【お問合わせ】 全国削ろう会川越大会実行委員会
◎NPO法人川越蔵の会 FAX:049-223-0204
◎川越市文化スポーツ部 文化振興課 電話:049-224-8811(内線 3312)
「第27回 削ろう会 川越大会」日程と開催内容
9月10日(土) 9月11日(日)
11時~ 受付開始
13時~ 開会式
13~16時 各イベント
14~16時 文化講演会「匠リレー対談」
川越町並み見学会 9時~ 開場・鉋薄削り競技開始
10時~ 各イベント開始
14時~ 表彰式
15時 閉会
【主なイベント】
鉋薄削り競技/大鉋削り/変り鉋コンテスト/鉋の台入れ・鑿の成形・製鉄・製材等の実演や体験/
文化講演会/大工道具や県産材等の展示・販売/地元グルメの販売/町並み見学会やまちなかでの
パフォーマンス・・・など。
【文化講演会 「(仮)匠リレー対談」】
◎鋼と和釘・・・白鷹幸伯(しらたかゆきのり)氏
◎徒弟制度と堂宮大工・・・小川三夫氏
◎錦帯橋の架け替え・・・海老崎粂次(えびさきくめつぐ)氏
【主催】 全国削ろう会川越大会実行委員会
【共催】 川越市、NPO法人川越蔵の会
【後援】 埼玉県、川越市教育委員会、川越商工会。(社)小江戸川越観光協会
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村













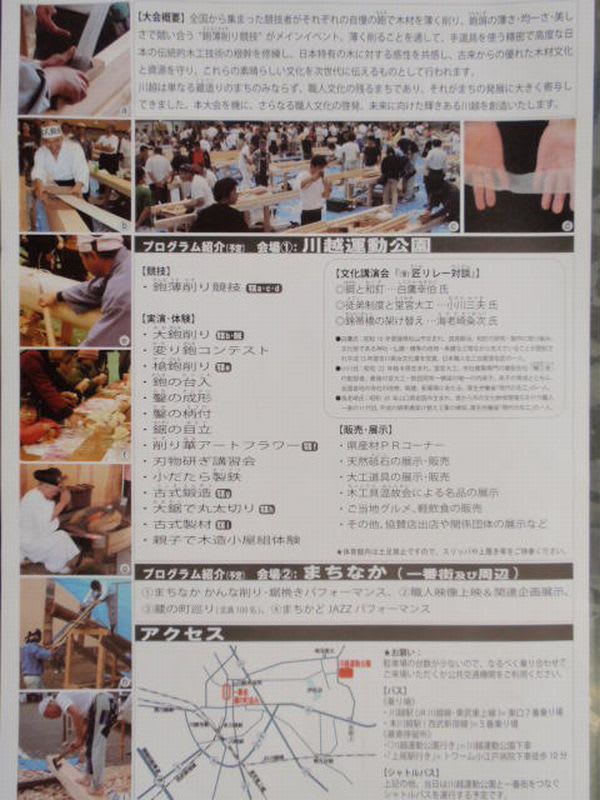



 これが何とも言えないのです。
これが何とも言えないのです。











