関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。
関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行
■ 弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場-1
お大師さまゆかりの寺院を巡る弘法大師霊場には、主に八十八ヶ所と二十一ヶ所があります。
→ ご参考(「ニッポンの霊場」様)
八十八ヶ所はかなりの時間と根気を要し、結願までの道のりはなかなか困難です。
そこで生まれたのが簡易(ミニ)版である二十一ヶ所という説がみられます。
簡易(ミニ)版であれば八十八ヶ所の札所からダイジェスト的に選定すればいい筈ですが、そうはなっていないケースもみられます。
「弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場」(以下、御府内二十一ヶ所霊場)もそのひとつです。
「御府内二十一ヶ所霊場」は、『東都歳事記』(国書データベース)に霊場名「弘法大師二十一ヶ所参」と、第21番が湯島霊雲寺であることが記載されていますが、札所一覧は記載されていません。
(これは後述する「弘法大師二十一ヶ寺」を示すものかもしれません。)
しかし、「ニッポンの霊場」様に札所リストが掲載されているので、こちらにもとづき巡拝しました。
『東都歳事記』の編纂は天保九年(1838年)ですから、それ以前の開創とみられます。
「ニッポンの霊場」様によると、この霊場は元禄(1688年)から宝暦(1751年)の間に開創とされる古い霊場で、宝暦五年(1755年)頃の開創とされる御府内霊場より古い可能性があります。
第21番がふたつあるようで、札所数は22となります。
台東区内の札所が多く、御府内八十八ヶ所霊場よりも東(下町)寄りの霊場となっています。
当初は第20番の寛永寺 一乗院のみ天台宗で残りはすべて(広義の)新義真言宗でしたが、明治に一乗院が廃寺となったのちは根岸の時雨岡不動堂(西蔵院の境外仏堂)に承継されたといい、現在はすべて(広義の)新義真言宗寺院となっています。
【弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場】
■ 弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場-1
1番 法輪山 法幢院 浄光寺
真言宗豊山派 荒川区西日暮里3-4-3 /豊・荒
2番 補陀落山 観音院 養福寺
真言宗豊山派 荒川区西日暮里3-3-8 /豊・荒
■ 弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場-2
3番 蓮葉山 妙智院 観音寺
真言宗豊山派 台東区谷中5-8-28 /御・江
4番 長谷山 元興寺 加納院
新義真言宗 台東区谷中5-8-5 /御・江
5番 天瑞山 観福寺 明王院
真言宗豊山派 台東区谷中5-4-2 /御・江
6番 初音山 東漸寺 観智院
真言宗豊山派 台東区谷中5-2-4 /御・江
■ 弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場-3
7番 仏到山 無量寿院 西光寺
新義真言宗 台東区谷中6-2-20 /江
8番 瑠璃光山 薬王寺 長久院
真言宗豊山派 台東区谷中6-2-16 /御・江
9番 宝塔山 龍門寺 多寶院
真言宗豊山派 台東区谷中6-2-35 /御・江
10番 本覚山 宝光寺 自性院
新義真言宗 台東区谷中6-2-8 /御・江
■ 弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場-4
11番 圓明山 宝福寺 西蔵院
真言宗智山派 台東区根岸3-12-38 /荒
12番 鐡砂山 観音院 世尊寺
真言宗豊山派 台東区根岸3-13-22 /荒
13番 東光山 等印院 龍泉寺
真言宗智山派 台東区竜泉2-17-15 /荒
14番 恵日山 延命寺 地蔵院
真言宗智山派 台東区元浅草1-15-8 /荒
■ 弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場-5
15番 瑞光山 如意寺 密厳院
真言宗豊山派 荒川区荒川4-16-3 /豊
16番 五剣山 普門寺 大乗院
真言宗智山派 台東区元浅草4-5-16 /荒
17番 和光山 興源院 大龍寺
真言宗霊雲寺派 北区田端4-18-4 /御・豊
18番 象頭山 観音寺 本智院
真言宗智山派 北区滝野川1-58-2 /荒
19番 阿遮羅山 蓮華寺 阿遮院
真言宗豊山派 荒川区東尾久3-6-25 /豊
■ 弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場-6
20番 東叡山 寛永寺 一乗院(廃寺)
天台宗 台東区上野公園
→(20番) 時雨岡(御行の松)不動堂
真言宗智山派 台東区根岸4-9-5
21番-1 宝林山 大悲心院 霊雲寺
真言宗霊雲寺派 文京区湯島2-21-6 /御・江
21番-2* 大黒山 宝生院
真言宗智山派 葛飾区柴又5-9-8 /南
※ 21番-2* 宝生院は池之端茅町から移転
〔八十八ヶ所霊場の略記凡例〕
御:御府内八十八ヶ所霊場
江:江戸八十八ヶ所霊場
豊:豊島八十八ヶ所霊場
荒:荒川辺八十八ヶ所霊場
南:南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)
↑をみると、22ヶ所のうち御府内八十八ヶ所霊場との重複札所はわずか9ですが、ほぼすべての札所が複数の八十八ヶ所弘法大師霊場と重複しています。
しかも第12番世尊寺は、荒川辺八十八ヶ所霊場の第1番を担われています。
ここからしても、御府内二十一ヶ所霊場は、単なる御府内八十八ヶ所霊場の簡易(ミニ)版とはいえないと思います。
上記のとおり、「ニッポンの霊場」様によると、この霊場は元禄(1688年)から宝暦(1751年)の間に開創とされ、宝暦五年(1755年)頃の開創とされる「御府内八十八ヶ所霊場」より古い可能性があります。
同じく「ニッポンの霊場」様によると、「荒川辺八十八ヶ所霊場」は天保九年(1838年)年頃かそれ以前、「豊島八十八ヶ所霊場」は明治41年(1908年)の開創ですから、やはりこの霊場の方が古いとみられます。
「江戸八十八ヶ所霊場」を「御府内八十八ヶ所霊場」の前身と仮定すると、むしろ「江戸八十八ヶ所霊場」をベースのひとつとして成立したのかもしれません。
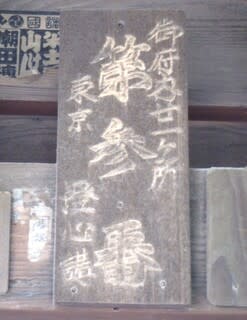
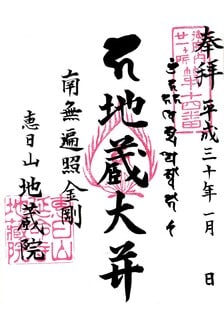
【写真 上(左)】 第3番観音寺の札所板
【写真 下(右)】 第14番地蔵院の御朱印
---------------------------------
「御府内二十一ヶ所霊場」とは別に「弘法大師二十一ヶ寺」という霊場もあります。
【弘法大師二十一ヶ寺】 (八十八ヶ所霊場の略記凡例は同上)
1番 萬昌山 金剛幢院 圓満寺
真言宗御室派 文京区湯島1-6-2 /御・江
○2番 宝塔山 多寶院
真言宗豊山派 台東区谷中6-2-35 /御・江
○3番 五剣山 普門寺 大乗院
真言宗智山派 台東区元浅草4-5-16 /荒
4番 清光院 台東区下谷(廃寺)
○5番 恵日山 延命寺 地蔵院
真言宗智山派 台東区元浅草1-15-8 /荒
6番 阿遮山 円満寺 不動院
真言宗智山派 台東区寿2-5-2 /御・江
7番 峯松山 遮那院 仙蔵寺
真言宗智山派 台東区寿2-8-15 /荒
8番 高野山 金剛閣 大徳院
高野山真言宗 墨田区両国2-7-13 /御・江
9番 青林山 最勝寺 龍福院
真言宗智山派 台東区元浅草3-17-2 /御・江
○10番 本覚山 宝光寺 自性院
新義真言宗 台東区谷中6-2-8 /御・江
11番 摩尼山 隆全寺 吉祥院
真言宗智山派 台東区元浅草2-1-14 /御・江
12番 神勝山 成就院
真言宗智山派 台東区元浅草4-8-12 /御・江
13番 広幡山 観蔵院
真言宗智山派 台東区元浅草3-18-5 /御・荒
14番 望月山 般若寺 正福院
真言宗智山派 台東区元浅草4-7-21 /御・江
○15番 仏到山 無量寿院 西光寺
新義真言宗 台東区谷中6-2-20 /江
16番 鶴亭山 隆全寺 威光院
真言宗智山派 台東区寿2-6-8 /御・江
17番 十善山 蓮花寺 密蔵院
真言宗御室派 中野区沼袋2-33-4(移転) /御・江
○18番 象頭山 観音寺 本智院
真言宗智山派 北区滝野川1-58-2 /荒
○19番 瑠璃光山 薬王寺 長久院
真言宗豊山派 台東区谷中6-2-16 /御・江
20番 玉龍山 弘憲寺 延命院
真言宗智山派 台東区元浅草4-5-2 /御・荒
○21番 宝林山 大悲心院 霊雲寺
真言宗霊雲寺派 文京区湯島2-21-6 /御・江
札所の出所は↓『御府内八十八ヶ所 弘法大師二十一ヶ寺 版木』(台東区教育委員会刊)です。
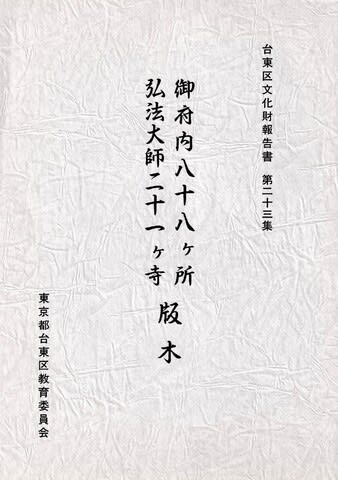
「弘法大師二十一ヶ寺御詠歌所附版木」が伝える弘法大師霊場で、この附版木は寛政二年(1790年)の開版ですからこちらもかなり古い来歴をもちます。
「御府内二十一ヶ所霊場」と「弘法大師二十一ヶ寺」の重複札所は○を付した8ヶ所ですが、両者の関係についてはよくわかりません。
「弘法大師二十一ヶ寺」は「御府内二十一ヶ所霊場」よりも御府内八十八ヶ所霊場との重複が多く、こちらの方が「御府内八十八ヶ所霊場の簡易(ミニ)版」の性格が強いのでは。
筆者は「弘法大師二十一ヶ寺」も結願していますが、こちらは21札所のうち廃寺となった第4番清光院を除いてすべて御朱印を拝受しています。
---------------------------------
■ 「御府内二十一ヶ所霊場」と「弘法大師二十一ヶ寺」の関係について
『御府内八十八ヶ所 弘法大師二十一ヶ寺 版木』(台東区教育委員会刊、以下「同書」)には下記の記載があります。
**********(引用)
当巡礼(弘法大師二十一ヶ寺)の開設は、御府内札所(御府内八十八ヶ所霊場)設定の宝暦年間(1751-1764年)より本版木開版の寛政二年(1790年)までの三〇数年の間のことと考えたい。
さらに『東都八十八ヶ所』は明治時代の二十一ヶ所を紹介している(巻末一覧表/註:同書『弘法大師御府内二十一所』項には「明治期の案内によったものである」というが、出典は明記されていない)。
これによれば、寛政二年と比べ十五ヶ寺の異動があり、他の六ヶ寺中の五ヶ寺は札所番号が変わっている。明治時代の札所中、第一一番西蔵院には(中略)江戸末期までに大きな改変があったと推定できる。
ところが、(御府内八十八ヶ所霊場)のように札所の改変は寺院の統・廃合に応じた場合が多いが、寛政二年当時の札所は明治一〇年までは確実に顕在していた。
このことから改変の理由は他にあったと思われ、あるいは、当巡礼(弘法大師二十一ヶ寺)は一時衰え、江戸末期に改めて編成されたとも考えられる。
**********(引用おわり)
上記の「明治時代の二十一ヶ所」は、「御府内二十一ヶ所霊場」と同一です。
「ニッポンの霊場」様によると「御府内二十一ヶ所霊場」の開創は元禄(1688年)から宝暦(1751年)。
これに対して同書による「弘法大師二十一ヶ寺」の開設は宝暦年間(1751-1764年)より寛政二年(1790年)の間で、「御府内二十一ヶ所霊場」の方が古い可能性があります。
さらに、同書でも「札所の改変は寺院の統・廃合に応じた場合が多い」と述べているとおり、神仏分離前の江戸期に全面改編に等しい札所改編があったとはどうしても考えられません。
「弘法大師二十一ヶ寺」の札所の多くが江戸時代に廃されたならばともかく、ほとんどの札所は現存しています。
となると、「弘法大師二十一ヶ寺」が改編されて「御府内二十一ヶ所霊場」(同書では「明治時代の二十一ヶ所」)になったのではなく、もともと江戸期から別個の霊場だったのでは?
なにぶん、弘法大師二十一ヶ寺の版木は発見されたばかり(おそらく平成に入ってからの発見と思われる)で、今後研究が進めば新たな関係がみえてくるのかもしれません。
---------------------------------
その他、近隣の墨田・葛飾両区をメインとする「弘法大師 隅田川二十一ヶ所霊場」という霊場もあり、下町エリアの二十一ヶ所の札所は錯綜気味です。
なお、「弘法大師 隅田川二十一ヶ所霊場」は「荒川辺八十八ヶ所霊場」あるいは「荒綾八十八ヶ所霊場」の簡易(ミニ)版とみる説もありますが詳細は不明です。
---------------------------------
「御府内二十一ヶ所霊場」の御朱印については、「御府内八十八ヶ所霊場」との重複札所では後者の御朱印の授与となるようです。
「豊島八十八ヶ所霊場」との重複札所でも同様の模様です。
この条件のもとですが、筆者は22ヶ所のうち20ヶ所で御朱印を拝受しています。
「御府内二十一ヶ所霊場」のみの札所の場合は御府内二十一ヶ所霊場での申告としましたが、この霊場を回る人は極めて希らしく、霊場名が通じない場合もありました。
むしろ、「お大師さまのお参り」あるいは「二十一大師のお参り」と申告した方が通りがいいかもしれません。
「御府内八十八ヶ所霊場」との重複札所以外では御朱印授与を想定されていない感じがあり、ご不在のケースもかなりあります。
御朱印目当てというより、荒綾霊場や荒川辺霊場と同様、往年の弘法大師霊場を辿るというスタンスが必要かもしれません。
御府内八十八ヶ所霊場は結願し、ご案内の記事もUP(→ こちら)していますが、御府内二十一ヶ所霊場は先日ようやく結願しましたので、御府内八十八ヶ所霊場の記事と同様のフォーマットでご紹介していきたいと思います。
それでは第1番から順にご紹介していきます。
なお、御朱印の授与については現在休廃止している可能性があります。
■ 第1番 法輪山 法幢院 浄光寺
(じょうこうじ)
荒川区西日暮里3-4-3
真言宗豊山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来?
司元別当:諏方神社(荒川区西日暮里)
他札所:豊島八十八ヶ所霊場第5番、荒川辺八十八ヶ所霊場第8番、東都六地蔵霊場第3番、豊島六地蔵霊場第3番
第1番札所は日暮里の浄光寺です。
谷中から日暮里につづく「諏訪台」にある真言宗豊山派の寺院です。
『新編武蔵風土記稿』、『江戸名所図会』、現地掲示などから縁起・沿革を追ってみます。
創建年代は当山が諏方神社の別当であったため、諏方神社の創建(現地掲示によると元久二年(1205年))と同時期とみられています。
なお、諏方神社は豊嶋左衛門尉経泰の創建と伝わりますが、太田道灌(1432-1486年)とする説もあり、別当の浄光寺についても豊島左衛門尉経泰説と太田道灌説があるようです。
創建時から法輪山法幢院を号したとみられ、御本尊は薬師如来と伝わります。
諏方神社は三代将軍徳川家光公(1604-1651年)に社領五石を安堵され、日暮里・谷中の総鎮守として広く信仰を集めたといい、その別当である当山も重要な役割を果たしていたとみられます。
元禄四年(1691年)には空無上人の勧化により「江戸六地蔵」(近郷六地蔵)のひとつが安置されています。
この「江戸六地蔵」は、現在まで伝わる「後の六地蔵」ではなく、下谷池之端影向山心行寺三世の(慈済庵)本誉空無(浄土木食)が元禄四年(1691年)に建立開眼した「はじめの六地蔵」です。
『江戸砂子温故名蹟誌 6巻3』(国立国会図書館DC)の醫王山 真性寺の項には以下の記載があります。
***************
地蔵坊正元法師建立唐銅六地蔵の三番也所謂六軀ハ
一番 品川 真言 品川寺
二番 四谷 浄土 大宗寺
三番 巣鴨 同(真言) 真性寺
四番 山谷 禅 東禅寺
五番 深川 浄土 霊巌寺
六番 深川 真言 永代寺
右六地蔵の●●元坊ハ俗名吉之郎とて八百屋の女お七●●もの●出家と云もの●●出家 ●六軀を造立●といひつ
されは宝永年中沙門正元坊か建立せし金銅丈六の六軀ハ世に後の六地藏といふと也
慈済庵空無上人勧化の助力を以 金銅立像八尺の地藏六軀を造立し江戶六ヶ所に安置す 元禄四年開眼供養を執行す これをはしめの六地藏といふ所謂六所ハ
一番 駒込 浄土 瑞泰寺
二番 千駄木 浄土 專念寺
三番 日暮里 諏訪 浄光寺
四番 池端 心行寺
五番 東叡山 大仏側 慈濟庵
六番 淺艸寺内 正智院
***************
下欄の「はし(じ)めの六地藏」の三番に浄光寺の記載があります。
「はじめの六地蔵」は毎月二十四日ないし十八日の縁日に多くの信者を集めたと伝わりますがいつしか衰退し、いくつかは廃寺となったこともあり、現在江戸六地蔵として知られているのは正元坊建立の「後の六地蔵」です。
「はじめの六地蔵」で現存するのは浄光寺と専念寺だけとみられています。
なお、「江戸六地蔵」については→ (こちらの記事)をご覧ください。
元文二年(1737年)有徳院殿(八代将軍徳川吉宗公)が御遊猟の折りに当山に立ち寄られて以降、将軍鷹狩りの際の御膳所に定められたという格式をもちます。
山内には、三代将軍徳川家光公が腰掛けたという「三代将軍御腰掛石」があります。
高台にあって眺望に優れた「諏訪台」は江戸時代、人気の景勝地で、諏訪台八景(筑波茂陰、黒髪晴雪、前畦落雁、後岳夜鹿、隅田秋月、利根遠帆、暮荘烟雨、神祠老松)が定められて詩歌にうたわれました。
とくに浄光寺の雪景色は有名で「雪見寺」と称されました。
近くの本行寺は「月見寺」、青雲寺は「花見寺」と呼ばれ、江戸の文人墨客を集めたことが記録に残っています。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編武蔵風土記稿 豊島郡巻十』(国立国会図書館)
(新堀村)諏訪社
村内及谷中ノ惣鎮守トス 一寸許ナル薄黒キ圓石ヲ神躰トス 社領五石ノ御朱印ハ慶安二年(1649年)附ラル 元享年中(1321-1324年)豊嶋左衛門尉経泰信州ノ諏訪ヲ勧請セル由縁起ニ載タリ 例祭七月廿六日社邊東ノ方ヲ諏訪臺ト号シ眺望勝景ノ地ナリ 林信充カ浄光寺八景詩歌ハ則此処ニテノ作ナリ 所謂八景ハ筑波茂陰 黒髪晴雪 前畦落雁 後岳夜鹿 隅田秋月 利根遠帆 暮荘烟雨 神祠老松ナリ 皆望中ノ景色ナリ 末社 山王 稲荷
別当浄光寺
新義真言宗田端村与楽寺末 法輪山法幢院ト号ス 本尊薬師 元文二年四月十四日 有徳院殿御遊猟ノ時始テ当寺ヘ成セ給ヒ 同五年正月廿五日御膳所ニ命セラレシヨリ 今モ此邊放鷹ノ節ハ御膳所トナレリ
御腰掛石 庭前ニアリ 有徳院殿始テ渡御アリシ時憩セ給フ石ナリト云傳フ
人麿社 頓阿作ノ像ヲ安ス 享保年中起立ス
地蔵 銅像ニテ近郷六地蔵ノ一ナリ
■ 『江戸名所図会 巻之五』(国立国会図書館)
同所(日暮里)北の方、諏訪の台にあり。信州諏訪の祭神におなじ。当社は元享の頃、豊島左衛門佐建立す。其後太田道灌、此地を江戸城の出張の砦とせしみぎり、修営して、郭内の鎮守となせしとぞ。社頭今も杉の木立生茂りて上久(かみさび)たり。当社別当は真言宗にして、法輪山浄光寺と号す。当寺の書院は、高崖に架して、眼下に千歩の田園を見下せり。風色尤も幽雅にして、四時の眺望たらずと云ふ事なし。中に雪のながめ勝れたれば、世に称して雪見寺とも名くとかや。
人麻呂の祠
当院庭中に安ず。頓阿法師の作にして、杉の白木をもって作り。是則ち播州住吉社へ奉納ありし三百体の其一なりといへり。
地蔵堂
同じく門のかたはらにあり。本尊は紫銅(カラカネ)にて、立像八尺の地蔵尊なり。慈済庵空無上人建立ありて、元禄四年に開眼供養す。六地蔵の一なり。
■ 『荒川区史』(国立国会図書館)
法輪山浄光寺は法幢院とも号し新義真言宗豊山派に属し田端町與楽寺末、本尊は薬師如来である。
当寺の創立は不明であるが、古老の説に太田道灌の建立と云ふ。一説には元享年間(1321-1324年)豊島左衛門尉経泰の創建せし所とも云ふ。
寺は諏訪台の高処を占め、舊幕時代は諏方神社の別当職で、此の境内は展望開豁であって雪見に適していたので俗に之を雪見寺と称した。
元文二年(1737年)将軍吉宗(一説には三大将軍家光とも云ふ)が遊猟に際し当寺に休憩し、又同五年正月膳所に命ぜられしよりその事幕府の末に及んだ。(中略)
江戸六地蔵の内二體が当寺入口左側にある。
古記に、「地蔵堂 本尊は紫銅にて立像八尺の地蔵尊なり。慈済庵空無上人建立ありて元禄四年(1691年)に開眼供養す、六地蔵の一なり。」とある。
尚、地蔵の外不動、観音、厄除大師等も安置されている。古くは人麻呂祠があった。
【現地案内掲示/荒川区教育委員会】
■ 江戸六地蔵と雪見寺(浄光寺)
山門をくぐって左手に、高さ一丈(約三メートル)の銅造地蔵菩薩がある。元禄四年(1691年)、空無上人の勧化により江戸東部六か所に六地蔵として開眼された。もと門のかたわらの地蔵堂に安置されていたもので門前は「地蔵前」ともよばれる。
浄光寺は、真言宗豊山派の寺院。法輪山法幢院と称し、江戸時代までは諏方神社の別当寺であった。元文二年(1737年)、八代将軍吉宗が鷹狩の際にお成りになり、同五年以降御膳所となった。境内に「将軍腰かけの石」がある。
眺望にすぐれた諏訪台上にあり、特に雪景色がすばらしいというので「雪見寺」ともよばれた。
【現地案内掲示/荒川区教育委員会】
■ 諏訪神社
信濃国上諏訪社と同じ建御名方命を祀る。
当社の縁起によると、元久二年(1205年)豊嶋左衛門尉経泰の造営と伝える。
江戸時代、三代将軍徳川家光に社領五石を安堵され、日暮里・谷中の総鎮守として広く信仰を集めた。
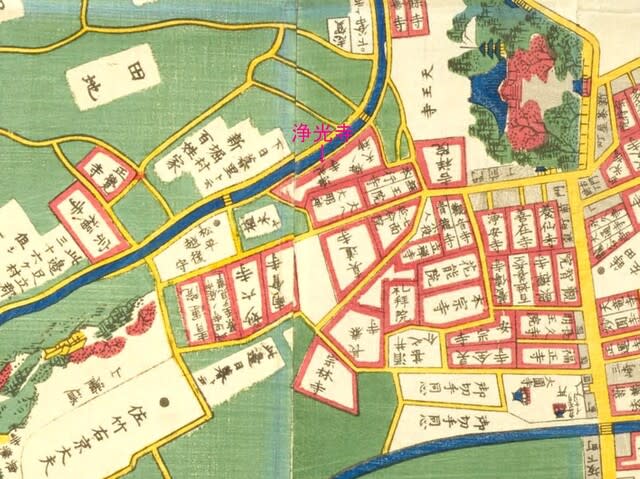
出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』 根岸谷中辺絵図,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはJR・メトロ千代田線「西日暮里」駅で徒歩数分。
「西日暮里」駅は武蔵野台地の崖の下にあり、駅出口からすぐの歩道橋を兼ねた急な階段を上ると西日暮里公園です。

西日暮里公園
この公園の案内板には下記のとおりあります。
---------------------------------
道灌山は、上野から飛鳥山へと続く台地上に位置します。(中略)この公園を含む台地上にひろがる寺町あたりは、ひぐらしの里と呼ばれていました。
道灌山の地名の由来として、中世、新堀(日暮里)の土豪、関道閑が屋敷を構えたとか、江戸城を築いた太田道灌が出城を造ったなどの伝承があります。
江戸時代、人々が日の暮れるのも忘れて四季おりおりの景色を楽しんだことから、「新堀」に「日暮里」の文字をあてたといわれています。(中略)
道灌山・ひぐらしの里は、江戸時代の中頃になると、人々の憩いの場として親しまれるようになりました。寺社が競って庭園を造り、さながら台地全体が一大庭園のようでした。
桃さくら 鯛より酒のさかなには みところ多き 日くらしの里
十返舎一九
雪見寺(浄光寺)、月見寺(本行寺)、花見寺(妙隆寺、修性院、青雲寺)、諏訪台の花見、道灌山の虫聴きなど、長谷川雪旦や安藤広重ら著名な絵師の画題となり、今日にその作品が知られています。
---------------------------------
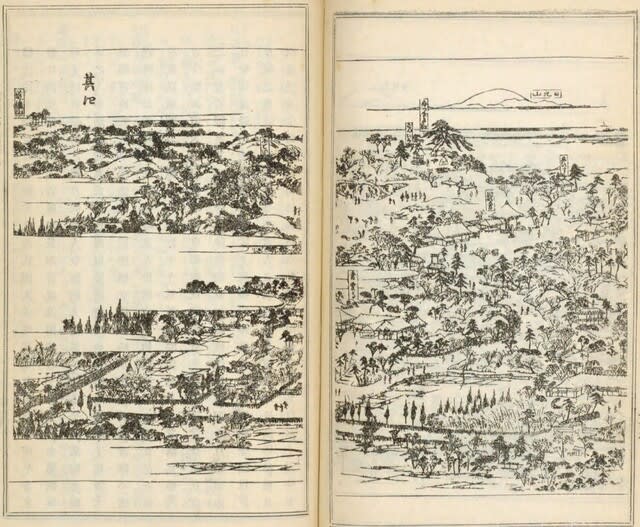
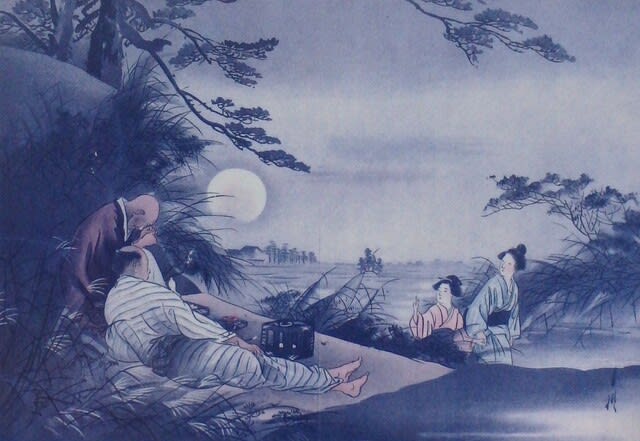
【写真 上(左)】 ■ 『江戸名所図会 第3 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)
【写真 下(右)】 道灌山の虫聴き(現地掲示より)
西日暮里公園あたりは「虫聴き」の名所として知られていたようです。
公園を抜けて左手の社叢は諏方神社。
日暮里・谷中の総鎮守として人々の崇敬を集め、浄光寺はその別当でした。
諏方神社では、日暮里・谷中エリアでは貴重な神社の御朱印を授与されています。

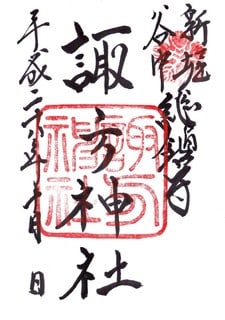
【写真 上(左)】 諏方神社
【写真 下(右)】 諏方神社の御朱印
浄光寺は、諏方神社の鳥居のよこに山門を構えています。
いかにも別当然とした位置関係です。


【写真 上(左)】 諏方神社鳥居と浄光寺山門
【写真 下(右)】 浄光寺山門


【写真 上(左)】 山門の扁額
【写真 下(右)】 六地蔵三番目の石標
山門脇には「六地蔵三番目」の石標が置かれています。
山門は切妻屋根桟瓦葺の高麗門で、見上げに山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 二体の地蔵尊
【写真 下(右)】 西村和泉守作の地蔵尊
山門をくぐって左手には座像と立像の二体の銅造地蔵尊が御座し、いずれも区の指定文化財。
手前の銅造地蔵菩薩座像は江戸の鋳物師として有名な西村和泉守の作で、文化六年(1809年)の造立。
奥の銅造地蔵菩薩立像は元禄四年(1691年)造立の江戸六地蔵三番目の尊像で、下谷心行寺二世空無上人の権化により元禄四年(1691年)に開眼されています。
もとは山門脇に奉じられていましたが、昭和初期に山内に遷されたとのことです。
江戸六地蔵はもとより、西村和泉守作の地蔵尊の台座にも多数の願主の名が刻まれていることから、浄光寺は江戸時代地蔵信仰の寺として知られていたとみられます。


【写真 上(左)】 江戸六地蔵の地蔵尊
【写真 下(右)】 土蔵造りの堂宇
地蔵尊のさらに奥に土蔵造りの堂宇がありますが、扁額がなく堂宇本尊は不明です。


【写真 上(左)】 本堂-1
【写真 下(右)】 本堂-2


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝の扁額
山内左手奥の階段上に本堂。
入母屋造桟瓦葺で手前に向拝を附設しています。
身舎はコンクリ造で、水引虹梁は装飾少なく直線的ですが中備に蟇股を置いています。
向拝見上げには寺号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 山門と六地蔵
【写真 下(右)】 石佛群
山門右手の壁際には石佛群と六地蔵。
山内のどこかにおそらく「将軍の腰掛石」があると思いますが、超うかつにも撮りわすれました。
御朱印は庫裏にて拝受しました。
先日(2024年4月)の参拝時には庫裏の扉に「御朱印対応自粛中です。」の張り紙があり、御朱印授与を休止している模様ですが、Web情報には「セルフ捺しの御朱印あり」の情報もあって、よくわかりません。
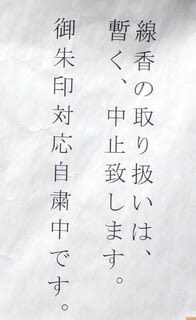
もし、御朱印授与休止中だとしたら、現時点では豊島八十八ヶ所霊場の御朱印はコンプリートできないことになります。
〔 浄光寺の御朱印 〕
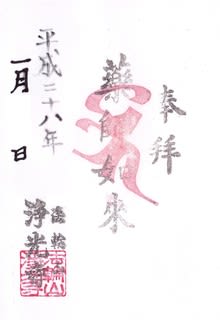
中央に「薬師如来」の印判と薬師如来のお種子「バイ」の御寶印。
左に山号・寺号の印判と寺院印が捺されています。
■ 第2番 補陀落山 観音院 養福寺
(ようふくじ)
荒川区西日暮里3-3-8
真言宗豊山派
御本尊:如意輪観世音菩薩
札所本尊:如意輪観世音菩薩?
司元別当:
他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第7番、東京三十三観音霊場第28番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第27番、東都七観音霊場第5番、近世江戸三十三観音霊場第10番、東方三十三観音霊場第12番、江戸坂東三十三ヶ所観音霊場第9番、豊島六地蔵霊場第6番
第2番札所は日暮里の養福寺です。
こちらも「諏訪台」にある真言宗豊山派の寺院です。
『新編武蔵風土記稿』、 『江戸名所図会』、荒川区資料、現地掲示などから縁起・沿革を追ってみます。
Wikipediaには元和六年(1620年)、法印乗蓮によって開山とあります。
『江戸名所図会』には開山は木食義高上人とありますが、荒川区資料その他には湯島圓満寺の木食義高上人(享保三年(1718年)没)は中興とあります。
『江戸名所図会』によると、義高上人は初め高野山高臺院の住職でしたが当地に赴き、百番の観音札所を遷す事を企られたといいます。
当地にあった小庵を開いて寺とし、野山より遷し奉る霊像を礼拝しつつ修補して、ついに百體の尊像を安されたといいます。
『新編武蔵風土記稿』によれば新義真言宗田端村東覺寺門徒(末)、補院山観王院と号し、御本尊は阿弥陀如来。
仁王門、鐘楼を擁し、天神社、諏訪社が御鎮座とあります。
観音堂には春日作の如意輪観世音菩薩、弘法大師御作の十一面観世音菩薩、慈覚大師御作の正観世音菩薩を安置ともあります。
寺宝として台徳院殿(二代将軍徳川秀忠公)御筆の色紙ありと記されています。
仁王門は宝永年間(1704-1711年)に建立とされ、門中の仁王像は運慶作とも伝わります。
養福寺には、「日暮里(ひぐらしのさと)」を訪れた江戸時代の文人たちの遺蹟が残ります。
「梅翁花樽碑」「雪の碑」「月の碑」などからなる「談林派歴代の句碑(区指定文化財)」や、江戸時代の四大詩人の一人、柏木如亭を偲んで建てられた「柏木如亭の碑」、自堕落先生こと山崎北華が自ら建立の「自堕落先生の墓」など、文学の香り高い寺院として知られています。
当山は、筆者にて確認できた範囲でじつに9もの霊場札所となっています。
『新編武蔵風土記稿』には「観音堂には春日作の如意輪観世音菩薩、弘法大師御作の十一面観世音菩薩、慈覚大師御作の正観世音菩薩を安置」とあり、おのおのの観音様が札所本尊となられていた可能性があります。
『江戸名所図会』の記事からすると、上野王子駒込辺三十三観音霊場は西國写しなので春日作の如意輪観音、江戸坂東三十三ヶ所観音霊場は板東写しなので弘法大師御作の十一面観音、近世江戸三十三観音霊場ないし東方三十三観音霊場を秩父写しと見立てると慈覚大師御作の正観音がそれぞれ札所本尊であった可能性があります。
『江戸切絵図』では当山とおぼしき場所に「梅ノ天神」の記載があります。
『新編武蔵風土記稿』には山内に「天神社」とあるので、こちらの天神社は梅の名所だったのかもしれません。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編武蔵風土記稿 豊島郡巻十』(国立国会図書館)
(新堀村)養福寺
新義真言宗田端村東覺寺門徒 補院山観王院ト号ス 中興ハ湯嶋圓満寺住職木食義高ナリ 本尊彌陀 寺寶ニ台徳院殿御筆ノ色紙アリ 伝来詳ナラス左ノ如シ
~ いか●にむかし むすへる契にて こ乃世にかゝる 中乃隔り ~
天神社 諏訪社
観音堂 春日作ノ如意輪観音 弘法大師作ノ十一面観音 慈覚大師作ノ正観音ヲ安置ス
鐘楼 仁王門
■ 『江戸名所図会 巻之五』(国立国会図書館)
観王院と号す。同所(日暮里)北の方にあり。本尊は三尊の彌陀佛、開山は木食義高上人なり。
観音堂
西國板東秩父百番の札所をうつせり。
本尊如意輪観音 佛工春日の作にして、西國札所第一番紀州那智山のうつしなり。
十一面観音 弘法大師の作にして、板東札所第一番鎌倉杉本のうつしなり。
正観音 慈覚大師の作にして、秩父札所第一番四萬部寺のうつしなり。
抑此百観音は、義高上人の建立なり。上人初め高野山の高臺院に住職たりしが、後彼寺を退去し、当地に赴き、百番の札所をうつさん事を企つ。是本土に至りがたき兒女等の結縁の為となり。拠て此地に小庵のありけるを、闢きて寺とし(往古太田道灌勧請ありし下諏訪明神の社地なり)、数千歩の地を寄付せられしとぞ。
本尊おほくは野山より遷し奉る霊像なりといへども、百體に充たざるを嘆き、これを修補し、一軆毎に佛舎利一顆を御首に籠め、竟に百體の尊像全からしむとなん。
二王門の額に補陀山とあるは、油小路隆貞卿の眞蹟なり。
■ 『荒川区史』(国立国会図書館)
補陀落山養福寺は又観音院と称し新義真言宗豊山派に属し田端の與楽寺末である。
本尊は阿弥陀如来、開基並びに其の年代は不明であるが、中興開山は木食義高上人(湯島圓満寺)と云はれ享保三年(1718年)示寂。
今本堂の外に観音堂地蔵堂等がある。
観音堂は如意輪観音(帝都七観音の一)を本尊とし、其の他百軆観音像が安置されて居る。
西國第二十七番播磨國書寫山及び秩父第一番四萬部より移したものである。
又御府内二十一ヶ所第二番 豊島弘法大師 荒川辺八十八ヶ所第七十三の霊場である。
当寺の仁王門は寶永年間の建立で仁王尊二天王像が安置されて居る。二天王像は運慶の作と伝へる。
本堂の如意輪観音は春日作と伝へ、其の他弘法大師作の十一面観音、慈覚大師作の正観音と伝へられるものも安置されて居る。
境内の枝絲桜は古来有名。
【現地案内掲示/荒川区教育委員会】
■ 養福寺と文人たち
養福寺は真言宗豊山派の寺院で、補陀落山観音院と号し、湯島円満寺の木食義高(享保三年(1718年)没)によって中興されたという。江戸時代、多くの文人たちが江戸の名所である「日暮里(ひぐらしのさと)」を訪れ、その足跡を残した。なかでも養福寺は「梅翁花樽碑」「雪の碑」「月の碑」などからなる「談林派歴代の句碑(区指定文化財)」や、江戸時代の四大詩人の一人、柏木如亭を偲んで建てられた「柏木如亭の碑」、畸人で知られた自堕落先生こと山崎北華が自ら建てた「自堕落先生の墓」などさまざまな文人の碑が残る寺として知られている。
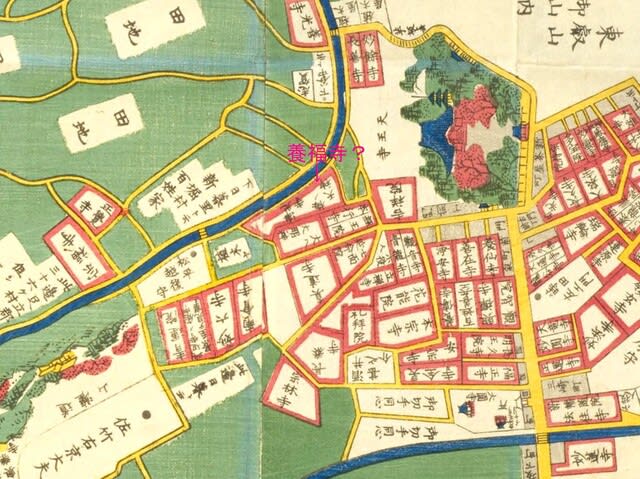
出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』 根岸谷中辺絵図,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはJR・メトロ千代田線「西日暮里」駅で徒歩約5分。
「西日暮里」駅方向から来ると「諏訪台通り」の浄光寺の並びにあります。


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 山内入口


【写真 上(左)】 門柱の寺号札
【写真 下(右)】 六地蔵
「諏訪台通り」からやや引きこんで、まずは門柱を構え、その先の朱塗りの仁王門が目を引きます。
切妻屋根桟瓦葺、三間一戸の八脚門で見上げに寺号扁額を掲げ、脇間に二王尊が御座します。


【写真 上(左)】 仁王門
【写真 下(右)】 鐘楼
山内は緑が多く、しっとりと落ち着いた空気感。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 修行大師像
本堂は入母屋造桟瓦葺で、前面すべてに向拝屋根が置かれているので、二重屋根風の意匠となっています。
身舎はコンクリ造ながら向拝正面に桟唐戸を置き、その両側に二つ引き紋を配して風格をたたえる堂前です。

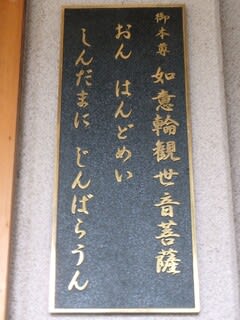
【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 御本尊の御真言
御本尊は如意輪観世音菩薩で、向拝柱には御真言が掲出されていました。
堂前には修行大師像が御座され、御府内弘法大師霊場の趣ゆたかです。
御朱印は庫裏にて拝受しました。
〔 養福寺の御朱印 〕※豊島霊場の御朱印
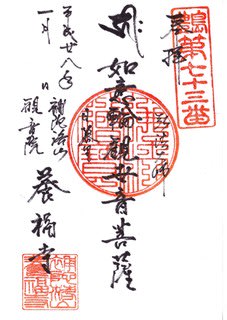
中央に「如意輪観世音菩薩」のお種子「キリーク」&尊格と「弘法大師」の揮毫と三寶印。
右上に「豊島第七十三番」の札所印。
左に山号・院号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内二十一ヶ所霊場の御朱印-2)
【 BGM 】
■ 夢の大地 - Kalafina
■ This Love - アンジェラ・アキ
■ 本当の音 [Hontou no Oto] (True Sound) - KOKIA
→ ご参考(「ニッポンの霊場」様)
八十八ヶ所はかなりの時間と根気を要し、結願までの道のりはなかなか困難です。
そこで生まれたのが簡易(ミニ)版である二十一ヶ所という説がみられます。
簡易(ミニ)版であれば八十八ヶ所の札所からダイジェスト的に選定すればいい筈ですが、そうはなっていないケースもみられます。
「弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場」(以下、御府内二十一ヶ所霊場)もそのひとつです。
「御府内二十一ヶ所霊場」は、『東都歳事記』(国書データベース)に霊場名「弘法大師二十一ヶ所参」と、第21番が湯島霊雲寺であることが記載されていますが、札所一覧は記載されていません。
(これは後述する「弘法大師二十一ヶ寺」を示すものかもしれません。)
しかし、「ニッポンの霊場」様に札所リストが掲載されているので、こちらにもとづき巡拝しました。
『東都歳事記』の編纂は天保九年(1838年)ですから、それ以前の開創とみられます。
「ニッポンの霊場」様によると、この霊場は元禄(1688年)から宝暦(1751年)の間に開創とされる古い霊場で、宝暦五年(1755年)頃の開創とされる御府内霊場より古い可能性があります。
第21番がふたつあるようで、札所数は22となります。
台東区内の札所が多く、御府内八十八ヶ所霊場よりも東(下町)寄りの霊場となっています。
当初は第20番の寛永寺 一乗院のみ天台宗で残りはすべて(広義の)新義真言宗でしたが、明治に一乗院が廃寺となったのちは根岸の時雨岡不動堂(西蔵院の境外仏堂)に承継されたといい、現在はすべて(広義の)新義真言宗寺院となっています。
【弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場】
■ 弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場-1
1番 法輪山 法幢院 浄光寺
真言宗豊山派 荒川区西日暮里3-4-3 /豊・荒
2番 補陀落山 観音院 養福寺
真言宗豊山派 荒川区西日暮里3-3-8 /豊・荒
■ 弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場-2
3番 蓮葉山 妙智院 観音寺
真言宗豊山派 台東区谷中5-8-28 /御・江
4番 長谷山 元興寺 加納院
新義真言宗 台東区谷中5-8-5 /御・江
5番 天瑞山 観福寺 明王院
真言宗豊山派 台東区谷中5-4-2 /御・江
6番 初音山 東漸寺 観智院
真言宗豊山派 台東区谷中5-2-4 /御・江
■ 弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場-3
7番 仏到山 無量寿院 西光寺
新義真言宗 台東区谷中6-2-20 /江
8番 瑠璃光山 薬王寺 長久院
真言宗豊山派 台東区谷中6-2-16 /御・江
9番 宝塔山 龍門寺 多寶院
真言宗豊山派 台東区谷中6-2-35 /御・江
10番 本覚山 宝光寺 自性院
新義真言宗 台東区谷中6-2-8 /御・江
■ 弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場-4
11番 圓明山 宝福寺 西蔵院
真言宗智山派 台東区根岸3-12-38 /荒
12番 鐡砂山 観音院 世尊寺
真言宗豊山派 台東区根岸3-13-22 /荒
13番 東光山 等印院 龍泉寺
真言宗智山派 台東区竜泉2-17-15 /荒
14番 恵日山 延命寺 地蔵院
真言宗智山派 台東区元浅草1-15-8 /荒
■ 弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場-5
15番 瑞光山 如意寺 密厳院
真言宗豊山派 荒川区荒川4-16-3 /豊
16番 五剣山 普門寺 大乗院
真言宗智山派 台東区元浅草4-5-16 /荒
17番 和光山 興源院 大龍寺
真言宗霊雲寺派 北区田端4-18-4 /御・豊
18番 象頭山 観音寺 本智院
真言宗智山派 北区滝野川1-58-2 /荒
19番 阿遮羅山 蓮華寺 阿遮院
真言宗豊山派 荒川区東尾久3-6-25 /豊
■ 弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場-6
20番 東叡山 寛永寺 一乗院(廃寺)
天台宗 台東区上野公園
→(20番) 時雨岡(御行の松)不動堂
真言宗智山派 台東区根岸4-9-5
21番-1 宝林山 大悲心院 霊雲寺
真言宗霊雲寺派 文京区湯島2-21-6 /御・江
21番-2* 大黒山 宝生院
真言宗智山派 葛飾区柴又5-9-8 /南
※ 21番-2* 宝生院は池之端茅町から移転
〔八十八ヶ所霊場の略記凡例〕
御:御府内八十八ヶ所霊場
江:江戸八十八ヶ所霊場
豊:豊島八十八ヶ所霊場
荒:荒川辺八十八ヶ所霊場
南:南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)
↑をみると、22ヶ所のうち御府内八十八ヶ所霊場との重複札所はわずか9ですが、ほぼすべての札所が複数の八十八ヶ所弘法大師霊場と重複しています。
しかも第12番世尊寺は、荒川辺八十八ヶ所霊場の第1番を担われています。
ここからしても、御府内二十一ヶ所霊場は、単なる御府内八十八ヶ所霊場の簡易(ミニ)版とはいえないと思います。
上記のとおり、「ニッポンの霊場」様によると、この霊場は元禄(1688年)から宝暦(1751年)の間に開創とされ、宝暦五年(1755年)頃の開創とされる「御府内八十八ヶ所霊場」より古い可能性があります。
同じく「ニッポンの霊場」様によると、「荒川辺八十八ヶ所霊場」は天保九年(1838年)年頃かそれ以前、「豊島八十八ヶ所霊場」は明治41年(1908年)の開創ですから、やはりこの霊場の方が古いとみられます。
「江戸八十八ヶ所霊場」を「御府内八十八ヶ所霊場」の前身と仮定すると、むしろ「江戸八十八ヶ所霊場」をベースのひとつとして成立したのかもしれません。
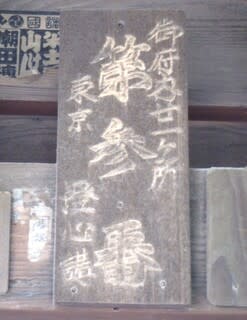
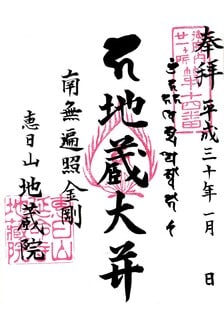
【写真 上(左)】 第3番観音寺の札所板
【写真 下(右)】 第14番地蔵院の御朱印
---------------------------------
「御府内二十一ヶ所霊場」とは別に「弘法大師二十一ヶ寺」という霊場もあります。
【弘法大師二十一ヶ寺】 (八十八ヶ所霊場の略記凡例は同上)
1番 萬昌山 金剛幢院 圓満寺
真言宗御室派 文京区湯島1-6-2 /御・江
○2番 宝塔山 多寶院
真言宗豊山派 台東区谷中6-2-35 /御・江
○3番 五剣山 普門寺 大乗院
真言宗智山派 台東区元浅草4-5-16 /荒
4番 清光院 台東区下谷(廃寺)
○5番 恵日山 延命寺 地蔵院
真言宗智山派 台東区元浅草1-15-8 /荒
6番 阿遮山 円満寺 不動院
真言宗智山派 台東区寿2-5-2 /御・江
7番 峯松山 遮那院 仙蔵寺
真言宗智山派 台東区寿2-8-15 /荒
8番 高野山 金剛閣 大徳院
高野山真言宗 墨田区両国2-7-13 /御・江
9番 青林山 最勝寺 龍福院
真言宗智山派 台東区元浅草3-17-2 /御・江
○10番 本覚山 宝光寺 自性院
新義真言宗 台東区谷中6-2-8 /御・江
11番 摩尼山 隆全寺 吉祥院
真言宗智山派 台東区元浅草2-1-14 /御・江
12番 神勝山 成就院
真言宗智山派 台東区元浅草4-8-12 /御・江
13番 広幡山 観蔵院
真言宗智山派 台東区元浅草3-18-5 /御・荒
14番 望月山 般若寺 正福院
真言宗智山派 台東区元浅草4-7-21 /御・江
○15番 仏到山 無量寿院 西光寺
新義真言宗 台東区谷中6-2-20 /江
16番 鶴亭山 隆全寺 威光院
真言宗智山派 台東区寿2-6-8 /御・江
17番 十善山 蓮花寺 密蔵院
真言宗御室派 中野区沼袋2-33-4(移転) /御・江
○18番 象頭山 観音寺 本智院
真言宗智山派 北区滝野川1-58-2 /荒
○19番 瑠璃光山 薬王寺 長久院
真言宗豊山派 台東区谷中6-2-16 /御・江
20番 玉龍山 弘憲寺 延命院
真言宗智山派 台東区元浅草4-5-2 /御・荒
○21番 宝林山 大悲心院 霊雲寺
真言宗霊雲寺派 文京区湯島2-21-6 /御・江
札所の出所は↓『御府内八十八ヶ所 弘法大師二十一ヶ寺 版木』(台東区教育委員会刊)です。
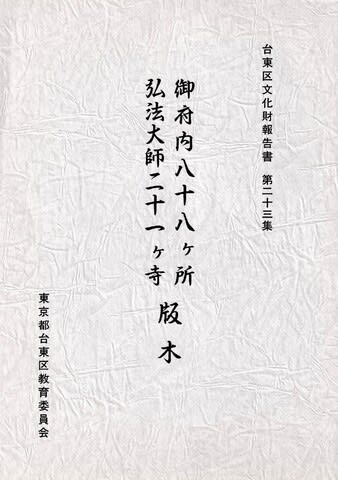
「弘法大師二十一ヶ寺御詠歌所附版木」が伝える弘法大師霊場で、この附版木は寛政二年(1790年)の開版ですからこちらもかなり古い来歴をもちます。
「御府内二十一ヶ所霊場」と「弘法大師二十一ヶ寺」の重複札所は○を付した8ヶ所ですが、両者の関係についてはよくわかりません。
「弘法大師二十一ヶ寺」は「御府内二十一ヶ所霊場」よりも御府内八十八ヶ所霊場との重複が多く、こちらの方が「御府内八十八ヶ所霊場の簡易(ミニ)版」の性格が強いのでは。
筆者は「弘法大師二十一ヶ寺」も結願していますが、こちらは21札所のうち廃寺となった第4番清光院を除いてすべて御朱印を拝受しています。
---------------------------------
■ 「御府内二十一ヶ所霊場」と「弘法大師二十一ヶ寺」の関係について
『御府内八十八ヶ所 弘法大師二十一ヶ寺 版木』(台東区教育委員会刊、以下「同書」)には下記の記載があります。
**********(引用)
当巡礼(弘法大師二十一ヶ寺)の開設は、御府内札所(御府内八十八ヶ所霊場)設定の宝暦年間(1751-1764年)より本版木開版の寛政二年(1790年)までの三〇数年の間のことと考えたい。
さらに『東都八十八ヶ所』は明治時代の二十一ヶ所を紹介している(巻末一覧表/註:同書『弘法大師御府内二十一所』項には「明治期の案内によったものである」というが、出典は明記されていない)。
これによれば、寛政二年と比べ十五ヶ寺の異動があり、他の六ヶ寺中の五ヶ寺は札所番号が変わっている。明治時代の札所中、第一一番西蔵院には(中略)江戸末期までに大きな改変があったと推定できる。
ところが、(御府内八十八ヶ所霊場)のように札所の改変は寺院の統・廃合に応じた場合が多いが、寛政二年当時の札所は明治一〇年までは確実に顕在していた。
このことから改変の理由は他にあったと思われ、あるいは、当巡礼(弘法大師二十一ヶ寺)は一時衰え、江戸末期に改めて編成されたとも考えられる。
**********(引用おわり)
上記の「明治時代の二十一ヶ所」は、「御府内二十一ヶ所霊場」と同一です。
「ニッポンの霊場」様によると「御府内二十一ヶ所霊場」の開創は元禄(1688年)から宝暦(1751年)。
これに対して同書による「弘法大師二十一ヶ寺」の開設は宝暦年間(1751-1764年)より寛政二年(1790年)の間で、「御府内二十一ヶ所霊場」の方が古い可能性があります。
さらに、同書でも「札所の改変は寺院の統・廃合に応じた場合が多い」と述べているとおり、神仏分離前の江戸期に全面改編に等しい札所改編があったとはどうしても考えられません。
「弘法大師二十一ヶ寺」の札所の多くが江戸時代に廃されたならばともかく、ほとんどの札所は現存しています。
となると、「弘法大師二十一ヶ寺」が改編されて「御府内二十一ヶ所霊場」(同書では「明治時代の二十一ヶ所」)になったのではなく、もともと江戸期から別個の霊場だったのでは?
なにぶん、弘法大師二十一ヶ寺の版木は発見されたばかり(おそらく平成に入ってからの発見と思われる)で、今後研究が進めば新たな関係がみえてくるのかもしれません。
---------------------------------
その他、近隣の墨田・葛飾両区をメインとする「弘法大師 隅田川二十一ヶ所霊場」という霊場もあり、下町エリアの二十一ヶ所の札所は錯綜気味です。
なお、「弘法大師 隅田川二十一ヶ所霊場」は「荒川辺八十八ヶ所霊場」あるいは「荒綾八十八ヶ所霊場」の簡易(ミニ)版とみる説もありますが詳細は不明です。
---------------------------------
「御府内二十一ヶ所霊場」の御朱印については、「御府内八十八ヶ所霊場」との重複札所では後者の御朱印の授与となるようです。
「豊島八十八ヶ所霊場」との重複札所でも同様の模様です。
この条件のもとですが、筆者は22ヶ所のうち20ヶ所で御朱印を拝受しています。
「御府内二十一ヶ所霊場」のみの札所の場合は御府内二十一ヶ所霊場での申告としましたが、この霊場を回る人は極めて希らしく、霊場名が通じない場合もありました。
むしろ、「お大師さまのお参り」あるいは「二十一大師のお参り」と申告した方が通りがいいかもしれません。
「御府内八十八ヶ所霊場」との重複札所以外では御朱印授与を想定されていない感じがあり、ご不在のケースもかなりあります。
御朱印目当てというより、荒綾霊場や荒川辺霊場と同様、往年の弘法大師霊場を辿るというスタンスが必要かもしれません。
御府内八十八ヶ所霊場は結願し、ご案内の記事もUP(→ こちら)していますが、御府内二十一ヶ所霊場は先日ようやく結願しましたので、御府内八十八ヶ所霊場の記事と同様のフォーマットでご紹介していきたいと思います。
それでは第1番から順にご紹介していきます。
なお、御朱印の授与については現在休廃止している可能性があります。
■ 第1番 法輪山 法幢院 浄光寺
(じょうこうじ)
荒川区西日暮里3-4-3
真言宗豊山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来?
司元別当:諏方神社(荒川区西日暮里)
他札所:豊島八十八ヶ所霊場第5番、荒川辺八十八ヶ所霊場第8番、東都六地蔵霊場第3番、豊島六地蔵霊場第3番
第1番札所は日暮里の浄光寺です。
谷中から日暮里につづく「諏訪台」にある真言宗豊山派の寺院です。
『新編武蔵風土記稿』、『江戸名所図会』、現地掲示などから縁起・沿革を追ってみます。
創建年代は当山が諏方神社の別当であったため、諏方神社の創建(現地掲示によると元久二年(1205年))と同時期とみられています。
なお、諏方神社は豊嶋左衛門尉経泰の創建と伝わりますが、太田道灌(1432-1486年)とする説もあり、別当の浄光寺についても豊島左衛門尉経泰説と太田道灌説があるようです。
創建時から法輪山法幢院を号したとみられ、御本尊は薬師如来と伝わります。
諏方神社は三代将軍徳川家光公(1604-1651年)に社領五石を安堵され、日暮里・谷中の総鎮守として広く信仰を集めたといい、その別当である当山も重要な役割を果たしていたとみられます。
元禄四年(1691年)には空無上人の勧化により「江戸六地蔵」(近郷六地蔵)のひとつが安置されています。
この「江戸六地蔵」は、現在まで伝わる「後の六地蔵」ではなく、下谷池之端影向山心行寺三世の(慈済庵)本誉空無(浄土木食)が元禄四年(1691年)に建立開眼した「はじめの六地蔵」です。
『江戸砂子温故名蹟誌 6巻3』(国立国会図書館DC)の醫王山 真性寺の項には以下の記載があります。
***************
地蔵坊正元法師建立唐銅六地蔵の三番也所謂六軀ハ
一番 品川 真言 品川寺
二番 四谷 浄土 大宗寺
三番 巣鴨 同(真言) 真性寺
四番 山谷 禅 東禅寺
五番 深川 浄土 霊巌寺
六番 深川 真言 永代寺
右六地蔵の●●元坊ハ俗名吉之郎とて八百屋の女お七●●もの●出家と云もの●●出家 ●六軀を造立●といひつ
されは宝永年中沙門正元坊か建立せし金銅丈六の六軀ハ世に後の六地藏といふと也
慈済庵空無上人勧化の助力を以 金銅立像八尺の地藏六軀を造立し江戶六ヶ所に安置す 元禄四年開眼供養を執行す これをはしめの六地藏といふ所謂六所ハ
一番 駒込 浄土 瑞泰寺
二番 千駄木 浄土 專念寺
三番 日暮里 諏訪 浄光寺
四番 池端 心行寺
五番 東叡山 大仏側 慈濟庵
六番 淺艸寺内 正智院
***************
下欄の「はし(じ)めの六地藏」の三番に浄光寺の記載があります。
「はじめの六地蔵」は毎月二十四日ないし十八日の縁日に多くの信者を集めたと伝わりますがいつしか衰退し、いくつかは廃寺となったこともあり、現在江戸六地蔵として知られているのは正元坊建立の「後の六地蔵」です。
「はじめの六地蔵」で現存するのは浄光寺と専念寺だけとみられています。
なお、「江戸六地蔵」については→ (こちらの記事)をご覧ください。
元文二年(1737年)有徳院殿(八代将軍徳川吉宗公)が御遊猟の折りに当山に立ち寄られて以降、将軍鷹狩りの際の御膳所に定められたという格式をもちます。
山内には、三代将軍徳川家光公が腰掛けたという「三代将軍御腰掛石」があります。
高台にあって眺望に優れた「諏訪台」は江戸時代、人気の景勝地で、諏訪台八景(筑波茂陰、黒髪晴雪、前畦落雁、後岳夜鹿、隅田秋月、利根遠帆、暮荘烟雨、神祠老松)が定められて詩歌にうたわれました。
とくに浄光寺の雪景色は有名で「雪見寺」と称されました。
近くの本行寺は「月見寺」、青雲寺は「花見寺」と呼ばれ、江戸の文人墨客を集めたことが記録に残っています。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編武蔵風土記稿 豊島郡巻十』(国立国会図書館)
(新堀村)諏訪社
村内及谷中ノ惣鎮守トス 一寸許ナル薄黒キ圓石ヲ神躰トス 社領五石ノ御朱印ハ慶安二年(1649年)附ラル 元享年中(1321-1324年)豊嶋左衛門尉経泰信州ノ諏訪ヲ勧請セル由縁起ニ載タリ 例祭七月廿六日社邊東ノ方ヲ諏訪臺ト号シ眺望勝景ノ地ナリ 林信充カ浄光寺八景詩歌ハ則此処ニテノ作ナリ 所謂八景ハ筑波茂陰 黒髪晴雪 前畦落雁 後岳夜鹿 隅田秋月 利根遠帆 暮荘烟雨 神祠老松ナリ 皆望中ノ景色ナリ 末社 山王 稲荷
別当浄光寺
新義真言宗田端村与楽寺末 法輪山法幢院ト号ス 本尊薬師 元文二年四月十四日 有徳院殿御遊猟ノ時始テ当寺ヘ成セ給ヒ 同五年正月廿五日御膳所ニ命セラレシヨリ 今モ此邊放鷹ノ節ハ御膳所トナレリ
御腰掛石 庭前ニアリ 有徳院殿始テ渡御アリシ時憩セ給フ石ナリト云傳フ
人麿社 頓阿作ノ像ヲ安ス 享保年中起立ス
地蔵 銅像ニテ近郷六地蔵ノ一ナリ
■ 『江戸名所図会 巻之五』(国立国会図書館)
同所(日暮里)北の方、諏訪の台にあり。信州諏訪の祭神におなじ。当社は元享の頃、豊島左衛門佐建立す。其後太田道灌、此地を江戸城の出張の砦とせしみぎり、修営して、郭内の鎮守となせしとぞ。社頭今も杉の木立生茂りて上久(かみさび)たり。当社別当は真言宗にして、法輪山浄光寺と号す。当寺の書院は、高崖に架して、眼下に千歩の田園を見下せり。風色尤も幽雅にして、四時の眺望たらずと云ふ事なし。中に雪のながめ勝れたれば、世に称して雪見寺とも名くとかや。
人麻呂の祠
当院庭中に安ず。頓阿法師の作にして、杉の白木をもって作り。是則ち播州住吉社へ奉納ありし三百体の其一なりといへり。
地蔵堂
同じく門のかたはらにあり。本尊は紫銅(カラカネ)にて、立像八尺の地蔵尊なり。慈済庵空無上人建立ありて、元禄四年に開眼供養す。六地蔵の一なり。
■ 『荒川区史』(国立国会図書館)
法輪山浄光寺は法幢院とも号し新義真言宗豊山派に属し田端町與楽寺末、本尊は薬師如来である。
当寺の創立は不明であるが、古老の説に太田道灌の建立と云ふ。一説には元享年間(1321-1324年)豊島左衛門尉経泰の創建せし所とも云ふ。
寺は諏訪台の高処を占め、舊幕時代は諏方神社の別当職で、此の境内は展望開豁であって雪見に適していたので俗に之を雪見寺と称した。
元文二年(1737年)将軍吉宗(一説には三大将軍家光とも云ふ)が遊猟に際し当寺に休憩し、又同五年正月膳所に命ぜられしよりその事幕府の末に及んだ。(中略)
江戸六地蔵の内二體が当寺入口左側にある。
古記に、「地蔵堂 本尊は紫銅にて立像八尺の地蔵尊なり。慈済庵空無上人建立ありて元禄四年(1691年)に開眼供養す、六地蔵の一なり。」とある。
尚、地蔵の外不動、観音、厄除大師等も安置されている。古くは人麻呂祠があった。
【現地案内掲示/荒川区教育委員会】
■ 江戸六地蔵と雪見寺(浄光寺)
山門をくぐって左手に、高さ一丈(約三メートル)の銅造地蔵菩薩がある。元禄四年(1691年)、空無上人の勧化により江戸東部六か所に六地蔵として開眼された。もと門のかたわらの地蔵堂に安置されていたもので門前は「地蔵前」ともよばれる。
浄光寺は、真言宗豊山派の寺院。法輪山法幢院と称し、江戸時代までは諏方神社の別当寺であった。元文二年(1737年)、八代将軍吉宗が鷹狩の際にお成りになり、同五年以降御膳所となった。境内に「将軍腰かけの石」がある。
眺望にすぐれた諏訪台上にあり、特に雪景色がすばらしいというので「雪見寺」ともよばれた。
【現地案内掲示/荒川区教育委員会】
■ 諏訪神社
信濃国上諏訪社と同じ建御名方命を祀る。
当社の縁起によると、元久二年(1205年)豊嶋左衛門尉経泰の造営と伝える。
江戸時代、三代将軍徳川家光に社領五石を安堵され、日暮里・谷中の総鎮守として広く信仰を集めた。
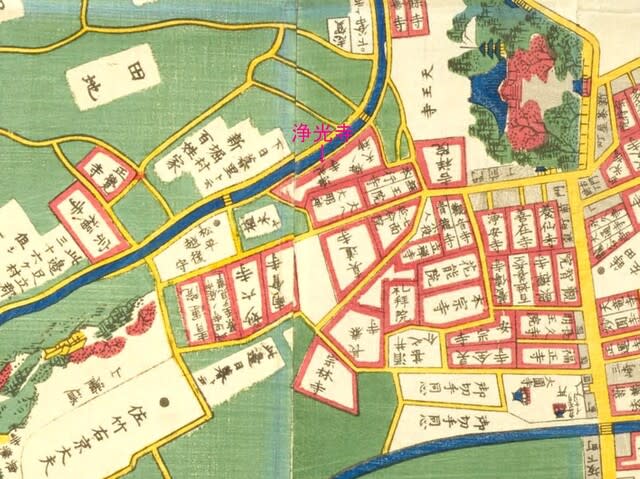
出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』 根岸谷中辺絵図,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはJR・メトロ千代田線「西日暮里」駅で徒歩数分。
「西日暮里」駅は武蔵野台地の崖の下にあり、駅出口からすぐの歩道橋を兼ねた急な階段を上ると西日暮里公園です。

西日暮里公園
この公園の案内板には下記のとおりあります。
---------------------------------
道灌山は、上野から飛鳥山へと続く台地上に位置します。(中略)この公園を含む台地上にひろがる寺町あたりは、ひぐらしの里と呼ばれていました。
道灌山の地名の由来として、中世、新堀(日暮里)の土豪、関道閑が屋敷を構えたとか、江戸城を築いた太田道灌が出城を造ったなどの伝承があります。
江戸時代、人々が日の暮れるのも忘れて四季おりおりの景色を楽しんだことから、「新堀」に「日暮里」の文字をあてたといわれています。(中略)
道灌山・ひぐらしの里は、江戸時代の中頃になると、人々の憩いの場として親しまれるようになりました。寺社が競って庭園を造り、さながら台地全体が一大庭園のようでした。
桃さくら 鯛より酒のさかなには みところ多き 日くらしの里
十返舎一九
雪見寺(浄光寺)、月見寺(本行寺)、花見寺(妙隆寺、修性院、青雲寺)、諏訪台の花見、道灌山の虫聴きなど、長谷川雪旦や安藤広重ら著名な絵師の画題となり、今日にその作品が知られています。
---------------------------------
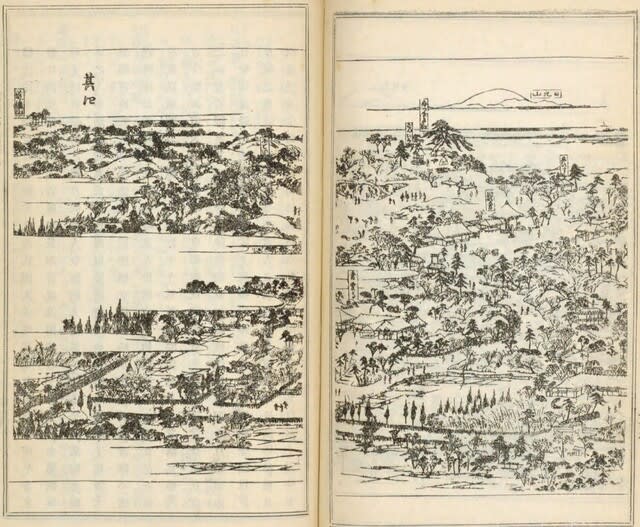
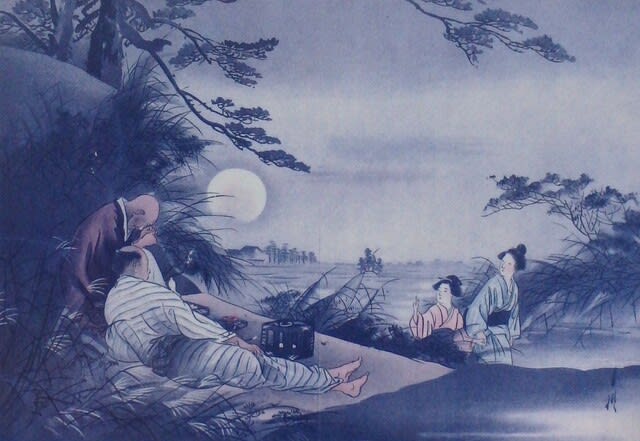
【写真 上(左)】 ■ 『江戸名所図会 第3 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)
【写真 下(右)】 道灌山の虫聴き(現地掲示より)
西日暮里公園あたりは「虫聴き」の名所として知られていたようです。
公園を抜けて左手の社叢は諏方神社。
日暮里・谷中の総鎮守として人々の崇敬を集め、浄光寺はその別当でした。
諏方神社では、日暮里・谷中エリアでは貴重な神社の御朱印を授与されています。

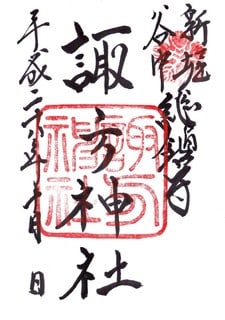
【写真 上(左)】 諏方神社
【写真 下(右)】 諏方神社の御朱印
浄光寺は、諏方神社の鳥居のよこに山門を構えています。
いかにも別当然とした位置関係です。


【写真 上(左)】 諏方神社鳥居と浄光寺山門
【写真 下(右)】 浄光寺山門


【写真 上(左)】 山門の扁額
【写真 下(右)】 六地蔵三番目の石標
山門脇には「六地蔵三番目」の石標が置かれています。
山門は切妻屋根桟瓦葺の高麗門で、見上げに山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 二体の地蔵尊
【写真 下(右)】 西村和泉守作の地蔵尊
山門をくぐって左手には座像と立像の二体の銅造地蔵尊が御座し、いずれも区の指定文化財。
手前の銅造地蔵菩薩座像は江戸の鋳物師として有名な西村和泉守の作で、文化六年(1809年)の造立。
奥の銅造地蔵菩薩立像は元禄四年(1691年)造立の江戸六地蔵三番目の尊像で、下谷心行寺二世空無上人の権化により元禄四年(1691年)に開眼されています。
もとは山門脇に奉じられていましたが、昭和初期に山内に遷されたとのことです。
江戸六地蔵はもとより、西村和泉守作の地蔵尊の台座にも多数の願主の名が刻まれていることから、浄光寺は江戸時代地蔵信仰の寺として知られていたとみられます。


【写真 上(左)】 江戸六地蔵の地蔵尊
【写真 下(右)】 土蔵造りの堂宇
地蔵尊のさらに奥に土蔵造りの堂宇がありますが、扁額がなく堂宇本尊は不明です。


【写真 上(左)】 本堂-1
【写真 下(右)】 本堂-2


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝の扁額
山内左手奥の階段上に本堂。
入母屋造桟瓦葺で手前に向拝を附設しています。
身舎はコンクリ造で、水引虹梁は装飾少なく直線的ですが中備に蟇股を置いています。
向拝見上げには寺号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 山門と六地蔵
【写真 下(右)】 石佛群
山門右手の壁際には石佛群と六地蔵。
山内のどこかにおそらく「将軍の腰掛石」があると思いますが、超うかつにも撮りわすれました。
御朱印は庫裏にて拝受しました。
先日(2024年4月)の参拝時には庫裏の扉に「御朱印対応自粛中です。」の張り紙があり、御朱印授与を休止している模様ですが、Web情報には「セルフ捺しの御朱印あり」の情報もあって、よくわかりません。
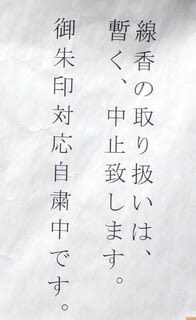
もし、御朱印授与休止中だとしたら、現時点では豊島八十八ヶ所霊場の御朱印はコンプリートできないことになります。
〔 浄光寺の御朱印 〕
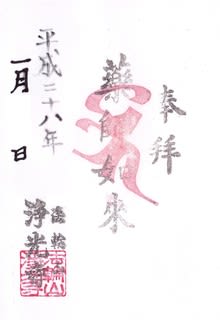
中央に「薬師如来」の印判と薬師如来のお種子「バイ」の御寶印。
左に山号・寺号の印判と寺院印が捺されています。
■ 第2番 補陀落山 観音院 養福寺
(ようふくじ)
荒川区西日暮里3-3-8
真言宗豊山派
御本尊:如意輪観世音菩薩
札所本尊:如意輪観世音菩薩?
司元別当:
他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第7番、東京三十三観音霊場第28番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第27番、東都七観音霊場第5番、近世江戸三十三観音霊場第10番、東方三十三観音霊場第12番、江戸坂東三十三ヶ所観音霊場第9番、豊島六地蔵霊場第6番
第2番札所は日暮里の養福寺です。
こちらも「諏訪台」にある真言宗豊山派の寺院です。
『新編武蔵風土記稿』、 『江戸名所図会』、荒川区資料、現地掲示などから縁起・沿革を追ってみます。
Wikipediaには元和六年(1620年)、法印乗蓮によって開山とあります。
『江戸名所図会』には開山は木食義高上人とありますが、荒川区資料その他には湯島圓満寺の木食義高上人(享保三年(1718年)没)は中興とあります。
『江戸名所図会』によると、義高上人は初め高野山高臺院の住職でしたが当地に赴き、百番の観音札所を遷す事を企られたといいます。
当地にあった小庵を開いて寺とし、野山より遷し奉る霊像を礼拝しつつ修補して、ついに百體の尊像を安されたといいます。
『新編武蔵風土記稿』によれば新義真言宗田端村東覺寺門徒(末)、補院山観王院と号し、御本尊は阿弥陀如来。
仁王門、鐘楼を擁し、天神社、諏訪社が御鎮座とあります。
観音堂には春日作の如意輪観世音菩薩、弘法大師御作の十一面観世音菩薩、慈覚大師御作の正観世音菩薩を安置ともあります。
寺宝として台徳院殿(二代将軍徳川秀忠公)御筆の色紙ありと記されています。
仁王門は宝永年間(1704-1711年)に建立とされ、門中の仁王像は運慶作とも伝わります。
養福寺には、「日暮里(ひぐらしのさと)」を訪れた江戸時代の文人たちの遺蹟が残ります。
「梅翁花樽碑」「雪の碑」「月の碑」などからなる「談林派歴代の句碑(区指定文化財)」や、江戸時代の四大詩人の一人、柏木如亭を偲んで建てられた「柏木如亭の碑」、自堕落先生こと山崎北華が自ら建立の「自堕落先生の墓」など、文学の香り高い寺院として知られています。
当山は、筆者にて確認できた範囲でじつに9もの霊場札所となっています。
『新編武蔵風土記稿』には「観音堂には春日作の如意輪観世音菩薩、弘法大師御作の十一面観世音菩薩、慈覚大師御作の正観世音菩薩を安置」とあり、おのおのの観音様が札所本尊となられていた可能性があります。
『江戸名所図会』の記事からすると、上野王子駒込辺三十三観音霊場は西國写しなので春日作の如意輪観音、江戸坂東三十三ヶ所観音霊場は板東写しなので弘法大師御作の十一面観音、近世江戸三十三観音霊場ないし東方三十三観音霊場を秩父写しと見立てると慈覚大師御作の正観音がそれぞれ札所本尊であった可能性があります。
『江戸切絵図』では当山とおぼしき場所に「梅ノ天神」の記載があります。
『新編武蔵風土記稿』には山内に「天神社」とあるので、こちらの天神社は梅の名所だったのかもしれません。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編武蔵風土記稿 豊島郡巻十』(国立国会図書館)
(新堀村)養福寺
新義真言宗田端村東覺寺門徒 補院山観王院ト号ス 中興ハ湯嶋圓満寺住職木食義高ナリ 本尊彌陀 寺寶ニ台徳院殿御筆ノ色紙アリ 伝来詳ナラス左ノ如シ
~ いか●にむかし むすへる契にて こ乃世にかゝる 中乃隔り ~
天神社 諏訪社
観音堂 春日作ノ如意輪観音 弘法大師作ノ十一面観音 慈覚大師作ノ正観音ヲ安置ス
鐘楼 仁王門
■ 『江戸名所図会 巻之五』(国立国会図書館)
観王院と号す。同所(日暮里)北の方にあり。本尊は三尊の彌陀佛、開山は木食義高上人なり。
観音堂
西國板東秩父百番の札所をうつせり。
本尊如意輪観音 佛工春日の作にして、西國札所第一番紀州那智山のうつしなり。
十一面観音 弘法大師の作にして、板東札所第一番鎌倉杉本のうつしなり。
正観音 慈覚大師の作にして、秩父札所第一番四萬部寺のうつしなり。
抑此百観音は、義高上人の建立なり。上人初め高野山の高臺院に住職たりしが、後彼寺を退去し、当地に赴き、百番の札所をうつさん事を企つ。是本土に至りがたき兒女等の結縁の為となり。拠て此地に小庵のありけるを、闢きて寺とし(往古太田道灌勧請ありし下諏訪明神の社地なり)、数千歩の地を寄付せられしとぞ。
本尊おほくは野山より遷し奉る霊像なりといへども、百體に充たざるを嘆き、これを修補し、一軆毎に佛舎利一顆を御首に籠め、竟に百體の尊像全からしむとなん。
二王門の額に補陀山とあるは、油小路隆貞卿の眞蹟なり。
■ 『荒川区史』(国立国会図書館)
補陀落山養福寺は又観音院と称し新義真言宗豊山派に属し田端の與楽寺末である。
本尊は阿弥陀如来、開基並びに其の年代は不明であるが、中興開山は木食義高上人(湯島圓満寺)と云はれ享保三年(1718年)示寂。
今本堂の外に観音堂地蔵堂等がある。
観音堂は如意輪観音(帝都七観音の一)を本尊とし、其の他百軆観音像が安置されて居る。
西國第二十七番播磨國書寫山及び秩父第一番四萬部より移したものである。
又御府内二十一ヶ所第二番 豊島弘法大師 荒川辺八十八ヶ所第七十三の霊場である。
当寺の仁王門は寶永年間の建立で仁王尊二天王像が安置されて居る。二天王像は運慶の作と伝へる。
本堂の如意輪観音は春日作と伝へ、其の他弘法大師作の十一面観音、慈覚大師作の正観音と伝へられるものも安置されて居る。
境内の枝絲桜は古来有名。
【現地案内掲示/荒川区教育委員会】
■ 養福寺と文人たち
養福寺は真言宗豊山派の寺院で、補陀落山観音院と号し、湯島円満寺の木食義高(享保三年(1718年)没)によって中興されたという。江戸時代、多くの文人たちが江戸の名所である「日暮里(ひぐらしのさと)」を訪れ、その足跡を残した。なかでも養福寺は「梅翁花樽碑」「雪の碑」「月の碑」などからなる「談林派歴代の句碑(区指定文化財)」や、江戸時代の四大詩人の一人、柏木如亭を偲んで建てられた「柏木如亭の碑」、畸人で知られた自堕落先生こと山崎北華が自ら建てた「自堕落先生の墓」などさまざまな文人の碑が残る寺として知られている。
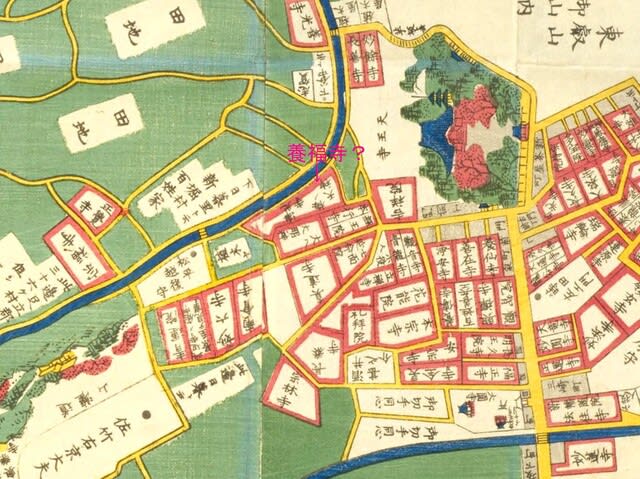
出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』 根岸谷中辺絵図,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはJR・メトロ千代田線「西日暮里」駅で徒歩約5分。
「西日暮里」駅方向から来ると「諏訪台通り」の浄光寺の並びにあります。


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 山内入口


【写真 上(左)】 門柱の寺号札
【写真 下(右)】 六地蔵
「諏訪台通り」からやや引きこんで、まずは門柱を構え、その先の朱塗りの仁王門が目を引きます。
切妻屋根桟瓦葺、三間一戸の八脚門で見上げに寺号扁額を掲げ、脇間に二王尊が御座します。


【写真 上(左)】 仁王門
【写真 下(右)】 鐘楼
山内は緑が多く、しっとりと落ち着いた空気感。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 修行大師像
本堂は入母屋造桟瓦葺で、前面すべてに向拝屋根が置かれているので、二重屋根風の意匠となっています。
身舎はコンクリ造ながら向拝正面に桟唐戸を置き、その両側に二つ引き紋を配して風格をたたえる堂前です。

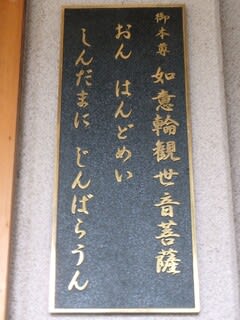
【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 御本尊の御真言
御本尊は如意輪観世音菩薩で、向拝柱には御真言が掲出されていました。
堂前には修行大師像が御座され、御府内弘法大師霊場の趣ゆたかです。
御朱印は庫裏にて拝受しました。
〔 養福寺の御朱印 〕※豊島霊場の御朱印
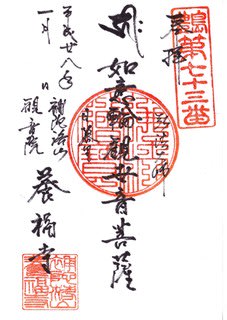
中央に「如意輪観世音菩薩」のお種子「キリーク」&尊格と「弘法大師」の揮毫と三寶印。
右上に「豊島第七十三番」の札所印。
左に山号・院号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内二十一ヶ所霊場の御朱印-2)
【 BGM 】
■ 夢の大地 - Kalafina
■ This Love - アンジェラ・アキ
■ 本当の音 [Hontou no Oto] (True Sound) - KOKIA
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 谷中の御朱印・御首題
※ この記事は2025年9月に「はてなブログ」に移行します。
はてなブログURLのブックマークをお願いします。
久しぶりに追加しました。
なお、これまで非掲載としていた寺院の御朱印もWeb上でみつかるようになったので、こちらも併せてUPします。
---------------------------
2021/02/23 UP
※ さらに御朱印や写真を追加しました。
---------------------------
2020/03/07 UP
※ エリアや寺社の写真を追加してみました。
谷中で拝受できる御朱印については、「東京都台東区の札所と御朱印」でご紹介していますが、今回は谷中の最新情報を交えて整理してみます。




谷中は日蓮宗・法華宗の御首題を抜きにして語ることはできません。
このところ、本妙院様や長運寺様がカラフルな絵御首題(絵御朱印)を出され拝受層が広がっていること、また、Web上でも授与情報が増えてきているので、今回日蓮宗・法華宗寺院(御首題)情報も加えて再UPします。
なお、拝受したところと、不授与の確認がとれたところは記載していますが、現時点で不明な日蓮宗・法華宗寺院については記載しておりません。
谷中はメディアのとりあげも多く、ガイド類もたくさん出ているので御朱印のメッカと思われがちですが(実際、授与される寺院はかなり多い)、じつは敷居の高い寺院もかなりあります。
もちろん、丁寧なご対応をいただけるお寺さんもたくさんあり、お寺ごとの対応の差が大きい印象があります。
神社がすくないことも拝受難易度を高めている一因です。
このあたりは、御朱印拝受が容易な上野公園エリアとは様相が異なり、御朱印初心者は上野公園エリアから入った方がベターかと思われます。
(なお、いわゆる「塩対応」はお寺さんのお考えやそういうお考えをもたれた背景をお伺いするまたとない機会(実際、委細にお話を伺えた場合、勉強になることが多い)なのですが、不慣れな局面でいきなりこれをくらうと正直キツイです(笑))
以前、御府内霊場を結願したときも「谷中のお寺は予想以上に手ごわい」という印象がありましたが、その傾向はますます強まっているような感じがします。
納経所前に「御朱印は、御府内霊場専用の御朱印帳にしか授与しない。」旨の明示をされている寺院もあります。
(たしかに、谷中界隈でとんでもない態度で御朱印を乞う観光客を見たことは一度や二度ではないですし、お寺さんのこのような対応はわからなくもないです。
ただし、(専用納経帳でなく)汎用御朱印帳で札番を振り、弘法大師霊場(八十八ヶ所)をコンプリートするのはまず不可能です。
となると、新規巡拝者の間口も狭まってしまう感じも(個人的には)します。発願寺の高野山東京別院をはじめ、すばらしい対応をしていただける札所も多いだけに、こういう流れはいささか残念な気もします。)
一方、マイナー系札所や非札所では、御朱印授与に積極的なお寺さんが増えている感じもします。
上記の本妙院様や長運寺様、数年前は非授与だった西光寺様が御朱印授与をはじめられたなどがその具体例です。
また、御朱印をお断りされたお寺さんでも「いまのところはお出ししていない。」という、含みのある表現をされたところが数箇寺ありました。
今回は、不授与の寺院(私自身が直接ご住職ないし大黒さんに確認したもの(2017~2019年)、日蓮宗寺院も含む)もご紹介します。
動線的に連続している荒川区西日暮里三丁目の御朱印も併せてご紹介します。




【エリア概要】
言問通りから北は、いよいよ都内屈指の寺町、谷中エリアに入る。
このエリアは上野駅から入るよりも、千代田線「根津」駅から入った方が便利がよい。
ちなみにこのあたりは、「谷根千」(谷中・根津・千駄木)と呼ばれ、下町情緒やグルメが楽しめるエリアとして近年人気急上昇中。
言問通り・善光寺坂北側の谷中一丁目は日蓮宗・御首題メインのエリア。坂を上りきった谷中六丁目は日蓮宗と他宗派の混在エリアとなり、御府内八十八箇所の札所も。
ここから北側の谷中五丁目から西日暮里三丁目(荒川区)にかけてが谷中のメインエリア。
東は谷中霊園で、JR「日暮里」駅からスタートする散策客も目立つ。
谷中五丁目の真言宗寺院は御府内八十八箇所の札所も多く、御朱印収集的に外せないエリア。これを抜きにしても寺町の趣ゆたかで散策する価値は十分にあると思う。

【拝受データ】 (おおむね谷中一丁目から。現時点で授与休廃止の可能性あり、形態(直書・書置など)は状況により変化する可能性大です。)
なお、末尾○欄は御朱印をいただいていない霊場で、古いものが多いです。
■楞伽山 天眼寺
台東区谷中1-2-14
臨済宗妙心寺派
〔御朱印不授与〕
■栄源山 本寿寺
台東区谷中1-4-9
日蓮宗
〔御首題不授与・・・Web上に拝受御首題ありますが不授与とのこと〕
■祝融山 瑞松院
台東区谷中1-4-10
臨済宗妙心寺派 御本尊:釈迦牟尼佛
〔御朱印不授与〕
■妙経山 成就院 信行寺
台東区谷中1-5-7
日蓮宗
〔御首題不授与・・・Web上に拝受御首題ありますが不授与とのこと〕
■長久山 妙泉寺
台東区谷中1-5-34
法華宗本門流


・御首題 書置(筆書)
■顕寿山 佛心寺
台東区谷中1-5-35
日蓮宗


【写真 上(左)】 佛心寺山門
【写真 下(右)】 佛心寺本堂

・御首題 直書(筆書)


・御朱印 書置(筆書)
・毘沙門天の御朱印 直書(筆書)
※ご対応はたいへん親切です。御首題は書置ご用意の可能性があります。
■大法山 一乗寺
台東区谷中1-6-1
日蓮宗


【写真 上(左)】 一乗寺山門
【写真 下(右)】 一乗寺本堂


【写真 上(左)】 ・御首題 直書(筆書)
【写真 下(右)】 ・御朱印 直書(筆書)
※御朱印・御首題についてのご対応は→こちら。時間限定ですが、快く授与いただけます。
カラー御朱印・御首題は郵送対応可。墨朱御朱印・御首題は参拝者のみに授与のようです。
■倍増山 宝城院 金嶺寺
台東区谷中1-6-27
天台宗 御本尊:阿弥陀如来


・朱印尊格:阿弥陀如来 札番:なし 直書(筆書)
○上野王子駒込辺三十三観音霊場第31番
■大乗山 長運寺
台東区谷中1-7-4
日蓮宗


【写真 上(左)】 長運寺山門
【写真 下(右)】 長運寺本堂
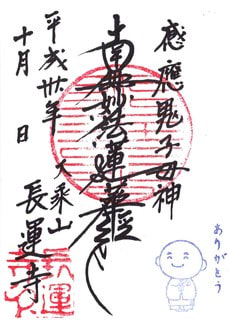

【写真 上(左)】 ・御首題 直書(筆書)
【写真 下(右)】 ・絵御首題 直書(筆書)
※絵御首題・絵御朱印で有名。授与時間は→こちら(インスタ)でUPされます。。
■望湖山 玉林寺
台東区谷中1-7-15
曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛


・朱印尊格:釋迦牟尼佛 札番:なし 直書(筆書)
○江戸浅草辺三十三観音霊場第25番
■六浦山 延壽寺 (日荷堂)
台東区谷中1-7-36
日蓮宗


【写真 上(左)】 延壽寺本堂
【写真 下(右)】 延壽寺日荷堂

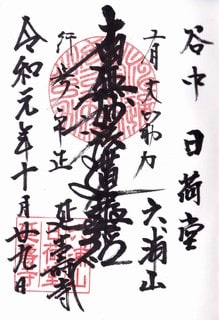
【写真 上(左)】 ・御首題 書置(筆書)
【写真 下(右)】 ・御首題 直書(筆書)
■正栄山 妙行寺
台東区谷中1-7-37
日蓮宗


・御首題 直書(筆書)
■石岡山 妙福寺
台東区谷中1-7-41
日蓮宗
〔御首題不授与・・・Web上に拝受御首題ありますが不授与とのこと〕
■龍興山 臨江寺
台東区谷中1-4-13
臨済宗大徳寺派 御本尊:釈迦牟尼佛


・朱印尊格:南無本師釋迦牟尼佛 札番:なし 直書(筆書)
○秩父写山の手三十四観音霊場第3番
■谷中冨士
台東区谷中1-6-14
参拝記念スタンプあり


■光雲山 元導寺 法蔵院
台東区谷中1-6-26
天台宗 御本尊:阿弥陀如来


・朱印尊格:阿弥陀如来 札番:なし 直書(筆書)
■高光山 大圓寺
台東区谷中3-1-2
日蓮宗


【写真 上(左)】 大圓寺山門
【写真 下(右)】 大圓寺境内


【写真 上(左)】 ・御首題 直書(筆書)
【写真 下(右)】 ・御朱印 直書(筆書)
■妙祐山 宗林寺 (江戸十大祖師/舟守祖師)
台東区谷中3-10-22
日蓮宗


・御首題 書置(筆書)
■円妙山 本授寺
台東区谷中3-11-6
顕本法華宗
〔御首題不授与〕
■慈雲山 久成院
台東区谷中4-1-5
日蓮宗


・御首題 直書(筆書)
■正行院
台東区谷中4-1-6
日蓮宗

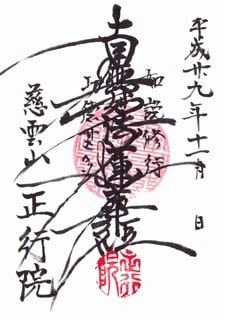
・御首題 直書(筆書)
■慈雲山 浄延院
台東区谷中4-1-8
日蓮宗


・御首題 直書(筆書)
■慈雲山 瑞輪寺 (江戸十大祖師/安産飯匙の祖師)
台東区谷中4-2-5
日蓮宗


【写真 上(左)】 瑞輪寺参道
【写真 下(右)】 瑞輪寺山門


【写真 上(左)】 瑞輪寺本堂
【写真 下(右)】 東京七面山
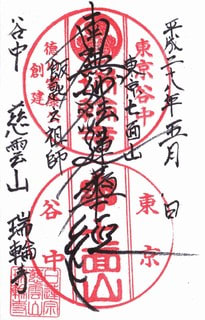
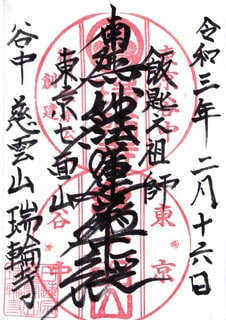
・御首題 直書(筆書)


・御朱印(妙法) 直書(筆書)
■本妙院
台東区谷中4-2-11
日蓮宗


【写真 上(左)】 本妙院山門
【写真 下(右)】 本妙院本堂

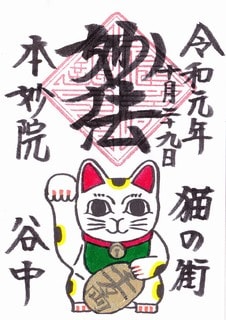
【写真 上(左)】 ・御首題 直書(筆書)
【写真 下(右)】 ・御朱印(妙法) 書置(筆書)
※絵御首題・絵御朱印で有名。
■法栄山 本通寺
台東区谷中4-2-33
法華宗陣門流


・御首題 直書(筆書)
■栄照山 龍谷寺
台東区谷中4-2-35
日蓮宗


・御首題 直書(筆書)
■寂静山 蓮華寺
台東区谷中4-3-1
日蓮宗


・御首題 書置(筆書)
■日長山 領玄寺
台東区谷中4-3-5
日蓮宗
〔御首題不授与〕
■円住山 妙円寺
台東区谷中4-4-29
日蓮宗
〔御首題不授与・・・「御朱印不授与」の貼紙あり、御首題も不授与とのこと〕
■海雲山 天龍院
台東区谷中4-4-33
臨済宗妙心寺派 御本尊:釈迦牟尼佛
〔御朱印不授与・・・Web上に拝受御朱印ありますが不授与とのこと〕
■興福山 永久寺
台東区谷中4-2-37
曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛


・朱印尊格:南無釈迦牟尼佛 札番:なし 直書(筆書)
○江戸浅草辺三十三観音霊場第31番、秩父写山の手三十四観音霊場第6番
■象頭山 頣神院
台東区谷中4-3-27
臨済宗妙心寺派 御本尊:不詳

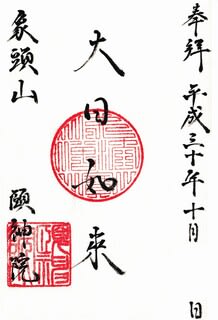
・朱印尊格:大日如来 札番:なし 直書(筆書)
■初音山 東漸寺 観智院
台東区谷中5-2-4
真言宗豊山派 御本尊:大日如来


・朱印尊格:本尊 阿弥陀如来・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所第63番印判 直書(筆書)
○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第6番、江戸八十八ヶ所霊場第64番
※「谷中の火除不動尊」の御朱印は不授与。幼稚園があるので開園時参拝のタイミング留意要。
■大道山 興禅寺
台東区谷中5-2-11
臨済宗興聖寺派
〔御朱印不授与〕
○弁財天百社参り第58番
■運立山 養傅寺
台東区谷中5-2-16
日蓮宗


・御首題 直書(筆書)
■大道山 長安寺
台東区谷中5-2-22
臨済宗妙心寺派 御本尊:千手観世音菩薩


・朱印尊格:大悲殿 上野王子駒込辺三十三観音霊場第22番印判 直書(筆書)
○谷中七福神(寿老人)、東方三十三観音霊場第14番
■感応山 常在寺
台東区谷中5-2-25
日蓮宗

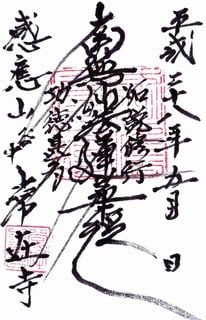
・御首題 直書(筆書)
■長清山 養泉寺
台東区谷中5-2-28
日蓮宗


・御首題 直書(筆書)
■常観山 安立寺
台東区谷中5-3-17
日蓮宗


・御首題 直書(筆書)
■天瑞山 観福寺 明王院
台東区谷中5-4-2
真言宗豊山派 御本尊:阿弥陀如来

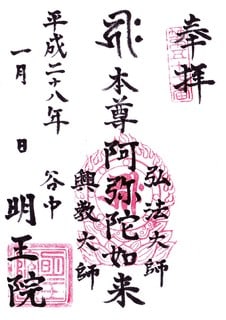
・朱印尊格:本尊 阿弥陀如来・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所57番印判 直書(筆書)
○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第5番、江戸八十八ヶ所霊場第57番
■普門山 全生庵
台東区谷中5-4-7
臨済宗国泰寺派 御本尊:葵正観世音菩薩

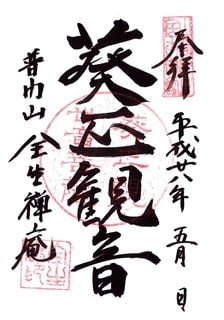
・朱印尊格:葵正観音 札番:なし 直書(筆書)
○大東京百観音霊場第25番
■松栄山 福相寺
台東区谷中5-4-9
日蓮宗


・御首題 書置(筆書)
■延寿山 長久寺
台東区谷中5-4-11
日蓮宗


・御首題 直書(筆書)
※多忙時不可。
■長興山 立善寺
台東区谷中5-4-19
日蓮宗


・御首題 (筆書)
■長谷山 元興寺 加納院
台東区谷中5-8-5
新義真言宗 御本尊:阿弥陀如来


・朱印尊格:本尊 阿弥陀如来・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所第64番印判 直書(筆書)
○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第4番、江戸八十八ヶ所霊場第63番
■妙見山 本立寺
台東区谷中5-8-7
日蓮宗


・御首題 直書(筆書)
※ご丁寧なご対応、頭が下がります。
■百丈山 霊梅院
台東区谷中5-8-19
臨済宗妙心寺派 御本尊:釈迦牟尼佛
〔御朱印不授与〕
■福聚山 海蔵院
台東区谷中5-8-25
臨済宗妙心寺派
〔御朱印不授与〕
■蓮葉山 妙智院 観音寺
台東区谷中5-8-28
真言宗豊山派 御本尊:大日如来


【写真 上(左)】 観音寺本堂
【写真 下(右)】 観音寺の築地塀

・朱印尊格:大日如来(御本尊) 札番:なし 書置(筆書)

・朱印尊格:大日如来・弘法大師 御府内八十八箇所42番印判 直書(筆書)

・お種子(ア)の御朱印

・スワロフスキー付御朱印
○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第3番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第32番、東方三十三観音霊場第13番、江戸八十八ヶ所霊場第42番
※参拝客以外は山内立入禁止の掲示あり。
■長光山 龍泉寺
台東区谷中5-9-26
日蓮宗
〔山内立入制限看板あり/御朱印不授与?〕
■日照山 長明寺
台東区谷中5-10-15
日蓮宗


・御首題 直書(筆書)
■円妙山 大行寺
台東区谷中6-1-13
日蓮宗


・御首題 直書(筆書)
■長昌山 大雄寺
台東区谷中6-1-26
日蓮宗


・御首題 直書(筆書)
■光照山 感應寺
台東区谷中6-2-4
日蓮宗


・御首題 直書(筆書)
■本覚山 宝光寺 自性院
台東区谷中6-2-8
新義真言宗 御本尊:大日如来


・朱印尊格:本尊 大日如来・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所第53番印判 直書(筆書)
○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第10番、江戸八十八ヶ所霊場第53番
■薬王寺 長久院
台東区谷中6-2-16
真言宗豊山派 御本尊:大日如来


・朱印尊格:本尊 大日如来・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所第55番印判 直書(筆書)
○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第8番、江戸八十八ヶ所霊場第55番
※閻魔大王(江戸・東京四十四閻魔第12番)の御朱印は不授与
■仏到山 無量寿院 西光寺
台東区谷中6-2-20
新義真言宗


【写真 上(左)】 西光寺山門
【写真 下(右)】 西光寺本堂
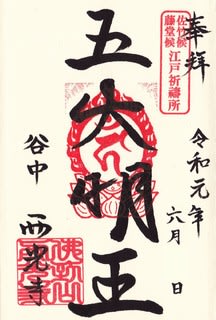
・朱印尊格:五大明王 主印判:種子 札番:なし 直書(筆書)

・朱印尊格:五大明王 主印判:不動明王御影印 札番:なし 直書(筆書)
こちらをメインに授与されているようです。
※以前は不授与でしたが御朱印授与を開始され対応も親切です。カラー御朱印マニアを中心に人気を集めている模様。
○上野王子駒込辺三十三観音霊場第7番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第7番、江戸八十八ヶ所霊場第70番
■金輪山 最勝寺 總持院
台東区谷中6-2-33
天台宗 御本尊:阿弥陀如来


・朱印尊格:谷中不動尊 札番:なし 直書(筆書)
※こちらのお寺様につきましては、Web上での拝受情報がほとんどみつからず、現在でも授与されているかは不明です。
なお、御本尊の御朱印は授与されておりません。
■宝塔山 龍門寺 多宝院
台東区谷中6-2-35
真言宗豊山派 御本尊:多宝如来


・朱印尊格:本尊 多宝如来・弘法大師 御府内八十八箇所第49番印判 直書(筆書)
○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第9番、江戸八十八ヶ所霊場第49番
※「谷中吉祥天」の御朱印は不授与
■清林山 和光院 大泉寺
台東区谷中6-2-13
天台宗 御本尊:阿弥陀如来


・朱印尊格:阿彌陀如来 札番:なし 直書(筆書)
■無量山 功徳林寺
台東区谷中7-6-9
浄土宗 御本尊:阿弥陀如来


【写真 上(左)】 功徳林寺本堂
【写真 下(右)】 笠森稲荷堂

・朱印尊格:無量壽 札番:なし 書置(筆書)
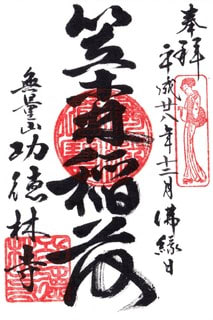
・朱印尊格:笠森稲荷 札番:なし 書置(筆書)
■安立院
台東区谷中7-10-4
曹洞宗系単立
〔御朱印不授与〕
■護国山 尊重院 天王寺
台東区谷中7-14-8
天台宗 御本尊:阿弥陀如来


【写真 上(左)】 天王寺山門
【写真 下(右)】 天王寺本堂

・朱印尊格:本尊 阿弥陀如来 札番:なし 直書(筆書)

・朱印尊格:毘沙門天 札番:なし 直書(筆書)(谷中七福神)

・朱印尊格:閻魔大王 札番:なし 直書(筆書)(ご縁日のみ?/江戸・東京四十四閻魔参り第11番)
○谷中七福神(毘沙門天)、上野王子駒込辺三十三観音霊場第9番
※上野王子駒込辺三十三観音霊場第9番の御朱印は不授与
■隨龍山 境智院 了俒寺
台東区谷中7-17-2
天台宗 御本尊:阿弥陀如来
〔御朱印不授与〕
【荒川区西日暮里三丁目】
■長久山 本行寺
荒川区西日暮里3-1-3
日蓮宗


・御首題 直書(筆書)
■大黒山 経王寺
荒川区西日暮里3-2-6
日蓮宗

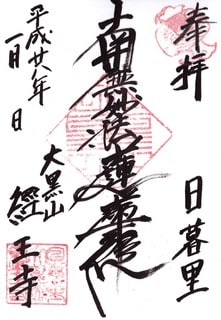
・御首題 直書(筆書)
〔大黒天(荒川下町七福神)の御朱印は不授与・・・Web上に拝受御朱印ありますが不授与とのこと〕
■法要山 啓運寺
荒川区西日暮里3-2-14
法華宗本門流


・御首題 直書(筆書)
〔毘沙門天(荒川下町七福神)の御朱印は不授与〕
■補陀落山 観音院 養福寺
荒川区西日暮里3-3-8
真言宗豊山派

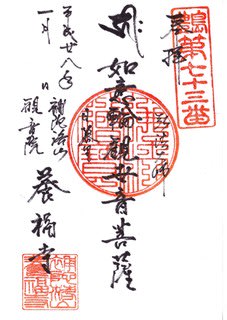
・朱印尊格:如意輪観世音菩薩・弘法大師 豊島八十八ヶ所霊場第73番印判 直書(筆書)
○東京三十三観音霊場第28番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第2番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第27番、荒川辺八十八ヶ所霊場第7番、東都七観音霊場第5番、近世江戸三十三観音霊場第10番、東方三十三観音霊場第12番
■法輪山 法幢院 浄光寺
荒川区西日暮里3-4-3
真言宗豊山派 御本尊:薬師如来

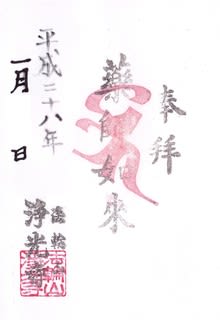
・朱印尊格:薬師如来 札番:なし 印判(豊島八十八ヶ所霊場第5番)
○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第1番、荒川辺八十八ヶ所霊場第8番、東都六地蔵霊場第3番
(神社御朱印)
■諏方神社
荒川区西日暮里3-4-8

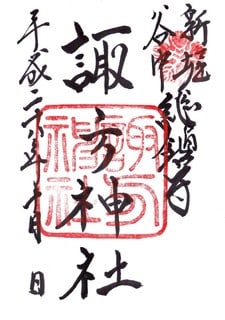
・諏方神社 直書(筆書)
■浄居山 青雲寺
荒川区西日暮里3-6-4
臨済宗妙心寺派


・朱印尊格:恵比寿神(谷中七福神) 書置(筆書)
※御本尊の御朱印は不授与
○荒川下町七福神(恵比寿神)
■運啓山 修性院
荒川区西日暮里3-7-12
日蓮宗


【写真 上(左)】 修性院山門
【写真 下(右)】 修性院本堂

・御首題 直書(筆書)

・朱印尊格:布袋尊(谷中七福神) 札番:なし 直書(筆書)
○荒川下町七福神(布袋尊)
■瑞応山 南泉寺
荒川区西日暮里3-8-3
臨済宗妙心寺派
〔御朱印不授与〕
○東方三十三観音霊場第11番
■日照山 法光寺
荒川区西日暮里3-8-6
法華宗陣門流


・御首題 直書(筆書)
■宝珠山 延命院
荒川区西日暮里3-10-1
日蓮宗


【写真 上(左)】 延命院境内
【写真 下(右)】 延命院の授与案内


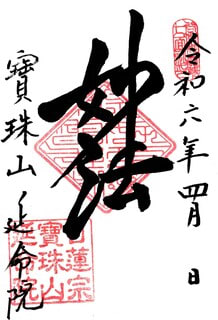
【写真 上(左)】 ・御朱印(妙法)
【写真 下(右)】 ・御朱印(妙法)
【 BGM 】
■ 空気力学少女と少年の詩 -piano vocal ver.-
■ 消えてしまえたならいいのに、なんて - めありー(歌ってみた)
■ 夢の大地 - Kalafina
■ This Love - アンジェラ・アキ
■ 本当の音 [Hontou no Oto] (True Sound) - KOKIA
→ 歌詞
「日本よりも海外で評価が高い説」あり。どーゆーこと??
はてなブログURLのブックマークをお願いします。
久しぶりに追加しました。
なお、これまで非掲載としていた寺院の御朱印もWeb上でみつかるようになったので、こちらも併せてUPします。
---------------------------
2021/02/23 UP
※ さらに御朱印や写真を追加しました。
---------------------------
2020/03/07 UP
※ エリアや寺社の写真を追加してみました。
谷中で拝受できる御朱印については、「東京都台東区の札所と御朱印」でご紹介していますが、今回は谷中の最新情報を交えて整理してみます。




谷中は日蓮宗・法華宗の御首題を抜きにして語ることはできません。
このところ、本妙院様や長運寺様がカラフルな絵御首題(絵御朱印)を出され拝受層が広がっていること、また、Web上でも授与情報が増えてきているので、今回日蓮宗・法華宗寺院(御首題)情報も加えて再UPします。
なお、拝受したところと、不授与の確認がとれたところは記載していますが、現時点で不明な日蓮宗・法華宗寺院については記載しておりません。
谷中はメディアのとりあげも多く、ガイド類もたくさん出ているので御朱印のメッカと思われがちですが(実際、授与される寺院はかなり多い)、じつは敷居の高い寺院もかなりあります。
もちろん、丁寧なご対応をいただけるお寺さんもたくさんあり、お寺ごとの対応の差が大きい印象があります。
神社がすくないことも拝受難易度を高めている一因です。
このあたりは、御朱印拝受が容易な上野公園エリアとは様相が異なり、御朱印初心者は上野公園エリアから入った方がベターかと思われます。
(なお、いわゆる「塩対応」はお寺さんのお考えやそういうお考えをもたれた背景をお伺いするまたとない機会(実際、委細にお話を伺えた場合、勉強になることが多い)なのですが、不慣れな局面でいきなりこれをくらうと正直キツイです(笑))
以前、御府内霊場を結願したときも「谷中のお寺は予想以上に手ごわい」という印象がありましたが、その傾向はますます強まっているような感じがします。
納経所前に「御朱印は、御府内霊場専用の御朱印帳にしか授与しない。」旨の明示をされている寺院もあります。
(たしかに、谷中界隈でとんでもない態度で御朱印を乞う観光客を見たことは一度や二度ではないですし、お寺さんのこのような対応はわからなくもないです。
ただし、(専用納経帳でなく)汎用御朱印帳で札番を振り、弘法大師霊場(八十八ヶ所)をコンプリートするのはまず不可能です。
となると、新規巡拝者の間口も狭まってしまう感じも(個人的には)します。発願寺の高野山東京別院をはじめ、すばらしい対応をしていただける札所も多いだけに、こういう流れはいささか残念な気もします。)
一方、マイナー系札所や非札所では、御朱印授与に積極的なお寺さんが増えている感じもします。
上記の本妙院様や長運寺様、数年前は非授与だった西光寺様が御朱印授与をはじめられたなどがその具体例です。
また、御朱印をお断りされたお寺さんでも「いまのところはお出ししていない。」という、含みのある表現をされたところが数箇寺ありました。
今回は、不授与の寺院(私自身が直接ご住職ないし大黒さんに確認したもの(2017~2019年)、日蓮宗寺院も含む)もご紹介します。
動線的に連続している荒川区西日暮里三丁目の御朱印も併せてご紹介します。




【エリア概要】
言問通りから北は、いよいよ都内屈指の寺町、谷中エリアに入る。
このエリアは上野駅から入るよりも、千代田線「根津」駅から入った方が便利がよい。
ちなみにこのあたりは、「谷根千」(谷中・根津・千駄木)と呼ばれ、下町情緒やグルメが楽しめるエリアとして近年人気急上昇中。
言問通り・善光寺坂北側の谷中一丁目は日蓮宗・御首題メインのエリア。坂を上りきった谷中六丁目は日蓮宗と他宗派の混在エリアとなり、御府内八十八箇所の札所も。
ここから北側の谷中五丁目から西日暮里三丁目(荒川区)にかけてが谷中のメインエリア。
東は谷中霊園で、JR「日暮里」駅からスタートする散策客も目立つ。
谷中五丁目の真言宗寺院は御府内八十八箇所の札所も多く、御朱印収集的に外せないエリア。これを抜きにしても寺町の趣ゆたかで散策する価値は十分にあると思う。

【拝受データ】 (おおむね谷中一丁目から。現時点で授与休廃止の可能性あり、形態(直書・書置など)は状況により変化する可能性大です。)
なお、末尾○欄は御朱印をいただいていない霊場で、古いものが多いです。
■楞伽山 天眼寺
台東区谷中1-2-14
臨済宗妙心寺派
〔御朱印不授与〕
■栄源山 本寿寺
台東区谷中1-4-9
日蓮宗
〔御首題不授与・・・Web上に拝受御首題ありますが不授与とのこと〕
■祝融山 瑞松院
台東区谷中1-4-10
臨済宗妙心寺派 御本尊:釈迦牟尼佛
〔御朱印不授与〕
■妙経山 成就院 信行寺
台東区谷中1-5-7
日蓮宗
〔御首題不授与・・・Web上に拝受御首題ありますが不授与とのこと〕
■長久山 妙泉寺
台東区谷中1-5-34
法華宗本門流


・御首題 書置(筆書)
■顕寿山 佛心寺
台東区谷中1-5-35
日蓮宗


【写真 上(左)】 佛心寺山門
【写真 下(右)】 佛心寺本堂

・御首題 直書(筆書)


・御朱印 書置(筆書)
・毘沙門天の御朱印 直書(筆書)
※ご対応はたいへん親切です。御首題は書置ご用意の可能性があります。
■大法山 一乗寺
台東区谷中1-6-1
日蓮宗


【写真 上(左)】 一乗寺山門
【写真 下(右)】 一乗寺本堂


【写真 上(左)】 ・御首題 直書(筆書)
【写真 下(右)】 ・御朱印 直書(筆書)
※御朱印・御首題についてのご対応は→こちら。時間限定ですが、快く授与いただけます。
カラー御朱印・御首題は郵送対応可。墨朱御朱印・御首題は参拝者のみに授与のようです。
■倍増山 宝城院 金嶺寺
台東区谷中1-6-27
天台宗 御本尊:阿弥陀如来


・朱印尊格:阿弥陀如来 札番:なし 直書(筆書)
○上野王子駒込辺三十三観音霊場第31番
■大乗山 長運寺
台東区谷中1-7-4
日蓮宗


【写真 上(左)】 長運寺山門
【写真 下(右)】 長運寺本堂
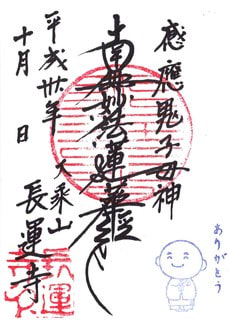

【写真 上(左)】 ・御首題 直書(筆書)
【写真 下(右)】 ・絵御首題 直書(筆書)
※絵御首題・絵御朱印で有名。授与時間は→こちら(インスタ)でUPされます。。
■望湖山 玉林寺
台東区谷中1-7-15
曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛


・朱印尊格:釋迦牟尼佛 札番:なし 直書(筆書)
○江戸浅草辺三十三観音霊場第25番
■六浦山 延壽寺 (日荷堂)
台東区谷中1-7-36
日蓮宗


【写真 上(左)】 延壽寺本堂
【写真 下(右)】 延壽寺日荷堂

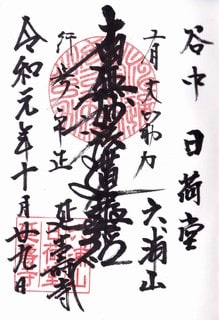
【写真 上(左)】 ・御首題 書置(筆書)
【写真 下(右)】 ・御首題 直書(筆書)
■正栄山 妙行寺
台東区谷中1-7-37
日蓮宗


・御首題 直書(筆書)
■石岡山 妙福寺
台東区谷中1-7-41
日蓮宗
〔御首題不授与・・・Web上に拝受御首題ありますが不授与とのこと〕
■龍興山 臨江寺
台東区谷中1-4-13
臨済宗大徳寺派 御本尊:釈迦牟尼佛


・朱印尊格:南無本師釋迦牟尼佛 札番:なし 直書(筆書)
○秩父写山の手三十四観音霊場第3番
■谷中冨士
台東区谷中1-6-14
参拝記念スタンプあり


■光雲山 元導寺 法蔵院
台東区谷中1-6-26
天台宗 御本尊:阿弥陀如来


・朱印尊格:阿弥陀如来 札番:なし 直書(筆書)
■高光山 大圓寺
台東区谷中3-1-2
日蓮宗


【写真 上(左)】 大圓寺山門
【写真 下(右)】 大圓寺境内


【写真 上(左)】 ・御首題 直書(筆書)
【写真 下(右)】 ・御朱印 直書(筆書)
■妙祐山 宗林寺 (江戸十大祖師/舟守祖師)
台東区谷中3-10-22
日蓮宗


・御首題 書置(筆書)
■円妙山 本授寺
台東区谷中3-11-6
顕本法華宗
〔御首題不授与〕
■慈雲山 久成院
台東区谷中4-1-5
日蓮宗


・御首題 直書(筆書)
■正行院
台東区谷中4-1-6
日蓮宗

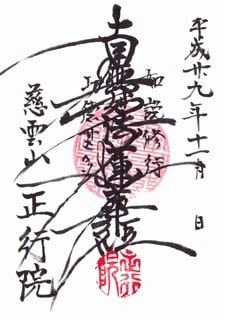
・御首題 直書(筆書)
■慈雲山 浄延院
台東区谷中4-1-8
日蓮宗


・御首題 直書(筆書)
■慈雲山 瑞輪寺 (江戸十大祖師/安産飯匙の祖師)
台東区谷中4-2-5
日蓮宗


【写真 上(左)】 瑞輪寺参道
【写真 下(右)】 瑞輪寺山門


【写真 上(左)】 瑞輪寺本堂
【写真 下(右)】 東京七面山
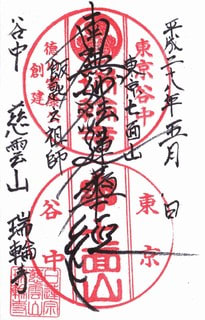
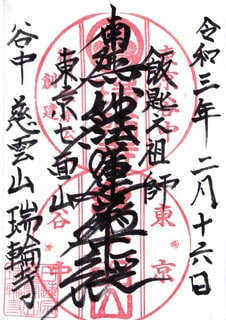
・御首題 直書(筆書)


・御朱印(妙法) 直書(筆書)
■本妙院
台東区谷中4-2-11
日蓮宗


【写真 上(左)】 本妙院山門
【写真 下(右)】 本妙院本堂

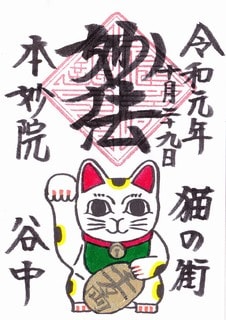
【写真 上(左)】 ・御首題 直書(筆書)
【写真 下(右)】 ・御朱印(妙法) 書置(筆書)
※絵御首題・絵御朱印で有名。
■法栄山 本通寺
台東区谷中4-2-33
法華宗陣門流


・御首題 直書(筆書)
■栄照山 龍谷寺
台東区谷中4-2-35
日蓮宗


・御首題 直書(筆書)
■寂静山 蓮華寺
台東区谷中4-3-1
日蓮宗


・御首題 書置(筆書)
■日長山 領玄寺
台東区谷中4-3-5
日蓮宗
〔御首題不授与〕
■円住山 妙円寺
台東区谷中4-4-29
日蓮宗
〔御首題不授与・・・「御朱印不授与」の貼紙あり、御首題も不授与とのこと〕
■海雲山 天龍院
台東区谷中4-4-33
臨済宗妙心寺派 御本尊:釈迦牟尼佛
〔御朱印不授与・・・Web上に拝受御朱印ありますが不授与とのこと〕
■興福山 永久寺
台東区谷中4-2-37
曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛


・朱印尊格:南無釈迦牟尼佛 札番:なし 直書(筆書)
○江戸浅草辺三十三観音霊場第31番、秩父写山の手三十四観音霊場第6番
■象頭山 頣神院
台東区谷中4-3-27
臨済宗妙心寺派 御本尊:不詳

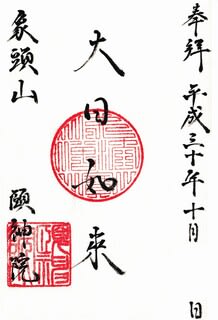
・朱印尊格:大日如来 札番:なし 直書(筆書)
■初音山 東漸寺 観智院
台東区谷中5-2-4
真言宗豊山派 御本尊:大日如来


・朱印尊格:本尊 阿弥陀如来・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所第63番印判 直書(筆書)
○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第6番、江戸八十八ヶ所霊場第64番
※「谷中の火除不動尊」の御朱印は不授与。幼稚園があるので開園時参拝のタイミング留意要。
■大道山 興禅寺
台東区谷中5-2-11
臨済宗興聖寺派
〔御朱印不授与〕
○弁財天百社参り第58番
■運立山 養傅寺
台東区谷中5-2-16
日蓮宗


・御首題 直書(筆書)
■大道山 長安寺
台東区谷中5-2-22
臨済宗妙心寺派 御本尊:千手観世音菩薩


・朱印尊格:大悲殿 上野王子駒込辺三十三観音霊場第22番印判 直書(筆書)
○谷中七福神(寿老人)、東方三十三観音霊場第14番
■感応山 常在寺
台東区谷中5-2-25
日蓮宗

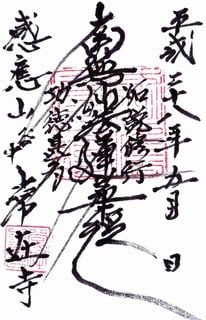
・御首題 直書(筆書)
■長清山 養泉寺
台東区谷中5-2-28
日蓮宗


・御首題 直書(筆書)
■常観山 安立寺
台東区谷中5-3-17
日蓮宗


・御首題 直書(筆書)
■天瑞山 観福寺 明王院
台東区谷中5-4-2
真言宗豊山派 御本尊:阿弥陀如来

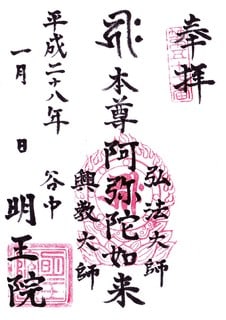
・朱印尊格:本尊 阿弥陀如来・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所57番印判 直書(筆書)
○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第5番、江戸八十八ヶ所霊場第57番
■普門山 全生庵
台東区谷中5-4-7
臨済宗国泰寺派 御本尊:葵正観世音菩薩

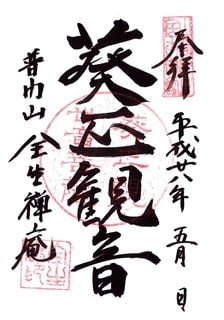
・朱印尊格:葵正観音 札番:なし 直書(筆書)
○大東京百観音霊場第25番
■松栄山 福相寺
台東区谷中5-4-9
日蓮宗


・御首題 書置(筆書)
■延寿山 長久寺
台東区谷中5-4-11
日蓮宗


・御首題 直書(筆書)
※多忙時不可。
■長興山 立善寺
台東区谷中5-4-19
日蓮宗


・御首題 (筆書)
■長谷山 元興寺 加納院
台東区谷中5-8-5
新義真言宗 御本尊:阿弥陀如来


・朱印尊格:本尊 阿弥陀如来・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所第64番印判 直書(筆書)
○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第4番、江戸八十八ヶ所霊場第63番
■妙見山 本立寺
台東区谷中5-8-7
日蓮宗


・御首題 直書(筆書)
※ご丁寧なご対応、頭が下がります。
■百丈山 霊梅院
台東区谷中5-8-19
臨済宗妙心寺派 御本尊:釈迦牟尼佛
〔御朱印不授与〕
■福聚山 海蔵院
台東区谷中5-8-25
臨済宗妙心寺派
〔御朱印不授与〕
■蓮葉山 妙智院 観音寺
台東区谷中5-8-28
真言宗豊山派 御本尊:大日如来


【写真 上(左)】 観音寺本堂
【写真 下(右)】 観音寺の築地塀

・朱印尊格:大日如来(御本尊) 札番:なし 書置(筆書)

・朱印尊格:大日如来・弘法大師 御府内八十八箇所42番印判 直書(筆書)

・お種子(ア)の御朱印

・スワロフスキー付御朱印
○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第3番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第32番、東方三十三観音霊場第13番、江戸八十八ヶ所霊場第42番
※参拝客以外は山内立入禁止の掲示あり。
■長光山 龍泉寺
台東区谷中5-9-26
日蓮宗
〔山内立入制限看板あり/御朱印不授与?〕
■日照山 長明寺
台東区谷中5-10-15
日蓮宗


・御首題 直書(筆書)
■円妙山 大行寺
台東区谷中6-1-13
日蓮宗


・御首題 直書(筆書)
■長昌山 大雄寺
台東区谷中6-1-26
日蓮宗


・御首題 直書(筆書)
■光照山 感應寺
台東区谷中6-2-4
日蓮宗


・御首題 直書(筆書)
■本覚山 宝光寺 自性院
台東区谷中6-2-8
新義真言宗 御本尊:大日如来


・朱印尊格:本尊 大日如来・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所第53番印判 直書(筆書)
○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第10番、江戸八十八ヶ所霊場第53番
■薬王寺 長久院
台東区谷中6-2-16
真言宗豊山派 御本尊:大日如来


・朱印尊格:本尊 大日如来・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所第55番印判 直書(筆書)
○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第8番、江戸八十八ヶ所霊場第55番
※閻魔大王(江戸・東京四十四閻魔第12番)の御朱印は不授与
■仏到山 無量寿院 西光寺
台東区谷中6-2-20
新義真言宗


【写真 上(左)】 西光寺山門
【写真 下(右)】 西光寺本堂
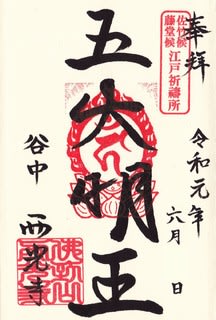
・朱印尊格:五大明王 主印判:種子 札番:なし 直書(筆書)

・朱印尊格:五大明王 主印判:不動明王御影印 札番:なし 直書(筆書)
こちらをメインに授与されているようです。
※以前は不授与でしたが御朱印授与を開始され対応も親切です。カラー御朱印マニアを中心に人気を集めている模様。
○上野王子駒込辺三十三観音霊場第7番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第7番、江戸八十八ヶ所霊場第70番
■金輪山 最勝寺 總持院
台東区谷中6-2-33
天台宗 御本尊:阿弥陀如来


・朱印尊格:谷中不動尊 札番:なし 直書(筆書)
※こちらのお寺様につきましては、Web上での拝受情報がほとんどみつからず、現在でも授与されているかは不明です。
なお、御本尊の御朱印は授与されておりません。
■宝塔山 龍門寺 多宝院
台東区谷中6-2-35
真言宗豊山派 御本尊:多宝如来


・朱印尊格:本尊 多宝如来・弘法大師 御府内八十八箇所第49番印判 直書(筆書)
○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第9番、江戸八十八ヶ所霊場第49番
※「谷中吉祥天」の御朱印は不授与
■清林山 和光院 大泉寺
台東区谷中6-2-13
天台宗 御本尊:阿弥陀如来


・朱印尊格:阿彌陀如来 札番:なし 直書(筆書)
■無量山 功徳林寺
台東区谷中7-6-9
浄土宗 御本尊:阿弥陀如来


【写真 上(左)】 功徳林寺本堂
【写真 下(右)】 笠森稲荷堂

・朱印尊格:無量壽 札番:なし 書置(筆書)
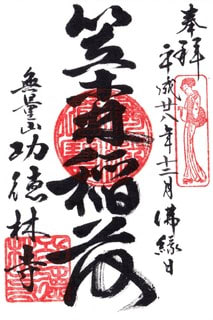
・朱印尊格:笠森稲荷 札番:なし 書置(筆書)
■安立院
台東区谷中7-10-4
曹洞宗系単立
〔御朱印不授与〕
■護国山 尊重院 天王寺
台東区谷中7-14-8
天台宗 御本尊:阿弥陀如来


【写真 上(左)】 天王寺山門
【写真 下(右)】 天王寺本堂

・朱印尊格:本尊 阿弥陀如来 札番:なし 直書(筆書)

・朱印尊格:毘沙門天 札番:なし 直書(筆書)(谷中七福神)

・朱印尊格:閻魔大王 札番:なし 直書(筆書)(ご縁日のみ?/江戸・東京四十四閻魔参り第11番)
○谷中七福神(毘沙門天)、上野王子駒込辺三十三観音霊場第9番
※上野王子駒込辺三十三観音霊場第9番の御朱印は不授与
■隨龍山 境智院 了俒寺
台東区谷中7-17-2
天台宗 御本尊:阿弥陀如来
〔御朱印不授与〕
【荒川区西日暮里三丁目】
■長久山 本行寺
荒川区西日暮里3-1-3
日蓮宗


・御首題 直書(筆書)
■大黒山 経王寺
荒川区西日暮里3-2-6
日蓮宗

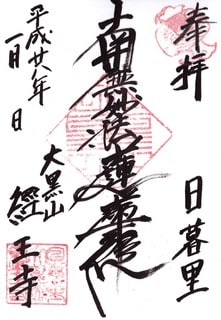
・御首題 直書(筆書)
〔大黒天(荒川下町七福神)の御朱印は不授与・・・Web上に拝受御朱印ありますが不授与とのこと〕
■法要山 啓運寺
荒川区西日暮里3-2-14
法華宗本門流


・御首題 直書(筆書)
〔毘沙門天(荒川下町七福神)の御朱印は不授与〕
■補陀落山 観音院 養福寺
荒川区西日暮里3-3-8
真言宗豊山派

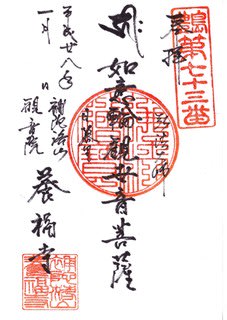
・朱印尊格:如意輪観世音菩薩・弘法大師 豊島八十八ヶ所霊場第73番印判 直書(筆書)
○東京三十三観音霊場第28番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第2番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第27番、荒川辺八十八ヶ所霊場第7番、東都七観音霊場第5番、近世江戸三十三観音霊場第10番、東方三十三観音霊場第12番
■法輪山 法幢院 浄光寺
荒川区西日暮里3-4-3
真言宗豊山派 御本尊:薬師如来

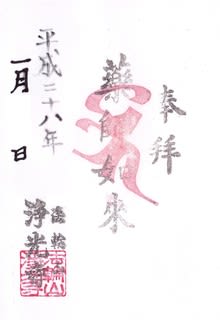
・朱印尊格:薬師如来 札番:なし 印判(豊島八十八ヶ所霊場第5番)
○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第1番、荒川辺八十八ヶ所霊場第8番、東都六地蔵霊場第3番
(神社御朱印)
■諏方神社
荒川区西日暮里3-4-8

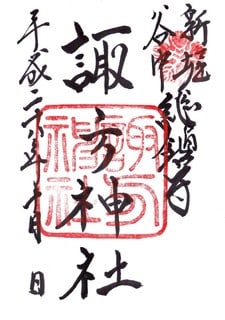
・諏方神社 直書(筆書)
■浄居山 青雲寺
荒川区西日暮里3-6-4
臨済宗妙心寺派


・朱印尊格:恵比寿神(谷中七福神) 書置(筆書)
※御本尊の御朱印は不授与
○荒川下町七福神(恵比寿神)
■運啓山 修性院
荒川区西日暮里3-7-12
日蓮宗


【写真 上(左)】 修性院山門
【写真 下(右)】 修性院本堂

・御首題 直書(筆書)

・朱印尊格:布袋尊(谷中七福神) 札番:なし 直書(筆書)
○荒川下町七福神(布袋尊)
■瑞応山 南泉寺
荒川区西日暮里3-8-3
臨済宗妙心寺派
〔御朱印不授与〕
○東方三十三観音霊場第11番
■日照山 法光寺
荒川区西日暮里3-8-6
法華宗陣門流


・御首題 直書(筆書)
■宝珠山 延命院
荒川区西日暮里3-10-1
日蓮宗


【写真 上(左)】 延命院境内
【写真 下(右)】 延命院の授与案内


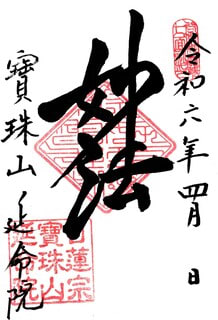
【写真 上(左)】 ・御朱印(妙法)
【写真 下(右)】 ・御朱印(妙法)
【 BGM 】
■ 空気力学少女と少年の詩 -piano vocal ver.-
■ 消えてしまえたならいいのに、なんて - めありー(歌ってみた)
■ 夢の大地 - Kalafina
■ This Love - アンジェラ・アキ
■ 本当の音 [Hontou no Oto] (True Sound) - KOKIA
→ 歌詞
「日本よりも海外で評価が高い説」あり。どーゆーこと??
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 富士山周辺の御朱印
目下、富士山周辺はインバウンドに占拠されている感もありますが、GWで訪れる方も多いと思います。
先日、富士山周辺の御朱印情報をWebで当たってみたところ、浅間神社メインのものが多く、網羅的にまとめたものがあまりないので、一念発起して(こればっかし(笑))まとめてみることにしました。
富士山周辺の御朱印はおおむね拝受していますが、富士山頂の浅間大社奥宮をはじめ、未拝受の寺社もいくつかあります。
未拝受御朱印は拝受次第UPすることとし、とりあえず拝受済の御朱印情報をUPしてみます。
なお、御朱印は寺社様の状況やお考えにもとづき授与されるもので、以下の御朱印が現在も授与されているかは不明です。
---------------------------------
富士山の北側から時計まわりにリストしていきます。
富士河口湖町、富士吉田市、西桂町、忍野村、山中湖村、小山町、御殿場市、裾野市、三島市、長泉町、清水町、沼津市、富士市、富士宮市の順です。
まずは御朱印のみUPし、後日寺社の写真とコメントを入れていきます。
なお、現在、富士北麓の7社で「神玉巡拝」を催行している模様です。
詳細は→(こちら(富士吉田市観光ガイド))。
01.富士河口湖町
■ 河口浅間神社
(かわぐちあさまじんじゃ)
公式Web
富士河口湖町河口1
主祭神:浅間大神
社格等:式内社(名神大)論社
授与所:境内
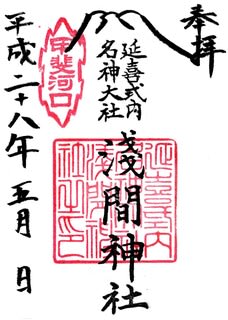
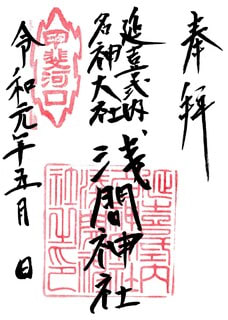
■ 母の白滝神社
(ははのしらたきじんじゃ)
やまなし観光推進機構Web
富士河口湖町河口
御祭神:栲幡千千姫命
授与所:河口浅間神社

■ 富士山遥拝所 (天空の鳥居)
(ふじさんようはいじょ)
河口湖.net
富士河口湖町河口1119-2
御祭神:浅間大神
授与所:遙拝所売店にて

□ 富士山パノラマロープウェイ山頂 うさぎ神社
御祭神:大国主命・大山祇命・木花開耶姫命
※御朱印未拝受です。
□ 浅間日月神社 (大石浅間神社)
山梨県神社庁
富士河口湖町大石268
御祭神:木花開耶姫命、天照皇大神、月読命
社格等:旧村社
授与所:境内
※御朱印未拝受です。
■ 鸕鷀嶋神社
(うのしまじんじゃ)
河口湖.net
富士河口湖町大石2584
主祭神:豊玉姫命
授与所:浅間日月神社 (大石浅間神社)
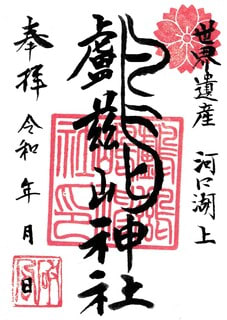
■ 霊鷲山 常在寺
(じょうざいじ)
富士河口湖町観光連盟Web
富士河口湖町小立139
法華宗本門流
札所:甲斐百八霊場第33番
授与所:山内庫裏
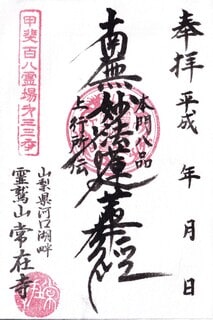
■ 蓮華山 妙法寺
(みょうほうじ)
富士河口湖町観光情報Web
富士河口湖町小立692
法華宗本門流
札所:甲斐百八霊場第32番
授与所:山内庫裏
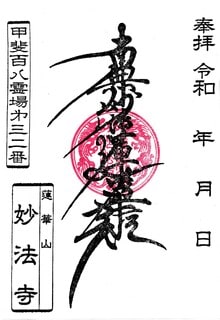
■ 冨士御室浅間神社二合目本宮(奥宮)
(ふじおむろせんげんじゃ)
公式Web
富士河口湖町勝山
主祭神:木花咲耶姫命
社格等:別表神社/旧県社
授与所:冨士御室浅間神社里宮
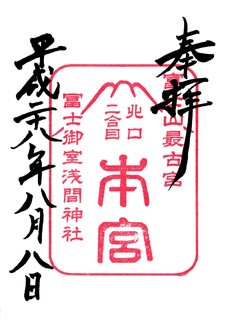
■ 冨士御室浅間神社里宮
(ふじおむろせんげんじゃ)
公式Web
富士河口湖町勝山3951
主祭神:木花咲耶姫命
社格等:別表神社/旧県社
授与所:境内

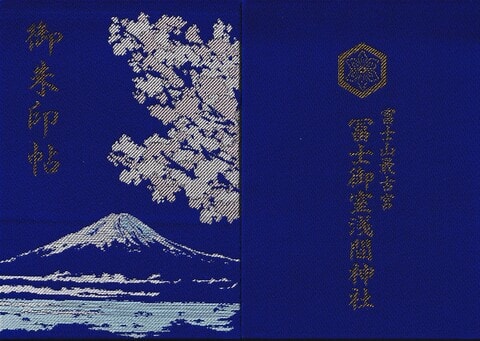
■ 長徳山 妙本寺
(みょうほんじ)
富士河口湖町勝山609
法華宗
授与所:山内庫裏
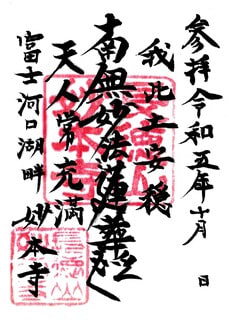
■ 広大山 圓通寺
(えんつうじ)
河口湖.net
富士河口湖町船津3932
臨済宗妙心寺派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:甲斐之国都留郡三十三ヶ所観音霊場第3番
授与所:山内庫裏
※要事前予約
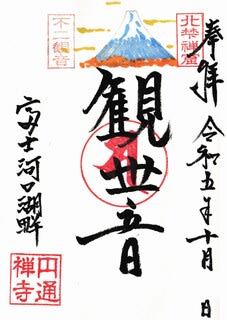
■ 筒口神社
(つつぐちじんじゃ)
山梨県神社庁Web
富士河口湖町船津5
主祭神:中筒男命
社格等:小船津組産土神、旧村社、神饌幣帛供進社
※タイミングが合えば拝受可?
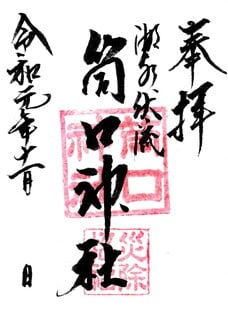
■ 八王子神社
(はちおうじじんじゃ)
山梨県神社庁Web
富士河口湖町船津4013
御祭神:素戔嗚尊、、五男三女神
社格等:大船津組産土神、旧村社、神饌幣帛供進社
※タイミングが合えば拝受可?
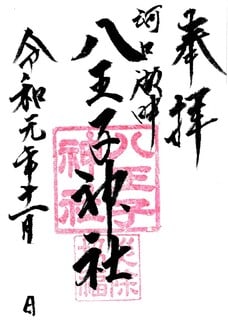
■ 無戸室浅間神社(船津胎内神社)
(むつむろせんげんじんじゃ)
山梨県神社庁Web
富士河口湖町船津6603(船津胎内樹型フィールドセンター)
主祭神:木花開耶姫命
授与所:船津胎内樹型フィールドセンター
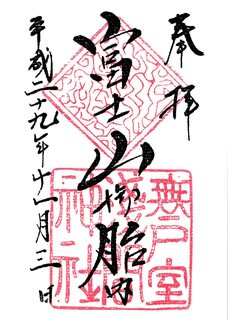
02.富士吉田市
□ 富士山天拝宮
富士吉田市上吉田(吉田口登山道八合目)
※御朱印未拝受
□ 富士山小御嶽神社
富士吉田市上吉田小御岳下5617(五合目御鎮座)
御祭神:磐長姫命、桜大刀自命、苔虫命
※御朱印未拝受
■ 新屋山神社 本宮
(あらややまじんじゃ)
公式Web
富士吉田市新屋1230
御祭神:大山祇大神、天照大御神、木花開耶姫命
授与所:境内
・金運上昇、商売繁盛の神様として広く知られる。
※ 御朱印はWebでたくさんみつかるので、そちらを参照下さい。
■ 新屋山神社 奥宮
(あらややまじんじゃ)
公式Web
富士吉田市侭5615
御祭神:大山祇大神、天照大御神、木花開耶姫命
授与所:境内
※12~4月下旬までアプローチ林道のゲート閉鎖。
・富士山麓を代表するパワスポとして知られる。
・Webには「ご縁のある人だけがたどり着ける」などのスピリチュアルな記事があるが、本宮で地図をいただけるので特段迷うことはない。ただし林道を30分弱も走るので慣れない方は要注意。
※ 御朱印はWebでたくさんみつかるので、そちらを参照下さい。
□ 冨士山小御嶽神社 里宮
(ふじさんこみたけじんじや さとみや)
富士吉田市上吉田4202
※御朱印未拝受
■ 北口本宮冨士浅間神社
(きたぐちほんぐうふじせんげんじんじゃ)
公式Web
富士吉田市上吉田5558
主祭神:木花開耶姫命、彦火瓊瓊杵命、大山祇神
社格等:別表神社、旧県社
授与所:境内授与所
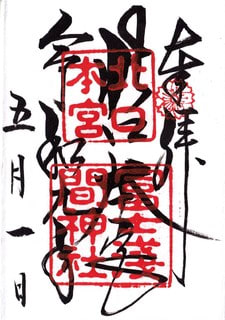

■ 諏訪神社
(すわじんじゃ)
公式Web
富士吉田市上吉田5558
(北口本宮冨士浅間神社境内社)
御祭神:建御名方神、八坂刀売神
授与所:北口本宮冨士浅間神社授与所
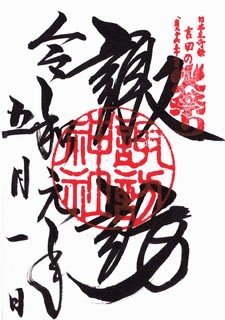
■ 大塚丘社
(おつかやましゃ)
公式Web
富士吉田市上吉田5619
(北口本宮冨士浅間神社境内社)
御祭神:日本武尊
授与所:北口本宮冨士浅間神社授与所
・景行天皇40年(西暦110年)、日本武尊ご東征の折、相模国足柄の坂本より甲斐国酒折宮へ向かわれる途中に冨士を遥拝された丘で、当社発祥の地とされる。
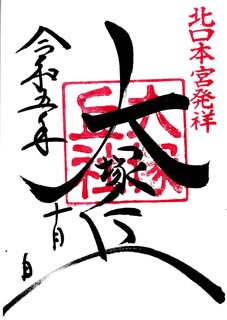
■ 吉祥山 上行寺
(じょうぎょうじ)
富士吉田市上吉田38
日蓮宗
授与所:山内庫裏
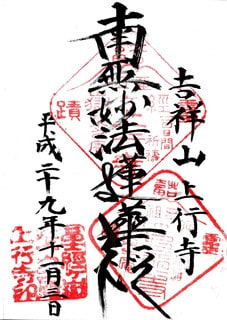
■ 吉積山 西念寺
(さいねんじ)
公式Web
富士吉田市上吉田7-7-1
時宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:甲斐百八霊場第30番
授与所:山内庫裏

・寺伝によると、養老三年(719年)行基菩薩が富士山二合目付近・錫原の地に庵を結んだのが草創という。
・富士山頂に出現の阿弥陀三尊を行基みずからが三寸八分の像に彫刻し、この尊像を御本尊として、富士道場大蓮院と号したという。
・その後、古吉田に移転ののち、永仁六年(1298年)遊行二祖他阿真教上人が諸国遊行の砌、西念寺に留錫して念仏の法門を説かれたところ多くの信者が参集し、ついに宗派を時宗に改めたという。
・遊行二祖真教上人を開基上人、その弟子の真海和尚が開山となる。
・永仁年間、武田氏の一族・一条右衛門大夫吉積が伽藍を造営寄進し、吉積山西念寺と改めたという。
・元亀三年(1572年)、旧地の村が富士山の雪代(雪解け水の災害)を避けるため村をあげて移転の折、当山も現在地に移転。
・富士山信仰とのゆかり深く、江戸時代、富士講の信者は西念寺が定めた「西念寺精進場」で身を清めた後、富士に登拝したといわれる。
■ 水上山 月江寺
(げっこうじ)
富士吉田市下吉田869
臨済宗妙心寺派
御本尊:釈迦如来
札所:甲斐百八霊場第29番
授与所:山内庫裏
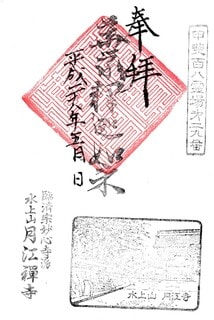
■ 小室浅間神社(下宮浅間神社)
(おむろせんげんじんじゃ/しもみやせんげんじんじゃ)
公式Web
富士吉田市下吉田5221
主祭神:木花咲耶姫命
社格等:別表神社、旧郷社
授与所:境内授与所

■ 大塔宮社・雛鶴社
公式Web
富士吉田市下吉田5221
(小室浅間神社境内社)
御祭神・大塔宮護良親王、雛鶴姫
授与所:小室浅間神社境内授与所
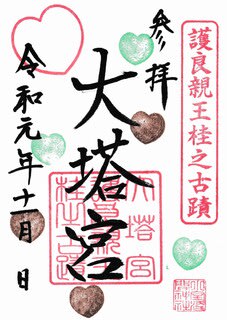
■ 寶松山 大正寺
(だいしょうじ)
公式Web
富士吉田市新倉621
浄土真宗本願寺派
授与所:山内庫裏
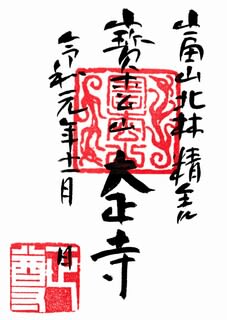
・寺伝によると文永年間(1264-1275年)、真宗祖門六老僧の源誓上人が、宗祖親鸞聖人御真筆の無碍光如来の画像を安置した草庵を当所字宮の下に草創という。
・文安年間(1444-1449年)に本願寺8世蓮如上人が当地を御巡錫ま際、藤原氏の末裔・遠山伊豆守重正が蓮如上人に帰依し法名乗欽を賜る。
・その後、草庵を念仏道場として水石山新念寺と号し、後に新福寺と改め、さらに正保元年(1644年)に現在地へ移転、寛文八年(16658年)に寺号を大正寺と改めた。
■ 大原山 如来寺
(にょらいじ)
公式Web
富士吉田市浅間1-5-6
浄土真宗本願寺派
授与所:山内庫裏

・嘉禄三年(1228年)勝沼万福寺の聖徳太子旧跡を巡排中の親鸞聖人に帰依して真宗へ改宗。
・宝徳三年(1451年)法性寺、慶長十五年(1610年)万蔵寺と寺号を改め、さらに享保二年(1718年)如来寺と改めて現在に至る。
■ 新倉山 正福寺
(しょうふくじ)
TERA MACHI(築地本願寺Web)
富士吉田市浅間1-5-38
浄土真宗本願寺派
授与所:山内庫裏
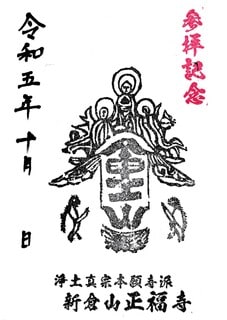
・大同二年(807年)に弘法大師が当地を訪れ、弟子道海に寺院建立を命じ、富北院(ふほくいん/真言宗)として創建。
・当時は神仏習合色を帯び、富士山五合目神域の別当を勤めたという記録も残るとの由。
・安貞二年(1228年)、9代住職道祐が親鸞聖人に邂逅して真宗に改宗し、正福寺と改めた。
■ 三國第一山 新倉富士浅間神社
(さんごくだいいちさん あらくらふじせんげんじんじゃ)
公式Web
富士吉田市浅間2-4-1
御祭神:木花咲耶姫命、大山祗命、瓊瓊杵尊
社格等:旧村社、甲斐国八代郡荒倉郷氏神
授与所:境内授与所
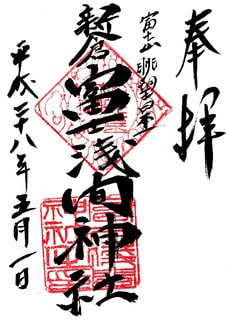
・慶雲三年(705年)、甲斐国八代郡荒倉郷へ富士北口郷の氏神として創祀。
・大同二年(807年)の富士山大噴火に際し、朝廷からの勅使が参向せられ、国土安泰富士山鎮火祭を執行、平城天皇より「三国第一山」の称号および天皇御親筆の勅額等を奉納。
・境内上部の戦没者慰霊の五重塔「忠霊塔」と新倉山浅間公園の桜と富士山が重なる絶景はSNSなどでも人気で、とくにインバウンドの来訪が多い。
■ 荒濱神社
(あらはまじんじゃ)
公式Web
富士吉田市浅間2-4-1
(新倉富士浅間神社境内社)
御祭神:機神様
授与所:新倉富士浅間神社境内授与所
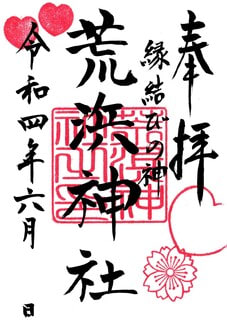
・当地はふるくから養蚕・織物の産地として栄え、養蚕・織物の神様として当社がお祀りされている。
・織物はタテとヨコの糸を交差させて織ることから、縁結びの神様としても知られている。
■ 福地八幡宮/福地八幡社
(ふじはちまんぐう/ふくちはちまんしゃ)
山梨県神社庁
富士吉田市下吉田5178
御祭神:天照皇大神、息長足姫、誉田別命、渡辺綱命
授与所:境内に案内あり

■ 北東本宮小室浅間神社(大明見浅間神社)
(おおあすみおむろせんげんじんじゃ)
山梨県神社庁Web
富士吉田市大明見2-1-1
御祭神:木花開耶姫命、誉田別命、国狭槌命、泥土煮命、上筒男命、他十三柱
授与所:境内授与所
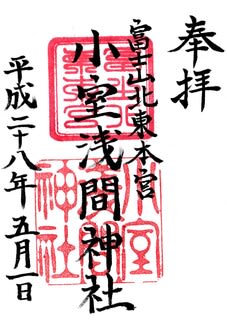
■ 護国神社
(ごこくじんじゃ)
富士吉田市大明見2-1-1
(北東本宮小室浅間神社境内社)
授与所:小室浅間神社境内授与所
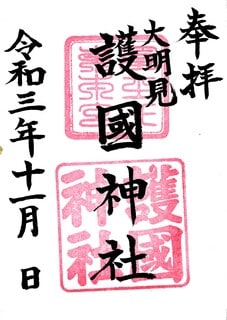
■ 明見山 慈光院
(じこういん)
公式SNS
富士吉田市大明見3-246
臨済宗妙心寺派
御本尊:
授与所:山内庫裏
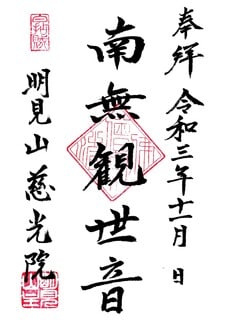
■ 不二阿祖山太神宮
(ふじあそやまだいじんぐう)
公式Web
富士吉田市大明見3537
授与所:境内授与所

■ 引接山 西方寺
(さいほうじ)
公式Web
富士吉田市小明見2058
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:甲斐百八霊場第28番、郡内三十三番観音霊場第8番
授与所:山内庫裏
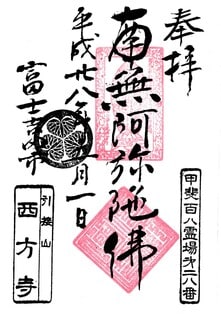
■ 小明見富士浅間神社
(こあすみふじせんげんじんじゃ)
富士吉田市向原1-21-11
主祭神:木花咲耶姫命
社格等:旧村社
授与所:忍野八海(忍草)浅間神社
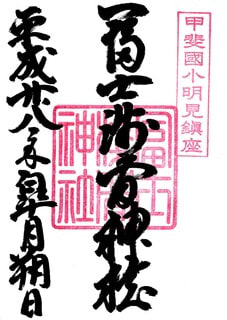
■ 三寳山 此教院 萬年寺
(まんねんじ)
富士吉田市小明見6071
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:郡内三十三番観音霊場第7番、同第14番
授与所:山内庫裏
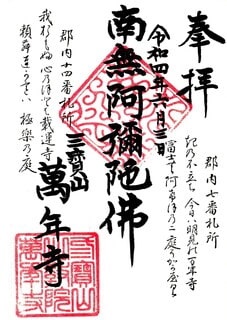
■ 山之神社
山梨県神社庁Web
富士吉田市小明見4-9-22
主祭神:大山祗命
授与所:忍野八海(忍草)浅間神社
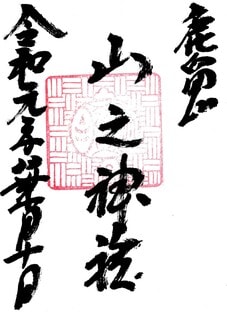
■ 明見根元神社
(あすみねのがみ)
山梨県神社庁Web
富士吉田市小明見6214
御祭神:天御柱命、罔象女命
社格等:御大沢部落の守護神
授与所:忍野八海(忍草)浅間神社
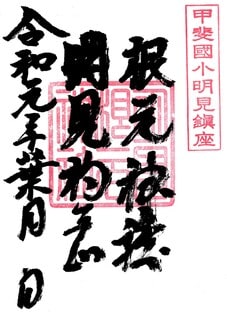
03.西桂町
■ 不二山 一乗寺
(いちじょうじ)
公式Web
西桂町小沼1997
臨済宗妙心寺派
御本尊:延命地蔵菩薩
札所:甲斐八十八ヶ所霊場12番、郡内三十三番観音霊場15番
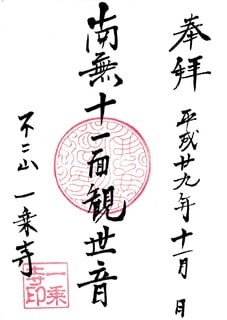
・開祖は笑山西堂和尚。開山は永享三年(1431年)本如実性景川禅師(妙心寺四派の一・龍泉派開祖)
・延暦十九年~廿三年(800-804年)の富士山延暦大噴火の際、国家安寧の祈祷と衆生供養のために建てられた永興庵が前身と伝わる。
・元禄二年(1689年)鳳谷守逸和尚により再興、永興寺から一乗寺へと改める。
・昭和39年、旧品第寺本堂を移転して書院として再建した際に、旧品第寺の十一面観世音菩薩(郡内三十三番観音霊場札所第15番札所本尊)を合祭して札所となる。
04.忍野村
■ 忍草山 大日院 東圓寺
(とうえんじ)
公式Web
忍野村忍草38
天台宗
御本尊:阿弥陀三尊
司元別当:忍草浅間神社
札所:甲斐之国都留郡三十三ヶ所観音霊場第4番、富士山北口元八湖霊場発願・結願
授与所:山内庫裏
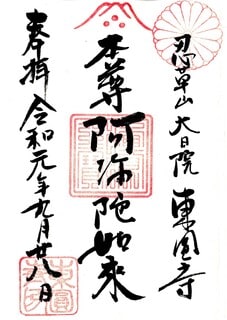
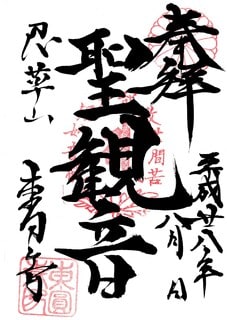
【写真 上(左)】 御本尊の御朱印(常時授与かは不明)
【写真 下(右)】 聖観世音菩薩の御朱印

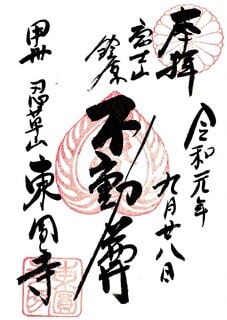
【写真 上(左)】 鈴原不動尊の御朱印
【写真 下(右)】 鈴原不動尊の御朱印
・弘仁年間(810-824年)、弘法大師が東国巡錫の折、富士山北麓で霊泉の湧出を見つけられここに一宇を建立、大日如来を安置されたのが創建と伝わり、当初は湖畑山南泉寺と号した真言宗寺院とされる。
・鎌倉時代に入って天台宗寺院となり忍草山大日院東圓寺と改めたという。
・寺伝によると、古くは富士山の鬼門を守護する蛇頭疫神社に隣接する地にあったといい、源頼朝公より広大な寺領の寄進を得たという。
・正徳元年(1711年)現在地に移転。
・古くから富士修験の道場として重要なポジションにあり、朝日浅間宮(現・忍草浅間神社)の別当を務めた。
・江戸後期には、富士講中が禊の地とした元八湖霊場(現・忍野八海)の拠点の寺として隆盛したという。
・古本尊は大日如来。現在の御本尊として阿弥陀三尊を奉じている。
・明治の神仏分離で富士山北口一合目より御遷座の不動明王像は鈴原不動尊と呼ばれて信仰を集める。
■ 蛇頭疫神社
忍野村忍草1967
御祭神:大禍津日神、八十禍津日神
授与所:忍野八海(忍草)浅間神社
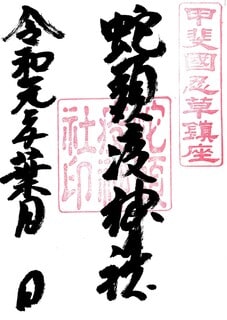
・御祭神の性格については諸説あるようだが、現地縁起書に「忍草部落の北東艮(うしとら)の方表鬼門に位置し、古来から部落の安泰をみそなはしてきた。」とあり、東圓寺公式Webに「富士山の鬼門を守護する」とあるので、当社は富士山および忍草部落の鬼門鎮護の性格がうかがわれる。
■ (忍野八海)浅間神社/忍草浅間神社
(おしのはっかいせんげんじんじゃ/しぼくさせんげんじんじゃ)
公式SNS
忍野村忍草456
御祭神:木花開耶姫命、天津日高日子番能邇々藝能尊、大山祇命
旧社格:村社
元別当:忍草山 大日院 東圓寺(忍草)
授与所:境内授与所

・大同二年(807年)創建、建久四年(1193年)源頼朝公の富士巻狩りの際に広大な御朱地を賜り、和田義盛と畠山重忠が随神門と金剛力士像(運慶作)を建立したという。
・広い地域の神社を官掌され、複数の御朱印を授与されている。
[ 富士山北口元八湖霊場 ]
世界遺産富士山の構成資産の一部として認定された忍野八海の8つの池それぞれを守護する八大竜王を巡拝する霊場。発願、結願ともに忍草の東圓寺。
八のつく日(8・18・28日)限定で御朱印が授与されている。→ 情報
■ 忍草山 大日院 東圓寺
(とうえんじ)
忍野村忍草38
札所:富士山北口元八湖霊場発願・結願
札所本尊:八大竜王(守護)
授与所:山内庫裏

■ 忍野八海一番出口池守護 灘陀竜王
(でぐちいけしゅご なんだりゅうおう)
忍野村忍草3483-2
札所:富士山北口元八湖霊場第1番
授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)
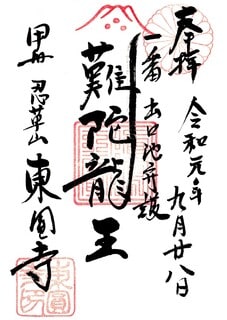
・やや離れて最も面積が広い池で水深0.5メートル。
・別名「精進池」とも呼ばれ、富士講信者はこの池の湧水で登山前に身を清めたという。
■ 忍野八海二番お釜池守護 跋難陀竜王
(おかまいけしゅご うぱなんだりゅうおう)
忍野村忍草111-2
札所:富士山北口元八湖霊場第2番
授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)
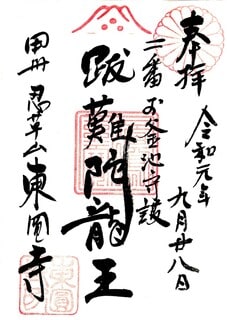
・最も小さな池で 水深:4メートル。
■ 忍野八海三番底抜池守護 娑加羅竜王
(そこなしいけしゅご しゃがらりゅうおう)
忍野村忍草272-2
札所:富士山北口元八湖霊場第3番
授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)
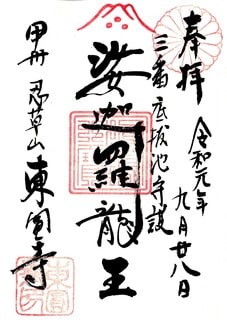
・樹林が生い茂る静かな池で水深1.5メートル。「はんの木林資料館」入館料300円が必要。
■ 忍野八海四番銚子池守護 和修吉竜王
(ちょうしいけしゅご ぶぁ-すきりゅうおう)
忍野村忍草266-3
札所:富士山北口元八湖霊場第4番
授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)
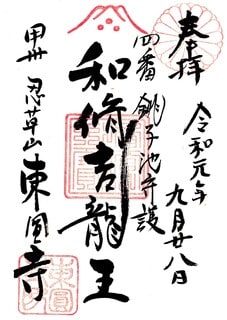
・銚子の形から名付けられたといい水深4メートル。縁結びの池と伝わる。
■ 忍野八海五番湧池守護 徳叉迦竜王
(わくいけしゅご とくしゃかりゅうおう)
忍野村忍草361-2
札所:富士山北口元八湖霊場第5番
授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)
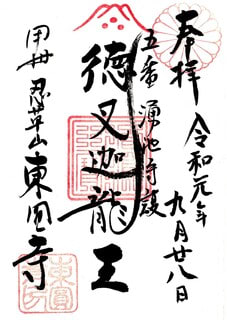
・八海一の湧水量で水深4メートル。中心部にあり賑わう。
■ 忍野八海六番濁池守護 阿那婆達多竜王
(にごりいけしゅご あなぶぁたぶたりゅうおう)
忍野村忍草269-2
札所:富士山北口元八湖霊場第6番
授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)
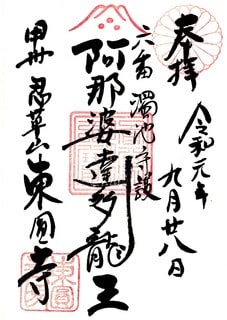
・湧池に隣接し、阿原川と合流して水深0.5メートル。濁ってはいない。
■ 忍野八海七番鏡池守護 摩那斯竜王
(かがみいけしゅご まなすう゛ぃんりゅうおう)
忍野村忍草339-2
札所:富士山北口元八湖霊場第7番
授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)

・見事な逆さ富士で知られ水深0.3メートル。
■ 忍野八海八番菖蒲池守護 優鉢羅竜王
(しょうぶいけしゅご うっぱらかりゅうおう)
忍野村忍草444-2
札所:富士山北口元八湖霊場第8番
授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)
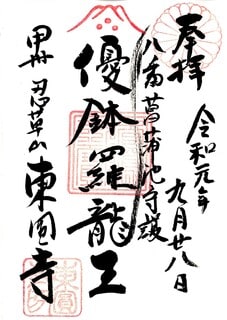
・菖蒲が繁る水深0.5メートルの池。奥は八海菖蒲池公園。
■ 出口稲荷社
(でぐちいなりしゃ)
忍野村忍草3483-2
御祭神:
授与所:忍野八海(忍草)浅間神社

・忍野八海一番出口池のほとりの小高い場所に御鎮座の稲荷社。
・池のほとりに3匹のキツネが棲み、いたずらをしては村人を困らせていた。『キツネを神として祀れば災いは無くなる』とのお告げを受けた村人たちは、大正14年お告げ通りに「出口稲荷大明神」を建立し祀ったところ、キツネの被害はなくなったという。
■ 穂見神社
(ほみじんじゃ)
忍野村忍草2206
御祭神:保食神
授与所:忍野八海(忍草)浅間神社
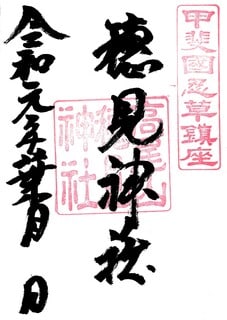
・金融通の守護神として崇敬される。
■ 醫王山 承天寺
(じょうてんじ)
公式Web
忍野村内野192
臨済宗妙心寺派
御本尊:薬師如来
札所:甲斐百八霊場第31番、郡内三十三番観音霊場第9番
授与所:山内庫裏
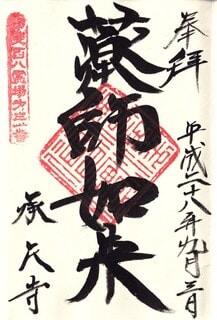
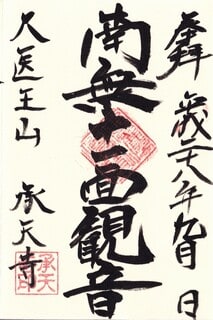
【写真 上(左)】 甲斐百八霊場の御朱印
【写真 下(右)】 郡内三十三番観音霊場の御朱印
・寺記によると壽永三年(1184年)、真言宗寺院、長寿山上天寺として現在より山寄りの地に創建。
・開基は鎌倉の有力御家人・畠山重忠公。建久四年(1193年)に鎌倉往還の普請奉行として忍野に来た重忠公がこの寺を定宿とし、時の住職に帰依して堂宇を整え開基となったという。
・御本尊薬師如来像、脇立日光大士十二神将像はいずれも運慶作と伝わる。
・江戸時代の再建時に臨済宗に改め山号を醫王山とし、寺号を承天寺としたという。
・甲斐百八霊場、郡内三十三番観音霊場のふたつの霊場の札所となっており、郡内三十三番観音霊場の札所本尊は十一面観世音菩薩。
■ 内野八幡神社(八幡社)
(うちのはちまんじんじゃ)
山梨県神社庁Web
忍野村内野3
御祭神:誉田別尊
授与所:忍野八海(忍草)浅間神社
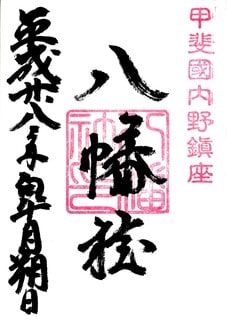
・幕末までは神仏混淆で法華経の題目講が行われていたという。
・神仏分離令により神社と視点から存続するが、村資料によると9月15日の例祭日の前日14日の夜には現在でも法華経信者が集まり、唱題が行われるという。
・例祭では相撲が奉納され、境内は賑わいをみせる。
■ (内野)浅間神社
(うちのせんげんじんじゃ)
山梨県神社庁Web
忍野村内野1
御祭神:木花開耶姫命、天児屋根命、太玉命
旧社格:村社、神饌幣帛供進指定社
授与所:忍野八海(忍草)浅間神社
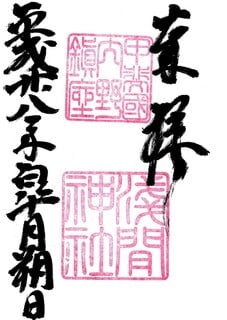
・山梨県神社庁資料によると、南北朝後の応永年間(1394-1428年)に尹良親王が南朝の四皇を奉祀して四皇三社浅間大神と称した。永享六年(1434年)尹良親王の従兄・與良親王の孫・梅若王が神主となるが3年で亡くなり、その霊を祀り富士浅間神社と称したという。山梨県神社庁資料には「其の霊を産土神に祀る足利氏に憚り富士浅間神社と稱す。」とある。
・本殿には貞治二年(1363年)の棟札が現存し、村内最古の建物とされる。
■ (内野)天狗社
(てんぐしゃ)
山梨県神社庁Web
忍野村内野381-1
御祭神:武甕槌命
授与所:忍野八海(忍草)浅間神社
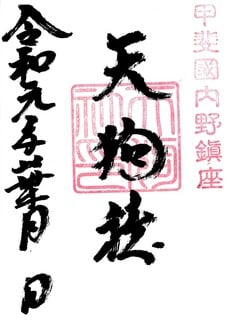
・創祀不詳。御神体は三百年以上前に稲荷坂の脇から掘り出されたという。
・内野地区は日清日露戦争で多くの兵士を送り出したが一人の戦死者も無かったことから天狗社のご加護と崇められている。
05.山中湖村
■ 山中諏訪神社
(やまなかすわじんじゃ)
公式Web
山中湖村山中13
御祭神:建御名方命、豊玉姫命
旧社格:村社
授与所:境内授与所
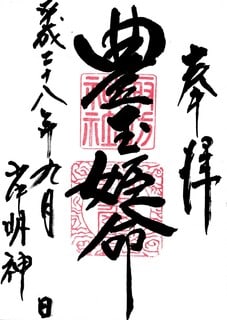
・人皇十代崇神天皇の御代七年(西暦104年)、国中に疫病が蔓延したとき、勅命をもって土人創祀されたのが創祀と伝わる。康保三年(966年)には、村人が諏訪大明神を奉ったといい、天文二十一年(1552年)には武田信玄公が北条氏との合戦に際して、戦勝祈願のため本殿を造営寄進という。
・安産子授けの守護神として広く崇敬される。
■ 山中浅間神社
(やまなかせんげんじんじゃ)
公式Web
山中湖村山中113
御祭神:木花開耶姫命、天津彦々火瓊々杵尊、大山祇命
授与所:山中諏訪神社境内授与所
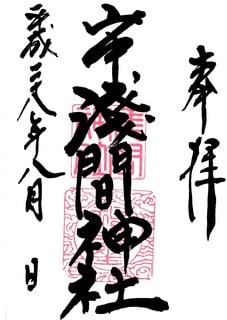
・承平元年(931年)、郷民が社殿を造営し、三柱の神を勧請して奉ったのが創祀という。
□ 平野天満宮((平野)天神社)
(ひらのてんまんぐう)
山梨県神社庁Web
山中湖村平野1877
御祭神:素盞鳴尊、菅原道真朝臣
授与所:
※御朱印未拝受
□ 石割神社
(いしわりじんじゃ)
山梨県神社庁Web
山中湖村平野1979
御祭神:天手力男命
授与所:
※御朱印未拝受
■ 海雲山 寿徳寺
(じゅとくじ)
公式Web
山中湖村平野147
臨済宗妙心寺派
御本尊:地蔵菩薩
札所:郡内三十三番観音霊場第10番
授与所:山内庫裏
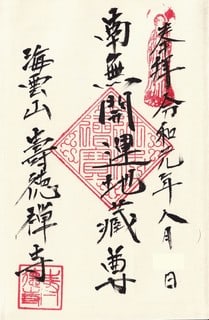

【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 郡内三十三番観音霊場の御朱印
・山中湖東岸にある臨済宗の古刹。甲斐、駿河、相模の国境に当たる要衝の地のため、武田信玄公が国境守備の祈願所に定めて栄えたという。
・狩野常信作という涅槃図、明兆作といわれる星曼陀羅など多くの文化財を蔵する。
・国際的なプリマドンナとして知られた三浦環の墓所。
■ 山中観音堂
(やまなかかんのんどう)
山中湖村平野741
臨済宗妙心寺派?
御本尊:一葉観世音菩薩
札所:郡内三十三番観音霊場第11番
授与所:海雲山 寿徳寺(平野147)
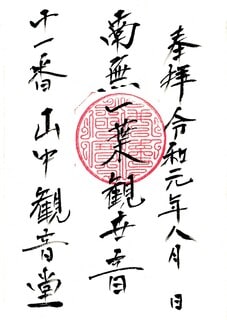
・江戸時代中期には創建されていたという郡内三十三番観音霊場の札所観音堂。
・郡内三十三番観音霊場は、現在でも御朱印をいただける札所が多い。
【関連記事】
■ 箱根の御朱印
■ 熱海温泉&湯河原温泉周辺の御朱印
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-0(導入編)
■ 甲斐百八霊場の御朱印-1
■ 甲斐百八霊場の御朱印-2
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編&全記事のリスト)
【 BGM 】
■ ヒカリノイト - 池田綾子 in Moerenuma Park
■ 空に近い週末 - 今井美樹
■ far on the water - Kalafina
先日、富士山周辺の御朱印情報をWebで当たってみたところ、浅間神社メインのものが多く、網羅的にまとめたものがあまりないので、一念発起して(こればっかし(笑))まとめてみることにしました。
富士山周辺の御朱印はおおむね拝受していますが、富士山頂の浅間大社奥宮をはじめ、未拝受の寺社もいくつかあります。
未拝受御朱印は拝受次第UPすることとし、とりあえず拝受済の御朱印情報をUPしてみます。
なお、御朱印は寺社様の状況やお考えにもとづき授与されるもので、以下の御朱印が現在も授与されているかは不明です。
---------------------------------
富士山の北側から時計まわりにリストしていきます。
富士河口湖町、富士吉田市、西桂町、忍野村、山中湖村、小山町、御殿場市、裾野市、三島市、長泉町、清水町、沼津市、富士市、富士宮市の順です。
まずは御朱印のみUPし、後日寺社の写真とコメントを入れていきます。
なお、現在、富士北麓の7社で「神玉巡拝」を催行している模様です。
詳細は→(こちら(富士吉田市観光ガイド))。
01.富士河口湖町
■ 河口浅間神社
(かわぐちあさまじんじゃ)
公式Web
富士河口湖町河口1
主祭神:浅間大神
社格等:式内社(名神大)論社
授与所:境内
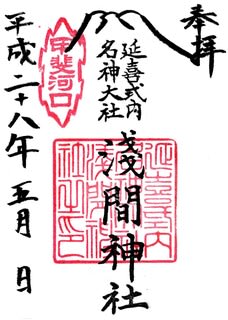
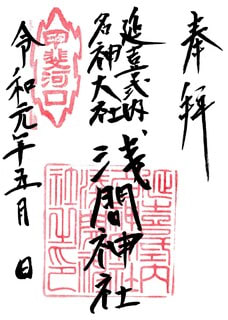
■ 母の白滝神社
(ははのしらたきじんじゃ)
やまなし観光推進機構Web
富士河口湖町河口
御祭神:栲幡千千姫命
授与所:河口浅間神社

■ 富士山遥拝所 (天空の鳥居)
(ふじさんようはいじょ)
河口湖.net
富士河口湖町河口1119-2
御祭神:浅間大神
授与所:遙拝所売店にて

□ 富士山パノラマロープウェイ山頂 うさぎ神社
御祭神:大国主命・大山祇命・木花開耶姫命
※御朱印未拝受です。
□ 浅間日月神社 (大石浅間神社)
山梨県神社庁
富士河口湖町大石268
御祭神:木花開耶姫命、天照皇大神、月読命
社格等:旧村社
授与所:境内
※御朱印未拝受です。
■ 鸕鷀嶋神社
(うのしまじんじゃ)
河口湖.net
富士河口湖町大石2584
主祭神:豊玉姫命
授与所:浅間日月神社 (大石浅間神社)
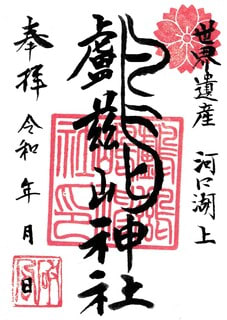
■ 霊鷲山 常在寺
(じょうざいじ)
富士河口湖町観光連盟Web
富士河口湖町小立139
法華宗本門流
札所:甲斐百八霊場第33番
授与所:山内庫裏
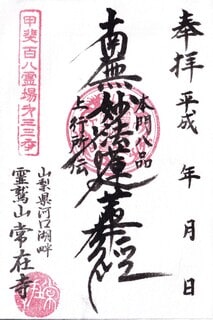
■ 蓮華山 妙法寺
(みょうほうじ)
富士河口湖町観光情報Web
富士河口湖町小立692
法華宗本門流
札所:甲斐百八霊場第32番
授与所:山内庫裏
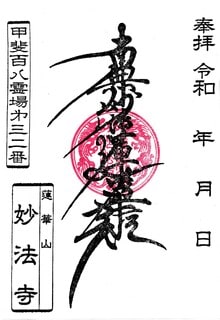
■ 冨士御室浅間神社二合目本宮(奥宮)
(ふじおむろせんげんじゃ)
公式Web
富士河口湖町勝山
主祭神:木花咲耶姫命
社格等:別表神社/旧県社
授与所:冨士御室浅間神社里宮
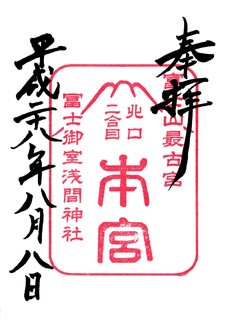
■ 冨士御室浅間神社里宮
(ふじおむろせんげんじゃ)
公式Web
富士河口湖町勝山3951
主祭神:木花咲耶姫命
社格等:別表神社/旧県社
授与所:境内

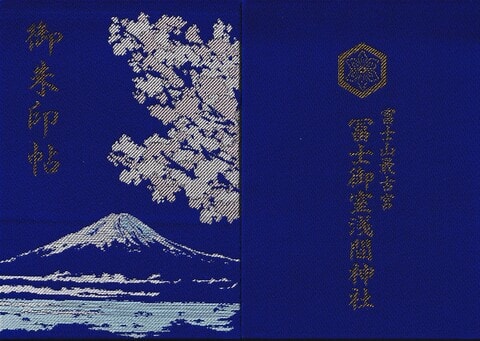
■ 長徳山 妙本寺
(みょうほんじ)
富士河口湖町勝山609
法華宗
授与所:山内庫裏
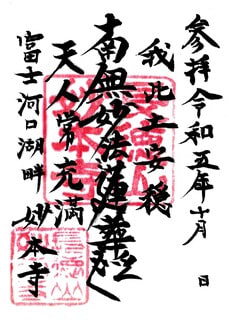
■ 広大山 圓通寺
(えんつうじ)
河口湖.net
富士河口湖町船津3932
臨済宗妙心寺派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:甲斐之国都留郡三十三ヶ所観音霊場第3番
授与所:山内庫裏
※要事前予約
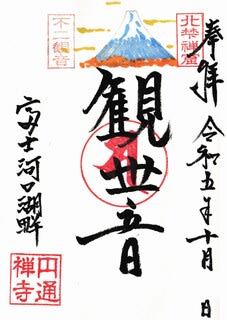
■ 筒口神社
(つつぐちじんじゃ)
山梨県神社庁Web
富士河口湖町船津5
主祭神:中筒男命
社格等:小船津組産土神、旧村社、神饌幣帛供進社
※タイミングが合えば拝受可?
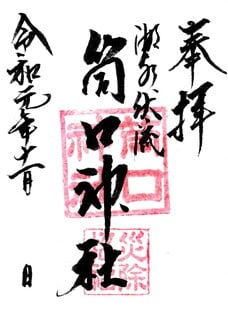
■ 八王子神社
(はちおうじじんじゃ)
山梨県神社庁Web
富士河口湖町船津4013
御祭神:素戔嗚尊、、五男三女神
社格等:大船津組産土神、旧村社、神饌幣帛供進社
※タイミングが合えば拝受可?
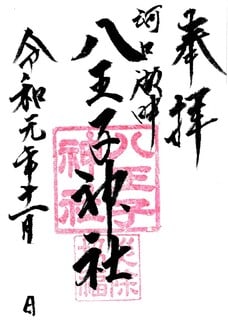
■ 無戸室浅間神社(船津胎内神社)
(むつむろせんげんじんじゃ)
山梨県神社庁Web
富士河口湖町船津6603(船津胎内樹型フィールドセンター)
主祭神:木花開耶姫命
授与所:船津胎内樹型フィールドセンター
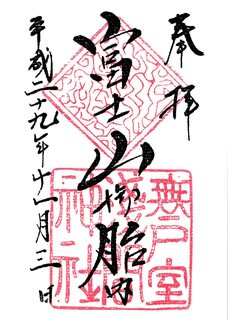
02.富士吉田市
□ 富士山天拝宮
富士吉田市上吉田(吉田口登山道八合目)
※御朱印未拝受
□ 富士山小御嶽神社
富士吉田市上吉田小御岳下5617(五合目御鎮座)
御祭神:磐長姫命、桜大刀自命、苔虫命
※御朱印未拝受
■ 新屋山神社 本宮
(あらややまじんじゃ)
公式Web
富士吉田市新屋1230
御祭神:大山祇大神、天照大御神、木花開耶姫命
授与所:境内
・金運上昇、商売繁盛の神様として広く知られる。
※ 御朱印はWebでたくさんみつかるので、そちらを参照下さい。
■ 新屋山神社 奥宮
(あらややまじんじゃ)
公式Web
富士吉田市侭5615
御祭神:大山祇大神、天照大御神、木花開耶姫命
授与所:境内
※12~4月下旬までアプローチ林道のゲート閉鎖。
・富士山麓を代表するパワスポとして知られる。
・Webには「ご縁のある人だけがたどり着ける」などのスピリチュアルな記事があるが、本宮で地図をいただけるので特段迷うことはない。ただし林道を30分弱も走るので慣れない方は要注意。
※ 御朱印はWebでたくさんみつかるので、そちらを参照下さい。
□ 冨士山小御嶽神社 里宮
(ふじさんこみたけじんじや さとみや)
富士吉田市上吉田4202
※御朱印未拝受
■ 北口本宮冨士浅間神社
(きたぐちほんぐうふじせんげんじんじゃ)
公式Web
富士吉田市上吉田5558
主祭神:木花開耶姫命、彦火瓊瓊杵命、大山祇神
社格等:別表神社、旧県社
授与所:境内授与所
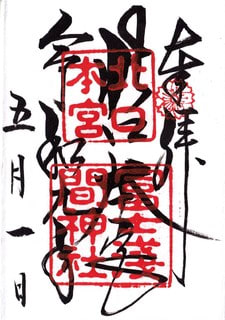

■ 諏訪神社
(すわじんじゃ)
公式Web
富士吉田市上吉田5558
(北口本宮冨士浅間神社境内社)
御祭神:建御名方神、八坂刀売神
授与所:北口本宮冨士浅間神社授与所
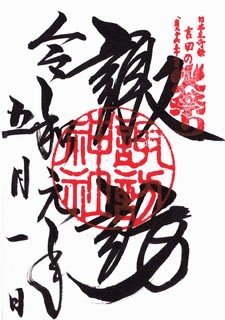
■ 大塚丘社
(おつかやましゃ)
公式Web
富士吉田市上吉田5619
(北口本宮冨士浅間神社境内社)
御祭神:日本武尊
授与所:北口本宮冨士浅間神社授与所
・景行天皇40年(西暦110年)、日本武尊ご東征の折、相模国足柄の坂本より甲斐国酒折宮へ向かわれる途中に冨士を遥拝された丘で、当社発祥の地とされる。
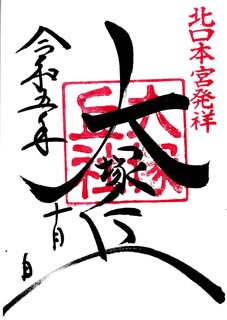
■ 吉祥山 上行寺
(じょうぎょうじ)
富士吉田市上吉田38
日蓮宗
授与所:山内庫裏
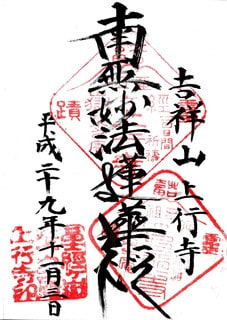
■ 吉積山 西念寺
(さいねんじ)
公式Web
富士吉田市上吉田7-7-1
時宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:甲斐百八霊場第30番
授与所:山内庫裏

・寺伝によると、養老三年(719年)行基菩薩が富士山二合目付近・錫原の地に庵を結んだのが草創という。
・富士山頂に出現の阿弥陀三尊を行基みずからが三寸八分の像に彫刻し、この尊像を御本尊として、富士道場大蓮院と号したという。
・その後、古吉田に移転ののち、永仁六年(1298年)遊行二祖他阿真教上人が諸国遊行の砌、西念寺に留錫して念仏の法門を説かれたところ多くの信者が参集し、ついに宗派を時宗に改めたという。
・遊行二祖真教上人を開基上人、その弟子の真海和尚が開山となる。
・永仁年間、武田氏の一族・一条右衛門大夫吉積が伽藍を造営寄進し、吉積山西念寺と改めたという。
・元亀三年(1572年)、旧地の村が富士山の雪代(雪解け水の災害)を避けるため村をあげて移転の折、当山も現在地に移転。
・富士山信仰とのゆかり深く、江戸時代、富士講の信者は西念寺が定めた「西念寺精進場」で身を清めた後、富士に登拝したといわれる。
■ 水上山 月江寺
(げっこうじ)
富士吉田市下吉田869
臨済宗妙心寺派
御本尊:釈迦如来
札所:甲斐百八霊場第29番
授与所:山内庫裏
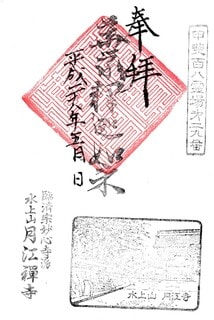
■ 小室浅間神社(下宮浅間神社)
(おむろせんげんじんじゃ/しもみやせんげんじんじゃ)
公式Web
富士吉田市下吉田5221
主祭神:木花咲耶姫命
社格等:別表神社、旧郷社
授与所:境内授与所

■ 大塔宮社・雛鶴社
公式Web
富士吉田市下吉田5221
(小室浅間神社境内社)
御祭神・大塔宮護良親王、雛鶴姫
授与所:小室浅間神社境内授与所
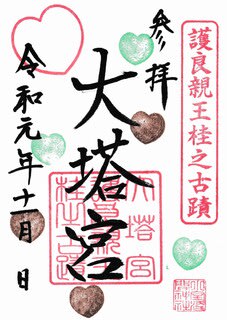
■ 寶松山 大正寺
(だいしょうじ)
公式Web
富士吉田市新倉621
浄土真宗本願寺派
授与所:山内庫裏
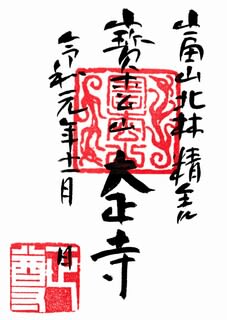
・寺伝によると文永年間(1264-1275年)、真宗祖門六老僧の源誓上人が、宗祖親鸞聖人御真筆の無碍光如来の画像を安置した草庵を当所字宮の下に草創という。
・文安年間(1444-1449年)に本願寺8世蓮如上人が当地を御巡錫ま際、藤原氏の末裔・遠山伊豆守重正が蓮如上人に帰依し法名乗欽を賜る。
・その後、草庵を念仏道場として水石山新念寺と号し、後に新福寺と改め、さらに正保元年(1644年)に現在地へ移転、寛文八年(16658年)に寺号を大正寺と改めた。
■ 大原山 如来寺
(にょらいじ)
公式Web
富士吉田市浅間1-5-6
浄土真宗本願寺派
授与所:山内庫裏

・嘉禄三年(1228年)勝沼万福寺の聖徳太子旧跡を巡排中の親鸞聖人に帰依して真宗へ改宗。
・宝徳三年(1451年)法性寺、慶長十五年(1610年)万蔵寺と寺号を改め、さらに享保二年(1718年)如来寺と改めて現在に至る。
■ 新倉山 正福寺
(しょうふくじ)
TERA MACHI(築地本願寺Web)
富士吉田市浅間1-5-38
浄土真宗本願寺派
授与所:山内庫裏
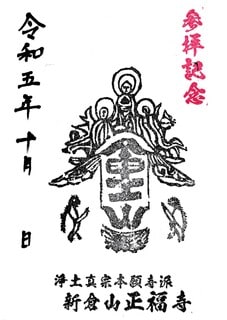
・大同二年(807年)に弘法大師が当地を訪れ、弟子道海に寺院建立を命じ、富北院(ふほくいん/真言宗)として創建。
・当時は神仏習合色を帯び、富士山五合目神域の別当を勤めたという記録も残るとの由。
・安貞二年(1228年)、9代住職道祐が親鸞聖人に邂逅して真宗に改宗し、正福寺と改めた。
■ 三國第一山 新倉富士浅間神社
(さんごくだいいちさん あらくらふじせんげんじんじゃ)
公式Web
富士吉田市浅間2-4-1
御祭神:木花咲耶姫命、大山祗命、瓊瓊杵尊
社格等:旧村社、甲斐国八代郡荒倉郷氏神
授与所:境内授与所
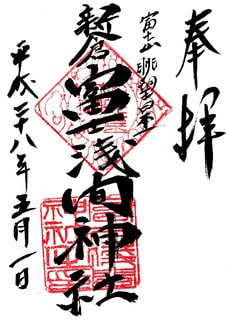
・慶雲三年(705年)、甲斐国八代郡荒倉郷へ富士北口郷の氏神として創祀。
・大同二年(807年)の富士山大噴火に際し、朝廷からの勅使が参向せられ、国土安泰富士山鎮火祭を執行、平城天皇より「三国第一山」の称号および天皇御親筆の勅額等を奉納。
・境内上部の戦没者慰霊の五重塔「忠霊塔」と新倉山浅間公園の桜と富士山が重なる絶景はSNSなどでも人気で、とくにインバウンドの来訪が多い。
■ 荒濱神社
(あらはまじんじゃ)
公式Web
富士吉田市浅間2-4-1
(新倉富士浅間神社境内社)
御祭神:機神様
授与所:新倉富士浅間神社境内授与所
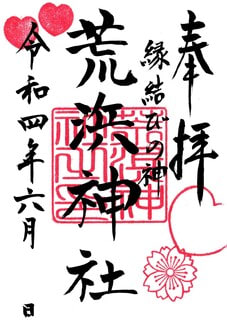
・当地はふるくから養蚕・織物の産地として栄え、養蚕・織物の神様として当社がお祀りされている。
・織物はタテとヨコの糸を交差させて織ることから、縁結びの神様としても知られている。
■ 福地八幡宮/福地八幡社
(ふじはちまんぐう/ふくちはちまんしゃ)
山梨県神社庁
富士吉田市下吉田5178
御祭神:天照皇大神、息長足姫、誉田別命、渡辺綱命
授与所:境内に案内あり

■ 北東本宮小室浅間神社(大明見浅間神社)
(おおあすみおむろせんげんじんじゃ)
山梨県神社庁Web
富士吉田市大明見2-1-1
御祭神:木花開耶姫命、誉田別命、国狭槌命、泥土煮命、上筒男命、他十三柱
授与所:境内授与所
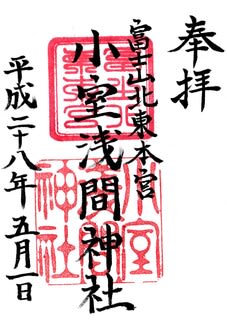
■ 護国神社
(ごこくじんじゃ)
富士吉田市大明見2-1-1
(北東本宮小室浅間神社境内社)
授与所:小室浅間神社境内授与所
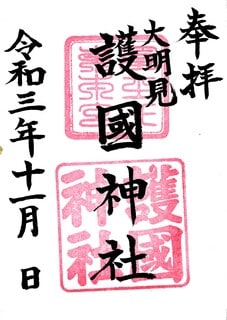
■ 明見山 慈光院
(じこういん)
公式SNS
富士吉田市大明見3-246
臨済宗妙心寺派
御本尊:
授与所:山内庫裏
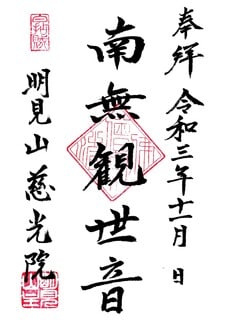
■ 不二阿祖山太神宮
(ふじあそやまだいじんぐう)
公式Web
富士吉田市大明見3537
授与所:境内授与所

■ 引接山 西方寺
(さいほうじ)
公式Web
富士吉田市小明見2058
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:甲斐百八霊場第28番、郡内三十三番観音霊場第8番
授与所:山内庫裏
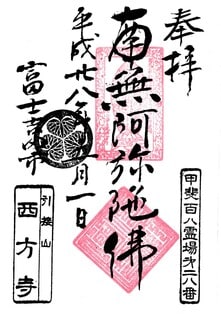
■ 小明見富士浅間神社
(こあすみふじせんげんじんじゃ)
富士吉田市向原1-21-11
主祭神:木花咲耶姫命
社格等:旧村社
授与所:忍野八海(忍草)浅間神社
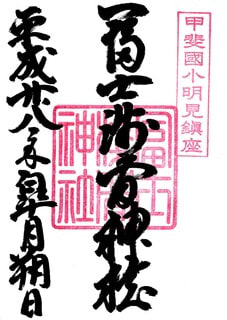
■ 三寳山 此教院 萬年寺
(まんねんじ)
富士吉田市小明見6071
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:郡内三十三番観音霊場第7番、同第14番
授与所:山内庫裏
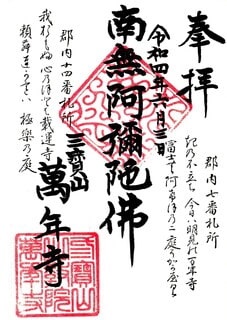
■ 山之神社
山梨県神社庁Web
富士吉田市小明見4-9-22
主祭神:大山祗命
授与所:忍野八海(忍草)浅間神社
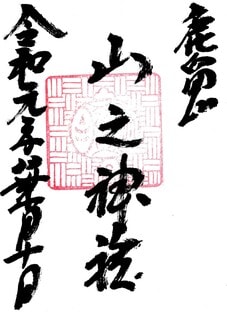
■ 明見根元神社
(あすみねのがみ)
山梨県神社庁Web
富士吉田市小明見6214
御祭神:天御柱命、罔象女命
社格等:御大沢部落の守護神
授与所:忍野八海(忍草)浅間神社
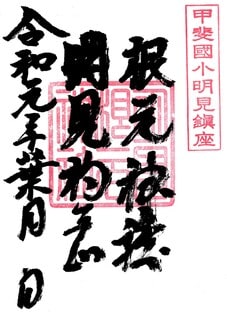
03.西桂町
■ 不二山 一乗寺
(いちじょうじ)
公式Web
西桂町小沼1997
臨済宗妙心寺派
御本尊:延命地蔵菩薩
札所:甲斐八十八ヶ所霊場12番、郡内三十三番観音霊場15番
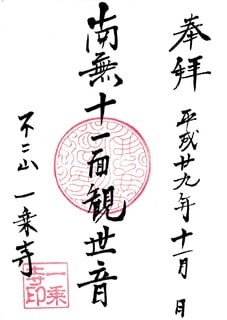
・開祖は笑山西堂和尚。開山は永享三年(1431年)本如実性景川禅師(妙心寺四派の一・龍泉派開祖)
・延暦十九年~廿三年(800-804年)の富士山延暦大噴火の際、国家安寧の祈祷と衆生供養のために建てられた永興庵が前身と伝わる。
・元禄二年(1689年)鳳谷守逸和尚により再興、永興寺から一乗寺へと改める。
・昭和39年、旧品第寺本堂を移転して書院として再建した際に、旧品第寺の十一面観世音菩薩(郡内三十三番観音霊場札所第15番札所本尊)を合祭して札所となる。
04.忍野村
■ 忍草山 大日院 東圓寺
(とうえんじ)
公式Web
忍野村忍草38
天台宗
御本尊:阿弥陀三尊
司元別当:忍草浅間神社
札所:甲斐之国都留郡三十三ヶ所観音霊場第4番、富士山北口元八湖霊場発願・結願
授与所:山内庫裏
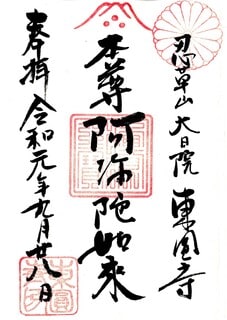
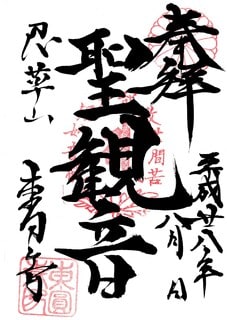
【写真 上(左)】 御本尊の御朱印(常時授与かは不明)
【写真 下(右)】 聖観世音菩薩の御朱印

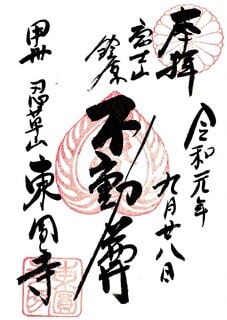
【写真 上(左)】 鈴原不動尊の御朱印
【写真 下(右)】 鈴原不動尊の御朱印
・弘仁年間(810-824年)、弘法大師が東国巡錫の折、富士山北麓で霊泉の湧出を見つけられここに一宇を建立、大日如来を安置されたのが創建と伝わり、当初は湖畑山南泉寺と号した真言宗寺院とされる。
・鎌倉時代に入って天台宗寺院となり忍草山大日院東圓寺と改めたという。
・寺伝によると、古くは富士山の鬼門を守護する蛇頭疫神社に隣接する地にあったといい、源頼朝公より広大な寺領の寄進を得たという。
・正徳元年(1711年)現在地に移転。
・古くから富士修験の道場として重要なポジションにあり、朝日浅間宮(現・忍草浅間神社)の別当を務めた。
・江戸後期には、富士講中が禊の地とした元八湖霊場(現・忍野八海)の拠点の寺として隆盛したという。
・古本尊は大日如来。現在の御本尊として阿弥陀三尊を奉じている。
・明治の神仏分離で富士山北口一合目より御遷座の不動明王像は鈴原不動尊と呼ばれて信仰を集める。
■ 蛇頭疫神社
忍野村忍草1967
御祭神:大禍津日神、八十禍津日神
授与所:忍野八海(忍草)浅間神社
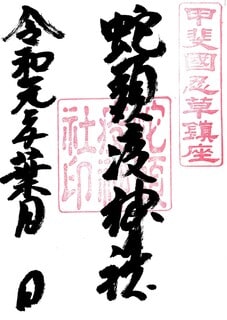
・御祭神の性格については諸説あるようだが、現地縁起書に「忍草部落の北東艮(うしとら)の方表鬼門に位置し、古来から部落の安泰をみそなはしてきた。」とあり、東圓寺公式Webに「富士山の鬼門を守護する」とあるので、当社は富士山および忍草部落の鬼門鎮護の性格がうかがわれる。
■ (忍野八海)浅間神社/忍草浅間神社
(おしのはっかいせんげんじんじゃ/しぼくさせんげんじんじゃ)
公式SNS
忍野村忍草456
御祭神:木花開耶姫命、天津日高日子番能邇々藝能尊、大山祇命
旧社格:村社
元別当:忍草山 大日院 東圓寺(忍草)
授与所:境内授与所

・大同二年(807年)創建、建久四年(1193年)源頼朝公の富士巻狩りの際に広大な御朱地を賜り、和田義盛と畠山重忠が随神門と金剛力士像(運慶作)を建立したという。
・広い地域の神社を官掌され、複数の御朱印を授与されている。
[ 富士山北口元八湖霊場 ]
世界遺産富士山の構成資産の一部として認定された忍野八海の8つの池それぞれを守護する八大竜王を巡拝する霊場。発願、結願ともに忍草の東圓寺。
八のつく日(8・18・28日)限定で御朱印が授与されている。→ 情報
■ 忍草山 大日院 東圓寺
(とうえんじ)
忍野村忍草38
札所:富士山北口元八湖霊場発願・結願
札所本尊:八大竜王(守護)
授与所:山内庫裏

■ 忍野八海一番出口池守護 灘陀竜王
(でぐちいけしゅご なんだりゅうおう)
忍野村忍草3483-2
札所:富士山北口元八湖霊場第1番
授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)
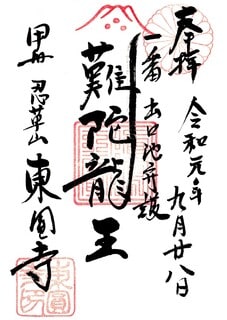
・やや離れて最も面積が広い池で水深0.5メートル。
・別名「精進池」とも呼ばれ、富士講信者はこの池の湧水で登山前に身を清めたという。
■ 忍野八海二番お釜池守護 跋難陀竜王
(おかまいけしゅご うぱなんだりゅうおう)
忍野村忍草111-2
札所:富士山北口元八湖霊場第2番
授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)
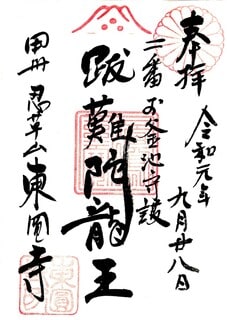
・最も小さな池で 水深:4メートル。
■ 忍野八海三番底抜池守護 娑加羅竜王
(そこなしいけしゅご しゃがらりゅうおう)
忍野村忍草272-2
札所:富士山北口元八湖霊場第3番
授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)
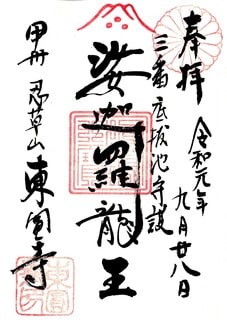
・樹林が生い茂る静かな池で水深1.5メートル。「はんの木林資料館」入館料300円が必要。
■ 忍野八海四番銚子池守護 和修吉竜王
(ちょうしいけしゅご ぶぁ-すきりゅうおう)
忍野村忍草266-3
札所:富士山北口元八湖霊場第4番
授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)
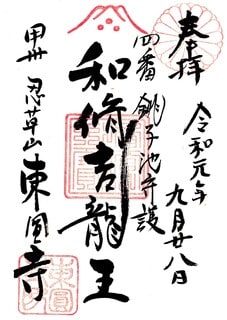
・銚子の形から名付けられたといい水深4メートル。縁結びの池と伝わる。
■ 忍野八海五番湧池守護 徳叉迦竜王
(わくいけしゅご とくしゃかりゅうおう)
忍野村忍草361-2
札所:富士山北口元八湖霊場第5番
授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)
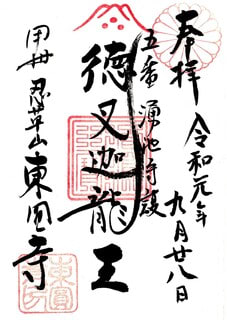
・八海一の湧水量で水深4メートル。中心部にあり賑わう。
■ 忍野八海六番濁池守護 阿那婆達多竜王
(にごりいけしゅご あなぶぁたぶたりゅうおう)
忍野村忍草269-2
札所:富士山北口元八湖霊場第6番
授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)
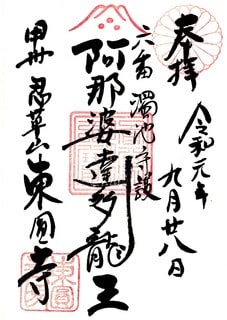
・湧池に隣接し、阿原川と合流して水深0.5メートル。濁ってはいない。
■ 忍野八海七番鏡池守護 摩那斯竜王
(かがみいけしゅご まなすう゛ぃんりゅうおう)
忍野村忍草339-2
札所:富士山北口元八湖霊場第7番
授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)

・見事な逆さ富士で知られ水深0.3メートル。
■ 忍野八海八番菖蒲池守護 優鉢羅竜王
(しょうぶいけしゅご うっぱらかりゅうおう)
忍野村忍草444-2
札所:富士山北口元八湖霊場第8番
授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)
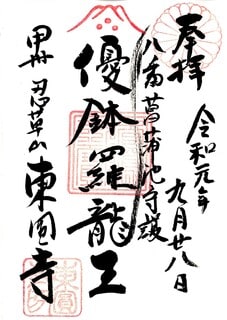
・菖蒲が繁る水深0.5メートルの池。奥は八海菖蒲池公園。
■ 出口稲荷社
(でぐちいなりしゃ)
忍野村忍草3483-2
御祭神:
授与所:忍野八海(忍草)浅間神社

・忍野八海一番出口池のほとりの小高い場所に御鎮座の稲荷社。
・池のほとりに3匹のキツネが棲み、いたずらをしては村人を困らせていた。『キツネを神として祀れば災いは無くなる』とのお告げを受けた村人たちは、大正14年お告げ通りに「出口稲荷大明神」を建立し祀ったところ、キツネの被害はなくなったという。
■ 穂見神社
(ほみじんじゃ)
忍野村忍草2206
御祭神:保食神
授与所:忍野八海(忍草)浅間神社
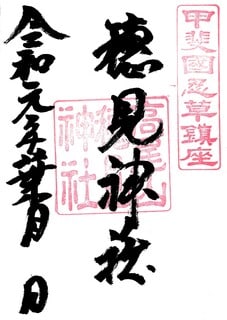
・金融通の守護神として崇敬される。
■ 醫王山 承天寺
(じょうてんじ)
公式Web
忍野村内野192
臨済宗妙心寺派
御本尊:薬師如来
札所:甲斐百八霊場第31番、郡内三十三番観音霊場第9番
授与所:山内庫裏
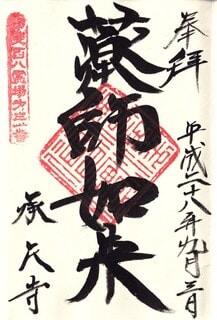
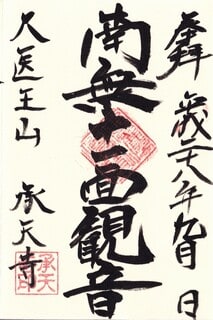
【写真 上(左)】 甲斐百八霊場の御朱印
【写真 下(右)】 郡内三十三番観音霊場の御朱印
・寺記によると壽永三年(1184年)、真言宗寺院、長寿山上天寺として現在より山寄りの地に創建。
・開基は鎌倉の有力御家人・畠山重忠公。建久四年(1193年)に鎌倉往還の普請奉行として忍野に来た重忠公がこの寺を定宿とし、時の住職に帰依して堂宇を整え開基となったという。
・御本尊薬師如来像、脇立日光大士十二神将像はいずれも運慶作と伝わる。
・江戸時代の再建時に臨済宗に改め山号を醫王山とし、寺号を承天寺としたという。
・甲斐百八霊場、郡内三十三番観音霊場のふたつの霊場の札所となっており、郡内三十三番観音霊場の札所本尊は十一面観世音菩薩。
■ 内野八幡神社(八幡社)
(うちのはちまんじんじゃ)
山梨県神社庁Web
忍野村内野3
御祭神:誉田別尊
授与所:忍野八海(忍草)浅間神社
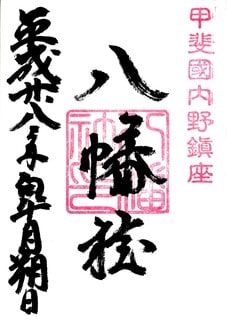
・幕末までは神仏混淆で法華経の題目講が行われていたという。
・神仏分離令により神社と視点から存続するが、村資料によると9月15日の例祭日の前日14日の夜には現在でも法華経信者が集まり、唱題が行われるという。
・例祭では相撲が奉納され、境内は賑わいをみせる。
■ (内野)浅間神社
(うちのせんげんじんじゃ)
山梨県神社庁Web
忍野村内野1
御祭神:木花開耶姫命、天児屋根命、太玉命
旧社格:村社、神饌幣帛供進指定社
授与所:忍野八海(忍草)浅間神社
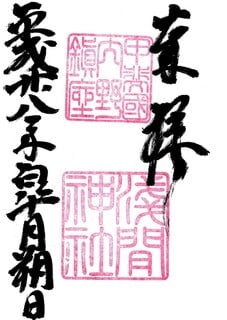
・山梨県神社庁資料によると、南北朝後の応永年間(1394-1428年)に尹良親王が南朝の四皇を奉祀して四皇三社浅間大神と称した。永享六年(1434年)尹良親王の従兄・與良親王の孫・梅若王が神主となるが3年で亡くなり、その霊を祀り富士浅間神社と称したという。山梨県神社庁資料には「其の霊を産土神に祀る足利氏に憚り富士浅間神社と稱す。」とある。
・本殿には貞治二年(1363年)の棟札が現存し、村内最古の建物とされる。
■ (内野)天狗社
(てんぐしゃ)
山梨県神社庁Web
忍野村内野381-1
御祭神:武甕槌命
授与所:忍野八海(忍草)浅間神社
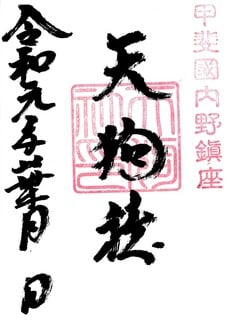
・創祀不詳。御神体は三百年以上前に稲荷坂の脇から掘り出されたという。
・内野地区は日清日露戦争で多くの兵士を送り出したが一人の戦死者も無かったことから天狗社のご加護と崇められている。
05.山中湖村
■ 山中諏訪神社
(やまなかすわじんじゃ)
公式Web
山中湖村山中13
御祭神:建御名方命、豊玉姫命
旧社格:村社
授与所:境内授与所
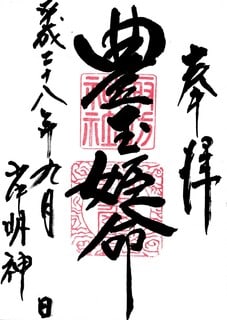
・人皇十代崇神天皇の御代七年(西暦104年)、国中に疫病が蔓延したとき、勅命をもって土人創祀されたのが創祀と伝わる。康保三年(966年)には、村人が諏訪大明神を奉ったといい、天文二十一年(1552年)には武田信玄公が北条氏との合戦に際して、戦勝祈願のため本殿を造営寄進という。
・安産子授けの守護神として広く崇敬される。
■ 山中浅間神社
(やまなかせんげんじんじゃ)
公式Web
山中湖村山中113
御祭神:木花開耶姫命、天津彦々火瓊々杵尊、大山祇命
授与所:山中諏訪神社境内授与所
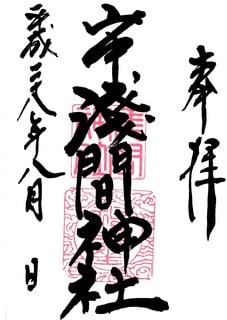
・承平元年(931年)、郷民が社殿を造営し、三柱の神を勧請して奉ったのが創祀という。
□ 平野天満宮((平野)天神社)
(ひらのてんまんぐう)
山梨県神社庁Web
山中湖村平野1877
御祭神:素盞鳴尊、菅原道真朝臣
授与所:
※御朱印未拝受
□ 石割神社
(いしわりじんじゃ)
山梨県神社庁Web
山中湖村平野1979
御祭神:天手力男命
授与所:
※御朱印未拝受
■ 海雲山 寿徳寺
(じゅとくじ)
公式Web
山中湖村平野147
臨済宗妙心寺派
御本尊:地蔵菩薩
札所:郡内三十三番観音霊場第10番
授与所:山内庫裏
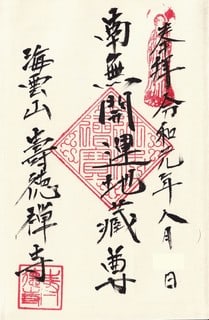

【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 郡内三十三番観音霊場の御朱印
・山中湖東岸にある臨済宗の古刹。甲斐、駿河、相模の国境に当たる要衝の地のため、武田信玄公が国境守備の祈願所に定めて栄えたという。
・狩野常信作という涅槃図、明兆作といわれる星曼陀羅など多くの文化財を蔵する。
・国際的なプリマドンナとして知られた三浦環の墓所。
■ 山中観音堂
(やまなかかんのんどう)
山中湖村平野741
臨済宗妙心寺派?
御本尊:一葉観世音菩薩
札所:郡内三十三番観音霊場第11番
授与所:海雲山 寿徳寺(平野147)
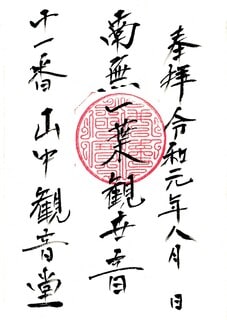
・江戸時代中期には創建されていたという郡内三十三番観音霊場の札所観音堂。
・郡内三十三番観音霊場は、現在でも御朱印をいただける札所が多い。
【関連記事】
■ 箱根の御朱印
■ 熱海温泉&湯河原温泉周辺の御朱印
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-0(導入編)
■ 甲斐百八霊場の御朱印-1
■ 甲斐百八霊場の御朱印-2
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編&全記事のリスト)
【 BGM 】
■ ヒカリノイト - 池田綾子 in Moerenuma Park
■ 空に近い週末 - 今井美樹
■ far on the water - Kalafina
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 埼玉県秩父市・横瀬町・小鹿野町・皆野町の御朱印-1




埼玉県・秩父地方は関東有数の御朱印エリアです。
秩父を代表する霊場、秩父札所三十四観音霊場(秩父札所)は文暦元年(1234年)開創説がある歴史ある霊場で、第32番札所の法性寺に残る長享二年(1488年)の札所番付(長享番付)から、すでに室町時代後期には観音霊場として定着していたとみられています。
秩父札所は当初三十三所(33箇寺)で開創され、天文五年(1536年)頃に第2番真福寺(大棚観音)が加わって34箇寺となりました。
西国三十三所巡礼、坂東三十三観音霊場、秩父札所三十四観音霊場の3つの観音霊場の百の札所を巡ることを「日本百観音巡礼(巡拝)」といいます。
後に「日本百観音」の写し霊場が各地で開創されますが、西国写、板東写はそれぞれ33箇所、秩父写は34箇所の計100箇所の構成となっています。
西国三十三所巡礼は関西の広域、坂東三十三観音霊場も関東の広域を巡る霊場ですが、秩父札所は秩父地方の限られたエリアを巡ります。
よって、秩父には札所寺院が多く存在します。
秩父札所のほかにも秩父十三仏霊場(とみまいり)、秩父七福神があり、それぞれ多彩な尊格の御朱印を授与されています。
霊山に囲まれる秩父はふるくからのパワスポで、三峯神社、両神神社、秩父神社、椋神社などの名社が御鎮座されます。
いずれも御朱印を授与され、秩父市中町の今宮神社、秩父市黒谷の聖神社、小鹿野町の小鹿神社の御朱印も人気です。
このように複数の霊場札所、名社を擁する秩父は、さながら御朱印王国の様相を呈しています。
秩父札所三十四観音霊場(秩父札所)は午歳(うまどし)の総開帳で、次回は再来年の令和8年(2026年)3月18日~11月30日の予定です。

このようなタイミングでもあるので、一念発起して(笑)、これまでいただいた御朱印をすべてご紹介します。
なお、秩父市・横瀬町・小鹿野町・皆野町の4市町はおおむね秩父盆地に位置し、それぞれ秩父札所の札所寺院が立地するので、ひとつの記事にまとめます。
適宜『古寺巡礼 秩父三十四カ所めぐり』(JTBパブリッシング刊)を参照しています。引用時には『古寺巡礼』と記します。
【エリア概要】 (秩父市・横瀬町・小鹿野町・皆野町を併せてまとめています。)
「ちちぶ」は延喜年間(901-923年)成立とされる『旧事本紀』の『国造本紀』に「知知夫国造、瑞籬朝の御世に八意思兼命の十世の孫、知知夫彦命国造に定め賜ふ。」とあり、この時代から国造が置かれていたことがわかります。
また、平安時代中期の延喜式には式内社として秩父神社、椋神社が収録されています。
中世の秩父は武蔵七党の丹党中村氏の勢力下にあったとみられ、11世紀初頭からは桓武平氏良文流の平将恒公が入って、秩父氏の本拠地ともなっています。
秩父氏初代・将恒公は、武蔵介・平忠頼公と平将門公の娘・春姫の子で、秩父には将門公ゆかりの地がいくつかあります。
秩父氏は関東屈指の名族で、「武蔵国留守所総検校職」として武蔵国内の武士を統率・動員する権限をもち、「坂東八平氏」のひとつに数えられます。
秩父氏からは畠山氏、河越氏、江戸氏などの秩父党を輩出。
治承四年(1180年)の源頼朝公の挙兵時、秩父党は当初平家方につき、衣笠城合戦で三浦義明を討ち取っています。
しかし葛西清重の仲裁により頼朝公に服属し、以降は鎌倉幕府の開創に尽力しました。
小山田氏、稲毛氏、榛谷氏、渋谷氏、高山氏などの鎌倉御家人は秩父党で、豊島氏、葛西氏も秩父党の流れとされます。
鎌倉幕府内の政争のなか河越氏、畠山氏は勢いを失い、室町時代には挽回したものの、正平二十三年(1368年)の武蔵平一揆で敗れて地盤を失いました。
後北条氏の時代には鉢形北条氏の支配下に入りましたが、隣国甲斐からしばしば武田氏の侵攻を受けたことは、多くの伝承が語っています。
後北条氏没落ののちは徳川家康公の配下に入り、後北条氏の旧臣は秩父地方に隠棲、あるいは地主として存続したともいいます。
江戸期は忍藩秩父領となり、忍藩主の統治下にありました。
なお、秩父党の江戸氏は武蔵平一揆後も勢力を保ち、世田谷城主吉良氏の家臣から徳川家康公の家臣に転じて喜多見藩藩主となりましたが、元禄二年(1689年)に改易され大名の地位を失いました。
秩父に(江戸期の)城下町はないため、大名家や重臣の菩提寺や祈願寺は多くなく、寺院は秩父札所がメインだったようです。
秩父の寺院は素朴で親しみやすい雰囲気がありますが、このような歴史によって育まれたものかもしれません。
秩父札所は江戸時代に入るといよいよ隆盛となりました。
江戸から秩父まで関所がなかったこともあり、江戸の町人や商家の娘達は観音巡礼の名のもとにこぞって秩父を訪れたといいます。
秩父札所の江戸出開帳の功績も大きいとみられます。
ことに、明和元年(1764年)、音羽の護国寺で催された秩父札所惣出開帳は、将軍家治公の代参のほか、諸大名、大奥女中、旗本などの参詣を集め大いに賑わったといいます。
秩父は養蚕が盛んで、郡内各地に「秩父絹」や「鬼秩父」(秩父銘仙の前身)の市が立ちました。
大宮郷の妙見宮(秩父神社)は最大の市で、現在「秩父夜祭」として知られている付祭りも催されて賑わいをみせました。
大正~昭和にかけて秩父鉄道が開通、秩父セメントが設立され、秩父はセメント生産の要地としてさらに発展しました。
このように、山間にありながら、江戸をはじめ各地からの巡拝者や交易者を迎え、各地の最新情報が得られたことが、秩父独特の文化を育てたという見方があります。
---------------------------------
江戸から秩父へのルートはつぎの3つがありました。
1.正丸峠越えの「吾野通り」
2.粥仁田峠越えの「河越通り」
3.熊谷から荒川沿いに入る「熊ヶ谷通り」(秩父往還)
現在の東京から秩父方面へのアプローチは通常、関越道「花園」IC(深谷市)~皆野寄居有料道路経由となります。(秩父往還)
このルートは多摩エリアや埼玉中西部からは遠回りとなるので、国道299号から正丸峠を越えて横瀬に入るルートもあります。(旧・「吾野通り」)
ただし、この国道はほとんど昭和の国道で、カーブが多く車の流れも速いので、運転に不慣れな方は「花園」ICルートをおすすめします。
【秩父エリアと札所】
なんといっても秩父札所三十四観音霊場(秩父札所)が代表格。
上記のとおり「日本百観音」を構成するとともに、武蔵野三十三観音霊場、狭山三十三観音霊場と併せて「武蔵の国百観音」も構成しています。
正丸峠を挟んで秩父側が秩父札所、飯能側が武蔵野三十三観音霊場の領域となります。
秩父札所は曹洞宗寺院が多いですが、御本尊は観世音菩薩の例が多く、御本尊の御朱印は不授与の例が多いです。
秩父札所に曹洞宗寺院が多いことは、『武蔵国秩父札所三十四観音霊場の形成にみる中世後期禅宗の地方展開』(小野澤 眞氏/PDF)に詳しいです。
同書によると、当初の秩父札所の堂宇の多くは修験の影響を受けた小堂や草庵だったとの由。
秩父では武甲山の男神と秩父氏の妙見信仰(女神)が混淆した独自の修験が発展したといいます。
秩父の妙見信仰は、上野国花園の七星山息災寺の「羊妙見菩薩」由来とされます。
息災寺は天台宗とみられ、秩父の修験寺もおおむね天台宗系の本山修験ないし天台宗寺門派の配下にあったようです。
(七星山息災寺については→こちら(■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1.6.三鈷山 吉祥院 妙見寺)をご覧ください。)
なお、『千葉市地域情報デジタルアーカイブ』では、「羊妙見菩薩」ゆかりの羊一族は和銅元年(708年)、秩父郡より和銅を献上した一族と推測しています。
妙見信仰といえば千葉氏が有名ですが、秩父もまた妙見信仰が盛んで、とくに秩父神社は「秩父妙見宮」と呼ばれて当地の妙見信仰の中心でした。
このような天台宗地盤の秩父で曹洞宗が勢力を伸ばした理由については、いくつかの説がみられます。
秩父の禅宗が鎌倉由来とする説がいくつかあります。
横瀬の西善寺のWebには、これを裏付ける記述があります。
鎌倉圓覚寺の白涯寛正禅師が熊谷直俊公の請に応じ、応安元年(1373年)圓福寺(幻住派~白涯禅)を開山、圓福寺3世の竹印昌岩禅師が長興寺(秩父札所第5番)を開山し、続いて寛正元年(1460年)に西善(禅)寺(秩父札所第8番)を開山といいます。
この系譜からすると、秩父には鎌倉圓覚寺の法統が入っていることになります。
しかし鎌倉は臨済禅の牙城で、曹洞宗寺院はほとんどなく、鎌倉をもととするには無理があります。
秩父曹洞宗の発祥として知られる廣見寺は、奥州水沢の正法寺2祖月泉良印禅師の高弟天光良産大和尚が明徳二年(1391年)開創といいます。
正法寺は奥州・水沢の妙見山 黒石寺の奥の院に建てられた奥州初の曹洞宗寺院とされます。
また、黒石寺は天台宗で、もとは修験寺という情報(Wikipedia)があります。
つまり、正法寺は天台修験に曹洞禅が入って成立発展した寺院とみることができます。
曹洞宗寺院の御本尊は釈迦牟尼佛が多いですが、正法寺の御本尊は如意輪観世音菩薩です。
廣見寺の末寺には秩父札所の寺院がいくつかあるので、秩父の曹洞宗はあるいは奥州・正法寺系とみることができるかも。
秩父札所の寺院のいくつかが修験系の発祥であること、曹洞宗寺院でありながら観世音菩薩を御本尊とすることなどは、奥州・正法寺の系譜とみることで説明がつくような感じもします。
脇道がながくなりました。
秩父エリアを巡拝範囲とする秩父十三仏霊場は秩父札所と重複がなく、秩父の御朱印のバリェーションを高めています。
秩父七福神も他霊場との重複が少なくなっています。
新しいところでは横瀬町で「横瀬まいり」が設定され、参画の8箇寺できれいな切り絵御朱印が授与されています。

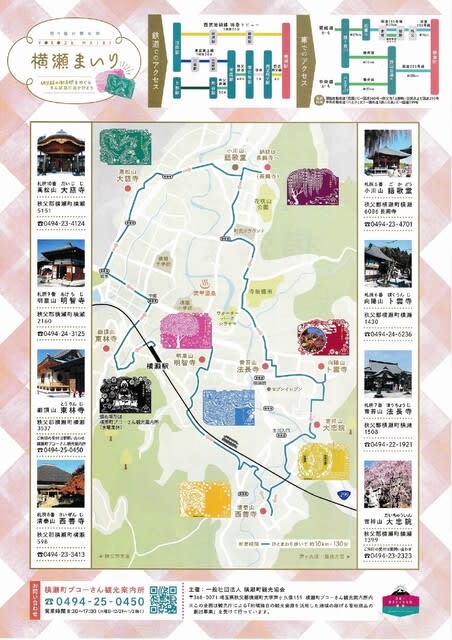
なお、秩父エリアの弘法大師霊場は確認できておりません。
その他、関東八十八箇所、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)、関東百八地蔵尊霊場、東国花の寺百ヶ寺霊場、七観音霊場など広域霊場の札所が立地しますが数は多くありません。
秩父の霊場札所はいずれも御朱印授与率が高く、ご不在出直しもほとんどありません。
このあたりは、関東有数の札所文化圏の矜持が感じられます。
----------------------------------------
それでは、秩父札所の札番にしたがって横瀬町、秩父市、小鹿野町、皆野町の順に、おおむね南東から北西に向かう方向でご紹介していきます。
件数が多いので、連載形式でじっくりといきます。
なお、秩父は熊谷と並んで日本有数の酷暑の地です。
夏場の巡拝は、どうぞ充分にお気をつけくださいませ。
---------------------------------
1.横瀬町
■ 武甲山御嶽神社(里宮)
横瀬町大字横瀬880-2
御祭神:日本武尊、男大述尊、広国押武金日天皇
旧社格:
授与所:境内のご神職宅


・武甲山山頂に御鎮座の武甲山御嶽神社(奥宮)の里宮として、明治初期にご遷座された里宮。
・秩父は日本武尊とのゆかりふかく、三峯神社は日本武尊東征の折、伊弉諾尊、伊弉册尊をお祀りしたのが草祀といい、秩父の名山・武甲山にも日本武尊を主祭神とする当社が祀られている。
・御朱印は境内のご神職宅にて拝受しましたが、ご不在の場合もあるようです。
〔拝受御朱印〕
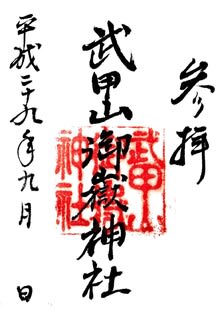
御朱印揮毫:武甲山御嶽神社 書置(筆書)
■ 清泰山 西善寺
横瀬町横瀬598
公式Web
臨済宗南禅寺派
御本尊:阿弥陀三尊(公式Webより)
秩父札所の札所本尊:十一面観世音菩薩
旧・秩父札所:第31番西禅寺(十一面観世音菩薩)
札所:秩父札所三十四観音霊場第8番、東国花の寺百ヶ寺霊場埼玉第1番、横瀬まいり


・秩父札所第8番で、もっとも東寄りの札所。
・寺伝によると、鎌倉時代初期、旅の僧侶が武甲山の麓にお堂(根岸堂)を建立したのが草創といい、当初は秩父札所の第31番札所だったと伝わる。
・「長享番付」には「三一番 西禅寺 十一面」とあるが、当山が別当として管理していた「根岸堂」(永正十二年(1515年)山内に移築)がもともとの秩父札所の堂宇という説もみられる。
・恵心僧都作と伝わる十一面観世音菩薩は、「持山観音」とも呼ばれる坐像。
・『古寺巡礼』によると、当山は当初浄土宗、または天台宗と考えられ西方浄土の阿弥陀三尊を祀ることから「安楽往生の寺」とも呼ばれているとの由。
・本堂前の樹齢約600年の巨大なコミネカエデは秩父を代表する銘木として知られ、東国花の寺百ヶ寺霊場の札所にもなっている。
・御朱印は本堂向かって右手の庫裏か、山門左手の授与所で拝受できます。
・秩父札所の御朱印のほか、東国花の寺百ヶ寺霊場、横瀬まいりの切り絵御朱印も拝受できます。
・東国花の寺百ヶ寺の御寶印は御本尊の阿弥陀三尊、横瀬まいりの切り絵御朱印には「根岸堂」「本師釋迦三尊」の揮毫があります。
〔拝受御朱印〕
1.秩父札所第8番の御朱印
十一面観世音菩薩
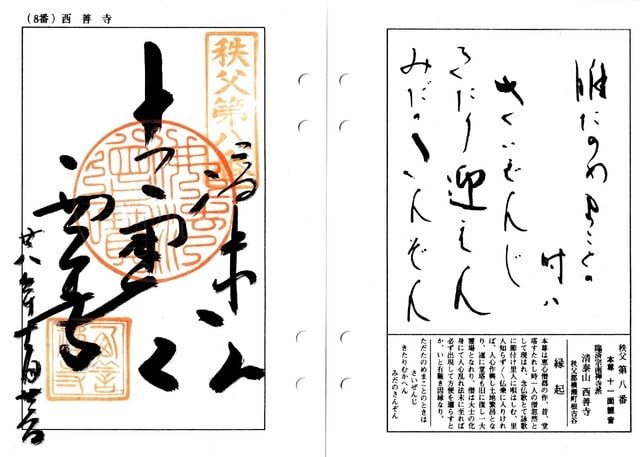
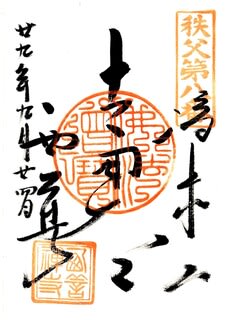
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
2.東国花の寺百ヶ寺霊場埼玉第1番の御朱印
阿弥陀三尊
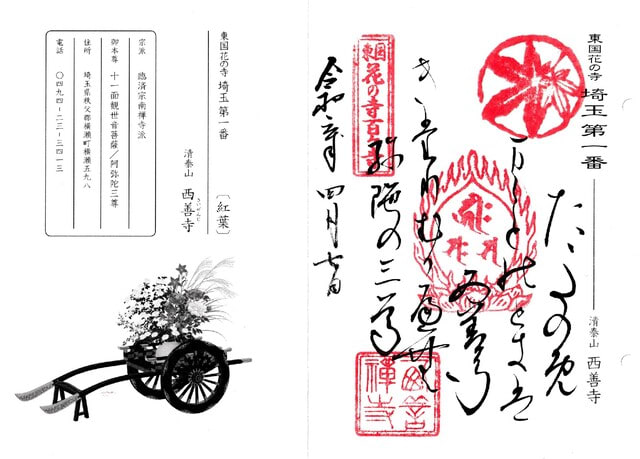
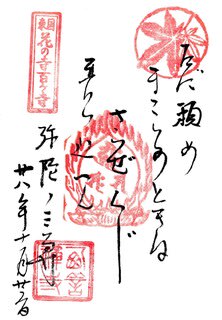
【写真 上(左)】 専用用紙
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
3.横瀬まいりの切り絵御朱印
釋迦三尊
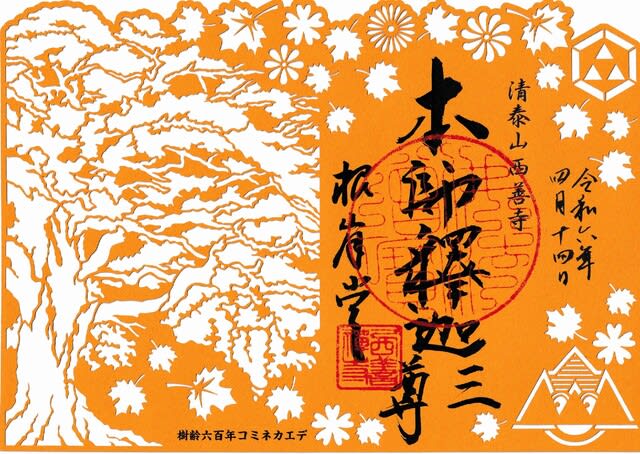
■ 吉祥山 大忠院
横瀬町横瀬1399
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所:横瀬まいり


・『新編武蔵風土記稿』によると、善庵良置禅師(天正元年(1573年)寂)の開山と伝わる曹洞宗寺院で入間郡越生郷龍穏寺末。
・御本尊は正観世音菩薩座像で、裏山の愛宕社から遷られたという勝軍地蔵菩薩立像は江戸時代中期頃の鋳造仏の美作とされ、横瀬町の有形文化財に指定されている。
・愛宕権現-勝軍地蔵菩薩という尊格から火伏せの霊験あらたかとみられ、切り絵御朱印にも「火伏せ佛」の揮毫がある。
・切り絵御朱印は在庫切れということで、卜雲寺にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.横瀬まいりの切り絵御朱印
勝軍地蔵菩薩

2.汎用御朱印張の御朱印
勝軍地蔵菩薩
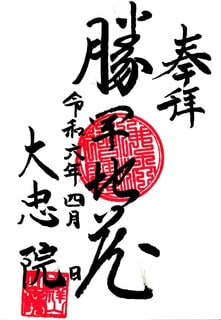
■ 向陽山 卜雲寺
横瀬町横瀬1430
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩(荻の堂観音)
秩父札所の札所本尊:聖観世音菩薩
旧・秩父札所:旧・秩父札所:第30番荻(野)堂
札所:秩父札所三十四観音霊場第6番


・江戸時代初期、嶋田與左衛門により撫外春道を開山に創建と伝わる曹洞宗寺院で、寺号は與左衛門の法号“卜雲源心庵主”に由来という。入間郡越生郷龍穏寺末。
・武甲山山頂の蔵王権現社に行基作と伝わる聖観世音菩薩を祀ったのが草創で、大蛇が住む”とが池”をこの観音さまに祈願して退散させたことから、”とが池”を埋め立てて荻(野)堂を建て、武甲山頂から観音さまをお遷しし、さらに宝暦十年(1760年)現在地に移転したという。
・山門よこの「ねがい地蔵」は、元文二年(1737年)、疫病退散、病気平癒を願い建立された尊像で、病気平癒だけでなく、子授け、入試合格などにも霊験あらたかとして信仰を集める。
・山内には弘法大師の御作というも伝わる薬師如来、鎮守社とみられる卜雲稲荷、寺宝として行基菩薩ゆかりの「山姥の歯」も納められている。
・武甲山に近い高台にあって、山内からの武甲山の眺望は圧巻。
・御朱印は本堂向かって右手の授与所にて拝受できます。
〔拝受御朱印〕
1.秩父札所第6番の御朱印
聖円通閣(聖観世音菩薩)

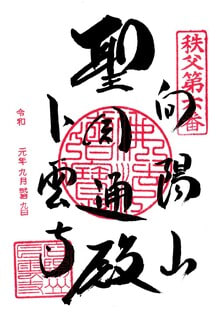
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
2.横瀬まいりの切り絵御朱印
聖円通閣(聖観世音菩薩)
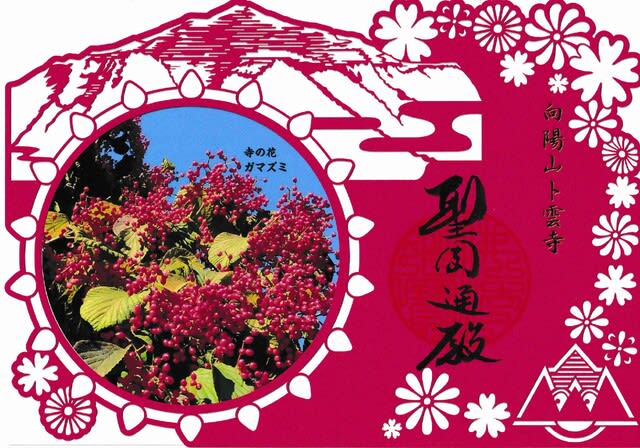
■ 青苔山 法長寺
横瀬町横瀬1508
曹洞宗
御本尊:釋迦牟尼佛
秩父札所の札所本尊:十一面観世音菩薩
旧・秩父札所:第32番牛伏
札所:秩父札所三十四観音霊場第7番、横瀬まいり


・青苔院傑岑常英が開基となり、凉室清和和尚(慶長十一年(1606年)寂)が開山したという禅刹。
・秩父札所として行基菩薩の御作という十一面観世音菩薩を安する根古屋の牛伏堂があり、別当を法長寺が勤めていたところ、天明二年(1782年)現在地(法長寺)に移転という。
・本堂は江戸の科学者・平賀源内の原図をもとに設計されたといい、秩父札所最大規模の伽藍といわれる。
・堂内正面の欄間には四国八十八箇所第86番志度寺の縁起、海女の珠取り物語の彫刻がある。
・平賀源内は讃岐・志度の出身で、その縁から海女の珠取り図の彫刻が置かれたのかもしれない。
・御朱印は本堂対面の授与所にて拝受できます。
〔拝受御朱印〕
1.秩父札所第7番の御朱印
大光普照殿(十一面観世音菩薩)
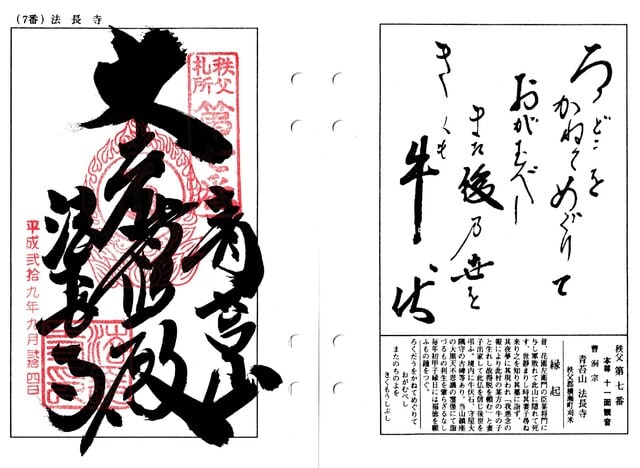
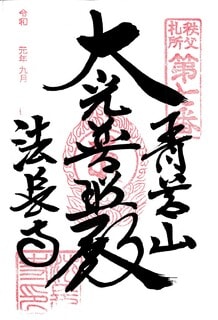
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
2.横瀬まいりの切り絵御朱印
欄間彫刻(海女の珠取り伝説)
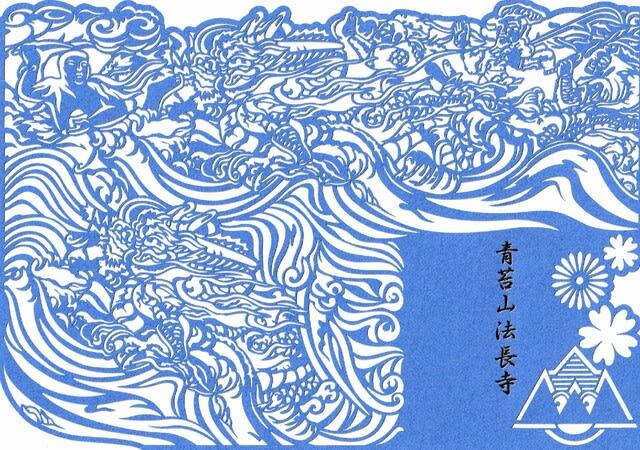
■ 明星山 明智寺
横瀬町横瀬2160
臨済宗南禅寺派
御本尊:如意輪観世音菩薩
秩父札所の札所本尊:如意輪観世音菩薩
旧・秩父札所:第29番明地
札所:秩父札所三十四観音霊場第9番、横瀬まいり


・建久二年(1191年)明智禅師の開創と伝わる古刹。
・御本尊は長七寸二分の如意輪観世音菩薩木坐像で惠心僧都の御作という。
・一条天皇(980-1011年)の中宮・藤原道長の娘の彰子が難産の折、(この?)仏像を祀り祈願すると玉のような男子を授かった。
その後すぐにこの仏像はお姿を隠され、人々が探しているときに明星があたりを照らし(仏像が御座する)観音堂に入ってこの尊像を得たという逸話にちなみ明星山と号したとも。
・安産子育ての観音さまとして知られ、1月16日、8月16日の縁日には女性の参詣者で賑わいを見せたという。
・参拝した女人が苦悩から救われるために願いを書いて納めたという文塚が残る。
・観音堂は札所第5番語歌堂と同時代同形式だったが明治16年焼失。平成2年に現在の観音堂(六角堂)が再建される。
・御朱印は観音堂(六角堂)向かって左手の授与所にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.秩父札所第9番の御朱印
如意輪大士(如意輪観世音菩薩)
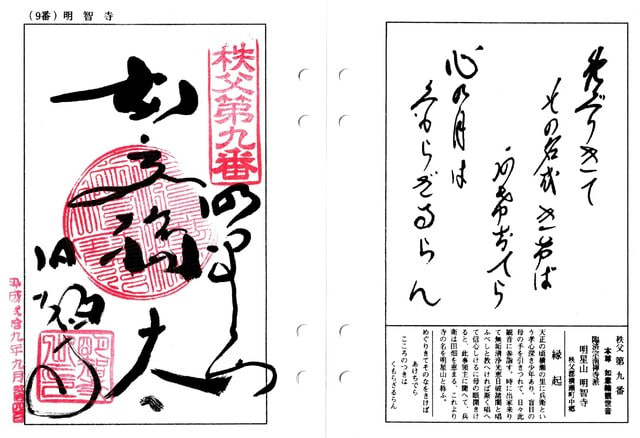
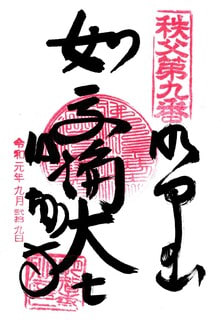
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
2.横瀬まいりの切り絵御朱印
如意輪観世音菩薩
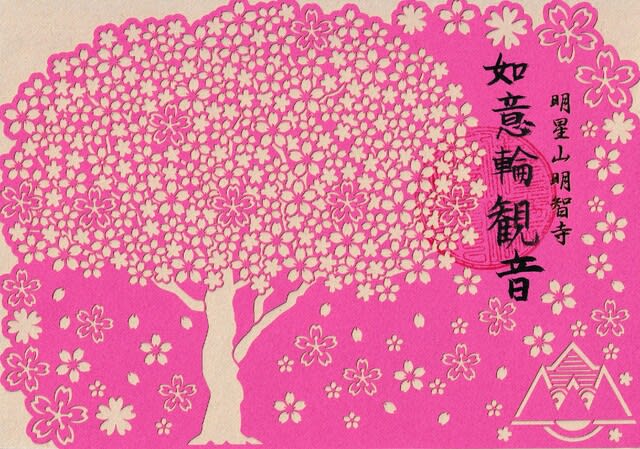
■ 小川山 語歌堂(長興寺)
横瀬町横瀬6086
臨済宗南禅寺派
御本尊:准胝観世音菩薩(語歌堂)
秩父札所の札所本尊:准胝観世音菩薩
旧・秩父札所:旧・秩父札所:第26番五閣堂
札所:秩父札所三十四観音霊場第5番、七観音霊場第6番


・めずらしい准胝観世音菩薩が御座す観音堂。
・本間孫八が慈覚大師作と伝えられる准胝観音を安置するため建立と伝わる。
・孫八は詩歌に堪能で、堂宇を訪れた旅僧と歌の道を語り合い和歌の奥義を極めたことにちなんで号したという。
・別当は長興寺で、いまでも語歌堂の納経所は長興寺となっている。
・語歌堂の堂宇は端正な宝形造で、横瀬町の指定史跡。
・長興寺は渓苔山と号して田村郷の圓福寺末。『新編武蔵風土記稿』によると御本尊は地蔵菩薩だが、御本尊の御朱印は授与されていない。
・准胝観世音菩薩を札所本尊とする日本百観音の札所は当山と西国第11番上醍醐寺のふたつしかなく、貴重な存在となっている。
・語歌堂は「七観音霊場」の札所。
「七観音霊場」とは「七種七躰それぞれの変化観音を御本尊とする寺院七箇寺により結成される霊場」で、札所は以下のとおり。
第1番 海照山 品川寺 聖観世音菩薩(品川区南品川)
第2番 瑞應山 弘明寺 十一面観世音菩薩(横浜市南区弘明寺町)
第3番 天照山 光明寺 如意輪観世音菩薩(鎌倉市材木座)
第4番 飯盛山 妙音寺 不空羂索観世音菩薩(神奈川県三浦市初声町下宮田)
第5番 巌殿山 正法寺 千手観世音菩薩(埼玉県東松山市岩殿)
第6番 小川山 語歌堂 准胝観世音菩薩(横瀬町横瀬)
第7番 石龍山 橋立堂 馬頭観世音菩薩(秩父市上影森)
札所の多くは大寺名刹だが、語歌堂が選ばれているのは慈覚大師作という縁起と、秩父札所の名声があるのかも。
・御朱印は長興寺の授与所にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.秩父札所第5番の御朱印
大悲殿(准胝観世音菩薩)
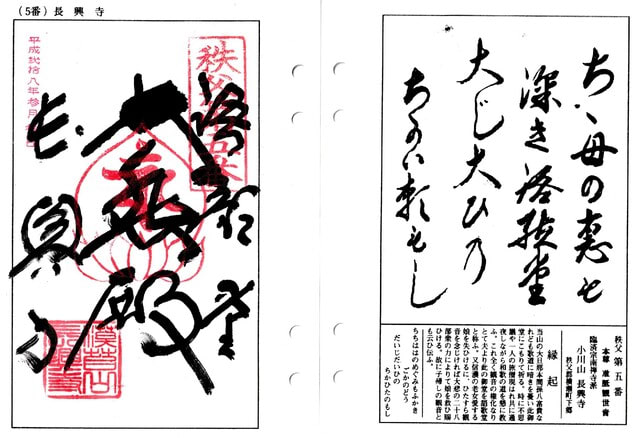
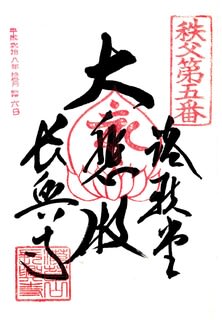
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
2.七観音霊場第6番
大悲殿(准胝観世音菩薩)
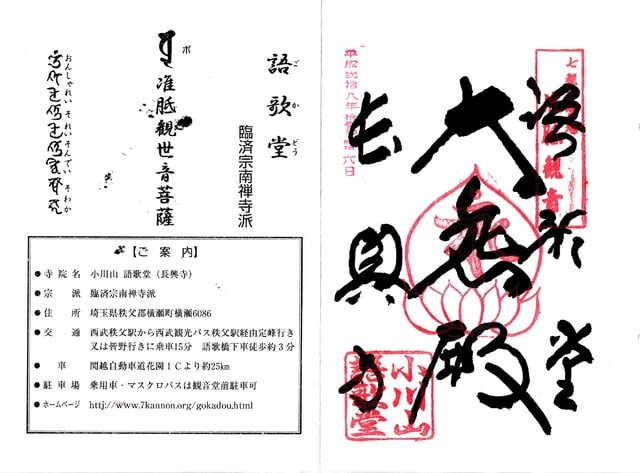
3.横瀬まいりの切り絵御朱印
藤の花
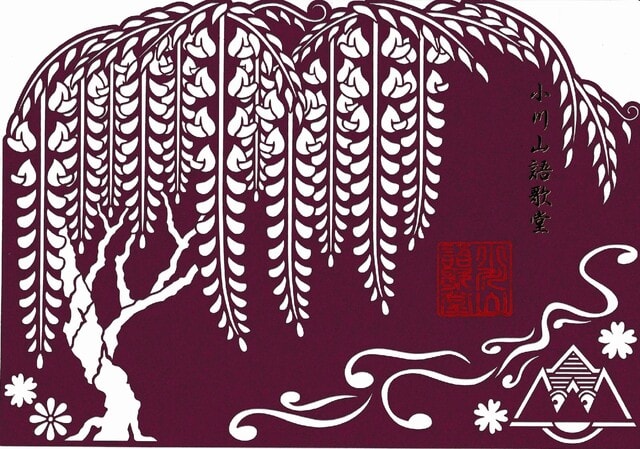
■ 萬松山 大慈寺
横瀬町横瀬5151
曹洞宗
御本尊:正観世音菩薩
秩父札所の札所本尊:正観世音菩薩
旧・秩父札所:第27番大慈寺
札所:秩父札所三十四観音霊場第10番


・延徳二年(1490年)開創、明応二年(1493年)東雄朔方大和尚により開山の禅刹で、当初は秩父札所第27番だったとみられる。
・御本尊の聖観世音菩薩は惠心僧都の御作と伝わる長一尺三寸の木坐像で、秩父ではめずらしいとされる法衣垂下像。町指定有形文化財。
・山門は三間一戸の樓門で左右脇間に仁王尊を安置。
・往時から多くの尊仏を安し、子育観音金銅仏は寛政六年、寄木造りの地蔵菩薩像は正徳四年の作とされ、十一面観音菩薩も奉安という。
・本堂内の宮殿厨子は優れた彫刻が施され、秩父札所の中でも屈指の名作として知られる。町指定有形文化財。
・本堂入口の「おびんずる様(なで仏)」は存在感を放ち人気の模様。
・アニメ映画の舞台となり、アニメファンの聖地としても知られている。
・御朱印は本堂向かって右の授与所にて拝受しました。
〔拝受御朱印〕
1.秩父札所第10番の御朱印
南無正観音(正観世音菩薩)
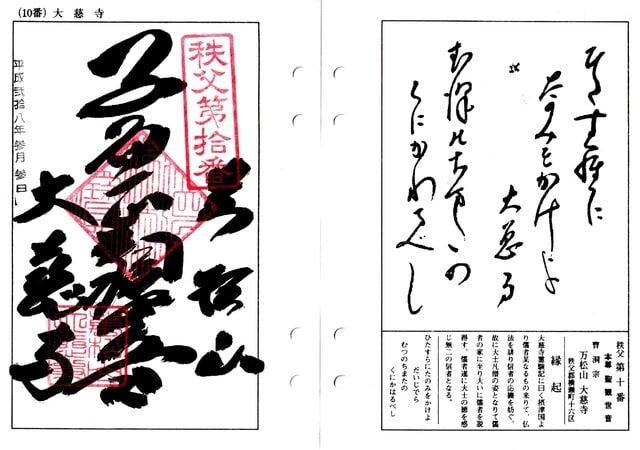

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
3.横瀬まいりの切り絵御朱印
聖観音/夫婦龍
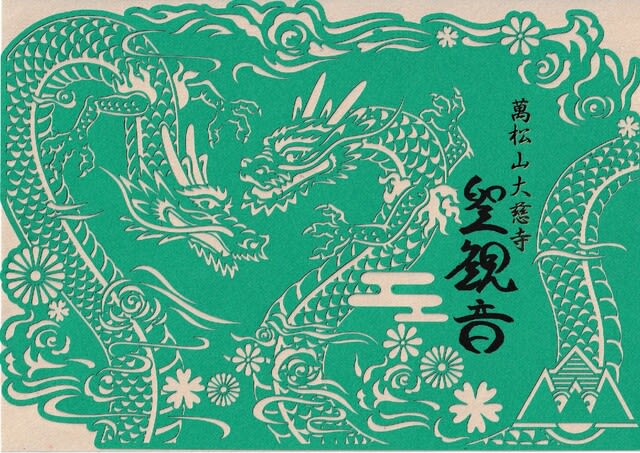
■ 嶽頂山 東林寺
横瀬町横瀬3537
曹洞宗
御本尊:准胝観世音菩薩
札所:秩父七福神(宇根恵比寿)、横瀬まいり
公式Web


・寛永年間(1624-1645年)初頭、吉田の清泉寺七世清翁全吉大和尚が大檀那今井家の寄進を受け創建と伝わる。開基は東林院殿慶香妙瑞大姉。
・御本尊は仏母ともいわれる准胝観世音菩薩で、開基のご遺徳をたたえるためとも伝わる。
・平成元年に秩父大仏造立(翠雲堂)、平成9年に客殿建築、平成26年には本堂の改築造立と、近年伽藍が整えられている。
・本堂向かって右手の高みの御堂に御座す恵比寿は「宇根恵比寿」と称され秩父七福神の一尊。
・ちなみに秩父七福神は下記のとおりで、大寺名刹が多く廻り応えがあります。
東林寺(宇根恵比寿)/横瀬町横瀬3537
惣圓寺(八臂大弁財天)/秩父市東町17-19
金仙寺(聖山布袋尊)/秩父市下影森6650
円福寺(延命寿老人)/秩父市田村967
鳳林寺(大悲毘沙門天)/小鹿野町下小鹿野1387
円福寺(福寿大黒天)/皆野町皆野293
総持寺(殿平福禄寿)/長瀞町本野上924
・御朱印は庫裏にて拝受しましたが、お正月以外はご不在のケースもありそうです。
・「横瀬まいり」の札所ですが、こちらの御朱印は横瀬町ブコーさん観光案内所(横瀬町大字芦ヶ久保159)で授与されています。
〔拝受御朱印〕 御本尊の御朱印は不授与の模様
1.秩父七福神(宇根恵比寿)の御朱印
恵比寿神
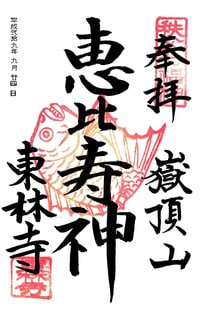
2.横瀬まいりの切り絵御朱印
佛心(秩父大仏)

これで横瀬町は終了です。
つぎは秩父市となります。
以下、つづきます。
【 BGM 】
■ 夢の大地 - kalafina
■ Erato - 志方あきこ
■ One Reason - milet
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 東京都世田谷区の札所と御朱印 (前編)
2024/04/24 追加UP
2021/08/29 追加UP
2021/01/02 追加UP
→ ■ 東京都世田谷区の札所と御朱印(後編)
東急線 花御朱印巡り 第2弾の御朱印は→ こちらをご覧ください。
------------------------
2020/07/03 UP
リストだけUPして3年以上も放置していましたが、神社とその後参拝した寺社を追記し、御朱印と画像を追加します。
日蓮宗・法華宗系の御首題についても追記しました。
ブログの字数制限に引っかかるので、前後2編に分けました。
寺社概要は、追って加えていきます。
--------------------------------------------
2017/03/31 UP
東京都世田谷区の札所と御朱印授与寺社のご紹介です。
【エリア概要】
東京山の手、屈指の高級住宅地として知られる世田谷区だが、山谷が複雑に入り組む地勢で、区域も広いためじつは多彩な顔をもつ。
住宅地メインながら寺院は意外に多く、御朱印授与寺もさりげに多い。隠れた御朱印エリアといってもいいかもしれない。
中世には奥州(武蔵)吉良氏の本拠地となり、豪徳寺(世田谷城)、九品仏浄真寺(奥沢城)、満願寺(兎々呂城)など、吉良氏の城跡とされる寺院があり、吉良氏ゆかりの名刹も少なくない。
神社では鎮守社が多く残り、別当寺との関係をわかりやすく示す例も多くみられるが、これは江戸近郊の農村から城西の戸建て住宅地へと、比較的穏やかに都市化した背景もあるかもしれない。
都心寄りの北沢・世田谷地域は東急田園都市線・世田谷線・東横線、京王井の頭線、小田急線などに囲まれ、鉄道アプローチに恵まれたエリアといえる。
人気タウン三軒茶屋駅のそばには名刹目青不動尊(教学院)があり、複数の霊場の札所となっている。近くには月替わりの絵御朱印が人気の太子堂八幡神社も鎮座されている。
ここから南の目黒区寄り、下馬・野沢エリアにかけての住宅地にも札所寺院が点在している。
北側、下北沢駅周辺や北沢、代田、大原、松原方面にかけては寺院は少ないが、北澤八幡宮は世田谷区内では稀少な御朱印帳を頒布されている。北澤八幡宮の元別当、森巌寺も御朱印を授与されている。
世田谷線沿線には名刹、豪徳寺をはじめとして、玉川八十八ヶ所霊場、世田谷三十三ヶ所観音霊場の札所が複数立地している。授与寺が多く、区内有数の御朱印エリアとなっている。
歴史の香り高い落ちついた寺院が適度な距離をもって点在し、まわっていて楽しいエリア。
松陰神社、世田谷八幡宮など格式の高い神社も鎮座されている。
この界隈をまわるには「世田谷線散策きっぷ/340円」が有効だが、小田急線乗り換え駅の「山下」駅では発売がなく、車内発売もないので一旦発売駅の「上町」駅までいかないと精算&購入できないのは不便。
小田急線と京王線の間、桜上水、船橋、千歳台、上祖師谷あたりになると両線の距離が次第に離れるのでややアプローチが不便となる。
たいていのお寺は駐車場を持っているが、住宅地で細い道が錯綜し、一方通行など交通規制も多いので、車でのアプローチは神経をつかうところ。
このエリアにも玉川八十八ヶ所霊場、世田谷三十三ヶ所観音霊場の札所が点在している。
北烏山界隈は関東大震災を契機に、浅草、築地、本所、荒川など東京下町から移転してきた寺院が集積し、城西エリア有数の大規模な寺町を形成している。
区資料などで紹介されている26軒のうち、真宗13、日蓮宗4、法華宗3、浄土宗4、真言宗1、臨済宗1と、真宗、日蓮宗、法華宗寺院が過半を占め、御朱印エリアとしてのイメージはあまり強くはないものの、メジャー霊場・御府内八十八箇所の札所(多聞院)があり、御朱印収集的には外せないところか。
区中央部の弦巻、上馬、駒沢、深沢あたりは寺院は少なく、御朱印授与寺も深沢の醫王寺を数える程度だが、いくつかの神社が御朱印を授与されている。
区西南部にあたる東急大井町線沿線には比較的多くの寺院が立地する。
九品仏浄真寺、傳乗寺、満願寺、等々力不動尊(満願寺別院)、などの名刹をはじめ、二子玉川駅北側の瀬田四丁目には御朱印授与寺が集中している。
いくつかの神社も点在し、等々力の玉川神社、瀬田玉川神社ともに境内社や兼務社の御朱印も授与されている。
武蔵野台の南端、国分寺崖線に沿ったこのあたりは予想以上に土地の起伏が激しく、歩き応えがある。
ここから多摩川上流方向に向かった鎌田、喜多見エリアにも霊場札所がいくつか点在する。
鉄道交通の便はいまひとつで、車によるアプローチの効率がよい。
区全体でみると、宗派的には真宗、日蓮宗、浄土宗が多く、曹洞宗寺院も10以上を数えるものの授与寺は多くない。真言宗は智山派、豊山派併せて20以上を数え、相当数が霊場札所となっている。
世田谷区内での御朱印収集では、この真言宗寺院の存在が大きい。
【世田谷区と札所】
弘法大師霊場としては区内ほぼ全域に玉川八十八ヶ所霊場の札所が立地している。
最近はまわる人が増えているらしく、対応はおおむね手慣れておられるが、小規模なお寺も多くご住職ご不在時には大判の規定用紙書置対応となるケースが多い。

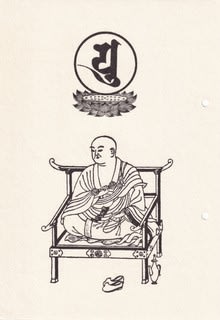
【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の専用納経帳-1
【写真 下(右)】 玉川八十八ヶ所霊場の専用納経帳-2
観音霊場では世田谷三十三ヶ所観音霊場があるものの授与状況は微妙で、札所印付きの揮毫御朱印を授与いただける寺院もあれば、不授与の寺院もある。
玉川八十八ヶ所との兼務寺も相当数あるが、玉川霊場で授与されている場合は観音霊場で授与されていないケースが多い模様。
また、多摩川三十四観音霊場が喜多見方面で一部入ってくる。
他に御府内八十八箇所(多聞院・北烏山)、江戸三十三観音札所(観音寺・下馬)、関東三十六不動尊霊場(等々力不動尊)、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)(玉真院・瀬田)、関東九十一薬師霊場(醫王寺・深沢)、関東百八地蔵尊霊場(知行院・喜多見)などの御朱印授与札所がある。
その他、京王三十三観音霊場、小田急武相三十三観音霊場、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)、玉川北百番霊場などの札所があるが、いずれも現役の札所として機能している寺院は少ない模様。
【拝受データ】 (おおむね東部から。番地・号は昇順。現時点で授与休廃止の可能性あり、授与形態(直書・書置など)は状況により変化する可能性大です。)
こちらのデータについては下記サイトのデータを参考・引用させていただきました。いずれも貴重なデータ満載のすばらしい内容です。
「日本を巡礼する」様 → リンク
「東大和と寺院散策」様 → リンク
「猫のあしあと」様 → リンク
「マッハ墨朱&絵馬による布陣(仮)」様 → リンク
--------------------------------------------
■ 池尻稲荷神社


公式Web
世田谷区池尻2-34-15
御祭神:宇迦之御魂神
旧社格:村社、旧池尻村・池沢村鎮守
元別当:常光院(池尻)
授与所:境内授与所
■ 聖王山 法明院 圓泉寺

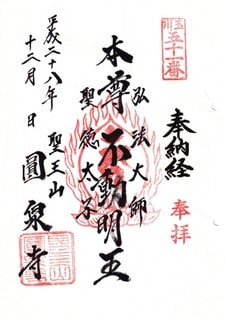
公式Web
世田谷区太子堂3-30-8
真言宗豊山派
元司別当:太子堂八幡神社
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:玉川八十八ヶ所霊場第51番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第14番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第27番
〔玉川八十八ヶ所霊場第51番の御朱印〕
・御朱印尊格:不動明王 玉川八十八ヶ所霊場第51番印判 書置(筆書) 規定用紙
■ 竹園山 最勝寺 教学院(目青不動尊)




世田谷区太子堂4-15-1
天台宗 御本尊:阿弥陀如来
札所:江戸五色不動尊、関東三十六不動尊霊場第16番、大東京百観音霊場第54番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第15番、東京三十三観音霊場第10番
〔江戸五色不動尊の御朱印〕
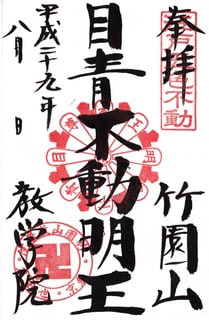
・御朱印尊格:目青不動明王 江戸五色不動尊印判 直書(筆書)
〔関東三十六不動尊霊場第16番の御朱印/専用納経帳〕
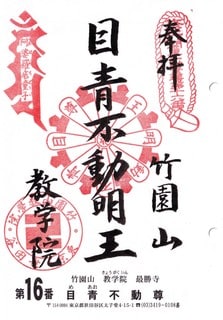
・御朱印尊格:目青不動明王 関東三十六不動尊霊場第16番印判 書置(筆書)
〔関東三十六不動尊霊場第16番の御朱印/御朱印帳〕
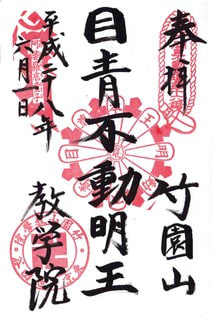
・御朱印尊格:目青不動明王 関東三十六不動尊霊場第16番印判 直書(筆書)
〔大東京百観音霊場第54番の御朱印〕
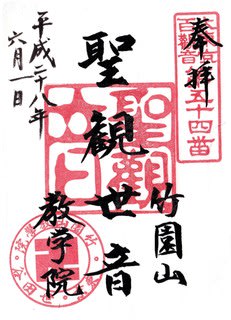
・御朱印尊格:聖観世音 大東京百観音霊場第54番印判 書置(筆書)
〔世田谷三十三ヶ所観音霊場第15番の御朱印〕
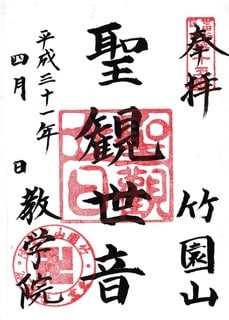
・御朱印尊格:聖観世音 世田谷区内第15番印判 直書(筆書)
※御本尊の御朱印は不授与です。
■ 太子堂八幡神社


公式Web
世田谷区太子堂5-23-5
御祭神:誉田別尊
旧社格:村社
元別当:聖王山 圓泉寺(太子堂)
授与所:境内授与所
御朱印揮毫:太子堂八幡神社 印判
※月替わりの絵御朱印で有名。
■ 太子堂弁財天社

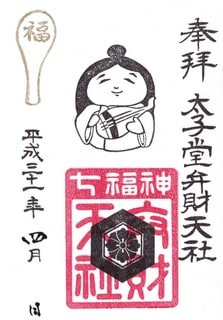
世田谷区太子堂5-23-5
御祭神:弁財天
太子堂八幡神社境内社
授与所:太子堂八幡神社境内授与所
御朱印揮毫:太子堂弁財天社 印判
■ 松陰神社

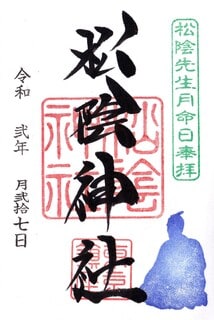
公式Web
世田谷区若林4-35-1
御祭神:吉田寅次郎藤原矩方命
旧社格:府社
授与所::境内授与所
御朱印揮毫:松陰神社 直書(筆書)(27日月命日御朱印)
■ 日輪山 薬王院 西澄寺

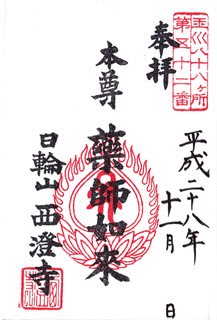
世田谷区下馬2-11-6
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所:玉川八十八ヶ所霊場第52番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第16番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第25番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第63番
〔玉川八十八ヶ所霊場第52番の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 薬師如来 玉川八十八ヶ所霊場第52番印判 印判
■ 世田谷山 観音寺(世田谷観音)

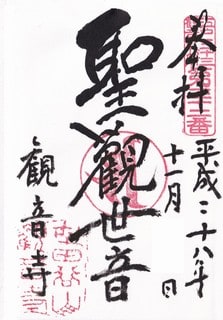
公式Web
世田谷区下馬4-9-4
天台宗系単立 御本尊:聖観世音菩薩
札所:江戸三十三観音札所第32番
〔江戸三十三観音札所第32番の御朱印〕
・御朱印尊格:聖観世音菩薩 江戸三十三観音札所第32番印判 直書(筆書)
■ 駒繋神社

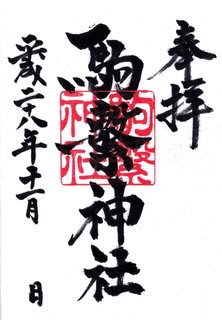
公式Web
世田谷区下馬4-27-26
御祭神:大国主命
旧社格:無格社
元別当:新清山 寿福寺(上目黒)
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:駒繋神社 直書(筆書)
■ 八幡山 宗圓寺

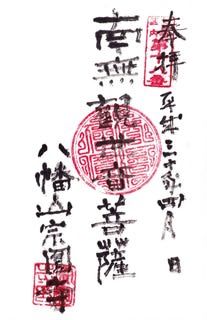
世田谷区上馬3-6-8
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
元司別当:駒留八幡神社(若宮八幡)
札所:世田谷三十三ヶ所観音霊場第18番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第23番
〔世田谷三十三ヶ所観音霊場第18番の御朱印〕
・御朱印尊格:南無観世音菩薩 世田谷区内第18番印判 直書(筆書)
■ 如法山 感應寺

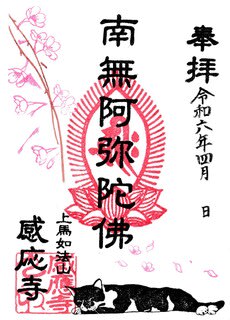
公式Web
世田谷区上馬4-30-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
元司別当:
札所:江戸東方四十八地蔵霊場第41番
〔御本尊の御朱印〕
・御朱印尊格:南無阿弥陀佛 書置(筆書)
■ 駒留八幡神社(若宮八幡)

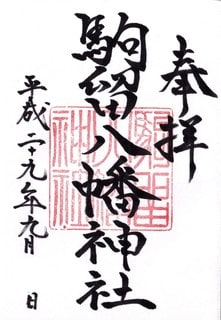
世田谷区上馬5-35-3
御祭神:天照大神、応神天皇
旧社格:村社 旧馬引澤村鎮守
元別当:八幡山 宗圓寺(上馬)
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:駒留八幡神社 直書(筆書)
■ 大澤山 龍雲寺

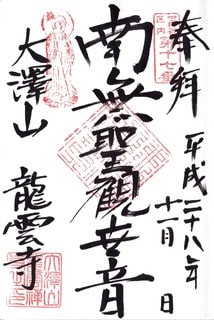
公式Web
世田谷区野沢3-38-1
臨済宗妙心寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所:世田谷三十三ヶ所観音霊場第17番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第24番
〔世田谷三十三ヶ所観音霊場第17番の御朱印〕
・御朱印尊格:聖観世音菩薩 世田谷三十三ヶ所観音霊場第17番印判 直書(筆書)
○玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第24番
※御本尊の御朱印授与は不明。
■ 北澤八幡宮(七澤八社随一正八幡宮)

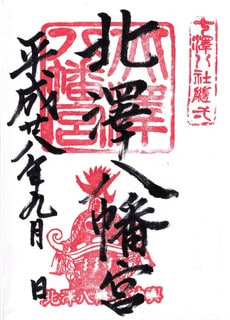
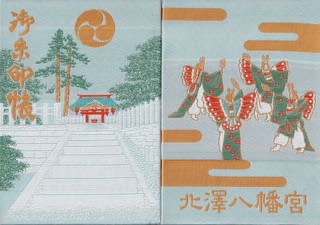
世田谷区代沢3-25-3
御祭神:応神天皇、比売神、神功皇后、仁徳天皇
旧社格:無格社
元別当:八幡山 森巌寺(代沢)
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:北澤八幡宮 直書(筆書)
※御朱印帳頒布あり
■ 八幡山 浄光院 森巌寺

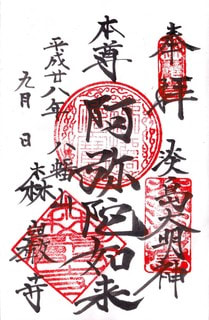
公式Web
世田谷区代沢3-27-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
元司別当:北澤八幡宮(七澤八社随一正八幡宮)
札所:小田急武相三十三観音霊場第3番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第13番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第28番
〔御本尊の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 阿弥陀如来 札番:なし 直書(筆書)
■ 代永山 真勝寺 圓乗院

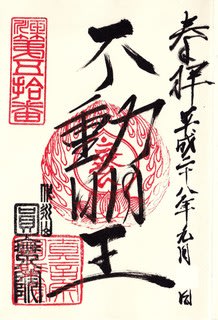
世田谷区代田2-17-3
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
元司別当:代田八幡神社
札所:玉川八十八ヶ所霊場第50番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第12番、玉川北百番霊場第33番
〔玉川八十八ヶ所霊場第50番の御朱印〕
・御朱印尊格:不動明王 玉川八十八ヶ所霊場第50番印判 書置(筆書)
■ 代田八幡神社

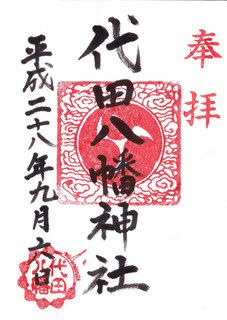
世田谷区代田3-57-1
御祭神:応神天皇
旧代田村鎮守
元別当:代永山 圓乗院(代田)
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:代田八幡神社 直書(筆書)
■ 大原稲荷神社

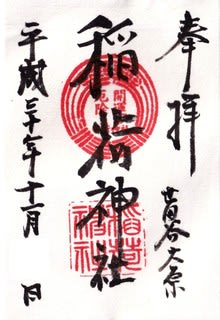
世田谷区大原2-29-21
御祭神:倉稲魂神
大原町、代田町の一部の鎮守
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:稲荷神社 書置(筆書)
■ 代田橋大鳥神社

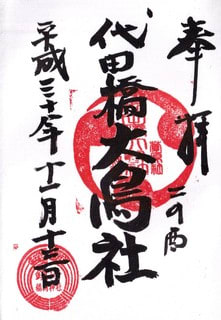
世田谷区大原2-29-21
御祭神:天鳥船大神
大原稲荷神社の境内社
授与所:大原稲荷神社境内社務所
御朱印揮毫:代田橋大鳥神社 直書(筆書)
※酉の市限定の授与
■ 九品山 往生院 浄光寺

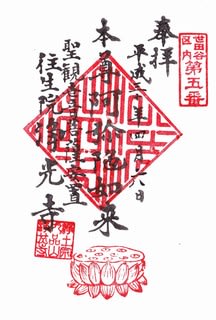
世田谷区世田谷1-38-20
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:世田谷三十三ヶ所観音霊場第5番、玉川北百番霊場第18番
〔世田谷三十三ヶ所観音霊場第5番の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 阿弥陀如来・聖観世音菩薩 世田谷区内第5番印判 印刷?
■ 護国山 天照院 大吉寺


世田谷区世田谷4-7-9
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:世田谷三十三ヶ所観音霊場第4番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第31番
〔御本尊の御朱印〕

・御朱印尊格:阿弥陀如来 札番:なし 書置(筆書)
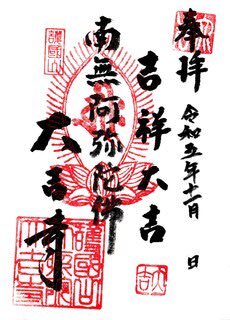
・御朱印尊格:南無阿弥陀佛 札番:なし 書置(筆書)
■ 大悲山 明王寺 円光院

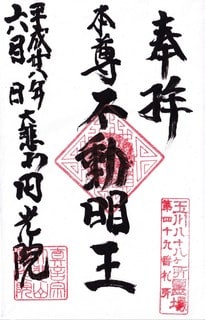
公式Web
世田谷区世田谷4-7-12
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所:玉川八十八ヶ所霊場第49番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第3番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第32番
〔玉川八十八ヶ所霊場第49番の御朱印〕
・御朱印尊格:不動明王 玉川八十八ヶ所霊場第49番印判 直書(筆書)
■ 青龍山 勝国寺

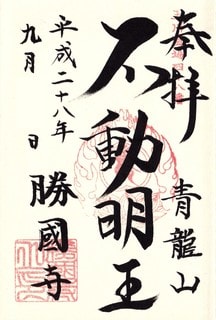
世田谷区世田谷4-27-4
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所:玉川八十八ヶ所霊場第48番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第2番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第33番
〔玉川八十八ヶ所霊場第48番の御朱印〕
・御朱印尊格:不動明王 玉川八十八ヶ所霊場48番印判 直書(筆書)
■ 延命山 勝光院

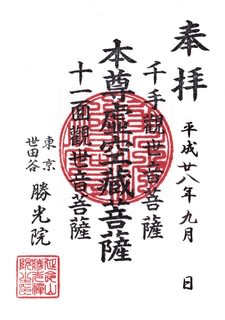
世田谷区桜1-26-35
曹洞宗
御本尊:虚空蔵菩薩
札所:世田谷三十三ヶ所観音霊場第7番、玉川北百番霊場第20番
〔御本尊の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 虚空蔵菩薩 札判:なし 印判
■ 寶樹山 常在寺


世田谷区弦巻1-34-17
日蓮宗
・御首題 直書(筆書)
■ 弦巻神社

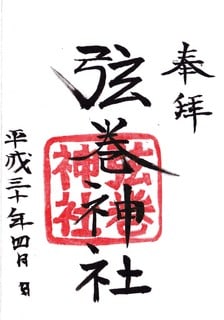
世田谷区弦巻3-18-22
御祭神:宇迦之御魂神、応神天皇、菅原道真公
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:弦巻神社 直書(筆書)
■ 鶴松山 実相院

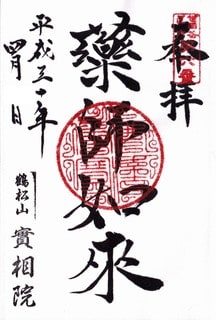
世田谷区弦巻3-29-6
曹洞宗
御本尊:薬師如来
札所:世田谷三十三ヶ所観音霊場第6番、玉川北百番霊場第17番
〔世田谷三十三ヶ所観音霊場第6番の御朱印〕
・御朱印尊格:薬師如来 世田谷区内第6番印判 直書(筆書)
■ 赤堤山 善性寺

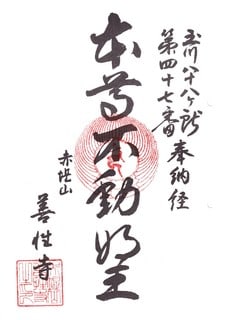
世田谷区豪徳寺1-55-23
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所:玉川八十八ヶ所霊場第47番、玉川北百番霊場第31番
〔玉川八十八ヶ所霊場第47番の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 不動明王 玉川八十八ヶ所霊場第47番印刷 印刷
■ 大谿山 豪徳寺


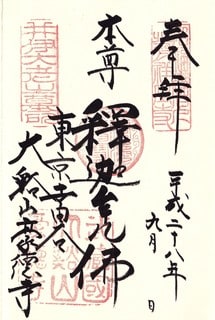
世田谷区豪徳寺2-24-7
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼仏
札所:東京三十三観音霊場第11番、大東京百観音霊場特番7、小田急武相三十三観音霊場特別、世田谷三十三ヶ所観音霊場第1番、玉川北百番霊場第30番
〔御本尊の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 釋迦牟尼佛 札判:なし 直書(筆書)
※霊場札所の御朱印は不授与の模様。
■ 世田谷八幡宮


世田谷区宮坂1-26-3
御祭神:応神天皇(誉田別命)、仲哀天皇、神功皇后
旧社格:郷社 旧世田谷村鎮守
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:世田谷八幡宮 印判
■ 観谷山 常徳院

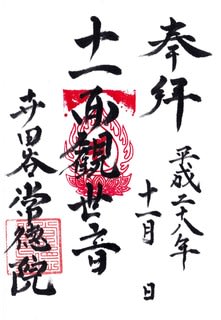
世田谷区宮坂2-1-11
曹洞宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:世田谷三十三ヶ所観音霊場第8番、玉川北百番霊場第28番
〔御本尊の御朱印〕
・御朱印尊格:十一面観世音 札判:なし 直書(筆書)
■ 経堂山 福昌寺

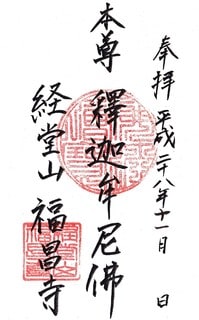
世田谷区経堂1-22-1
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
元司別当:経堂鎮守天祖神社
札所:小田急武相三十三観音霊場第4番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第9番、玉川北百番霊場第29番
〔御本尊の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 釋迦牟尼佛 札判:なし 書置(筆書)
■ 経堂鎮守天祖神社

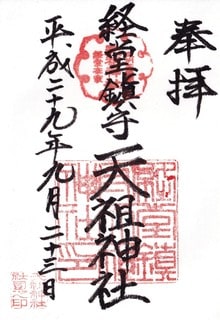
公式Web
世田谷区経堂4-33-2
御祭神:天照大御神、稲荷大神、北野大神
旧社格:村社、旧経堂在家村鎮守
元別当:経堂山 福昌寺(経堂)
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:経堂鎮守 天祖神社 直書(筆書)
■ 稲荷森稲荷神社


公式Web
世田谷区桜丘2-29-3
御祭神:宇迦之御魂神
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:稲荷森稲荷神社 直書(筆書)
■ (赤堤)六所神社


公式Web
世田谷区赤堤2-25-2
御祭神:大国魂命、伊弉冊尊、素戔嗚尊、布留大神、大宮売命
旧社格:村社、旧赤堤村鎮守
元別当:光林山 西福寺(赤堤)
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:六所神社 印判
■ 光林山 持明院 西福寺

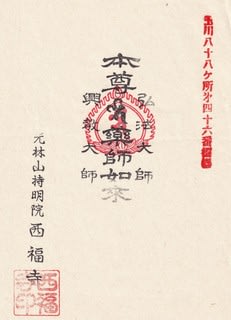
公式Web
世田谷区赤堤3-28-29
真言宗豊山派
御本尊:薬師如来
元司別当:(赤堤)六所神社
札所:玉川八十八ヶ所霊場第46番、京王三十三観音霊場第4番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第11番、玉川北百番霊場第27番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第62番
〔玉川八十八ヶ所霊場第46番の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 薬師如来 玉川八十八ヶ所霊場46番印判 印判 規定用紙
■ (世田谷)菅原神社

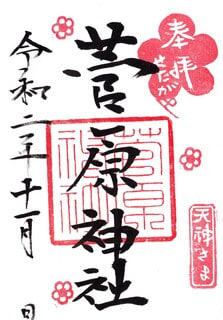
世田谷区松原3-20-16
御祭神:菅原道真公
旧社格:村社、松原地区鎮守
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:菅原神社 直書(筆書)
■ 幽谿山 観音寺 密蔵院


世田谷区桜上水2-24-6
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所:玉川八十八ヶ所霊場第45番、小田急武相三十三観音霊場第5番、京王三十三観音霊場第5番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第10番、玉川北百番霊場第26番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第61番
〔玉川八十八ヶ所霊場第45番の御朱印〕
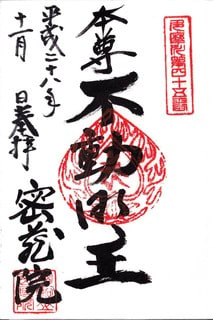
・御朱印尊格:本尊 不動明王 玉川八十八ヶ所霊場第45番印判 直書(筆書)
〔小田急武相三十三観音霊場第5番の御朱印〕

・御朱印尊格:百體観世音 小田急武相三十三観音霊場第5番印判 直書(筆書)
■ 勝利八幡神社

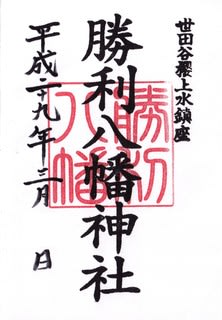
世田谷区桜上水3-21-6
御祭神:誉田別命
旧社格:村社、旧上北沢村鎮守
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:勝利八幡神社 印判
■ 波羅密山 観光院 寶性寺


世田谷区船橋4-39-32
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所:玉川八十八ヶ所霊場第43番、玉川北百番霊場第23番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第58番
〔玉川八十八ヶ所霊場第43番の御朱印〕
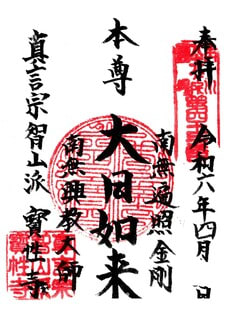
・御朱印尊格:大日如来 南無遍照金剛 南無興教大師 玉川八十八ヶ所霊場第43番印判 書置(筆書)
〔玉川八十八ヶ所霊場第43番の御朱印〕
・御朱印尊格:不動明王 玉川八十八ヶ所霊場第43番印判 直書(筆書)
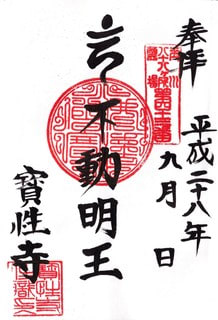
■ 青林山 薬王寺 東覺院

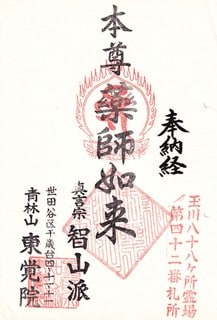
世田谷区千歳台4-11-11
真言宗智山派
御本尊:薬師如来
札所:玉川八十八ヶ所霊場第42番、玉川北百番霊場第24番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第59番、江戸・東京四十四閻魔参り第26番
〔玉川八十八ヶ所霊場第42番の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 不動明王 玉川八十八ヶ所霊場第42番印判 印判 規定用紙
■ 舜栄山 行王院 安穏寺

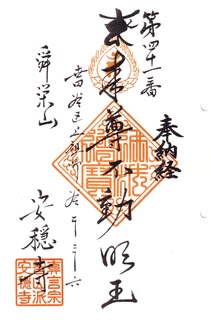
世田谷区上祖師谷2-3-6
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所:玉川八十八ヶ所霊場第41番、○大東京百観音霊場第86番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第57番
〔玉川八十八ヶ所霊場第41番の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 不動明王 玉川八十八ヶ所霊場第41番揮毫 印刷 規定用紙
■ 向旭山 源良院

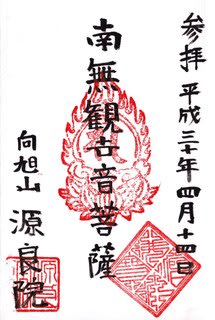
世田谷区北烏山4-10-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
〔観音様の御朱印〕
・御朱印尊格:南無観世音菩薩 札番:なし 直書(筆書)
※非札所につき、常時御朱印授与されているかは不明。
■ 金剛山 悲願寺 多聞院


世田谷区北烏山4-12-1
真言宗豊山派
御本尊:地蔵菩薩
札所:御府内八十八箇所第3番、玉川八十八ヶ所霊場第44番
〔御府内八十八箇所第3番の御朱印/専用納経帳〕
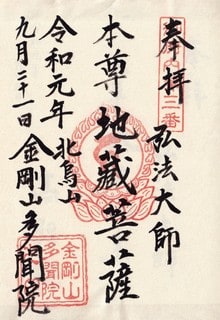
・御朱印尊格:本尊 地蔵菩薩 御府内八十八箇所第3番印判 直書(筆書) 規定用紙
〔御府内八十八箇所第3番の御朱印/御朱印帳〕
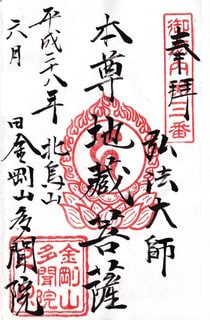
・御朱印尊格:本尊 地蔵菩薩 御府内八十八箇所第3番印判 直書(筆書)
〔玉川八十八ヶ所霊場第44番の御朱印〕
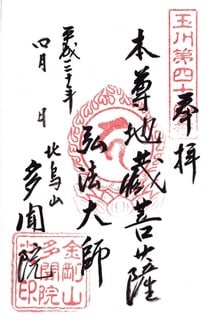
・御朱印尊格:本尊 地蔵菩薩 玉川八十八ヶ所霊場第44番 直書(筆書)
○江戸八十八ヶ所霊場第3番
■ 春陽山 永隆寺


公式Web
世田谷区北烏山4-17-1
法華宗本門流本能寺派
札所:○京王三十三観音霊場第9番
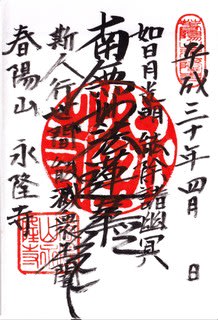
・御首題 直書(筆書)

・御朱印尊格:神保大黒天 (筆書) ※正月のみ
■ 常徳山 玄照寺
世田谷区北烏山4-21-1
日蓮宗

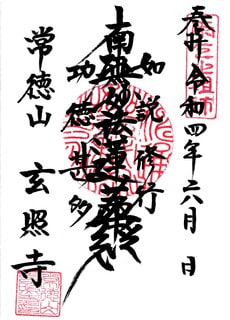
・御首題 直書(筆書)
■ 霊照山 蓮池院 専光寺

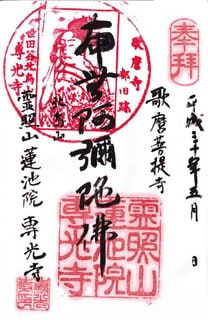
世田谷区北烏山4-28-1
〔御本尊の御朱印〕
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
・御朱印尊格:南無阿彌陀佛 札番:なし 直書(筆書)
※非札所につき、常時御朱印授与されているかは不明。
■ 瑞泉山 高源院


世田谷区北烏山4-30-1
臨済宗大徳寺派
御本尊:釈迦牟尼仏
〔御本尊の御朱印〕
・御朱印尊格:釋迦牟尼佛 札番:なし 直書(筆書)
※非札所につき、常時御朱印授与されているかは不明。
■ 妙祐山 幸龍寺

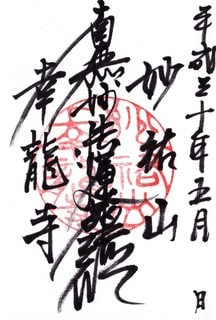
世田谷区北烏山5-8-1
日蓮宗
・御首題 直書(筆書) 江戸十大祖師
■ 一心山 極楽寺 称往院


世田谷区北烏山5-9-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
〔御本尊(御名号)の御朱印〕
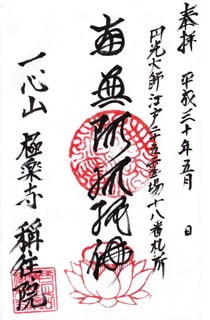
・御朱印尊格:南無阿弥陀佛 直書(筆書)
〔京王三十三観音霊場第8番の御朱印〕
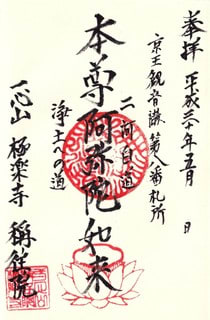
・御朱印尊格:本尊 阿弥陀如来 京王三十三観音霊場第8番 直書(筆書)
○円光大師東都二十五ヶ所霊場第18番、御府内円光大師二十五拝霊場第19番、坂東写東都三十三観音霊場第3番
■ 本覚山 妙壽寺
世田谷区北烏山5-15-1


法華宗本門流
・御首題 書置(筆書)
→ ■ 東京都世田谷区の札所と御朱印(後編)
【 BGM 】
John Jarvis - A Perfect Rain
Dwight Sills - I'll be Right Here
Richard Elliot - Take To The Skies
2021/08/29 追加UP
2021/01/02 追加UP
→ ■ 東京都世田谷区の札所と御朱印(後編)
東急線 花御朱印巡り 第2弾の御朱印は→ こちらをご覧ください。
------------------------
2020/07/03 UP
リストだけUPして3年以上も放置していましたが、神社とその後参拝した寺社を追記し、御朱印と画像を追加します。
日蓮宗・法華宗系の御首題についても追記しました。
ブログの字数制限に引っかかるので、前後2編に分けました。
寺社概要は、追って加えていきます。
--------------------------------------------
2017/03/31 UP
東京都世田谷区の札所と御朱印授与寺社のご紹介です。
【エリア概要】
東京山の手、屈指の高級住宅地として知られる世田谷区だが、山谷が複雑に入り組む地勢で、区域も広いためじつは多彩な顔をもつ。
住宅地メインながら寺院は意外に多く、御朱印授与寺もさりげに多い。隠れた御朱印エリアといってもいいかもしれない。
中世には奥州(武蔵)吉良氏の本拠地となり、豪徳寺(世田谷城)、九品仏浄真寺(奥沢城)、満願寺(兎々呂城)など、吉良氏の城跡とされる寺院があり、吉良氏ゆかりの名刹も少なくない。
神社では鎮守社が多く残り、別当寺との関係をわかりやすく示す例も多くみられるが、これは江戸近郊の農村から城西の戸建て住宅地へと、比較的穏やかに都市化した背景もあるかもしれない。
都心寄りの北沢・世田谷地域は東急田園都市線・世田谷線・東横線、京王井の頭線、小田急線などに囲まれ、鉄道アプローチに恵まれたエリアといえる。
人気タウン三軒茶屋駅のそばには名刹目青不動尊(教学院)があり、複数の霊場の札所となっている。近くには月替わりの絵御朱印が人気の太子堂八幡神社も鎮座されている。
ここから南の目黒区寄り、下馬・野沢エリアにかけての住宅地にも札所寺院が点在している。
北側、下北沢駅周辺や北沢、代田、大原、松原方面にかけては寺院は少ないが、北澤八幡宮は世田谷区内では稀少な御朱印帳を頒布されている。北澤八幡宮の元別当、森巌寺も御朱印を授与されている。
世田谷線沿線には名刹、豪徳寺をはじめとして、玉川八十八ヶ所霊場、世田谷三十三ヶ所観音霊場の札所が複数立地している。授与寺が多く、区内有数の御朱印エリアとなっている。
歴史の香り高い落ちついた寺院が適度な距離をもって点在し、まわっていて楽しいエリア。
松陰神社、世田谷八幡宮など格式の高い神社も鎮座されている。
この界隈をまわるには「世田谷線散策きっぷ/340円」が有効だが、小田急線乗り換え駅の「山下」駅では発売がなく、車内発売もないので一旦発売駅の「上町」駅までいかないと精算&購入できないのは不便。
小田急線と京王線の間、桜上水、船橋、千歳台、上祖師谷あたりになると両線の距離が次第に離れるのでややアプローチが不便となる。
たいていのお寺は駐車場を持っているが、住宅地で細い道が錯綜し、一方通行など交通規制も多いので、車でのアプローチは神経をつかうところ。
このエリアにも玉川八十八ヶ所霊場、世田谷三十三ヶ所観音霊場の札所が点在している。
北烏山界隈は関東大震災を契機に、浅草、築地、本所、荒川など東京下町から移転してきた寺院が集積し、城西エリア有数の大規模な寺町を形成している。
区資料などで紹介されている26軒のうち、真宗13、日蓮宗4、法華宗3、浄土宗4、真言宗1、臨済宗1と、真宗、日蓮宗、法華宗寺院が過半を占め、御朱印エリアとしてのイメージはあまり強くはないものの、メジャー霊場・御府内八十八箇所の札所(多聞院)があり、御朱印収集的には外せないところか。
区中央部の弦巻、上馬、駒沢、深沢あたりは寺院は少なく、御朱印授与寺も深沢の醫王寺を数える程度だが、いくつかの神社が御朱印を授与されている。
区西南部にあたる東急大井町線沿線には比較的多くの寺院が立地する。
九品仏浄真寺、傳乗寺、満願寺、等々力不動尊(満願寺別院)、などの名刹をはじめ、二子玉川駅北側の瀬田四丁目には御朱印授与寺が集中している。
いくつかの神社も点在し、等々力の玉川神社、瀬田玉川神社ともに境内社や兼務社の御朱印も授与されている。
武蔵野台の南端、国分寺崖線に沿ったこのあたりは予想以上に土地の起伏が激しく、歩き応えがある。
ここから多摩川上流方向に向かった鎌田、喜多見エリアにも霊場札所がいくつか点在する。
鉄道交通の便はいまひとつで、車によるアプローチの効率がよい。
区全体でみると、宗派的には真宗、日蓮宗、浄土宗が多く、曹洞宗寺院も10以上を数えるものの授与寺は多くない。真言宗は智山派、豊山派併せて20以上を数え、相当数が霊場札所となっている。
世田谷区内での御朱印収集では、この真言宗寺院の存在が大きい。
【世田谷区と札所】
弘法大師霊場としては区内ほぼ全域に玉川八十八ヶ所霊場の札所が立地している。
最近はまわる人が増えているらしく、対応はおおむね手慣れておられるが、小規模なお寺も多くご住職ご不在時には大判の規定用紙書置対応となるケースが多い。

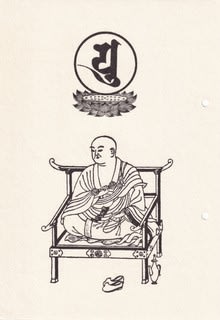
【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の専用納経帳-1
【写真 下(右)】 玉川八十八ヶ所霊場の専用納経帳-2
観音霊場では世田谷三十三ヶ所観音霊場があるものの授与状況は微妙で、札所印付きの揮毫御朱印を授与いただける寺院もあれば、不授与の寺院もある。
玉川八十八ヶ所との兼務寺も相当数あるが、玉川霊場で授与されている場合は観音霊場で授与されていないケースが多い模様。
また、多摩川三十四観音霊場が喜多見方面で一部入ってくる。
他に御府内八十八箇所(多聞院・北烏山)、江戸三十三観音札所(観音寺・下馬)、関東三十六不動尊霊場(等々力不動尊)、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)(玉真院・瀬田)、関東九十一薬師霊場(醫王寺・深沢)、関東百八地蔵尊霊場(知行院・喜多見)などの御朱印授与札所がある。
その他、京王三十三観音霊場、小田急武相三十三観音霊場、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)、玉川北百番霊場などの札所があるが、いずれも現役の札所として機能している寺院は少ない模様。
【拝受データ】 (おおむね東部から。番地・号は昇順。現時点で授与休廃止の可能性あり、授与形態(直書・書置など)は状況により変化する可能性大です。)
こちらのデータについては下記サイトのデータを参考・引用させていただきました。いずれも貴重なデータ満載のすばらしい内容です。
「日本を巡礼する」様 → リンク
「東大和と寺院散策」様 → リンク
「猫のあしあと」様 → リンク
「マッハ墨朱&絵馬による布陣(仮)」様 → リンク
--------------------------------------------
■ 池尻稲荷神社


公式Web
世田谷区池尻2-34-15
御祭神:宇迦之御魂神
旧社格:村社、旧池尻村・池沢村鎮守
元別当:常光院(池尻)
授与所:境内授与所
■ 聖王山 法明院 圓泉寺

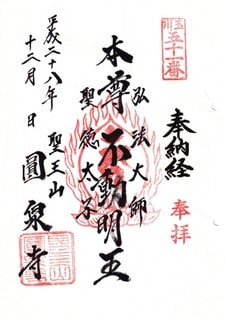
公式Web
世田谷区太子堂3-30-8
真言宗豊山派
元司別当:太子堂八幡神社
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:玉川八十八ヶ所霊場第51番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第14番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第27番
〔玉川八十八ヶ所霊場第51番の御朱印〕
・御朱印尊格:不動明王 玉川八十八ヶ所霊場第51番印判 書置(筆書) 規定用紙
■ 竹園山 最勝寺 教学院(目青不動尊)




世田谷区太子堂4-15-1
天台宗 御本尊:阿弥陀如来
札所:江戸五色不動尊、関東三十六不動尊霊場第16番、大東京百観音霊場第54番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第15番、東京三十三観音霊場第10番
〔江戸五色不動尊の御朱印〕
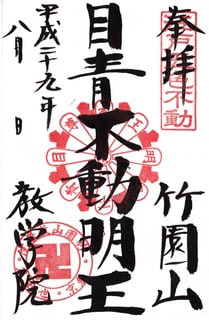
・御朱印尊格:目青不動明王 江戸五色不動尊印判 直書(筆書)
〔関東三十六不動尊霊場第16番の御朱印/専用納経帳〕
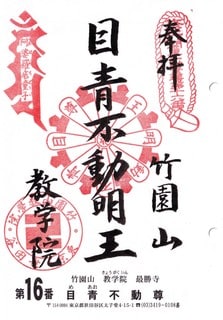
・御朱印尊格:目青不動明王 関東三十六不動尊霊場第16番印判 書置(筆書)
〔関東三十六不動尊霊場第16番の御朱印/御朱印帳〕
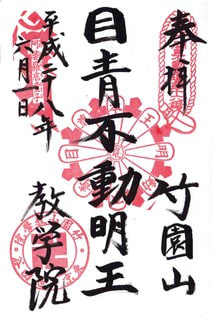
・御朱印尊格:目青不動明王 関東三十六不動尊霊場第16番印判 直書(筆書)
〔大東京百観音霊場第54番の御朱印〕
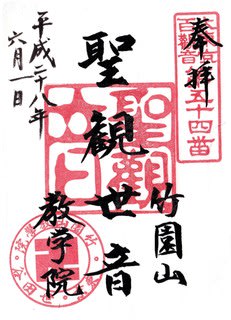
・御朱印尊格:聖観世音 大東京百観音霊場第54番印判 書置(筆書)
〔世田谷三十三ヶ所観音霊場第15番の御朱印〕
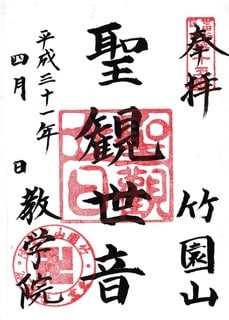
・御朱印尊格:聖観世音 世田谷区内第15番印判 直書(筆書)
※御本尊の御朱印は不授与です。
■ 太子堂八幡神社


公式Web
世田谷区太子堂5-23-5
御祭神:誉田別尊
旧社格:村社
元別当:聖王山 圓泉寺(太子堂)
授与所:境内授与所
御朱印揮毫:太子堂八幡神社 印判
※月替わりの絵御朱印で有名。
■ 太子堂弁財天社

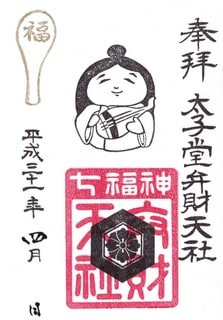
世田谷区太子堂5-23-5
御祭神:弁財天
太子堂八幡神社境内社
授与所:太子堂八幡神社境内授与所
御朱印揮毫:太子堂弁財天社 印判
■ 松陰神社

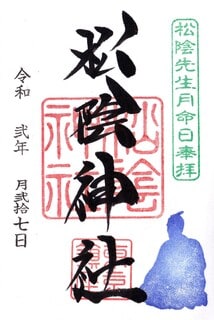
公式Web
世田谷区若林4-35-1
御祭神:吉田寅次郎藤原矩方命
旧社格:府社
授与所::境内授与所
御朱印揮毫:松陰神社 直書(筆書)(27日月命日御朱印)
■ 日輪山 薬王院 西澄寺

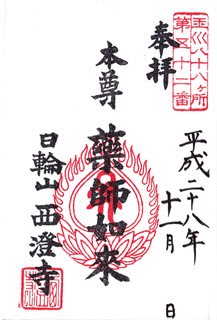
世田谷区下馬2-11-6
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所:玉川八十八ヶ所霊場第52番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第16番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第25番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第63番
〔玉川八十八ヶ所霊場第52番の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 薬師如来 玉川八十八ヶ所霊場第52番印判 印判
■ 世田谷山 観音寺(世田谷観音)

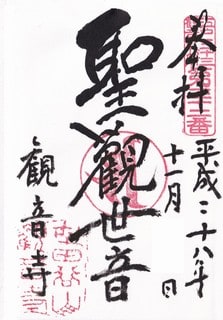
公式Web
世田谷区下馬4-9-4
天台宗系単立 御本尊:聖観世音菩薩
札所:江戸三十三観音札所第32番
〔江戸三十三観音札所第32番の御朱印〕
・御朱印尊格:聖観世音菩薩 江戸三十三観音札所第32番印判 直書(筆書)
■ 駒繋神社

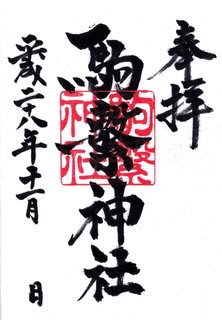
公式Web
世田谷区下馬4-27-26
御祭神:大国主命
旧社格:無格社
元別当:新清山 寿福寺(上目黒)
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:駒繋神社 直書(筆書)
■ 八幡山 宗圓寺

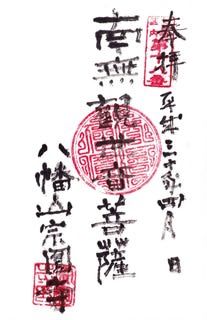
世田谷区上馬3-6-8
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
元司別当:駒留八幡神社(若宮八幡)
札所:世田谷三十三ヶ所観音霊場第18番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第23番
〔世田谷三十三ヶ所観音霊場第18番の御朱印〕
・御朱印尊格:南無観世音菩薩 世田谷区内第18番印判 直書(筆書)
■ 如法山 感應寺

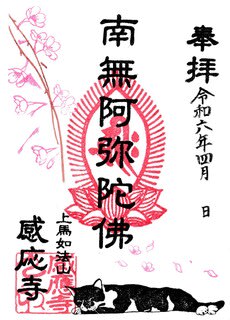
公式Web
世田谷区上馬4-30-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
元司別当:
札所:江戸東方四十八地蔵霊場第41番
〔御本尊の御朱印〕
・御朱印尊格:南無阿弥陀佛 書置(筆書)
■ 駒留八幡神社(若宮八幡)

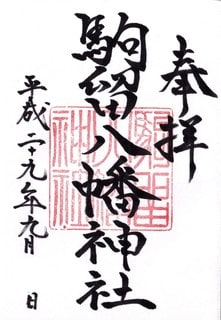
世田谷区上馬5-35-3
御祭神:天照大神、応神天皇
旧社格:村社 旧馬引澤村鎮守
元別当:八幡山 宗圓寺(上馬)
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:駒留八幡神社 直書(筆書)
■ 大澤山 龍雲寺

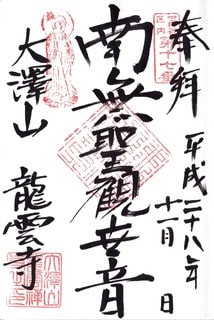
公式Web
世田谷区野沢3-38-1
臨済宗妙心寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所:世田谷三十三ヶ所観音霊場第17番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第24番
〔世田谷三十三ヶ所観音霊場第17番の御朱印〕
・御朱印尊格:聖観世音菩薩 世田谷三十三ヶ所観音霊場第17番印判 直書(筆書)
○玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第24番
※御本尊の御朱印授与は不明。
■ 北澤八幡宮(七澤八社随一正八幡宮)

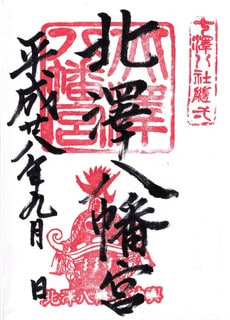
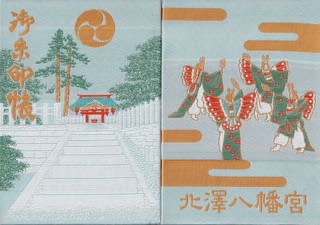
世田谷区代沢3-25-3
御祭神:応神天皇、比売神、神功皇后、仁徳天皇
旧社格:無格社
元別当:八幡山 森巌寺(代沢)
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:北澤八幡宮 直書(筆書)
※御朱印帳頒布あり
■ 八幡山 浄光院 森巌寺

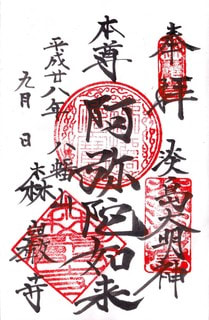
公式Web
世田谷区代沢3-27-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
元司別当:北澤八幡宮(七澤八社随一正八幡宮)
札所:小田急武相三十三観音霊場第3番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第13番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第28番
〔御本尊の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 阿弥陀如来 札番:なし 直書(筆書)
■ 代永山 真勝寺 圓乗院

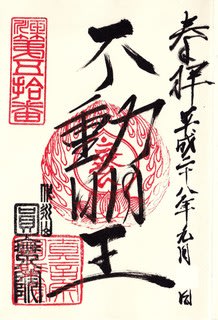
世田谷区代田2-17-3
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
元司別当:代田八幡神社
札所:玉川八十八ヶ所霊場第50番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第12番、玉川北百番霊場第33番
〔玉川八十八ヶ所霊場第50番の御朱印〕
・御朱印尊格:不動明王 玉川八十八ヶ所霊場第50番印判 書置(筆書)
■ 代田八幡神社

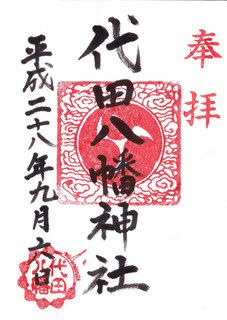
世田谷区代田3-57-1
御祭神:応神天皇
旧代田村鎮守
元別当:代永山 圓乗院(代田)
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:代田八幡神社 直書(筆書)
■ 大原稲荷神社

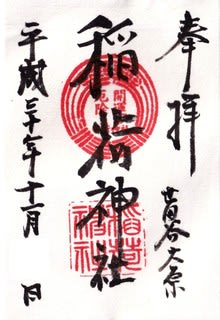
世田谷区大原2-29-21
御祭神:倉稲魂神
大原町、代田町の一部の鎮守
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:稲荷神社 書置(筆書)
■ 代田橋大鳥神社

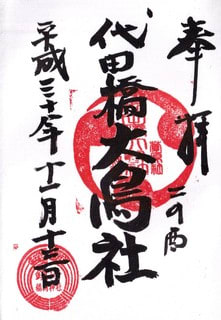
世田谷区大原2-29-21
御祭神:天鳥船大神
大原稲荷神社の境内社
授与所:大原稲荷神社境内社務所
御朱印揮毫:代田橋大鳥神社 直書(筆書)
※酉の市限定の授与
■ 九品山 往生院 浄光寺

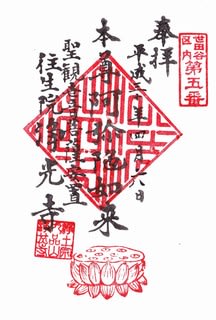
世田谷区世田谷1-38-20
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:世田谷三十三ヶ所観音霊場第5番、玉川北百番霊場第18番
〔世田谷三十三ヶ所観音霊場第5番の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 阿弥陀如来・聖観世音菩薩 世田谷区内第5番印判 印刷?
■ 護国山 天照院 大吉寺


世田谷区世田谷4-7-9
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:世田谷三十三ヶ所観音霊場第4番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第31番
〔御本尊の御朱印〕

・御朱印尊格:阿弥陀如来 札番:なし 書置(筆書)
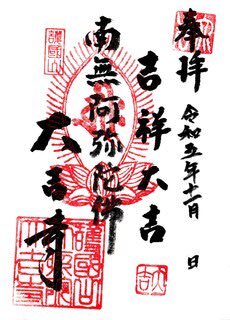
・御朱印尊格:南無阿弥陀佛 札番:なし 書置(筆書)
■ 大悲山 明王寺 円光院

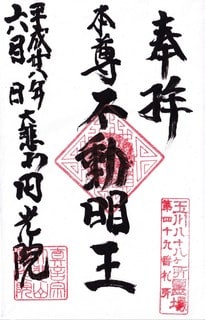
公式Web
世田谷区世田谷4-7-12
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所:玉川八十八ヶ所霊場第49番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第3番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第32番
〔玉川八十八ヶ所霊場第49番の御朱印〕
・御朱印尊格:不動明王 玉川八十八ヶ所霊場第49番印判 直書(筆書)
■ 青龍山 勝国寺

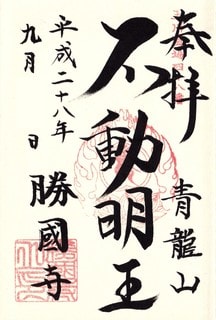
世田谷区世田谷4-27-4
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所:玉川八十八ヶ所霊場第48番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第2番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第33番
〔玉川八十八ヶ所霊場第48番の御朱印〕
・御朱印尊格:不動明王 玉川八十八ヶ所霊場48番印判 直書(筆書)
■ 延命山 勝光院

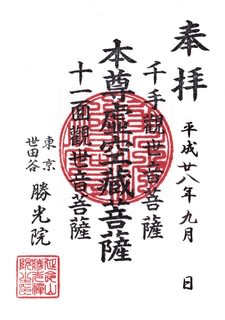
世田谷区桜1-26-35
曹洞宗
御本尊:虚空蔵菩薩
札所:世田谷三十三ヶ所観音霊場第7番、玉川北百番霊場第20番
〔御本尊の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 虚空蔵菩薩 札判:なし 印判
■ 寶樹山 常在寺


世田谷区弦巻1-34-17
日蓮宗
・御首題 直書(筆書)
■ 弦巻神社

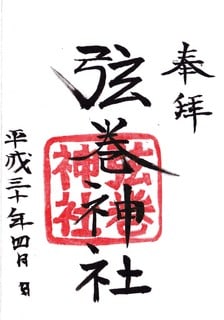
世田谷区弦巻3-18-22
御祭神:宇迦之御魂神、応神天皇、菅原道真公
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:弦巻神社 直書(筆書)
■ 鶴松山 実相院

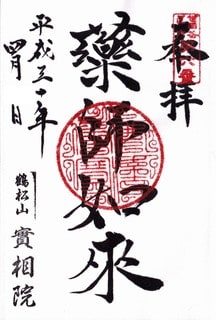
世田谷区弦巻3-29-6
曹洞宗
御本尊:薬師如来
札所:世田谷三十三ヶ所観音霊場第6番、玉川北百番霊場第17番
〔世田谷三十三ヶ所観音霊場第6番の御朱印〕
・御朱印尊格:薬師如来 世田谷区内第6番印判 直書(筆書)
■ 赤堤山 善性寺

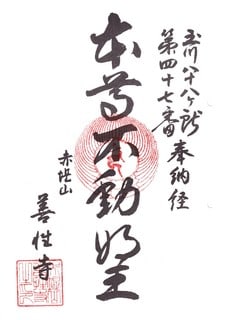
世田谷区豪徳寺1-55-23
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所:玉川八十八ヶ所霊場第47番、玉川北百番霊場第31番
〔玉川八十八ヶ所霊場第47番の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 不動明王 玉川八十八ヶ所霊場第47番印刷 印刷
■ 大谿山 豪徳寺


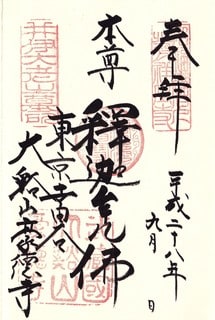
世田谷区豪徳寺2-24-7
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼仏
札所:東京三十三観音霊場第11番、大東京百観音霊場特番7、小田急武相三十三観音霊場特別、世田谷三十三ヶ所観音霊場第1番、玉川北百番霊場第30番
〔御本尊の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 釋迦牟尼佛 札判:なし 直書(筆書)
※霊場札所の御朱印は不授与の模様。
■ 世田谷八幡宮


世田谷区宮坂1-26-3
御祭神:応神天皇(誉田別命)、仲哀天皇、神功皇后
旧社格:郷社 旧世田谷村鎮守
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:世田谷八幡宮 印判
■ 観谷山 常徳院

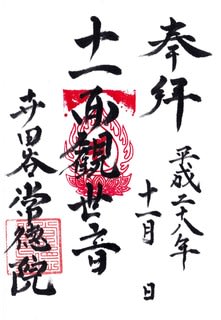
世田谷区宮坂2-1-11
曹洞宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所:世田谷三十三ヶ所観音霊場第8番、玉川北百番霊場第28番
〔御本尊の御朱印〕
・御朱印尊格:十一面観世音 札判:なし 直書(筆書)
■ 経堂山 福昌寺

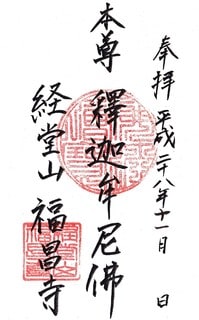
世田谷区経堂1-22-1
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
元司別当:経堂鎮守天祖神社
札所:小田急武相三十三観音霊場第4番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第9番、玉川北百番霊場第29番
〔御本尊の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 釋迦牟尼佛 札判:なし 書置(筆書)
■ 経堂鎮守天祖神社

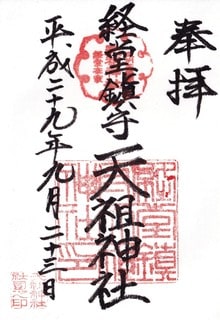
公式Web
世田谷区経堂4-33-2
御祭神:天照大御神、稲荷大神、北野大神
旧社格:村社、旧経堂在家村鎮守
元別当:経堂山 福昌寺(経堂)
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:経堂鎮守 天祖神社 直書(筆書)
■ 稲荷森稲荷神社


公式Web
世田谷区桜丘2-29-3
御祭神:宇迦之御魂神
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:稲荷森稲荷神社 直書(筆書)
■ (赤堤)六所神社


公式Web
世田谷区赤堤2-25-2
御祭神:大国魂命、伊弉冊尊、素戔嗚尊、布留大神、大宮売命
旧社格:村社、旧赤堤村鎮守
元別当:光林山 西福寺(赤堤)
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:六所神社 印判
■ 光林山 持明院 西福寺

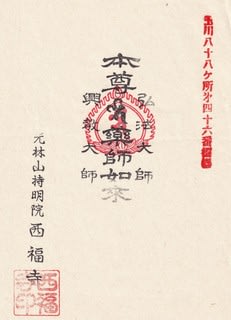
公式Web
世田谷区赤堤3-28-29
真言宗豊山派
御本尊:薬師如来
元司別当:(赤堤)六所神社
札所:玉川八十八ヶ所霊場第46番、京王三十三観音霊場第4番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第11番、玉川北百番霊場第27番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第62番
〔玉川八十八ヶ所霊場第46番の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 薬師如来 玉川八十八ヶ所霊場46番印判 印判 規定用紙
■ (世田谷)菅原神社

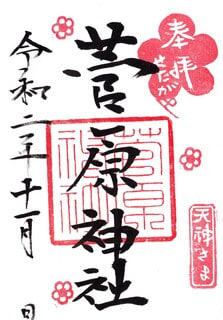
世田谷区松原3-20-16
御祭神:菅原道真公
旧社格:村社、松原地区鎮守
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:菅原神社 直書(筆書)
■ 幽谿山 観音寺 密蔵院


世田谷区桜上水2-24-6
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所:玉川八十八ヶ所霊場第45番、小田急武相三十三観音霊場第5番、京王三十三観音霊場第5番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第10番、玉川北百番霊場第26番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第61番
〔玉川八十八ヶ所霊場第45番の御朱印〕
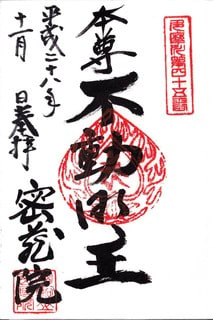
・御朱印尊格:本尊 不動明王 玉川八十八ヶ所霊場第45番印判 直書(筆書)
〔小田急武相三十三観音霊場第5番の御朱印〕

・御朱印尊格:百體観世音 小田急武相三十三観音霊場第5番印判 直書(筆書)
■ 勝利八幡神社

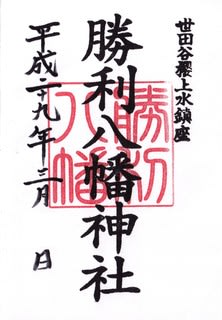
世田谷区桜上水3-21-6
御祭神:誉田別命
旧社格:村社、旧上北沢村鎮守
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:勝利八幡神社 印判
■ 波羅密山 観光院 寶性寺


世田谷区船橋4-39-32
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所:玉川八十八ヶ所霊場第43番、玉川北百番霊場第23番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第58番
〔玉川八十八ヶ所霊場第43番の御朱印〕
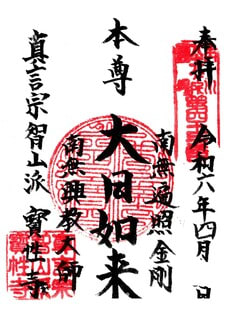
・御朱印尊格:大日如来 南無遍照金剛 南無興教大師 玉川八十八ヶ所霊場第43番印判 書置(筆書)
〔玉川八十八ヶ所霊場第43番の御朱印〕
・御朱印尊格:不動明王 玉川八十八ヶ所霊場第43番印判 直書(筆書)
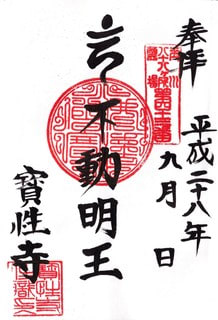
■ 青林山 薬王寺 東覺院

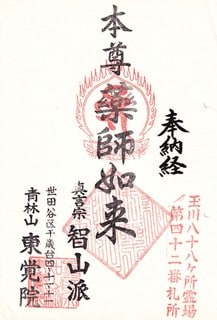
世田谷区千歳台4-11-11
真言宗智山派
御本尊:薬師如来
札所:玉川八十八ヶ所霊場第42番、玉川北百番霊場第24番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第59番、江戸・東京四十四閻魔参り第26番
〔玉川八十八ヶ所霊場第42番の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 不動明王 玉川八十八ヶ所霊場第42番印判 印判 規定用紙
■ 舜栄山 行王院 安穏寺

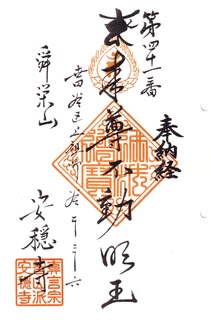
世田谷区上祖師谷2-3-6
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所:玉川八十八ヶ所霊場第41番、○大東京百観音霊場第86番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第57番
〔玉川八十八ヶ所霊場第41番の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 不動明王 玉川八十八ヶ所霊場第41番揮毫 印刷 規定用紙
■ 向旭山 源良院

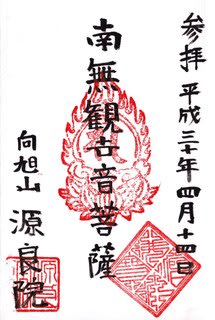
世田谷区北烏山4-10-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
〔観音様の御朱印〕
・御朱印尊格:南無観世音菩薩 札番:なし 直書(筆書)
※非札所につき、常時御朱印授与されているかは不明。
■ 金剛山 悲願寺 多聞院


世田谷区北烏山4-12-1
真言宗豊山派
御本尊:地蔵菩薩
札所:御府内八十八箇所第3番、玉川八十八ヶ所霊場第44番
〔御府内八十八箇所第3番の御朱印/専用納経帳〕
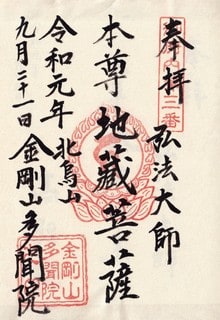
・御朱印尊格:本尊 地蔵菩薩 御府内八十八箇所第3番印判 直書(筆書) 規定用紙
〔御府内八十八箇所第3番の御朱印/御朱印帳〕
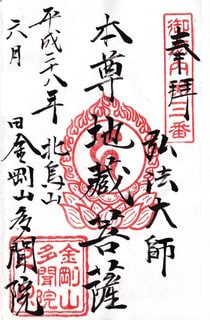
・御朱印尊格:本尊 地蔵菩薩 御府内八十八箇所第3番印判 直書(筆書)
〔玉川八十八ヶ所霊場第44番の御朱印〕
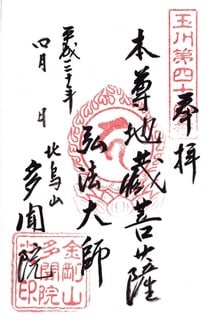
・御朱印尊格:本尊 地蔵菩薩 玉川八十八ヶ所霊場第44番 直書(筆書)
○江戸八十八ヶ所霊場第3番
■ 春陽山 永隆寺


公式Web
世田谷区北烏山4-17-1
法華宗本門流本能寺派
札所:○京王三十三観音霊場第9番
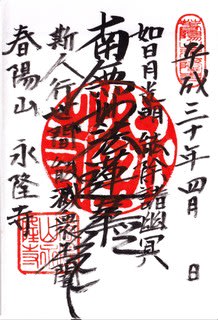
・御首題 直書(筆書)

・御朱印尊格:神保大黒天 (筆書) ※正月のみ
■ 常徳山 玄照寺
世田谷区北烏山4-21-1
日蓮宗

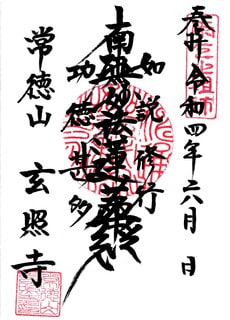
・御首題 直書(筆書)
■ 霊照山 蓮池院 専光寺

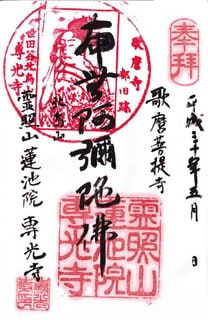
世田谷区北烏山4-28-1
〔御本尊の御朱印〕
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
・御朱印尊格:南無阿彌陀佛 札番:なし 直書(筆書)
※非札所につき、常時御朱印授与されているかは不明。
■ 瑞泉山 高源院


世田谷区北烏山4-30-1
臨済宗大徳寺派
御本尊:釈迦牟尼仏
〔御本尊の御朱印〕
・御朱印尊格:釋迦牟尼佛 札番:なし 直書(筆書)
※非札所につき、常時御朱印授与されているかは不明。
■ 妙祐山 幸龍寺

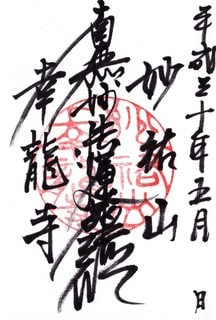
世田谷区北烏山5-8-1
日蓮宗
・御首題 直書(筆書) 江戸十大祖師
■ 一心山 極楽寺 称往院


世田谷区北烏山5-9-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
〔御本尊(御名号)の御朱印〕
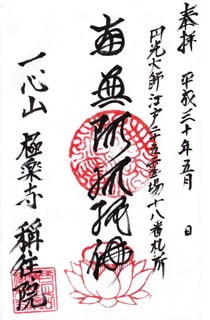
・御朱印尊格:南無阿弥陀佛 直書(筆書)
〔京王三十三観音霊場第8番の御朱印〕
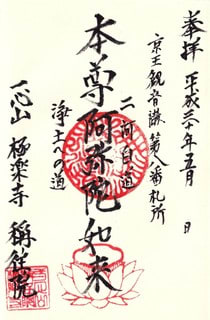
・御朱印尊格:本尊 阿弥陀如来 京王三十三観音霊場第8番 直書(筆書)
○円光大師東都二十五ヶ所霊場第18番、御府内円光大師二十五拝霊場第19番、坂東写東都三十三観音霊場第3番
■ 本覚山 妙壽寺
世田谷区北烏山5-15-1


法華宗本門流
・御首題 書置(筆書)
→ ■ 東京都世田谷区の札所と御朱印(後編)
【 BGM 】
John Jarvis - A Perfect Rain
Dwight Sills - I'll be Right Here
Richard Elliot - Take To The Skies
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 東京都世田谷区の札所と御朱印 (後編)
2024/04/24 追加UP
2021/08/29 追加UP
2020/07/03 追加UP
→ ■ 東京都世田谷区の札所と御朱印(前編)
リストだけUPして3年以上も放置していましたが、神社とその後参拝した寺社を追記し、御朱印と画像を追加します。
日蓮宗・法華宗系の御首題についても追記しました。
ブログの字数制限に引っかかるので、前後2編に分けました。
寺社概要は、追って加えていきます。
東急線 花御朱印巡り 第2弾の御朱印は→ こちらをご覧ください。
--------------------------------------------
■ 深澤神社

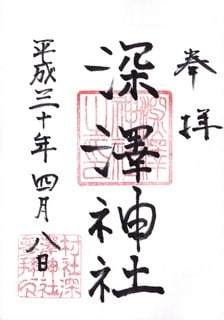
公式Web
世田谷区深沢5-11-1
御祭神:天照皇大神、大山都見尊、倉稲魂命
旧社格:村社
御朱印揮毫:深澤神社 直書(筆書)
■ 薬應山 寳壽院 醫王寺


世田谷区深沢6-14-2
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所:玉川八十八ヶ所霊場第34番、関東九十一薬師霊場第11番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第19番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第9番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第65番
〔玉川八十八ヶ所霊場第34番の御朱印〕
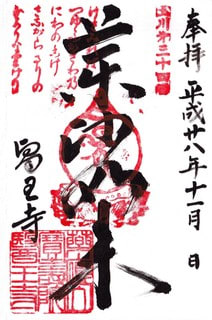
・御朱印尊格:薬師如来 玉川八十八ヶ所霊場34番印判 直書(筆書)
〔関東九十一薬師霊場第11番の御朱印〕
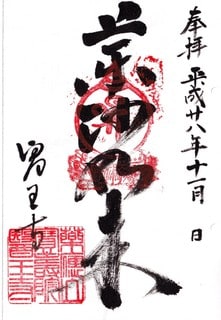
・御朱印尊格:薬師如来 札番:なし 書置 規定用紙
※深沢不動尊の御朱印は不授与
■ 奥澤神社

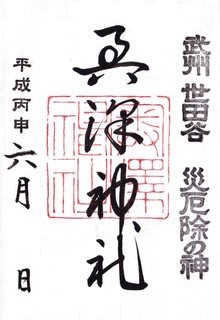
世田谷区奥沢5-22-1
御祭神:誉田別命、倉稲魂之命
旧社格:村社 旧奥澤新田村鎮守
元別当:明楽山 密蔵院(下沼部)
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:奥澤神社 直書(筆書)
■ 九品山 唯在念仏院 浄真寺




公式Web
世田谷区奥沢7-41-3
浄土宗
御本尊:釈迦牟尼如来
札所:大東京百観音霊場第53番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第33番、江戸・東京四十四閻魔参り第24番、閻魔三拾遺第26番、第全国善光寺会
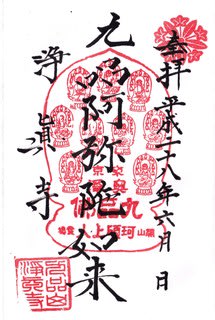
・御朱印尊格:九品阿弥陀如来 札番:なし 直書(筆書)
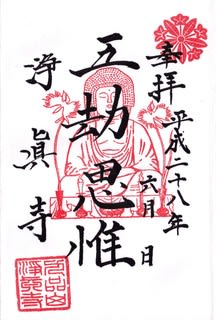
・御朱印尊格:五劫思惟 札番:なし 直書(筆書)
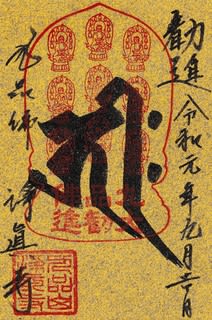
・御朱印尊格:阿弥陀如来の梵字 札番:なし 印判 ※勧進御朱印
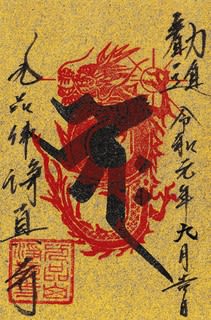
・御朱印尊格:釈迦牟尼如来の梵字 札番:なし 印判 ※勧進御朱印
※御朱印帳頒布あり
※閻魔大王の御朱印は不授与。
※ 私事ですが、こちらは母方の実家の菩提寺なので、子供の頃からなじみがあります。
3年に一度(2014年までは8月16日、以降は5月5日)厳修されるこちらの行事「二十五菩薩来迎会(おめんかぶり)」は、令和2年5月5日の予定でしたが、新型コロナ禍により令和3年に延期となり、更に令和3年5月5日の勤修も中止となっています。
■ 東玉川神社

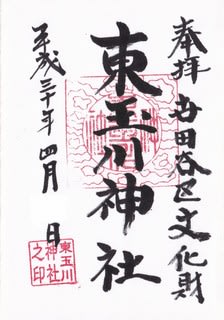
世田谷区東玉川1-32-9
御祭神:建御名方命、大山咋尊
旧社格:無格社
元別当:西光寺(等々力村)
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:東玉川神社 直書(筆書)
■ 松高山 法生院 傳乗寺

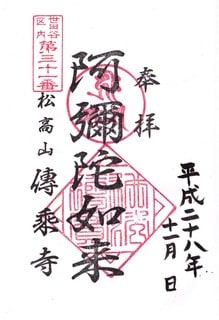
世田谷区尾山台2-10-3
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
元司別当:宇佐神社(尾山台)
札所:世田谷三十三ヶ所観音霊場31番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第16番
〔世田谷三十三ヶ所観音霊場31番の御朱印〕
・御朱印尊格:阿彌陀如来 世田谷三十三ヶ所観音霊場31番印判 印判
■ 宇佐神社

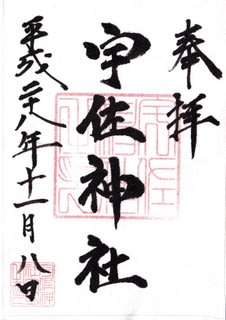
世田谷区尾山台2-11-3
御祭神:応神天皇
旧社格:無格社、旧小山村鎮守
元別当:松高山 傳乗寺(尾山台)
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:宇佐神社 直書(筆書)
■ 致航山 満願寺

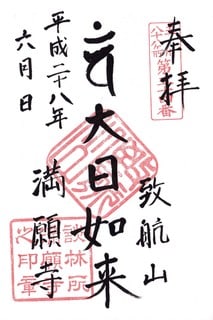
公式Web
世田谷区等々力3-15-1
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所:玉川八十八ヶ所霊場第54番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第29番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第13番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第71番
〔玉川八十八ヶ所霊場第54番の御朱印〕
・御朱印尊格:大日如来 玉川八十八ヶ所霊場第54番印判 直書(筆書)
■瀧轟山 満願寺別院 明王院 (等々力不動尊)


公式Web
世田谷区等々力1-22-47
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所:関東三十六不動尊霊場17番、玉川八十八ヶ所霊場第33番
〔関東三十六不動尊霊場17番の御朱印/専用納経帳〕
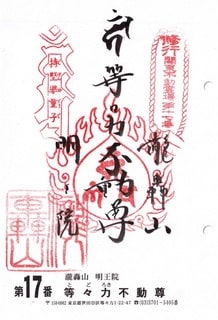
・御朱印尊格:等々力不動尊 関東三十六不動尊霊場17番印判 直書(筆書) 規定用紙
〔関東三十六不動尊霊場17番の御朱印/御朱印帳〕
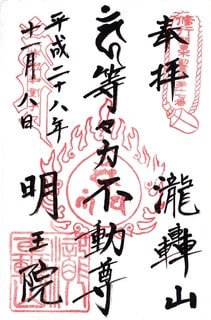
・御朱印尊格:等々力不動尊 関東三十六不動尊霊場17番印判 直書(筆書)
〔玉川八十八ヶ所霊場第33番の御朱印〕
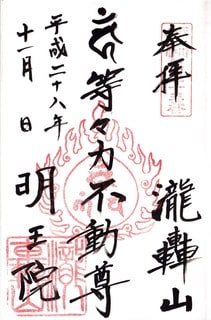
・御朱印尊格:等々力不動尊 玉川八十八ヶ所霊場第33番印判 直書(筆書)
■ 玉川神社

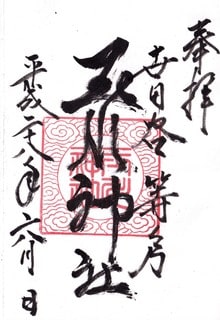
世田谷区等々力3-27-7
御祭神:伊弉諾尊、伊弉冉尊、事解命
旧社格:村社、旧等々力村鎮守
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:玉川神社 直書(筆書)
■ 家岳山 善養院

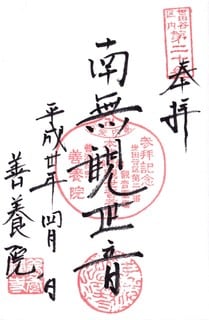
世田谷区新町2-5-12
曹洞宗
御本尊:如意輪観世音菩薩
札所:世田谷三十三ヶ所観音霊場第20番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第8番
〔世田谷三十三ヶ所観音霊場第20番の御朱印〕
・御朱印尊格:南無観世音 世田谷区内第20番印判 直書(筆書)
■ 久富稲荷神社



公式Web
世田谷区新町2-17-1
御祭神:宇迦之魂命、大宮女命、猿田彦命
旧枝郷新町村鎮守
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:久富稲荷神社 直書(筆書)/御朱印帳購入時
※御朱印帳頒布あり。
■ 桜神宮

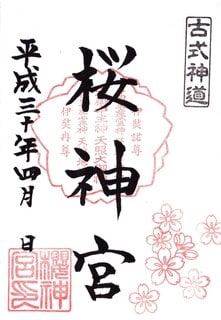
公式Web
世田谷区新町3-21-3
古式神道(教派神道十三派の一派)
御朱印揮毫:桜神宮 直書(筆書)
※御朱印帳頒布あり。
■ 影光山 佛生院 善養寺

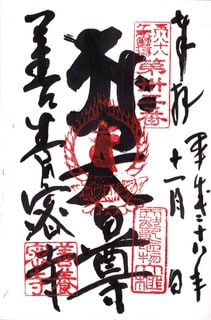
世田谷区野毛2-7-11
真言宗智山派
御本尊:大日如来
元司別当:野毛六所神社
札所:玉川八十八ヶ所霊場第32番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第30番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第15番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第69番
〔玉川八十八ヶ所霊場第32番の御朱印〕
・御朱印尊格:大日尊 玉川八十八ヶ所霊場第32番印判 直書(筆書)
■ 野毛六所神社

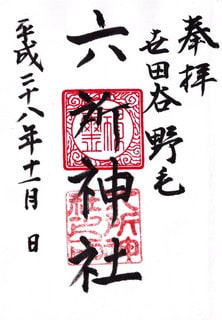
世田谷区野毛2-14-2
御祭神:伊弉諾命、伊弉冉命、天照皇大神、譽田和気命、大山都見命、菅原道真命
旧社格:村社、旧上野毛村・下野毛村鎮守
元別当:影光山 善養寺(野毛)
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:六所神社 直書(筆書)
■ 東陽山 薬王院 金剛寺

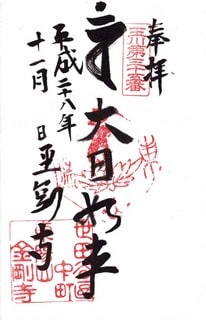
世田谷区中町2-20-11
真言宗智山派
御本尊:大日如来
元司別当:中町天祖神社
札所:玉川八十八ヶ所霊場第35番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第28番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第10番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第67番
〔玉川八十八ヶ所霊場第35番の御朱印〕
・御朱印尊格:大日如来 玉川八十八ヶ所霊場第35番印判 直書(筆書)
■ 中町天祖神社

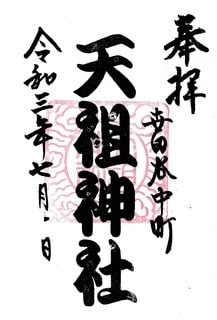
世田谷区中町3-18-1
御祭神:天照皇大神、倉稲魂神
旧社格:無格社、旧野良田村鎮守
元別当:東陽山 金剛寺(中町)
授与所:玉川神社(等々力)社務所
御朱印揮毫:天祖神社 印判
■ 自性山 聖徳院 覚願寺

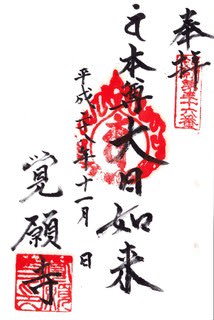
世田谷区上野毛2-15-15
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所:玉川八十八ヶ所霊場第36番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第27番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第11番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第68番
〔玉川八十八ヶ所霊場第36番の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 大日如来 玉川八十八ヶ所霊場第36番印判 直書(筆書)
■ 上野毛稲荷神社

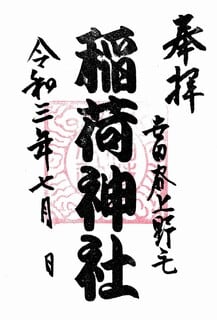
世田谷区上野毛3-22-2
御祭神:倉稲魂神
旧社格:無格社、旧上野毛村鎮守
授与所:玉川神社(等々力)社務所
御朱印揮毫:稲荷神社 印判
■ 獅子山 西光院 行善寺

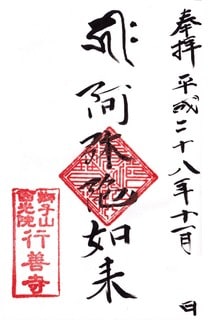
世田谷区瀬田1-12-23
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:玉川六阿弥陀霊場第4番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第26番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第1番
〔御本尊の御朱印〕
・御朱印尊格:阿弥陀如来 札番:なし 直書(筆書)
■ 喜楽山 教令院 慈眼寺

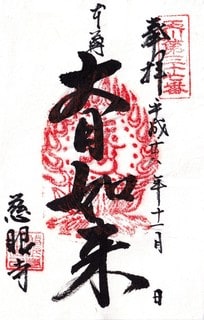
公式Web
世田谷区瀬田4-10-3
真言宗智山派
御本尊:大日如来・虚空蔵菩薩
元司別当:瀬田玉川神社
札所:玉川八十八ヶ所霊場第37番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第24番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第3番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第54番
〔玉川八十八ヶ所霊場第37番の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 大日如来 玉川八十八ヶ所霊場第37番印判 書置(筆書)
■ 瀬田玉川神社

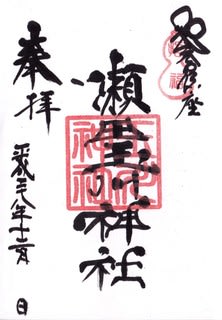
公式Web
世田谷区瀬田4-11-32
御祭神:日本武尊、大己貴命、少彦名命
旧社格:村社
元別当:喜楽山 慈眼寺(瀬田)
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:瀬田玉川神社 直書(筆書)
■ 瘡守稲荷神社

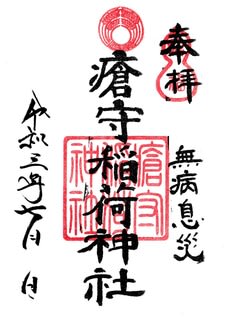
世田谷区瀬田4-32-19
御祭神:倉稲魂命
瀬田玉川神社の飛地境内末社
授与所:瀬田玉川神社社務所
御朱印揮毫:瘡守稲荷神社 直書(筆書)
■ 妙隆山 玉川寺(身延山関東別院)


世田谷区瀬田4-12-4
日蓮宗
・御首題 印判
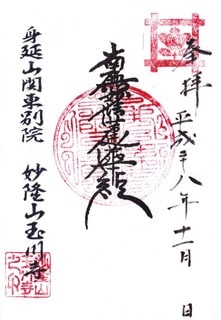
・御朱印 直書(筆書)
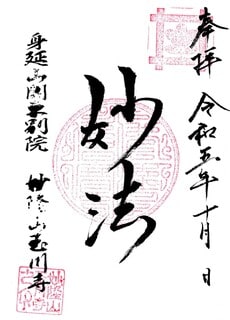
■ 寶泉山 玉真院(玉川大師)

世田谷区瀬田4-13-3
真言宗智山派
御本尊:弘法大師
札所:玉川八十八ヶ所霊場第5番、関東三十三観音霊場第10番、○世田谷三十三ヶ所観音霊場第25番
〔御本尊の御朱印〕
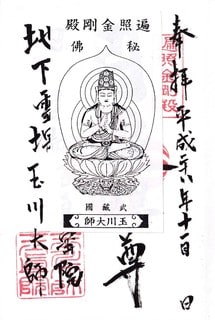
・御朱印尊格:遍照尊 札番:なし 直書(筆書)
〔玉川八十八ヶ所霊場第5番の御朱印〕
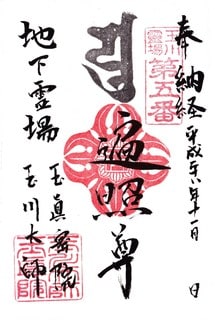
・御朱印尊格:遍照尊 玉川八十八ヶ所霊場第5番印判 直書(筆書)
〔関東三十三観音霊場第10番の御朱印〕
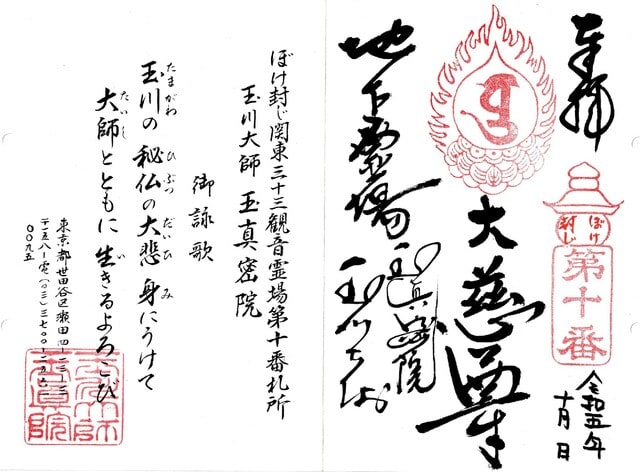
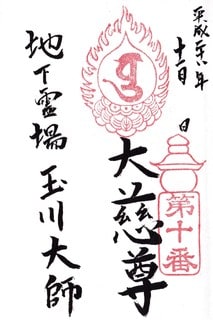
・御朱印尊格:大慈尊 関東三十三観音霊場第10番印判 直書(筆書)
■ 妙日山 妙蓮寺 両親閣東京別院(敬親玉川教会)

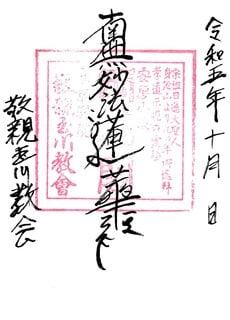
世田谷区瀬田4-13-4
日蓮宗
・御首題 直書(筆書)
■ 如意山 大空閣寺

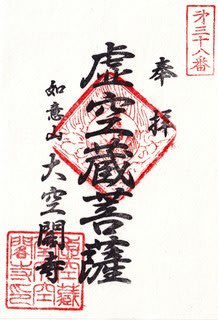
公式Web
世田谷区瀬田4-21-15
真言宗豊山派
御本尊:虚空蔵菩薩
札所:玉川八十八ヶ所霊場第38番、○世田谷三十三ヶ所観音霊場第23番
〔玉川八十八ヶ所霊場第38番の御朱印〕
・御朱印尊格:虚空蔵菩薩 玉川八十八ヶ所霊場第38番印判 書置(筆書)
■ 用賀神社

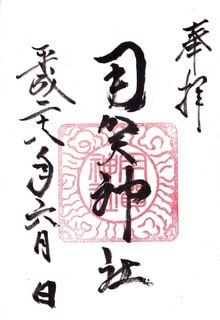
世田谷区用賀2-16-26
御祭神:天照大神、応神天皇、仲哀天皇、神功皇后
旧社格:村社、旧用賀村鎮守
元別当:瑜伽山 眞福寺(用賀)
授与所:境内社務所 or 玉川神社?
御朱印揮毫:用賀神社 直書(筆書)
■ 瑜伽山 眞如院 眞福寺


公式Web
世田谷区用賀4-14-4
真言宗智山派
御本尊:大日如来
元司別当:用賀神社
札所:玉川八十八ヶ所霊場第39番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第21番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第66番
〔玉川八十八ヶ所霊場第39番の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 大日如来 玉川八十八ヶ所霊場第39番印判 直書(書置)規定用紙
■ 祟鎮山 観音院 無量寺

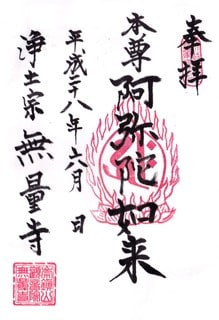
世田谷区用賀4-20-1
浄土宗
御本尊:三尊阿弥陀如来
札所:世田谷三十三ヶ所観音霊場第22番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第5番
〔御本尊の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 阿弥陀如来 札判:なし 直書(筆書)
■ 岡本山 安養院 長円寺

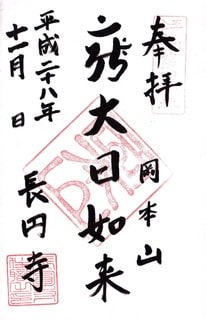
世田谷区岡本1-20-1
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所:玉川八十八ヶ所霊場第40番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第4番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第55番
〔玉川八十八ヶ所霊場第40番の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 大日如来 玉川八十八ヶ所霊場第40番印判 直書(筆書)
※現在無住のようです。等々力の満願寺で拝受できます。
■ 鎌田山 地蔵寺 吉祥院

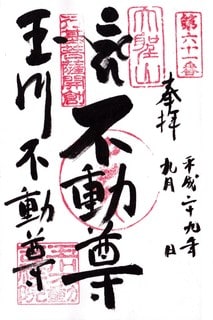
世田谷区鎌田4-11-18
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所:玉川八十八ヶ所霊場第61番、玉川北百番霊場第14番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第56番
〔玉川八十八ヶ所霊場第61番の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 大日如来 玉川八十八ヶ所霊場第61番印判 直書(筆書)
※ご不在気味のようです。
■ 成城山 耕雲寺

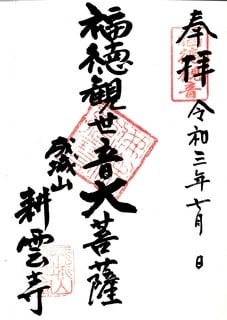
公式Web
世田谷区砧7-12-22
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
〔福徳観世音大菩薩の御朱印〕
・御朱印尊格:福徳観世音大菩薩 直書(筆書)
■ 東光山 妙法寺

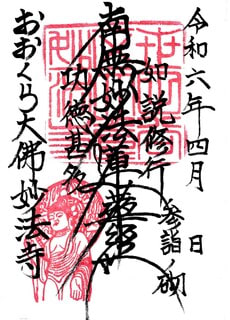
世田谷区大蔵5-12-3
日蓮宗
・御首題 直書(筆書)
■ 永劫山 華林院 慶元寺


世田谷区喜多見4-17-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:多摩川三十四観音霊場第4番、玉川六阿弥陀霊場第2番、小田急武相三十三観音霊場第6番、玉川北百番霊場第10番
〔御本尊の御朱印〕
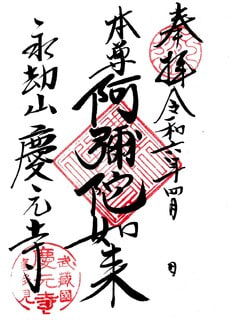
・御朱印尊格:阿弥陀如来 直書(筆書)
〔多摩川三十四観音霊場第4番の御朱印〕
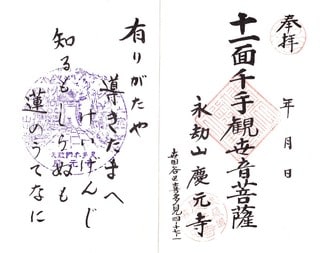
・御朱印尊格:十一面千手観世音菩薩 多摩川三十四観音霊場第4番 印刷 規定用紙
■ (喜多見)氷川神社

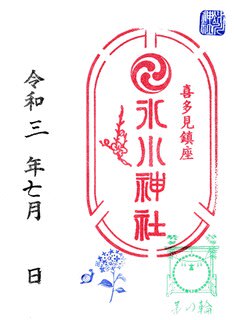
公式Web
世田谷区喜多見4-26-1
御祭神:素戔鳴尊、天照大神、稲田姫命
旧社格:郷社、旧喜多見村鎮守
元別当:禱善寺(喜多見)
授与所:境内社務所
未参拝です。御朱印授与情報あり。
■ 長徳山 宝寿院 光伝寺

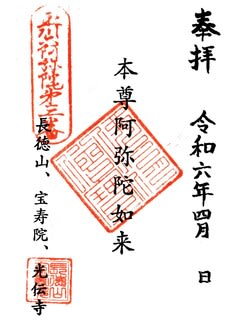
世田谷区喜多見4-17-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
〔御本尊(玉川六阿弥陀霊場第3番)の御朱印〕
・御朱印尊格:阿弥陀如来 玉川六阿弥陀霊場第3番印判
■ 龍寶山 常楽寺 知行院

世田谷区喜多見5-19-2
天台宗
御本尊:薬師如来
札所:関東百八地蔵尊霊場第99番、玉川北百番霊場第12番
〔御本尊の御朱印〕
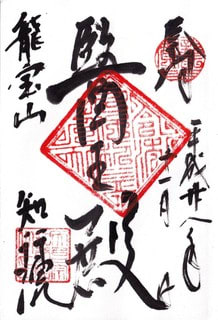
・御朱印尊格:醫王殿 印判:なし(御本尊) 直書(筆書)
〔関東百八地蔵尊霊場第99番の御朱印〕
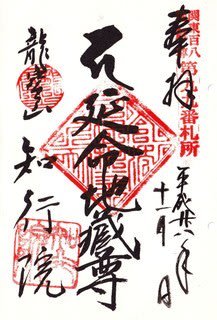
・御朱印尊格:延命地蔵尊 関東百八地蔵尊霊場第99番印判 書置 規定用紙
【 BGM 】
Tim Heintz - We Live For Love
Norman Brown - Just Between Us
Earl Klugh - Whisper and Promises
2021/08/29 追加UP
2020/07/03 追加UP
→ ■ 東京都世田谷区の札所と御朱印(前編)
リストだけUPして3年以上も放置していましたが、神社とその後参拝した寺社を追記し、御朱印と画像を追加します。
日蓮宗・法華宗系の御首題についても追記しました。
ブログの字数制限に引っかかるので、前後2編に分けました。
寺社概要は、追って加えていきます。
東急線 花御朱印巡り 第2弾の御朱印は→ こちらをご覧ください。
--------------------------------------------
■ 深澤神社

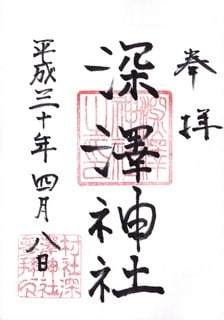
公式Web
世田谷区深沢5-11-1
御祭神:天照皇大神、大山都見尊、倉稲魂命
旧社格:村社
御朱印揮毫:深澤神社 直書(筆書)
■ 薬應山 寳壽院 醫王寺


世田谷区深沢6-14-2
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所:玉川八十八ヶ所霊場第34番、関東九十一薬師霊場第11番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第19番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第9番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第65番
〔玉川八十八ヶ所霊場第34番の御朱印〕
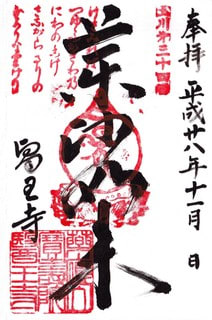
・御朱印尊格:薬師如来 玉川八十八ヶ所霊場34番印判 直書(筆書)
〔関東九十一薬師霊場第11番の御朱印〕
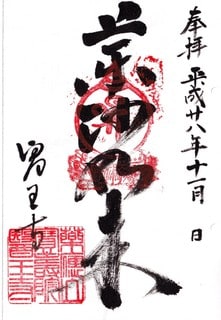
・御朱印尊格:薬師如来 札番:なし 書置 規定用紙
※深沢不動尊の御朱印は不授与
■ 奥澤神社

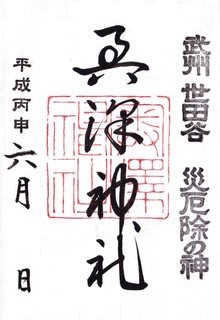
世田谷区奥沢5-22-1
御祭神:誉田別命、倉稲魂之命
旧社格:村社 旧奥澤新田村鎮守
元別当:明楽山 密蔵院(下沼部)
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:奥澤神社 直書(筆書)
■ 九品山 唯在念仏院 浄真寺




公式Web
世田谷区奥沢7-41-3
浄土宗
御本尊:釈迦牟尼如来
札所:大東京百観音霊場第53番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第33番、江戸・東京四十四閻魔参り第24番、閻魔三拾遺第26番、第全国善光寺会
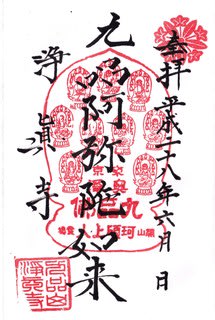
・御朱印尊格:九品阿弥陀如来 札番:なし 直書(筆書)
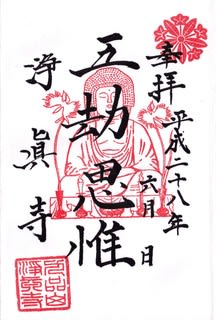
・御朱印尊格:五劫思惟 札番:なし 直書(筆書)
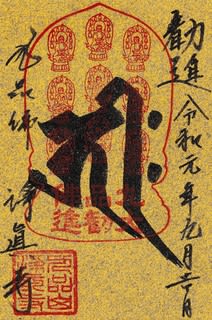
・御朱印尊格:阿弥陀如来の梵字 札番:なし 印判 ※勧進御朱印
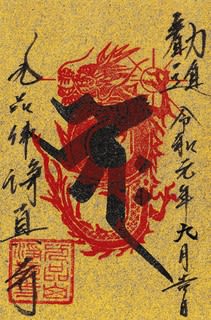
・御朱印尊格:釈迦牟尼如来の梵字 札番:なし 印判 ※勧進御朱印
※御朱印帳頒布あり
※閻魔大王の御朱印は不授与。
※ 私事ですが、こちらは母方の実家の菩提寺なので、子供の頃からなじみがあります。
3年に一度(2014年までは8月16日、以降は5月5日)厳修されるこちらの行事「二十五菩薩来迎会(おめんかぶり)」は、令和2年5月5日の予定でしたが、新型コロナ禍により令和3年に延期となり、更に令和3年5月5日の勤修も中止となっています。
■ 東玉川神社

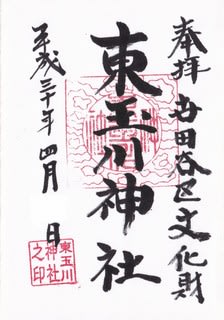
世田谷区東玉川1-32-9
御祭神:建御名方命、大山咋尊
旧社格:無格社
元別当:西光寺(等々力村)
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:東玉川神社 直書(筆書)
■ 松高山 法生院 傳乗寺

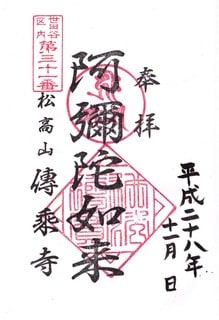
世田谷区尾山台2-10-3
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
元司別当:宇佐神社(尾山台)
札所:世田谷三十三ヶ所観音霊場31番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第16番
〔世田谷三十三ヶ所観音霊場31番の御朱印〕
・御朱印尊格:阿彌陀如来 世田谷三十三ヶ所観音霊場31番印判 印判
■ 宇佐神社

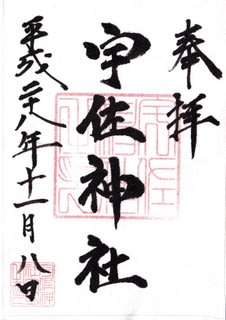
世田谷区尾山台2-11-3
御祭神:応神天皇
旧社格:無格社、旧小山村鎮守
元別当:松高山 傳乗寺(尾山台)
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:宇佐神社 直書(筆書)
■ 致航山 満願寺

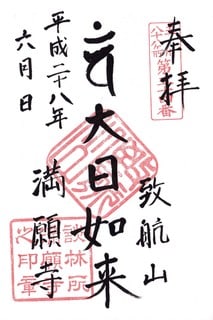
公式Web
世田谷区等々力3-15-1
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所:玉川八十八ヶ所霊場第54番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第29番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第13番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第71番
〔玉川八十八ヶ所霊場第54番の御朱印〕
・御朱印尊格:大日如来 玉川八十八ヶ所霊場第54番印判 直書(筆書)
■瀧轟山 満願寺別院 明王院 (等々力不動尊)


公式Web
世田谷区等々力1-22-47
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所:関東三十六不動尊霊場17番、玉川八十八ヶ所霊場第33番
〔関東三十六不動尊霊場17番の御朱印/専用納経帳〕
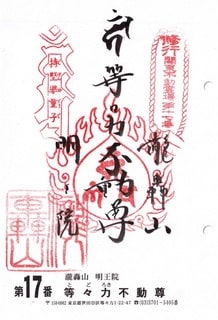
・御朱印尊格:等々力不動尊 関東三十六不動尊霊場17番印判 直書(筆書) 規定用紙
〔関東三十六不動尊霊場17番の御朱印/御朱印帳〕
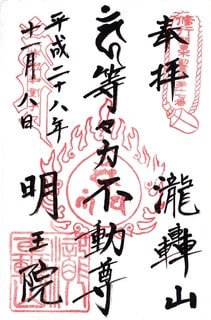
・御朱印尊格:等々力不動尊 関東三十六不動尊霊場17番印判 直書(筆書)
〔玉川八十八ヶ所霊場第33番の御朱印〕
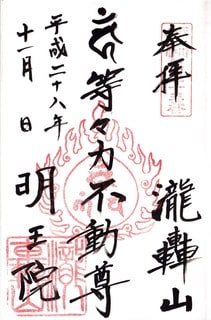
・御朱印尊格:等々力不動尊 玉川八十八ヶ所霊場第33番印判 直書(筆書)
■ 玉川神社

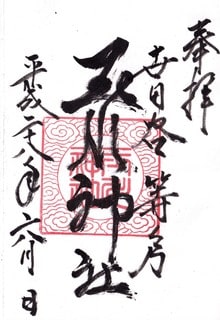
世田谷区等々力3-27-7
御祭神:伊弉諾尊、伊弉冉尊、事解命
旧社格:村社、旧等々力村鎮守
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:玉川神社 直書(筆書)
■ 家岳山 善養院

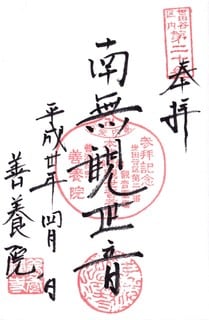
世田谷区新町2-5-12
曹洞宗
御本尊:如意輪観世音菩薩
札所:世田谷三十三ヶ所観音霊場第20番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第8番
〔世田谷三十三ヶ所観音霊場第20番の御朱印〕
・御朱印尊格:南無観世音 世田谷区内第20番印判 直書(筆書)
■ 久富稲荷神社



公式Web
世田谷区新町2-17-1
御祭神:宇迦之魂命、大宮女命、猿田彦命
旧枝郷新町村鎮守
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:久富稲荷神社 直書(筆書)/御朱印帳購入時
※御朱印帳頒布あり。
■ 桜神宮

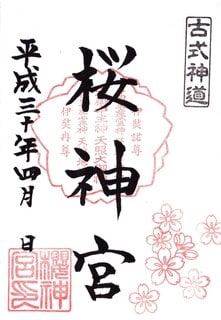
公式Web
世田谷区新町3-21-3
古式神道(教派神道十三派の一派)
御朱印揮毫:桜神宮 直書(筆書)
※御朱印帳頒布あり。
■ 影光山 佛生院 善養寺

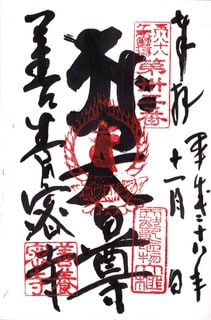
世田谷区野毛2-7-11
真言宗智山派
御本尊:大日如来
元司別当:野毛六所神社
札所:玉川八十八ヶ所霊場第32番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第30番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第15番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第69番
〔玉川八十八ヶ所霊場第32番の御朱印〕
・御朱印尊格:大日尊 玉川八十八ヶ所霊場第32番印判 直書(筆書)
■ 野毛六所神社

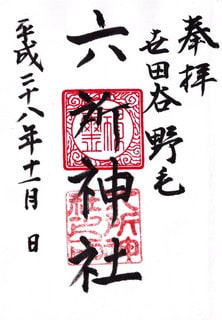
世田谷区野毛2-14-2
御祭神:伊弉諾命、伊弉冉命、天照皇大神、譽田和気命、大山都見命、菅原道真命
旧社格:村社、旧上野毛村・下野毛村鎮守
元別当:影光山 善養寺(野毛)
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:六所神社 直書(筆書)
■ 東陽山 薬王院 金剛寺

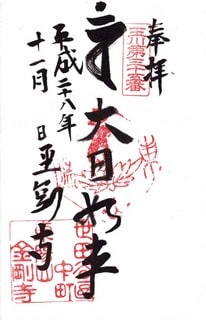
世田谷区中町2-20-11
真言宗智山派
御本尊:大日如来
元司別当:中町天祖神社
札所:玉川八十八ヶ所霊場第35番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第28番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第10番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第67番
〔玉川八十八ヶ所霊場第35番の御朱印〕
・御朱印尊格:大日如来 玉川八十八ヶ所霊場第35番印判 直書(筆書)
■ 中町天祖神社

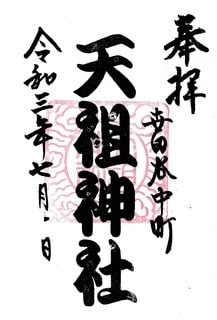
世田谷区中町3-18-1
御祭神:天照皇大神、倉稲魂神
旧社格:無格社、旧野良田村鎮守
元別当:東陽山 金剛寺(中町)
授与所:玉川神社(等々力)社務所
御朱印揮毫:天祖神社 印判
■ 自性山 聖徳院 覚願寺

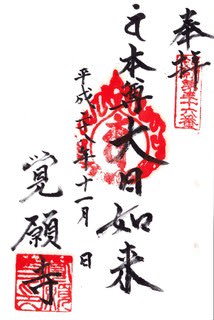
世田谷区上野毛2-15-15
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所:玉川八十八ヶ所霊場第36番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第27番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第11番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第68番
〔玉川八十八ヶ所霊場第36番の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 大日如来 玉川八十八ヶ所霊場第36番印判 直書(筆書)
■ 上野毛稲荷神社

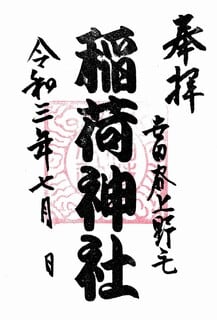
世田谷区上野毛3-22-2
御祭神:倉稲魂神
旧社格:無格社、旧上野毛村鎮守
授与所:玉川神社(等々力)社務所
御朱印揮毫:稲荷神社 印判
■ 獅子山 西光院 行善寺

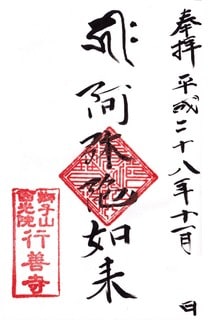
世田谷区瀬田1-12-23
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:玉川六阿弥陀霊場第4番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第26番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第1番
〔御本尊の御朱印〕
・御朱印尊格:阿弥陀如来 札番:なし 直書(筆書)
■ 喜楽山 教令院 慈眼寺

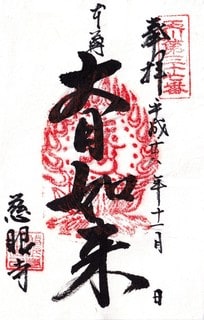
公式Web
世田谷区瀬田4-10-3
真言宗智山派
御本尊:大日如来・虚空蔵菩薩
元司別当:瀬田玉川神社
札所:玉川八十八ヶ所霊場第37番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第24番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第3番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第54番
〔玉川八十八ヶ所霊場第37番の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 大日如来 玉川八十八ヶ所霊場第37番印判 書置(筆書)
■ 瀬田玉川神社

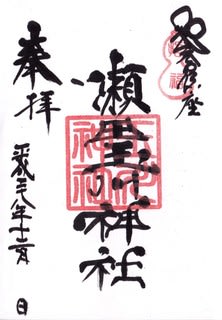
公式Web
世田谷区瀬田4-11-32
御祭神:日本武尊、大己貴命、少彦名命
旧社格:村社
元別当:喜楽山 慈眼寺(瀬田)
授与所:境内社務所
御朱印揮毫:瀬田玉川神社 直書(筆書)
■ 瘡守稲荷神社

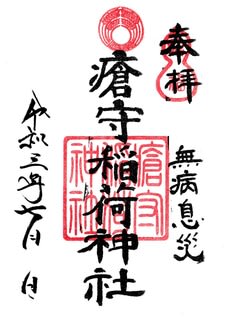
世田谷区瀬田4-32-19
御祭神:倉稲魂命
瀬田玉川神社の飛地境内末社
授与所:瀬田玉川神社社務所
御朱印揮毫:瘡守稲荷神社 直書(筆書)
■ 妙隆山 玉川寺(身延山関東別院)


世田谷区瀬田4-12-4
日蓮宗
・御首題 印判
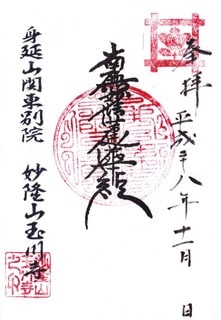
・御朱印 直書(筆書)
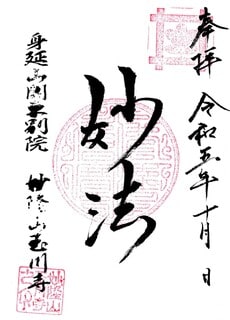
■ 寶泉山 玉真院(玉川大師)

世田谷区瀬田4-13-3
真言宗智山派
御本尊:弘法大師
札所:玉川八十八ヶ所霊場第5番、関東三十三観音霊場第10番、○世田谷三十三ヶ所観音霊場第25番
〔御本尊の御朱印〕
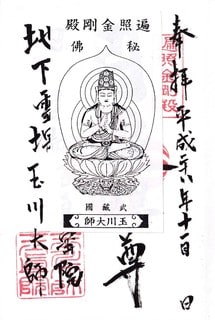
・御朱印尊格:遍照尊 札番:なし 直書(筆書)
〔玉川八十八ヶ所霊場第5番の御朱印〕
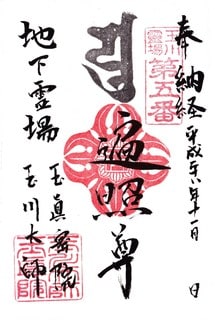
・御朱印尊格:遍照尊 玉川八十八ヶ所霊場第5番印判 直書(筆書)
〔関東三十三観音霊場第10番の御朱印〕
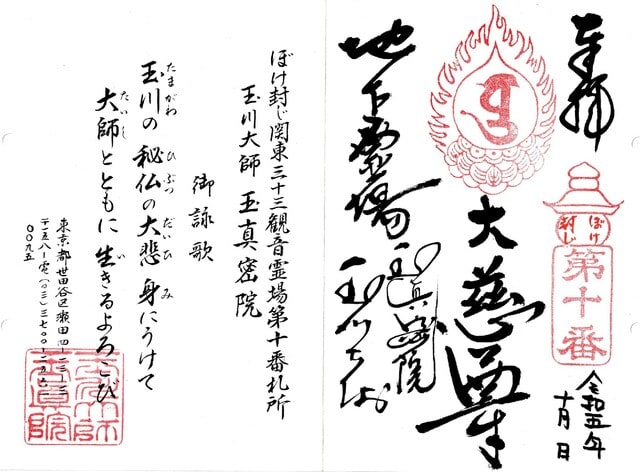
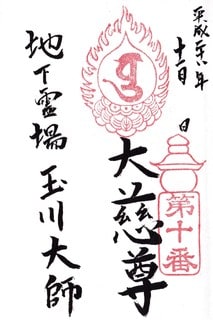
・御朱印尊格:大慈尊 関東三十三観音霊場第10番印判 直書(筆書)
■ 妙日山 妙蓮寺 両親閣東京別院(敬親玉川教会)

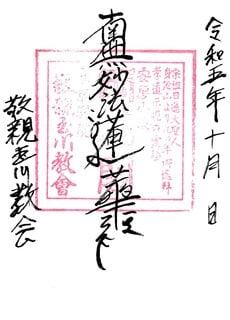
世田谷区瀬田4-13-4
日蓮宗
・御首題 直書(筆書)
■ 如意山 大空閣寺

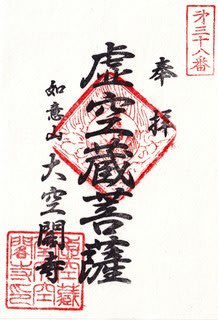
公式Web
世田谷区瀬田4-21-15
真言宗豊山派
御本尊:虚空蔵菩薩
札所:玉川八十八ヶ所霊場第38番、○世田谷三十三ヶ所観音霊場第23番
〔玉川八十八ヶ所霊場第38番の御朱印〕
・御朱印尊格:虚空蔵菩薩 玉川八十八ヶ所霊場第38番印判 書置(筆書)
■ 用賀神社

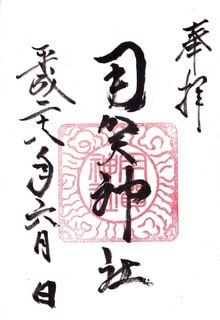
世田谷区用賀2-16-26
御祭神:天照大神、応神天皇、仲哀天皇、神功皇后
旧社格:村社、旧用賀村鎮守
元別当:瑜伽山 眞福寺(用賀)
授与所:境内社務所 or 玉川神社?
御朱印揮毫:用賀神社 直書(筆書)
■ 瑜伽山 眞如院 眞福寺


公式Web
世田谷区用賀4-14-4
真言宗智山派
御本尊:大日如来
元司別当:用賀神社
札所:玉川八十八ヶ所霊場第39番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第21番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第66番
〔玉川八十八ヶ所霊場第39番の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 大日如来 玉川八十八ヶ所霊場第39番印判 直書(書置)規定用紙
■ 祟鎮山 観音院 無量寺

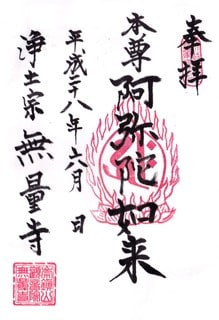
世田谷区用賀4-20-1
浄土宗
御本尊:三尊阿弥陀如来
札所:世田谷三十三ヶ所観音霊場第22番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第5番
〔御本尊の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 阿弥陀如来 札判:なし 直書(筆書)
■ 岡本山 安養院 長円寺

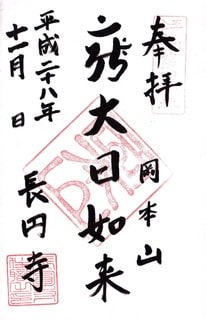
世田谷区岡本1-20-1
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所:玉川八十八ヶ所霊場第40番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第4番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第55番
〔玉川八十八ヶ所霊場第40番の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 大日如来 玉川八十八ヶ所霊場第40番印判 直書(筆書)
※現在無住のようです。等々力の満願寺で拝受できます。
■ 鎌田山 地蔵寺 吉祥院

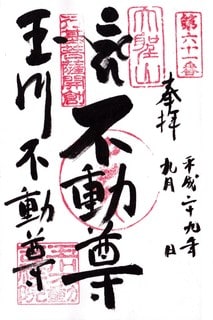
世田谷区鎌田4-11-18
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所:玉川八十八ヶ所霊場第61番、玉川北百番霊場第14番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第56番
〔玉川八十八ヶ所霊場第61番の御朱印〕
・御朱印尊格:本尊 大日如来 玉川八十八ヶ所霊場第61番印判 直書(筆書)
※ご不在気味のようです。
■ 成城山 耕雲寺

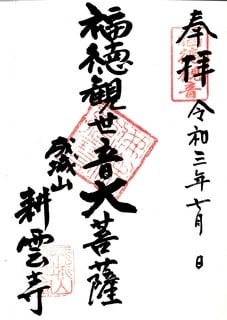
公式Web
世田谷区砧7-12-22
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
〔福徳観世音大菩薩の御朱印〕
・御朱印尊格:福徳観世音大菩薩 直書(筆書)
■ 東光山 妙法寺

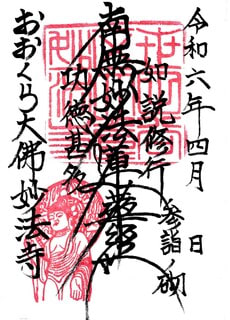
世田谷区大蔵5-12-3
日蓮宗
・御首題 直書(筆書)
■ 永劫山 華林院 慶元寺


世田谷区喜多見4-17-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所:多摩川三十四観音霊場第4番、玉川六阿弥陀霊場第2番、小田急武相三十三観音霊場第6番、玉川北百番霊場第10番
〔御本尊の御朱印〕
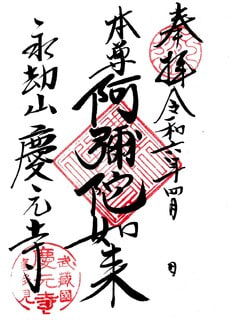
・御朱印尊格:阿弥陀如来 直書(筆書)
〔多摩川三十四観音霊場第4番の御朱印〕
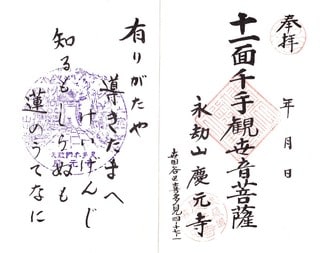
・御朱印尊格:十一面千手観世音菩薩 多摩川三十四観音霊場第4番 印刷 規定用紙
■ (喜多見)氷川神社

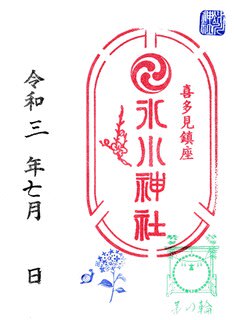
公式Web
世田谷区喜多見4-26-1
御祭神:素戔鳴尊、天照大神、稲田姫命
旧社格:郷社、旧喜多見村鎮守
元別当:禱善寺(喜多見)
授与所:境内社務所
未参拝です。御朱印授与情報あり。
■ 長徳山 宝寿院 光伝寺

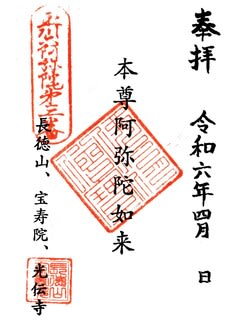
世田谷区喜多見4-17-1
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
〔御本尊(玉川六阿弥陀霊場第3番)の御朱印〕
・御朱印尊格:阿弥陀如来 玉川六阿弥陀霊場第3番印判
■ 龍寶山 常楽寺 知行院

世田谷区喜多見5-19-2
天台宗
御本尊:薬師如来
札所:関東百八地蔵尊霊場第99番、玉川北百番霊場第12番
〔御本尊の御朱印〕
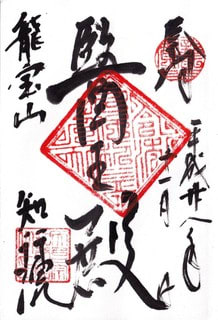
・御朱印尊格:醫王殿 印判:なし(御本尊) 直書(筆書)
〔関東百八地蔵尊霊場第99番の御朱印〕
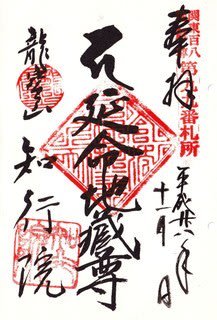
・御朱印尊格:延命地蔵尊 関東百八地蔵尊霊場第99番印判 書置 規定用紙
【 BGM 】
Tim Heintz - We Live For Love
Norman Brown - Just Between Us
Earl Klugh - Whisper and Promises
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 東急線 花御朱印巡り 第2弾
期間は2024年5月6日(祝)まで。残り約1ヶ月です。
これから気候もよくなりますし、いかがですか。
■ ひらひら ひらら - ClariS
■ 桜 - 中村舞子
■ 朧月夜 - 中島美嘉
-------------------------
2024/01/06 UP
令和6年能登半島地震によりお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。
また、被災者救助・支援に入られている皆様のご苦労・ご心労をお察し申し上げるとともに、被災地の一日も早い復旧をお祈り申し上げます。
かたや世界各地の紛争も終息の気配がみえず、日々犠牲者が増えつづけている状況です。
**********
真言宗の勤行式のなかに「祈願文」(きがんぶん・きがんもん)があります。
わが国では、中世の昔から僧侶のみならず在家の人々もこのような大きな願いを営々と託してきたとは、おどろくばかりです。
祈願文
至心発願(ししんほつがん)
天長地久(てんちょうちきゅう)
即身成仏(そくしんじょうぶつ)
密厳国土(みつごんこくど)
風雨順時(ふううじゅんじ)
五穀豊饒(ごこくぶにょう)
万邦協和(ばんぽきょうわ)
諸人快楽(しょにんけらく)
乃至(及以)法界(ないし(ぎゅうい)ほうかい)
平等利益(びょうどうりやく)
(意訳)愛宕山弘正寺様(愛知県岡崎市)の公式Webより引用
----------
真心を持って祈ります。
宇宙が永遠に存在し
すべての人がこの身このままで仏様になり
この世が仏様の世界となり
天地宇宙が順調に進み
農作物が豊かに実り
この世が平和で
人々が幸せであって
世界であまねく
仏様の恵みが平等でありますように
----------
こういう状況だからこそ、世の中の安寧と人々の幸せを願っての寺社巡りは意義あることなのかもしれません。
現在、■ 東急線 花御朱印巡り 第2弾が下記のとおり開催されています。
先般、西上州(群馬県西部)の寺院で企画実施された「ウクライナ難民支援御朱印」とは企画趣旨が異なりますが、東急グループが企業の社会貢献活動としてこの寺社巡り企画を能登半島地震復興支援に役立てる方策はあるのかも。
(ex.全額寄附の「復興支援御朱印」を追加するなど・・・)
東急沿線は生活に余裕のある方も多いですし、情報発信力の高い方も多くお住まいなので、このような方々の賛同を集めればさらに大きな動きとなるかもしれません。
個人の勝手なアイデアで申し訳ないですが、いちおう提起させていただきます。
-------------------------
2023/12/11 UP
先日結願しましたので、とりまとめてみます。



あらためて御朱印尊格をながめると、神仏霊場の趣きがあります。
真言宗の弘法大師御影、禅宗の「南無釋迦牟尼佛」、六字御名号(天台宗ですが)、日蓮宗の御首題も入って宗派的にもバラエティゆたかです。
それにしても、エリアが飛びまくるガイドブックの整理No.には最後まで苦しめられました(笑)
路線別に振っていったのが間違い(?)のもとかとも思いますが、鉄道会社の企画なのでいたしかたないところか・・・。
筆者がエリアを勘案して勝手につけた番号順に、寺社データといただいた御朱印をUPしていきます。
※ ( )はガイドブックの整理No.
※※ 写真 上(左)は東急花御朱印、下(右)は通常御朱印(御首題)。通常御朱印は以前拝受の(現行とことなる)ものもあります。
-------------------------
01.(1).金王八幡宮
東京都渋谷区渋谷3-5-12
御祭神:応神天皇
御朱印尊格:金王八幡宮
渋谷・青山地区総鎮守
元別当:東福寺


02.(12).(青山)熊野神社
東京都渋谷区神宮前2-2-2
御祭神:五十猛命、大屋津姫命、抓津姫命、伊弉冊命
御朱印尊格:青山 熊野神社社号
旧村社、神宮前・北青山総鎮守
元別当:浄性院
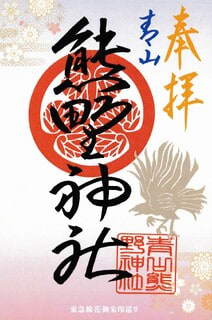

03.(11).金吾龍神社 東京分祠
東京都渋谷区代々木2-26-5 バロール代々木510
御祭神:大元尊神、国常立尊
御朱印尊格:金吾龍神社


04.(10).平田神社
東京都渋谷区代々木3-8-10
御祭神:神霊真柱平田篤胤大人命
御朱印尊格:平田神社(神代文字版もあり)
旧無格社
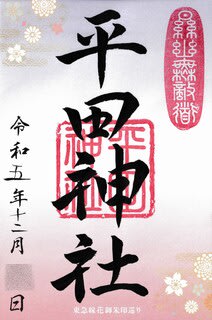
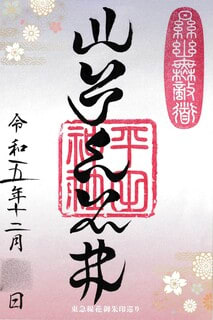
【写真 上(左)】 平田神社の花御朱印(漢字)
【写真 下(右)】 平田神社の花御朱印(神代文字)
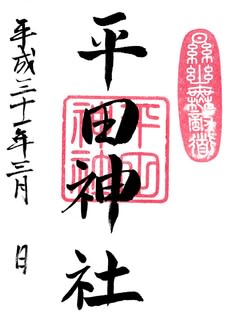
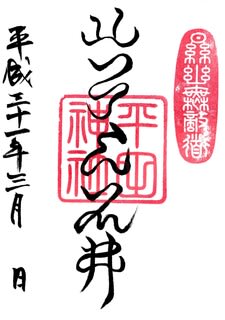
【写真 上(左)】 同 通常御朱印(漢字)
【写真 下(右)】 同 通常御朱印(神代文字)
05.(20).(渋谷)氷川神社
東京都渋谷区東2-5-6
御祭神:素盞嗚尊、稲田姫命、大己貴尊、天照皇大神
御朱印尊格:渋谷氷川神社
旧下渋谷村、豊沢村総鎮守
元別当:寳泉寺
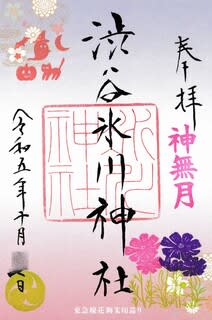

06.(21).(上目黒)氷川神社
東京都目黒区大橋2-16-21
御祭神:素盞嗚尊、天照大御神、菅原道真公
御朱印尊格:上目黒氷川神社
旧上目黒村宿山組の鎮守
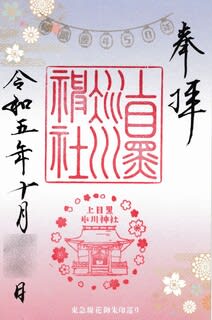
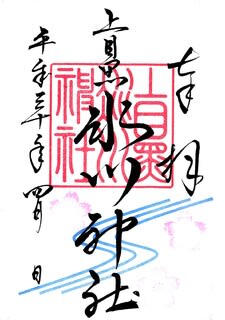
07.(22).世田谷山 観音寺 (世田谷観音)
東京都世田谷区下馬4-9-4
天台宗系単立系
御本尊:聖観世音菩薩
御朱印尊格:大悲殿(江戸観音霊場札番)
札所:江戸三十三観音札所第32番
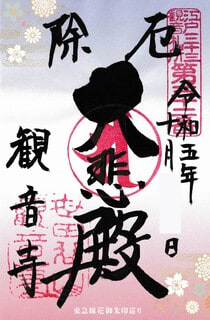
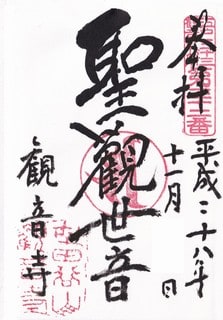
08.(3).駒繋神社
東京都世田谷区下馬4-27-26
御祭神:大国主命
御朱印尊格:駒繋神社
旧無格社、旧下馬引沢村鎮守
元別当:寿福寺
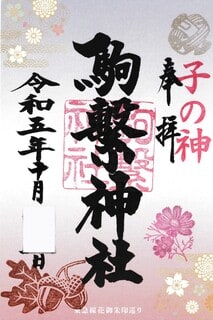
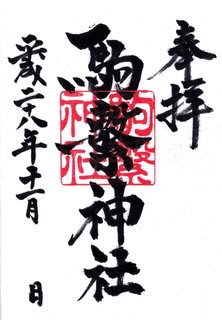
09.(56).寶樹山 常在寺
東京都世田谷区弦巻1-34-17
日蓮宗
御本尊:久遠実成の釈迦牟尼仏
御朱印尊格:御首題(お題目)
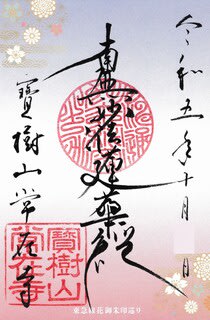

10.(57).大悲山 明王寺 円光院
東京都世田谷区世田谷4-7-12
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
御朱印尊格:本尊不動明王(玉川霊場札番)
札所:玉川八十八ヶ所霊場第49番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第3番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第32番
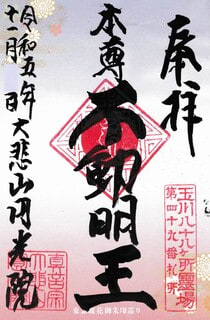
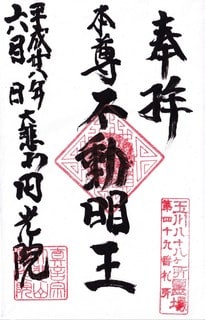
11.(24).寶泉山 玉真院 (玉川大師)
東京都世田谷区瀬田4-13-3
真言宗智山派
御本尊:大日如来
御朱印尊格:弘法大師(御影)
札所:玉川八十八ヶ所霊場第5番、関東三十三観音霊場第10番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第25番
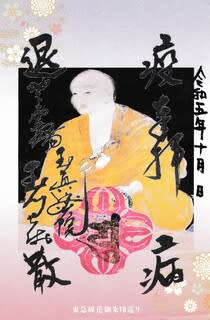
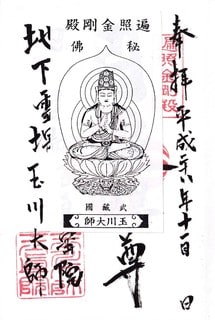
12.(55).(赤堤)六所神社
東京都世田谷区赤堤2-25-2
御祭神:大国魂命、伊弉冊尊、素戔嗚尊、布留大神、大宮売命
御朱印尊格:世田谷赤堤 六所神社
旧村社、旧赤堤村鎮守
元別当:西福寺
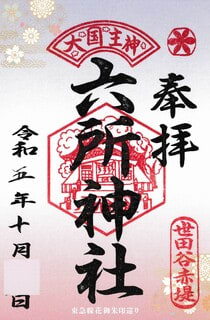

13.(59).(太子堂)八幡神社
東京都世田谷区太子堂5-23-5
御祭神:誉田別命
御朱印尊格:太子堂八幡神社
旧村社
元別当:圓泉寺
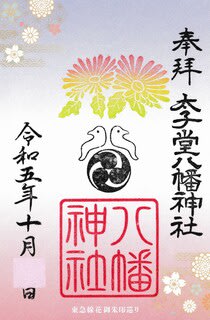

14.(23).用賀神社
東京都世田谷区用賀2-16-26
御祭神:天照大御神、応神天皇、菅原道真公
御朱印尊格:用賀神社
旧村社、旧用賀村鎮守
元別当:真福寺
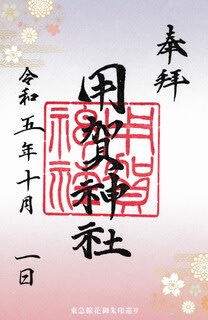
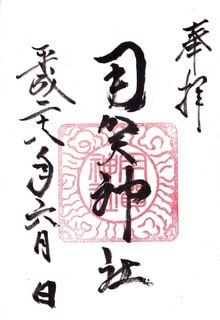
15.(58).松陰神社
東京都世田谷区若林4-35-1
御祭神:吉田寅次郎藤原矩方命
御朱印尊格:松陰神社
旧府社
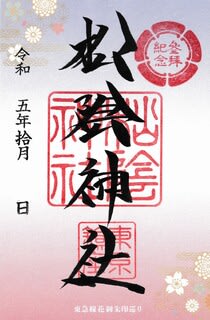
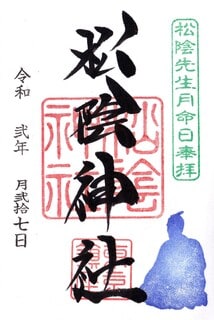
16.(25).瀬田玉川神社
東京都世田谷区瀬田4-11-3
御祭神:日本武尊、大己貴命、少彦名命
御朱印尊格:瀬田玉川神社
旧村社
元別当:慈眼寺
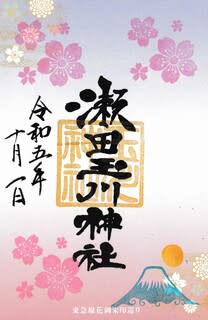
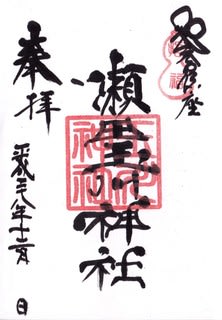
17.(13).松林山 大圓寺(大円寺)
東京都目黒区下目黒1-8-5
天台宗
御本尊:釈迦如来
御朱印尊格:大黒天(山手七福神札番)
札所:山手七福神(大黒天)
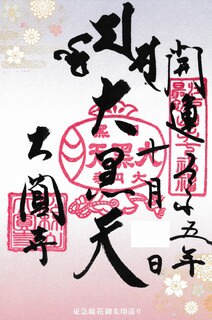
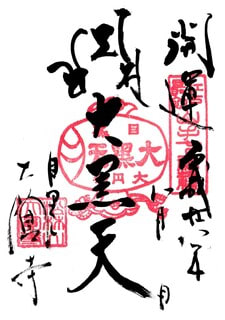
18.(14).不老山 薬師寺 成就院 (蛸薬師)
東京都目黒区下目黒3-11-11
天台宗
御本尊:薬師如来
御朱印尊格:蛸薬師如来
札所:江戸薬師如来霊場三十二ヶ所(25番)

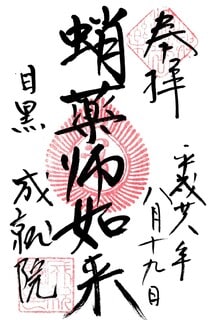
19.(16).霊雲山 称明院 蟠龍寺 (目黒岩屋辨天)
東京都目黒区下目黒3-4-4
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
御朱印尊格:辨財天(山手七福神札番)
札所:山手七福神(辨財天)
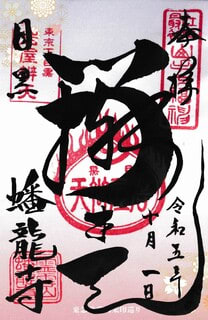
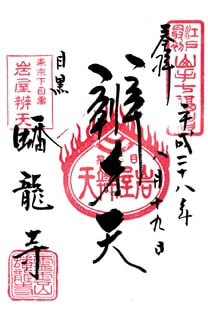
20.(15).天恩山 羅漢寺 (五百羅漢寺)
東京都目黒区下目黒3-20-11
浄土宗系単立
御本尊:釈迦如来
御朱印尊格:五百羅漢尊
札所:江戸・東京四十四閻魔参り第44番、江戸南方四十八地蔵霊場第3番、弁財天百社参り番外30
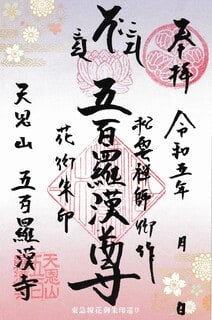
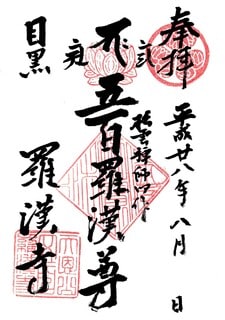
21.(2).實相山 正覚寺
東京都目黒区中目黒3-1-6
日蓮宗
御朱印尊格:御首題(お題目)

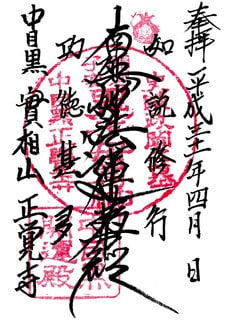
22.(4).(自由が丘)熊野神社
東京都目黒区自由が丘1-24-12
御祭神:速玉之男尊、伊弉冊命、泉津事解之男尊
御朱印尊格:自由が丘 緑が丘 熊野神社
旧村社、緑が丘一帯鎮守
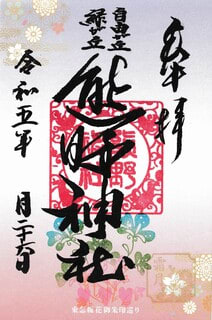
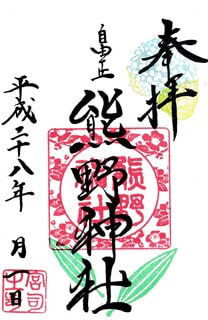
23.(36).(旗岡)八幡神社 (中延八幡宮)
東京都品川区旗の台3-6-12
御祭神:誉田別尊、比売大神、息長帯比売命
御朱印尊格:旗岡八幡神社
旧郷社
元別当:法蓮寺
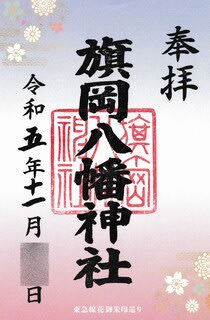
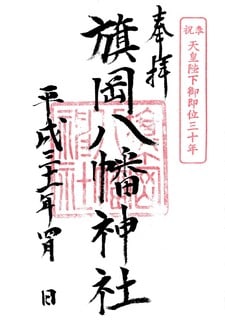
24.(46).(戸越)八幡神社
東京都品川区戸越2-6-23
御祭神:誉田別命
御朱印尊格:戸越八幡神社
旧村社、旧戸越村鎮守
元別当:行慶寺
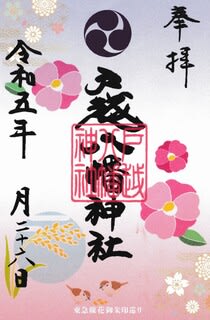
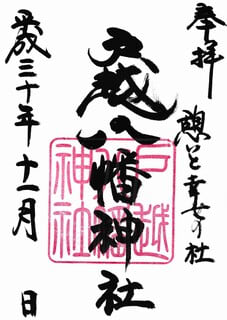
25.(48).帰命山 如来寺 養玉院 (大井の大仏)
東京都品川区西大井5-22-25
天台宗
御本尊:釈迦如来
御朱印尊格:五智如来殿
札所:大東京百観音霊場第41番、荏原七福神(布袋尊)
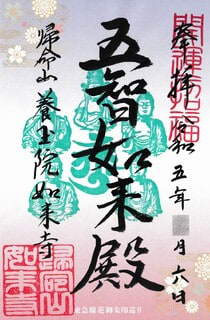
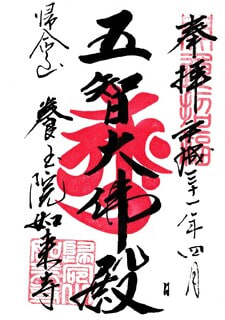
26.(39).大井蔵王権現神社
東京都品川区大井1-14-8
御祭神:蔵王大権現
御朱印尊格:大井蔵王権現神社
大井権現台鎮守
札所:荏原七福神(福禄寿)
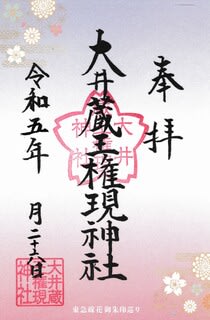

27.(47).居木神社(いるぎ神社)
東京都品川区大崎3-8-20
御祭神:日本武尊
御朱印尊格:居木神社
旧村社、大崎鎮守、旧居木橋村鎮守?
元別当:観音寺

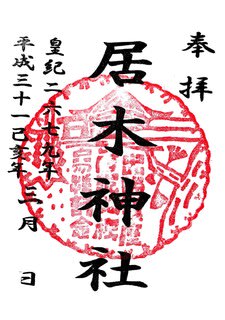
28.(38).(下神明)天祖神社
東京都品川区二葉1-3-24
御祭神:天照大御神、応神天皇、天児屋根命
御朱印尊格:下神明 天祖神社
旧村社、旧蛇窪村(のち旧下蛇窪村)鎮守
元別当:東光寺
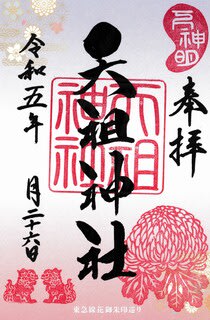
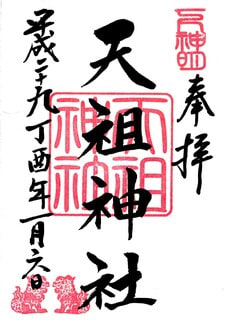
29.(37).蛇窪神社((上神明)天祖神社)
東京都品川区二葉4-4-42
御祭神:天照大御神
御朱印尊格:蛇窪神社
旧村社、旧蛇窪村(のち旧上蛇窪村)鎮守
元別当:長遠寺
札所:荏原七福神(弁財天)
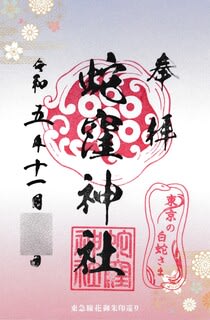

30.(40).明鏡山 善行院 養願寺
東京都品川区北品川2-3-12
天台宗
御本尊:虚空藏菩薩
御朱印尊格:虚空藏尊
札所:東海七福神(布袋尊)
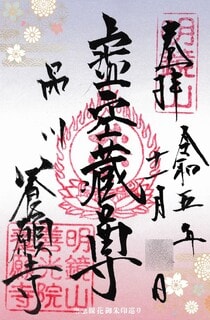
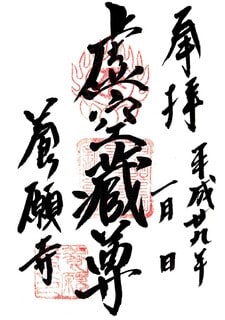
31.(49) .(下丸子)六所神社
東京都大田区下丸子4-16-5
御祭神:大己貴命、伊邪那岐命、素盞嗚命、大宮比売命、瓊々杵命、布留大神
御朱印尊格:六所神社
旧村社、旧下丸子村鎮守
元別当:蓮光院
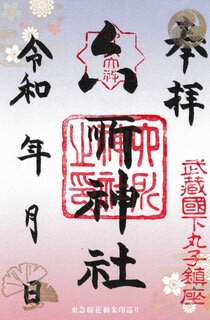
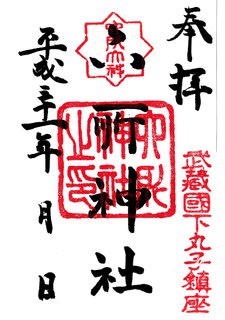
32.(54).(多摩川)諏訪神社
東京都大田区多摩川2-10-22
御祭神:建御名方命、八坂戸売命
御朱印尊格:諏訪神社
多摩川二丁目地区(旧原地区)鎮守
元別当:東福寺
御朱印授与所:徳持神社(大田区池上3-38-17)
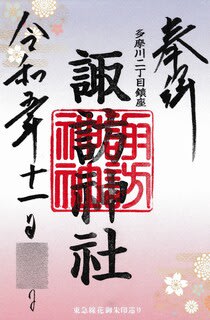
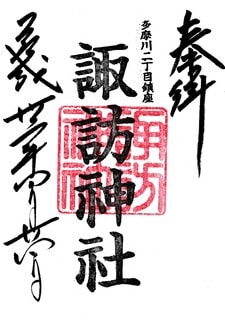
33.(42).長栄山 大国院 池上本門寺
東京都大田区池上1-1-1
日蓮宗大本山
御本尊:三宝尊
御朱印尊格:妙法
札所:池上の寺めぐり-朗師講第6番、東国花の寺百ヶ寺霊場東京第4番
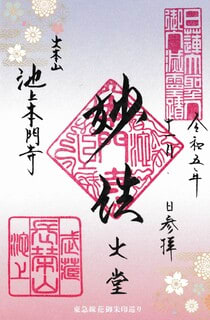
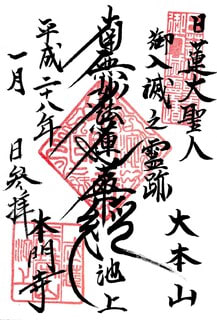
34.(41).徳持神社(御幡山八幡宮)
東京都大田区池上3-38-17
御祭神:誉田別之命
御朱印尊格:徳持神社
旧無格社、旧徳持村鎮守
元別当:徳乗院
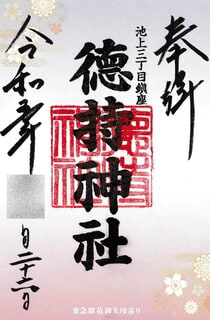

35.(45).(雪ヶ谷)八幡神社
東京都大田区東雪谷2-25-1
御祭神:誉田別命
御朱印尊格:雪ヶ谷八幡神社
旧村社、東雪谷六郷領鎮守
元別当:圓長寺、長慶寺
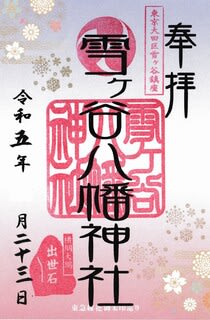
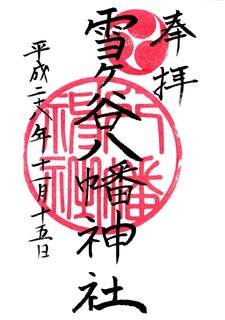
36.(50).新田神社
東京都大田区矢口1-21-23
御祭神:新田義興公
御朱印尊格:新田大明神
旧府社
元別当:真福寺
札所:多摩川七福神(恵比寿)

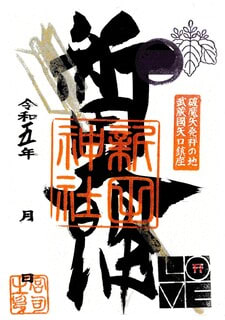
37.(52).十寄神社(とよせ神社)
東京都大田区矢口2-17-28
御祭神:新田義興公の支族および近習将兵
御朱印尊格:十寄神社
旧無格社
札所:多摩川七福神(毘沙門天)
御朱印授与所:徳持神社(大田区池上3-38-17)
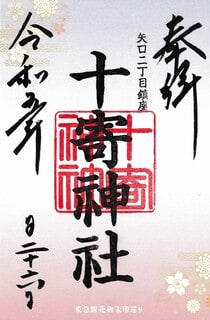
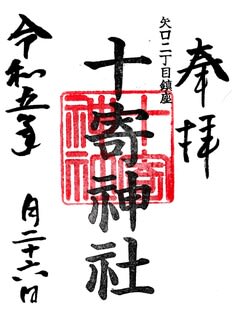
38.(51).福田山 蓮花寺 花光院
東京都大田区矢口2-3-12
真言宗智山派
御本尊:大日如来
御朱印尊格:本尊大日如来(玉川霊場札番)
札所:玉川八十八ヶ所霊場第62番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第25番
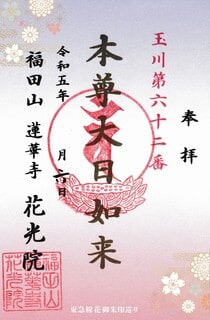
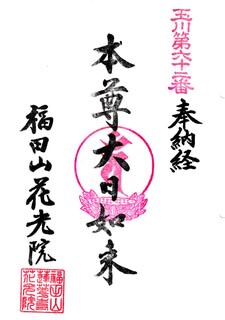
39.(53).(東)八幡神社 (湯坂八幡)
東京都大田区矢口3-17-3
御祭神:誉田別命
御朱印尊格:東八幡神社
旧村社、旧古市場村鎮守
元別当:圓應寺
札所:多摩川七福神(弁財天)
御朱印授与所:徳持神社(大田区池上3-38-17)
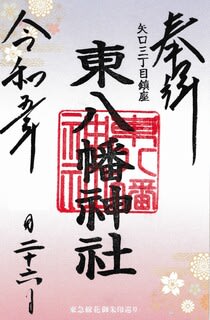

40.(43).(久が原東部)八幡神社
東京都大田区久が原2-18-4
御祭神:誉田別尊
御朱印尊格:久が原東部八幡神社
旧村社、旧久ヶ原村(馬込領)鎮守
御朱印授与所:徳持神社(大田区池上3-38-17)
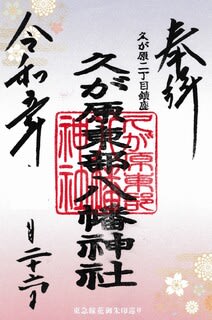
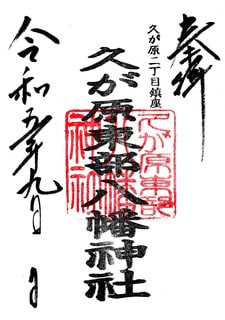
41.(44).(久が原西部)八幡神社
東京都大田区久が原4-2-7
御祭神:誉田別尊
御朱印尊格:久が原西部八幡神社
旧村社、旧久ヶ原村(六郷領)鎮守
元別当:安詳寺
御朱印授与所:徳持神社(大田区池上3-38-17)
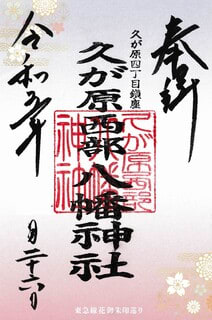
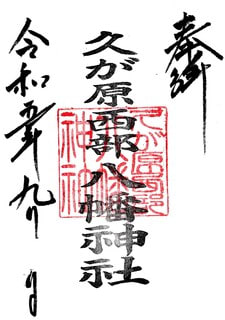
42.(32).(武州柿生)琴平神社
神奈川県川崎市麻生区王禅寺東5-46-15
御祭神:大物主神、天照大御神
御朱印尊格:武州柿生 琴平神社
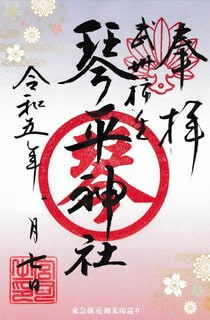

43.(31).長尾山 薬王院 妙楽寺
神奈川県川崎市多摩区長尾3-9-3
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
御朱印尊格:阿弥陀佛
札所:関東百八地蔵尊霊場第83番、小田急沿線花の寺四季めぐり第21番
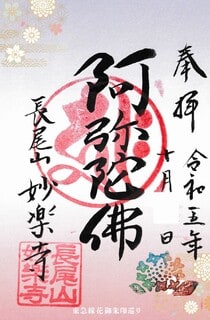
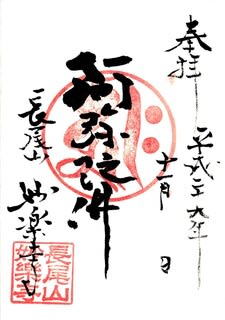
44.(30).神木山 長徳寺 等覚院
神奈川県川崎市宮前区神木本町1-8-1
天台宗
御本尊:不動明王
御朱印尊格:種子(カン)(東国花の寺霊場札番)
札所:関東三十六不動尊霊場第6番、関東九十一薬師霊場第16番、東国花の寺百ヶ寺霊場神奈川第5番、小田急沿線花の寺四季めぐり第16番

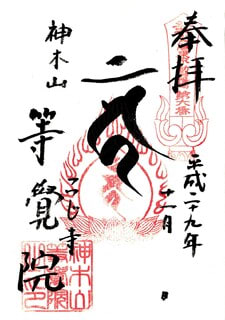
45.(29).高津山 大明王院(身代り不動尊)
神奈川県川崎市高津区下作延692
真言宗醍醐派
御本尊:不動明王
御朱印尊格:身代不動尊(武相不動尊霊場札番)
札所:武相二十八不動尊霊場第2番、武相四十八ヶ所不動尊霊場第1番
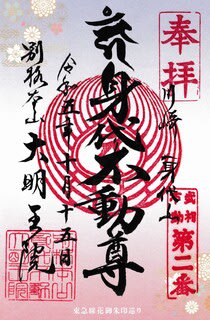
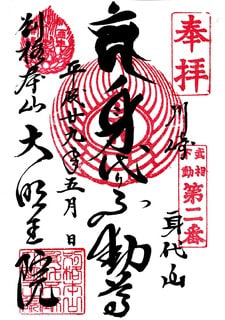
46.(26).興林山 宗隆寺
神奈川県川崎市高津区溝口2-29-1
日蓮宗
御朱印尊格:諸天宝華

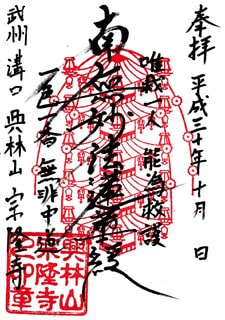
47.(27).医王山 薬師院
神奈川県川崎市高津区新作3-27-1
臨済宗妙心寺派
御本尊:薬師如来
御朱印尊格:薬師瑠璃光(稲毛七薬師霊場札番)
札所:稲毛七薬師霊場第7番
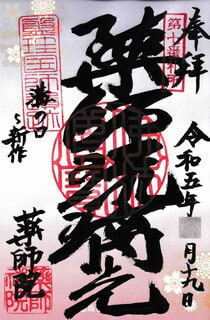
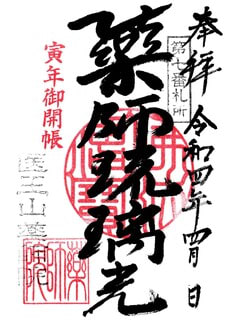
48.(28).松林山 安楽院 明鏡寺
神奈川県川崎市高津区末長2-27-42
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
御朱印尊格:南無阿弥陀佛(六字御名号)
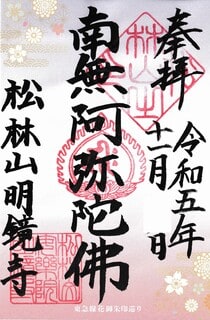
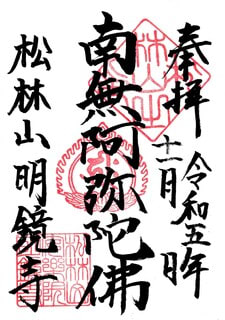
49.(5).(丸子山王)日枝神社
神奈川県川崎市中原区上丸子山王町1-1555
御祭神:大己貴神(大国主神)
御朱印尊格:丸子山王 日枝神社
旧村社、丸子庄総鎮守
元別当:大楽院
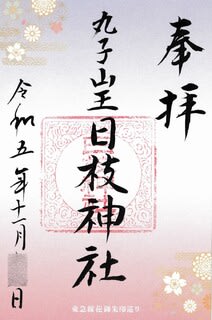
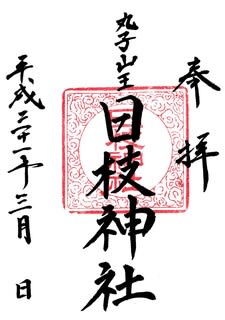
50.(33).神鳥前川神社(しとどまえかわ神社)
神奈川県横浜市青葉区しらとり台61-12
御祭神:日本武尊、弟橘比売命
御朱印尊格:神鳥前川神社
元別当:萬福寺
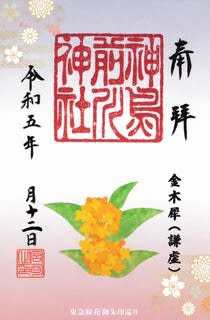

51.(34).慈雲山 大林寺
神奈川県横浜市緑区長津田6-6-24
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
御朱印尊格:南無釋迦牟尼佛
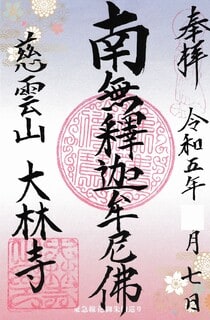
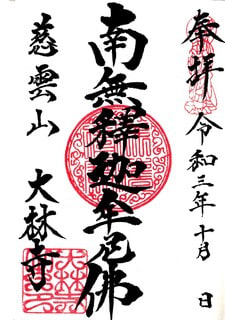
52.(35).薬王山 医王院 福泉寺
神奈川県横浜市緑区長津田町3113
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
御朱印尊格:本尊薬師如来
札所:関東八十八箇所霊場第65番、関東九十一薬師霊場第17番、 武相寅歳薬師如来霊場第23番、富士見楽寿観音霊場第4番
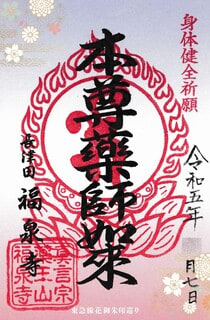
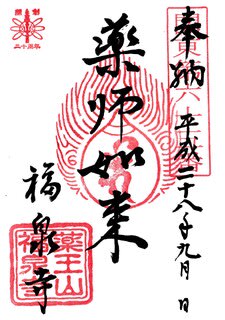
53.(18).歸命山 安國院 無量寺
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町2021
高野山真言宗
御本尊:無量寿如来
御朱印尊格:無量寿
札所:武相寅歳薬師如来霊場第9番
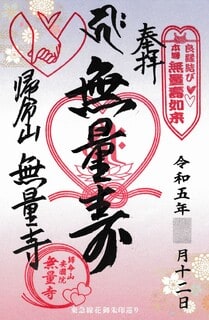
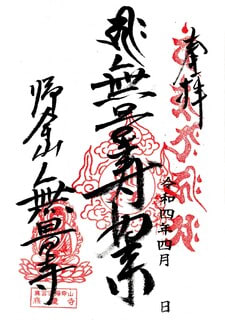
54.(19).佛法山 般若院 東漸寺
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町2240
高野山真言宗
御本尊:不動明王
御朱印尊格:文殊菩薩
札所:関東八十八箇所霊場第67番、武相二十八不動尊霊場第12番、武相寅歳薬師如来霊場第8番、武相四十八ヶ所不動尊霊場第28番

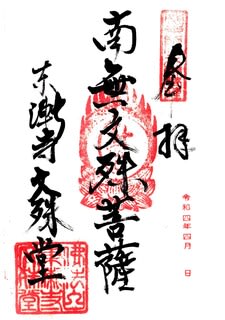
55.(7).菊名神社
神奈川県横浜市港北区菊名6-5-14
御祭神:誉田別命、天照皇大神、日本武尊、木花咲耶姫命、武内宿禰命
御朱印尊格:菊名神社
旧村社
元別当:本乗院、法華寺、長福寺
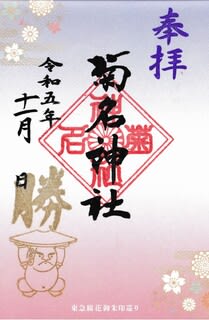
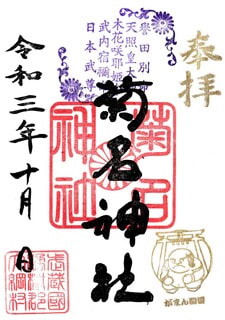
56.(17).八幡山 観音寺
神奈川県横浜市港北区篠原町2777
真言宗智山派
御本尊:十一面観世音菩薩
御朱印尊格:大悲殿 不動明王(2種あり)
札所:玉川八十八ヶ所霊場第82番、新四国東国八十八ヶ所霊場第24番
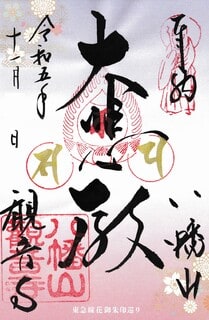
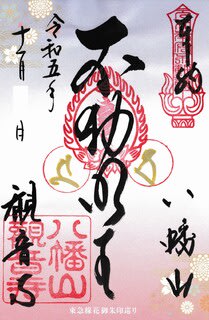
【写真 上(左)】 花御朱印(大悲殿(観世音菩薩))
【写真 下(右)】 花御朱印(不動明王)
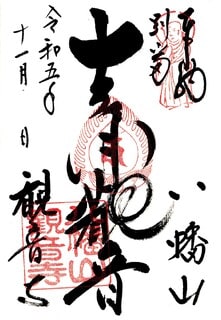
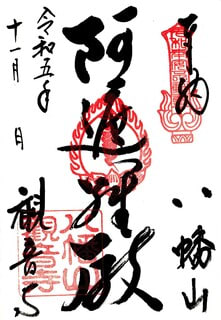
【写真 上(左)】 通常御朱印(十一面観世音菩薩)
【写真 下(右)】 通常御朱印(阿遮羅殿(不動明王))
57.(6) .補陀洛山 安養院 西方寺
神奈川県横浜市港北区新羽町2586
真言宗系単立
御本尊:阿弥陀如来
御朱印尊格:黒阿弥陀
札所:武相二十八不動尊霊場第9番、旧小机領三十三観音霊場第15番、横浜七福神(恵比寿大神)、武相四十八ヶ所不動尊霊場第22番
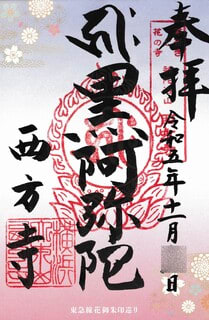
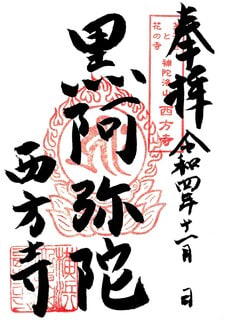
58.(9).開塔山 日輪院 宗興寺
神奈川県横浜市神奈川区幸ヶ谷10-6
曹洞宗
御本尊:聖觀世音菩薩
御朱印尊格:聖觀世音菩薩(小机観音霊場札番)
札所:旧小机領三十三観音霊場第8番、横浜市内三十三観音霊場第15番
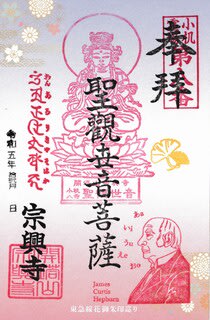
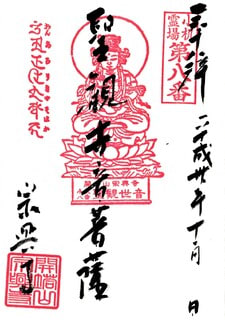
59.(8).吉祥山 芳艸院 慶運寺(浦島寺)
神奈川県横浜市神奈川区神奈川本町18-2
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
御朱印尊格:浦島聖観世音(小机霊場札番)
札所:旧小机領三十三観音霊場第9番
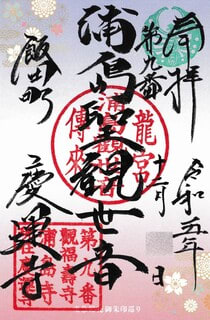

-------------------------
2023/10/03 UP
2023年9月16日(土)~2024年5月6日(祝)、「東急線 花御朱印巡り 第2弾」が開催されています。→公式Web
東急線・東急バス沿線の59の寺社が参画、期間中「花」をテーマとした特別御朱印が授与されています。
第1弾は参加しませんでしたが、今回はトライしてみます。
10/1に専用御朱印帳をゲットしてすこしまわってみたので、感想や気になった点など書いてみます。

■ チラシ
1.寺社選定のコンセプト
↑の参画寺社リストをみてもわかるとおり、寺院宗派は多岐にわたり、特定の霊場をベースにしているものではなさそうです。
かなり渋めの寺社が参画されている一方、沿線を代表するメジャーな寺社が不参画だったりして、寺社選定のコンセプトがよくわかりません。
たとえば、豪徳寺、目黒不動尊(瀧泉寺)、目青不動尊(教学院)、祐天寺、嶺御嶽神社、浄真寺(九品仏)、等々力不動尊、多摩川浅間神社、溝口神社、師岡熊野神社、妙蓮寺、伊勢山皇大神宮などが不参画です。
2.御朱印帳
専用納経帳は3,500円(税込)といいお値段ですが、これがないと専用御朱印を授与されない寺社もありそうなので、よんどころなく購入することになります。
装丁はかなり華奢で傷つきやすいので、ビニールカバーがほしいところか。
(筆者は手元にあった大サイズ御朱印帳用のビニールカバーを装着しました。)
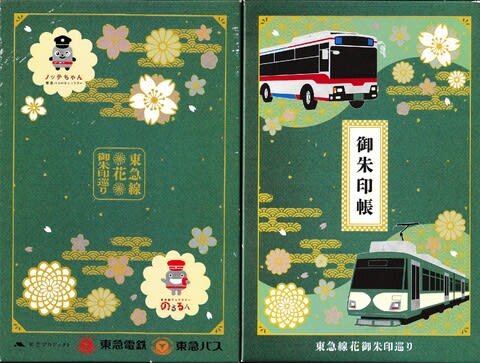
■ 専用御朱印帳
御朱印はすべて書置。
3,500円の高額御朱印帳なので四隅挿込み式を想定しましたが、ごくふつうののり貼り式でした。

■ 四隅挿込み式の例(養平寺/埼玉県熊谷市)
サイズは横12.1㎝×縦18.2㎝で、ほぼ大サイズ御朱印帳規格です。
筆者はワンデーパスセット(1日有効のワンデーパス(特別仕様)、専用御朱印帳、ガイドブック、4,000円(税込))を購入しました。
ワンデーパスは、通常780円で発売されているものの特別仕様です。
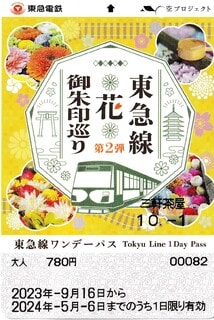
■ 特別仕様のワンデーパス
今回は東急バス沿線寺社の参画が目玉のようなので、鉄道のみの「ワンデーパス」ではなく「東急線・東急バス 一日乗り放題パス」(1,070円)がほしいところ。
4,000円(税込)の高額セットなので、そのくらいの振る舞いはあってもバチはあたらないかと。
3.ガイドブック
おそらくプロのデザイナーが入っているので、全体に綺麗な仕上がり。
でも、機能優先の霊場案内や御開帳手引に慣れている筆者にとって、これは使いにくいものでした。
全体図から沿線図に飛び、そこからさらに「御利益」毎にまとめられている寺社案内に飛ぶのでふた手間かかります。

■ ガイドブック
どうにも使いにくいので、↑のとおり一覧をつくってみました。
なお、ガイドブックで整理No.は振られていますが、これは「札番」とは異なるもののようです。
御朱印対応時間は概ね9時~16時ないし16時半。
17時までの対応は少数で、これは日の短い秋~春の企画ゆえいたしかたないかも。
期間はたっぷりあるし、見どころの多い寺社多数なので、時間をかけてゆったりまわるのがベターかと。
4.御朱印授与料
ガイドブックには明示なしですが、多くの寺社が500円の模様です。(通常御朱印が300円のところも500円)
なので、最大59枚×500円+御朱印帳セット4,000円=33,500円となります。
収まらぬ物価高騰、下がりつづける実質賃金。
しかも10月からのインボイス導入でさらに景況の悪化が懸念されている状況で、寺社巡りに大枚3万円以上もはたいて参加する人がはたしてどれだけいるかどうか・・・。
全寺社の御朱印コンプリートというより、自宅近くの、日頃お参りしている寺社の特別御朱印ゲットというニーズがメインでは?
あるいは、交通費や宿泊費高騰で旅行を諦めた人が、身近なレジャーとしてトライするニーズもあるかも。
なんか、だんだんと家のそばの写し霊場を廻っていた江戸時代に回帰しているような・・・(笑)
【追記】
その後巡拝したところでは、お納め300円の寺社もそれなりにありました。
とくに川崎市内の寺院の多くは300円で、↑ の概算額よりは低額で巡拝できるかと思います。


【写真 上(左)】 上目黒氷川神社の花手水
【写真 下(右)】 渋谷氷川神社の花手水
まぁ、いろいろ書きましたが、趣きある寺社も多いし、御朱印も美しいのでこれはこれでありかと思います。
全59社寺のほとんどの通常御朱印を拝受していますので、これから随時花御朱印と通常御朱印を比較できるかたちでご紹介していきます。
-------------------------
前回(第1弾)の紹介記事がみつかりましたのでリンクします。
期間は2022年4月29日(金)~2022年10月31日(月)
参加対象寺社は下記の48寺社でした。
日蓮宗本山 池上大坊 本行寺、日蓮宗大本山 池上本門寺、長尾山 妙楽寺、興林山 宗隆寺、宗興寺、吉祥山 慶運寺、宮益御嶽神社、松林山 明鏡寺、下神明天祖神社、寶樹山 常在寺、満願寺、たこ薬師 成就院、臥龍山 安養院、名楽山 森立寺 密蔵院、薬王山 医王院 福泉寺、上目黒氷川神社、正覚寺、大崎鎮守 居木神社、摩尼山 延壽院 徳恩寺、菊名神社、高田天満宮、松陰神社、蟠龍寺、赤堤六所神社、桜神宮、神鳥前川神社、浅間神社、新田神社、本牧神社、雪ヶ谷八幡神社、太子堂八幡神社、旗岡八幡神社、世田谷八幡宮、戸越八幡神社、千束八幡神社(洗足池八幡宮)、寶泉山 玉眞院 玉川大師、長谷山 祥泉院、補陀洛山 西方寺、天恩山 五百羅漢寺、松林山 大圓寺、蛇窪神社、身代り不動尊 大明王院 川崎本山、円光院、泉福寺、神木山 等覚院(神木不動)、八幡山観音寺、等々力不動尊、蒲田不動尊 大楽寺
※ 関連記事
■ 東京都世田谷区の札所と御朱印 (前編)
■ 東京都世田谷区の札所と御朱印 (後編)
【 首都圏の私鉄と霊場札所 】
京成電鉄の歴史は成田山新勝寺への参詣客輸送を鏑矢とする説があるように、首都圏の私鉄と著名参詣地との関係は密接なものがありました。
京成は成田山新勝寺や柴又帝釈天、東武本線系は日光・足利・赤城、東武東上線は川越・秩父・三峯、西武は飯能・秩父・三峯、京王は高尾山・八王子・府中、小田急は大山・箱根・江ノ島、京急は川崎大師・三浦など、名だたる参詣地を擁しています。
一方、東急は通勤・通学路線としての色彩が強く、決定的な参詣地はみあたりません。
昭和初期、私鉄各社で沿線の寺院を巡る霊場札所が相次いで設けられたのに対し、東急ではそのような動きがみられなかったのは、このような背景があったからかもしれません。
それでも、格式の高い神社や名刹には事欠きませんので、遅ればせながら(?)このような企画が導入されているのかも。
なお、昭和初期に私鉄が主導した霊場は、現在「幻の霊場」的な存在となっており、現役霊場として活動しているのは西武の武蔵野三十三観音霊場くらいです。
西武は秩父三十四箇所霊場、狭山三十三観音霊場ともにサポート的な動きをしており、沿線で百観音すべての御朱印が揃う、貴重な例となっています。
また、三浦半島の各霊場(観音、不動尊、薬師、地蔵尊など)の御開帳時に京急が後援に入る例もみられます。
※ご参考(別記事「■ 希少な札所印」から一部転載)
■ 小田急武相三十三観音霊場(小田急電鉄)

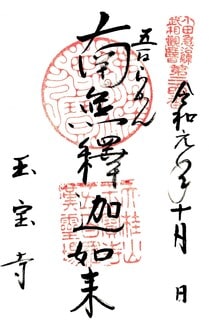

天桂山 王寶寺
小田原市扇町5-1-28
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所:〔小田急武相三十三観音霊場第24番〕
札所本尊:十一面観世音菩薩
昭和11年(1936年)、小田急電鉄が企画し沿線寺院によって札所が選定された観音霊場。
発願は新宿の天龍寺、第4番で経堂、第7番で向ヶ丘遊園、第10番で町田、第13番で海老名、第15番で厚木、第21番で秦野、第24番で小田原に至り、第33番結願はなぜか鎌倉・腰越の満福寺なので、江ノ島線利用の巡拝も兼ねていたと思われます。
宗派は多彩ですが、比較的禅宗が多く歴史ある名刹が目立ちます。
札所33ヶ寺のほか、特別霊場として豪徳寺、伊勢原の日向薬師、大山寺、大雄山最乗寺、藤沢の清浄光寺(遊行寺)のメジャー5寺院を招聘し、豪華な顔ぶれとなっています。
札所一覧は→こちら(「ニッポンの霊場」様)
このような鉄道会社が企画した霊場は、京成の「東三十三観音」、西武の「武蔵野三十三観音」、京王の「京王三十三観音」などがありますが、現役の霊場として活動しているのは「武蔵野三十三観音」のみとみられます。
札所印は稀少ですが、小田原の王寶寺(五百羅漢)でいただけました。
札所本尊は十一面観世音菩薩のようですが、御朱印尊格は御本尊(釈迦如来)でした。
古の観音霊場の場合、よくみられるケースです。
札所印は「小田急沿線武相観音第二十四番」と読めます。
■ 京王三十三観音霊場(京王電鉄)


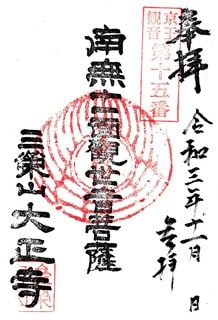
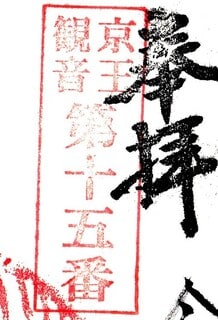
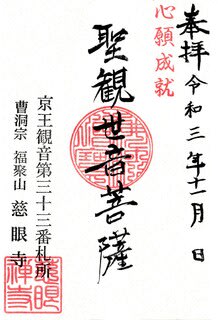
第33番結願寺 福聚山 慈眼寺(八王子市長房町)の御朱印
三栄山 常行院 大正寺
調布市調布ケ丘1-22-1
新義真言宗
御本尊:大日如来
札所:〔京王三十三観音霊場第15番〕、多摩新四国八十八ヶ所霊場第5番、多摩川三十四観音霊場第8番、調布七福神(恵比寿)
札所本尊:十一面観世音菩薩
「ニッポンの霊場」様によると、「観光ブーム+電車利用の促進を目的に、京王電鉄と沿線の寺院によって霊場札所が選定された。」とのこと。
開創時期、開創の経緯など詳細は不明です。
発願は新宿の天龍寺、第6番で下高井戸、第10番で調布、第18番で府中、第24番で八王子に至り、結願は八王子の慈眼寺です。
鉄道系の札所だけあって宗派は変化に富み、多摩川三十四観音、多摩八十八ヶ所、八王子三十三観音、武相卯歳四十八観音との重複札所がかなりあり、京王観音霊場の御朱印を出されている札所もいくつかありますが、どことなく通向けのイメージがある霊場です。
これは、兼務の霊場じたいがかなりマニアックなためと思われます。
発願寺の天龍寺は現在御朱印不授与のようですが、筆者の調べでは33の札所のうち31で、御朱印ないし御首題を授与されている模様です。
(ただし、京王観音霊場の札所印つきは数箇寺。大正寺様のように、現役の兼務札所がありながら、京王観音霊場の札所印をいただける例は希だと思われます。)
布多天神社のそばにある、すこぶる趣きのある寺院です。
京王三十三観音霊場の札所本尊は多摩川三十四観音霊場と同様、立入禁止の庭園おくにある観音堂に御座します。
■ 東三十三観音霊場(京成電鉄)

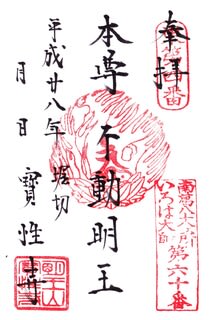
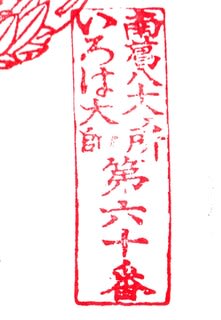

明王山 不動院 寳性寺
葛飾区堀切2-25-21
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所:〔南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第60番〕、〔(京成)東三十三観音霊場第4番〕、荒綾八十八ヶ所霊場第12番、荒川辺八十八ヶ所霊場第62番、隅田川二十一ヵ所霊場第8番
札所本尊:不動明王
南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師/大心講)も比較的古く、御朱印拝受がむずかしい霊場です。
こちらではこの南葛霊場札所印のみならず、希少な東三十三観音霊場(昭和十年京成電車が企画した霊場)の印判もいただけました。
御本尊の不動明王で、「南葛八十八ヶ所いろは大師第六十番」と「東第四番」の印判が別個に捺されています。
こちらは他に荒綾八十八ヶ所霊場12番、荒川辺八十八ヶ所霊場62番、隅田川二十一ヵ所霊場8番の札所も兼ねていますが、霊場を申告せずにお願いしたところ、この御朱印を拝受できました。
なお「南葛八十八ヶ所霊場」は2系統あります。
1.「いろは大師」(大心講)と呼ばれ、発願は葛飾区奥戸の善紹寺、結願は葛飾区奥戸の妙厳寺
2.通称名は不明。発願は江戸川区東小松川の善照寺、結願は江戸川区東小松川の宝積院
(2については、「南葛新四国霊場」と呼ばれることもあるようです。)
一部の札所は重複し、このふたつの南葛霊場の識別をよりむずかしいものにしています。
たとえば、「いろは大師」の葛飾区鎌倉の札所は「南葛八十八ヶ所まんだら六ヶ所参り」として、毎年11月下旬の1日のみ御開帳(というか巡拝)されます。
この6札所のうち、浄光院(1.では第14番、2.では第55番)、輪福寺(1.では第17番、2.では第56番)は札所が重複していますが、「六ヶ所参り」では、1.の「いろは大師」の御朱印が授与されます。
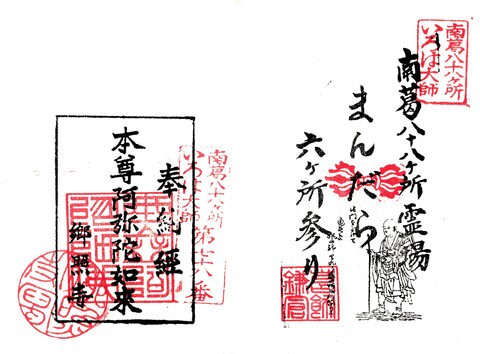
■「南葛八十八ヶ所まんだら六ヶ所参り」の御朱印
どちらも御朱印拝受がむずかしいですが、「1.いろは大師」の方が授与札所は多そうです。(調査中)
【 BGM 】
■ A Perfect Rain - John Jarvis
■ Getaway - Keith Thomas feat. Halston Dare
■ The Time Is Now - Michael Omartian
これから気候もよくなりますし、いかがですか。
■ ひらひら ひらら - ClariS
■ 桜 - 中村舞子
■ 朧月夜 - 中島美嘉
-------------------------
2024/01/06 UP
令和6年能登半島地震によりお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。
また、被災者救助・支援に入られている皆様のご苦労・ご心労をお察し申し上げるとともに、被災地の一日も早い復旧をお祈り申し上げます。
かたや世界各地の紛争も終息の気配がみえず、日々犠牲者が増えつづけている状況です。
**********
真言宗の勤行式のなかに「祈願文」(きがんぶん・きがんもん)があります。
わが国では、中世の昔から僧侶のみならず在家の人々もこのような大きな願いを営々と託してきたとは、おどろくばかりです。
祈願文
至心発願(ししんほつがん)
天長地久(てんちょうちきゅう)
即身成仏(そくしんじょうぶつ)
密厳国土(みつごんこくど)
風雨順時(ふううじゅんじ)
五穀豊饒(ごこくぶにょう)
万邦協和(ばんぽきょうわ)
諸人快楽(しょにんけらく)
乃至(及以)法界(ないし(ぎゅうい)ほうかい)
平等利益(びょうどうりやく)
(意訳)愛宕山弘正寺様(愛知県岡崎市)の公式Webより引用
----------
真心を持って祈ります。
宇宙が永遠に存在し
すべての人がこの身このままで仏様になり
この世が仏様の世界となり
天地宇宙が順調に進み
農作物が豊かに実り
この世が平和で
人々が幸せであって
世界であまねく
仏様の恵みが平等でありますように
----------
こういう状況だからこそ、世の中の安寧と人々の幸せを願っての寺社巡りは意義あることなのかもしれません。
現在、■ 東急線 花御朱印巡り 第2弾が下記のとおり開催されています。
先般、西上州(群馬県西部)の寺院で企画実施された「ウクライナ難民支援御朱印」とは企画趣旨が異なりますが、東急グループが企業の社会貢献活動としてこの寺社巡り企画を能登半島地震復興支援に役立てる方策はあるのかも。
(ex.全額寄附の「復興支援御朱印」を追加するなど・・・)
東急沿線は生活に余裕のある方も多いですし、情報発信力の高い方も多くお住まいなので、このような方々の賛同を集めればさらに大きな動きとなるかもしれません。
個人の勝手なアイデアで申し訳ないですが、いちおう提起させていただきます。
-------------------------
2023/12/11 UP
先日結願しましたので、とりまとめてみます。



あらためて御朱印尊格をながめると、神仏霊場の趣きがあります。
真言宗の弘法大師御影、禅宗の「南無釋迦牟尼佛」、六字御名号(天台宗ですが)、日蓮宗の御首題も入って宗派的にもバラエティゆたかです。
それにしても、エリアが飛びまくるガイドブックの整理No.には最後まで苦しめられました(笑)
路線別に振っていったのが間違い(?)のもとかとも思いますが、鉄道会社の企画なのでいたしかたないところか・・・。
筆者がエリアを勘案して勝手につけた番号順に、寺社データといただいた御朱印をUPしていきます。
※ ( )はガイドブックの整理No.
※※ 写真 上(左)は東急花御朱印、下(右)は通常御朱印(御首題)。通常御朱印は以前拝受の(現行とことなる)ものもあります。
-------------------------
01.(1).金王八幡宮
東京都渋谷区渋谷3-5-12
御祭神:応神天皇
御朱印尊格:金王八幡宮
渋谷・青山地区総鎮守
元別当:東福寺


02.(12).(青山)熊野神社
東京都渋谷区神宮前2-2-2
御祭神:五十猛命、大屋津姫命、抓津姫命、伊弉冊命
御朱印尊格:青山 熊野神社社号
旧村社、神宮前・北青山総鎮守
元別当:浄性院
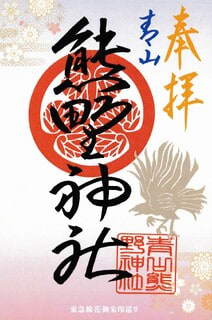

03.(11).金吾龍神社 東京分祠
東京都渋谷区代々木2-26-5 バロール代々木510
御祭神:大元尊神、国常立尊
御朱印尊格:金吾龍神社


04.(10).平田神社
東京都渋谷区代々木3-8-10
御祭神:神霊真柱平田篤胤大人命
御朱印尊格:平田神社(神代文字版もあり)
旧無格社
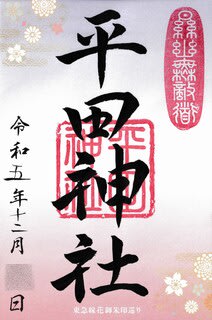
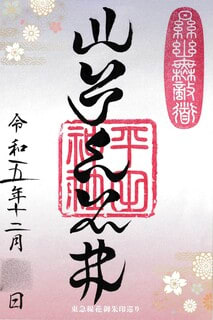
【写真 上(左)】 平田神社の花御朱印(漢字)
【写真 下(右)】 平田神社の花御朱印(神代文字)
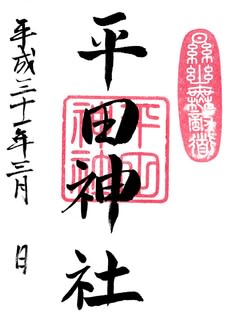
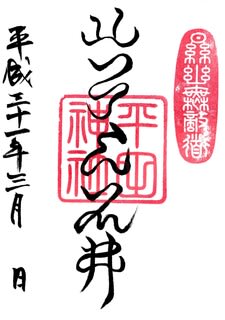
【写真 上(左)】 同 通常御朱印(漢字)
【写真 下(右)】 同 通常御朱印(神代文字)
05.(20).(渋谷)氷川神社
東京都渋谷区東2-5-6
御祭神:素盞嗚尊、稲田姫命、大己貴尊、天照皇大神
御朱印尊格:渋谷氷川神社
旧下渋谷村、豊沢村総鎮守
元別当:寳泉寺
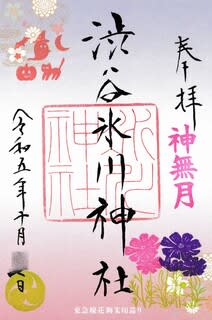

06.(21).(上目黒)氷川神社
東京都目黒区大橋2-16-21
御祭神:素盞嗚尊、天照大御神、菅原道真公
御朱印尊格:上目黒氷川神社
旧上目黒村宿山組の鎮守
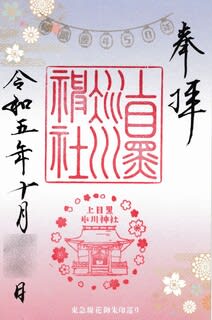
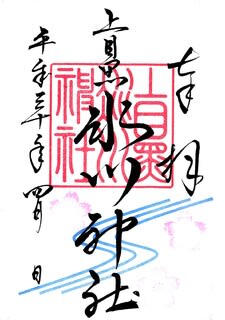
07.(22).世田谷山 観音寺 (世田谷観音)
東京都世田谷区下馬4-9-4
天台宗系単立系
御本尊:聖観世音菩薩
御朱印尊格:大悲殿(江戸観音霊場札番)
札所:江戸三十三観音札所第32番
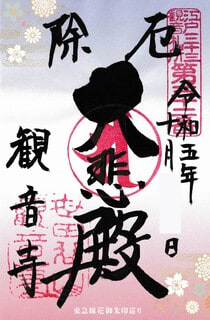
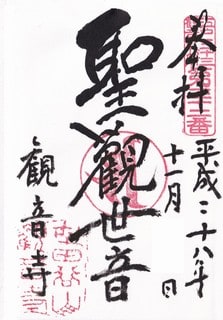
08.(3).駒繋神社
東京都世田谷区下馬4-27-26
御祭神:大国主命
御朱印尊格:駒繋神社
旧無格社、旧下馬引沢村鎮守
元別当:寿福寺
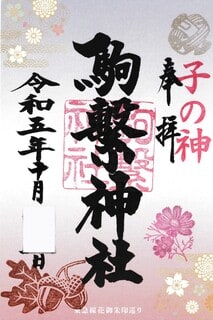
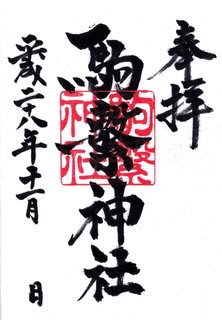
09.(56).寶樹山 常在寺
東京都世田谷区弦巻1-34-17
日蓮宗
御本尊:久遠実成の釈迦牟尼仏
御朱印尊格:御首題(お題目)
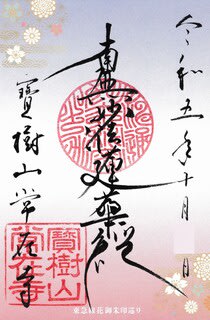

10.(57).大悲山 明王寺 円光院
東京都世田谷区世田谷4-7-12
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
御朱印尊格:本尊不動明王(玉川霊場札番)
札所:玉川八十八ヶ所霊場第49番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第3番、玉川東組三十三ヶ所霊場(写坂東)第32番
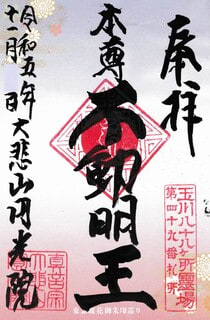
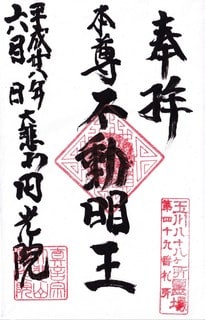
11.(24).寶泉山 玉真院 (玉川大師)
東京都世田谷区瀬田4-13-3
真言宗智山派
御本尊:大日如来
御朱印尊格:弘法大師(御影)
札所:玉川八十八ヶ所霊場第5番、関東三十三観音霊場第10番、世田谷三十三ヶ所観音霊場第25番
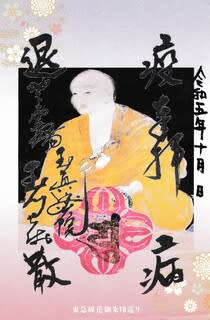
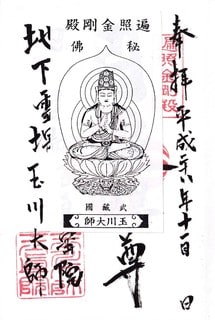
12.(55).(赤堤)六所神社
東京都世田谷区赤堤2-25-2
御祭神:大国魂命、伊弉冊尊、素戔嗚尊、布留大神、大宮売命
御朱印尊格:世田谷赤堤 六所神社
旧村社、旧赤堤村鎮守
元別当:西福寺
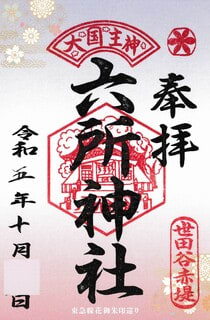

13.(59).(太子堂)八幡神社
東京都世田谷区太子堂5-23-5
御祭神:誉田別命
御朱印尊格:太子堂八幡神社
旧村社
元別当:圓泉寺
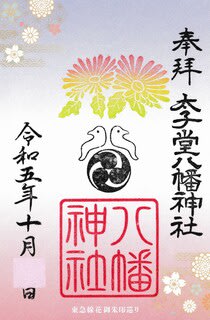

14.(23).用賀神社
東京都世田谷区用賀2-16-26
御祭神:天照大御神、応神天皇、菅原道真公
御朱印尊格:用賀神社
旧村社、旧用賀村鎮守
元別当:真福寺
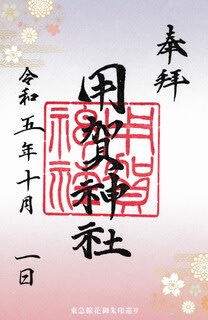
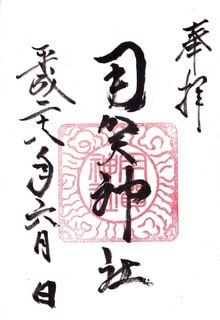
15.(58).松陰神社
東京都世田谷区若林4-35-1
御祭神:吉田寅次郎藤原矩方命
御朱印尊格:松陰神社
旧府社
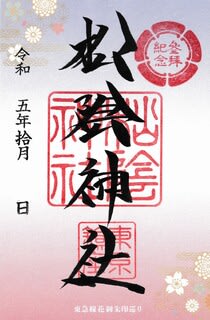
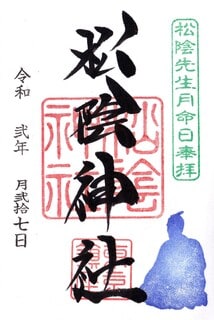
16.(25).瀬田玉川神社
東京都世田谷区瀬田4-11-3
御祭神:日本武尊、大己貴命、少彦名命
御朱印尊格:瀬田玉川神社
旧村社
元別当:慈眼寺
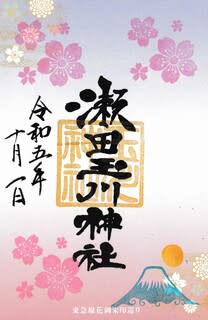
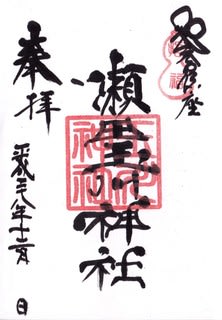
17.(13).松林山 大圓寺(大円寺)
東京都目黒区下目黒1-8-5
天台宗
御本尊:釈迦如来
御朱印尊格:大黒天(山手七福神札番)
札所:山手七福神(大黒天)
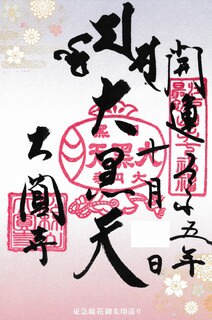
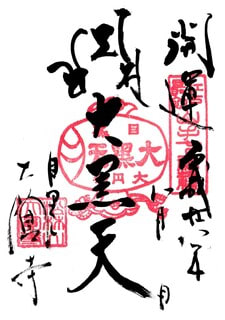
18.(14).不老山 薬師寺 成就院 (蛸薬師)
東京都目黒区下目黒3-11-11
天台宗
御本尊:薬師如来
御朱印尊格:蛸薬師如来
札所:江戸薬師如来霊場三十二ヶ所(25番)

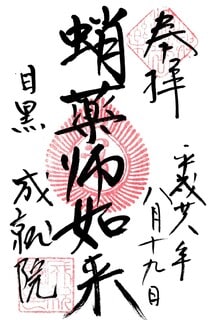
19.(16).霊雲山 称明院 蟠龍寺 (目黒岩屋辨天)
東京都目黒区下目黒3-4-4
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
御朱印尊格:辨財天(山手七福神札番)
札所:山手七福神(辨財天)
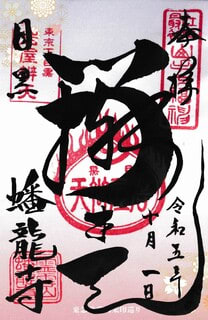
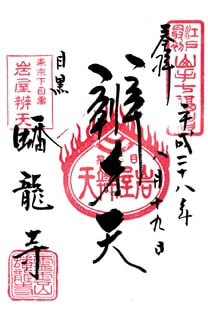
20.(15).天恩山 羅漢寺 (五百羅漢寺)
東京都目黒区下目黒3-20-11
浄土宗系単立
御本尊:釈迦如来
御朱印尊格:五百羅漢尊
札所:江戸・東京四十四閻魔参り第44番、江戸南方四十八地蔵霊場第3番、弁財天百社参り番外30
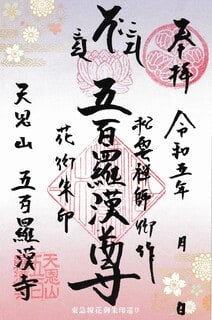
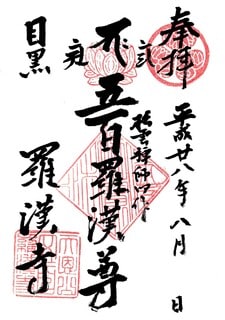
21.(2).實相山 正覚寺
東京都目黒区中目黒3-1-6
日蓮宗
御朱印尊格:御首題(お題目)

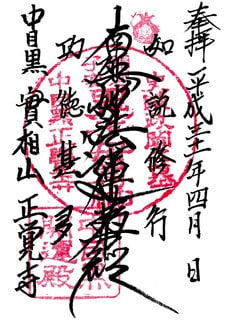
22.(4).(自由が丘)熊野神社
東京都目黒区自由が丘1-24-12
御祭神:速玉之男尊、伊弉冊命、泉津事解之男尊
御朱印尊格:自由が丘 緑が丘 熊野神社
旧村社、緑が丘一帯鎮守
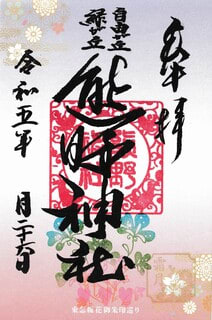
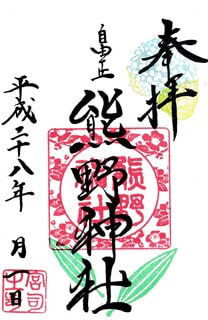
23.(36).(旗岡)八幡神社 (中延八幡宮)
東京都品川区旗の台3-6-12
御祭神:誉田別尊、比売大神、息長帯比売命
御朱印尊格:旗岡八幡神社
旧郷社
元別当:法蓮寺
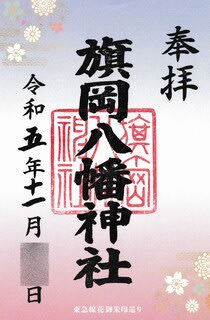
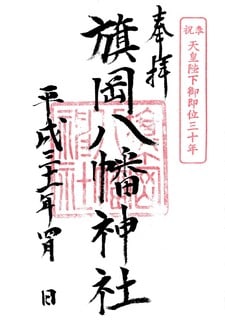
24.(46).(戸越)八幡神社
東京都品川区戸越2-6-23
御祭神:誉田別命
御朱印尊格:戸越八幡神社
旧村社、旧戸越村鎮守
元別当:行慶寺
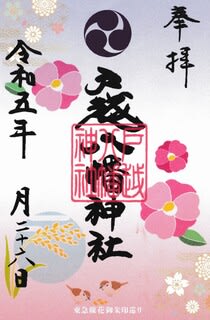
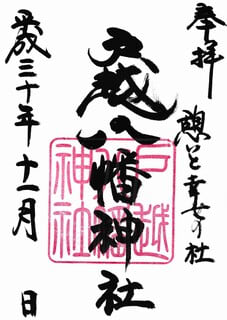
25.(48).帰命山 如来寺 養玉院 (大井の大仏)
東京都品川区西大井5-22-25
天台宗
御本尊:釈迦如来
御朱印尊格:五智如来殿
札所:大東京百観音霊場第41番、荏原七福神(布袋尊)
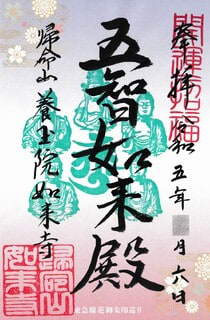
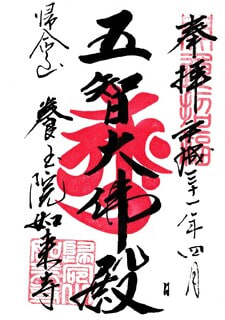
26.(39).大井蔵王権現神社
東京都品川区大井1-14-8
御祭神:蔵王大権現
御朱印尊格:大井蔵王権現神社
大井権現台鎮守
札所:荏原七福神(福禄寿)
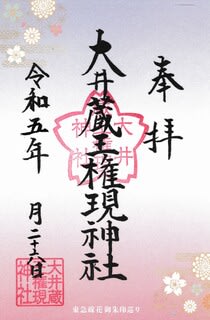

27.(47).居木神社(いるぎ神社)
東京都品川区大崎3-8-20
御祭神:日本武尊
御朱印尊格:居木神社
旧村社、大崎鎮守、旧居木橋村鎮守?
元別当:観音寺

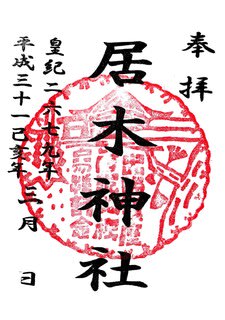
28.(38).(下神明)天祖神社
東京都品川区二葉1-3-24
御祭神:天照大御神、応神天皇、天児屋根命
御朱印尊格:下神明 天祖神社
旧村社、旧蛇窪村(のち旧下蛇窪村)鎮守
元別当:東光寺
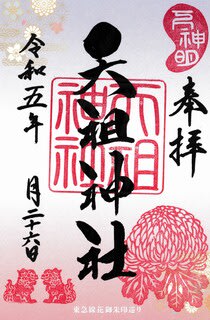
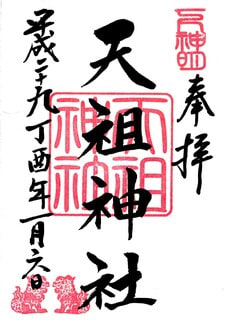
29.(37).蛇窪神社((上神明)天祖神社)
東京都品川区二葉4-4-42
御祭神:天照大御神
御朱印尊格:蛇窪神社
旧村社、旧蛇窪村(のち旧上蛇窪村)鎮守
元別当:長遠寺
札所:荏原七福神(弁財天)
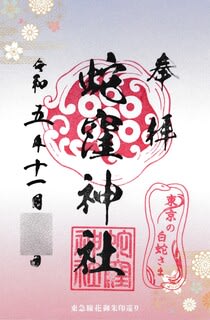

30.(40).明鏡山 善行院 養願寺
東京都品川区北品川2-3-12
天台宗
御本尊:虚空藏菩薩
御朱印尊格:虚空藏尊
札所:東海七福神(布袋尊)
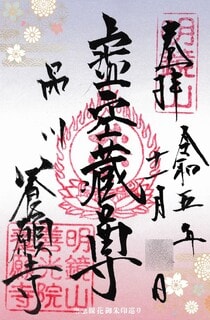
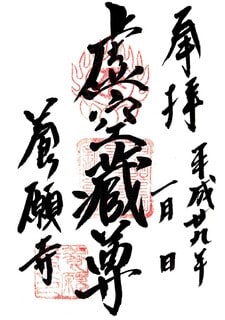
31.(49) .(下丸子)六所神社
東京都大田区下丸子4-16-5
御祭神:大己貴命、伊邪那岐命、素盞嗚命、大宮比売命、瓊々杵命、布留大神
御朱印尊格:六所神社
旧村社、旧下丸子村鎮守
元別当:蓮光院
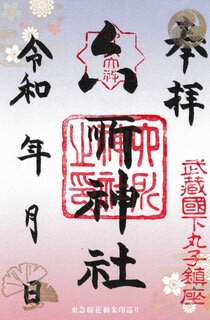
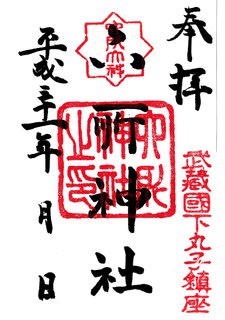
32.(54).(多摩川)諏訪神社
東京都大田区多摩川2-10-22
御祭神:建御名方命、八坂戸売命
御朱印尊格:諏訪神社
多摩川二丁目地区(旧原地区)鎮守
元別当:東福寺
御朱印授与所:徳持神社(大田区池上3-38-17)
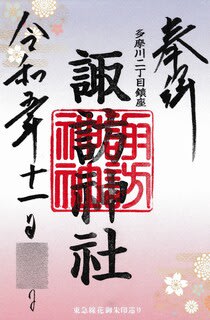
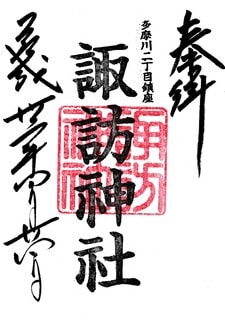
33.(42).長栄山 大国院 池上本門寺
東京都大田区池上1-1-1
日蓮宗大本山
御本尊:三宝尊
御朱印尊格:妙法
札所:池上の寺めぐり-朗師講第6番、東国花の寺百ヶ寺霊場東京第4番
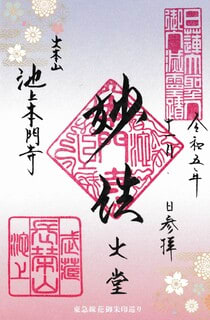
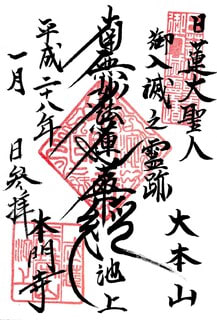
34.(41).徳持神社(御幡山八幡宮)
東京都大田区池上3-38-17
御祭神:誉田別之命
御朱印尊格:徳持神社
旧無格社、旧徳持村鎮守
元別当:徳乗院
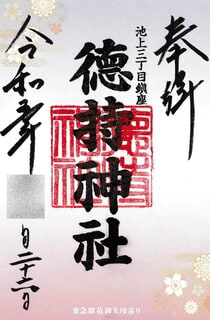

35.(45).(雪ヶ谷)八幡神社
東京都大田区東雪谷2-25-1
御祭神:誉田別命
御朱印尊格:雪ヶ谷八幡神社
旧村社、東雪谷六郷領鎮守
元別当:圓長寺、長慶寺
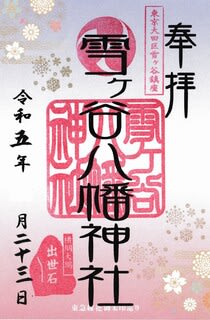
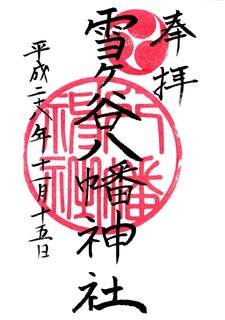
36.(50).新田神社
東京都大田区矢口1-21-23
御祭神:新田義興公
御朱印尊格:新田大明神
旧府社
元別当:真福寺
札所:多摩川七福神(恵比寿)

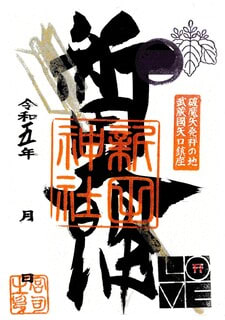
37.(52).十寄神社(とよせ神社)
東京都大田区矢口2-17-28
御祭神:新田義興公の支族および近習将兵
御朱印尊格:十寄神社
旧無格社
札所:多摩川七福神(毘沙門天)
御朱印授与所:徳持神社(大田区池上3-38-17)
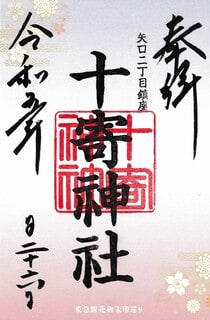
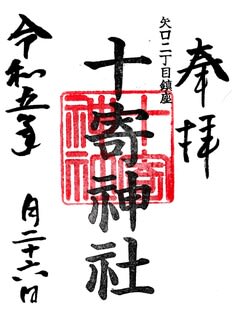
38.(51).福田山 蓮花寺 花光院
東京都大田区矢口2-3-12
真言宗智山派
御本尊:大日如来
御朱印尊格:本尊大日如来(玉川霊場札番)
札所:玉川八十八ヶ所霊場第62番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第25番
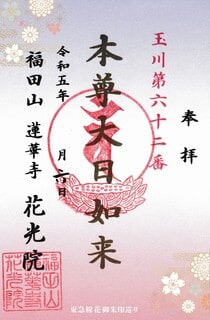
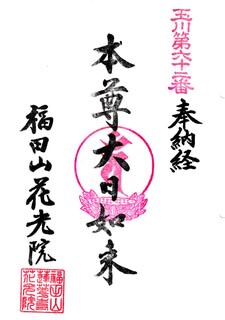
39.(53).(東)八幡神社 (湯坂八幡)
東京都大田区矢口3-17-3
御祭神:誉田別命
御朱印尊格:東八幡神社
旧村社、旧古市場村鎮守
元別当:圓應寺
札所:多摩川七福神(弁財天)
御朱印授与所:徳持神社(大田区池上3-38-17)
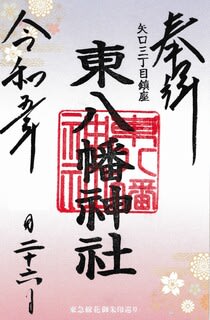

40.(43).(久が原東部)八幡神社
東京都大田区久が原2-18-4
御祭神:誉田別尊
御朱印尊格:久が原東部八幡神社
旧村社、旧久ヶ原村(馬込領)鎮守
御朱印授与所:徳持神社(大田区池上3-38-17)
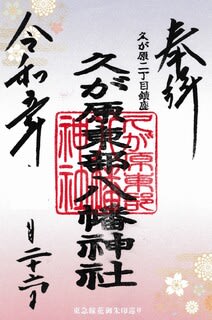
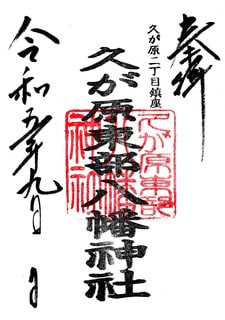
41.(44).(久が原西部)八幡神社
東京都大田区久が原4-2-7
御祭神:誉田別尊
御朱印尊格:久が原西部八幡神社
旧村社、旧久ヶ原村(六郷領)鎮守
元別当:安詳寺
御朱印授与所:徳持神社(大田区池上3-38-17)
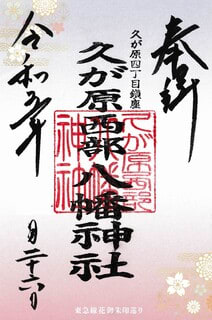
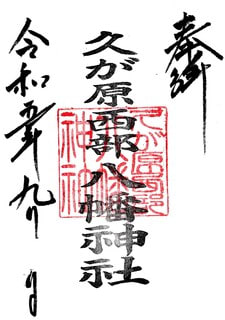
42.(32).(武州柿生)琴平神社
神奈川県川崎市麻生区王禅寺東5-46-15
御祭神:大物主神、天照大御神
御朱印尊格:武州柿生 琴平神社
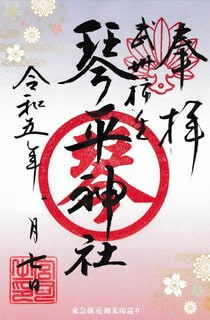

43.(31).長尾山 薬王院 妙楽寺
神奈川県川崎市多摩区長尾3-9-3
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
御朱印尊格:阿弥陀佛
札所:関東百八地蔵尊霊場第83番、小田急沿線花の寺四季めぐり第21番
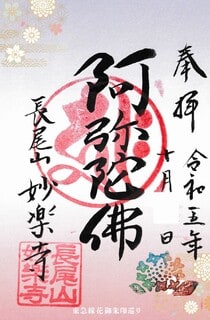
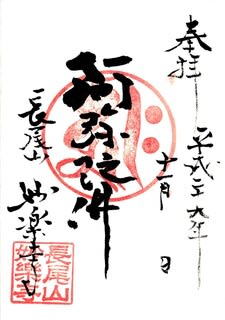
44.(30).神木山 長徳寺 等覚院
神奈川県川崎市宮前区神木本町1-8-1
天台宗
御本尊:不動明王
御朱印尊格:種子(カン)(東国花の寺霊場札番)
札所:関東三十六不動尊霊場第6番、関東九十一薬師霊場第16番、東国花の寺百ヶ寺霊場神奈川第5番、小田急沿線花の寺四季めぐり第16番

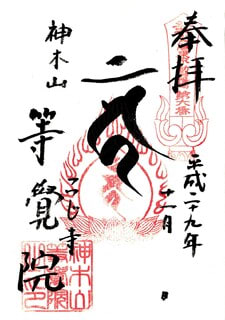
45.(29).高津山 大明王院(身代り不動尊)
神奈川県川崎市高津区下作延692
真言宗醍醐派
御本尊:不動明王
御朱印尊格:身代不動尊(武相不動尊霊場札番)
札所:武相二十八不動尊霊場第2番、武相四十八ヶ所不動尊霊場第1番
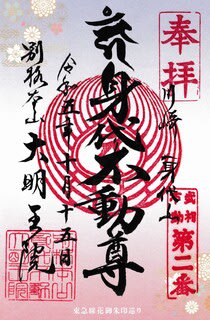
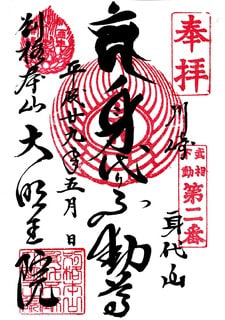
46.(26).興林山 宗隆寺
神奈川県川崎市高津区溝口2-29-1
日蓮宗
御朱印尊格:諸天宝華

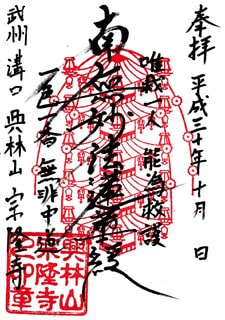
47.(27).医王山 薬師院
神奈川県川崎市高津区新作3-27-1
臨済宗妙心寺派
御本尊:薬師如来
御朱印尊格:薬師瑠璃光(稲毛七薬師霊場札番)
札所:稲毛七薬師霊場第7番
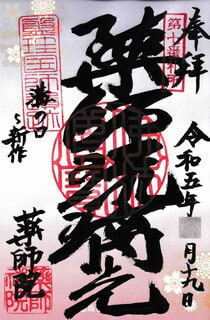
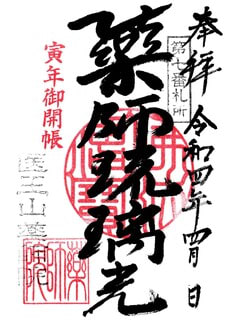
48.(28).松林山 安楽院 明鏡寺
神奈川県川崎市高津区末長2-27-42
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
御朱印尊格:南無阿弥陀佛(六字御名号)
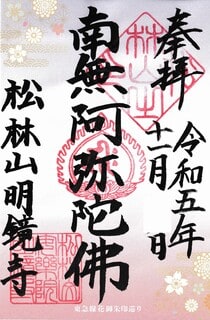
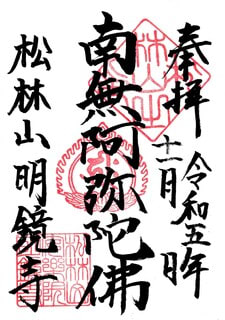
49.(5).(丸子山王)日枝神社
神奈川県川崎市中原区上丸子山王町1-1555
御祭神:大己貴神(大国主神)
御朱印尊格:丸子山王 日枝神社
旧村社、丸子庄総鎮守
元別当:大楽院
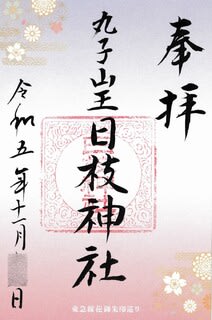
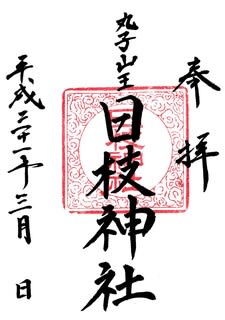
50.(33).神鳥前川神社(しとどまえかわ神社)
神奈川県横浜市青葉区しらとり台61-12
御祭神:日本武尊、弟橘比売命
御朱印尊格:神鳥前川神社
元別当:萬福寺
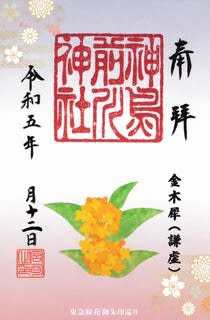

51.(34).慈雲山 大林寺
神奈川県横浜市緑区長津田6-6-24
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
御朱印尊格:南無釋迦牟尼佛
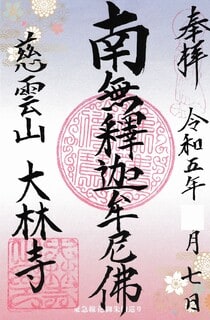
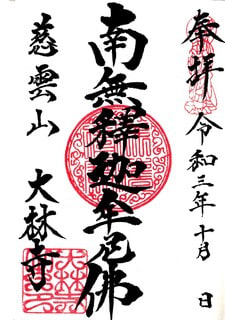
52.(35).薬王山 医王院 福泉寺
神奈川県横浜市緑区長津田町3113
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
御朱印尊格:本尊薬師如来
札所:関東八十八箇所霊場第65番、関東九十一薬師霊場第17番、 武相寅歳薬師如来霊場第23番、富士見楽寿観音霊場第4番
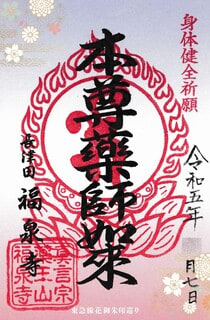
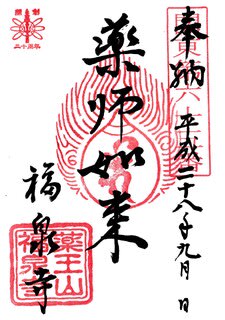
53.(18).歸命山 安國院 無量寺
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町2021
高野山真言宗
御本尊:無量寿如来
御朱印尊格:無量寿
札所:武相寅歳薬師如来霊場第9番
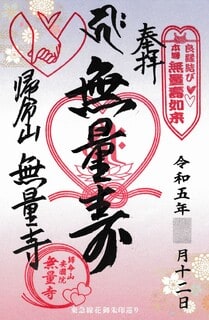
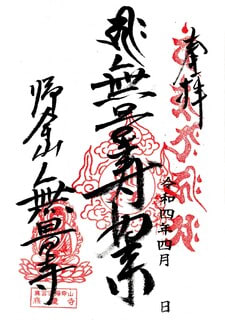
54.(19).佛法山 般若院 東漸寺
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町2240
高野山真言宗
御本尊:不動明王
御朱印尊格:文殊菩薩
札所:関東八十八箇所霊場第67番、武相二十八不動尊霊場第12番、武相寅歳薬師如来霊場第8番、武相四十八ヶ所不動尊霊場第28番

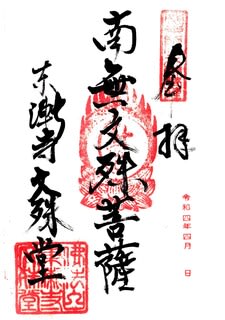
55.(7).菊名神社
神奈川県横浜市港北区菊名6-5-14
御祭神:誉田別命、天照皇大神、日本武尊、木花咲耶姫命、武内宿禰命
御朱印尊格:菊名神社
旧村社
元別当:本乗院、法華寺、長福寺
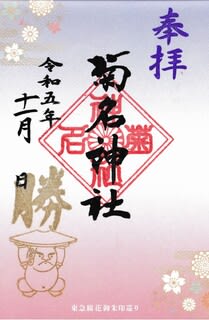
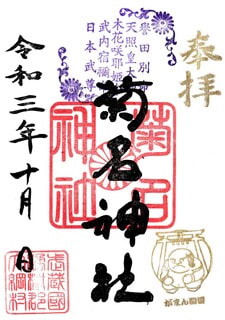
56.(17).八幡山 観音寺
神奈川県横浜市港北区篠原町2777
真言宗智山派
御本尊:十一面観世音菩薩
御朱印尊格:大悲殿 不動明王(2種あり)
札所:玉川八十八ヶ所霊場第82番、新四国東国八十八ヶ所霊場第24番
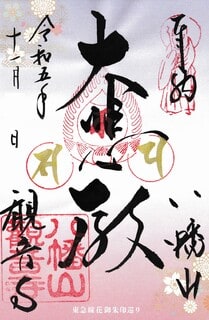
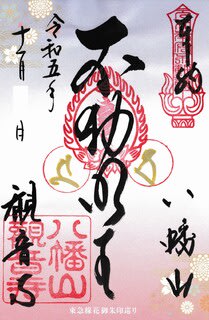
【写真 上(左)】 花御朱印(大悲殿(観世音菩薩))
【写真 下(右)】 花御朱印(不動明王)
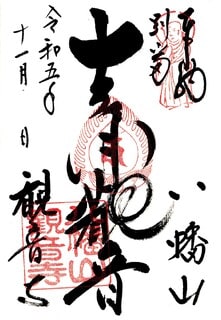
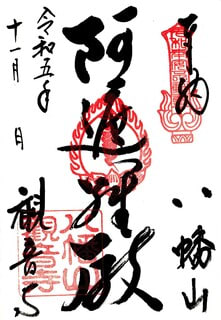
【写真 上(左)】 通常御朱印(十一面観世音菩薩)
【写真 下(右)】 通常御朱印(阿遮羅殿(不動明王))
57.(6) .補陀洛山 安養院 西方寺
神奈川県横浜市港北区新羽町2586
真言宗系単立
御本尊:阿弥陀如来
御朱印尊格:黒阿弥陀
札所:武相二十八不動尊霊場第9番、旧小机領三十三観音霊場第15番、横浜七福神(恵比寿大神)、武相四十八ヶ所不動尊霊場第22番
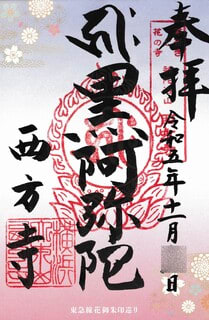
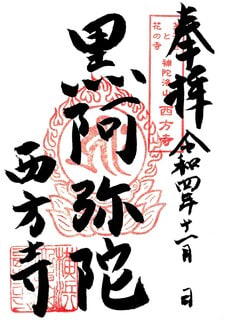
58.(9).開塔山 日輪院 宗興寺
神奈川県横浜市神奈川区幸ヶ谷10-6
曹洞宗
御本尊:聖觀世音菩薩
御朱印尊格:聖觀世音菩薩(小机観音霊場札番)
札所:旧小机領三十三観音霊場第8番、横浜市内三十三観音霊場第15番
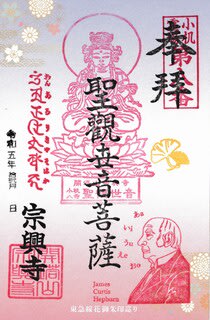
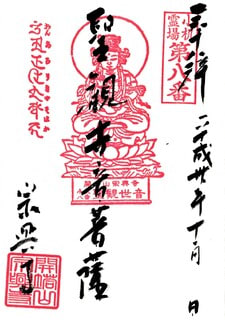
59.(8).吉祥山 芳艸院 慶運寺(浦島寺)
神奈川県横浜市神奈川区神奈川本町18-2
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
御朱印尊格:浦島聖観世音(小机霊場札番)
札所:旧小机領三十三観音霊場第9番
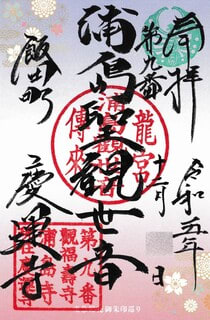

-------------------------
2023/10/03 UP
2023年9月16日(土)~2024年5月6日(祝)、「東急線 花御朱印巡り 第2弾」が開催されています。→公式Web
東急線・東急バス沿線の59の寺社が参画、期間中「花」をテーマとした特別御朱印が授与されています。
第1弾は参加しませんでしたが、今回はトライしてみます。
10/1に専用御朱印帳をゲットしてすこしまわってみたので、感想や気になった点など書いてみます。

■ チラシ
1.寺社選定のコンセプト
↑の参画寺社リストをみてもわかるとおり、寺院宗派は多岐にわたり、特定の霊場をベースにしているものではなさそうです。
かなり渋めの寺社が参画されている一方、沿線を代表するメジャーな寺社が不参画だったりして、寺社選定のコンセプトがよくわかりません。
たとえば、豪徳寺、目黒不動尊(瀧泉寺)、目青不動尊(教学院)、祐天寺、嶺御嶽神社、浄真寺(九品仏)、等々力不動尊、多摩川浅間神社、溝口神社、師岡熊野神社、妙蓮寺、伊勢山皇大神宮などが不参画です。
2.御朱印帳
専用納経帳は3,500円(税込)といいお値段ですが、これがないと専用御朱印を授与されない寺社もありそうなので、よんどころなく購入することになります。
装丁はかなり華奢で傷つきやすいので、ビニールカバーがほしいところか。
(筆者は手元にあった大サイズ御朱印帳用のビニールカバーを装着しました。)
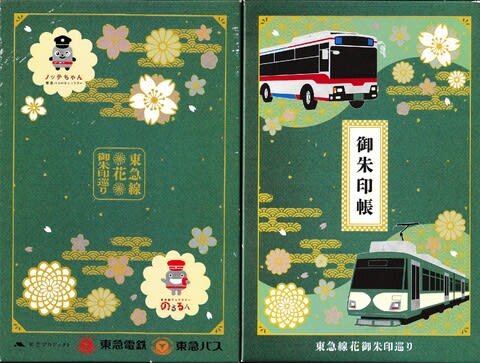
■ 専用御朱印帳
御朱印はすべて書置。
3,500円の高額御朱印帳なので四隅挿込み式を想定しましたが、ごくふつうののり貼り式でした。

■ 四隅挿込み式の例(養平寺/埼玉県熊谷市)
サイズは横12.1㎝×縦18.2㎝で、ほぼ大サイズ御朱印帳規格です。
筆者はワンデーパスセット(1日有効のワンデーパス(特別仕様)、専用御朱印帳、ガイドブック、4,000円(税込))を購入しました。
ワンデーパスは、通常780円で発売されているものの特別仕様です。
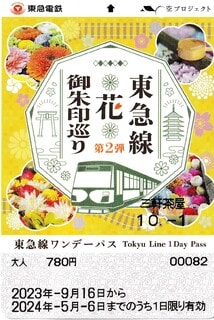
■ 特別仕様のワンデーパス
今回は東急バス沿線寺社の参画が目玉のようなので、鉄道のみの「ワンデーパス」ではなく「東急線・東急バス 一日乗り放題パス」(1,070円)がほしいところ。
4,000円(税込)の高額セットなので、そのくらいの振る舞いはあってもバチはあたらないかと。
3.ガイドブック
おそらくプロのデザイナーが入っているので、全体に綺麗な仕上がり。
でも、機能優先の霊場案内や御開帳手引に慣れている筆者にとって、これは使いにくいものでした。
全体図から沿線図に飛び、そこからさらに「御利益」毎にまとめられている寺社案内に飛ぶのでふた手間かかります。

■ ガイドブック
どうにも使いにくいので、↑のとおり一覧をつくってみました。
なお、ガイドブックで整理No.は振られていますが、これは「札番」とは異なるもののようです。
御朱印対応時間は概ね9時~16時ないし16時半。
17時までの対応は少数で、これは日の短い秋~春の企画ゆえいたしかたないかも。
期間はたっぷりあるし、見どころの多い寺社多数なので、時間をかけてゆったりまわるのがベターかと。
4.御朱印授与料
ガイドブックには明示なしですが、多くの寺社が500円の模様です。(通常御朱印が300円のところも500円)
なので、最大59枚×500円+御朱印帳セット4,000円=33,500円となります。
収まらぬ物価高騰、下がりつづける実質賃金。
しかも10月からのインボイス導入でさらに景況の悪化が懸念されている状況で、寺社巡りに大枚3万円以上もはたいて参加する人がはたしてどれだけいるかどうか・・・。
全寺社の御朱印コンプリートというより、自宅近くの、日頃お参りしている寺社の特別御朱印ゲットというニーズがメインでは?
あるいは、交通費や宿泊費高騰で旅行を諦めた人が、身近なレジャーとしてトライするニーズもあるかも。
なんか、だんだんと家のそばの写し霊場を廻っていた江戸時代に回帰しているような・・・(笑)
【追記】
その後巡拝したところでは、お納め300円の寺社もそれなりにありました。
とくに川崎市内の寺院の多くは300円で、↑ の概算額よりは低額で巡拝できるかと思います。


【写真 上(左)】 上目黒氷川神社の花手水
【写真 下(右)】 渋谷氷川神社の花手水
まぁ、いろいろ書きましたが、趣きある寺社も多いし、御朱印も美しいのでこれはこれでありかと思います。
全59社寺のほとんどの通常御朱印を拝受していますので、これから随時花御朱印と通常御朱印を比較できるかたちでご紹介していきます。
-------------------------
前回(第1弾)の紹介記事がみつかりましたのでリンクします。
期間は2022年4月29日(金)~2022年10月31日(月)
参加対象寺社は下記の48寺社でした。
日蓮宗本山 池上大坊 本行寺、日蓮宗大本山 池上本門寺、長尾山 妙楽寺、興林山 宗隆寺、宗興寺、吉祥山 慶運寺、宮益御嶽神社、松林山 明鏡寺、下神明天祖神社、寶樹山 常在寺、満願寺、たこ薬師 成就院、臥龍山 安養院、名楽山 森立寺 密蔵院、薬王山 医王院 福泉寺、上目黒氷川神社、正覚寺、大崎鎮守 居木神社、摩尼山 延壽院 徳恩寺、菊名神社、高田天満宮、松陰神社、蟠龍寺、赤堤六所神社、桜神宮、神鳥前川神社、浅間神社、新田神社、本牧神社、雪ヶ谷八幡神社、太子堂八幡神社、旗岡八幡神社、世田谷八幡宮、戸越八幡神社、千束八幡神社(洗足池八幡宮)、寶泉山 玉眞院 玉川大師、長谷山 祥泉院、補陀洛山 西方寺、天恩山 五百羅漢寺、松林山 大圓寺、蛇窪神社、身代り不動尊 大明王院 川崎本山、円光院、泉福寺、神木山 等覚院(神木不動)、八幡山観音寺、等々力不動尊、蒲田不動尊 大楽寺
※ 関連記事
■ 東京都世田谷区の札所と御朱印 (前編)
■ 東京都世田谷区の札所と御朱印 (後編)
【 首都圏の私鉄と霊場札所 】
京成電鉄の歴史は成田山新勝寺への参詣客輸送を鏑矢とする説があるように、首都圏の私鉄と著名参詣地との関係は密接なものがありました。
京成は成田山新勝寺や柴又帝釈天、東武本線系は日光・足利・赤城、東武東上線は川越・秩父・三峯、西武は飯能・秩父・三峯、京王は高尾山・八王子・府中、小田急は大山・箱根・江ノ島、京急は川崎大師・三浦など、名だたる参詣地を擁しています。
一方、東急は通勤・通学路線としての色彩が強く、決定的な参詣地はみあたりません。
昭和初期、私鉄各社で沿線の寺院を巡る霊場札所が相次いで設けられたのに対し、東急ではそのような動きがみられなかったのは、このような背景があったからかもしれません。
それでも、格式の高い神社や名刹には事欠きませんので、遅ればせながら(?)このような企画が導入されているのかも。
なお、昭和初期に私鉄が主導した霊場は、現在「幻の霊場」的な存在となっており、現役霊場として活動しているのは西武の武蔵野三十三観音霊場くらいです。
西武は秩父三十四箇所霊場、狭山三十三観音霊場ともにサポート的な動きをしており、沿線で百観音すべての御朱印が揃う、貴重な例となっています。
また、三浦半島の各霊場(観音、不動尊、薬師、地蔵尊など)の御開帳時に京急が後援に入る例もみられます。
※ご参考(別記事「■ 希少な札所印」から一部転載)
■ 小田急武相三十三観音霊場(小田急電鉄)

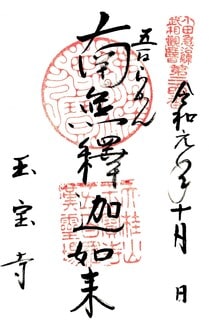

天桂山 王寶寺
小田原市扇町5-1-28
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所:〔小田急武相三十三観音霊場第24番〕
札所本尊:十一面観世音菩薩
昭和11年(1936年)、小田急電鉄が企画し沿線寺院によって札所が選定された観音霊場。
発願は新宿の天龍寺、第4番で経堂、第7番で向ヶ丘遊園、第10番で町田、第13番で海老名、第15番で厚木、第21番で秦野、第24番で小田原に至り、第33番結願はなぜか鎌倉・腰越の満福寺なので、江ノ島線利用の巡拝も兼ねていたと思われます。
宗派は多彩ですが、比較的禅宗が多く歴史ある名刹が目立ちます。
札所33ヶ寺のほか、特別霊場として豪徳寺、伊勢原の日向薬師、大山寺、大雄山最乗寺、藤沢の清浄光寺(遊行寺)のメジャー5寺院を招聘し、豪華な顔ぶれとなっています。
札所一覧は→こちら(「ニッポンの霊場」様)
このような鉄道会社が企画した霊場は、京成の「東三十三観音」、西武の「武蔵野三十三観音」、京王の「京王三十三観音」などがありますが、現役の霊場として活動しているのは「武蔵野三十三観音」のみとみられます。
札所印は稀少ですが、小田原の王寶寺(五百羅漢)でいただけました。
札所本尊は十一面観世音菩薩のようですが、御朱印尊格は御本尊(釈迦如来)でした。
古の観音霊場の場合、よくみられるケースです。
札所印は「小田急沿線武相観音第二十四番」と読めます。
■ 京王三十三観音霊場(京王電鉄)


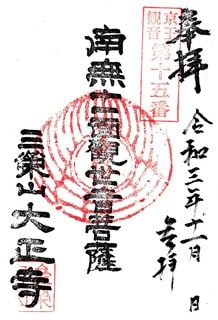
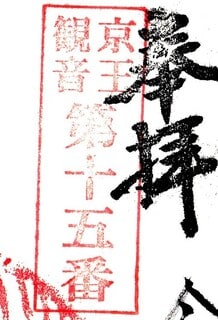
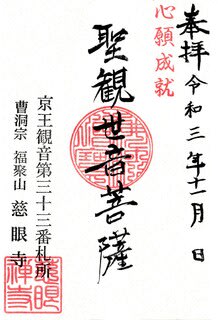
第33番結願寺 福聚山 慈眼寺(八王子市長房町)の御朱印
三栄山 常行院 大正寺
調布市調布ケ丘1-22-1
新義真言宗
御本尊:大日如来
札所:〔京王三十三観音霊場第15番〕、多摩新四国八十八ヶ所霊場第5番、多摩川三十四観音霊場第8番、調布七福神(恵比寿)
札所本尊:十一面観世音菩薩
「ニッポンの霊場」様によると、「観光ブーム+電車利用の促進を目的に、京王電鉄と沿線の寺院によって霊場札所が選定された。」とのこと。
開創時期、開創の経緯など詳細は不明です。
発願は新宿の天龍寺、第6番で下高井戸、第10番で調布、第18番で府中、第24番で八王子に至り、結願は八王子の慈眼寺です。
鉄道系の札所だけあって宗派は変化に富み、多摩川三十四観音、多摩八十八ヶ所、八王子三十三観音、武相卯歳四十八観音との重複札所がかなりあり、京王観音霊場の御朱印を出されている札所もいくつかありますが、どことなく通向けのイメージがある霊場です。
これは、兼務の霊場じたいがかなりマニアックなためと思われます。
発願寺の天龍寺は現在御朱印不授与のようですが、筆者の調べでは33の札所のうち31で、御朱印ないし御首題を授与されている模様です。
(ただし、京王観音霊場の札所印つきは数箇寺。大正寺様のように、現役の兼務札所がありながら、京王観音霊場の札所印をいただける例は希だと思われます。)
布多天神社のそばにある、すこぶる趣きのある寺院です。
京王三十三観音霊場の札所本尊は多摩川三十四観音霊場と同様、立入禁止の庭園おくにある観音堂に御座します。
■ 東三十三観音霊場(京成電鉄)

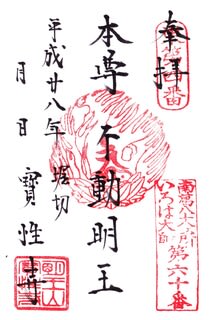
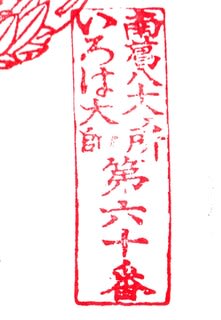

明王山 不動院 寳性寺
葛飾区堀切2-25-21
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所:〔南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第60番〕、〔(京成)東三十三観音霊場第4番〕、荒綾八十八ヶ所霊場第12番、荒川辺八十八ヶ所霊場第62番、隅田川二十一ヵ所霊場第8番
札所本尊:不動明王
南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師/大心講)も比較的古く、御朱印拝受がむずかしい霊場です。
こちらではこの南葛霊場札所印のみならず、希少な東三十三観音霊場(昭和十年京成電車が企画した霊場)の印判もいただけました。
御本尊の不動明王で、「南葛八十八ヶ所いろは大師第六十番」と「東第四番」の印判が別個に捺されています。
こちらは他に荒綾八十八ヶ所霊場12番、荒川辺八十八ヶ所霊場62番、隅田川二十一ヵ所霊場8番の札所も兼ねていますが、霊場を申告せずにお願いしたところ、この御朱印を拝受できました。
なお「南葛八十八ヶ所霊場」は2系統あります。
1.「いろは大師」(大心講)と呼ばれ、発願は葛飾区奥戸の善紹寺、結願は葛飾区奥戸の妙厳寺
2.通称名は不明。発願は江戸川区東小松川の善照寺、結願は江戸川区東小松川の宝積院
(2については、「南葛新四国霊場」と呼ばれることもあるようです。)
一部の札所は重複し、このふたつの南葛霊場の識別をよりむずかしいものにしています。
たとえば、「いろは大師」の葛飾区鎌倉の札所は「南葛八十八ヶ所まんだら六ヶ所参り」として、毎年11月下旬の1日のみ御開帳(というか巡拝)されます。
この6札所のうち、浄光院(1.では第14番、2.では第55番)、輪福寺(1.では第17番、2.では第56番)は札所が重複していますが、「六ヶ所参り」では、1.の「いろは大師」の御朱印が授与されます。
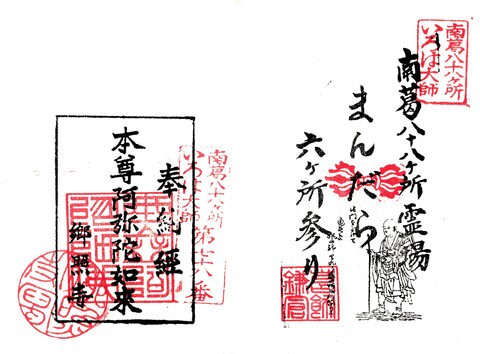
■「南葛八十八ヶ所まんだら六ヶ所参り」の御朱印
どちらも御朱印拝受がむずかしいですが、「1.いろは大師」の方が授与札所は多そうです。(調査中)
【 BGM 】
■ A Perfect Rain - John Jarvis
■ Getaway - Keith Thomas feat. Halston Dare
■ The Time Is Now - Michael Omartian
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 江戸六地蔵の御朱印
自分で書いたことを忘れていた記事です。
目下、年度末で仕事がテンパってるので時間ができたら追記します。
■ 武州江戸六阿弥陀詣 → 記事
■ 江戸五色不動 → 記事
これらの札所には桜の名所もいくつかあります。
また、武州江戸六阿弥陀詣は、お彼岸に詣でるものとされていました。
春の一日、桜を愛でつつ寺院めぐりでもいかがでしょうか。
■ 朧月夜 - 中島美嘉
名曲だから、こういう優れたアレンジテイクが生まれる。
中島美嘉の歌唱力も凄いが、葉加瀬太郎のバイオリンも圧巻。
-------------------------
作詞:高野辰之 作曲:岡野貞一
大正3年『尋常小学唱歌 第六学年用』に初出
菜の花畠に 入日薄れ
見わたす山の端(は) 霞ふかし
春風そよふく 空を見れば
夕月かかりて にほひ淡し
里わの火影(ほかげ)も 森の色も
田中の小路を たどる人も
蛙(かわづ)のなくねも かねの音も
さながら霞める 朧月夜
-------------------------
→ ■ 桜曲40曲! もどうぞ。
-------------------------
2021/09/06 UP
「武州江戸六阿弥陀詣の御朱印」、「江戸五色不動の御朱印」がけっこうなアクセスをいただいているので、江戸六地蔵についてもまとめてみます。
作成中です。文字だらけですみません。
江戸六地蔵は、江戸に入る街道の入口に安置された6体の地蔵菩薩を巡拝する地蔵尊霊場です。
江戸六地蔵には「はじめの六地蔵(最初建立江戸六地蔵)」と「後の六地蔵」があり、これを把握しないと混乱するので最初にまとめてみます。
「はじめの六地蔵」は、下谷池之端影向山心行寺三世の(慈済庵)本誉空無(浄土木食)が元禄四年(1691年)に建立開眼したと伝わります。
(こちら(『本譽空無上人道影贊』翻刻と解題/関口靜雄氏・PDFに直リンク、以下資料1)に詳しいです。)
「後の六地蔵」は、沙門正元坊が宝永年間(1704-1711年)に建立したと伝わります。
「はじめの六地蔵」は毎月二十四日ないし十八日の縁日に多くの信者を集めたと伝わりますがいつしか衰退し、いくつかは廃寺となったこともあり、現在江戸六地蔵として知られているのは正元坊建立の「後の六地蔵」です。
ただし、資料1によると『地藏本願經囑累品』/谷中安立院光輪印施には、
------------
空無上人發願造立
○六地藏尊靈塲 ○毎月十八日巡拜ノ衜順ニ記ス
番外 湯島新花町 靈雲寺
四番 池ノ端七軒町 心行寺
一番 駒込蓬萊町 瑞泰寺
二番 同千駄木町 專念寺
三番 日暮里 淨光寺
番外 谷中五重塔ノ奥 安立院
八万四千躰 上野山内 淨名院
五番 上野慈眼堂内 地藏堂
六番 金龍山仲見世 正智院
番外 淺草 駒形堂
------------
とあり、「はじめの六地蔵」の番外に「後の六地蔵」関連の靈雲寺と淨名院が姿をみせています。
また、Web上でみつかった『地藏菩薩俗談(三』)/眞鍋廣濟氏・PDFに直リンクには、「元緑四年になつてから『江戸はじめの六地藏』が設定せられ、次いで寳永三年には『江戸六地藏建立勘化帳』一巻が著されてゐるが、今日いふ東都の六地藏は、本郷駒込蓬莱町の瑞泰寺、同じく駒込千駄木町の專念寺、豊島區日暮里町の浄光寺、下谷廣池端七軒町の心行寺、同じく上野慈眼堂内の地藏堂、それに淺草寺雷門内の正智院の六個所で、尚この外に鋳銅六地藏と構してゐるのもあるが、これは荏原區品川町南品川宿の品川寺、淺草榮久町の東禅寺、豊島區巣鴨町の眞性寺、四谷區新宿二丁目の大宗寺、深川區霊岸町の霊巌寺、下谷區上野山内の浄名院の六寺院で、洛陽の信仰に摸つて、江戸の人士たちがそこに安置した鋳銅の地藏尊を一組として巡拝するものである。」とあります。
「東都の六地蔵」が「はじめの六地蔵」、「鋳銅六地藏」が「後の六地蔵」を示していることがわかります。
以降は「後の六地蔵」を江戸六地蔵とし、その概略を辿ってみます。
史料のほか、こちら(巣鴨史跡散歩)/巣鴨駅前商店街振興組合・PDFに直リンクの資料がたいへんよくまとまっているので、参考にさせていただきました。
〔 江戸六地蔵の略縁起と概要 〕
江戸深川の(地蔵坊)正元坊が若い頃大病を患い、父母とともに病気平癒を地蔵菩薩に祈願したところ無事治癒しました。
快癒ののち、諸国を廻った正元坊は7つの苦行を成就しました。
正元坊は京都の六地蔵に倣い、宝永三年(1706年)に丈六金銅の地蔵菩薩坐像六体の造立の願を発しました。
正元坊は地蔵尊建立にあたり、愛宕、深川、神田、湯島などの神前に4年をかけて千日参りをなし、『江戸六地蔵建立之略縁起』という教化書(寄付を募る趣旨を記した書)発刊し、衆生に地蔵尊の御利益を説いて寄進活動をはじめました。
14年間にわたり寄進を募り浄財を集め、東都の(街道の)出入口にあたる六ヶ所にそれぞれ一体づつ安置開眼したといいます。
その六ヶ所とは東海道の品川寺(品川)・奥州街道の東禅寺(浅草)・甲州街道の太宗寺(新宿)・中山道の真性寺(巣鴨)・水戸街道の霊巌寺(白河)・千葉街道の永代寺(深川)です。
六体の地蔵菩薩像の像身ないし台座には勧進者や造立年代などが陰刻され、神田鍋町の鋳物師、太田駿河守藤原正義(儀)によって鋳造されたことがわかります。
寄進額は一文から二十両、身分を問わず幅広い人々から募ったという記録があるようです。
なお、『江戸砂子』や『東都(江戸)歳事記』には、正元坊は俗名を吉之郎といい、浮世草子『好色五人女』(貞享三年(1686年)刊)、浄瑠璃、歌舞伎などで広くとりあげられた八百屋お七の恋人(吉三郎)であったことを示す記述があります。(時代が合いませんが・・・)
江都三十三観音霊場(江戸三十三観音霊場の前身とされる)第11番の南緑山 圓乗寺はお七にゆかりがあり、江戸五色不動の目黒不動尊に向かう途中の明王院も、お七の恋人吉三郎が出家(西運上人)して入った寺と伝わるので、江戸のお寺めぐりと八百屋お七は、いずれつながりがあったのかもしれません。
六地蔵のうち、深川富岡八幡宮の二の鳥居付近にあった永代寺の地蔵菩薩(第6番)は、明治の廃仏毀釈で取り壊され現在は5体が残っています。
6体のうち、太田正義作の5体はすべて東京都指定有形文化財に指定されています。
現在は復興された永代寺のほか、旧6番の代仏とされる上野桜木の浄名院も参拝することが多いので、実質7ヶ寺の巡拝となります。
「後の六地蔵」の縁起は寶永三年(1706年)刊の『當國六地蔵造立之意趣』(『江戸六地蔵建立之略縁起』所収)(東京国立博物館デジタルライブラリー)に記載され、享保十七年(1732年)刊の『江戸砂子温故名跡誌』、天保九年(1838年)刊の『東都歳事記』にもとり上げられています。
原典とみられる『當國六地蔵造立之意趣』(同)から引用しますが、誤読があるかもしれません。(●は解読不能)
「抑(そもそも)(正元房)十二歳の頃故郷を出。十六歳に志て剃髪受戒す。そののち廿四歳の秋乃頃より重病を請。廿五歳の春の末に至て。醫術も叶難く死既に極れり。是●来のませるところにを。前日よりその相既に現れり。父母是を悲。偏に地蔵菩薩に延命を祷奉る。自も親の歎骨髄に通(とをり)。一心に地蔵菩薩に誓願すら●。我●菩薩の慈恩を蒙て。父母存生の内命を延るを得(ゑ)ば。盡未来際に至るまで。衆生の為に菩薩の御利益を勧。多(おおく)尊像を造立して衆生に帰依せしめ。共に安楽を得(ゑ)せしめんと誓。其夜不思議の霊験を得(ゑ)て重病速に本復す。其後諸国をめぐり無縁の衆生に多縁を結ば志む。我まさに世に生をふるとも。●●●●に。報恩乃ため地蔵菩薩の像前にて。七の難苦行を修せり。(中略)人のあざけりを省●。名利を求るに似たりといへども。------予づ願誓のこ妄にあらざるを示す。童男童女の信を勧て。尊像造立の願速に成就せしめんが為の事あり。我先年回国志せし砌。御在城を拝奉るに前念願しける。回国依り●べ二度こくに来て信人を勧。帝都の六地蔵に同く 御当地の入口毎に一躰づつ金銅壱丈六尺の地蔵菩薩を六所(むところ)に都合六躰造立して。天下安全 武運長久 御城下繁栄を祝願し。兼●ハ又諸国往来の一切衆生へ。普(あまね)く縁を結べ志めんと誓。」
「抑(そもそも)帝都六地蔵の濫觴ハ。人王五十四代仁明天皇の御宇参議小野篁。平等利益乃旨を思惟し給ひて。六度の能化なれバとて。自(みずから)六地蔵菩薩を造立し。天下安全宝祚延長洛陽繁栄万民快楽の為。かつ諸人性来の衢(ちまた)に安置し奉て。一切の衆生に普(あまね)く縁を結バしめ給んとぞ。帝都の六地蔵是也。我既に時節を得て。今度六躰の尊像像立をもよほして。此書見もんの人々。吾志を憐れ●ひて。一紙半銭の撰なく助成を加させ●え。我生ゞ世ゞにおいて永くその恩を報べし。大凡この尊像像立ハ。国土あらん限りの宝なるべし。金銅仏なれば火災●●滅せじ。壱丈六尺の大像なれば盗賊の失もなかるべし。諸人往来の衢(ちまた)に立れば一切●生皆悉く縁を結び奉る。拝願ハ神明仏薩の加護を蒙て。六躰の尊像つつがなく像立志て。万代の一切衆生と共に同く善行に●ん事を。」
勤化沙門 深川 地蔵坊正元謹言 寶永三丙戌年5月吉祥日 地蔵坊(印)
『江戸砂子温故名蹟誌 6巻3』(国立国会図書館DC)の醫王山 真性寺の項には以下の記載があります。
***************
地蔵坊正元法師建立唐銅六地蔵の三番也所謂六軀ハ
一番 品川 真言 品川寺
二番 四谷 浄土 大宗寺
三番 巣鴨 同(真言) 真性寺
四番 山谷 禅 東禅寺
五番 深川 浄土 霊巌寺
六番 深川 真言 永代寺
右六地蔵の●●元坊ハ俗名吉之郎とて八百屋の女お七●●もの●出家と云もの●●出家 ●六軀を造立●といひつ
されは宝永年中沙門正元坊か建立せし金銅丈六の六軀ハ世に後の六地藏といふと也
慈済庵空無上人勧化の助力を以 金銅立像八尺の地藏六軀を造立し江戶六ヶ所に安置す 元禄四年開眼供養を執行す これをはしめの六地藏といふ所謂六所ハ
一番 駒込 浄土 瑞泰寺
二番 千駄木 浄土 專念寺
三番 日暮里 諏訪 浄光寺
四番 池端 心行寺
五番 東叡山 大仏側 慈濟庵
六番 淺艸寺内 正智院
***************
また、『東都(江戸)歳事記 4巻 付録1巻』(国立国会図書館DC)に以下の記載があります。
***************
「江戸六地藏參 銅仏壹丈六尺坐像なり享條の頃深川の沙門地蔵坊正元造立す●●勤化の以宝永三戌六月(托鉢)して施銭をつのり●●建立縁起あり
一番 品川品川寺
二番 四谷大宗寺
三番 巣鴨真性寺
四番 山谷東禅寺
五番 深川霊巌寺
六番 同(深川)永代寺
正元房●十二歳の頃故地(未詳)を辞し其師に従ひ十六歳にして薙髪受戒を志うるに廿四歳の頃より重キヤマヒに伏し●●薬石の験もあらで今ハ黄泉の客と成ぬ●うりし●ハ 父母深く悲しみ地蔵尊●願●●れハ(中略)命を延る●らば(中略)多くの尊像を像立し後世の衆生に永く帰依せしめ●るべしと一心に誓しに 其夜不思議の霊夢(験)を感じて忽に快復しぬ 爾後諸国を回●●●衆生に縁を結ひ(中略)を修し或ハ千日に万巻の地蔵経をずしなりと東都●●
頃●●必復ひ●に此に来て銅像の六地蔵を造立し一軀ツツ東都の入口毎に安置し
保元二年例●●慕し天下安全を祈り●●往来の人々に●く縁を結んで
宝永三年●●の五月に●て初て●人と勤化し愛宕深川●田の三所へ
心願成就を祈り享保の(中略)建立縁起の●を志●●江戸砂子小云六地蔵の願主正元●俗名吉●●とて八百屋の女や七と云●●ふ出家し●六軀を造立●といひつ●ふ
***************
六地蔵の造立については、『蓮華三昧経』の所説に依るという説があります。
資料1では、當國六地蔵造立之意趣(東京国立博物館デジタルライブラリー)の「六地蔵の図」に「御姿ハ十王経によるなり。利益●ハ蓮花経に志たかふ」とあるのは、「その出典を明らかにしている。」とし、「正元のいう『蓮華経』は『蓮華三昧経』すなわち『法蓮華三昧秘密三昧耶経』のことである。」と記されています。
それにしても、東都江戸の街道の出入口に「天下安全洛陽繁栄万民快楽の為」に地蔵菩薩を造立安置するというのは、どうみても為政者の発想です。
実際、江戸守護のために置かれたという江戸五色不動は、「天海大僧正が江戸の守護結界のために五色の不動尊を安置」あるいは将軍家光公の命により整備されたと伝わります。
発願・建立者の正元坊の出自ははっきりとしていませんが、いかに地蔵尊への誓願により重病が快癒したとはいえ、六体の金銅仏を建立し市内各寺に安置開願するということは並大抵の苦労ではなかったと思われます。
6体の地蔵尊のうち5体までが東京都指定有形文化財に認定されている名作で、露仏で身近に拝せるということもあってか、江戸六地蔵はいまもなお参拝者を集めています。
〔 江戸六地蔵の所在 〕
江戸六地蔵には札番が振られていますので順にリストします。
第6番永代寺の代仏とされる浄名院、江戸六地蔵と同じ仏師作とされる地蔵尊が御座す浄土寺についてもご紹介します。
第1番 旧東海道
■ 海照山 普門院 品川寺
品川区南品川3-5-17
真言宗醍醐派 御本尊:正観世音菩薩
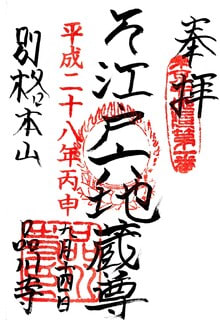
第2番 奥州街道
■ 洞雲山 東禅寺
台東区東浅草2-12-13
曹洞宗 御本尊:釈迦如来
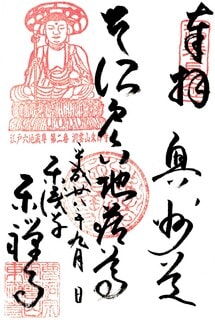
第3番 甲州街道
■ 霞関山 本覚院 太宗寺
新宿区新宿2-9-2
浄土宗
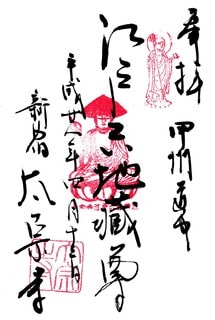
第4番 旧中山道
■ 医王山 東光院 真性寺
豊島区巣鴨3-21-21
真言宗豊山派 御本尊:薬師如来
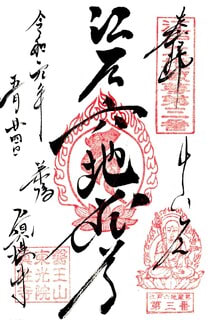
第5番 水戸街道
■ 道本山 東海院 霊巌寺
江東区白河1-3-32
浄土宗 御本尊:阿弥陀如来
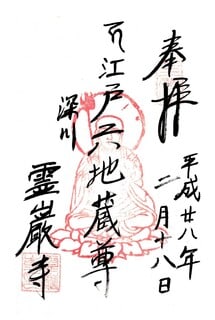
第6番 千葉街道(房総往還)
■ 大栄山 金剛神院 永代寺
江東区富岡1-15-1
高野山真言宗 御本尊:

第6番 千葉街道(房総往還)の代仏
■ 東叡山 浄名院
江東区富岡1-15-1
高野山真言宗 御本尊:阿弥陀如来

-------------
■ 平河山 源照院 浄土寺
港区赤坂4-3-5
浄土宗 御本尊:阿弥陀如来
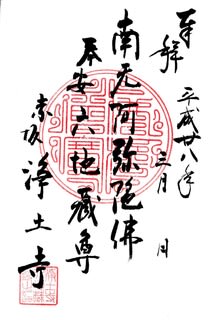
〔 江戸六地蔵の宗派 〕
第1番 海照山 普門院 品川寺 / 真言宗醍醐派
第2番 洞雲山 東禅寺 / 曹洞宗
第3番 霞関山 本覚院 太宗寺 / 浄土宗
第4番 医王山 東光院 真性寺 / 真言宗豊山派
第5番 道本山 東海院 霊巌寺 / 浄土宗
第6番 大栄山 金剛神院 永代寺 / 高野山真言宗
第6番(代仏) 東叡山 浄名院 / 高野山真言宗
7箇寺のうち、真言宗が4、浄土宗が2、曹洞宗が1で、江戸五色不動や江戸六阿弥陀でみられる天台宗寺院が入っていないのが特徴かもしれません。
〔 江戸六地蔵の回り方 〕
江戸時代には1番と6番以外は札番にこだわらず回られていたようなので、1日で回れそうな下のコースを考えてみました。
1.品川寺/1番(青物横丁)
2.太宗寺/4番(新宿御苑前・新宿三丁目)
3.真性寺/3番(巣鴨)
4.東禅寺/2番(東浅草)
5.霊巌寺/5番(清澄白河)
6.永代寺/旧6番(門前仲町)
7.浄名院/6番代仏(上野桜木)
駅からのアプローチはおおむねいいですが、4.東禅寺は駅から離れており、ここへのアプローチがポイントになります。
各寺見どころも多いので、できれば9時すぎには品川寺に到着したいところです。
1.品川寺/1番(青物横丁)
最寄り駅は京浜急行「青物横丁」駅、徒歩4分です。
「青物横丁」から「新宿御苑前」までは、JRを使うと品川・新宿の乗り換えがやっかいなので、下記がおすすめです。
■青物横丁(京浜急行・都営浅草線)→新橋〔乗換〕(メトロ銀座線)→赤坂見附〔乗換〕(メトロ丸ノ内線)→ 新宿御苑前 【乗換2回、約40分】
※青物横丁から都営浅草線直通に乗るか、品川で浅草線直通に乗り換える必要があります。
2.太宗寺/4番(新宿御苑前・新宿三丁目)
「新宿御苑前」駅3番出口(前寄り)、徒歩2分。
■太宗寺(徒歩3分位)→新宿三丁目(都営新宿線)→神保町〔乗換〕(都営三田線)→巣鴨 【乗換1回、約25分】
3.真性寺/3番(巣鴨)
「巣鴨」駅A3番出口(前寄り)、徒歩3分。
巣鴨からつぎの東禅寺(東浅草)までが最大の難関です。
ルートはいろいろとれますが、徒歩と乗り換えが少ないのは以下のルートかと思います。
■巣鴨(山手線・9分)→鶯谷〔乗換・徒歩約7分〕根岸三丁目バス停(区営バスぐるーりめぐりん・17分・時刻表)→吉原大門バス停 【乗換1回、約40分】
4.東禅寺/2番(東浅草)
吉原大門バス停、約200m徒歩3分。
鉄道駅までは遠いので、バスを使います。
■東禅寺→(徒歩200m3分位)→東浅草バス停(都バス42-1または42-2系統/本数多い・12分)→蔵前駅前バス停〔乗換〕蔵前(都営大江戸線・5分)→清澄白河 【乗換1回、約20分】
5.霊巌寺/5番(清澄白河)
「清澄白河」駅A3番出口(前寄り)、徒歩2分。
霊巌寺から旧6番永代寺までは1㎞ほどで歩けます。鉄道利用の場合は↓。
■霊巌寺→(徒歩2分)→清澄白河(都営大江戸線・2分)→門前仲町 【乗換なし、約4分】
6.永代寺/旧6番(門前仲町)
「門前仲町」駅1番出口(前寄り)、徒歩2分。
門前仲町から浄名院まではいろいろなルートがありますが、徒歩距離が短いのは下記のルートです。
■永代寺→(徒歩2分)→清澄白河(都営大江戸線・12分)→上野御徒町(A3出口)〔乗換・徒歩約2分〕上野公園バス停(都バス上25系統・時刻表・15分)→上野桜木バス停 【乗換1回、約30分】
ただし、都バス上25系統は30分~1時間に1本と本数が少ないので、時間が合わないときは御徒町からJRに乗り、鶯谷下車(北口・前寄り)で浄名院まで徒歩約8分です。
7.浄名院/6番代仏(上野桜木)
上野桜木バス停下車すぐです。
こちらは「上野さくら浄苑」寺務所で御朱印受付しており対応時間は原則17時までのようですが、16時を過ぎる場合はTEL確認がベターです。(0120-257-577/03-5832-9511)
なお、六地蔵の御朱印はすべての寺院で拝受できます。
それでは、1番から順にご案内していきます。
(つづく)
目下、年度末で仕事がテンパってるので時間ができたら追記します。
■ 武州江戸六阿弥陀詣 → 記事
■ 江戸五色不動 → 記事
これらの札所には桜の名所もいくつかあります。
また、武州江戸六阿弥陀詣は、お彼岸に詣でるものとされていました。
春の一日、桜を愛でつつ寺院めぐりでもいかがでしょうか。
■ 朧月夜 - 中島美嘉
名曲だから、こういう優れたアレンジテイクが生まれる。
中島美嘉の歌唱力も凄いが、葉加瀬太郎のバイオリンも圧巻。
-------------------------
作詞:高野辰之 作曲:岡野貞一
大正3年『尋常小学唱歌 第六学年用』に初出
菜の花畠に 入日薄れ
見わたす山の端(は) 霞ふかし
春風そよふく 空を見れば
夕月かかりて にほひ淡し
里わの火影(ほかげ)も 森の色も
田中の小路を たどる人も
蛙(かわづ)のなくねも かねの音も
さながら霞める 朧月夜
-------------------------
→ ■ 桜曲40曲! もどうぞ。
-------------------------
2021/09/06 UP
「武州江戸六阿弥陀詣の御朱印」、「江戸五色不動の御朱印」がけっこうなアクセスをいただいているので、江戸六地蔵についてもまとめてみます。
作成中です。文字だらけですみません。
江戸六地蔵は、江戸に入る街道の入口に安置された6体の地蔵菩薩を巡拝する地蔵尊霊場です。
江戸六地蔵には「はじめの六地蔵(最初建立江戸六地蔵)」と「後の六地蔵」があり、これを把握しないと混乱するので最初にまとめてみます。
「はじめの六地蔵」は、下谷池之端影向山心行寺三世の(慈済庵)本誉空無(浄土木食)が元禄四年(1691年)に建立開眼したと伝わります。
(こちら(『本譽空無上人道影贊』翻刻と解題/関口靜雄氏・PDFに直リンク、以下資料1)に詳しいです。)
「後の六地蔵」は、沙門正元坊が宝永年間(1704-1711年)に建立したと伝わります。
「はじめの六地蔵」は毎月二十四日ないし十八日の縁日に多くの信者を集めたと伝わりますがいつしか衰退し、いくつかは廃寺となったこともあり、現在江戸六地蔵として知られているのは正元坊建立の「後の六地蔵」です。
ただし、資料1によると『地藏本願經囑累品』/谷中安立院光輪印施には、
------------
空無上人發願造立
○六地藏尊靈塲 ○毎月十八日巡拜ノ衜順ニ記ス
番外 湯島新花町 靈雲寺
四番 池ノ端七軒町 心行寺
一番 駒込蓬萊町 瑞泰寺
二番 同千駄木町 專念寺
三番 日暮里 淨光寺
番外 谷中五重塔ノ奥 安立院
八万四千躰 上野山内 淨名院
五番 上野慈眼堂内 地藏堂
六番 金龍山仲見世 正智院
番外 淺草 駒形堂
------------
とあり、「はじめの六地蔵」の番外に「後の六地蔵」関連の靈雲寺と淨名院が姿をみせています。
また、Web上でみつかった『地藏菩薩俗談(三』)/眞鍋廣濟氏・PDFに直リンクには、「元緑四年になつてから『江戸はじめの六地藏』が設定せられ、次いで寳永三年には『江戸六地藏建立勘化帳』一巻が著されてゐるが、今日いふ東都の六地藏は、本郷駒込蓬莱町の瑞泰寺、同じく駒込千駄木町の專念寺、豊島區日暮里町の浄光寺、下谷廣池端七軒町の心行寺、同じく上野慈眼堂内の地藏堂、それに淺草寺雷門内の正智院の六個所で、尚この外に鋳銅六地藏と構してゐるのもあるが、これは荏原區品川町南品川宿の品川寺、淺草榮久町の東禅寺、豊島區巣鴨町の眞性寺、四谷區新宿二丁目の大宗寺、深川區霊岸町の霊巌寺、下谷區上野山内の浄名院の六寺院で、洛陽の信仰に摸つて、江戸の人士たちがそこに安置した鋳銅の地藏尊を一組として巡拝するものである。」とあります。
「東都の六地蔵」が「はじめの六地蔵」、「鋳銅六地藏」が「後の六地蔵」を示していることがわかります。
以降は「後の六地蔵」を江戸六地蔵とし、その概略を辿ってみます。
史料のほか、こちら(巣鴨史跡散歩)/巣鴨駅前商店街振興組合・PDFに直リンクの資料がたいへんよくまとまっているので、参考にさせていただきました。
〔 江戸六地蔵の略縁起と概要 〕
江戸深川の(地蔵坊)正元坊が若い頃大病を患い、父母とともに病気平癒を地蔵菩薩に祈願したところ無事治癒しました。
快癒ののち、諸国を廻った正元坊は7つの苦行を成就しました。
正元坊は京都の六地蔵に倣い、宝永三年(1706年)に丈六金銅の地蔵菩薩坐像六体の造立の願を発しました。
正元坊は地蔵尊建立にあたり、愛宕、深川、神田、湯島などの神前に4年をかけて千日参りをなし、『江戸六地蔵建立之略縁起』という教化書(寄付を募る趣旨を記した書)発刊し、衆生に地蔵尊の御利益を説いて寄進活動をはじめました。
14年間にわたり寄進を募り浄財を集め、東都の(街道の)出入口にあたる六ヶ所にそれぞれ一体づつ安置開眼したといいます。
その六ヶ所とは東海道の品川寺(品川)・奥州街道の東禅寺(浅草)・甲州街道の太宗寺(新宿)・中山道の真性寺(巣鴨)・水戸街道の霊巌寺(白河)・千葉街道の永代寺(深川)です。
六体の地蔵菩薩像の像身ないし台座には勧進者や造立年代などが陰刻され、神田鍋町の鋳物師、太田駿河守藤原正義(儀)によって鋳造されたことがわかります。
寄進額は一文から二十両、身分を問わず幅広い人々から募ったという記録があるようです。
なお、『江戸砂子』や『東都(江戸)歳事記』には、正元坊は俗名を吉之郎といい、浮世草子『好色五人女』(貞享三年(1686年)刊)、浄瑠璃、歌舞伎などで広くとりあげられた八百屋お七の恋人(吉三郎)であったことを示す記述があります。(時代が合いませんが・・・)
江都三十三観音霊場(江戸三十三観音霊場の前身とされる)第11番の南緑山 圓乗寺はお七にゆかりがあり、江戸五色不動の目黒不動尊に向かう途中の明王院も、お七の恋人吉三郎が出家(西運上人)して入った寺と伝わるので、江戸のお寺めぐりと八百屋お七は、いずれつながりがあったのかもしれません。
六地蔵のうち、深川富岡八幡宮の二の鳥居付近にあった永代寺の地蔵菩薩(第6番)は、明治の廃仏毀釈で取り壊され現在は5体が残っています。
6体のうち、太田正義作の5体はすべて東京都指定有形文化財に指定されています。
現在は復興された永代寺のほか、旧6番の代仏とされる上野桜木の浄名院も参拝することが多いので、実質7ヶ寺の巡拝となります。
「後の六地蔵」の縁起は寶永三年(1706年)刊の『當國六地蔵造立之意趣』(『江戸六地蔵建立之略縁起』所収)(東京国立博物館デジタルライブラリー)に記載され、享保十七年(1732年)刊の『江戸砂子温故名跡誌』、天保九年(1838年)刊の『東都歳事記』にもとり上げられています。
原典とみられる『當國六地蔵造立之意趣』(同)から引用しますが、誤読があるかもしれません。(●は解読不能)
「抑(そもそも)(正元房)十二歳の頃故郷を出。十六歳に志て剃髪受戒す。そののち廿四歳の秋乃頃より重病を請。廿五歳の春の末に至て。醫術も叶難く死既に極れり。是●来のませるところにを。前日よりその相既に現れり。父母是を悲。偏に地蔵菩薩に延命を祷奉る。自も親の歎骨髄に通(とをり)。一心に地蔵菩薩に誓願すら●。我●菩薩の慈恩を蒙て。父母存生の内命を延るを得(ゑ)ば。盡未来際に至るまで。衆生の為に菩薩の御利益を勧。多(おおく)尊像を造立して衆生に帰依せしめ。共に安楽を得(ゑ)せしめんと誓。其夜不思議の霊験を得(ゑ)て重病速に本復す。其後諸国をめぐり無縁の衆生に多縁を結ば志む。我まさに世に生をふるとも。●●●●に。報恩乃ため地蔵菩薩の像前にて。七の難苦行を修せり。(中略)人のあざけりを省●。名利を求るに似たりといへども。------予づ願誓のこ妄にあらざるを示す。童男童女の信を勧て。尊像造立の願速に成就せしめんが為の事あり。我先年回国志せし砌。御在城を拝奉るに前念願しける。回国依り●べ二度こくに来て信人を勧。帝都の六地蔵に同く 御当地の入口毎に一躰づつ金銅壱丈六尺の地蔵菩薩を六所(むところ)に都合六躰造立して。天下安全 武運長久 御城下繁栄を祝願し。兼●ハ又諸国往来の一切衆生へ。普(あまね)く縁を結べ志めんと誓。」
「抑(そもそも)帝都六地蔵の濫觴ハ。人王五十四代仁明天皇の御宇参議小野篁。平等利益乃旨を思惟し給ひて。六度の能化なれバとて。自(みずから)六地蔵菩薩を造立し。天下安全宝祚延長洛陽繁栄万民快楽の為。かつ諸人性来の衢(ちまた)に安置し奉て。一切の衆生に普(あまね)く縁を結バしめ給んとぞ。帝都の六地蔵是也。我既に時節を得て。今度六躰の尊像像立をもよほして。此書見もんの人々。吾志を憐れ●ひて。一紙半銭の撰なく助成を加させ●え。我生ゞ世ゞにおいて永くその恩を報べし。大凡この尊像像立ハ。国土あらん限りの宝なるべし。金銅仏なれば火災●●滅せじ。壱丈六尺の大像なれば盗賊の失もなかるべし。諸人往来の衢(ちまた)に立れば一切●生皆悉く縁を結び奉る。拝願ハ神明仏薩の加護を蒙て。六躰の尊像つつがなく像立志て。万代の一切衆生と共に同く善行に●ん事を。」
勤化沙門 深川 地蔵坊正元謹言 寶永三丙戌年5月吉祥日 地蔵坊(印)
『江戸砂子温故名蹟誌 6巻3』(国立国会図書館DC)の醫王山 真性寺の項には以下の記載があります。
***************
地蔵坊正元法師建立唐銅六地蔵の三番也所謂六軀ハ
一番 品川 真言 品川寺
二番 四谷 浄土 大宗寺
三番 巣鴨 同(真言) 真性寺
四番 山谷 禅 東禅寺
五番 深川 浄土 霊巌寺
六番 深川 真言 永代寺
右六地蔵の●●元坊ハ俗名吉之郎とて八百屋の女お七●●もの●出家と云もの●●出家 ●六軀を造立●といひつ
されは宝永年中沙門正元坊か建立せし金銅丈六の六軀ハ世に後の六地藏といふと也
慈済庵空無上人勧化の助力を以 金銅立像八尺の地藏六軀を造立し江戶六ヶ所に安置す 元禄四年開眼供養を執行す これをはしめの六地藏といふ所謂六所ハ
一番 駒込 浄土 瑞泰寺
二番 千駄木 浄土 專念寺
三番 日暮里 諏訪 浄光寺
四番 池端 心行寺
五番 東叡山 大仏側 慈濟庵
六番 淺艸寺内 正智院
***************
また、『東都(江戸)歳事記 4巻 付録1巻』(国立国会図書館DC)に以下の記載があります。
***************
「江戸六地藏參 銅仏壹丈六尺坐像なり享條の頃深川の沙門地蔵坊正元造立す●●勤化の以宝永三戌六月(托鉢)して施銭をつのり●●建立縁起あり
一番 品川品川寺
二番 四谷大宗寺
三番 巣鴨真性寺
四番 山谷東禅寺
五番 深川霊巌寺
六番 同(深川)永代寺
正元房●十二歳の頃故地(未詳)を辞し其師に従ひ十六歳にして薙髪受戒を志うるに廿四歳の頃より重キヤマヒに伏し●●薬石の験もあらで今ハ黄泉の客と成ぬ●うりし●ハ 父母深く悲しみ地蔵尊●願●●れハ(中略)命を延る●らば(中略)多くの尊像を像立し後世の衆生に永く帰依せしめ●るべしと一心に誓しに 其夜不思議の霊夢(験)を感じて忽に快復しぬ 爾後諸国を回●●●衆生に縁を結ひ(中略)を修し或ハ千日に万巻の地蔵経をずしなりと東都●●
頃●●必復ひ●に此に来て銅像の六地蔵を造立し一軀ツツ東都の入口毎に安置し
保元二年例●●慕し天下安全を祈り●●往来の人々に●く縁を結んで
宝永三年●●の五月に●て初て●人と勤化し愛宕深川●田の三所へ
心願成就を祈り享保の(中略)建立縁起の●を志●●江戸砂子小云六地蔵の願主正元●俗名吉●●とて八百屋の女や七と云●●ふ出家し●六軀を造立●といひつ●ふ
***************
六地蔵の造立については、『蓮華三昧経』の所説に依るという説があります。
資料1では、當國六地蔵造立之意趣(東京国立博物館デジタルライブラリー)の「六地蔵の図」に「御姿ハ十王経によるなり。利益●ハ蓮花経に志たかふ」とあるのは、「その出典を明らかにしている。」とし、「正元のいう『蓮華経』は『蓮華三昧経』すなわち『法蓮華三昧秘密三昧耶経』のことである。」と記されています。
それにしても、東都江戸の街道の出入口に「天下安全洛陽繁栄万民快楽の為」に地蔵菩薩を造立安置するというのは、どうみても為政者の発想です。
実際、江戸守護のために置かれたという江戸五色不動は、「天海大僧正が江戸の守護結界のために五色の不動尊を安置」あるいは将軍家光公の命により整備されたと伝わります。
発願・建立者の正元坊の出自ははっきりとしていませんが、いかに地蔵尊への誓願により重病が快癒したとはいえ、六体の金銅仏を建立し市内各寺に安置開願するということは並大抵の苦労ではなかったと思われます。
6体の地蔵尊のうち5体までが東京都指定有形文化財に認定されている名作で、露仏で身近に拝せるということもあってか、江戸六地蔵はいまもなお参拝者を集めています。
〔 江戸六地蔵の所在 〕
江戸六地蔵には札番が振られていますので順にリストします。
第6番永代寺の代仏とされる浄名院、江戸六地蔵と同じ仏師作とされる地蔵尊が御座す浄土寺についてもご紹介します。
第1番 旧東海道
■ 海照山 普門院 品川寺
品川区南品川3-5-17
真言宗醍醐派 御本尊:正観世音菩薩
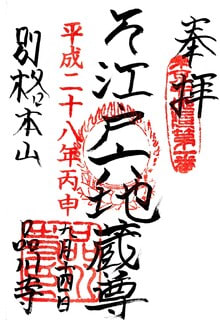
第2番 奥州街道
■ 洞雲山 東禅寺
台東区東浅草2-12-13
曹洞宗 御本尊:釈迦如来
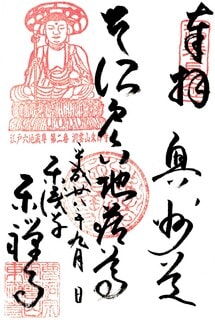
第3番 甲州街道
■ 霞関山 本覚院 太宗寺
新宿区新宿2-9-2
浄土宗
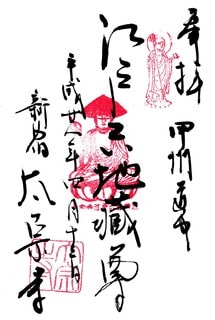
第4番 旧中山道
■ 医王山 東光院 真性寺
豊島区巣鴨3-21-21
真言宗豊山派 御本尊:薬師如来
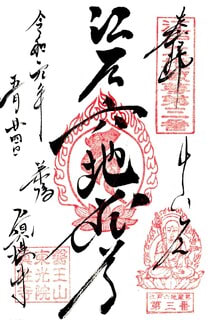
第5番 水戸街道
■ 道本山 東海院 霊巌寺
江東区白河1-3-32
浄土宗 御本尊:阿弥陀如来
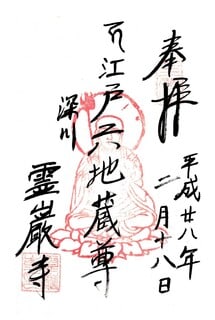
第6番 千葉街道(房総往還)
■ 大栄山 金剛神院 永代寺
江東区富岡1-15-1
高野山真言宗 御本尊:

第6番 千葉街道(房総往還)の代仏
■ 東叡山 浄名院
江東区富岡1-15-1
高野山真言宗 御本尊:阿弥陀如来

-------------
■ 平河山 源照院 浄土寺
港区赤坂4-3-5
浄土宗 御本尊:阿弥陀如来
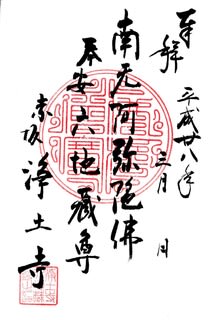
〔 江戸六地蔵の宗派 〕
第1番 海照山 普門院 品川寺 / 真言宗醍醐派
第2番 洞雲山 東禅寺 / 曹洞宗
第3番 霞関山 本覚院 太宗寺 / 浄土宗
第4番 医王山 東光院 真性寺 / 真言宗豊山派
第5番 道本山 東海院 霊巌寺 / 浄土宗
第6番 大栄山 金剛神院 永代寺 / 高野山真言宗
第6番(代仏) 東叡山 浄名院 / 高野山真言宗
7箇寺のうち、真言宗が4、浄土宗が2、曹洞宗が1で、江戸五色不動や江戸六阿弥陀でみられる天台宗寺院が入っていないのが特徴かもしれません。
〔 江戸六地蔵の回り方 〕
江戸時代には1番と6番以外は札番にこだわらず回られていたようなので、1日で回れそうな下のコースを考えてみました。
1.品川寺/1番(青物横丁)
2.太宗寺/4番(新宿御苑前・新宿三丁目)
3.真性寺/3番(巣鴨)
4.東禅寺/2番(東浅草)
5.霊巌寺/5番(清澄白河)
6.永代寺/旧6番(門前仲町)
7.浄名院/6番代仏(上野桜木)
駅からのアプローチはおおむねいいですが、4.東禅寺は駅から離れており、ここへのアプローチがポイントになります。
各寺見どころも多いので、できれば9時すぎには品川寺に到着したいところです。
1.品川寺/1番(青物横丁)
最寄り駅は京浜急行「青物横丁」駅、徒歩4分です。
「青物横丁」から「新宿御苑前」までは、JRを使うと品川・新宿の乗り換えがやっかいなので、下記がおすすめです。
■青物横丁(京浜急行・都営浅草線)→新橋〔乗換〕(メトロ銀座線)→赤坂見附〔乗換〕(メトロ丸ノ内線)→ 新宿御苑前 【乗換2回、約40分】
※青物横丁から都営浅草線直通に乗るか、品川で浅草線直通に乗り換える必要があります。
2.太宗寺/4番(新宿御苑前・新宿三丁目)
「新宿御苑前」駅3番出口(前寄り)、徒歩2分。
■太宗寺(徒歩3分位)→新宿三丁目(都営新宿線)→神保町〔乗換〕(都営三田線)→巣鴨 【乗換1回、約25分】
3.真性寺/3番(巣鴨)
「巣鴨」駅A3番出口(前寄り)、徒歩3分。
巣鴨からつぎの東禅寺(東浅草)までが最大の難関です。
ルートはいろいろとれますが、徒歩と乗り換えが少ないのは以下のルートかと思います。
■巣鴨(山手線・9分)→鶯谷〔乗換・徒歩約7分〕根岸三丁目バス停(区営バスぐるーりめぐりん・17分・時刻表)→吉原大門バス停 【乗換1回、約40分】
4.東禅寺/2番(東浅草)
吉原大門バス停、約200m徒歩3分。
鉄道駅までは遠いので、バスを使います。
■東禅寺→(徒歩200m3分位)→東浅草バス停(都バス42-1または42-2系統/本数多い・12分)→蔵前駅前バス停〔乗換〕蔵前(都営大江戸線・5分)→清澄白河 【乗換1回、約20分】
5.霊巌寺/5番(清澄白河)
「清澄白河」駅A3番出口(前寄り)、徒歩2分。
霊巌寺から旧6番永代寺までは1㎞ほどで歩けます。鉄道利用の場合は↓。
■霊巌寺→(徒歩2分)→清澄白河(都営大江戸線・2分)→門前仲町 【乗換なし、約4分】
6.永代寺/旧6番(門前仲町)
「門前仲町」駅1番出口(前寄り)、徒歩2分。
門前仲町から浄名院まではいろいろなルートがありますが、徒歩距離が短いのは下記のルートです。
■永代寺→(徒歩2分)→清澄白河(都営大江戸線・12分)→上野御徒町(A3出口)〔乗換・徒歩約2分〕上野公園バス停(都バス上25系統・時刻表・15分)→上野桜木バス停 【乗換1回、約30分】
ただし、都バス上25系統は30分~1時間に1本と本数が少ないので、時間が合わないときは御徒町からJRに乗り、鶯谷下車(北口・前寄り)で浄名院まで徒歩約8分です。
7.浄名院/6番代仏(上野桜木)
上野桜木バス停下車すぐです。
こちらは「上野さくら浄苑」寺務所で御朱印受付しており対応時間は原則17時までのようですが、16時を過ぎる場合はTEL確認がベターです。(0120-257-577/03-5832-9511)
なお、六地蔵の御朱印はすべての寺院で拝受できます。
それでは、1番から順にご案内していきます。
(つづく)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1A(導入編)
■ 2023/02/15 UP
今年(令和五年)は弘法大師御誕生1250年の記念の年です。
→ 金剛峯寺の公式Web
そこで、御府内八十八ヶ所霊場の御朱印のご紹介をはじめることにしました。
■ 2024/02/28 UP
ようやく(一応)完成しました。
この記事を書いている途中で『御府内八十八ケ所道しるべ』の存在に気づいたため、途中から構成が変わっております。
ひとまずはこれで完結としますが、後日前半の構成を整えていきたいと思います。
-------------------------
□ 札所リスト
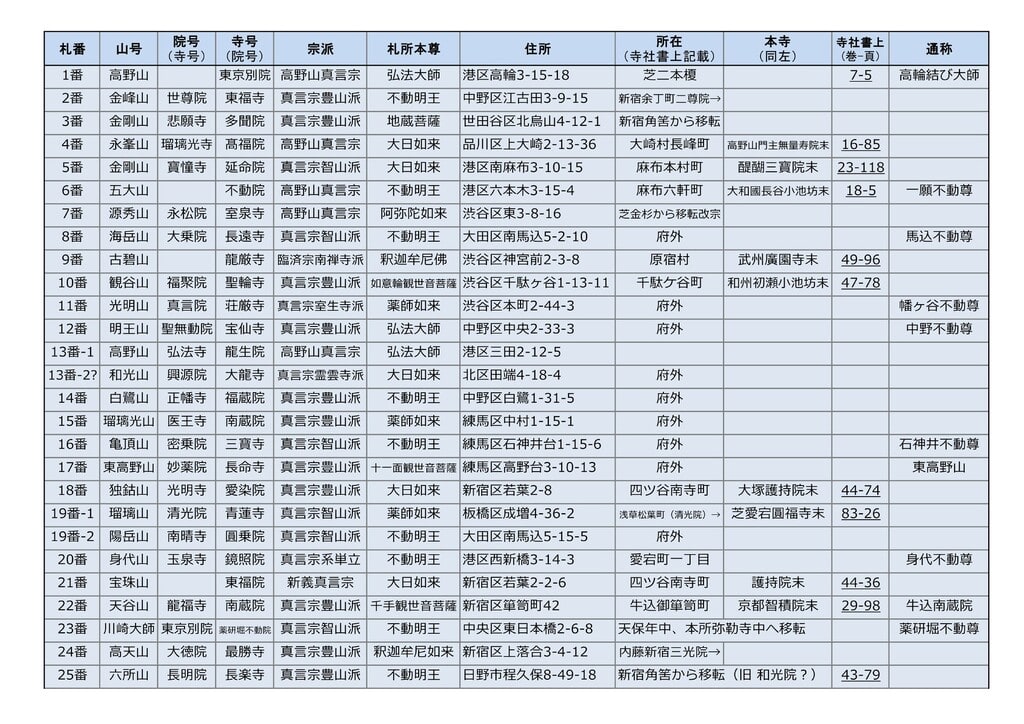
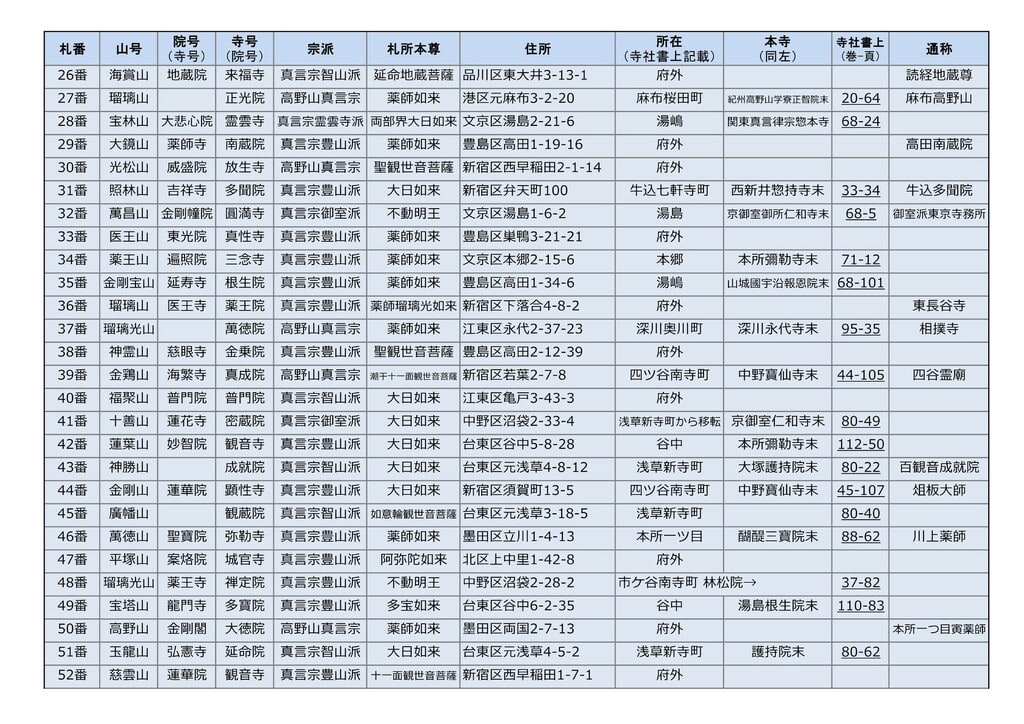
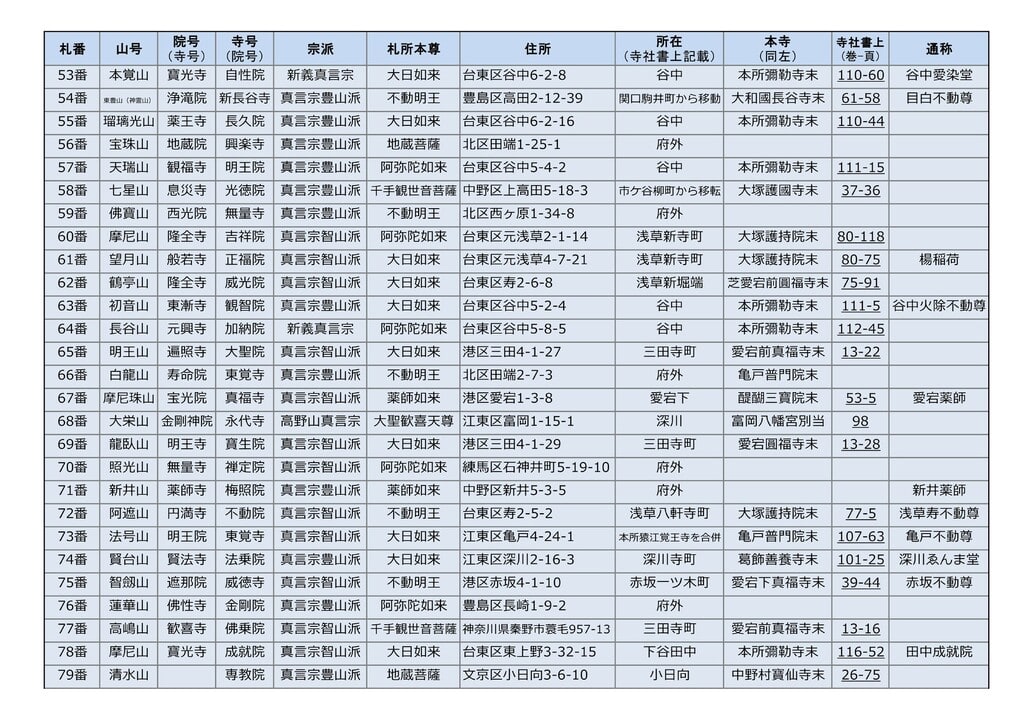
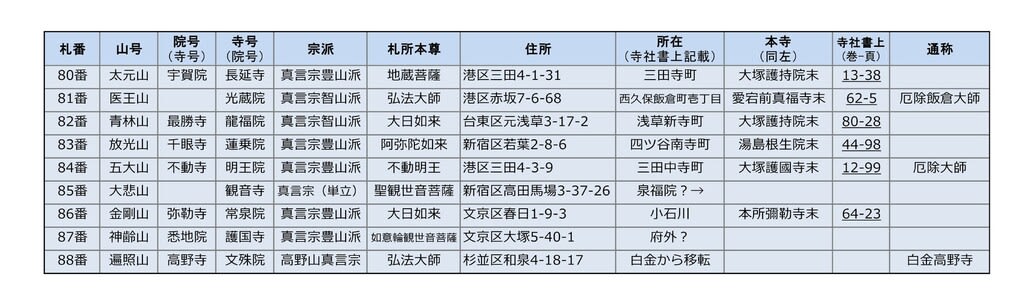
□ 記事へのリンク
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1B
第1番
高野山東京別院(港区高輪)
第2番
金峰山 東福寺(中野区江古田)
第3番
金剛山 多聞院(世田谷区北烏)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-2
第4番
永峯山 高福院(品川区上大崎)
第5番
金剛山 延命院(港区南麻布)
第6番
五大山 不動院(港区六本木)
第7番
源秀山 室泉寺(渋谷区東)
第8番
海岳山 長遠寺(大田区南馬込)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-3
第9番
古碧山 龍厳寺(渋谷区神宮前)
第10番
観谷山 聖輪寺(渋谷区千駄ヶ谷)
第11番
光明山 荘厳寺(渋谷区本町)
第12番
明王山 宝仙寺(中野区中央)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-4
第13番-1
三田高野山 龍生院(弘法寺)(港区三田)
第13番-2
和光山 大龍寺(北区田端)
第14番
白鷺山 福蔵院(中野区白鷺)
第15番
瑠璃光山 南蔵院(練馬区中村)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-5
第16番
亀頂山 三寶寺(練馬区石神井台)
第17番
東高野山 長命寺(練馬区高野台)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-6
第18番
獨鈷山 愛染院(新宿区若葉)
第19番-1
瑠璃山 青蓮寺(板橋区成増)
第19番-2
陽岳山 圓乗院(大田区南馬込)
第20番
身代山 鏡照院(港区西新橋)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-7
第21番
寶珠山 東福院(新宿区若葉)
第22番
天谷山 南蔵院(新宿区箪笥町)
第23番
川崎大師東京別院 薬研堀不動院(中央区東日本橋)
第24番
高天山 最勝寺(新宿区上落合)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-8
第25番
六所山 長楽寺(日野市程久保)
第26番
海賞山 来福寺(品川区東大井)
第27番
瑠璃山 正光院(港区元麻布)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-9
第28番
宝林山 霊雲寺(文京区湯島)
第29番
大鏡山 南蔵院(豊島区高田)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-10
第30番
光松山 放生寺(新宿区西早稲田)
第31番
照林山 多聞院(新宿区弁天町)
第32番
萬昌山 圓満寺(文京区湯島)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-11
第33番
醫王山 眞性寺(豊島区巣鴨)
第34番
薬王山 三念寺(文京区本郷)
第35番
金剛寶山 根生院(豊島区高田)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-12
第36番
瑠璃山 薬王院(新宿区下落合)
第37番
瑠璃光山 萬徳院(江東区永代)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-13
第38番
神霊山 金乗院(豊島区高田)
第39番
金鶏山 真成院(新宿区若葉)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-14
第40番
福聚山 普門院(江東区亀戸)
第41番
十善山 密蔵院(中野区沼袋)
第42番
蓮葉山 観音寺(台東区谷中)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-15
第43番
神勝山 成就院(台東区元浅草)
第44番
金剛山 顕性寺(新宿区須賀町)
第45番
廣幡山 観蔵院(台東区元浅草)
第46番
萬徳山 弥勒寺(墨田区立川)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-16
第47番
平塚山 城官寺(北区上中里)
第48番
瑠璃光山 禅定院(中野区沼袋)
第49番
寶塔山 多寶院(台東区谷中)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-17
第50番
高野山 大徳院(墨田区両国)
第51番
玉龍山 延命院(台東区元浅草)
第52番
慈雲山 観音寺(新宿区西早稲田)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-18
第53番
本覚山 自性院(台東区谷中)
第54番
東豊山 新長谷寺(豊島区高田)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-19
第55番
瑠璃光山 長久院(台東区谷中)
第56番
宝珠山 與楽寺(北区田端)
第57番
天瑞山 明王院(台東区谷中)
第58番
七星山 光徳院(中野区上高田)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-20
第59番
佛寶山 無量寺(北区西ヶ原)
第60番
摩尼山 吉祥院(台東区元浅草)
第61番
望月山 正福院(台東区元浅草)
第62番
鶴亭山 威光院(台東区寿)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-21
第63番
初音山 観智院(台東区谷中)
第64番
長谷山 加納院(台東区谷中)
第65番
明王山 大聖院(港区三田)
第66番
白龍山 東覚寺(北区田端)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-22
第67番
摩尼珠山 真福寺(港区愛宕)
第68番
大栄山 永代寺(江東区富岡)
第69番
龍臥山 宝生院(港区三田)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-23
第70番
照光山 禅定院(練馬区石神井町)
第71番
新井山 梅照院(中野区新井)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-24
第72番
阿遮山 不動院(台東区寿)
第73番
法号山 東覚寺(江東区亀戸)
第74番
賢臺山 法乗院(江東区深川)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-25
第75番
智劔山 威徳寺(港区赤坂)
第76番
蓮華山 金剛院(豊島区長崎)
第77番
高嶋山 佛乗院(神奈川県秦野市蓑毛)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-26
第78番
摩尼山 成就院(台東区東上野)
第79番
清水山 専教院(文京区小日向)
第80番
太元山 長延寺(港区三田)
第81番
医王山 光蔵院(港区赤坂)
第82番
青林山 龍福院(台東区元浅草)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-27
第83番
放光山 蓮乗院(新宿区若葉)
第84番
五大山 明王院(港区三田)
第85番
大悲山 観音寺(新宿区高田馬場)
第86番
金剛山 常泉院(文京区春日)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-28
第87番
神齢山 護国寺(文京区大塚)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-29
第88番
遍照山 文殊院(杉並区和泉)
-------------------------
御府内八十八ヶ(箇)所とは、東京都内にある弘法大師ゆかりの寺院を巡拝する弘法大師霊場です。(以下、「御府内霊場」と記します。)
「御府内」とは「江戸町奉行が支配の対象とする江戸(の範囲内)」ないし「寺社勧化場として許可された江戸(の範囲内)」といわれ、時代によって変化したといいます。
東京都公文書館のWeb資料には以下のとおりあります。
-------------------------
文政元年(1818)8月に、目付牧助右衛門から「御府内外境筋之儀」についての伺いが出されました。
この伺いを契機に、評定所で入念な評議が行われました。このときの答申にもとづき、同年12月に老中阿部正精から「書面伺之趣、別紙絵図朱引ノ内ヲ御府内ト相心得候様」と、幕府の正式見解が示されたのです。
その朱引で示された御府内の範囲とは、およそ次のようになります。
東…中川限り
西…神田上水限り
南…南品川町を含む目黒川辺
北…荒川・石神井川下流限り
この朱引図には、朱線と同時に黒線(墨引)が引かれており、この墨引で示された範囲が、町奉行所支配の範囲を表しています。朱引と墨引を見比べると、例外的に目黒付近で墨引が朱引の外側に突出していることを除けば、ほぼ朱引の範囲内に墨引が含まれる形になっていることが見てとれます。
以来、江戸の範囲といえば、この朱引の範囲と解釈されるようになったのです。
-------------------------
このようにきわめて明快に説明されています。
つまり、江戸御府内=江戸朱引図内ということです。
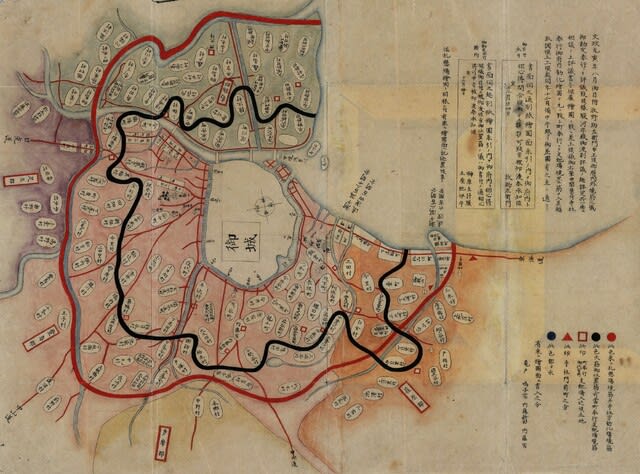
■ 江戸朱引図(東京都公文書館Web公開資料)
たとえば 江戸朱引図(東京都公文書館)をみると田畑村はしっかり朱引図内に収まっており、田端は御府内に位置することがわかります。

■ 朱引きと田畑村の位置関係(東京都公文書館Web公開資料を筆者にて加工)
以上のとおり、文政元年(1818年)頃の「御府内」の範囲は、東は亀戸・小名木村辺、西は角筈村・代々木辺、南は上大崎村・南品川町辺、北は上尾久・下板橋村辺の内側と定められています。
-------------------------
『全国霊場大事典』(六月書房)によると、御府内霊場の開創は宝暦年間(1751年~)頃とされています。
同書によると、信州・浅間山真楽寺の憲浄僧正と千葉県松戸の諦信によって四国八十八ヶ所霊場が写されたものとされ、四国霊場の札所の土(お砂)を各札所の拝前におき、こちらを踏んで巡拝すれば四国霊場巡拝と同様のご利益が得られるとされる点は、全国各地の弘法大師(新四国)霊場と同様です。
『全国霊場巡拝事典』(大法輪閣)では、宝暦五年(1755年)刊の『大進夜話』に「江戸にも此頃は信州浅間山の上人本願にて、四国の八十八箇所を移して立札など見えたり」とあり、文化十三年(1816年)の札所案内には「宝暦五乙亥三月下総葛飾松戸宿諦信の子、出家して信州浅間山真楽寺の住になりぬ。両人本願して江戸に霊場をうつす」とあることを紹介しています。
さらに文政五年(1822年)刊の十返舎一九著『諸国道中金の草鞋』にも「宝暦の頃下総の國松戸宿の諦信●子●預して東都に八十八ヶ所の霊場を●●といへり。」との記載があり、宝暦年間、憲浄僧正と松戸の諦信による開創説でおおむね定まっているようです。
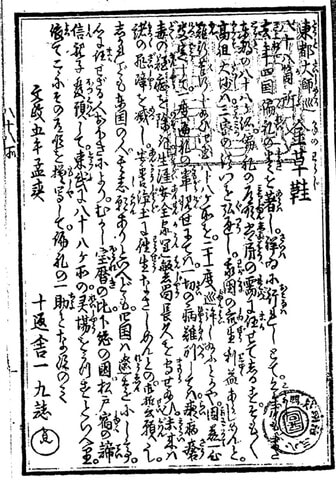
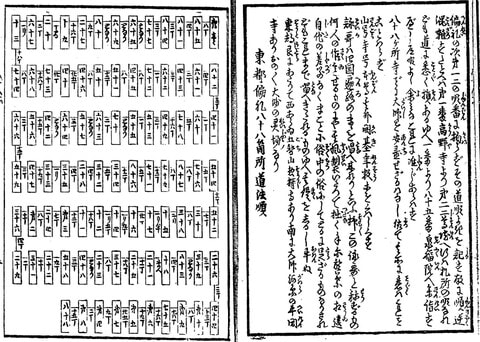
【写真 上(左)】 十返舎一九『諸国道中金の草鞋』二十一篇「東都大師巡八十八箇所」(文政五年(1822年))
【写真 下(右)】 同
※ 十返舎一九 著 ほか『諸国道中金の草鞋』21,嵩山堂,〔 〕. 国立国会図書館DC より転載。
このことは「公訴発願 信州浅間真楽寺上人 巡行願主 下総国 諦信」と刻まれた札所碑が第42番観音寺にあり、他の札所にも同様の石碑が残ることからも裏付けられるとされています。(『全国霊場巡拝事典』)
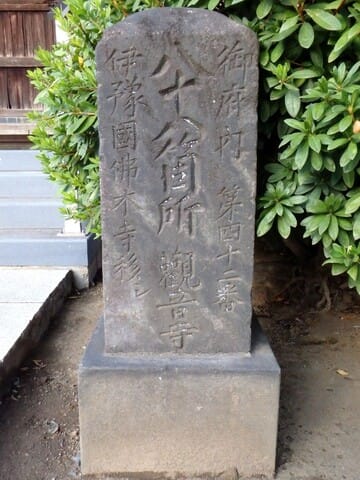
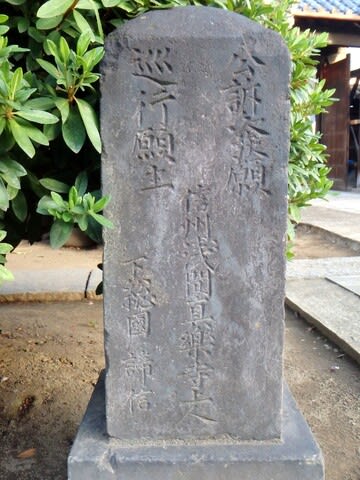
【写真 上(左)】 第42番観音寺の御府内霊場札所碑
【写真 下(右)】 「公訴発願 信州浅間真楽寺上人 巡行願主 下総國 諦信」とあります
なお、同書によると、これとは別に正等和尚(1703-1774年)という人が開創という説もあるようです。
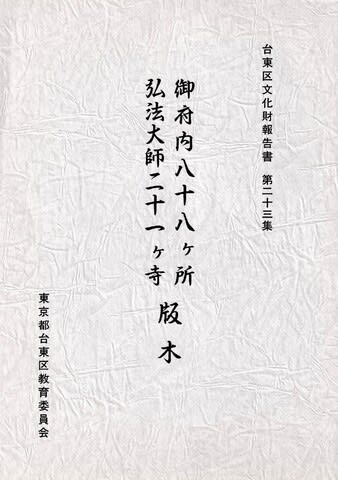
『御府内八十八ヶ所 弘法大師二十一ヶ寺 版木』(台東区教育委員会刊)には、「第十七番札所長命寺には「宝暦三癸酉三月廿一日」銘の御府内八十八ヶ所標石が現存する。(略)この銘文を信じる限り宝暦三年(1753年)三月までに開設されていたことになる。」
同書では第17番長命寺の標石と宝暦五年(1755年)刊の『大進夜話』を根拠とし、「ここでは、宝暦二年(1752年)頃『浅間山真楽寺住職』の開設とし、不明な点は後考に俟つこととしたい。」とあります。


【写真 上(左)】 第17番長命寺の御府内八十八ヶ所標石-1
【写真 下(右)】 同-2
また、同書には「本版木第二六丁によれば『廿三里十三丁五間』、約九二キロの行程で、御府内在住の健脚であれば三~四日で巡ったものと思われる。」とあります。
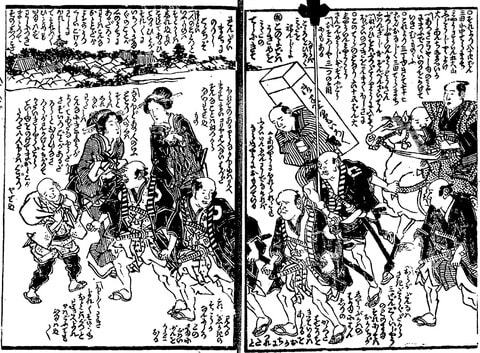
十返舎一九『諸国道中金の草鞋』二十一篇「東都大師巡八十八箇所」(文政五年(1822年))
※ 十返舎一九 著 ほか『諸国道中金の草鞋』21,嵩山堂,〔 〕. 国立国会図書館DC より転載。
---------------------------------
御府内霊場の前身ともいわれる霊場に江戸八十八ヶ所霊場があります。
初番は高輪の正覚院、第88番結願は御府内霊場と同様文殊院で、御府内霊場と重複する札所が多いですが、微妙に異なる札番構成で廃寺も含みます。
→ 札所リストはこちら(『ニッポンの霊場』様)
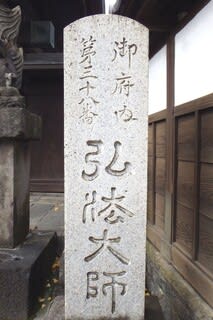
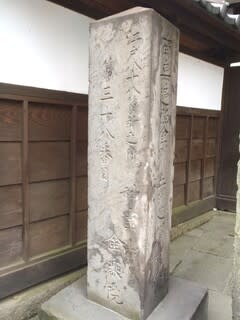
【写真 上(左)】 第38番金乗院の御府内霊場札所碑
【写真 下(右)】 同 江戸八十八ヶ所霊場第38番の札所碑
御府内霊場第2番はもともとは新宿・余丁町の二尊院で、のちに江古田・東福寺に遷ったともされますが、江戸八十八ヶ所霊場第2番は二尊院となっています。
また、江戸八十八ヶ所の札所は御府内霊場に比べて御府内の札所が多くなっているので、あるいは御府内霊場の前身の可能性もあるのかもしれません。
廃寺・移動となった札番の変遷をこまかく追っていけばなにか見えてくるものがあるのかも知れませんが、なにぶん江戸八十八ヶ所霊場は記録がすくなく、それもむずかしいかもしれません。
現在、寺院移転により御府内霊場の2つの札所は都区外に移転していますが、それ以外は東京都区内の所在で、まさに「東京のお遍路」ということができます。
■ 第56番 宝珠山 地蔵院 與楽寺(北区田端)
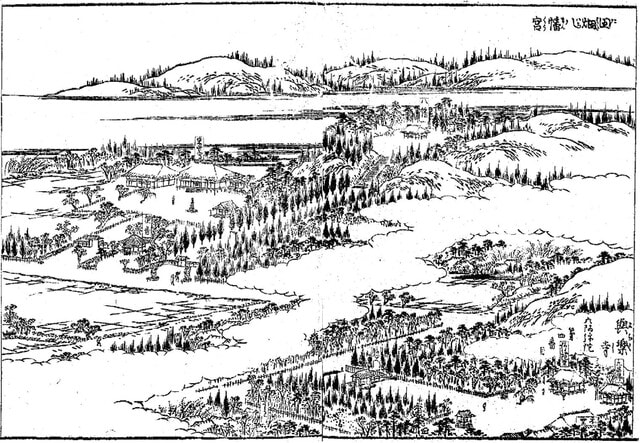
※ 『江戸名所図会』十五(国会図書館DC(保護期間満了資料)より転載)
■ 第59番 佛寶山 西光院 無量寺(北区西ヶ原)
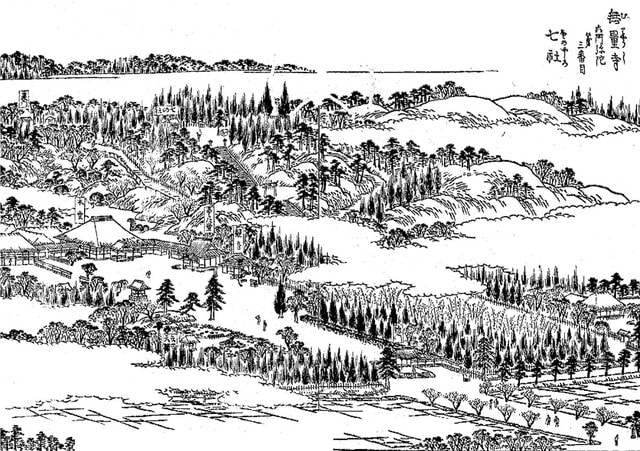
※ 『江戸名所図会』十五(国会図書館DC(保護期間満了資料)より転載)
-------------------------
現在、霊場会の活動があるかは不明ですが、すべての札所で御朱印を授与され、発願(第1番)の高野山東京別院では専用の集印帳を頒布されています。
この集印帳は白地ですが差し替え方式もとれるため、現在はこの専用集印帳の使用が奨励されている模様です。
また、筆者は専用集印帳以外では御朱印を授与しないという掲示をされている札所も確認しています。(現況は不明)
多くの札所では汎用御朱印帳でも快く授与いただけますが、御朱印コンプリートを目指す向きは専用集印帳使用がベターかと思います。
札所一覧は→こちら(ニッポンの霊場様)、札所位置図については→こちら(第76番蓮華山金剛院様公式Web)に掲載があります。
筆者にて札番重複札所がふたつ(第13番、第19番)あることは確認しており、いずれも御朱印を拝受できます。
掛所、番外、特別札所はないので、コンプリートは90箇寺(札所)ということになります。
順路は、札番がエリアを越えて飛んでいるので順打ち、逆打ちともに効率が悪くなります。
発願(第1番)の高野山東京別院(港区高輪)、結願(第88番)の遍照山 文殊院(杉並区和泉)はおさえるとしても、その他の札所はアクセスを考えてランダムに回ってもいいかもしれません。
駐車場がない札所や狭い路地奥の札所もありますので、車での巡拝はおすすめしません。
多くの札所は鉄道駅から徒歩圏内で、東京メトロ駅利用も多いので「東京メトロ24時間券」が威力を発揮します。
日本橋、六本木、赤坂、四ッ谷など都心のお寺をはじめ、谷根千、高田、沼袋や烏山など都内有数の寺町も外さずに回る、エリア的にも変化に富んだ巡礼が味わえます。
ただし、荒綾霊場、南葛霊場、荒川辺霊場などがある下町エリアの札所は少なくなっており、どちらかというと都心~山の手寄りの霊場といえます。
宗派は禅宗1箇寺をのぞきすべて真言宗で、多くは新義真言宗(智山派、豊山派など)。
新義真言宗寺院が多い東京らしい弘法大師霊場といえましょう。
御朱印は多くが御寶印(札所本尊のお種子)で、札所本尊、弘法大師、興教大師が揮毫され、札所印も捺される華々しいものです。
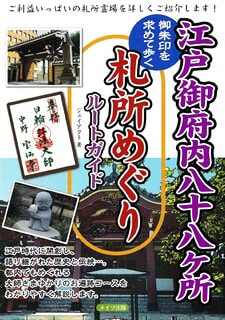
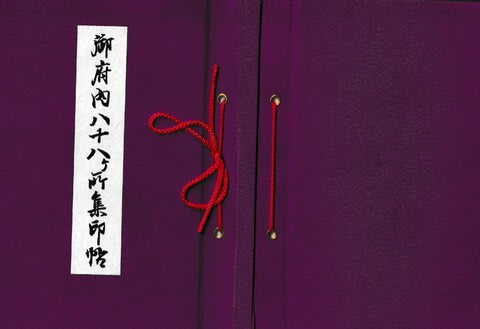
【写真 上(左)】 霊場ガイド(メイツ出版)(以下『札所めぐり』)
【写真 下(右)】 専用集印帳
専用集印帳は大判で紙質がよく筆の走りもよいようで、いただいた御朱印はどれも見応えがあります。
和綴じ様式なので参拝の順序にかかわらず、札番順に綴じ込むことができるのは大きな利点です。
なお、お納めは以前は300円でしたが、現在は500円に改定されているかもしれません。(札所によりまちまちのようです。)
都内の札所メインですが、御朱印対応時間は9:00~16:00が多く夕刻には件数を稼げません。
札所での拝所は札所本尊(多くは本堂の御本尊)と弘法大師尊像ないし大師堂の二箇所となり、各寺見どころも多いので、じっくりと時間をかけて回る霊場かと思います。
また、他の霊場との兼任札所も複数ありますが、御府内霊場については1参拝ひとつの拝受がベターかもしれません。
とくに豊島八十八箇所の御朱印と併せてお願いすることは、実質的な弘法大師霊場の掛け持ち巡拝となるので個人的には避けた方がベターかと思います。
【 いわゆる「難所」について 】
八十八もの札所を数える弘法大師霊場では、いわゆる「難所」といわれる札所がでてきます。
「難所」にはいくつかのパターンがあるかと思います。
1.物理的にアクセスしにくい札所
エリア外に離れている札所。この霊場でも東京都日野市、神奈川県秦野市の札所があり、半日~1日がかりの巡拝となります。
2.ご不在気味の札所
ご多忙でご不在が多く、書置御朱印もご用意されていない札所があります。
とくに御府内霊場の場合、小規模な寺院札所も多く書置御朱印をご用意されていてもどなたもいらっしゃらない(ベルを押しても応答がない)という局面がかなりあります。
ご不在の場合、出直し参拝となるので、この場合は事前に電話で確認のうえお伺いした方がいいかもしれません。
3.いわゆる「塩対応」の札所
御府内八十八ヶ所は人気の御朱印スポットに立地する札所も多く、一時期御朱印拝受希望者が殺到したことがありました。
本堂にお参りもせず、いきなり御朱印所に向かう人も少なくなく、勤行が前提となる弘法大師霊場の札所として「御朱印ブーム」に疑問を抱かれたお寺様も少なくないのでは。
こういった経緯を受けてか、拝受希望者に納経や読経を促されたり、状況によっては参拝方法についてご指導をなされるお寺様もあるかと思います。
霊場札所としては自然なご対応だとは思いますが、慣れない人には「敷居が高い」「塩対応」などと感じられてしまうことはあるかもしれません。
そういう意味からすると、ある程度霊場巡拝に慣れた方向けの霊場ともいえ、メジャー寺院が多い「江戸三十三観音霊場」などで巡拝経験を積んだうえでトライするのがベターかもしれません。
筆者は二巡+αし、専用集印帳と汎用御朱印帳にいただいておりますので、両方ご紹介します。
ただし上記のとおり、現在汎用御朱印帳での拝受がむずかしい札所もあるかもしれません。
以前UPした「伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印」と同様、フルバージョンで時間をかけてUPしていきます。
-------------------------
2023-05-14 UP
続編を書き進めたいのですが、御府内についてまとめた『御府内風土記』は明治5年に火災で焼失。
御府内の寺社の由緒・沿革は、『新編武蔵風土記稿』を使える都下や下町よりもたどりにくくなっています。
目下、『御府内風土記』の編纂史料『寺社書上』と格闘中です。
しばらくお待ちくださいませ。
それにしても、江戸の先人の記稿(というか記録全般)に対する執念はものすごいものがあります。
何百年でも残そうという気迫が感じられます。
これを自宅のPCで閲覧できるとは、すごい時代になったものです。
-----------------------
2023/05/26 UP
御府内霊場の記録を当たっていたところ『御府内八十八ケ所道しるべ』という文献にたどり着きました。
これは、御府内霊場の札所ガイドのような内容で、しかも、国立国会図書館によりWeb公開されています。
御府内八十八ケ所道しるべ 天( 国立国会図書館DC)
御府内八十八ケ所道しるべ 地( 国立国会図書館DC)
御府内八十八ケ所道しるべ 人( 国立国会図書館DC)
Wikipediaによると、神仏分離は「明治新政府により出された神仏判然令(慶応4年3月13日から明治元年10月18日までに出された、太政官布告・神祇官事務局達・太政官達など一連の通達[2]の総称)に基づき、全国的に公的に行われたものを指す。」とあります。
これを受けた廃寺の動きは明治初期に目立ったとみられています。
一方、『御府内八十八ケ所道しるべ』は慶応元年(1865年)序、明治二年(1869年)跋で、後半は神仏分離のさなかに編纂されたとみられます。
御府内霊場の札所は江戸期を通じて比較的変動が少なく安定しているのですが、この神仏分離の時期に複数の札所の異動がみられます。
『御府内八十八ケ所道しるべ』は神仏分離前の慶応元年序なので、神仏分離を受けて廃寺となった札所が記載された、たいへん貴重な記録となっています。
御府内に真言宗寺院はさほど多くなく、ほとんどの寺院が札所となっています。
天下の御府内の弘法大師霊場のご開創となれば、多くの真言宗寺院が諸手を挙げて参画したのかもしれません。
『御府内八十八ケ所道しるべ』によって明治初期時点での札所が確定できるので、憶測が少なくなると思います。
これまで書いた記事は当面そのままとし、今後の記事は『御府内八十八ケ所道しるべ』を参照したいと思います。
(『御府内寺社備考』(御府内備考第147巻)もゲットしたので、こちらもあわせて参照します。)
-----------------------
『御府内八十八ケ所道しるべ』『寺社書上』と江戸八十八ヶ所霊場のデータを一覧形式にしたリストをつくってみました。
『寺社書上』は120巻もあって、88の札所をその中から探し出さなければならないので悪戦苦闘でした。
たとえば、第31番の牛込多聞院の記事はこんな感じです。(33巻34頁)
これで史料原典に直リンクする体制はできたのですが、果たして毛筆の達筆すぎる原文が読解できるかどうか・・・(笑)
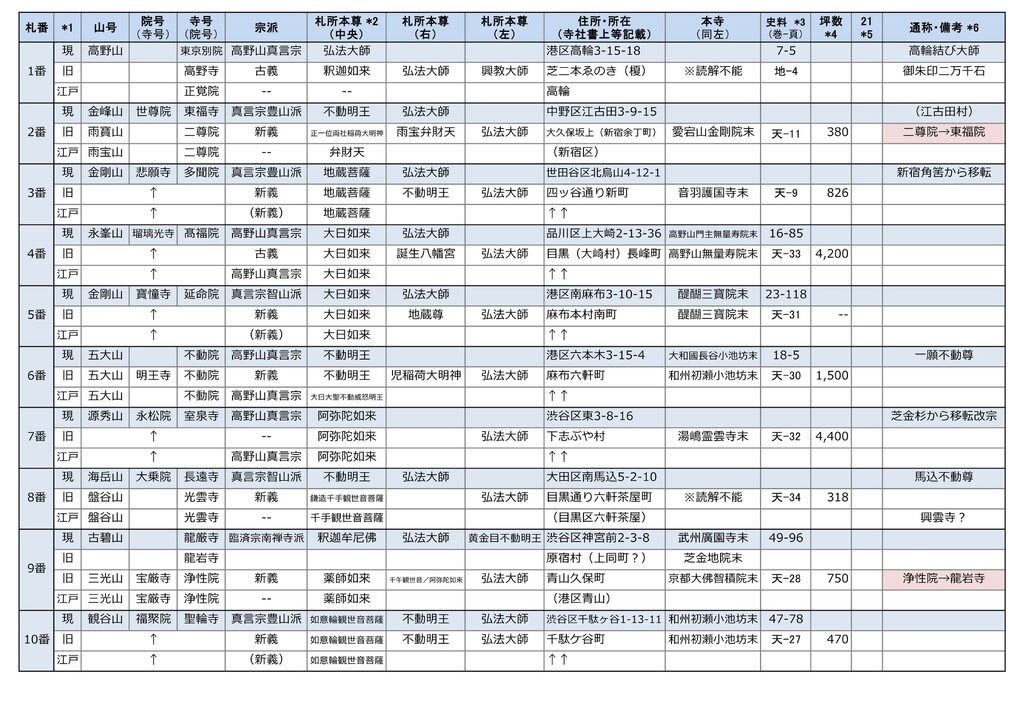
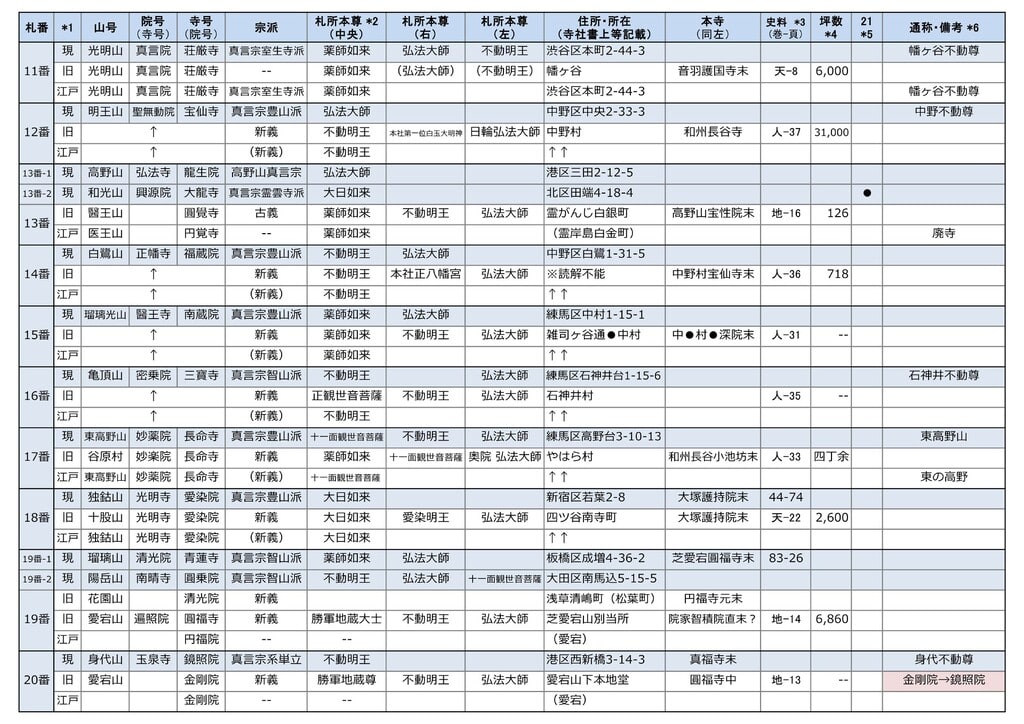
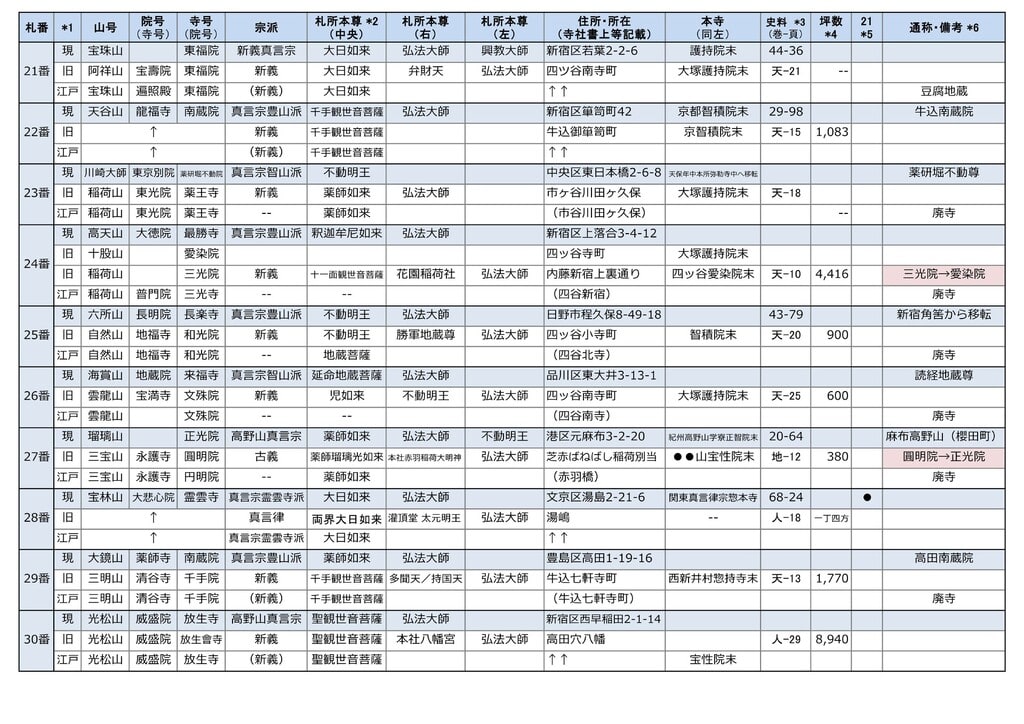
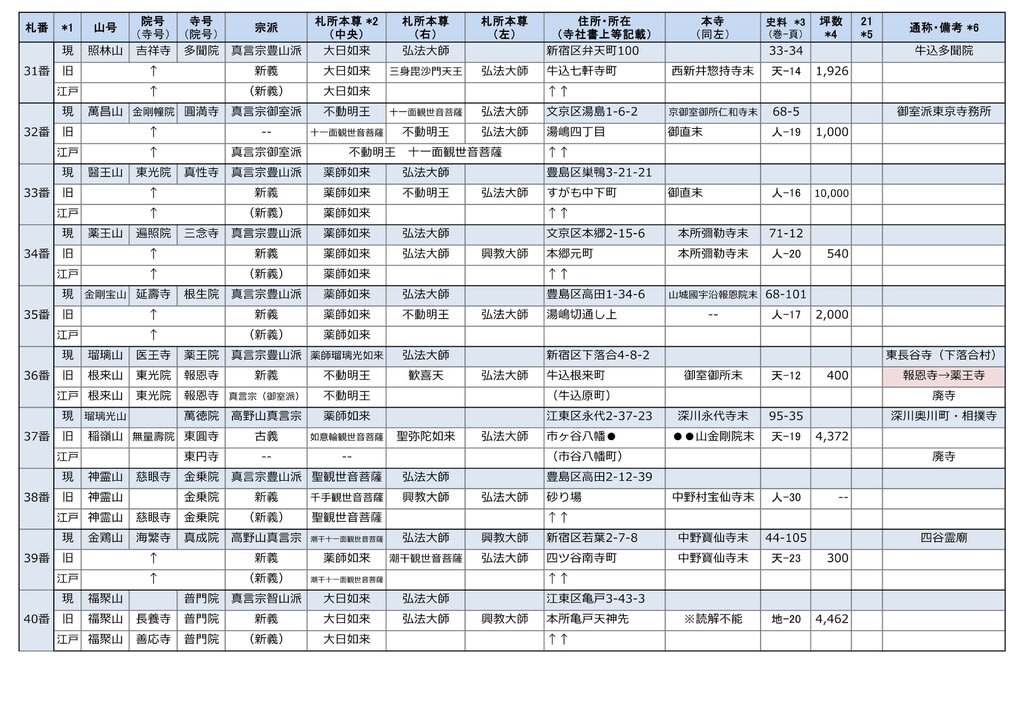
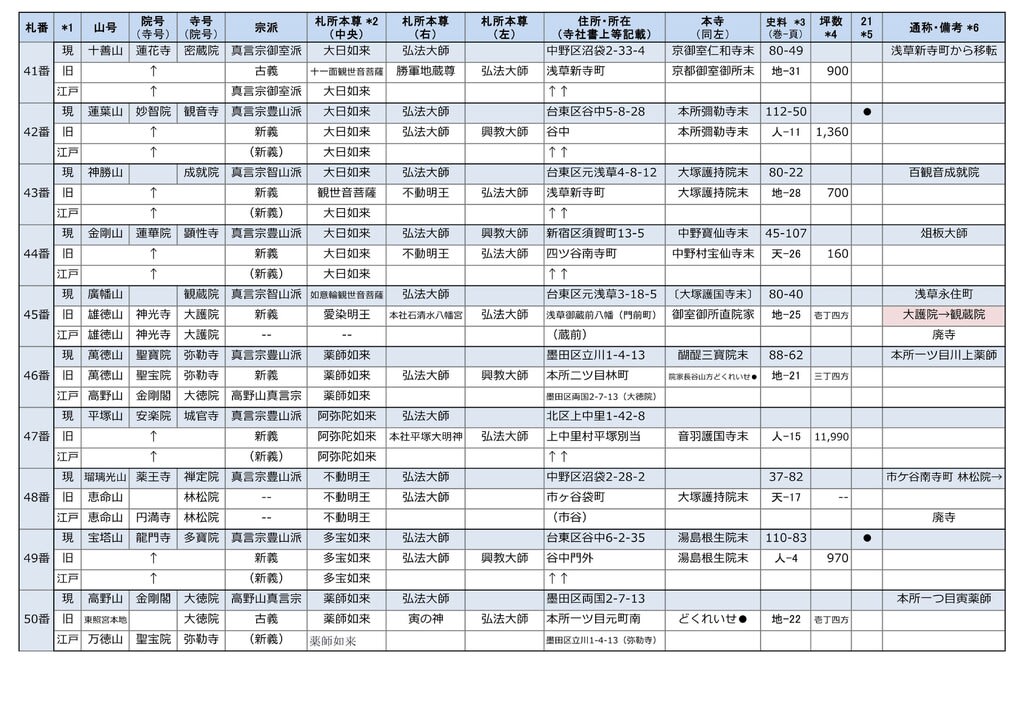
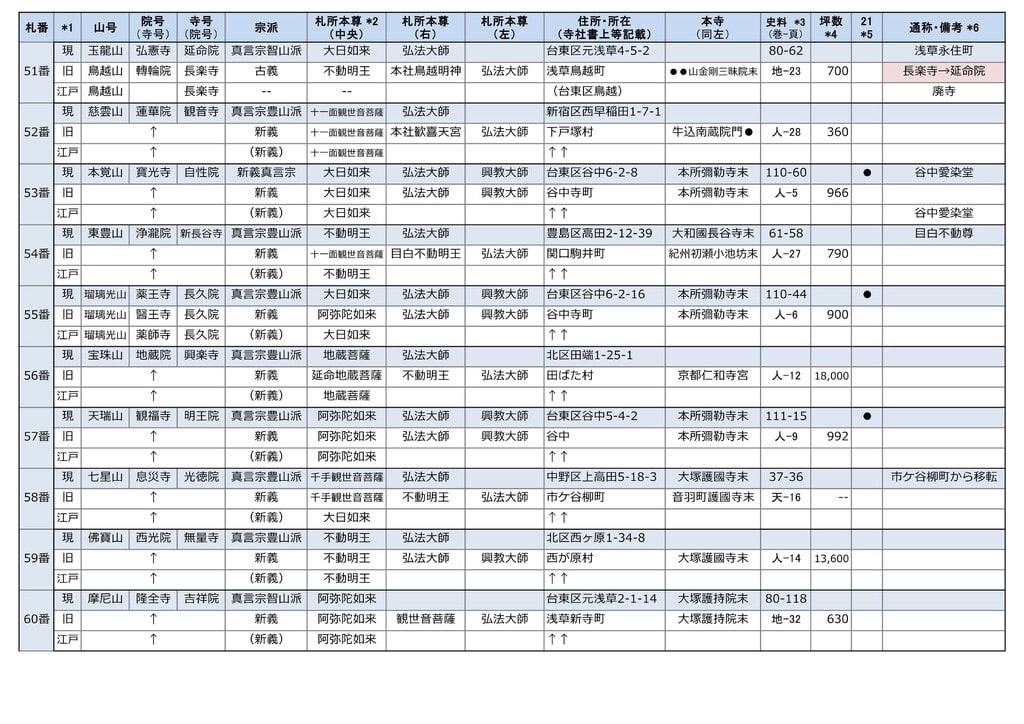
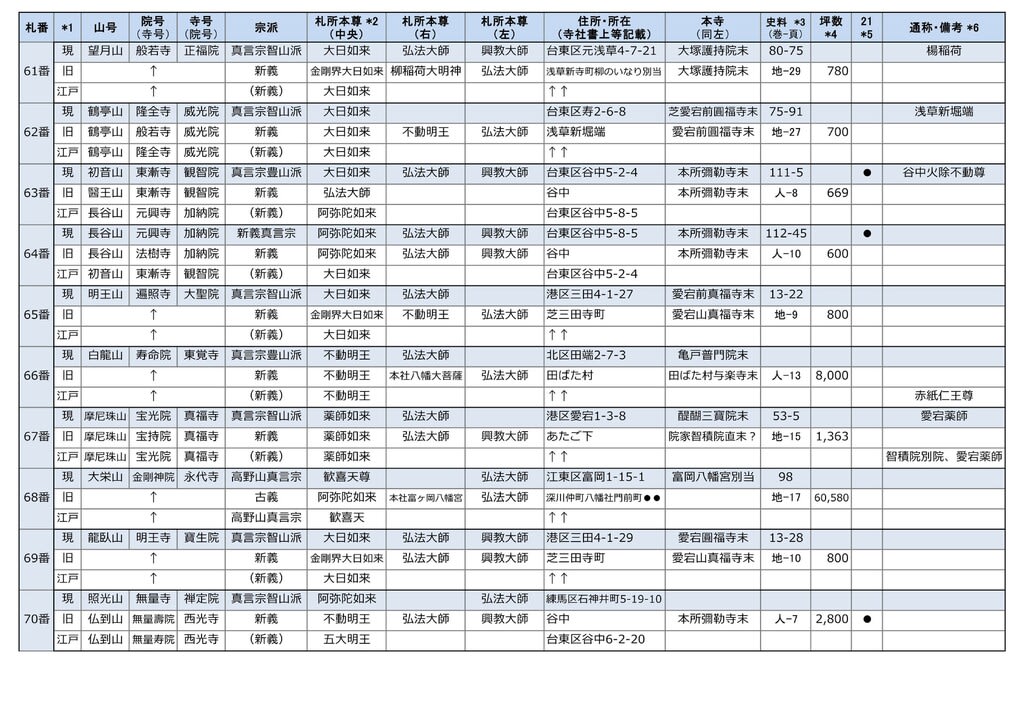
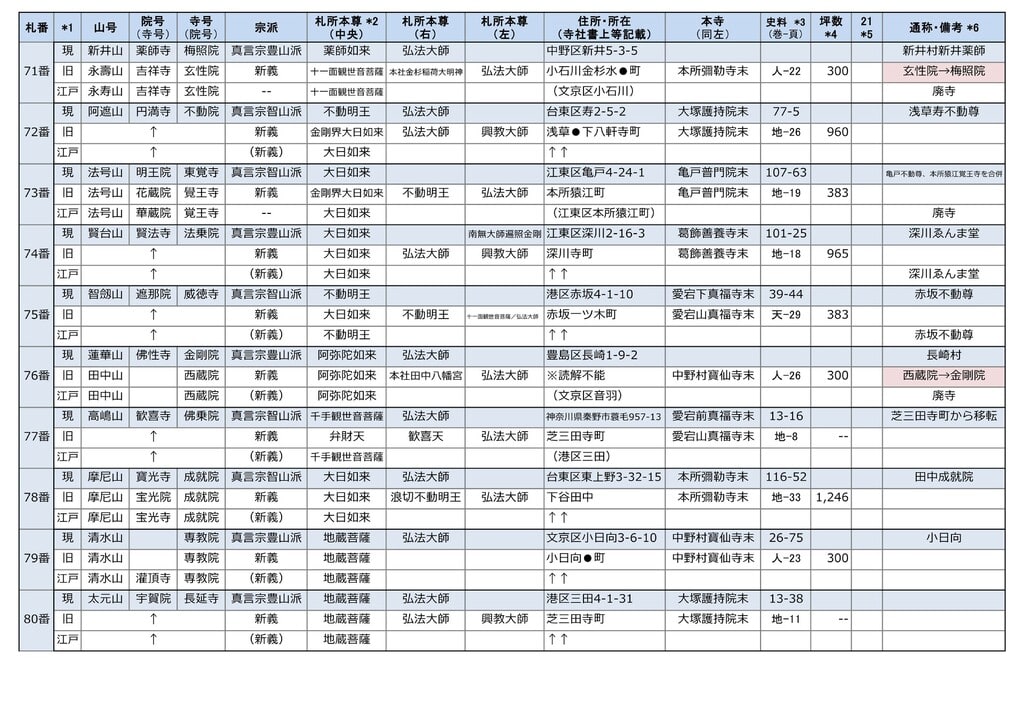
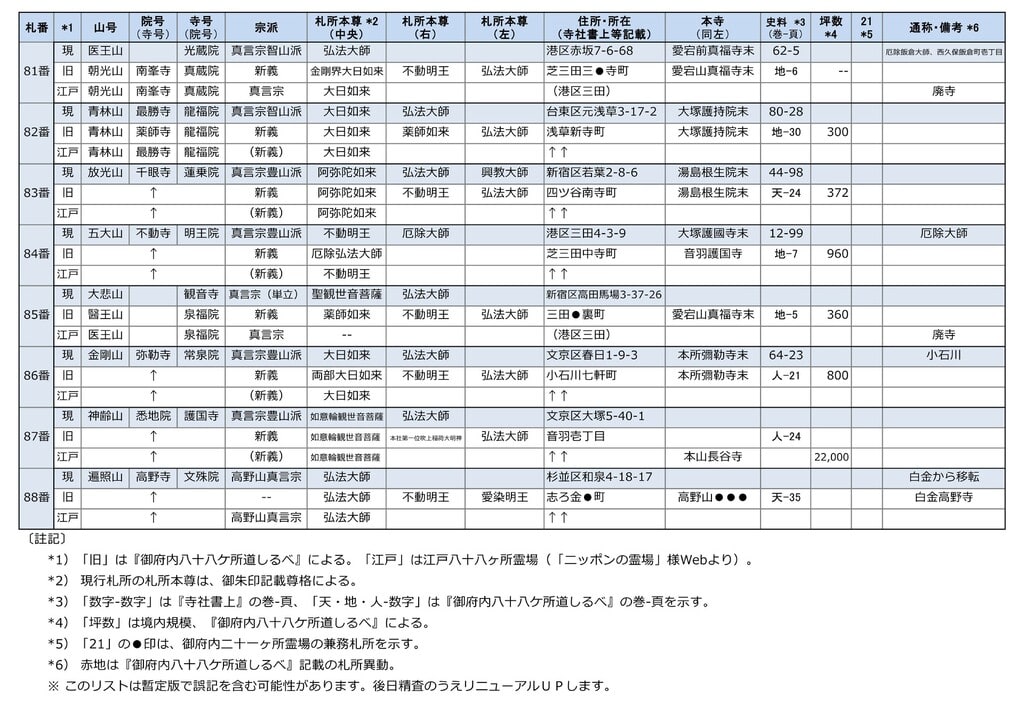
このリストから、
・江戸八十八ヶ所霊場は、御府内霊場の前身または異称であった可能性がある。
・江戸時代の御府内霊場では神社が札所(内の拝所)として定められていた可能性がある。
・江戸時代は比較的札所は安定し、明治初期の神仏分離の流れを受けて複数の札所が異動した。
・明治以降の寺院の郊外移転の動きを受けて、札所も郊外に移動したケースがある。
・中野、幡ヶ谷、石神井、谷原など府外立地でも当初から御府内霊場札所となっていた寺院がある。
などが推定されます。
ともあれ、記事UPを再開します。
Vol.-1Bへつづきます。
【 BGM 】
■ 夢の大地 - Kalafina
■ 桜 - 中村舞子
■ 栞 - 天野月 feat.YURiCa/花たん
今年(令和五年)は弘法大師御誕生1250年の記念の年です。
→ 金剛峯寺の公式Web
そこで、御府内八十八ヶ所霊場の御朱印のご紹介をはじめることにしました。
■ 2024/02/28 UP
ようやく(一応)完成しました。
この記事を書いている途中で『御府内八十八ケ所道しるべ』の存在に気づいたため、途中から構成が変わっております。
ひとまずはこれで完結としますが、後日前半の構成を整えていきたいと思います。
-------------------------
□ 札所リスト
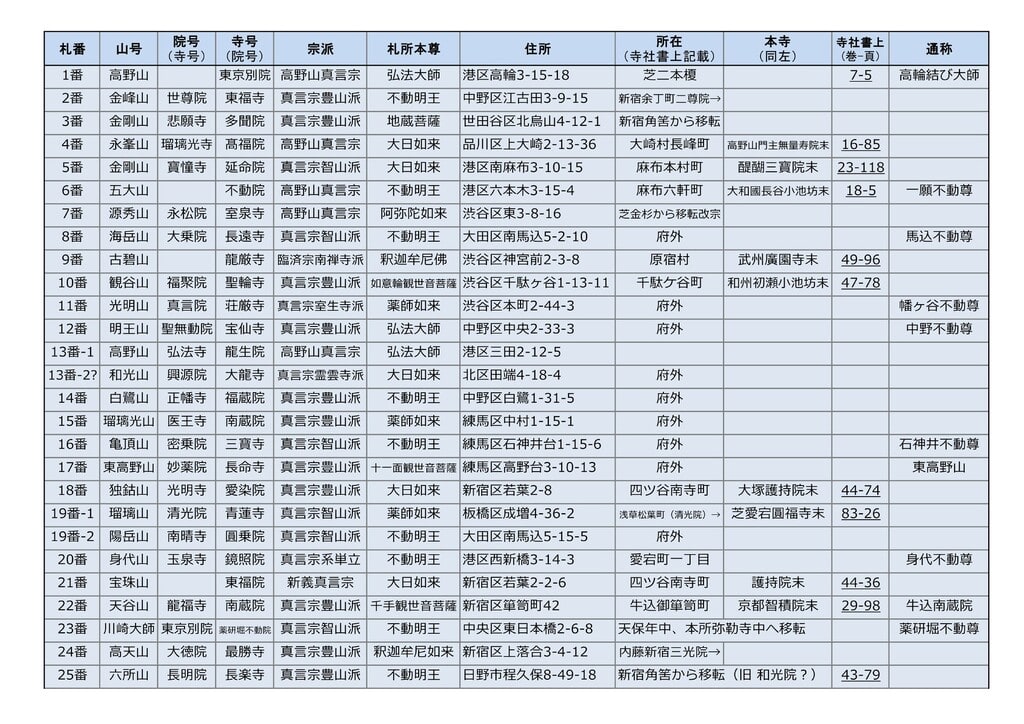
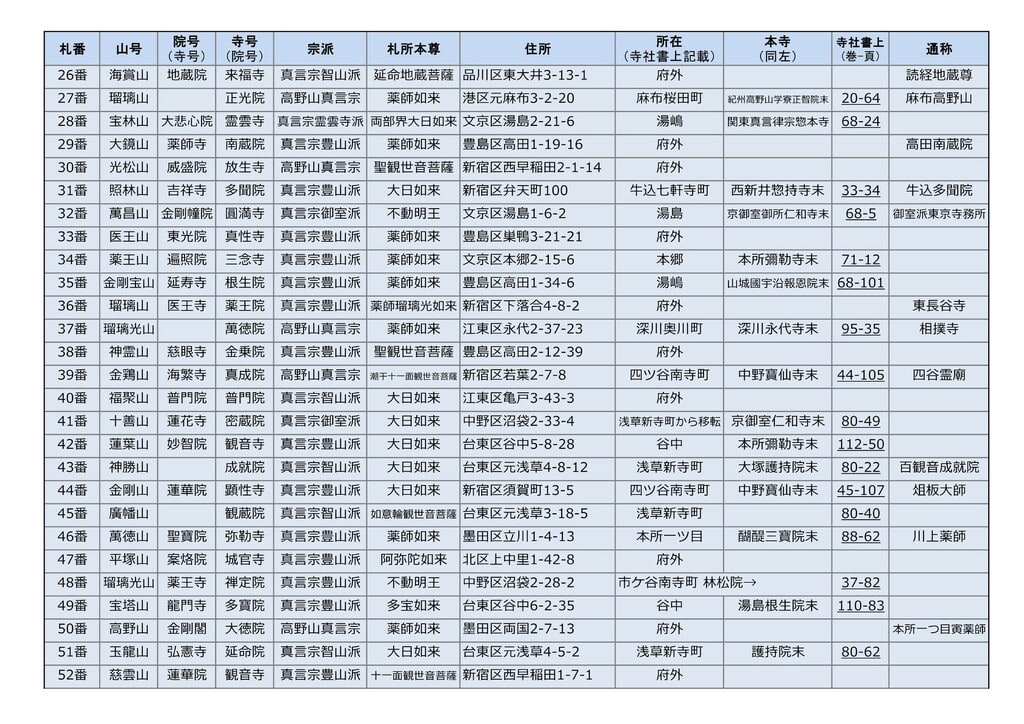
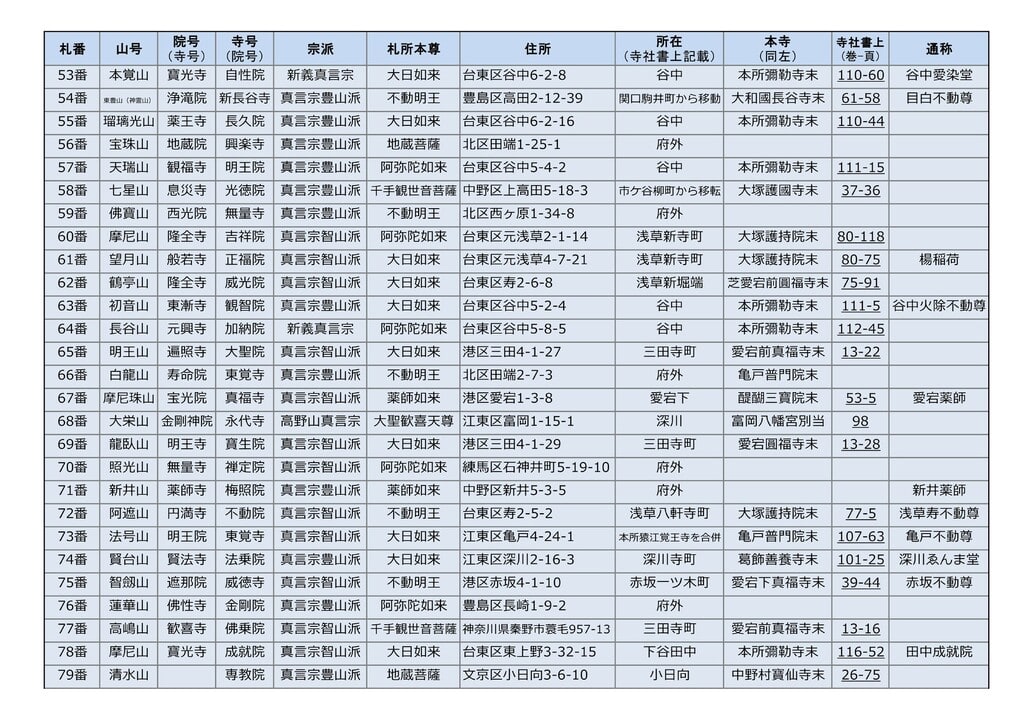
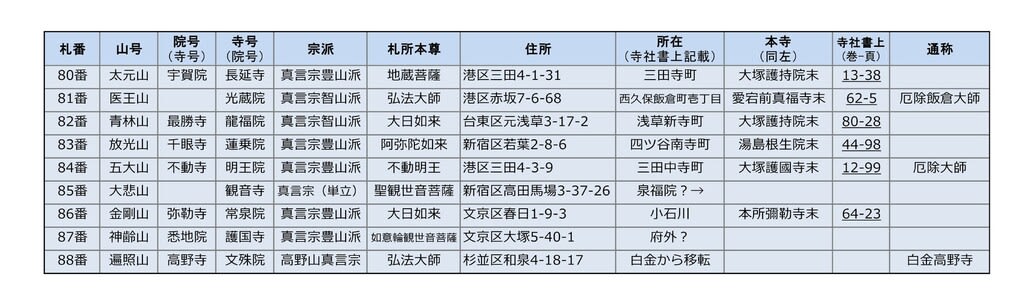
□ 記事へのリンク
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1B
第1番
高野山東京別院(港区高輪)
第2番
金峰山 東福寺(中野区江古田)
第3番
金剛山 多聞院(世田谷区北烏)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-2
第4番
永峯山 高福院(品川区上大崎)
第5番
金剛山 延命院(港区南麻布)
第6番
五大山 不動院(港区六本木)
第7番
源秀山 室泉寺(渋谷区東)
第8番
海岳山 長遠寺(大田区南馬込)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-3
第9番
古碧山 龍厳寺(渋谷区神宮前)
第10番
観谷山 聖輪寺(渋谷区千駄ヶ谷)
第11番
光明山 荘厳寺(渋谷区本町)
第12番
明王山 宝仙寺(中野区中央)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-4
第13番-1
三田高野山 龍生院(弘法寺)(港区三田)
第13番-2
和光山 大龍寺(北区田端)
第14番
白鷺山 福蔵院(中野区白鷺)
第15番
瑠璃光山 南蔵院(練馬区中村)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-5
第16番
亀頂山 三寶寺(練馬区石神井台)
第17番
東高野山 長命寺(練馬区高野台)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-6
第18番
獨鈷山 愛染院(新宿区若葉)
第19番-1
瑠璃山 青蓮寺(板橋区成増)
第19番-2
陽岳山 圓乗院(大田区南馬込)
第20番
身代山 鏡照院(港区西新橋)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-7
第21番
寶珠山 東福院(新宿区若葉)
第22番
天谷山 南蔵院(新宿区箪笥町)
第23番
川崎大師東京別院 薬研堀不動院(中央区東日本橋)
第24番
高天山 最勝寺(新宿区上落合)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-8
第25番
六所山 長楽寺(日野市程久保)
第26番
海賞山 来福寺(品川区東大井)
第27番
瑠璃山 正光院(港区元麻布)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-9
第28番
宝林山 霊雲寺(文京区湯島)
第29番
大鏡山 南蔵院(豊島区高田)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-10
第30番
光松山 放生寺(新宿区西早稲田)
第31番
照林山 多聞院(新宿区弁天町)
第32番
萬昌山 圓満寺(文京区湯島)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-11
第33番
醫王山 眞性寺(豊島区巣鴨)
第34番
薬王山 三念寺(文京区本郷)
第35番
金剛寶山 根生院(豊島区高田)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-12
第36番
瑠璃山 薬王院(新宿区下落合)
第37番
瑠璃光山 萬徳院(江東区永代)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-13
第38番
神霊山 金乗院(豊島区高田)
第39番
金鶏山 真成院(新宿区若葉)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-14
第40番
福聚山 普門院(江東区亀戸)
第41番
十善山 密蔵院(中野区沼袋)
第42番
蓮葉山 観音寺(台東区谷中)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-15
第43番
神勝山 成就院(台東区元浅草)
第44番
金剛山 顕性寺(新宿区須賀町)
第45番
廣幡山 観蔵院(台東区元浅草)
第46番
萬徳山 弥勒寺(墨田区立川)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-16
第47番
平塚山 城官寺(北区上中里)
第48番
瑠璃光山 禅定院(中野区沼袋)
第49番
寶塔山 多寶院(台東区谷中)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-17
第50番
高野山 大徳院(墨田区両国)
第51番
玉龍山 延命院(台東区元浅草)
第52番
慈雲山 観音寺(新宿区西早稲田)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-18
第53番
本覚山 自性院(台東区谷中)
第54番
東豊山 新長谷寺(豊島区高田)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-19
第55番
瑠璃光山 長久院(台東区谷中)
第56番
宝珠山 與楽寺(北区田端)
第57番
天瑞山 明王院(台東区谷中)
第58番
七星山 光徳院(中野区上高田)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-20
第59番
佛寶山 無量寺(北区西ヶ原)
第60番
摩尼山 吉祥院(台東区元浅草)
第61番
望月山 正福院(台東区元浅草)
第62番
鶴亭山 威光院(台東区寿)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-21
第63番
初音山 観智院(台東区谷中)
第64番
長谷山 加納院(台東区谷中)
第65番
明王山 大聖院(港区三田)
第66番
白龍山 東覚寺(北区田端)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-22
第67番
摩尼珠山 真福寺(港区愛宕)
第68番
大栄山 永代寺(江東区富岡)
第69番
龍臥山 宝生院(港区三田)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-23
第70番
照光山 禅定院(練馬区石神井町)
第71番
新井山 梅照院(中野区新井)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-24
第72番
阿遮山 不動院(台東区寿)
第73番
法号山 東覚寺(江東区亀戸)
第74番
賢臺山 法乗院(江東区深川)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-25
第75番
智劔山 威徳寺(港区赤坂)
第76番
蓮華山 金剛院(豊島区長崎)
第77番
高嶋山 佛乗院(神奈川県秦野市蓑毛)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-26
第78番
摩尼山 成就院(台東区東上野)
第79番
清水山 専教院(文京区小日向)
第80番
太元山 長延寺(港区三田)
第81番
医王山 光蔵院(港区赤坂)
第82番
青林山 龍福院(台東区元浅草)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-27
第83番
放光山 蓮乗院(新宿区若葉)
第84番
五大山 明王院(港区三田)
第85番
大悲山 観音寺(新宿区高田馬場)
第86番
金剛山 常泉院(文京区春日)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-28
第87番
神齢山 護国寺(文京区大塚)
御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-29
第88番
遍照山 文殊院(杉並区和泉)
-------------------------
御府内八十八ヶ(箇)所とは、東京都内にある弘法大師ゆかりの寺院を巡拝する弘法大師霊場です。(以下、「御府内霊場」と記します。)
「御府内」とは「江戸町奉行が支配の対象とする江戸(の範囲内)」ないし「寺社勧化場として許可された江戸(の範囲内)」といわれ、時代によって変化したといいます。
東京都公文書館のWeb資料には以下のとおりあります。
-------------------------
文政元年(1818)8月に、目付牧助右衛門から「御府内外境筋之儀」についての伺いが出されました。
この伺いを契機に、評定所で入念な評議が行われました。このときの答申にもとづき、同年12月に老中阿部正精から「書面伺之趣、別紙絵図朱引ノ内ヲ御府内ト相心得候様」と、幕府の正式見解が示されたのです。
その朱引で示された御府内の範囲とは、およそ次のようになります。
東…中川限り
西…神田上水限り
南…南品川町を含む目黒川辺
北…荒川・石神井川下流限り
この朱引図には、朱線と同時に黒線(墨引)が引かれており、この墨引で示された範囲が、町奉行所支配の範囲を表しています。朱引と墨引を見比べると、例外的に目黒付近で墨引が朱引の外側に突出していることを除けば、ほぼ朱引の範囲内に墨引が含まれる形になっていることが見てとれます。
以来、江戸の範囲といえば、この朱引の範囲と解釈されるようになったのです。
-------------------------
このようにきわめて明快に説明されています。
つまり、江戸御府内=江戸朱引図内ということです。
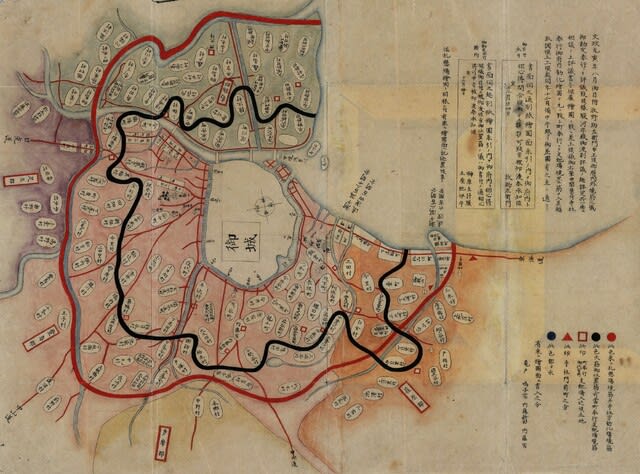
■ 江戸朱引図(東京都公文書館Web公開資料)
たとえば 江戸朱引図(東京都公文書館)をみると田畑村はしっかり朱引図内に収まっており、田端は御府内に位置することがわかります。

■ 朱引きと田畑村の位置関係(東京都公文書館Web公開資料を筆者にて加工)
以上のとおり、文政元年(1818年)頃の「御府内」の範囲は、東は亀戸・小名木村辺、西は角筈村・代々木辺、南は上大崎村・南品川町辺、北は上尾久・下板橋村辺の内側と定められています。
-------------------------
『全国霊場大事典』(六月書房)によると、御府内霊場の開創は宝暦年間(1751年~)頃とされています。
同書によると、信州・浅間山真楽寺の憲浄僧正と千葉県松戸の諦信によって四国八十八ヶ所霊場が写されたものとされ、四国霊場の札所の土(お砂)を各札所の拝前におき、こちらを踏んで巡拝すれば四国霊場巡拝と同様のご利益が得られるとされる点は、全国各地の弘法大師(新四国)霊場と同様です。
『全国霊場巡拝事典』(大法輪閣)では、宝暦五年(1755年)刊の『大進夜話』に「江戸にも此頃は信州浅間山の上人本願にて、四国の八十八箇所を移して立札など見えたり」とあり、文化十三年(1816年)の札所案内には「宝暦五乙亥三月下総葛飾松戸宿諦信の子、出家して信州浅間山真楽寺の住になりぬ。両人本願して江戸に霊場をうつす」とあることを紹介しています。
さらに文政五年(1822年)刊の十返舎一九著『諸国道中金の草鞋』にも「宝暦の頃下総の國松戸宿の諦信●子●預して東都に八十八ヶ所の霊場を●●といへり。」との記載があり、宝暦年間、憲浄僧正と松戸の諦信による開創説でおおむね定まっているようです。
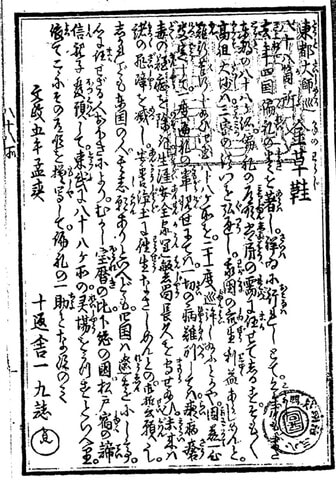
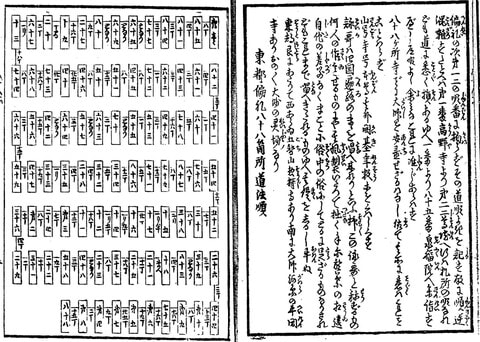
【写真 上(左)】 十返舎一九『諸国道中金の草鞋』二十一篇「東都大師巡八十八箇所」(文政五年(1822年))
【写真 下(右)】 同
※ 十返舎一九 著 ほか『諸国道中金の草鞋』21,嵩山堂,〔 〕. 国立国会図書館DC より転載。
このことは「公訴発願 信州浅間真楽寺上人 巡行願主 下総国 諦信」と刻まれた札所碑が第42番観音寺にあり、他の札所にも同様の石碑が残ることからも裏付けられるとされています。(『全国霊場巡拝事典』)
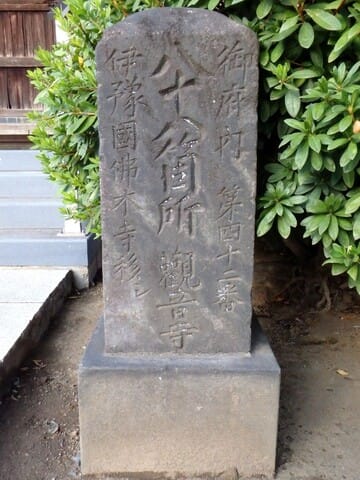
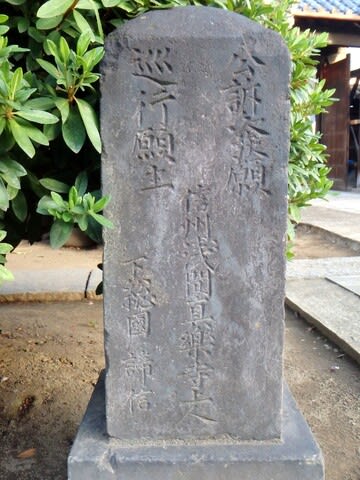
【写真 上(左)】 第42番観音寺の御府内霊場札所碑
【写真 下(右)】 「公訴発願 信州浅間真楽寺上人 巡行願主 下総國 諦信」とあります
なお、同書によると、これとは別に正等和尚(1703-1774年)という人が開創という説もあるようです。
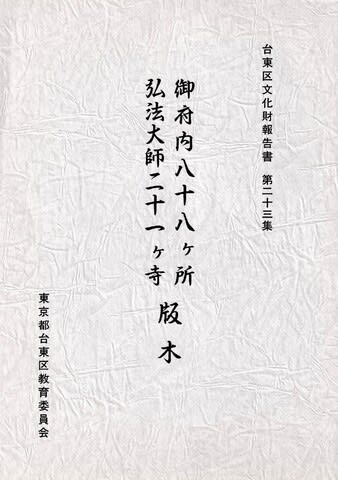
『御府内八十八ヶ所 弘法大師二十一ヶ寺 版木』(台東区教育委員会刊)には、「第十七番札所長命寺には「宝暦三癸酉三月廿一日」銘の御府内八十八ヶ所標石が現存する。(略)この銘文を信じる限り宝暦三年(1753年)三月までに開設されていたことになる。」
同書では第17番長命寺の標石と宝暦五年(1755年)刊の『大進夜話』を根拠とし、「ここでは、宝暦二年(1752年)頃『浅間山真楽寺住職』の開設とし、不明な点は後考に俟つこととしたい。」とあります。


【写真 上(左)】 第17番長命寺の御府内八十八ヶ所標石-1
【写真 下(右)】 同-2
また、同書には「本版木第二六丁によれば『廿三里十三丁五間』、約九二キロの行程で、御府内在住の健脚であれば三~四日で巡ったものと思われる。」とあります。
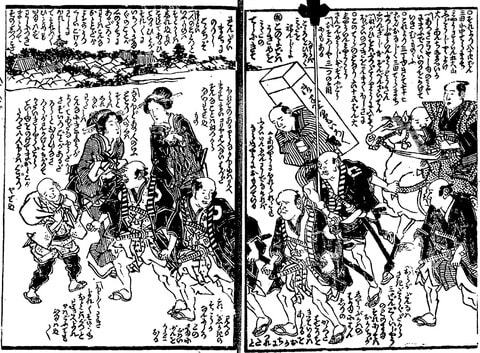
十返舎一九『諸国道中金の草鞋』二十一篇「東都大師巡八十八箇所」(文政五年(1822年))
※ 十返舎一九 著 ほか『諸国道中金の草鞋』21,嵩山堂,〔 〕. 国立国会図書館DC より転載。
---------------------------------
御府内霊場の前身ともいわれる霊場に江戸八十八ヶ所霊場があります。
初番は高輪の正覚院、第88番結願は御府内霊場と同様文殊院で、御府内霊場と重複する札所が多いですが、微妙に異なる札番構成で廃寺も含みます。
→ 札所リストはこちら(『ニッポンの霊場』様)
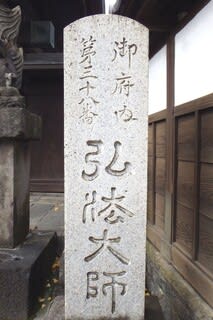
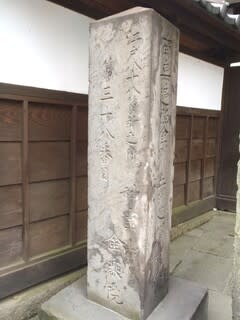
【写真 上(左)】 第38番金乗院の御府内霊場札所碑
【写真 下(右)】 同 江戸八十八ヶ所霊場第38番の札所碑
御府内霊場第2番はもともとは新宿・余丁町の二尊院で、のちに江古田・東福寺に遷ったともされますが、江戸八十八ヶ所霊場第2番は二尊院となっています。
また、江戸八十八ヶ所の札所は御府内霊場に比べて御府内の札所が多くなっているので、あるいは御府内霊場の前身の可能性もあるのかもしれません。
廃寺・移動となった札番の変遷をこまかく追っていけばなにか見えてくるものがあるのかも知れませんが、なにぶん江戸八十八ヶ所霊場は記録がすくなく、それもむずかしいかもしれません。
現在、寺院移転により御府内霊場の2つの札所は都区外に移転していますが、それ以外は東京都区内の所在で、まさに「東京のお遍路」ということができます。
■ 第56番 宝珠山 地蔵院 與楽寺(北区田端)
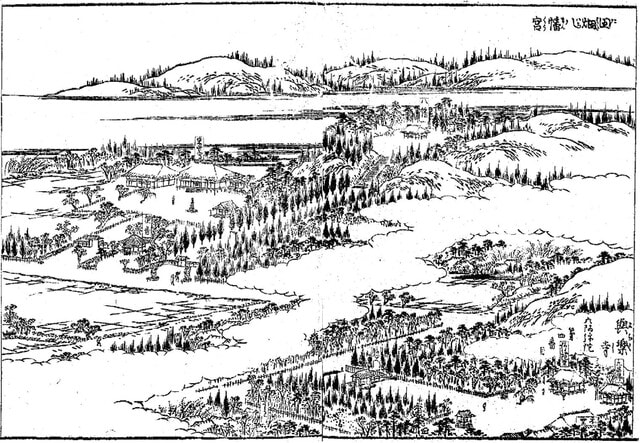
※ 『江戸名所図会』十五(国会図書館DC(保護期間満了資料)より転載)
■ 第59番 佛寶山 西光院 無量寺(北区西ヶ原)
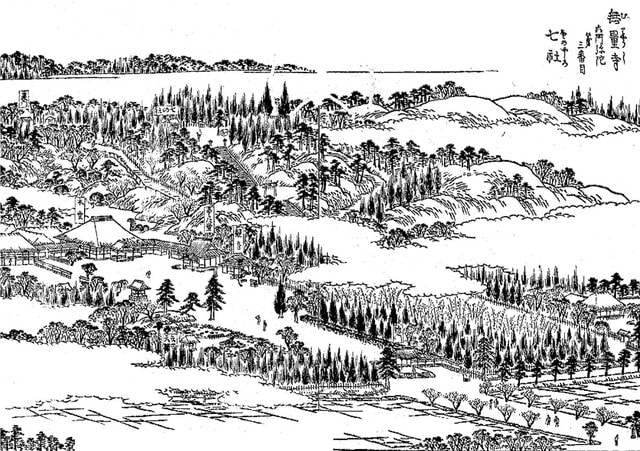
※ 『江戸名所図会』十五(国会図書館DC(保護期間満了資料)より転載)
-------------------------
現在、霊場会の活動があるかは不明ですが、すべての札所で御朱印を授与され、発願(第1番)の高野山東京別院では専用の集印帳を頒布されています。
この集印帳は白地ですが差し替え方式もとれるため、現在はこの専用集印帳の使用が奨励されている模様です。
また、筆者は専用集印帳以外では御朱印を授与しないという掲示をされている札所も確認しています。(現況は不明)
多くの札所では汎用御朱印帳でも快く授与いただけますが、御朱印コンプリートを目指す向きは専用集印帳使用がベターかと思います。
札所一覧は→こちら(ニッポンの霊場様)、札所位置図については→こちら(第76番蓮華山金剛院様公式Web)に掲載があります。
筆者にて札番重複札所がふたつ(第13番、第19番)あることは確認しており、いずれも御朱印を拝受できます。
掛所、番外、特別札所はないので、コンプリートは90箇寺(札所)ということになります。
順路は、札番がエリアを越えて飛んでいるので順打ち、逆打ちともに効率が悪くなります。
発願(第1番)の高野山東京別院(港区高輪)、結願(第88番)の遍照山 文殊院(杉並区和泉)はおさえるとしても、その他の札所はアクセスを考えてランダムに回ってもいいかもしれません。
駐車場がない札所や狭い路地奥の札所もありますので、車での巡拝はおすすめしません。
多くの札所は鉄道駅から徒歩圏内で、東京メトロ駅利用も多いので「東京メトロ24時間券」が威力を発揮します。
日本橋、六本木、赤坂、四ッ谷など都心のお寺をはじめ、谷根千、高田、沼袋や烏山など都内有数の寺町も外さずに回る、エリア的にも変化に富んだ巡礼が味わえます。
ただし、荒綾霊場、南葛霊場、荒川辺霊場などがある下町エリアの札所は少なくなっており、どちらかというと都心~山の手寄りの霊場といえます。
宗派は禅宗1箇寺をのぞきすべて真言宗で、多くは新義真言宗(智山派、豊山派など)。
新義真言宗寺院が多い東京らしい弘法大師霊場といえましょう。
御朱印は多くが御寶印(札所本尊のお種子)で、札所本尊、弘法大師、興教大師が揮毫され、札所印も捺される華々しいものです。
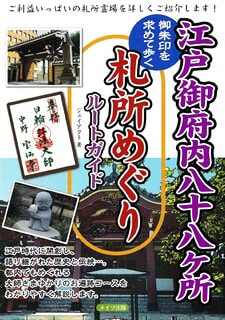
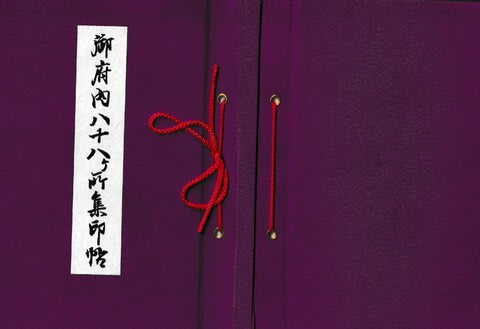
【写真 上(左)】 霊場ガイド(メイツ出版)(以下『札所めぐり』)
【写真 下(右)】 専用集印帳
専用集印帳は大判で紙質がよく筆の走りもよいようで、いただいた御朱印はどれも見応えがあります。
和綴じ様式なので参拝の順序にかかわらず、札番順に綴じ込むことができるのは大きな利点です。
なお、お納めは以前は300円でしたが、現在は500円に改定されているかもしれません。(札所によりまちまちのようです。)
都内の札所メインですが、御朱印対応時間は9:00~16:00が多く夕刻には件数を稼げません。
札所での拝所は札所本尊(多くは本堂の御本尊)と弘法大師尊像ないし大師堂の二箇所となり、各寺見どころも多いので、じっくりと時間をかけて回る霊場かと思います。
また、他の霊場との兼任札所も複数ありますが、御府内霊場については1参拝ひとつの拝受がベターかもしれません。
とくに豊島八十八箇所の御朱印と併せてお願いすることは、実質的な弘法大師霊場の掛け持ち巡拝となるので個人的には避けた方がベターかと思います。
【 いわゆる「難所」について 】
八十八もの札所を数える弘法大師霊場では、いわゆる「難所」といわれる札所がでてきます。
「難所」にはいくつかのパターンがあるかと思います。
1.物理的にアクセスしにくい札所
エリア外に離れている札所。この霊場でも東京都日野市、神奈川県秦野市の札所があり、半日~1日がかりの巡拝となります。
2.ご不在気味の札所
ご多忙でご不在が多く、書置御朱印もご用意されていない札所があります。
とくに御府内霊場の場合、小規模な寺院札所も多く書置御朱印をご用意されていてもどなたもいらっしゃらない(ベルを押しても応答がない)という局面がかなりあります。
ご不在の場合、出直し参拝となるので、この場合は事前に電話で確認のうえお伺いした方がいいかもしれません。
3.いわゆる「塩対応」の札所
御府内八十八ヶ所は人気の御朱印スポットに立地する札所も多く、一時期御朱印拝受希望者が殺到したことがありました。
本堂にお参りもせず、いきなり御朱印所に向かう人も少なくなく、勤行が前提となる弘法大師霊場の札所として「御朱印ブーム」に疑問を抱かれたお寺様も少なくないのでは。
こういった経緯を受けてか、拝受希望者に納経や読経を促されたり、状況によっては参拝方法についてご指導をなされるお寺様もあるかと思います。
霊場札所としては自然なご対応だとは思いますが、慣れない人には「敷居が高い」「塩対応」などと感じられてしまうことはあるかもしれません。
そういう意味からすると、ある程度霊場巡拝に慣れた方向けの霊場ともいえ、メジャー寺院が多い「江戸三十三観音霊場」などで巡拝経験を積んだうえでトライするのがベターかもしれません。
筆者は二巡+αし、専用集印帳と汎用御朱印帳にいただいておりますので、両方ご紹介します。
ただし上記のとおり、現在汎用御朱印帳での拝受がむずかしい札所もあるかもしれません。
以前UPした「伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印」と同様、フルバージョンで時間をかけてUPしていきます。
-------------------------
2023-05-14 UP
続編を書き進めたいのですが、御府内についてまとめた『御府内風土記』は明治5年に火災で焼失。
御府内の寺社の由緒・沿革は、『新編武蔵風土記稿』を使える都下や下町よりもたどりにくくなっています。
目下、『御府内風土記』の編纂史料『寺社書上』と格闘中です。
しばらくお待ちくださいませ。
それにしても、江戸の先人の記稿(というか記録全般)に対する執念はものすごいものがあります。
何百年でも残そうという気迫が感じられます。
これを自宅のPCで閲覧できるとは、すごい時代になったものです。
-----------------------
2023/05/26 UP
御府内霊場の記録を当たっていたところ『御府内八十八ケ所道しるべ』という文献にたどり着きました。
これは、御府内霊場の札所ガイドのような内容で、しかも、国立国会図書館によりWeb公開されています。
御府内八十八ケ所道しるべ 天( 国立国会図書館DC)
御府内八十八ケ所道しるべ 地( 国立国会図書館DC)
御府内八十八ケ所道しるべ 人( 国立国会図書館DC)
Wikipediaによると、神仏分離は「明治新政府により出された神仏判然令(慶応4年3月13日から明治元年10月18日までに出された、太政官布告・神祇官事務局達・太政官達など一連の通達[2]の総称)に基づき、全国的に公的に行われたものを指す。」とあります。
これを受けた廃寺の動きは明治初期に目立ったとみられています。
一方、『御府内八十八ケ所道しるべ』は慶応元年(1865年)序、明治二年(1869年)跋で、後半は神仏分離のさなかに編纂されたとみられます。
御府内霊場の札所は江戸期を通じて比較的変動が少なく安定しているのですが、この神仏分離の時期に複数の札所の異動がみられます。
『御府内八十八ケ所道しるべ』は神仏分離前の慶応元年序なので、神仏分離を受けて廃寺となった札所が記載された、たいへん貴重な記録となっています。
御府内に真言宗寺院はさほど多くなく、ほとんどの寺院が札所となっています。
天下の御府内の弘法大師霊場のご開創となれば、多くの真言宗寺院が諸手を挙げて参画したのかもしれません。
『御府内八十八ケ所道しるべ』によって明治初期時点での札所が確定できるので、憶測が少なくなると思います。
これまで書いた記事は当面そのままとし、今後の記事は『御府内八十八ケ所道しるべ』を参照したいと思います。
(『御府内寺社備考』(御府内備考第147巻)もゲットしたので、こちらもあわせて参照します。)
-----------------------
『御府内八十八ケ所道しるべ』『寺社書上』と江戸八十八ヶ所霊場のデータを一覧形式にしたリストをつくってみました。
『寺社書上』は120巻もあって、88の札所をその中から探し出さなければならないので悪戦苦闘でした。
たとえば、第31番の牛込多聞院の記事はこんな感じです。(33巻34頁)
これで史料原典に直リンクする体制はできたのですが、果たして毛筆の達筆すぎる原文が読解できるかどうか・・・(笑)
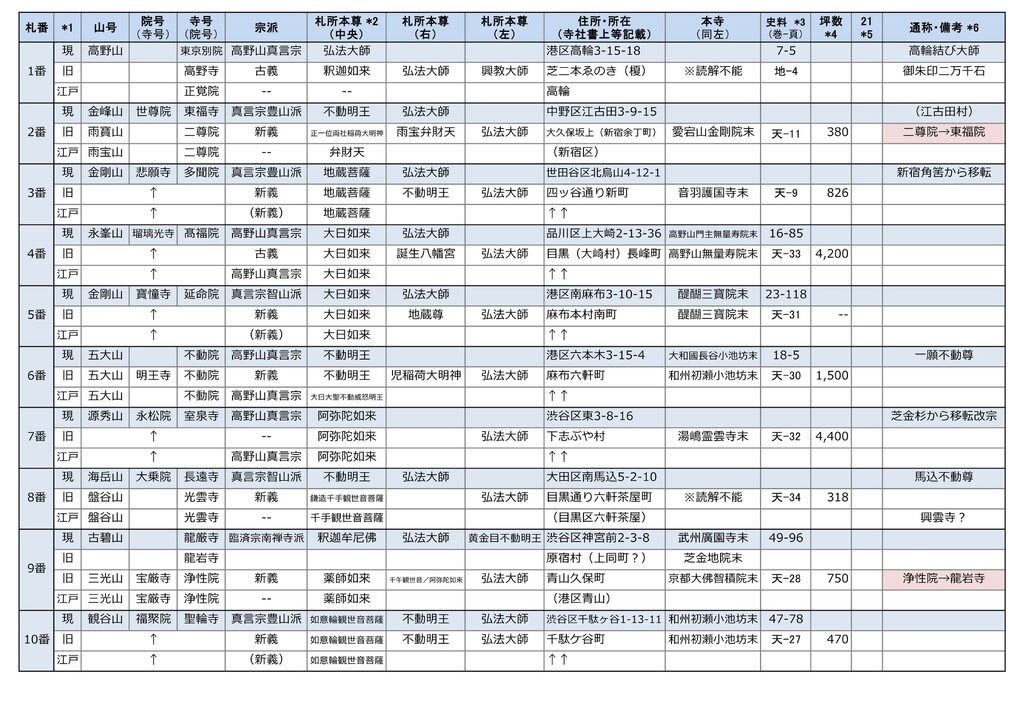
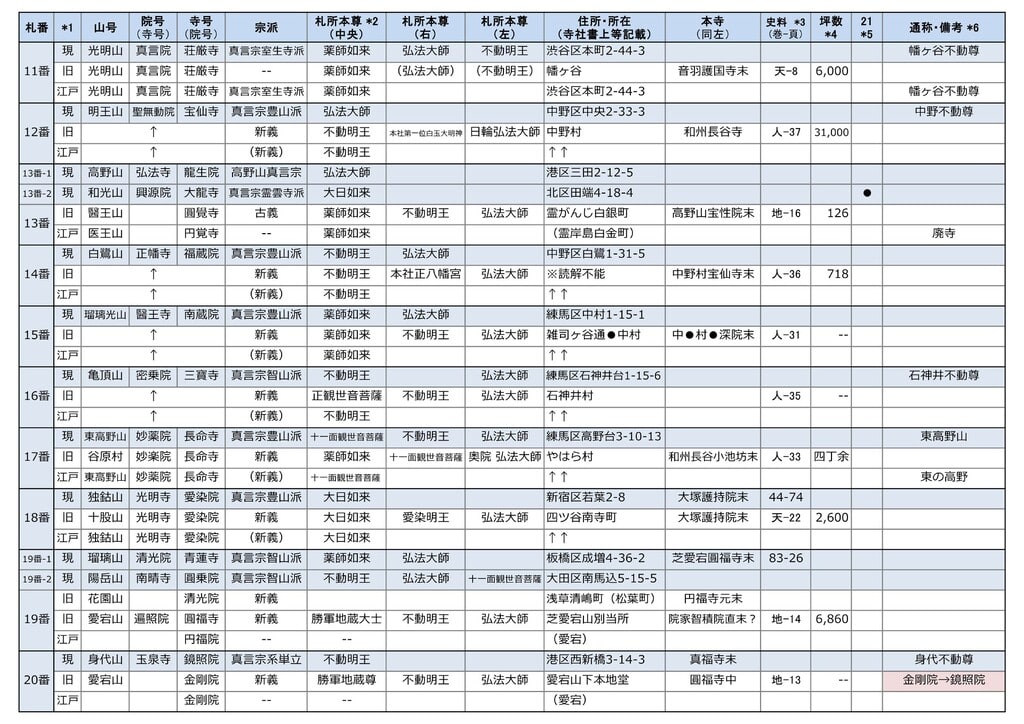
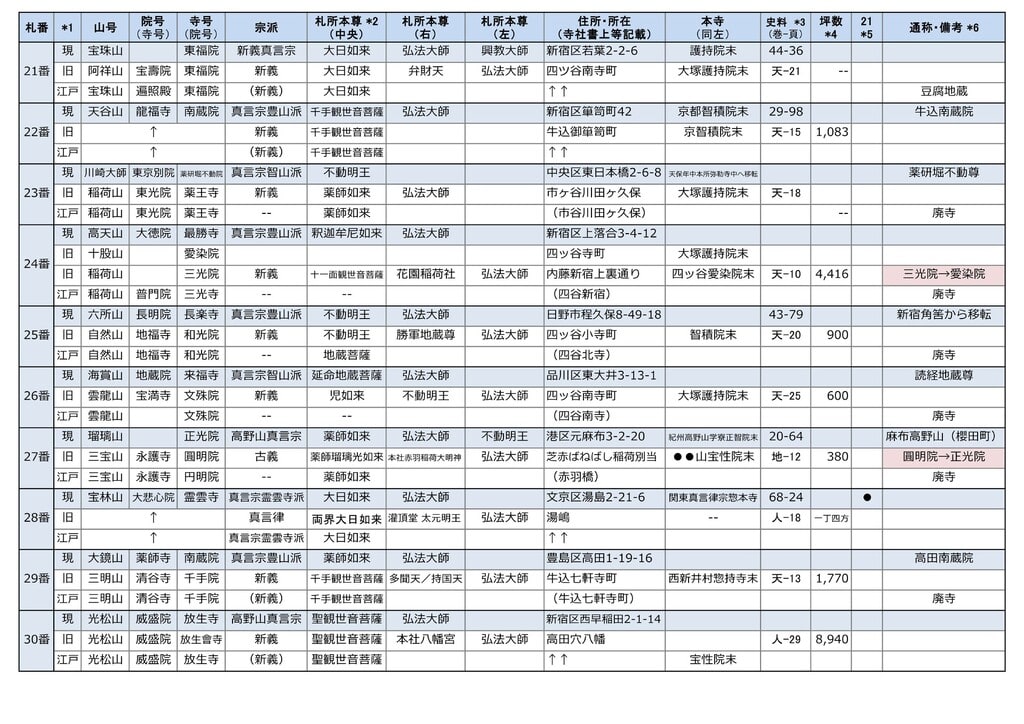
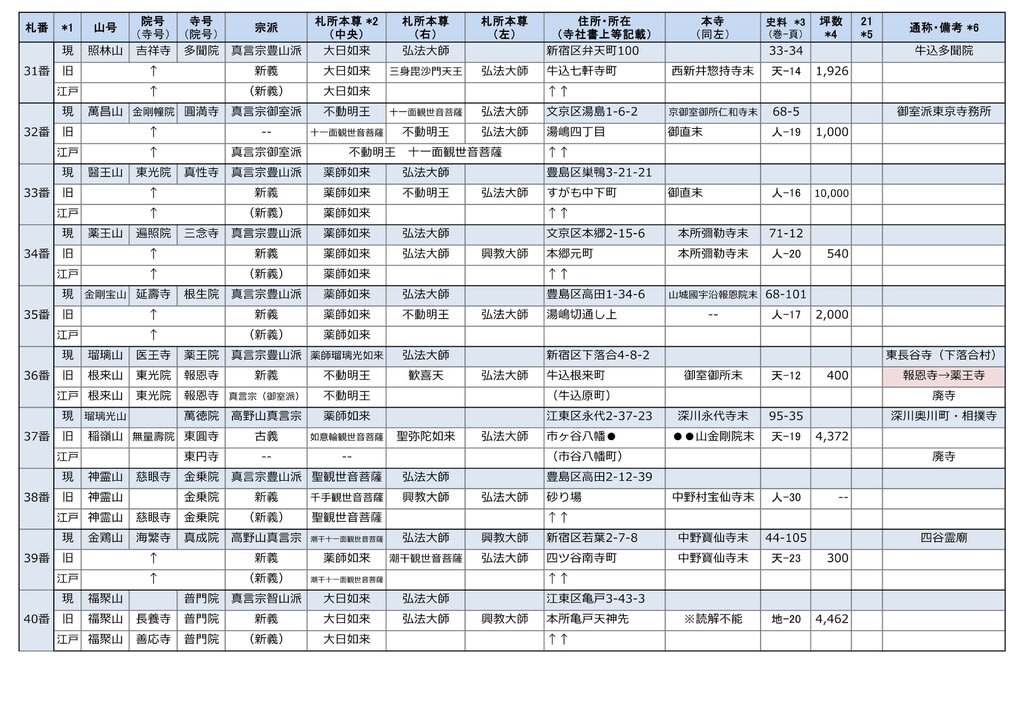
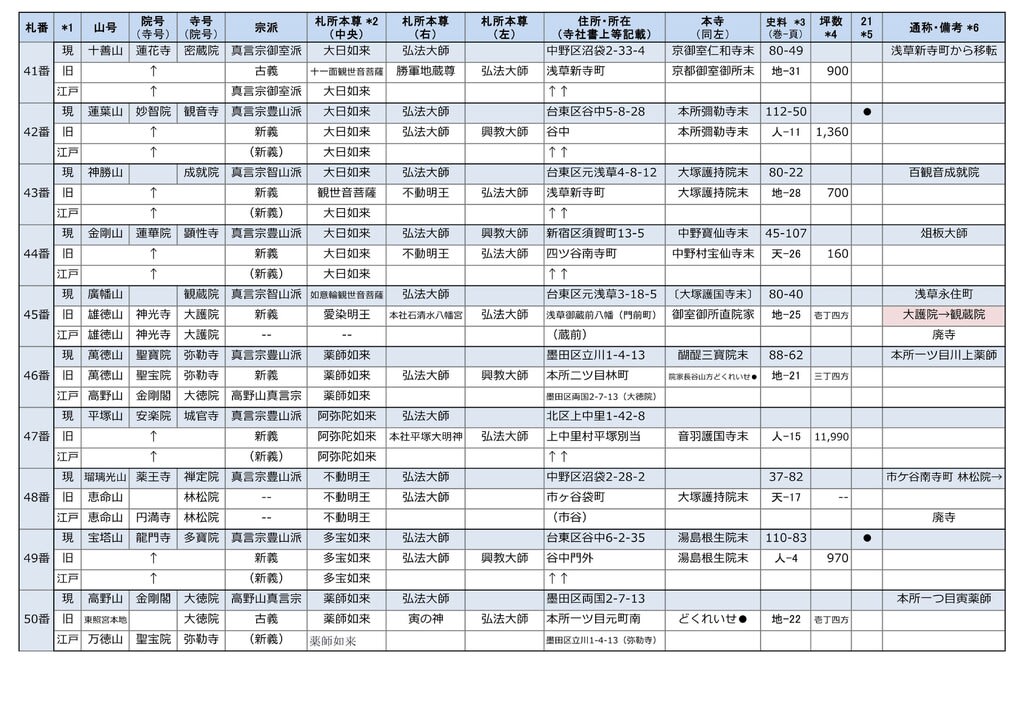
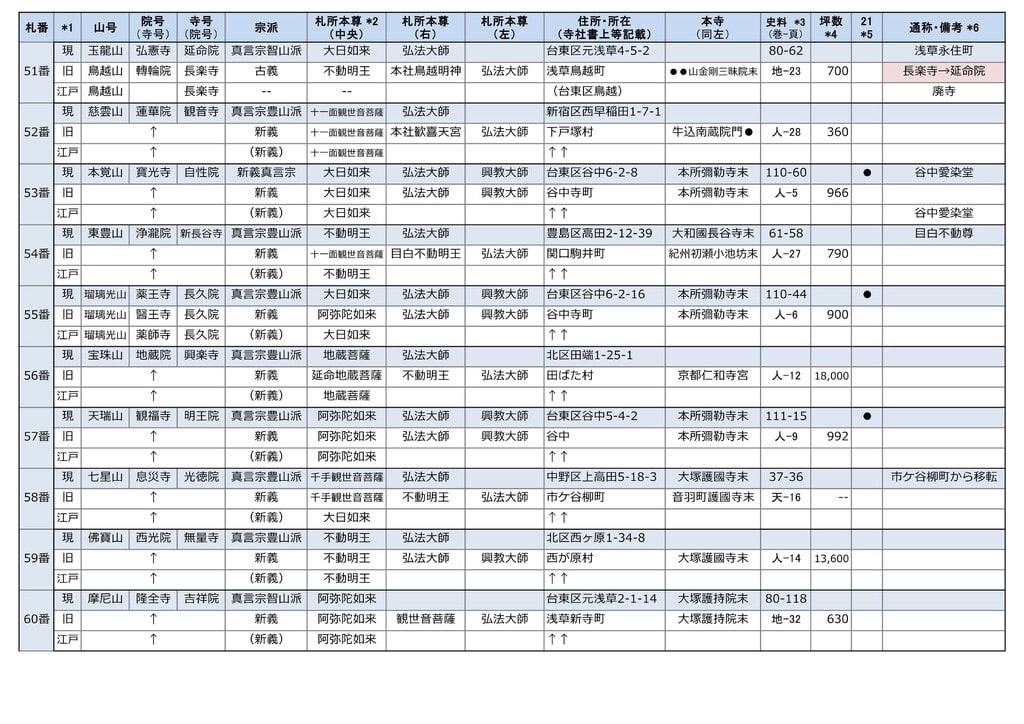
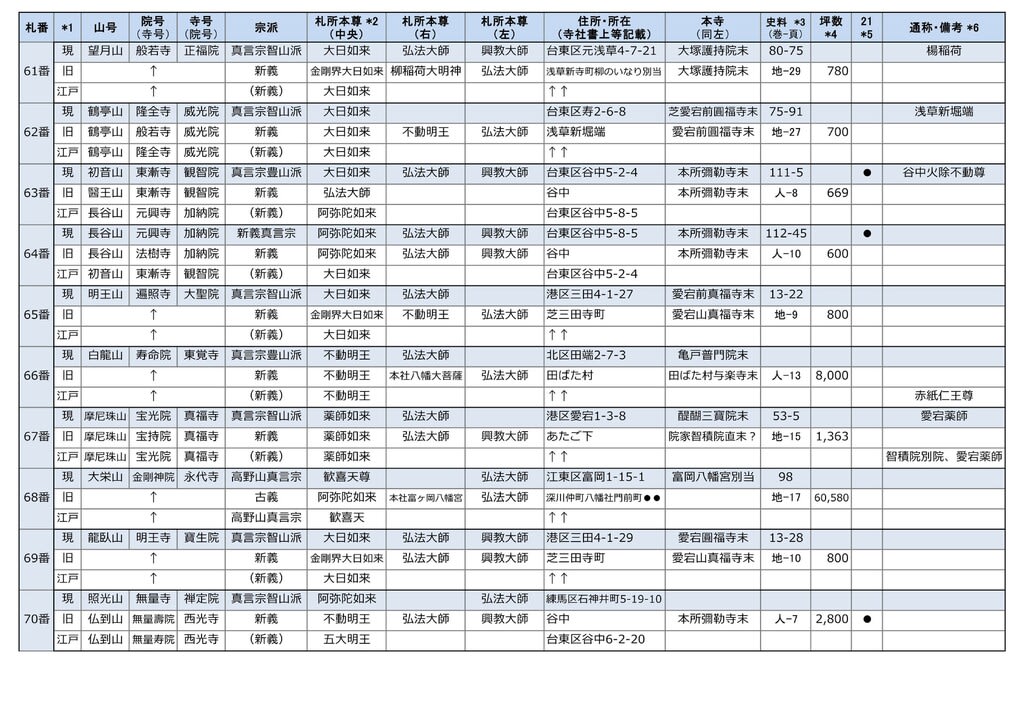
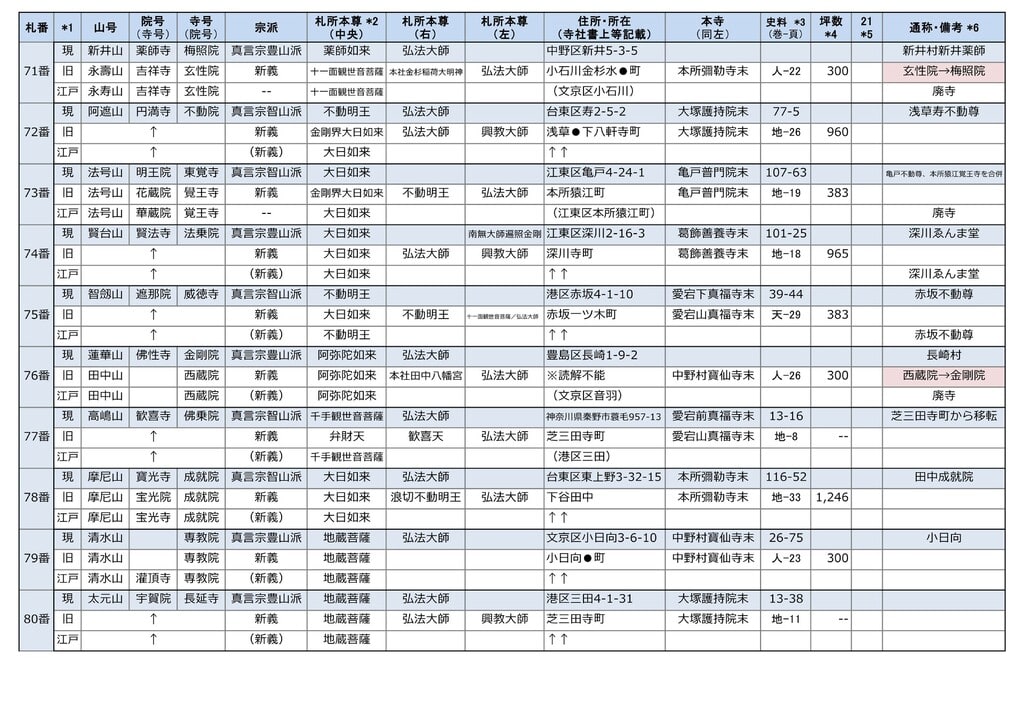
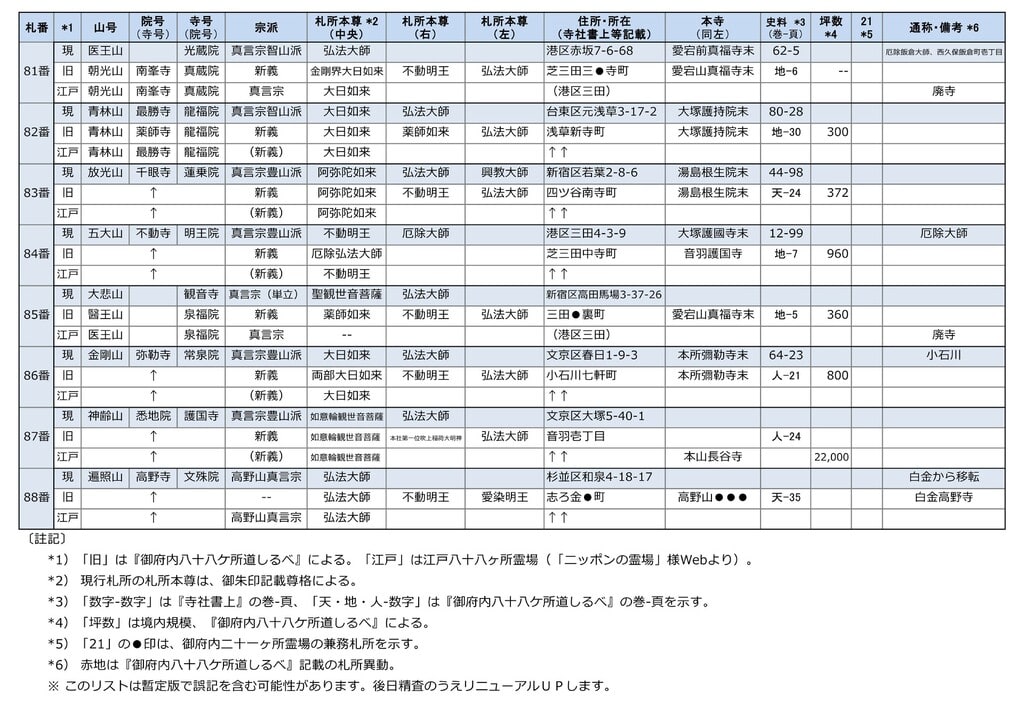
このリストから、
・江戸八十八ヶ所霊場は、御府内霊場の前身または異称であった可能性がある。
・江戸時代の御府内霊場では神社が札所(内の拝所)として定められていた可能性がある。
・江戸時代は比較的札所は安定し、明治初期の神仏分離の流れを受けて複数の札所が異動した。
・明治以降の寺院の郊外移転の動きを受けて、札所も郊外に移動したケースがある。
・中野、幡ヶ谷、石神井、谷原など府外立地でも当初から御府内霊場札所となっていた寺院がある。
などが推定されます。
ともあれ、記事UPを再開します。
Vol.-1Bへつづきます。
【 BGM 】
■ 夢の大地 - Kalafina
■ 桜 - 中村舞子
■ 栞 - 天野月 feat.YURiCa/花たん
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-29
Vol.-28からのつづきです。
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第88番 遍照山 高野寺 文殊院
(もんじゅいん)
杉並区の紹介Web
杉並区和泉4-18-17
高野山真言宗
御本尊:弘法大師
札所本尊:弘法大師
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第88番
ついに札所第88番、結願です。
結願所の第88番は杉並の文殊院です。
第88番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに高野寺文殊院で、第88番札所は開創当初から白金臺町の高野寺文殊院であったとみられます。
杉並区の紹介Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
文殊院は開山を高野山興山寺の木食応其上人ともいいますが、『寺社書上』には慶長五年(1600年)文殊院勢誉師が徳川家康公の帰依を受けて駿府に寺地を拝領して開創とあるようです。
開創当時は興山寺を号していました。
寛永四年(1627年)、文殊院応昌師が江戸浅草に寺地を賜り、駿府城北の丸の建物を拝領して移築といいます。
元禄九年(1696年)麻布白金台町(現・白金二丁目)に移り「白金高野寺」と呼ばれました。
江戸期の当山は、高野山在番所行人方触頭として真言宗では重要ポジションの寺院でした。
高野山行人方については第50番の大徳院でもふれています。
江戸時代、高野山内の組織は学侶方・行人方・聖方の「高野三方(三派)」から成り立っていました。
wikipediaの「高野三方」(こうやさんかた)には以下のとおりあります
-------------------------
高野三方は、平安時代から江戸時代まで高野山を構成した、学侶方・行人方・聖方による三派の総称。
・学侶方
密教に関する学問の研究・祈祷を行った集団。代表寺院は青巌寺であった。
・行人方
寺院の管理・法会といった実務を行った集団。また、僧兵としての役割も担った。代表寺院は興山寺であった。
・聖方
全国を行脚して高野山に対する信仰・勧進を行った集団。全国各地に伝わる空海による開湯・開山の伝説を生む要因となった。代表寺院は大徳院であった。
-------------------------
江戸における高野三方の拠点(在番所等)は、学侶方が高野山学侶方江戸在番所(現・高野山東京別院/第1番札所)、行人方が高野寺文殊院(第88番札所)、聖方が大徳院(第50番札所)。
いずれも御府内霊場札所で、しかも学侶方が第1番発願所、行人方が第88番結願所、聖方が第50番を押さえていたことになります。
御府内霊場は新義真言宗寺院が多いですが、こうしてみると高野山の江戸写し的な性格を帯びていることがわかります。
文殊院が結願所をつとめられている理由は、ここにあるのかとも思います。
『江戸切絵図』には芝三田日本榎高輪辺絵図に「高野寺」がふたつみえます。
ひとつは東禅寺の北側、もうひとつは清正公覚林寺の東側です。
前者が学侶方高野寺(現・高野山東京別院)、後者が行人方高野寺(現・文殊院、杉並に移転)とみられます。
行人方高野寺(文殊院の旧地)は、法華宗立行寺(港区白金2-2-6)の南側辺だったとみられます。
白金高野山(文殊院)と二本榎高野寺(高野山東京別院)は至近に位置し、御府内霊場は白金で発願し、白金で結願する霊場だったことがわかります。
また、■ 『江戸名所図会 7巻 [7]』の挿絵をみると、かなり広壮な敷地をもっていたことがわかります。
大正9年、文殊院は区画整理により現在地(杉並区和泉)に移転しました。
周辺は住宅地ですが、山内には弘法大師信仰を示す八十八ヶ寺大師石像や「お砂踏の石」があり、往年の御府内霊場結願所の趣きをいまに伝えています。
御本尊の弘法大師坐像は室町末期の作といわれ、「安産守護のご本尊」として広く信仰を集めたといいます。
弘法大師座像、弁財天像・付近出土の板碑・百度石・文殊院文書などが区の文化財に指定されている模様ですが、弘法大師座像をのぞいて詳細は不明です。
→ 弘法大師坐像についての杉並区史料(PDF)。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
八十八番
●●●●町
高野寺
高野山●人●直番所
本尊:弘法大師 不動明王 愛染明王
■ 『寺社書上 [16] 白銀寺社書上 弐』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.30』
麻布白金臺町壱町目
高野山行人方在番所
古義真言宗触頭 東西二箇寺
慶長五年(1600年)大権現様於駿府文殊院(当時興山寺ト申候)勢誉寺地拝領仕
其御御当地浅草から砌 寛永四年(1627年)於浅草●-● 文殊院應昌拝領仕
●-● 元禄九年(1696年)於白金臺町替地拝領仕候
本堂
本尊 弘法大師木座像
二脇士 不動明王木坐像 愛染明王木坐像
二天幷八祖画像
本堂内護摩所
不動明王木立像
本堂内大師前
大聖歓喜天
賓頭盧木座像
東在番所
西在番所
東在番交替所
西在番交替所
鎮守社
丹生大明神 高野大明神 神體幣
八幡宮 神體幣
摩利支天小社 神體幣
入船稲荷社
金毘羅小社
■ 『江戸名所図会 7巻 [7]』(国立国会図書館)
白金高野寺
高野山在ばん所行人方触所なり
本尊に弘法大師 幷 不動愛染観音歓喜天を安す
八十八ヶ所の札の打とめなり
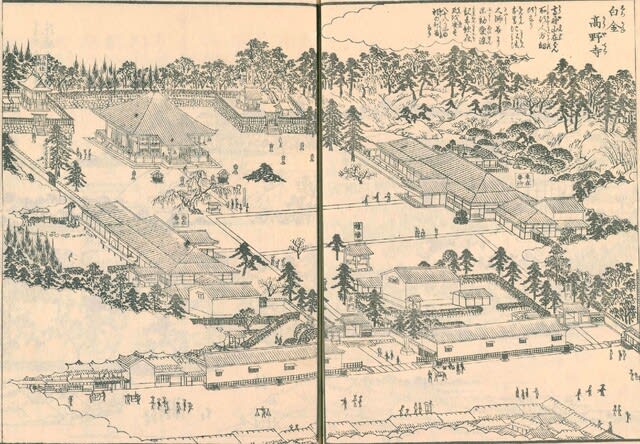
「白金高野寺」/原典:松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[7],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836].国立国会図書館DC(保護期間満了)
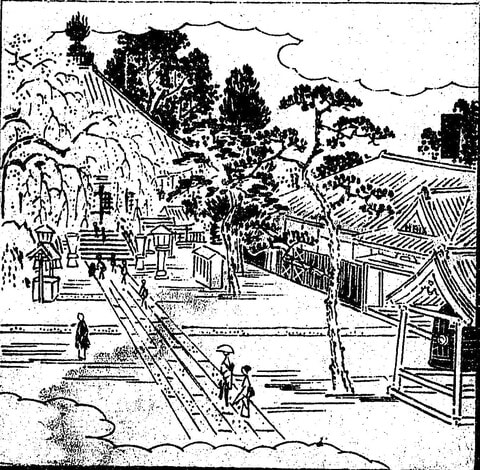
「高野寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』目黒白金辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはJR・メトロ丸ノ内線「方南町」駅で徒歩約15分。
駅から南下して神田川を渡り、住宅街の路地をたどる道行きです。
駅からそれなりに歩きますが、御府内霊場結願に向かうにはこの程度のアプローチがあってもいいかもしれません。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 門前
住宅地のなかに突然に寺院があらわれます。
門前から背後を振り返ると、参道らしいまっすぐの道が延びているので歩いていくと院号標&札所標がありました。
正式にはここからが参道なのだと想います。
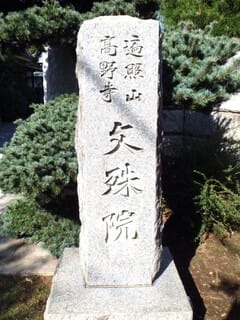

【写真 上(左)】 院号標
【写真 下(右)】 山内
門は門柱で、その手前に院号標。
山内は住宅地の寺院にしてはかなりの広さで、格式の高さが感じられます。
参道左手に文殊堂、正面が本堂、本堂向かって右手が庫裡です。


【写真 上(左)】 文殊堂
【写真 下(右)】 文殊堂扁額
文殊堂は宝形造銅板葺で頂に宝珠を置き、向拝に「文殊堂」の扁額と文殊菩薩の御真言が掲げられています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 修行大師像
本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝、屋根の勾配が急で迫力があります。
本堂向かって右手に修行大師像。本堂前には御宝号の石碑?があります。


【写真 上(左)】 修行大師像と本堂
【写真 下(右)】 弘法大師御寶前の石碑?
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。
向拝見上げに院号扁額を掲げています。
向拝柱には札所板と御寶号の板とが掲げられています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
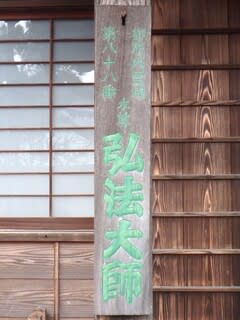

【写真 上(左)】 札所板
【写真 下(右)】 御寶号の板
シンプルながら随所にお大師さまゆかりの事物が配され、さすがに御府内霊場結願寺らしい趣きがあります。
御本尊は弘法大師。
初番・高野山東京別院の御本尊は弘法大師ですから、弘法大師で発願し、弘法大師で結願する、まことに弘法大師霊場らしい霊場といえましょう。
本堂向かって右のおくには五輪塔があり、そのまわりにはたくさんのお大師さまが御座されています。
そして、その回りがお砂踏場となっていて、これまでの巡拝をしのびながら巡拝することができます。


【写真 上(左)】 本堂向かって左手
【写真 下(右)】 お大師さま
御朱印は庫裡にて拝受しました。
結願証は授与されておられませんが、御朱印には「御府内霊場第八十八番 結願寺」の札所印を捺していただけます。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
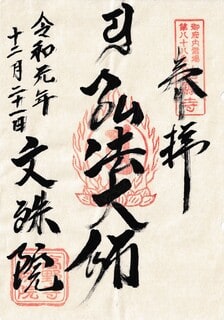

【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に弘法大師のお種子「ユ」「弘法大師」の揮毫と「ユ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「御府内霊場第八十八番 結願寺」の札所印。
左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
-------------------------
これにて江戸・東京の弘法大師霊場・御府内八十八ヶ所霊場は結願となります。
結願に至るまでは長い道程ですが、それだけに達成したときの満足感はひとしおです。
興味をもたれた方は、トライされてみてはいかがでしょうか。
【註記】
この連載記事は、書いている途中で『御府内八十八ケ所道しるべ』の存在に気づいたため、
途中から構成が変わっております。
ひとまずはこれで完結としますが、後日前半の構成を整えていきたいと思います。
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ Goodbye Yesterday - 今井美樹
■ Mirai 未来 - Kalafina
■ 時代 - 薬師丸ひろ子
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第88番 遍照山 高野寺 文殊院
(もんじゅいん)
杉並区の紹介Web
杉並区和泉4-18-17
高野山真言宗
御本尊:弘法大師
札所本尊:弘法大師
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第88番
ついに札所第88番、結願です。
結願所の第88番は杉並の文殊院です。
第88番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに高野寺文殊院で、第88番札所は開創当初から白金臺町の高野寺文殊院であったとみられます。
杉並区の紹介Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
文殊院は開山を高野山興山寺の木食応其上人ともいいますが、『寺社書上』には慶長五年(1600年)文殊院勢誉師が徳川家康公の帰依を受けて駿府に寺地を拝領して開創とあるようです。
開創当時は興山寺を号していました。
寛永四年(1627年)、文殊院応昌師が江戸浅草に寺地を賜り、駿府城北の丸の建物を拝領して移築といいます。
元禄九年(1696年)麻布白金台町(現・白金二丁目)に移り「白金高野寺」と呼ばれました。
江戸期の当山は、高野山在番所行人方触頭として真言宗では重要ポジションの寺院でした。
高野山行人方については第50番の大徳院でもふれています。
江戸時代、高野山内の組織は学侶方・行人方・聖方の「高野三方(三派)」から成り立っていました。
wikipediaの「高野三方」(こうやさんかた)には以下のとおりあります
-------------------------
高野三方は、平安時代から江戸時代まで高野山を構成した、学侶方・行人方・聖方による三派の総称。
・学侶方
密教に関する学問の研究・祈祷を行った集団。代表寺院は青巌寺であった。
・行人方
寺院の管理・法会といった実務を行った集団。また、僧兵としての役割も担った。代表寺院は興山寺であった。
・聖方
全国を行脚して高野山に対する信仰・勧進を行った集団。全国各地に伝わる空海による開湯・開山の伝説を生む要因となった。代表寺院は大徳院であった。
-------------------------
江戸における高野三方の拠点(在番所等)は、学侶方が高野山学侶方江戸在番所(現・高野山東京別院/第1番札所)、行人方が高野寺文殊院(第88番札所)、聖方が大徳院(第50番札所)。
いずれも御府内霊場札所で、しかも学侶方が第1番発願所、行人方が第88番結願所、聖方が第50番を押さえていたことになります。
御府内霊場は新義真言宗寺院が多いですが、こうしてみると高野山の江戸写し的な性格を帯びていることがわかります。
文殊院が結願所をつとめられている理由は、ここにあるのかとも思います。
『江戸切絵図』には芝三田日本榎高輪辺絵図に「高野寺」がふたつみえます。
ひとつは東禅寺の北側、もうひとつは清正公覚林寺の東側です。
前者が学侶方高野寺(現・高野山東京別院)、後者が行人方高野寺(現・文殊院、杉並に移転)とみられます。
行人方高野寺(文殊院の旧地)は、法華宗立行寺(港区白金2-2-6)の南側辺だったとみられます。
白金高野山(文殊院)と二本榎高野寺(高野山東京別院)は至近に位置し、御府内霊場は白金で発願し、白金で結願する霊場だったことがわかります。
また、■ 『江戸名所図会 7巻 [7]』の挿絵をみると、かなり広壮な敷地をもっていたことがわかります。
大正9年、文殊院は区画整理により現在地(杉並区和泉)に移転しました。
周辺は住宅地ですが、山内には弘法大師信仰を示す八十八ヶ寺大師石像や「お砂踏の石」があり、往年の御府内霊場結願所の趣きをいまに伝えています。
御本尊の弘法大師坐像は室町末期の作といわれ、「安産守護のご本尊」として広く信仰を集めたといいます。
弘法大師座像、弁財天像・付近出土の板碑・百度石・文殊院文書などが区の文化財に指定されている模様ですが、弘法大師座像をのぞいて詳細は不明です。
→ 弘法大師坐像についての杉並区史料(PDF)。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
八十八番
●●●●町
高野寺
高野山●人●直番所
本尊:弘法大師 不動明王 愛染明王
■ 『寺社書上 [16] 白銀寺社書上 弐』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.30』
麻布白金臺町壱町目
高野山行人方在番所
古義真言宗触頭 東西二箇寺
慶長五年(1600年)大権現様於駿府文殊院(当時興山寺ト申候)勢誉寺地拝領仕
其御御当地浅草から砌 寛永四年(1627年)於浅草●-● 文殊院應昌拝領仕
●-● 元禄九年(1696年)於白金臺町替地拝領仕候
本堂
本尊 弘法大師木座像
二脇士 不動明王木坐像 愛染明王木坐像
二天幷八祖画像
本堂内護摩所
不動明王木立像
本堂内大師前
大聖歓喜天
賓頭盧木座像
東在番所
西在番所
東在番交替所
西在番交替所
鎮守社
丹生大明神 高野大明神 神體幣
八幡宮 神體幣
摩利支天小社 神體幣
入船稲荷社
金毘羅小社
■ 『江戸名所図会 7巻 [7]』(国立国会図書館)
白金高野寺
高野山在ばん所行人方触所なり
本尊に弘法大師 幷 不動愛染観音歓喜天を安す
八十八ヶ所の札の打とめなり
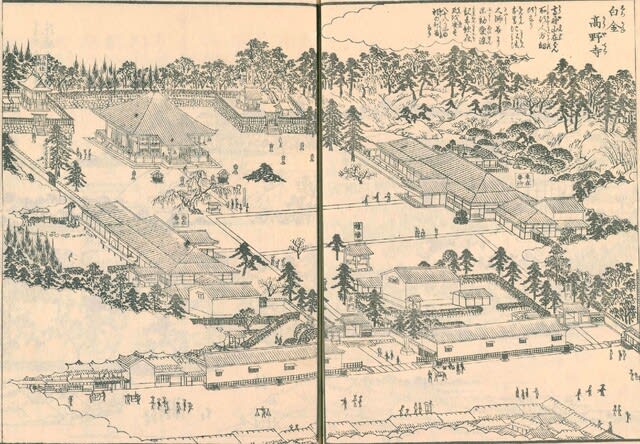
「白金高野寺」/原典:松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[7],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836].国立国会図書館DC(保護期間満了)
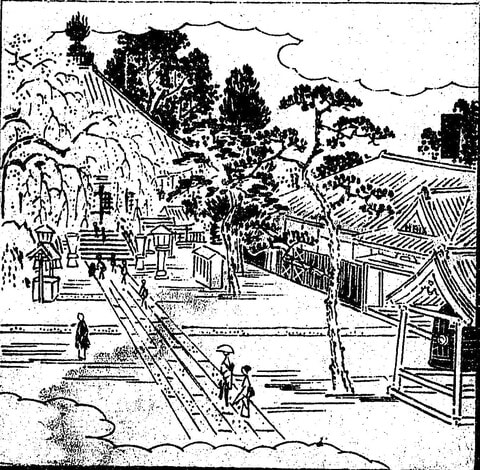
「高野寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』目黒白金辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはJR・メトロ丸ノ内線「方南町」駅で徒歩約15分。
駅から南下して神田川を渡り、住宅街の路地をたどる道行きです。
駅からそれなりに歩きますが、御府内霊場結願に向かうにはこの程度のアプローチがあってもいいかもしれません。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 門前
住宅地のなかに突然に寺院があらわれます。
門前から背後を振り返ると、参道らしいまっすぐの道が延びているので歩いていくと院号標&札所標がありました。
正式にはここからが参道なのだと想います。
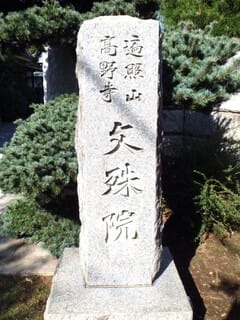

【写真 上(左)】 院号標
【写真 下(右)】 山内
門は門柱で、その手前に院号標。
山内は住宅地の寺院にしてはかなりの広さで、格式の高さが感じられます。
参道左手に文殊堂、正面が本堂、本堂向かって右手が庫裡です。


【写真 上(左)】 文殊堂
【写真 下(右)】 文殊堂扁額
文殊堂は宝形造銅板葺で頂に宝珠を置き、向拝に「文殊堂」の扁額と文殊菩薩の御真言が掲げられています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 修行大師像
本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝、屋根の勾配が急で迫力があります。
本堂向かって右手に修行大師像。本堂前には御宝号の石碑?があります。


【写真 上(左)】 修行大師像と本堂
【写真 下(右)】 弘法大師御寶前の石碑?
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。
向拝見上げに院号扁額を掲げています。
向拝柱には札所板と御寶号の板とが掲げられています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
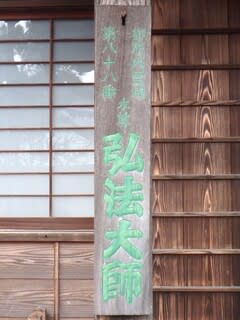

【写真 上(左)】 札所板
【写真 下(右)】 御寶号の板
シンプルながら随所にお大師さまゆかりの事物が配され、さすがに御府内霊場結願寺らしい趣きがあります。
御本尊は弘法大師。
初番・高野山東京別院の御本尊は弘法大師ですから、弘法大師で発願し、弘法大師で結願する、まことに弘法大師霊場らしい霊場といえましょう。
本堂向かって右のおくには五輪塔があり、そのまわりにはたくさんのお大師さまが御座されています。
そして、その回りがお砂踏場となっていて、これまでの巡拝をしのびながら巡拝することができます。


【写真 上(左)】 本堂向かって左手
【写真 下(右)】 お大師さま
御朱印は庫裡にて拝受しました。
結願証は授与されておられませんが、御朱印には「御府内霊場第八十八番 結願寺」の札所印を捺していただけます。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
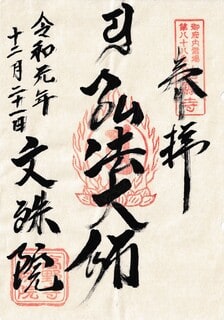

【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に弘法大師のお種子「ユ」「弘法大師」の揮毫と「ユ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「御府内霊場第八十八番 結願寺」の札所印。
左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
-------------------------
これにて江戸・東京の弘法大師霊場・御府内八十八ヶ所霊場は結願となります。
結願に至るまでは長い道程ですが、それだけに達成したときの満足感はひとしおです。
興味をもたれた方は、トライされてみてはいかがでしょうか。
【註記】
この連載記事は、書いている途中で『御府内八十八ケ所道しるべ』の存在に気づいたため、
途中から構成が変わっております。
ひとまずはこれで完結としますが、後日前半の構成を整えていきたいと思います。
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ Goodbye Yesterday - 今井美樹
■ Mirai 未来 - Kalafina
■ 時代 - 薬師丸ひろ子
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-28
Vol.-27からのつづきです。
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第87番 神齢山 悉地院 護国寺
(ごこくじ)
公式Web
文京区大塚5-40-1
真言宗豊山派
御本尊:如意輪観世音菩薩
札所本尊:如意輪観世音菩薩
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第87番、江戸三十三観音札所第13番、近世江戸三十三観音霊場第13番、東京三十三所観世音霊場第24番、山の手三十三観音霊場第7番、東都七観音霊場第7番、弁財天百社参り第46番、東国花の寺百ヶ寺霊場東京第3番
御府内霊場は、結願直前の第87番に御府内きっての名刹を配しています。
音羽の護国寺です。
第87番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに護国寺で、第87番札所は開創当初から音羽の護国寺であったとみられます。
護国寺は御府内有数の名刹につき記録類はふんだんにあり、逐一追っていくときりがないので、公式Web、『江戸名所図会』、『小石川区史』をメインに縁起・沿革を追ってみます。
護国寺は天和元年(1681年)、徳川5代将軍綱吉公(大猷公)が生母・桂昌院の発願を受け、上野国碓氷八幡宮(上野國一社八幡宮)の別当・大聖護国寺の亮賢僧正を招き開山として創建されました。
幕府の高田薬園の地を賜い堂宇を建立、桂昌院の念持仏である天然琥珀如意輪観世音菩薩像を御本尊とし、神齢山悉地院護国寺と号しました。
なお、碓氷八幡宮(上野國一社八幡宮)の元別当・大聖護国寺(高崎市)は現存し、多彩な御朱印を授与されています。
公式Webには、御本尊の不動明王を含む五大明王、および三十六童子が桂昌院寄進であることが記されています。

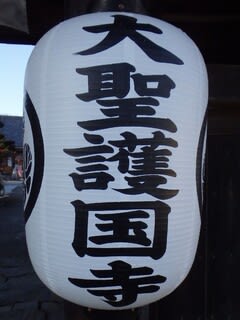
【写真 上(左)】 大聖護国寺
【写真 下(右)】 同
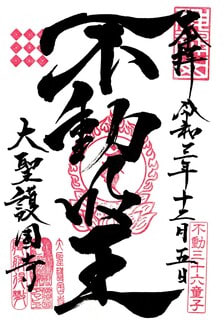

【写真 上(左)】 大聖護国寺の御朱印
【写真 下(右)】 同
寺領三百石の寄進を受けて当山は大伽藍を整え、御府内屈指の巨刹となりました。
幕府の祈願所にもなり綱吉公、桂昌院も度々参詣したといいます。
音羽は江戸城の北方、武蔵野台地のほぼ南端にあり、その台地の高みは武州の山々や、遠く上信の霊山までつながっています。
風水では北の丘陵には玄武が備わり守護するという考えがあります。
幕府の祈願所を音羽に置いたのは、あるいは音羽の丘陵の玄武の守護を期待したものかもしれません。
護国寺は大和長谷寺末ながらすこぶる高い寺格を有し、御府内に多くの末寺を抱えていきます。
享保二年(1717年)正月、神田の護持院が焼失したのち、享保五年(1720年)幕命により護持院を当山内に併置。
観音堂を護国寺、本坊を護持院と称して、護持院の住持が当山を兼攝しました。
〔護持院〕
護持院は、筑波山知足院を号した御府内有数の名刹です。
護持院の開祖権僧正光誉は和州初瀬の西蔵院の住職でしたが(おそらく家康公の)篤い帰依を受けて江戸に招聘され、常州筑波山の宿寺の住持となり知足院と号しました。
筑波山・中善(禅)寺(知足院)との関係については史料により錯綜していますので、簡潔にまとまっている筑波山大御堂の公式Webから抜粋引用させていただきます。
-------------------------
・筑波・知足院中興の祖・宥俊(第1世)は家康公の帰依篤く慶長七年(1602年)朱印五百石を賜る
・慶長十五年(1610年)筑波山中禅寺知足院の江戸別院として江戸に護摩堂を建立
・第2世・光誉は護摩堂の経営に当たるため江戸在府となり、以降筑波山には院代を置いて寺務執行が通例となる
・元禄元年(1688年)綱吉公の後押しで護摩堂を護持院と改称して開山
・江戸将軍家代々の加持祈祷を行う寺院へ発展、上野寛永寺と並び称されるほどの巨刹となる
-------------------------
上記と史料類をまとめてみると、
筑波山知足院の宥俊は家康公の帰依篤く慶長七年(1602年)朱印五百石を賜りました。
慶長十五年(1610年)、大神君(家康公)の命を受けて寺地を賜り、筑波山中禅寺知足院の江戸別院として江戸銀町(神田九軒町ないし日本橋?)に護摩堂を建立。
江戸城の護持所と定めました。
和州初瀬・西蔵院の住職・光誉は(おそらく家康公の)篤い帰依を受けて江戸に招聘され、筑波山中禅寺知足院第2世になるとともに、江戸別院の護摩堂(のちの護持院)を護持しました。
以降、筑波山知足院の住持は江戸(護持院)在所となり、筑波山には院代を置きました。
光誉上人は大阪冬の陣の際に陣中で祈祷をおこなったとありますから、家康公の帰依まことに篤かったとみられます。
常陸の名山・筑波山は古来から人々の信仰を集め、建久二年(1191年)源頼朝公は安西景益、上総介広常、千葉介常胤等を伴って筑波山当神社に参詣、神領を寄進しています。
頼朝公への尊敬の念が篤かったという徳川家康公が、関東鎮護に当たり筑波山を重視したのは故あることかもしれません。
実際、筑波山神社の公式Webには、これをうかがわせる記述がありますので抜粋引用させていただきます。
-------------------------
・天正十八年(1590年)八月、徳川家康は江戸城に入城、東北に聳える筑波山を仰いで江戸城鎮護の霊山と崇め(た)
・慶長五年(1600年)九月、関ヶ原の合戦に大勝の後(略)家康が厚く帰依していた大和国長谷寺の別当梅心院宥俊を筑波別当に補し、知足院を再興せしめて将軍家の御祈願所と為し、筑波山神社御座替祭を以て江戸城鎮護の神事と定めた
・宥俊の弟子二世光誉も家康の信任厚く、慶長十五年(1610年)江戸白銀町に護摩堂を建てて常府を仰付けられ、慶長・元和の大阪夏冬の陣には陣中に在って戦勝を祈願
-------------------------
結城の総鎮守・健田須賀神社の公式Webには「霊峰筑波山を拝するのに素晴らしい地にあり、古代人はここで祭りを行い、日の出から暦を察した」とあり、筑波山信仰との関係を示唆しています。
健田須賀神社はまた、結城家第一の氏神として知られています。
家康公の次男・秀康公は羽柴家(豊臣家)の養子となったのち結城家に入り結城秀康を名乗りました。
秀康公の結城家入りは秀吉公と結城晴朝とで進められたとされますが、秀康公は関ヶ原の戦いの際に宇都宮に留まり、北方・上杉勢の南下を能く抑えました。
筑波山は江戸からみて鬼門の方角に当たり、江戸鎮護という観点からも重要な霊地だったとみられます。
このように、筑波山信仰や鬼門鎮護、そして北方を抑えた結城秀康公の事績などが重なり、筑波別当・知足院が将軍家代々の祈祷寺院となっていったのでは。
上野寛永寺が江戸城の鬼門にあることはよく知られていますが、こちらは天台宗。
さらに北東の筑波山に真言宗系の知足院を置き、二重の江戸鎮護結界を張ったという想像も許されるかもしれません。
知足院江戸護摩堂は、元和八年(1622年)夏以前に成立とされる「新義真言宗触頭江戸四箇寺」の一寺となり寺格を高めました。
御本尊は不動明王で、古くは御本尊に釈迦如来を安したとも伝わります。
寛永三年(1626年)大猷公(徳川家光公)により諸伽藍を建立、延宝二年(1674年)再修するも火災に罹り、貞享元年(1684年)湯島切通(かつての根生院の在地)に一旦移転しました。
元禄元年(1688年)綱吉公の後押しで(知足院江戸)護摩堂を護持院と改号して開山。
江戸将軍家代々の加持祈祷を行う寺院へと発展し、上野寛永寺と並び称されるほどの巨刹となりました。
元禄(1688-1704年)任元の年に神田橋に移転。
移転後も徳川将軍家の帰依浅からず、松平若狭守・仙石越前守により護摩堂、祖師堂、観音堂、経堂、灌頂堂、鐘楼堂、二天門などの伽藍が整備されました。
このとき、隆光を開山とし権僧正に任せられ、元禄四年(1691年)寺領千五百石を拝領して院家に列し、関東新義(真言宗)惣録と定められました。
おそらくこの神田橋移転の前後に、護持院は「新義真言宗触頭江戸四箇寺」を外れたとみられます。
「新義真言宗触頭江戸四箇寺」については第35番の根生院でふれていますが、再掲します。
Wikipediaに「触頭(ふれがしら)とは、「江戸時代に江戸幕府や藩の寺社奉行の下で各宗派ごとに任命された特定の寺院のこと。本山及びその他寺院との上申下達などの連絡を行い、地域内の寺院の統制を行った。」とあります。
『新義真言宗触頭江戸四箇寺成立年次考』(宇高良哲氏、PDF)では、新義真言宗触頭江戸四箇寺は知足院(湯島~一ツ橋→大塚護持院)、真福寺(愛宕)、円福寺(愛宕)、彌勒寺(本所)で、元和八年(1622年)夏以前に成立の可能性が高いとしています。
「港区Web資料」には「新義真言宗の江戸触頭は江戸四箇寺と呼ばれ、本所弥勒寺・湯島知足院(後に湯島根生院)・円福寺・真福寺からなる。」とあり、『寺社書上』にも「根生院儀● 新義真言宗之触頭江戸四ヶ寺之内ニ御座候」とあるので、貞享四年(1687年)に根生院は触頭の地位を湯島知足院から承継したとみられます。
これは護持院が降格になったわけではなく、むしろその逆で「護持院は江戸城守護の役割に専らにするため触頭江戸四ヶ寺」を外れたとする史料が複数みられます。
じっさい、護持院は元禄四年(1691年)寺領千五百石を拝領して院家に列し、関東新義(真言宗)惣録に定められています。
職掌範囲が江戸から関東に広がっているわけで、これはどうみても格上げかと。
松平若狭守・仙石越前守という幕府重鎮肝入りの普請も、これを裏付けています。
元禄五年(1692年)隆光上人は大僧正に昇進し、元禄九年(1696年)元禄山護持院の号を賜わりました。
濃州大野郡實相院から弘法大師御自作の真像をお迎えして、祖師堂に奉安。
観音堂の御本尊も霊験あらたかな御守護として信仰を集めていたようです。
しかし、享保二年(1717年)正月、火災によりすべての堂宇を焼失しました。
享保五年(1720年)、幕命により護持院の住持僧侶は音羽の護国寺内に移り、江戸城祈祷所も音羽の地に遷りました。
観音堂を護国寺、本坊を護持院と称して護持院の住持が当山を兼攝したといいます。
なお、音羽移転時に御本尊についての記載がないので、従前どおり不動明王を御本尊に安していたとみられます。
護持院域内には、この地の蟹ヶ池から出現された薬師如来、歓喜天尊、東照大権現御正真の御尊像を奉安と記されています。
護国寺と同様、護持院も御府内に多くの末寺を抱えていたので、護国寺山内は御府内屈指の新義真言宗の宗務センターとなりました。
なお、本末記載ではそれぞれ「音羽護国寺」「大塚護持院」とされる例が多くみられますが、これは護国寺本坊(=護持院)が大塚寄りだったからかもしれません。
護国寺・護持院両寺併せてじつに二千七百石を賜わり、壮大な山内は『江戸名所図会』所載の絵図からもうかがえます。
高台にある景勝の地で、御府内霊場、江戸三十三観音の札所でもあったことから多くの参拝者を集めたといいます。
明治維新後、護持院は復職(復飾?)して寺号を廃しましたが護国寺は法派を堅持し、これまで護持院と称した部分も護国寺に復しました。
しかし、公式Webに筑波山大御堂のリンクが張られていることからも、旧護持院(筑波山知足院(大御堂))の法統はいまも護国寺のなかに息づいていると思われます。

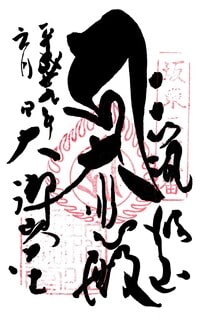
【写真 上(左)】 筑波山大御堂
【写真 下(右)】 筑波山大御堂の御朱印
明治16年旧本坊を焼失、大正15年にも天和草創の大師堂を失いましたが、本坊はすぐに再建、元禄時代建立の薬師堂を大師堂跡に移して大師堂としています。
現在の本堂は元禄十年(1697年)建立の観音堂で、壮大な結構は元禄時代の代表的建築物として国の重要文化財に指定されています。
-------------------------
護国寺本堂 江戸中期/1697
桁行七間、梁間七間、一重、入母屋造、向拝三間、瓦棒銅板葺
重要文化財
-------------------------
昭和3年、原氏寄進の月光殿は三井園城寺の中院にあった日光院の客殿で、桃山時代の書院作りの形式を備えた代表的建築物として、こちらも国の重要文化財となっています。
その他にも薬師堂、大師堂、多宝塔、忠霊堂や創建当時のものと伝えられる仁王門、惣門、中門など、山内には多くの見どころが点在し、いまも多くの参拝客を迎えています。
〔吹上稲荷大明神〕
『御府内八十八ケ所道しるべ』に「本尊:如意輪観世音菩薩 本社 正一位吹上稲荷大明神 弘法大師」という記載があります。
この史料で「本社」とある場合、ほとんどは札所寺院が別当をつとめる神社です。
しかし、 『江戸名所図会 7巻 [12]』(国立国会図書館)には「今宮五社 当所鎮守と云 天照太神宮 八幡大神 春日大明神 今宮大明神 三部大権現五社を祭る 音羽町青柳町桜木町古の鎮守なりと云伝ふ」とあり、当山鎮守で当地の鎮守でもあったのは山内の今宮五社でした。
それではどうして御府内霊場拝所として吹上稲荷大明神が記されているのでしょうか。
境内掲示、『小石川区史』および東京都神社庁Webによると吹上稲荷神社(吹上稲荷大明神)の創祀沿革は以下のとおりです。
元和八年(1622年)、徳川秀忠公が日光山より稲荷大神の御神体を奉戴し江戸城吹上御殿内に「東稲荷宮」号して勧請斎祀。
のちに水戸徳川家の分家松平大学頭家が徳川家より拝領し、宝暦年間(1751-1764年)前に大塚村の総鎮守として松平家より拝受し小石川四丁目に奉斎とあります。
また、このときに江戸城内吹上御殿に鎮座せられるを以て吹上稲荷神社を号したといいます。
その後、護国寺月光殿から大塚上町、大塚仲町と御遷座され、明治45年に大塚坂下町(現在地)に御鎮座といいます。
一時期小日向の善仁寺山内に御遷座という史料もあり、御遷座地について諸説あります。
『小石川区史』に「後護國寺境内に移され、明治五年更に今の地に移った。」とあり、『御府内八十八ケ所道しるべ』が編纂された明治初頭時点では護国寺月光殿に御鎮座とみられます。
護国寺は徳川将軍家とゆかりのふかい寺院、吹上稲荷大明神ももともとは徳川将軍家とのゆかりをもたれるので、護国寺月光殿に御鎮座の吹上稲荷大明神が御府内霊場の拝所とされたのかもしれません。

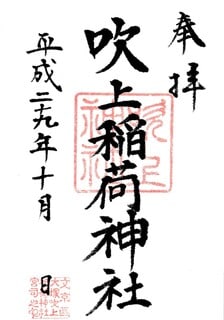
【写真 上(左)】 吹上稲荷神社
【写真 下(右)】 吹上稲荷神社の御朱印
なお、護国寺鎮守の今宮五社については、第76番金剛院でふれていますが、すこしく複雑なので再掲整理します。
御府内霊場第76番札所は、もともとは小日向の田中八幡宮の別当・西蔵院でした。
田中八幡宮(別当:西蔵院)は現在の今宮神社の場所(音羽裏)にありましたが、明治の神佛分離で西蔵院が廃寺となり、田中八幡宮は氷川社(別当:日輪寺)と合祀されて、現在の小日向神社の地に御遷座、小日向神社と号されました。
一方、田中八幡宮の跡地には護国寺の鎮守であった今宮五社が明治6年に御遷座され、今宮神社を号していまに至るようです。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
八十七番
音羽壱丁目
神齢山 悉地院 護國寺
本山長谷寺 新義
本尊:如意輪観世音菩薩 本社 正一位吹上稲荷大明神 弘法大師
■ 『江戸名所図会 7巻 [12]』(国立国会図書館)
神齢山護國寺
悉地院と号し音羽町の北にあり新義の真言宗なり
和州長谷小池坊に属す
開山を亮賢僧正と号し公より寺領二千百石を附せられ盛大の地なり
古鹿子に云 寺領三百石大猷公(徳川家光公)守御本尊瑪瑙石観音像開基
本堂
本尊 如意輪観世音菩薩
瑪瑙石にして天然のものなり 元禄半の頃 前川三左衛門入道道寿といへる人 異邦に渡り持ち来りしを黄檗隠元老師の弟子黒滝の潮音 前川氏と子弟の縁ある●-● 潮音に授与す 其御故ありて桂昌一位尼公崇敬したまひし由
薬師堂
本堂左にあり本尊薬師如来ハ昔当寺草創の時 此地蟹ヶ池より出現ありし霊像なりといへり 今の本尊薬師仏の胎中に収む 左右に十二神将の像を置り
西國三十三番巡礼所写
本堂より西の方の山間にあり天明年間(1781-1789年)深林を伐開き各其地勢によって●を模す
歓喜天
境内寿●院に安す 桂昌一位尼公尊信の本尊なりとそ永代不退ぢんす 天下安全の浴油の法を修せしめられ寺産を●ふ
仁王門
仁王の裏に置所の廣目増長の二天の像ハ古への火災に残りしといふ
今宮五社
当所鎮守と云 天照太神宮 八幡大神 春日大明神 今宮大明神 三部大権現五社を祭る 音羽町青柳町桜木町古の鎮守なりと云伝ふ
当寺ハ延宝九年上野國八幡別当大聖護國寺の住持 法印亮賢に高田御菜園の地を賜ひて寺とす 依って大聖護國寺と号亮賢初
御在胎の時より御祈祷を●りし故 天和元年(1681年)に 憲廟将軍の宣下蒙りて同年都下新建の大聖護國寺を仁和寺に録し●て院家と●依って寺領三百石を附したまふ
貞享二年(1685年)大聖護國寺の住持法印賢廣 黄衣を許る
其後元禄年中(1688-1704年)桂昌院殿一位尼公の御志願によろしく御菜園の地をちんし其頃御建立ありし
江戸密乗最大の梵宇にして結構奉り 春時ハ櫻花爛漫として頗る地勢洛の御室を彷彿せり
■ 『江戸名所図会 7巻 [12]』(国立国会図書館)
筑波山護持院
音羽町の北にあり真言宗にして和州長谷の一派なり
寺領千有五百石を附せらる
本堂
本尊 不動明王 古ハ本尊に釈迦佛を安せしと云
歓喜天
蟹ヶ池 昔此所より薬師如来の像出現ありしとそ
権現山 東照大神君御正真の御尊像を安置し奉る
当寺開祖権僧正光譽ハ和州初瀬寺の西蔵院に住職ありしに 御帰依浅●●に江府に召され 常州筑波山の宿寺を下したまふ 即知足院と号す
其始知足院宥俊ハ下野國筑波山中善寺を兼帯し 真言宗新義四箇寺の支配●り 慶長(1596-1615年)の始 大神君の厳命を蒙り江城の護持所と定させられ 同庚戌の年(慶長十五年(1610年))江戸銀町に寺院をたまふ 其地末考九軒町の●
依光譽知足院をうつし営建を 同癸亥年大阪御陣の頃も光譽命を受けて御陣中に於て祈祷其御寛永三年(1626年)大猷公(徳川家光公)諸伽藍御建立あり
延宝二年(1674年)有廟御再修ありし● 天和五年(1685年?)火災に罹るよりて貞享元年(1684年)湯島切通に移したまふ 今の根生院の地なり
憲廟御帰依浅●●に元禄(1688-1704年)任元の年神田橋外武士屋敷の地に移され松平若狭守仙石越前守に命せられ 護摩堂 祖師堂 観音堂 経堂 灌頂堂 鐘楼堂 二天門 坊舎に至迄 金銀をちりばめたまひ 隆光を開山とし権僧正に任せらる 又護持堂後建立ありて釋迦佛を安せらる
同四年(1691年)寺領千五百石を附したまひ院家に列し 関東新義惣録とせしたまひ 色衣免許の●り当院より沙汰せしと命したまふ
同五年(1692年)覚鑁上人贈官の時に及び隆光改任し大僧正に昇進を 同九年(1696年)元禄山護持院の号を賜ハり(略)弘法大師自作の真像ハ濃州大野郡實相院と云 真言寺にありしを取寄られ祖師堂に安置せり 観音堂の本尊ハ有廟御信敬の御守護佛なり
享保二年(1717年)正月火災ありて 堂塔一宇も不残焼失すれハ 其頃住持とも護國寺に●ひ 大塚護國寺の内にうつし江府城護持の祈祷●所となさしめられ 筑波山兼帯●坊舎日輪院月輪院と云あり
■ 『小石川区史/第七章P.822』(文京区立図書館)
神齢山悉地院護國寺。
新義真言宗豊山派大和長谷寺末。本尊は琥珀如意輪観世音菩薩、開山は亮賢僧正である。当寺の草創については『江戸名所図会』に『求凉亭云く、当寺は京の清水寺を模さるゝ故に、前の町を音羽と名付け、又青柳町、櫻木町など名付けられ、又音羽町九丁あるも、京に一條より九條までの名あるにもとづくとぞ』とあり、天和元年(1681年)将軍綱吉が母公桂昌院の請に依り、元の高田御薬園の地へ一寺を建立し、桂昌院の念持佛であつた天然琥珀観音像を本尊とし、寺領三百石を寄進したのに始まる。
その後桂昌院及び綱吉も度々参詣し(略)本寺は善美を尽せる大伽藍を擁し、将軍の祈願所として、府内屈指の巨刹として、誰れ一人知らぬものがないほど著名になつた。
享保五年(1720年)神田護持院が焼失した時、幕命に依って護持院を当寺に併置し、観音堂の方を護國寺、本坊の方を護持院と称し、護持院の住持が当寺を兼攝した。
兩寺領凡て二千七百石を賜わり、其規模の壮大であった事は、『江戸名所図会』所載の護持院、及び護國寺の圖を見ても知られる。又府内八十八ヶ所の八十七番札所としても多くの参詣者を集めた。
明治維新後、護持院は復職して寺号を廃したが、護國寺は開山以来の法派を保持し、従来護持院と称した部分の堂宇も護國寺分に復した。
然るに明治十六年失火して舊本坊を焼失し、更に大正十五年には天和草創当時の本堂たりし大師堂を失ったが、本坊は直に再建し、元禄時代に建築した薬師堂を大師堂跡に移して大師堂とした。
現在の本堂は元禄十年(1697年)建立の観音堂で、その結構は雄大であり、元禄時代の代表的建築物として寛永時代に建立された浅草寺本堂と併称せられ、都下の江戸時代代表的大建築として特別保護建造物に指定されて居る。
また昭和三年、原氏の寄進になる月光殿が有る。これは元滋賀縣大津市の三井園城寺の中院にあった日光院の客殿で、桃山時代の書院作りの形式を備えた代表的建築物の一つとして、特別保護建造物に指定されて居り、桃山時代の建築としては東都随一の物である。
尚ほ本堂の側に、畿内各地の名物を模造して高橋箒庵居士の寄進した石燈籠二十基があり、東都の一名物として好古家の推賞する所となっている。
又大師堂前には同じく箒庵居士の尽力に依って成った茶亭、仲麿堂及び圓成庵がある。
当寺の墓地は明治二十四年三條實美公の墓地に選ばれて以来、山田顯義伯、大隈侯、山縣公、二荒伯、田中伯、酒井伯、島津公、南部伯、平田伯、河野盤州、梅謙次郎、竹添進一郎氏等維新の元勲を始め、多くの近代名士の墓域となり、俗に『公園墓地』の称がある。
是等の諸建築物や墓地を有する当寺は概ね丘陵の上に有り、境内頗る廣濶、林樹風致に富み、築山、池水等もあって公園の趣を呈し、又音羽通り十数町を其門前町とし、現に市内屈指の佛刹である。
当寺は現在新義真言宗豊山派別格本山で、寺内には豊山派宗務所(がある。)
■ 『小石川区史』(国立国会図書館)
今宮神社
音羽町九丁目に在る。祭神は天照大神、素戔嗚尊、伊弉册尊、譽田別尊、天兒屋根命、大國主命、少彦名命、大宮乃賣命である。
その創建は社伝に依れば、元禄年中(1688-1704年)五代将軍綱吉の生母桂昌院が、護國寺建立と共にその境内に奉祀したと言ふ。
明治初年、神佛混淆禁止に依り、同六年元田中八幡宮の跡なる現地へ遷座した。明治五年村社に列せられ、現在境内は三百餘坪、祭日は九月七日で、東・西青柳町、音羽一丁目乃至九丁目、櫻木町を氏子としてゐる。
■ 『小石川区史』(国立国会図書館)
稲荷神社(吹上)
大塚坂下町に在る。保食命を祭神とする。
俗に吹上稲荷と言はれ、其創建年代も由緒も不明であるが、江戸末期の切絵図に今の大塚窪町邊を吹上と記してあり、又『小石川志料』には、智香寺境内に吹上稲荷大明神のあった事が見えて居るから、それが此の神社の起りであらうと思はれる。後護國寺境内に移され、明治五年更に今の地に移つた。社格は無格社であるが、境内は約二百坪あり、祭典は九月二十二日。竹早町、窪町、大塚町、大塚上町、同仲町、同坂下町を氏子としてゐる。

「護國寺」/原典:松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[12],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836].国立国会図書館DC(保護期間満了)

「大塚護持院」/原典:松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[12],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836].国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』音羽絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ有楽町線「護国寺」駅で駅出口が山門前です。
振り返ると音羽通りは江戸川橋に向けてまっすぐに伸び、かつてはこのあたり門前町だったのかもしれません。
(『江戸名所図会』には、当山が京の清水寺を模したため門前の町を”音羽”と名付けたとあります。)
護国寺については見どころ満載すぎるので、さらっといきます。
素晴らしい山内なので、ぜひいちどお運びくださいませ。(と逃げる・・・(笑))
山内の伽藍配置については、↓の案内図をご覧くださいませ。



【写真 上(左)】 護国寺駅と仁王門
【写真 下(右)】 仁王門
仁王門前に交番を守衛所のように置くさまは、まさに名刹の風格。
仁王門は、切妻屋根桟本瓦葺の単層丹塗り三間一戸の八脚門です。
建立は元禄十年(1697年)造営の観音堂(本堂)よりやや時代が下るとみられていますが、徳川将軍家祈願寺の表門の役割を果たしただけあって、単層とはいえ軒高が高くかなりのスケール感。
本瓦葺、丸柱、丹塗りと、山門からしてすでに寺格の高さを見せつけています。
- 護国寺の 山門の朱の丸柱 強きものこそ 美しくあれ -
窪田空穂

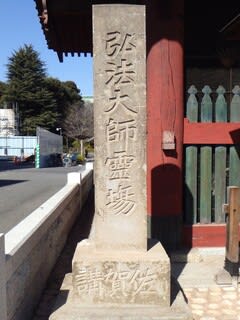
【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 札所碑

仁王門扁額
向かって右手に「大本山護國寺」の寺号標、左手には御府内霊場の札所標。
左右に「大本山護國寺」の提灯を掲げ、見上げには山号扁額を掲げています。
正面南側の両脇間に阿吽の金剛力士像、背面北側両脇間には二天像(右側増長天、左側広目天)が安置されています。


【写真 上(左)】 ご縁日の仁王門
【写真 下(右)】 ご縁日の掲示
山門をくぐると右手に宗務所。こちらは真言宗豊山派の大本山です。


【写真 上(左)】 惣門
【写真 下(右)】 惣門の扁額
仁王門の西側に惣門があり、こちらは本坊(旧護持院)の門かと思われます。
綱吉公と桂昌院の御成のために建築されたといい、冠木門をとりこんだ住宅門の造りです。
案内板によると、五万石以上の大名クラスの格式に相当する形式だそうです。
見上げに独特な字体の寺号扁額。
惣門の先に本坊(寺務所)、書院、桂昌殿(葬祭場)、内仏殿を置いています。
山内は北の大塚方面から伸びる武蔵野台地が音羽谷に降るところで、山門と本堂(観音堂)にかなりの高低差があります。


【写真 上(左)】 音羽富士
【写真 下(右)】 音羽富士山頂
本坊裏手の高みには富士浅間神社(音羽富士)が御遷座、一合目から合標が置かれ頂には石祠があります。


【写真 上(左)】 仁王門前から山内
【写真 下(右)】 縁日の参道
仁王門からはしばらく平坦な参道がつづき、ご縁日などこちらに屋台が並びます。


【写真 上(左)】 手水舎と階段
【写真 下(右)】 水盤
左右に手水舎を置いたところから、いよいよ急な参道階段がはじまります。
この手水舎の唐銅蓮葉手洗水盤は桂昌院の寄進で、元禄十年(1697年)江戸の鋳物師権名伊豫良寛の作と記されています。


【写真 上(左)】 階段
【写真 下(右)】 不老門

不老門扁額
ここで身心を清めてから登りはじめます。
すぐ上に不老門が聳え段数もさほどではないですが、なぜかかなりの登りでがあります。
浅草の辨天堂から観音堂に登る階段もそうですが、低平地から台地に登る参道階段は、段数以上に登りでがあるように感じます。
不老門は昭和13年月建立。京都の鞍馬寺の門を基本に設計されたといいます。
懸造り、入母屋造桟瓦葺身舎朱塗りで正面上部に唐破風を興し、扁額「不老」の二字は徳川家達公の筆によるもの。
懸造りなので構造は複雑ですが、桁行三間で中央一戸かと思います。


【写真 上(左)】 不老門からの本堂
【写真 下(右)】 地蔵尊と仁王尊
参道階段の傾斜が急なので、不老門を抜けるまでは本堂(観音堂)エリアは見えません。
不老門を抜けた左手に地蔵尊立像と仁王尊像、右手が大師堂参道です。

多宝塔
さらに数段登ると本堂(観音堂)エリアです。
参道左手の多宝塔は昭和13年の建立。石山寺の多宝塔(国宝)の模写で周囲に桜を配して春先は花見客で賑わいます。


【写真 上(左)】 円成庵
【写真 下(右)】 拝観謝絶の庵(茶席)
多宝塔手前には蘿装庵、円成庵、不昧軒、宗澄庵などの風情ある庵が点在しますが、参詣者は立ち入りできません。
不老門右手の三笠亭、仲麿堂、簑庵も同様のようです。
その上手の鐘楼は近くまで寄ることができます。
格高の袴腰付重層入母屋造で、江戸時代中期の建立とされます。
梵鐘は天和二年(1682年)寄進、銘文には桂昌院による観音堂建立の経緯が刻まれています。


【写真 上(左)】 鐘楼
【写真 下(右)】 釈迦如来坐像
鐘楼前、参道横には結跏趺坐される釈迦如来の青銅坐像。


【写真 上(左)】 月光殿
【写真 下(右)】 葵の御紋
本堂(観音堂)手前で参道を左に折れると正面が月光殿。
大津三井寺の塔頭・日光院の客殿を昭和3年に現在の場所に移築したもの。
桃山時代の建造で書院様式を伝える貴重な建物として国の重要文化財に指定されています。
附設の建物として草蕾庵、月窓軒、化生庵があるようです。
なお、山内の庵(茶席)は明治から昭和初期にかけて高橋箒庵翁が再興されたとの由。


【写真 上(左)】 多宝塔と月光殿
【写真 下(右)】 山内からビル群
月光殿前から多宝塔方面をのぞむと背景は折り重なるビル群で、護国寺が都心のビル街にオアシス的にあることがわかります。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 ご縁日の本堂
さて、いよいよ本堂(観音堂)です。
元禄十年(1697年)正月、観音堂新営の幕命があり、約半年余りで大造営を完成、同年八月落慶供養と伝わります。
元禄時代の建築工芸の粋を結集した大伽藍とされ、震災・戦災をしのいで江戸期の面影をいまに伝えています。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
桁行七間梁間七間の入母屋造瓦棒銅板葺でこちらも国の重要文化財です。
向拝は三間で、三間に渡って水引虹梁を置き、両端に獅子貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に板蟇股。
軒裏は朱塗りで手前二軒の垂木が目立ちます。
向拝柱には「本尊 如意輪観世音菩薩」の札が掛かっています。
扁額はないですが、羯磨金剛が刻まれた賽銭箱が存在感を放っています。


【写真 上(左)】 御本尊の札
【写真 下(右)】 賽銭箱
こちらの素晴らしいのは、本堂内にあげていただけるところです。
本堂向かって右手の扉が開くのでこちらから参内します。
入ると右手に授与所があるので御朱印帳をお預けします。
堂内はほどよい加減でうす暗く、厳粛な空気がただよっています。
正面が現・御本尊の六臂如意輪観世音菩薩像。
桂昌院の念持仏である唐物天然琥珀如意輪観世音菩薩像は以前に秘仏となり、現在御本尊として安置されているのがこちらの菩薩像のようです。
江戸三十三観音札所、東国花の寺霊場の札所本尊はこちらの観音様になります。
授与所の上には観音霊場札所板が掲げられていました。
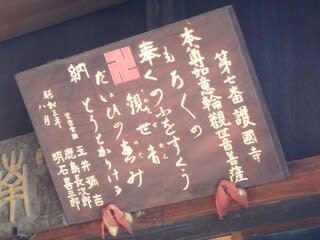

【写真 上(左)】 観音霊場札所板
【写真 下(右)】 観音霊場札所標
堀田正虎の母栄隆院を願主とし、元禄十三年(1700年)寄進され、御頭は恵心僧都の作で身体はこの折に新たに作られたといいます。
もろもろの くのうをすくう 観世音
大悲の恵み 尊うとかりける
なお、如意輪観世音菩薩については、→こちら(東京都区内の如意輪観音の御朱印)をご覧ください。
本堂内は撮影禁止で記憶も定かではありません。
向かって左手には地蔵尊など諸仏、右手には不動明王が御座と記憶しています。
本堂裏手左右が墓域で、本堂正面裏の霊廟は平成8年落慶、聖観世音菩薩像が奉安されています。


【写真 上(左)】 本堂裏手
【写真 下(右)】 閼伽水の井戸
本堂向かって斜め左手おくに傳法灌頂用閼伽水の井戸。
そちらのさらに左おくが薬師堂。
元禄四年(1691年)の建立で、かつての一切経堂を現在の位置に移築し、薬師堂として使用するもの。


【写真 上(左)】 薬師堂
【写真 下(右)】 薬師堂向拝
宝形造桟瓦葺、頂に宝珠を置いて流れ向拝のバランス感に優れた堂宇。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、中備に蟇股で、身舎側への繋ぎ虹梁は置いていません。
向拝正面桟唐戸、両脇に花頭窓を据えるなど禅宗様の手法をとりいれ、元禄期の遺構として価値ある建造物とされます。
こちらの堂宇本尊はこの地にあった蟹ヶ池より出現した薬師如来の霊像を胎内に収められるお薬師さまで、左右に十二神将の像を安置します。
こららの霊像は「江戸名所図会」で護持院の項に記載されているので、旧護持院系の御像とみられます。


【写真 上(左)】 忠霊堂
【写真 下(右)】 山内の梅
薬師堂のさらに左手おくには忠霊堂。
明治35年建立。日清戦争で戦死された軍人の遺骨を埋葬する堂宇で、唐金の多宝塔を建立し、その前に拝殿として建てられたのがこの忠霊堂とのことです。
入母屋造瓦葺平入りで、軒唐破風の大がかりな向拝とスクエアな虹梁を備える特徴ある建物です。
さて、御府内霊場巡拝のハイライト、大師堂です。
上で延べたとおり、大師堂への参道は不老門をくぐって右に折れたところから始まります。
参道入口に整った面立ちの六地蔵。
石敷の参道の正面が大師堂です。


【写真 上(左)】 大師堂参道
【写真 下(右)】 大師堂
元禄十四年(1701年)に再営された旧薬師堂を大正15年に大修理し現在の位置に移築して大師堂としたものです。


【写真 上(左)】 大師堂向拝
【写真 下(右)】 大師堂扁額
寄棟造桟瓦葺流れ向拝で身舎・柱ともに朱塗りです。
がっしりとした水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、中備に蟇股。
真言宗伽藍における大師堂の格式の高さと、中世的な伝統を重んじた貴重な建造物として区の指定建造物に指定されています。
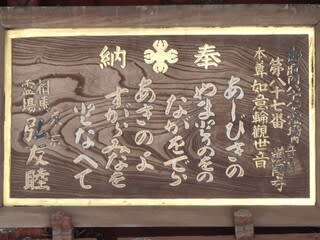

【写真 上(左)】 大師堂札所板
【写真 下(右)】 斜めからの大師堂向拝


【写真 上(左)】 磐座に御座すお大師さま
【写真 下(右)】 大師堂天水鉢
繋ぎ虹梁を置かずすっきりとした向拝。
正面桟唐戸のうえに「遍照金剛」の扁額とそのよこに御府内霊場の札所板、奉納額。
大師堂向かって左の磐座に御座すお大師さまと天水鉢の羯磨金剛が、御府内霊場札所感をひとしお盛り上げています。
堂前説明板には「高祖弘法大師、宗祖興教大師、派祖本覚大師の三尊が安置されている。」とあります。
こちらは本堂(観音堂)に比べて参拝者が少ないので、落ち着いて勤行をあげることができます。


【写真 上(左)】 一言地蔵尊
【写真 下(右)】 身代地蔵尊
大師堂向かって右手には一言地蔵尊のお堂。
願いを一言だけ成就いただけるという霊験あらたかなお地蔵さまです。
その左隣には身代地蔵尊が御座されています。
「さらっといきます。」といいながらやはりこれだけのボリュームになってしまいました(笑)
それだけ見どころの多い名刹ということでしょう。
御朱印は本堂(観音堂)内授与所にて拝受できます。
本堂内の拝観および御朱印授与は、昼の休憩時間を除いた9:00(10:00)〜12:00、13:00~15:00(16:00)で昼はお休みなので要注意です。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

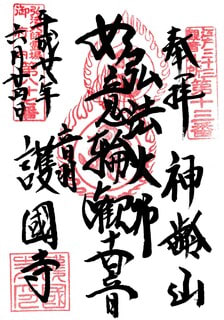
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に如意輪観世音菩薩のお種子「キリク」「本尊 阿彌陀如来」「弘法大師」の揮毫と三寶印。
右に「弘法大師霊場 御府内第八十七番」の札所印。
左に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
主印は「キリク」の御寶印の場合もあるようです。
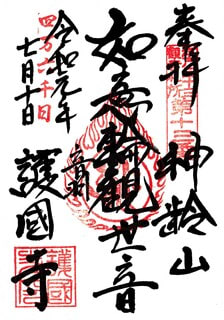
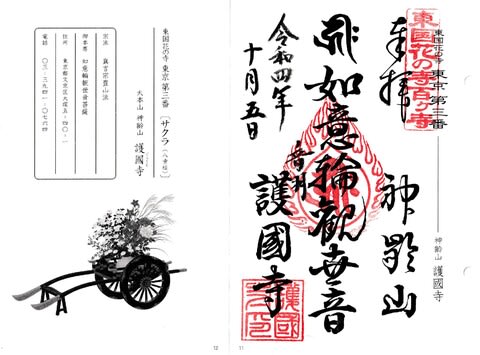
【写真 上(左)】 四万六千日の観音霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東国花の寺霊場の御朱印
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-29)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ 桜 - 中村舞子
■ キミトセカイ - 佳仙(歌ってみた)
■ Boogie-Woogie Lonesome High-Heel - 今井美樹
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第87番 神齢山 悉地院 護国寺
(ごこくじ)
公式Web
文京区大塚5-40-1
真言宗豊山派
御本尊:如意輪観世音菩薩
札所本尊:如意輪観世音菩薩
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第87番、江戸三十三観音札所第13番、近世江戸三十三観音霊場第13番、東京三十三所観世音霊場第24番、山の手三十三観音霊場第7番、東都七観音霊場第7番、弁財天百社参り第46番、東国花の寺百ヶ寺霊場東京第3番
御府内霊場は、結願直前の第87番に御府内きっての名刹を配しています。
音羽の護国寺です。
第87番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに護国寺で、第87番札所は開創当初から音羽の護国寺であったとみられます。
護国寺は御府内有数の名刹につき記録類はふんだんにあり、逐一追っていくときりがないので、公式Web、『江戸名所図会』、『小石川区史』をメインに縁起・沿革を追ってみます。
護国寺は天和元年(1681年)、徳川5代将軍綱吉公(大猷公)が生母・桂昌院の発願を受け、上野国碓氷八幡宮(上野國一社八幡宮)の別当・大聖護国寺の亮賢僧正を招き開山として創建されました。
幕府の高田薬園の地を賜い堂宇を建立、桂昌院の念持仏である天然琥珀如意輪観世音菩薩像を御本尊とし、神齢山悉地院護国寺と号しました。
なお、碓氷八幡宮(上野國一社八幡宮)の元別当・大聖護国寺(高崎市)は現存し、多彩な御朱印を授与されています。
公式Webには、御本尊の不動明王を含む五大明王、および三十六童子が桂昌院寄進であることが記されています。

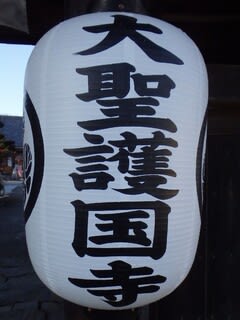
【写真 上(左)】 大聖護国寺
【写真 下(右)】 同
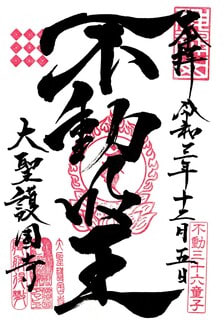

【写真 上(左)】 大聖護国寺の御朱印
【写真 下(右)】 同
寺領三百石の寄進を受けて当山は大伽藍を整え、御府内屈指の巨刹となりました。
幕府の祈願所にもなり綱吉公、桂昌院も度々参詣したといいます。
音羽は江戸城の北方、武蔵野台地のほぼ南端にあり、その台地の高みは武州の山々や、遠く上信の霊山までつながっています。
風水では北の丘陵には玄武が備わり守護するという考えがあります。
幕府の祈願所を音羽に置いたのは、あるいは音羽の丘陵の玄武の守護を期待したものかもしれません。
護国寺は大和長谷寺末ながらすこぶる高い寺格を有し、御府内に多くの末寺を抱えていきます。
享保二年(1717年)正月、神田の護持院が焼失したのち、享保五年(1720年)幕命により護持院を当山内に併置。
観音堂を護国寺、本坊を護持院と称して、護持院の住持が当山を兼攝しました。
〔護持院〕
護持院は、筑波山知足院を号した御府内有数の名刹です。
護持院の開祖権僧正光誉は和州初瀬の西蔵院の住職でしたが(おそらく家康公の)篤い帰依を受けて江戸に招聘され、常州筑波山の宿寺の住持となり知足院と号しました。
筑波山・中善(禅)寺(知足院)との関係については史料により錯綜していますので、簡潔にまとまっている筑波山大御堂の公式Webから抜粋引用させていただきます。
-------------------------
・筑波・知足院中興の祖・宥俊(第1世)は家康公の帰依篤く慶長七年(1602年)朱印五百石を賜る
・慶長十五年(1610年)筑波山中禅寺知足院の江戸別院として江戸に護摩堂を建立
・第2世・光誉は護摩堂の経営に当たるため江戸在府となり、以降筑波山には院代を置いて寺務執行が通例となる
・元禄元年(1688年)綱吉公の後押しで護摩堂を護持院と改称して開山
・江戸将軍家代々の加持祈祷を行う寺院へ発展、上野寛永寺と並び称されるほどの巨刹となる
-------------------------
上記と史料類をまとめてみると、
筑波山知足院の宥俊は家康公の帰依篤く慶長七年(1602年)朱印五百石を賜りました。
慶長十五年(1610年)、大神君(家康公)の命を受けて寺地を賜り、筑波山中禅寺知足院の江戸別院として江戸銀町(神田九軒町ないし日本橋?)に護摩堂を建立。
江戸城の護持所と定めました。
和州初瀬・西蔵院の住職・光誉は(おそらく家康公の)篤い帰依を受けて江戸に招聘され、筑波山中禅寺知足院第2世になるとともに、江戸別院の護摩堂(のちの護持院)を護持しました。
以降、筑波山知足院の住持は江戸(護持院)在所となり、筑波山には院代を置きました。
光誉上人は大阪冬の陣の際に陣中で祈祷をおこなったとありますから、家康公の帰依まことに篤かったとみられます。
常陸の名山・筑波山は古来から人々の信仰を集め、建久二年(1191年)源頼朝公は安西景益、上総介広常、千葉介常胤等を伴って筑波山当神社に参詣、神領を寄進しています。
頼朝公への尊敬の念が篤かったという徳川家康公が、関東鎮護に当たり筑波山を重視したのは故あることかもしれません。
実際、筑波山神社の公式Webには、これをうかがわせる記述がありますので抜粋引用させていただきます。
-------------------------
・天正十八年(1590年)八月、徳川家康は江戸城に入城、東北に聳える筑波山を仰いで江戸城鎮護の霊山と崇め(た)
・慶長五年(1600年)九月、関ヶ原の合戦に大勝の後(略)家康が厚く帰依していた大和国長谷寺の別当梅心院宥俊を筑波別当に補し、知足院を再興せしめて将軍家の御祈願所と為し、筑波山神社御座替祭を以て江戸城鎮護の神事と定めた
・宥俊の弟子二世光誉も家康の信任厚く、慶長十五年(1610年)江戸白銀町に護摩堂を建てて常府を仰付けられ、慶長・元和の大阪夏冬の陣には陣中に在って戦勝を祈願
-------------------------
結城の総鎮守・健田須賀神社の公式Webには「霊峰筑波山を拝するのに素晴らしい地にあり、古代人はここで祭りを行い、日の出から暦を察した」とあり、筑波山信仰との関係を示唆しています。
健田須賀神社はまた、結城家第一の氏神として知られています。
家康公の次男・秀康公は羽柴家(豊臣家)の養子となったのち結城家に入り結城秀康を名乗りました。
秀康公の結城家入りは秀吉公と結城晴朝とで進められたとされますが、秀康公は関ヶ原の戦いの際に宇都宮に留まり、北方・上杉勢の南下を能く抑えました。
筑波山は江戸からみて鬼門の方角に当たり、江戸鎮護という観点からも重要な霊地だったとみられます。
このように、筑波山信仰や鬼門鎮護、そして北方を抑えた結城秀康公の事績などが重なり、筑波別当・知足院が将軍家代々の祈祷寺院となっていったのでは。
上野寛永寺が江戸城の鬼門にあることはよく知られていますが、こちらは天台宗。
さらに北東の筑波山に真言宗系の知足院を置き、二重の江戸鎮護結界を張ったという想像も許されるかもしれません。
知足院江戸護摩堂は、元和八年(1622年)夏以前に成立とされる「新義真言宗触頭江戸四箇寺」の一寺となり寺格を高めました。
御本尊は不動明王で、古くは御本尊に釈迦如来を安したとも伝わります。
寛永三年(1626年)大猷公(徳川家光公)により諸伽藍を建立、延宝二年(1674年)再修するも火災に罹り、貞享元年(1684年)湯島切通(かつての根生院の在地)に一旦移転しました。
元禄元年(1688年)綱吉公の後押しで(知足院江戸)護摩堂を護持院と改号して開山。
江戸将軍家代々の加持祈祷を行う寺院へと発展し、上野寛永寺と並び称されるほどの巨刹となりました。
元禄(1688-1704年)任元の年に神田橋に移転。
移転後も徳川将軍家の帰依浅からず、松平若狭守・仙石越前守により護摩堂、祖師堂、観音堂、経堂、灌頂堂、鐘楼堂、二天門などの伽藍が整備されました。
このとき、隆光を開山とし権僧正に任せられ、元禄四年(1691年)寺領千五百石を拝領して院家に列し、関東新義(真言宗)惣録と定められました。
おそらくこの神田橋移転の前後に、護持院は「新義真言宗触頭江戸四箇寺」を外れたとみられます。
「新義真言宗触頭江戸四箇寺」については第35番の根生院でふれていますが、再掲します。
Wikipediaに「触頭(ふれがしら)とは、「江戸時代に江戸幕府や藩の寺社奉行の下で各宗派ごとに任命された特定の寺院のこと。本山及びその他寺院との上申下達などの連絡を行い、地域内の寺院の統制を行った。」とあります。
『新義真言宗触頭江戸四箇寺成立年次考』(宇高良哲氏、PDF)では、新義真言宗触頭江戸四箇寺は知足院(湯島~一ツ橋→大塚護持院)、真福寺(愛宕)、円福寺(愛宕)、彌勒寺(本所)で、元和八年(1622年)夏以前に成立の可能性が高いとしています。
「港区Web資料」には「新義真言宗の江戸触頭は江戸四箇寺と呼ばれ、本所弥勒寺・湯島知足院(後に湯島根生院)・円福寺・真福寺からなる。」とあり、『寺社書上』にも「根生院儀● 新義真言宗之触頭江戸四ヶ寺之内ニ御座候」とあるので、貞享四年(1687年)に根生院は触頭の地位を湯島知足院から承継したとみられます。
これは護持院が降格になったわけではなく、むしろその逆で「護持院は江戸城守護の役割に専らにするため触頭江戸四ヶ寺」を外れたとする史料が複数みられます。
じっさい、護持院は元禄四年(1691年)寺領千五百石を拝領して院家に列し、関東新義(真言宗)惣録に定められています。
職掌範囲が江戸から関東に広がっているわけで、これはどうみても格上げかと。
松平若狭守・仙石越前守という幕府重鎮肝入りの普請も、これを裏付けています。
元禄五年(1692年)隆光上人は大僧正に昇進し、元禄九年(1696年)元禄山護持院の号を賜わりました。
濃州大野郡實相院から弘法大師御自作の真像をお迎えして、祖師堂に奉安。
観音堂の御本尊も霊験あらたかな御守護として信仰を集めていたようです。
しかし、享保二年(1717年)正月、火災によりすべての堂宇を焼失しました。
享保五年(1720年)、幕命により護持院の住持僧侶は音羽の護国寺内に移り、江戸城祈祷所も音羽の地に遷りました。
観音堂を護国寺、本坊を護持院と称して護持院の住持が当山を兼攝したといいます。
なお、音羽移転時に御本尊についての記載がないので、従前どおり不動明王を御本尊に安していたとみられます。
護持院域内には、この地の蟹ヶ池から出現された薬師如来、歓喜天尊、東照大権現御正真の御尊像を奉安と記されています。
護国寺と同様、護持院も御府内に多くの末寺を抱えていたので、護国寺山内は御府内屈指の新義真言宗の宗務センターとなりました。
なお、本末記載ではそれぞれ「音羽護国寺」「大塚護持院」とされる例が多くみられますが、これは護国寺本坊(=護持院)が大塚寄りだったからかもしれません。
護国寺・護持院両寺併せてじつに二千七百石を賜わり、壮大な山内は『江戸名所図会』所載の絵図からもうかがえます。
高台にある景勝の地で、御府内霊場、江戸三十三観音の札所でもあったことから多くの参拝者を集めたといいます。
明治維新後、護持院は復職(復飾?)して寺号を廃しましたが護国寺は法派を堅持し、これまで護持院と称した部分も護国寺に復しました。
しかし、公式Webに筑波山大御堂のリンクが張られていることからも、旧護持院(筑波山知足院(大御堂))の法統はいまも護国寺のなかに息づいていると思われます。

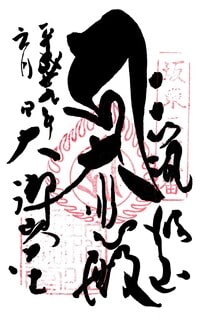
【写真 上(左)】 筑波山大御堂
【写真 下(右)】 筑波山大御堂の御朱印
明治16年旧本坊を焼失、大正15年にも天和草創の大師堂を失いましたが、本坊はすぐに再建、元禄時代建立の薬師堂を大師堂跡に移して大師堂としています。
現在の本堂は元禄十年(1697年)建立の観音堂で、壮大な結構は元禄時代の代表的建築物として国の重要文化財に指定されています。
-------------------------
護国寺本堂 江戸中期/1697
桁行七間、梁間七間、一重、入母屋造、向拝三間、瓦棒銅板葺
重要文化財
-------------------------
昭和3年、原氏寄進の月光殿は三井園城寺の中院にあった日光院の客殿で、桃山時代の書院作りの形式を備えた代表的建築物として、こちらも国の重要文化財となっています。
その他にも薬師堂、大師堂、多宝塔、忠霊堂や創建当時のものと伝えられる仁王門、惣門、中門など、山内には多くの見どころが点在し、いまも多くの参拝客を迎えています。
〔吹上稲荷大明神〕
『御府内八十八ケ所道しるべ』に「本尊:如意輪観世音菩薩 本社 正一位吹上稲荷大明神 弘法大師」という記載があります。
この史料で「本社」とある場合、ほとんどは札所寺院が別当をつとめる神社です。
しかし、 『江戸名所図会 7巻 [12]』(国立国会図書館)には「今宮五社 当所鎮守と云 天照太神宮 八幡大神 春日大明神 今宮大明神 三部大権現五社を祭る 音羽町青柳町桜木町古の鎮守なりと云伝ふ」とあり、当山鎮守で当地の鎮守でもあったのは山内の今宮五社でした。
それではどうして御府内霊場拝所として吹上稲荷大明神が記されているのでしょうか。
境内掲示、『小石川区史』および東京都神社庁Webによると吹上稲荷神社(吹上稲荷大明神)の創祀沿革は以下のとおりです。
元和八年(1622年)、徳川秀忠公が日光山より稲荷大神の御神体を奉戴し江戸城吹上御殿内に「東稲荷宮」号して勧請斎祀。
のちに水戸徳川家の分家松平大学頭家が徳川家より拝領し、宝暦年間(1751-1764年)前に大塚村の総鎮守として松平家より拝受し小石川四丁目に奉斎とあります。
また、このときに江戸城内吹上御殿に鎮座せられるを以て吹上稲荷神社を号したといいます。
その後、護国寺月光殿から大塚上町、大塚仲町と御遷座され、明治45年に大塚坂下町(現在地)に御鎮座といいます。
一時期小日向の善仁寺山内に御遷座という史料もあり、御遷座地について諸説あります。
『小石川区史』に「後護國寺境内に移され、明治五年更に今の地に移った。」とあり、『御府内八十八ケ所道しるべ』が編纂された明治初頭時点では護国寺月光殿に御鎮座とみられます。
護国寺は徳川将軍家とゆかりのふかい寺院、吹上稲荷大明神ももともとは徳川将軍家とのゆかりをもたれるので、護国寺月光殿に御鎮座の吹上稲荷大明神が御府内霊場の拝所とされたのかもしれません。

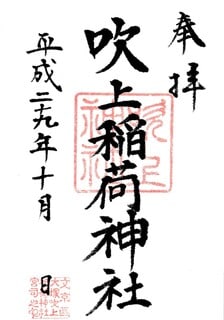
【写真 上(左)】 吹上稲荷神社
【写真 下(右)】 吹上稲荷神社の御朱印
なお、護国寺鎮守の今宮五社については、第76番金剛院でふれていますが、すこしく複雑なので再掲整理します。
御府内霊場第76番札所は、もともとは小日向の田中八幡宮の別当・西蔵院でした。
田中八幡宮(別当:西蔵院)は現在の今宮神社の場所(音羽裏)にありましたが、明治の神佛分離で西蔵院が廃寺となり、田中八幡宮は氷川社(別当:日輪寺)と合祀されて、現在の小日向神社の地に御遷座、小日向神社と号されました。
一方、田中八幡宮の跡地には護国寺の鎮守であった今宮五社が明治6年に御遷座され、今宮神社を号していまに至るようです。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
八十七番
音羽壱丁目
神齢山 悉地院 護國寺
本山長谷寺 新義
本尊:如意輪観世音菩薩 本社 正一位吹上稲荷大明神 弘法大師
■ 『江戸名所図会 7巻 [12]』(国立国会図書館)
神齢山護國寺
悉地院と号し音羽町の北にあり新義の真言宗なり
和州長谷小池坊に属す
開山を亮賢僧正と号し公より寺領二千百石を附せられ盛大の地なり
古鹿子に云 寺領三百石大猷公(徳川家光公)守御本尊瑪瑙石観音像開基
本堂
本尊 如意輪観世音菩薩
瑪瑙石にして天然のものなり 元禄半の頃 前川三左衛門入道道寿といへる人 異邦に渡り持ち来りしを黄檗隠元老師の弟子黒滝の潮音 前川氏と子弟の縁ある●-● 潮音に授与す 其御故ありて桂昌一位尼公崇敬したまひし由
薬師堂
本堂左にあり本尊薬師如来ハ昔当寺草創の時 此地蟹ヶ池より出現ありし霊像なりといへり 今の本尊薬師仏の胎中に収む 左右に十二神将の像を置り
西國三十三番巡礼所写
本堂より西の方の山間にあり天明年間(1781-1789年)深林を伐開き各其地勢によって●を模す
歓喜天
境内寿●院に安す 桂昌一位尼公尊信の本尊なりとそ永代不退ぢんす 天下安全の浴油の法を修せしめられ寺産を●ふ
仁王門
仁王の裏に置所の廣目増長の二天の像ハ古への火災に残りしといふ
今宮五社
当所鎮守と云 天照太神宮 八幡大神 春日大明神 今宮大明神 三部大権現五社を祭る 音羽町青柳町桜木町古の鎮守なりと云伝ふ
当寺ハ延宝九年上野國八幡別当大聖護國寺の住持 法印亮賢に高田御菜園の地を賜ひて寺とす 依って大聖護國寺と号亮賢初
御在胎の時より御祈祷を●りし故 天和元年(1681年)に 憲廟将軍の宣下蒙りて同年都下新建の大聖護國寺を仁和寺に録し●て院家と●依って寺領三百石を附したまふ
貞享二年(1685年)大聖護國寺の住持法印賢廣 黄衣を許る
其後元禄年中(1688-1704年)桂昌院殿一位尼公の御志願によろしく御菜園の地をちんし其頃御建立ありし
江戸密乗最大の梵宇にして結構奉り 春時ハ櫻花爛漫として頗る地勢洛の御室を彷彿せり
■ 『江戸名所図会 7巻 [12]』(国立国会図書館)
筑波山護持院
音羽町の北にあり真言宗にして和州長谷の一派なり
寺領千有五百石を附せらる
本堂
本尊 不動明王 古ハ本尊に釈迦佛を安せしと云
歓喜天
蟹ヶ池 昔此所より薬師如来の像出現ありしとそ
権現山 東照大神君御正真の御尊像を安置し奉る
当寺開祖権僧正光譽ハ和州初瀬寺の西蔵院に住職ありしに 御帰依浅●●に江府に召され 常州筑波山の宿寺を下したまふ 即知足院と号す
其始知足院宥俊ハ下野國筑波山中善寺を兼帯し 真言宗新義四箇寺の支配●り 慶長(1596-1615年)の始 大神君の厳命を蒙り江城の護持所と定させられ 同庚戌の年(慶長十五年(1610年))江戸銀町に寺院をたまふ 其地末考九軒町の●
依光譽知足院をうつし営建を 同癸亥年大阪御陣の頃も光譽命を受けて御陣中に於て祈祷其御寛永三年(1626年)大猷公(徳川家光公)諸伽藍御建立あり
延宝二年(1674年)有廟御再修ありし● 天和五年(1685年?)火災に罹るよりて貞享元年(1684年)湯島切通に移したまふ 今の根生院の地なり
憲廟御帰依浅●●に元禄(1688-1704年)任元の年神田橋外武士屋敷の地に移され松平若狭守仙石越前守に命せられ 護摩堂 祖師堂 観音堂 経堂 灌頂堂 鐘楼堂 二天門 坊舎に至迄 金銀をちりばめたまひ 隆光を開山とし権僧正に任せらる 又護持堂後建立ありて釋迦佛を安せらる
同四年(1691年)寺領千五百石を附したまひ院家に列し 関東新義惣録とせしたまひ 色衣免許の●り当院より沙汰せしと命したまふ
同五年(1692年)覚鑁上人贈官の時に及び隆光改任し大僧正に昇進を 同九年(1696年)元禄山護持院の号を賜ハり(略)弘法大師自作の真像ハ濃州大野郡實相院と云 真言寺にありしを取寄られ祖師堂に安置せり 観音堂の本尊ハ有廟御信敬の御守護佛なり
享保二年(1717年)正月火災ありて 堂塔一宇も不残焼失すれハ 其頃住持とも護國寺に●ひ 大塚護國寺の内にうつし江府城護持の祈祷●所となさしめられ 筑波山兼帯●坊舎日輪院月輪院と云あり
■ 『小石川区史/第七章P.822』(文京区立図書館)
神齢山悉地院護國寺。
新義真言宗豊山派大和長谷寺末。本尊は琥珀如意輪観世音菩薩、開山は亮賢僧正である。当寺の草創については『江戸名所図会』に『求凉亭云く、当寺は京の清水寺を模さるゝ故に、前の町を音羽と名付け、又青柳町、櫻木町など名付けられ、又音羽町九丁あるも、京に一條より九條までの名あるにもとづくとぞ』とあり、天和元年(1681年)将軍綱吉が母公桂昌院の請に依り、元の高田御薬園の地へ一寺を建立し、桂昌院の念持佛であつた天然琥珀観音像を本尊とし、寺領三百石を寄進したのに始まる。
その後桂昌院及び綱吉も度々参詣し(略)本寺は善美を尽せる大伽藍を擁し、将軍の祈願所として、府内屈指の巨刹として、誰れ一人知らぬものがないほど著名になつた。
享保五年(1720年)神田護持院が焼失した時、幕命に依って護持院を当寺に併置し、観音堂の方を護國寺、本坊の方を護持院と称し、護持院の住持が当寺を兼攝した。
兩寺領凡て二千七百石を賜わり、其規模の壮大であった事は、『江戸名所図会』所載の護持院、及び護國寺の圖を見ても知られる。又府内八十八ヶ所の八十七番札所としても多くの参詣者を集めた。
明治維新後、護持院は復職して寺号を廃したが、護國寺は開山以来の法派を保持し、従来護持院と称した部分の堂宇も護國寺分に復した。
然るに明治十六年失火して舊本坊を焼失し、更に大正十五年には天和草創当時の本堂たりし大師堂を失ったが、本坊は直に再建し、元禄時代に建築した薬師堂を大師堂跡に移して大師堂とした。
現在の本堂は元禄十年(1697年)建立の観音堂で、その結構は雄大であり、元禄時代の代表的建築物として寛永時代に建立された浅草寺本堂と併称せられ、都下の江戸時代代表的大建築として特別保護建造物に指定されて居る。
また昭和三年、原氏の寄進になる月光殿が有る。これは元滋賀縣大津市の三井園城寺の中院にあった日光院の客殿で、桃山時代の書院作りの形式を備えた代表的建築物の一つとして、特別保護建造物に指定されて居り、桃山時代の建築としては東都随一の物である。
尚ほ本堂の側に、畿内各地の名物を模造して高橋箒庵居士の寄進した石燈籠二十基があり、東都の一名物として好古家の推賞する所となっている。
又大師堂前には同じく箒庵居士の尽力に依って成った茶亭、仲麿堂及び圓成庵がある。
当寺の墓地は明治二十四年三條實美公の墓地に選ばれて以来、山田顯義伯、大隈侯、山縣公、二荒伯、田中伯、酒井伯、島津公、南部伯、平田伯、河野盤州、梅謙次郎、竹添進一郎氏等維新の元勲を始め、多くの近代名士の墓域となり、俗に『公園墓地』の称がある。
是等の諸建築物や墓地を有する当寺は概ね丘陵の上に有り、境内頗る廣濶、林樹風致に富み、築山、池水等もあって公園の趣を呈し、又音羽通り十数町を其門前町とし、現に市内屈指の佛刹である。
当寺は現在新義真言宗豊山派別格本山で、寺内には豊山派宗務所(がある。)
■ 『小石川区史』(国立国会図書館)
今宮神社
音羽町九丁目に在る。祭神は天照大神、素戔嗚尊、伊弉册尊、譽田別尊、天兒屋根命、大國主命、少彦名命、大宮乃賣命である。
その創建は社伝に依れば、元禄年中(1688-1704年)五代将軍綱吉の生母桂昌院が、護國寺建立と共にその境内に奉祀したと言ふ。
明治初年、神佛混淆禁止に依り、同六年元田中八幡宮の跡なる現地へ遷座した。明治五年村社に列せられ、現在境内は三百餘坪、祭日は九月七日で、東・西青柳町、音羽一丁目乃至九丁目、櫻木町を氏子としてゐる。
■ 『小石川区史』(国立国会図書館)
稲荷神社(吹上)
大塚坂下町に在る。保食命を祭神とする。
俗に吹上稲荷と言はれ、其創建年代も由緒も不明であるが、江戸末期の切絵図に今の大塚窪町邊を吹上と記してあり、又『小石川志料』には、智香寺境内に吹上稲荷大明神のあった事が見えて居るから、それが此の神社の起りであらうと思はれる。後護國寺境内に移され、明治五年更に今の地に移つた。社格は無格社であるが、境内は約二百坪あり、祭典は九月二十二日。竹早町、窪町、大塚町、大塚上町、同仲町、同坂下町を氏子としてゐる。

「護國寺」/原典:松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[12],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836].国立国会図書館DC(保護期間満了)

「大塚護持院」/原典:松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[12],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836].国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』音羽絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ有楽町線「護国寺」駅で駅出口が山門前です。
振り返ると音羽通りは江戸川橋に向けてまっすぐに伸び、かつてはこのあたり門前町だったのかもしれません。
(『江戸名所図会』には、当山が京の清水寺を模したため門前の町を”音羽”と名付けたとあります。)
護国寺については見どころ満載すぎるので、さらっといきます。
素晴らしい山内なので、ぜひいちどお運びくださいませ。(と逃げる・・・(笑))
山内の伽藍配置については、↓の案内図をご覧くださいませ。



【写真 上(左)】 護国寺駅と仁王門
【写真 下(右)】 仁王門
仁王門前に交番を守衛所のように置くさまは、まさに名刹の風格。
仁王門は、切妻屋根桟本瓦葺の単層丹塗り三間一戸の八脚門です。
建立は元禄十年(1697年)造営の観音堂(本堂)よりやや時代が下るとみられていますが、徳川将軍家祈願寺の表門の役割を果たしただけあって、単層とはいえ軒高が高くかなりのスケール感。
本瓦葺、丸柱、丹塗りと、山門からしてすでに寺格の高さを見せつけています。
- 護国寺の 山門の朱の丸柱 強きものこそ 美しくあれ -
窪田空穂

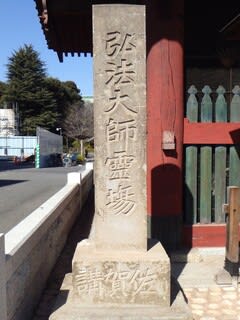
【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 札所碑

仁王門扁額
向かって右手に「大本山護國寺」の寺号標、左手には御府内霊場の札所標。
左右に「大本山護國寺」の提灯を掲げ、見上げには山号扁額を掲げています。
正面南側の両脇間に阿吽の金剛力士像、背面北側両脇間には二天像(右側増長天、左側広目天)が安置されています。


【写真 上(左)】 ご縁日の仁王門
【写真 下(右)】 ご縁日の掲示
山門をくぐると右手に宗務所。こちらは真言宗豊山派の大本山です。


【写真 上(左)】 惣門
【写真 下(右)】 惣門の扁額
仁王門の西側に惣門があり、こちらは本坊(旧護持院)の門かと思われます。
綱吉公と桂昌院の御成のために建築されたといい、冠木門をとりこんだ住宅門の造りです。
案内板によると、五万石以上の大名クラスの格式に相当する形式だそうです。
見上げに独特な字体の寺号扁額。
惣門の先に本坊(寺務所)、書院、桂昌殿(葬祭場)、内仏殿を置いています。
山内は北の大塚方面から伸びる武蔵野台地が音羽谷に降るところで、山門と本堂(観音堂)にかなりの高低差があります。


【写真 上(左)】 音羽富士
【写真 下(右)】 音羽富士山頂
本坊裏手の高みには富士浅間神社(音羽富士)が御遷座、一合目から合標が置かれ頂には石祠があります。


【写真 上(左)】 仁王門前から山内
【写真 下(右)】 縁日の参道
仁王門からはしばらく平坦な参道がつづき、ご縁日などこちらに屋台が並びます。


【写真 上(左)】 手水舎と階段
【写真 下(右)】 水盤
左右に手水舎を置いたところから、いよいよ急な参道階段がはじまります。
この手水舎の唐銅蓮葉手洗水盤は桂昌院の寄進で、元禄十年(1697年)江戸の鋳物師権名伊豫良寛の作と記されています。


【写真 上(左)】 階段
【写真 下(右)】 不老門

不老門扁額
ここで身心を清めてから登りはじめます。
すぐ上に不老門が聳え段数もさほどではないですが、なぜかかなりの登りでがあります。
浅草の辨天堂から観音堂に登る階段もそうですが、低平地から台地に登る参道階段は、段数以上に登りでがあるように感じます。
不老門は昭和13年月建立。京都の鞍馬寺の門を基本に設計されたといいます。
懸造り、入母屋造桟瓦葺身舎朱塗りで正面上部に唐破風を興し、扁額「不老」の二字は徳川家達公の筆によるもの。
懸造りなので構造は複雑ですが、桁行三間で中央一戸かと思います。


【写真 上(左)】 不老門からの本堂
【写真 下(右)】 地蔵尊と仁王尊
参道階段の傾斜が急なので、不老門を抜けるまでは本堂(観音堂)エリアは見えません。
不老門を抜けた左手に地蔵尊立像と仁王尊像、右手が大師堂参道です。

多宝塔
さらに数段登ると本堂(観音堂)エリアです。
参道左手の多宝塔は昭和13年の建立。石山寺の多宝塔(国宝)の模写で周囲に桜を配して春先は花見客で賑わいます。


【写真 上(左)】 円成庵
【写真 下(右)】 拝観謝絶の庵(茶席)
多宝塔手前には蘿装庵、円成庵、不昧軒、宗澄庵などの風情ある庵が点在しますが、参詣者は立ち入りできません。
不老門右手の三笠亭、仲麿堂、簑庵も同様のようです。
その上手の鐘楼は近くまで寄ることができます。
格高の袴腰付重層入母屋造で、江戸時代中期の建立とされます。
梵鐘は天和二年(1682年)寄進、銘文には桂昌院による観音堂建立の経緯が刻まれています。


【写真 上(左)】 鐘楼
【写真 下(右)】 釈迦如来坐像
鐘楼前、参道横には結跏趺坐される釈迦如来の青銅坐像。


【写真 上(左)】 月光殿
【写真 下(右)】 葵の御紋
本堂(観音堂)手前で参道を左に折れると正面が月光殿。
大津三井寺の塔頭・日光院の客殿を昭和3年に現在の場所に移築したもの。
桃山時代の建造で書院様式を伝える貴重な建物として国の重要文化財に指定されています。
附設の建物として草蕾庵、月窓軒、化生庵があるようです。
なお、山内の庵(茶席)は明治から昭和初期にかけて高橋箒庵翁が再興されたとの由。


【写真 上(左)】 多宝塔と月光殿
【写真 下(右)】 山内からビル群
月光殿前から多宝塔方面をのぞむと背景は折り重なるビル群で、護国寺が都心のビル街にオアシス的にあることがわかります。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 ご縁日の本堂
さて、いよいよ本堂(観音堂)です。
元禄十年(1697年)正月、観音堂新営の幕命があり、約半年余りで大造営を完成、同年八月落慶供養と伝わります。
元禄時代の建築工芸の粋を結集した大伽藍とされ、震災・戦災をしのいで江戸期の面影をいまに伝えています。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
桁行七間梁間七間の入母屋造瓦棒銅板葺でこちらも国の重要文化財です。
向拝は三間で、三間に渡って水引虹梁を置き、両端に獅子貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に板蟇股。
軒裏は朱塗りで手前二軒の垂木が目立ちます。
向拝柱には「本尊 如意輪観世音菩薩」の札が掛かっています。
扁額はないですが、羯磨金剛が刻まれた賽銭箱が存在感を放っています。


【写真 上(左)】 御本尊の札
【写真 下(右)】 賽銭箱
こちらの素晴らしいのは、本堂内にあげていただけるところです。
本堂向かって右手の扉が開くのでこちらから参内します。
入ると右手に授与所があるので御朱印帳をお預けします。
堂内はほどよい加減でうす暗く、厳粛な空気がただよっています。
正面が現・御本尊の六臂如意輪観世音菩薩像。
桂昌院の念持仏である唐物天然琥珀如意輪観世音菩薩像は以前に秘仏となり、現在御本尊として安置されているのがこちらの菩薩像のようです。
江戸三十三観音札所、東国花の寺霊場の札所本尊はこちらの観音様になります。
授与所の上には観音霊場札所板が掲げられていました。
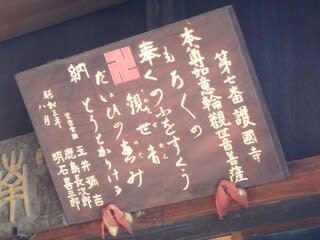

【写真 上(左)】 観音霊場札所板
【写真 下(右)】 観音霊場札所標
堀田正虎の母栄隆院を願主とし、元禄十三年(1700年)寄進され、御頭は恵心僧都の作で身体はこの折に新たに作られたといいます。
もろもろの くのうをすくう 観世音
大悲の恵み 尊うとかりける
なお、如意輪観世音菩薩については、→こちら(東京都区内の如意輪観音の御朱印)をご覧ください。
本堂内は撮影禁止で記憶も定かではありません。
向かって左手には地蔵尊など諸仏、右手には不動明王が御座と記憶しています。
本堂裏手左右が墓域で、本堂正面裏の霊廟は平成8年落慶、聖観世音菩薩像が奉安されています。


【写真 上(左)】 本堂裏手
【写真 下(右)】 閼伽水の井戸
本堂向かって斜め左手おくに傳法灌頂用閼伽水の井戸。
そちらのさらに左おくが薬師堂。
元禄四年(1691年)の建立で、かつての一切経堂を現在の位置に移築し、薬師堂として使用するもの。


【写真 上(左)】 薬師堂
【写真 下(右)】 薬師堂向拝
宝形造桟瓦葺、頂に宝珠を置いて流れ向拝のバランス感に優れた堂宇。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、中備に蟇股で、身舎側への繋ぎ虹梁は置いていません。
向拝正面桟唐戸、両脇に花頭窓を据えるなど禅宗様の手法をとりいれ、元禄期の遺構として価値ある建造物とされます。
こちらの堂宇本尊はこの地にあった蟹ヶ池より出現した薬師如来の霊像を胎内に収められるお薬師さまで、左右に十二神将の像を安置します。
こららの霊像は「江戸名所図会」で護持院の項に記載されているので、旧護持院系の御像とみられます。


【写真 上(左)】 忠霊堂
【写真 下(右)】 山内の梅
薬師堂のさらに左手おくには忠霊堂。
明治35年建立。日清戦争で戦死された軍人の遺骨を埋葬する堂宇で、唐金の多宝塔を建立し、その前に拝殿として建てられたのがこの忠霊堂とのことです。
入母屋造瓦葺平入りで、軒唐破風の大がかりな向拝とスクエアな虹梁を備える特徴ある建物です。
さて、御府内霊場巡拝のハイライト、大師堂です。
上で延べたとおり、大師堂への参道は不老門をくぐって右に折れたところから始まります。
参道入口に整った面立ちの六地蔵。
石敷の参道の正面が大師堂です。


【写真 上(左)】 大師堂参道
【写真 下(右)】 大師堂
元禄十四年(1701年)に再営された旧薬師堂を大正15年に大修理し現在の位置に移築して大師堂としたものです。


【写真 上(左)】 大師堂向拝
【写真 下(右)】 大師堂扁額
寄棟造桟瓦葺流れ向拝で身舎・柱ともに朱塗りです。
がっしりとした水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、中備に蟇股。
真言宗伽藍における大師堂の格式の高さと、中世的な伝統を重んじた貴重な建造物として区の指定建造物に指定されています。
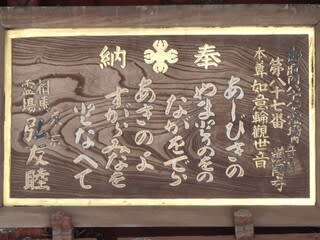

【写真 上(左)】 大師堂札所板
【写真 下(右)】 斜めからの大師堂向拝


【写真 上(左)】 磐座に御座すお大師さま
【写真 下(右)】 大師堂天水鉢
繋ぎ虹梁を置かずすっきりとした向拝。
正面桟唐戸のうえに「遍照金剛」の扁額とそのよこに御府内霊場の札所板、奉納額。
大師堂向かって左の磐座に御座すお大師さまと天水鉢の羯磨金剛が、御府内霊場札所感をひとしお盛り上げています。
堂前説明板には「高祖弘法大師、宗祖興教大師、派祖本覚大師の三尊が安置されている。」とあります。
こちらは本堂(観音堂)に比べて参拝者が少ないので、落ち着いて勤行をあげることができます。


【写真 上(左)】 一言地蔵尊
【写真 下(右)】 身代地蔵尊
大師堂向かって右手には一言地蔵尊のお堂。
願いを一言だけ成就いただけるという霊験あらたかなお地蔵さまです。
その左隣には身代地蔵尊が御座されています。
「さらっといきます。」といいながらやはりこれだけのボリュームになってしまいました(笑)
それだけ見どころの多い名刹ということでしょう。
御朱印は本堂(観音堂)内授与所にて拝受できます。
本堂内の拝観および御朱印授与は、昼の休憩時間を除いた9:00(10:00)〜12:00、13:00~15:00(16:00)で昼はお休みなので要注意です。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

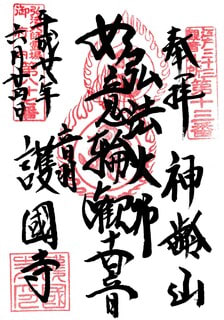
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に如意輪観世音菩薩のお種子「キリク」「本尊 阿彌陀如来」「弘法大師」の揮毫と三寶印。
右に「弘法大師霊場 御府内第八十七番」の札所印。
左に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
主印は「キリク」の御寶印の場合もあるようです。
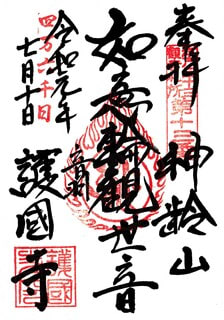
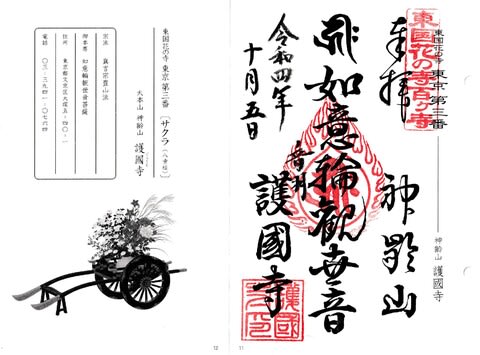
【写真 上(左)】 四万六千日の観音霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東国花の寺霊場の御朱印
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-29)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ 桜 - 中村舞子
■ キミトセカイ - 佳仙(歌ってみた)
■ Boogie-Woogie Lonesome High-Heel - 今井美樹
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-27
Vol.-26からのつづきです。
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第83番 放光山 千眼寺 蓮乗院
(れんじょういん)
新宿区若葉2-8-6
真言宗豊山派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第83番
第83番は四ッ谷・若葉の蓮乗院です。
第83番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに蓮乗院で、第83番札所は開創当初から四ッ谷南寺町の蓮乗院であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
蓮乗院の開闢起立の年代は不明ですが、開山鏡現は天正十八年(1590年)に遷化されているので、徳川家康公江戸入府以前の創立とみられています。
当初の在所は麹町七丁目でしたが慶長十六年(1611年)当地(四ッ谷南寺町)に移転と伝わります。
湯島根生院末の新義真言宗。
本堂に弘法大師御作と伝わる阿弥陀如来銅立像、不動尊木坐像、聖天尊を奉安し、地蔵堂には地蔵尊六躰と弘法大師唐銅座像を奉安と伝わります。
畧縁起によると、こちらの阿弥陀如来像は弘智法印が高野山に参籠の際、善光寺ノ如来を模して鋳された霊像があるとの弘法大師の夢告を受け、大和國橘寺の地中から得られた弘法大師御作の霊像といいます。
弘智法印はこの霊像を持佛とされましたが諸国巡行の際、霞ヶ関に至ったところでこの霊像が俄に重くなりました。
弘智法印はこの地が霊像を奉安する場と悟られ、堂宇を建てて霊像を安置しました。
この霊像は不思議にも眉間から白光を放たれたため、群衆は参詣群集し、霊像を「放光千眼佛」と呼んで崇めたといいます。
これよりこの堂宇を放光山と号し、千眼寺とも号したといいます。
また、弘智法印はもとは下総國の蓮花寺に住されたことから、蓮乗院と号したとも。
「善光寺生身ノ如来ニ異ナラス雖有大師御作ナリトテ貴賎弥々信心之袖ヲ●カヘシケリ」(『寺社書上』/蓮乗院中興沙門記)
弘智法印とは、江戸時代初期に演じられた古浄瑠璃『弘知法印御伝記』の主役で即身仏となられた弘知法印との所縁があるかもしれませんが、よくわかりません。
(この浄瑠璃のなかで、弘知法印は弘法大師(空海)の弟子となり「弘知」の名を授かったとされます。)
蓮乗院の当初の在所は麹町七丁目。
畧縁起で阿弥陀如来の堂宇が建てられたという霞ヶ関は、千代田区Webによると、「(霞ヶ関の由来は)古代までさかのぼり、日本武尊が蝦夷の襲撃に備えて、武蔵国に置いた関所『霞ヶ関』から名付けられたといいます。」とあるので、相当に古い地名のようです。
霞ヶ関と麹町はさほど離れていないので、阿弥陀如来畧縁起と当山在所はほぼ符合するといえましょうか。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
八十三番
四ッ谷南寺町
放光山 千眼寺 蓮乗院
湯島根生院末 新義
本尊:阿弥陀如来 不動明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [44] 四谷寺社書上 参』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.116』
四ッ谷南寺町
湯島根生院末 新義真言宗
放光山千眼寺蓮乗院
起立年代不相知候
元寺地麹町七丁目●-●御用地に召上 慶長十六年(1611年)右替地として当所拝領仕候
開山 鏡現 天正十八年(1590年)遷化
但し開闢起立之年代相不知申候
中興開山 海● 延享五年(1748年)寂
本堂
本尊 阿弥陀如来銅立像 弘法大師御作(畧縁起あり)
不動尊木坐像
聖天
地蔵堂
地蔵尊六躰
弘法大師唐銅座像
■ 『四谷区史 [本編]』(国立国会図書館)
放光山千眼寺蓮乗院は湯島根生院末の新義真言宗、四谷南寺町今の寺町にある。境内拝領地三百七十二坪、起立の時代は明ならず。慶長十六年(1611年)麹町七丁目から此地に移転したと伝へられる。但し開山鏡現は天正十八年(1590年)に遷化したから、徳川氏入國前の創立であるのは略推察することか出来る。府内八十八箇所中八十三番の札所として知られた。

「蓮乗院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』四ツ谷絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはJR・メトロ丸ノ内線「四ッ谷」駅から徒歩約7分。
南隣は第39番の真成院、西隣は第18番の愛染院という御府内霊場札所の密集エリアです。
現在の地図と『江戸切絵図』をくらべてみると、多くの寺院の位置関係がそのままで、このエリアが江戸期の寺町のたたずまいを色濃く残していることがわかります。

観音坂
「鮫ヶ橋谷丁」と呼ばれた土地の高低差の大きいところで、蓮乗院も「観音坂」の途中に位置します。
第39番真成院の並びに、こぢんまりとした参道入口。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 御寶号碑
門前に御寶院碑で、側面が御府内霊場札所碑になっています。
門柱に院号標。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 院号標


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 観音菩薩像
山内もコンパクトですが、緑が多くしっとりとした風情が感じられます。
参道脇に御座す観音様もどこかやさしげな面差しです。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 向拝上部
【写真 下(右)】 扁額
正面の本堂は、おそらく入母屋造で瓦葺流れ向拝、ゆったりとした曲線を描く軒唐破風と大がかりな兎毛通が個性的な堂宇です。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
水引虹梁に山号扁額を掲げています。
御朱印は本堂向かって右の庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
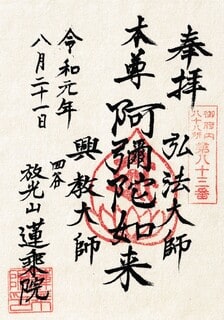
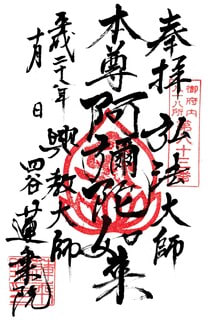
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 阿彌陀如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫と阿弥陀如来のお種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「御府内八十八所第八十三番」の札所印。
左に山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第84番 五大山 不動寺 明王院
(みょうおういん)
港区三田4-3-9
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第84番
第84番はふたたび三田に戻って明王院です。
第84番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに明王院となっており、第84番札所は御府内霊場開創当初から三田寺町の明王院であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
明王院の創建年代は不明ですが、長禄年間(1457-1460年)武蔵国長江(今の八丁堀)に移転、寛永十二年(1635年)に当地(三田寺町)に移ったといいます。
開山開基は不詳ですが、中興開山は賢榮法印(元禄十六年(1703年)寂)と伝わります。
当山は「厄除大師」と称する坐像を奉安し、人々の尊崇を集めたといいます。
こちらの弘法大師像は、嵯峨天皇が四二歳の厄年を迎えたとき、弘法大師が厄除けを祈願されみずから天皇等身大の像を刻まれたという伝承があります。
源頼朝公により相模国に迎えられ、縁あって当山に奉安と伝わります。
御本尊の五大明王は智證大師・弘法大師の御相作といい、寺寶として弘法大師御筆の日出愛染明王画像、鎮守稲荷社の御神躰翁は弘法大師御作と伝わり、弘法大師御筆の「鼠心経」を蔵するなど、ことに弘法大師とのご縁のふかい寺院です。
もと三田臺裏町にあった泉福寺は、本寺へ合併されたといいます。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
八十四番
芝三田中寺町
五大山 不動寺 明王院
音羽護国寺末 新義
本尊:勅賜 厄除弘法大師 一刀三礼御真作 嵯峨天皇御当身
■ 『寺社書上 [12] 三田寺社書上 弐』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.49』
芝三田中寺町
大塚護國寺末
五大山不動寺明王院
起立年代相不知申候
寛永十二年(1635年)八町堀から当地に替地
中興開山 法印賢榮 寛永二年(1625年)卒
元禄九年常憲院様御代金子拝領仕護國寺末
本堂
本尊 五大明王 中尊坐像左右立像 智證大師 弘法大師御相作
内棟
厄除弘法大師木坐像 御自作(縁起書あり)
弘法大師厨子入坐像
寺寶
不動幷二童子画像 役行者筆
日出愛染明王画像 弘法大師筆 右ハ頼朝公御寄附
鎮守稲荷社 神躰翁 弘法大師作ト云
■ 『芝區誌』(デジタル版 港区のあゆみ)
明王院 三田豊岡町二十三番地
新義派真言宗護國寺末、五大山不動寺。もと今の八丁堀にあつたが、寛永十二年(1635年)此地に移つた。開山不詳。中興の開山は賢榮である。厄除大師と称する坐像があつて、八十八所札所の第八十四番である。もと三田臺裏町にあつた泉福寺は本寺へ合併された。
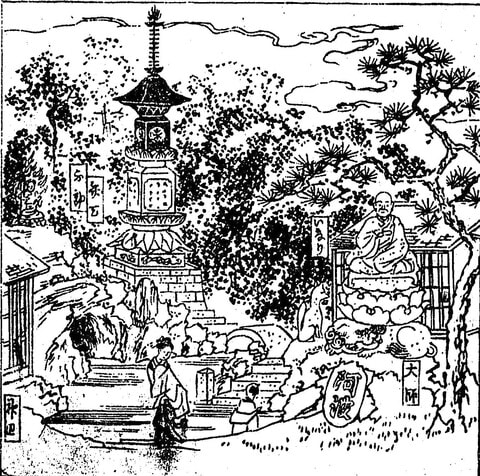
「明王院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』芝高輪辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは都営三田線「三田」駅で徒歩約15分。
三田寺町の御府内霊場札所は国道1号に面したビルタイプの寺院が多いですが、こちらは一本裏手に引き込み、昔ながらの寺院のたたずまいをみせています。
位置的には国道1号沿いの林泉寺の南側にあたります。
三田は面白い地形で国道1号が谷筋を走り、海寄りの南側に聖坂の尾根筋が走ります。
なので、このエリアは北傾の坂道で、明王院も南向きながらどことなくしっとり落ち着いた風情があります。
山門は切妻屋根桟瓦葺、脇門付きの薬医門で院号扁額を掲げています。
門の手前には古色を帯びた「厄除弘法大師」の石碑。


【写真 上(左)】 門前
【写真 下(右)】 「厄除弘法大師」の石碑


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 山内
参道左手のお像は修行大師像とも思われますが、確信がもてません。
参道のたしか左手に堂宇があり、弘法大師像、不動明王像と、どこかはかなげな地蔵尊像が御座します。


【写真 上(左)】 参道左手のお像
【写真 下(右)】 堂宇
御府内霊場札所碑も確認できました。


【写真 上(左)】 弘法大師像
【写真 下(右)】 札所碑
本堂前には弘法大師御遠忌の供養塔、佛塔などが並び、「弘法大師のお寺」の叙情ゆたかです。


【写真 上(左)】 佛塔
【写真 下(右)】 本堂
本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝、水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に本蟇股。

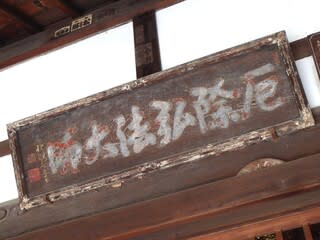
【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額


【写真 上(左)】 札所板
【写真 下(右)】 不動明王御真言
正面格子扉の向拝の見上げには「厄除弘法大師」の扁額と御府内霊場の札所板を掲げています。
向拝には不動明王御真言(小咒)も掲げられていて、まことに至れり尽くせりです。
都心の真ん中にこのように心やすまるお寺さまが残っていることも、東京の大きな魅力だと思います。
御朱印は本堂向かって右手の、これまた風情あふれる庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
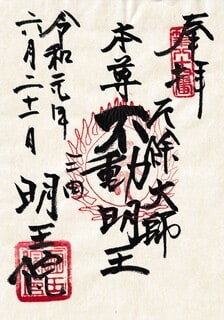
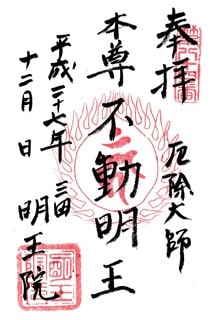
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊不動明王」「厄除大師」の揮毫、不動明王のお種子「カン/カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。右に「第八十四番」の札所印。
左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第85番 大悲山 観音寺
(かんのんじ)
公式Web
新宿区高田馬場3-37-26
真言宗(単立)
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
司元別当:(戸塚村)神明社
他札所:豊島八十八ヶ所霊場第85番、近世江戸三十三観音霊場第15番
第85番は高田馬場の観音寺です。
第52番は早稲田の観音寺です。
御府内霊場には「観音寺」を号する札所寺院が3つ(第42番蓮葉山 観音寺(谷中)、第52番慈雲山 観音寺(早稲田)、第85番大悲山 観音寺(高田馬場))あり、前2者をそれぞれ谷中観音寺、早稲田観音寺と呼んで区別されます。
第85番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに泉福院で、第85番札所は御府内霊場開創当初から江戸末期まで三田の泉福院で、『御府内八十八ケ所道しるべ』の札所変更資料には泉福院から観音寺への変更が記されていないので、第85番札所は明治初期以降にかけて高田馬場の観音寺に変更とみられます。
公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから両山の縁起・沿革を追ってみます。
【観音寺】
観音寺は、江戸時代のはじめにかんこう坊という僧により開山されました。
かんこう坊は中村氏の出自で、子孫はこの地の名主でした。
『ルートガイド』には「寛永年間(1624-1645年)頃の創建」とあります。
大悲山蓮花院観音寺を号し、大塚護国寺末の新義真言宗でした。
御本尊に聖観世音菩薩を奉安し、山内には薬師堂もあったといいます。
幾度の火災で寺伝類の多くを失っているようですが、寺勢は保ち、御府内八十八ヵ所霊場第85番、豊島八十八ヵ所霊場第85番の札所となっています。
現在の本堂は昭和60年に建立された現代建築です。
-------------------------
【泉福院】
泉福院は三田臺裏町にあった新義真言宗寺院。
愛宕前真福寺末で醫王山泉福院を号しました。
起立の年代、開山開基などは伝わっておりませんが、『寺社書上』『御府内寺社備考』に掲載されています。
「江戸町巡り」様Webには「三田台裏町」は「現町名:港区三田四丁目8番20~36号、9番10~13号、高輪一丁目5番18号の辺り」とあり、「三田台裏町」には曹洞宗正山寺、日蓮宗薬王寺もあったようです。
『江戸切絵図』には薬王寺の隣に「泉福寺」という寺院がみえるので、こちらが泉福院かと思われます。
本堂に奉安の御本尊、薬師如来木座像は弘法大師の御作と伝わり、十二神将木立像を従えていたようです。
本堂に釈迦如来、阿弥陀如来、千手観音、不動明王、弘法大師厨子入木座像、興教大師厨子入木座像を奉安し、御府内霊場札所の要件を満たしていました。
鎮守社として淡島大明神が御鎮座され、こちらの社殿には弘法大師座像石佛が安していたと記されています。
泉福院が御府内霊場の札所を外れた理由は不明ですが、『芝區誌』の明王院の項に「もと三田臺裏町にあつた泉福寺は本寺(明王院、御府内霊場第84番)へ合併された。」とあるので、泉福院は明王院に合併されたとみられます。
泉福院は愛宕真福寺末、観音寺は大塚護国寺末(現在は単立)で本寺が異なり、三田から高田馬場は距離もあるので、札所承継の経緯はよくわかりません。
ただし、観音寺は豊島八十八ヶ所霊場(明治40年開創)札所となっており、その所縁で御府内霊場札所も承継されたのかもしれません。
-------------------------
【史料】
【観音寺】
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
(戸塚村)観音寺
新義真言宗、大塚護国寺末 大悲山蓮花院ト号ス 本尊正観音 開基ハカンコウ坊ト云人ニテ 俗姓中村氏 故アリテ当所ニ来リ 草庵ヲ営ミ 遂ニ一寺トナセシト云 子孫外記ハ寛永ノ頃断絶ス 其屋敷跡ハ今 高木伊勢守抱地ノ内ニテ 東大久保村名主理右衛門モ其一族ナリト云
薬師堂
(戸塚村)神明社 観音寺持
【泉福院】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
八十五番
三田臺裏町
醫王山 泉福院
愛宕山真福寺末 新義真言宗
本尊:薬師如来 不動明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [11] 三田寺社書上 壱』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.92』
三田臺裏町
愛宕前真福寺末
醫王山泉福院
起立之年代開山開基相不知申候
本堂
本尊 薬師如来木座像 弘法大師作
十二神将木立像
釈迦如来 阿弥陀如来 千手観音 不動明王
弘法大師 厨子入木座像
興教大師 厨子入木座像
鎮守社
淡島大明神 神躰幣
弘法大師座像石佛
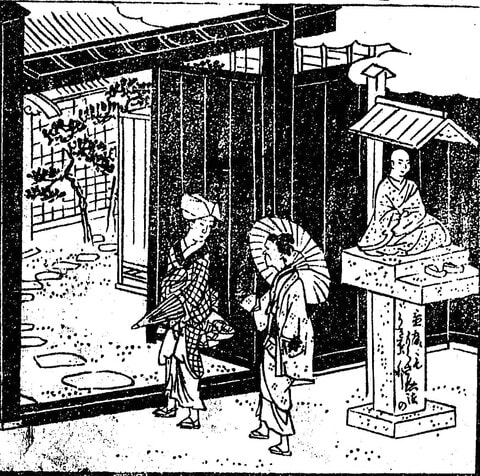
「泉福院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
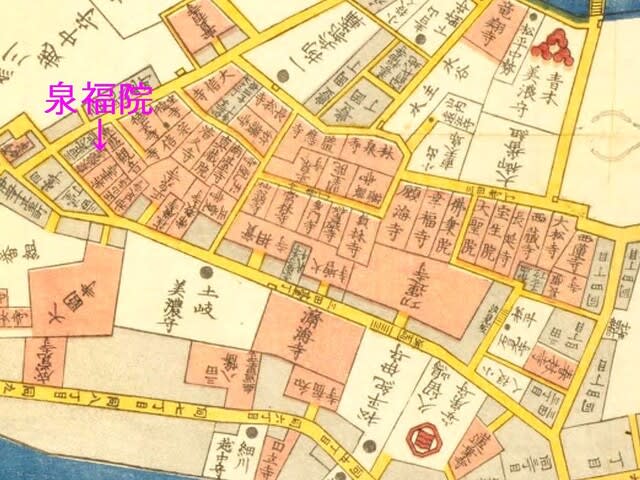
原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』芝高輪辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは「高田馬場」駅で徒歩約15分。あるいはメトロ東西線「落合」駅の方が近いかもしれません。
神田川沿いの低地であたりは民家が密集していますが、そのなかにかなり広い山内を構えています。
早稲田通り沿いに寺号標が置かれ、そこからまっすぐに参道が伸びているので、かつてはもっと広大な敷地をもっていたのかも。


【写真 上(左)】 早稲田通り沿いの寺号標
【写真 下(右)】 参道
門前から山門と本堂がみえます。
特徴のある緑色が目立つモダンでシャープな外観。


【写真 上(左)】 門前
【写真 下(右)】 観音像


【写真 上(左)】 地蔵尊像
【写真 下(右)】 札所碑
門前には観世音菩薩像、地蔵尊像、弘法大師霊場札所碑が並びます。
山門は二脚門で、門柱に山号標と寺号標を掲げています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 寺号標
手水舎のつくりもなかなかモダンです。


【写真 上(左)】 手水舎
【写真 下(右)】 本堂
すぐ正面が本堂で、御内陣は2階です。
本堂内に入っていいのかわからなかったので、先に本堂向かって右手の寺務所にお伺いすると、館内での参拝可能とのことでした。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
本堂は陸屋根の近代建築で、各所に格子が使われているのでどこか厳めしい雰囲気です。
2階の見上げに「慈光」の扁額を掲げています。
本堂内はどこか公共施設か学校のような感じで、講堂のような御内陣に数躰の聖観世音菩薩像と弘法大師像が奉安されています。
御府内霊場札所のなかではなかなか異色の本堂ですが、すぐまぢかで御尊像を拝せるのはありがたいことです。
なお、山内には吉川英治先生の文筆仲間であった呼潮に聞いた四国遍路の体験談にもとづき執筆した「呼潮へんろ」にちなむ塚があります。
御朱印は本堂向かって右手の寺務所で拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
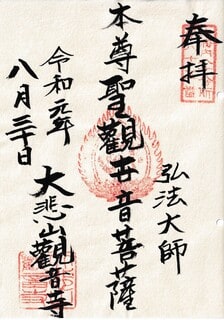
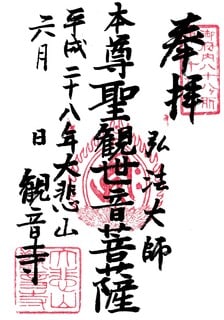
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 聖観世音菩薩」「弘法大師」の揮毫と御寶印(蓮華座+火焔宝珠)のお種子は「キリク」にみえます。
右に「御府内八十八ヶ所第八十五番」の札所印。
左に山号寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
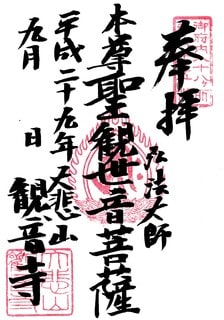
■ 豊島霊場の御朱印
■ 第86番 金剛山 弥勒寺 常泉院
(じょうせんいん)
文京区春日1-9-3
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第86番
第86番は春日の常泉院です。
第86番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに常泉院で、第86番札所は開創当初から小石川七軒町の常泉院であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
常泉院は、寛永四年(1627年)以前に卓意によって開山という彌勒寺末の新義真言宗寺院です。
水戸家の帰依を受けての創建とも伝わります。
本堂内に御本尊として両部大日如来二躰を奉安。
本堂には、中尊・弥勒菩薩木座像、弘法大師木座像、興教大師木座像、不動明王、愛染明王、地蔵菩薩、子安観世音菩薩、閻魔王木座像(運慶作)、石地蔵尊など多彩な尊格を安置されていたことが記されています。
本堂内の弘法大師像は、御府内霊場の拝所となっていたことも記されています。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
八十六番
小石川七軒町
金剛山 弥勒寺 常泉院
本所彌勒寺末 新義
本尊:両部大日如来 不動明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [64] 小石川寺社書上 一』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.106』
小石川不唱小名
本所彌勒寺末 新義真言宗
金剛山弥勒寺常泉院
起立年代不詳
本堂
本尊 両部大日如来二躰
中尊 弥勒菩薩木座像
弘法大師木座像 御府内八十八ヶ所之内 第八十六番之札所
興教大師木座像
不動明王木座像
愛染明王木座像
地蔵菩薩木座像
子安観世音木座像
閻魔王木座像 運慶作
石地蔵尊
■ 『小石川区史/第七章P.822』(文京区立図書館)
金剛山彌勒寺常泉院。真言宗豊山派、彌勒寺(本所林町)末。本尊両部大日如来。当寺の創立年代は明らかでないが、『御府内沿革図書』によれば、延寶(1673-1681年)の頃既に存在した事が明らかであり、又寺伝によれば現本堂は寛永四年(1627年)の建立といふから、それよりも以前に建立されたものと思はれる。『文政書上』に依れば、当寺境内は拝領地六百余坪であった。現に府内八十八ヶ所大師の内、第八十六番の札所に当り、日々の参詣者が多い。
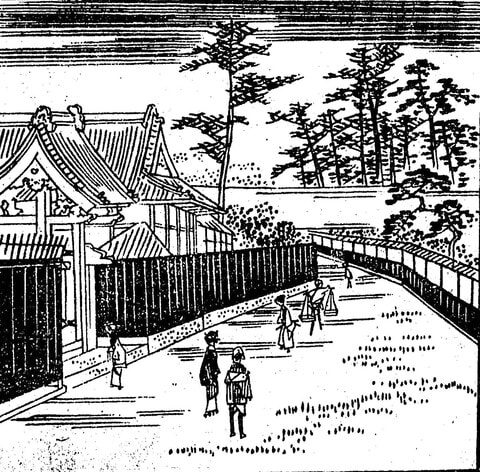
「常泉院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)
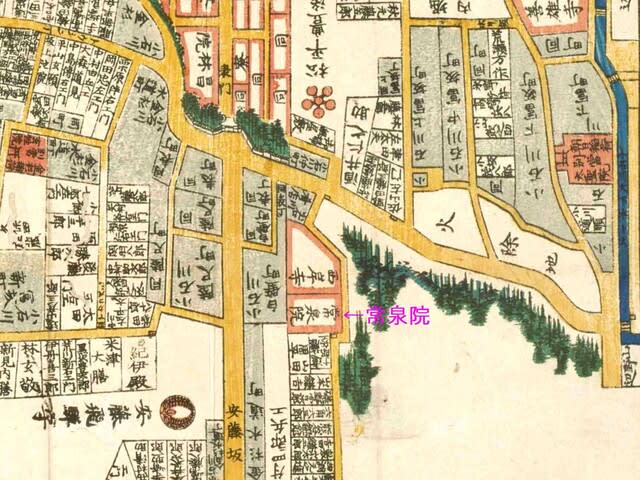
原典:戸松昌訓著『〔尾張屋板切絵図 18〕』東都小石川絵図,尾張屋清七,嘉永7[1854]/安政[4][1857]改.東京都立中央図書館TOKYOアーカイブ(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ丸ノ内線・南北線「後楽園」駅で徒歩約3分と至便。
御朱印ファンには牛天神北野神社のすぐ北側といった方がわかりやすいでしょうか。
春日の高台にあるこの辺りは、交通至便な立地とは思えないしっとりとした落ち着きが感じられます。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 御府内霊場札所標
山門はないですが、緑が多く雰囲気のある山内です。
山内入口に御府内霊場の札所標。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 聖天堂


【写真 上(左)】 弘法大師像
【写真 下(右)】 弘法大師碑
参道右手手前に奥まって聖天堂。
左手には高野山開創一千年を記念して建立された弘法大師像、弘法大師碑、御寶号碑、御府内霊場札所碑、石佛群がところ狭しとならびます。


【写真 上(左)】 御寶号碑
【写真 下(右)】 御府内霊場札所碑


【写真 上(左)】 石佛群
【写真 下(右)】 小島烏水の碑
登山家・随筆家で、日本山岳会初代会長でもあった小島烏水(こじま うすい、1873-1948年)永住之地の碑もあります。


【写真 上(左)】 本堂?
【写真 下(右)】 向拝?
こちらの堂宇構成はえらく複雑で、どちらが本堂かよくわかりません。
参道右手の建物の2階に向拝らしきものがあり、正面の渡り廊下をくぐった先にも向拝を備えた建物があります。
どちらも勤行をあげさせていただきました。


【写真 上(左)】 庫裡
【写真 下(右)】 昭和初めの山門(山内掲示)
御朱印は参道左手の庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
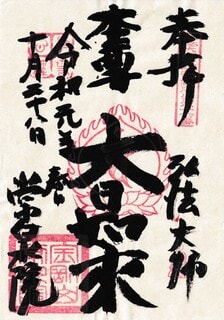
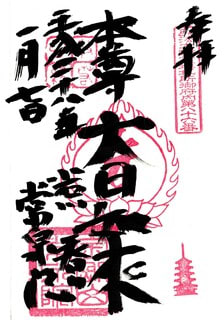
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 大日如来」「弘法大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「弘法大師霊場札所御府内第八十六番」の札所印。
左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-28)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ 桜 - 中村舞子
■ キミトセカイ - 佳仙(歌ってみた)
■ Boogie-Woogie Lonesome High-Heel - 今井美樹
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第83番 放光山 千眼寺 蓮乗院
(れんじょういん)
新宿区若葉2-8-6
真言宗豊山派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第83番
第83番は四ッ谷・若葉の蓮乗院です。
第83番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに蓮乗院で、第83番札所は開創当初から四ッ谷南寺町の蓮乗院であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
蓮乗院の開闢起立の年代は不明ですが、開山鏡現は天正十八年(1590年)に遷化されているので、徳川家康公江戸入府以前の創立とみられています。
当初の在所は麹町七丁目でしたが慶長十六年(1611年)当地(四ッ谷南寺町)に移転と伝わります。
湯島根生院末の新義真言宗。
本堂に弘法大師御作と伝わる阿弥陀如来銅立像、不動尊木坐像、聖天尊を奉安し、地蔵堂には地蔵尊六躰と弘法大師唐銅座像を奉安と伝わります。
畧縁起によると、こちらの阿弥陀如来像は弘智法印が高野山に参籠の際、善光寺ノ如来を模して鋳された霊像があるとの弘法大師の夢告を受け、大和國橘寺の地中から得られた弘法大師御作の霊像といいます。
弘智法印はこの霊像を持佛とされましたが諸国巡行の際、霞ヶ関に至ったところでこの霊像が俄に重くなりました。
弘智法印はこの地が霊像を奉安する場と悟られ、堂宇を建てて霊像を安置しました。
この霊像は不思議にも眉間から白光を放たれたため、群衆は参詣群集し、霊像を「放光千眼佛」と呼んで崇めたといいます。
これよりこの堂宇を放光山と号し、千眼寺とも号したといいます。
また、弘智法印はもとは下総國の蓮花寺に住されたことから、蓮乗院と号したとも。
「善光寺生身ノ如来ニ異ナラス雖有大師御作ナリトテ貴賎弥々信心之袖ヲ●カヘシケリ」(『寺社書上』/蓮乗院中興沙門記)
弘智法印とは、江戸時代初期に演じられた古浄瑠璃『弘知法印御伝記』の主役で即身仏となられた弘知法印との所縁があるかもしれませんが、よくわかりません。
(この浄瑠璃のなかで、弘知法印は弘法大師(空海)の弟子となり「弘知」の名を授かったとされます。)
蓮乗院の当初の在所は麹町七丁目。
畧縁起で阿弥陀如来の堂宇が建てられたという霞ヶ関は、千代田区Webによると、「(霞ヶ関の由来は)古代までさかのぼり、日本武尊が蝦夷の襲撃に備えて、武蔵国に置いた関所『霞ヶ関』から名付けられたといいます。」とあるので、相当に古い地名のようです。
霞ヶ関と麹町はさほど離れていないので、阿弥陀如来畧縁起と当山在所はほぼ符合するといえましょうか。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
八十三番
四ッ谷南寺町
放光山 千眼寺 蓮乗院
湯島根生院末 新義
本尊:阿弥陀如来 不動明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [44] 四谷寺社書上 参』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.116』
四ッ谷南寺町
湯島根生院末 新義真言宗
放光山千眼寺蓮乗院
起立年代不相知候
元寺地麹町七丁目●-●御用地に召上 慶長十六年(1611年)右替地として当所拝領仕候
開山 鏡現 天正十八年(1590年)遷化
但し開闢起立之年代相不知申候
中興開山 海● 延享五年(1748年)寂
本堂
本尊 阿弥陀如来銅立像 弘法大師御作(畧縁起あり)
不動尊木坐像
聖天
地蔵堂
地蔵尊六躰
弘法大師唐銅座像
■ 『四谷区史 [本編]』(国立国会図書館)
放光山千眼寺蓮乗院は湯島根生院末の新義真言宗、四谷南寺町今の寺町にある。境内拝領地三百七十二坪、起立の時代は明ならず。慶長十六年(1611年)麹町七丁目から此地に移転したと伝へられる。但し開山鏡現は天正十八年(1590年)に遷化したから、徳川氏入國前の創立であるのは略推察することか出来る。府内八十八箇所中八十三番の札所として知られた。

「蓮乗院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』四ツ谷絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはJR・メトロ丸ノ内線「四ッ谷」駅から徒歩約7分。
南隣は第39番の真成院、西隣は第18番の愛染院という御府内霊場札所の密集エリアです。
現在の地図と『江戸切絵図』をくらべてみると、多くの寺院の位置関係がそのままで、このエリアが江戸期の寺町のたたずまいを色濃く残していることがわかります。

観音坂
「鮫ヶ橋谷丁」と呼ばれた土地の高低差の大きいところで、蓮乗院も「観音坂」の途中に位置します。
第39番真成院の並びに、こぢんまりとした参道入口。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 御寶号碑
門前に御寶院碑で、側面が御府内霊場札所碑になっています。
門柱に院号標。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 院号標


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 観音菩薩像
山内もコンパクトですが、緑が多くしっとりとした風情が感じられます。
参道脇に御座す観音様もどこかやさしげな面差しです。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 向拝上部
【写真 下(右)】 扁額
正面の本堂は、おそらく入母屋造で瓦葺流れ向拝、ゆったりとした曲線を描く軒唐破風と大がかりな兎毛通が個性的な堂宇です。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
水引虹梁に山号扁額を掲げています。
御朱印は本堂向かって右の庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
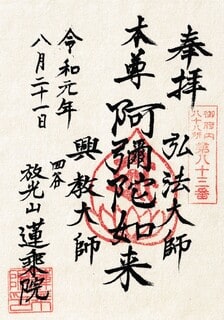
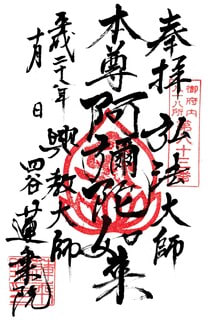
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 阿彌陀如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫と阿弥陀如来のお種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「御府内八十八所第八十三番」の札所印。
左に山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第84番 五大山 不動寺 明王院
(みょうおういん)
港区三田4-3-9
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第84番
第84番はふたたび三田に戻って明王院です。
第84番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに明王院となっており、第84番札所は御府内霊場開創当初から三田寺町の明王院であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
明王院の創建年代は不明ですが、長禄年間(1457-1460年)武蔵国長江(今の八丁堀)に移転、寛永十二年(1635年)に当地(三田寺町)に移ったといいます。
開山開基は不詳ですが、中興開山は賢榮法印(元禄十六年(1703年)寂)と伝わります。
当山は「厄除大師」と称する坐像を奉安し、人々の尊崇を集めたといいます。
こちらの弘法大師像は、嵯峨天皇が四二歳の厄年を迎えたとき、弘法大師が厄除けを祈願されみずから天皇等身大の像を刻まれたという伝承があります。
源頼朝公により相模国に迎えられ、縁あって当山に奉安と伝わります。
御本尊の五大明王は智證大師・弘法大師の御相作といい、寺寶として弘法大師御筆の日出愛染明王画像、鎮守稲荷社の御神躰翁は弘法大師御作と伝わり、弘法大師御筆の「鼠心経」を蔵するなど、ことに弘法大師とのご縁のふかい寺院です。
もと三田臺裏町にあった泉福寺は、本寺へ合併されたといいます。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
八十四番
芝三田中寺町
五大山 不動寺 明王院
音羽護国寺末 新義
本尊:勅賜 厄除弘法大師 一刀三礼御真作 嵯峨天皇御当身
■ 『寺社書上 [12] 三田寺社書上 弐』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.49』
芝三田中寺町
大塚護國寺末
五大山不動寺明王院
起立年代相不知申候
寛永十二年(1635年)八町堀から当地に替地
中興開山 法印賢榮 寛永二年(1625年)卒
元禄九年常憲院様御代金子拝領仕護國寺末
本堂
本尊 五大明王 中尊坐像左右立像 智證大師 弘法大師御相作
内棟
厄除弘法大師木坐像 御自作(縁起書あり)
弘法大師厨子入坐像
寺寶
不動幷二童子画像 役行者筆
日出愛染明王画像 弘法大師筆 右ハ頼朝公御寄附
鎮守稲荷社 神躰翁 弘法大師作ト云
■ 『芝區誌』(デジタル版 港区のあゆみ)
明王院 三田豊岡町二十三番地
新義派真言宗護國寺末、五大山不動寺。もと今の八丁堀にあつたが、寛永十二年(1635年)此地に移つた。開山不詳。中興の開山は賢榮である。厄除大師と称する坐像があつて、八十八所札所の第八十四番である。もと三田臺裏町にあつた泉福寺は本寺へ合併された。
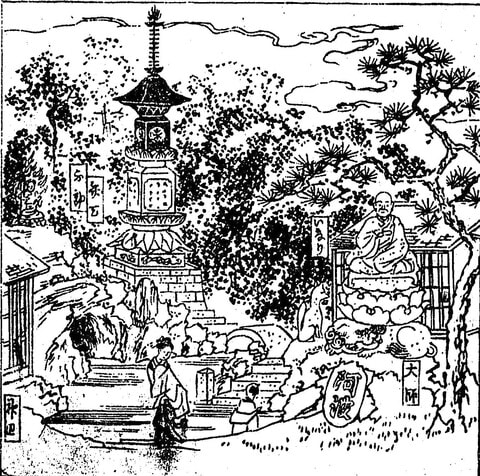
「明王院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』芝高輪辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは都営三田線「三田」駅で徒歩約15分。
三田寺町の御府内霊場札所は国道1号に面したビルタイプの寺院が多いですが、こちらは一本裏手に引き込み、昔ながらの寺院のたたずまいをみせています。
位置的には国道1号沿いの林泉寺の南側にあたります。
三田は面白い地形で国道1号が谷筋を走り、海寄りの南側に聖坂の尾根筋が走ります。
なので、このエリアは北傾の坂道で、明王院も南向きながらどことなくしっとり落ち着いた風情があります。
山門は切妻屋根桟瓦葺、脇門付きの薬医門で院号扁額を掲げています。
門の手前には古色を帯びた「厄除弘法大師」の石碑。


【写真 上(左)】 門前
【写真 下(右)】 「厄除弘法大師」の石碑


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 山内
参道左手のお像は修行大師像とも思われますが、確信がもてません。
参道のたしか左手に堂宇があり、弘法大師像、不動明王像と、どこかはかなげな地蔵尊像が御座します。


【写真 上(左)】 参道左手のお像
【写真 下(右)】 堂宇
御府内霊場札所碑も確認できました。


【写真 上(左)】 弘法大師像
【写真 下(右)】 札所碑
本堂前には弘法大師御遠忌の供養塔、佛塔などが並び、「弘法大師のお寺」の叙情ゆたかです。


【写真 上(左)】 佛塔
【写真 下(右)】 本堂
本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝、水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に本蟇股。

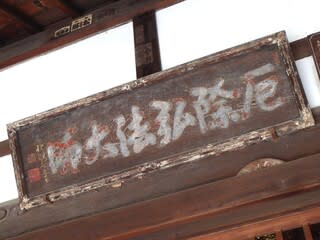
【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額


【写真 上(左)】 札所板
【写真 下(右)】 不動明王御真言
正面格子扉の向拝の見上げには「厄除弘法大師」の扁額と御府内霊場の札所板を掲げています。
向拝には不動明王御真言(小咒)も掲げられていて、まことに至れり尽くせりです。
都心の真ん中にこのように心やすまるお寺さまが残っていることも、東京の大きな魅力だと思います。
御朱印は本堂向かって右手の、これまた風情あふれる庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
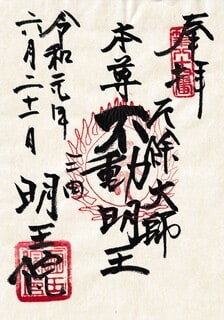
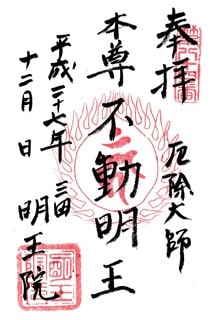
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊不動明王」「厄除大師」の揮毫、不動明王のお種子「カン/カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。右に「第八十四番」の札所印。
左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第85番 大悲山 観音寺
(かんのんじ)
公式Web
新宿区高田馬場3-37-26
真言宗(単立)
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
司元別当:(戸塚村)神明社
他札所:豊島八十八ヶ所霊場第85番、近世江戸三十三観音霊場第15番
第85番は高田馬場の観音寺です。
第52番は早稲田の観音寺です。
御府内霊場には「観音寺」を号する札所寺院が3つ(第42番蓮葉山 観音寺(谷中)、第52番慈雲山 観音寺(早稲田)、第85番大悲山 観音寺(高田馬場))あり、前2者をそれぞれ谷中観音寺、早稲田観音寺と呼んで区別されます。
第85番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに泉福院で、第85番札所は御府内霊場開創当初から江戸末期まで三田の泉福院で、『御府内八十八ケ所道しるべ』の札所変更資料には泉福院から観音寺への変更が記されていないので、第85番札所は明治初期以降にかけて高田馬場の観音寺に変更とみられます。
公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから両山の縁起・沿革を追ってみます。
【観音寺】
観音寺は、江戸時代のはじめにかんこう坊という僧により開山されました。
かんこう坊は中村氏の出自で、子孫はこの地の名主でした。
『ルートガイド』には「寛永年間(1624-1645年)頃の創建」とあります。
大悲山蓮花院観音寺を号し、大塚護国寺末の新義真言宗でした。
御本尊に聖観世音菩薩を奉安し、山内には薬師堂もあったといいます。
幾度の火災で寺伝類の多くを失っているようですが、寺勢は保ち、御府内八十八ヵ所霊場第85番、豊島八十八ヵ所霊場第85番の札所となっています。
現在の本堂は昭和60年に建立された現代建築です。
-------------------------
【泉福院】
泉福院は三田臺裏町にあった新義真言宗寺院。
愛宕前真福寺末で醫王山泉福院を号しました。
起立の年代、開山開基などは伝わっておりませんが、『寺社書上』『御府内寺社備考』に掲載されています。
「江戸町巡り」様Webには「三田台裏町」は「現町名:港区三田四丁目8番20~36号、9番10~13号、高輪一丁目5番18号の辺り」とあり、「三田台裏町」には曹洞宗正山寺、日蓮宗薬王寺もあったようです。
『江戸切絵図』には薬王寺の隣に「泉福寺」という寺院がみえるので、こちらが泉福院かと思われます。
本堂に奉安の御本尊、薬師如来木座像は弘法大師の御作と伝わり、十二神将木立像を従えていたようです。
本堂に釈迦如来、阿弥陀如来、千手観音、不動明王、弘法大師厨子入木座像、興教大師厨子入木座像を奉安し、御府内霊場札所の要件を満たしていました。
鎮守社として淡島大明神が御鎮座され、こちらの社殿には弘法大師座像石佛が安していたと記されています。
泉福院が御府内霊場の札所を外れた理由は不明ですが、『芝區誌』の明王院の項に「もと三田臺裏町にあつた泉福寺は本寺(明王院、御府内霊場第84番)へ合併された。」とあるので、泉福院は明王院に合併されたとみられます。
泉福院は愛宕真福寺末、観音寺は大塚護国寺末(現在は単立)で本寺が異なり、三田から高田馬場は距離もあるので、札所承継の経緯はよくわかりません。
ただし、観音寺は豊島八十八ヶ所霊場(明治40年開創)札所となっており、その所縁で御府内霊場札所も承継されたのかもしれません。
-------------------------
【史料】
【観音寺】
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
(戸塚村)観音寺
新義真言宗、大塚護国寺末 大悲山蓮花院ト号ス 本尊正観音 開基ハカンコウ坊ト云人ニテ 俗姓中村氏 故アリテ当所ニ来リ 草庵ヲ営ミ 遂ニ一寺トナセシト云 子孫外記ハ寛永ノ頃断絶ス 其屋敷跡ハ今 高木伊勢守抱地ノ内ニテ 東大久保村名主理右衛門モ其一族ナリト云
薬師堂
(戸塚村)神明社 観音寺持
【泉福院】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
八十五番
三田臺裏町
醫王山 泉福院
愛宕山真福寺末 新義真言宗
本尊:薬師如来 不動明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [11] 三田寺社書上 壱』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.92』
三田臺裏町
愛宕前真福寺末
醫王山泉福院
起立之年代開山開基相不知申候
本堂
本尊 薬師如来木座像 弘法大師作
十二神将木立像
釈迦如来 阿弥陀如来 千手観音 不動明王
弘法大師 厨子入木座像
興教大師 厨子入木座像
鎮守社
淡島大明神 神躰幣
弘法大師座像石佛
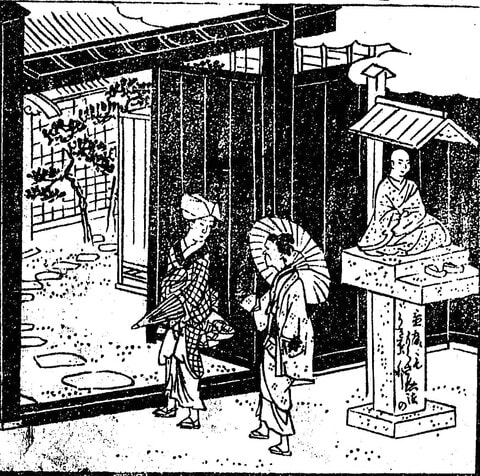
「泉福院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
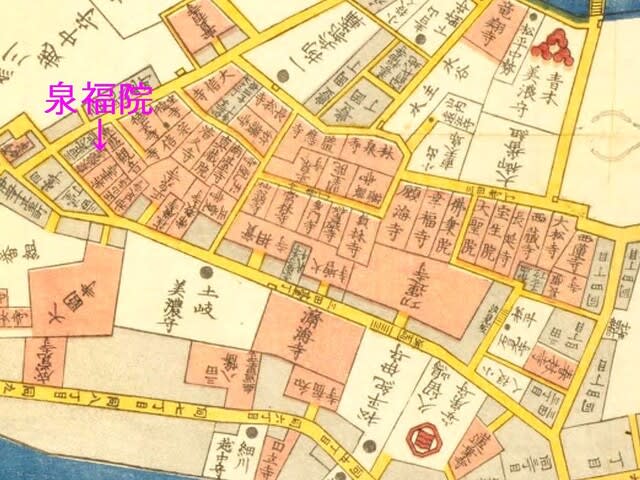
原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』芝高輪辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは「高田馬場」駅で徒歩約15分。あるいはメトロ東西線「落合」駅の方が近いかもしれません。
神田川沿いの低地であたりは民家が密集していますが、そのなかにかなり広い山内を構えています。
早稲田通り沿いに寺号標が置かれ、そこからまっすぐに参道が伸びているので、かつてはもっと広大な敷地をもっていたのかも。


【写真 上(左)】 早稲田通り沿いの寺号標
【写真 下(右)】 参道
門前から山門と本堂がみえます。
特徴のある緑色が目立つモダンでシャープな外観。


【写真 上(左)】 門前
【写真 下(右)】 観音像


【写真 上(左)】 地蔵尊像
【写真 下(右)】 札所碑
門前には観世音菩薩像、地蔵尊像、弘法大師霊場札所碑が並びます。
山門は二脚門で、門柱に山号標と寺号標を掲げています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 寺号標
手水舎のつくりもなかなかモダンです。


【写真 上(左)】 手水舎
【写真 下(右)】 本堂
すぐ正面が本堂で、御内陣は2階です。
本堂内に入っていいのかわからなかったので、先に本堂向かって右手の寺務所にお伺いすると、館内での参拝可能とのことでした。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
本堂は陸屋根の近代建築で、各所に格子が使われているのでどこか厳めしい雰囲気です。
2階の見上げに「慈光」の扁額を掲げています。
本堂内はどこか公共施設か学校のような感じで、講堂のような御内陣に数躰の聖観世音菩薩像と弘法大師像が奉安されています。
御府内霊場札所のなかではなかなか異色の本堂ですが、すぐまぢかで御尊像を拝せるのはありがたいことです。
なお、山内には吉川英治先生の文筆仲間であった呼潮に聞いた四国遍路の体験談にもとづき執筆した「呼潮へんろ」にちなむ塚があります。
御朱印は本堂向かって右手の寺務所で拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
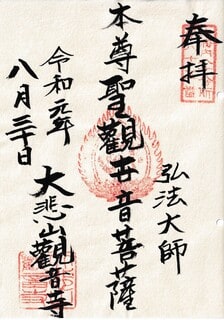
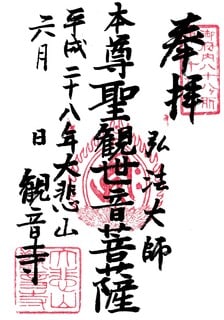
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 聖観世音菩薩」「弘法大師」の揮毫と御寶印(蓮華座+火焔宝珠)のお種子は「キリク」にみえます。
右に「御府内八十八ヶ所第八十五番」の札所印。
左に山号寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
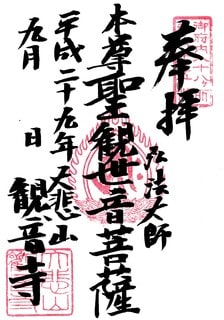
■ 豊島霊場の御朱印
■ 第86番 金剛山 弥勒寺 常泉院
(じょうせんいん)
文京区春日1-9-3
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第86番
第86番は春日の常泉院です。
第86番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに常泉院で、第86番札所は開創当初から小石川七軒町の常泉院であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
常泉院は、寛永四年(1627年)以前に卓意によって開山という彌勒寺末の新義真言宗寺院です。
水戸家の帰依を受けての創建とも伝わります。
本堂内に御本尊として両部大日如来二躰を奉安。
本堂には、中尊・弥勒菩薩木座像、弘法大師木座像、興教大師木座像、不動明王、愛染明王、地蔵菩薩、子安観世音菩薩、閻魔王木座像(運慶作)、石地蔵尊など多彩な尊格を安置されていたことが記されています。
本堂内の弘法大師像は、御府内霊場の拝所となっていたことも記されています。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
八十六番
小石川七軒町
金剛山 弥勒寺 常泉院
本所彌勒寺末 新義
本尊:両部大日如来 不動明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [64] 小石川寺社書上 一』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.106』
小石川不唱小名
本所彌勒寺末 新義真言宗
金剛山弥勒寺常泉院
起立年代不詳
本堂
本尊 両部大日如来二躰
中尊 弥勒菩薩木座像
弘法大師木座像 御府内八十八ヶ所之内 第八十六番之札所
興教大師木座像
不動明王木座像
愛染明王木座像
地蔵菩薩木座像
子安観世音木座像
閻魔王木座像 運慶作
石地蔵尊
■ 『小石川区史/第七章P.822』(文京区立図書館)
金剛山彌勒寺常泉院。真言宗豊山派、彌勒寺(本所林町)末。本尊両部大日如来。当寺の創立年代は明らかでないが、『御府内沿革図書』によれば、延寶(1673-1681年)の頃既に存在した事が明らかであり、又寺伝によれば現本堂は寛永四年(1627年)の建立といふから、それよりも以前に建立されたものと思はれる。『文政書上』に依れば、当寺境内は拝領地六百余坪であった。現に府内八十八ヶ所大師の内、第八十六番の札所に当り、日々の参詣者が多い。
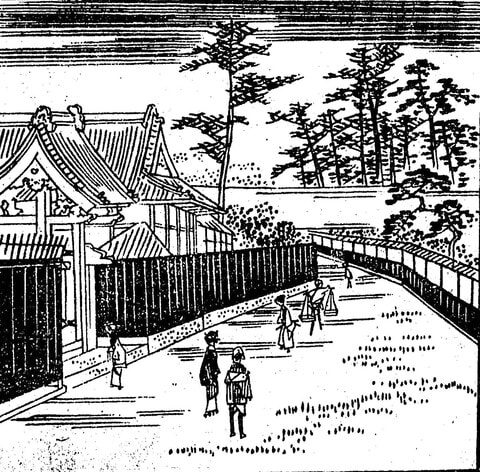
「常泉院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)
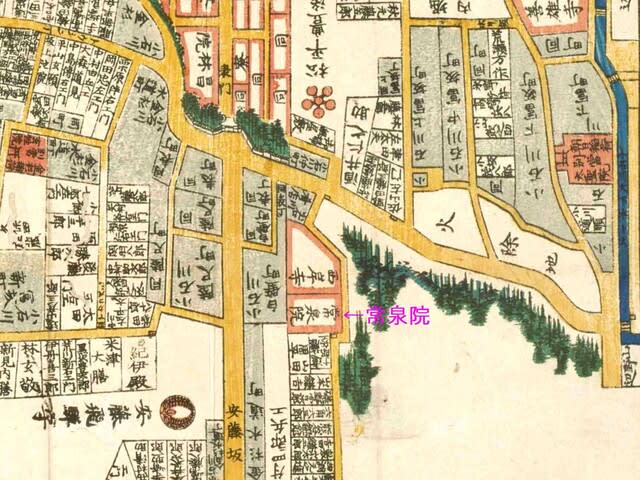
原典:戸松昌訓著『〔尾張屋板切絵図 18〕』東都小石川絵図,尾張屋清七,嘉永7[1854]/安政[4][1857]改.東京都立中央図書館TOKYOアーカイブ(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ丸ノ内線・南北線「後楽園」駅で徒歩約3分と至便。
御朱印ファンには牛天神北野神社のすぐ北側といった方がわかりやすいでしょうか。
春日の高台にあるこの辺りは、交通至便な立地とは思えないしっとりとした落ち着きが感じられます。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 御府内霊場札所標
山門はないですが、緑が多く雰囲気のある山内です。
山内入口に御府内霊場の札所標。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 聖天堂


【写真 上(左)】 弘法大師像
【写真 下(右)】 弘法大師碑
参道右手手前に奥まって聖天堂。
左手には高野山開創一千年を記念して建立された弘法大師像、弘法大師碑、御寶号碑、御府内霊場札所碑、石佛群がところ狭しとならびます。


【写真 上(左)】 御寶号碑
【写真 下(右)】 御府内霊場札所碑


【写真 上(左)】 石佛群
【写真 下(右)】 小島烏水の碑
登山家・随筆家で、日本山岳会初代会長でもあった小島烏水(こじま うすい、1873-1948年)永住之地の碑もあります。


【写真 上(左)】 本堂?
【写真 下(右)】 向拝?
こちらの堂宇構成はえらく複雑で、どちらが本堂かよくわかりません。
参道右手の建物の2階に向拝らしきものがあり、正面の渡り廊下をくぐった先にも向拝を備えた建物があります。
どちらも勤行をあげさせていただきました。


【写真 上(左)】 庫裡
【写真 下(右)】 昭和初めの山門(山内掲示)
御朱印は参道左手の庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
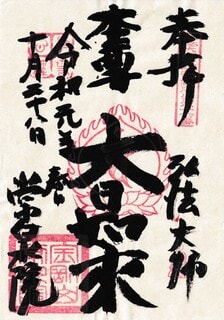
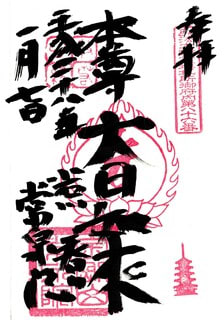
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 大日如来」「弘法大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「弘法大師霊場札所御府内第八十六番」の札所印。
左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-28)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ 桜 - 中村舞子
■ キミトセカイ - 佳仙(歌ってみた)
■ Boogie-Woogie Lonesome High-Heel - 今井美樹
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-26
Vol.-25からのつづきです。
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第78番 摩尼山 寶光寺 成就院
(じょうじゅいん)
公式Web
台東区東上野3-32-15
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第78番、奥の細道関東路三十三所霊場第5番
第78番は東上野の成就院です。
御府内霊場には「成就院」を号する札所寺院がふたつ(第43番(元浅草)、第78番(東上野))あり、前者を百観音成就院、後者を田中成就院と呼んで区別しているようです。
第78番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに成就院で、第78番札所は開創当初から下谷田中の成就院であったとみられます。
公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
成就院は、慶長十六年(1611年)、開山・鏡傳法印が神田北寺町に寺地を与えられ開創しました。
『ルートガイド』には、鏡傳法印は徳川家康公に従い江戸に入ったとあります。
慶安元年(1648年)、下谷の現在地を拝領し移転しています。
中興開山と伝わる法印鏡伝は寛文二年(1662年)卒なので、おそらく下谷への移転で功をなされたのかと思います。
当時の下谷は江戸の町外れで、まわりは田んぼだったので「田中(の)成就院」と呼ばれ、いまでも通称として残っています。
浅草の成就院(百観音成就院)との識別のためにも、この通称は必須だったのでは。
■ 『寺社書上』、『御府内寺社備考』には、本所彌勒寺末の新義真言宗とあります。
御本尊には大日如来木坐像、本堂内に弘法大師木坐像、輿教大師木坐像を安し、御府内霊場札所の要件を満たしていました。
「不動尊木立像 弘法大師作」という見逃せない記述もあります。
本堂とは別に地蔵堂があり、地蔵尊の石仏を安していました。
「稲荷社」とあるのは鎮守だったのかもしれません。
公式Webによると、地蔵堂・稲荷社は、いまは伝えられていないとのこと。
また、安政の大地震や関東大震災などの火災で堂宇を消失し、明治の廃仏毀釈の波を受けて衰微してしまったことなどが記されています。
『江戸切絵図』をみるとかなりの敷地をもつ大寺院だったようですが、関東大震災後、境内地が大きく削られてしまったとのことです。
それでも公式Webには寺伝等が詳細に記載され、名刹の矜持が伝わってきます。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
七十八番
下谷田中
摩尼山 宝光院 成就院
本所二ツ目彌勒寺末 新義
本尊:大日如来 浪切不動明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [116] 下谷寺社書上 弐』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.96』
下谷田中
本所彌勒寺末 新義真言宗
摩尼山宝光寺成就院
拙寺起立之儀ハ相知不申候ヘ共 往古慶長十六年(1611年)神田北寺町三十七年往居 慶安元年(1648年)中只今之地面拝領仕引移申候
中興開山 法印鏡伝 寛文二年(1662年)卒
当寺往昔田の中にありし故 田中成就院と唱ヘならはしたるよし 惣ての書上に下谷中成就院と書せり されは田中の唱ハ当寺に限たる事なり 浅草に同宗にて同名の寺あり 是をハ百観音成就院と俗に呼へり
本尊 大日如来木坐像
弘法大師木坐像 輿教大師木坐像
不動尊木立像 弘法大師作
地蔵堂 地蔵尊石像
稲荷社

「成就院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)
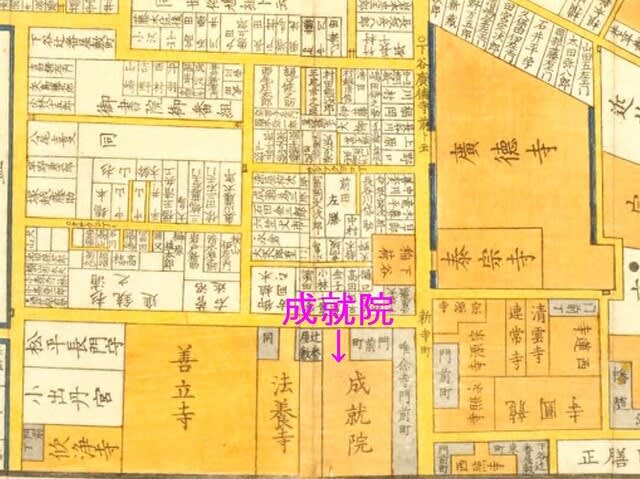
原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』下谷絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ銀座線「稲荷町」駅で徒歩約1分と至近、元浅草~寿とつづく、御府内霊場札所密集エリアの入口にあります。
「稲荷町」駅から南に伸びる清洲橋通り沿いにあります。
山門は門柱で、間口はさほど広くはないですが、敷地はそれなりの広さがあります。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 山内入口
門柱に院号標、門柱前に御府内霊場札所碑。


【写真 上(左)】 御府内霊場札所碑
【写真 下(右)】 緑濃い山内


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
下町とは思えない緑濃い山内。
参道正面が庫裡で、屋根に千鳥破風を配してこ洒落たつくり。
その右よこが本堂で、入母屋造瓦葺流れ向拝、向拝に大がかりな唐破風を起こし、庫裡の千鳥破風と意匠的に呼応しています。


【写真 上(左)】 見事な彫刻
【写真 下(右)】 本堂扁額
水引虹梁は上下二連。両端に見返り(阿吽の)獅子と雲形の木鼻、頭貫上に連三ッ斗以上を端正に連ねるテクニカルな斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に玉持龍の彫刻。
木鼻の見返り獅子、手挟の波紋、中備の玉持龍ともに見事な仕上がりで、こちらは「昭和の名工」といわれた金子光清師の作とのこと。
すこぶる雰囲気のある向拝で、上部には山号扁額を掲げています。
本堂の須弥壇には御本尊大日如来、左手に観世音菩薩、右手に阿弥陀如来の大日三尊を奉安。
左端に吉祥天、右端には多聞天、不動明王を安置しているそうです。


【写真 上(左)】 修行大師像
【写真 下(右)】 修行大師像と大師堂
本堂前には修行大師像、その裏手には大師堂があります。
御府内霊場で大師堂が残っている札所は意外に少ないのですが、こちらはしっかりとした大師堂を護持されています。


【写真 上(左)】 大師堂
【写真 下(右)】 大師堂向拝


【写真 上(左)】 大師堂扁額
【写真 下(右)】 御府内霊場札所板
公式Webによると、『鬼平犯科帳』の一幕に成就院が登場するため、たまに鬼平ファンが寺を訪れるそうで、池波正太郎先生はごく近所に住んでいたことがあるとの由。
そのほか、観音さまをお祀りする「与楽」とご遺骨をお納めする「抜苦」の二つのお堂で成り立つ「称観堂」。
東日本大震災の大津波でなぎ倒された岩手県陸前高田市の高田松原の被災松を材として造立された「やすらぎ聖観音像」も御座されます。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

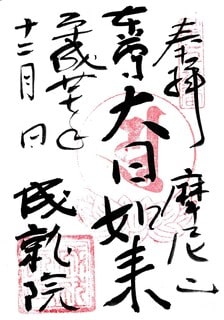
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 大日如来」「弘法大師」の揮毫と弘法大師のお種子「ユ」の御寶印(蓮華座+宝珠)、右に「第七十八番」の札所印。
左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
御府内霊場の御朱印で、本尊大日如来で「ユ」の御寶印が捺されている例はめずらしいです。
■ 第79番 清水山 専教院
(せんきょういん)
文京区小日向3-6-10
真言宗豊山派
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第79番
第79番は小日向の専教院です。
第79番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに専教院で、第79番札所は開創当初から小日向の専教院であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
専教院は寛文五年(1665年)ないし延宝九年(1681)の創建で、開山は良法法印。
中興は法印尊椄(文化十年(1813年)寂)と伝わります。
天明(1781-1789年)の頃、四國八十八ヶ所第七十九番、讃岐國西ノ庄崇徳山天王寺の札所を写し、御府内八十八ヶ所の内七十九番札所となり、以降参詣人を集めています。
本堂内に御本尊として地蔵菩薩木立像を奉安。
両脇士に如意輪観世音菩薩、聖観世音菩薩を安するといういささか変わった尊格配置です。
厨子入の弘法大師木像は、御本尊とともに御府内霊場の拝所となっていました。
さらに十二童子を従えた辨財天も霊場札所の拝所とされていたようです。
文政(1818-1830年)の頃には境内は三百三十八坪ほどもあったといいますが、いまは住宅?の1室に収まっています。
それでも御府内霊場第79番の札所を堅持しておられるのはありがたいことです。
灌頂寺の寺号については記されている資料が少ないですが、正式な号では入るのかもしれません。(清水山 灌頂寺 専教院)
専教院については史料類がすくなく、これ以上掘り下げられませんでした。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
七十九番
小日向臺町
清水山 専教院
中野村宝仙寺末 新義
本尊:地蔵菩薩 弁才天 弘法大師
■ 『寺社書上 [26] 小日向寺社書上 弐』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.126』
小日向臺町
中野村宝仙寺末 新義真言宗
清水山専教院
起立年月日相知不申候
開山 相知不申候
開基 相知不申候
中興 法印尊椄 文化十年(1813年)寂
本堂
本尊 地蔵菩薩木佛立像 両脇士 如意輪木佛立像 聖観音木佛立像
弘法大師木像厨子入 八十八ヶ所内七十九番之札所
辨財天 十二童子
江府八十八観音の内第七拾九番 号ハ讃州崇徳天皇

「専教院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:戸松昌訓著『〔尾張屋板切絵図 18〕』東都小石川絵図,尾張屋清七,嘉永7[1854]/安政[4][1857]改.東京都立中央図書館TOKYOアーカイブ(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅ないし有楽町線「江戸川橋」駅でいずれも徒歩約10分。
小日向あたりは狭くて入り組んだ路地が多く、アプローチはなかなかやっかいです。
「茗荷谷」駅からだと拓殖大学を回り込むかたちとなりわかりにくいです。
駅から大日坂を登って突き当たりを右折して到達する「江戸川橋」駅ルートの方が、登り坂となりますがおそらくわかりやすいかと。


【写真 上(左)】 外観(2016.5)
【写真 下(右)】 石仏群(2016.5)


【写真 上(左)】 百万遍の碑(2016.5)
【写真 下(右)】 扁額(2016.5)
2016年に参拝したときは3階建の集合住宅のような外観で、本堂は2階でしたが、2019年参拝時には建て替えられていて、シックな2階建の建物の1階が本堂となっていました。


【写真 上(左)】 外観(2019.10)
【写真 下(右)】 エントランス(2019.10)
ご在院の場合は、室内の本堂にあげていただける可能性があります。
こういうシチュエーションでは、御真言だけでなく読経のひとつもあげないとどうにも手持ち無沙汰になるので、やはり御府内霊場巡拝には数珠と勤行式は携帯した方がベターかと思います。


【写真 上(左)】 向拝(2019.10)
【写真 下(右)】 扁額(2019.10)


【写真 上(左)】 札所碑(2019.10)
【写真 下(右)】 百万遍の碑と石仏群(2019.10)
本堂前には御府内霊場札所碑、石仏群が並び、御府内霊場札所寺院であることを示しています。
ひときわ目立つ梵字碑は、明治維新に廃仏毀釈に対し仏教復興を主張し、戒律運動の普及に努められた名僧・雲照律師の百万遍の碑とのことです。(『ルートガイド』)
御朱印は堂内(室内)にて拝受しました。
なお、ご不在時は専用集印帳用紙との差し替え授与となる模様なので、通常の書置御朱印はいただけないかもしれません。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

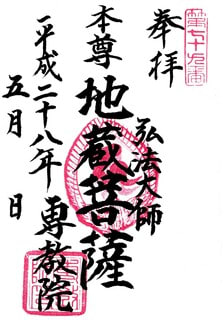
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 地蔵菩薩」「弘法大師」の揮毫と地蔵菩薩のお種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「第七十九番」の札所印。
左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第80番 太元山 宇賀院 長延寺
(ちょうえんじ)
港区三田4-1-29
真言宗豊山派
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第80番
第80番は再度三田に戻って長延寺です。
第80番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに長延寺となっており、第80番札所は御府内霊場開創当初から三田寺町の長延寺であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
長延寺の開山は不明ですが、往古は数寄屋町あたりにあり、慶長六年(1601年)八丁堀に移り、寛永十二年(1635年)現在地(三田下寺町)に転じたといいます。
中興開山は覺順法印(元禄十六年(1703年)寂)と伝わります。
大塚護持院末の新義真言宗。
御本尊の地蔵菩薩木座像は菅原道真公の御作と伝わります。
本堂に弘法大師木座像、興教大師木座像、胎蔵界大日如来木座像、不動明王木立像、十一面観音木立像、大黒天木立像などを安していました。
御本尊は大日如来。
本堂内に弘法大師木座像、興教大師木座像、三尊阿弥陀如来木佛立像を奉安と伝わります。
『ルートガイド』によると、本堂には漆喰の鏝絵『不動明王霊夢』と『俵藤太』があり、作者である伊豆長八の高弟、今泉善吉の墓も当山にあるようです。
長延寺も史料類が少なく、この程度しか掘り下げられませんでした。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
八十番
芝三田寺町
太元山 宇賀院 長延寺
大塚護持院末 新義
本尊:地蔵菩薩 弘法大師 興教大師
■ 『寺社書上 [13] 三田寺社書上 参』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.69』
三田下寺町
大塚護持院末 新義真言宗
太元山宇賀院長延寺
開闢起立之年暦 開山開基等之儀相知不申候
開山大僧都者 寛永三年(1626年)遷化(『御府内寺社備考』)
古に数寄屋町に寺地●るゝ処 慶長十六年(1611年)右寺地より八町堀に代地拝領仕
寛永十二年(1635年)当地より当所(三田下寺町)に替地拝領仕候
中興開山 法印覚順 元禄十六年(1703年)寂
本堂
本尊 地蔵菩薩木座像 菅原道真卿作ト云
弘法大師木座像
興教大師同前(木座像)
胎蔵界大日如来木座像
不動明王木立像
十一面観音木立像
大黒天木立像
地蔵尊石佛
■ 『芝區誌』(デジタル版 港区のあゆみ)
長延寺 三田北寺町十三番地
新義真言宗の末寺で、太元山宇賀院と号する。創建年月不詳。往古数寄屋町邊にあり、慶長六年(1601年)八丁堀に移り、寛永十二年(1635年)此地に転じた。中興開山覺順は元禄十六年(1703年)十二月入寂した。府内八十八ヶ所札所の八十番である。

「長延寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』芝高輪辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは都営三田線「三田」駅で徒歩約10分。
国道1号に面したマンション内の寺院です。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 寺号標


【写真 上(左)】 参道入口の案内板
【写真 下(右)】 門扉
国道1号沿いから参道入口で、塀に寺号標と寺院・札所案内板が掲げられています。
その先が鉄の門扉でここにも寺号標が掲げられています。


【写真 上(左)】 門扉の寺号標
【写真 下(右)】 手前からの本堂
正面右手が本堂、左手が寺務所です。
本堂手前には御府内霊場札所碑。


【写真 上(左)】 札所碑
【写真 下(右)】 御寶号碑


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝上部
本堂は半地下的なつくりで、向拝見上げに山号扁額、弘法大師の扁額、御府内霊場札所板が掲げられています。
古色を帯びた御寶号碑も建ち、マンション内寺院ながら御府内霊場札所を示す事物が豊富な札所です。


【写真 上(左)】 山号扁額
【写真 下(右)】 弘法大師の扁額


【写真 上(左)】 札所板
【写真 下(右)】 御真言
本堂内には地蔵菩薩立像が御座され、地蔵菩薩の御真言と光明真言が掲げられていました。
御朱印は寺務所にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「地蔵菩薩」「弘法大師」の揮毫、地蔵菩薩のお種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と三寶印。右に「御府内第八十番」の札所印。
左に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第81番 医王山 光蔵院
(こうぞういん)
港区赤坂7-6-68
真言宗智山派
御本尊:弘法大師
札所本尊:弘法大師
司元別当:
他札所:
第81番は赤坂の光蔵院です。
第81番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに真藏院となっており、第81番札所は御府内霊場開創当初から江戸期を通じて三田寺町の真藏院であったとみられます。
光蔵院、真藏院について、光蔵院掲出の由来書、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
【光蔵院】
光蔵院は、寛永年代(1624-1644年)に西久保飯倉町一丁目(現・港区麻布台一丁目)に創立といい、芝愛宕前真福寺末寺の新義真言宗寺院です。
御本尊は薬師如来。
毘沙門天、弘法大師木座像、不動明王、愛染明王、歓喜天尊、稲荷小社一宇と石佛地蔵を安していました。
享保年間(1716-1736年)の頃から、川崎大師河原平間寺(金剛山平原寺金乗密院)が江戸の御旅所とし、弘法大師を御本尊として安置され(飯倉)厄除け大師として庶民の参詣が多かったといいます。
第23番札所の薬研堀不動院が川崎大師東京別院となったのは明治25年ですから、江戸期の光蔵院は御旅所ながら江戸別院的な役割を果たしていたのかもしれません。
その後御府内霊場第81番の札所となり、大正10年本堂を改築したものの、昭和20年5月戦災に遭って焼失しました。
昭和37年5月、御本尊に弘法大師を安置し飯倉の地で再建を果たしています。
その後飯倉は繁華地に変貌したため、現在地の赤坂に遷られ昭和63年3月に落成慶讃式法要を挙行、以降、赤坂の地で御府内霊場巡拝者を迎えています。
なお、現時点で光蔵院は『江戸切絵図』で発見できておりません。
【真藏院】
真藏院は、当初数寄屋橋に寺地を拝領して開創といい、寺地が御用地となったため慶長十六年(1611年)八丁堀に移転、こちらも御用地となったため寛永十二年(1635年)当所(三田寺町)に寺地を得て移転といいます。
開基の泉尊法印は寛永三年(1626年)卒と伝わります。
御本尊は胎蔵界大日如来。
弘法大師木座像、興教大師同前を安して御府内霊場の要件を満たしていました。
興教大師の御筆と伝わる不動尊、細川越中守家から寄附の不動尊(辨慶筆)も奉安していたようです。
山内に稲荷社を擁し、不動明王、愛染明王、十一面観世音菩薩を堂内に奉安と記されています。
明治初頭編纂の『御府内八十八ケ所道しるべ』の札所異動資料に真藏院から光蔵院への異動の記載がないので、光蔵院への札所承継はそれ以降とみられます。
別当寺の性格が強くない真藏院が廃寺となった経緯は不明ですが、真藏院、光蔵院ともに愛宕前真福寺末寺の新義真言宗寺院。
光蔵院は(飯倉)厄除け大師として庶民の参詣が多かったといいますから、もとより弘法大師霊場札所の資格は有していたともみられ、この札所承継は自然な流れだったのかもしれません。
-------------------------
【史料】
【光蔵院】
■ 『寺社書上 [62] 飯倉寺社書上』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.90』
西久保飯倉町一丁目
醫王山光蔵院
愛宕前真福寺末 新義真言宗
起立開山開基相知不申候
本堂
本尊 薬師如来木座像
毘沙門天木立像
弘法大師木座像
不動明王木座像
愛染明王木座像
歓喜天
稲荷小社一宇
石佛地蔵
【真藏院】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
八十一番
芝三田三軒寺町
朝光山 南峯寺 真藏院
愛宕山真福寺末 新義
本尊:金剛界大日如来 不動明王 弘法大師
■ 『御府内寺社備考P.93』
三田寺町
愛宕前真福寺末 新義真言宗
朝光山南峯寺真藏院
開闢之年代相知不申候
●●数寄屋橋に寺地拝領仕候 ●御用地と相成 慶長十六年(1611年)八丁堀に替地 是又●御用地と相成 寛永十二年(1635年)当所を替地ニ
開基 泉尊 寛永三年(1626年)卒
中興開山 宥●
本堂
本尊 胎蔵界大日如来木座像 通途作
弘法大師木座像 通途作
興教大師同前(木座像)
胎蔵界大日如来木座像
地蔵尊唐銅立像 通途作
不動尊 興教大師筆ト云
不動尊 辨慶筆 右ハ細川越中守殿●寄附
不動尊 妙沢筆
稲荷社
神躰不知
不動木坐像 通途作
愛染 同
十一面観音金佛
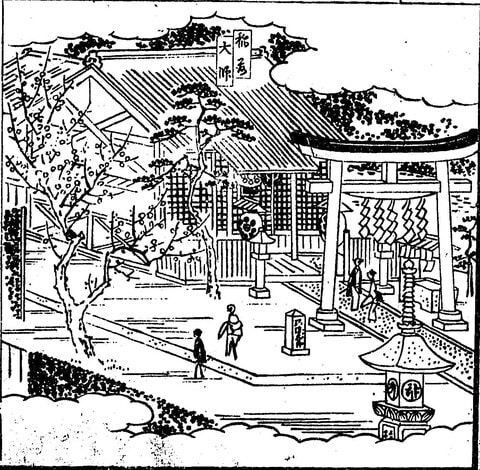
「真藏院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』芝高輪辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ千代田線「赤坂」駅で徒歩約6分。
「赤坂」駅からTBSを回り込み三分坂を登ります。
この三分坂はかなりの急坂で、光蔵院が赤坂の高台にあることがわかります。


【写真 上(左)】 三分坂
【写真 下(右)】 三分坂方向から
三分坂を登ってひとつめの路地を左に入り、クランクを抜けたところが入口です。
あたりは都心屈指の閑静な高級住宅地で、とくにランドマークもないので、東京で生まれ育った人でもなかなか訪れないところです。


【写真 上(左)】 光蔵院_側面(クランク前)
【写真 下(右)】 外観
邸宅風の寺院で、門脇の院号標がなれればおそらく寺院とは気づきません。
周囲に塀をまわし、金属の門扉はピシャリと閉められています。
超高級住宅地然としたあたりの雰囲気といい、この拒絶的な門扉といい、なかなか緊張を強いられる門前です。
意を決して門前のインターホンを推しても、反応があることは少ないともいいます。(Web情報)
こちらは、ご不在が多いらしく『ルートガイド』にも「事前連絡の上の訪問が望ましい」とあります。
なので、筆者は電話予約のうえお伺いしました。


【写真 上(左)】 院号標
【写真 下(右)】 本堂
インターフォンを推し来意を告げると、門扉を開けていただけ、手入れの行き届いた本堂にご案内いただきました。
本堂は寄棟造。二重の金属葺屋根で右寄りが向拝。
向拝見上げには院号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 奉納額
山内、塀の側面には年季の入った奉納額も掲げられていました。
本堂内正面に、お厨子内に御座される弘法大師像。
向かって右の壁面には胎蔵曼荼羅、左には金剛界曼荼羅が掲げられています。
御朱印は堂前で勤行をあげている間にお書きいただけます。
都心とは思えない閑静な空間。
高級住宅地に読経の声が流れていく様は、どこか不思議な感じがします。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に弘法大師のお種子「ユ」「弘法大師」の揮毫と三寶印と「災厄消除」の印判。右に「第八十一番」の札番揮毫。
左に印号の揮毫と寺院印が捺されています。
御府内霊場で弘法大師を御本尊とする寺院は意外に少なく、第1番高野山東京別院、第12番宝仙寺、第13番龍生院、第81番光蔵院、第88番文殊院の5箇寺を数えるのみです。
■ 第82番 青林山 最勝寺 龍福院
(りゅうふくいん)
台東区元浅草3-17-2
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第82番、弘法大師二十一ヶ寺第9番
第82番は元浅草の龍福院です。
第82番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに龍福院で、第82番札所は開創当初から浅草新寺町の龍福院であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
龍福院の創建年代は不明ですが、正保元年(1644年)日本橋・谷町から当地へ移転したといいます。
開山・開基は伝わっていないようですが、法流開山として法印如桂(宝永三年(1706年))の名が伝わります。
本堂に御本尊として弘法大師の御作と伝わる大日如来木座像、祈祷仏として薬師如来木座像を奉安といいます。
寺号については、『御府内八十八ケ所道しるべ』に「薬師寺」とあり、一時期「最勝寺」ではなく「薬師寺」を号していたのかもしれません。
弘法大師の御作と伝わる大日如来奉安の1点でも、弘法大師霊場札所の資格は充分有していたのでは。
当山は史料類が少なく、これ以上は掘り下げられませんでした。
なお、山内には「最後の木版浮世絵師」と呼ばれた小林清親画伯の墓と記念碑があります。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
八十二番
浅草新寺町
青林山 薬師寺 龍福院
大塚護持末 新義
本尊:大日如来 薬師如来 弘法大師
■ 『寺社書上 [80] 浅草寺社書上 甲五』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.96』
浅草新寺町
大塚護持末 新義真言宗
青林山最勝寺龍福院
起立年代相知不申
往古谷町ニ●● 大猷院様御代御用ニ付 正保元年(1644年)当寺町ヘ●●仰付候
開山・開基 知不申
法流開山 法印如桂 宝永三年(1706年)卒
本堂
本尊 大日如来木座像 弘法大師作
祈祷仏 薬師如来木座像
稲荷社
庚申塚

「龍福院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ銀座線「稲荷町」駅で徒歩約5分。
都道463号浅草通り「松が谷一丁目」交差点から左衛門橋通りを南下して4つめ角を東に入ったところです。
元浅草~寿とつづく、御府内霊場札所密集エリアでは南寄りに位置し、むしろ「新御徒町」駅(都営大江戸線・つくばエクスプレス)の方が近いと思います。


【写真 上(左)】 門前
【写真 下(右)】 院号標
門柱と主門・脇門の構成で2度の参拝時はいずれもすべての門扉は閉ざされていましたが、脇門の施錠はされていなかったので、こちらから参内しました。
この門扉は「鉄御納戸色」とでもいうのでしょうか、くすんだ青灰色でかなりの威圧感があります。
御府内霊場札所でなかったら、ふつうは山内に入らないかと思います。
『ルートガイド』には「門が閉まっている日もあるようなので、事前に訪問させていただきたい旨を連絡しておくほうがベター。」とあります。
たしかに、こちらは事前確認がベターかもしれません。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 天水鉢
門柱に院号標と御府内霊場札所標。
参道正面の本堂は宝形造ないし寄棟造桟瓦葺で頂に宝珠を置いています。
流れ向拝でコンクリ造のがっしりとした水引虹梁。
左右に花頭窓を置いて近代建築ながら雰囲気のある仏堂です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
無断で勤行をあげるのも憚られるので、まずは庫裡で御府内霊場巡拝の旨と御朱印をお願いし、勤行のあいだに御朱印のご準備をいただきました。
本堂内はよく見えませんでしたが、『ルートガイド』によると御本尊は金剛界大日如来、左右に弘法大師と興教大師の御像が奉安されているようです。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

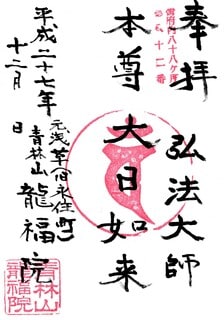
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 大日如来」「弘法大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+宝珠)、右に「御府内八十八ヶ所第八十二番」の札所印。
左に山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-27)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ 黄昏に風る feat.Osakana / Music&Arrangement:Koa
■ 春空-ハルソラ- - 石野田奈津代
■ Far On The Water - kalafina Live FOTW Special Final
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第78番 摩尼山 寶光寺 成就院
(じょうじゅいん)
公式Web
台東区東上野3-32-15
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第78番、奥の細道関東路三十三所霊場第5番
第78番は東上野の成就院です。
御府内霊場には「成就院」を号する札所寺院がふたつ(第43番(元浅草)、第78番(東上野))あり、前者を百観音成就院、後者を田中成就院と呼んで区別しているようです。
第78番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに成就院で、第78番札所は開創当初から下谷田中の成就院であったとみられます。
公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
成就院は、慶長十六年(1611年)、開山・鏡傳法印が神田北寺町に寺地を与えられ開創しました。
『ルートガイド』には、鏡傳法印は徳川家康公に従い江戸に入ったとあります。
慶安元年(1648年)、下谷の現在地を拝領し移転しています。
中興開山と伝わる法印鏡伝は寛文二年(1662年)卒なので、おそらく下谷への移転で功をなされたのかと思います。
当時の下谷は江戸の町外れで、まわりは田んぼだったので「田中(の)成就院」と呼ばれ、いまでも通称として残っています。
浅草の成就院(百観音成就院)との識別のためにも、この通称は必須だったのでは。
■ 『寺社書上』、『御府内寺社備考』には、本所彌勒寺末の新義真言宗とあります。
御本尊には大日如来木坐像、本堂内に弘法大師木坐像、輿教大師木坐像を安し、御府内霊場札所の要件を満たしていました。
「不動尊木立像 弘法大師作」という見逃せない記述もあります。
本堂とは別に地蔵堂があり、地蔵尊の石仏を安していました。
「稲荷社」とあるのは鎮守だったのかもしれません。
公式Webによると、地蔵堂・稲荷社は、いまは伝えられていないとのこと。
また、安政の大地震や関東大震災などの火災で堂宇を消失し、明治の廃仏毀釈の波を受けて衰微してしまったことなどが記されています。
『江戸切絵図』をみるとかなりの敷地をもつ大寺院だったようですが、関東大震災後、境内地が大きく削られてしまったとのことです。
それでも公式Webには寺伝等が詳細に記載され、名刹の矜持が伝わってきます。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
七十八番
下谷田中
摩尼山 宝光院 成就院
本所二ツ目彌勒寺末 新義
本尊:大日如来 浪切不動明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [116] 下谷寺社書上 弐』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.96』
下谷田中
本所彌勒寺末 新義真言宗
摩尼山宝光寺成就院
拙寺起立之儀ハ相知不申候ヘ共 往古慶長十六年(1611年)神田北寺町三十七年往居 慶安元年(1648年)中只今之地面拝領仕引移申候
中興開山 法印鏡伝 寛文二年(1662年)卒
当寺往昔田の中にありし故 田中成就院と唱ヘならはしたるよし 惣ての書上に下谷中成就院と書せり されは田中の唱ハ当寺に限たる事なり 浅草に同宗にて同名の寺あり 是をハ百観音成就院と俗に呼へり
本尊 大日如来木坐像
弘法大師木坐像 輿教大師木坐像
不動尊木立像 弘法大師作
地蔵堂 地蔵尊石像
稲荷社

「成就院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)
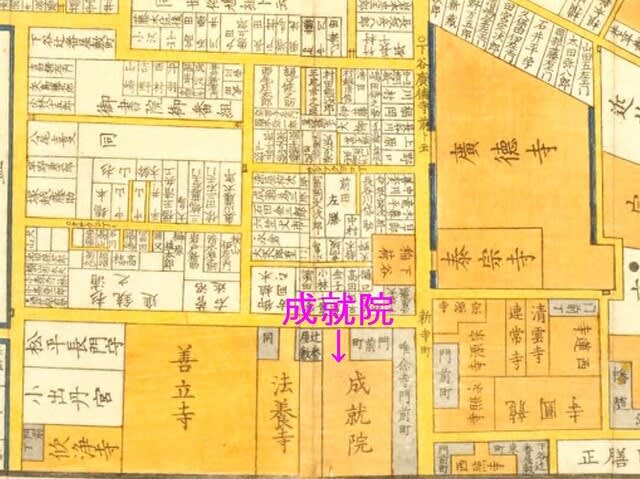
原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』下谷絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ銀座線「稲荷町」駅で徒歩約1分と至近、元浅草~寿とつづく、御府内霊場札所密集エリアの入口にあります。
「稲荷町」駅から南に伸びる清洲橋通り沿いにあります。
山門は門柱で、間口はさほど広くはないですが、敷地はそれなりの広さがあります。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 山内入口
門柱に院号標、門柱前に御府内霊場札所碑。


【写真 上(左)】 御府内霊場札所碑
【写真 下(右)】 緑濃い山内


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
下町とは思えない緑濃い山内。
参道正面が庫裡で、屋根に千鳥破風を配してこ洒落たつくり。
その右よこが本堂で、入母屋造瓦葺流れ向拝、向拝に大がかりな唐破風を起こし、庫裡の千鳥破風と意匠的に呼応しています。


【写真 上(左)】 見事な彫刻
【写真 下(右)】 本堂扁額
水引虹梁は上下二連。両端に見返り(阿吽の)獅子と雲形の木鼻、頭貫上に連三ッ斗以上を端正に連ねるテクニカルな斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に玉持龍の彫刻。
木鼻の見返り獅子、手挟の波紋、中備の玉持龍ともに見事な仕上がりで、こちらは「昭和の名工」といわれた金子光清師の作とのこと。
すこぶる雰囲気のある向拝で、上部には山号扁額を掲げています。
本堂の須弥壇には御本尊大日如来、左手に観世音菩薩、右手に阿弥陀如来の大日三尊を奉安。
左端に吉祥天、右端には多聞天、不動明王を安置しているそうです。


【写真 上(左)】 修行大師像
【写真 下(右)】 修行大師像と大師堂
本堂前には修行大師像、その裏手には大師堂があります。
御府内霊場で大師堂が残っている札所は意外に少ないのですが、こちらはしっかりとした大師堂を護持されています。


【写真 上(左)】 大師堂
【写真 下(右)】 大師堂向拝


【写真 上(左)】 大師堂扁額
【写真 下(右)】 御府内霊場札所板
公式Webによると、『鬼平犯科帳』の一幕に成就院が登場するため、たまに鬼平ファンが寺を訪れるそうで、池波正太郎先生はごく近所に住んでいたことがあるとの由。
そのほか、観音さまをお祀りする「与楽」とご遺骨をお納めする「抜苦」の二つのお堂で成り立つ「称観堂」。
東日本大震災の大津波でなぎ倒された岩手県陸前高田市の高田松原の被災松を材として造立された「やすらぎ聖観音像」も御座されます。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

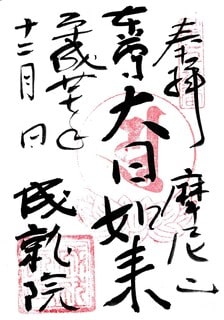
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 大日如来」「弘法大師」の揮毫と弘法大師のお種子「ユ」の御寶印(蓮華座+宝珠)、右に「第七十八番」の札所印。
左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
御府内霊場の御朱印で、本尊大日如来で「ユ」の御寶印が捺されている例はめずらしいです。
■ 第79番 清水山 専教院
(せんきょういん)
文京区小日向3-6-10
真言宗豊山派
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第79番
第79番は小日向の専教院です。
第79番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに専教院で、第79番札所は開創当初から小日向の専教院であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
専教院は寛文五年(1665年)ないし延宝九年(1681)の創建で、開山は良法法印。
中興は法印尊椄(文化十年(1813年)寂)と伝わります。
天明(1781-1789年)の頃、四國八十八ヶ所第七十九番、讃岐國西ノ庄崇徳山天王寺の札所を写し、御府内八十八ヶ所の内七十九番札所となり、以降参詣人を集めています。
本堂内に御本尊として地蔵菩薩木立像を奉安。
両脇士に如意輪観世音菩薩、聖観世音菩薩を安するといういささか変わった尊格配置です。
厨子入の弘法大師木像は、御本尊とともに御府内霊場の拝所となっていました。
さらに十二童子を従えた辨財天も霊場札所の拝所とされていたようです。
文政(1818-1830年)の頃には境内は三百三十八坪ほどもあったといいますが、いまは住宅?の1室に収まっています。
それでも御府内霊場第79番の札所を堅持しておられるのはありがたいことです。
灌頂寺の寺号については記されている資料が少ないですが、正式な号では入るのかもしれません。(清水山 灌頂寺 専教院)
専教院については史料類がすくなく、これ以上掘り下げられませんでした。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
七十九番
小日向臺町
清水山 専教院
中野村宝仙寺末 新義
本尊:地蔵菩薩 弁才天 弘法大師
■ 『寺社書上 [26] 小日向寺社書上 弐』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.126』
小日向臺町
中野村宝仙寺末 新義真言宗
清水山専教院
起立年月日相知不申候
開山 相知不申候
開基 相知不申候
中興 法印尊椄 文化十年(1813年)寂
本堂
本尊 地蔵菩薩木佛立像 両脇士 如意輪木佛立像 聖観音木佛立像
弘法大師木像厨子入 八十八ヶ所内七十九番之札所
辨財天 十二童子
江府八十八観音の内第七拾九番 号ハ讃州崇徳天皇

「専教院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:戸松昌訓著『〔尾張屋板切絵図 18〕』東都小石川絵図,尾張屋清七,嘉永7[1854]/安政[4][1857]改.東京都立中央図書館TOKYOアーカイブ(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅ないし有楽町線「江戸川橋」駅でいずれも徒歩約10分。
小日向あたりは狭くて入り組んだ路地が多く、アプローチはなかなかやっかいです。
「茗荷谷」駅からだと拓殖大学を回り込むかたちとなりわかりにくいです。
駅から大日坂を登って突き当たりを右折して到達する「江戸川橋」駅ルートの方が、登り坂となりますがおそらくわかりやすいかと。


【写真 上(左)】 外観(2016.5)
【写真 下(右)】 石仏群(2016.5)


【写真 上(左)】 百万遍の碑(2016.5)
【写真 下(右)】 扁額(2016.5)
2016年に参拝したときは3階建の集合住宅のような外観で、本堂は2階でしたが、2019年参拝時には建て替えられていて、シックな2階建の建物の1階が本堂となっていました。


【写真 上(左)】 外観(2019.10)
【写真 下(右)】 エントランス(2019.10)
ご在院の場合は、室内の本堂にあげていただける可能性があります。
こういうシチュエーションでは、御真言だけでなく読経のひとつもあげないとどうにも手持ち無沙汰になるので、やはり御府内霊場巡拝には数珠と勤行式は携帯した方がベターかと思います。


【写真 上(左)】 向拝(2019.10)
【写真 下(右)】 扁額(2019.10)


【写真 上(左)】 札所碑(2019.10)
【写真 下(右)】 百万遍の碑と石仏群(2019.10)
本堂前には御府内霊場札所碑、石仏群が並び、御府内霊場札所寺院であることを示しています。
ひときわ目立つ梵字碑は、明治維新に廃仏毀釈に対し仏教復興を主張し、戒律運動の普及に努められた名僧・雲照律師の百万遍の碑とのことです。(『ルートガイド』)
御朱印は堂内(室内)にて拝受しました。
なお、ご不在時は専用集印帳用紙との差し替え授与となる模様なので、通常の書置御朱印はいただけないかもしれません。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

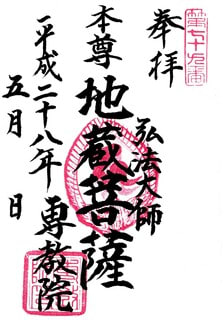
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 地蔵菩薩」「弘法大師」の揮毫と地蔵菩薩のお種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「第七十九番」の札所印。
左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第80番 太元山 宇賀院 長延寺
(ちょうえんじ)
港区三田4-1-29
真言宗豊山派
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第80番
第80番は再度三田に戻って長延寺です。
第80番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに長延寺となっており、第80番札所は御府内霊場開創当初から三田寺町の長延寺であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
長延寺の開山は不明ですが、往古は数寄屋町あたりにあり、慶長六年(1601年)八丁堀に移り、寛永十二年(1635年)現在地(三田下寺町)に転じたといいます。
中興開山は覺順法印(元禄十六年(1703年)寂)と伝わります。
大塚護持院末の新義真言宗。
御本尊の地蔵菩薩木座像は菅原道真公の御作と伝わります。
本堂に弘法大師木座像、興教大師木座像、胎蔵界大日如来木座像、不動明王木立像、十一面観音木立像、大黒天木立像などを安していました。
御本尊は大日如来。
本堂内に弘法大師木座像、興教大師木座像、三尊阿弥陀如来木佛立像を奉安と伝わります。
『ルートガイド』によると、本堂には漆喰の鏝絵『不動明王霊夢』と『俵藤太』があり、作者である伊豆長八の高弟、今泉善吉の墓も当山にあるようです。
長延寺も史料類が少なく、この程度しか掘り下げられませんでした。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
八十番
芝三田寺町
太元山 宇賀院 長延寺
大塚護持院末 新義
本尊:地蔵菩薩 弘法大師 興教大師
■ 『寺社書上 [13] 三田寺社書上 参』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.69』
三田下寺町
大塚護持院末 新義真言宗
太元山宇賀院長延寺
開闢起立之年暦 開山開基等之儀相知不申候
開山大僧都者 寛永三年(1626年)遷化(『御府内寺社備考』)
古に数寄屋町に寺地●るゝ処 慶長十六年(1611年)右寺地より八町堀に代地拝領仕
寛永十二年(1635年)当地より当所(三田下寺町)に替地拝領仕候
中興開山 法印覚順 元禄十六年(1703年)寂
本堂
本尊 地蔵菩薩木座像 菅原道真卿作ト云
弘法大師木座像
興教大師同前(木座像)
胎蔵界大日如来木座像
不動明王木立像
十一面観音木立像
大黒天木立像
地蔵尊石佛
■ 『芝區誌』(デジタル版 港区のあゆみ)
長延寺 三田北寺町十三番地
新義真言宗の末寺で、太元山宇賀院と号する。創建年月不詳。往古数寄屋町邊にあり、慶長六年(1601年)八丁堀に移り、寛永十二年(1635年)此地に転じた。中興開山覺順は元禄十六年(1703年)十二月入寂した。府内八十八ヶ所札所の八十番である。

「長延寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』芝高輪辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは都営三田線「三田」駅で徒歩約10分。
国道1号に面したマンション内の寺院です。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 寺号標


【写真 上(左)】 参道入口の案内板
【写真 下(右)】 門扉
国道1号沿いから参道入口で、塀に寺号標と寺院・札所案内板が掲げられています。
その先が鉄の門扉でここにも寺号標が掲げられています。


【写真 上(左)】 門扉の寺号標
【写真 下(右)】 手前からの本堂
正面右手が本堂、左手が寺務所です。
本堂手前には御府内霊場札所碑。


【写真 上(左)】 札所碑
【写真 下(右)】 御寶号碑


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝上部
本堂は半地下的なつくりで、向拝見上げに山号扁額、弘法大師の扁額、御府内霊場札所板が掲げられています。
古色を帯びた御寶号碑も建ち、マンション内寺院ながら御府内霊場札所を示す事物が豊富な札所です。


【写真 上(左)】 山号扁額
【写真 下(右)】 弘法大師の扁額


【写真 上(左)】 札所板
【写真 下(右)】 御真言
本堂内には地蔵菩薩立像が御座され、地蔵菩薩の御真言と光明真言が掲げられていました。
御朱印は寺務所にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「地蔵菩薩」「弘法大師」の揮毫、地蔵菩薩のお種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と三寶印。右に「御府内第八十番」の札所印。
左に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第81番 医王山 光蔵院
(こうぞういん)
港区赤坂7-6-68
真言宗智山派
御本尊:弘法大師
札所本尊:弘法大師
司元別当:
他札所:
第81番は赤坂の光蔵院です。
第81番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに真藏院となっており、第81番札所は御府内霊場開創当初から江戸期を通じて三田寺町の真藏院であったとみられます。
光蔵院、真藏院について、光蔵院掲出の由来書、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
【光蔵院】
光蔵院は、寛永年代(1624-1644年)に西久保飯倉町一丁目(現・港区麻布台一丁目)に創立といい、芝愛宕前真福寺末寺の新義真言宗寺院です。
御本尊は薬師如来。
毘沙門天、弘法大師木座像、不動明王、愛染明王、歓喜天尊、稲荷小社一宇と石佛地蔵を安していました。
享保年間(1716-1736年)の頃から、川崎大師河原平間寺(金剛山平原寺金乗密院)が江戸の御旅所とし、弘法大師を御本尊として安置され(飯倉)厄除け大師として庶民の参詣が多かったといいます。
第23番札所の薬研堀不動院が川崎大師東京別院となったのは明治25年ですから、江戸期の光蔵院は御旅所ながら江戸別院的な役割を果たしていたのかもしれません。
その後御府内霊場第81番の札所となり、大正10年本堂を改築したものの、昭和20年5月戦災に遭って焼失しました。
昭和37年5月、御本尊に弘法大師を安置し飯倉の地で再建を果たしています。
その後飯倉は繁華地に変貌したため、現在地の赤坂に遷られ昭和63年3月に落成慶讃式法要を挙行、以降、赤坂の地で御府内霊場巡拝者を迎えています。
なお、現時点で光蔵院は『江戸切絵図』で発見できておりません。
【真藏院】
真藏院は、当初数寄屋橋に寺地を拝領して開創といい、寺地が御用地となったため慶長十六年(1611年)八丁堀に移転、こちらも御用地となったため寛永十二年(1635年)当所(三田寺町)に寺地を得て移転といいます。
開基の泉尊法印は寛永三年(1626年)卒と伝わります。
御本尊は胎蔵界大日如来。
弘法大師木座像、興教大師同前を安して御府内霊場の要件を満たしていました。
興教大師の御筆と伝わる不動尊、細川越中守家から寄附の不動尊(辨慶筆)も奉安していたようです。
山内に稲荷社を擁し、不動明王、愛染明王、十一面観世音菩薩を堂内に奉安と記されています。
明治初頭編纂の『御府内八十八ケ所道しるべ』の札所異動資料に真藏院から光蔵院への異動の記載がないので、光蔵院への札所承継はそれ以降とみられます。
別当寺の性格が強くない真藏院が廃寺となった経緯は不明ですが、真藏院、光蔵院ともに愛宕前真福寺末寺の新義真言宗寺院。
光蔵院は(飯倉)厄除け大師として庶民の参詣が多かったといいますから、もとより弘法大師霊場札所の資格は有していたともみられ、この札所承継は自然な流れだったのかもしれません。
-------------------------
【史料】
【光蔵院】
■ 『寺社書上 [62] 飯倉寺社書上』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.90』
西久保飯倉町一丁目
醫王山光蔵院
愛宕前真福寺末 新義真言宗
起立開山開基相知不申候
本堂
本尊 薬師如来木座像
毘沙門天木立像
弘法大師木座像
不動明王木座像
愛染明王木座像
歓喜天
稲荷小社一宇
石佛地蔵
【真藏院】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
八十一番
芝三田三軒寺町
朝光山 南峯寺 真藏院
愛宕山真福寺末 新義
本尊:金剛界大日如来 不動明王 弘法大師
■ 『御府内寺社備考P.93』
三田寺町
愛宕前真福寺末 新義真言宗
朝光山南峯寺真藏院
開闢之年代相知不申候
●●数寄屋橋に寺地拝領仕候 ●御用地と相成 慶長十六年(1611年)八丁堀に替地 是又●御用地と相成 寛永十二年(1635年)当所を替地ニ
開基 泉尊 寛永三年(1626年)卒
中興開山 宥●
本堂
本尊 胎蔵界大日如来木座像 通途作
弘法大師木座像 通途作
興教大師同前(木座像)
胎蔵界大日如来木座像
地蔵尊唐銅立像 通途作
不動尊 興教大師筆ト云
不動尊 辨慶筆 右ハ細川越中守殿●寄附
不動尊 妙沢筆
稲荷社
神躰不知
不動木坐像 通途作
愛染 同
十一面観音金佛
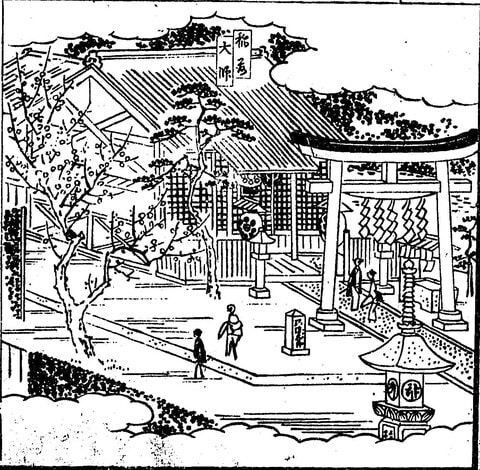
「真藏院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』芝高輪辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ千代田線「赤坂」駅で徒歩約6分。
「赤坂」駅からTBSを回り込み三分坂を登ります。
この三分坂はかなりの急坂で、光蔵院が赤坂の高台にあることがわかります。


【写真 上(左)】 三分坂
【写真 下(右)】 三分坂方向から
三分坂を登ってひとつめの路地を左に入り、クランクを抜けたところが入口です。
あたりは都心屈指の閑静な高級住宅地で、とくにランドマークもないので、東京で生まれ育った人でもなかなか訪れないところです。


【写真 上(左)】 光蔵院_側面(クランク前)
【写真 下(右)】 外観
邸宅風の寺院で、門脇の院号標がなれればおそらく寺院とは気づきません。
周囲に塀をまわし、金属の門扉はピシャリと閉められています。
超高級住宅地然としたあたりの雰囲気といい、この拒絶的な門扉といい、なかなか緊張を強いられる門前です。
意を決して門前のインターホンを推しても、反応があることは少ないともいいます。(Web情報)
こちらは、ご不在が多いらしく『ルートガイド』にも「事前連絡の上の訪問が望ましい」とあります。
なので、筆者は電話予約のうえお伺いしました。


【写真 上(左)】 院号標
【写真 下(右)】 本堂
インターフォンを推し来意を告げると、門扉を開けていただけ、手入れの行き届いた本堂にご案内いただきました。
本堂は寄棟造。二重の金属葺屋根で右寄りが向拝。
向拝見上げには院号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 奉納額
山内、塀の側面には年季の入った奉納額も掲げられていました。
本堂内正面に、お厨子内に御座される弘法大師像。
向かって右の壁面には胎蔵曼荼羅、左には金剛界曼荼羅が掲げられています。
御朱印は堂前で勤行をあげている間にお書きいただけます。
都心とは思えない閑静な空間。
高級住宅地に読経の声が流れていく様は、どこか不思議な感じがします。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に弘法大師のお種子「ユ」「弘法大師」の揮毫と三寶印と「災厄消除」の印判。右に「第八十一番」の札番揮毫。
左に印号の揮毫と寺院印が捺されています。
御府内霊場で弘法大師を御本尊とする寺院は意外に少なく、第1番高野山東京別院、第12番宝仙寺、第13番龍生院、第81番光蔵院、第88番文殊院の5箇寺を数えるのみです。
■ 第82番 青林山 最勝寺 龍福院
(りゅうふくいん)
台東区元浅草3-17-2
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第82番、弘法大師二十一ヶ寺第9番
第82番は元浅草の龍福院です。
第82番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに龍福院で、第82番札所は開創当初から浅草新寺町の龍福院であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
龍福院の創建年代は不明ですが、正保元年(1644年)日本橋・谷町から当地へ移転したといいます。
開山・開基は伝わっていないようですが、法流開山として法印如桂(宝永三年(1706年))の名が伝わります。
本堂に御本尊として弘法大師の御作と伝わる大日如来木座像、祈祷仏として薬師如来木座像を奉安といいます。
寺号については、『御府内八十八ケ所道しるべ』に「薬師寺」とあり、一時期「最勝寺」ではなく「薬師寺」を号していたのかもしれません。
弘法大師の御作と伝わる大日如来奉安の1点でも、弘法大師霊場札所の資格は充分有していたのでは。
当山は史料類が少なく、これ以上は掘り下げられませんでした。
なお、山内には「最後の木版浮世絵師」と呼ばれた小林清親画伯の墓と記念碑があります。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
八十二番
浅草新寺町
青林山 薬師寺 龍福院
大塚護持末 新義
本尊:大日如来 薬師如来 弘法大師
■ 『寺社書上 [80] 浅草寺社書上 甲五』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.96』
浅草新寺町
大塚護持末 新義真言宗
青林山最勝寺龍福院
起立年代相知不申
往古谷町ニ●● 大猷院様御代御用ニ付 正保元年(1644年)当寺町ヘ●●仰付候
開山・開基 知不申
法流開山 法印如桂 宝永三年(1706年)卒
本堂
本尊 大日如来木座像 弘法大師作
祈祷仏 薬師如来木座像
稲荷社
庚申塚

「龍福院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ銀座線「稲荷町」駅で徒歩約5分。
都道463号浅草通り「松が谷一丁目」交差点から左衛門橋通りを南下して4つめ角を東に入ったところです。
元浅草~寿とつづく、御府内霊場札所密集エリアでは南寄りに位置し、むしろ「新御徒町」駅(都営大江戸線・つくばエクスプレス)の方が近いと思います。


【写真 上(左)】 門前
【写真 下(右)】 院号標
門柱と主門・脇門の構成で2度の参拝時はいずれもすべての門扉は閉ざされていましたが、脇門の施錠はされていなかったので、こちらから参内しました。
この門扉は「鉄御納戸色」とでもいうのでしょうか、くすんだ青灰色でかなりの威圧感があります。
御府内霊場札所でなかったら、ふつうは山内に入らないかと思います。
『ルートガイド』には「門が閉まっている日もあるようなので、事前に訪問させていただきたい旨を連絡しておくほうがベター。」とあります。
たしかに、こちらは事前確認がベターかもしれません。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 天水鉢
門柱に院号標と御府内霊場札所標。
参道正面の本堂は宝形造ないし寄棟造桟瓦葺で頂に宝珠を置いています。
流れ向拝でコンクリ造のがっしりとした水引虹梁。
左右に花頭窓を置いて近代建築ながら雰囲気のある仏堂です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
無断で勤行をあげるのも憚られるので、まずは庫裡で御府内霊場巡拝の旨と御朱印をお願いし、勤行のあいだに御朱印のご準備をいただきました。
本堂内はよく見えませんでしたが、『ルートガイド』によると御本尊は金剛界大日如来、左右に弘法大師と興教大師の御像が奉安されているようです。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

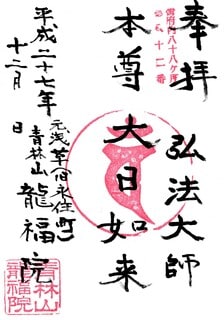
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 大日如来」「弘法大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+宝珠)、右に「御府内八十八ヶ所第八十二番」の札所印。
左に山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-27)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ 黄昏に風る feat.Osakana / Music&Arrangement:Koa
■ 春空-ハルソラ- - 石野田奈津代
■ Far On The Water - kalafina Live FOTW Special Final
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 日本仏教13宗派と御朱印(首都圏版)
御朱印を加えました。
-------------------------
2022/11/06 UP
■ 日本仏教13宗派を完全解説! 仏教 | 宗教 | 日本史
■ 【仏教】仏教の宗派を知る 前編
-----------------
「宗派 御朱印」でぐぐると、この記事→「御朱印帳の使い分け」がけっこう上位にくるので、日本仏教13宗派毎に代表的な御朱印をまとめてみます。
今回は首都圏に限定してのご紹介です。
(公財)全日本仏教会公式Webの「宗派一覧」には13どころか、50を超える宗派が掲載されています。
こちらのデータをベースにいくつか追加をした下記リストに沿って、ご紹介していきます。
(記載順は年代順とし、同年代の宗派については原則として上記資料を踏襲しました。)
なお、日本仏教13宗派は、現代でも大きな宗派として存在する法相宗、華厳宗、律宗、天台宗、真言宗、融通念仏宗、浄土宗、浄土真宗、時宗、臨済宗、曹洞宗、黄檗宗、日蓮宗をさすようです。
------------------------------
■ 中国からの系譜
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)「中国十三宗」』
01.成実宗 → 三論宗の付宗(寓宗)に
02.三論宗 → 南都六宗
03.毘曇宗(倶舎宗) → 法相宗(南都六宗)の付宗(寓宗)に
04.地論宗 → 華厳宗(南道派)
05.摂論宗 → 法相宗(南都六宗)に吸収
06.法相宗 → 南都六宗
07.律宗 → 南都六宗
08.華厳宗 → 南都六宗
09.涅槃宗 → 天台宗に吸収
10.天台宗 → 天台宗
11.密宗 → 真言宗・天台宗
12.禅宗 → 禅宗
13.浄土宗 → 浄土教(浄土宗、(浄土)真宗、時宗、融通念仏宗など)
------------------------------
※法統、宗祖派祖、立宗立派の時期、所依教典などは、『日本仏教思想のあゆみ』(竹村牧男氏著、講談社学術文庫)およびWikipediaに拠りました。
【奈良仏教】
〔南都六宗系〕
※南都六宗:三論宗、成実宗、法相宗、倶舎宗、華厳宗、律宗
※付宗(寓宗):独立せずに他宗に付属している宗
■(三論宗)
法統:インド中観派・龍樹→嘉祥大師吉蔵
宗祖派祖:嘉祥大師吉蔵
伝来:625年 慧漑(第一伝)
所依教典:『中論』『十二門論』『百論』
教義の特徴:四種釈義、破邪顕正など

飯盛山 修福寺(静岡県南伊豆町)
※ 曹洞宗ですが、三論宗の流れと伝わります。
■(成実宗) 三論宗の付宗(寓宗)
■法相宗
法統:インド瑜伽行派→玄奘三蔵→慈恩大師基
宗祖派祖:慈恩大師基
伝来:道招(629-700年)(第一伝)
所依教典:『成唯識論』
教義の特徴:唯識思想など
大本山:薬師寺(奈良市西ノ京町)
大本山:興福寺(奈良市登大路町)


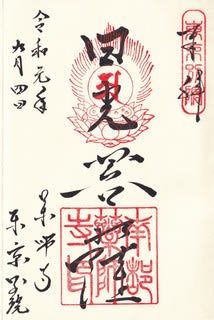
薬師寺東京別院(品川区東五反田)

水雲山 潮音寺(奈良薬師寺 東関東別院)(茨城県潮来市)
■(倶舎宗) 法相宗の付宗(寓宗)
■ 聖徳宗
宗祖:聖徳太子
立宗:昭和25年法相宗から独立
所依教典:『三経義疏』
大本山:法隆寺(奈良県斑鳩町)
■華厳宗
法統:インドor西域→(地論宗)→智儼
宗祖派祖:法蔵
伝来:736年 審祥・良弁
所依教典:『華厳経』
教義の特徴:重々無尽の縁起、円教・別教一乗など
大本山:東大寺(奈良市雑司町)
■律宗
法統:四分律宗・南山律宗→(戒律学)→文綱
宗祖派祖:
伝来:753年 鑑真
所依教典:『四分律』
教義の特徴:戒律
総本山:唐招提寺(奈良市五条町)
■(北京律)
■(南都律)
※下記は律宗の流れを汲んでいるため、【奈良仏教】に記載しました。
■真言律宗
法統:四分律宗・南山律宗→(戒律学)→文綱
宗祖派祖:高祖弘法大師、叡尊(興正菩薩)
所依教典:『十誦律』
教義の特徴:戒律、具足戒、三昧耶戒など
総本山:西大寺(奈良市西大寺芝町)

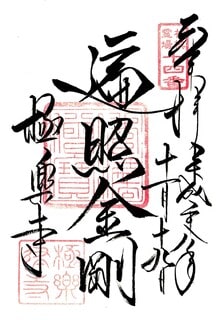
【写真 上(左)】 金沢山 彌勒院 称名寺(横浜市金沢区)
【写真 下(右)】 霊鷲山 感応院 極楽律寺(鎌倉市極楽寺)
■真言宗霊雲寺派
法統:真言律宗→
宗祖派祖:高祖弘法大師、叡尊(興正菩薩)
立派:昭和22年真言律宗から独立
所依教典:『十誦律』?
教義の特徴:戒律、具足戒、三昧耶戒など
総本山:霊雲寺(文京区湯島)

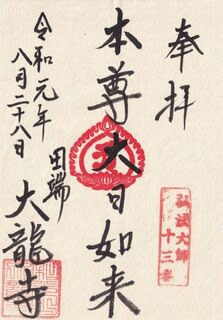
【写真 上(左)】 宝林山 大悲心院 霊雲寺(文京区湯島)
【写真 下(右)】 和光山 興源院 大龍寺(北区田端)
【平安仏教】
〔天台宗系〕
■天台宗
法統:智顗(天台大師)・天台教学
宗祖派祖:(智顗)
伝来:806年 伝教大師最澄
天台密教将来:最澄・円仁
所依教典:『妙法蓮華経』『涅槃経』など
教義の特徴:四宗兼学、止観行など
総本山:延暦寺(滋賀県大津市)
●天台宗の御朱印尊格は多彩です。
特徴的な尊格に「元三大師」があります。
主印は御寶印(種子)が多くなっています。


【写真 上(左)】 東叡山 寛永寺(台東区上野公園)
【写真 下(右)】 日光山 輪王寺(栃木県日光市)


【写真 上(左)】 星野山 無量寿寺 中院(川越市小仙波町)
【写真 下(右)】 浮岳山 昌楽院 深大寺(調布市深大寺元町)
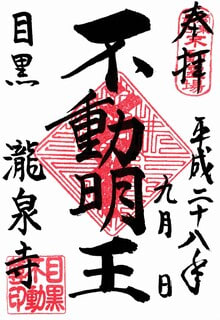

【写真 上(左)】 泰叡山 護國院 瀧泉寺(目黒不動尊)(目黒区下目黒)
【写真 下(右)】 小野寺山 転法輪院 大慈寺(栃木県栃木市)
■天台真盛宗
法統:天台教学→真盛
宗祖派祖:真盛
(立宗):1486年 真盛
所依教典:
教義の特徴:天台念仏、戒律など
総本山:西教寺(滋賀県大津市)


【写真 上(左)】 天羅山 養善院 真盛寺(杉並区梅里)
【写真 下(右)】 率渓山 新善光寺(横浜市南区)
■天台寺門宗
法統:智顗(天台大師)・天台教学→円珍
宗祖派祖:智証大師円珍
立宗:智証大師円珍(814-891年)
所依教典:『妙法蓮華経』など
教義の特徴:円・密・禅・戒・修験五法門など
総本山:三井寺(滋賀県大津市)
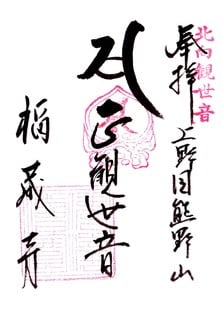

熊野山 福蔵寺(群馬県高山村)
明光山 大善院(さいたま市浦和区)
■聖観音宗
立宗:昭和25年天台宗より独立
本山:浅草寺(台東区浅草)
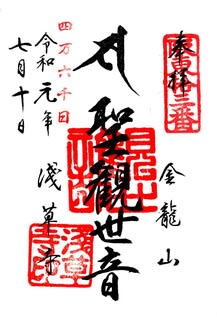
金龍山 浅草寺(台東区浅草)
■金峯山修験本宗
立宗:昭和23年、天台宗から分派独立し大峯修験宗
昭和27年、金峯山修験本宗と改称
総本山:金峯山寺(奈良県吉野町)
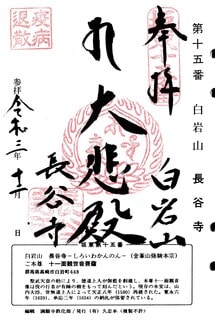

【写真 上(左)】 白岩山 長谷寺(群馬県高崎市)
【写真 下(右)】 大照山 相慈寺(品川区二葉)
■本山修験宗
法統等:智証大師円珍→増誉
寺格等:聖護院門跡、天台宗寺門派三門跡、修験道本山派
総本山:聖護院(京都市左京区)
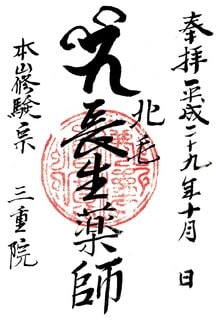
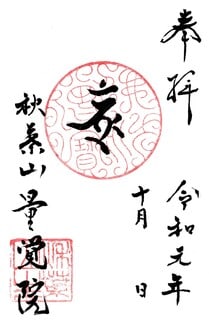
【写真 上(左)】 長生山 瑠璃光寺 三重院(群馬県みなかみ町)
【写真 下(右)】 秋葉山 量覚院(小田原市板橋)
■和宗
総本山:四天王寺(大阪市天王寺区)
■孝道教団
開宗:昭和11年岡野正道始祖(天台宗大僧正)
孝道山 本仏殿(横浜市神奈川区)

■妙見宗
立宗:昭和21年天台宗から独立
総本山:本瀧寺(大阪府能勢町)
■念法眞教
総本山:金剛寺(大阪市鶴見区)
■天台宗弾誓派

【写真 上(左)】 無常山 一之澤院 浄発願寺(神奈川県伊勢原市)
〔真言宗系〕
法統:インド密教→竜猛→竜智→金剛智→不空→恵果→空海
宗祖派祖:付法の八祖
立教開宗:弘法大師空海(774-835年)
所依教典:『大日経』『金剛頂経』『理趣経』など
教義の特徴:事相と教相、身口意三密など
総本山:教王護国寺(東寺)(京都市南区)
●真言宗の御朱印尊格は多彩です。
特徴的な尊格に「弘法大師」「遍照金剛」があります。
大日如来、不動明王の御朱印も多くみられます。
主印は御寶印(種子)が多くなっています。
〔古義真言宗系〕
教義の特徴:事相と教相、身口意三密、本地身説法など
■高野山真言宗
法統等:古義真言宗総本山・金剛峯寺
総本山:金剛峯寺(和歌山県高野町)
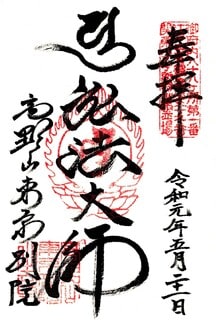

【写真 上(左)】 高野山 東京別院(港区高輪)
【写真 下(右)】 同

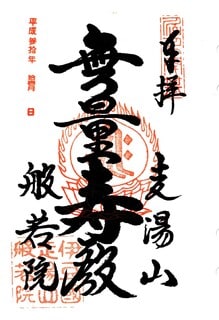
【写真 上(左)】 飯盛山 仁王院 青蓮寺(鎌倉市手広)
【写真 下(右)】 走湯山 般若院(静岡県熱海市)
■真言宗大覚寺派
法統等:宇多帝、後嵯峨帝、亀山帝、御宇多帝、保寿院流
大本山:大覚寺(京都市右京区)


【写真 上(左)】 雨降山 大山寺(神奈川県伊勢原市)
【写真 下(右)】 天衛山 多聞院 福寿寺(鎌倉市大船)


【写真 上(左)】 南向山 帰命院 補陀洛寺(鎌倉市材木座)
【写真 下(右)】 小動山 浄泉寺(鎌倉市腰越)
■真言宗善通寺派
法統等:増俊僧正、成尊、随心院(仁海)流、小野流、旧・小野派
総本山:善通寺(香川県善通寺市)

朝日山 平等院(埼玉県飯能市)
■真言宗御室派
法統等:寛平法皇(宇多天皇)、紫金台寺御室、広沢流
総本山:仁和寺(京都市右京区)

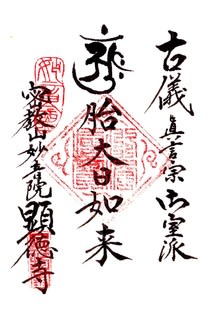
【写真 上(左)】 萬昌山 金剛幢院 圓満寺(文京区湯島)
【写真 下(右)】 密教山 如音院 顕徳寺(群馬県東吾妻町)
■真言宗山階派
法統等:承俊、済高、寛信、勧修寺流
大本山:勧修寺(京都市山科区)
■真言宗泉涌寺派
法統等:月輪大師俊芿、四宗兼学、皇室御陵所
総本山:泉涌寺(京都市東山区)

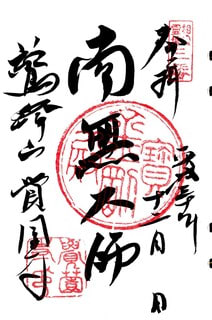
【写真 上(左)】 泉谷山 浄光明寺(鎌倉市扇ガ谷)
【写真 下(右)】 鷲峰山 覚園寺(鎌倉市二階堂)
■真言宗醍醐派
法統等:理源大師聖宝、義演准后、小野流、恵印法流、修験道当山派
総本山:醍醐寺(京都市伏見区)
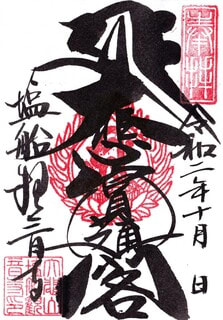
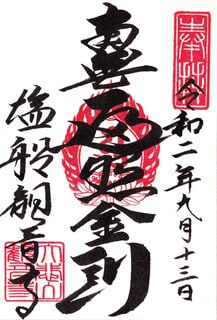
【写真 上(左)】 大悲山 塩船観音寺(東京都青梅市)
【写真 下(右)】 同


【写真 上(左)】 海照山 普門院 品川寺(品川区南品川)
【写真 下(右)】 神谷山 成就院(埼玉県三郷市)
■真言宗国分寺派
法統等:日本法相宗の祖・道昭、勅願道場
大本山:国分寺(大阪市北区)

應雲山 感応院(さいたま市見沼区)
■真言宗須磨寺派
法統等:淳和帝、光孝帝
大本山:須磨寺(神戸市須磨区)
■真言宗中山寺派
法統等:聖徳太子、源氏祈願所
大本山:中山寺(兵庫県宝塚市)
■真言三宝宗
法統等:宇多天皇勅願、三宝荒神社、神仏習合、三宝三福
大本山:清荒神清澄寺(兵庫県宝塚市)

瑠璃山 南谷寺 東光院(神奈川県小田原市)
■信貴山真言宗
法統等:聖徳太子、毘沙門天(多聞天)
大本山:朝護孫子寺(奈良県平群町)


【写真 上(左)】 慈眼山 圓通寺(埼玉県川島町)
【写真 下(右)】 頂寳山 弘福院(千葉県袖ケ浦市)
■真言宗犬鳴派
法統等:役小角、葛城二十八宿修験道
大本山:七宝瀧寺(大阪府泉佐野市)
■東寺真言宗
法統等:教王護国寺(東寺)、真言密教の根本道場
総本山:教王護国寺(京都市南区)
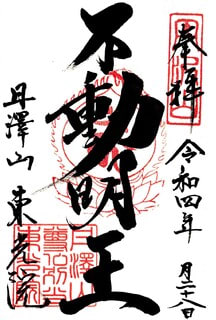

【写真 上(左)】 丹澤山 東光院(神奈川県山北町)
【写真 下(右)】 醫王山 薬師院 圓福寺(小田原市本町)
■真言宗東寺派
法統等:教王護国寺(東寺)、真言密教の根本道場
別格本山:正法寺(京都市西京区)

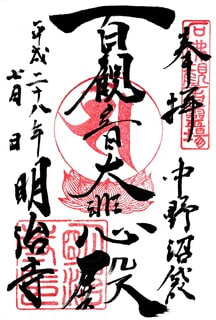
【写真 上(左)】 飯泉山 勝福寺(小田原市飯泉)
【写真 下(右)】 新浮侘落山 世尊院 明治寺(中野区沼袋)
〔新義真言宗系〕
法統等:弘法大師空海→興教大師覚鑁→頼瑜
教義の特徴:事相と教相、身口意三密、加持身説法など
■真言宗智山派
法統等:弘法大師空海→興教大師覚鑁→玄宥
総本山:智積院(京都市東山区)
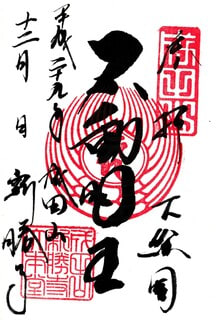

【写真 上(左)】 成田山 新勝寺(千葉県成田市)
【写真 下(右)】 金剛山 平間寺(川崎大師)(川崎市川崎区)


【写真 上(左)】 高尾山 薬王院(八王子市高尾町)
【写真 下(右)】 高幡山 明王院 金剛寺(高幡不動尊)(日野市高幡)
■真言宗豊山派
法統等:弘法大師空海→興教大師覚鑁→専誉僧正
総本山:長谷寺(奈良県桜井市)


【写真 上(左)】 神齢山 悉地院 護国寺(文京区大塚)
【写真 下(右)】 五智山 遍照院 總持寺(西新井大師)(足立区西新井)
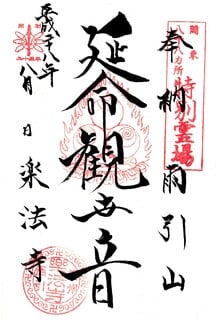
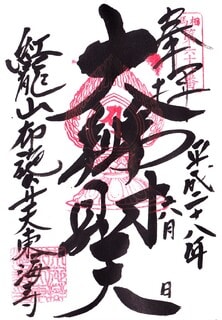
【写真 上(左)】 雨引山 楽法寺(茨城県桜川市)
【写真 下(右)】 紅龍山 布施弁天 東海寺(千葉県柏市)
■真言宗大日派
法統等:弘法大師空海→興教大師覚鑁→専誉僧正
(真言宗豊山派から独立)
根本道場:鑁阿寺(栃木県足利市)

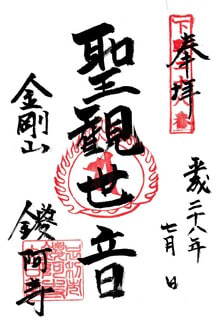
【写真 上(左)】 金剛山 仁王院 法華坊 鑁阿寺(栃木県足利市)
【写真 下(右)】 同
■真言宗室生寺派
法統等:弘法大師空海→興教大師覚鑁→専誉僧正
(真言宗豊山派から独立)
大本山:室生寺(奈良県宇陀市)
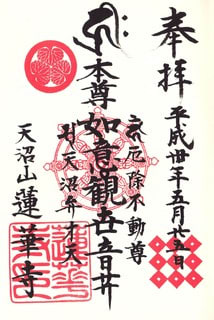

【写真 上(左)】 天沼山 蓮華寺(杉並区本天沼)
【写真 下(右)】 光明山 真言院 荘厳寺(渋谷区本町)
■新義真言宗
法統等:弘法大師空海→興教大師覚鑁→頼瑜
総本山:根來寺(和歌山県岩出市)
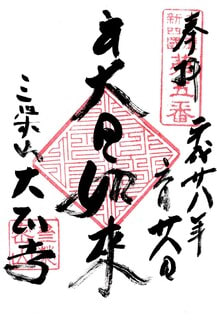

【写真 上(左)】 三栄山 大正寺(調布市調布ケ丘)
【写真 下(右)】 新照山 蓮華寺(横浜市港北区)


【写真 上(左)】 長谷山 元興寺 加納院(台東区谷中)
【写真 下(右)】 法然山 伝灯寺 釋藏院(千葉県市原市)
【鎌倉仏教】
〔浄土宗系〕
■浄土宗
法統:法然上人→弁長・良忠(鎮西義)→良暁(白旗派)
宗祖派祖:法然上人
立教開宗:1175年 法然上人
所依教典:『浄土三部経』『観無量寿経疏』『選択本願念仏集』など
教義の特徴:念仏・御名号「南無阿弥陀仏」、他力本願
総本山:知恩院(京都市東山区)
●浄土宗の御朱印尊格は阿弥陀如来が多くなっています。
特徴的な尊格に「南無阿弥陀佛」(六字御名号)があります。
主印は三寶印(佛法僧寶)がメインです。
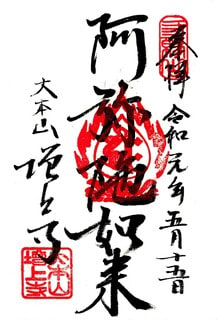
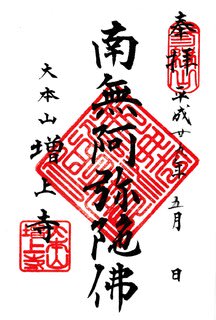
三縁山 広度院 増上寺(港区芝公園)


天照山 蓮華院 光明寺(鎌倉市材木座)


【写真 上(左)】 無量山 寿経寺 伝通院(文京区小石川)
【写真 下(右)】 寿亀山 天樹院 (飯沼)弘経寺(鎮西義白旗派流/茨城県常総市)

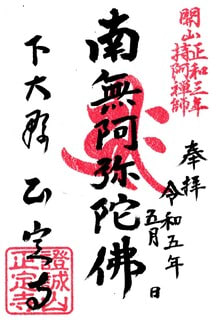
【写真 上(左)】 祇園山 田代寺(長楽寺) 安養院(鎮西義名越派(善導寺義)流/鎌倉市大町)
【写真 下(右)】 証誠山 等持院 (大野)正定寺(鎮西義藤田派流/茨城県古河市)

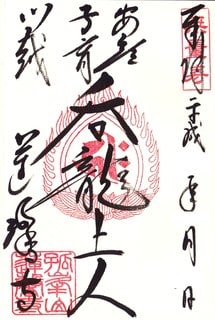
【写真 上(左)】 明顯山 善久院 祐天寺(目黒区中目黒)
【写真 下(右)】 孤峰山 宝池院 蓮馨寺(川越市蓮雀町)
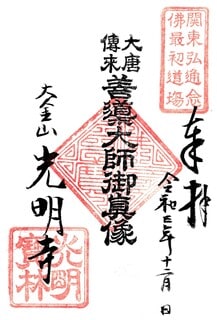

【写真 上(左)】 大金山 宝幢院 光明寺(大田区鵜の木)
【写真 下(右)】 三縁山 増上寺 妙定院(港区芝公園)
■浄土宗西山禅林寺派
法統:法然上人→証空(西山義)→浄音(西谷義)
総本山:永観堂 禅林寺(京都市左京区)
■浄土宗西山深草派
法統:法然上人→証空(西山義)→立信(深草義)
総本山:誓願寺(京都市中京区)
■西山浄土宗
法統:法然上人→証空(西山義)→浄音(西谷義)
総本山:光明寺(京都府長岡京市)
〔(浄土)真宗系〕
法統:法然上人→親鸞上人
宗祖派祖:親鸞上人
立教開宗:1224年 親鸞上人
所依教典:『浄土三部経』『教行信証』『選択本願念仏集』など
教義の特徴:念仏・御名号「南無阿弥陀仏」、絶対他力(本願)
●(浄土)真宗は教義上、御朱印を授与されない寺院が多くみられます。
授与される場合の尊格や主印は多彩です。
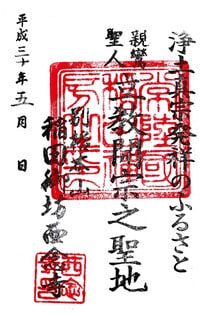
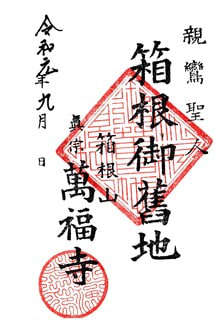
【写真 上(左)】 稲田山 西念寺(稲田御坊)(茨城県笠間市)
【写真 下(右)】 箱根山 萬福寺(箱根御舊地)(神奈川県箱根町)
■浄土真宗本願寺派 (「お西」「本派」)
本山:本願寺(京都市下京区)


【写真 上(左)】 築地本願寺(中央区築地)
【写真 下(右)】 麻布山 善福寺(港区元麻布)
■真宗大谷派 (「お東」「大派」)
本山:東本願寺(京都市下京区)
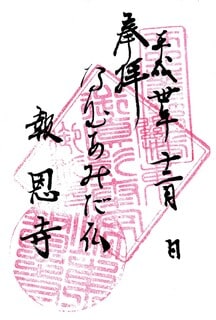
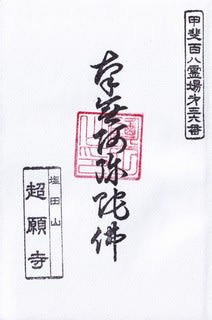
【写真 上(左)】 高龍山 謝徳院 坂東報恩寺(台東区東上野)
【写真 下(右)】 塩田山 超願寺(山梨県笛吹市)
■浄土真宗東本願寺派
本山:浄土真宗東本願寺派本山東本願寺(台東区西浅草)
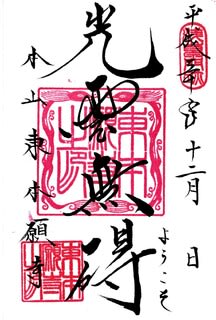

【写真 上(左)】 東本願寺(台東区西浅草)
【写真 下(右)】 牛久大佛(茨城県牛久市)
■真宗高田派
法統:親鸞上人→顕智(高田門徒)
本山:専修寺(三重県津市)

高田山 専修寺(栃木県真岡市)
■真宗佛光寺派
本山:佛光寺(京都市下京区)
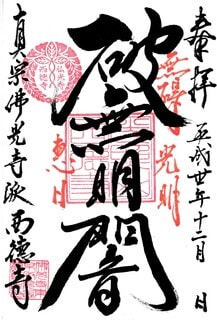
光照山 西徳寺(台東区竜泉)
■真宗興正派
本山:興正寺(京都市下京区)
■真宗木辺派
本山:錦織寺(滋賀県野州市)
〔時宗系〕
■時宗
法統:浄土宗西山義→一遍上人→他阿(遊行上人)
開祖:一遍上人(1239-1289年)
所依教典:『観経疏』など
教義の特徴:念仏・御名号「南無阿弥陀仏」、他力本願、融通念仏、踊念仏
総本山:清浄光寺(遊行寺)(神奈川県藤沢市)
●時宗の御朱印尊格は阿弥陀如来が多くなっています。
特徴的な尊格に「南無阿弥陀佛」(六字御名号)があります。
主印は三寶印(佛法僧寶)がメインです。

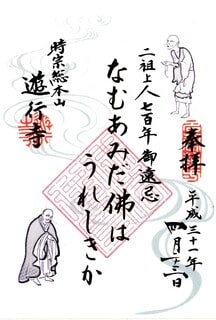
【写真 上(左)】 藤沢山 無量光院 清浄光寺(遊行寺)(神奈川県藤沢市)
【写真 下(右)】 同

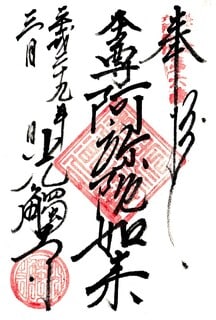
【写真 上(左)】 河越山 三芳野院 常楽寺(川越市上戸)
【写真 下(右)】 岩蔵山 長春院 光觸寺(鎌倉市十二所)
〔融通念佛宗系〕
■融通念佛宗
法統:天台宗→良忍(大念仏宗)→大通
開宗:1127年 聖応大師良忍
所依教典:『華厳経』『法華経』など
教義の特徴:念仏「南無阿弥陀仏」、他力本願、融通念仏
総本山:大念佛寺(大阪市平野区)
〔禅宗系〕
□臨済宗
法統:達磨大師→臨済義玄→明菴栄西
宗祖:臨済義玄(唐)
開祖:明菴栄西(日本)(1141-1215年)
所依教典:
教義の特徴:悟り、座禅、公案、法嗣
●禅宗の御朱印尊格は釋迦牟尼佛(南無釋迦牟尼佛)が多くなっています。
密教系からかわった寺院では以前の御本尊を踏襲し、そちらの御朱印となるケースが多くみられます。
主印は三寶印(佛法僧寶)がメインです。
■臨済宗妙心寺派
大本山:妙心寺(京都市右京区)

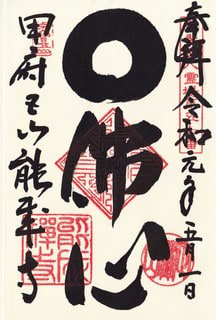
【写真 上(左)】 金鳳山 平林寺(埼玉県新座市)
【写真 下(右)】 定林山 能成寺(山梨県甲府市)
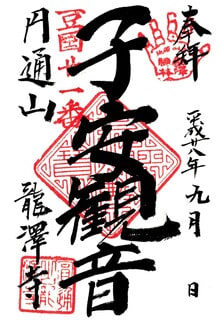
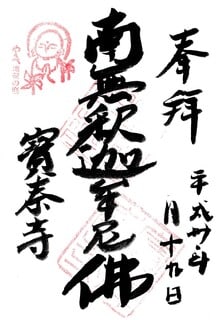
【写真 上(左)】 圓通山 龍澤寺(静岡県三島市)
【写真 下(右)】 金剛山 寶泰寺(静岡市葵区)
■臨済宗南禅寺派
大本山:南禅寺(京都市左京区)

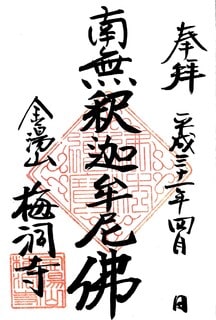
【写真 上(左)】 勝林山 金地院(港区芝公園)
【写真 上(左)】 金湯山 梅洞寺(八王子市打越町)


【写真 上(左)】 龍王山 宝円寺(埼玉県小鹿野町)
【写真 下(右)】 飯盛山 青苔寺(山梨県上野原市)
■臨済宗円覚寺派
大本山:円覚寺(神奈川県鎌倉市)
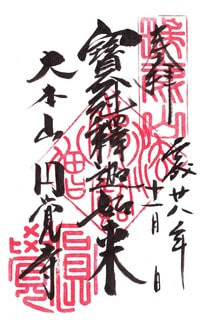
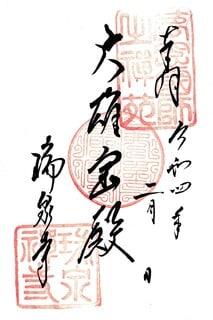
【写真 上(左)】 瑞鹿山 円覚興聖禅寺(鎌倉市山ノ内)
【写真 下(右)】 錦屏山 瑞泉寺(鎌倉市二階堂)
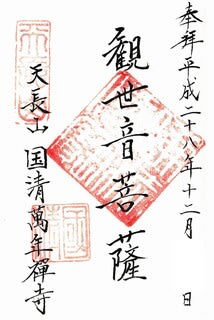

【写真 上(左)】 天長山 国清寺(静岡県伊豆の国市)
【写真 下(右)】 月海山 法身寺(新宿区原町)
■臨済宗建長寺派
大本山:建長寺(神奈川県鎌倉市)
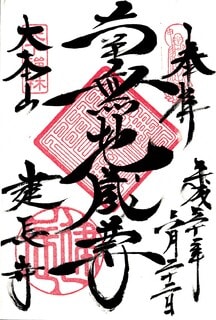
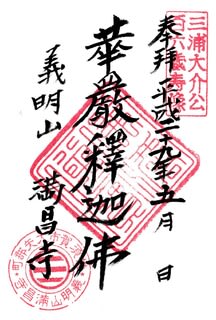
【写真 上(左)】 巨福山 建長寺(鎌倉市山ノ内)
【写真 下(右)】 義明山 満昌寺(神奈川県横須賀市)

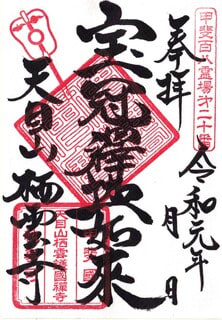
【写真 上(左)】 青龍山 吉祥寺(群馬県川場村)
【写真 下(右)】 天目山 栖雲寺(山梨県甲州市)
■臨済宗天龍寺派
大本山:天龍寺(京都市右京区)
■臨済宗相国寺派
大本山:相国寺(京都市上京区)
■臨済宗東福寺派
大本山:東福寺(京都市東山区)
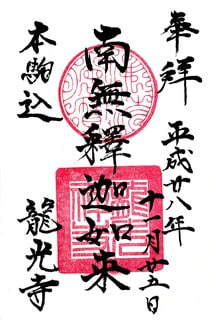
天澤山 龍光寺(文京区本駒込)
■臨済宗建仁寺派
大本山:建仁寺(京都市東山区)
■臨済宗国泰寺派
本山:国泰寺(富山県高岡市)
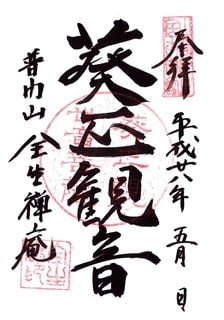
普門山 全生庵(台東区谷中)
■臨済宗大徳寺派
大本山:大徳寺(京都市北区)
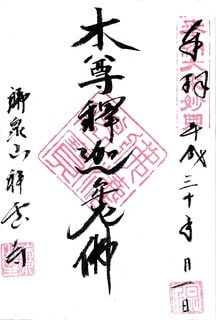

【写真 上(左)】 瑞泉山 祥雲寺(渋谷区広尾)
【写真 下(右)】 瑞泉山 高源院(世田谷区北烏山)

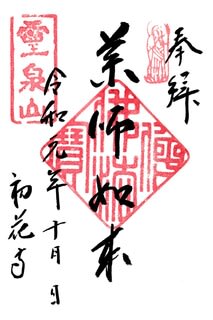
【写真 上(左)】 多聞山 天現寺(港区南麻布)
【写真 下(右)】 霊泉山 鎖雲寺(神奈川県箱根町)
■臨済宗永源寺派
大本山:永源寺(滋賀県東近江市)
■臨済宗向嶽寺派
大本山:向嶽寺(山梨県甲州市)
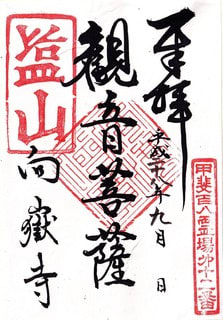
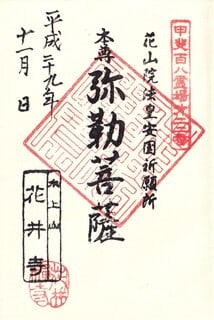
【写真 上(左)】 塩山 向嶽寺(山梨県甲州市)
【写真 下(右)】 水上山 花井寺(山梨県大月市)
■臨済宗相国寺派
大本山:相国寺(京都市上京区)
■臨済宗方広寺派
大本山:方広寺(静岡県浜松市北区)
■臨済宗佛通寺派
大本山:佛通寺(広島県三原市)
■臨済宗興聖寺派
本山:興聖寺(京都市上京区)
■臨済宗白隠派
大本山:松蔭寺(静岡県沼津市)

鵠林山 松蔭寺(静岡県沼津市)
■曹洞宗
法統:達磨大師→洞山良价→天童如浄→ 道元禅師
開祖:洞山良价(唐)
開祖:道元禅師(高祖承陽大師)(日本)(1200-1253年)
所依教典:
教義の特徴:悟り、座禅、只管打坐、正伝の仏法
大本山:永平寺(福井県永平寺町)
大本山:總持寺(横浜市鶴見区)


【写真 上(左)】 諸嶽山 總持寺(横浜市鶴見区)
【写真 下(右)】 大雄山 金剛壽院 最乗寺(神奈川県南足柄市)


【写真 上(左)】 福地山 修禅萬安禅寺(修禅寺)(静岡県伊豆市)
【写真 下(右)】 長昌山 龍穏寺(埼玉県越生町)


【写真 上(左)】 大平山 大中寺(栃木県栃木市)
【写真 下(右)】 安国山 總寧寺(千葉県市川市)
■黄檗宗
法統:(黄檗希運)→隠元隆琦
開祖:隠元隆琦(明→日本)(1592-1673年)
所依教典:
教義の特徴:臨済宗に近い、混淆禅、普茶料理、煎茶道
大本山:萬福寺(京都府宇治市)


【写真 上(左)】 少林山 達磨寺(群馬県高崎市)
【写真 下(右)】 牛頭山 弘福寺(墨田区向島)
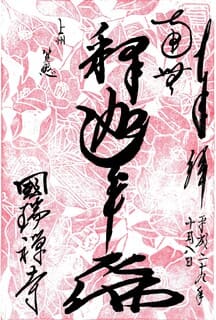

【写真 上(左)】 鳳陽山 国瑞寺(群馬県みどり市)
【写真 下(右)】 紫雲山 瑞聖寺(黄檗宗系単立)(港区白金台)
〔日蓮宗系〕
■日蓮宗
法統:天台の教観二門(教相門・止観門)→日蓮聖人
宗祖:日蓮聖人(1222-1282年)
立教開宗:1253年 日蓮聖人
所依教典:『妙法蓮華経』
教義の特徴:題目「南無妙法蓮華経」、二乗作仏、久遠実成など
大本山:久遠寺(山梨県身延町)
●日蓮宗は御首題(南無妙法蓮華経)がメインですが、専用の御首題帳がない場合、御朱印の「妙法」となったり不授与の場合もあります。
鬼子母神や帝釈天など、日蓮宗ゆかりの尊格の御朱印授与も多くみられます。
主印は多彩です。
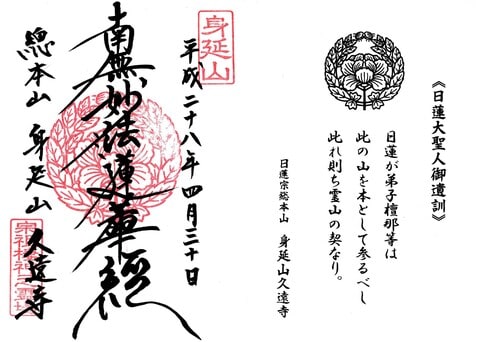
身延山 久遠寺(山梨県身延町)
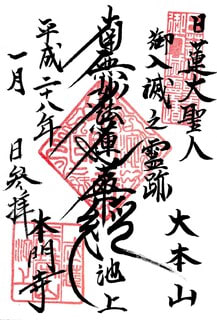
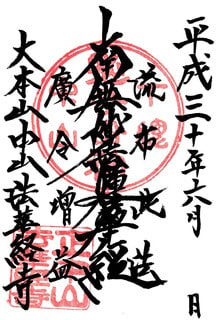
【写真 上(左)】 長栄山 大国院 池上本門寺(大田区池上)
【写真 下(右)】 正中山 法華経寺(千葉県市川市)
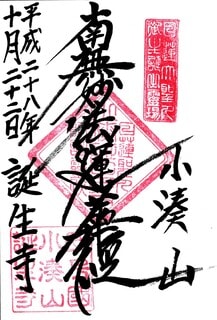

【写真 上(左)】 小湊山 誕生寺(千葉県鴨川市)
【写真 下(右)】 千光山 清澄寺(千葉県鴨川市)
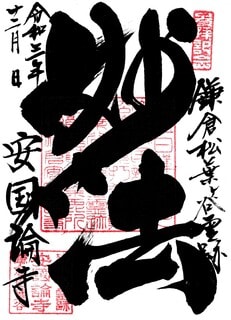

【写真 上(左)】 妙法華経山 安国論寺の御朱印(鎌倉市大町)
【写真 下(右)】 慈雲山 瑞輪寺の御朱印(台東区谷中)

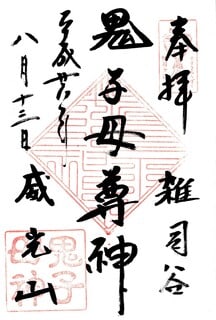
【写真 上(左)】 経栄山 題経寺(柴又帝釈天)(葛飾区柴又)
【写真 下(右)】 威光山 法明寺 鬼子母神堂(豊島区雑司ヶ谷)
〔法華宗系〕
●法華宗の御首題、御朱印は日蓮宗とほぼ同様です。
■法華宗本門流
法統:日蓮上人→日隆聖人
宗祖:日蓮聖人(1222-1282年)
門祖:日隆聖人(1385-1464年)
大本山:光長寺(静岡県沼津市)
大本山:鷲山寺(千葉県茂原市)
大本山:本能寺(京都市中京区)
大本山:本興寺(兵庫県尼崎市)
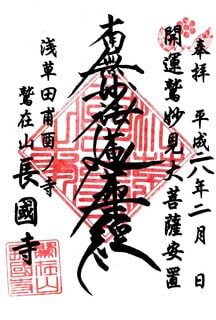
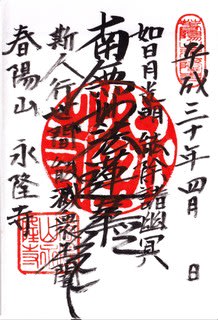
【写真 上(左)】 鷲在山 長國寺(台東区千束)
【写真 下(右)】 春陽山 永隆寺(世田谷区北烏山)
■法華宗陣門流
法統:日蓮聖人→日朗上人→日陣上人
宗祖:日蓮聖人(1222-1282年)
門祖:日陣上人(1339-1419年)
総本山:本成寺(新潟県三条市)


【写真 上(左)】 徳栄山 総持院 本妙寺(豊島区巣鴨)
【写真 下(右)】 俎岩山 蓮着寺(静岡県伊東市)
■顕本法華宗
法統:日蓮聖人→日什上人
宗祖:日蓮聖人(1222-1282年)
開祖:日什上人(1314-1392年)
総本山:妙満寺(京都市左京区)


【写真 上(左)】 鳳凰山 天妙国寺(品川区南品川)
【写真 下(右)】 長遠山 常楽寺(新宿区原町)
■本門佛立宗
法統:日蓮聖人→長松清風(日扇)
宗祖:日蓮聖人(1222-1282年)
開祖:長松清風(日扇)(1817-1890年)
大本山:宥清寺(京都市上京区)
■本門法華宗
法統:日蓮聖人→日隆上人
宗祖:日蓮聖人(1222-1282年)
門祖:日隆上人(1385-1464年)
大本山:妙蓮寺(京都市上京区)
〔富士門流・日興門流/興門八本山〕
・富士(上条)大石寺(日蓮正宗/富士五山)(静岡県富士宮市)
・下条妙蓮寺(日蓮正宗/富士五山)(静岡県富士宮市)
・北山本門寺(日蓮宗/富士五山)(静岡県富士宮市)
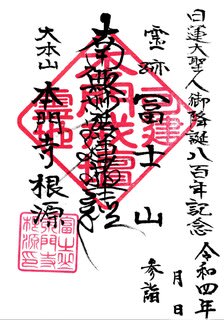
【写真 上(左)】 北山本門寺(静岡県富士宮市)
・小泉久遠寺(日蓮宗/富士五山)(静岡県富士宮市)
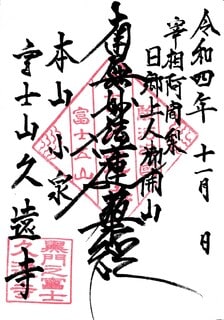
小泉久遠寺(静岡県富士宮市)
・西山本門寺(単立、法華宗興門派/富士五山)(静岡県富士宮市)
・伊豆實成寺(日蓮宗)(静岡県伊豆市)
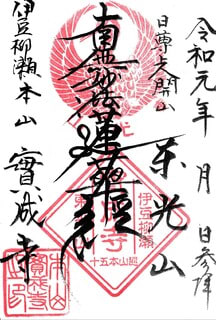
東光山 實成寺(静岡県伊豆市)
・保田妙本寺(単立)(千葉県鋸南町)
・京都要法寺(日蓮本宗)(京都市左京区)
-------------------------
2022/11/06 UP
■ 日本仏教13宗派を完全解説! 仏教 | 宗教 | 日本史
■ 【仏教】仏教の宗派を知る 前編
-----------------
「宗派 御朱印」でぐぐると、この記事→「御朱印帳の使い分け」がけっこう上位にくるので、日本仏教13宗派毎に代表的な御朱印をまとめてみます。
今回は首都圏に限定してのご紹介です。
(公財)全日本仏教会公式Webの「宗派一覧」には13どころか、50を超える宗派が掲載されています。
こちらのデータをベースにいくつか追加をした下記リストに沿って、ご紹介していきます。
(記載順は年代順とし、同年代の宗派については原則として上記資料を踏襲しました。)
なお、日本仏教13宗派は、現代でも大きな宗派として存在する法相宗、華厳宗、律宗、天台宗、真言宗、融通念仏宗、浄土宗、浄土真宗、時宗、臨済宗、曹洞宗、黄檗宗、日蓮宗をさすようです。
------------------------------
■ 中国からの系譜
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)「中国十三宗」』
01.成実宗 → 三論宗の付宗(寓宗)に
02.三論宗 → 南都六宗
03.毘曇宗(倶舎宗) → 法相宗(南都六宗)の付宗(寓宗)に
04.地論宗 → 華厳宗(南道派)
05.摂論宗 → 法相宗(南都六宗)に吸収
06.法相宗 → 南都六宗
07.律宗 → 南都六宗
08.華厳宗 → 南都六宗
09.涅槃宗 → 天台宗に吸収
10.天台宗 → 天台宗
11.密宗 → 真言宗・天台宗
12.禅宗 → 禅宗
13.浄土宗 → 浄土教(浄土宗、(浄土)真宗、時宗、融通念仏宗など)
------------------------------
※法統、宗祖派祖、立宗立派の時期、所依教典などは、『日本仏教思想のあゆみ』(竹村牧男氏著、講談社学術文庫)およびWikipediaに拠りました。
【奈良仏教】
〔南都六宗系〕
※南都六宗:三論宗、成実宗、法相宗、倶舎宗、華厳宗、律宗
※付宗(寓宗):独立せずに他宗に付属している宗
■(三論宗)
法統:インド中観派・龍樹→嘉祥大師吉蔵
宗祖派祖:嘉祥大師吉蔵
伝来:625年 慧漑(第一伝)
所依教典:『中論』『十二門論』『百論』
教義の特徴:四種釈義、破邪顕正など

飯盛山 修福寺(静岡県南伊豆町)
※ 曹洞宗ですが、三論宗の流れと伝わります。
■(成実宗) 三論宗の付宗(寓宗)
■法相宗
法統:インド瑜伽行派→玄奘三蔵→慈恩大師基
宗祖派祖:慈恩大師基
伝来:道招(629-700年)(第一伝)
所依教典:『成唯識論』
教義の特徴:唯識思想など
大本山:薬師寺(奈良市西ノ京町)
大本山:興福寺(奈良市登大路町)


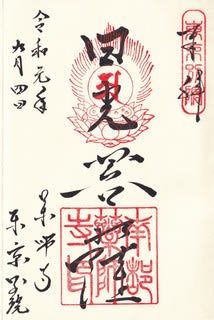
薬師寺東京別院(品川区東五反田)

水雲山 潮音寺(奈良薬師寺 東関東別院)(茨城県潮来市)
■(倶舎宗) 法相宗の付宗(寓宗)
■ 聖徳宗
宗祖:聖徳太子
立宗:昭和25年法相宗から独立
所依教典:『三経義疏』
大本山:法隆寺(奈良県斑鳩町)
■華厳宗
法統:インドor西域→(地論宗)→智儼
宗祖派祖:法蔵
伝来:736年 審祥・良弁
所依教典:『華厳経』
教義の特徴:重々無尽の縁起、円教・別教一乗など
大本山:東大寺(奈良市雑司町)
■律宗
法統:四分律宗・南山律宗→(戒律学)→文綱
宗祖派祖:
伝来:753年 鑑真
所依教典:『四分律』
教義の特徴:戒律
総本山:唐招提寺(奈良市五条町)
■(北京律)
■(南都律)
※下記は律宗の流れを汲んでいるため、【奈良仏教】に記載しました。
■真言律宗
法統:四分律宗・南山律宗→(戒律学)→文綱
宗祖派祖:高祖弘法大師、叡尊(興正菩薩)
所依教典:『十誦律』
教義の特徴:戒律、具足戒、三昧耶戒など
総本山:西大寺(奈良市西大寺芝町)

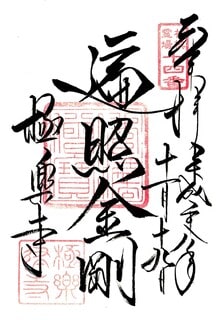
【写真 上(左)】 金沢山 彌勒院 称名寺(横浜市金沢区)
【写真 下(右)】 霊鷲山 感応院 極楽律寺(鎌倉市極楽寺)
■真言宗霊雲寺派
法統:真言律宗→
宗祖派祖:高祖弘法大師、叡尊(興正菩薩)
立派:昭和22年真言律宗から独立
所依教典:『十誦律』?
教義の特徴:戒律、具足戒、三昧耶戒など
総本山:霊雲寺(文京区湯島)

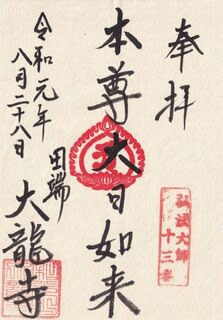
【写真 上(左)】 宝林山 大悲心院 霊雲寺(文京区湯島)
【写真 下(右)】 和光山 興源院 大龍寺(北区田端)
【平安仏教】
〔天台宗系〕
■天台宗
法統:智顗(天台大師)・天台教学
宗祖派祖:(智顗)
伝来:806年 伝教大師最澄
天台密教将来:最澄・円仁
所依教典:『妙法蓮華経』『涅槃経』など
教義の特徴:四宗兼学、止観行など
総本山:延暦寺(滋賀県大津市)
●天台宗の御朱印尊格は多彩です。
特徴的な尊格に「元三大師」があります。
主印は御寶印(種子)が多くなっています。


【写真 上(左)】 東叡山 寛永寺(台東区上野公園)
【写真 下(右)】 日光山 輪王寺(栃木県日光市)


【写真 上(左)】 星野山 無量寿寺 中院(川越市小仙波町)
【写真 下(右)】 浮岳山 昌楽院 深大寺(調布市深大寺元町)
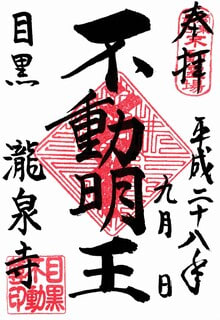

【写真 上(左)】 泰叡山 護國院 瀧泉寺(目黒不動尊)(目黒区下目黒)
【写真 下(右)】 小野寺山 転法輪院 大慈寺(栃木県栃木市)
■天台真盛宗
法統:天台教学→真盛
宗祖派祖:真盛
(立宗):1486年 真盛
所依教典:
教義の特徴:天台念仏、戒律など
総本山:西教寺(滋賀県大津市)


【写真 上(左)】 天羅山 養善院 真盛寺(杉並区梅里)
【写真 下(右)】 率渓山 新善光寺(横浜市南区)
■天台寺門宗
法統:智顗(天台大師)・天台教学→円珍
宗祖派祖:智証大師円珍
立宗:智証大師円珍(814-891年)
所依教典:『妙法蓮華経』など
教義の特徴:円・密・禅・戒・修験五法門など
総本山:三井寺(滋賀県大津市)
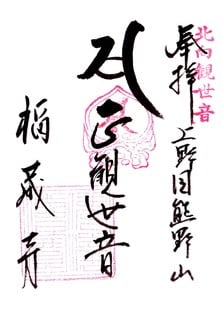

熊野山 福蔵寺(群馬県高山村)
明光山 大善院(さいたま市浦和区)
■聖観音宗
立宗:昭和25年天台宗より独立
本山:浅草寺(台東区浅草)
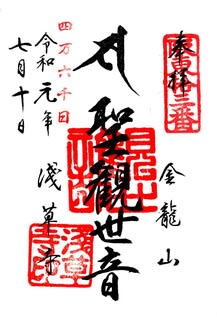
金龍山 浅草寺(台東区浅草)
■金峯山修験本宗
立宗:昭和23年、天台宗から分派独立し大峯修験宗
昭和27年、金峯山修験本宗と改称
総本山:金峯山寺(奈良県吉野町)
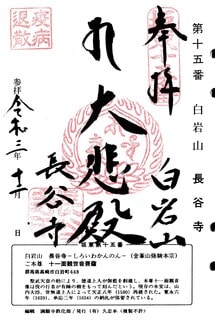

【写真 上(左)】 白岩山 長谷寺(群馬県高崎市)
【写真 下(右)】 大照山 相慈寺(品川区二葉)
■本山修験宗
法統等:智証大師円珍→増誉
寺格等:聖護院門跡、天台宗寺門派三門跡、修験道本山派
総本山:聖護院(京都市左京区)
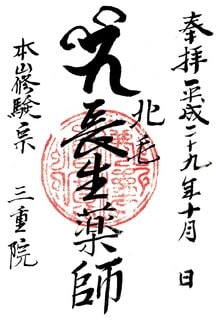
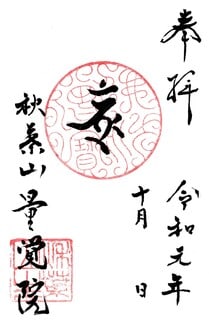
【写真 上(左)】 長生山 瑠璃光寺 三重院(群馬県みなかみ町)
【写真 下(右)】 秋葉山 量覚院(小田原市板橋)
■和宗
総本山:四天王寺(大阪市天王寺区)
■孝道教団
開宗:昭和11年岡野正道始祖(天台宗大僧正)
孝道山 本仏殿(横浜市神奈川区)

■妙見宗
立宗:昭和21年天台宗から独立
総本山:本瀧寺(大阪府能勢町)
■念法眞教
総本山:金剛寺(大阪市鶴見区)
■天台宗弾誓派

【写真 上(左)】 無常山 一之澤院 浄発願寺(神奈川県伊勢原市)
〔真言宗系〕
法統:インド密教→竜猛→竜智→金剛智→不空→恵果→空海
宗祖派祖:付法の八祖
立教開宗:弘法大師空海(774-835年)
所依教典:『大日経』『金剛頂経』『理趣経』など
教義の特徴:事相と教相、身口意三密など
総本山:教王護国寺(東寺)(京都市南区)
●真言宗の御朱印尊格は多彩です。
特徴的な尊格に「弘法大師」「遍照金剛」があります。
大日如来、不動明王の御朱印も多くみられます。
主印は御寶印(種子)が多くなっています。
〔古義真言宗系〕
教義の特徴:事相と教相、身口意三密、本地身説法など
■高野山真言宗
法統等:古義真言宗総本山・金剛峯寺
総本山:金剛峯寺(和歌山県高野町)
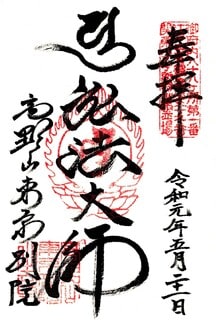

【写真 上(左)】 高野山 東京別院(港区高輪)
【写真 下(右)】 同

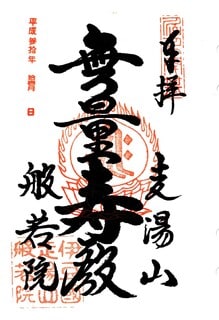
【写真 上(左)】 飯盛山 仁王院 青蓮寺(鎌倉市手広)
【写真 下(右)】 走湯山 般若院(静岡県熱海市)
■真言宗大覚寺派
法統等:宇多帝、後嵯峨帝、亀山帝、御宇多帝、保寿院流
大本山:大覚寺(京都市右京区)


【写真 上(左)】 雨降山 大山寺(神奈川県伊勢原市)
【写真 下(右)】 天衛山 多聞院 福寿寺(鎌倉市大船)


【写真 上(左)】 南向山 帰命院 補陀洛寺(鎌倉市材木座)
【写真 下(右)】 小動山 浄泉寺(鎌倉市腰越)
■真言宗善通寺派
法統等:増俊僧正、成尊、随心院(仁海)流、小野流、旧・小野派
総本山:善通寺(香川県善通寺市)

朝日山 平等院(埼玉県飯能市)
■真言宗御室派
法統等:寛平法皇(宇多天皇)、紫金台寺御室、広沢流
総本山:仁和寺(京都市右京区)

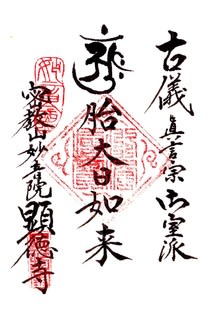
【写真 上(左)】 萬昌山 金剛幢院 圓満寺(文京区湯島)
【写真 下(右)】 密教山 如音院 顕徳寺(群馬県東吾妻町)
■真言宗山階派
法統等:承俊、済高、寛信、勧修寺流
大本山:勧修寺(京都市山科区)
■真言宗泉涌寺派
法統等:月輪大師俊芿、四宗兼学、皇室御陵所
総本山:泉涌寺(京都市東山区)

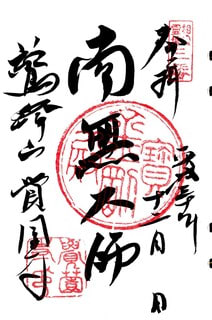
【写真 上(左)】 泉谷山 浄光明寺(鎌倉市扇ガ谷)
【写真 下(右)】 鷲峰山 覚園寺(鎌倉市二階堂)
■真言宗醍醐派
法統等:理源大師聖宝、義演准后、小野流、恵印法流、修験道当山派
総本山:醍醐寺(京都市伏見区)
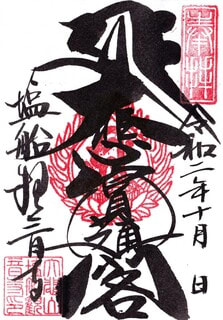
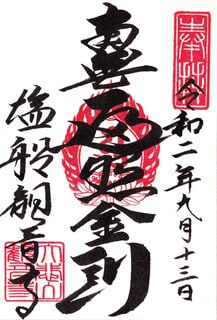
【写真 上(左)】 大悲山 塩船観音寺(東京都青梅市)
【写真 下(右)】 同


【写真 上(左)】 海照山 普門院 品川寺(品川区南品川)
【写真 下(右)】 神谷山 成就院(埼玉県三郷市)
■真言宗国分寺派
法統等:日本法相宗の祖・道昭、勅願道場
大本山:国分寺(大阪市北区)

應雲山 感応院(さいたま市見沼区)
■真言宗須磨寺派
法統等:淳和帝、光孝帝
大本山:須磨寺(神戸市須磨区)
■真言宗中山寺派
法統等:聖徳太子、源氏祈願所
大本山:中山寺(兵庫県宝塚市)
■真言三宝宗
法統等:宇多天皇勅願、三宝荒神社、神仏習合、三宝三福
大本山:清荒神清澄寺(兵庫県宝塚市)

瑠璃山 南谷寺 東光院(神奈川県小田原市)
■信貴山真言宗
法統等:聖徳太子、毘沙門天(多聞天)
大本山:朝護孫子寺(奈良県平群町)


【写真 上(左)】 慈眼山 圓通寺(埼玉県川島町)
【写真 下(右)】 頂寳山 弘福院(千葉県袖ケ浦市)
■真言宗犬鳴派
法統等:役小角、葛城二十八宿修験道
大本山:七宝瀧寺(大阪府泉佐野市)
■東寺真言宗
法統等:教王護国寺(東寺)、真言密教の根本道場
総本山:教王護国寺(京都市南区)
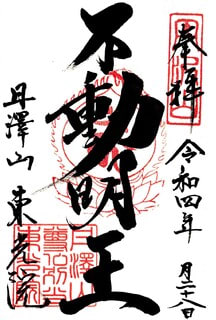

【写真 上(左)】 丹澤山 東光院(神奈川県山北町)
【写真 下(右)】 醫王山 薬師院 圓福寺(小田原市本町)
■真言宗東寺派
法統等:教王護国寺(東寺)、真言密教の根本道場
別格本山:正法寺(京都市西京区)

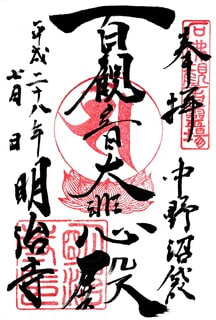
【写真 上(左)】 飯泉山 勝福寺(小田原市飯泉)
【写真 下(右)】 新浮侘落山 世尊院 明治寺(中野区沼袋)
〔新義真言宗系〕
法統等:弘法大師空海→興教大師覚鑁→頼瑜
教義の特徴:事相と教相、身口意三密、加持身説法など
■真言宗智山派
法統等:弘法大師空海→興教大師覚鑁→玄宥
総本山:智積院(京都市東山区)
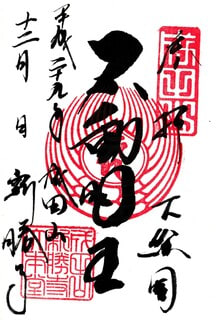

【写真 上(左)】 成田山 新勝寺(千葉県成田市)
【写真 下(右)】 金剛山 平間寺(川崎大師)(川崎市川崎区)


【写真 上(左)】 高尾山 薬王院(八王子市高尾町)
【写真 下(右)】 高幡山 明王院 金剛寺(高幡不動尊)(日野市高幡)
■真言宗豊山派
法統等:弘法大師空海→興教大師覚鑁→専誉僧正
総本山:長谷寺(奈良県桜井市)


【写真 上(左)】 神齢山 悉地院 護国寺(文京区大塚)
【写真 下(右)】 五智山 遍照院 總持寺(西新井大師)(足立区西新井)
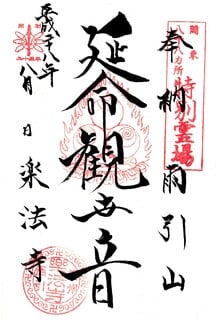
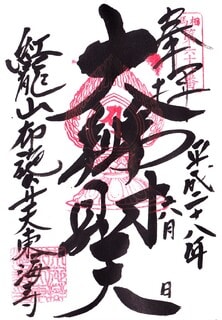
【写真 上(左)】 雨引山 楽法寺(茨城県桜川市)
【写真 下(右)】 紅龍山 布施弁天 東海寺(千葉県柏市)
■真言宗大日派
法統等:弘法大師空海→興教大師覚鑁→専誉僧正
(真言宗豊山派から独立)
根本道場:鑁阿寺(栃木県足利市)

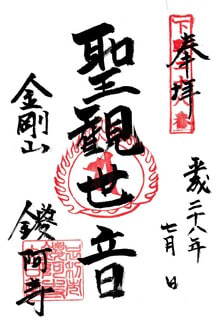
【写真 上(左)】 金剛山 仁王院 法華坊 鑁阿寺(栃木県足利市)
【写真 下(右)】 同
■真言宗室生寺派
法統等:弘法大師空海→興教大師覚鑁→専誉僧正
(真言宗豊山派から独立)
大本山:室生寺(奈良県宇陀市)
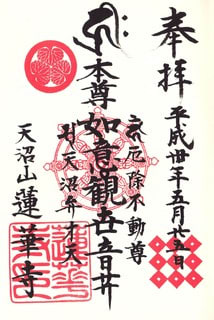

【写真 上(左)】 天沼山 蓮華寺(杉並区本天沼)
【写真 下(右)】 光明山 真言院 荘厳寺(渋谷区本町)
■新義真言宗
法統等:弘法大師空海→興教大師覚鑁→頼瑜
総本山:根來寺(和歌山県岩出市)
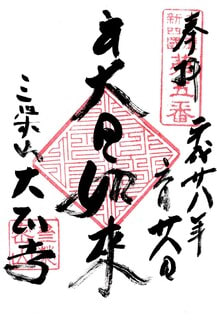

【写真 上(左)】 三栄山 大正寺(調布市調布ケ丘)
【写真 下(右)】 新照山 蓮華寺(横浜市港北区)


【写真 上(左)】 長谷山 元興寺 加納院(台東区谷中)
【写真 下(右)】 法然山 伝灯寺 釋藏院(千葉県市原市)
【鎌倉仏教】
〔浄土宗系〕
■浄土宗
法統:法然上人→弁長・良忠(鎮西義)→良暁(白旗派)
宗祖派祖:法然上人
立教開宗:1175年 法然上人
所依教典:『浄土三部経』『観無量寿経疏』『選択本願念仏集』など
教義の特徴:念仏・御名号「南無阿弥陀仏」、他力本願
総本山:知恩院(京都市東山区)
●浄土宗の御朱印尊格は阿弥陀如来が多くなっています。
特徴的な尊格に「南無阿弥陀佛」(六字御名号)があります。
主印は三寶印(佛法僧寶)がメインです。
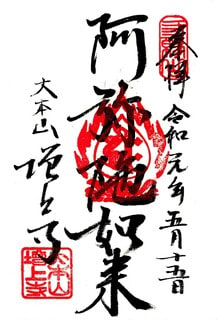
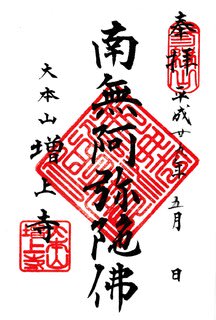
三縁山 広度院 増上寺(港区芝公園)


天照山 蓮華院 光明寺(鎌倉市材木座)


【写真 上(左)】 無量山 寿経寺 伝通院(文京区小石川)
【写真 下(右)】 寿亀山 天樹院 (飯沼)弘経寺(鎮西義白旗派流/茨城県常総市)

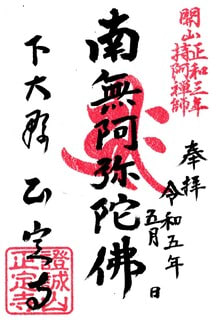
【写真 上(左)】 祇園山 田代寺(長楽寺) 安養院(鎮西義名越派(善導寺義)流/鎌倉市大町)
【写真 下(右)】 証誠山 等持院 (大野)正定寺(鎮西義藤田派流/茨城県古河市)

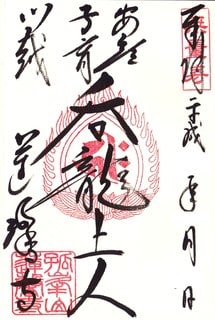
【写真 上(左)】 明顯山 善久院 祐天寺(目黒区中目黒)
【写真 下(右)】 孤峰山 宝池院 蓮馨寺(川越市蓮雀町)
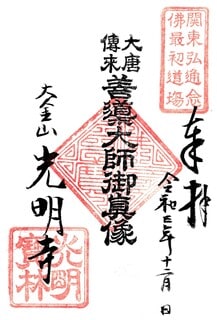

【写真 上(左)】 大金山 宝幢院 光明寺(大田区鵜の木)
【写真 下(右)】 三縁山 増上寺 妙定院(港区芝公園)
■浄土宗西山禅林寺派
法統:法然上人→証空(西山義)→浄音(西谷義)
総本山:永観堂 禅林寺(京都市左京区)
■浄土宗西山深草派
法統:法然上人→証空(西山義)→立信(深草義)
総本山:誓願寺(京都市中京区)
■西山浄土宗
法統:法然上人→証空(西山義)→浄音(西谷義)
総本山:光明寺(京都府長岡京市)
〔(浄土)真宗系〕
法統:法然上人→親鸞上人
宗祖派祖:親鸞上人
立教開宗:1224年 親鸞上人
所依教典:『浄土三部経』『教行信証』『選択本願念仏集』など
教義の特徴:念仏・御名号「南無阿弥陀仏」、絶対他力(本願)
●(浄土)真宗は教義上、御朱印を授与されない寺院が多くみられます。
授与される場合の尊格や主印は多彩です。
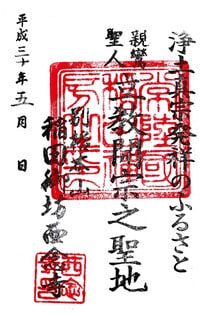
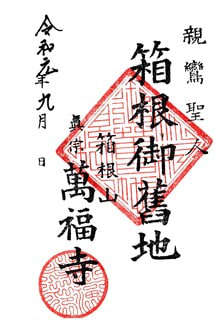
【写真 上(左)】 稲田山 西念寺(稲田御坊)(茨城県笠間市)
【写真 下(右)】 箱根山 萬福寺(箱根御舊地)(神奈川県箱根町)
■浄土真宗本願寺派 (「お西」「本派」)
本山:本願寺(京都市下京区)


【写真 上(左)】 築地本願寺(中央区築地)
【写真 下(右)】 麻布山 善福寺(港区元麻布)
■真宗大谷派 (「お東」「大派」)
本山:東本願寺(京都市下京区)
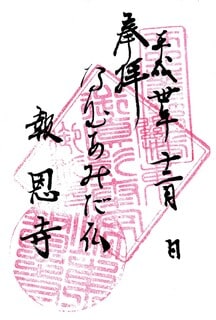
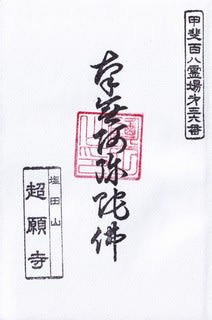
【写真 上(左)】 高龍山 謝徳院 坂東報恩寺(台東区東上野)
【写真 下(右)】 塩田山 超願寺(山梨県笛吹市)
■浄土真宗東本願寺派
本山:浄土真宗東本願寺派本山東本願寺(台東区西浅草)
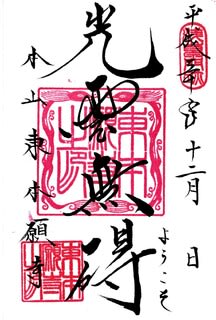

【写真 上(左)】 東本願寺(台東区西浅草)
【写真 下(右)】 牛久大佛(茨城県牛久市)
■真宗高田派
法統:親鸞上人→顕智(高田門徒)
本山:専修寺(三重県津市)

高田山 専修寺(栃木県真岡市)
■真宗佛光寺派
本山:佛光寺(京都市下京区)
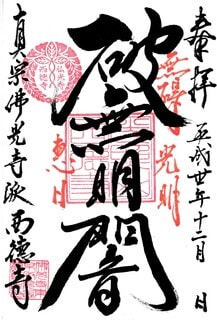
光照山 西徳寺(台東区竜泉)
■真宗興正派
本山:興正寺(京都市下京区)
■真宗木辺派
本山:錦織寺(滋賀県野州市)
〔時宗系〕
■時宗
法統:浄土宗西山義→一遍上人→他阿(遊行上人)
開祖:一遍上人(1239-1289年)
所依教典:『観経疏』など
教義の特徴:念仏・御名号「南無阿弥陀仏」、他力本願、融通念仏、踊念仏
総本山:清浄光寺(遊行寺)(神奈川県藤沢市)
●時宗の御朱印尊格は阿弥陀如来が多くなっています。
特徴的な尊格に「南無阿弥陀佛」(六字御名号)があります。
主印は三寶印(佛法僧寶)がメインです。

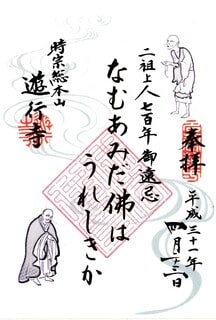
【写真 上(左)】 藤沢山 無量光院 清浄光寺(遊行寺)(神奈川県藤沢市)
【写真 下(右)】 同

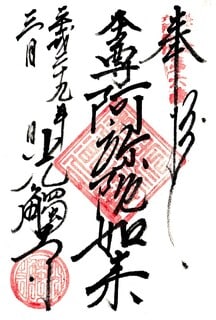
【写真 上(左)】 河越山 三芳野院 常楽寺(川越市上戸)
【写真 下(右)】 岩蔵山 長春院 光觸寺(鎌倉市十二所)
〔融通念佛宗系〕
■融通念佛宗
法統:天台宗→良忍(大念仏宗)→大通
開宗:1127年 聖応大師良忍
所依教典:『華厳経』『法華経』など
教義の特徴:念仏「南無阿弥陀仏」、他力本願、融通念仏
総本山:大念佛寺(大阪市平野区)
〔禅宗系〕
□臨済宗
法統:達磨大師→臨済義玄→明菴栄西
宗祖:臨済義玄(唐)
開祖:明菴栄西(日本)(1141-1215年)
所依教典:
教義の特徴:悟り、座禅、公案、法嗣
●禅宗の御朱印尊格は釋迦牟尼佛(南無釋迦牟尼佛)が多くなっています。
密教系からかわった寺院では以前の御本尊を踏襲し、そちらの御朱印となるケースが多くみられます。
主印は三寶印(佛法僧寶)がメインです。
■臨済宗妙心寺派
大本山:妙心寺(京都市右京区)

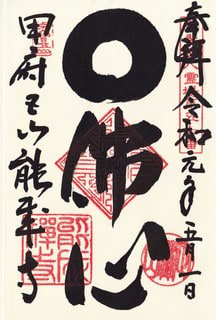
【写真 上(左)】 金鳳山 平林寺(埼玉県新座市)
【写真 下(右)】 定林山 能成寺(山梨県甲府市)
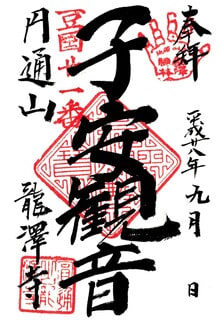
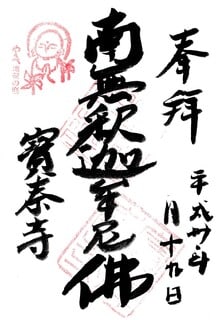
【写真 上(左)】 圓通山 龍澤寺(静岡県三島市)
【写真 下(右)】 金剛山 寶泰寺(静岡市葵区)
■臨済宗南禅寺派
大本山:南禅寺(京都市左京区)

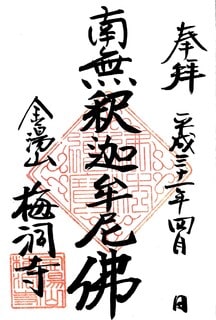
【写真 上(左)】 勝林山 金地院(港区芝公園)
【写真 上(左)】 金湯山 梅洞寺(八王子市打越町)


【写真 上(左)】 龍王山 宝円寺(埼玉県小鹿野町)
【写真 下(右)】 飯盛山 青苔寺(山梨県上野原市)
■臨済宗円覚寺派
大本山:円覚寺(神奈川県鎌倉市)
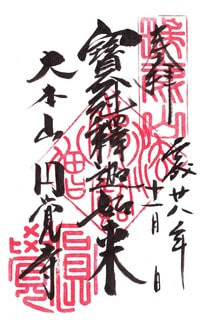
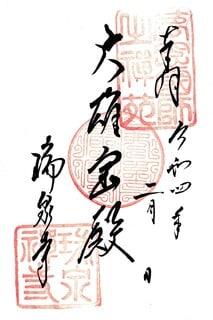
【写真 上(左)】 瑞鹿山 円覚興聖禅寺(鎌倉市山ノ内)
【写真 下(右)】 錦屏山 瑞泉寺(鎌倉市二階堂)
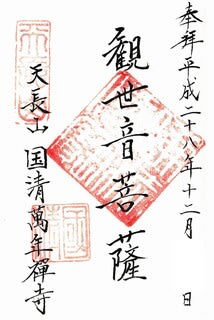

【写真 上(左)】 天長山 国清寺(静岡県伊豆の国市)
【写真 下(右)】 月海山 法身寺(新宿区原町)
■臨済宗建長寺派
大本山:建長寺(神奈川県鎌倉市)
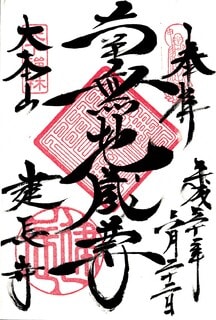
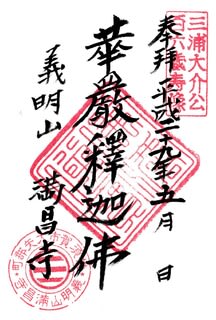
【写真 上(左)】 巨福山 建長寺(鎌倉市山ノ内)
【写真 下(右)】 義明山 満昌寺(神奈川県横須賀市)

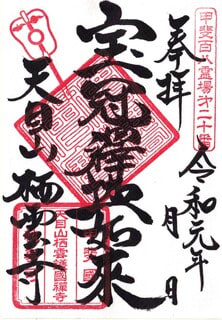
【写真 上(左)】 青龍山 吉祥寺(群馬県川場村)
【写真 下(右)】 天目山 栖雲寺(山梨県甲州市)
■臨済宗天龍寺派
大本山:天龍寺(京都市右京区)
■臨済宗相国寺派
大本山:相国寺(京都市上京区)
■臨済宗東福寺派
大本山:東福寺(京都市東山区)
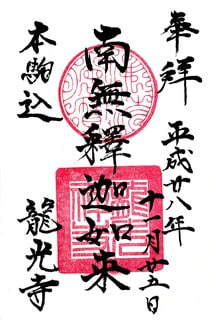
天澤山 龍光寺(文京区本駒込)
■臨済宗建仁寺派
大本山:建仁寺(京都市東山区)
■臨済宗国泰寺派
本山:国泰寺(富山県高岡市)
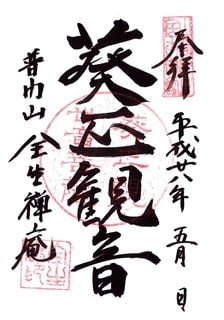
普門山 全生庵(台東区谷中)
■臨済宗大徳寺派
大本山:大徳寺(京都市北区)
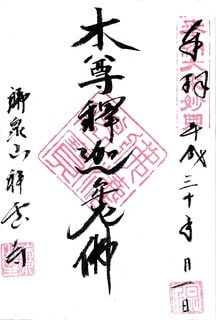

【写真 上(左)】 瑞泉山 祥雲寺(渋谷区広尾)
【写真 下(右)】 瑞泉山 高源院(世田谷区北烏山)

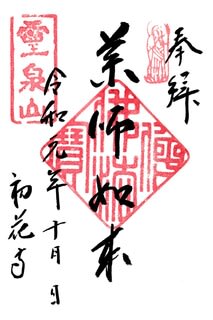
【写真 上(左)】 多聞山 天現寺(港区南麻布)
【写真 下(右)】 霊泉山 鎖雲寺(神奈川県箱根町)
■臨済宗永源寺派
大本山:永源寺(滋賀県東近江市)
■臨済宗向嶽寺派
大本山:向嶽寺(山梨県甲州市)
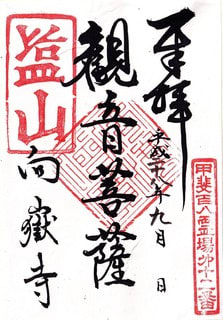
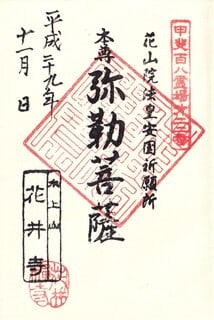
【写真 上(左)】 塩山 向嶽寺(山梨県甲州市)
【写真 下(右)】 水上山 花井寺(山梨県大月市)
■臨済宗相国寺派
大本山:相国寺(京都市上京区)
■臨済宗方広寺派
大本山:方広寺(静岡県浜松市北区)
■臨済宗佛通寺派
大本山:佛通寺(広島県三原市)
■臨済宗興聖寺派
本山:興聖寺(京都市上京区)
■臨済宗白隠派
大本山:松蔭寺(静岡県沼津市)

鵠林山 松蔭寺(静岡県沼津市)
■曹洞宗
法統:達磨大師→洞山良价→天童如浄→ 道元禅師
開祖:洞山良价(唐)
開祖:道元禅師(高祖承陽大師)(日本)(1200-1253年)
所依教典:
教義の特徴:悟り、座禅、只管打坐、正伝の仏法
大本山:永平寺(福井県永平寺町)
大本山:總持寺(横浜市鶴見区)


【写真 上(左)】 諸嶽山 總持寺(横浜市鶴見区)
【写真 下(右)】 大雄山 金剛壽院 最乗寺(神奈川県南足柄市)


【写真 上(左)】 福地山 修禅萬安禅寺(修禅寺)(静岡県伊豆市)
【写真 下(右)】 長昌山 龍穏寺(埼玉県越生町)


【写真 上(左)】 大平山 大中寺(栃木県栃木市)
【写真 下(右)】 安国山 總寧寺(千葉県市川市)
■黄檗宗
法統:(黄檗希運)→隠元隆琦
開祖:隠元隆琦(明→日本)(1592-1673年)
所依教典:
教義の特徴:臨済宗に近い、混淆禅、普茶料理、煎茶道
大本山:萬福寺(京都府宇治市)


【写真 上(左)】 少林山 達磨寺(群馬県高崎市)
【写真 下(右)】 牛頭山 弘福寺(墨田区向島)
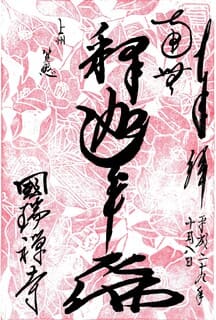

【写真 上(左)】 鳳陽山 国瑞寺(群馬県みどり市)
【写真 下(右)】 紫雲山 瑞聖寺(黄檗宗系単立)(港区白金台)
〔日蓮宗系〕
■日蓮宗
法統:天台の教観二門(教相門・止観門)→日蓮聖人
宗祖:日蓮聖人(1222-1282年)
立教開宗:1253年 日蓮聖人
所依教典:『妙法蓮華経』
教義の特徴:題目「南無妙法蓮華経」、二乗作仏、久遠実成など
大本山:久遠寺(山梨県身延町)
●日蓮宗は御首題(南無妙法蓮華経)がメインですが、専用の御首題帳がない場合、御朱印の「妙法」となったり不授与の場合もあります。
鬼子母神や帝釈天など、日蓮宗ゆかりの尊格の御朱印授与も多くみられます。
主印は多彩です。
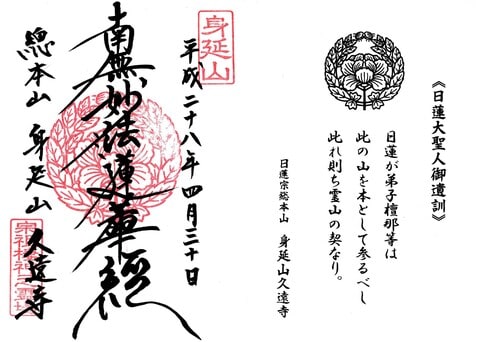
身延山 久遠寺(山梨県身延町)
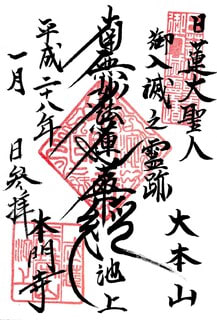
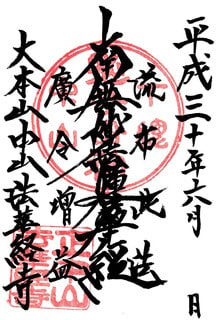
【写真 上(左)】 長栄山 大国院 池上本門寺(大田区池上)
【写真 下(右)】 正中山 法華経寺(千葉県市川市)
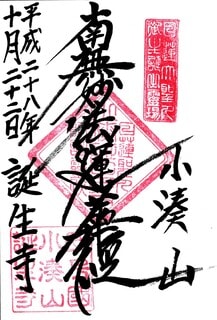

【写真 上(左)】 小湊山 誕生寺(千葉県鴨川市)
【写真 下(右)】 千光山 清澄寺(千葉県鴨川市)
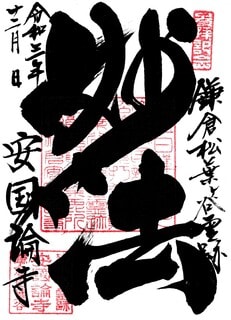

【写真 上(左)】 妙法華経山 安国論寺の御朱印(鎌倉市大町)
【写真 下(右)】 慈雲山 瑞輪寺の御朱印(台東区谷中)

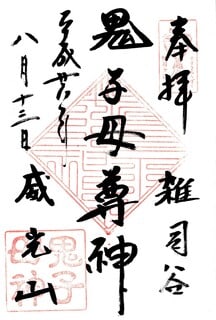
【写真 上(左)】 経栄山 題経寺(柴又帝釈天)(葛飾区柴又)
【写真 下(右)】 威光山 法明寺 鬼子母神堂(豊島区雑司ヶ谷)
〔法華宗系〕
●法華宗の御首題、御朱印は日蓮宗とほぼ同様です。
■法華宗本門流
法統:日蓮上人→日隆聖人
宗祖:日蓮聖人(1222-1282年)
門祖:日隆聖人(1385-1464年)
大本山:光長寺(静岡県沼津市)
大本山:鷲山寺(千葉県茂原市)
大本山:本能寺(京都市中京区)
大本山:本興寺(兵庫県尼崎市)
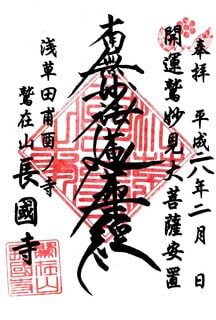
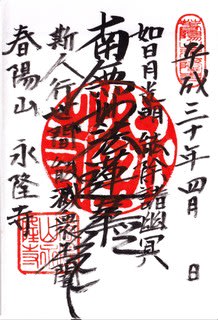
【写真 上(左)】 鷲在山 長國寺(台東区千束)
【写真 下(右)】 春陽山 永隆寺(世田谷区北烏山)
■法華宗陣門流
法統:日蓮聖人→日朗上人→日陣上人
宗祖:日蓮聖人(1222-1282年)
門祖:日陣上人(1339-1419年)
総本山:本成寺(新潟県三条市)


【写真 上(左)】 徳栄山 総持院 本妙寺(豊島区巣鴨)
【写真 下(右)】 俎岩山 蓮着寺(静岡県伊東市)
■顕本法華宗
法統:日蓮聖人→日什上人
宗祖:日蓮聖人(1222-1282年)
開祖:日什上人(1314-1392年)
総本山:妙満寺(京都市左京区)


【写真 上(左)】 鳳凰山 天妙国寺(品川区南品川)
【写真 下(右)】 長遠山 常楽寺(新宿区原町)
■本門佛立宗
法統:日蓮聖人→長松清風(日扇)
宗祖:日蓮聖人(1222-1282年)
開祖:長松清風(日扇)(1817-1890年)
大本山:宥清寺(京都市上京区)
■本門法華宗
法統:日蓮聖人→日隆上人
宗祖:日蓮聖人(1222-1282年)
門祖:日隆上人(1385-1464年)
大本山:妙蓮寺(京都市上京区)
〔富士門流・日興門流/興門八本山〕
・富士(上条)大石寺(日蓮正宗/富士五山)(静岡県富士宮市)
・下条妙蓮寺(日蓮正宗/富士五山)(静岡県富士宮市)
・北山本門寺(日蓮宗/富士五山)(静岡県富士宮市)
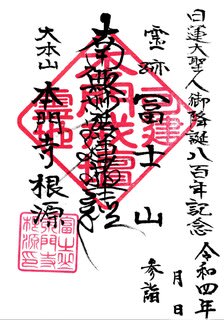
【写真 上(左)】 北山本門寺(静岡県富士宮市)
・小泉久遠寺(日蓮宗/富士五山)(静岡県富士宮市)
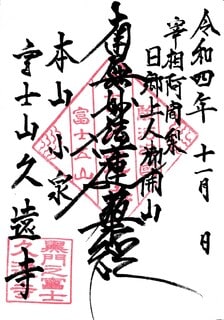
小泉久遠寺(静岡県富士宮市)
・西山本門寺(単立、法華宗興門派/富士五山)(静岡県富士宮市)
・伊豆實成寺(日蓮宗)(静岡県伊豆市)
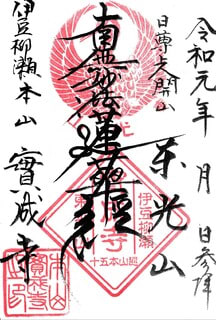
東光山 實成寺(静岡県伊豆市)
・保田妙本寺(単立)(千葉県鋸南町)
・京都要法寺(日蓮本宗)(京都市左京区)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-25
Vol.-24からのつづきです。
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第75番 智劔山 遮那院 威徳寺(赤坂不動尊)
(いとくじ)
公式Web
港区赤坂4-1-10
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第75番、御府内二十八不動霊場第23番、大東京百観音霊場第12番
第75番は「赤坂不動尊」として知られる威徳寺です。
第75番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに威徳寺で、第75番札所は開創当初から赤坂の威徳寺であったとみられます。
公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』、『赤坂不動尊栞』などから縁起・沿革を追ってみます。
延暦二十四年(805年)伝教大師最澄が唐より帰国の途上、嵐に遭い船が沈みそうになったとき、御自作の不動明王を海に沈めて祈願され難破をのがれたといいます。
天安二年(858年)、越後國三島郡出雲崎の漁師が毎夜海辺に不思議な光を見るので探索したところ、海中から大師がお沈めになった不動明王が現れたため茅屋を結んで尊像を安置、お祀りしたのが創始と伝わります。
永承六年(1063年)、源頼義公が当山に戦勝祈願したところ、霊験を感じて下総國香取郡米澤村(現・千葉県香取郡神崎町)にお遷ししたといいます。
寶冶年中(1247-1249年)、鎌倉幕府5代執権・北條時頼公が米澤村の不動堂へ願書を奉ったと伝わるのは、こちらの不動尊とみられています。
文永十一年(1274年)には8代執権北條時宗公が文永の役で戦勝祈願・成就して北條執権家の尊崇を高め、寺勢いよいよ興隆したといいます。
慶長五年(1600年)、住僧良臺が当尊より夢告をうけて赤坂人継(一ツ木)の地へ移転し、赤坂の威徳寺として開山。
眼下に溜池、遠くに愛宕の高塔を望む風光絶佳の地であったため池見山遮那院と号しました。
霊験あらたかな不動尊にあやかってか、当山は紀州徳川家の祈願寺となりました。
五大明王をはじめ多彩な祈祷佛を安したのは、紀州徳川家の祈願寺という背景があったためとみられます。
江戸期には御府内霊場の札所にもなって人々の尊崇を集めました。
不動明王の利生の劔に因んで智劔山、また不動尊の威徳を尊んで威徳寺と号したといいます。
赤坂不動尊威徳寺の法統は現在に至るまで赤坂の地で受け継がれ、平成29年には大規模なビルに改築、都心・赤坂のお不動様として人々の信仰を集めています。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
七十五番
赤坂一ツ木町
愛宕山真福寺末 新義真言宗
智劔山 遮那院 威徳寺
本尊:大日如来 海中出現不動明王 勝軍十一面観世音 弘法大師
■ 『寺社書上 [39] 赤坂寺社書上 壱』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.88』
深川七軒寺町
愛宕下真福寺末 新義真言宗
智劔山遮那院威徳寺
起立年代相不知申候
開山 良臺 元和三年(1617年)卒(元和八年(1622年)遷化とも)
本堂
本尊 不動明王木立像 伝教大師作海中出現 秘仏(略縁起)
前立 不動明王座像 願行上人作
両童子
本堂中安置
大威徳明王木立像
降三世明王木立像
軍荼利明王木立像
金剛夜叉明王木立像
愛染明王木座像
辨財天 弘法大師作灰佛
薬師如来木座像 脇士 日光菩薩木立像 月光菩薩木立像
金剛界大日如来木座像 胎蔵界大日如来銅座像
妙見尊木立像
賓頭盧尊者木座像
位牌安置土蔵内
大日如来木座像 阿弥陀如来木座像
地蔵菩薩木座像 弘法大師木座像 興教大師木座像
焔魔堂聖天相殿
聖天尊 秘佛 本地十一面観音木立像
焔魔大王木座像
大黒天木立像
大黒天木立像
毘沙門天王木座像
子安地蔵尊石座像 上屋有り
■ 『赤坂区史』/東京市赤坂区 昭和17年(国立国会図書館/保護期間満了)
眞言宗威徳寺 山号及別号智劔山阿遮院 愛宕下真福寺末
一ツ木町十三番地
寺門は市廛の間にあつて、本堂は一ツ木町十三番地の丘上に位置してゐる。門前に建てた大石柱には、「智劔山威徳寺、現在茲海代」「八十八ヶ所七十五番弘法大師」「傳教大師御眞作海中出現不動明王」「将軍十一面観世音」-天保八丁酉五月-の文字が刻まれてゐる。
当寺の起立された年代は詳かでないが、開山は良臺是年(元和八年(1622年)寂)である。
本堂の傍にある大師堂は寶形造で讃岐善通寺の写しである。此處は昔は星が岡の鬱陵に対し、溜池の池塘を下瞰し、又遠く愛宕の高塔を望むことが出来て、風光絶佳の地であつた。山號の智劔山は、續江戸砂子に「池見山威徳寺」と記されてゐるやうに、以前は溜池に臨むといふ意味から池見山と書いたのだが、後に至つて不動明王の利生の劔に因んで智劔と改めたのであらう。
境内に弘法大師千五百回忌塔がある。また不動尊に就いては、寺傳によれば、文徳天皇の天安二年(858年)越後國出雲崎の海濵に毎夜光明赫々たるものを認め海底を探つて此像を得たので、茅屋を結んで之を安置し、後に下総國米澤村に移した。寶冶年中(1247-1249年)に北條時頼が米澤村の不動堂へ願書を奉つたと傳へられるのは、即ちこの不動に祈願したもので、其後米澤村から武蔵國貝塚領人繼村へ遷座したのがこの像であると云ふ。

「威徳寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』赤坂絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
※一ツ木丁に「寍徳寺」という寺院がみえます。位置関係からするとこちらが「威徳寺」のようにも思われますが、どうでしょうか。
-------------------------
メトロ「赤坂見附」駅は「永田町」駅と接続し、銀座線・丸ノ内線(赤坂見附)、半蔵門線・有楽町線・南北線(永田町)の5路線が利用できる交通の要衝です。
「赤坂見附」駅から徒歩約5分の一ツ木通りに面しています。
もともと一ツ木通りにはTBS本館ビルがあり、メディア、芸能関係など時代の先端を行く人々の街でした。
TBSが赤坂に移転したあともその遺伝子は遺り、いまでも界隈は華やいだ雰囲気です。
不動尊は繁華街に祀られる例も多く、赤坂不動尊も違和感なく人々の尊崇を集めていると思われます。


【写真 上(左)】 工事中の山内
【写真 下(右)】 工事中の参拝所
はじめて参拝したときは工事中でプレハブの参拝所での奉拝でしたが、古色を帯びた不動尊を間近で拝せてかなりの迫力でした。
平成29年の新ビル竣工後は、立派なビル内の本堂で参拝できます。


【写真 上(左)】 工事中の参拝案内
【写真 下(右)】 一ツ木通りからの参道


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 山内入口
一ツ木通りに接して参道。
「南無不動明王」の幟がはためき、附設の「赤坂浄苑」のサイン、その奥には山門も見えて寺院めぐりに不慣れな人にはかなりのインパクトがあるかも。
参道入口に寺号標。その先に「赤坂不動尊」の石標と御府内霊場の札所碑。
その先のアーチ状の山門には「赤坂不動尊」の扁額が掲げられ、門柱にはさらに寺号標。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門の寺号標


【写真 上(左)】 不動尊碑と札所碑
【写真 下(右)】 参道


【写真 上(左)】 寺号標とエントランス
【写真 下(右)】 紀州徳川家御祈願所
重厚なブラックフェースのエントランスと、たたみかけるように寺号標。
その前庭には石像の不動尊像と修行大師像。
どちらも古色を帯びているので、改修前から御座される濡佛では。


【写真 上(左)】 不動尊像
【写真 下(右)】 修行大師像修行大師像
エントランス手前には「紀州徳川家御祈祷所」の石碑と子授子育地蔵尊。
山号扁額が掲げられたエントランスを入ると受付で、こちらで拝観と御朱印のお願いをします。
ご対応はたいへんにご親切で、たしかエレベーターで上層階の本堂に昇ったと思います。
(あるいは1階奥かもしれぬ。記憶があいまいですみません。)


【写真 上(左)】 エントランスの扁額
【写真 下(右)】 本堂向拝


【写真 上(左)】 「赤坂不動尊」の提灯
【写真 下(右)】 本堂扁額
本堂前には「赤坂不動尊」の提灯とそのおくに真言宗智山派の宗紋「桔梗紋」が染められた紫の向拝幕。
上部左右に欄間彫刻、中央に山号扁額で、ビル内ながら仏堂の趣きゆたかです。
都内有数の繁華街立地、瀟洒なビル内本堂と、まさに都会の霊場・御府内霊場ならではの札所といえましょう。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
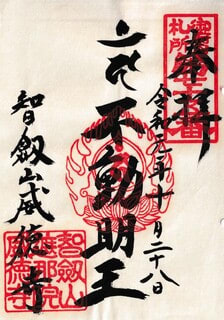

【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

【写真 上(左)】■ 専用集印帳(平成28年拝受)
中央に不動明王のお種子「カン/カーン」「不動明王」の揮毫と「カン/カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内札所第七十五番」の札所印。
左下に山号寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
なお、平成28年に拝受した御朱印の寺院印は「赤坂不動尊印」でした。
■ 第76番 蓮華山 佛性寺 金剛院
(こんごういん)
公式Web
豊島区長崎1-9-2
真言宗豊山派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
司元別当:長崎神社(豊島区長崎)
他札所:豊島八十八ヶ所霊場第76番
第76番は豊島区長崎の金剛院です。
第76番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに西蔵院で、第76番札所は御府内霊場開創当初から江戸末期まで音羽の西蔵院で、『御府内八十八ケ所道しるべ』の札所変更資料には西蔵院から金剛院への変更が記され、第76番札所は幕末から明治初頭にかけて長崎の金剛院に変更とみられます。
公式Web、豊島区資料、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから両山の縁起・沿革を追ってみます。
【金剛院】
金剛院は、大永二年(1522年)聖弁和尚が新義真言宗寺院として”観音堂”の地(現・長崎3-28-1)に開創といいます。
当初の御本尊は阿弥陀三尊ないし五智如来(『新編武蔵風土記稿』)。
開創の地(長崎3-28-1)は現在当山の境外仏堂となっています。
元和七年(1621年)幕府の「諸宗諸本山諸法度」を受けて中野村宝仙寺の末寺となりました。
延宝年中(1673-1681年)ないし元禄年中(1688-1704年)、火災により仏像や古文書を焼失し宝永六年(1709年)頃に現在地へ移転しました。
正徳五年(1715年)聖誉和尚が再建。この頃、長崎神社の別当になったといいます。


【写真 上(左)】 長崎神社
【写真 下(右)】 長崎神社の御朱印
天明年中(1781-1788年)の大火の折、19世・宥憲和尚は多くの罹災者を金剛院に収容して命を助け、その功績により10代将軍家治公から山門(安永九年(1780年)建立)を朱塗りとする許可を受けました。
朱塗りの門の許可は名誉あることで、金剛院は以降「赤門寺」とも尊称されました。
この赤門は、豊島区の有形文化財に指定されています。
安政年中(1845-1849年)、本寺の中野宝仙寺から智観比丘尼が入山。
比丘尼は金剛院へ村の子供たちを集めて寺子屋をはじめ、礼儀作法や読み書きを教えました。
当地の庶民教育の創始者とも云える智観比丘尼の功績を称える碑が山内に建立されています。
明治34年には山内に長崎村役場がおかれ、長崎村の中心的な存在であったことがわかります。
明治初頭の神仏分離の波を乗り越え、御府内霊場第76番札所を承継、明治40年開創とされる豊島八十八ヶ所霊場の札所にもなっています。
小日向の西蔵院からの御府内霊場札所承継については、いずれも中野村宝仙寺末であった所縁によるものと思われます。
江戸期以降の御府内の寺院や札所はおおむね西遷傾向。
廃寺等を受けた札所承継で、同宗派の西側の郊外寺院に遷る例は他にもいくつかみられます。
-------------------------
【西蔵院】
西蔵院は小日向にあった新義真言宗寺院。
『寺社書上 (小日向寺社書上)』に「小日向別当 小日向村田地●●●出現ニ付田中八幡●神宮●唱」とあり、小日向の田中八幡宮の別当であったことがわかります。
『小石川区史』の小日向神社の項にも「田中八幡社は、社伝に依ればその神體を小日向村の田地より感得したので田中八幡宮と唱へ、始めは八幡坂町に奉祀したが、明暦元年其地が久世大和守の抱屋敷となつた為め、音羽裏の地に引移り、明治に至つて氷川社と合し、今日の地に移つたのである。」とあります。
同書によると、氷川社の別当は慈照山日輪寺で小日向の總鎮守。
また、音羽町九丁目の今宮神社の項には「創建は社伝に依れば、元禄年中(1688-1704年)五代将軍綱吉の生母桂昌院が、護國寺建立と共にその境内に奉祀したと言ふ。明治初年、神佛混淆禁止に依り、同六年元田中八幡宮の跡なる現地へ遷座した。」とあります。
整理すると、現在の今宮神社の場所に御鎮座の田中八幡宮(別当:西蔵院)は明治の神佛分離の際に西蔵院が廃寺となり、田中八幡宮は氷川社(別当:日輪寺)と合祀されて、現在の小日向神社の地に御遷座、小日向神社と号されました。


【写真 上(左)】 小日向神社
【写真 下(右)】 小日向神社の御朱印
一方、音羽裏の田中八幡宮の跡地には元禄年中(1688-1704年)徳川5代将軍綱吉公の生母桂昌院が、護國寺建立とともに境内に奉祀したという今宮神社が明治6年に御遷座されいまに至るようです。
以上から、田中八幡宮の別当・西蔵院は、現在の今宮神社の地にあったとみられます。
『江戸切絵図』をみても『田中八幡 別当西蔵院』は還国寺の北西、大泉寺の北東にあって、ちょうどいまの今宮神社辺に当たっています。


【写真 上(左)】 今宮神社
【写真 下(右)】 今宮神社の掲示(御朱印不授与)
また、 『江戸名所図会 7巻 [12]』の神齢山護国寺の項には「今宮五社 当所鎮守と云 天照太神宮 八幡大神 春日大明神 今宮大明神 三部大権現五社を祭る 音羽町青柳町桜木町の鎮守なりと云伝ふ」とあり、今宮五社が護国寺鎮守であったことがわかります。
田中八幡宮別当の性格が強かった西蔵院は明治初頭の神仏分離で廃され、御府内霊場札所は上記のとおり同宗派の長崎・金剛院に承継されました。
なので、田中八幡宮の系譜は小日向神社、別当・西蔵院の系譜は金剛院で、それぞれいまも辿ることができます。
-------------------------
【史料】
【金剛院】
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
(長崎村)金剛院
新義真言宗 多磨郡中野村寶仙寺末 蓮華山佛性寺ト号ス 本尊五智如来中興僧ハ貞享五年(1688年)寂ス
■ 『北豊島郡誌』(国立国会図書館)
(長崎村)金剛院
千四百三十六番地に在り、新義真言宗豊山派、中野寶泉寺末、蓮華山佛性寺と号す。本尊五智如来を安置す。当寺往年火災に罹り寺伝を失ふて開創詳ならざるも、約四百年前の剏建にして開山を聖辨和尚と云ふよし、新編武蔵風土記稿に『中興の僧は貞享五年(1688年)寂す』とあるに見ても其の古き寺なることを知るべし。境内は長崎神社の東に続き小丘の上にあり、本堂は萱葺にして堂前東に大師堂あり、豊島八十八ヶ所の札所にあり、鐘樓ありて寛文年中(1661-1673年)の梵鐘を吊れり。
■ 『北豊島郡誌』(国立国会図書館)
長崎神社
祭神素盒嗚尊、舊来長崎村の鎮守なり。当社舊別当は金剛院なり、現今神域は寺地と相続けり。
【西蔵院】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
七十六番
●●町八丁目
田中山 西蔵院
中野村宝仙寺末 新義
本尊:阿弥陀如来 本社田中八幡宮 弘法大師
■ 『寺社書上 [27] 小日向寺社書上 参止』(国立国会図書館)
小日向別当
新義真言宗中野村宝仙寺末
田中山西蔵院
八幡宮●●
但本像馬上にあり御丈八寸
右●像之儀ハ当代ふ知 小日向村田地●●●出現ニ付田中八幡●神宮●唱 八幡坂町(不詳)明暦元年(1655年)久世大和守殿御抱屋敷(不詳)当地之場所に引移候
相殿
弘法大師
但御府内八拾八ヶ所第七十六番札所
相殿
八幡宮本地佛●阿弥陀如来木佛立像
末社
庚申堂 稲荷社 三峯山 地蔵堂
八幡宮拝殿 本社
別当 内佛不動木座像
別当起立之年月不相知
開山●年月世代の儀相知不申候
開基無●●候
■ 『小石川区史』(国立国会図書館)
小日向神社
小日向水道町服部坂の中腹に鎮座し、素戔嗚尊、譽田別尊、櫛稲田姫命、大巳貴命を祀る。其創建は明治二年で、水道町日輪寺境内の氷川社と音羽裏の田中八幡とを今の場所に移し、合祀して地名を取り社号としたものである。
氷川社は『新編江戸志』に依れば、『小日向の總鎮守にして、勸請の年歴詳かならず、四五百年の鎮座と言へり』。といひ、又『太田道灌再興す』と記してゐる。『江戸名所図會』には其図が載つてゐる。
田中八幡社は、社伝に依ればその神體を小日向村の田地より感得したので田中八幡宮と唱へ、始めは八幡坂町に奉祀したが、明暦元年(1655年)其地が久世大和守の抱屋敷となつた為め、音羽裏の地に引移り、明治に至つて氷川社と合し、今日の地に移つたのである。
明治五年村社に列し、祭日は九月十五日である。
現在の氏子町は小日向臺町一・二・三丁目、同三軒町、清水谷町、茗荷谷町、第六天町、水道端一・二丁目、武島町、小日向水道町、東・西古川町、松ヶ枝町、小日向町、西江戸川町等、小日向の全部である。
■ 『小石川区史』(国立国会図書館)
今宮神社
音羽町九丁目に在る。祭神は天照大神、素戔嗚尊、伊弉册尊、譽田別尊、天兒屋根命、大國主命、少彦名命、大宮乃賣命である。
その創建は社伝に依れば、元禄年中(1688-1704年)五代将軍綱吉の生母桂昌院が、護國寺建立と共にその境内に奉祀したと言ふ。
明治初年、神佛混淆禁止に依り、同六年元田中八幡宮の跡なる現地へ遷座した。明治五年村社に列せられ、現在境内は三百餘坪、祭日は九月七日で、東・西青柳町、音羽一丁目乃至九丁目、櫻木町を氏子としてゐる。
■ 『江戸名所図会 7巻 [12]』(国立国会図書館)
神齢山護国寺
今宮五社
当所鎮守と云 天照太神宮 八幡大神 春日大明神 今宮大明神 三部大権現五社を祭る 音羽町青柳町桜木町の鎮守なりと云伝ふ
■ 『小石川区史』(国立国会図書館)
日輪寺
慈照山日輪寺。曹洞宗大本山総持寺、本山駒込吉祥寺末。本尊釋迦如来。
当地は元小日向の鎮守と伝へられる氷川明神の社地で、慶長十三年(1608年)吉祥寺第八世松栖用鶴大和尚が、明神別当として一寺を開いたのが当寺の基となつた。尤も氷川明神の縁起については、『新編江戸志』に『氷川神社、上水の上、別当慈照山日輪寺、神主宮崎伊勢守。社伝に小日向總鎮守にして、勧請の年歴詳かならず、四五百年の鎮座といへり。社伝に太田道灌再興すといふなり』とあり、『江戸名所図會』にも『氷川明神祠上水堀の端慈照山日蓮寺といへる禅林にあり。祭神は当國一宮に同じ。勧請の始久しうして知るべからずといへり。中古太田道灌の再興にして、小日向の鎮守なり。祭禮は正五九月の十七日なり。當社に元亀の年號ある庚申待供養の古碑あり』とあり(略)明治に至り神佛分離の際、氷川社の神體は小日向神社に奉遷し、社殿は観音堂となり、爾後寺院として今日に伝へた。

「西蔵院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』音羽絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは西武新宿線「椎名町」駅で徒歩1分と至近。
元別当をつとめた長崎神社ととなりあっています。
都内には駅前に寺社がある駅はけっこうありますが、神社・元別当ともに並んでいる例はなかなか貴重です。


【写真 上(左)】 院号標と長崎不動尊
【写真 下(右)】 長崎不動尊の扁額
山門手前、駅側にせり出すように堂宇を構えられる「長崎不動尊」は、昭和24年に地域の守護仏として造立奉安された比較的あたらしい尊像ながら、不動尊ならではの力づよいオーラを放たれています。
堂内には平成8年造立の聖観世音菩薩像も奉安されています。


【写真 上(左)】 舟型道標地蔵尊
【写真 下(右)】 地蔵尊の御真言
「長崎不動尊」のさらに手前には「舟型道標地蔵尊」。
寛政八年(1796年)造立、中山道板橋仲宿、厄除け祖師・妙法寺方面への道標となっていて、御仏体は江戸城築城時につかわれた石の一部と云われています。


【写真 上(左)】 寺カフェ『なゆた』
【写真 下(右)】 山門
右手には寺カフェ・赤門テラス『なゆた』。
正面の参道を進むと山門(赤門)です。
由来は上記のとおりで、切妻屋根銅板葺の薬医門で左右の袖塀を脇塀に当て付けています。
屋根の銅板はえんじ色ながら門柱・門扉は鮮やかな朱で、「赤門」のイメージを伝えています。

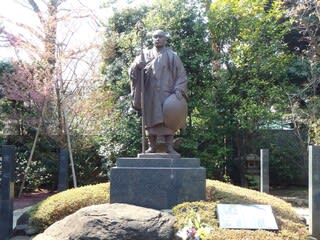
【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 修行大師像
山門をくぐると左手に修行大師像と四国八十八ヶ所お砂踏み霊場。
修行大師像の本堂寄りには「弘法大師・興教大師碑」、御朱印霊場札所標、マンガ地蔵尊などが並びます。
椎名町五丁目にあった「トキワ荘」は、手塚治虫、藤子不二雄、石ノ森章太郎、赤塚不二夫ら著名な漫画家が居住していた「漫画の聖地」です。
→ 豊島区立トキワ荘マンガミュージアム公式Web


【写真 上(左)】 マンガ地蔵尊
【写真 下(右)】 マンガ地蔵尊の台座銘
金剛院山内にはこれを記念して平成27年に「マンガ地蔵尊」が造立奉安されています。
錫杖の代わりにペンを持たれ、法衣の柄は漫画のコマ、光背がGペンという特徴あるおすがたです。
マンガ地蔵尊の御朱印も授与されています。


【写真 上(左)】 御府内霊場札所碑
【写真 下(右)】 修行大師像、大師堂と本堂
その先の大師堂は宝形造桟瓦葺で頂部に宝珠を置いています。
向かって左の柱に御寶号、右には御府内霊場札所板。

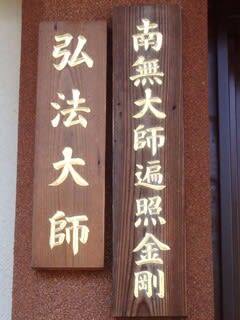
【写真 上(左)】 大師堂
【写真 下(右)】 御寶号板


【写真 上(左)】 御府内霊場札所板
【写真 下(右)】 霊場札所板
向拝上部には御府内・豊島両霊場の札所板と和讃(御詠歌)板が掲げられ、弘法大師霊場札所の趣きゆたか。
当山公式Webの御府内霊場の手引きページは懇切丁寧にまとめられ、Web検索でも上位ヒットします。
御府内霊場の巡拝者迎え入れに積極的なお寺さまかと思われます。
参道右手に建つ二基の板碑と庚申塔は区登録文化財。


【写真 上(左)】 板碑と仏塔
【写真 下(右)】 本堂
本堂は入母屋造本瓦葺流れ向拝の伽藍(外陣)とその後ろに宝形造二重屋根の伽藍(内陣)を隣接し、入母屋造平入りの後ろに相輪をみせる面白い意匠となっています。
昭和29年落慶の本堂は、コンクリ造ながら古典建築の造形を単純化してまとめた寺院建築として国の登録有形文化財に指定。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 客殿と庫裡
本堂向かって右手前の客殿は千鳥破風と起り屋根が印象的な瀟洒な建物で、こちらも国の登録有形文化財に指定されています。
御朱印は客殿よこの庫裡にて拝受しました。
こちらでは豊島八十八ヶ所霊場とマンガ地蔵尊の御朱印も授与されています。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に阿弥陀如来のお種子「キリーク」「無量壽」「弘法大師」の揮毫と宝珠の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「御府内八十八所第七十六番」の札所印。
左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
※「無量壽」は、阿弥陀如来の別号です。
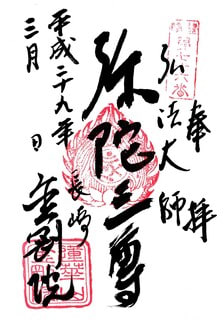
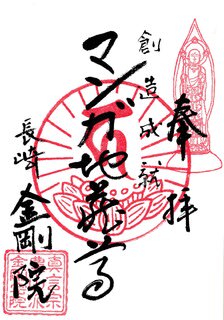
【写真 上(左)】 豊島霊場の御朱印
【写真 下(右)】 マンガ地蔵尊の御朱印
■ 第77番 高嶋山 歓喜寺 佛乗院
(ぶつじょういん)
神奈川県秦野市蓑毛957-13
真言宗智山派
御本尊:千手観世音菩薩
札所本尊:千手観世音菩薩
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第77番、御府内二十八不動霊場第17番、弁財天百社参り第17番
第77番は神奈川県秦野市の佛乗院です。
御府内霊場唯一の東京都外の札所です。
神奈川県といっても川崎や横浜ではありません。遠く丹沢山中の札所で、参拝は1日がかりとなります。
第77番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに佛乗院で、第77番札所は開創当初から芝三田の佛乗院であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
佛乗院の開山開基は不明ですが、当所は八丁堀にあり、寛永十二年(1635年)三田ないし日本橋に引移り、延宝年間(1763-1780年)に芝三田寺町に移転といいます。
中興開基は法印宥補(宝)と伝わります。
芝三田寺町の在所は大聖院と幸福寺の間、蛇坂の登り口付近でしたから、現在のケーヨーデイツー三田店あたりとみられます。
昭和62年、三田寺町から神奈川県秦野市の丹沢山中へ移転し、同時に御府内霊場第77番札所も移転して、最も遠方の札所となりました。
当初の御本尊は弘法大師の御作と伝わる旭辨財天木立像。
弘法大師御作とされる大聖歓喜天尊も奉安されていました。
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 』には「本尊:弁財天 歓喜天 弘法大師」とあり、すくなくとも幕末までは弁財天、大聖歓喜天尊、弘法大師の三尊が御府内霊場の拝尊であったことがわかります。
弁財天百社参り第17番の札所であり、御府内でも著名な辨財天霊場であったとみられます。
また、御府内二十八不動霊場第17番の札所本尊は、おそらく智證大師御作と伝わる不動明王とみられます。
現在の御本尊・札所本尊は千手観世音菩薩。
御本尊・札所本尊が替わられた経緯は不明です。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
七十七番
芝三田寺町
愛宕山真福寺末 新義真言宗
高嶋山 歓喜寺 佛乗院
本尊:弁財天 歓喜天 弘法大師
■ 『寺社書上 [13] 三田寺社書上 参』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.94』
三田寺町
愛宕前真福寺末 新義真言宗
高嶋山佛乗院歓喜寺
開闢起立之年代不分明
開山中興開山共ニ不分明
八丁(町)堀から当地に替地拝領仕 寛永十二年(1635年)当所(三田寺町)ニ引移●●
中興開基 法印宥補(宝)寛文六年(1666年)遷化
本堂
本尊 旭辨財天木立像 弘法大師作ト云 十五童子
大黒天 四天王 前立辨財天木座像
大聖歓喜天木立像 弘法大師作
大聖歓喜天真鍮立像
十一面観音木立像
不動明王木立像 智證大師作ト云
弘法大師
千躰地蔵尊木座像
阿弥陀如来木座像
鎮守八幡稲荷合社 但し御幣勧請
旭弁天社●-● 弘法大師近江國竹生島に三七日来●あり ●-● 手つから彫刻の尊像なり 元禄の頃吉水●●といふ医師弁天を伝●る事あり 当寺の住良運法印に●し弁天の●●
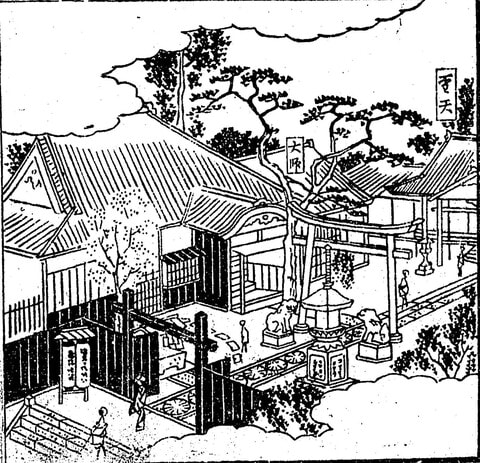
「佛乗院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』芝高輪辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2.国立国会図書館DC(保護期間満了)
■ 現在の三田寺町(蛇坂登り口付近)周辺の地図 ↓
-------------------------
小田急線「秦野」駅から神奈中バス蓑毛行きに乗り終点で下車。
バス停からさらに500mほど歩いたところです。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 御府内霊場札所標-1

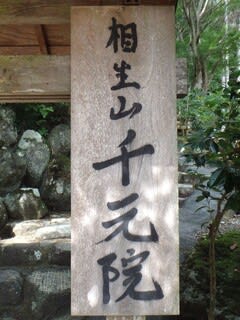
【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 千元院の院号標
林道的なロケーションに突然参道入口があらわれます。
右手おくの切妻屋根の建物には「相生山 千元院」とあり??マークがつきますが、参道入口には「札所七拾七番 佛乗院」とあります。
その先の山門には「相生山 千元院」とあり、どうやらふたつの号を号されているようです。
参道沿いに「南無相生大権現」の登りが並び、神仏習合の趣きがあります。
丹沢周辺には山気横溢するパワスポ的な寺院が多いですが、こちらもそのようなイメージがあります。
山門は簡素な二脚門で、門柱に札所板を掲げています。


【写真 上(左)】 御寶号碑
【写真 下(右)】 山内


【写真 上(左)】 御府内霊場札所標-2
【写真 下(右)】 相生大明神と本堂
石段を登ると右手に相生大明神。
『寺社書上』にある「鎮守八幡稲荷合社」と系譜がつながるかは不明です。
その先右奥の木立の下には水垢離場や小祠、お不動様の石像などが建ち並び、修験道場的なオーラを発しています。


【写真 上(左)】 御府内霊場札所碑
【写真 下(右)】 本堂
本堂はその先階段の上で、手前に観世音菩薩立像(平和観音)が御座します。
本堂は入母屋造妻入りかと思いますが、全貌がつかめないので断言できません。
手前に大きく張り出した向拝屋根。
雨の多い丹沢では、しっかり雨粒を防げるこのくらいの屋根が必要なのでしょう。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、中備に本蟇股を置き、向拝見上げには山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 御朱印案内
【写真 下(右)】 簑庵
御朱印は本堂向かって左手奥の庫裡にて拝受しました。
なお、山内掲示の 御朱印案内によると、ご不在の場合御朱印は郵送可能なようですが、やはり事前にTEL問いしてからお伺いするのがベターかと思います。
なお、以前は山内に割烹料理「蓑庵」がありましたが、現況の営業状況は不明です。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に千手観世音菩薩のお種子「キリク」「千住観音」「弘法大師」の揮毫と札番付の「キリク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「七十七番」の札所印。
左下に山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-26)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ Airport - 今井優子
■ 泣きたかった - 今井美樹
■Just Be Yourself - 杏里
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第75番 智劔山 遮那院 威徳寺(赤坂不動尊)
(いとくじ)
公式Web
港区赤坂4-1-10
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第75番、御府内二十八不動霊場第23番、大東京百観音霊場第12番
第75番は「赤坂不動尊」として知られる威徳寺です。
第75番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに威徳寺で、第75番札所は開創当初から赤坂の威徳寺であったとみられます。
公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』、『赤坂不動尊栞』などから縁起・沿革を追ってみます。
延暦二十四年(805年)伝教大師最澄が唐より帰国の途上、嵐に遭い船が沈みそうになったとき、御自作の不動明王を海に沈めて祈願され難破をのがれたといいます。
天安二年(858年)、越後國三島郡出雲崎の漁師が毎夜海辺に不思議な光を見るので探索したところ、海中から大師がお沈めになった不動明王が現れたため茅屋を結んで尊像を安置、お祀りしたのが創始と伝わります。
永承六年(1063年)、源頼義公が当山に戦勝祈願したところ、霊験を感じて下総國香取郡米澤村(現・千葉県香取郡神崎町)にお遷ししたといいます。
寶冶年中(1247-1249年)、鎌倉幕府5代執権・北條時頼公が米澤村の不動堂へ願書を奉ったと伝わるのは、こちらの不動尊とみられています。
文永十一年(1274年)には8代執権北條時宗公が文永の役で戦勝祈願・成就して北條執権家の尊崇を高め、寺勢いよいよ興隆したといいます。
慶長五年(1600年)、住僧良臺が当尊より夢告をうけて赤坂人継(一ツ木)の地へ移転し、赤坂の威徳寺として開山。
眼下に溜池、遠くに愛宕の高塔を望む風光絶佳の地であったため池見山遮那院と号しました。
霊験あらたかな不動尊にあやかってか、当山は紀州徳川家の祈願寺となりました。
五大明王をはじめ多彩な祈祷佛を安したのは、紀州徳川家の祈願寺という背景があったためとみられます。
江戸期には御府内霊場の札所にもなって人々の尊崇を集めました。
不動明王の利生の劔に因んで智劔山、また不動尊の威徳を尊んで威徳寺と号したといいます。
赤坂不動尊威徳寺の法統は現在に至るまで赤坂の地で受け継がれ、平成29年には大規模なビルに改築、都心・赤坂のお不動様として人々の信仰を集めています。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
七十五番
赤坂一ツ木町
愛宕山真福寺末 新義真言宗
智劔山 遮那院 威徳寺
本尊:大日如来 海中出現不動明王 勝軍十一面観世音 弘法大師
■ 『寺社書上 [39] 赤坂寺社書上 壱』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.88』
深川七軒寺町
愛宕下真福寺末 新義真言宗
智劔山遮那院威徳寺
起立年代相不知申候
開山 良臺 元和三年(1617年)卒(元和八年(1622年)遷化とも)
本堂
本尊 不動明王木立像 伝教大師作海中出現 秘仏(略縁起)
前立 不動明王座像 願行上人作
両童子
本堂中安置
大威徳明王木立像
降三世明王木立像
軍荼利明王木立像
金剛夜叉明王木立像
愛染明王木座像
辨財天 弘法大師作灰佛
薬師如来木座像 脇士 日光菩薩木立像 月光菩薩木立像
金剛界大日如来木座像 胎蔵界大日如来銅座像
妙見尊木立像
賓頭盧尊者木座像
位牌安置土蔵内
大日如来木座像 阿弥陀如来木座像
地蔵菩薩木座像 弘法大師木座像 興教大師木座像
焔魔堂聖天相殿
聖天尊 秘佛 本地十一面観音木立像
焔魔大王木座像
大黒天木立像
大黒天木立像
毘沙門天王木座像
子安地蔵尊石座像 上屋有り
■ 『赤坂区史』/東京市赤坂区 昭和17年(国立国会図書館/保護期間満了)
眞言宗威徳寺 山号及別号智劔山阿遮院 愛宕下真福寺末
一ツ木町十三番地
寺門は市廛の間にあつて、本堂は一ツ木町十三番地の丘上に位置してゐる。門前に建てた大石柱には、「智劔山威徳寺、現在茲海代」「八十八ヶ所七十五番弘法大師」「傳教大師御眞作海中出現不動明王」「将軍十一面観世音」-天保八丁酉五月-の文字が刻まれてゐる。
当寺の起立された年代は詳かでないが、開山は良臺是年(元和八年(1622年)寂)である。
本堂の傍にある大師堂は寶形造で讃岐善通寺の写しである。此處は昔は星が岡の鬱陵に対し、溜池の池塘を下瞰し、又遠く愛宕の高塔を望むことが出来て、風光絶佳の地であつた。山號の智劔山は、續江戸砂子に「池見山威徳寺」と記されてゐるやうに、以前は溜池に臨むといふ意味から池見山と書いたのだが、後に至つて不動明王の利生の劔に因んで智劔と改めたのであらう。
境内に弘法大師千五百回忌塔がある。また不動尊に就いては、寺傳によれば、文徳天皇の天安二年(858年)越後國出雲崎の海濵に毎夜光明赫々たるものを認め海底を探つて此像を得たので、茅屋を結んで之を安置し、後に下総國米澤村に移した。寶冶年中(1247-1249年)に北條時頼が米澤村の不動堂へ願書を奉つたと傳へられるのは、即ちこの不動に祈願したもので、其後米澤村から武蔵國貝塚領人繼村へ遷座したのがこの像であると云ふ。

「威徳寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』赤坂絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
※一ツ木丁に「寍徳寺」という寺院がみえます。位置関係からするとこちらが「威徳寺」のようにも思われますが、どうでしょうか。
-------------------------
メトロ「赤坂見附」駅は「永田町」駅と接続し、銀座線・丸ノ内線(赤坂見附)、半蔵門線・有楽町線・南北線(永田町)の5路線が利用できる交通の要衝です。
「赤坂見附」駅から徒歩約5分の一ツ木通りに面しています。
もともと一ツ木通りにはTBS本館ビルがあり、メディア、芸能関係など時代の先端を行く人々の街でした。
TBSが赤坂に移転したあともその遺伝子は遺り、いまでも界隈は華やいだ雰囲気です。
不動尊は繁華街に祀られる例も多く、赤坂不動尊も違和感なく人々の尊崇を集めていると思われます。


【写真 上(左)】 工事中の山内
【写真 下(右)】 工事中の参拝所
はじめて参拝したときは工事中でプレハブの参拝所での奉拝でしたが、古色を帯びた不動尊を間近で拝せてかなりの迫力でした。
平成29年の新ビル竣工後は、立派なビル内の本堂で参拝できます。


【写真 上(左)】 工事中の参拝案内
【写真 下(右)】 一ツ木通りからの参道


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 山内入口
一ツ木通りに接して参道。
「南無不動明王」の幟がはためき、附設の「赤坂浄苑」のサイン、その奥には山門も見えて寺院めぐりに不慣れな人にはかなりのインパクトがあるかも。
参道入口に寺号標。その先に「赤坂不動尊」の石標と御府内霊場の札所碑。
その先のアーチ状の山門には「赤坂不動尊」の扁額が掲げられ、門柱にはさらに寺号標。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門の寺号標


【写真 上(左)】 不動尊碑と札所碑
【写真 下(右)】 参道


【写真 上(左)】 寺号標とエントランス
【写真 下(右)】 紀州徳川家御祈願所
重厚なブラックフェースのエントランスと、たたみかけるように寺号標。
その前庭には石像の不動尊像と修行大師像。
どちらも古色を帯びているので、改修前から御座される濡佛では。


【写真 上(左)】 不動尊像
【写真 下(右)】 修行大師像修行大師像
エントランス手前には「紀州徳川家御祈祷所」の石碑と子授子育地蔵尊。
山号扁額が掲げられたエントランスを入ると受付で、こちらで拝観と御朱印のお願いをします。
ご対応はたいへんにご親切で、たしかエレベーターで上層階の本堂に昇ったと思います。
(あるいは1階奥かもしれぬ。記憶があいまいですみません。)


【写真 上(左)】 エントランスの扁額
【写真 下(右)】 本堂向拝


【写真 上(左)】 「赤坂不動尊」の提灯
【写真 下(右)】 本堂扁額
本堂前には「赤坂不動尊」の提灯とそのおくに真言宗智山派の宗紋「桔梗紋」が染められた紫の向拝幕。
上部左右に欄間彫刻、中央に山号扁額で、ビル内ながら仏堂の趣きゆたかです。
都内有数の繁華街立地、瀟洒なビル内本堂と、まさに都会の霊場・御府内霊場ならではの札所といえましょう。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
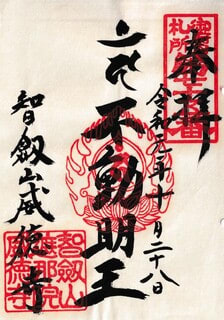

【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

【写真 上(左)】■ 専用集印帳(平成28年拝受)
中央に不動明王のお種子「カン/カーン」「不動明王」の揮毫と「カン/カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内札所第七十五番」の札所印。
左下に山号寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
なお、平成28年に拝受した御朱印の寺院印は「赤坂不動尊印」でした。
■ 第76番 蓮華山 佛性寺 金剛院
(こんごういん)
公式Web
豊島区長崎1-9-2
真言宗豊山派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
司元別当:長崎神社(豊島区長崎)
他札所:豊島八十八ヶ所霊場第76番
第76番は豊島区長崎の金剛院です。
第76番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに西蔵院で、第76番札所は御府内霊場開創当初から江戸末期まで音羽の西蔵院で、『御府内八十八ケ所道しるべ』の札所変更資料には西蔵院から金剛院への変更が記され、第76番札所は幕末から明治初頭にかけて長崎の金剛院に変更とみられます。
公式Web、豊島区資料、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから両山の縁起・沿革を追ってみます。
【金剛院】
金剛院は、大永二年(1522年)聖弁和尚が新義真言宗寺院として”観音堂”の地(現・長崎3-28-1)に開創といいます。
当初の御本尊は阿弥陀三尊ないし五智如来(『新編武蔵風土記稿』)。
開創の地(長崎3-28-1)は現在当山の境外仏堂となっています。
元和七年(1621年)幕府の「諸宗諸本山諸法度」を受けて中野村宝仙寺の末寺となりました。
延宝年中(1673-1681年)ないし元禄年中(1688-1704年)、火災により仏像や古文書を焼失し宝永六年(1709年)頃に現在地へ移転しました。
正徳五年(1715年)聖誉和尚が再建。この頃、長崎神社の別当になったといいます。


【写真 上(左)】 長崎神社
【写真 下(右)】 長崎神社の御朱印
天明年中(1781-1788年)の大火の折、19世・宥憲和尚は多くの罹災者を金剛院に収容して命を助け、その功績により10代将軍家治公から山門(安永九年(1780年)建立)を朱塗りとする許可を受けました。
朱塗りの門の許可は名誉あることで、金剛院は以降「赤門寺」とも尊称されました。
この赤門は、豊島区の有形文化財に指定されています。
安政年中(1845-1849年)、本寺の中野宝仙寺から智観比丘尼が入山。
比丘尼は金剛院へ村の子供たちを集めて寺子屋をはじめ、礼儀作法や読み書きを教えました。
当地の庶民教育の創始者とも云える智観比丘尼の功績を称える碑が山内に建立されています。
明治34年には山内に長崎村役場がおかれ、長崎村の中心的な存在であったことがわかります。
明治初頭の神仏分離の波を乗り越え、御府内霊場第76番札所を承継、明治40年開創とされる豊島八十八ヶ所霊場の札所にもなっています。
小日向の西蔵院からの御府内霊場札所承継については、いずれも中野村宝仙寺末であった所縁によるものと思われます。
江戸期以降の御府内の寺院や札所はおおむね西遷傾向。
廃寺等を受けた札所承継で、同宗派の西側の郊外寺院に遷る例は他にもいくつかみられます。
-------------------------
【西蔵院】
西蔵院は小日向にあった新義真言宗寺院。
『寺社書上 (小日向寺社書上)』に「小日向別当 小日向村田地●●●出現ニ付田中八幡●神宮●唱」とあり、小日向の田中八幡宮の別当であったことがわかります。
『小石川区史』の小日向神社の項にも「田中八幡社は、社伝に依ればその神體を小日向村の田地より感得したので田中八幡宮と唱へ、始めは八幡坂町に奉祀したが、明暦元年其地が久世大和守の抱屋敷となつた為め、音羽裏の地に引移り、明治に至つて氷川社と合し、今日の地に移つたのである。」とあります。
同書によると、氷川社の別当は慈照山日輪寺で小日向の總鎮守。
また、音羽町九丁目の今宮神社の項には「創建は社伝に依れば、元禄年中(1688-1704年)五代将軍綱吉の生母桂昌院が、護國寺建立と共にその境内に奉祀したと言ふ。明治初年、神佛混淆禁止に依り、同六年元田中八幡宮の跡なる現地へ遷座した。」とあります。
整理すると、現在の今宮神社の場所に御鎮座の田中八幡宮(別当:西蔵院)は明治の神佛分離の際に西蔵院が廃寺となり、田中八幡宮は氷川社(別当:日輪寺)と合祀されて、現在の小日向神社の地に御遷座、小日向神社と号されました。


【写真 上(左)】 小日向神社
【写真 下(右)】 小日向神社の御朱印
一方、音羽裏の田中八幡宮の跡地には元禄年中(1688-1704年)徳川5代将軍綱吉公の生母桂昌院が、護國寺建立とともに境内に奉祀したという今宮神社が明治6年に御遷座されいまに至るようです。
以上から、田中八幡宮の別当・西蔵院は、現在の今宮神社の地にあったとみられます。
『江戸切絵図』をみても『田中八幡 別当西蔵院』は還国寺の北西、大泉寺の北東にあって、ちょうどいまの今宮神社辺に当たっています。


【写真 上(左)】 今宮神社
【写真 下(右)】 今宮神社の掲示(御朱印不授与)
また、 『江戸名所図会 7巻 [12]』の神齢山護国寺の項には「今宮五社 当所鎮守と云 天照太神宮 八幡大神 春日大明神 今宮大明神 三部大権現五社を祭る 音羽町青柳町桜木町の鎮守なりと云伝ふ」とあり、今宮五社が護国寺鎮守であったことがわかります。
田中八幡宮別当の性格が強かった西蔵院は明治初頭の神仏分離で廃され、御府内霊場札所は上記のとおり同宗派の長崎・金剛院に承継されました。
なので、田中八幡宮の系譜は小日向神社、別当・西蔵院の系譜は金剛院で、それぞれいまも辿ることができます。
-------------------------
【史料】
【金剛院】
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
(長崎村)金剛院
新義真言宗 多磨郡中野村寶仙寺末 蓮華山佛性寺ト号ス 本尊五智如来中興僧ハ貞享五年(1688年)寂ス
■ 『北豊島郡誌』(国立国会図書館)
(長崎村)金剛院
千四百三十六番地に在り、新義真言宗豊山派、中野寶泉寺末、蓮華山佛性寺と号す。本尊五智如来を安置す。当寺往年火災に罹り寺伝を失ふて開創詳ならざるも、約四百年前の剏建にして開山を聖辨和尚と云ふよし、新編武蔵風土記稿に『中興の僧は貞享五年(1688年)寂す』とあるに見ても其の古き寺なることを知るべし。境内は長崎神社の東に続き小丘の上にあり、本堂は萱葺にして堂前東に大師堂あり、豊島八十八ヶ所の札所にあり、鐘樓ありて寛文年中(1661-1673年)の梵鐘を吊れり。
■ 『北豊島郡誌』(国立国会図書館)
長崎神社
祭神素盒嗚尊、舊来長崎村の鎮守なり。当社舊別当は金剛院なり、現今神域は寺地と相続けり。
【西蔵院】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
七十六番
●●町八丁目
田中山 西蔵院
中野村宝仙寺末 新義
本尊:阿弥陀如来 本社田中八幡宮 弘法大師
■ 『寺社書上 [27] 小日向寺社書上 参止』(国立国会図書館)
小日向別当
新義真言宗中野村宝仙寺末
田中山西蔵院
八幡宮●●
但本像馬上にあり御丈八寸
右●像之儀ハ当代ふ知 小日向村田地●●●出現ニ付田中八幡●神宮●唱 八幡坂町(不詳)明暦元年(1655年)久世大和守殿御抱屋敷(不詳)当地之場所に引移候
相殿
弘法大師
但御府内八拾八ヶ所第七十六番札所
相殿
八幡宮本地佛●阿弥陀如来木佛立像
末社
庚申堂 稲荷社 三峯山 地蔵堂
八幡宮拝殿 本社
別当 内佛不動木座像
別当起立之年月不相知
開山●年月世代の儀相知不申候
開基無●●候
■ 『小石川区史』(国立国会図書館)
小日向神社
小日向水道町服部坂の中腹に鎮座し、素戔嗚尊、譽田別尊、櫛稲田姫命、大巳貴命を祀る。其創建は明治二年で、水道町日輪寺境内の氷川社と音羽裏の田中八幡とを今の場所に移し、合祀して地名を取り社号としたものである。
氷川社は『新編江戸志』に依れば、『小日向の總鎮守にして、勸請の年歴詳かならず、四五百年の鎮座と言へり』。といひ、又『太田道灌再興す』と記してゐる。『江戸名所図會』には其図が載つてゐる。
田中八幡社は、社伝に依ればその神體を小日向村の田地より感得したので田中八幡宮と唱へ、始めは八幡坂町に奉祀したが、明暦元年(1655年)其地が久世大和守の抱屋敷となつた為め、音羽裏の地に引移り、明治に至つて氷川社と合し、今日の地に移つたのである。
明治五年村社に列し、祭日は九月十五日である。
現在の氏子町は小日向臺町一・二・三丁目、同三軒町、清水谷町、茗荷谷町、第六天町、水道端一・二丁目、武島町、小日向水道町、東・西古川町、松ヶ枝町、小日向町、西江戸川町等、小日向の全部である。
■ 『小石川区史』(国立国会図書館)
今宮神社
音羽町九丁目に在る。祭神は天照大神、素戔嗚尊、伊弉册尊、譽田別尊、天兒屋根命、大國主命、少彦名命、大宮乃賣命である。
その創建は社伝に依れば、元禄年中(1688-1704年)五代将軍綱吉の生母桂昌院が、護國寺建立と共にその境内に奉祀したと言ふ。
明治初年、神佛混淆禁止に依り、同六年元田中八幡宮の跡なる現地へ遷座した。明治五年村社に列せられ、現在境内は三百餘坪、祭日は九月七日で、東・西青柳町、音羽一丁目乃至九丁目、櫻木町を氏子としてゐる。
■ 『江戸名所図会 7巻 [12]』(国立国会図書館)
神齢山護国寺
今宮五社
当所鎮守と云 天照太神宮 八幡大神 春日大明神 今宮大明神 三部大権現五社を祭る 音羽町青柳町桜木町の鎮守なりと云伝ふ
■ 『小石川区史』(国立国会図書館)
日輪寺
慈照山日輪寺。曹洞宗大本山総持寺、本山駒込吉祥寺末。本尊釋迦如来。
当地は元小日向の鎮守と伝へられる氷川明神の社地で、慶長十三年(1608年)吉祥寺第八世松栖用鶴大和尚が、明神別当として一寺を開いたのが当寺の基となつた。尤も氷川明神の縁起については、『新編江戸志』に『氷川神社、上水の上、別当慈照山日輪寺、神主宮崎伊勢守。社伝に小日向總鎮守にして、勧請の年歴詳かならず、四五百年の鎮座といへり。社伝に太田道灌再興すといふなり』とあり、『江戸名所図會』にも『氷川明神祠上水堀の端慈照山日蓮寺といへる禅林にあり。祭神は当國一宮に同じ。勧請の始久しうして知るべからずといへり。中古太田道灌の再興にして、小日向の鎮守なり。祭禮は正五九月の十七日なり。當社に元亀の年號ある庚申待供養の古碑あり』とあり(略)明治に至り神佛分離の際、氷川社の神體は小日向神社に奉遷し、社殿は観音堂となり、爾後寺院として今日に伝へた。

「西蔵院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』音羽絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは西武新宿線「椎名町」駅で徒歩1分と至近。
元別当をつとめた長崎神社ととなりあっています。
都内には駅前に寺社がある駅はけっこうありますが、神社・元別当ともに並んでいる例はなかなか貴重です。


【写真 上(左)】 院号標と長崎不動尊
【写真 下(右)】 長崎不動尊の扁額
山門手前、駅側にせり出すように堂宇を構えられる「長崎不動尊」は、昭和24年に地域の守護仏として造立奉安された比較的あたらしい尊像ながら、不動尊ならではの力づよいオーラを放たれています。
堂内には平成8年造立の聖観世音菩薩像も奉安されています。


【写真 上(左)】 舟型道標地蔵尊
【写真 下(右)】 地蔵尊の御真言
「長崎不動尊」のさらに手前には「舟型道標地蔵尊」。
寛政八年(1796年)造立、中山道板橋仲宿、厄除け祖師・妙法寺方面への道標となっていて、御仏体は江戸城築城時につかわれた石の一部と云われています。


【写真 上(左)】 寺カフェ『なゆた』
【写真 下(右)】 山門
右手には寺カフェ・赤門テラス『なゆた』。
正面の参道を進むと山門(赤門)です。
由来は上記のとおりで、切妻屋根銅板葺の薬医門で左右の袖塀を脇塀に当て付けています。
屋根の銅板はえんじ色ながら門柱・門扉は鮮やかな朱で、「赤門」のイメージを伝えています。

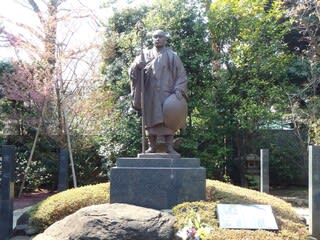
【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 修行大師像
山門をくぐると左手に修行大師像と四国八十八ヶ所お砂踏み霊場。
修行大師像の本堂寄りには「弘法大師・興教大師碑」、御朱印霊場札所標、マンガ地蔵尊などが並びます。
椎名町五丁目にあった「トキワ荘」は、手塚治虫、藤子不二雄、石ノ森章太郎、赤塚不二夫ら著名な漫画家が居住していた「漫画の聖地」です。
→ 豊島区立トキワ荘マンガミュージアム公式Web


【写真 上(左)】 マンガ地蔵尊
【写真 下(右)】 マンガ地蔵尊の台座銘
金剛院山内にはこれを記念して平成27年に「マンガ地蔵尊」が造立奉安されています。
錫杖の代わりにペンを持たれ、法衣の柄は漫画のコマ、光背がGペンという特徴あるおすがたです。
マンガ地蔵尊の御朱印も授与されています。


【写真 上(左)】 御府内霊場札所碑
【写真 下(右)】 修行大師像、大師堂と本堂
その先の大師堂は宝形造桟瓦葺で頂部に宝珠を置いています。
向かって左の柱に御寶号、右には御府内霊場札所板。

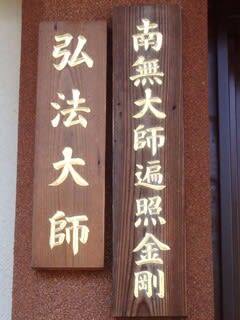
【写真 上(左)】 大師堂
【写真 下(右)】 御寶号板


【写真 上(左)】 御府内霊場札所板
【写真 下(右)】 霊場札所板
向拝上部には御府内・豊島両霊場の札所板と和讃(御詠歌)板が掲げられ、弘法大師霊場札所の趣きゆたか。
当山公式Webの御府内霊場の手引きページは懇切丁寧にまとめられ、Web検索でも上位ヒットします。
御府内霊場の巡拝者迎え入れに積極的なお寺さまかと思われます。
参道右手に建つ二基の板碑と庚申塔は区登録文化財。


【写真 上(左)】 板碑と仏塔
【写真 下(右)】 本堂
本堂は入母屋造本瓦葺流れ向拝の伽藍(外陣)とその後ろに宝形造二重屋根の伽藍(内陣)を隣接し、入母屋造平入りの後ろに相輪をみせる面白い意匠となっています。
昭和29年落慶の本堂は、コンクリ造ながら古典建築の造形を単純化してまとめた寺院建築として国の登録有形文化財に指定。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 客殿と庫裡
本堂向かって右手前の客殿は千鳥破風と起り屋根が印象的な瀟洒な建物で、こちらも国の登録有形文化財に指定されています。
御朱印は客殿よこの庫裡にて拝受しました。
こちらでは豊島八十八ヶ所霊場とマンガ地蔵尊の御朱印も授与されています。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に阿弥陀如来のお種子「キリーク」「無量壽」「弘法大師」の揮毫と宝珠の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「御府内八十八所第七十六番」の札所印。
左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
※「無量壽」は、阿弥陀如来の別号です。
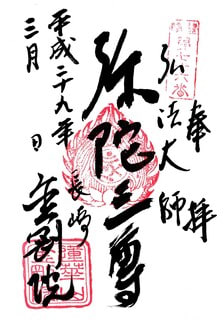
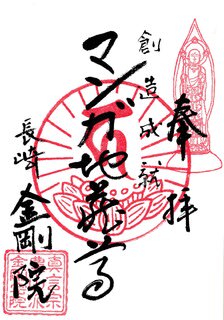
【写真 上(左)】 豊島霊場の御朱印
【写真 下(右)】 マンガ地蔵尊の御朱印
■ 第77番 高嶋山 歓喜寺 佛乗院
(ぶつじょういん)
神奈川県秦野市蓑毛957-13
真言宗智山派
御本尊:千手観世音菩薩
札所本尊:千手観世音菩薩
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第77番、御府内二十八不動霊場第17番、弁財天百社参り第17番
第77番は神奈川県秦野市の佛乗院です。
御府内霊場唯一の東京都外の札所です。
神奈川県といっても川崎や横浜ではありません。遠く丹沢山中の札所で、参拝は1日がかりとなります。
第77番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに佛乗院で、第77番札所は開創当初から芝三田の佛乗院であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
佛乗院の開山開基は不明ですが、当所は八丁堀にあり、寛永十二年(1635年)三田ないし日本橋に引移り、延宝年間(1763-1780年)に芝三田寺町に移転といいます。
中興開基は法印宥補(宝)と伝わります。
芝三田寺町の在所は大聖院と幸福寺の間、蛇坂の登り口付近でしたから、現在のケーヨーデイツー三田店あたりとみられます。
昭和62年、三田寺町から神奈川県秦野市の丹沢山中へ移転し、同時に御府内霊場第77番札所も移転して、最も遠方の札所となりました。
当初の御本尊は弘法大師の御作と伝わる旭辨財天木立像。
弘法大師御作とされる大聖歓喜天尊も奉安されていました。
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 』には「本尊:弁財天 歓喜天 弘法大師」とあり、すくなくとも幕末までは弁財天、大聖歓喜天尊、弘法大師の三尊が御府内霊場の拝尊であったことがわかります。
弁財天百社参り第17番の札所であり、御府内でも著名な辨財天霊場であったとみられます。
また、御府内二十八不動霊場第17番の札所本尊は、おそらく智證大師御作と伝わる不動明王とみられます。
現在の御本尊・札所本尊は千手観世音菩薩。
御本尊・札所本尊が替わられた経緯は不明です。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
七十七番
芝三田寺町
愛宕山真福寺末 新義真言宗
高嶋山 歓喜寺 佛乗院
本尊:弁財天 歓喜天 弘法大師
■ 『寺社書上 [13] 三田寺社書上 参』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.94』
三田寺町
愛宕前真福寺末 新義真言宗
高嶋山佛乗院歓喜寺
開闢起立之年代不分明
開山中興開山共ニ不分明
八丁(町)堀から当地に替地拝領仕 寛永十二年(1635年)当所(三田寺町)ニ引移●●
中興開基 法印宥補(宝)寛文六年(1666年)遷化
本堂
本尊 旭辨財天木立像 弘法大師作ト云 十五童子
大黒天 四天王 前立辨財天木座像
大聖歓喜天木立像 弘法大師作
大聖歓喜天真鍮立像
十一面観音木立像
不動明王木立像 智證大師作ト云
弘法大師
千躰地蔵尊木座像
阿弥陀如来木座像
鎮守八幡稲荷合社 但し御幣勧請
旭弁天社●-● 弘法大師近江國竹生島に三七日来●あり ●-● 手つから彫刻の尊像なり 元禄の頃吉水●●といふ医師弁天を伝●る事あり 当寺の住良運法印に●し弁天の●●
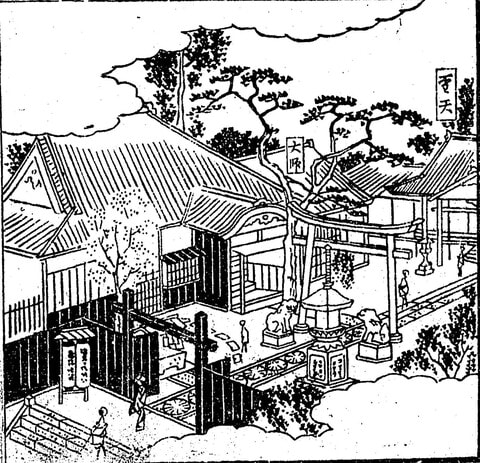
「佛乗院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』芝高輪辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2.国立国会図書館DC(保護期間満了)
■ 現在の三田寺町(蛇坂登り口付近)周辺の地図 ↓
-------------------------
小田急線「秦野」駅から神奈中バス蓑毛行きに乗り終点で下車。
バス停からさらに500mほど歩いたところです。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 御府内霊場札所標-1

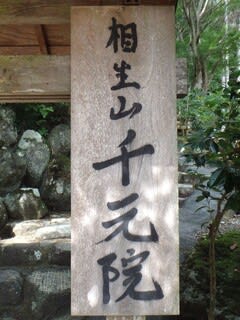
【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 千元院の院号標
林道的なロケーションに突然参道入口があらわれます。
右手おくの切妻屋根の建物には「相生山 千元院」とあり??マークがつきますが、参道入口には「札所七拾七番 佛乗院」とあります。
その先の山門には「相生山 千元院」とあり、どうやらふたつの号を号されているようです。
参道沿いに「南無相生大権現」の登りが並び、神仏習合の趣きがあります。
丹沢周辺には山気横溢するパワスポ的な寺院が多いですが、こちらもそのようなイメージがあります。
山門は簡素な二脚門で、門柱に札所板を掲げています。


【写真 上(左)】 御寶号碑
【写真 下(右)】 山内


【写真 上(左)】 御府内霊場札所標-2
【写真 下(右)】 相生大明神と本堂
石段を登ると右手に相生大明神。
『寺社書上』にある「鎮守八幡稲荷合社」と系譜がつながるかは不明です。
その先右奥の木立の下には水垢離場や小祠、お不動様の石像などが建ち並び、修験道場的なオーラを発しています。


【写真 上(左)】 御府内霊場札所碑
【写真 下(右)】 本堂
本堂はその先階段の上で、手前に観世音菩薩立像(平和観音)が御座します。
本堂は入母屋造妻入りかと思いますが、全貌がつかめないので断言できません。
手前に大きく張り出した向拝屋根。
雨の多い丹沢では、しっかり雨粒を防げるこのくらいの屋根が必要なのでしょう。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、中備に本蟇股を置き、向拝見上げには山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 御朱印案内
【写真 下(右)】 簑庵
御朱印は本堂向かって左手奥の庫裡にて拝受しました。
なお、山内掲示の 御朱印案内によると、ご不在の場合御朱印は郵送可能なようですが、やはり事前にTEL問いしてからお伺いするのがベターかと思います。
なお、以前は山内に割烹料理「蓑庵」がありましたが、現況の営業状況は不明です。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に千手観世音菩薩のお種子「キリク」「千住観音」「弘法大師」の揮毫と札番付の「キリク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「七十七番」の札所印。
左下に山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-26)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ Airport - 今井優子
■ 泣きたかった - 今井美樹
■Just Be Yourself - 杏里
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
| « 前ページ | 次ページ » |




