関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。
関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行
■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-24
Vol.-23からのつづきです。
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第72番 阿遮山 圓満寺 不動院
(ふどういん)
台東区寿2-5-2
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第72番、弘法大師二十一ヶ寺第6番、御府内二十八不動霊場第18番、坂東写東都三十三観音霊場第14番、関東三十六不動尊霊場第22番
第72番は寿の不動院です。
御府内霊場には「不動院」を号する札所寺院がふたつ(第6番(六本木)、第72番(浅草寿))あり、後者を寿不動院と呼んで区別しているようです。
第72番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに不動院で、第72番札所は開創当初から浅草寿の不動院であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』、『関東三十六不動霊場ガイドブック』などから縁起・沿革を追ってみます。
不動院は慶長十六年(1611年)、賢鏡法印が八丁堀に寺地を拝領して開山と伝わります。
御本尊は金剛界大日如来で、護摩堂に大日如来の教令輪身である不動明王を安置し祈祷を修したといいます。
不動院は往時から護摩堂の不動尊の験力の強さで知られていたようです。
寛永十二年(1635年)寺地を御用地として収公。
不動尊のあらたかな験力から、浅草の観音様の裏鬼門にあたる旧浅草(新寺町?)の地に遷ったともいいます。
(新寺町から明暦年間(1655-1658年)に現在地に移転という史料もあり。)
元禄期(1688-1704年)の不動院の住職は第6世覚意法印。
壱岐国領主日高覚左衛門の子で、松浦家家老の子息ともいいます。
元禄十年(1697年)、肥前国平戸藩主松浦鎮信は不動院の住職が家老の子息で、不動院が浅草鳥越の松浦家上屋敷の鬼門にあたることから当山を松浦家の祈願所とし、平戸に祀っていた松浦家守護仏の不動尊を、平戸の安満嶽に祀っていた金銅聖天尊像とともに当山に安置して一族の守護を祈念しました。
このときより、松浦家守護仏の不動尊を当山御本尊とし、従前より奉安の不動尊を御前立として安置と伝わります。
このときの住職・第6世覚意法印は、松浦家守護所となした功績もあってか中興開基とされています。
御本尊の不動明王は、奈良時代の華厳宗の高僧で東大寺の開山・良弁僧都(689-774年)の御作といいます。
良弁僧都には母親が仕事の最中、目を離した隙に鷲にさらわれ奈良の二月堂前の杉の木に引っかかっているのを師・義淵に助けられたという逸話があります。
良弁の母親は良弁を探し求めて全国を歩きつづけ、30年後ついに再会を果たしたといいます。
良弁は自身のような母親とのつらい別離が世の中からなくなるよう一心に念じつつ、不動明王の御像を謹刻されました。
この不動尊像は数多の変遷を経て肥前国平戸の松浦家の守護仏となり、島原の乱(1637-1638年)では数々の霊験をあらわされて、人々の尊崇いよいよ高まったといいます。
この尊像が不動院の御本尊で、わが子のことを一心に願えば無病息災に育ち、良縁にも恵まれ、たとえ悪病に罹ったとしても平癒するというので「子守り不動尊」と呼ばれて江戸庶民の信仰を集めました。
なお、『御府内八十八ケ所道しるべ』では「本尊:金剛界大日如来 弘法大師 興教大師」となっていますが、「本尊方除不動明王 良弁僧都之御作」ともあり、御府内霊場巡拝では不動尊も参拝されていたのでは。
明治初頭の神仏分離の波を乗り越え、御府内霊場札所も堅持されています。
昭和20年の空襲により諸伽藍を焼失しましたが、昭和40年現本堂を落慶。
昭和62年開創の関東三十六不動尊霊場第22番札所でもあり、浅草を代表する不動尊霊場として参拝者を迎えています。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
七十二番
浅草●下八軒寺町
阿遮山 圓満寺 不動院
大塚護持院末 新義
本尊:金剛界大日如来 弘法大師 興教大師
■ 『寺社書上 [75] 浅草寺社書上 甲三』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.52』
浅草八軒寺町
大塚護持院末 新義真言宗
阿遮山圓満寺不動院
江戸大塚護持院末、浅草八軒寺町
慶長十六年(1611年)寺地拝領仕 八丁堀二廿五ヶ年罷在候之処 御用地ニ付浅草新寺町ニ而替地拝領仕候
開山 賢鏡法印 年代不相知寂
中興開基 覚意儀 肥前平戸之産ニ● 壱岐国領主日高覚左衛門倅 只今●松浦家ニ覚左衛門子孫家老を勤罷在候
中興 栄実法印
旧浅草にあり明暦(1655-1658年)中此地に移る(江戸図説)
起立来暦詳ならす 慶長十六年(1611年)江戸八丁堀に寺地を賜り 夫より廿五年を経て寛永十二年(1635年)其地を収公せられ 今の所を賜り小坊を建 不動を安す
爰ニ肥前國平戸の城主松浦家の領内に良弁僧都の作の不動又歓喜天の像往古より安置せる所、嶋原退治の時、霊験掲焉に依て信●浅からす 今の浅草鳥越の屋敷に安せし●又奇瑞度々あるにより、汚穢の地に置障あらん事を恐● 元禄年中(1688-1704年)一宇を建立し是に移さんの発願にて彼是沙汰せしか 今の不動院破壊せる小宇にて名のみなるにより其上この屋敷より鬼門に当り殊に密宗なれハとて こゝに国家安鎮の為堂塔を建立弐百石寄附 両尊を安置しもとの像を前立とし第五世覚意といへるを住持とし 祈念怠慢なかりき 此覚意ハ松浦外記(今の家老)の子たれハ 幸に護持なさしむとそ 其後寄附の石高も多く減しけるとなり 去れとも今に松浦家の祈願所なりと
本堂
本尊 金剛界大日如来木座像
弘法大師木座像 興教大師木座像 理現(源)大師木座像 地蔵尊木像立像
護摩堂
不動尊木座像 良弁僧都作 両童子木立像 同作
縁起左之通(略)
霊府神木像 二童子木像
聖天鋼像 本地十一両観音木立像
肥前国安満嶽に安置御座候処 霊験有て備相●不自由ニ付 鳥越松浦肥前守屋敷江安置ニ而御座候 其後元禄中(1688-1704年)松浦鎮信公思召を以て 当院江祈祷処引移され覚意江住職被申付
大神宮木立像 大黒天木像 辨財天木座像 毘沙門天木像 摩利支天木像
大黒天木像(一体三身大黒天) 謁摩作
大黒天木像 弘法大師作 千手観音木像長
愛染明王 弘法大師作
鎮守社
金毘羅 保呂輪権現 稲荷大明神

「不動院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ銀座線「田原町」駅で徒歩約3分。
都道463号浅草通り「西浅草一丁目」交差点から「ことぶきこども園通り」を南下して、ふたつ目の角を西(右手)に入って少し行った右側です。


【写真 上(左)】 外観-1
【写真 下(右)】 外観-2


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 院号標
道沿いに築地塀を巡らし、山内入口に山門。
山門は切妻屋根桟瓦葺の薬医門で、門柱に院号標と御府内霊場・関東不動尊霊場併記の札所標を掲げています。


【写真 上(左)】 札所板
【写真 下(右)】 山門より山内
すぐ奥が本堂で、均整のとれた山門と鶯色の近代建築陸屋根2層の本堂が意匠的に面白い対比をみせています。
エントランスのベルを鳴らすとお寺の方が出てこられ、2階本堂のご案内をいただきました。
この際に御朱印帳をお預けし、参拝後に受けとります。


【写真 上(左)】 エントランス
【写真 下(右)】 2階の本堂
左手階段を登ると本堂。
1階はなんとなく学校を思わせる雰囲気でしたが、2階にあがると欄間彫刻、護摩壇の上に天蓋、そのおくの御内陣に御本尊が御座と、厳粛な仏堂の空気感。
御府内霊場は堂外向拝からの参拝が多いですが、このように堂内に上げていただけるのはありがたいことです。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

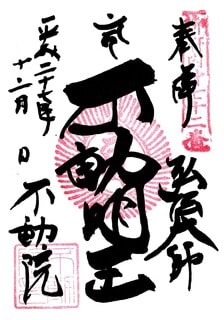
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央にお種子「カン/カーン」? 「不動明王」「弘法大師」の揮毫と不動明王のお種子「カン/カーン」の御寶印(火焔宝珠)。
右に「御府内七十二番」の札所印。
左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 関東三十六不動尊霊場の御朱印
■ 第73番 法号山 明王院 東覚寺
(とうがくじ)
江東区亀戸4-24-1
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第75番、亀戸七福神(弁財天)
第73番札所は下町・亀戸の東覚寺です。
御府内霊場には「東覚寺」を号する札所寺院がふたつ(第66番(田端)、第73番(亀戸))あり、前者を田端東覚寺、後者を亀戸東覚寺と呼んで区別しているようです。
第73番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに本所猿江町の法号山 花蔵院 覺王寺なので、江戸期の御府内霊場第73番は本所猿江の覺王寺であったとみられます。
明治34年、亀戸の東覚寺が本所猿江の法号山覺王寺を合併して明王山から法号山に号を改めるとともに、御府内霊場第73番札所を承継しています。
下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
東覚寺は、享禄四年(1531年)玄學法印の開山起立、明王山と号し御本尊に阿弥陀三尊を安したと伝わります。
不動堂に奉安の不動尊(亀戸不動尊)は良弁の御作で相州大山寺の御本尊と同木同作といい、霊験ことにあらたかとして正五九の月の廿八日に御開扉され、近郷の参詣人で賑わったといいます。
明治34年、本所猿江の法号山覺王寺を合併して明王山から法号山に号を改めました。
覺王寺は御府内八十八ヶ所霊場第73番札所で、それを示す碑が東覚寺に残されているそうです。
東覚寺は天保九年(1838年)以前の開創とみられる荒川辺八十八ヶ所霊場第75番の札所でしたから、この時点で御府内霊場、荒川辺霊場のふたつの弘法大師霊場の札所を兼ねることとなりました。
亀戸七福神の辨財天霊場としても親しまれています。
「猫の足あと」様には亀戸不動尊に関する『江東区の民俗城東編』の興味深い記事が紹介されているので、抜粋孫引きさせていただきます。
-------------------------
享禄四年(1531年)、玄學法印の草庵に笈を背負った優婆塞が宿を請うた。
翌朝、仏間に一人の男が呆然と立ちすくんでいたので法印が誰何するも何も答えなかった。
件の優婆塞が云うには、自分が背負ってきた不動尊の下した罰であろうと。
優婆塞が笈の前に脆き祈ると、その男は話せ、身体も動くようになったが、その男は自分は盗賊だがもうこれ以上の悪事はしないと誓って去った。
法印は仔細を優婆塞に尋ねると、良弁僧正が相州大山寺を開かれたとき、優婆塞の先祖が大山の麓で手助けした。良弁僧正はこの労に謝してこの不動尊を与え、この霊像により盗難や剣難から遁れられると告げた。
霊像は優婆塞の家に伝わって二五代。優婆塞もこの霊像の霊験により難を遁れること多かったという。
法印はこの霊像をこの地に安することを願い、優婆塞もその意に応じて法印に与えた。
以降、人々はこの霊像を「盗難除け不動尊」と呼び慣わしたという。
-------------------------
現在の御本尊は大日如来ですが、霊験あらたかな亀戸不動尊(盗難除け不動尊)も篤い信仰を集めていることがわかります。
********
覺王寺は慶長十九年(1614年)宗順法印が深川六間堀に開山し、当初は幸蔵寺を号したといいます。
元禄六年(1693年)に寺地が御用地となったため隣寺の慈眼寺とともに本所猿江町に移され、宝永六年(1709年)に覺王寺と改めたとされます。
亀戸普門院末の新義真言宗で御本尊に大日如来を安し、本堂内に弘法大師座像、興教大師座像、如意輪観世音菩薩、地蔵菩薩を奉安し、御府内霊場第73番の札所でした。
境内の石弘法大師の(傍らの?)石碑にも「御府内八拾八ヶ所」とあったようです。
『御府内八十八ケ所道しるべ 地』では御府内霊場の拝所は「本尊:金剛界大日如来 不動明王 弘法大師」とみえます。
仔細は不明ですが、上記のとおり明治34年に亀戸の東覚寺に合併され、御府内霊場第73番の札所も東覚寺に承継されています。
-------------------------
【史料】
【東覚寺関連】
■『新編武蔵風土記稿 巻之24 葛飾郡之5』(国立国会図書館)
(亀戸村)東覺寺
明王山ト号ス 本尊三尊弥陀ヲ安ス 開山玄學 享禄四年(1531年)ノ起立ナリト云傳フ
不動堂 不動ハ良弁ノ作 霊験アリシトテ正五九の月廿八日開扉シ近郷ノモノ参詣多シ
■『江戸名所図会 第4 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)
明王山東覺寺
真言宗にして、寺嶋の蓮華寺に属す。本尊は、彌陀、観音、勢至の三尊なり。当寺は、享禄四年(1531年)草創する所の寺院にして、開山を玄學法印と号す。
不動堂
当寺に安置す。良辨僧都の彫像にして、相州大山寺の本尊と同体なりといへり。
(以下縁起あり)
【覺王寺関連】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
七十三番
本所猿江町
法号山 花蔵院 覺王寺
亀戸普門院末 新義
本尊:金剛界大日如来 不動明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [107] 深川猿江寺社書上 十一』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.118』
本所猿江
亀戸普門院末 新義真言宗
法号山花蔵院覺王寺
当寺●元六間堀ニ有 御用地と●付 元禄六年(1693年)当地ニ替地
開山 宗順 慶長十九年(1614年)寂
中興開山 秀山 正徳五年(1715年)寂
開基 不分明
慶長十九年(1614年)の起立なり もとハ幸蔵寺と称して深川六間堀の邉にあり
元禄六年(1693年)隣寺慈眼寺と共ニここへ移され その後宝永六年(1709年)●●今の寺号に改しと云
本堂
本尊 大日如来座像
弘法大師座像 興教大師座像 如意輪観世音座像 地蔵尊立像
境内
石地蔵尊
石弘法大師 但御府内八拾八ヶ所石碑表ニ南無大師遍照金剛有り

「覺王寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』深川絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはJR・東武亀戸線「亀戸」駅で徒歩約10分。
亀戸香取神社の南東にあります。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 門柱の寺号標
入口は門柱で、手前に「不動明王」の石標。
山内は石敷きで広々とあかるいイメージ。


【写真 上(左)】 不動明王の石
【写真 下(右)】 山内
山内のたしか右手に辨天堂があり、亀戸七福神の札所となっています。


【写真 上(左)】 辨天堂
【写真 下(右)】 辨天堂の扁額
本堂は入母屋造銅板葺流れ向拝、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を備えています。
向拝見上げには山号扁額。
真新しいですが、端正で落ち着きのある伽藍です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
史料にある覚王寺の御府内八十八ヶ所霊場第73番札所を示す碑は、筆者にはみつけられませんでした。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 納経所案内
御朱印は本堂向かって右の庫裡にて拝受しました。
亀戸七福神の辨財天と亀戸不動尊の御朱印も授与されています。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

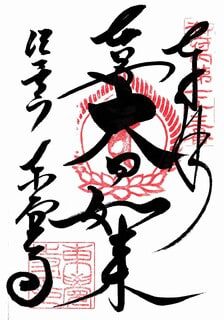
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊大日如来」「弘法大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内第七十三番」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。


【写真 上(左)】 亀戸不動尊の御朱印
【写真 下(右)】 亀戸七福神(辨財天)の御朱印
■ 第74番 賢臺山 賢法寺 法乗院(深川ゑんま堂)
(ほうじょういん)
公式Web
江東区深川2-16-3
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第74番、御府内二十八不動霊場第14番、坂東写東都三十三観音霊場第28番、江戸・東京四十四閻魔参り第15番
第74番は「深川ゑんま堂」で有名な法乗院です。
第74番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに法乗院で、第74番札所は開創当初から深川の法乗院であったとみられます。
公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
法乗院は寛永六年(1629年)、深川猟師町相川町富吉町(現・江東区佐賀)に覚譽法印(『寺社書上』では覚春法印)の開山で創建といいます。
寛永十八年(1641年)、寺地が御用地となったため現在地(深川七軒寺町)に替地を得て移転。
『御府内寺社備考』によると当初の御本尊は閻魔大王でしたが、宝暦十年(1760年)類焼したため行基菩薩の御作という金剛界大日如来が御本尊になったといいます。
類焼ののち閻魔大王の代仏?を奉安とみられ、以降も「深川のおゑんまさま」として親しまれ、「江戸三閻魔」に数えられたとも。
なお、「江戸三閻魔」は下谷坂本の善養寺、蔵前の華徳院、内藤新宿の太宗寺をさすという説もありますが、『江戸歳時記』の閻魔霊場をまとめた記事に、しっかり「深川寺町 法乗院」とあるのでやはり著名な閻魔さまであったことは間違いないかと。
(■ 参考記事 都内の閻魔大王の御朱印)
当山正面に通じる道の十五間川(油堀)には「ゑんま堂橋」が架けられ、いまの清澄通りがなかった時代は深川のメイン通りでした。
「ゑんま堂橋」跡は史跡(富岡橋跡)に指定されています。
法乗院の公式Webには「里俗に為永春水『春暁八幡佳年』、河竹黙阿弥『梅雨小袖昔八丈』などの江戸町人気質を盛り込んだ代表的江戸文芸や芝居の作品中にも当山は描かれており、当時の様子を伺い知ることが出来ます。なかでも『髪結い新三』の「ゑんま堂の場」は、当山が描かれた名場面の一つです。」とあり、深川ゑんま堂が江戸っ子に広く知られていた様子がうかがえます。
本堂には御本尊大日如来、弘法大師像、興教大師像を奉安。
護摩堂に奉安の不動尊像は良辨僧都の御作で、海中出現の縁起をもたれます。
当山は御府内二十八不動霊場第14番の札所で、不動尊霊場の役割も果たしていました。
平成元年像立の閻魔大王像は全高3.5m、全幅4.5m、重さ1.5tの日本最大級の巨大な座像で、左手には金色の地蔵菩薩を載せられるというインパクトあるお姿です。
インパクトはそのお姿だけではありません。
この閻魔さまは19の御祈願に対してお賽銭を投入すると、おもむろに説教を始められるのです。
↓ こんな感じです。(動画のラストに音が大きくなるので要注意)
あまりにすばらしいのでもう一本!
どうです、日々の煩悩でざらついた心に閻魔さまの一言一言が染み渡りませんか(笑)
筆者は深川あたりに行くと法乗院に参拝し、閻魔様のお説教をいくつも聞いてしまいます。
本堂一階には天明四年(1784年)に江戸の宋庵という絵師によって描かれた全16枚の地獄・極楽図が展示されています。
「御仏の教えの根本理念は、因果応報にあります。悪行を積めば悪い結果に、善行はよい結果になるように、人間は生きている時の行いが全ての原因になるということなのです。」(公式Webより引用)
こんな時代だからこそ、閻魔さま詣でをしつつ、勧善懲悪、因果応報の教えを噛みしめてみるのもいいかもしれせん。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
七十四番
深川七軒寺町
葛飾小岩村善養寺末 新義
賢臺山 賢法寺 法乗院
本尊:大日如来 弘法大師 興教大師
■ 『寺社書上 [101] 深川寺社書上 五』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.120』
深川七軒寺町
葛飾西領小岩村善養寺末 新義真言宗
賢臺山賢法寺法乗院
起立之儀寛永六年(1629年)、深川猟師町相川町富吉町(現・江東区佐賀)に有 寺地●●寛永十八年(1641年)御用地に相成只今の場所に替地
開山 覚春法印 寛永二十年(1643年)卒
開基 不分明
中興開山 覚譽法印 万治二年(1659年)卒
本堂
本尊 金剛界大日如来木座像 行基菩薩作
元々本尊閻魔王に候●候 宝暦十年(1760年)類焼 只今之本尊これ也
弘法大師木座像 興教大師
護摩堂
不動明王木座像 良辨僧都作 二童子木座像
右不動尊ハ寛永年中(1624-1644年)深川今の相川町遠海にて毎夜光を放ち●● 猟師是所を尋るに木像の不動尊有 海中より上らせぬ●ハ覚譽法印猟師より申請当寺に安置
閻魔堂
閻魔王木座像六尺五寸 運慶作
十王
三途川老婆木座像
子育地蔵尊石立像 右は築地之海●上らせぬ尊像
地中 不動院
開山 賢覚法印 延宝元年(1673年)卒
本尊 胎蔵界大日如来木座像

「法乗院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』深川絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ東西線・都営大江戸線「門前仲町」駅。
大江戸線両国寄りの6番出口が至近です。
門前仲町から清澄・白河にかけての一帯は谷中ほどの知名度はないものの都内有数の寺町で、多くの寺院が御朱印・御首題を授与されています。
宗派は浄土宗、日蓮宗が多く真言宗寺院は比較的少ないので、御府内霊場札所は第37番萬徳院、第68番永代寺、第74番法乗院を数えるのみです。


【写真 上(左)】 提灯と院号標
【写真 下(右)】 門前にお出ましの閻魔さま
清澄通り沿いに「深川ゑんま堂」の提灯をならべ、山門脇には写真の閻魔さまがお出ましになって、すでに門前から閻魔霊場の趣きを色濃くただよわせています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 院号標
朱塗りの山門は変わった様式で、これをどう呼ぶのか筆者にはわかりません。
山門をくぐると正面が本堂、向かって左手が閻魔堂です。


【写真 上(左)】 山門から山内
【写真 下(右)】 本堂と閻魔堂


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
本堂は二層で、二階が本堂、一階が墓苑と思われます。
本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝、身舎の朱と欄干の緑青色のコントラストが絶妙。
一階中央は預骨仏(墓苑内本尊釈迦如来像胎内)。向かって右手に延命普賢菩薩、左手に大孔雀明王という、あまりみられない尊格配置。
とくに孔雀明王は間近で拝する機会が少ないので貴重です。
二階の本堂は閉扉されて薄暗いですが、中央に智拳印を結ばれる金剛界大日如来が御座されていました。
不動尊霊場の札所本尊もこちらに御座されているのかもしれません。
本堂前向かって右手には4体の地蔵尊立像。
それぞれ本堂寄りから「十日地蔵尊」「光岳地蔵尊」「子育地蔵尊」「水子地蔵尊」とありました。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 深川のお閻魔さま


【写真 上(左)】 閻魔堂
【写真 下(右)】 閉扉時の閻魔堂向拝
閻魔堂は二層の楼閣で桟瓦葺。二層頂部に宝珠、一層向拝上に唐破風を興しています。
朱塗りメインで華々しい印象の堂宇です。
毎月一日と十六日はアクリル扉が御開扉され、より閻魔様が拝みやすくなります。


【写真 上(左)】 御開扉時の閻魔堂向拝
【写真 下(右)】 閻魔さま
「これぞ閻魔さま」ともいえる迫力のお姿で、左手の掌上には金色の地蔵尊立像が輝いています。
上記の「お賽銭お説教」は、一聴の価値ありなのでぜひぜひどうぞ。


【写真 上(左)】 豊田鳳憬尺八塚
【写真 下(右)】 鳥塚
山内には尺八琴古流宗家・初代豊田鳳憬の「豊田鳳憬尺八塚」、鳥類殺生供養の「鳥塚」と曾我五郎の足跡石があります。
曾我五郎は歌舞伎「曾我物語」の主人公で、足跡石は歌舞伎に縁深い当山に移されたそうです。
御朱印は本堂向かって右手の寺務所にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
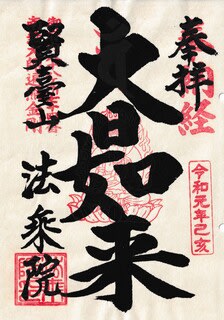

【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「大日如来」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」と御影印。
左上に「御府内八十八ヶ所七十四番南無大師遍照金剛」の札所印。
左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
こちらは揮毫御朱印と印判御朱印を授与されますが、現在は御府内霊場専用集印帳のみ揮毫御朱印かもしれません。

■ 閻魔大王の御朱印
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-25)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ 夏空の下 - やなわらばー
■ Erato - 志方あきこ
■Saikou no Kataomoi (最高の片想い) - Sachi Tainaka
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第72番 阿遮山 圓満寺 不動院
(ふどういん)
台東区寿2-5-2
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第72番、弘法大師二十一ヶ寺第6番、御府内二十八不動霊場第18番、坂東写東都三十三観音霊場第14番、関東三十六不動尊霊場第22番
第72番は寿の不動院です。
御府内霊場には「不動院」を号する札所寺院がふたつ(第6番(六本木)、第72番(浅草寿))あり、後者を寿不動院と呼んで区別しているようです。
第72番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに不動院で、第72番札所は開創当初から浅草寿の不動院であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』、『関東三十六不動霊場ガイドブック』などから縁起・沿革を追ってみます。
不動院は慶長十六年(1611年)、賢鏡法印が八丁堀に寺地を拝領して開山と伝わります。
御本尊は金剛界大日如来で、護摩堂に大日如来の教令輪身である不動明王を安置し祈祷を修したといいます。
不動院は往時から護摩堂の不動尊の験力の強さで知られていたようです。
寛永十二年(1635年)寺地を御用地として収公。
不動尊のあらたかな験力から、浅草の観音様の裏鬼門にあたる旧浅草(新寺町?)の地に遷ったともいいます。
(新寺町から明暦年間(1655-1658年)に現在地に移転という史料もあり。)
元禄期(1688-1704年)の不動院の住職は第6世覚意法印。
壱岐国領主日高覚左衛門の子で、松浦家家老の子息ともいいます。
元禄十年(1697年)、肥前国平戸藩主松浦鎮信は不動院の住職が家老の子息で、不動院が浅草鳥越の松浦家上屋敷の鬼門にあたることから当山を松浦家の祈願所とし、平戸に祀っていた松浦家守護仏の不動尊を、平戸の安満嶽に祀っていた金銅聖天尊像とともに当山に安置して一族の守護を祈念しました。
このときより、松浦家守護仏の不動尊を当山御本尊とし、従前より奉安の不動尊を御前立として安置と伝わります。
このときの住職・第6世覚意法印は、松浦家守護所となした功績もあってか中興開基とされています。
御本尊の不動明王は、奈良時代の華厳宗の高僧で東大寺の開山・良弁僧都(689-774年)の御作といいます。
良弁僧都には母親が仕事の最中、目を離した隙に鷲にさらわれ奈良の二月堂前の杉の木に引っかかっているのを師・義淵に助けられたという逸話があります。
良弁の母親は良弁を探し求めて全国を歩きつづけ、30年後ついに再会を果たしたといいます。
良弁は自身のような母親とのつらい別離が世の中からなくなるよう一心に念じつつ、不動明王の御像を謹刻されました。
この不動尊像は数多の変遷を経て肥前国平戸の松浦家の守護仏となり、島原の乱(1637-1638年)では数々の霊験をあらわされて、人々の尊崇いよいよ高まったといいます。
この尊像が不動院の御本尊で、わが子のことを一心に願えば無病息災に育ち、良縁にも恵まれ、たとえ悪病に罹ったとしても平癒するというので「子守り不動尊」と呼ばれて江戸庶民の信仰を集めました。
なお、『御府内八十八ケ所道しるべ』では「本尊:金剛界大日如来 弘法大師 興教大師」となっていますが、「本尊方除不動明王 良弁僧都之御作」ともあり、御府内霊場巡拝では不動尊も参拝されていたのでは。
明治初頭の神仏分離の波を乗り越え、御府内霊場札所も堅持されています。
昭和20年の空襲により諸伽藍を焼失しましたが、昭和40年現本堂を落慶。
昭和62年開創の関東三十六不動尊霊場第22番札所でもあり、浅草を代表する不動尊霊場として参拝者を迎えています。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
七十二番
浅草●下八軒寺町
阿遮山 圓満寺 不動院
大塚護持院末 新義
本尊:金剛界大日如来 弘法大師 興教大師
■ 『寺社書上 [75] 浅草寺社書上 甲三』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.52』
浅草八軒寺町
大塚護持院末 新義真言宗
阿遮山圓満寺不動院
江戸大塚護持院末、浅草八軒寺町
慶長十六年(1611年)寺地拝領仕 八丁堀二廿五ヶ年罷在候之処 御用地ニ付浅草新寺町ニ而替地拝領仕候
開山 賢鏡法印 年代不相知寂
中興開基 覚意儀 肥前平戸之産ニ● 壱岐国領主日高覚左衛門倅 只今●松浦家ニ覚左衛門子孫家老を勤罷在候
中興 栄実法印
旧浅草にあり明暦(1655-1658年)中此地に移る(江戸図説)
起立来暦詳ならす 慶長十六年(1611年)江戸八丁堀に寺地を賜り 夫より廿五年を経て寛永十二年(1635年)其地を収公せられ 今の所を賜り小坊を建 不動を安す
爰ニ肥前國平戸の城主松浦家の領内に良弁僧都の作の不動又歓喜天の像往古より安置せる所、嶋原退治の時、霊験掲焉に依て信●浅からす 今の浅草鳥越の屋敷に安せし●又奇瑞度々あるにより、汚穢の地に置障あらん事を恐● 元禄年中(1688-1704年)一宇を建立し是に移さんの発願にて彼是沙汰せしか 今の不動院破壊せる小宇にて名のみなるにより其上この屋敷より鬼門に当り殊に密宗なれハとて こゝに国家安鎮の為堂塔を建立弐百石寄附 両尊を安置しもとの像を前立とし第五世覚意といへるを住持とし 祈念怠慢なかりき 此覚意ハ松浦外記(今の家老)の子たれハ 幸に護持なさしむとそ 其後寄附の石高も多く減しけるとなり 去れとも今に松浦家の祈願所なりと
本堂
本尊 金剛界大日如来木座像
弘法大師木座像 興教大師木座像 理現(源)大師木座像 地蔵尊木像立像
護摩堂
不動尊木座像 良弁僧都作 両童子木立像 同作
縁起左之通(略)
霊府神木像 二童子木像
聖天鋼像 本地十一両観音木立像
肥前国安満嶽に安置御座候処 霊験有て備相●不自由ニ付 鳥越松浦肥前守屋敷江安置ニ而御座候 其後元禄中(1688-1704年)松浦鎮信公思召を以て 当院江祈祷処引移され覚意江住職被申付
大神宮木立像 大黒天木像 辨財天木座像 毘沙門天木像 摩利支天木像
大黒天木像(一体三身大黒天) 謁摩作
大黒天木像 弘法大師作 千手観音木像長
愛染明王 弘法大師作
鎮守社
金毘羅 保呂輪権現 稲荷大明神

「不動院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ銀座線「田原町」駅で徒歩約3分。
都道463号浅草通り「西浅草一丁目」交差点から「ことぶきこども園通り」を南下して、ふたつ目の角を西(右手)に入って少し行った右側です。


【写真 上(左)】 外観-1
【写真 下(右)】 外観-2


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 院号標
道沿いに築地塀を巡らし、山内入口に山門。
山門は切妻屋根桟瓦葺の薬医門で、門柱に院号標と御府内霊場・関東不動尊霊場併記の札所標を掲げています。


【写真 上(左)】 札所板
【写真 下(右)】 山門より山内
すぐ奥が本堂で、均整のとれた山門と鶯色の近代建築陸屋根2層の本堂が意匠的に面白い対比をみせています。
エントランスのベルを鳴らすとお寺の方が出てこられ、2階本堂のご案内をいただきました。
この際に御朱印帳をお預けし、参拝後に受けとります。


【写真 上(左)】 エントランス
【写真 下(右)】 2階の本堂
左手階段を登ると本堂。
1階はなんとなく学校を思わせる雰囲気でしたが、2階にあがると欄間彫刻、護摩壇の上に天蓋、そのおくの御内陣に御本尊が御座と、厳粛な仏堂の空気感。
御府内霊場は堂外向拝からの参拝が多いですが、このように堂内に上げていただけるのはありがたいことです。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

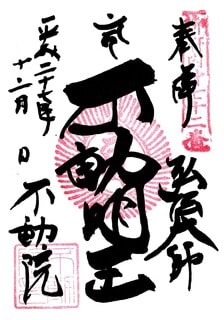
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央にお種子「カン/カーン」? 「不動明王」「弘法大師」の揮毫と不動明王のお種子「カン/カーン」の御寶印(火焔宝珠)。
右に「御府内七十二番」の札所印。
左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 関東三十六不動尊霊場の御朱印
■ 第73番 法号山 明王院 東覚寺
(とうがくじ)
江東区亀戸4-24-1
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第75番、亀戸七福神(弁財天)
第73番札所は下町・亀戸の東覚寺です。
御府内霊場には「東覚寺」を号する札所寺院がふたつ(第66番(田端)、第73番(亀戸))あり、前者を田端東覚寺、後者を亀戸東覚寺と呼んで区別しているようです。
第73番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに本所猿江町の法号山 花蔵院 覺王寺なので、江戸期の御府内霊場第73番は本所猿江の覺王寺であったとみられます。
明治34年、亀戸の東覚寺が本所猿江の法号山覺王寺を合併して明王山から法号山に号を改めるとともに、御府内霊場第73番札所を承継しています。
下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
東覚寺は、享禄四年(1531年)玄學法印の開山起立、明王山と号し御本尊に阿弥陀三尊を安したと伝わります。
不動堂に奉安の不動尊(亀戸不動尊)は良弁の御作で相州大山寺の御本尊と同木同作といい、霊験ことにあらたかとして正五九の月の廿八日に御開扉され、近郷の参詣人で賑わったといいます。
明治34年、本所猿江の法号山覺王寺を合併して明王山から法号山に号を改めました。
覺王寺は御府内八十八ヶ所霊場第73番札所で、それを示す碑が東覚寺に残されているそうです。
東覚寺は天保九年(1838年)以前の開創とみられる荒川辺八十八ヶ所霊場第75番の札所でしたから、この時点で御府内霊場、荒川辺霊場のふたつの弘法大師霊場の札所を兼ねることとなりました。
亀戸七福神の辨財天霊場としても親しまれています。
「猫の足あと」様には亀戸不動尊に関する『江東区の民俗城東編』の興味深い記事が紹介されているので、抜粋孫引きさせていただきます。
-------------------------
享禄四年(1531年)、玄學法印の草庵に笈を背負った優婆塞が宿を請うた。
翌朝、仏間に一人の男が呆然と立ちすくんでいたので法印が誰何するも何も答えなかった。
件の優婆塞が云うには、自分が背負ってきた不動尊の下した罰であろうと。
優婆塞が笈の前に脆き祈ると、その男は話せ、身体も動くようになったが、その男は自分は盗賊だがもうこれ以上の悪事はしないと誓って去った。
法印は仔細を優婆塞に尋ねると、良弁僧正が相州大山寺を開かれたとき、優婆塞の先祖が大山の麓で手助けした。良弁僧正はこの労に謝してこの不動尊を与え、この霊像により盗難や剣難から遁れられると告げた。
霊像は優婆塞の家に伝わって二五代。優婆塞もこの霊像の霊験により難を遁れること多かったという。
法印はこの霊像をこの地に安することを願い、優婆塞もその意に応じて法印に与えた。
以降、人々はこの霊像を「盗難除け不動尊」と呼び慣わしたという。
-------------------------
現在の御本尊は大日如来ですが、霊験あらたかな亀戸不動尊(盗難除け不動尊)も篤い信仰を集めていることがわかります。
********
覺王寺は慶長十九年(1614年)宗順法印が深川六間堀に開山し、当初は幸蔵寺を号したといいます。
元禄六年(1693年)に寺地が御用地となったため隣寺の慈眼寺とともに本所猿江町に移され、宝永六年(1709年)に覺王寺と改めたとされます。
亀戸普門院末の新義真言宗で御本尊に大日如来を安し、本堂内に弘法大師座像、興教大師座像、如意輪観世音菩薩、地蔵菩薩を奉安し、御府内霊場第73番の札所でした。
境内の石弘法大師の(傍らの?)石碑にも「御府内八拾八ヶ所」とあったようです。
『御府内八十八ケ所道しるべ 地』では御府内霊場の拝所は「本尊:金剛界大日如来 不動明王 弘法大師」とみえます。
仔細は不明ですが、上記のとおり明治34年に亀戸の東覚寺に合併され、御府内霊場第73番の札所も東覚寺に承継されています。
-------------------------
【史料】
【東覚寺関連】
■『新編武蔵風土記稿 巻之24 葛飾郡之5』(国立国会図書館)
(亀戸村)東覺寺
明王山ト号ス 本尊三尊弥陀ヲ安ス 開山玄學 享禄四年(1531年)ノ起立ナリト云傳フ
不動堂 不動ハ良弁ノ作 霊験アリシトテ正五九の月廿八日開扉シ近郷ノモノ参詣多シ
■『江戸名所図会 第4 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)
明王山東覺寺
真言宗にして、寺嶋の蓮華寺に属す。本尊は、彌陀、観音、勢至の三尊なり。当寺は、享禄四年(1531年)草創する所の寺院にして、開山を玄學法印と号す。
不動堂
当寺に安置す。良辨僧都の彫像にして、相州大山寺の本尊と同体なりといへり。
(以下縁起あり)
【覺王寺関連】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
七十三番
本所猿江町
法号山 花蔵院 覺王寺
亀戸普門院末 新義
本尊:金剛界大日如来 不動明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [107] 深川猿江寺社書上 十一』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.118』
本所猿江
亀戸普門院末 新義真言宗
法号山花蔵院覺王寺
当寺●元六間堀ニ有 御用地と●付 元禄六年(1693年)当地ニ替地
開山 宗順 慶長十九年(1614年)寂
中興開山 秀山 正徳五年(1715年)寂
開基 不分明
慶長十九年(1614年)の起立なり もとハ幸蔵寺と称して深川六間堀の邉にあり
元禄六年(1693年)隣寺慈眼寺と共ニここへ移され その後宝永六年(1709年)●●今の寺号に改しと云
本堂
本尊 大日如来座像
弘法大師座像 興教大師座像 如意輪観世音座像 地蔵尊立像
境内
石地蔵尊
石弘法大師 但御府内八拾八ヶ所石碑表ニ南無大師遍照金剛有り

「覺王寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』深川絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはJR・東武亀戸線「亀戸」駅で徒歩約10分。
亀戸香取神社の南東にあります。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 門柱の寺号標
入口は門柱で、手前に「不動明王」の石標。
山内は石敷きで広々とあかるいイメージ。


【写真 上(左)】 不動明王の石
【写真 下(右)】 山内
山内のたしか右手に辨天堂があり、亀戸七福神の札所となっています。


【写真 上(左)】 辨天堂
【写真 下(右)】 辨天堂の扁額
本堂は入母屋造銅板葺流れ向拝、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を備えています。
向拝見上げには山号扁額。
真新しいですが、端正で落ち着きのある伽藍です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
史料にある覚王寺の御府内八十八ヶ所霊場第73番札所を示す碑は、筆者にはみつけられませんでした。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 納経所案内
御朱印は本堂向かって右の庫裡にて拝受しました。
亀戸七福神の辨財天と亀戸不動尊の御朱印も授与されています。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

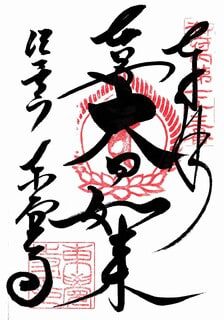
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊大日如来」「弘法大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内第七十三番」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。


【写真 上(左)】 亀戸不動尊の御朱印
【写真 下(右)】 亀戸七福神(辨財天)の御朱印
■ 第74番 賢臺山 賢法寺 法乗院(深川ゑんま堂)
(ほうじょういん)
公式Web
江東区深川2-16-3
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第74番、御府内二十八不動霊場第14番、坂東写東都三十三観音霊場第28番、江戸・東京四十四閻魔参り第15番
第74番は「深川ゑんま堂」で有名な法乗院です。
第74番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに法乗院で、第74番札所は開創当初から深川の法乗院であったとみられます。
公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
法乗院は寛永六年(1629年)、深川猟師町相川町富吉町(現・江東区佐賀)に覚譽法印(『寺社書上』では覚春法印)の開山で創建といいます。
寛永十八年(1641年)、寺地が御用地となったため現在地(深川七軒寺町)に替地を得て移転。
『御府内寺社備考』によると当初の御本尊は閻魔大王でしたが、宝暦十年(1760年)類焼したため行基菩薩の御作という金剛界大日如来が御本尊になったといいます。
類焼ののち閻魔大王の代仏?を奉安とみられ、以降も「深川のおゑんまさま」として親しまれ、「江戸三閻魔」に数えられたとも。
なお、「江戸三閻魔」は下谷坂本の善養寺、蔵前の華徳院、内藤新宿の太宗寺をさすという説もありますが、『江戸歳時記』の閻魔霊場をまとめた記事に、しっかり「深川寺町 法乗院」とあるのでやはり著名な閻魔さまであったことは間違いないかと。
(■ 参考記事 都内の閻魔大王の御朱印)
当山正面に通じる道の十五間川(油堀)には「ゑんま堂橋」が架けられ、いまの清澄通りがなかった時代は深川のメイン通りでした。
「ゑんま堂橋」跡は史跡(富岡橋跡)に指定されています。
法乗院の公式Webには「里俗に為永春水『春暁八幡佳年』、河竹黙阿弥『梅雨小袖昔八丈』などの江戸町人気質を盛り込んだ代表的江戸文芸や芝居の作品中にも当山は描かれており、当時の様子を伺い知ることが出来ます。なかでも『髪結い新三』の「ゑんま堂の場」は、当山が描かれた名場面の一つです。」とあり、深川ゑんま堂が江戸っ子に広く知られていた様子がうかがえます。
本堂には御本尊大日如来、弘法大師像、興教大師像を奉安。
護摩堂に奉安の不動尊像は良辨僧都の御作で、海中出現の縁起をもたれます。
当山は御府内二十八不動霊場第14番の札所で、不動尊霊場の役割も果たしていました。
平成元年像立の閻魔大王像は全高3.5m、全幅4.5m、重さ1.5tの日本最大級の巨大な座像で、左手には金色の地蔵菩薩を載せられるというインパクトあるお姿です。
インパクトはそのお姿だけではありません。
この閻魔さまは19の御祈願に対してお賽銭を投入すると、おもむろに説教を始められるのです。
↓ こんな感じです。(動画のラストに音が大きくなるので要注意)
あまりにすばらしいのでもう一本!
どうです、日々の煩悩でざらついた心に閻魔さまの一言一言が染み渡りませんか(笑)
筆者は深川あたりに行くと法乗院に参拝し、閻魔様のお説教をいくつも聞いてしまいます。
本堂一階には天明四年(1784年)に江戸の宋庵という絵師によって描かれた全16枚の地獄・極楽図が展示されています。
「御仏の教えの根本理念は、因果応報にあります。悪行を積めば悪い結果に、善行はよい結果になるように、人間は生きている時の行いが全ての原因になるということなのです。」(公式Webより引用)
こんな時代だからこそ、閻魔さま詣でをしつつ、勧善懲悪、因果応報の教えを噛みしめてみるのもいいかもしれせん。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
七十四番
深川七軒寺町
葛飾小岩村善養寺末 新義
賢臺山 賢法寺 法乗院
本尊:大日如来 弘法大師 興教大師
■ 『寺社書上 [101] 深川寺社書上 五』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.120』
深川七軒寺町
葛飾西領小岩村善養寺末 新義真言宗
賢臺山賢法寺法乗院
起立之儀寛永六年(1629年)、深川猟師町相川町富吉町(現・江東区佐賀)に有 寺地●●寛永十八年(1641年)御用地に相成只今の場所に替地
開山 覚春法印 寛永二十年(1643年)卒
開基 不分明
中興開山 覚譽法印 万治二年(1659年)卒
本堂
本尊 金剛界大日如来木座像 行基菩薩作
元々本尊閻魔王に候●候 宝暦十年(1760年)類焼 只今之本尊これ也
弘法大師木座像 興教大師
護摩堂
不動明王木座像 良辨僧都作 二童子木座像
右不動尊ハ寛永年中(1624-1644年)深川今の相川町遠海にて毎夜光を放ち●● 猟師是所を尋るに木像の不動尊有 海中より上らせぬ●ハ覚譽法印猟師より申請当寺に安置
閻魔堂
閻魔王木座像六尺五寸 運慶作
十王
三途川老婆木座像
子育地蔵尊石立像 右は築地之海●上らせぬ尊像
地中 不動院
開山 賢覚法印 延宝元年(1673年)卒
本尊 胎蔵界大日如来木座像

「法乗院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』深川絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ東西線・都営大江戸線「門前仲町」駅。
大江戸線両国寄りの6番出口が至近です。
門前仲町から清澄・白河にかけての一帯は谷中ほどの知名度はないものの都内有数の寺町で、多くの寺院が御朱印・御首題を授与されています。
宗派は浄土宗、日蓮宗が多く真言宗寺院は比較的少ないので、御府内霊場札所は第37番萬徳院、第68番永代寺、第74番法乗院を数えるのみです。


【写真 上(左)】 提灯と院号標
【写真 下(右)】 門前にお出ましの閻魔さま
清澄通り沿いに「深川ゑんま堂」の提灯をならべ、山門脇には写真の閻魔さまがお出ましになって、すでに門前から閻魔霊場の趣きを色濃くただよわせています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 院号標
朱塗りの山門は変わった様式で、これをどう呼ぶのか筆者にはわかりません。
山門をくぐると正面が本堂、向かって左手が閻魔堂です。


【写真 上(左)】 山門から山内
【写真 下(右)】 本堂と閻魔堂


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
本堂は二層で、二階が本堂、一階が墓苑と思われます。
本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝、身舎の朱と欄干の緑青色のコントラストが絶妙。
一階中央は預骨仏(墓苑内本尊釈迦如来像胎内)。向かって右手に延命普賢菩薩、左手に大孔雀明王という、あまりみられない尊格配置。
とくに孔雀明王は間近で拝する機会が少ないので貴重です。
二階の本堂は閉扉されて薄暗いですが、中央に智拳印を結ばれる金剛界大日如来が御座されていました。
不動尊霊場の札所本尊もこちらに御座されているのかもしれません。
本堂前向かって右手には4体の地蔵尊立像。
それぞれ本堂寄りから「十日地蔵尊」「光岳地蔵尊」「子育地蔵尊」「水子地蔵尊」とありました。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 深川のお閻魔さま


【写真 上(左)】 閻魔堂
【写真 下(右)】 閉扉時の閻魔堂向拝
閻魔堂は二層の楼閣で桟瓦葺。二層頂部に宝珠、一層向拝上に唐破風を興しています。
朱塗りメインで華々しい印象の堂宇です。
毎月一日と十六日はアクリル扉が御開扉され、より閻魔様が拝みやすくなります。


【写真 上(左)】 御開扉時の閻魔堂向拝
【写真 下(右)】 閻魔さま
「これぞ閻魔さま」ともいえる迫力のお姿で、左手の掌上には金色の地蔵尊立像が輝いています。
上記の「お賽銭お説教」は、一聴の価値ありなのでぜひぜひどうぞ。


【写真 上(左)】 豊田鳳憬尺八塚
【写真 下(右)】 鳥塚
山内には尺八琴古流宗家・初代豊田鳳憬の「豊田鳳憬尺八塚」、鳥類殺生供養の「鳥塚」と曾我五郎の足跡石があります。
曾我五郎は歌舞伎「曾我物語」の主人公で、足跡石は歌舞伎に縁深い当山に移されたそうです。
御朱印は本堂向かって右手の寺務所にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
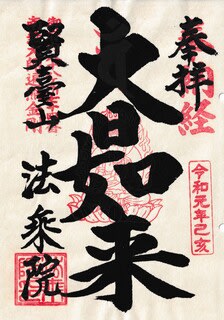

【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「大日如来」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」と御影印。
左上に「御府内八十八ヶ所七十四番南無大師遍照金剛」の札所印。
左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
こちらは揮毫御朱印と印判御朱印を授与されますが、現在は御府内霊場専用集印帳のみ揮毫御朱印かもしれません。

■ 閻魔大王の御朱印
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-25)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ 夏空の下 - やなわらばー
■ Erato - 志方あきこ
■Saikou no Kataomoi (最高の片想い) - Sachi Tainaka
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-23
Vol.-22からのつづきです。
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第70番 照光山 無量寺 禅定院
(ぜんじょういん)
練馬区石神井町5-19-10
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
司元別当:
他札所:豊島八十八ヶ所霊場第70番
第70番は石神井の禅定院です。
御府内霊場に「禅定院」を号する札所寺院がふたつ(第48番(中野沼袋)と第70番(練馬石神井))あり、前者を(中野)沼袋禅定院、後者を石神井禅定院と呼んで区別しているようです。
第70番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに谷中の西光寺となっており、第70番札所は御府内霊場開創当初から江戸末期まで谷中の西光寺で、明治初頭以降に石神井の禅定院に変更となった可能性があります。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから両山の縁起・沿革を追ってみます。
【禅定院】
禅定院は、鎌倉時代の高僧、願行上人によって開かれたと伝わります。
願行上人(憲静)については「鎌倉市の御朱印-7 (B.名越口-2)」で触れていますので、この記事から抜粋してもってきます。
**********
願行上人は相州や鎌倉の古寺をたどるときしばしばその名が出てきますが、史料が少なくナゾの多い高僧です。
『願行上人憲静の研究(上)』(伊藤宏見氏/PDF)」、『願行上人憲静の研究(下)』(同/PDF)から経歴・事績の要点を引いてみます。
願行上人憲静は、健保三年(1215年)生誕、永仁三年(1295年)寂の鎌倉時代の高僧です。
「ナゾが多い」とされるのは、様々な法統を受け継がれ、しかもおのおの重要なポジションを占められたこと、北条政子や北条一門に強い影響力をもったことなどによると思われます。
〔法統・真言宗系統〕
・建長四年(1252年)鎌倉の佐々目谷の遺身院において守海より潅頂を受ける。三宝院流。(『血脈類集記』)
・弘長元年(1261年)定清?から潅頂を受ける。定清は金剛王院流を奉じた小野流の事相家(『血脈類集記』)
・文永九年(1272年)三宝院流を意教上人より受ける。(『真言宗年表』『鶏足寺譜』)
三宝院流は真言宗醍醐派の一派で、醍醐寺三宝院門跡初代勝覚を派祖とし、いわゆる「小野六流」のひとつ。
真言宗醍醐派は古義真言宗で修験道の一派、当山派の中心でもある。派祖は理源大師聖宝。
これより、願行上人は真言宗醍醐派三宝院流の法流を受けられていることがわかります。
〔法統・律宗系統〕
・月翁智鏡に律部を受学。月翁智鏡は泉涌寺来迎院の開山で泉涌寺四世。当時の泉涌寺は律・密・禅・浄土の四宗兼学(密を天台、東密に分けると五宗兼学)の道場。
・『鎌倉初期の禅宗と律宗』(中尾良信氏/PDF)には、「北京律の祖とされる泉涌寺の俊芿」「北京律の中心たる泉涌寺」「月翁は俊芿から教律を学んだ」とある。
月輪大師俊芿(1166-1227年)は渡宗され、天台と律を学び建暦元年(1211年)帰朝。泉涌寺の実質的な開山といわれ四宗兼学の道場として再興されました。
その律は北京律(ほっきょうりつ)といわれ、日本における開祖とされます。
この北京律が、月輪大師俊芿-月翁智鏡-願行上人と伝わったとみられます。
以上から、願行上人は真言宗三宝院流と北京律兼学の高僧で、祇園山はこの流れから当初律宗(北京律)とされたとみられます。
〔鎌倉での活動〕
願行上人の鎌倉下向期間については錯綜気味ですが、「鎌倉下向僧の研究 - 願行房憲静の事跡 -」(高橋秀栄氏/PDF)には下記のとおりあります。
・弘長三年(1263年)から正応三年(1290年)までの28年間。
ただし、「建長四年(1252年)鎌倉の佐々目谷の遺身院において守海より潅頂を受ける。三宝院流(『血脈類集記』)」という記録があり、それ以前に下向されているかも。
また、文永二年(1265年)意教上人に従って関東に赴くという諸伝もあります。
「勝賢開山の佐々目西方寺にはじまり、関東の三宝院流はここに発祥し、大門寺、遺身院その他の寺院群が佐々目の地にあった模様である。守海は成賢の資の一人憲深から受法している。」(『願行上人憲静の研究(上)』P.5/血脈類集記より)
これによると長谷の佐々目(笹目)は当時真言宗三宝院流の本拠地で、願行上人はこの地(遺身院)で守海より三宝院流を受法の記録があります。
佐々目西方寺は現在の補陀洛山 西方寺(横浜市港北区新羽町)とされ、西方寺の公式Webには「西方寺は源頼朝卿の頃、建久年間(1190)に鎌倉の笹目と言う所に『補陀洛山、安養院、西方寺』として創建され、開山は大納言通憲公の息、醍醐覚洞院座主、東大寺の別当であった勝賢僧正」とあります。
なお、西方寺は現在真言宗系単立のようですが、公式Webによると極楽寺(真言律宗)との関係が深かったようです。
願行上人と関係のある金沢の称名寺も真言律宗なので、佐々目の三宝院流はのちに真言律宗とかかわりを強めたのかもしれません。
「(願行上人は)金沢越後守平実時堂廊に能禅方(西院)の灌頂を授けている。北条実時が金沢文庫を開設するのはそれよりのちの建治元年(1275年)である。その翌年願行の自筆文書が残っている。願行はのちにこの住持審海をも弟子として指導しているのであるから、その教界での位置を想像することができる。かくて建治の頃はすでに極楽寺とならぶ新興の律院の称名寺において、伝法灌頂を授けるほどの名徳(以下略)」(『願行上人憲静の研究(上)』P.18)
佐々目の守海は願行上人と頼助(佐々目僧正)に受戒しており、頼助は鎌倉幕府4代執権北条経時の子です。
Wikipediaには頼助は「父経時の菩提所である鎌倉佐々目の遺身院を拠点とし、佐々目頼助とも呼ばれる。」とあり、経時の没年は寛元四年(1246年)なので、「(願行上人が)建長四年(1252年)鎌倉の佐々目谷の遺身院(北条経時の菩提寺)において守海より潅頂を受ける。三宝院流。(『血脈類集記』)。」という記録はタイミング的に符合します。
同僚の頼助が執権の子という有力者なので、願行上人の鎌倉での立場も強かったとみられます。
また、師・意教上人が一時、高野山金剛三昧院(実朝公菩提のため北条政子が発願)に入られたことも、願行上人と鎌倉幕府の結びつきを強めたという説があります。
『本朝高僧伝』には「乃至稲瀬川滸。設念仏会。名祇園山安養院」とあり、これは「文永十一年(1274年)~建治元年(1275年)、願行上人が鎌倉稲瀬川のほとりで頼朝公の霊のお告げに従い、説法念仏会を37日間行う」という諸伝と符合します。
『新編鎌倉志』の(覚園寺)地蔵堂の項には「地蔵を、俗に火燒地蔵と云ふ(中略)【沙石集】には丈六の地蔵とあり。鎌倉の濱に有しを、東大寺の願行上人、二階堂へ移すと云へり。」とあり、願行上人の稲瀬川念仏会との関連を指摘する説もあります。
さらに安養院所蔵の願行上人像胎内銘に「鎌倉由井浜安養院開山願行上人、建治二年(1275年)八月廿八日、未剋往生。春秋八十二」とあり、説法念仏会の前後に鎌倉稲瀬川に安養院ないしその前身となる寺院を開山された可能性があります。
なお、上記の参考資料によると、願行上人が係わられた関東の代表的な寺社はつぎのとおりです。
二階堂永福寺真言院、鎌倉観音寺、(金澤)称名寺、相州大山寺、二階堂理智光寺、二階堂大楽寺、二階堂覚圓寺、大町安養院、最明寺(足柄上郡大井金子)、鶴岡八幡宮。
**********
御府内霊場では願行上人所縁の寺院は多くはみられませんが、禅定院は願行上人を開山とする貴重な例です。
文政年間(1818-1830年)の火災で、伽藍・寺伝などことごとく焼失しましたが、境内には応安・至徳(南北朝時代)年号の板碑が残り、創建の古さを裏付けています。
かつての御本尊は不動明王で、側に閻魔大王を奉安といいます。
門前の堂宇に安置された六地蔵や鐘楼前の大宝篋印塔は、石神井村の光明真言講中によって造立されたものです。
本堂前、寛文十三年(1673年)銘の織部灯籠は形状から「キリシタン灯籠」ともいわれ、区内でもめずらしい石造物の一つとして区登録文化財に指定されています。
墓地入口に御座のいぼ神地蔵尊は、いぼの治癒に霊験のありとして「いぼとり地蔵」とも呼ばれます。
石神井小学校の前身である豊島小学校は、明治7年区内初の公立小学校としてここに創立され、墓地内には寺子屋師匠の菩提を弔った筆子塚があるなど、教育との所縁がふかい寺院です。
-------------------------
【西光寺】
仏到山 無量寿院 西光寺
台東区谷中6-2-20
新義真言宗
御本尊:五大明王
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第70番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第7番、弘法大師二十一ヶ寺第15番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第7番
公式Web


【写真 上(左)】 西光寺入口
【写真 下(右)】 西光寺本堂
西光寺は慶長八年(1603年)、傳燈大阿闍梨妙音院法印宥義大和尚(佐竹氏代16代当主・義篤次子、元和四年(1618年)寂)が幕府より神田北寺町に寺地を賜り開山。
開基檀越は佐竹右京大夫義宣。
当山は佐竹氏との所縁がふかいので、佐竹氏について少しく追ってみます。
佐竹氏は新羅三郎源義光公の孫昌義(1081-1147?年)が常陸国久慈郡佐竹郷(現・茨城県常陸太田市)に土着し、佐竹氏を称したという清和源氏の名族です。
源平合戦では平家にくみしたため頼朝公により所領を没収された(Wikipedia)ものの、後に再興し奥州討伐では鎌倉方に加わりました。
南北朝時代の8代当主・貞義、9代・義篤は足利氏に応じて北朝方として活躍し、その功から守護職に任ぜられて家勢は興隆しました。
足利満兼公制定と伝わる「関東八屋形」に列せられ、戦国時代の15代当主・義舜は反目する佐竹山入家を討って佐竹氏統一を果たし、18代の義重は常陸の大半を支配下に置き、奥州南部にも進出して有力戦国大名としてその名を馳せました。
義重の子・19代義宣は秀吉公の小田原征伐に参陣し、常陸國54万5800石の大名となり、
徳川・上杉・毛利・前田・島津とともに「豊臣六大将」と呼ばれるほど勢力を拡大。
佐竹義宣は佐竹義重の嫡男で母は伊達晴宗の娘。
官位は従四位上・左近衛中将、右京大夫を賜るという、家柄・格式を有する、名実兼ね備えた太守でした。
義宣は幾度か石田三成のとりなしを受け、天正十八年(1590年)三成の忍城攻めに加勢したこともあり、石田三成との関係は良好でした。
慶長四年(1599年)3月、前田利家逝去ののち、加藤清正、福島正則、加藤嘉明、浅野幸長、黒田長政、細川忠興、池田輝政らが三成の屋敷を襲撃した際、義宣が三成を女輿に乗せ、宇喜多秀家邸に逃れさせたという逸話は有名です。
また、秀吉から羽柴姓を与えられるなど豊臣色の強い大名でした。
関ヶ原の戦いでは水戸城へ引き上げ、積極的に徳川方に与力しなかったため戦後咎を受けましたが家康公に謝罪し、家名断絶は遁れたものの出羽国秋田、54万石から20万石への減転封となりました。
義宣が家康公から転封の沙汰を受けたのは慶長7年(1602年)5月(Wikipedia)、出羽(秋田)入国は同年9月なので、水戸から秋田への転封直後にみずから開基となって西光寺を創建(慶長八年(1603年))したことになりますが、その背景は史料からは辿れませんだした。
慶安元年(1648年)神田北寺町の寺地が幕府用地として収公、谷中の現所に替地となりました。
慶安二年(1649年)佐竹修理大夫義隆(秋田久保田藩第2代当主)が堂舎を再建したため、義隆は中興開基とされます。
以降何度か火災に遭っていますが、都度佐竹家により再建されています。
公式Webによると、当山は「秋田藩(秋田市)佐竹家・伊勢津藩(三重県津市)藤堂家の祈願寺として信仰されてきた歴史」があるそうです。
公式Webによると、仏寺創建の際には藤堂高虎が財政的支持をおこなったと伝えられ、山内の韋駄天像は藤堂高虎安置と伝わり、別名を「韋駄天寺」ともいわれたようです。


【写真 上(左)】 韋駄天石碑
【写真 下(右)】 左が韋駄天
江戸時代の西光寺は御府内霊場のほか、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場、弘法大師二十一ヶ寺、上野王子駒込辺(西國)三十三観音霊場の札所を兼ねられてお大師さまとの所縁もふかい寺院でした。
明治初頭の神仏分離の波も乗り越えているのに、おそらく明治初頭以降のどこかのタイミングで御府内霊場第70番の札所は石神井の禅定院に変更となっています。
西光寺は和歌山の根來寺を総本山とする新義真言宗。
禅定院は真言宗智山派で宗派も異なり、変更の理由についてはよくわかりません。
西光寺は以前は御朱印不授与でしたが、近年カラフルな月替わり御朱印で一気に人気のお寺となり、おそらく参拝者(というか絵御朱印ファン)の数は御府内霊場札所より多いかと思います。
絵御朱印の威力おそるべし。
■ 西光寺の御朱印
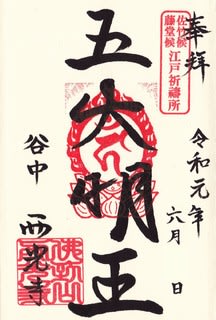

-------------------------
【史料】
【禅定院】
■ 『新編武蔵風土記稿 豊島郡巻五』(国立国会図書館)
(下石神井村)禅定院
新義真言宗 上石神井村三寶寺寺ノ末 照光山ト号ス 願行上人ノ開キシ寺二テ 本寺ヨリハ古跡ナリト云 本尊不動 側ニ閻魔ヲ安ス 是ハ元ハ別堂ニアリ 境内二明応四年(1498年)二月八日妙慶禅尼ト彫ル古碑アリ
八幡社
阿彌陀堂三 一ハ道場寺 一ハ禅定院 一ハ三寶寺ノ持
【西光寺】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
七十番
谷中 門前町あり
佛到山 無量壽院 西光寺
本所彌勒寺末 新義
本尊:不動明王 弘法大師 興教大師
■ 『寺社書上 [110] 谷中寺社書上 』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考 P.98』
谷中 不唱小名
本所彌勒寺末
佛到山無量壽院西光寺
当寺之濫觴慶長八年(1603年) 開山宥義 於神田北寺町寺地拝領仕
堂舎 佐竹右京太夫義宣公建立
慶安元年(1648年)右寺地御用地ニ付 於当所旧地之●第四世宥鏡代拝領仕
慶安二年(1649年)佐竹修理太夫義隆公堂舎再建仕候
開山 伝灯大阿闍梨法印宥義、俗姓佐竹大膳太夫義篤公二男 元和四年(1618年)寂
開基 佐竹右京太夫義宣公 寛永十年(1633年)卒
中興開基 佐竹修理太夫義隆公(秋田久保田藩第2代当主) 寛文十一年(1671年)卒
本堂
本尊 不動尊鋳型座像 附二童子木像
四大明王木像 十一面観音木像 聖天府秘符
阿弥陀如来木像
弘法大師木像 興教大師木像
愛染明王木像座像 地蔵菩薩木像座像 不動明王古像座像
境内鎮守社 天神稲荷疱瘡合殿
十一面観音石像
地蔵尊石像
韋駄天石像
■ 『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)
西光寺(谷中上三崎南町二〇番地)
本所彌勒寺末、佛到山無量壽院と号す。本尊不動明王、五大尊。慶長八年(1603年)、開山妙音院宥義。(佐竹義篤次子、元和四年(1618年)寂)
幕府より神田北寺町に於て寺地を給せられ、佐竹右京大夫義宣開基檀越として当寺を創建した。慶安元年(1648年)同所幕府用地となるや、現所に替地を給せられ、翌二年(1649年)佐竹修理大夫義隆堂舎を再建した。義隆はために中興開基と呼ばれる。時の住持は第四世宥鏡であつた。(略)佐竹家の他に藤堂家の祈願所であつた。境内の韋駄天石像は同家の寄進する所で、韋駄天寺の俗称は之に基くのである。

「西光寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
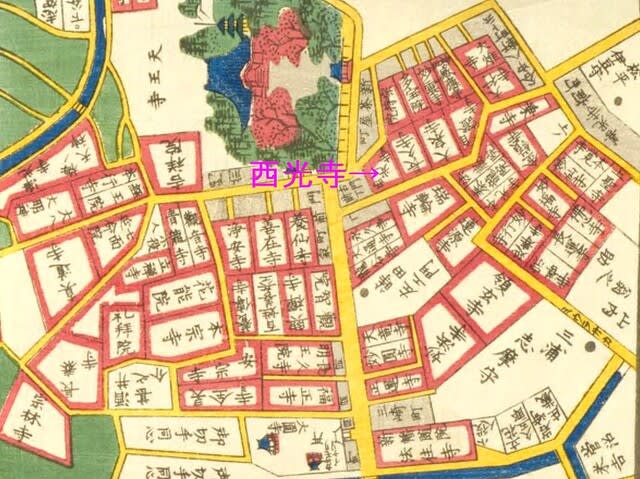
原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは西武池袋線「石神井公園」駅で徒歩約10分。
石神井池の南に広がる緑ゆたかな一帯で、第16番三寶寺にもほど近いところです。


【写真 上(左)】 山門入口
【写真 下(右)】 山門
前面通りから引き込んで山門。
本瓦葺に唐破風を配した重厚な四脚門で、常閉のようです。
山門脇には「光明真言講中」の銘がある延命地蔵尊座像の両脇に端正な六地蔵。

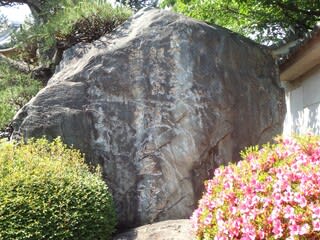
【写真 上(左)】 六地蔵
【写真 下(右)】 院号標
山門向かって左手に回り込むと山内入口で立派な院号標。
郊外寺院らしく、緑多くゆったりとした山内です。
庫裡前の見事なヒヨクヒバは「ねりまの名木」に指定されています。
茅葺きの鐘楼も趣きがあります。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 ヒヨクヒバ


【写真 上(左)】 鐘楼
【写真 下(右)】 観世音菩薩
右手に入母屋造銅板葺流れ向拝で唐破風を附設した堂々たる本堂。
向拝は桁行三間で朱塗りの水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に二連の蟇股を置いています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
水引虹梁装飾には曲線を多様、身舎まわりにはシャープな連子格子を置いて、その対比が面白い意匠。
向拝見上げには院号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 いぼ神地蔵尊
【写真 下(右)】 弘法大師尊像
山内には区の文化財である「石幢六面六地蔵」「織部燈籠」(キリシタン燈籠)、いぼ神地蔵尊などがありますが、三回参拝しているのになぜか「石幢六面六地蔵」「織部燈籠」(キリシタン燈籠)の写真がありません。
(庫裡前の重石塔の右に御座と思われます。)

→ こちら(練馬区Web史料)をご覧ください。


【写真 上(左)】 御府内霊場の札所板
【写真 下(右)】 豊島霊場の札所板
御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受しました。
こちらでは豊島八十八ヶ所霊場の御朱印も授与されています。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
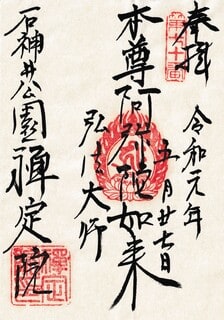

【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊阿弥陀如来」「弘法大師」の揮毫と阿弥陀如来のお種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「第七十番」の札所印。
左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
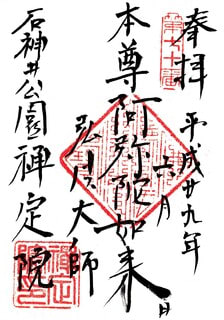
■ 豊島霊場の御朱印
※ 御府内霊場と豊島霊場の御朱印を同日に拝受していますが、これは御府内霊場参拝日にご不在で拝受できなかったためで、基本的には弘法大師霊場のかけもち巡拝は避けた方がベターかと思います。
■ 第71番 新井山 薬王寺 梅照院(新井薬師)
(ばいしょういん)
公式Web
中野区新井5-3-5
真言宗豊山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
司元別当:(新井村)天満宮、稲荷社、秋葉社、諏訪社
他札所:江戸・東京四十四閻魔参り第27番、閻魔三拾遺第30番
第71番は中野区新井の梅照院(新井薬師)です。
第71番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに小石川の玄性院となっており、第71番札所は御府内霊場開創当初から江戸末期まで小石川の玄性院で、『御府内八十八ケ所道しるべ』の札所変更資料に玄性院から梅照院への変更が記されているので、第71番札所は幕末から明治初頭にかけて中野の梅照院に変更とみられます。
公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから両山の縁起・沿革を追ってみます。
【梅照院】
永禄年間(1558-1570年)、相模國の沙門行春が行脚の途中、ここ新井を有縁の地と定め草案を結んで日夜行法に励んでいました。
(『ルートガイド』には、沙門行春は元北条家の家臣・梅村将監とあります。)
天正十四年(1586年)のある晩、庭の老梅の梢から光明が輝くのを見た行春が、件の梅の木を索ると梢の空洞から二仏一体(薬師瑠璃光如来・如意輪観世音菩薩)の尊像が出現されました。
村内の新田氏所縁の人々がこの御佛を拝すると、この尊像こそ新田家伝来の守り本尊と悟り、この奇縁に因んで一宇を建立したのが創始と伝わります。
梅樹から光明が照り輝いた奇瑞から、梅照院と号しました。
「新田家伝来の守り本尊」については以下の縁起が伝わります。
清和源氏の名族・新田家伝来の守り本尊は、薬師如来・如意輪観世音菩薩の二仏一体丈一寸八分の坐像黄金仏で弘法大師の御作と伝わります。
南北朝時代、新田家嫡流は上野國大田の金山城に拠り、守り本尊を宝庫に収めていましたがあるとき御本尊はお姿を消されました。
その後の変遷については公式Webをご覧ください。
戦に敗れた新田家所縁の人々が新井の庄に定住していたところ、沙門行春の霊夢により、行方知らずとなっていた新田家代々の守護仏を迎えたので恐懼し、また欣喜雀躍して堂宇に奉安したのでは。
公式Webによると、新田一族は薬師如来信仰の家系が多く、それぞれの家系に薬師如来の尊像が存在したといいます。
四散した新田一門がそれぞれの御本尊を各地で奉安したため「新田家の薬師如来」の系譜は錯綜していますが、当山の御本尊が「新田家伝来の守り本尊」とされています。
開創当時は山内に日本一ともいわれた傘松があったため、高松山梅照院薬王寺と号しましたが、新井薬師の名が高まるにつれ新井山と山号を改めたといいます。
新井薬師の通称が知られているので、新井薬師梅照院とも称します。
公式Webには行基が開基、中興は朝曇・聖道とあります。
『新編武蔵風土記稿』には、開山を快儀(正保三年(1646年)寂)、天正年中(1573-1592年)に僧・行春が開基、第六世朝曇を中興とあります。
元和三年(1617年)、第五代住職玄鏡の夢中に薬師如来が現れて御手の瑠璃の壺中より法軌を授与されました。
玄鏡和上は早速授与された法軌のとおりに薬を処方、難病の小児に施すとすこぶる効いて治らない者がひとりもいないため、この薬を「夢想丸(むそうがん)」と称して参詣者にわかちました。
中興の朝曇和上はこの霊験譚を世に広めたため御本尊の霊験が広く世に知られるようになり、「子育薬師」として諸人の信仰を集め、門前は市をなしたといいます。
寛永六年(1629年)徳川2代将軍秀忠公の第五女和子の方(東福門院)が眼病に罹られ、秀忠公をはじめ側近の人々が名医名薬、祈祷など八方手を尽くしましたが効果なく、万策つきたと思われたとき、当山の御本尊の霊験を伝え聞いて御本尊に祈願せしめました。
すると眼病はたちまち快癒したので、秀忠公は当山に厚く御礼を賜りました。
この逸話はたちまち天下に広まり、当院は「治願薬師」(ぢがんやくし)とも呼ばれてさらに参詣者を集めたといいます。
以降も参詣者は途絶えることなく、中野から新井薬師へと至る参道は門前町として大いに栄えて「東の浅草寺、西の新井薬師」と並び称されるほどでした。
門前町はいまでも「薬師あいロード商店街」として賑わいをみせ、8がつく日のお薬師さまのご縁日はことに賑わいをみせます。
和子の方の逸話に因み、とくに眼病にご利益ありとして広く参詣客を集めています。
西武新宿線の駅名にもなり、知名度の高い城西の名刹です。
なお、『新編武蔵風土記稿』には「(新井村)天満宮、稲荷社、秋葉社、諏訪社 供ニ村内梅照院ノ持ナリ」とあるので、こちらの4社の別当を司っていたとみられます。
新井天神 北野神社の公式Webに「天正年間(1573-1592年)、新井薬師の開祖である沙門行春が建立したとも、それ以前よりこの地の鎮守社であったとも言われています。」と、沙門行春との関係を示す記載があります。
また、「残存する梅照院縁起に『開基の行春より数代後の住持玄鏡が、天和年間に手植の梅一株を北野天満宮に献じた』とあります。」とあり、すでに天和年間(1681-1684年)から梅照院と良好な関係を保っていたことがわかります。


【写真 上(左)】 新井天神北野神社(旧拝殿)
【写真 下(右)】 同 御朱印


【写真 上(左)】 (新井天神)稲荷神社
【写真 下(右)】 同 御朱印
-------------------------
【玄性院】
玄性院は小石川の金剛寺坂辺にあった新義真言宗寺院です。
当地に御鎮座の金杉稲荷社の別当で、本社金杉稲荷大明神の本地、十一面観世音菩薩を奉安していたとみられます。
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ』には「本尊:十一面観世音菩薩 本社金杉稲荷大明神 弘法大師」とあり、こちらが御府内霊場の拝所であったことがわかります。
玄性院は史料が少なく詳細を辿れないのですが、『江戸町巡り』様によると小石川金杉水道町のうちに稲荷前町という場所があり、由来は金杉稲荷の前の町屋であったためとの由。
現在の文京区春日二丁目です。
また、『東京さまよい記』様の記事には以下のとおりあります。
-------------------------
荷風「断腸亭日乗」昭和16年(1941)9月28日に、「・・・金剛寺坂左側の駒井氏、右側の岩崎氏、其鄰の石橋氏なり。その筋向に稲荷の祠あり。余の遊びし頃には桐畑なり。・・・」(前回の記事)とあるが、その稲荷が金杉稲荷であろう。現在はないようである。
-------------------------
以上に『江戸切絵図』の情報を加えると、金杉稲荷大明神(玄性院)は小石川・金剛寺坂の春日通り寄りにあったのでは。
『寺社書上』には「中興開基 六角越前」とありますが、『江戸切絵図』では比較的近い場所に「六角越前守」の屋敷がみえます。
「六角越前守」で検索するとwikipediaの「六角広孝」がヒットしたので、こちらとの由縁を考えましたが、中興開山の聖譽法印は正徳三年(1713年)卒で、中興開山・開基を同時期と考えると六角広孝(1747-1815年)とは年代が合いません。
六角氏というと宇多源氏佐々木氏流で近江守護職もつとめた名族を思い起こしますが、Wikipediaによると、高家六角家は正二位権大納言烏丸光広の次男・広賢が江戸幕府に仕えて高家に列した流れ(日野流六角家)のようです。
当山中興開山・聖譽法印と同年代の高家六角家当主は2代の六角広治(1644-1719年)。
元禄二年(1689年)二月、従五位下侍従・越前守に叙任され「六角越前」に符合します。
禄は二千石で、高家の身分を考えると「大身の旗本」といってもいいかもしれません。
この六角広治が玄性院に中興開基となさしめるほどの大きな寄進をしたか、あるいは檀家総代として貢献したのかもしれません。
玄性院は本所彌勒寺の末なので現在の真言宗豊山派。
梅照院も真言宗豊山派ですから宗派的なつながりはあり、中野の名刹・梅照院に御府内霊場札所を承継したのかもしれません。
ただし、不思議なのは梅照院が豊島八十八ヶ所霊場の札所になっていないことです。
豊島八十八ヶ所霊場の開創は明治に入ってからで、中野区内にもいくつかの札所があります。
梅照院が弘法大師霊場の札所入りを考えていたとしたら、当然有力候補にあがるはずです。
あるいは明治初期にすでに御府内霊場の札所を承継していたので、それでよしとされたのかもしれません。
-------------------------
【史料】
【梅照院】
■ 『新編武蔵風土記稿 多磨郡巻三十五』(国立国会図書館)
(新井村)梅照院
当村(新井村)ト上高田村トノ接地ニアリ松高山ト号ス 新義真言宗ニテ 当郡中野村寶仙寺末 客殿六間四方南向
本尊薬師坐像ノ石佛ニテ長一寸八分 厨子ニ入
開山ヲ快儀ト云 正保三年(1646年)示寂ス 又云天正年中(1573-1592年)行春ト云僧開基セシト 其後第六世朝曇ヲ中興トス 此僧ノ頃ヨリ本尊ノ霊験世ニアラハル
子育薬師ト称シテ遠近コソッテ歩ヲ運フ者多シ 就中近キ比江戸日本橋邊ノ商売願ヲカケシニ 速ニ霊数ヲ蒙フリシカハ渇仰斜ナラス ソノ後同志参詣ノ者ノ便リセントテ 豊島郡下高田馬場ノホトリヨリ 道ノ辻々ニ碑標ヲタテヽ方角ヲ示ス コレヨリ次第ニ参詣ノ者多クナリテ 今ハ新井ノ薬師トテ其名隠レナキコトニソナリケル
(新井村)天満宮、稲荷社、秋葉社、諏訪社
供ニ村内梅照院ノ持ナリ
-------------------------
【玄性院】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
七十一番
小石川金杉●●町
永壽山 吉祥寺 玄性院
本所彌勒寺末 新義
本尊:十一面観世音菩薩 本社金杉稲荷大明神 弘法大師
■ 『寺社書上 [64] 小石川寺社書上 一』(国立国会図書館)
金杉稲荷社
小石川金杉
神躰無之
本地 十一面観音立像
弘法大師 辨財天十五童子付 阿弥陀如来
相殿 六角稲荷
神體宝珠
氏子町 金杉水道町四ヶ町 富坂新町
別当 永壽山吉祥寺玄性院
彌勒寺末 起立年代不詳
中興開山 聖譽法印 正徳三年(1713年)卒
中興開基 六角越前
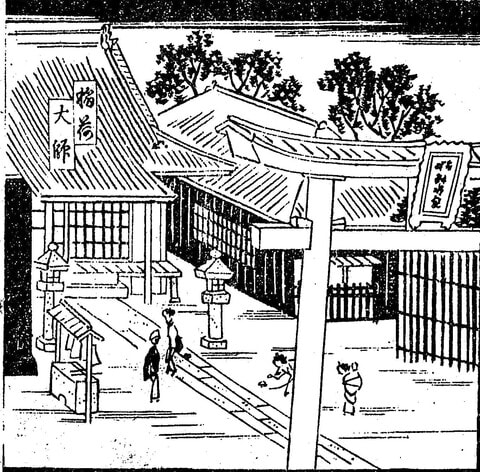
「玄性院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
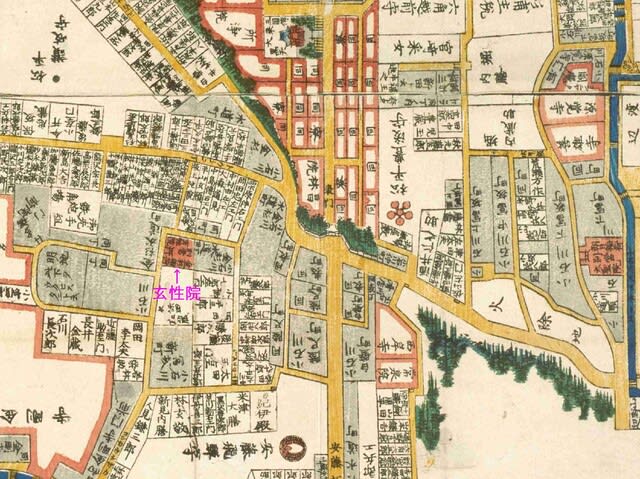
原典:戸松昌訓著、版元金鱗堂尾張屋清七、『〔江戸切絵図〕』東都小石川絵図 嘉永7[1854]/安政[4][1857]改刊.東京都立中央図書館Web(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは西武池袋線「石神井公園」駅で徒歩約10分。
「新井薬師門前」の五叉路から長い参道を構え、さすがに名刹のスケール感があります。
この五叉路から北西に進むと菅原道真公をお祀りする新井天神で、近在屈指の参詣エリアとなっています。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 院号標


【写真 上(左)】 新井薬師の碑
【写真 下(右)】 御府内霊場札所碑
参道入口には院号標と新東京百景の「新井薬師」の碑。
石畳の参道正面の山門左手前に御府内霊場の札所碑。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門の提灯
山門は切妻屋根桟瓦葺の四脚門で、軒下には新井薬師の提灯が掲げられています。
山門をくぐると正面が本堂。左手に霊堂、右が不動堂です。
順にご紹介していきます。
(公式Webの境内案内)


【写真 上(左)】 霊堂
【写真 下(右)】 修行大師と聖観世音菩薩
霊堂は均整のとれた朱塗りの二重の楼閣で、堂前向かって左手に修行大師像と聖観世音菩薩立像。
向拝見上げに「薬師霊堂」の扁額を掲げています。
霊堂の向拝扉には「御本尊真言」として阿弥陀如来と閻魔大王の御真言が掲出されているので、おそらくこちらの二尊を主尊として奉安とみられます。
なお、梅照院は江戸・東京四十四閻魔参り第27番、閻魔三拾遺第30番の札所で、閻魔様のお寺としても知られていたと思われます。
閻魔大王のご縁日16日に参拝しましたが、現在、閻魔大王の御朱印は不授与とのことだした。
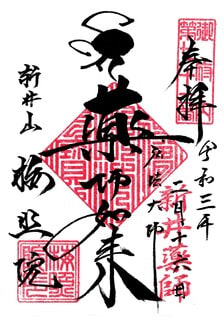
■ 閻魔大王のご縁日の御朱印


【写真 上(左)】 霊堂の扁額
【写真 下(右)】 不動堂


【写真 上(左)】 お願い地蔵尊
【写真 下(右)】 水屋
右手には不動堂。堂前右手にはお願い地蔵尊、左手には水子地蔵尊。
不動堂は宝形造桟瓦葺で流れ向拝。水引虹梁に木鼻、斗栱、海老虹梁、中備に蟇股を備えています。


【写真 上(左)】 鐘楼
【写真 下(右)】 大香炉
不動堂の本堂寄りには本瓦葺の屋根付きの立派な水屋(手水舎)とその奥に鐘楼。
参道を進むと大香炉。そこから左手に進むと西門で、墓所入口には六地蔵。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
本堂は基壇のうえに入母屋造本瓦葺流れ向拝、向拝の張りだしが大きくスケール感ある堂容で、向かって右手が授与所(札所)となっています。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 提灯と扁額
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に本蟇股。
水引虹梁奥に「新井薬師」の提灯、向拝見上げには「瑠璃殿」の扁額、向拝柱には御府内霊場の札所板を掲げています。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 札所板
御本尊は秘佛で、寅年の御開帳です。


【写真 上(左)】 白龍権現水屋
【写真 下(右)】 大悲殿
本堂を向かって右手に回り込み、回廊をくぐると右手に白龍権現水屋と大悲殿。
当山北側の瓢箪池(新井薬師公園)はその昔、霊泉の水垢離場として修行の道場となり不動尊を奉安していました。
その不動尊の傍には常に白蛇がいて不動尊を守護していたとも。
いつしか霊泉は枯れ、不動尊は山内の不動堂に遷られ、守護の白蛇供養のために白瀧権現を不動堂に祀りました。
当山貫首が「大悲殿に聖観世音菩薩を迎えて井戸の霊泉を閼伽水として衆生に施す」旨の夢告を受け、大悲殿(聖観世音菩薩の堂宇)を建立したところ、その敷地の地下に大井戸を発見し霊水が湧き出たためこの瑞祥を祝し、双竜を鋳造して水屋を建立し、「白龍権現水屋」と称しました。
大悲殿は二層の大規模な建物で、向拝には「大悲殿」の扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 大悲殿の扁額
【写真 下(右)】 聖徳太子像
本堂裏手には聖徳太子像。
昭和34年、聖徳太子の遺訓を仰ぐため、東京都左官職組合連合会中野支部の鶴谷善平氏が梅照院と支部の協力を得て像立・奉安されたお像です。
本堂のすぐ裏には年季の入った「魚がし」の天水鉢も置かれています。


【写真 上(左)】 「魚がし」の天水鉢
【写真 下(右)】 本堂再建供養塔
場所が定かでないのですが、本堂再建祈念塔(中野区登録有形文化財)の説明書には、当山再興に尽くされた蓮樹住職、後継英俊住職の功績と、この塔が高野山延命院の引導地蔵尊を模して建立されたことが記されています。
御朱印は本堂右手の札所にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
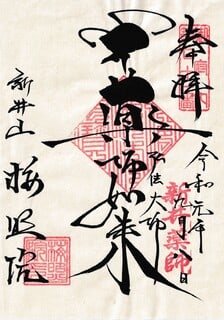
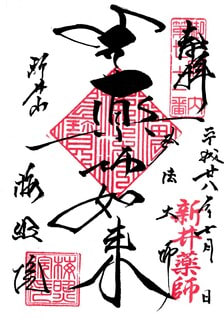
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に薬師如来のお種子「バイ」「薬師如来」「弘法大師」の揮毫と三寶印。
右に「御府内第七十一番」の札所印と「新井薬師」の印判。
左に山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-24)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ retour - 今井美樹
■ Sayonara Solitia - Yuki Kajiura(FictionJunction)
■ ここにあること - @うさ(歌ってみた)
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第70番 照光山 無量寺 禅定院
(ぜんじょういん)
練馬区石神井町5-19-10
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
司元別当:
他札所:豊島八十八ヶ所霊場第70番
第70番は石神井の禅定院です。
御府内霊場に「禅定院」を号する札所寺院がふたつ(第48番(中野沼袋)と第70番(練馬石神井))あり、前者を(中野)沼袋禅定院、後者を石神井禅定院と呼んで区別しているようです。
第70番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに谷中の西光寺となっており、第70番札所は御府内霊場開創当初から江戸末期まで谷中の西光寺で、明治初頭以降に石神井の禅定院に変更となった可能性があります。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから両山の縁起・沿革を追ってみます。
【禅定院】
禅定院は、鎌倉時代の高僧、願行上人によって開かれたと伝わります。
願行上人(憲静)については「鎌倉市の御朱印-7 (B.名越口-2)」で触れていますので、この記事から抜粋してもってきます。
**********
願行上人は相州や鎌倉の古寺をたどるときしばしばその名が出てきますが、史料が少なくナゾの多い高僧です。
『願行上人憲静の研究(上)』(伊藤宏見氏/PDF)」、『願行上人憲静の研究(下)』(同/PDF)から経歴・事績の要点を引いてみます。
願行上人憲静は、健保三年(1215年)生誕、永仁三年(1295年)寂の鎌倉時代の高僧です。
「ナゾが多い」とされるのは、様々な法統を受け継がれ、しかもおのおの重要なポジションを占められたこと、北条政子や北条一門に強い影響力をもったことなどによると思われます。
〔法統・真言宗系統〕
・建長四年(1252年)鎌倉の佐々目谷の遺身院において守海より潅頂を受ける。三宝院流。(『血脈類集記』)
・弘長元年(1261年)定清?から潅頂を受ける。定清は金剛王院流を奉じた小野流の事相家(『血脈類集記』)
・文永九年(1272年)三宝院流を意教上人より受ける。(『真言宗年表』『鶏足寺譜』)
三宝院流は真言宗醍醐派の一派で、醍醐寺三宝院門跡初代勝覚を派祖とし、いわゆる「小野六流」のひとつ。
真言宗醍醐派は古義真言宗で修験道の一派、当山派の中心でもある。派祖は理源大師聖宝。
これより、願行上人は真言宗醍醐派三宝院流の法流を受けられていることがわかります。
〔法統・律宗系統〕
・月翁智鏡に律部を受学。月翁智鏡は泉涌寺来迎院の開山で泉涌寺四世。当時の泉涌寺は律・密・禅・浄土の四宗兼学(密を天台、東密に分けると五宗兼学)の道場。
・『鎌倉初期の禅宗と律宗』(中尾良信氏/PDF)には、「北京律の祖とされる泉涌寺の俊芿」「北京律の中心たる泉涌寺」「月翁は俊芿から教律を学んだ」とある。
月輪大師俊芿(1166-1227年)は渡宗され、天台と律を学び建暦元年(1211年)帰朝。泉涌寺の実質的な開山といわれ四宗兼学の道場として再興されました。
その律は北京律(ほっきょうりつ)といわれ、日本における開祖とされます。
この北京律が、月輪大師俊芿-月翁智鏡-願行上人と伝わったとみられます。
以上から、願行上人は真言宗三宝院流と北京律兼学の高僧で、祇園山はこの流れから当初律宗(北京律)とされたとみられます。
〔鎌倉での活動〕
願行上人の鎌倉下向期間については錯綜気味ですが、「鎌倉下向僧の研究 - 願行房憲静の事跡 -」(高橋秀栄氏/PDF)には下記のとおりあります。
・弘長三年(1263年)から正応三年(1290年)までの28年間。
ただし、「建長四年(1252年)鎌倉の佐々目谷の遺身院において守海より潅頂を受ける。三宝院流(『血脈類集記』)」という記録があり、それ以前に下向されているかも。
また、文永二年(1265年)意教上人に従って関東に赴くという諸伝もあります。
「勝賢開山の佐々目西方寺にはじまり、関東の三宝院流はここに発祥し、大門寺、遺身院その他の寺院群が佐々目の地にあった模様である。守海は成賢の資の一人憲深から受法している。」(『願行上人憲静の研究(上)』P.5/血脈類集記より)
これによると長谷の佐々目(笹目)は当時真言宗三宝院流の本拠地で、願行上人はこの地(遺身院)で守海より三宝院流を受法の記録があります。
佐々目西方寺は現在の補陀洛山 西方寺(横浜市港北区新羽町)とされ、西方寺の公式Webには「西方寺は源頼朝卿の頃、建久年間(1190)に鎌倉の笹目と言う所に『補陀洛山、安養院、西方寺』として創建され、開山は大納言通憲公の息、醍醐覚洞院座主、東大寺の別当であった勝賢僧正」とあります。
なお、西方寺は現在真言宗系単立のようですが、公式Webによると極楽寺(真言律宗)との関係が深かったようです。
願行上人と関係のある金沢の称名寺も真言律宗なので、佐々目の三宝院流はのちに真言律宗とかかわりを強めたのかもしれません。
「(願行上人は)金沢越後守平実時堂廊に能禅方(西院)の灌頂を授けている。北条実時が金沢文庫を開設するのはそれよりのちの建治元年(1275年)である。その翌年願行の自筆文書が残っている。願行はのちにこの住持審海をも弟子として指導しているのであるから、その教界での位置を想像することができる。かくて建治の頃はすでに極楽寺とならぶ新興の律院の称名寺において、伝法灌頂を授けるほどの名徳(以下略)」(『願行上人憲静の研究(上)』P.18)
佐々目の守海は願行上人と頼助(佐々目僧正)に受戒しており、頼助は鎌倉幕府4代執権北条経時の子です。
Wikipediaには頼助は「父経時の菩提所である鎌倉佐々目の遺身院を拠点とし、佐々目頼助とも呼ばれる。」とあり、経時の没年は寛元四年(1246年)なので、「(願行上人が)建長四年(1252年)鎌倉の佐々目谷の遺身院(北条経時の菩提寺)において守海より潅頂を受ける。三宝院流。(『血脈類集記』)。」という記録はタイミング的に符合します。
同僚の頼助が執権の子という有力者なので、願行上人の鎌倉での立場も強かったとみられます。
また、師・意教上人が一時、高野山金剛三昧院(実朝公菩提のため北条政子が発願)に入られたことも、願行上人と鎌倉幕府の結びつきを強めたという説があります。
『本朝高僧伝』には「乃至稲瀬川滸。設念仏会。名祇園山安養院」とあり、これは「文永十一年(1274年)~建治元年(1275年)、願行上人が鎌倉稲瀬川のほとりで頼朝公の霊のお告げに従い、説法念仏会を37日間行う」という諸伝と符合します。
『新編鎌倉志』の(覚園寺)地蔵堂の項には「地蔵を、俗に火燒地蔵と云ふ(中略)【沙石集】には丈六の地蔵とあり。鎌倉の濱に有しを、東大寺の願行上人、二階堂へ移すと云へり。」とあり、願行上人の稲瀬川念仏会との関連を指摘する説もあります。
さらに安養院所蔵の願行上人像胎内銘に「鎌倉由井浜安養院開山願行上人、建治二年(1275年)八月廿八日、未剋往生。春秋八十二」とあり、説法念仏会の前後に鎌倉稲瀬川に安養院ないしその前身となる寺院を開山された可能性があります。
なお、上記の参考資料によると、願行上人が係わられた関東の代表的な寺社はつぎのとおりです。
二階堂永福寺真言院、鎌倉観音寺、(金澤)称名寺、相州大山寺、二階堂理智光寺、二階堂大楽寺、二階堂覚圓寺、大町安養院、最明寺(足柄上郡大井金子)、鶴岡八幡宮。
**********
御府内霊場では願行上人所縁の寺院は多くはみられませんが、禅定院は願行上人を開山とする貴重な例です。
文政年間(1818-1830年)の火災で、伽藍・寺伝などことごとく焼失しましたが、境内には応安・至徳(南北朝時代)年号の板碑が残り、創建の古さを裏付けています。
かつての御本尊は不動明王で、側に閻魔大王を奉安といいます。
門前の堂宇に安置された六地蔵や鐘楼前の大宝篋印塔は、石神井村の光明真言講中によって造立されたものです。
本堂前、寛文十三年(1673年)銘の織部灯籠は形状から「キリシタン灯籠」ともいわれ、区内でもめずらしい石造物の一つとして区登録文化財に指定されています。
墓地入口に御座のいぼ神地蔵尊は、いぼの治癒に霊験のありとして「いぼとり地蔵」とも呼ばれます。
石神井小学校の前身である豊島小学校は、明治7年区内初の公立小学校としてここに創立され、墓地内には寺子屋師匠の菩提を弔った筆子塚があるなど、教育との所縁がふかい寺院です。
-------------------------
【西光寺】
仏到山 無量寿院 西光寺
台東区谷中6-2-20
新義真言宗
御本尊:五大明王
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第70番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第7番、弘法大師二十一ヶ寺第15番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第7番
公式Web


【写真 上(左)】 西光寺入口
【写真 下(右)】 西光寺本堂
西光寺は慶長八年(1603年)、傳燈大阿闍梨妙音院法印宥義大和尚(佐竹氏代16代当主・義篤次子、元和四年(1618年)寂)が幕府より神田北寺町に寺地を賜り開山。
開基檀越は佐竹右京大夫義宣。
当山は佐竹氏との所縁がふかいので、佐竹氏について少しく追ってみます。
佐竹氏は新羅三郎源義光公の孫昌義(1081-1147?年)が常陸国久慈郡佐竹郷(現・茨城県常陸太田市)に土着し、佐竹氏を称したという清和源氏の名族です。
源平合戦では平家にくみしたため頼朝公により所領を没収された(Wikipedia)ものの、後に再興し奥州討伐では鎌倉方に加わりました。
南北朝時代の8代当主・貞義、9代・義篤は足利氏に応じて北朝方として活躍し、その功から守護職に任ぜられて家勢は興隆しました。
足利満兼公制定と伝わる「関東八屋形」に列せられ、戦国時代の15代当主・義舜は反目する佐竹山入家を討って佐竹氏統一を果たし、18代の義重は常陸の大半を支配下に置き、奥州南部にも進出して有力戦国大名としてその名を馳せました。
義重の子・19代義宣は秀吉公の小田原征伐に参陣し、常陸國54万5800石の大名となり、
徳川・上杉・毛利・前田・島津とともに「豊臣六大将」と呼ばれるほど勢力を拡大。
佐竹義宣は佐竹義重の嫡男で母は伊達晴宗の娘。
官位は従四位上・左近衛中将、右京大夫を賜るという、家柄・格式を有する、名実兼ね備えた太守でした。
義宣は幾度か石田三成のとりなしを受け、天正十八年(1590年)三成の忍城攻めに加勢したこともあり、石田三成との関係は良好でした。
慶長四年(1599年)3月、前田利家逝去ののち、加藤清正、福島正則、加藤嘉明、浅野幸長、黒田長政、細川忠興、池田輝政らが三成の屋敷を襲撃した際、義宣が三成を女輿に乗せ、宇喜多秀家邸に逃れさせたという逸話は有名です。
また、秀吉から羽柴姓を与えられるなど豊臣色の強い大名でした。
関ヶ原の戦いでは水戸城へ引き上げ、積極的に徳川方に与力しなかったため戦後咎を受けましたが家康公に謝罪し、家名断絶は遁れたものの出羽国秋田、54万石から20万石への減転封となりました。
義宣が家康公から転封の沙汰を受けたのは慶長7年(1602年)5月(Wikipedia)、出羽(秋田)入国は同年9月なので、水戸から秋田への転封直後にみずから開基となって西光寺を創建(慶長八年(1603年))したことになりますが、その背景は史料からは辿れませんだした。
慶安元年(1648年)神田北寺町の寺地が幕府用地として収公、谷中の現所に替地となりました。
慶安二年(1649年)佐竹修理大夫義隆(秋田久保田藩第2代当主)が堂舎を再建したため、義隆は中興開基とされます。
以降何度か火災に遭っていますが、都度佐竹家により再建されています。
公式Webによると、当山は「秋田藩(秋田市)佐竹家・伊勢津藩(三重県津市)藤堂家の祈願寺として信仰されてきた歴史」があるそうです。
公式Webによると、仏寺創建の際には藤堂高虎が財政的支持をおこなったと伝えられ、山内の韋駄天像は藤堂高虎安置と伝わり、別名を「韋駄天寺」ともいわれたようです。


【写真 上(左)】 韋駄天石碑
【写真 下(右)】 左が韋駄天
江戸時代の西光寺は御府内霊場のほか、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場、弘法大師二十一ヶ寺、上野王子駒込辺(西國)三十三観音霊場の札所を兼ねられてお大師さまとの所縁もふかい寺院でした。
明治初頭の神仏分離の波も乗り越えているのに、おそらく明治初頭以降のどこかのタイミングで御府内霊場第70番の札所は石神井の禅定院に変更となっています。
西光寺は和歌山の根來寺を総本山とする新義真言宗。
禅定院は真言宗智山派で宗派も異なり、変更の理由についてはよくわかりません。
西光寺は以前は御朱印不授与でしたが、近年カラフルな月替わり御朱印で一気に人気のお寺となり、おそらく参拝者(というか絵御朱印ファン)の数は御府内霊場札所より多いかと思います。
絵御朱印の威力おそるべし。
■ 西光寺の御朱印
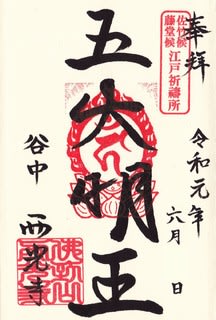

-------------------------
【史料】
【禅定院】
■ 『新編武蔵風土記稿 豊島郡巻五』(国立国会図書館)
(下石神井村)禅定院
新義真言宗 上石神井村三寶寺寺ノ末 照光山ト号ス 願行上人ノ開キシ寺二テ 本寺ヨリハ古跡ナリト云 本尊不動 側ニ閻魔ヲ安ス 是ハ元ハ別堂ニアリ 境内二明応四年(1498年)二月八日妙慶禅尼ト彫ル古碑アリ
八幡社
阿彌陀堂三 一ハ道場寺 一ハ禅定院 一ハ三寶寺ノ持
【西光寺】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
七十番
谷中 門前町あり
佛到山 無量壽院 西光寺
本所彌勒寺末 新義
本尊:不動明王 弘法大師 興教大師
■ 『寺社書上 [110] 谷中寺社書上 』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考 P.98』
谷中 不唱小名
本所彌勒寺末
佛到山無量壽院西光寺
当寺之濫觴慶長八年(1603年) 開山宥義 於神田北寺町寺地拝領仕
堂舎 佐竹右京太夫義宣公建立
慶安元年(1648年)右寺地御用地ニ付 於当所旧地之●第四世宥鏡代拝領仕
慶安二年(1649年)佐竹修理太夫義隆公堂舎再建仕候
開山 伝灯大阿闍梨法印宥義、俗姓佐竹大膳太夫義篤公二男 元和四年(1618年)寂
開基 佐竹右京太夫義宣公 寛永十年(1633年)卒
中興開基 佐竹修理太夫義隆公(秋田久保田藩第2代当主) 寛文十一年(1671年)卒
本堂
本尊 不動尊鋳型座像 附二童子木像
四大明王木像 十一面観音木像 聖天府秘符
阿弥陀如来木像
弘法大師木像 興教大師木像
愛染明王木像座像 地蔵菩薩木像座像 不動明王古像座像
境内鎮守社 天神稲荷疱瘡合殿
十一面観音石像
地蔵尊石像
韋駄天石像
■ 『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)
西光寺(谷中上三崎南町二〇番地)
本所彌勒寺末、佛到山無量壽院と号す。本尊不動明王、五大尊。慶長八年(1603年)、開山妙音院宥義。(佐竹義篤次子、元和四年(1618年)寂)
幕府より神田北寺町に於て寺地を給せられ、佐竹右京大夫義宣開基檀越として当寺を創建した。慶安元年(1648年)同所幕府用地となるや、現所に替地を給せられ、翌二年(1649年)佐竹修理大夫義隆堂舎を再建した。義隆はために中興開基と呼ばれる。時の住持は第四世宥鏡であつた。(略)佐竹家の他に藤堂家の祈願所であつた。境内の韋駄天石像は同家の寄進する所で、韋駄天寺の俗称は之に基くのである。

「西光寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
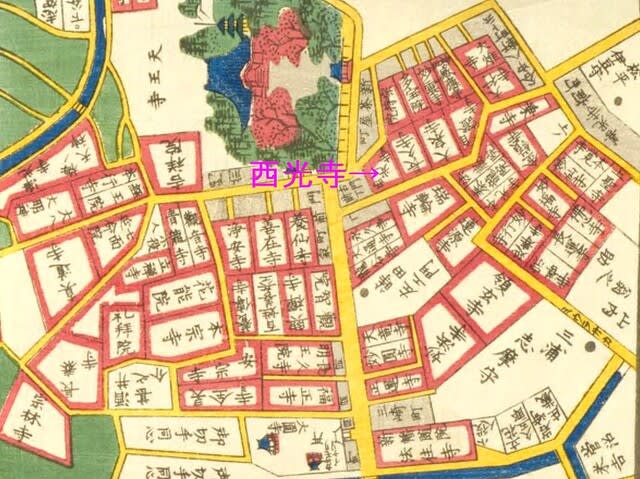
原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは西武池袋線「石神井公園」駅で徒歩約10分。
石神井池の南に広がる緑ゆたかな一帯で、第16番三寶寺にもほど近いところです。


【写真 上(左)】 山門入口
【写真 下(右)】 山門
前面通りから引き込んで山門。
本瓦葺に唐破風を配した重厚な四脚門で、常閉のようです。
山門脇には「光明真言講中」の銘がある延命地蔵尊座像の両脇に端正な六地蔵。

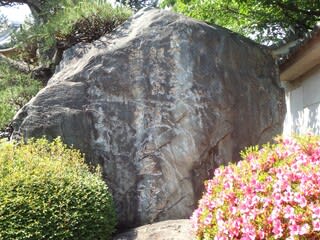
【写真 上(左)】 六地蔵
【写真 下(右)】 院号標
山門向かって左手に回り込むと山内入口で立派な院号標。
郊外寺院らしく、緑多くゆったりとした山内です。
庫裡前の見事なヒヨクヒバは「ねりまの名木」に指定されています。
茅葺きの鐘楼も趣きがあります。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 ヒヨクヒバ


【写真 上(左)】 鐘楼
【写真 下(右)】 観世音菩薩
右手に入母屋造銅板葺流れ向拝で唐破風を附設した堂々たる本堂。
向拝は桁行三間で朱塗りの水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に二連の蟇股を置いています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
水引虹梁装飾には曲線を多様、身舎まわりにはシャープな連子格子を置いて、その対比が面白い意匠。
向拝見上げには院号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 いぼ神地蔵尊
【写真 下(右)】 弘法大師尊像
山内には区の文化財である「石幢六面六地蔵」「織部燈籠」(キリシタン燈籠)、いぼ神地蔵尊などがありますが、三回参拝しているのになぜか「石幢六面六地蔵」「織部燈籠」(キリシタン燈籠)の写真がありません。
(庫裡前の重石塔の右に御座と思われます。)

→ こちら(練馬区Web史料)をご覧ください。


【写真 上(左)】 御府内霊場の札所板
【写真 下(右)】 豊島霊場の札所板
御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受しました。
こちらでは豊島八十八ヶ所霊場の御朱印も授与されています。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
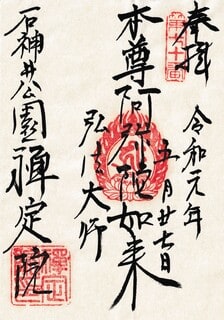

【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊阿弥陀如来」「弘法大師」の揮毫と阿弥陀如来のお種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「第七十番」の札所印。
左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
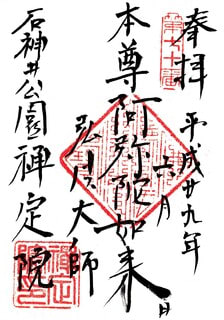
■ 豊島霊場の御朱印
※ 御府内霊場と豊島霊場の御朱印を同日に拝受していますが、これは御府内霊場参拝日にご不在で拝受できなかったためで、基本的には弘法大師霊場のかけもち巡拝は避けた方がベターかと思います。
■ 第71番 新井山 薬王寺 梅照院(新井薬師)
(ばいしょういん)
公式Web
中野区新井5-3-5
真言宗豊山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
司元別当:(新井村)天満宮、稲荷社、秋葉社、諏訪社
他札所:江戸・東京四十四閻魔参り第27番、閻魔三拾遺第30番
第71番は中野区新井の梅照院(新井薬師)です。
第71番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに小石川の玄性院となっており、第71番札所は御府内霊場開創当初から江戸末期まで小石川の玄性院で、『御府内八十八ケ所道しるべ』の札所変更資料に玄性院から梅照院への変更が記されているので、第71番札所は幕末から明治初頭にかけて中野の梅照院に変更とみられます。
公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから両山の縁起・沿革を追ってみます。
【梅照院】
永禄年間(1558-1570年)、相模國の沙門行春が行脚の途中、ここ新井を有縁の地と定め草案を結んで日夜行法に励んでいました。
(『ルートガイド』には、沙門行春は元北条家の家臣・梅村将監とあります。)
天正十四年(1586年)のある晩、庭の老梅の梢から光明が輝くのを見た行春が、件の梅の木を索ると梢の空洞から二仏一体(薬師瑠璃光如来・如意輪観世音菩薩)の尊像が出現されました。
村内の新田氏所縁の人々がこの御佛を拝すると、この尊像こそ新田家伝来の守り本尊と悟り、この奇縁に因んで一宇を建立したのが創始と伝わります。
梅樹から光明が照り輝いた奇瑞から、梅照院と号しました。
「新田家伝来の守り本尊」については以下の縁起が伝わります。
清和源氏の名族・新田家伝来の守り本尊は、薬師如来・如意輪観世音菩薩の二仏一体丈一寸八分の坐像黄金仏で弘法大師の御作と伝わります。
南北朝時代、新田家嫡流は上野國大田の金山城に拠り、守り本尊を宝庫に収めていましたがあるとき御本尊はお姿を消されました。
その後の変遷については公式Webをご覧ください。
戦に敗れた新田家所縁の人々が新井の庄に定住していたところ、沙門行春の霊夢により、行方知らずとなっていた新田家代々の守護仏を迎えたので恐懼し、また欣喜雀躍して堂宇に奉安したのでは。
公式Webによると、新田一族は薬師如来信仰の家系が多く、それぞれの家系に薬師如来の尊像が存在したといいます。
四散した新田一門がそれぞれの御本尊を各地で奉安したため「新田家の薬師如来」の系譜は錯綜していますが、当山の御本尊が「新田家伝来の守り本尊」とされています。
開創当時は山内に日本一ともいわれた傘松があったため、高松山梅照院薬王寺と号しましたが、新井薬師の名が高まるにつれ新井山と山号を改めたといいます。
新井薬師の通称が知られているので、新井薬師梅照院とも称します。
公式Webには行基が開基、中興は朝曇・聖道とあります。
『新編武蔵風土記稿』には、開山を快儀(正保三年(1646年)寂)、天正年中(1573-1592年)に僧・行春が開基、第六世朝曇を中興とあります。
元和三年(1617年)、第五代住職玄鏡の夢中に薬師如来が現れて御手の瑠璃の壺中より法軌を授与されました。
玄鏡和上は早速授与された法軌のとおりに薬を処方、難病の小児に施すとすこぶる効いて治らない者がひとりもいないため、この薬を「夢想丸(むそうがん)」と称して参詣者にわかちました。
中興の朝曇和上はこの霊験譚を世に広めたため御本尊の霊験が広く世に知られるようになり、「子育薬師」として諸人の信仰を集め、門前は市をなしたといいます。
寛永六年(1629年)徳川2代将軍秀忠公の第五女和子の方(東福門院)が眼病に罹られ、秀忠公をはじめ側近の人々が名医名薬、祈祷など八方手を尽くしましたが効果なく、万策つきたと思われたとき、当山の御本尊の霊験を伝え聞いて御本尊に祈願せしめました。
すると眼病はたちまち快癒したので、秀忠公は当山に厚く御礼を賜りました。
この逸話はたちまち天下に広まり、当院は「治願薬師」(ぢがんやくし)とも呼ばれてさらに参詣者を集めたといいます。
以降も参詣者は途絶えることなく、中野から新井薬師へと至る参道は門前町として大いに栄えて「東の浅草寺、西の新井薬師」と並び称されるほどでした。
門前町はいまでも「薬師あいロード商店街」として賑わいをみせ、8がつく日のお薬師さまのご縁日はことに賑わいをみせます。
和子の方の逸話に因み、とくに眼病にご利益ありとして広く参詣客を集めています。
西武新宿線の駅名にもなり、知名度の高い城西の名刹です。
なお、『新編武蔵風土記稿』には「(新井村)天満宮、稲荷社、秋葉社、諏訪社 供ニ村内梅照院ノ持ナリ」とあるので、こちらの4社の別当を司っていたとみられます。
新井天神 北野神社の公式Webに「天正年間(1573-1592年)、新井薬師の開祖である沙門行春が建立したとも、それ以前よりこの地の鎮守社であったとも言われています。」と、沙門行春との関係を示す記載があります。
また、「残存する梅照院縁起に『開基の行春より数代後の住持玄鏡が、天和年間に手植の梅一株を北野天満宮に献じた』とあります。」とあり、すでに天和年間(1681-1684年)から梅照院と良好な関係を保っていたことがわかります。


【写真 上(左)】 新井天神北野神社(旧拝殿)
【写真 下(右)】 同 御朱印


【写真 上(左)】 (新井天神)稲荷神社
【写真 下(右)】 同 御朱印
-------------------------
【玄性院】
玄性院は小石川の金剛寺坂辺にあった新義真言宗寺院です。
当地に御鎮座の金杉稲荷社の別当で、本社金杉稲荷大明神の本地、十一面観世音菩薩を奉安していたとみられます。
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ』には「本尊:十一面観世音菩薩 本社金杉稲荷大明神 弘法大師」とあり、こちらが御府内霊場の拝所であったことがわかります。
玄性院は史料が少なく詳細を辿れないのですが、『江戸町巡り』様によると小石川金杉水道町のうちに稲荷前町という場所があり、由来は金杉稲荷の前の町屋であったためとの由。
現在の文京区春日二丁目です。
また、『東京さまよい記』様の記事には以下のとおりあります。
-------------------------
荷風「断腸亭日乗」昭和16年(1941)9月28日に、「・・・金剛寺坂左側の駒井氏、右側の岩崎氏、其鄰の石橋氏なり。その筋向に稲荷の祠あり。余の遊びし頃には桐畑なり。・・・」(前回の記事)とあるが、その稲荷が金杉稲荷であろう。現在はないようである。
-------------------------
以上に『江戸切絵図』の情報を加えると、金杉稲荷大明神(玄性院)は小石川・金剛寺坂の春日通り寄りにあったのでは。
『寺社書上』には「中興開基 六角越前」とありますが、『江戸切絵図』では比較的近い場所に「六角越前守」の屋敷がみえます。
「六角越前守」で検索するとwikipediaの「六角広孝」がヒットしたので、こちらとの由縁を考えましたが、中興開山の聖譽法印は正徳三年(1713年)卒で、中興開山・開基を同時期と考えると六角広孝(1747-1815年)とは年代が合いません。
六角氏というと宇多源氏佐々木氏流で近江守護職もつとめた名族を思い起こしますが、Wikipediaによると、高家六角家は正二位権大納言烏丸光広の次男・広賢が江戸幕府に仕えて高家に列した流れ(日野流六角家)のようです。
当山中興開山・聖譽法印と同年代の高家六角家当主は2代の六角広治(1644-1719年)。
元禄二年(1689年)二月、従五位下侍従・越前守に叙任され「六角越前」に符合します。
禄は二千石で、高家の身分を考えると「大身の旗本」といってもいいかもしれません。
この六角広治が玄性院に中興開基となさしめるほどの大きな寄進をしたか、あるいは檀家総代として貢献したのかもしれません。
玄性院は本所彌勒寺の末なので現在の真言宗豊山派。
梅照院も真言宗豊山派ですから宗派的なつながりはあり、中野の名刹・梅照院に御府内霊場札所を承継したのかもしれません。
ただし、不思議なのは梅照院が豊島八十八ヶ所霊場の札所になっていないことです。
豊島八十八ヶ所霊場の開創は明治に入ってからで、中野区内にもいくつかの札所があります。
梅照院が弘法大師霊場の札所入りを考えていたとしたら、当然有力候補にあがるはずです。
あるいは明治初期にすでに御府内霊場の札所を承継していたので、それでよしとされたのかもしれません。
-------------------------
【史料】
【梅照院】
■ 『新編武蔵風土記稿 多磨郡巻三十五』(国立国会図書館)
(新井村)梅照院
当村(新井村)ト上高田村トノ接地ニアリ松高山ト号ス 新義真言宗ニテ 当郡中野村寶仙寺末 客殿六間四方南向
本尊薬師坐像ノ石佛ニテ長一寸八分 厨子ニ入
開山ヲ快儀ト云 正保三年(1646年)示寂ス 又云天正年中(1573-1592年)行春ト云僧開基セシト 其後第六世朝曇ヲ中興トス 此僧ノ頃ヨリ本尊ノ霊験世ニアラハル
子育薬師ト称シテ遠近コソッテ歩ヲ運フ者多シ 就中近キ比江戸日本橋邊ノ商売願ヲカケシニ 速ニ霊数ヲ蒙フリシカハ渇仰斜ナラス ソノ後同志参詣ノ者ノ便リセントテ 豊島郡下高田馬場ノホトリヨリ 道ノ辻々ニ碑標ヲタテヽ方角ヲ示ス コレヨリ次第ニ参詣ノ者多クナリテ 今ハ新井ノ薬師トテ其名隠レナキコトニソナリケル
(新井村)天満宮、稲荷社、秋葉社、諏訪社
供ニ村内梅照院ノ持ナリ
-------------------------
【玄性院】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
七十一番
小石川金杉●●町
永壽山 吉祥寺 玄性院
本所彌勒寺末 新義
本尊:十一面観世音菩薩 本社金杉稲荷大明神 弘法大師
■ 『寺社書上 [64] 小石川寺社書上 一』(国立国会図書館)
金杉稲荷社
小石川金杉
神躰無之
本地 十一面観音立像
弘法大師 辨財天十五童子付 阿弥陀如来
相殿 六角稲荷
神體宝珠
氏子町 金杉水道町四ヶ町 富坂新町
別当 永壽山吉祥寺玄性院
彌勒寺末 起立年代不詳
中興開山 聖譽法印 正徳三年(1713年)卒
中興開基 六角越前
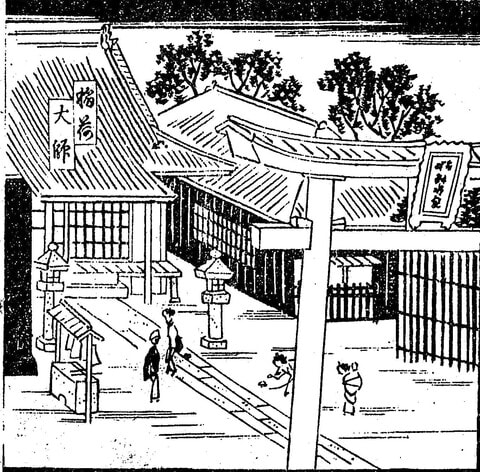
「玄性院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
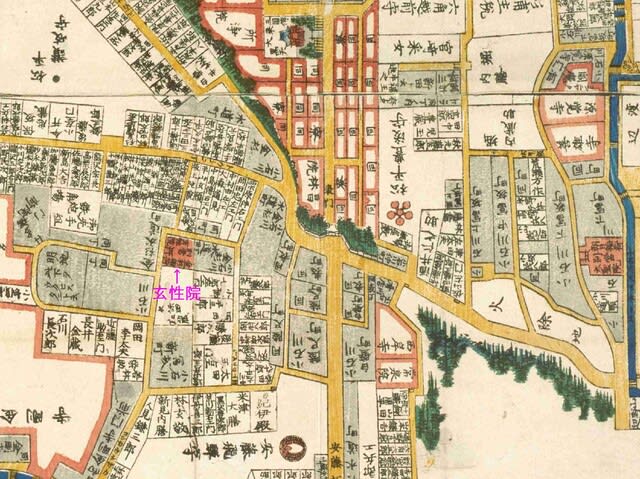
原典:戸松昌訓著、版元金鱗堂尾張屋清七、『〔江戸切絵図〕』東都小石川絵図 嘉永7[1854]/安政[4][1857]改刊.東京都立中央図書館Web(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは西武池袋線「石神井公園」駅で徒歩約10分。
「新井薬師門前」の五叉路から長い参道を構え、さすがに名刹のスケール感があります。
この五叉路から北西に進むと菅原道真公をお祀りする新井天神で、近在屈指の参詣エリアとなっています。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 院号標


【写真 上(左)】 新井薬師の碑
【写真 下(右)】 御府内霊場札所碑
参道入口には院号標と新東京百景の「新井薬師」の碑。
石畳の参道正面の山門左手前に御府内霊場の札所碑。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門の提灯
山門は切妻屋根桟瓦葺の四脚門で、軒下には新井薬師の提灯が掲げられています。
山門をくぐると正面が本堂。左手に霊堂、右が不動堂です。
順にご紹介していきます。
(公式Webの境内案内)


【写真 上(左)】 霊堂
【写真 下(右)】 修行大師と聖観世音菩薩
霊堂は均整のとれた朱塗りの二重の楼閣で、堂前向かって左手に修行大師像と聖観世音菩薩立像。
向拝見上げに「薬師霊堂」の扁額を掲げています。
霊堂の向拝扉には「御本尊真言」として阿弥陀如来と閻魔大王の御真言が掲出されているので、おそらくこちらの二尊を主尊として奉安とみられます。
なお、梅照院は江戸・東京四十四閻魔参り第27番、閻魔三拾遺第30番の札所で、閻魔様のお寺としても知られていたと思われます。
閻魔大王のご縁日16日に参拝しましたが、現在、閻魔大王の御朱印は不授与とのことだした。
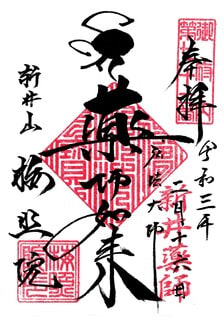
■ 閻魔大王のご縁日の御朱印


【写真 上(左)】 霊堂の扁額
【写真 下(右)】 不動堂


【写真 上(左)】 お願い地蔵尊
【写真 下(右)】 水屋
右手には不動堂。堂前右手にはお願い地蔵尊、左手には水子地蔵尊。
不動堂は宝形造桟瓦葺で流れ向拝。水引虹梁に木鼻、斗栱、海老虹梁、中備に蟇股を備えています。


【写真 上(左)】 鐘楼
【写真 下(右)】 大香炉
不動堂の本堂寄りには本瓦葺の屋根付きの立派な水屋(手水舎)とその奥に鐘楼。
参道を進むと大香炉。そこから左手に進むと西門で、墓所入口には六地蔵。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
本堂は基壇のうえに入母屋造本瓦葺流れ向拝、向拝の張りだしが大きくスケール感ある堂容で、向かって右手が授与所(札所)となっています。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 提灯と扁額
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に本蟇股。
水引虹梁奥に「新井薬師」の提灯、向拝見上げには「瑠璃殿」の扁額、向拝柱には御府内霊場の札所板を掲げています。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 札所板
御本尊は秘佛で、寅年の御開帳です。


【写真 上(左)】 白龍権現水屋
【写真 下(右)】 大悲殿
本堂を向かって右手に回り込み、回廊をくぐると右手に白龍権現水屋と大悲殿。
当山北側の瓢箪池(新井薬師公園)はその昔、霊泉の水垢離場として修行の道場となり不動尊を奉安していました。
その不動尊の傍には常に白蛇がいて不動尊を守護していたとも。
いつしか霊泉は枯れ、不動尊は山内の不動堂に遷られ、守護の白蛇供養のために白瀧権現を不動堂に祀りました。
当山貫首が「大悲殿に聖観世音菩薩を迎えて井戸の霊泉を閼伽水として衆生に施す」旨の夢告を受け、大悲殿(聖観世音菩薩の堂宇)を建立したところ、その敷地の地下に大井戸を発見し霊水が湧き出たためこの瑞祥を祝し、双竜を鋳造して水屋を建立し、「白龍権現水屋」と称しました。
大悲殿は二層の大規模な建物で、向拝には「大悲殿」の扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 大悲殿の扁額
【写真 下(右)】 聖徳太子像
本堂裏手には聖徳太子像。
昭和34年、聖徳太子の遺訓を仰ぐため、東京都左官職組合連合会中野支部の鶴谷善平氏が梅照院と支部の協力を得て像立・奉安されたお像です。
本堂のすぐ裏には年季の入った「魚がし」の天水鉢も置かれています。


【写真 上(左)】 「魚がし」の天水鉢
【写真 下(右)】 本堂再建供養塔
場所が定かでないのですが、本堂再建祈念塔(中野区登録有形文化財)の説明書には、当山再興に尽くされた蓮樹住職、後継英俊住職の功績と、この塔が高野山延命院の引導地蔵尊を模して建立されたことが記されています。
御朱印は本堂右手の札所にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
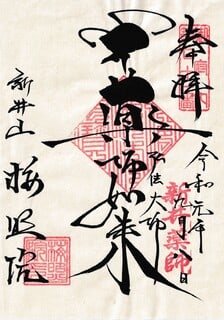
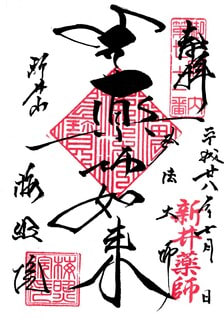
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に薬師如来のお種子「バイ」「薬師如来」「弘法大師」の揮毫と三寶印。
右に「御府内第七十一番」の札所印と「新井薬師」の印判。
左に山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-24)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ retour - 今井美樹
■ Sayonara Solitia - Yuki Kajiura(FictionJunction)
■ ここにあること - @うさ(歌ってみた)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1B
※ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1から分離。
Vol.-1Aからのつづきです。
■ 第1番 高野山東京別院(こうやさんとうきょうべついん)
公式Web
港区高輪3-15-18
高野山真言宗
御本尊:弘法大師
札所本尊:弘法大師
他札所:関東八十八箇所特別札所、江戸三十三観音札所第29番
授与所:本堂左手の納経所
御府内八十八ヶ所霊場の初番発願所は、高野山真言宗の高野山東京別院です。
正式名称は、高野山真言宗総本山金剛峯寺 高野山東京別院。
ご住職は総本山金剛峯寺座主が兼摂され、「高輪結び大師」の通称をもち、首都圏における「大師信仰」の教化の拠点として広く親しまれています。
東都の弘法大師霊場の発願所として、誠にふさわしい名刹といえましょう。
慶長年間(1596-1615年)、高野山学侶方の江戸在番所として浅草日輪寺に寄留して開創。明暦元年(1655年)に幕府より芝二本榎に土地が下賜され、延宝元年(1673年)高野山江戸在番所高野寺として建立されました。
以降、幕府方との宗務にかかる交渉、幕府諸通達を全国の古義真言宗寺院に通達する「触頭」(ふれがしら)を務められ、江戸における古義真言宗の中核としての役割を果たされました。
明治に入って在番所が廃止され、葛飾牛島の長壽寺の名蹟を移して継承し、昭和2年現号に改号しています。
-------------------------


【写真 上(左)】 二本榎通りからの山門
【写真 下(右)】 修行大師像と山門
高野山東京別院は、高輪の海辺から桂坂を登ったところ、門前の二本榎通りは古代東海道ともいわれる主要道で要衝の地にあることがわかります。
このあたりの寺院は武蔵野台地の突端に置かれていることが多いですが、当山もその好例かと思います。
二本榎通り沿いに山門。
切妻屋根本瓦葺。門後に控柱を立てその上に小屋根を置いているのでおそらく高麗門。
門の左右に脇門付きの築地、さらにそのよこになまこ壁を配して変化をもたせた意匠です。


【写真 上(左)】 修行大師像
【写真 下(右)】 院号板
山門向かって左手には、修行大師像が門外までお出ましになられています。
さすがに「首都圏における『大師信仰』の教化の拠点」です。


【写真 上(左)】 札所碑(表面)
【写真 下(右)】 札所碑(側面)


【写真 上(左)】 別の札所碑
【写真 下(右)】 弘法大師碑
そのよこの石碑は正面に「第壱番」、側面に「御府内八十八●●」とあるので御府内霊場の札所碑です。
そばには別の札所碑もあります。
山門向かって右には「弘法大師」の石碑。
山門幕には高野山真言宗の宗紋、「五三の桐」と「三頭右巴(さんとうみぎどもえ)」が染め抜かれています。
こうやさん便りWebによると、
五三桐 - 豊臣秀吉拝領の青厳寺の寺紋。
三つ巴 - 鎮守・丹生都比売神社(通称・天野神社)の定紋。
ということで、通常このふたつの紋をセットで使用されます。
すでに山門前からして「お大師さまのお寺」のイメージ炸裂です。
また、札所碑の位置からして、御府内八十八ヶ所が弘法大師信仰のうえから重要な霊場であることがわかります。


【写真 上(左)】 参道とお砂踏み霊場
【写真 下(右)】 以前のお砂踏み霊場


【写真 上(左)】 幟旗
【写真 下(右)】 六地蔵
山門をくぐると都心らしからぬ広々とした空間が広がります。
最近山門周辺の四国八十八箇所お砂踏み霊場が参道沿いに移設され、以前よりもひろびろ感が増しています。
日当たりのよい台地にあるためか、山内は明るい雰囲気です。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 明神社参道


【写真 上(左)】 明神社鳥居扁額
【写真 下(右)】 明神社
参道右手に明神社が御鎮座です。
第一殿は、丹生明神(丹生都比売大神)・気比明神(大食津比売大神)
第二殿は、高野明神(高野御子大神)・厳島明神(市杵島比売大神)
第三殿は、十二王子・百二十番神(高野山の周囲を守る神々)
第四殿は、高輪神社の御祭神(東京別院の氏神社)
うち、第一殿、第二殿の御祭神を高野山の(天野)四社明神といい、高野山と関係のふかい丹生都比売神社(和歌山県かつらぎ町、紀伊国一宮、旧官幣大社)の御祭神です。
丹生明神は、高野山の鎮守神とされ、高野明神は丹生明神の子で弘法大師を高野山上に案内されたと伝わります。
弘法大師は高野山を開かれるに当たり、まず明神社を祀られ、その後山内伽藍の建築に着手されたといいます。
高野山には明神社が祀られ、山内諸行事はすべて明神社参拝からはじまるとされます。
神仏習合の江戸期には当山山内に明神社が祭祀されていましたが、明治の神仏分離で廃され、平成27年の高野山開創千二百年の記念事業により再建されました。
10月16日の明神社の鎮座祭は丹生都比売神社の宮司様により執行され、翌日の萬燈萬華大法会では宮司様と管長猊下により、奉祝祭と開眼法要が神仏混淆で奉修されたとのことです。(山内掲示より)


【写真 上(左)】 不動堂
【写真 下(右)】 元旦の本堂


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 向拝前
その先右手には宝形造の不動堂。ここまでくると本堂は目の前です。
昭和63年落慶の本堂は二層建築で、おそらく入母屋造本瓦葺の妻入かと思います。
上層に千鳥破風、下層向拝上に唐破風を興してスケール感があります。
行事日には向拝まわりに五色の幔幕が廻らされ、ひときわ華やいだ雰囲気になります。
向拝の「遍照殿」の扁額が、当山御本尊が弘法大師であることを示しています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝扁額
天井高く奥行き深く、荘厳な堂内。
タイミングにより、御内陣まで上げていただけることもあります。(新型コロナ禍以降のご対応は不明)
密寺らしく、堂内には多くの尊像が奉安されています。


【写真 上(左)】 聖観世音菩薩
【写真 下(右)】 一願大師
本堂向かって右手には端正な聖観世音菩薩立像、そして一願大師も御座されています。
御朱印は本堂向かって左手の納経所で授与されています。
複数の札所を兼任されているので、御府内霊場の申告は必須。ご対応はたいへんに親切です。
なお、御府内霊場専用集印帳の頒布は、おそらくこちらのみとみられます。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
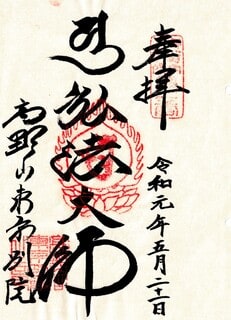
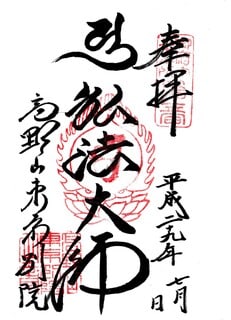
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳-1
主印は弘法大師のお種子「ユ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)、揮毫は「弘法大師」で札所印と寺院印が捺されています。
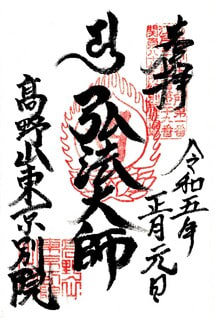
汎用御朱印帳-2
御府内八十八ヶ所、江戸三十三観音札所、関東八十八箇所の3札所兼印が捺されることもあります。
※霊場無申告の場合は、こちらの御朱印になる模様です。
御府内霊場の掛け持ち参拝はおすすめしませんが、いちおう他の御朱印もご紹介します。
〔 関東八十八箇所特別霊場の御朱印 〕
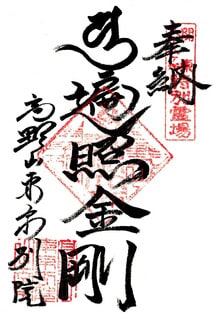
「遍照金剛」の御朱印をいただきたい場合は、こちらで申告します。
原則として日付は入らないようです。
〔 江戸三十三観音札所第29番の御朱印 〕
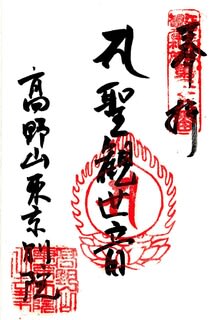
札所本尊の聖観世音菩薩は、当山四世増舜大阿闍梨が高野山青巌寺より奉持・安置された尊像です。
■ 第2番 金峰山 世尊院 東福寺(とうふくじ)
中野区江古田3-9-15
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:豊島八十八ヶ所第2番
授与所:授与所
中野区江古田にある真言宗豊山派寺院です。
オフィシャルな由緒沿革資料がみつからなかったので、「中野区史 下巻』を当たってみました。P.497に以下の記載があります。
「金峯山世尊院と号する。本尊不動明王。立像長一尺二寸。舊(旧)は字御嶽山にあつたのを、某年現在の地に移した。開山は未詳、開基は村民次郎右衛門の先祖某で、天正年中(1573-1592年)の起立と傳へるけれども未だ詳でない。法流の祖は法運といひ、享保七年(1722年)十一月五日示寂した。(略)本堂の左に大師堂があり、府内八十八箇所の第二番に当る。もと大久保の二尊院に在つたのを明治の初年当寺に遷したのである。(略)当寺は、舊と氷川神社(現在村社、江古田三丁目一一五九鎮座)の別当であり、又江戸時代には将軍放鷹の際の御膳所であつた。」
また、『新編武蔵風土記稿』には以下のとおりあります。
「除地五段 村ノ南ノ方上鷺ノ宮村堺ニアリ 金峯山世尊院ト号ス 新義真言宗ニテ中野村寶仙寺ノ末 此寺元ハ村内御嶽山ノ邊ニアリシヲ 年月詳ナラス此処ヘ移シタリト云 本堂ハ八間半ニ七間 本尊不動ノ立像長一尺二寸 開山詳ナラス 法流ノ祖ヲ法運ト云 享保七年(1722年)十一月五日示寂 開基ハ村民次郎右衛門カ先祖ニテ 天正年中(1573-1592年)ニ起立トイヘト 其詳ナルコトヲ傳ヘス」
さらに「中野区公式観光サイト『まるっと中野』」(PDF)には、「旧江古田村には正保年間(1644-1648年)の鷹狩の折に東福寺で江古田獅子舞を上覧したという言い伝えがあります。江古田獅子舞の上覧は、8代将軍吉宗の時、享保十三年(1728年)2月12日にこのときに御膳所に指定された東福寺で行われています。」「東福寺には『御成の間』が造られ将軍来訪に備えました」とありました。
上記と『中野区寺院・仏事ガイド』および山内掲示の内容をあわせ、由緒沿革をまとめてみます。
中世、江古田本村に御鎮座の御嶽神社の氏子・二郎左衛門(堀野氏)が、武州御獄神社の社僧源教の教化を受けて神社の南麓に堂宇を建立、弘法大師の御作と伝わる一本彫の不動明王立像を御本尊として奉安し、金峰山世尊院東福寺の号を贈られたといいます。
開山は未詳、開基は村民次郎右衛門の先祖某(江古田御嶽神社の氏子・二郎左衛門(堀野氏)か)。
天正年中(1573-1592年)に堂宇が焼失、寛永年間(1624-1644年)?に当地に遷して再建(起立)。
法流の祖は法運(享保七年(1722年)寂)とあるので、法運による中興があったのかもしれません。
当山は江戸時代にしばしば将軍の鷹狩の御膳所となりました。
記録の残る正保年間(1644-1648年)の鷹狩御座と江古田獅子舞上覧は、三代将軍徳川家光公(在職:1623-1651年)とみられます。
この江古田獅子舞(祈祷獅子)は御嶽神社の社憎から伝授と伝わり、当山梵鐘の四面には獅子舞ゆかりの四神を模写した彫刻があります。
八代将軍・吉宗公は享保十三年(1728年)2月に来臨、すでに承応年間(1652-1655年に『御成りの間』として改築されていた客殿で休息したといい、跡地には「徳川将軍御膳所跡」の石碑が建てられています。
「中野区史 下巻』によると、弘法大師霊場としての系譜は新宿・余丁町の厳島神社の元別当・二尊院からで、明治の神仏分離により廃寺となったため東福寺に遷されたとのこと。
余丁町の厳島神社とは抜弁天(ぬけべんてん)のことで、新宿山ノ手七福神の弁財天となられて、本務社(?)の西向天神社で御朱印を授与されています。
『新編武蔵風土記稿 巻之11』の東大久保村の項に以下のとおりあります。
「辨天社 意形ノ像ナリ 弘法大師ノ作(以下略)」
「別当二尊院 新義真言宗 愛宕圓福寺地中金剛院ノ末 雨寶山ト号ス 本尊大日ヲ置」
↑によると、厳島神社(抜弁天)の御神体は弘法大師の御作とされ、別当二尊院は新義真言宗。
いずれもお大師さまゆかりの寺社です。

抜弁天の御朱印
『札所めぐり』によると、二尊院は弘安三年(1280年)の創建で、御本尊の不動明王は弘法大師の御作と伝わります。
二尊院の御本尊は弘法大師御作の不動明王というWeb記事もいくつかみつかりましたが出典は不明。
『新編武蔵風土記稿』には二尊院の御本尊は大日如来とありますが、弘法大師御作の不動明王奉安となると、こちらが御本尊になるとも思われよくわかりません。
ともあれ、御府内八十八箇所第2番は明治に二尊院から東福寺に遷ったという複数の資料があるのでこれは事実かと。
『新編武蔵風土記稿』には東福寺の御本尊は不動明王とあるので、こちらの(伝・弘法大師作の)お不動様が札所異動後の札所本尊となられたとみるのが自然かもしれません。
旧第2番が新宿余丁町だったとしても、初番の高輪から新宿余丁町の間には御府内霊場の札所がいくつもあるので、どうも御府内霊場の札番は単純にルート的な廻りやすさから振ったものではないような気もします。
(札所位置図→第76番蓮華山金剛院様公式Webで新宿余丁町は四ッ谷の上あたり。)
そんなこともあって、この霊場の順打ち(逆打ち)はすこぶる時間がかかるものとなります。
-------------------------


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 札所碑
沼袋周辺は細い路地が多いですが、その北の新青梅街道から江古田の森公園にかけては比較的ゆったりとした街区となります。
東福寺は江古田の森公園の南側に、広めの山内を構えています。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 参道
山門は切妻屋根銅板葺で寺号扁額を掲げ、左右に築地をまわしています。
山門右手には御府内霊場の札所碑。
山門をくぐった右手は幼稚園で、平日は園児の声で賑やかです。
参道左手の山手は墓地で、その山裾に手前から庚申塔、大蔵院不動尊、徳川将軍御膳所跡の碑、鐘楼と並びます。


【写真 上(左)】 大蔵院不動尊と鐘楼
【写真 下(右)】 興教大師像と御膳所跡碑
大蔵院不動尊は青山鳳閣寺配下大蔵院ゆかりの尊像で、もとは現・江古田二丁目に御座し耳や眼の病に霊験あらたかな不動尊として多数の信者を集めたといいます。
大蔵院不動尊の上方に鐘楼、その手前には新義真言宗寺院らしく興教大師のお像が御座します。
そのよこの徳川将軍御膳所跡碑の前から本堂に向かって階段をのぼります。
間口の広い堂々たる参道階段で、その途中右手に大師堂があります。


【写真 上(左)】 参道階段
【写真 下(右)】 大師堂
大師堂は宝形造銅板葺きの整った堂容で向拝には弘法大師の扁額が掲げられ、さすがに札所第2番、弘法大師霊場の趣きゆたかです。
弘法大師霊場の巡拝では当然こちらも参拝することになります。


【写真 上(左)】 修行大師像
【写真 下(右)】 本堂
のぼり切った正面が本堂で、向かって右手前には修行大師像が御座します。。
入母屋造本瓦葺流れ向拝のスケール感あふれるつくりで、向拝見上げに山号扁額を置いています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝扁額
山内掲示には不動堂は「成田不動尊写」とあり、境外佛堂として江原町観音堂が記されていますが、不動堂の所在はわかりませんでした。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
主印は不動明王のお種子「カン/カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)、揮毫は「不動明王」「弘法大師」で札所印と寺院印が捺されています。
〔 豊島八十八ヶ所第2番の御朱印 〕
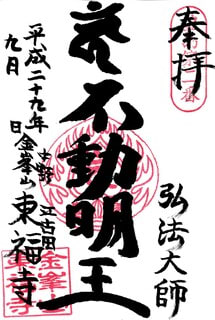
豊島八十八ヶ所も第2番です。主印、揮毫はおなじですが札所印が異なります。
■ 第3番 金剛山 悲願寺 多聞院(たもんいん)
世田谷区北烏山4-10-1
真言宗豊山派
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第44番、江戸八十八ヶ所霊場第3番
授与所:庫裡
御府内八十八ヶ所の札所のうちには、府内(都心部)から郊外に移転したケースがいくつかあって、こちらものひとつです。
場所は世田谷区北烏山。
ここは都心部から移転した二十六もの寺院が集中し「烏山寺町」という大規模な寺町を形成しています。
手元にさるお寺様からいただいた『烏山寺町』という冊子があるので、こちらを参考に沿革を辿ってみます。

『烏山北町』
烏山寺町のおいたちは大正12年の関東大震災を直接の契機としますが、すでに明治21年には「東京市区改正条例」により都心部寺院・墓地等の共葬墓地・郊外への移転方針が決定していました。
共葬墓地への移転は順調に進み青山、雑司ヶ谷、染井、谷中、亀戸などは早い時期にすでに飽和状態になりました。
このため郊外の多摩共葬墓地の整備が進められ、大正12年春より共用開始しています。
同年9月の関東大震災は、この都心から郊外への寺院・墓地移転の流れを一気に加速しました。
練馬の寺町には浅草田島町から11箇寺、足立区伊興には元浅草・下谷・本所から、築地の西本願寺別院および塔頭55箇寺は杉並区和泉、仙川、調布そして烏山に移転しました。
烏山へは築地・浅草をはじめ、下谷、麻布、三田、品川などから寺院が移転しています。
当時の烏山は民家はほとんどなく、畑や桑圓が広がる農村地帯だったといいます。
移転した26箇寺は、真宗13、日蓮宗4、法華宗3、浄土宗4、真言宗1、臨済宗1と、真宗・日蓮宗・法華宗寺院が過半を占め、御朱印エリアのイメージはあまり強くはないものの、複数の寺院で御朱印・御首題を授与され、なかでももっとも御朱印がいただきやすいのが御府内八十八箇所の札所である多聞院です。
(→ 東京都世田谷区の札所と御朱印 (前編)をご参照。)
「烏山寺町」によると、多聞院は元和元年(1615年)新宿角筈村に創建。
開山は述譽法印、開基は角筈村名主・渡邉與(小)兵衛(法名天雪舊満)と伝わり、大塚(音羽)護国寺の末でした。
昭和20年5月の戦火で堂宇を焼失して現在地に移転、昭和29年末には本堂・庫裡が完成しています。
『新編武蔵風土記稿』には「新義真言宗、江戸大塚護國寺末金剛山慈願寺ト号ス 開山述誉ハ寛永元年(1624年)五月五日寂ス 開基ハ村内名主傳右衛門先祖與兵衛ニテ 法名天雪舊満ト云 明暦四年(1658年)六月十日死ス 本尊地蔵ヲ安ス」とあります。
御府内八十八ヶ所霊場3番札所、玉川八十八ヶ所霊場44番札所となっています。
玉川八十八ヶ所霊場の前身である四郡多摩川八十八所は江戸期の開創と伝わりますが、昭和48年に玉川八十八ヶ所として再編しているので、そのときに札所となったとみられます。
世田谷区内の弘法大師霊場は玉川八十八ヶ所がメインで、多聞寺は世田谷区内唯一の御府内霊場札所です。
山内に「天竺渡来石彫涅槃図」があり、これは奈良・壺坂寺(南法華寺)よりの寄贈。
説明碑によると多聞院先々代中興教荘和尚は壺坂寺住職として在職時の昭和36年に日本で最初の養護盲老人ホーム「慈母園」を開設されました。
(壺坂寺は眼病に霊験で有名)
壺坂寺は長年の救ライ活動に対して、インド政府より大観音石像の寄贈を受け、これが発展して昭和61年壺坂寺に大仏伝図(涅槃図)レリーフが建立され、そのゆかりの図が多聞院に寄贈されたのでは。
壺坂寺(南法華寺)は大宝三年(703年)創建の真言宗系の古刹で、元正天皇の祈願寺となっています。
承和十四年(847年)には長谷寺とともに定額寺に列せらたという名刹で、多聞院先々代教荘和尚が壺坂寺住職として在職されていたとなると、多聞院はかなりの寺格ではないでしょうか。
また、ふるくから壺坂寺と関係をもっていた事も想像されます。
壺坂寺は西国三十三所第6番札所ですから、そのゆかりで御府内霊場札所に列したのかもしれません。
-------------------------


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 参道
烏山寺町は一部路地的な街区もありますが、たいていは広い道路に面して車でのアクセスは楽です。
当山も広めの駐車場がありますが、お盆やお彼岸などの参拝はさけた方がベターかと思います。


【写真 上(左)】 観世音菩薩
【写真 下(右)】 延命地蔵尊


【写真 上(左)】 観世音菩薩
【写真 下(右)】 不動明王
山門入口は門柱。ここから正面の本堂に向かって参道が伸びています。
木々は少なめで開放的な山内。
参道まわりには、不動明王、地蔵尊、観世音菩薩などが御座します。


【写真 上(左)】 仏足石
【写真 下(右)】 レリーフ
精緻な仕上がりの仏足石と、上記の「天竺渡来石彫涅槃図」レリーフが見どころです。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
向拝上に山号扁額を置いています。
堂前に修行大師像は御座されず、弘法大師は本堂内御座と思われます。
墓域には天保八年(1837年)の大飢饉の犠牲者を供養する「五百六十八人無縁墓」、明治詩壇の重鎮・本田種竹の墓、館林藩の尊皇攘夷の士・大久保鼎の墓があります。
御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受しました。
ふたつのメジャー霊場を兼務され、手なれたご対応です。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
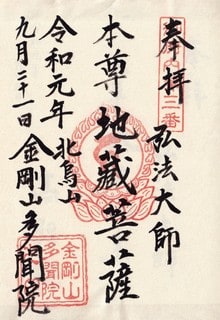

【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
主印は地蔵菩薩のお種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)、揮毫は「本尊 地蔵菩薩」「弘法大師」で札所印と寺院印が捺されています。
〔 玉川八十八ヶ所霊場第44番の御朱印 〕
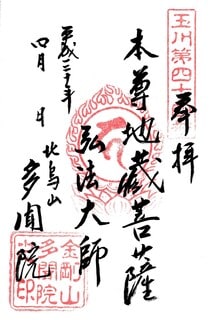
主印、揮毫はおなじですが札所印が異なります。
以下、Vol.-2へつづきます。
【 BGM 】
■ 夢の大地 - Kalafina
■ 桜 - 中村舞子
■ 栞 - 天野月 feat.YURiCa/花たん
Vol.-1Aからのつづきです。
■ 第1番 高野山東京別院(こうやさんとうきょうべついん)
公式Web
港区高輪3-15-18
高野山真言宗
御本尊:弘法大師
札所本尊:弘法大師
他札所:関東八十八箇所特別札所、江戸三十三観音札所第29番
授与所:本堂左手の納経所
御府内八十八ヶ所霊場の初番発願所は、高野山真言宗の高野山東京別院です。
正式名称は、高野山真言宗総本山金剛峯寺 高野山東京別院。
ご住職は総本山金剛峯寺座主が兼摂され、「高輪結び大師」の通称をもち、首都圏における「大師信仰」の教化の拠点として広く親しまれています。
東都の弘法大師霊場の発願所として、誠にふさわしい名刹といえましょう。
慶長年間(1596-1615年)、高野山学侶方の江戸在番所として浅草日輪寺に寄留して開創。明暦元年(1655年)に幕府より芝二本榎に土地が下賜され、延宝元年(1673年)高野山江戸在番所高野寺として建立されました。
以降、幕府方との宗務にかかる交渉、幕府諸通達を全国の古義真言宗寺院に通達する「触頭」(ふれがしら)を務められ、江戸における古義真言宗の中核としての役割を果たされました。
明治に入って在番所が廃止され、葛飾牛島の長壽寺の名蹟を移して継承し、昭和2年現号に改号しています。
-------------------------


【写真 上(左)】 二本榎通りからの山門
【写真 下(右)】 修行大師像と山門
高野山東京別院は、高輪の海辺から桂坂を登ったところ、門前の二本榎通りは古代東海道ともいわれる主要道で要衝の地にあることがわかります。
このあたりの寺院は武蔵野台地の突端に置かれていることが多いですが、当山もその好例かと思います。
二本榎通り沿いに山門。
切妻屋根本瓦葺。門後に控柱を立てその上に小屋根を置いているのでおそらく高麗門。
門の左右に脇門付きの築地、さらにそのよこになまこ壁を配して変化をもたせた意匠です。


【写真 上(左)】 修行大師像
【写真 下(右)】 院号板
山門向かって左手には、修行大師像が門外までお出ましになられています。
さすがに「首都圏における『大師信仰』の教化の拠点」です。


【写真 上(左)】 札所碑(表面)
【写真 下(右)】 札所碑(側面)


【写真 上(左)】 別の札所碑
【写真 下(右)】 弘法大師碑
そのよこの石碑は正面に「第壱番」、側面に「御府内八十八●●」とあるので御府内霊場の札所碑です。
そばには別の札所碑もあります。
山門向かって右には「弘法大師」の石碑。
山門幕には高野山真言宗の宗紋、「五三の桐」と「三頭右巴(さんとうみぎどもえ)」が染め抜かれています。
こうやさん便りWebによると、
五三桐 - 豊臣秀吉拝領の青厳寺の寺紋。
三つ巴 - 鎮守・丹生都比売神社(通称・天野神社)の定紋。
ということで、通常このふたつの紋をセットで使用されます。
すでに山門前からして「お大師さまのお寺」のイメージ炸裂です。
また、札所碑の位置からして、御府内八十八ヶ所が弘法大師信仰のうえから重要な霊場であることがわかります。


【写真 上(左)】 参道とお砂踏み霊場
【写真 下(右)】 以前のお砂踏み霊場


【写真 上(左)】 幟旗
【写真 下(右)】 六地蔵
山門をくぐると都心らしからぬ広々とした空間が広がります。
最近山門周辺の四国八十八箇所お砂踏み霊場が参道沿いに移設され、以前よりもひろびろ感が増しています。
日当たりのよい台地にあるためか、山内は明るい雰囲気です。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 明神社参道


【写真 上(左)】 明神社鳥居扁額
【写真 下(右)】 明神社
参道右手に明神社が御鎮座です。
第一殿は、丹生明神(丹生都比売大神)・気比明神(大食津比売大神)
第二殿は、高野明神(高野御子大神)・厳島明神(市杵島比売大神)
第三殿は、十二王子・百二十番神(高野山の周囲を守る神々)
第四殿は、高輪神社の御祭神(東京別院の氏神社)
うち、第一殿、第二殿の御祭神を高野山の(天野)四社明神といい、高野山と関係のふかい丹生都比売神社(和歌山県かつらぎ町、紀伊国一宮、旧官幣大社)の御祭神です。
丹生明神は、高野山の鎮守神とされ、高野明神は丹生明神の子で弘法大師を高野山上に案内されたと伝わります。
弘法大師は高野山を開かれるに当たり、まず明神社を祀られ、その後山内伽藍の建築に着手されたといいます。
高野山には明神社が祀られ、山内諸行事はすべて明神社参拝からはじまるとされます。
神仏習合の江戸期には当山山内に明神社が祭祀されていましたが、明治の神仏分離で廃され、平成27年の高野山開創千二百年の記念事業により再建されました。
10月16日の明神社の鎮座祭は丹生都比売神社の宮司様により執行され、翌日の萬燈萬華大法会では宮司様と管長猊下により、奉祝祭と開眼法要が神仏混淆で奉修されたとのことです。(山内掲示より)


【写真 上(左)】 不動堂
【写真 下(右)】 元旦の本堂


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 向拝前
その先右手には宝形造の不動堂。ここまでくると本堂は目の前です。
昭和63年落慶の本堂は二層建築で、おそらく入母屋造本瓦葺の妻入かと思います。
上層に千鳥破風、下層向拝上に唐破風を興してスケール感があります。
行事日には向拝まわりに五色の幔幕が廻らされ、ひときわ華やいだ雰囲気になります。
向拝の「遍照殿」の扁額が、当山御本尊が弘法大師であることを示しています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝扁額
天井高く奥行き深く、荘厳な堂内。
タイミングにより、御内陣まで上げていただけることもあります。(新型コロナ禍以降のご対応は不明)
密寺らしく、堂内には多くの尊像が奉安されています。


【写真 上(左)】 聖観世音菩薩
【写真 下(右)】 一願大師
本堂向かって右手には端正な聖観世音菩薩立像、そして一願大師も御座されています。
御朱印は本堂向かって左手の納経所で授与されています。
複数の札所を兼任されているので、御府内霊場の申告は必須。ご対応はたいへんに親切です。
なお、御府内霊場専用集印帳の頒布は、おそらくこちらのみとみられます。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
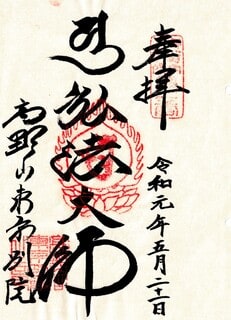
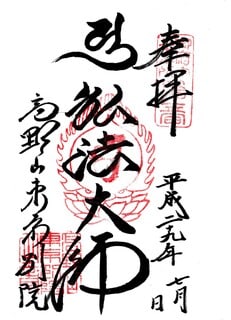
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳-1
主印は弘法大師のお種子「ユ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)、揮毫は「弘法大師」で札所印と寺院印が捺されています。
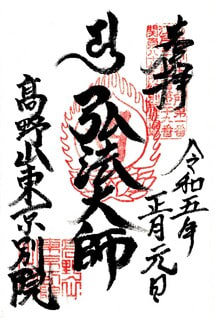
汎用御朱印帳-2
御府内八十八ヶ所、江戸三十三観音札所、関東八十八箇所の3札所兼印が捺されることもあります。
※霊場無申告の場合は、こちらの御朱印になる模様です。
御府内霊場の掛け持ち参拝はおすすめしませんが、いちおう他の御朱印もご紹介します。
〔 関東八十八箇所特別霊場の御朱印 〕
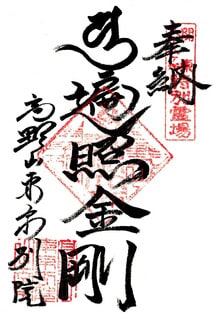
「遍照金剛」の御朱印をいただきたい場合は、こちらで申告します。
原則として日付は入らないようです。
〔 江戸三十三観音札所第29番の御朱印 〕
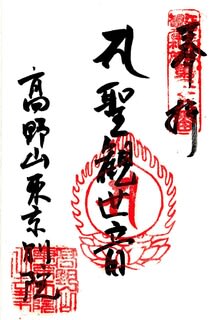
札所本尊の聖観世音菩薩は、当山四世増舜大阿闍梨が高野山青巌寺より奉持・安置された尊像です。
■ 第2番 金峰山 世尊院 東福寺(とうふくじ)
中野区江古田3-9-15
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:豊島八十八ヶ所第2番
授与所:授与所
中野区江古田にある真言宗豊山派寺院です。
オフィシャルな由緒沿革資料がみつからなかったので、「中野区史 下巻』を当たってみました。P.497に以下の記載があります。
「金峯山世尊院と号する。本尊不動明王。立像長一尺二寸。舊(旧)は字御嶽山にあつたのを、某年現在の地に移した。開山は未詳、開基は村民次郎右衛門の先祖某で、天正年中(1573-1592年)の起立と傳へるけれども未だ詳でない。法流の祖は法運といひ、享保七年(1722年)十一月五日示寂した。(略)本堂の左に大師堂があり、府内八十八箇所の第二番に当る。もと大久保の二尊院に在つたのを明治の初年当寺に遷したのである。(略)当寺は、舊と氷川神社(現在村社、江古田三丁目一一五九鎮座)の別当であり、又江戸時代には将軍放鷹の際の御膳所であつた。」
また、『新編武蔵風土記稿』には以下のとおりあります。
「除地五段 村ノ南ノ方上鷺ノ宮村堺ニアリ 金峯山世尊院ト号ス 新義真言宗ニテ中野村寶仙寺ノ末 此寺元ハ村内御嶽山ノ邊ニアリシヲ 年月詳ナラス此処ヘ移シタリト云 本堂ハ八間半ニ七間 本尊不動ノ立像長一尺二寸 開山詳ナラス 法流ノ祖ヲ法運ト云 享保七年(1722年)十一月五日示寂 開基ハ村民次郎右衛門カ先祖ニテ 天正年中(1573-1592年)ニ起立トイヘト 其詳ナルコトヲ傳ヘス」
さらに「中野区公式観光サイト『まるっと中野』」(PDF)には、「旧江古田村には正保年間(1644-1648年)の鷹狩の折に東福寺で江古田獅子舞を上覧したという言い伝えがあります。江古田獅子舞の上覧は、8代将軍吉宗の時、享保十三年(1728年)2月12日にこのときに御膳所に指定された東福寺で行われています。」「東福寺には『御成の間』が造られ将軍来訪に備えました」とありました。
上記と『中野区寺院・仏事ガイド』および山内掲示の内容をあわせ、由緒沿革をまとめてみます。
中世、江古田本村に御鎮座の御嶽神社の氏子・二郎左衛門(堀野氏)が、武州御獄神社の社僧源教の教化を受けて神社の南麓に堂宇を建立、弘法大師の御作と伝わる一本彫の不動明王立像を御本尊として奉安し、金峰山世尊院東福寺の号を贈られたといいます。
開山は未詳、開基は村民次郎右衛門の先祖某(江古田御嶽神社の氏子・二郎左衛門(堀野氏)か)。
天正年中(1573-1592年)に堂宇が焼失、寛永年間(1624-1644年)?に当地に遷して再建(起立)。
法流の祖は法運(享保七年(1722年)寂)とあるので、法運による中興があったのかもしれません。
当山は江戸時代にしばしば将軍の鷹狩の御膳所となりました。
記録の残る正保年間(1644-1648年)の鷹狩御座と江古田獅子舞上覧は、三代将軍徳川家光公(在職:1623-1651年)とみられます。
この江古田獅子舞(祈祷獅子)は御嶽神社の社憎から伝授と伝わり、当山梵鐘の四面には獅子舞ゆかりの四神を模写した彫刻があります。
八代将軍・吉宗公は享保十三年(1728年)2月に来臨、すでに承応年間(1652-1655年に『御成りの間』として改築されていた客殿で休息したといい、跡地には「徳川将軍御膳所跡」の石碑が建てられています。
「中野区史 下巻』によると、弘法大師霊場としての系譜は新宿・余丁町の厳島神社の元別当・二尊院からで、明治の神仏分離により廃寺となったため東福寺に遷されたとのこと。
余丁町の厳島神社とは抜弁天(ぬけべんてん)のことで、新宿山ノ手七福神の弁財天となられて、本務社(?)の西向天神社で御朱印を授与されています。
『新編武蔵風土記稿 巻之11』の東大久保村の項に以下のとおりあります。
「辨天社 意形ノ像ナリ 弘法大師ノ作(以下略)」
「別当二尊院 新義真言宗 愛宕圓福寺地中金剛院ノ末 雨寶山ト号ス 本尊大日ヲ置」
↑によると、厳島神社(抜弁天)の御神体は弘法大師の御作とされ、別当二尊院は新義真言宗。
いずれもお大師さまゆかりの寺社です。

抜弁天の御朱印
『札所めぐり』によると、二尊院は弘安三年(1280年)の創建で、御本尊の不動明王は弘法大師の御作と伝わります。
二尊院の御本尊は弘法大師御作の不動明王というWeb記事もいくつかみつかりましたが出典は不明。
『新編武蔵風土記稿』には二尊院の御本尊は大日如来とありますが、弘法大師御作の不動明王奉安となると、こちらが御本尊になるとも思われよくわかりません。
ともあれ、御府内八十八箇所第2番は明治に二尊院から東福寺に遷ったという複数の資料があるのでこれは事実かと。
『新編武蔵風土記稿』には東福寺の御本尊は不動明王とあるので、こちらの(伝・弘法大師作の)お不動様が札所異動後の札所本尊となられたとみるのが自然かもしれません。
旧第2番が新宿余丁町だったとしても、初番の高輪から新宿余丁町の間には御府内霊場の札所がいくつもあるので、どうも御府内霊場の札番は単純にルート的な廻りやすさから振ったものではないような気もします。
(札所位置図→第76番蓮華山金剛院様公式Webで新宿余丁町は四ッ谷の上あたり。)
そんなこともあって、この霊場の順打ち(逆打ち)はすこぶる時間がかかるものとなります。
-------------------------


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 札所碑
沼袋周辺は細い路地が多いですが、その北の新青梅街道から江古田の森公園にかけては比較的ゆったりとした街区となります。
東福寺は江古田の森公園の南側に、広めの山内を構えています。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 参道
山門は切妻屋根銅板葺で寺号扁額を掲げ、左右に築地をまわしています。
山門右手には御府内霊場の札所碑。
山門をくぐった右手は幼稚園で、平日は園児の声で賑やかです。
参道左手の山手は墓地で、その山裾に手前から庚申塔、大蔵院不動尊、徳川将軍御膳所跡の碑、鐘楼と並びます。


【写真 上(左)】 大蔵院不動尊と鐘楼
【写真 下(右)】 興教大師像と御膳所跡碑
大蔵院不動尊は青山鳳閣寺配下大蔵院ゆかりの尊像で、もとは現・江古田二丁目に御座し耳や眼の病に霊験あらたかな不動尊として多数の信者を集めたといいます。
大蔵院不動尊の上方に鐘楼、その手前には新義真言宗寺院らしく興教大師のお像が御座します。
そのよこの徳川将軍御膳所跡碑の前から本堂に向かって階段をのぼります。
間口の広い堂々たる参道階段で、その途中右手に大師堂があります。


【写真 上(左)】 参道階段
【写真 下(右)】 大師堂
大師堂は宝形造銅板葺きの整った堂容で向拝には弘法大師の扁額が掲げられ、さすがに札所第2番、弘法大師霊場の趣きゆたかです。
弘法大師霊場の巡拝では当然こちらも参拝することになります。


【写真 上(左)】 修行大師像
【写真 下(右)】 本堂
のぼり切った正面が本堂で、向かって右手前には修行大師像が御座します。。
入母屋造本瓦葺流れ向拝のスケール感あふれるつくりで、向拝見上げに山号扁額を置いています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝扁額
山内掲示には不動堂は「成田不動尊写」とあり、境外佛堂として江原町観音堂が記されていますが、不動堂の所在はわかりませんでした。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
主印は不動明王のお種子「カン/カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)、揮毫は「不動明王」「弘法大師」で札所印と寺院印が捺されています。
〔 豊島八十八ヶ所第2番の御朱印 〕
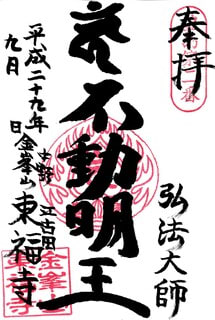
豊島八十八ヶ所も第2番です。主印、揮毫はおなじですが札所印が異なります。
■ 第3番 金剛山 悲願寺 多聞院(たもんいん)
世田谷区北烏山4-10-1
真言宗豊山派
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第44番、江戸八十八ヶ所霊場第3番
授与所:庫裡
御府内八十八ヶ所の札所のうちには、府内(都心部)から郊外に移転したケースがいくつかあって、こちらものひとつです。
場所は世田谷区北烏山。
ここは都心部から移転した二十六もの寺院が集中し「烏山寺町」という大規模な寺町を形成しています。
手元にさるお寺様からいただいた『烏山寺町』という冊子があるので、こちらを参考に沿革を辿ってみます。

『烏山北町』
烏山寺町のおいたちは大正12年の関東大震災を直接の契機としますが、すでに明治21年には「東京市区改正条例」により都心部寺院・墓地等の共葬墓地・郊外への移転方針が決定していました。
共葬墓地への移転は順調に進み青山、雑司ヶ谷、染井、谷中、亀戸などは早い時期にすでに飽和状態になりました。
このため郊外の多摩共葬墓地の整備が進められ、大正12年春より共用開始しています。
同年9月の関東大震災は、この都心から郊外への寺院・墓地移転の流れを一気に加速しました。
練馬の寺町には浅草田島町から11箇寺、足立区伊興には元浅草・下谷・本所から、築地の西本願寺別院および塔頭55箇寺は杉並区和泉、仙川、調布そして烏山に移転しました。
烏山へは築地・浅草をはじめ、下谷、麻布、三田、品川などから寺院が移転しています。
当時の烏山は民家はほとんどなく、畑や桑圓が広がる農村地帯だったといいます。
移転した26箇寺は、真宗13、日蓮宗4、法華宗3、浄土宗4、真言宗1、臨済宗1と、真宗・日蓮宗・法華宗寺院が過半を占め、御朱印エリアのイメージはあまり強くはないものの、複数の寺院で御朱印・御首題を授与され、なかでももっとも御朱印がいただきやすいのが御府内八十八箇所の札所である多聞院です。
(→ 東京都世田谷区の札所と御朱印 (前編)をご参照。)
「烏山寺町」によると、多聞院は元和元年(1615年)新宿角筈村に創建。
開山は述譽法印、開基は角筈村名主・渡邉與(小)兵衛(法名天雪舊満)と伝わり、大塚(音羽)護国寺の末でした。
昭和20年5月の戦火で堂宇を焼失して現在地に移転、昭和29年末には本堂・庫裡が完成しています。
『新編武蔵風土記稿』には「新義真言宗、江戸大塚護國寺末金剛山慈願寺ト号ス 開山述誉ハ寛永元年(1624年)五月五日寂ス 開基ハ村内名主傳右衛門先祖與兵衛ニテ 法名天雪舊満ト云 明暦四年(1658年)六月十日死ス 本尊地蔵ヲ安ス」とあります。
御府内八十八ヶ所霊場3番札所、玉川八十八ヶ所霊場44番札所となっています。
玉川八十八ヶ所霊場の前身である四郡多摩川八十八所は江戸期の開創と伝わりますが、昭和48年に玉川八十八ヶ所として再編しているので、そのときに札所となったとみられます。
世田谷区内の弘法大師霊場は玉川八十八ヶ所がメインで、多聞寺は世田谷区内唯一の御府内霊場札所です。
山内に「天竺渡来石彫涅槃図」があり、これは奈良・壺坂寺(南法華寺)よりの寄贈。
説明碑によると多聞院先々代中興教荘和尚は壺坂寺住職として在職時の昭和36年に日本で最初の養護盲老人ホーム「慈母園」を開設されました。
(壺坂寺は眼病に霊験で有名)
壺坂寺は長年の救ライ活動に対して、インド政府より大観音石像の寄贈を受け、これが発展して昭和61年壺坂寺に大仏伝図(涅槃図)レリーフが建立され、そのゆかりの図が多聞院に寄贈されたのでは。
壺坂寺(南法華寺)は大宝三年(703年)創建の真言宗系の古刹で、元正天皇の祈願寺となっています。
承和十四年(847年)には長谷寺とともに定額寺に列せらたという名刹で、多聞院先々代教荘和尚が壺坂寺住職として在職されていたとなると、多聞院はかなりの寺格ではないでしょうか。
また、ふるくから壺坂寺と関係をもっていた事も想像されます。
壺坂寺は西国三十三所第6番札所ですから、そのゆかりで御府内霊場札所に列したのかもしれません。
-------------------------


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 参道
烏山寺町は一部路地的な街区もありますが、たいていは広い道路に面して車でのアクセスは楽です。
当山も広めの駐車場がありますが、お盆やお彼岸などの参拝はさけた方がベターかと思います。


【写真 上(左)】 観世音菩薩
【写真 下(右)】 延命地蔵尊


【写真 上(左)】 観世音菩薩
【写真 下(右)】 不動明王
山門入口は門柱。ここから正面の本堂に向かって参道が伸びています。
木々は少なめで開放的な山内。
参道まわりには、不動明王、地蔵尊、観世音菩薩などが御座します。


【写真 上(左)】 仏足石
【写真 下(右)】 レリーフ
精緻な仕上がりの仏足石と、上記の「天竺渡来石彫涅槃図」レリーフが見どころです。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
向拝上に山号扁額を置いています。
堂前に修行大師像は御座されず、弘法大師は本堂内御座と思われます。
墓域には天保八年(1837年)の大飢饉の犠牲者を供養する「五百六十八人無縁墓」、明治詩壇の重鎮・本田種竹の墓、館林藩の尊皇攘夷の士・大久保鼎の墓があります。
御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受しました。
ふたつのメジャー霊場を兼務され、手なれたご対応です。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
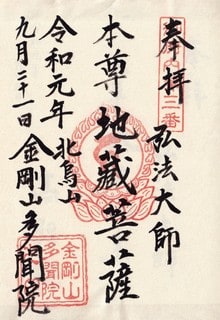

【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
主印は地蔵菩薩のお種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)、揮毫は「本尊 地蔵菩薩」「弘法大師」で札所印と寺院印が捺されています。
〔 玉川八十八ヶ所霊場第44番の御朱印 〕
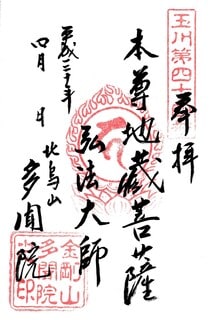
主印、揮毫はおなじですが札所印が異なります。
以下、Vol.-2へつづきます。
【 BGM 】
■ 夢の大地 - Kalafina
■ 桜 - 中村舞子
■ 栞 - 天野月 feat.YURiCa/花たん
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-22
Vol.-21からのつづきです。
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第67番 摩尼珠山 宝光院 真福寺
(しんぷくじ)
公式Web
港区愛宕1-3-8
真言宗智山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第67番、江戸薬師如来霊場三十二ヶ所(第23番)、江戸地蔵菩薩霊場三十六ヶ所(第23番/一言地蔵尊)、江戸西方三十三観音霊場第4番(真福寺内長久寺)、弁財天百社参り第7番(真福寺本道)、弁財天百社参り第8番(真福寺弁天堂)、大東京百観音霊場 特番4
第67番は愛宕の真福寺です。
第67番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに真福寺となっており、第67番札所は御府内霊場開創当初から愛宕の真福寺であったとみられます。
公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
真福寺は、天正十九年(1591年)照海上人が鐵砲洲に小庵を営み、慶長十年(1605年)徳川家康公より愛宕下に土地を賜り開創されました。
新義真言宗江戸四箇寺のひとつで、智積院の触頭でした。
御本尊は弘法大師御作の薬師如来像で、浅野幸長は等身の薬師如来を造立し、弘法大師御作の薬師如来像をその胎内に安置したとも伝わります。
江戸時代は「愛宕のお薬師さん」として庶民に親しまれ、毎月8日のご縁日には門前市を成す賑わいをみせたそうです。
明治初頭の神仏分離の波は乗り越えたものの、大正の大震災で焼失。
昭和6年現堂宇を再建、平成7年に近代的な『真福寺・愛宕東洋ビル』として再生されています。
現在も、真言宗智山派総本山・智積院の東京別院として智山教化を担われています。
山内には勝軍地蔵尊銅像があります。
この勝軍地蔵尊は廃寺となった圓福寺ゆかりの尊像と伝わります。
圓福寺は江戸時代、御府内霊場第19番の札所であった可能性があります。
詳細は第19番青蓮寺で記していますが、圓福寺は真福寺同様、新義真言宗江戸四箇寺のひとつでもあるので、要旨を抜粋して再掲します。
江戸期の真言宗には「江戸四箇寺触頭」という制度があり、これにより本末関係が精緻に整えられていました。
『新義真言宗触頭江戸四箇寺成立年次考』(宇高良哲氏/PDF)によると、発足当初の「江戸四箇寺触頭」はつぎの4箇寺です。
・知足院(江戸白銀町)
→ 関連資料
・真福寺(愛宕下)
・円(圓)福寺(愛宕下)
・弥勒寺(本所)
智積院公式Webには「貞享4年(1687)七月に知足院が将軍家の祈祷寺を理由に免除され、代わりに根生院が任じられます。以後、明治までは変化はありません(円福寺は明治二年に廃仏毀釈により廃寺)。」とあるので、貞享四年(1687年)以降は真福寺(67)、圓福寺(19)、弥勒寺(46)、根生院(35)の四箇寺体制となっています。
( )内は御府内霊場の札番で、これをみても御府内霊場が真言宗の名刹をおおむねカバーしていたことがわかります。
また、『宝瞳寺文書解題』(国文学研究資料館/PDF)にも「江戸四箇寺触頭」の役割が詳細に記されています。
圓福寺は「江戸四箇寺触頭」を勤められ、御府内にいくつもの末寺をもつ御府内有数の名刹でした。
これほどの名刹がどうして明治の廃仏毀釈でいともあっさり(?)と廃絶してしまったのでしょうか。
(実際、触頭4箇寺のうち他の3箇寺は現存しています。)
どうにも気になったので、まずはここから調べてみました。
真福寺の勝軍地蔵尊の説明書には以下のとおりあります。
「この勝軍地蔵菩薩は、天平十年(738年)行基が近江信楽遊行の砌、造顕したもので、同地に安置され、霊験あらたかなり。天正十年(1582年)徳川家康、本能寺の変の難を逃れんがため伊賀越に際し、信楽の土豪多羅尾氏、当勝軍地蔵を献上、沙門神証これを護持し、三河に帰還するをえたり。爾来、家康の帰依厚し。慶長八年(1603年)家康、征夷大将軍に栄進するにより、江戸に愛宕神社を創建し、同社の本地仏として勧請、神証を別当の円福寺第一世とせり。明治の廃仏毀釈で円福寺は廃寺、尊像は真福寺に移されたが、大正十二年 (1923年)関東大震災で焼失、昭和九年(1934年)弘法大師一千百年御遠忌記念として、霊験を不朽にせんがため、銅製で造顕せり。」
一方、愛宕神社の公式Webには配祀として将軍地蔵尊が明記され、愛宕権現(神社)にとって将軍(勝軍)地蔵尊がいかに重要な尊格であるかがわかります。
以上から、圓福寺は愛宕権現の別当の色彩がすこぶる濃厚だったとみられます。
この点は、全国の愛宕神社の総本社とされる愛宕神社(京都市右京区嵯峨愛宕町)と、その別当・白雲寺との関係とよく似ています。
中世~江戸期の愛宕権現社の多くは、本殿に愛宕大権現の本地仏である勝軍地蔵、奥の院に愛宕山の天狗の太郎坊が祀られたといいます。
神仏習合のもと修験道の道場として栄えたこともあり、別当の勢力はたいへん強かったとみられます。
この強大な立場が明治の廃仏毀釈で裏目に出て、愛宕権現の別当・圓福寺は存続の危機に見舞われたのでは。
実際、京都の愛宕神社総本社の別当・白雲寺は廃仏毀釈で廃絶となっています。
総本社の別当・白雲寺が廃絶となった以上、東都の愛宕権現の別当・圓福寺も、たとえ「江戸四箇寺触頭」の格式があったとしても廃絶を遁れられなかったのでは?
ちなみに『寺社書上』の圓福寺の項には「従是愛宕山上之分」として以下のとおりあります。
□「(圓福寺)従是愛宕山上之分」(諸佛のみ抜粋引用)
-------------------------
【史料】
■ 『寺社書上 [53] 愛宕下寺社書上』(国立国会図書館)
愛宕大権現御神● 秘像
御前立 勝軍地蔵尊
脇立 不動明王 毘沙門天
本地堂 脇坊金剛院持
朝日愛染明王
太郎坊北之方
唐●地蔵尊 勝軍地蔵尊 地蔵尊 石地蔵尊
女坂
勝軍地蔵尊
男坂上り口
役行者堂
-------------------------
これをみると江戸期の愛宕権現が諸佛に満ち、神仏習合していたことがよくわかります。
本地堂の別当は金剛院(圓福寺地内末寺)とあるので、愛宕権現全体の別当が圓福寺、本地堂の別当が金剛院という二重構造だったのかもしれません。
なお、『江戸名所図会』の愛宕社總門の絵図をみると、男坂の右手に本地堂、左手に別当(おそらく圓福寺)がみえ、本地・別当系の諸堂は坂下にあったことがわかります。
ここから「出世の石段」を登って参拝する愛宕権現は海抜26mという都内随一の高みにあり、ここからの見晴らしと桜花のすばらしさは御府内有数と称えられ、ほおずき市や羽子板市も賑わいをみせて江戸の図絵類に描かれています。
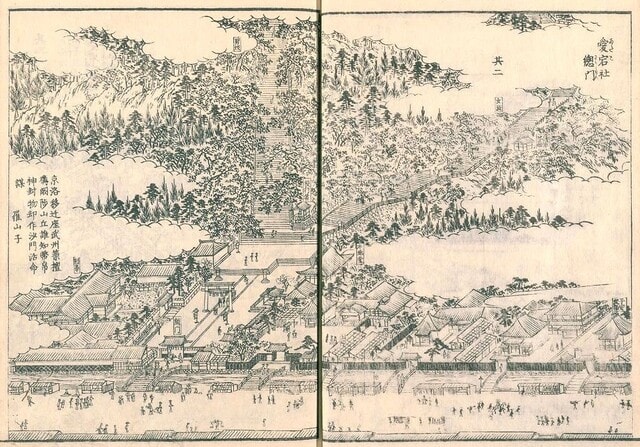
■『江戸名所図会』 7巻 (須原屋茂兵衛[ほか])/愛宕社總門
(国立国会図書館インターネット公開(保護期間満了)より転載 → 出所 )
~ 伊勢へ七度 熊野へ三度 芝の愛宕へ月まいり ~ (愛宕神社御由緒書より)


【写真 上(左)】 愛宕神社社頭
【写真 下(右)】 出世の石段

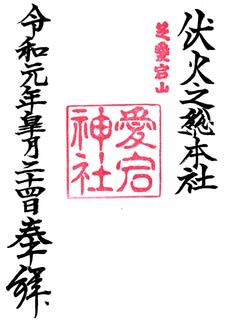
【写真 上(左)】 愛宕神社拝殿
【写真 下(右)】 愛宕神社の御朱印
真福寺勝軍地蔵尊の説明文のとおり、圓福寺が廃寺となったとき、御本尊の(勝軍)地蔵菩薩は愛宕の真福寺に遷られました。
このとき真福寺はすでに御府内霊場第67番の札所だったので、重番を避けるため御府内霊場第19番は浅草の清光院に承継されたとみられます。
江戸時代の真福寺と圓福寺の関係はよくわかりませんが、真福寺は智積院の触頭としての性格、圓福寺は愛宕権現別当としての性格が強く、それぞれ棲み分けしていたのではないでしょうか。
いずれにしても、真言宗「江戸四箇寺触頭」のうち2箇寺までが愛宕に位置しており、この地が江戸の真言宗にとって特別な地であったことがうかがえます。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
六十七番
あたご下
摩尼珠山 宝持院 真福寺
院家智積院方
本尊:薬師如来 弘法大師 興教大師
■ 『寺社書上 [53] 愛宕下寺社書上 全』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.71』
愛宕下
山城国三寶院末 新義真言宗
摩尼珠山宝光院真福寺
天正十九年下総国匝瑳郡谷辺村真福寺住層照海上人開山 常陸●●と由緒(略)鉄砲洲に草庵を結び●● 慶長十年●付寺地拝領仕 同十五年●●●● 仰付候
開山 照海上人 元和二年卒
常憲院様御代●●朱印頂戴仕候 御文云写応之通
本堂
本尊 薬師如来木立像(縁起書あり)
前立薬師座像 日光月光木立像 四天王、十二神 大黒天
弘法大師木座像 興教大師木座像
不動明王 両童子
十一面観音 一言地蔵
聖天 辨財天 賓頭尊
稲荷社
地中 玉藏院
地中 長久院
本尊 観音木立像
真養院
本尊 庚申
■ 『江戸名所図会 7巻 [15]』(国立国会図書館)
摩尼珠山 真福寺
櫻川の西岸に傍びてあり 新義の真言宗にして江戸四個寺の一員 智積院の触頭なり 当寺本尊薬師如来の霊像ハ 弘法大師の作なり 慶長の頃甲州の領主浅野長政当寺中興照海上人をして自 らの等身に薬師佛の像を手刻せしめ 件の霊像をハ其胎中に籠●るといへり 毎月八日ハ縁日にして参詣多し
■ 『芝區誌』(デジタル版 港区のあゆみ)
眞福寺 愛宕町一丁目八番地
新義眞言宗智山派に属し、摩尼珠山と号する。江戸時代には本宗派四役寺の随一であり、總本山智山派の觸頭として派内の公務を處辨する樞要な宗冶機関であった。今尚同本山の東京別院として同派の宗務所が置いてある。天正十九年僧照海鐵砲洲に一小庵を営み、慶長十年此地に本寺を建立した。本尊は浅野幸長等身の薬師如来である。大正大震火災の為め炎上したので、昭和六年現堂宇を再建した。境内には勝軍地蔵の銅像がある。御府内第六十七番の札所である。
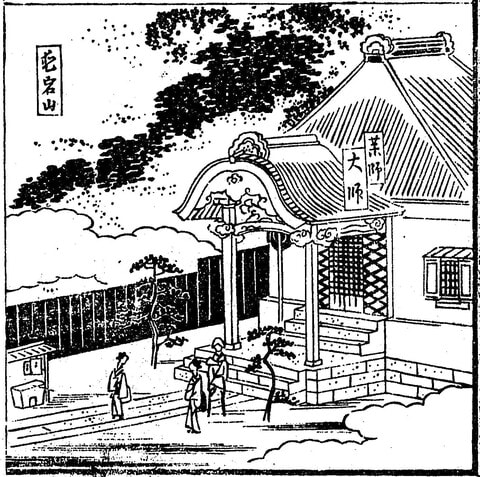
「真福寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』芝愛宕下絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
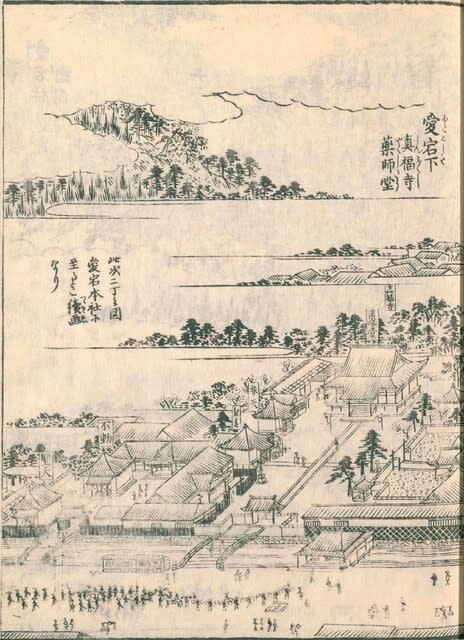
「愛宕下 真福寺薬師堂」/原典:松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[3],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836] .国立国会図書館DC(保護期間満了)

「名所江戸百景 愛宕下藪小路」/原典:江戸百景 絵師:広重出版者:魚栄 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------


【写真 上(左)】 愛宕神社車道(女坂)入口と真福寺
【写真 下(右)】 外観-1
最寄りはメトロ「虎ノ門ヒルズ」駅で徒歩約3分。
都営三田線「御成門」駅やメトロ銀座線「虎ノ門」駅からも歩けます。
周辺はハイグレードなオフィスやホテルが建ち並ぶ都心の一等地です。

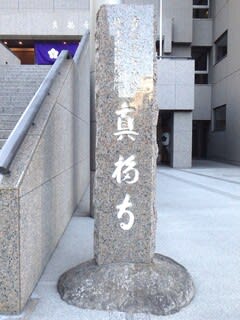
【写真 上(左)】 外観-2
【写真 下(右)】 寺号標
すぐ右隣は愛宕神社の車道(女坂)入口で、真福寺が愛宕権現のすぐ隣にあったことがわかります。
7階建程度の瀟洒なビルですが、ビル前に寺号標があり、そこから登る階段のうえには向拝が見えるのですぐに寺院とわかります。


【写真 上(左)】 参道階段
【写真 下(右)】 向拝-1

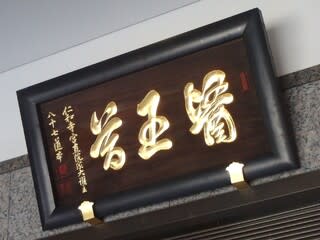
【写真 上(左)】 向拝-2
【写真 下(右)】 扁額
向拝上に巡らされた紫色の向拝幕には真言宗智山派宗紋の「桔梗紋」が染め抜かれています。


【写真 上(左)】 堂内
【写真 下(右)】 御真言
向拝正面に御本尊・薬師如来が御座される開放的な堂内です。
向拝幕の後ろに「醫王尊」の扁額が掲げられています。
御縁日には五色幕も掲げられ、より華々しい雰囲気となります。
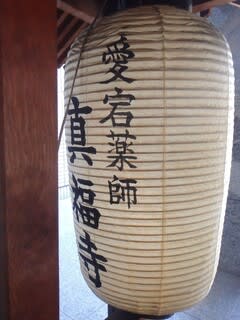

【写真 上(左)】 寺号提灯
【写真 下(右)】 1階寺務所前
本堂下向かって左手に回り込むと、上記の旧・圓福寺から遷られた勝軍地蔵尊が御座します。
一帯は緑濃く、都心のオアシスとなっています。


【写真 上(左)】 真福寺外構と勝軍地蔵尊
【写真 下(右)】 勝軍地蔵尊
御朱印は1階の寺務所にて拝受しました。
寺務所はまさにオフィスですが、ご対応は事務的ではなくとてもご親切です。
なお、勝軍地蔵尊の御朱印は不授与とのことでした。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
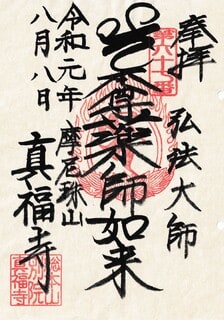
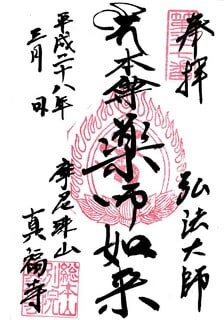
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に薬師如来のお種子「バイ」「本尊薬師如来」「弘法大師」の揮毫と「バイ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「第六十七番」の札所印。
左に山号寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
智山派総本山の東京別院だけあって、さすがに安定感のある御朱印です。
■ 第68番 大栄山 金剛神院 永代寺
(えいたいじ)
江東区富岡1-15-1
高野山真言宗
御本尊:歓喜天尊
札所本尊:歓喜天尊
司元別当:富岡八幡宮(永代島八幡社)
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第68番、江戸六地蔵6番目、大東京百観音霊場第37番
第68番は深川富岡の永代寺です。
第68番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに永代寺となっており、第68番札所は御府内霊場開創当初から深川富岡の永代寺であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
永代寺は、寛永四年(1627年)ないし同五年長盛上人によって永代島に遍照院と号して創建され、富岡八幡宮(永代島八幡社)の別当をつとめました。
永代島とは現在の門前仲町周辺で、中世以降の海退、埋め立てなどによって隅田川河口域に形成された六万坪強にもおよぶ砂州をいいます。
寛永四年(1627年)ないし同五年の夏、開山・長盛上人が弘法大師の夢告を受け、高野山の碩学等の僧が永代島に参集して一夏九旬の間法要を催し、弘法大師の御影堂を建立したといいます。
現地の略縁起によると長盛上人は菅原道真公の末裔で、夢のお告げにより八幡大菩薩を携えて江戸に下向とあるので、寛永四年(1627年)西国でお大師さまの夢告を受け、翌五年(1628年)東国・永代島に下向されて永代寺開山に至ったのかもしれません。
なお、夢告を受けたのは周光阿闍梨とする史料もあり、 『御府内八十八ケ所道しるべ』にも「開山 周光阿闍梨 寛文年中」とあります。
一方、富岡八幡宮公式Webの御由緒には「富岡八幡宮は寛永4年(1627年)、当時永代島と呼ばれていた現在地に御神託により創建されました。」とあり、長盛上人が富岡八幡宮およびその別当・永代寺を開創されたとみるのが通説のようです。
※詳細は → こちら(永代寺略縁起(『寺社書上』))
ただし、『江戸名所図会』には富岡八幡宮の草祀はさらにふるく、源三位頼政公(1104-1180年)が当社八幡宮の神像を尊信し、千葉家および足利将軍尊氏公、鎌倉公方・足利基氏、関東管領・上杉家、太田道灌等の崇敬殊に厚かったとあります。
「今当社より十二町ばかり東の方 砂村の海浜に元八幡宮と称する宮居あり」とあるので、当初は砂村に御鎮座かもしれません。
「砂村の元八幡宮」とは、おそらく江東区南砂の富賀岡八幡宮をさすと思われます。
『新編武蔵風土記稿』の (砂村新田村)八幡社(富賀岡八幡宮)の項には「村ノ鎮守トス 土人云 当社地ハ富岡八幡宮ヲ始テ勧請セシ地ニテ 寛永(1624-1644年)ノ始今ノ深川ノ地ニ引移セシヨリ 彼舊地ナレハトテ 寛文五年(1665年)八幡ヲ勧請セシカハ元八幡ト唱ヘ 今ニ永代寺持ナリ サレト同寺ニテハ寛文ノ勧請ノコトノミニテ元地タリシコトハ傳ヘサレト イマ深川八幡ノ神体僧形八幡ハ弘法大師ノ作ニテ 寛永ノ始マテ郡中立石川端等ノ内ニ鎮座アリシヲ 同十年伊奈半十郎ノ臣興津角左衛門入道玄理寄附セシヨシ旧記アレハ 土人ノ説ノ如ク始此地ニ移シ祀リ 後ニ今ノ深川ノ社地草創シテ 再ヒ移セシ其舊地ナリヘシ」という意味深な記述があります。
これによると、富岡八幡宮がはじめて勧請されたのは砂村の元八幡宮(富賀岡八幡宮)で、寛永(1624-1644年)のはじめ頃にいまの深川の地に御遷座。
深川八幡の僧形の御神体は弘法大師の御作で、寛永のはじめ頃まで郡中立石川端(立石川端(いまの葛飾区東立石))等の内に御鎮座を、寛永十年(1633年)伊奈半十郎の臣・興津角左衛門入道玄理が寄附したとも。
このように富岡八幡宮の創祀沿革には諸説ありますが、ともかくも寛永五年(1628年)には深川の地に御鎮座され、別当に永代寺が就いたのは確かなようです。
『江戸名所図会』には、大和國生駒山の開基寶山師が正保三年(1646年)永代寺周光阿闍梨の法弟となり 寛文四年(1664年)の頃霊夢を感得し宮社を落成され、以降ますます栄えたとあります。
たしかに、生駒山寶山寺(生駒聖天)の公式Webには、「伊勢に生まれ、江戸永代寺に入った宝山湛海律師(一六二九~一七一六)は歓喜天に対する修法に優れ、江戸の大火で焼失した永代寺八幡宮の復興では思わぬ所から金や資材が集まる祈祷の効験を発揮、人々を驚かせた。」とあり、永代寺との浅からぬ所縁を伝えています。
また、永代寺山内にはその旨を示す石碑も建っています。
※詳細は → こちら(寶山寺開祖行業記(『寺社書上』))
現在の永代寺の御本尊が歓喜天尊であるのも、このような所縁によるものかもしれません。
永代寺は関東五ヵ寺同等の寺格を賜り、有章院殿(徳川家継公)、有徳院殿(吉宗公)が参詣され、将軍家の祈祷も修されました。
『寺社書上』の永代寺の項には本坊のほか10院(多聞院、功徳院、吉祥院、般若院、明王院、長壽院、大勝院、海岸院、支王院、東光院)の支院が記載され、密教の一大拠点を形成していたことがわかります。
四隅の鎮守として蛭子宮(艮隅)、荒神宮(巽隅)、摩利支天宮(坤隅)、大勝金剛宮(乾隅)というすこぶる強力な尊格を奉安。
永代島はもともと低平な新開地。
河東屈指の勝地(神仏が御座されるにふさわしい霊地)と成すにはこのような強力な布陣による結界が必要だったのでしょうか。
このうち大勝金剛尊は金剛峯楼閣瑜伽瑜祇経(瑜祇経)を儀軌とする歴とした密教尊格ですが、大日如来、愛染明王、金剛菩薩などの特徴を備えられ、仏頂とも菩薩とも明王ともいわれるナゾの多い尊格で、東日本での奉安例は少ないとみられ、こちらに奉安されたのは何らかの意味合いがあったのかも。
永代寺は富岡八幡宮とともに多くの参詣者を集め、ことに毎年三月二十一日から二十八日までは弘法大師の御影供が催され、「山開き」と称して庭園も開放されてたいへんな賑わいをみせたそうです。
なお、『御府内八十八ケ所道しるべ』には以下のとおりあります。
「本尊阿弥陀如来 本社富ヶ岡八幡宮 弘法大師」
本地垂迹説では八幡神の本地佛として阿弥陀如来奉安の例が多く、八幡宮別当・永代寺の御本尊が阿弥陀如来であったのはこの例に沿ったものかもしれません。
(ただし『寺社書上』には永代寺御本尊の阿弥陀如来は夢告により感得との記載があるので、この例には当たらないかも。)
宝永三年(1706年)、深川の地蔵坊正元が発願し江戸市中から広く寄進者を得て、江戸の出入口6箇所に丈六の地蔵菩薩坐像を造立した「江戸六地蔵」。
永代寺は第6番の札所で地蔵尊像は享保五年(1720年)に千葉街道(諸説あり)の守護佛として造立安置されました。
以降、江戸六地蔵の札所としても参詣者を集めましたが、明治初頭の廃仏毀釈の波を受けてかこちらの地蔵尊像は現存しません。
しかし、「江戸六地蔵」第6番のポジションはいまも保たれ、「江戸六地蔵」の巡拝では永代寺の参詣は欠かせないものとされて御朱印も授与されています。
永代寺、というか支院・吉祥院を語るとき外せないのが深川不動尊(成田山東京別院 深川不動堂)との関係です。
深川不動堂公式Webには、「元禄十六年(1703年)に(成田不動尊の)第一回目の出開帳が富岡八幡宮の別当寺である永代寺で行われました。(略)以来出開帳はたびたび行われ、大勢の江戸っ子が押し寄せ大いに賑わったと伝えられております。(略)明治元年(1868年)に神仏分離令とそれにもとづく廃仏運動のなかで(略)旧来しばしば出開帳を行った特縁の地である現在地に、不動明王御分霊が正式に遷座されたのであります。『深川不動堂』の名のもとに堂宇が完成したのは、それから13年後の明治十四年(1881年)のことでした。」とあります。
「出開帳を行った特縁の地」は、永代寺支院の吉祥院とみられています。
広大な寺地を有した永代寺の旧地には、現在、吉祥院が継いだ永代寺(高野山真言宗)と深川不動堂(真言宗智山派)が存在しています。
富岡八幡宮の別当・永代寺は将軍家の尊崇も受けた名刹でしたが、明治初頭の神仏分離の際に一旦は廃寺となりました。
しかし支院・吉祥院の住僧覚阿坊は伽藍の取り壊し忍びがたく、永代寺法類の湯島円満寺の附属となし、これまで般若院付であった大師堂も吉祥院付とし、永代寺本坊代々の墓守と定めて存置を願い出てついに許可され、吉祥院が永代寺の名跡を継ぐこととなりました。
明治29年には吉祥院を改めて永代寺と号し、円満寺末から仁和寺直末となったといいます。(「猫のあしあと」様より)
八幡神との神仏習合色強い阿弥陀如来は御本尊として迎えにくいため、本坊および吉祥院で奉安され、従前から所縁のある歓喜天尊を御本尊とされたのでは。
永代寺再興にあたっては、当然御府内霊場札所の承継も意図されたはず。
再興時のうごきからみると、江戸時代の御府内霊場第68番札所(永代寺)の巡拝者は、すくなくとも本坊の阿弥陀如来、本社の富ヶ岡八幡宮、般若院の弘法大師堂を拝していたのではないでしょうか。
江戸時代の名刹が明治初頭の神仏分離で廃寺となり、支院・支坊がその名跡を継いだ例は永代寺のほかにもいくつかみられます。
たとえば王子神社および王子稲荷神社の別当を務め、徳川将軍家の御膳所にもなった名刹、禅夷山 金輪寺は神仏分離令もあって廃寺となりましたが、支坊(塔頭)の藤本坊が金輪寺の名跡を継いで再興しています。
富岡八幡宮別当としての永代寺の沿革は、下記の『寺社書上』を丹念に読み込んでいけば、新たなファクトも出てくるのかも知れませんが、筆者の拙い技量では到底かないません。
興味のある方はトライしてみてください↓(と、逃げる・・・(笑))
■ 『寺社書上 [96] 深川寺社書上 二 分冊ノ一/永代島八幡社』(国立国会図書館)
■ 『寺社書上 [96] 深川寺社書上 二 分冊ノ二/永代島八幡社』(国立国会図書館)
永代寺には複雑な縁起来歴が伝わり、深掘りすればまだまだ史料がみつかりそうですが、とりあえずこのくらいにしておきます。
それにしても、永代島八幡社(富岡八幡宮)と永代寺にかかわる『寺社書上』の書き様をみると、先人の記録に対する意思が伝わってきます。
どんな些末な事柄でも、書き逃すことなく何百年でも残そうという執念のようなものが感じられます。
このような貴重な史料がWebで閲覧できるとは、すごい時代になったものです。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
六十八番
深川仲町八幡社 門前町あり
大滎山 金剛神院 永代寺
御宝末 古義
本尊:阿弥陀如来 本社富ヶ岡八幡宮 弘法大師
開山 周光阿闍梨寛文年中
■ 『寺社書上 [98] 深川寺社書上 三 分冊ノ一』(国立国会図書館)
永代寺
別当大滎山金剛神院永代寺 称号開闢以来自坊建立将来
右別当称号之儀 寛永四年(1627年)開山以来遍照院と唱来●●
右開山長盛
本尊 阿弥陀如来木佛座像
脇士 大勢至菩薩 正観世音菩薩
八幡大菩薩 弘法大師 互相 影像
真言宗八大祖師像
大聖歓喜天 秘蔵 周光中興之弟子寶山持念し天像に●御座候
〔寺寶霊佛霊像書画幅物〕
阿彌陀三尊来迎之像
五輪種子塔●●金泥 弘法大師筆
蝋石大日如来座像
僧形八幡神影
■ 『寺社書上 [99] 深川寺社書上 三 分冊ノ二』(国立国会図書館)
【寺中幷境内に隅し鎮守堂守院号】
●多聞院
本尊 不動明王木佛座像 二童子木佛立像
金比羅権現神像
歓喜天 二軀 秘蔵ニ御座候
弘法大師木佛座像
●功徳院
本尊 不動明王木佛立像 顧行上人作
前立 同尊木佛立像 二童子木佛立像
弘法大師木佛座像
愛染明王木佛座像
稲魔法王
●吉祥院
本尊 毘沙門天木佛立像
脇士 吉祥天 善膩師童子木佛立像
大日如来木佛座像
歓喜天 秘蔵天像
十一面観音木佛立像
●般若院
右本尊次第之儀不●知
如意輪観音銅佛座像
地蔵菩薩木佛立像
弘法大師木佛座像
●明王院
本尊 千手観音木佛座像 千手観音木佛座像弘法大師作腹蔵ニ御座候
百観音 阿弥陀千躰佛 十一面観音木佛立像 阿弥陀如来木佛座像 不動明王木佛立像 地蔵大士石佛座像 焔魔法王木佛座像
●長壽院
本尊 辨財天女木佛立像 弘法大師作
脇士 毘沙門天木佛立像 運慶作 大黒天 伝教大師作 幷眷属十五童子
弘法大師木佛座像
●大勝院
本尊 大勝金剛木佛座像
●海岸院
本尊 大荒神木佛立像
●支王院
本尊 摩利支天木躰立像
●東光院
神躰 蛭子太神●木躰座像
同前立 木躰座像
同相殿 立像木躰
●正元稲荷社
本地佛 十一面観音木佛立像
■ 『江戸名所図会 7巻 [15]』(国立国会図書館)
富岡八幡宮
深川永代島にあり 別当は真言宗にして大栄山金剛神院永代寺と号す 江戸名所記に寛永五年の夏弘法大師の霊示あるにより 高野山の両門主碩学其外東国一●の●僧此永代嶋に集合し一夏九旬の間法彼あり 別に弘法大師の御影堂を建て真言三密の秘さくを講す(略)
本社 祭神 應神天皇(神影ハ菅神(菅原道真公)作) 相殿 右天照大神宮、左八幡大明神 三座
相傳 往古源三位頼政当社八幡宮の神像を尊信す 其後千葉家及び足利将軍尊氏公 鎌倉の公方基氏 又管領上杉等の家々に伝へ 太田道灌崇敬ことに厚かりしか 道灌没するののちハ 神像の所在も定かならさりしに 寛永年間(1624-1644年)長盛法印霊示によりて感得す 今当社より十二町ばかり東の方 砂村の海濱に元八幡宮と称する宮居あり 当社の旧地といふ 依此地に当社を創建すといへとも いまだ華構の飾におよハす 唯茅茨の営みをなすのみ 然るに大和国生駒山の開基宝山師 正保三年(1646年)永代寺周光阿闍梨の法弟となり 寛文四年(1664年)の頃霊夢を感じ宮社を経営す 日あらすして落成し結構備ハる 志しありしより以降 神光日々に新たにして河東第一の宮居となれり
当社四隅鎮守 艮隅 蛭子宮 巽隅 荒神宮 坤隅 摩利支天宮 乾隅 大勝金剛宮
■ 『新編武蔵風土記稿 巻之25』(国立国会図書館)
(砂村新田村)八幡社(富賀岡八幡宮)
村ノ鎮守トス 土人云 当社地ハ富岡八幡宮ヲ始テ勧請セシ地ニテ 寛永(1624-1644年)ノ始今ノ深川ノ地ニ引移セシヨリ 彼舊地ナレハトテ、寛文五年(1665年)八幡ヲ勧請セシカハ元八幡ト唱ヘ 今ニ永代寺持ナリ サレト同寺ニテハ寛文ノ勧請ノコトノミニテ元地タリシコトハ傳ヘサレト イマ深川八幡ノ神体僧形八幡ハ弘法大師ノ作ニテ 寛永ノ始マテ郡中立石川端等ノ内ニ鎮座アリシヲ 同十年伊奈半十郎ノ臣興津角左衛門入道玄理寄附セシヨシ旧記アレハ 土人ノ説ノ如ク始此地ニ移シ祀リ 後ニ今ノ深川ノ社地草創シテ 再ヒ移セシ其舊地ナリヘシ

「永代寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』深川絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
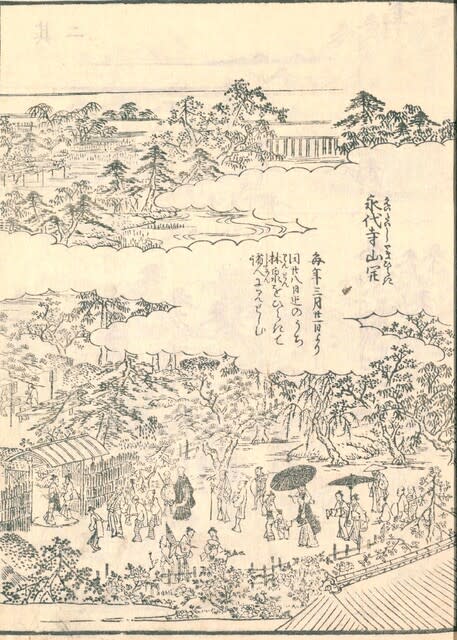
「永代寺山開」/原典:松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[18],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836].国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
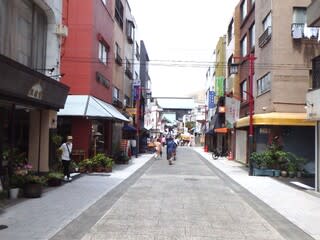

【写真 上(左)】 仲見世
【写真 下(右)】 仲見世の提灯
最寄りはメトロ東西線・都営大江戸線「門前仲町」駅。
東西線千葉寄りの1番出口が至近です。
駅を出るといきなり仲見世で、周囲はすでに門前町の趣。


【写真 上(左)】 永代寺門前から不動堂
【写真 下(右)】 外観-1
ここから右手おくの正面が深川不動尊で、そちら方向に歩いてすぐ右手。
間口はさほどではないもののさすがに名刹、本堂上に楼閣を設えて独特のオーラを放っています。


【写真 上(左)】 外観-2
【写真 下(右)】 門柱の寺号標


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 花手水
切妻屋根銅板葺の山門柱に寺号標。その手前に御府内霊場の札所標。
正面が本堂。
入母屋造桟瓦葺一部楼閣付きで、桁行三間の大がかりな向拝を配し、紫色の向拝幕が華やか。堂前は常に線香の煙がなびいています。


【写真 上(左)】 向拝-1
【写真 下(右)】 向拝-2
向拝小壁中央に寺号扁額、向かって右手には奉納額が掲げられ、向拝柱には札所板も。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 奉納額
本堂向かって左手には子育・取持地蔵尊のお堂。こちらも広く信仰を集めているようです。


【写真 上(左)】 地蔵堂
【写真 下(右)】 地蔵堂扁額
参拝の折は堂内にあげていただけます。
ほの暗い堂内には歓喜天尊霊場特有の厳粛な空気が流れ、物見遊山で訪れる場ではないと思います。
御朱印は堂内にて拝受しました。
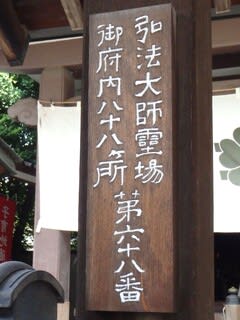

【写真 上(左)】 御府内霊場札所板
【写真 下(右)】 深川不動堂
現地掲示の旧配置図によると、永代寺本堂は現在の深川公園のグラウンドあたりで、永代寺跡の石碑が建っています。

■ 永代寺跡の石碑
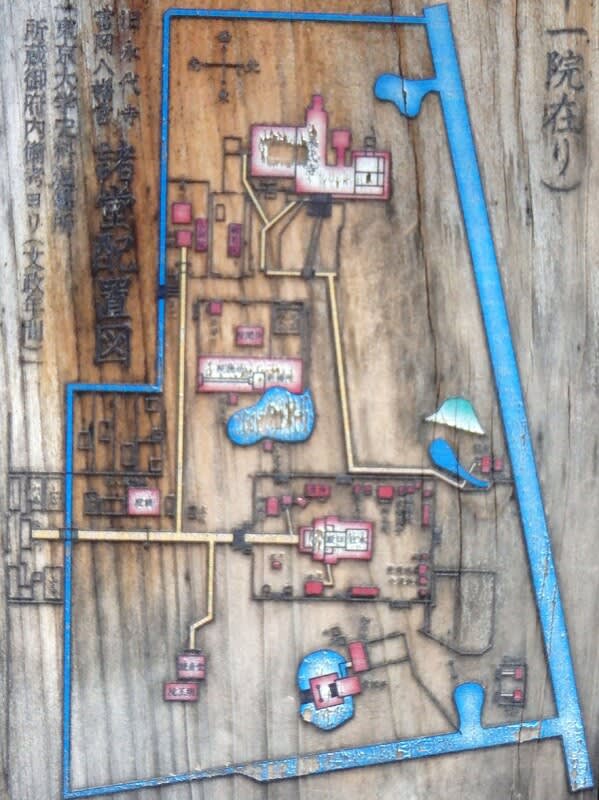
■ 旧配置図
〔 御府内霊場の御朱印 〕
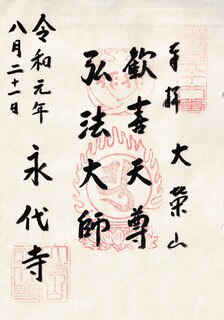

【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「歓喜天尊」「弘法大師」の揮毫、歓喜天尊のお種子「ギャク」の御寶印(巾着)と弘法大師のお種子「ユ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。右に「御府内第六十八番」の札所印。
左に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
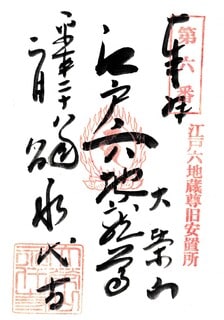
■ 江戸六地蔵の御朱印
■ 第69番 龍臥山 明王寺 宝生院
(ほうしょういん)
港区三田4-1-29
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第69番、江戸六地蔵6番目、御府内二十八不動霊場第22番
第69番はふたたび三田に戻って宝生院です。
第69番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに寶生院となっており、第69番札所は御府内霊場開創当初から三田寺町の宝生院であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
宝生院は慶長十六年(1611年)いまの八丁堀に創建し、寛永十二年(1635年)現在地(三田寺町)に移ったといいます。
中興開山は法印重昌(寶永四年(1707年)寂)。
御本尊は大日如来。
本堂内に弘法大師木座像、興教大師木座像、三尊阿弥陀如来木佛立像を奉安と伝わります。
不動堂には海中出現と伝わる(波切)不動尊を奉安。
御前立の不動尊木立像は興教大師の御作ともいいます。
相殿に奉安の地蔵尊石佛立像は弘法大師が伊豆にて彫刻された尊像といい、「伊豆石最初之尊像」とも伝わります。
辨財天像も弘法大師所縁の尊像と伝わります。
『ルートガイド』によると、明治8年境内に青山学院の前身となる寺子屋式の学校が開設されたそうです。
また、江戸末期から明治中期の名力士・陣幕久五郎の菩提寺とも伝わり、山内には大関昇進と横綱昇進の記念碑が建っています。
宝生院は史料が少なく、この程度しか掘り下げられませんでした。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
六十九番
芝三田寺町
龍臥山 明王寺 宝生院
愛宕圓福寺末 新義
本尊:金剛界大日如来 弘法大師 興教大師
■ 『寺社書上 [13] 三田寺社書上 参』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.110』
三田寺町
愛宕圓福寺末 新義真言宗
龍臥山寶生院明王寺
開闢起立之年代 開山開基等●●分不申候
慶長十六年(1611年)八町堀に寺地拝領仕
寛永十二年(1635年)右寺召上げ当所(三田寺町)に替地拝領仕候
中興開山 法印重昌 寶永四年(1707年)寂
本堂
本尊 大日如来木座像
弘法大師木座像
興教大師同前(木座像)
三尊阿弥陀如来木佛立像
不動堂
不動尊金佛立像 海中出現 前立不動尊木立像 興教大師作ト云
相殿
地蔵尊石佛立像 宗祖弘法大師豆州住●之砌 ●●伊豆山石切開此尊像彫刻●●申仕候 右伊豆石最初之尊像也ト申傳
毘沙門天木立像 辨財天木座像
辨財天 宗祖弘法大師江ノ島ニ於テ護摩修行之砌 右護摩之灰ヲ以テ作之萩原伊左衛門ト申者夢想感得之尊像ト申傳
宇賀神木古像
■ 『芝區誌』(デジタル版 港区のあゆみ)
寳生院 三田北寺町十三番地
新義眞言宗愛宕圓福寺派で、龍臥山明王寺と号する。慶長十六年(1611年)今の八丁堀に創建し、寛永十二年(1635年)此地に移った。開山不詳。寺内に波切不動がある。御府内第六十九番札所に該当する。
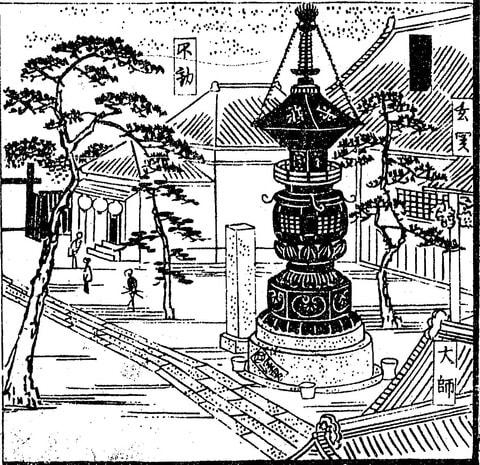
「宝生院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』芝高輪辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは都営三田線「三田」駅で徒歩約10分。
国道1号に面していますが、ビルではなく本堂は単層、庫裡は二層です。
街路からやや引き込んだ門柱に院号標。
山内は意外に広く、すっきりとしています。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 院号標
山内向かって右に土蔵造りの建物、左手に院号扁額を掲げた建物があります。
扁額を掲げた建物が本堂、土蔵が収蔵庫のようにもみえますが、土蔵造りの建物が本堂です。


【写真 上(左)】 本堂と庫裡(手前)
【写真 下(右)】 本堂
本堂はおそらく寄棟造桟瓦葺流れ向拝。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に梵字付きの蟇股を置いています。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 扁額
向拝扉がうすく開けられ、御本尊・大日如来の御像は確認できました。
『ルートガイド』によると本堂内には御本尊大日如来、弘法大師像、興教大師像を奉安されているようです。


【写真 上(左)】 弘法大師碑
【写真 下(右)】 陣幕の記念碑
上記の陣幕の記念碑は山内右手に、弘法大師碑とともにありました。
御朱印は本堂向かって左の庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
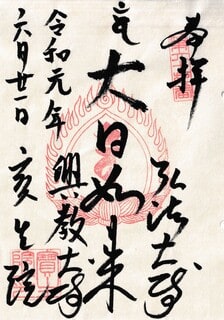
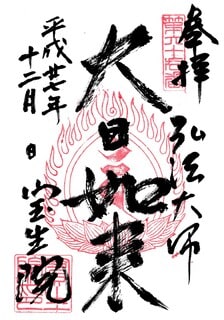
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に金剛界大日如来のお種子「バン」「大日如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫、「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。右に「第六十九番」の札所印。
左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-23)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ Miss You - 今井美樹
■ Roka - 遊佐未森
■ One Reason - milet
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第67番 摩尼珠山 宝光院 真福寺
(しんぷくじ)
公式Web
港区愛宕1-3-8
真言宗智山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第67番、江戸薬師如来霊場三十二ヶ所(第23番)、江戸地蔵菩薩霊場三十六ヶ所(第23番/一言地蔵尊)、江戸西方三十三観音霊場第4番(真福寺内長久寺)、弁財天百社参り第7番(真福寺本道)、弁財天百社参り第8番(真福寺弁天堂)、大東京百観音霊場 特番4
第67番は愛宕の真福寺です。
第67番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに真福寺となっており、第67番札所は御府内霊場開創当初から愛宕の真福寺であったとみられます。
公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
真福寺は、天正十九年(1591年)照海上人が鐵砲洲に小庵を営み、慶長十年(1605年)徳川家康公より愛宕下に土地を賜り開創されました。
新義真言宗江戸四箇寺のひとつで、智積院の触頭でした。
御本尊は弘法大師御作の薬師如来像で、浅野幸長は等身の薬師如来を造立し、弘法大師御作の薬師如来像をその胎内に安置したとも伝わります。
江戸時代は「愛宕のお薬師さん」として庶民に親しまれ、毎月8日のご縁日には門前市を成す賑わいをみせたそうです。
明治初頭の神仏分離の波は乗り越えたものの、大正の大震災で焼失。
昭和6年現堂宇を再建、平成7年に近代的な『真福寺・愛宕東洋ビル』として再生されています。
現在も、真言宗智山派総本山・智積院の東京別院として智山教化を担われています。
山内には勝軍地蔵尊銅像があります。
この勝軍地蔵尊は廃寺となった圓福寺ゆかりの尊像と伝わります。
圓福寺は江戸時代、御府内霊場第19番の札所であった可能性があります。
詳細は第19番青蓮寺で記していますが、圓福寺は真福寺同様、新義真言宗江戸四箇寺のひとつでもあるので、要旨を抜粋して再掲します。
江戸期の真言宗には「江戸四箇寺触頭」という制度があり、これにより本末関係が精緻に整えられていました。
『新義真言宗触頭江戸四箇寺成立年次考』(宇高良哲氏/PDF)によると、発足当初の「江戸四箇寺触頭」はつぎの4箇寺です。
・知足院(江戸白銀町)
→ 関連資料
・真福寺(愛宕下)
・円(圓)福寺(愛宕下)
・弥勒寺(本所)
智積院公式Webには「貞享4年(1687)七月に知足院が将軍家の祈祷寺を理由に免除され、代わりに根生院が任じられます。以後、明治までは変化はありません(円福寺は明治二年に廃仏毀釈により廃寺)。」とあるので、貞享四年(1687年)以降は真福寺(67)、圓福寺(19)、弥勒寺(46)、根生院(35)の四箇寺体制となっています。
( )内は御府内霊場の札番で、これをみても御府内霊場が真言宗の名刹をおおむねカバーしていたことがわかります。
また、『宝瞳寺文書解題』(国文学研究資料館/PDF)にも「江戸四箇寺触頭」の役割が詳細に記されています。
圓福寺は「江戸四箇寺触頭」を勤められ、御府内にいくつもの末寺をもつ御府内有数の名刹でした。
これほどの名刹がどうして明治の廃仏毀釈でいともあっさり(?)と廃絶してしまったのでしょうか。
(実際、触頭4箇寺のうち他の3箇寺は現存しています。)
どうにも気になったので、まずはここから調べてみました。
真福寺の勝軍地蔵尊の説明書には以下のとおりあります。
「この勝軍地蔵菩薩は、天平十年(738年)行基が近江信楽遊行の砌、造顕したもので、同地に安置され、霊験あらたかなり。天正十年(1582年)徳川家康、本能寺の変の難を逃れんがため伊賀越に際し、信楽の土豪多羅尾氏、当勝軍地蔵を献上、沙門神証これを護持し、三河に帰還するをえたり。爾来、家康の帰依厚し。慶長八年(1603年)家康、征夷大将軍に栄進するにより、江戸に愛宕神社を創建し、同社の本地仏として勧請、神証を別当の円福寺第一世とせり。明治の廃仏毀釈で円福寺は廃寺、尊像は真福寺に移されたが、大正十二年 (1923年)関東大震災で焼失、昭和九年(1934年)弘法大師一千百年御遠忌記念として、霊験を不朽にせんがため、銅製で造顕せり。」
一方、愛宕神社の公式Webには配祀として将軍地蔵尊が明記され、愛宕権現(神社)にとって将軍(勝軍)地蔵尊がいかに重要な尊格であるかがわかります。
以上から、圓福寺は愛宕権現の別当の色彩がすこぶる濃厚だったとみられます。
この点は、全国の愛宕神社の総本社とされる愛宕神社(京都市右京区嵯峨愛宕町)と、その別当・白雲寺との関係とよく似ています。
中世~江戸期の愛宕権現社の多くは、本殿に愛宕大権現の本地仏である勝軍地蔵、奥の院に愛宕山の天狗の太郎坊が祀られたといいます。
神仏習合のもと修験道の道場として栄えたこともあり、別当の勢力はたいへん強かったとみられます。
この強大な立場が明治の廃仏毀釈で裏目に出て、愛宕権現の別当・圓福寺は存続の危機に見舞われたのでは。
実際、京都の愛宕神社総本社の別当・白雲寺は廃仏毀釈で廃絶となっています。
総本社の別当・白雲寺が廃絶となった以上、東都の愛宕権現の別当・圓福寺も、たとえ「江戸四箇寺触頭」の格式があったとしても廃絶を遁れられなかったのでは?
ちなみに『寺社書上』の圓福寺の項には「従是愛宕山上之分」として以下のとおりあります。
□「(圓福寺)従是愛宕山上之分」(諸佛のみ抜粋引用)
-------------------------
【史料】
■ 『寺社書上 [53] 愛宕下寺社書上』(国立国会図書館)
愛宕大権現御神● 秘像
御前立 勝軍地蔵尊
脇立 不動明王 毘沙門天
本地堂 脇坊金剛院持
朝日愛染明王
太郎坊北之方
唐●地蔵尊 勝軍地蔵尊 地蔵尊 石地蔵尊
女坂
勝軍地蔵尊
男坂上り口
役行者堂
-------------------------
これをみると江戸期の愛宕権現が諸佛に満ち、神仏習合していたことがよくわかります。
本地堂の別当は金剛院(圓福寺地内末寺)とあるので、愛宕権現全体の別当が圓福寺、本地堂の別当が金剛院という二重構造だったのかもしれません。
なお、『江戸名所図会』の愛宕社總門の絵図をみると、男坂の右手に本地堂、左手に別当(おそらく圓福寺)がみえ、本地・別当系の諸堂は坂下にあったことがわかります。
ここから「出世の石段」を登って参拝する愛宕権現は海抜26mという都内随一の高みにあり、ここからの見晴らしと桜花のすばらしさは御府内有数と称えられ、ほおずき市や羽子板市も賑わいをみせて江戸の図絵類に描かれています。
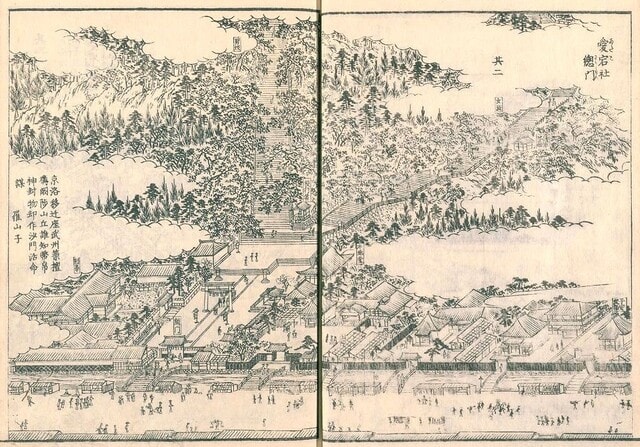
■『江戸名所図会』 7巻 (須原屋茂兵衛[ほか])/愛宕社總門
(国立国会図書館インターネット公開(保護期間満了)より転載 → 出所 )
~ 伊勢へ七度 熊野へ三度 芝の愛宕へ月まいり ~ (愛宕神社御由緒書より)


【写真 上(左)】 愛宕神社社頭
【写真 下(右)】 出世の石段

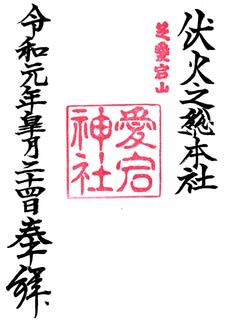
【写真 上(左)】 愛宕神社拝殿
【写真 下(右)】 愛宕神社の御朱印
真福寺勝軍地蔵尊の説明文のとおり、圓福寺が廃寺となったとき、御本尊の(勝軍)地蔵菩薩は愛宕の真福寺に遷られました。
このとき真福寺はすでに御府内霊場第67番の札所だったので、重番を避けるため御府内霊場第19番は浅草の清光院に承継されたとみられます。
江戸時代の真福寺と圓福寺の関係はよくわかりませんが、真福寺は智積院の触頭としての性格、圓福寺は愛宕権現別当としての性格が強く、それぞれ棲み分けしていたのではないでしょうか。
いずれにしても、真言宗「江戸四箇寺触頭」のうち2箇寺までが愛宕に位置しており、この地が江戸の真言宗にとって特別な地であったことがうかがえます。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
六十七番
あたご下
摩尼珠山 宝持院 真福寺
院家智積院方
本尊:薬師如来 弘法大師 興教大師
■ 『寺社書上 [53] 愛宕下寺社書上 全』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.71』
愛宕下
山城国三寶院末 新義真言宗
摩尼珠山宝光院真福寺
天正十九年下総国匝瑳郡谷辺村真福寺住層照海上人開山 常陸●●と由緒(略)鉄砲洲に草庵を結び●● 慶長十年●付寺地拝領仕 同十五年●●●● 仰付候
開山 照海上人 元和二年卒
常憲院様御代●●朱印頂戴仕候 御文云写応之通
本堂
本尊 薬師如来木立像(縁起書あり)
前立薬師座像 日光月光木立像 四天王、十二神 大黒天
弘法大師木座像 興教大師木座像
不動明王 両童子
十一面観音 一言地蔵
聖天 辨財天 賓頭尊
稲荷社
地中 玉藏院
地中 長久院
本尊 観音木立像
真養院
本尊 庚申
■ 『江戸名所図会 7巻 [15]』(国立国会図書館)
摩尼珠山 真福寺
櫻川の西岸に傍びてあり 新義の真言宗にして江戸四個寺の一員 智積院の触頭なり 当寺本尊薬師如来の霊像ハ 弘法大師の作なり 慶長の頃甲州の領主浅野長政当寺中興照海上人をして自 らの等身に薬師佛の像を手刻せしめ 件の霊像をハ其胎中に籠●るといへり 毎月八日ハ縁日にして参詣多し
■ 『芝區誌』(デジタル版 港区のあゆみ)
眞福寺 愛宕町一丁目八番地
新義眞言宗智山派に属し、摩尼珠山と号する。江戸時代には本宗派四役寺の随一であり、總本山智山派の觸頭として派内の公務を處辨する樞要な宗冶機関であった。今尚同本山の東京別院として同派の宗務所が置いてある。天正十九年僧照海鐵砲洲に一小庵を営み、慶長十年此地に本寺を建立した。本尊は浅野幸長等身の薬師如来である。大正大震火災の為め炎上したので、昭和六年現堂宇を再建した。境内には勝軍地蔵の銅像がある。御府内第六十七番の札所である。
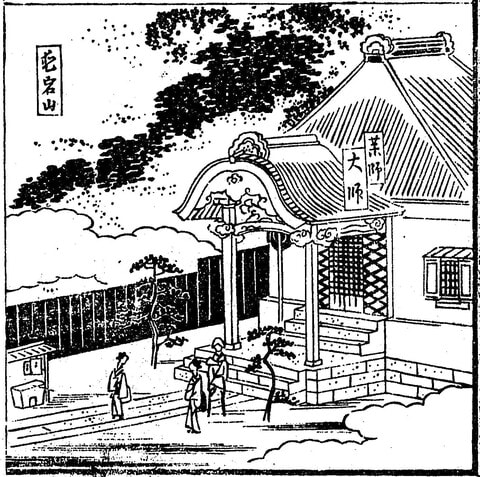
「真福寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』芝愛宕下絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
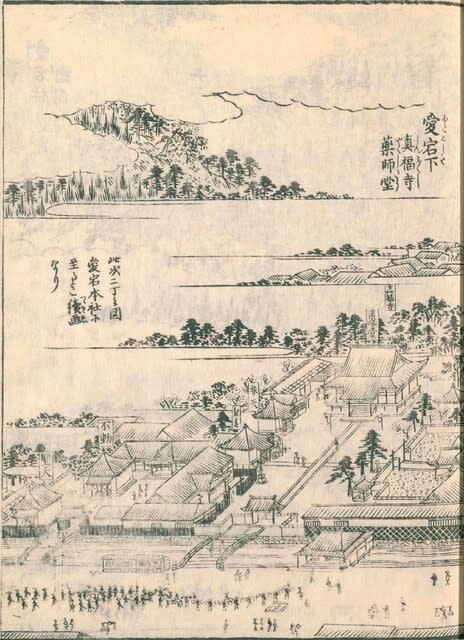
「愛宕下 真福寺薬師堂」/原典:松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[3],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836] .国立国会図書館DC(保護期間満了)

「名所江戸百景 愛宕下藪小路」/原典:江戸百景 絵師:広重出版者:魚栄 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------


【写真 上(左)】 愛宕神社車道(女坂)入口と真福寺
【写真 下(右)】 外観-1
最寄りはメトロ「虎ノ門ヒルズ」駅で徒歩約3分。
都営三田線「御成門」駅やメトロ銀座線「虎ノ門」駅からも歩けます。
周辺はハイグレードなオフィスやホテルが建ち並ぶ都心の一等地です。

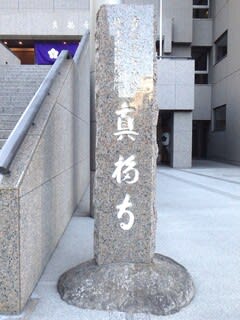
【写真 上(左)】 外観-2
【写真 下(右)】 寺号標
すぐ右隣は愛宕神社の車道(女坂)入口で、真福寺が愛宕権現のすぐ隣にあったことがわかります。
7階建程度の瀟洒なビルですが、ビル前に寺号標があり、そこから登る階段のうえには向拝が見えるのですぐに寺院とわかります。


【写真 上(左)】 参道階段
【写真 下(右)】 向拝-1

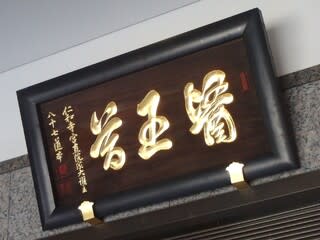
【写真 上(左)】 向拝-2
【写真 下(右)】 扁額
向拝上に巡らされた紫色の向拝幕には真言宗智山派宗紋の「桔梗紋」が染め抜かれています。


【写真 上(左)】 堂内
【写真 下(右)】 御真言
向拝正面に御本尊・薬師如来が御座される開放的な堂内です。
向拝幕の後ろに「醫王尊」の扁額が掲げられています。
御縁日には五色幕も掲げられ、より華々しい雰囲気となります。
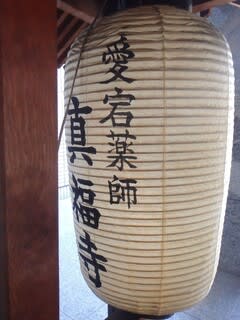

【写真 上(左)】 寺号提灯
【写真 下(右)】 1階寺務所前
本堂下向かって左手に回り込むと、上記の旧・圓福寺から遷られた勝軍地蔵尊が御座します。
一帯は緑濃く、都心のオアシスとなっています。


【写真 上(左)】 真福寺外構と勝軍地蔵尊
【写真 下(右)】 勝軍地蔵尊
御朱印は1階の寺務所にて拝受しました。
寺務所はまさにオフィスですが、ご対応は事務的ではなくとてもご親切です。
なお、勝軍地蔵尊の御朱印は不授与とのことでした。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
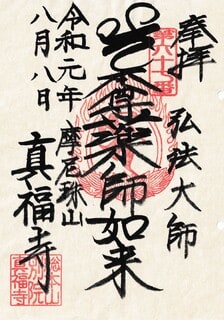
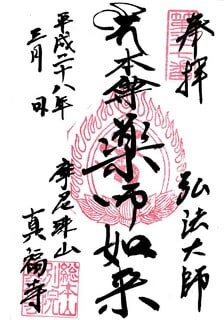
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に薬師如来のお種子「バイ」「本尊薬師如来」「弘法大師」の揮毫と「バイ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「第六十七番」の札所印。
左に山号寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
智山派総本山の東京別院だけあって、さすがに安定感のある御朱印です。
■ 第68番 大栄山 金剛神院 永代寺
(えいたいじ)
江東区富岡1-15-1
高野山真言宗
御本尊:歓喜天尊
札所本尊:歓喜天尊
司元別当:富岡八幡宮(永代島八幡社)
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第68番、江戸六地蔵6番目、大東京百観音霊場第37番
第68番は深川富岡の永代寺です。
第68番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに永代寺となっており、第68番札所は御府内霊場開創当初から深川富岡の永代寺であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
永代寺は、寛永四年(1627年)ないし同五年長盛上人によって永代島に遍照院と号して創建され、富岡八幡宮(永代島八幡社)の別当をつとめました。
永代島とは現在の門前仲町周辺で、中世以降の海退、埋め立てなどによって隅田川河口域に形成された六万坪強にもおよぶ砂州をいいます。
寛永四年(1627年)ないし同五年の夏、開山・長盛上人が弘法大師の夢告を受け、高野山の碩学等の僧が永代島に参集して一夏九旬の間法要を催し、弘法大師の御影堂を建立したといいます。
現地の略縁起によると長盛上人は菅原道真公の末裔で、夢のお告げにより八幡大菩薩を携えて江戸に下向とあるので、寛永四年(1627年)西国でお大師さまの夢告を受け、翌五年(1628年)東国・永代島に下向されて永代寺開山に至ったのかもしれません。
なお、夢告を受けたのは周光阿闍梨とする史料もあり、 『御府内八十八ケ所道しるべ』にも「開山 周光阿闍梨 寛文年中」とあります。
一方、富岡八幡宮公式Webの御由緒には「富岡八幡宮は寛永4年(1627年)、当時永代島と呼ばれていた現在地に御神託により創建されました。」とあり、長盛上人が富岡八幡宮およびその別当・永代寺を開創されたとみるのが通説のようです。
※詳細は → こちら(永代寺略縁起(『寺社書上』))
ただし、『江戸名所図会』には富岡八幡宮の草祀はさらにふるく、源三位頼政公(1104-1180年)が当社八幡宮の神像を尊信し、千葉家および足利将軍尊氏公、鎌倉公方・足利基氏、関東管領・上杉家、太田道灌等の崇敬殊に厚かったとあります。
「今当社より十二町ばかり東の方 砂村の海浜に元八幡宮と称する宮居あり」とあるので、当初は砂村に御鎮座かもしれません。
「砂村の元八幡宮」とは、おそらく江東区南砂の富賀岡八幡宮をさすと思われます。
『新編武蔵風土記稿』の (砂村新田村)八幡社(富賀岡八幡宮)の項には「村ノ鎮守トス 土人云 当社地ハ富岡八幡宮ヲ始テ勧請セシ地ニテ 寛永(1624-1644年)ノ始今ノ深川ノ地ニ引移セシヨリ 彼舊地ナレハトテ 寛文五年(1665年)八幡ヲ勧請セシカハ元八幡ト唱ヘ 今ニ永代寺持ナリ サレト同寺ニテハ寛文ノ勧請ノコトノミニテ元地タリシコトハ傳ヘサレト イマ深川八幡ノ神体僧形八幡ハ弘法大師ノ作ニテ 寛永ノ始マテ郡中立石川端等ノ内ニ鎮座アリシヲ 同十年伊奈半十郎ノ臣興津角左衛門入道玄理寄附セシヨシ旧記アレハ 土人ノ説ノ如ク始此地ニ移シ祀リ 後ニ今ノ深川ノ社地草創シテ 再ヒ移セシ其舊地ナリヘシ」という意味深な記述があります。
これによると、富岡八幡宮がはじめて勧請されたのは砂村の元八幡宮(富賀岡八幡宮)で、寛永(1624-1644年)のはじめ頃にいまの深川の地に御遷座。
深川八幡の僧形の御神体は弘法大師の御作で、寛永のはじめ頃まで郡中立石川端(立石川端(いまの葛飾区東立石))等の内に御鎮座を、寛永十年(1633年)伊奈半十郎の臣・興津角左衛門入道玄理が寄附したとも。
このように富岡八幡宮の創祀沿革には諸説ありますが、ともかくも寛永五年(1628年)には深川の地に御鎮座され、別当に永代寺が就いたのは確かなようです。
『江戸名所図会』には、大和國生駒山の開基寶山師が正保三年(1646年)永代寺周光阿闍梨の法弟となり 寛文四年(1664年)の頃霊夢を感得し宮社を落成され、以降ますます栄えたとあります。
たしかに、生駒山寶山寺(生駒聖天)の公式Webには、「伊勢に生まれ、江戸永代寺に入った宝山湛海律師(一六二九~一七一六)は歓喜天に対する修法に優れ、江戸の大火で焼失した永代寺八幡宮の復興では思わぬ所から金や資材が集まる祈祷の効験を発揮、人々を驚かせた。」とあり、永代寺との浅からぬ所縁を伝えています。
また、永代寺山内にはその旨を示す石碑も建っています。
※詳細は → こちら(寶山寺開祖行業記(『寺社書上』))
現在の永代寺の御本尊が歓喜天尊であるのも、このような所縁によるものかもしれません。
永代寺は関東五ヵ寺同等の寺格を賜り、有章院殿(徳川家継公)、有徳院殿(吉宗公)が参詣され、将軍家の祈祷も修されました。
『寺社書上』の永代寺の項には本坊のほか10院(多聞院、功徳院、吉祥院、般若院、明王院、長壽院、大勝院、海岸院、支王院、東光院)の支院が記載され、密教の一大拠点を形成していたことがわかります。
四隅の鎮守として蛭子宮(艮隅)、荒神宮(巽隅)、摩利支天宮(坤隅)、大勝金剛宮(乾隅)というすこぶる強力な尊格を奉安。
永代島はもともと低平な新開地。
河東屈指の勝地(神仏が御座されるにふさわしい霊地)と成すにはこのような強力な布陣による結界が必要だったのでしょうか。
このうち大勝金剛尊は金剛峯楼閣瑜伽瑜祇経(瑜祇経)を儀軌とする歴とした密教尊格ですが、大日如来、愛染明王、金剛菩薩などの特徴を備えられ、仏頂とも菩薩とも明王ともいわれるナゾの多い尊格で、東日本での奉安例は少ないとみられ、こちらに奉安されたのは何らかの意味合いがあったのかも。
永代寺は富岡八幡宮とともに多くの参詣者を集め、ことに毎年三月二十一日から二十八日までは弘法大師の御影供が催され、「山開き」と称して庭園も開放されてたいへんな賑わいをみせたそうです。
なお、『御府内八十八ケ所道しるべ』には以下のとおりあります。
「本尊阿弥陀如来 本社富ヶ岡八幡宮 弘法大師」
本地垂迹説では八幡神の本地佛として阿弥陀如来奉安の例が多く、八幡宮別当・永代寺の御本尊が阿弥陀如来であったのはこの例に沿ったものかもしれません。
(ただし『寺社書上』には永代寺御本尊の阿弥陀如来は夢告により感得との記載があるので、この例には当たらないかも。)
宝永三年(1706年)、深川の地蔵坊正元が発願し江戸市中から広く寄進者を得て、江戸の出入口6箇所に丈六の地蔵菩薩坐像を造立した「江戸六地蔵」。
永代寺は第6番の札所で地蔵尊像は享保五年(1720年)に千葉街道(諸説あり)の守護佛として造立安置されました。
以降、江戸六地蔵の札所としても参詣者を集めましたが、明治初頭の廃仏毀釈の波を受けてかこちらの地蔵尊像は現存しません。
しかし、「江戸六地蔵」第6番のポジションはいまも保たれ、「江戸六地蔵」の巡拝では永代寺の参詣は欠かせないものとされて御朱印も授与されています。
永代寺、というか支院・吉祥院を語るとき外せないのが深川不動尊(成田山東京別院 深川不動堂)との関係です。
深川不動堂公式Webには、「元禄十六年(1703年)に(成田不動尊の)第一回目の出開帳が富岡八幡宮の別当寺である永代寺で行われました。(略)以来出開帳はたびたび行われ、大勢の江戸っ子が押し寄せ大いに賑わったと伝えられております。(略)明治元年(1868年)に神仏分離令とそれにもとづく廃仏運動のなかで(略)旧来しばしば出開帳を行った特縁の地である現在地に、不動明王御分霊が正式に遷座されたのであります。『深川不動堂』の名のもとに堂宇が完成したのは、それから13年後の明治十四年(1881年)のことでした。」とあります。
「出開帳を行った特縁の地」は、永代寺支院の吉祥院とみられています。
広大な寺地を有した永代寺の旧地には、現在、吉祥院が継いだ永代寺(高野山真言宗)と深川不動堂(真言宗智山派)が存在しています。
富岡八幡宮の別当・永代寺は将軍家の尊崇も受けた名刹でしたが、明治初頭の神仏分離の際に一旦は廃寺となりました。
しかし支院・吉祥院の住僧覚阿坊は伽藍の取り壊し忍びがたく、永代寺法類の湯島円満寺の附属となし、これまで般若院付であった大師堂も吉祥院付とし、永代寺本坊代々の墓守と定めて存置を願い出てついに許可され、吉祥院が永代寺の名跡を継ぐこととなりました。
明治29年には吉祥院を改めて永代寺と号し、円満寺末から仁和寺直末となったといいます。(「猫のあしあと」様より)
八幡神との神仏習合色強い阿弥陀如来は御本尊として迎えにくいため、本坊および吉祥院で奉安され、従前から所縁のある歓喜天尊を御本尊とされたのでは。
永代寺再興にあたっては、当然御府内霊場札所の承継も意図されたはず。
再興時のうごきからみると、江戸時代の御府内霊場第68番札所(永代寺)の巡拝者は、すくなくとも本坊の阿弥陀如来、本社の富ヶ岡八幡宮、般若院の弘法大師堂を拝していたのではないでしょうか。
江戸時代の名刹が明治初頭の神仏分離で廃寺となり、支院・支坊がその名跡を継いだ例は永代寺のほかにもいくつかみられます。
たとえば王子神社および王子稲荷神社の別当を務め、徳川将軍家の御膳所にもなった名刹、禅夷山 金輪寺は神仏分離令もあって廃寺となりましたが、支坊(塔頭)の藤本坊が金輪寺の名跡を継いで再興しています。
富岡八幡宮別当としての永代寺の沿革は、下記の『寺社書上』を丹念に読み込んでいけば、新たなファクトも出てくるのかも知れませんが、筆者の拙い技量では到底かないません。
興味のある方はトライしてみてください↓(と、逃げる・・・(笑))
■ 『寺社書上 [96] 深川寺社書上 二 分冊ノ一/永代島八幡社』(国立国会図書館)
■ 『寺社書上 [96] 深川寺社書上 二 分冊ノ二/永代島八幡社』(国立国会図書館)
永代寺には複雑な縁起来歴が伝わり、深掘りすればまだまだ史料がみつかりそうですが、とりあえずこのくらいにしておきます。
それにしても、永代島八幡社(富岡八幡宮)と永代寺にかかわる『寺社書上』の書き様をみると、先人の記録に対する意思が伝わってきます。
どんな些末な事柄でも、書き逃すことなく何百年でも残そうという執念のようなものが感じられます。
このような貴重な史料がWebで閲覧できるとは、すごい時代になったものです。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
六十八番
深川仲町八幡社 門前町あり
大滎山 金剛神院 永代寺
御宝末 古義
本尊:阿弥陀如来 本社富ヶ岡八幡宮 弘法大師
開山 周光阿闍梨寛文年中
■ 『寺社書上 [98] 深川寺社書上 三 分冊ノ一』(国立国会図書館)
永代寺
別当大滎山金剛神院永代寺 称号開闢以来自坊建立将来
右別当称号之儀 寛永四年(1627年)開山以来遍照院と唱来●●
右開山長盛
本尊 阿弥陀如来木佛座像
脇士 大勢至菩薩 正観世音菩薩
八幡大菩薩 弘法大師 互相 影像
真言宗八大祖師像
大聖歓喜天 秘蔵 周光中興之弟子寶山持念し天像に●御座候
〔寺寶霊佛霊像書画幅物〕
阿彌陀三尊来迎之像
五輪種子塔●●金泥 弘法大師筆
蝋石大日如来座像
僧形八幡神影
■ 『寺社書上 [99] 深川寺社書上 三 分冊ノ二』(国立国会図書館)
【寺中幷境内に隅し鎮守堂守院号】
●多聞院
本尊 不動明王木佛座像 二童子木佛立像
金比羅権現神像
歓喜天 二軀 秘蔵ニ御座候
弘法大師木佛座像
●功徳院
本尊 不動明王木佛立像 顧行上人作
前立 同尊木佛立像 二童子木佛立像
弘法大師木佛座像
愛染明王木佛座像
稲魔法王
●吉祥院
本尊 毘沙門天木佛立像
脇士 吉祥天 善膩師童子木佛立像
大日如来木佛座像
歓喜天 秘蔵天像
十一面観音木佛立像
●般若院
右本尊次第之儀不●知
如意輪観音銅佛座像
地蔵菩薩木佛立像
弘法大師木佛座像
●明王院
本尊 千手観音木佛座像 千手観音木佛座像弘法大師作腹蔵ニ御座候
百観音 阿弥陀千躰佛 十一面観音木佛立像 阿弥陀如来木佛座像 不動明王木佛立像 地蔵大士石佛座像 焔魔法王木佛座像
●長壽院
本尊 辨財天女木佛立像 弘法大師作
脇士 毘沙門天木佛立像 運慶作 大黒天 伝教大師作 幷眷属十五童子
弘法大師木佛座像
●大勝院
本尊 大勝金剛木佛座像
●海岸院
本尊 大荒神木佛立像
●支王院
本尊 摩利支天木躰立像
●東光院
神躰 蛭子太神●木躰座像
同前立 木躰座像
同相殿 立像木躰
●正元稲荷社
本地佛 十一面観音木佛立像
■ 『江戸名所図会 7巻 [15]』(国立国会図書館)
富岡八幡宮
深川永代島にあり 別当は真言宗にして大栄山金剛神院永代寺と号す 江戸名所記に寛永五年の夏弘法大師の霊示あるにより 高野山の両門主碩学其外東国一●の●僧此永代嶋に集合し一夏九旬の間法彼あり 別に弘法大師の御影堂を建て真言三密の秘さくを講す(略)
本社 祭神 應神天皇(神影ハ菅神(菅原道真公)作) 相殿 右天照大神宮、左八幡大明神 三座
相傳 往古源三位頼政当社八幡宮の神像を尊信す 其後千葉家及び足利将軍尊氏公 鎌倉の公方基氏 又管領上杉等の家々に伝へ 太田道灌崇敬ことに厚かりしか 道灌没するののちハ 神像の所在も定かならさりしに 寛永年間(1624-1644年)長盛法印霊示によりて感得す 今当社より十二町ばかり東の方 砂村の海濱に元八幡宮と称する宮居あり 当社の旧地といふ 依此地に当社を創建すといへとも いまだ華構の飾におよハす 唯茅茨の営みをなすのみ 然るに大和国生駒山の開基宝山師 正保三年(1646年)永代寺周光阿闍梨の法弟となり 寛文四年(1664年)の頃霊夢を感じ宮社を経営す 日あらすして落成し結構備ハる 志しありしより以降 神光日々に新たにして河東第一の宮居となれり
当社四隅鎮守 艮隅 蛭子宮 巽隅 荒神宮 坤隅 摩利支天宮 乾隅 大勝金剛宮
■ 『新編武蔵風土記稿 巻之25』(国立国会図書館)
(砂村新田村)八幡社(富賀岡八幡宮)
村ノ鎮守トス 土人云 当社地ハ富岡八幡宮ヲ始テ勧請セシ地ニテ 寛永(1624-1644年)ノ始今ノ深川ノ地ニ引移セシヨリ 彼舊地ナレハトテ、寛文五年(1665年)八幡ヲ勧請セシカハ元八幡ト唱ヘ 今ニ永代寺持ナリ サレト同寺ニテハ寛文ノ勧請ノコトノミニテ元地タリシコトハ傳ヘサレト イマ深川八幡ノ神体僧形八幡ハ弘法大師ノ作ニテ 寛永ノ始マテ郡中立石川端等ノ内ニ鎮座アリシヲ 同十年伊奈半十郎ノ臣興津角左衛門入道玄理寄附セシヨシ旧記アレハ 土人ノ説ノ如ク始此地ニ移シ祀リ 後ニ今ノ深川ノ社地草創シテ 再ヒ移セシ其舊地ナリヘシ

「永代寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』深川絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
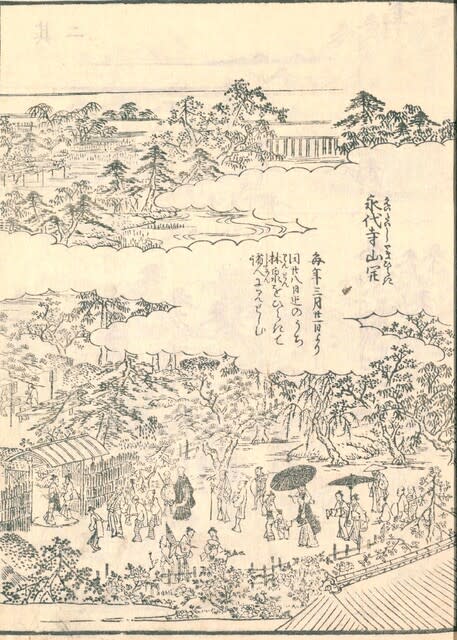
「永代寺山開」/原典:松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[18],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836].国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
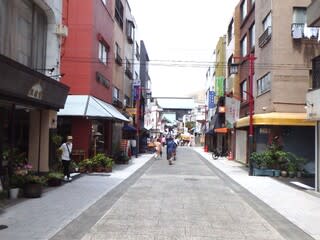

【写真 上(左)】 仲見世
【写真 下(右)】 仲見世の提灯
最寄りはメトロ東西線・都営大江戸線「門前仲町」駅。
東西線千葉寄りの1番出口が至近です。
駅を出るといきなり仲見世で、周囲はすでに門前町の趣。


【写真 上(左)】 永代寺門前から不動堂
【写真 下(右)】 外観-1
ここから右手おくの正面が深川不動尊で、そちら方向に歩いてすぐ右手。
間口はさほどではないもののさすがに名刹、本堂上に楼閣を設えて独特のオーラを放っています。


【写真 上(左)】 外観-2
【写真 下(右)】 門柱の寺号標


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 花手水
切妻屋根銅板葺の山門柱に寺号標。その手前に御府内霊場の札所標。
正面が本堂。
入母屋造桟瓦葺一部楼閣付きで、桁行三間の大がかりな向拝を配し、紫色の向拝幕が華やか。堂前は常に線香の煙がなびいています。


【写真 上(左)】 向拝-1
【写真 下(右)】 向拝-2
向拝小壁中央に寺号扁額、向かって右手には奉納額が掲げられ、向拝柱には札所板も。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 奉納額
本堂向かって左手には子育・取持地蔵尊のお堂。こちらも広く信仰を集めているようです。


【写真 上(左)】 地蔵堂
【写真 下(右)】 地蔵堂扁額
参拝の折は堂内にあげていただけます。
ほの暗い堂内には歓喜天尊霊場特有の厳粛な空気が流れ、物見遊山で訪れる場ではないと思います。
御朱印は堂内にて拝受しました。
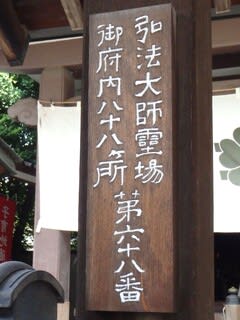

【写真 上(左)】 御府内霊場札所板
【写真 下(右)】 深川不動堂
現地掲示の旧配置図によると、永代寺本堂は現在の深川公園のグラウンドあたりで、永代寺跡の石碑が建っています。

■ 永代寺跡の石碑
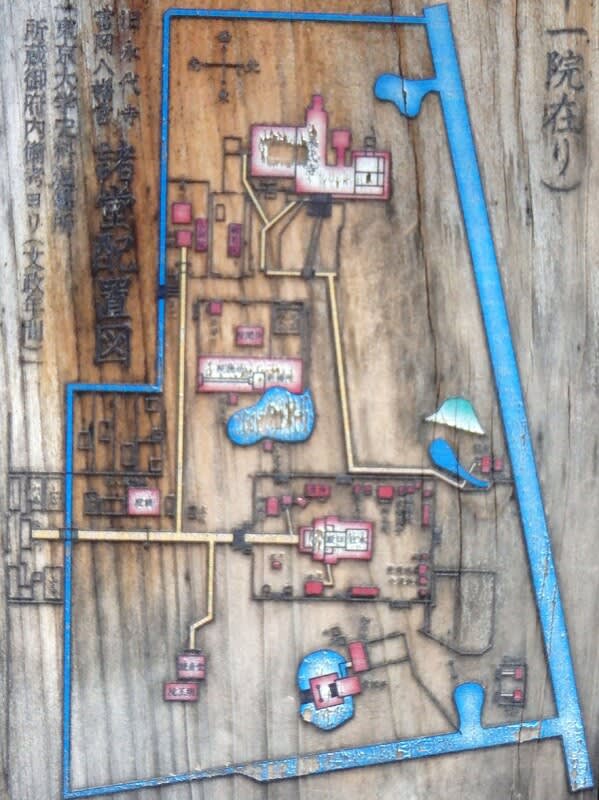
■ 旧配置図
〔 御府内霊場の御朱印 〕
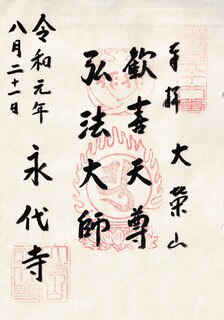

【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「歓喜天尊」「弘法大師」の揮毫、歓喜天尊のお種子「ギャク」の御寶印(巾着)と弘法大師のお種子「ユ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。右に「御府内第六十八番」の札所印。
左に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
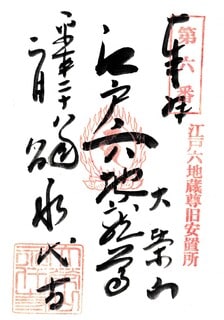
■ 江戸六地蔵の御朱印
■ 第69番 龍臥山 明王寺 宝生院
(ほうしょういん)
港区三田4-1-29
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第69番、江戸六地蔵6番目、御府内二十八不動霊場第22番
第69番はふたたび三田に戻って宝生院です。
第69番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに寶生院となっており、第69番札所は御府内霊場開創当初から三田寺町の宝生院であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
宝生院は慶長十六年(1611年)いまの八丁堀に創建し、寛永十二年(1635年)現在地(三田寺町)に移ったといいます。
中興開山は法印重昌(寶永四年(1707年)寂)。
御本尊は大日如来。
本堂内に弘法大師木座像、興教大師木座像、三尊阿弥陀如来木佛立像を奉安と伝わります。
不動堂には海中出現と伝わる(波切)不動尊を奉安。
御前立の不動尊木立像は興教大師の御作ともいいます。
相殿に奉安の地蔵尊石佛立像は弘法大師が伊豆にて彫刻された尊像といい、「伊豆石最初之尊像」とも伝わります。
辨財天像も弘法大師所縁の尊像と伝わります。
『ルートガイド』によると、明治8年境内に青山学院の前身となる寺子屋式の学校が開設されたそうです。
また、江戸末期から明治中期の名力士・陣幕久五郎の菩提寺とも伝わり、山内には大関昇進と横綱昇進の記念碑が建っています。
宝生院は史料が少なく、この程度しか掘り下げられませんでした。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
六十九番
芝三田寺町
龍臥山 明王寺 宝生院
愛宕圓福寺末 新義
本尊:金剛界大日如来 弘法大師 興教大師
■ 『寺社書上 [13] 三田寺社書上 参』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.110』
三田寺町
愛宕圓福寺末 新義真言宗
龍臥山寶生院明王寺
開闢起立之年代 開山開基等●●分不申候
慶長十六年(1611年)八町堀に寺地拝領仕
寛永十二年(1635年)右寺召上げ当所(三田寺町)に替地拝領仕候
中興開山 法印重昌 寶永四年(1707年)寂
本堂
本尊 大日如来木座像
弘法大師木座像
興教大師同前(木座像)
三尊阿弥陀如来木佛立像
不動堂
不動尊金佛立像 海中出現 前立不動尊木立像 興教大師作ト云
相殿
地蔵尊石佛立像 宗祖弘法大師豆州住●之砌 ●●伊豆山石切開此尊像彫刻●●申仕候 右伊豆石最初之尊像也ト申傳
毘沙門天木立像 辨財天木座像
辨財天 宗祖弘法大師江ノ島ニ於テ護摩修行之砌 右護摩之灰ヲ以テ作之萩原伊左衛門ト申者夢想感得之尊像ト申傳
宇賀神木古像
■ 『芝區誌』(デジタル版 港区のあゆみ)
寳生院 三田北寺町十三番地
新義眞言宗愛宕圓福寺派で、龍臥山明王寺と号する。慶長十六年(1611年)今の八丁堀に創建し、寛永十二年(1635年)此地に移った。開山不詳。寺内に波切不動がある。御府内第六十九番札所に該当する。
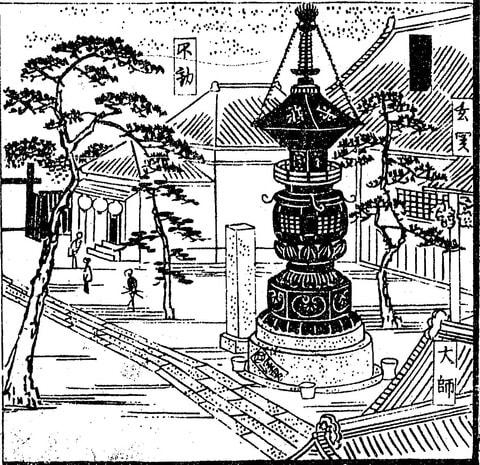
「宝生院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』芝高輪辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは都営三田線「三田」駅で徒歩約10分。
国道1号に面していますが、ビルではなく本堂は単層、庫裡は二層です。
街路からやや引き込んだ門柱に院号標。
山内は意外に広く、すっきりとしています。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 院号標
山内向かって右に土蔵造りの建物、左手に院号扁額を掲げた建物があります。
扁額を掲げた建物が本堂、土蔵が収蔵庫のようにもみえますが、土蔵造りの建物が本堂です。


【写真 上(左)】 本堂と庫裡(手前)
【写真 下(右)】 本堂
本堂はおそらく寄棟造桟瓦葺流れ向拝。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に梵字付きの蟇股を置いています。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 扁額
向拝扉がうすく開けられ、御本尊・大日如来の御像は確認できました。
『ルートガイド』によると本堂内には御本尊大日如来、弘法大師像、興教大師像を奉安されているようです。


【写真 上(左)】 弘法大師碑
【写真 下(右)】 陣幕の記念碑
上記の陣幕の記念碑は山内右手に、弘法大師碑とともにありました。
御朱印は本堂向かって左の庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
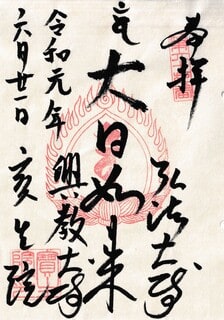
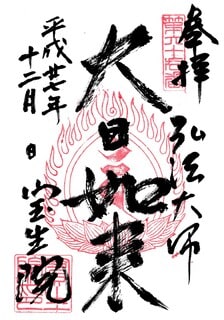
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に金剛界大日如来のお種子「バン」「大日如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫、「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。右に「第六十九番」の札所印。
左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-23)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ Miss You - 今井美樹
■ Roka - 遊佐未森
■ One Reason - milet
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-21
Vol.-20からのつづきです。
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第63番 初音山 東漸寺 観智院
(かんちいん)
公式Web
台東区谷中5-2-4
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第64番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第6番
第63番は谷中の観智院です。
第63番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』では観智院、江戸八十八ヶ所霊場では加納院となっています。
加納院は御府内霊場第64番ですから、どこかの時点で63番と64番の札所が入れ替わった可能性があります。
いずれにしても、谷中の観智院は御府内霊場開創当初からの札所であったとみられます。
公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
観智院は、慶長十六年(1611年)、照譽法印が小(北)寺町に開山、慶安元年(1648年)谷中へ移転したといいます。
慶安元年(1648年)の移転は旧寺地が幕府用地となつたためで、『下谷区史 〔本編〕』によると、神田北寺町での幕府からの賜地、谷中への移転の事由や時期は多寶院(第49番)、自性院(第53番)、長久院(第55番)、明王院(第57番)などと同様とみられますが、寺伝には慶安元年(1648年)に一旦谷中清水坂に遷ったあと、万治年中(1658-1660年)に現在地へ移転とあります。
延宝八年(1680年)、当山12世・宥朝法印が入山され元禄十一年(1698年)に院号を現在の観(觀)智院に改めました。
当初の院号は圓照院。
宥朝法印は「”圓照”は”炎焦”に通ずる」との霊告を受けられて号を改めたといいます。
宥朝法印の入山により寺勢はますます興隆しましたが、公式Webでは当山と檀越関係にあった奥医師・丸山玄棟の外護も大きかったと推察されています。
安永八年(1779年)には不動堂を建立、興教大師作と伝わる不動尊像が安置され、五大明王像を奉安という史料もみられます。
五大明王とは不動明王を中心に降三世明王(東)、軍荼利明王(南)、大威徳明王(西)、金剛夜叉明王(北)と配置される明王像で、霊験ことにあらたかとして広く信仰されます。
元禄十六年(1703年)十一月、大震災につづいて本郷追分、小石川辺から出火した火災は、折からの強風にあおられて江戸の町の大半を焼きつくしました。
谷中の寺院も多くが焼失しますが、観智院は奇跡的に炎禍を遁れたといいます。
観智院の不動尊は興教大師御作と伝わる霊像であること、中興開山・宥朝法印の「火除けの改号」のいわれ、そして大火の炎禍を免れたことなどもあってか、「谷中の火除不動尊」と呼ばれて多くの参詣者を集めたといいます。
文化・文政(1804-1829年)の頃になると、江戸御府内はもちろん近隣からも参詣人が訪れ、門前は市がたつほどの賑わいになったと伝わります。
谷中のメインロードであった「三崎坂」(さんざきざか)に面していたことも大きいのでは。
明治初頭の神仏分離の際には大店の商人をはじめとする町人の檀信徒が23世・真興法印のもとに結集して寺門を支えたといい、御府内霊場札所のポジションも堅持しています。
明治39年、24世・海隆法印が入山、先々代・石本海隆師も堂宇整備に尽力されて大正年間にはふたたび寺容を整えたといいます。
関東大震災では延焼を免れた当山に人々が避難したといい、昭和20年3月の東京大空襲では本堂・庫裡に砲弾を受けたものの大師堂・不動堂は焼失の難を遁れ、いまなお戦前の姿を残すとともに、御本尊・大日如来をはじめすべての仏像、什器もまた焼失を遁れています。
火除不動尊の霊験まことにあらたかというべきでしょうか。
昭和24年初音幼稚園を設置し、いまでも山内は園児の声でにぎやかです。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
六十三番
谷中三崎通り
醫王山 東漸寺 観智院
本所弥勒寺末 新義
本尊:弘法大師
■ 『寺社書上 [111] 谷中寺社書上 三』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.100』
谷中不唱小名
新義真言宗 本所彌勒寺末
醫王山東漸寺観智院
権現様御世慶長十六年(1611年)2月15日、当寺開山照誉法印代 於神田小寺町ニ寺地拝領仕候 大猷院様御世慶安元年(1648年)中、神田小寺町御用地ニ付被召上 谷中ニ代地拝領仕候
開山 照誉法印 卒年月不知
中興開基 宥朝法印 享保六年(1721年)遷化
本堂
本尊 弘法大師座像
不動尊土蔵
不動尊座像 興教大師作
稲荷社
■ 『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)
觀智院(谷中初音町一丁目二三番地)
本所彌勒寺末、醫王山東漸寺と号す。本尊弘法大師。当寺亦慶長十六年(1611年)二月、幕府より神田北寺町に地を賜うて起立し、慶安元年(1648年)同所幕府用地となるや現地に転じた。開山は僧照譽、中興は僧宥朝。(享保六年(1721年)五月二十二日寂)
境内に不動堂がある。
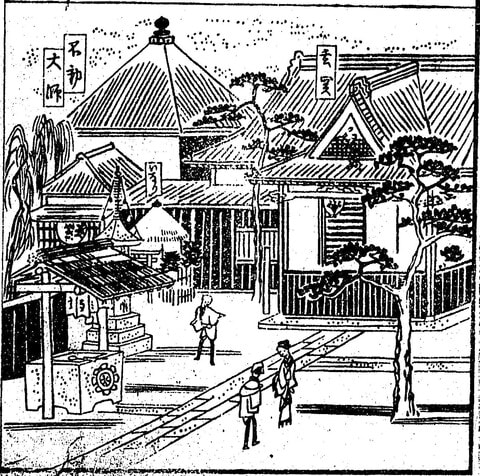
「観智院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)
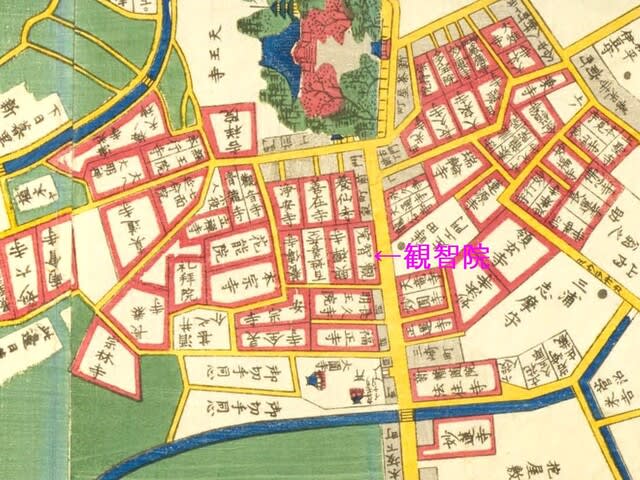
原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
※ 休園日に撮った写真がなぜか見つかりません。見つかったら追加します。
最寄りは東京メトロ千代田線「千駄木」で徒歩約7分ほど。
JR「日暮里」駅からも同じくらいで歩けます。
千駄木から谷中霊園へ向かう三崎坂をほぼ登り切ったところに道に面してあります。
第57番明王院の並びにあり、谷中寺町のほぼ中心部に当たります。


【写真 上(左)】 全景
【写真 下(右)】 本堂
山内のほとんどは幼稚園として使われ、平日の日中はセキュリティ上から閉門されているので、休日の参拝がベターとみられます。
山内入口に初音六地蔵。
昭和58年秋の像立と新しいお像ですが、手篤く供養されて存在感があります。
門柱に院号標があり、おくに本堂は見えますが、平日昼間は園児たちが走り回り幼稚園バスが停まっていたりしてほぼ幼稚園です。
正面の階段上に唐破風の向拝を備えた本堂。
複雑な意匠で見応えがあります。


【写真 上(左)】 不動堂(右)と大師堂(左)
【写真 下(右)】 不動堂の扁額
本堂向かって左手前に不動堂と大師堂があります。
不動堂は宝形造銅板葺で向拝に「火除不動尊」の扁額を掲げています。
大師堂は不動堂の向かって右手に連接してあります。
柱には御府内霊場ではなく、「弘法大師廿一ヶ所六番」の札所板が打ち付けられていました。
お大師さまは、堂内の大ぶりな厨子のなかに御座されています。
御朱印は本堂向かって左手前の庫裡にて拝受しました。
なお、「火除不動尊」の御朱印は授与されていないそうです。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
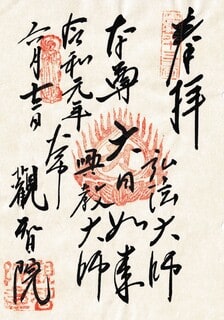
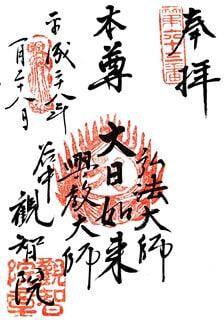
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊大日如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫と胎蔵大日如来のお種子「ア」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「第六十三番」の札所印。左に地蔵尊の御影印、院号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第64番 長谷山 元興寺 加納院
(かのういん)
台東区谷中5-8-5
新義真言宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第63番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第4番
第64番は谷中の加納院。御府内霊場では数すくない、紀州根來寺を総本山とする新義真言宗の寺院です。
第64番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』では加納院、江戸八十八ヶ所霊場では観智院となっています。
観智院は御府内霊場第63番ですから、どこかの時点で63番と64番の札所が入れ替わった可能性があります。
いずれにしても、谷中の加納院は御府内霊場開創当初からの札所であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
加納院は、慶長十六年(1611年)、幕府より神田小(北)寺町に寺地を給せられて尊慶上人が開基、慶安元年(1648年)谷中へ移転したといいます。
慶安元年(1648年)の移転は旧寺地が幕府用地となったためで、『下谷区史 〔本編〕』によると、神田北寺町での幕府からの賜地、谷中への移転の事由や時期は多寶院(第49番)、自性院(第53番)、長久院(第55番)、明王院(第57番)、観智院(第63番)などと同様とみられますが、慶安元年(1648年)に一旦谷中清水坂に遷ったあと、延宝八年(1680年)再び幕府用地となったため現在地へ移転といいます。
加納院は情報が少ないですが、『寺社書上』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考』には、本堂御本尊は阿弥陀如来で両脇侍は正観世音菩薩と勢至菩薩。
御本尊の阿弥陀如来は「(御府内)八十八ヶ所ノ第六十三番」と記されています。
本堂内(『下谷区史』では大師堂内)に弘法大師像、興教大師像を奉安し、御府内霊場札所としての要件は整っていたようです。
聖天堂には大聖歓喜天二躰(秘佛)と本地佛として十一面観世音菩薩を奉安。
相殿に稲荷。阿弥陀如来、弁財天二躰、千手観世音菩薩も安置と伝わります。
『ルートガイド』によると、当山所蔵の「両界曼荼羅版木」は台東区有形文化財に指定されているとのこと。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
六十四番
谷中
長谷山 元興寺 加納院
本所弥勒寺末 新義
本尊:阿弥陀如来 弘法大師 興教大師
■ 『寺社書上 [111] 谷中寺社書上 四』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.102』
谷中不唱小名
新義真言宗 本所彌勒寺末
長谷山元興寺加納院
起立 慶長十六年(1611年)
開基 尊慶 寛永十三年(1636年)寂
権現様御代 神田北寺町ニ寺地拝領仕候 慶安元年(1648年)大猷院様御代 神田北寺町御用ニ付 谷中清水坂ニテ替地拝領仕候 延宝八年(1680年)厳有院様御代御用地ニ付 清水坂地処差上● 只今ハ当所ニ住居仕候
本堂
本尊 阿弥陀如来木座像
八十八ヶ所ノ第六十三番
両脇士 観世音 勢至
弘法大師 興教大師
位牌壇 大日如来
聖天堂
歓喜天二躰 秘佛
本地 十一面観音
相殿稲荷 阿弥陀如来 弁財天二躰 千手観世音
■ 『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)
加納院(谷中上三崎北町六番地)
本所彌勒寺末、長谷山元興寺と号す。本尊阿彌陀如来。慶長十六年(1611年)幕府より神田北寺町に寺地を給せられて起立した。開山を尊慶(寛永十三年(1636年)四月六日寂)といふ。慶安元年(1648年)同所が幕府用地となったため谷中清水坂(現谷中清水町)に移り、延寶八年(1680年)同所亦用地となり、現地に転じた。
境内に聖天堂(大聖歡喜天を安置す)及び大師堂(弘法大師像及び興教大師像を安置す)がある。
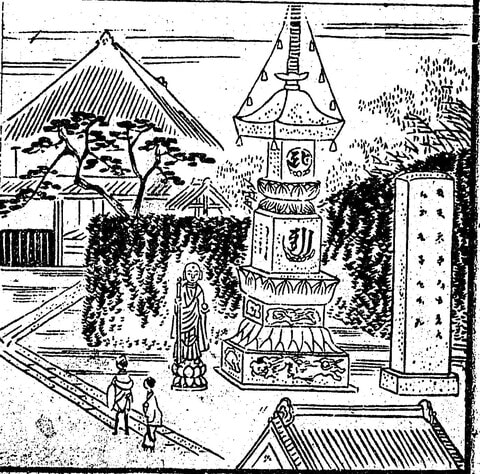
「加納院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)
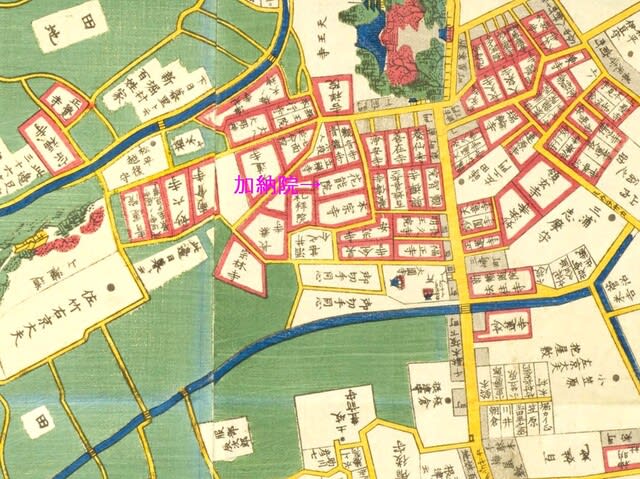
原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはJR「日暮里」駅で徒歩約7分。
東京メトロ千代田線「千駄木」駅からの方が距離的には近いくらいですが、急な登りとなります。
台地上にある「日暮里」駅から歩くとわかりにくいですが、千駄木方面から望むとかなりの高台にあることがわかります。
寺院に囲まれた路地奥の立地ですが、観光スポットの観音寺の築地塀の先にあり、目立つ朱塗り門を構えているので、訪れる人は意外に多いのかもしれません。
位置的には三崎坂から明王院と観智院のあいだの路地を北に入った路地の突き当たりにあります。
この路地まわりはほとんどが寺院で、谷中が都内屈指の寺町であることを実感できます。


【写真 上(左)】 加納院前から望む観音寺の築地塀(左)
【写真 下(右)】 山門
山門は切妻屋根桟瓦葺の朱塗りの薬医門で、脇塀とともにコの字型の空間をつくり出し、どこか城門のようです。
山門前に御府内霊場札所標。
これは御府内霊場(第64番)と御府内二十一ヶ所霊場(第4番)を併記したもので、比較的めずらしいかたちでは。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 山内
緑濃い山内はよく手入れされて心なごみます。
四季折々の花々が咲き誇る花の寺でもあるようです。
本堂は寄棟造桟瓦葺流れ向拝。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの向拝
向拝に扁額はないですが、向拝扉右手に御府内霊場(第64番)と御府内二十一ヶ所霊場(第4番)の札所板が掲げられています。

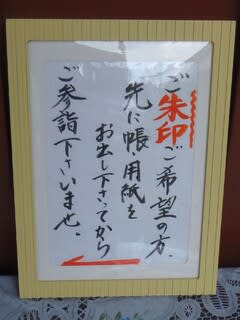
【写真 上(左)】 札所板
【写真 下(右)】 御朱印案内
御朱印は本堂向かって左の庫裡にて拝受しました。
御府内霊場は参拝後の御朱印申告が原則ですが、こちらでは参拝前に御朱印帳を預ける旨の掲示があります。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
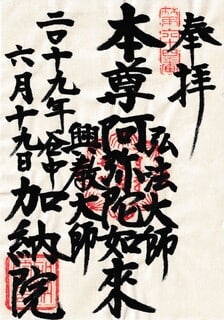
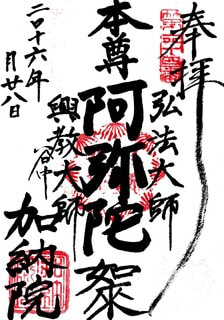
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊阿弥陀如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫とお種子(おそらく阿弥陀如来のお種子・キリーク)の御寶印。
御寶印は八葉をかたちどったもので、胎蔵曼荼羅の中心部・中台八葉院をモチーフとしたものかも。
右に「第六十四番」の札所印。左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
西暦で書かれた奉拝日が個性的です。
■ 第65番 明王山 遍照寺 大聖院
(だいしょういん)
港区三田4-1-27
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第65番
第65番は三田の大聖院。
御府内霊場の後半は、三田の札所が多くなります。
第65番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに大聖院で、三田の大聖院は御府内霊場開創当初からの第65番札所であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
大聖院は、慶長十六年(1611年)数寄屋町に創建ののち八丁堀に移り、寛永十二年(1635年)淀松尾氏等の外護を受けて三田の現在地に移転といいます。
開山は宥専上人、中興開基は法印祐壽と伝わります。
江戸期は愛宕前真福寺末でしたが、明治12年に智山派総本山智積院の直轄末寺となっています。
本堂には、御本尊の大日如来木座像を奉安。六躰の阿弥陀如来木座像と弘法大師木座像、興教大師木座像を安置して御府内霊場札所の体裁を整えていたようです。
護摩堂には不動尊木座像、千手観音木座像、愛染明王木座像、聖天尊真鍮立像を奉安し、鎮守は稲荷社と伝わります。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
六十五番
芝三田寺町
明王山 遍照寺 大聖院
愛宕山真福寺末 新義
本尊:金剛界大日如来 不動明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [13] 三田寺社書上 参』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.92』
三田寺町
愛宕前真福寺末 新義真言宗
明王山大聖院遍照寺
草創之年暦 開山 中興開山 開基 不分明
慶長十六年(1611年)四月数寄屋町 八町堀に替地拝領仕
寛永十二年(1635年)八月八町堀から三田寺町に替地拝領仕
中興開基 法印祐壽 寛永十二年(1635年)
本堂
本尊 大日如来木座像
阿彌陀如来木座像 六躰
弘法大師木座像
興教大師木座像
護摩堂
不動尊木座像 千手観音木座像 愛染明王木座像 聖天尊真鍮立像
鎮守稲荷社
■ 『芝區誌』(デジタル版 港区のあゆみ)
大聖院 三田北寺町二十一番地
初め眞言宗愛宕眞福寺末派で、慶長十六年(1611年)数寄屋町に創建し、後八丁堀に移り、寛永十二年(1635年)淀松尾氏等の外護に依って現在地に堂宇を定めた。開山は宥専上人である。明治十二年六月二日京都総本山智積院直轄末寺となった。御府内第六十五番の札所である。
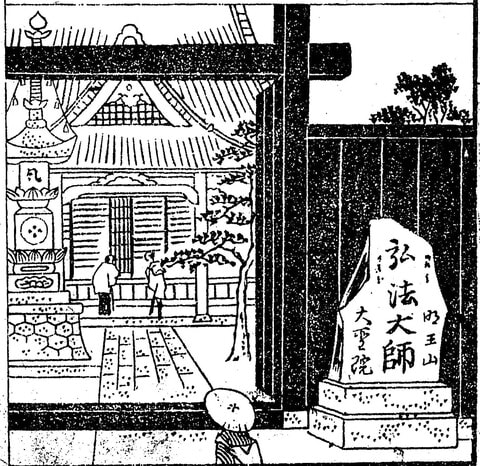
「大聖院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』芝高輪辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは都営三田線「三田」駅で徒歩約10分。
国道1号に面し、蛇坂の登り口にあります。
三田界隈は国道1号が低地を走り、台地上を走る二本榎通りに向かっていくつかの坂道があり、その坂道や国道1号に面して寺院が点在する寺町です。


【写真 上(左)】 入口
【写真 下(右)】 院号標
三田には都心霊場ならではのビルタイプの札所寺院がありますが、こちらもそのひとつ。
国道1号からスロープを介して少しく引き込んでいるので、入口壁面の院号標がなければ寺院とは思えません。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 尊像御座の一画
瀟洒なビルで、エントランスの唐破風がなければ近づいても寺院と気づかないかも。
エントランス向かって右手の一画に札所標、二童子を従えた不動明王、弘法大師像、地蔵尊像が御座し、俄然霊場札所らしい雰囲気が出てきます。


【写真 上(左)】 エントランス
【写真 下(右)】 向拝?
エントランスが拝所(向拝?)と思われ、こちらから参拝しました。
こちらは二度参拝しいずれもご不在だったので、ご在寺時にお声掛けすれば堂内に入れていただけるかは不明です。
『ルートガイド』には弘法大師の御作と伝わる不動明王を安置とありますが、御座所は不明です。
御朱印はエントランス脇の扉に書置が掛けてありました。
専用用紙、御朱印帳貼付、どちらのタイプも準備されていました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
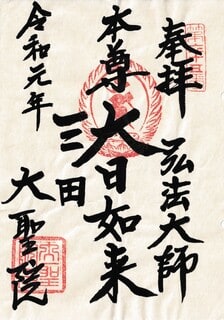
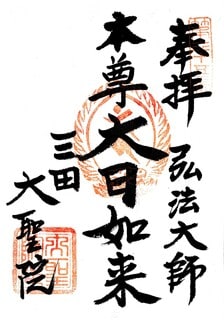
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊大日如来」「弘法大師」の揮毫と御寶印。
御寶印のお種子は不動明王の「カン/カーン」のようにも見えますが、どうでしょうか。
右に「第六十五番」の札所印。左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第66番 白龍山 寿命院 東覚寺
(とうかくじ)
公式Web
北区田端2-7-3
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
司元別当:(田端)八幡神社(北区田端2-7-2)
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第66番、豊島八十八ヶ所第66番、谷中七福神(福禄寿)、上野王子駒込辺三十三観音霊場第29番、九品仏霊場第2番(上品中生)、閻魔三拾遺第5番、江戸・東京四十四閻魔参り第35番、滝野川寺院めぐり第2番
※この記事は■ 滝野川寺院めぐり-1をアレンジして仕上げています。
第66番は田端の東覚寺です。
御府内霊場には東覚寺を号する札所がふたつ(当山と第73番/亀戸)ありますが、当山を「田端東覚寺」、第73番を「亀戸東覚寺」と呼んで区別しているようです。
ところで城北の田端あたりは御府内に入っていたのでしょうか。
「御府内」とは「江戸町奉行が支配の対象とする江戸(の範囲内)」ないし「寺社勧化場として許可された江戸(の範囲内)」といわれ、時代によって変化したといいます。
東京都公文書館のWeb資料には以下のとおりあります。
-------------------------
文政元年(1818)8月に、目付牧助右衛門から「御府内外境筋之儀」についての伺いが出されました。
この伺いを契機に、評定所で入念な評議が行われました。このときの答申にもとづき、同年12月に老中阿部正精から「書面伺之趣、別紙絵図朱引ノ内ヲ御府内ト相心得候様」と、幕府の正式見解が示されたのです。
その朱引で示された御府内の範囲とは、およそ次のようになります。
東…中川限り
西…神田上水限り
南…南品川町を含む目黒川辺
北…荒川・石神井川下流限り
この朱引図には、朱線と同時に黒線(墨引)が引かれており、この墨引で示された範囲が、町奉行所支配の範囲を表しています。朱引と墨引を見比べると、例外的に目黒付近で墨引が朱引の外側に突出していることを除けば、ほぼ朱引の範囲内に墨引が含まれる形になっていることが見てとれます。
以来、江戸の範囲といえば、この朱引の範囲と解釈されるようになったのです。
-------------------------
このようにきわめて明快に説明されています。
つまり、江戸御府内=江戸朱引図内ということです。
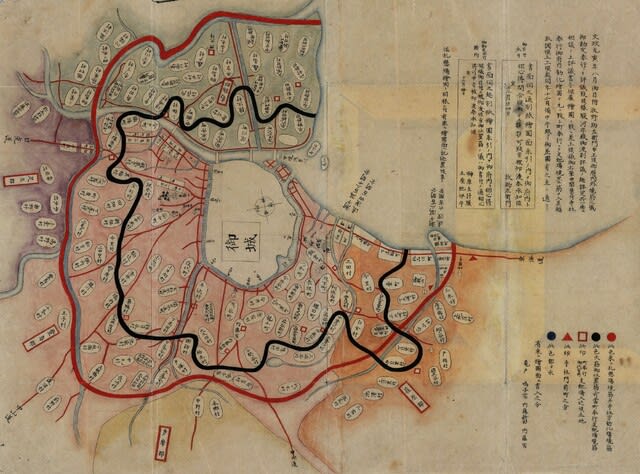
■ 江戸朱引図(東京都公文書館Web公開資料)
江戸朱引図(東京都公文書館)をみると田畑村はしっかり朱引図内に収まっており、田端が御府内に位置することがわかります。

■ 朱引きと田畑村の位置関係(東京都公文書館Web公開資料を筆者にて加工)
第66番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに東覚寺となっており、第66番札所は御府内霊場開創当初から田端の東覚寺であったとみられます。
公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
東覚寺は、延徳三年(1491年)真言宗御室派の僧、源雅和尚が神田筋違橋(現在の万世橋付近)に不動明王を御本尊に勧請して創建。
その後根岸の御印田を経て、慶長年間(1596-1615年)に田畑村の現在地に移転したと伝わります。
田端の名刹・與楽寺(第56番札所)の末寺で、20を数えた末寺のなかで筆頭に位置したといいます。
その名刹ぶりは、末寺なから養福寺・寿徳寺・福蔵寺・普門寺という4つの末寺を擁していたこと、御府内霊場、九品仏霊場、(西国)三十三観音霊場など複数の霊場札所を兼ねていたことからもわかります。
江戸時代には徳川歴代将軍の祈願所となり、寺紋に“葵の紋”を賜りました。
昭和20年4月13日の戦災で御本尊の不動明王を除いて諸堂などほぼ全てを焼失。
現在の本堂は、昭和42年の再建です。
東覚寺は江戸時代は八幡社(田端八幡宮)の別当で、『江戸名所図会』で八幡社の山裾に佇む様は別当としての性格をあらわしています。
八幡社(田端八幡宮)は文治五年(1189年)頼朝公の勧請と伝わる田畑村の鎮守です。
『新編武蔵風土記稿』には東覺寺、八幡社(田畑八幡宮)、石像仁王、九品佛堂、観音堂などが渾然と載せられ、神仏習合の霊地であったことがうかがえます。

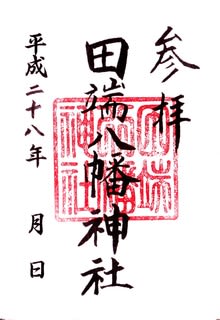
【写真 上(左)】 田端八幡神社
【写真 下(右)】 田端八幡神社の御朱印
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
六十六番
田ばた村
白龍山 壽命院 東覺寺
田ばた村与楽寺末
本尊:不動明王 本社八幡大菩薩 弘法大師
■ 『新編武蔵風土記稿 豊島郡巻十』(国立国会図書館)
(田端村)東覺寺
與楽寺末白龍山壽命院ト号ス 寺領七石ノ御朱印ヲ附セラル
本尊不動ハ弘法大師ノ作ナリ
八幡社
村ノ鎮守ナリ 江戸志等ニ文治五年(1189年)頼朝ノ勧請ナル由記シタレト 今社伝ニ存セス 社前ニ石像仁王アリ 昔銘ニ施主道如宗海上人東岳寺賢盛代 寛永十八年(1641年)八月二十一日ト彫ル
九品佛堂
惠心ノ作ノ三尊彌陀ヲ安置ス 第二番ノ堂ト云
観音堂
■ 『江戸名所図会 7巻 [15]』(国立国会図書館)
田畑八幡宮
同所(田畑村)西の方にあり田畑村の鎮守とす 相伝ふ文治五年(1189年)頼朝公勧請す すなはち駒込神明宮と同時の鎮座なりと云 別当ハ眞言宗東覚寺と号して弘法大師の作の不動尊を本尊とす 開山行基菩薩なり

「東覚寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

「田畑八幡宮」/原典:松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[15],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836] .国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------


【写真 上(左)】 赤紙仁王尊と明王堂
【写真 下(右)】 奉納された草鞋
最寄りはJR「田端」駅で徒歩約6分。
複数の霊場札所を兼ね、「赤紙仁王尊」でも知られる寺院です。
区画整理が進んだ広々とした街区に、赤紙を貼られた赤紙仁王尊の出現はインパクトがあります。
この赤紙仁王尊(区の指定文化財)は寛永十八年(1641年)の背銘があり、当時江戸市中に流行していた疫病を鎮めるため宋海上人が願主建立されたもので、赤紙を自分の患部と同じところに貼って願をかけると霊験ありと信じられ、いまもたくさんの赤紙が貼られています。
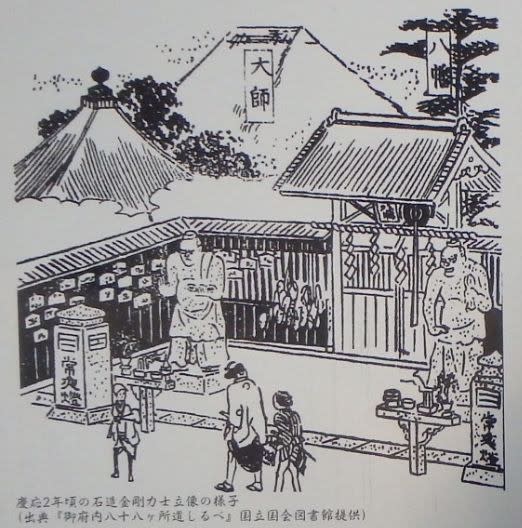
【絵図】 慶応2年頃の石像金剛力士像の様子(北区教育委員会の現地説明板より/出典『御府内八十八ヶ所道しるべ』/国立国会図書館提供)
ときどき赤紙を剥がすそうですが、剥がす前のタイミングだと石造の仁王尊は赤紙に貼り尽くされほとんどお姿が見えません。
病が治癒すると草履を供えるとされ、仁王尊の脇にはたくさんの草履が奉納されています。
この赤紙仁王尊は門前の明王堂(護摩堂)参道に御座しますが、もともとは当山が別当を務めた田端八幡神社の参道に安置されていたといいます。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 本堂
山門は新しいですが本瓦葺、二軒の平行垂木を備えた立派なものでおそらく薬医門。
正面本堂左手前の修行大師像と金色の金剛界大日如来坐像、向拝欄干には御本尊不動明王の御真言とお大師さまの御寶号が掲げられ、保守本流の真言宗寺院の空気感。


【写真 上(左)】 修行大師像
【写真 下(右)】 向拝
本堂は入母屋造銅板葺流れ向拝。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。
正面桟唐戸の上に「白龍山」の扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 向拝見上げ
【写真 下(右)】 札所標
本堂左手客殿前には金色の阿弥陀如来坐像、その奥に「九品佛第二番 阿弥陀如来」と西國廿九番(上野王子駒込辺三十三観音霊場、札所本尊馬頭観世音菩薩)の札所標が並びます。
九品佛霊場は江戸時代開創の古い霊場で発願は巣鴨の真性寺、結願は板橋の智清寺。東覚寺は第2番で上品中生の阿弥陀如来です。
両霊場ともに御朱印の有無をお伺いしましたが、いずれもお出しになられていないとのことでした。


【写真 上(左)】 鼓翼(はばたき)平和観音像
【写真 下(右)】 馬頭観世音
庫裡に回り込む手前に、鼓翼(はばたき)平和観音像と馬頭観世音菩薩が御座します。
馬頭観世音菩薩は三面八臂の坐像で、髻に馬頭をいだかれた憤怒相です。
馬頭観世音菩薩は観世音菩薩にはめずらしい憤怒尊で、「馬頭明王」と呼ばれることもあります。
この立派な馬頭観世音菩薩は、上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所本尊なのかもしれません。
本堂裏には回遊式の庭園があり、庭内に諸仏が安置されています。
- むらすずめ さわくち声も もも声も つるの林の つるの一声 -
太田蜀山人 / 雀塚の石塔
こちらは江戸・東京四十四閻魔参り第35番の札所で、御縁日に参拝したところ閻魔大王の御朱印は授与されていないとのことで、御本尊の御朱印をいただきました。
閻魔大王は奪衣婆とともに、本堂内に御座されているそうです。
また、歴史ある谷中七福神の福禄寿尊天をお祀りされます。
この福禄寿尊天は、もとは通称「六角山」にあった六角堂(西行庵)に西行法師坐像とともに祀られていたもので、明治に入って当寺に遷座されました。
毎年正月には本堂で御開帳されています。
御朱印は、向かって左裏手の寺務所で拝受します。
複数の霊場札所を兼務されているので、希望の御朱印をはっきりと申告します。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
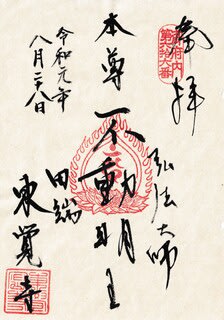

【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊不動明王」「弘法大師」の揮毫と不動明王のお種子「カン/カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「御府内第六拾六番」の札所印。
左に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
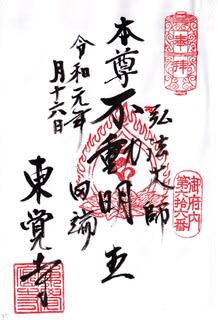

【上(左)】 閻魔様の御縁日に拝受した御本尊の御朱印
【下(右)】 豊島八十八ヶ所第66番の御朱印
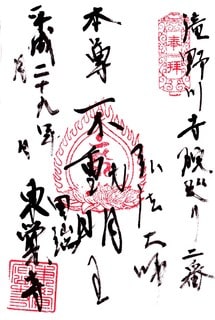
■ 滝野川寺院めぐり第2番の御朱印
※「滝野川寺院めぐり 第2番」の札所印はお持ちでないとのことでしたが、ご厚意で揮毫の札番をいただけました。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-22)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ ノーサイド - 松任谷由実
願い - 童子-T feat.YU-A
■ いつかまた咲く花へ - 西沢はぐみ
■ into the world - kalafina
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第63番 初音山 東漸寺 観智院
(かんちいん)
公式Web
台東区谷中5-2-4
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第64番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第6番
第63番は谷中の観智院です。
第63番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』では観智院、江戸八十八ヶ所霊場では加納院となっています。
加納院は御府内霊場第64番ですから、どこかの時点で63番と64番の札所が入れ替わった可能性があります。
いずれにしても、谷中の観智院は御府内霊場開創当初からの札所であったとみられます。
公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
観智院は、慶長十六年(1611年)、照譽法印が小(北)寺町に開山、慶安元年(1648年)谷中へ移転したといいます。
慶安元年(1648年)の移転は旧寺地が幕府用地となつたためで、『下谷区史 〔本編〕』によると、神田北寺町での幕府からの賜地、谷中への移転の事由や時期は多寶院(第49番)、自性院(第53番)、長久院(第55番)、明王院(第57番)などと同様とみられますが、寺伝には慶安元年(1648年)に一旦谷中清水坂に遷ったあと、万治年中(1658-1660年)に現在地へ移転とあります。
延宝八年(1680年)、当山12世・宥朝法印が入山され元禄十一年(1698年)に院号を現在の観(觀)智院に改めました。
当初の院号は圓照院。
宥朝法印は「”圓照”は”炎焦”に通ずる」との霊告を受けられて号を改めたといいます。
宥朝法印の入山により寺勢はますます興隆しましたが、公式Webでは当山と檀越関係にあった奥医師・丸山玄棟の外護も大きかったと推察されています。
安永八年(1779年)には不動堂を建立、興教大師作と伝わる不動尊像が安置され、五大明王像を奉安という史料もみられます。
五大明王とは不動明王を中心に降三世明王(東)、軍荼利明王(南)、大威徳明王(西)、金剛夜叉明王(北)と配置される明王像で、霊験ことにあらたかとして広く信仰されます。
元禄十六年(1703年)十一月、大震災につづいて本郷追分、小石川辺から出火した火災は、折からの強風にあおられて江戸の町の大半を焼きつくしました。
谷中の寺院も多くが焼失しますが、観智院は奇跡的に炎禍を遁れたといいます。
観智院の不動尊は興教大師御作と伝わる霊像であること、中興開山・宥朝法印の「火除けの改号」のいわれ、そして大火の炎禍を免れたことなどもあってか、「谷中の火除不動尊」と呼ばれて多くの参詣者を集めたといいます。
文化・文政(1804-1829年)の頃になると、江戸御府内はもちろん近隣からも参詣人が訪れ、門前は市がたつほどの賑わいになったと伝わります。
谷中のメインロードであった「三崎坂」(さんざきざか)に面していたことも大きいのでは。
明治初頭の神仏分離の際には大店の商人をはじめとする町人の檀信徒が23世・真興法印のもとに結集して寺門を支えたといい、御府内霊場札所のポジションも堅持しています。
明治39年、24世・海隆法印が入山、先々代・石本海隆師も堂宇整備に尽力されて大正年間にはふたたび寺容を整えたといいます。
関東大震災では延焼を免れた当山に人々が避難したといい、昭和20年3月の東京大空襲では本堂・庫裡に砲弾を受けたものの大師堂・不動堂は焼失の難を遁れ、いまなお戦前の姿を残すとともに、御本尊・大日如来をはじめすべての仏像、什器もまた焼失を遁れています。
火除不動尊の霊験まことにあらたかというべきでしょうか。
昭和24年初音幼稚園を設置し、いまでも山内は園児の声でにぎやかです。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
六十三番
谷中三崎通り
醫王山 東漸寺 観智院
本所弥勒寺末 新義
本尊:弘法大師
■ 『寺社書上 [111] 谷中寺社書上 三』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.100』
谷中不唱小名
新義真言宗 本所彌勒寺末
醫王山東漸寺観智院
権現様御世慶長十六年(1611年)2月15日、当寺開山照誉法印代 於神田小寺町ニ寺地拝領仕候 大猷院様御世慶安元年(1648年)中、神田小寺町御用地ニ付被召上 谷中ニ代地拝領仕候
開山 照誉法印 卒年月不知
中興開基 宥朝法印 享保六年(1721年)遷化
本堂
本尊 弘法大師座像
不動尊土蔵
不動尊座像 興教大師作
稲荷社
■ 『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)
觀智院(谷中初音町一丁目二三番地)
本所彌勒寺末、醫王山東漸寺と号す。本尊弘法大師。当寺亦慶長十六年(1611年)二月、幕府より神田北寺町に地を賜うて起立し、慶安元年(1648年)同所幕府用地となるや現地に転じた。開山は僧照譽、中興は僧宥朝。(享保六年(1721年)五月二十二日寂)
境内に不動堂がある。
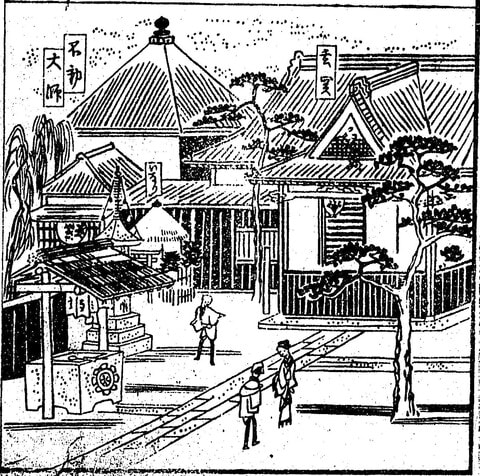
「観智院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)
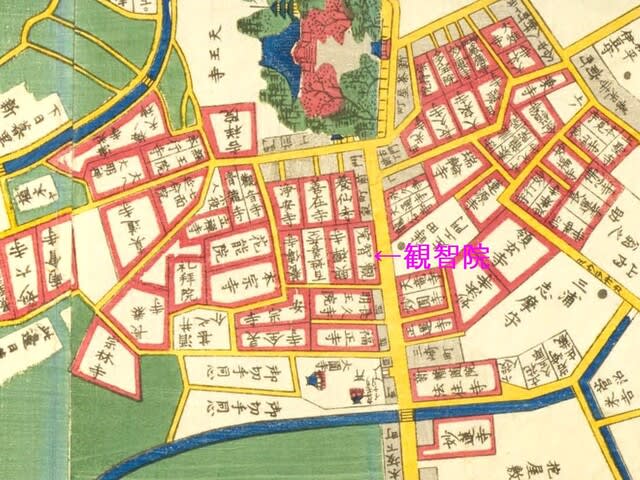
原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
※ 休園日に撮った写真がなぜか見つかりません。見つかったら追加します。
最寄りは東京メトロ千代田線「千駄木」で徒歩約7分ほど。
JR「日暮里」駅からも同じくらいで歩けます。
千駄木から谷中霊園へ向かう三崎坂をほぼ登り切ったところに道に面してあります。
第57番明王院の並びにあり、谷中寺町のほぼ中心部に当たります。


【写真 上(左)】 全景
【写真 下(右)】 本堂
山内のほとんどは幼稚園として使われ、平日の日中はセキュリティ上から閉門されているので、休日の参拝がベターとみられます。
山内入口に初音六地蔵。
昭和58年秋の像立と新しいお像ですが、手篤く供養されて存在感があります。
門柱に院号標があり、おくに本堂は見えますが、平日昼間は園児たちが走り回り幼稚園バスが停まっていたりしてほぼ幼稚園です。
正面の階段上に唐破風の向拝を備えた本堂。
複雑な意匠で見応えがあります。


【写真 上(左)】 不動堂(右)と大師堂(左)
【写真 下(右)】 不動堂の扁額
本堂向かって左手前に不動堂と大師堂があります。
不動堂は宝形造銅板葺で向拝に「火除不動尊」の扁額を掲げています。
大師堂は不動堂の向かって右手に連接してあります。
柱には御府内霊場ではなく、「弘法大師廿一ヶ所六番」の札所板が打ち付けられていました。
お大師さまは、堂内の大ぶりな厨子のなかに御座されています。
御朱印は本堂向かって左手前の庫裡にて拝受しました。
なお、「火除不動尊」の御朱印は授与されていないそうです。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
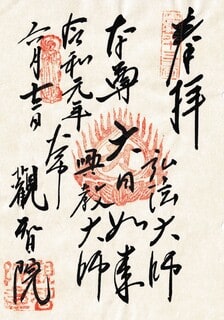
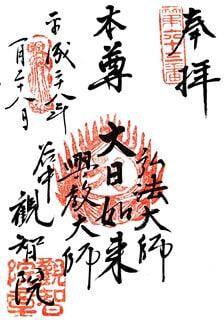
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊大日如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫と胎蔵大日如来のお種子「ア」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「第六十三番」の札所印。左に地蔵尊の御影印、院号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第64番 長谷山 元興寺 加納院
(かのういん)
台東区谷中5-8-5
新義真言宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第63番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第4番
第64番は谷中の加納院。御府内霊場では数すくない、紀州根來寺を総本山とする新義真言宗の寺院です。
第64番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』では加納院、江戸八十八ヶ所霊場では観智院となっています。
観智院は御府内霊場第63番ですから、どこかの時点で63番と64番の札所が入れ替わった可能性があります。
いずれにしても、谷中の加納院は御府内霊場開創当初からの札所であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
加納院は、慶長十六年(1611年)、幕府より神田小(北)寺町に寺地を給せられて尊慶上人が開基、慶安元年(1648年)谷中へ移転したといいます。
慶安元年(1648年)の移転は旧寺地が幕府用地となったためで、『下谷区史 〔本編〕』によると、神田北寺町での幕府からの賜地、谷中への移転の事由や時期は多寶院(第49番)、自性院(第53番)、長久院(第55番)、明王院(第57番)、観智院(第63番)などと同様とみられますが、慶安元年(1648年)に一旦谷中清水坂に遷ったあと、延宝八年(1680年)再び幕府用地となったため現在地へ移転といいます。
加納院は情報が少ないですが、『寺社書上』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考』には、本堂御本尊は阿弥陀如来で両脇侍は正観世音菩薩と勢至菩薩。
御本尊の阿弥陀如来は「(御府内)八十八ヶ所ノ第六十三番」と記されています。
本堂内(『下谷区史』では大師堂内)に弘法大師像、興教大師像を奉安し、御府内霊場札所としての要件は整っていたようです。
聖天堂には大聖歓喜天二躰(秘佛)と本地佛として十一面観世音菩薩を奉安。
相殿に稲荷。阿弥陀如来、弁財天二躰、千手観世音菩薩も安置と伝わります。
『ルートガイド』によると、当山所蔵の「両界曼荼羅版木」は台東区有形文化財に指定されているとのこと。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
六十四番
谷中
長谷山 元興寺 加納院
本所弥勒寺末 新義
本尊:阿弥陀如来 弘法大師 興教大師
■ 『寺社書上 [111] 谷中寺社書上 四』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.102』
谷中不唱小名
新義真言宗 本所彌勒寺末
長谷山元興寺加納院
起立 慶長十六年(1611年)
開基 尊慶 寛永十三年(1636年)寂
権現様御代 神田北寺町ニ寺地拝領仕候 慶安元年(1648年)大猷院様御代 神田北寺町御用ニ付 谷中清水坂ニテ替地拝領仕候 延宝八年(1680年)厳有院様御代御用地ニ付 清水坂地処差上● 只今ハ当所ニ住居仕候
本堂
本尊 阿弥陀如来木座像
八十八ヶ所ノ第六十三番
両脇士 観世音 勢至
弘法大師 興教大師
位牌壇 大日如来
聖天堂
歓喜天二躰 秘佛
本地 十一面観音
相殿稲荷 阿弥陀如来 弁財天二躰 千手観世音
■ 『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)
加納院(谷中上三崎北町六番地)
本所彌勒寺末、長谷山元興寺と号す。本尊阿彌陀如来。慶長十六年(1611年)幕府より神田北寺町に寺地を給せられて起立した。開山を尊慶(寛永十三年(1636年)四月六日寂)といふ。慶安元年(1648年)同所が幕府用地となったため谷中清水坂(現谷中清水町)に移り、延寶八年(1680年)同所亦用地となり、現地に転じた。
境内に聖天堂(大聖歡喜天を安置す)及び大師堂(弘法大師像及び興教大師像を安置す)がある。
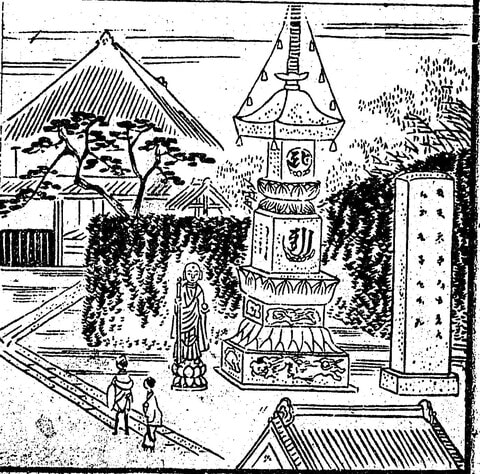
「加納院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)
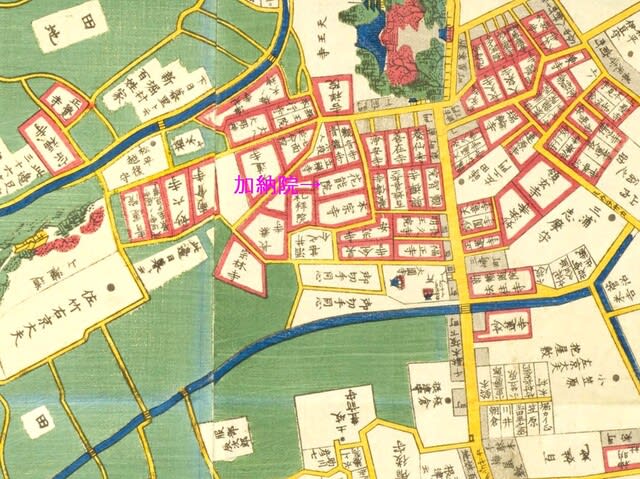
原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはJR「日暮里」駅で徒歩約7分。
東京メトロ千代田線「千駄木」駅からの方が距離的には近いくらいですが、急な登りとなります。
台地上にある「日暮里」駅から歩くとわかりにくいですが、千駄木方面から望むとかなりの高台にあることがわかります。
寺院に囲まれた路地奥の立地ですが、観光スポットの観音寺の築地塀の先にあり、目立つ朱塗り門を構えているので、訪れる人は意外に多いのかもしれません。
位置的には三崎坂から明王院と観智院のあいだの路地を北に入った路地の突き当たりにあります。
この路地まわりはほとんどが寺院で、谷中が都内屈指の寺町であることを実感できます。


【写真 上(左)】 加納院前から望む観音寺の築地塀(左)
【写真 下(右)】 山門
山門は切妻屋根桟瓦葺の朱塗りの薬医門で、脇塀とともにコの字型の空間をつくり出し、どこか城門のようです。
山門前に御府内霊場札所標。
これは御府内霊場(第64番)と御府内二十一ヶ所霊場(第4番)を併記したもので、比較的めずらしいかたちでは。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 山内
緑濃い山内はよく手入れされて心なごみます。
四季折々の花々が咲き誇る花の寺でもあるようです。
本堂は寄棟造桟瓦葺流れ向拝。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの向拝
向拝に扁額はないですが、向拝扉右手に御府内霊場(第64番)と御府内二十一ヶ所霊場(第4番)の札所板が掲げられています。

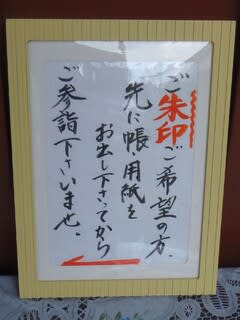
【写真 上(左)】 札所板
【写真 下(右)】 御朱印案内
御朱印は本堂向かって左の庫裡にて拝受しました。
御府内霊場は参拝後の御朱印申告が原則ですが、こちらでは参拝前に御朱印帳を預ける旨の掲示があります。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
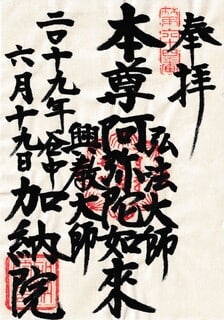
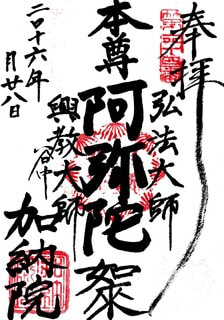
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊阿弥陀如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫とお種子(おそらく阿弥陀如来のお種子・キリーク)の御寶印。
御寶印は八葉をかたちどったもので、胎蔵曼荼羅の中心部・中台八葉院をモチーフとしたものかも。
右に「第六十四番」の札所印。左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
西暦で書かれた奉拝日が個性的です。
■ 第65番 明王山 遍照寺 大聖院
(だいしょういん)
港区三田4-1-27
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第65番
第65番は三田の大聖院。
御府内霊場の後半は、三田の札所が多くなります。
第65番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに大聖院で、三田の大聖院は御府内霊場開創当初からの第65番札所であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
大聖院は、慶長十六年(1611年)数寄屋町に創建ののち八丁堀に移り、寛永十二年(1635年)淀松尾氏等の外護を受けて三田の現在地に移転といいます。
開山は宥専上人、中興開基は法印祐壽と伝わります。
江戸期は愛宕前真福寺末でしたが、明治12年に智山派総本山智積院の直轄末寺となっています。
本堂には、御本尊の大日如来木座像を奉安。六躰の阿弥陀如来木座像と弘法大師木座像、興教大師木座像を安置して御府内霊場札所の体裁を整えていたようです。
護摩堂には不動尊木座像、千手観音木座像、愛染明王木座像、聖天尊真鍮立像を奉安し、鎮守は稲荷社と伝わります。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
六十五番
芝三田寺町
明王山 遍照寺 大聖院
愛宕山真福寺末 新義
本尊:金剛界大日如来 不動明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [13] 三田寺社書上 参』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.92』
三田寺町
愛宕前真福寺末 新義真言宗
明王山大聖院遍照寺
草創之年暦 開山 中興開山 開基 不分明
慶長十六年(1611年)四月数寄屋町 八町堀に替地拝領仕
寛永十二年(1635年)八月八町堀から三田寺町に替地拝領仕
中興開基 法印祐壽 寛永十二年(1635年)
本堂
本尊 大日如来木座像
阿彌陀如来木座像 六躰
弘法大師木座像
興教大師木座像
護摩堂
不動尊木座像 千手観音木座像 愛染明王木座像 聖天尊真鍮立像
鎮守稲荷社
■ 『芝區誌』(デジタル版 港区のあゆみ)
大聖院 三田北寺町二十一番地
初め眞言宗愛宕眞福寺末派で、慶長十六年(1611年)数寄屋町に創建し、後八丁堀に移り、寛永十二年(1635年)淀松尾氏等の外護に依って現在地に堂宇を定めた。開山は宥専上人である。明治十二年六月二日京都総本山智積院直轄末寺となった。御府内第六十五番の札所である。
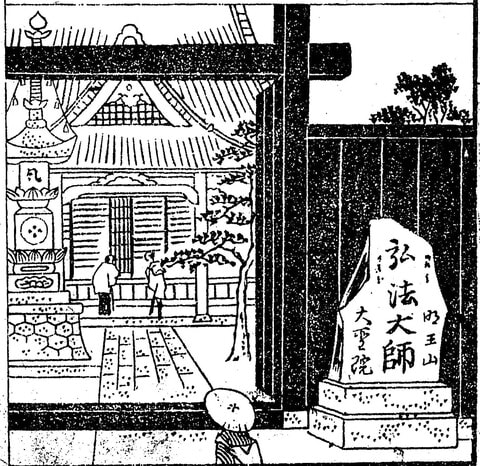
「大聖院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』芝高輪辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは都営三田線「三田」駅で徒歩約10分。
国道1号に面し、蛇坂の登り口にあります。
三田界隈は国道1号が低地を走り、台地上を走る二本榎通りに向かっていくつかの坂道があり、その坂道や国道1号に面して寺院が点在する寺町です。


【写真 上(左)】 入口
【写真 下(右)】 院号標
三田には都心霊場ならではのビルタイプの札所寺院がありますが、こちらもそのひとつ。
国道1号からスロープを介して少しく引き込んでいるので、入口壁面の院号標がなければ寺院とは思えません。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 尊像御座の一画
瀟洒なビルで、エントランスの唐破風がなければ近づいても寺院と気づかないかも。
エントランス向かって右手の一画に札所標、二童子を従えた不動明王、弘法大師像、地蔵尊像が御座し、俄然霊場札所らしい雰囲気が出てきます。


【写真 上(左)】 エントランス
【写真 下(右)】 向拝?
エントランスが拝所(向拝?)と思われ、こちらから参拝しました。
こちらは二度参拝しいずれもご不在だったので、ご在寺時にお声掛けすれば堂内に入れていただけるかは不明です。
『ルートガイド』には弘法大師の御作と伝わる不動明王を安置とありますが、御座所は不明です。
御朱印はエントランス脇の扉に書置が掛けてありました。
専用用紙、御朱印帳貼付、どちらのタイプも準備されていました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
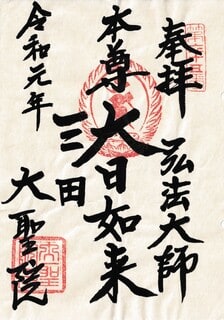
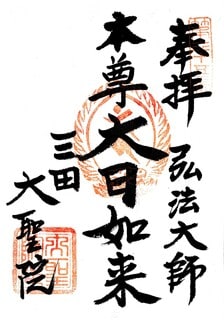
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊大日如来」「弘法大師」の揮毫と御寶印。
御寶印のお種子は不動明王の「カン/カーン」のようにも見えますが、どうでしょうか。
右に「第六十五番」の札所印。左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第66番 白龍山 寿命院 東覚寺
(とうかくじ)
公式Web
北区田端2-7-3
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
司元別当:(田端)八幡神社(北区田端2-7-2)
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第66番、豊島八十八ヶ所第66番、谷中七福神(福禄寿)、上野王子駒込辺三十三観音霊場第29番、九品仏霊場第2番(上品中生)、閻魔三拾遺第5番、江戸・東京四十四閻魔参り第35番、滝野川寺院めぐり第2番
※この記事は■ 滝野川寺院めぐり-1をアレンジして仕上げています。
第66番は田端の東覚寺です。
御府内霊場には東覚寺を号する札所がふたつ(当山と第73番/亀戸)ありますが、当山を「田端東覚寺」、第73番を「亀戸東覚寺」と呼んで区別しているようです。
ところで城北の田端あたりは御府内に入っていたのでしょうか。
「御府内」とは「江戸町奉行が支配の対象とする江戸(の範囲内)」ないし「寺社勧化場として許可された江戸(の範囲内)」といわれ、時代によって変化したといいます。
東京都公文書館のWeb資料には以下のとおりあります。
-------------------------
文政元年(1818)8月に、目付牧助右衛門から「御府内外境筋之儀」についての伺いが出されました。
この伺いを契機に、評定所で入念な評議が行われました。このときの答申にもとづき、同年12月に老中阿部正精から「書面伺之趣、別紙絵図朱引ノ内ヲ御府内ト相心得候様」と、幕府の正式見解が示されたのです。
その朱引で示された御府内の範囲とは、およそ次のようになります。
東…中川限り
西…神田上水限り
南…南品川町を含む目黒川辺
北…荒川・石神井川下流限り
この朱引図には、朱線と同時に黒線(墨引)が引かれており、この墨引で示された範囲が、町奉行所支配の範囲を表しています。朱引と墨引を見比べると、例外的に目黒付近で墨引が朱引の外側に突出していることを除けば、ほぼ朱引の範囲内に墨引が含まれる形になっていることが見てとれます。
以来、江戸の範囲といえば、この朱引の範囲と解釈されるようになったのです。
-------------------------
このようにきわめて明快に説明されています。
つまり、江戸御府内=江戸朱引図内ということです。
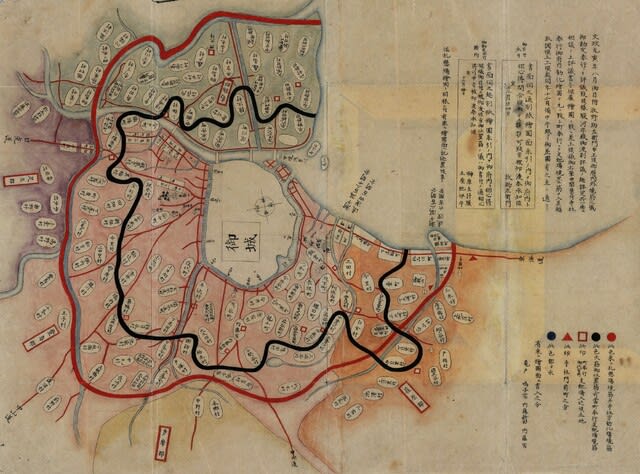
■ 江戸朱引図(東京都公文書館Web公開資料)
江戸朱引図(東京都公文書館)をみると田畑村はしっかり朱引図内に収まっており、田端が御府内に位置することがわかります。

■ 朱引きと田畑村の位置関係(東京都公文書館Web公開資料を筆者にて加工)
第66番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに東覚寺となっており、第66番札所は御府内霊場開創当初から田端の東覚寺であったとみられます。
公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
東覚寺は、延徳三年(1491年)真言宗御室派の僧、源雅和尚が神田筋違橋(現在の万世橋付近)に不動明王を御本尊に勧請して創建。
その後根岸の御印田を経て、慶長年間(1596-1615年)に田畑村の現在地に移転したと伝わります。
田端の名刹・與楽寺(第56番札所)の末寺で、20を数えた末寺のなかで筆頭に位置したといいます。
その名刹ぶりは、末寺なから養福寺・寿徳寺・福蔵寺・普門寺という4つの末寺を擁していたこと、御府内霊場、九品仏霊場、(西国)三十三観音霊場など複数の霊場札所を兼ねていたことからもわかります。
江戸時代には徳川歴代将軍の祈願所となり、寺紋に“葵の紋”を賜りました。
昭和20年4月13日の戦災で御本尊の不動明王を除いて諸堂などほぼ全てを焼失。
現在の本堂は、昭和42年の再建です。
東覚寺は江戸時代は八幡社(田端八幡宮)の別当で、『江戸名所図会』で八幡社の山裾に佇む様は別当としての性格をあらわしています。
八幡社(田端八幡宮)は文治五年(1189年)頼朝公の勧請と伝わる田畑村の鎮守です。
『新編武蔵風土記稿』には東覺寺、八幡社(田畑八幡宮)、石像仁王、九品佛堂、観音堂などが渾然と載せられ、神仏習合の霊地であったことがうかがえます。

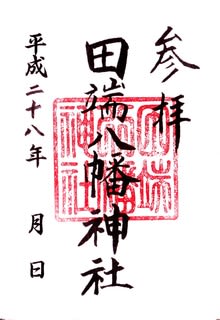
【写真 上(左)】 田端八幡神社
【写真 下(右)】 田端八幡神社の御朱印
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
六十六番
田ばた村
白龍山 壽命院 東覺寺
田ばた村与楽寺末
本尊:不動明王 本社八幡大菩薩 弘法大師
■ 『新編武蔵風土記稿 豊島郡巻十』(国立国会図書館)
(田端村)東覺寺
與楽寺末白龍山壽命院ト号ス 寺領七石ノ御朱印ヲ附セラル
本尊不動ハ弘法大師ノ作ナリ
八幡社
村ノ鎮守ナリ 江戸志等ニ文治五年(1189年)頼朝ノ勧請ナル由記シタレト 今社伝ニ存セス 社前ニ石像仁王アリ 昔銘ニ施主道如宗海上人東岳寺賢盛代 寛永十八年(1641年)八月二十一日ト彫ル
九品佛堂
惠心ノ作ノ三尊彌陀ヲ安置ス 第二番ノ堂ト云
観音堂
■ 『江戸名所図会 7巻 [15]』(国立国会図書館)
田畑八幡宮
同所(田畑村)西の方にあり田畑村の鎮守とす 相伝ふ文治五年(1189年)頼朝公勧請す すなはち駒込神明宮と同時の鎮座なりと云 別当ハ眞言宗東覚寺と号して弘法大師の作の不動尊を本尊とす 開山行基菩薩なり

「東覚寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

「田畑八幡宮」/原典:松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[15],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836] .国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------


【写真 上(左)】 赤紙仁王尊と明王堂
【写真 下(右)】 奉納された草鞋
最寄りはJR「田端」駅で徒歩約6分。
複数の霊場札所を兼ね、「赤紙仁王尊」でも知られる寺院です。
区画整理が進んだ広々とした街区に、赤紙を貼られた赤紙仁王尊の出現はインパクトがあります。
この赤紙仁王尊(区の指定文化財)は寛永十八年(1641年)の背銘があり、当時江戸市中に流行していた疫病を鎮めるため宋海上人が願主建立されたもので、赤紙を自分の患部と同じところに貼って願をかけると霊験ありと信じられ、いまもたくさんの赤紙が貼られています。
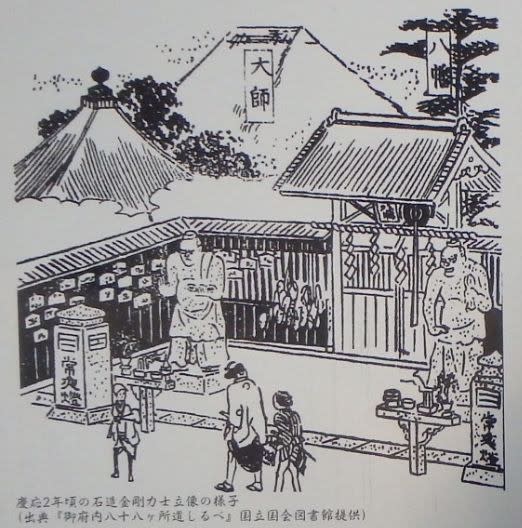
【絵図】 慶応2年頃の石像金剛力士像の様子(北区教育委員会の現地説明板より/出典『御府内八十八ヶ所道しるべ』/国立国会図書館提供)
ときどき赤紙を剥がすそうですが、剥がす前のタイミングだと石造の仁王尊は赤紙に貼り尽くされほとんどお姿が見えません。
病が治癒すると草履を供えるとされ、仁王尊の脇にはたくさんの草履が奉納されています。
この赤紙仁王尊は門前の明王堂(護摩堂)参道に御座しますが、もともとは当山が別当を務めた田端八幡神社の参道に安置されていたといいます。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 本堂
山門は新しいですが本瓦葺、二軒の平行垂木を備えた立派なものでおそらく薬医門。
正面本堂左手前の修行大師像と金色の金剛界大日如来坐像、向拝欄干には御本尊不動明王の御真言とお大師さまの御寶号が掲げられ、保守本流の真言宗寺院の空気感。


【写真 上(左)】 修行大師像
【写真 下(右)】 向拝
本堂は入母屋造銅板葺流れ向拝。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。
正面桟唐戸の上に「白龍山」の扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 向拝見上げ
【写真 下(右)】 札所標
本堂左手客殿前には金色の阿弥陀如来坐像、その奥に「九品佛第二番 阿弥陀如来」と西國廿九番(上野王子駒込辺三十三観音霊場、札所本尊馬頭観世音菩薩)の札所標が並びます。
九品佛霊場は江戸時代開創の古い霊場で発願は巣鴨の真性寺、結願は板橋の智清寺。東覚寺は第2番で上品中生の阿弥陀如来です。
両霊場ともに御朱印の有無をお伺いしましたが、いずれもお出しになられていないとのことでした。


【写真 上(左)】 鼓翼(はばたき)平和観音像
【写真 下(右)】 馬頭観世音
庫裡に回り込む手前に、鼓翼(はばたき)平和観音像と馬頭観世音菩薩が御座します。
馬頭観世音菩薩は三面八臂の坐像で、髻に馬頭をいだかれた憤怒相です。
馬頭観世音菩薩は観世音菩薩にはめずらしい憤怒尊で、「馬頭明王」と呼ばれることもあります。
この立派な馬頭観世音菩薩は、上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所本尊なのかもしれません。
本堂裏には回遊式の庭園があり、庭内に諸仏が安置されています。
- むらすずめ さわくち声も もも声も つるの林の つるの一声 -
太田蜀山人 / 雀塚の石塔
こちらは江戸・東京四十四閻魔参り第35番の札所で、御縁日に参拝したところ閻魔大王の御朱印は授与されていないとのことで、御本尊の御朱印をいただきました。
閻魔大王は奪衣婆とともに、本堂内に御座されているそうです。
また、歴史ある谷中七福神の福禄寿尊天をお祀りされます。
この福禄寿尊天は、もとは通称「六角山」にあった六角堂(西行庵)に西行法師坐像とともに祀られていたもので、明治に入って当寺に遷座されました。
毎年正月には本堂で御開帳されています。
御朱印は、向かって左裏手の寺務所で拝受します。
複数の霊場札所を兼務されているので、希望の御朱印をはっきりと申告します。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
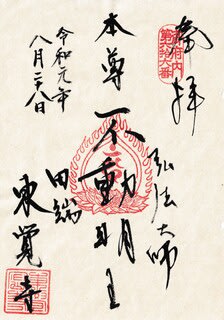

【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊不動明王」「弘法大師」の揮毫と不動明王のお種子「カン/カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「御府内第六拾六番」の札所印。
左に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
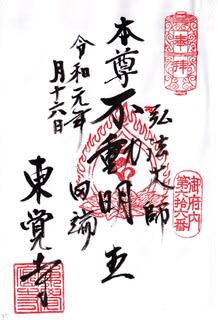

【上(左)】 閻魔様の御縁日に拝受した御本尊の御朱印
【下(右)】 豊島八十八ヶ所第66番の御朱印
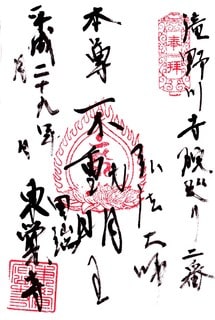
■ 滝野川寺院めぐり第2番の御朱印
※「滝野川寺院めぐり 第2番」の札所印はお持ちでないとのことでしたが、ご厚意で揮毫の札番をいただけました。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-22)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ ノーサイド - 松任谷由実
願い - 童子-T feat.YU-A
■ いつかまた咲く花へ - 西沢はぐみ
■ into the world - kalafina
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-20
Vol.-19からのつづきです。
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第59番 佛寶山 西光院 無量寺
(むりょうじ)
北区西ヶ原1-34-8
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
司元別当:七社(旧西ヶ原村総鎮守)
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第59番、豊島八十八ヶ所霊場第59番、江戸六阿弥陀如来第3番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第3番、大東京百観音霊場第81番
※本記事は「■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印」および「■ 滝野川寺院めぐり-2」から転載・追記したものです。
第59番は北区西ヶ原の無量寺です。
第59番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに無量寺で、第59番札所は開創当初から西ヶ原の無量寺であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
無量寺の創建年代は不明ですが、『滝野川寺院めぐり案内』には「現在当山には9~10世紀の未完成の木像菩薩小像と、12世紀末の都風といわれる等身の阿弥陀如来像が安置されている。さらに正和元年(1312年)、建武元年(1334年)の年号を始めとする30数枚の板碑が境内から出土しているから、少なくとも平安時代の後期には、この地に寺があったことはまず間違いないであろう。」と記されています。
『江戸名所図会』には開山は行基菩薩とあり、これは江戸六阿弥陀の縁起からきているものとみられます。
北区設置の山内説明板には『新編武蔵国風土記稿』や寺伝等には、慶安元年(1648年)に幕府から八石五斗余の年貢・課役を免除されたこと、元禄十四年(1701年)五代将軍綱吉公の生母桂昌院が参詣したこと、以前は長福寺と号していたが、寺号が九代将軍家重公の幼名長福丸と同じであるため、これを避けて現在の名称に改めたことなどが記されています。
江戸時代には広大な寺領を有していたとみられ、当山が別当を勤めた「七社」はその境内に鎮座されていたと伝わります。
『江戸名所図会』には無量寺山内とみられる高台(現・旧古河庭園)に「七社」があらわされ、現・旧古河庭園の一部も無量寺の境内であったのでは。
大正3年(1914年)、古河財閥3代当主の古河虎之助が周囲の土地を購入したという記録があるので、その時に古河家に移った可能性があります。
なお、「七社」は神仏分離の翌年明治二年(1869年)に一本杉神明宮の社地(現・七社神社)に御遷座されています。


【写真 上(左)】 七社神社の社頭
【写真 下(右)】 七社神社の境内
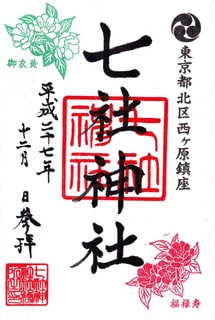

【上(左)】 七社神社の御朱印(旧)
【下(右)】 七社神社の御朱印
西ヶ原村の総鎮守であった七社神社には、西ヶ原村内に飛鳥山邸(別荘)を構えた渋沢栄一翁が氏子として重きをなし、所縁の品々が残されています。
無量寺は御府内霊場のほか、江戸時代、春夏のお彼岸にとくに賑わったといわれる江戸六阿弥陀詣の一寺(第3番目)で、もともと参詣者の多かった寺院とみられます。
また、豊島八十八ヶ所霊場第59番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第3番、滝野川寺院めぐり第9番の札所でもあります。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
五十九番
西ヶ原村
佛宝山 西光院 無量寺
大塚護持院末 新義
本尊:不動明王 弘法大師 興教大師
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
新義真言宗佛寶山西光院ト号ス 慶安元年(1648年)寺領八石五斗餘ノ御朱印ヲ附ラル 古ハ田端村與楽寺ノ末ナリシカ 常憲院殿厳命ヲ以テ大塚護持院ノ末トナレリ 又昔ハ長福寺ト称セシヲ 惇信院殿の御幼名ヲ避テ今ノ寺号ニ改ムト云 本尊不動外ニ正観音ノ立像ヲ置 長三尺五寸許惠心ノ作ニテ 雷除の本尊トイヘリ 中興眞惠享保三年(1718年)閏正月廿三日化ス 今ノ堂ハ昔村内ニ建置レシ御殿御取拂トナリシヲ賜リテ建シモノナリト云 元境内ニ母衣櫻ト名ツケシ櫻樹アリシカ今ハ枯タリ 母衣ノ名ハ寛永(1624-1644年)ノ頃御成アリシ時名ツケ給ヒシト云伝フ
寺寶
紅頗梨色彌陀像一幅 八組大師像八幅 妙澤像一幅 不動像一幅 六字名號一幅。以上弘法大師ノ筆ト云 其内名號ニハ大僧都空海ト落款アリ 菅家自畫像一幅
七所明神社 村ノ鎮守トス 紀伊國高野山四社明神ヲ寫シ祀リ天照大神 春日 八幡三座を合祀ス 故ニ七所明神ト号ス
末社ニ天神 稲荷アリ 辨天社
阿彌陀堂 行基の作 坐像長三尺許六阿弥陀ノ第三番ナリ 観音堂 西國三十三所札所寫ナリ 鐘樓 安永九年鑄造ノ鐘ヲ掛
寺中勝蔵院 不動ヲ本尊トス
■ 『江戸名所図会 十五』(国立国会図書館)
真言宗にして弘法大師の作の不動尊を本尊とし 開山ハ行基菩薩なり 本堂に●●る南無阿彌陀佛の額ハ幡随意院磧了和尚の筆なり
阿弥陀堂 本堂の右にあり 本尊ハ行基菩薩の作 録阿弥陀第三番目なり

「無量寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
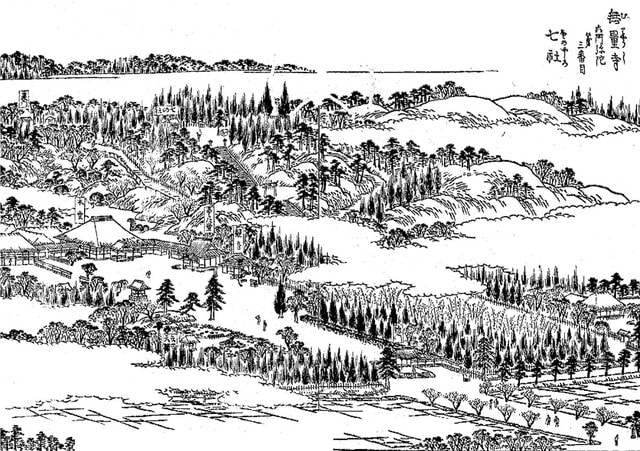
「無量寺」/原典:斎藤長秋 編 ほか『江戸名所図会』十五,博文館,1893.12. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは東京メトロ南北線「西ヶ原」駅で徒歩約7分。
JR「上中里」駅からも徒歩7分ほどですが、こちらは坂の上り下りがあるので下りのみの「西ヶ原」駅の方が楽です。
このあたりの主要道は、不忍通り、白山通り(中山道)など谷間を走る例が多いですが、本郷通りは例外で、律儀に馬の背の台地上を辿ります。
第47番城官寺、あるいは西ヶ原駅・上中里駅からだと本郷通りからの道順となり、かなりの急坂を下ってのアブローチとなります。
旧古河庭園の裏手にあたるこの坂道は木々に囲まれほの暗く、落ち着いた風情があります。
旧古河庭園は陸奥宗光や古河財閥の邸宅で、このあたりは府内屈指の高級住宅地であったことがうかがわれます。
いまでも落ち着いた邸宅がならぶ一画があり、いかにも東京山の手地付きの富裕層が住んでいそうな感じがあります。
内田康夫氏の人気推理小説「浅見光彦シリーズ」の主人公浅見光彦は西ヶ原出身の設定で、家柄がよく、相応の教養や見識を身につけていることなどは、このあたりの地柄を物語るものかもしれません。(内田康夫氏自身が西ヶ原出身らしい。)
坂を下りきり、右手に回り込むと参道入口です。
入口回りは車通りも少なく、相応の広さを保って名刹の風格を感じます。
ここで心を落ち着けてから参詣に向かうべき雰囲気があります。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 参道


【写真 上(左)】 ことぶき地蔵尊
【写真 下(右)】 山門
参道まわりに札所碑、地蔵立像、ことぶき地蔵尊など、はやくも見どころがつづきます。
そのおくに山門。
この山門は「大門」と呼ばれ、棟木墨書から伏見の柿浜御門が移築されたものとみられます。本瓦葺でおそらく薬医門かと思います。


【写真 上(左)】 御府内霊場札所碑
【写真 下(右)】 江戸六阿弥陀札所碑


【写真 上(左)】 中門
【写真 下(右)】 秋の山内


【写真 上(左)】 秋の地蔵堂と参道
【写真 下(右)】 地蔵堂と鐘楼
さらに桟瓦葺の中門を回り込んで進む奥行きのある山内。
緑ゆたかな山内は手入れも行き届き、枯淡な風情を湛えています。
御府内霊場のなかでも屈指の雰囲気ある寺院かと思います。
左手に地蔵堂と鐘楼を見て、さらに進みます。


【写真 上(左)】 見事な紅葉
【写真 上(左)】 冬の山内


【写真 上(左)】 早春の本堂
【写真 下(右)】 秋の本堂


【写真 上(左)】 右斜め前から本堂
【写真 下(右)】 向拝
正面に本堂、向かって右手に大師堂、左手に進むと庫裡があります。
本堂前では数匹のおネコちゃんがくつろいでいます。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 まどろむネコ
本堂は、寄棟造平入りで起り屋根の向拝を付設。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
扁額は「無量寺」。格天井。向拝屋根には「佛寶山」の山号を置く鬼板と兎毛通。
落ち着いた庭園に見合う、風雅な仏堂です。
『江戸名所図会』には、「(本堂の)『南無阿彌陀佛』の額ハ幡随意院磧了和尚の筆なり」とあります。
幡随意院磧了和尚はおそらく幡随院(神田駿河台、現・小金井市)開山の高僧と思われます。
幡随意上人(1542-1615年)は京都百万遍知恩寺の33世住持で、徳川家康公の帰依を得て神田駿河台に新知恩寺(のちの幡随院)を開創されました。
浄土宗本流の幡随意上人揮毫の扁額が、新義真言宗の当山にある理由は不明です。
幡随意上人は鎌倉の光明寺で浄土教学を修められたとされ、光明寺のそばには真言僧・願行上人に関係する安養院があるので、なにかの機会に真言宗と関係をもたれたのかもしれません。(これはさすがに牽強附会か?)
強引に安養院まで辿らなくとも、弘法大師 相模二十一ヶ所霊場(→ 札所リスト(「ニッポンの霊場」様))の札所には光明寺の子院・蓮乗院(第11番)が名を連ねているので、光明寺と真言宗はなんらかの関連があったのかもしれません。
→ 関連記事(■ 鎌倉市の御朱印-7 (24.祇園山 田代寺(長楽寺) 安養院)
本堂には御本尊の不動明王像と阿弥陀如来坐像が御座します。
御本尊の不動明王像は「当寺に忍び込んだ盗賊が不動明王像の前で急に動けなくなり、翌朝捕まったことから『足止め不動』として信仰されるようになった」という逸話が伝わります。
また、『江戸名所図会』には、不動尊は弘法大師の御作とあります。
阿弥陀如来像は、江戸時代に江戸六阿弥陀詣(豊島西福寺・沼田延命院(現・足立区恵明寺)・西ヶ原無量寺・田端与楽寺・下谷広小路常楽院(現・調布市)・亀戸常光寺)の第三番目として広く信仰を集めた阿弥陀様です。
→ ■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印
以前は阿弥陀堂に御座とみられ、『江戸名所図会』には「阿弥陀堂 本堂の右にあり 本尊ハ行基菩薩の作 録阿弥陀第三番目なり」とあります。


【写真 上(左)】 大師堂
【写真 上(左)】 大師堂の堂号板
本堂向かって右手の大師堂は宝形造桟瓦葺で向拝を付設し、向拝柱に「大師堂」の板標。
大師堂には恵心作と伝わる聖観世音菩薩像が安置され、「雷除けの本尊」として知られています。
本堂のそばには上野王子駒込辺三十三観音霊場第3番の札所標。
札所本尊は聖観世音菩薩と伝わるのでこの「雷除けの本尊」が札所本尊なのかもしれません。
御朱印は本堂向かって左の庫裡で拝受できます。
原則として書置はないようで、ご住職ご不在時は郵送にてご対応いただけます。
なお、複数の霊場の御朱印を授与されておられるので、事前に参詣目的の霊場を申告した方がよろしいかと思います。
素晴らしい風情をもつお寺さまですが、山内の環境保全のため団体での入山は禁止されています。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

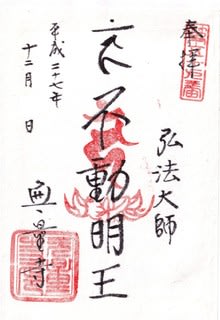
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に不動明王の種子のお種子「カン/カーン」「不動明王」「弘法大師」の揮毫と「カン/カーン」の御寶印(蓮華座)。
右に「第五十九番」の札所印。左に寺号の揮毫と寺院印が捺されています


【写真 上(左)】 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 江戸六阿弥陀如来の御朱印
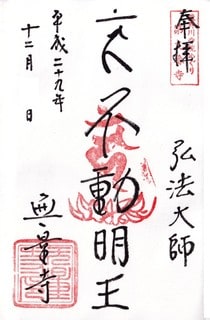
■ 滝野川寺院めぐりの御朱印
■ 第60番 摩尼山 隆全寺 吉祥院
(きっしょういん)
台東区元浅草2-1-14
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第60番、弘法大師二十一ヶ寺第11番
第60番は元浅草の吉祥院です。
第60番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに吉祥院で、第60番札所は開創当初から元浅草(浅草新寺町)の吉祥院であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
吉祥院の創建年代は不詳ですが開山宥教法印は万治三年(1660年)寂なので、それ以前の創建とみられます。
慶長十六年(1611年)に中野寺町に寺地を拝領、寛永二十一年(1644年)当地・浅草新寺町へ移転と伝わります。
御本尊は阿弥陀如来木立像。両脇に弘法大師、輿教大師を奉安。
護摩堂には聖天尊、不動尊、薬師佛、稲荷神を奉安と伝わります。
『御府内八十八ケ所道しるべ』には「本尊:阿弥陀如来 観世音菩薩 弘法大師」とあるので、観音様も奉安していたとみられます。
山内には秀明院、長寿院の二軒の塔頭を擁したといいます。
当山は史料が少なく、これ以上は辿れませんでした。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
六十番
浅草新寺町
摩尼山 降全寺 吉祥院
大塚護持院末 新義
本尊:阿弥陀如来 観世音菩薩 弘法大師
■ 『寺社書上 [80] 浅草寺社書上 甲五』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.56』
浅草新寺町
江戸大塚護持院末
摩尼山隆全寺吉祥院
拙寺起立之年代旧記に無く候得共 往古慶長十六年(1611年) 中野寺町地拝領仕●在候所 御用地二付所替被● 寛永二十一年(1644年)中当処●引移候由申伝候
開山 宥教法印 万治三年(1660年)寂
本堂
本尊 阿弥陀如来木立像 両脇弘法大師 輿教大師
護摩堂
聖天尊 不動尊 薬師佛 稲荷
地中二軒
秀明院
長寿院 右往古寛永二十一年(1644年)中当所●引移り候迄二ヶ院有之候処 長寿院儀は 地狭二付外●借地仕引越申候由申伝 秀明院儀●残り有之候処 其後年代不知退転仕候由申伝

「吉祥院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)
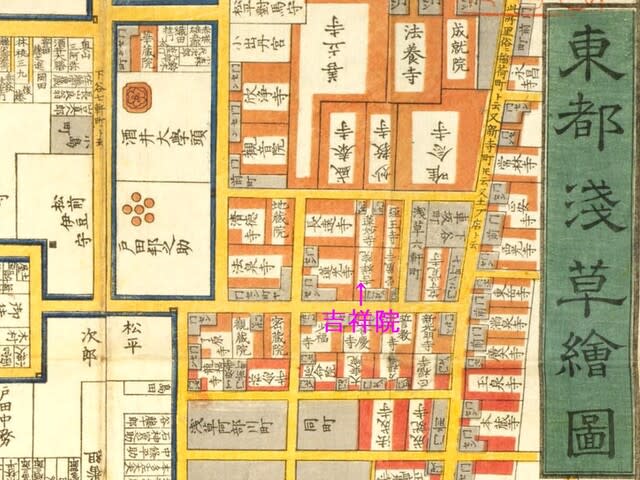
原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ銀座線「稲荷町」駅で徒歩約5分。
元浅草~寿とつづく、御府内霊場札所密集エリアにあります。
都道463号浅草通り「松が谷一丁目」交差点から左右衛門橋通りを南に入り少し行った右手(西側)です。

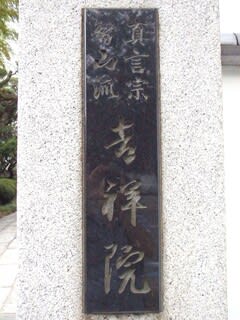
【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 院号標
市街地のなかにかなり広い山内を構えています。
山内入口手前に御府内霊場札所標。門柱に院号標。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 山内
緑ゆたかな境内は、よく手入れされてきもちがいいです。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
参道正面に宝形造ないし寄棟造桟瓦葺の本堂。
流れ向拝で、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
向拝左右の花頭窓が意匠的に効いています。
向拝上部に掲げられた扁額は達筆すぎて筆者には解読できません。


【写真 上(左)】 斜めからの向拝
【写真 下(右)】 扁額
『ルートガイド』によると、参道右手には御嶽山中興の祖・普寛行者の「贈大教普寛霊尊供養塔」(山岡鉄太郎(鉄舟)揮毫)があるそうですが、筆者はうかつにも撮りわすれました。
史料類からはうかがい知れませんが、御嶽修験となんらかの繋がりがあったのかもしれません。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に阿弥陀如来のお種子「キリーク」の揮毫と「本尊 阿弥陀如来」の印判。
右に「御府内八十八ヶ所第六十番」の札所印。
左に院号印と寺院印が捺されています。
紙面には御寶印も三寶印もありませんが、お種子「キリーク」の揮毫で御朱印となっています。
なお、平成27年に拝受した御朱印(御朱印帳揮毫)の尊格は「本尊 阿弥陀如来」の揮毫と「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)から構成されています。
Web検索すると、平成31年頃までは両パターンの御朱印がみつかりますが、令和に入ってからはお種子揮毫のパターンに統一されている模様です。
■ 第61番 望月山 般若寺 正福院
(しょうふくいん)
公式Web
台東区元浅草4-7-21
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第61番、弘法大師二十一ヶ寺第14番
第61番は元浅草の正福院です。
第61番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに正福院で、第61番札所は開創当初から浅草新寺町(元浅草)の正福院であったとみられます。
公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
正福院は慶長十六年(1611年)に、浜町橘町(現・中央区日本橋浜町)あたりで開創されたといいます。(草創の地は中野寺町とも。)
正保元年(1645年)、3代将軍徳川家光公の治世に、大塚の護持院の末寺として当地を拝領して移転しています。
開山は僧・源秀。
開基は橘町三丁目の名主を勤めた望月貞久ないしその子孫(廣壽院其融到行居士)で、その功績を称えて山号を「望月山(ぼうげつざん)」と号しました。
御本尊は金剛界大日如来。
本堂には弘法大師・興教大師両木座像も奉安し、御府内霊場としての体裁を整えていました。
山内に御座の六地蔵木立像は小野篁の御作、収蔵する両界曼荼羅は興教大師の御筆とも伝わります。
『御府内寺社備考』等によると享保三年(1718年)、開基ともされる望月貞久の子孫が夢中で洛東稲荷山(伏見稲荷)の稲荷大明神翁より「一顆の玉と弘法大師作の十一面観世音菩薩像を与えるにより此処に一社を建立すべし」とのお告げを受け、伏見稲荷を勧請して一社を建立しました。
伏見稲荷のお社は当院の柳の木の下に建立されたので、「柳の稲荷」と呼ばれて尊崇を集めました。
『御府内八十八ケ所道しるべ』には「浅草新寺町柳のいなり別当」とあり、当山が「柳の稲荷」の別当として捉えられていたことがわかります。
明治初頭の神仏分離を乗り越え御府内霊場札所を守りましたが、昭和20年の東京大空襲ですべての堂宇を焼失しました。
本堂は昭和28年に再建され、戦禍を遁れた御本尊の金剛界大日如来、弘法大師像、興教大師はいまも本堂内に御座されます。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
六十一番
浅草新寺町柳のいなり別当
望月山 般若寺 正福院
大塚護持院末 新義
本尊:金剛界大日如来 柳稲荷大明神 弘法大師
■ 『寺社書上 [80] 浅草寺社書上 甲五』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.54』
浅草新寺町
江戸大塚護持院末
望月山正福院
慶長十六年(1611年)起立●申伝候 寛永(1624-1644年)之末●野寺町と申処二●在
其後正保元年(1645年)当所●拝領仕候
開山 源秀 寛永十四年(1637年)遷化
開基 廣壽院其融到行居士 元禄十三年(1700年)卒 俗姓望月貞久子孫今幾八郎と称シ、橘町三丁目名主役ヲ勤
本堂
本尊 金剛界大日如来
弘法大師木座像 興教大師木座像 六地蔵木立像(長三尺小野篁作) 不動尊木立像(長四寸五分生駒宝山作)両界曼荼羅(興教大師筆)
鎮守柳稲荷社
神体 長七寸五分弘法大師作 本地十一面観世音。
(縁起記載あり略)
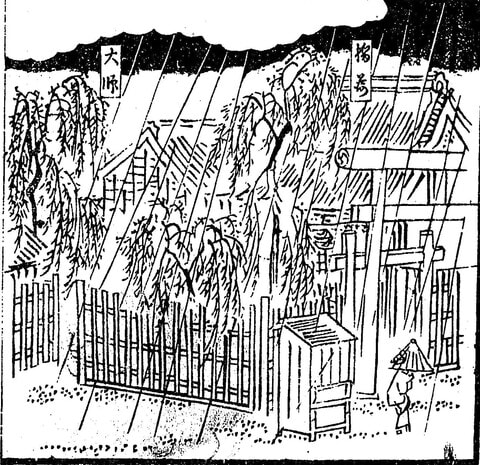
「正福院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
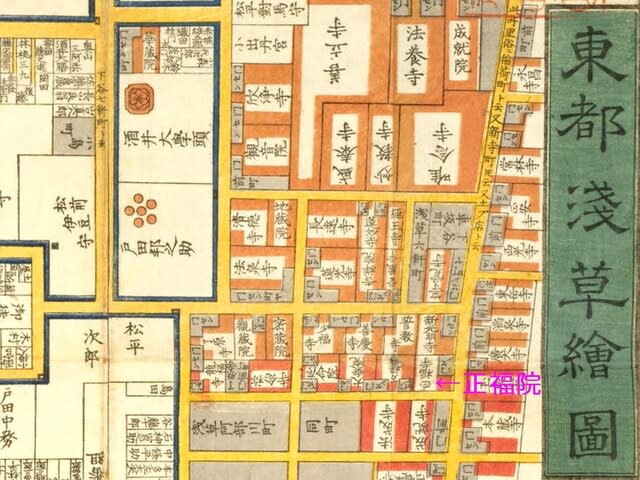
原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ銀座線「稲荷町」駅で徒歩約5分。
都道463号浅草通り「松が谷一丁目」交差点から一本東寄りの路地を南に入ってすぐ。
光明寺とは背中合わせで、江戸切絵図の配置と一致しています。
このあたりは元浅草~寿とつづく御府内霊場札所の集中エリアで、正福院の公式Webにあるとおり、メトロ銀座線「稲荷町」駅から「田原町」駅まで、一筆書きの順路で9箇所の札所を巡ることができます。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 札所標
街路から若干引き込んで参道入口。
その門柱手前には御府内霊場の札所標。
門柱の院号札には「浅草區南松山町九番地」とあります。
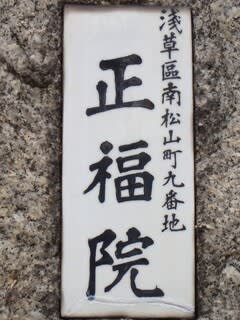

【写真 上(左)】 門柱の院号標
【写真 下(右)】 山内


【写真 上(左)】 観世音菩薩と地蔵尊
【写真 下(右)】 釈迦如来と地蔵尊
参道左手には白衣観世音菩薩と地蔵菩薩の立像で、いずれもおだやかな面立ち。
山内・墓域入口手前の壁際には東京大空襲の戦火により黒くすすけた釈迦如来立像と2体の地蔵尊が御座します。
古にはこのあたりに「柳稲荷」ゆかりの柳の木があったそうです。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 札所板
参道正面の本堂は入母屋造桟瓦葺とみられ、おそらく妻入りです。
奥行きのある敷地形状のため、妻入り様式としたのでは。
妻入り特有の千鳥破風を2連構成しています。
公式Webによると、本堂御内陣には正面に御本尊の金剛界大日如来坐像。
向かって右に牀座に結跏趺坐され五鈷杵と数珠を握られる真如親王様の弘法大師像。
向かって左には興教大師像が安置されているようです。
御朱印は御府内霊場の札所板が掛かる、本堂向かって右手前の庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

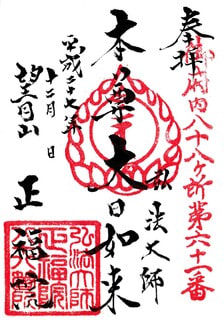
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 大日如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「御府内八十八ヶ所第六十一番」の札所印。
左に山号・院号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第62番 鶴亭山 隆全寺 威光院
(いこういん)
公式Web
台東区寿2-6-8
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第62番、弘法大師二十一ヶ寺第16番
第62番は寿の威光院です。
第62番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに威光院で、第62番札所は開創当初から浅草新堀端の威光院であったとみられます。
公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
威光院は太田道灌公によって「江戸城鎮守の別当として創建」といいます。
『ルートガイド』ではこの江戸城鎮守を「平川天神」(現・平河天満宮)としています。
平河天満宮の公式Web・現地掲示によると、「平川天神」の創祀は以下のとおりです。
江戸平河城城主の太田道灌公が、ある日菅原道真公の夢を見ました。
その翌朝に菅原道真公自筆の画像を贈られたため、道灌公はこの夢を霊夢と感じ、文明十年(1478年)に城内の北に自ら施主となり江戸の守護神として天満宮を建立しました。(「梅花無尽蔵」による)
家康公の江戸城入城後、築城のため平川門外に奉遷、慶長十二年(1607年)2代将軍秀忠公により現在地(貝塚)に奉遷され、本社にちなみこの地を平河町と名付けられました。
平河天満宮は、徳川幕府をはじめ紀州、尾張両徳川家、井伊家等の祈願所となり、新年の賀礼には宮司は将軍に単独拝謁できる高い格式を有していました。

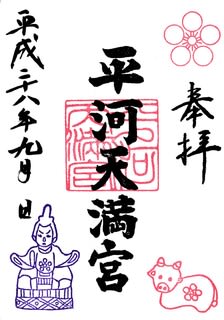
【写真 上(左)】 平河天満宮
【写真 下(右)】 平河天満宮の御朱印
威光院の公式Webには「平川天神」との所縁は記されておらず、平河天満宮の公式Webにも威光院との関係は記されていないので、『ルートガイド』が威光院を「平川天神」の別当とした根拠は不明です。
なお、『ルートガイド』には「(平川天神の)別当として鶴主計延豊が開基となって創建されたのが威光院」と明記されているので、これを記す寺伝等があるのかもしれません。
本堂御本尊は大日如来。護摩堂の不動明王は恵心僧都の作と伝わります。
その後櫻田村に移転、慶長六年(1600年)には八丁堀に遷り、文禄三年(1594年)ないし元和元年(1615年)辨清法印により現在地に移転再興(あるいは開山とも)といいます。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
六十二番
浅くさ新堀端
鶴亭山 般若寺 威光院
愛宕圓福寺末 新義
本尊:大日如来 不動明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [75] 浅草寺社書上 甲二』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.107』
浅草新堀端
芝愛宕前(下)圓福寺末 新義真言宗
鶴亭山威光院
当寺起立之年代不詳
開山 法印辨清 元和五年(1619年)三月寂
中興 法印秀仙 安永七年(1778年)七月寂
本堂
本尊 大日如来木佛坐像
護摩堂
不動明王 二童子アリ 恵心僧都作

「威光院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ銀座線「田原町」駅で徒歩約3分。
都道463号浅草通り「菊屋橋」交差点から新堀通りを南下して少し行った左手です。
この「新堀通り」は江戸切絵図では川沿いの通りとして記され、「此川ヲ新堀ト云」とあります。
新堀沿いに描かれている宗圓寺、永見寺、威光院、常福寺はいずれも「新堀通り」沿いに現存しています。
元浅草~寿界隈は郊外へ移転した寺院が少なく、江戸切絵図に描かれた寺院がよく残っています。

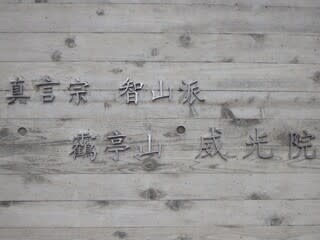
【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 壁面の院号標
コンクリ打放しの門塀、石敷き参道のおくにモダンな本堂は、美術感のようなイメージ。
外構も含めて2014年に一新された模様です。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 本堂
調べてみると設計は現・京都大学名誉教授の建築家・竹山聖氏。
(→ 情報元・『お宮、お寺を散歩しよう』様(紋谷幹男氏))
門塀にはステンレス浮き文字で山号・院号標。
参道右手には大師講の巡拝祈念碑、六地蔵、修行大師像とならび、本堂前には御府内霊場札所標も建っています。


【写真 上(左)】 霊場巡拝碑
【写真 下(右)】 六地蔵


【写真 上(左)】 修行大師像
【写真 下(右)】 札所標
新旧がほどよく調和した素晴らしい空間ですが、筆者の拙い知識ではこれをうまく表現できません(笑)
紋谷幹男氏のキレ味鋭い解説(→ こちら)をご覧くださいませ。
紋谷幹男氏の「当代きっての腕の立つ建築家の、おそろしくエッジの効いたお寺」。
この表現がぴったりの空間だと思います。
御府内霊場巡拝の旨お伝えすると、本堂内にお通しいただけました。
本堂内もコンクリ打ち放しで天井が赤く井桁に組まれた天吊りに天蓋が掛けられています。
(本堂内の様子は→ こちら)
護摩壇の向こうに智拳印を結ばれる金剛界大日如来坐像。
堂内の音響がすこぶるよく、読経の声が響きわたります。
東京のお遍路である御府内霊場。
このような斬新な空間はならではのものかと思います。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
公式Webには「御府内八十八ヶ所霊場とは弘法大師とゆかりがある寺院を巡る、四国八十八カ所の江戸版のようなモノで、 六十二番札所である当院ではお参りされた方に御朱印を承っております。※霊場専用の御朱印帳(納経帳)が御座いますので、出来ればそちらを推奨しております」とあります。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

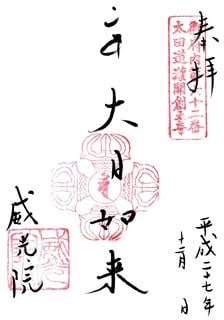
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に金剛界大日如来ののお種子「バン」「大日如来」の揮毫と「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「御府内六十二番」の札所印。
左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
※平成27年に拝受の御朱印の主印は御寶印(羯磨金剛(かつまこんごう))で、「太田道灌開創立寺」の印判があります。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-21)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ 瞳がほほえむから - 今井美樹
■ ebb and flow - LaLa(歌ってみた)
■ ヒカリヘ - miwa
→ ■ 透明感のある女性ヴォーカル50曲
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第59番 佛寶山 西光院 無量寺
(むりょうじ)
北区西ヶ原1-34-8
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
司元別当:七社(旧西ヶ原村総鎮守)
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第59番、豊島八十八ヶ所霊場第59番、江戸六阿弥陀如来第3番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第3番、大東京百観音霊場第81番
※本記事は「■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印」および「■ 滝野川寺院めぐり-2」から転載・追記したものです。
第59番は北区西ヶ原の無量寺です。
第59番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに無量寺で、第59番札所は開創当初から西ヶ原の無量寺であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
無量寺の創建年代は不明ですが、『滝野川寺院めぐり案内』には「現在当山には9~10世紀の未完成の木像菩薩小像と、12世紀末の都風といわれる等身の阿弥陀如来像が安置されている。さらに正和元年(1312年)、建武元年(1334年)の年号を始めとする30数枚の板碑が境内から出土しているから、少なくとも平安時代の後期には、この地に寺があったことはまず間違いないであろう。」と記されています。
『江戸名所図会』には開山は行基菩薩とあり、これは江戸六阿弥陀の縁起からきているものとみられます。
北区設置の山内説明板には『新編武蔵国風土記稿』や寺伝等には、慶安元年(1648年)に幕府から八石五斗余の年貢・課役を免除されたこと、元禄十四年(1701年)五代将軍綱吉公の生母桂昌院が参詣したこと、以前は長福寺と号していたが、寺号が九代将軍家重公の幼名長福丸と同じであるため、これを避けて現在の名称に改めたことなどが記されています。
江戸時代には広大な寺領を有していたとみられ、当山が別当を勤めた「七社」はその境内に鎮座されていたと伝わります。
『江戸名所図会』には無量寺山内とみられる高台(現・旧古河庭園)に「七社」があらわされ、現・旧古河庭園の一部も無量寺の境内であったのでは。
大正3年(1914年)、古河財閥3代当主の古河虎之助が周囲の土地を購入したという記録があるので、その時に古河家に移った可能性があります。
なお、「七社」は神仏分離の翌年明治二年(1869年)に一本杉神明宮の社地(現・七社神社)に御遷座されています。


【写真 上(左)】 七社神社の社頭
【写真 下(右)】 七社神社の境内
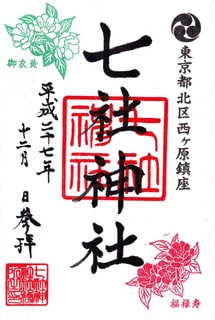

【上(左)】 七社神社の御朱印(旧)
【下(右)】 七社神社の御朱印
西ヶ原村の総鎮守であった七社神社には、西ヶ原村内に飛鳥山邸(別荘)を構えた渋沢栄一翁が氏子として重きをなし、所縁の品々が残されています。
無量寺は御府内霊場のほか、江戸時代、春夏のお彼岸にとくに賑わったといわれる江戸六阿弥陀詣の一寺(第3番目)で、もともと参詣者の多かった寺院とみられます。
また、豊島八十八ヶ所霊場第59番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第3番、滝野川寺院めぐり第9番の札所でもあります。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
五十九番
西ヶ原村
佛宝山 西光院 無量寺
大塚護持院末 新義
本尊:不動明王 弘法大師 興教大師
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
新義真言宗佛寶山西光院ト号ス 慶安元年(1648年)寺領八石五斗餘ノ御朱印ヲ附ラル 古ハ田端村與楽寺ノ末ナリシカ 常憲院殿厳命ヲ以テ大塚護持院ノ末トナレリ 又昔ハ長福寺ト称セシヲ 惇信院殿の御幼名ヲ避テ今ノ寺号ニ改ムト云 本尊不動外ニ正観音ノ立像ヲ置 長三尺五寸許惠心ノ作ニテ 雷除の本尊トイヘリ 中興眞惠享保三年(1718年)閏正月廿三日化ス 今ノ堂ハ昔村内ニ建置レシ御殿御取拂トナリシヲ賜リテ建シモノナリト云 元境内ニ母衣櫻ト名ツケシ櫻樹アリシカ今ハ枯タリ 母衣ノ名ハ寛永(1624-1644年)ノ頃御成アリシ時名ツケ給ヒシト云伝フ
寺寶
紅頗梨色彌陀像一幅 八組大師像八幅 妙澤像一幅 不動像一幅 六字名號一幅。以上弘法大師ノ筆ト云 其内名號ニハ大僧都空海ト落款アリ 菅家自畫像一幅
七所明神社 村ノ鎮守トス 紀伊國高野山四社明神ヲ寫シ祀リ天照大神 春日 八幡三座を合祀ス 故ニ七所明神ト号ス
末社ニ天神 稲荷アリ 辨天社
阿彌陀堂 行基の作 坐像長三尺許六阿弥陀ノ第三番ナリ 観音堂 西國三十三所札所寫ナリ 鐘樓 安永九年鑄造ノ鐘ヲ掛
寺中勝蔵院 不動ヲ本尊トス
■ 『江戸名所図会 十五』(国立国会図書館)
真言宗にして弘法大師の作の不動尊を本尊とし 開山ハ行基菩薩なり 本堂に●●る南無阿彌陀佛の額ハ幡随意院磧了和尚の筆なり
阿弥陀堂 本堂の右にあり 本尊ハ行基菩薩の作 録阿弥陀第三番目なり

「無量寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
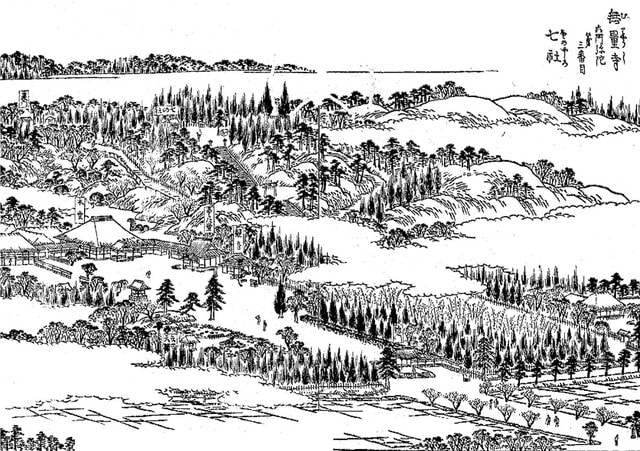
「無量寺」/原典:斎藤長秋 編 ほか『江戸名所図会』十五,博文館,1893.12. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは東京メトロ南北線「西ヶ原」駅で徒歩約7分。
JR「上中里」駅からも徒歩7分ほどですが、こちらは坂の上り下りがあるので下りのみの「西ヶ原」駅の方が楽です。
このあたりの主要道は、不忍通り、白山通り(中山道)など谷間を走る例が多いですが、本郷通りは例外で、律儀に馬の背の台地上を辿ります。
第47番城官寺、あるいは西ヶ原駅・上中里駅からだと本郷通りからの道順となり、かなりの急坂を下ってのアブローチとなります。
旧古河庭園の裏手にあたるこの坂道は木々に囲まれほの暗く、落ち着いた風情があります。
旧古河庭園は陸奥宗光や古河財閥の邸宅で、このあたりは府内屈指の高級住宅地であったことがうかがわれます。
いまでも落ち着いた邸宅がならぶ一画があり、いかにも東京山の手地付きの富裕層が住んでいそうな感じがあります。
内田康夫氏の人気推理小説「浅見光彦シリーズ」の主人公浅見光彦は西ヶ原出身の設定で、家柄がよく、相応の教養や見識を身につけていることなどは、このあたりの地柄を物語るものかもしれません。(内田康夫氏自身が西ヶ原出身らしい。)
坂を下りきり、右手に回り込むと参道入口です。
入口回りは車通りも少なく、相応の広さを保って名刹の風格を感じます。
ここで心を落ち着けてから参詣に向かうべき雰囲気があります。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 参道


【写真 上(左)】 ことぶき地蔵尊
【写真 下(右)】 山門
参道まわりに札所碑、地蔵立像、ことぶき地蔵尊など、はやくも見どころがつづきます。
そのおくに山門。
この山門は「大門」と呼ばれ、棟木墨書から伏見の柿浜御門が移築されたものとみられます。本瓦葺でおそらく薬医門かと思います。


【写真 上(左)】 御府内霊場札所碑
【写真 下(右)】 江戸六阿弥陀札所碑


【写真 上(左)】 中門
【写真 下(右)】 秋の山内


【写真 上(左)】 秋の地蔵堂と参道
【写真 下(右)】 地蔵堂と鐘楼
さらに桟瓦葺の中門を回り込んで進む奥行きのある山内。
緑ゆたかな山内は手入れも行き届き、枯淡な風情を湛えています。
御府内霊場のなかでも屈指の雰囲気ある寺院かと思います。
左手に地蔵堂と鐘楼を見て、さらに進みます。


【写真 上(左)】 見事な紅葉
【写真 上(左)】 冬の山内


【写真 上(左)】 早春の本堂
【写真 下(右)】 秋の本堂


【写真 上(左)】 右斜め前から本堂
【写真 下(右)】 向拝
正面に本堂、向かって右手に大師堂、左手に進むと庫裡があります。
本堂前では数匹のおネコちゃんがくつろいでいます。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 まどろむネコ
本堂は、寄棟造平入りで起り屋根の向拝を付設。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
扁額は「無量寺」。格天井。向拝屋根には「佛寶山」の山号を置く鬼板と兎毛通。
落ち着いた庭園に見合う、風雅な仏堂です。
『江戸名所図会』には、「(本堂の)『南無阿彌陀佛』の額ハ幡随意院磧了和尚の筆なり」とあります。
幡随意院磧了和尚はおそらく幡随院(神田駿河台、現・小金井市)開山の高僧と思われます。
幡随意上人(1542-1615年)は京都百万遍知恩寺の33世住持で、徳川家康公の帰依を得て神田駿河台に新知恩寺(のちの幡随院)を開創されました。
浄土宗本流の幡随意上人揮毫の扁額が、新義真言宗の当山にある理由は不明です。
幡随意上人は鎌倉の光明寺で浄土教学を修められたとされ、光明寺のそばには真言僧・願行上人に関係する安養院があるので、なにかの機会に真言宗と関係をもたれたのかもしれません。(これはさすがに牽強附会か?)
強引に安養院まで辿らなくとも、弘法大師 相模二十一ヶ所霊場(→ 札所リスト(「ニッポンの霊場」様))の札所には光明寺の子院・蓮乗院(第11番)が名を連ねているので、光明寺と真言宗はなんらかの関連があったのかもしれません。
→ 関連記事(■ 鎌倉市の御朱印-7 (24.祇園山 田代寺(長楽寺) 安養院)
本堂には御本尊の不動明王像と阿弥陀如来坐像が御座します。
御本尊の不動明王像は「当寺に忍び込んだ盗賊が不動明王像の前で急に動けなくなり、翌朝捕まったことから『足止め不動』として信仰されるようになった」という逸話が伝わります。
また、『江戸名所図会』には、不動尊は弘法大師の御作とあります。
阿弥陀如来像は、江戸時代に江戸六阿弥陀詣(豊島西福寺・沼田延命院(現・足立区恵明寺)・西ヶ原無量寺・田端与楽寺・下谷広小路常楽院(現・調布市)・亀戸常光寺)の第三番目として広く信仰を集めた阿弥陀様です。
→ ■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印
以前は阿弥陀堂に御座とみられ、『江戸名所図会』には「阿弥陀堂 本堂の右にあり 本尊ハ行基菩薩の作 録阿弥陀第三番目なり」とあります。


【写真 上(左)】 大師堂
【写真 上(左)】 大師堂の堂号板
本堂向かって右手の大師堂は宝形造桟瓦葺で向拝を付設し、向拝柱に「大師堂」の板標。
大師堂には恵心作と伝わる聖観世音菩薩像が安置され、「雷除けの本尊」として知られています。
本堂のそばには上野王子駒込辺三十三観音霊場第3番の札所標。
札所本尊は聖観世音菩薩と伝わるのでこの「雷除けの本尊」が札所本尊なのかもしれません。
御朱印は本堂向かって左の庫裡で拝受できます。
原則として書置はないようで、ご住職ご不在時は郵送にてご対応いただけます。
なお、複数の霊場の御朱印を授与されておられるので、事前に参詣目的の霊場を申告した方がよろしいかと思います。
素晴らしい風情をもつお寺さまですが、山内の環境保全のため団体での入山は禁止されています。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

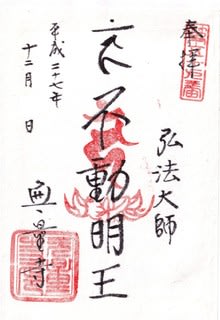
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に不動明王の種子のお種子「カン/カーン」「不動明王」「弘法大師」の揮毫と「カン/カーン」の御寶印(蓮華座)。
右に「第五十九番」の札所印。左に寺号の揮毫と寺院印が捺されています


【写真 上(左)】 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 江戸六阿弥陀如来の御朱印
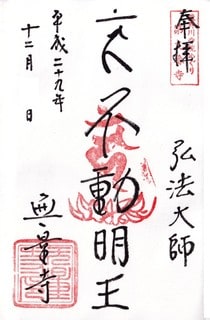
■ 滝野川寺院めぐりの御朱印
■ 第60番 摩尼山 隆全寺 吉祥院
(きっしょういん)
台東区元浅草2-1-14
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第60番、弘法大師二十一ヶ寺第11番
第60番は元浅草の吉祥院です。
第60番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに吉祥院で、第60番札所は開創当初から元浅草(浅草新寺町)の吉祥院であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
吉祥院の創建年代は不詳ですが開山宥教法印は万治三年(1660年)寂なので、それ以前の創建とみられます。
慶長十六年(1611年)に中野寺町に寺地を拝領、寛永二十一年(1644年)当地・浅草新寺町へ移転と伝わります。
御本尊は阿弥陀如来木立像。両脇に弘法大師、輿教大師を奉安。
護摩堂には聖天尊、不動尊、薬師佛、稲荷神を奉安と伝わります。
『御府内八十八ケ所道しるべ』には「本尊:阿弥陀如来 観世音菩薩 弘法大師」とあるので、観音様も奉安していたとみられます。
山内には秀明院、長寿院の二軒の塔頭を擁したといいます。
当山は史料が少なく、これ以上は辿れませんでした。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
六十番
浅草新寺町
摩尼山 降全寺 吉祥院
大塚護持院末 新義
本尊:阿弥陀如来 観世音菩薩 弘法大師
■ 『寺社書上 [80] 浅草寺社書上 甲五』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.56』
浅草新寺町
江戸大塚護持院末
摩尼山隆全寺吉祥院
拙寺起立之年代旧記に無く候得共 往古慶長十六年(1611年) 中野寺町地拝領仕●在候所 御用地二付所替被● 寛永二十一年(1644年)中当処●引移候由申伝候
開山 宥教法印 万治三年(1660年)寂
本堂
本尊 阿弥陀如来木立像 両脇弘法大師 輿教大師
護摩堂
聖天尊 不動尊 薬師佛 稲荷
地中二軒
秀明院
長寿院 右往古寛永二十一年(1644年)中当所●引移り候迄二ヶ院有之候処 長寿院儀は 地狭二付外●借地仕引越申候由申伝 秀明院儀●残り有之候処 其後年代不知退転仕候由申伝

「吉祥院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)
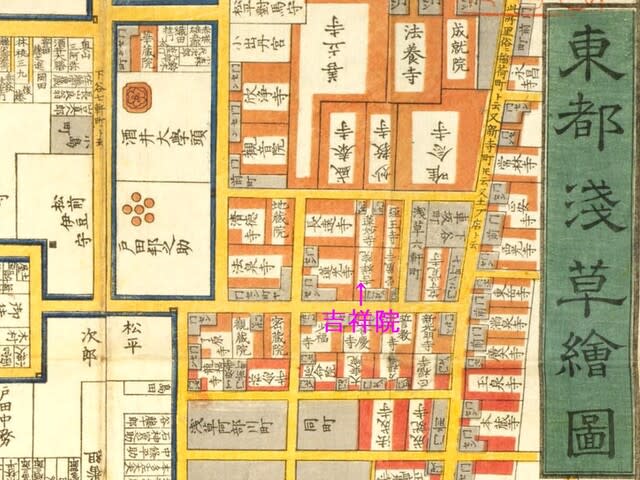
原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ銀座線「稲荷町」駅で徒歩約5分。
元浅草~寿とつづく、御府内霊場札所密集エリアにあります。
都道463号浅草通り「松が谷一丁目」交差点から左右衛門橋通りを南に入り少し行った右手(西側)です。

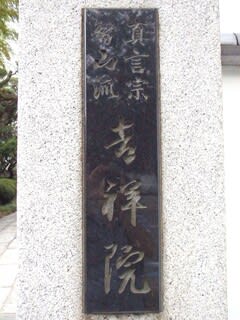
【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 院号標
市街地のなかにかなり広い山内を構えています。
山内入口手前に御府内霊場札所標。門柱に院号標。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 山内
緑ゆたかな境内は、よく手入れされてきもちがいいです。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
参道正面に宝形造ないし寄棟造桟瓦葺の本堂。
流れ向拝で、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
向拝左右の花頭窓が意匠的に効いています。
向拝上部に掲げられた扁額は達筆すぎて筆者には解読できません。


【写真 上(左)】 斜めからの向拝
【写真 下(右)】 扁額
『ルートガイド』によると、参道右手には御嶽山中興の祖・普寛行者の「贈大教普寛霊尊供養塔」(山岡鉄太郎(鉄舟)揮毫)があるそうですが、筆者はうかつにも撮りわすれました。
史料類からはうかがい知れませんが、御嶽修験となんらかの繋がりがあったのかもしれません。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に阿弥陀如来のお種子「キリーク」の揮毫と「本尊 阿弥陀如来」の印判。
右に「御府内八十八ヶ所第六十番」の札所印。
左に院号印と寺院印が捺されています。
紙面には御寶印も三寶印もありませんが、お種子「キリーク」の揮毫で御朱印となっています。
なお、平成27年に拝受した御朱印(御朱印帳揮毫)の尊格は「本尊 阿弥陀如来」の揮毫と「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)から構成されています。
Web検索すると、平成31年頃までは両パターンの御朱印がみつかりますが、令和に入ってからはお種子揮毫のパターンに統一されている模様です。
■ 第61番 望月山 般若寺 正福院
(しょうふくいん)
公式Web
台東区元浅草4-7-21
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第61番、弘法大師二十一ヶ寺第14番
第61番は元浅草の正福院です。
第61番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに正福院で、第61番札所は開創当初から浅草新寺町(元浅草)の正福院であったとみられます。
公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
正福院は慶長十六年(1611年)に、浜町橘町(現・中央区日本橋浜町)あたりで開創されたといいます。(草創の地は中野寺町とも。)
正保元年(1645年)、3代将軍徳川家光公の治世に、大塚の護持院の末寺として当地を拝領して移転しています。
開山は僧・源秀。
開基は橘町三丁目の名主を勤めた望月貞久ないしその子孫(廣壽院其融到行居士)で、その功績を称えて山号を「望月山(ぼうげつざん)」と号しました。
御本尊は金剛界大日如来。
本堂には弘法大師・興教大師両木座像も奉安し、御府内霊場としての体裁を整えていました。
山内に御座の六地蔵木立像は小野篁の御作、収蔵する両界曼荼羅は興教大師の御筆とも伝わります。
『御府内寺社備考』等によると享保三年(1718年)、開基ともされる望月貞久の子孫が夢中で洛東稲荷山(伏見稲荷)の稲荷大明神翁より「一顆の玉と弘法大師作の十一面観世音菩薩像を与えるにより此処に一社を建立すべし」とのお告げを受け、伏見稲荷を勧請して一社を建立しました。
伏見稲荷のお社は当院の柳の木の下に建立されたので、「柳の稲荷」と呼ばれて尊崇を集めました。
『御府内八十八ケ所道しるべ』には「浅草新寺町柳のいなり別当」とあり、当山が「柳の稲荷」の別当として捉えられていたことがわかります。
明治初頭の神仏分離を乗り越え御府内霊場札所を守りましたが、昭和20年の東京大空襲ですべての堂宇を焼失しました。
本堂は昭和28年に再建され、戦禍を遁れた御本尊の金剛界大日如来、弘法大師像、興教大師はいまも本堂内に御座されます。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
六十一番
浅草新寺町柳のいなり別当
望月山 般若寺 正福院
大塚護持院末 新義
本尊:金剛界大日如来 柳稲荷大明神 弘法大師
■ 『寺社書上 [80] 浅草寺社書上 甲五』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.54』
浅草新寺町
江戸大塚護持院末
望月山正福院
慶長十六年(1611年)起立●申伝候 寛永(1624-1644年)之末●野寺町と申処二●在
其後正保元年(1645年)当所●拝領仕候
開山 源秀 寛永十四年(1637年)遷化
開基 廣壽院其融到行居士 元禄十三年(1700年)卒 俗姓望月貞久子孫今幾八郎と称シ、橘町三丁目名主役ヲ勤
本堂
本尊 金剛界大日如来
弘法大師木座像 興教大師木座像 六地蔵木立像(長三尺小野篁作) 不動尊木立像(長四寸五分生駒宝山作)両界曼荼羅(興教大師筆)
鎮守柳稲荷社
神体 長七寸五分弘法大師作 本地十一面観世音。
(縁起記載あり略)
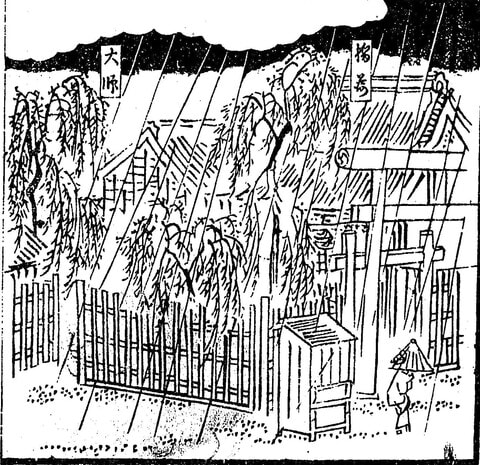
「正福院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
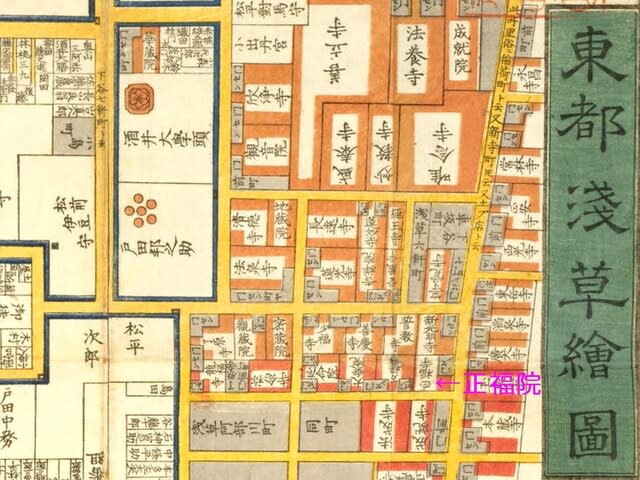
原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ銀座線「稲荷町」駅で徒歩約5分。
都道463号浅草通り「松が谷一丁目」交差点から一本東寄りの路地を南に入ってすぐ。
光明寺とは背中合わせで、江戸切絵図の配置と一致しています。
このあたりは元浅草~寿とつづく御府内霊場札所の集中エリアで、正福院の公式Webにあるとおり、メトロ銀座線「稲荷町」駅から「田原町」駅まで、一筆書きの順路で9箇所の札所を巡ることができます。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 札所標
街路から若干引き込んで参道入口。
その門柱手前には御府内霊場の札所標。
門柱の院号札には「浅草區南松山町九番地」とあります。
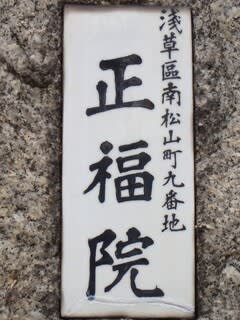

【写真 上(左)】 門柱の院号標
【写真 下(右)】 山内


【写真 上(左)】 観世音菩薩と地蔵尊
【写真 下(右)】 釈迦如来と地蔵尊
参道左手には白衣観世音菩薩と地蔵菩薩の立像で、いずれもおだやかな面立ち。
山内・墓域入口手前の壁際には東京大空襲の戦火により黒くすすけた釈迦如来立像と2体の地蔵尊が御座します。
古にはこのあたりに「柳稲荷」ゆかりの柳の木があったそうです。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 札所板
参道正面の本堂は入母屋造桟瓦葺とみられ、おそらく妻入りです。
奥行きのある敷地形状のため、妻入り様式としたのでは。
妻入り特有の千鳥破風を2連構成しています。
公式Webによると、本堂御内陣には正面に御本尊の金剛界大日如来坐像。
向かって右に牀座に結跏趺坐され五鈷杵と数珠を握られる真如親王様の弘法大師像。
向かって左には興教大師像が安置されているようです。
御朱印は御府内霊場の札所板が掛かる、本堂向かって右手前の庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

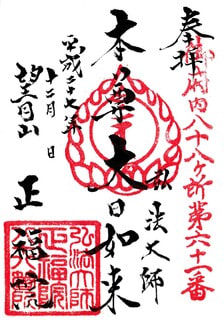
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 大日如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「御府内八十八ヶ所第六十一番」の札所印。
左に山号・院号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第62番 鶴亭山 隆全寺 威光院
(いこういん)
公式Web
台東区寿2-6-8
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第62番、弘法大師二十一ヶ寺第16番
第62番は寿の威光院です。
第62番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに威光院で、第62番札所は開創当初から浅草新堀端の威光院であったとみられます。
公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
威光院は太田道灌公によって「江戸城鎮守の別当として創建」といいます。
『ルートガイド』ではこの江戸城鎮守を「平川天神」(現・平河天満宮)としています。
平河天満宮の公式Web・現地掲示によると、「平川天神」の創祀は以下のとおりです。
江戸平河城城主の太田道灌公が、ある日菅原道真公の夢を見ました。
その翌朝に菅原道真公自筆の画像を贈られたため、道灌公はこの夢を霊夢と感じ、文明十年(1478年)に城内の北に自ら施主となり江戸の守護神として天満宮を建立しました。(「梅花無尽蔵」による)
家康公の江戸城入城後、築城のため平川門外に奉遷、慶長十二年(1607年)2代将軍秀忠公により現在地(貝塚)に奉遷され、本社にちなみこの地を平河町と名付けられました。
平河天満宮は、徳川幕府をはじめ紀州、尾張両徳川家、井伊家等の祈願所となり、新年の賀礼には宮司は将軍に単独拝謁できる高い格式を有していました。

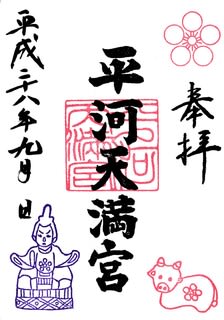
【写真 上(左)】 平河天満宮
【写真 下(右)】 平河天満宮の御朱印
威光院の公式Webには「平川天神」との所縁は記されておらず、平河天満宮の公式Webにも威光院との関係は記されていないので、『ルートガイド』が威光院を「平川天神」の別当とした根拠は不明です。
なお、『ルートガイド』には「(平川天神の)別当として鶴主計延豊が開基となって創建されたのが威光院」と明記されているので、これを記す寺伝等があるのかもしれません。
本堂御本尊は大日如来。護摩堂の不動明王は恵心僧都の作と伝わります。
その後櫻田村に移転、慶長六年(1600年)には八丁堀に遷り、文禄三年(1594年)ないし元和元年(1615年)辨清法印により現在地に移転再興(あるいは開山とも)といいます。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
六十二番
浅くさ新堀端
鶴亭山 般若寺 威光院
愛宕圓福寺末 新義
本尊:大日如来 不動明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [75] 浅草寺社書上 甲二』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.107』
浅草新堀端
芝愛宕前(下)圓福寺末 新義真言宗
鶴亭山威光院
当寺起立之年代不詳
開山 法印辨清 元和五年(1619年)三月寂
中興 法印秀仙 安永七年(1778年)七月寂
本堂
本尊 大日如来木佛坐像
護摩堂
不動明王 二童子アリ 恵心僧都作

「威光院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ銀座線「田原町」駅で徒歩約3分。
都道463号浅草通り「菊屋橋」交差点から新堀通りを南下して少し行った左手です。
この「新堀通り」は江戸切絵図では川沿いの通りとして記され、「此川ヲ新堀ト云」とあります。
新堀沿いに描かれている宗圓寺、永見寺、威光院、常福寺はいずれも「新堀通り」沿いに現存しています。
元浅草~寿界隈は郊外へ移転した寺院が少なく、江戸切絵図に描かれた寺院がよく残っています。

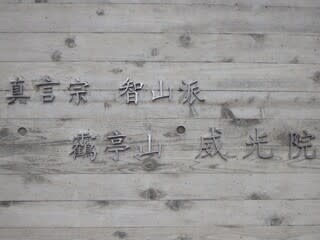
【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 壁面の院号標
コンクリ打放しの門塀、石敷き参道のおくにモダンな本堂は、美術感のようなイメージ。
外構も含めて2014年に一新された模様です。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 本堂
調べてみると設計は現・京都大学名誉教授の建築家・竹山聖氏。
(→ 情報元・『お宮、お寺を散歩しよう』様(紋谷幹男氏))
門塀にはステンレス浮き文字で山号・院号標。
参道右手には大師講の巡拝祈念碑、六地蔵、修行大師像とならび、本堂前には御府内霊場札所標も建っています。


【写真 上(左)】 霊場巡拝碑
【写真 下(右)】 六地蔵


【写真 上(左)】 修行大師像
【写真 下(右)】 札所標
新旧がほどよく調和した素晴らしい空間ですが、筆者の拙い知識ではこれをうまく表現できません(笑)
紋谷幹男氏のキレ味鋭い解説(→ こちら)をご覧くださいませ。
紋谷幹男氏の「当代きっての腕の立つ建築家の、おそろしくエッジの効いたお寺」。
この表現がぴったりの空間だと思います。
御府内霊場巡拝の旨お伝えすると、本堂内にお通しいただけました。
本堂内もコンクリ打ち放しで天井が赤く井桁に組まれた天吊りに天蓋が掛けられています。
(本堂内の様子は→ こちら)
護摩壇の向こうに智拳印を結ばれる金剛界大日如来坐像。
堂内の音響がすこぶるよく、読経の声が響きわたります。
東京のお遍路である御府内霊場。
このような斬新な空間はならではのものかと思います。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
公式Webには「御府内八十八ヶ所霊場とは弘法大師とゆかりがある寺院を巡る、四国八十八カ所の江戸版のようなモノで、 六十二番札所である当院ではお参りされた方に御朱印を承っております。※霊場専用の御朱印帳(納経帳)が御座いますので、出来ればそちらを推奨しております」とあります。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

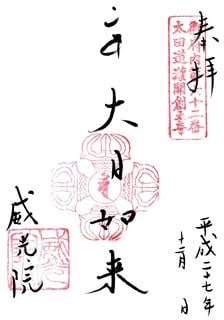
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に金剛界大日如来ののお種子「バン」「大日如来」の揮毫と「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「御府内六十二番」の札所印。
左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
※平成27年に拝受の御朱印の主印は御寶印(羯磨金剛(かつまこんごう))で、「太田道灌開創立寺」の印判があります。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-21)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ 瞳がほほえむから - 今井美樹
■ ebb and flow - LaLa(歌ってみた)
■ ヒカリヘ - miwa
→ ■ 透明感のある女性ヴォーカル50曲
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 奥多摩新四国八十八ヶ所霊場の御朱印


埼玉県から奥多摩にかけて、知られざる弘法大師霊場があります。
奥多摩新四国八十八ヶ所霊場です。
この霊場は先日、数年がかりでついに結願しました。
筆者はこれまでいくつかの弘法大師霊場(八十八ヶ所)を結願していますが、圧倒的に難易度が高かったのがこの霊場です。
というのは、この霊場は寺院札所もあるものの在家や路傍、はたまた山中の札所もあり、そもそも札所を見つけることすら困難なケースがあるからです。
以前、1978年初版・1985年改訂版のガイドブック「新四国奥多摩霊場八十八札所」(武蔵野郷土史刊行会)は発刊されていますが、おそらくすでに廃刊。
(近々入手予定です。)

現在購入可能な正規のガイドはおそらくなく、札所情報はもっぱら「東大和と寺院散策」様(→こちら)に頼らせていただきました。
おそらくこちらのWebがなかったら結願はできていなかったと思います。
ありがとうございました。
今年は弘法大師ご生誕1250年の記念の年です。
四国には行けなかったので、せめて巡拝中の弘法大師霊場を結願したいと思い、東国新四国八十八ヶ所霊場や多摩百八ヶ所霊場を結願するとすでに夏を過ぎていました。
→ ■ 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印-1
→ ■ 多摩新四国八十八ヶ所霊場/多摩百八ヶ所霊場の御朱印
残る難物は奥多摩新四国八十八ヶ所霊場ですが、この時点で未だ20以上の札所を残していました。
その多くは最難所とみられる奥多摩・日原エリアにあり、いくつかは札所に到達できるかどうかさえわかりませんでした。
おそるおそる回り始めてみると、意外に場所はわかりやすく御朱印もいただけることがわかり、こうなるともはや虚仮の一念、一気に奥多摩・日原エリアを攻めて結願に漕ぎ着けました。
奥多摩新四国八十八ヶ所霊場をはじめて知ったのはたしか2016年の初秋。
武蔵野三十三観音霊場を回っていたときに、見慣れぬ弘法大師のお像をみかけました。
それは弘法大師像と仏像がひとつの台座に安置され、小さな堂宇に収められたものでした。
台座に札番が彫り込んであるので山内八十八ヶ所かとも思いましたが、そうではなさそうです。

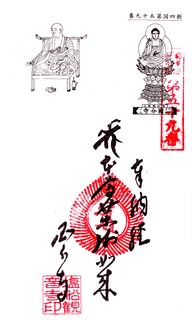
【写真 上(左)】 第59番・塩船観音寺の札所
【写真 下(右)】 第59番・塩船観音寺の札所御朱印
早速Webで検索してみるとこれが奥多摩新四国八十八ヶ所霊場の札所本尊で、初番(第1番)発願所の羽村市の小山家で専用納経帳を頒布されていることがわかりました。
2016年11月、小山家にて専用納経帳を入手して発願。
そもそも初番発願所が民家ということからも、前途の多難さが予想されました。
結願は2023年12月なので、途中新型コロナ禍があったとはいえ発願から結願まで実に7年の歳月を要したことになります。


【写真 上(左)】 第1番・(羽村)小山家の札所
【写真 下(右)】 第1番札所の御朱印


【写真 上(左)】 長岡開山所内の第88番札所
【写真 下(右)】 第88番札所の御朱印


【写真 上(左)】 番外札所・奥多摩修行大師(長岡開山所)
【写真 下(右)】 奥多摩修行大師の御朱印
奥多摩新四国八十八ヶ所霊場は八十八の札番札所と1つの奥の院、4つの番外札所の計93の札所からなります。→ 札所リスト(「東大和と寺院散策」様)
93札所のうち、御朱印を拝受できたのは92(授与率98.9%)と予想以上の授与率でした。
(巡拝中に札所の変更があったり、ひとつの札所御朱印をふたつの納経所で拝受したりで、実際はさらに拝受しています。)

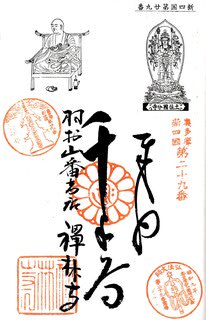
【写真 上(左)】 旧 第29番・(羽村)加藤家の札所
【写真 下(右)】 同 御朱印

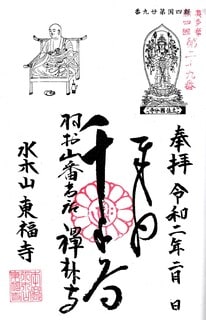
【写真 上(左)】 現 第29番・東福寺(所沢)の札所
【写真 下(右)】 同 御朱印


【写真 上(左)】 第45番・天覧山の能仁寺拝受の御朱印
【写真 下(右)】 第45番・天覧山の長岡開山所拝受の御朱印
御朱印帳への揮毫はほとんど期待できないので、専用納経帳の入手は必須かと思われます。
専用納経帳に直接捺印いただく必要があり、後日郵送戦略が通用しないこともこの霊場の難易度を高めています。
また、印判自捺しの札所も少なくなく、備え付けの朱肉がへたっている場合もあるので、朱肉持参が確実です。
塩船観音寺(青梅)、金乗院(所沢)、能仁寺(飯能)などのメジャー寺院内の札所もありますが、奥多摩霊場の御朱印は完全な裏メニューで当然授与案内などはなくこちらからの申告、しかも現在は専用納経帳でなければいただけないかもしれません。
■ 汎用御朱印帳に授与いただいた稀少な例(第66番・金仙寺(所沢))
(ただし、御朱印尊格は御本尊となっています。他札所でも御本尊+札所印のパターンとなるのでは?)


【写真 上(左)】 汎用御朱印帳
【写真 下(右)】 専用納経帳
第30番札所は日原鍾乳洞内の舟底岩付近にあり、御朱印は日原鍾乳洞入洞受付でいただけますが(というか印判をお借りして自分で納経帳に捺す)、日原鍾乳洞で正規の弘法大師霊場の御朱印をいただけるとは、ほとんど知られていないのでは。
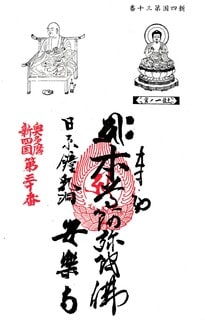
■ 第30番・日原鍾乳洞内舟底岩付近 弘法大師学問所の御朱印

■ 行程図(当初)

■ 札所一覧(当初)
札所エリアは所沢の市街地から日原鍾乳洞まで広域にわたるので車での巡拝の効率がいいですが、とくに奥多摩辺の札所は狭い路地奥やパーキングのないところもあります。
札所はみつかっても御朱印授与所が民家だったりするので、車巡拝はかなりの運転テク(というか狭い山道への慣れ)と嗅覚が必要かと思われます。(ETCはおろか、グーグルマップでも検索できないところがある。)
とくに奥多摩辺はコインパーキングがないうえに道が狭隘なので、不用意に駐車すると一発で無余地駐車となります。
さきに納経所に車を停めさせていただき、そこから札所に向かったケースもいくつかありました。
農作業の方に道を尋ねたのもたびたびで、札所の場所をお尋ねした他宗のお寺さまにご厚意で停めさせていただいたことさえありました。
ただし、この霊場は一時期多くの巡拝者を集めていたらしく、かなりの方が札所や納経所についてご存じでした。
整備されていない急峻な山道の上に御座される札所石佛もあり、ほとんど命がけのアプローチもありました。
(筆者はなんとしても間近で巡拝&札所の写真を撮りたかったので全札所に強行突入しましたが、一部札所については本当にキケンなので麓からの遙拝もやむなしかと思います。)
↓ 最難関と思われる第81番・大徳院(奥多摩町棚沢)


【写真 上(左)】 ハシゴを登ってのアプローチ
【写真 下(右)】 険しい山中にある札所


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 第81番・大徳院の御朱印
このような苦闘つづきの巡拝だけに、結願の達成感もまた一入でした。
「東大和と寺院散策」様に「特に在家など寺院以外の所では不在等が多々あるので、朱印帳持参での遍路は、事前準備と時間と根気が必要である。それは、ある面首都圏にあるのに秘境の札所とも言えようか。」とありますが、これは決して誇張ではなく、結願(&御朱印コプリート)にはほとんど執念にちかい根気が必要かと思われます。
霊場概要については、「東大和と寺院散策」様、Wikipedia等に記載されていますが、概略は以下のとおり。
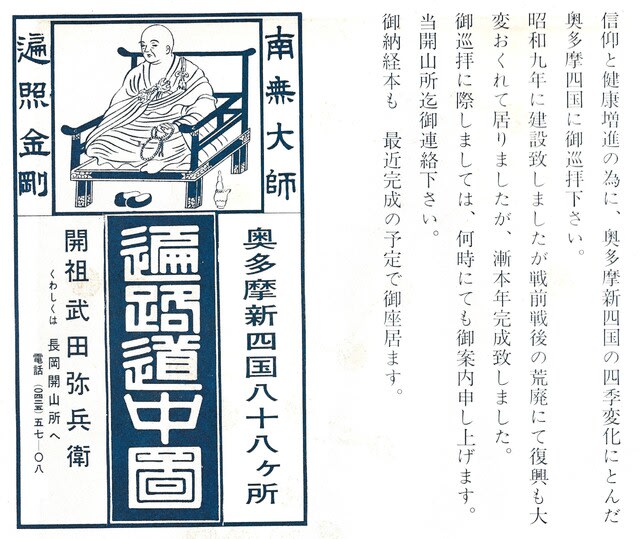
■ 手引き

■ 案内図
奥多摩新四国霊場八十八ヶ所は、昭和9年(1934年)5月に弘法大師御遠忌千百五十年を記念して、瑞穂町長岡在住の武田弥兵衛氏が開創した弘法大師霊場といいます。
札所エリアは東京都下で東大和市、羽村町(市)、福生市、瑞穂町、八王子市、秋川市(あきる野市)、青梅市、奥多摩町。
埼玉県で所沢市、狭山市、入間市、飯能市となります。
主に東京善心講という大師講の人々に支えられ、全盛期とされる昭和40~50年代には巡拝バスが仕立てられるほど賑わったといいます。
霊場名は公式資料や現地石碑類でも表記ゆれがあります。
具体的には、奥多摩霊場八十八札所、奥多摩新四国八十八ヶ霊場、奥多摩霊場新四国八十八札所、奥多摩新四国八十八ヶ所霊場などですが、本記事では奥多摩新四国八十八ヶ所霊場に統一します。
札所本尊は開創者の武田弥兵衛氏が自費を投じて造立された、弘法大師像と仏像がセットで台座に御座す尊像で、ほとんどが本堂ではなく小ぶりな堂宇(大師堂)に奉安されています。
札所寺院でこの堂宇をみつけると、なぜか無性にうれしくなります。
この霊場については青梅市小曽木の岩蔵温泉「儘多屋(ままだや)」のWeb(2018年2月17日付)に貴重な情報が載せられていますので、引用させていただきます。
引用はじめ -------------------------
この札所巡りは、昭和九年頃に創設されたもので、その範囲は奥多摩・青梅・羽村・福生・瑞穂・あきる野・八王子・東大和・入間・所沢・狭山…広範囲にわたります。
しかしながら、この札所巡りは、かなりマニアック。
これをコンプリートするのは、かなりの難関であり、上級者向けだと思われます。
なぜならば、札所には現在無住職のお寺や個人のお宅が含まれているからです。(もちろん、名だたる寺院も名前を連ねています。)
聞いた話ですと、これを主宰している事務局ももう存在していないとか…。
まさに、幻の御朱印巡り。
昭和四十年、五十年代は盛んであったこの札所巡りは、現在では知る人ぞ知る存在になっております。最近は御朱印ブームといいますが、この札所巡りはブームの影響をまったく受けておりません。
儘多屋も札所なので、御朱印を持っているのですが、札所巡りで訪ねてくる方は、年間4~5名様くらいです。
専用の御朱印帳(納経帳)があれば、そちらに印を押させていただきます。
ただ、当館に関しましては平日不定休ですので、必ず事前にお電話にてご確認をお願いいたします。
専用の御朱印帳ですが、私は先日、塩船観音寺さんで購入いたしました。まだ数冊残っているとのことです。
この幻の御朱印巡り、是非挑戦してみてはいかがでしょうか?
これを完成させたら、かなりの強者です。
引用おわり -------------------------
この記事によると、
・2018年2月時点で巡拝者は年間で4~5名で、御朱印ブームの影響をまったく受けていない。
・昭和四十年、五十年代は盛んであったこの札所巡りは、知る人ぞ知る存在になっている。
・2018年2月時点で塩船観音寺には数冊の専用納経帳の在庫があった。
ことなどがわかります。
筆者が直近で確認したある札所の参拝記帳にはおおむね月に1名程度の記帳があったので、2018年よりは増えているのかもしれません。
筆者の感覚でも2016年に回り始めたときよりも、2023年の方がすんなりと御朱印を受けられた気がします。
また、結願所の長岡開山所でお聞きしたところでは、御朱印拝受希望者は新型コロナ禍のさなかでは年間2~3名、最近はやや増えていて年間10名程度とのことでした。
増えたといっても年間10名程度ですから、「知る人ぞ知る弘法大師霊場」といっても過言ではないでしょう。
-------------------------
それでは第1番から順にご紹介していきます。
まずは札所概要と御朱印のみで、後日写真やコメントを入れていきます。
なお、納経所については「東大和と寺院散策」様をご覧ください。
専用納経帳は初版(白)と復刻版(水色)の2種あり、初版(白)は昭和48年、開創者の武田弥兵衛氏の米寿の祝を記念して自費製作されたものとのこと。
筆者は第1番札所で入手しましたが、そのときはすでに残りわずか。
もはや入手困難かと思いましたが、結願所の長岡開山所には若干の在庫がありそうです。
(ただし、こちらはお勤めでお忙しいとのことで、すぐの入手は難しいかと・・・。)
復刻版(水色)は第41番札所・龍圓寺様が平成21年11月の大師堂落慶に合わせ、檀家さんから寄進されたものとのことで、こちらは龍圓寺様で入手できる可能性があります。
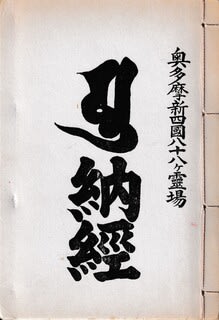

【写真 上(左)】 専用納経帳(初版)
【写真 下(右)】 同 奥付


【写真 上(左)】 専用納経帳(復刻版)
【写真 下(右)】 札番対照表
また、「東大和と寺院散策」様にて専用納経帳のPDF版を公開されているので、こちらを印刷して使うのもいいかもしれません。
また、専用納経帳は札番順ではないので、札所の頁を探すのがやっかいです。
「東大和と寺院散策」様で公開されている札番対照表(PDF)は優れもので、すぐに頁検索できるので活用させていただきました。
本当になにからなにまで至れり尽くせりで、頭が下がります。


【写真 上(左)】 拝受前(第1番)
【写真 下(右)】 拝受後(第1番)
-------------------------
第1番 (羽村) 小山家
東京都羽村市五ノ神4-15
小山家隣地堂宇内
御本尊:釈迦如来・弘法大師
札所本尊:釈迦如来・弘法大師
第2番 長岡開山所
東京都瑞穂町長岡1-58-21
開山所建屋内
御本尊:阿弥陀如来・弘法大師
札所本尊:阿弥陀如来・弘法大師
第3番 寶珠山 地蔵院
東京都青梅市畑中2-583-1
臨済宗建長寺派
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:釈迦如来・弘法大師
他札所:多摩(青梅)七福神(布袋尊)
第4番 (友田大日寺) 加藤家
東京都青梅市友田1-1009
加藤家邸内堂宇内
御本尊:大日如来・弘法大師
札所本尊:大日如来・弘法大師
第5番 宮寺山 無量壽寺 西勝院
埼玉県入間市宮寺489
山内堂宇内
真言宗豊山派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:地蔵菩薩・弘法大師
他札所:武玉八十八ヶ所霊場第32番、狭山三十七薬師霊場第10番
第6番 (友田乃木庵) 島田家
東京都青梅市友田1-1006
島田家邸内堂宇内
御本尊:薬師如来・弘法大師
札所本尊:薬師如来・弘法大師
第7番 東久山 地蔵院 宝光寺
埼玉県飯能市上畑219
本堂左手地蔵堂内
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:阿弥陀如来・弘法大師
第8番 友田山 花蔵院
東京都青梅市友田4-204
山内堂宇内
真言宗豊山派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:千手観世音菩薩・弘法大師
他札所:多摩新四国八十八ヶ所霊場第52番、 武玉八十八ヶ所霊場第18番
第9番 鳳林山 長光寺
埼玉県飯能市下直竹1056
山内慰霊堂内
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所本尊:寝釈迦像・弘法大師
第10番 寂光山 長寿院 浄心寺
埼玉県飯能市矢颪222
山内覆屋内
曹洞宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:千手観世音菩薩・弘法大師
他札所:武蔵野三十三観音霊場第23番、高麗板東三十三観音霊場第9番、武蔵野七福神(毘沙門天)
第11番 (岩藏温泉) 儘多屋
東京都青梅市小曽木5-3140
道の反対側池そばの堂宇
御本尊:薬師如来・弘法大師
札所本尊:薬師如来・弘法大師
第12番 日原籠岩
東京都奥多摩町日原
籠岩61番石仏のそば
御本尊:虚空蔵菩薩・弘法大師
札所本尊:虚空蔵菩薩・弘法大師
第13番 梅林山 天澤院
東京都青梅市梅郷4-586-1
本堂横堂宇内
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所本尊:十一面観世音菩薩・弘法大師
第14番 吉岡家
東京都瑞穂町長岡1
東善院そばの堂宇内
御本尊:弥勒菩薩・弘法大師
札所本尊:弥勒菩薩・弘法大師
第15番 萬貴山 常福寺
東京都青梅市富岡3-1107
山内堂宇内
曹洞宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来・弘法大師
他札所:関東九十一薬師霊場第8番
第16番 金軸山 無量院 金蔵寺
埼玉県飯能市大河原538
山内堂宇内
真言宗智山派
御本尊:千手観世音菩薩
札所本尊:千手観世音菩薩・弘法大師
第17番 横尾山 大徳院
東京都青梅市御岳本町252
山内堂宇内
真言宗醍醐派
御本尊:薬師如来
札所本尊:七佛薬師如来・弘法大師
第18番 摩尼珠山 金剛院 福昌寺
東京都青梅市小曽木3-1186
山内堂宇内
真言宗系単立
御本尊:大日如来
札所本尊:薬師如来・弘法大師
第19番 槙尾山 慈恩寺
東京都青梅市御岳町350
本堂向かって左手裏。濡佛
御本尊:
札所本尊:地蔵菩薩・弘法大師
第20番 高水山 龍學寺 常福院
東京都青梅市成木7-1192
山内堂宇内
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所本尊:地蔵菩薩・弘法大師
他札所:多摩新四国八十八ヶ所霊場第49番
第21番 慧日山 観音院 圓通寺
東京都八王子市高月町1158
山内堂宇内
天台宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:虚空蔵菩薩・弘法大師
他札所:関東百八地蔵尊霊場第103番
第22番 福昌山 心月院
東京都青梅市御岳1-132
山内堂宇内
御本尊:薬師如来・弘法大師
札所本尊:薬師如来・弘法大師
第23番 菩提山 仏國寺 密厳院
埼玉県所沢市山口2045
山内堂宇内
真言宗豊山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来・弘法大師
他札所:武玉八十八ヶ所霊場第40番、狭山三十七薬師霊場第19番
第24番 遊石山 観音院 新光寺
埼玉県所沢市宮本町1-7-3
山内。濡佛
真言宗豊山派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:虚空蔵菩薩・弘法大師
他札所:武蔵野三十三観音霊場第10番、狭山三十三観音霊場第8番
第25番 (海蔵院跡) 小曽木一丁目会館脇
東京都青梅市南小曽木1
会館脇堂宇内
御本尊:地蔵菩薩・弘法大師
札所本尊:地蔵菩薩・弘法大師
第26番 (御岳山) 原島家
東京都青梅市御岳65
原島荘入口左側
御本尊:薬師如来・弘法大師
札所本尊:薬師如来・弘法大師
第27番 金華山 長泉院
東京都青梅市二俣尾4-1066
山内堂宇内
曹洞宗
御本尊:
札所本尊:十一面観世音菩薩・弘法大師
第28番 常寂山 蓮華院 智観寺
埼玉県飯能市中山520
山内堂宇内
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所本尊:大日如来・弘法大師
他札所:高麗板東三十三観音霊場第1番
(旧)第29番 (羽村山禅林寺) 加藤家
東京都羽村市羽東1-4-13
御本尊:千手観世音菩薩・弘法大師
札所本尊:千手観世音菩薩・弘法大師
(新)第29番 成田山 観音院 東福寺
埼玉県所沢市本郷764
山内堂宇内(羽村から移転)
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所本尊:千手観世音菩薩・弘法大師
第30番 日原鍾乳洞内舟底岩付近 弘法大師学問所
東京都奥多摩町日原鍾乳洞内
舟底岩付近弘法大師学問所
御本尊:阿弥陀如来・弘法大師
札所本尊:阿弥陀如来・弘法大師
第31番 (御岳山) 原島家
東京都青梅市御岳65
原島荘入口左側
本尊:文殊菩薩・弘法大師
札所本尊:文殊菩薩・弘法大師
第32番 岸高山 福寿院 歓喜寺
埼玉県飯能市岩渕658甲
山内堂宇内
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:十一面観世音菩薩・弘法大師
他札所:武州八十八霊場第82番
第33番 醫王山 宗禅寺
東京都羽村市川崎2-8
山内薬師堂内
臨済宗建長寺派
御本尊:釈迦牟尼仏
札所本尊:薬師如来・弘法大師
第34番 持田家
東京都青梅市梅郷4-650
邸内山側堂宇内
御本尊:薬師如来・弘法大師
札所本尊:薬師如来・弘法大師
第35番 豊岡温故公園
埼玉県入間市豊岡1-7
公園内堂宇内
御本尊:薬師如来・弘法大師
札所本尊:薬師如来・弘法大師
第36番 宝塔山 吉祥寺 多聞院
埼玉県所沢市中冨1501
山内堂宇内
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
札所本尊:不動明王・弘法大師
第37番 福壽山 慈勝寺
東京都あきる野市草花1811
山内堂宇内
臨済宗建長寺派
御本尊:正観世音菩薩
札所本尊:五佛尊・弘法大師
他札所:秋川三十四所霊場第17番
第38番 成木山 愛染院 安楽寺
東京都青梅市成木1-583
山内堂宇内
真言宗単立
御本尊:不動明王
札所本尊:千手観世音菩薩・弘法大師
他札所:多摩新四国八十八ヶ所霊場第45番
第39番 金慶山 仙僧院 長福寺
東京都奥多摩町丹三郎233
山内堂宇内
真言宗豊山派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:薬師如来・弘法大師
第40番 (御岳上) 北島家
東京都青梅市御岳2-451
道沿い堂宇内
御本尊:薬師如来・弘法大師
札所本尊:薬師如来・弘法大師
第41番 龍岳山 歓喜院 龍圓寺
埼玉県入間市新久717
山内堂宇内
真言宗智山派
御本尊:虚空蔵菩薩
札所本尊:十一面観世音菩薩・弘法大師
他札所:武蔵野三十三観音霊場第20番、武州八十八霊場第75番
第42番 星見山 無量壽院 清照寺
埼玉県所沢市上山口439
山内堂宇内
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来・弘法大師
第43番 大柳山 月輪院 東光寺
東京都青梅市天ヶ瀬町1203
山内堂宇内
真言宗豊山派
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:千手観世音菩薩・弘法大師
他札所:多摩新四国八十八ヶ所霊場第48番
第44番 高竹山 光明院 明光寺
埼玉県狭山市根岸2-5-1
山内堂宇内
真言宗智山派
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:十一面観世音菩薩・弘法大師
他札所:武州八十八霊場第77番
第45番 天覧山 岩屋寺
埼玉県飯能市天覧山
(現)能仁寺不動堂
御本尊:不動明王・弘法大師
札所本尊:不動明王・弘法大師
第46番 法栄山 遍照院 東光寺
埼玉県入間市小谷田1437
山内
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所本尊:薬師如来・弘法大師
第47番 稲荷山 寳玉院
埼玉県所沢市三ヶ島3-1167
山内堂宇内
真言宗豊山派
御本尊:不動明王?
札所本尊:阿弥陀如来・弘法大師
第48番 三ツ井戸大師
埼玉県所沢市西所沢1-26
堂宇内
御本尊:弘法大師・十一面観世音菩薩
札所本尊:弘法大師・十一面観世音菩薩
第49番 愛宕山 明王院 即清寺
東京都青梅市柚木町1-4-1
参道堂宇内
真言宗豊山派
御本尊:不空羂索明王
札所本尊:釈迦如来・弘法大師
他札所:多摩新四国八十八ヶ所霊場第51番、武玉八十八ヶ所霊場第9番、関東八十八箇所霊場第71番
第49番(奥の院) 愛宕山 明王院 即清寺奥の院
東京都青梅市柚木町1-4-1
即清寺裏山堂宇内
真言宗豊山派
御本尊:不空羂索明王
札所本尊:弘法大師
第50番 北田山 長寿院 寳泉寺
埼玉県所沢市北岩岡130
山内堂宇内
真言宗豊山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来・弘法大師
第51番 金峰山 石倉院
東京都青梅市小曽木5-3063
山内堂宇内
曹洞宗
御本尊:
札所本尊:薬師如来・弘法大師
第52番 吾庵山 金乗院 放光寺
埼玉県所沢市上山口2203
本堂前参道濡佛
真言宗豊山派
御本尊:千手観世音菩薩
札所本尊:十一面観世音菩薩・弘法大師
他札所:武蔵野三十三観音霊場第13番、狭山三十三観音霊場第1番、武蔵野七福神(布袋尊)、武玉八十八ヶ所霊場第39番、狭山三十七薬師霊場第22番
第53番 王禅山 釋迦院 佛眼寺
埼玉県所沢市久米2445
山内地蔵堂内
真言宗豊山派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来・弘法大師
他札所:所沢七福神(福禄寿)、狭山三十七薬師霊場第26番
第54番 青梅山 無量寿院 金剛寺
東京都青梅市天ヶ瀬1032
山内堂宇内
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王・弘法大師
他札所:多摩新四国八十八ヶ所霊場第47番、武玉八十八ヶ所霊場第20番、東国花の寺百ヶ寺霊場東京第11番
第55番 清流山 無量院 清泰寺
埼玉県飯能市中居214-1
山内堂宇内
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:大通智勝仏・弘法大師
第56番 宥峰山 清泰寺
埼玉県入間市宮寺609
山内覆屋内
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所本尊:地蔵菩薩・弘法大師
第57番 梅松山 圓泉寺
埼玉県飯能市平松376
山内堂宇内
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:阿弥陀如来・弘法大師
他札所:武蔵野三十三観音霊場第25番、高麗板東三十三観音霊場第3番、武蔵野七福神(福禄寿)
第58番 光明山 正覚院 圓照寺
埼玉県入間市野田158
山内堂宇内
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀三尊
札所本尊:千手観世音菩薩・弘法大師
他札所:武蔵野三十三観音霊場第22番、高麗板東三十三観音霊場第11番、関東八十八箇所第73番、武州八十八霊場第80番、武蔵野七福神(弁財天)
第59番 大悲山 塩船観音寺
東京都青梅市塩船194
山内堂宇内
真言宗醍醐派
御本尊:十一面千手千眼観世音菩薩
札所本尊:薬師如来・弘法大師
他札所:武玉八十八ヶ所霊場第22番、多摩百八ヶ所霊場第102番、東国花の寺百ヶ寺霊場東京第12番、関東八十八箇所第72番
第60番 能満山 廣幢院 大光寺
埼玉県飯能市川寺48
山内堂宇内
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来・弘法大師
他札所:武州路十二支霊場(丑)
第61番 日原籠岩
東京都奥多摩町日原
籠岩付近濡佛
御本尊:大日如来・弘法大師
札所本尊:大日如来・弘法大師
第62番 浄悦山 涼光院 長久寺
埼玉県入間市宮寺2324
山内濡佛
真言宗豊山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:十一面観世音菩薩・弘法大師
他札所:武玉八十八ヶ所霊場第31番、狭山三十七薬師霊場第9番
第63番 岩井堂観音
埼玉県飯能市岩渕岩淵746-1
山内堂宇内
御本尊:観世音菩薩
札所本尊:毘沙門天・弘法大師
第64番 般若山 長寿院 観音寺
埼玉県飯能市山手町5-17
山内
真言宗智山派
御本尊:如意輪観世音菩薩
札所本尊:阿弥陀如来・弘法大師
他札所:武蔵野三十三観音霊場第24番、高麗板東三十三観音霊場第10番、武蔵野七福神(寿老人)、武州八十八霊場第85番
第65番 吾庵山 金乗院 放光寺
埼玉県所沢市上山口2203
本堂前参道濡佛
真言宗豊山派
御本尊:千手観世音菩薩
札所本尊:十一面観世音菩薩・弘法大師
他札所:武蔵野三十三観音霊場第13番、狭山三十三観音霊場第1番、武蔵野七福神(布袋尊)、武玉八十八ヶ所霊場第39番、狭山三十七薬師霊場第22番
第66番 別所山 西光院 金仙寺
埼玉県所沢市堀之内343
山内堂宇内
真言宗豊山派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:千手観世音菩薩・弘法大師
他札所:武玉八十八ヶ所霊場第34番
第67番 吾庵山 金乗院 放光寺
埼玉県所沢市上山口2203
本堂前参道濡佛
真言宗豊山派
御本尊:千手観世音菩薩
札所本尊:薬師如来・弘法大師
他札所:武蔵野三十三観音霊場第13番、狭山三十三観音霊場第1番、武蔵野七福神(布袋尊)、武玉八十八ヶ所霊場第39番、狭山三十七薬師霊場第22番
第68番 野老山 実蔵院
埼玉県所沢市元町20-15
山内濡佛
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
札所本尊:阿弥陀如来・弘法大師
他札所:武蔵野三十三観音霊場第9番
第69番 諏訪山 萬齢院 髙正寺
埼玉県入間市仏子1511
山内山手濡佛
曹洞宗
御本尊:虚空蔵菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩・弘法大師
他札所:武蔵野三十三観音霊場第21番
第70番 龍光山 能満院 梅岩寺
東京都青梅市仲町235
山内堂宇内
真言宗豊山派
御本尊:虚空蔵菩薩
札所本尊:馬頭観世音菩薩・弘法大師
他札所:多摩新四国八十八ヶ所霊場第46番
第71番 太平山 雲慶院
東京都青梅市沢井2-828
山内覆屋内
曹洞宗
御本尊:釈迦如来
札所本尊:千手観世音菩薩・弘法大師
第72番 上洗山 無量寺 普門院
埼玉県所沢市上新井189
山内堂宇内
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所本尊:大日如来・弘法大師
他札所:武蔵野三十三観音霊場第11番、狭山三十三観音霊場第7番
第73番 辰爾山 勝楽寺 佛蔵院
埼玉県所沢市山口1119
山内堂宇内
真言宗豊山派
御本尊:釈迦如来
札所本尊:釈迦如来・弘法大師
他札所:狭山三十三観音霊場第2番、武玉八十八ヶ所霊場第35番、狭山三十七薬師霊場第21番
第74番 世音山 妙智寺 蓮花院
埼玉県入間市春日町2-9-1
山内堂宇内
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:薬師如来・弘法大師
他札所:武蔵野三十三観音霊場第18番、武州八十八霊場第76番
第75番 朝日山 平等院
埼玉県飯能市美杉台5-16-3
本堂両脇
真言宗善通寺派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来・弘法大師
第76番 世音山 妙智寺 蓮花院
埼玉県入間市春日町2-9-1
山内堂宇内
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:薬師如来・弘法大師
他札所:武蔵野三十三観音霊場第18番、武州八十八霊場第76番
第77番 吾庵山 金乗院 放光寺
埼玉県所沢市上山口2203
本堂前参道濡佛
真言宗豊山派
御本尊:千手観世音菩薩
札所本尊:薬師如来・弘法大師
他札所:武蔵野三十三観音霊場第13番、狭山三十三観音霊場第1番、武蔵野七福神(布袋尊)、武玉八十八ヶ所霊場第39番、狭山三十七薬師霊場第22番
第78番 白部山 医王寺 慶性院
東京都東大和市芋窪6-1353
山内覆屋内
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所本尊:阿弥陀如来・弘法大師
他札所:多摩新四国八十八ヶ所霊場第41番、武玉八十八ヶ所霊場第36番、狭山三十七薬師霊場第36番
第79番 吾庵山 金乗院 放光寺
埼玉県所沢市上山口2203
本堂前参道濡佛
真言宗豊山派
御本尊:千手観世音菩薩
札所本尊:十一面観世音菩薩・弘法大師
他札所:武蔵野三十三観音霊場第13番、狭山三十三観音霊場第1番、武蔵野七福神(布袋尊)、武玉八十八ヶ所霊場第39番、狭山三十七薬師霊場第22番
第80番 (鳩ノ巣) 清水家
東京都奥多摩町棚沢747
清水工務店向かいの山中腹堂宇内
御本尊:十一面千手観世音菩薩・弘法大師
札所本尊:十一面千手観世音菩薩・弘法大師
第81番 (白丸) 大徳院
東京都奥多摩町棚沢661
小林燃料店裏山堂宇内
御本尊:千手観世音菩薩・弘法大師
札所本尊:千手観世音菩薩・弘法大師
第82番 大沢家
東京都奥多摩町白丸319
渓山窯敷地内堂宇内
御本尊:千手千眼観世音菩薩・弘法大師
札所本尊:千手千眼観世音菩薩・弘法大師
第83番 瑠璃山 周慶院
東京都奥多摩町氷川1513
庫裏手前池上の堂宇内
曹洞宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:聖観世音菩薩・弘法大師
第84番 (木村家) 弁天峡
東京都奥多摩町氷川
井登屋商店向かいの堂宇内
御本尊:十一面千手観世音菩薩・弘法大師
札所本尊:十一面千手観世音菩薩・弘法大師
第85番 小林家
東京都奥多摩町氷川1236
慈眼寺裏山の堂宇内
御本尊:聖観世音菩薩・弘法大師
札所本尊:聖観世音菩薩・弘法大師
第86番 葦桁山 永昌院
東京都福生市福生1791
山内堂宇内
真言宗醍醐寺派
御本尊:不動明王
札所本尊:十一面観世音菩薩・弘法大師
第87番 長岡開山所
東京都瑞穂町長岡1-58-21
長岡開山所堂宇内
御本尊:聖観世音菩薩・弘法大師
札所本尊:聖観世音菩薩・弘法大師
第88番 長岡開山所
東京都瑞穂町長岡1-58-21
長岡開山所堂宇内
御本尊:薬師如来・弘法大師
札所本尊:薬師如来・弘法大師
番外 玉應山 福生院
東京都福生市熊川716
山内濡佛
臨済宗建長寺派
御本尊:
札所本尊:鯖大師
番外 十夜橋霊場
東京都青梅市長淵1-793付近
旧鳶巣橋際堂宇内
御本尊:弥勒菩薩・弘法大師
札所本尊:弥勒菩薩・弘法大師
番外 奥多摩修行大師
東京都瑞穂町長岡1-58-21
長岡開山所堂宇内
御本尊:修行大師
札所本尊:修行大師
番外 一本杉霊場
東京都瑞穂町長岡1-58-21
(現)長岡開山所堂宇内
御本尊:大師御手植一本杉
札所本尊:大師御手植一本杉
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 鎌倉のお正月限定御朱印 & 霊場御朱印の最新状況
お正月に鎌倉に初詣に行かれる方も多いのでは。
そこで、今回は鎌倉でお正月に限定的にいただける御朱印と、知る人ぞ知る御朱印、そして鎌倉関連の霊場の最新状況についてまとめてみました。
【市内の交通状況】
鎌倉市内は下記期間に大規模な車両乗り入れ規制がかけられます。
・大晦日12/31の23:00~元旦1/1の17:00
・1/2、1/3の9:00~17:00
よって、正月三が日の鎌倉への車でのアクセスは原則できません。
鉄道でのアクセスをおすすめしますが、どうしても車で行きたい場合は、東京方面からだとおそらく逗子駅前のコインパーキング(数はかなりある)に停めて、横須賀線で逗子から鎌倉まで1駅乗ってのアクセスとなります。
→ 交通規制情報(鎌倉観光公式ガイド)
【お正月限定の御朱印、知る人ぞ知る御朱印】
お正月限定の御朱印は下記1.2のふたつが有名です。
(他にもあるかも。また、御朱印図柄や印判が変わるなどのケースはたくさんあるようです。)
1.(西御門(にしみかど)/大蔵)白旗神社
鎌倉市西御門2ー1
御祭神:源頼朝公
原則正月三が日のみの書置授与です。授与所は拝殿向かって右手前の授与所。
たしか15時くらいまでだったと思うので、早めの参拝をおすすめします。
(なお、令和6年正月の授与についてはWebで確認できていません。)
源頼朝公の墳墓堂「法華堂」ともふかい関わりをもち、頼朝公を御祭神とする歴史の香り高い神社で、「勝運の神様」として知られています。
→ 関連記事「鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)」

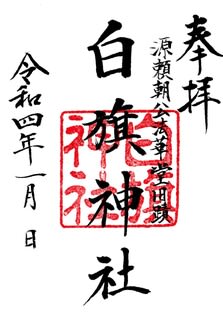
【写真 上(左)】 社頭(正月)
【写真 下(右)】 御朱印
2.(鶴岡八幡宮末社)白旗神社
神奈川県鎌倉市雪ノ下2-1
御祭神:源頼朝公・源実朝公
公式Web(PDF)によると、令和6年正月も授与される模様です。
「数量限定三社一組正月特別朱印」は鶴岡八幡宮・旗上辨戝天社・白旗神社の3社の御朱印がセットになったもので、白旗神社の御朱印は正月限定となります。
正月三が日の授与と思われ、公式Webには「※数に限りがございます。」とあり、授与の可否はそのときの授与状況によりますので、2日、3日の参拝で拝受できるかはわかりません。
また、1日あたりの授与数が決まっている可能性もあるので、元旦のなるべく早い時間の参拝をおすすめします。
境内東側に御鎮座。
源頼朝公・実朝公をお祀りし、学業成就・勝負運の御神徳あらたかとされます。

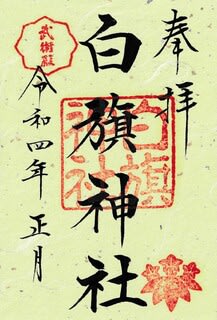
【写真 上(左)】 拝殿
【写真 下(右)】 御朱印
3.由比若宮(元八幡)
鎌倉観光公式ガイド
鎌倉市材木座1-7
御祭神:応神天皇・比売神・神功皇后
こちらは正月限定授与ではありませんが、ご不在が多く授与日がかなり限られている模様なのでご紹介します。
(なお、令和6年正月の授与についてはWebで確認できていませんが、可能性は高いのでは。)
康平六年(1063年)、源頼義公が前九年の役で奥州を鎮定され京に帰る帰途、鎌倉に立ち寄られこの地に源氏の守り神である京の石清水八幡宮の御祭神を勧請されて創祀と伝わります。
後に源頼朝公が現在の鶴岡八幡宮の地(小林郷北山)に社殿を遷してからは、「元八幡」とも呼ばれるようになりました。
鶴岡八幡宮境内には、由比若宮(元八幡)遥拝所があります。


【写真 上(左)】 由比若宮遙拝所(鶴岡八幡宮境内)
【写真 下(右)】 由比若宮の拝殿
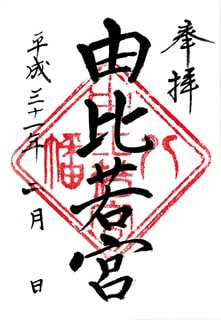
■ 御朱印
→ 関連記事「■「鎌倉殿の13人」と御朱印-1」
4.甘縄神明宮
鎌倉市長谷1-12-1
御祭神:天照大御神
こちらは正月限定ではありませんが、御朱印については意外に知られていないようなので御紹介します。
長谷の観光地近くに御鎮座ですが、やや奥まっているので参拝者は少なく御朱印もいただけそうな感じがありません。
しかし、参拝後、大町の八雲神社にて申告すると御朱印を授与いただけます。
和銅三年(710年)行基菩薩の草創、染谷太郎太夫時忠の創建と伝わり、鎌倉最古のお社ともいわれます。
永保元年(1081年)源義家公が社殿を再建、以降も源頼朝公、政子の方、源実朝公などの崇敬が篤かったと伝わります。
また、源頼義公が相模守として下向の折に当宮に祈願し、八幡太郎義家公が生まれたとも伝えられ、源氏とつよい所縁をもちます。
社殿がある場所は有力御家人・安達盛長の屋敷跡とされています。


【写真 上(左)】 甘縄神明宮
【写真 下(右)】 御朱印
→ 関連記事「■「鎌倉殿の13人」と御朱印-1」
5.(浄明寺)熊野神社
鎌倉市浄明寺3-8-55
御祭神:天宇須女命、伊弉諾命、伊弉册命
浄妙寺の西北に御鎮座の熊野神社。
森閑とした山中に御鎮座で、御朱印もいただけそうな感じがありません。
しかし、こちらも参拝後、大町の八雲神社にて申告すると御朱印を授与いただけます。
朝比奈切通しそばにも熊野神社がありますがこちらは横浜市金沢区の所在で、当社とは別のお社です。
境内由来書などになると、応永年間(1394-1427年)および永正年間(1504-1520年)に社殿を再建したと伝えられ、明治6年、国より正式に浄明寺地区の鎮守として公認されています。


【写真 上(左)】 (浄明寺)熊野神社
【写真 下(右)】 御朱印
→ 関連記事「■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)」
6.巌窟堂 岩谷不動尊
鎌倉市雪ノ下2-2-21
宗派不明
御本尊:不動明王
こちらは鎌倉の御朱印ガイドなどにもなかなか載っていない知る人ぞ知る御朱印で、正月限定ではありません。
ただし、雪ノ下の不動茶屋の営業日・営業時間内にしかいただけません。(正月の営業予定については不明。)
弘法大師の御作と伝わる由緒正しいお不動様で、頼朝公が伊豆の日金山から勧請した日金地蔵尊(日金山松源寺)のとなりにあったという歴史の香り高いところです。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 御朱印
→ 関連記事「■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)」
7.禅居院
鎌倉市山ノ内1534
臨済宗建長寺派
御本尊:聖観世音菩薩
建長寺の塔頭寺院で原則一般拝観不可ですが、令和5年5月15日より鎌倉十三佛霊場第8番札所となられ、鎌倉十三佛の巡拝者のみ限定で入山でき御朱印も拝受できるようになりました。
ただし、鎌倉十三佛霊場事務局ではオリジナル(専用)御朱印帳での集印を推奨されている模様で、汎用御朱印帳のみで入山が認められるかは不明です。
なお、入山に当たっては決まり事がありますのでご留意ください。
建長寺22世で鎌倉五山の浄智寺、円覚寺、京都五山の建仁寺、また五山の上位とされる南禅寺の住職を勅命により歴任された清拙正澄(大鑑禅師)の塔所寺院です。


【写真 上(左)】 禅居院
【写真 下(右)】 御朱印
8.多宝谷山 妙傳寺
鎌倉市扇ガ谷2-21-3
日蓮宗
御首題授与についてはながらく不明でしたが、先日拝受できました。
原則無住のようですが、定期的に御住職がこられるので、タイミングが合えば御首題を拝受できます。
ただし、御首題帳の用意がベターかと。
(正月の授与については不明です。→ 参考Web)
承応元年(1652年)、水戸藩主徳川頼房公が祈願所として現在の東京都文京区白山に創建した寺院が前身。
昭和20年(1945年)の東京大空襲で伽藍を焼失し、昭和49年(1974年)現在地へ移転した、鎌倉では比較的あたらしい寺院です。
なお、この地は弘長二年(1262年)忍性が開山した泉ヶ谷多宝寺の跡ともいわれます。


【写真 上(左)】 妙傳寺
【写真 下(右)】 御首題
-------------------------
■ 鎌倉関連の霊場御朱印の最新情報について
鎌倉にはいくつかの霊場があります。
そのうち、とくに御朱印関係の最新情報(令和5年12月初旬時点)をご紹介してみます。
1.鎌倉五山
こちらは霊場ではありませんが、とりあげてみます。
「五山」とは、南宋の寧宗のころにインドの五精舎十塔所にならって創設された寺格制度で、鎌倉にある五つの禅宗の寺院、建長寺、圓覚寺、壽福寺、浄智寺、浄妙寺をいいます。
「鎌倉五山」は鎌倉観光公式ガイドWebでも紹介され、「鎌倉の御朱印入門コース」とする御朱印ガイドもあります。
しかし、現時点(令和5年12月時点)で、この「鎌倉五山」の御朱印が揃わない可能性があります。
その理由は、第三位の壽福寺の御朱印を拝受できない可能性があるからです。
壽福寺の御朱印については、従前から拝受難易度の高さで知られていました。
ただし、「鎌倉五山」(御本尊)の御朱印については、比較的すんなりとお出しいただけた記憶があります。
ある時期から御朱印の授与自体を休止されているという情報があるものの、書置ながら拝受できるというWeb情報(リンク不可)もあり、実際、Web上でも新型コロナ禍以降の書置御朱印がいくつかUPされています。


【写真 上(左)】 壽福寺参道
【写真 下(右)】 御朱印休止中の掲示
しかし、先日(令和5年12月初旬)の参拝時には「御朱印休止中」の掲示が出ており御朱印は授与されていませんでした。
どうにも腑に落ちなかったので、鎌倉市観光協会に電話で尋ねてみました。
・壽福寺の御朱印は目下原則授与休止中となっているようだが、たまに授与所前で書置のものが授与されている場合があると聞く。
・複数の霊場札所を兼ねられているので、巡拝者の方から複数の問合せをいただいている。
・観光協会からも何度かお寺様に問合せしているが、電話がほとんど通じず状況がわからずに苦慮している。
・札所について、鎌倉十三佛については本年(令和5年)5月15日より第4番札所が壽福寺から報国寺に変更となっているが、他の霊場の札所変更の動きについては聞いていない。
・札所変更については関連の寺院様等でお決めになることなので、観光協会から働きかけることはできない。
回答された方の物腰ははなはだ恐縮モードで、それ以上問い詰めることもできず(笑)、お礼を述べて電話を切りました。
このやりとりは当山の山門前でしたのですが、その間にも「御朱印休止中」の掲示をみて、残念そうに引き返す方がおられました。
(まぁ、ふつうの人は(笑)観光協会まで電話して状況確認まではしないと思う。)
じっさい、鎌倉観光公式ガイドWebにも「しばらくの間、御朱印はお休みいたします※お電話によるお問い合わせはご遠慮ください」との記載があります。
現況からすると、このようにしか書き様がないかと思います。
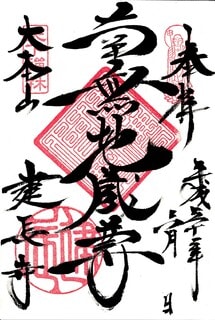

【写真 上(左)】 第一位 建長寺の御朱印
【写真 下(右)】 第一位 建長寺の扁額

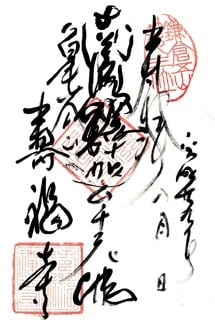
【写真 上(左)】 第二位 圓覚寺の御朱印
【写真 下(右)】 第三位 壽福寺の御朱印

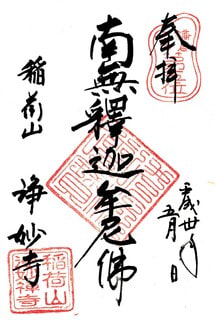
【写真 上(左)】 第四位 浄智寺の御朱印
【写真 下(右)】 第五位 浄妙寺の御朱印
2.鎌倉三十三観音霊場
鎌倉の名刹が参画される観音霊場で、新型コロナ禍では授与休止の札所もありましたが、現況、書置御朱印であればほとんど授与されている模様です。
ただし、こちらでも第24番札所の壽福寺が上記の状況でネックとなります。

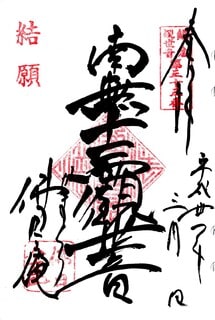
【写真 上(左)】 鎌倉三十三観音霊場第24番・壽福寺の御朱印
【写真 下(右)】 同 第33番・結願の御朱印(円覚寺佛日庵)
結願については事情をお話しすれば結願所で結願印をいただけるかもしれませんが、現況、御朱印コンプリートは難しいかもしれません。
3.鎌倉二十四地蔵霊場
鎌倉の名刹が参画される地蔵霊場で、新型コロナ禍では授与休止の札所もありましたが、現況、書置御朱印であればほとんど授与されている模様です。
ただし、こちらでも第18番札所の壽福寺が上記の状況でネックとなります。

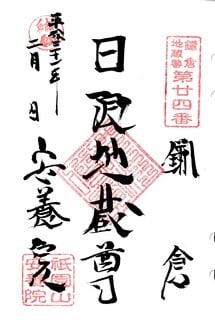
【写真 上(左)】 鎌倉二十四地蔵霊場第18番・壽福寺の御朱印
【写真 下(右)】 同 第24番・結願の御朱印(安養院)
こちらも観音霊場と同様で、御朱印コンプリートは難しいかもしれません。
4.鎌倉十三佛霊場
最近、霊場活動を活発化されている鎌倉の十三佛霊場で、令和5年5月15日より札所が以下のように変更となっています。
第4番札所(普賢菩薩) 壽福寺 → 報国寺
第8番札所(観世音菩薩) 報国寺 → 禅居院
現時点ではすべての札所で御朱印拝受できるので、御朱印コンプリート可能です。
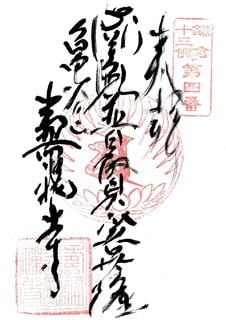
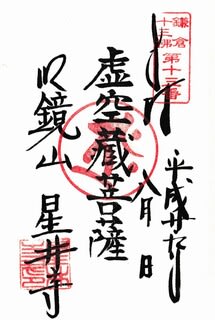
【写真 上(左)】 鎌倉十三佛霊場旧第4番・壽福寺の御朱印
【写真 下(右)】 同 第13番・結願寺の御朱印(星井寺)
5.相州二十一ヶ所霊場
知る人ぞ知る?、鎌倉の弘法大師霊場です。
もともと御朱印難易度が高い霊場ですが、メジャー寺院の札所では申告すれば(御朱印見本にはほぼ掲載されていない)おおむね拝受できます。
ただし、こちらでも第7番札所の壽福寺が上記の状況でネックとなります。
「書置あり」のWeb情報(リンク不可)でも、こちらの御朱印は授与されていないとの由。
また、第20番札所の感応院(藤沢市大鋸)もご不在気味で、郵送対応も不可なので、この霊場の御朱印コンプリートは現況かなり困難かもしれません。

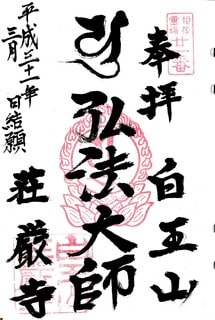
【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所霊場第7番・壽福寺の御朱印
【写真 下(右)】】 同 第21番・結願寺の御朱印(荘厳寺)
6.東国花の寺百ヶ寺霊場
「鎌倉」のエリアカテゴリーを置いているほど鎌倉の札所が多い霊場です。
令和3年5月17日に東慶寺(鎌倉第10番/通番99番)が退会となっており、現況この霊場の御朱印はいただけません。(鎌倉第10番は現在欠番。)
また、令和4年7月末時点の公式リーフレットでは鎌倉第6番(英勝寺)は「欠番」となっていますが、先日(令和5年12月初旬)参拝時には御朱印を拝受でき、公式Webでも鎌倉第6番は英勝寺となっています。

■ 令和4年7月末時点の公式リーフレット
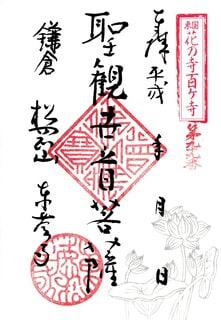
■ 東慶寺(鎌倉旧第10番/通番旧99番)の御朱印

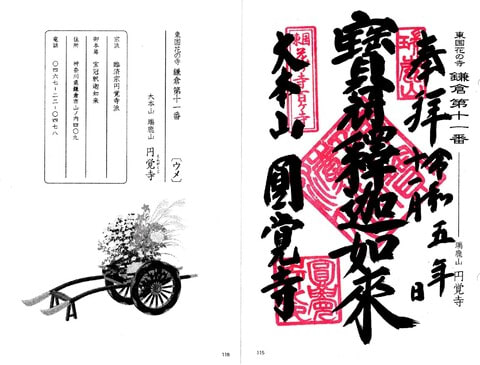
【写真 上(左)】 鎌倉第6番・英勝寺の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉の部結願第11番・圓覚寺の御朱印
-------------------------
なお、鎌倉の霊場(札所)は発願印の授与に厳格で、まっさらの御朱印の1頁目か、専用納経帳を購入しない限り授与いただけません。
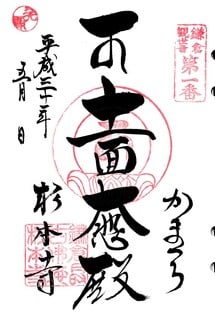
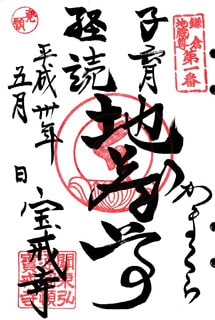
【写真 上(左)】 鎌倉三十三観音霊場 発願の御朱印(杉本寺)
【写真 下(右)】 鎌倉二十四地蔵霊場 発願の御朱印(宝戒寺)
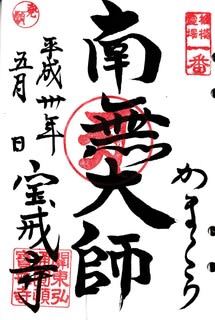

【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所霊場 発願の御朱印(宝戒寺)
【写真 下(右)】 鎌倉十三佛霊場 発願の御朱印(明王院)
【関連記事】
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編&全記事のリスト)
【 BGM 】
■ ヴィヴァルディ: 「四季」より冬
■ Ave Maria - 志方あきこ w / 葉加瀬太郎
■ 冬景色 - はいだしょうこ
そこで、今回は鎌倉でお正月に限定的にいただける御朱印と、知る人ぞ知る御朱印、そして鎌倉関連の霊場の最新状況についてまとめてみました。
【市内の交通状況】
鎌倉市内は下記期間に大規模な車両乗り入れ規制がかけられます。
・大晦日12/31の23:00~元旦1/1の17:00
・1/2、1/3の9:00~17:00
よって、正月三が日の鎌倉への車でのアクセスは原則できません。
鉄道でのアクセスをおすすめしますが、どうしても車で行きたい場合は、東京方面からだとおそらく逗子駅前のコインパーキング(数はかなりある)に停めて、横須賀線で逗子から鎌倉まで1駅乗ってのアクセスとなります。
→ 交通規制情報(鎌倉観光公式ガイド)
【お正月限定の御朱印、知る人ぞ知る御朱印】
お正月限定の御朱印は下記1.2のふたつが有名です。
(他にもあるかも。また、御朱印図柄や印判が変わるなどのケースはたくさんあるようです。)
1.(西御門(にしみかど)/大蔵)白旗神社
鎌倉市西御門2ー1
御祭神:源頼朝公
原則正月三が日のみの書置授与です。授与所は拝殿向かって右手前の授与所。
たしか15時くらいまでだったと思うので、早めの参拝をおすすめします。
(なお、令和6年正月の授与についてはWebで確認できていません。)
源頼朝公の墳墓堂「法華堂」ともふかい関わりをもち、頼朝公を御祭神とする歴史の香り高い神社で、「勝運の神様」として知られています。
→ 関連記事「鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)」

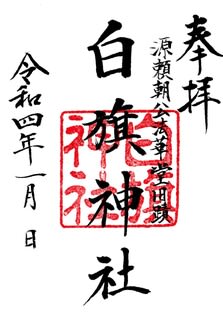
【写真 上(左)】 社頭(正月)
【写真 下(右)】 御朱印
2.(鶴岡八幡宮末社)白旗神社
神奈川県鎌倉市雪ノ下2-1
御祭神:源頼朝公・源実朝公
公式Web(PDF)によると、令和6年正月も授与される模様です。
「数量限定三社一組正月特別朱印」は鶴岡八幡宮・旗上辨戝天社・白旗神社の3社の御朱印がセットになったもので、白旗神社の御朱印は正月限定となります。
正月三が日の授与と思われ、公式Webには「※数に限りがございます。」とあり、授与の可否はそのときの授与状況によりますので、2日、3日の参拝で拝受できるかはわかりません。
また、1日あたりの授与数が決まっている可能性もあるので、元旦のなるべく早い時間の参拝をおすすめします。
境内東側に御鎮座。
源頼朝公・実朝公をお祀りし、学業成就・勝負運の御神徳あらたかとされます。

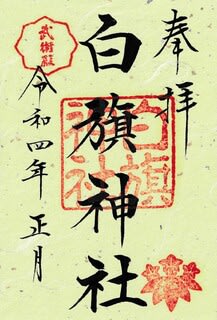
【写真 上(左)】 拝殿
【写真 下(右)】 御朱印
3.由比若宮(元八幡)
鎌倉観光公式ガイド
鎌倉市材木座1-7
御祭神:応神天皇・比売神・神功皇后
こちらは正月限定授与ではありませんが、ご不在が多く授与日がかなり限られている模様なのでご紹介します。
(なお、令和6年正月の授与についてはWebで確認できていませんが、可能性は高いのでは。)
康平六年(1063年)、源頼義公が前九年の役で奥州を鎮定され京に帰る帰途、鎌倉に立ち寄られこの地に源氏の守り神である京の石清水八幡宮の御祭神を勧請されて創祀と伝わります。
後に源頼朝公が現在の鶴岡八幡宮の地(小林郷北山)に社殿を遷してからは、「元八幡」とも呼ばれるようになりました。
鶴岡八幡宮境内には、由比若宮(元八幡)遥拝所があります。


【写真 上(左)】 由比若宮遙拝所(鶴岡八幡宮境内)
【写真 下(右)】 由比若宮の拝殿
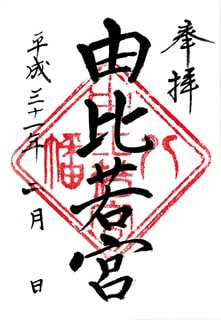
■ 御朱印
→ 関連記事「■「鎌倉殿の13人」と御朱印-1」
4.甘縄神明宮
鎌倉市長谷1-12-1
御祭神:天照大御神
こちらは正月限定ではありませんが、御朱印については意外に知られていないようなので御紹介します。
長谷の観光地近くに御鎮座ですが、やや奥まっているので参拝者は少なく御朱印もいただけそうな感じがありません。
しかし、参拝後、大町の八雲神社にて申告すると御朱印を授与いただけます。
和銅三年(710年)行基菩薩の草創、染谷太郎太夫時忠の創建と伝わり、鎌倉最古のお社ともいわれます。
永保元年(1081年)源義家公が社殿を再建、以降も源頼朝公、政子の方、源実朝公などの崇敬が篤かったと伝わります。
また、源頼義公が相模守として下向の折に当宮に祈願し、八幡太郎義家公が生まれたとも伝えられ、源氏とつよい所縁をもちます。
社殿がある場所は有力御家人・安達盛長の屋敷跡とされています。


【写真 上(左)】 甘縄神明宮
【写真 下(右)】 御朱印
→ 関連記事「■「鎌倉殿の13人」と御朱印-1」
5.(浄明寺)熊野神社
鎌倉市浄明寺3-8-55
御祭神:天宇須女命、伊弉諾命、伊弉册命
浄妙寺の西北に御鎮座の熊野神社。
森閑とした山中に御鎮座で、御朱印もいただけそうな感じがありません。
しかし、こちらも参拝後、大町の八雲神社にて申告すると御朱印を授与いただけます。
朝比奈切通しそばにも熊野神社がありますがこちらは横浜市金沢区の所在で、当社とは別のお社です。
境内由来書などになると、応永年間(1394-1427年)および永正年間(1504-1520年)に社殿を再建したと伝えられ、明治6年、国より正式に浄明寺地区の鎮守として公認されています。


【写真 上(左)】 (浄明寺)熊野神社
【写真 下(右)】 御朱印
→ 関連記事「■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)」
6.巌窟堂 岩谷不動尊
鎌倉市雪ノ下2-2-21
宗派不明
御本尊:不動明王
こちらは鎌倉の御朱印ガイドなどにもなかなか載っていない知る人ぞ知る御朱印で、正月限定ではありません。
ただし、雪ノ下の不動茶屋の営業日・営業時間内にしかいただけません。(正月の営業予定については不明。)
弘法大師の御作と伝わる由緒正しいお不動様で、頼朝公が伊豆の日金山から勧請した日金地蔵尊(日金山松源寺)のとなりにあったという歴史の香り高いところです。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 御朱印
→ 関連記事「■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)」
7.禅居院
鎌倉市山ノ内1534
臨済宗建長寺派
御本尊:聖観世音菩薩
建長寺の塔頭寺院で原則一般拝観不可ですが、令和5年5月15日より鎌倉十三佛霊場第8番札所となられ、鎌倉十三佛の巡拝者のみ限定で入山でき御朱印も拝受できるようになりました。
ただし、鎌倉十三佛霊場事務局ではオリジナル(専用)御朱印帳での集印を推奨されている模様で、汎用御朱印帳のみで入山が認められるかは不明です。
なお、入山に当たっては決まり事がありますのでご留意ください。
建長寺22世で鎌倉五山の浄智寺、円覚寺、京都五山の建仁寺、また五山の上位とされる南禅寺の住職を勅命により歴任された清拙正澄(大鑑禅師)の塔所寺院です。


【写真 上(左)】 禅居院
【写真 下(右)】 御朱印
8.多宝谷山 妙傳寺
鎌倉市扇ガ谷2-21-3
日蓮宗
御首題授与についてはながらく不明でしたが、先日拝受できました。
原則無住のようですが、定期的に御住職がこられるので、タイミングが合えば御首題を拝受できます。
ただし、御首題帳の用意がベターかと。
(正月の授与については不明です。→ 参考Web)
承応元年(1652年)、水戸藩主徳川頼房公が祈願所として現在の東京都文京区白山に創建した寺院が前身。
昭和20年(1945年)の東京大空襲で伽藍を焼失し、昭和49年(1974年)現在地へ移転した、鎌倉では比較的あたらしい寺院です。
なお、この地は弘長二年(1262年)忍性が開山した泉ヶ谷多宝寺の跡ともいわれます。


【写真 上(左)】 妙傳寺
【写真 下(右)】 御首題
-------------------------
■ 鎌倉関連の霊場御朱印の最新情報について
鎌倉にはいくつかの霊場があります。
そのうち、とくに御朱印関係の最新情報(令和5年12月初旬時点)をご紹介してみます。
1.鎌倉五山
こちらは霊場ではありませんが、とりあげてみます。
「五山」とは、南宋の寧宗のころにインドの五精舎十塔所にならって創設された寺格制度で、鎌倉にある五つの禅宗の寺院、建長寺、圓覚寺、壽福寺、浄智寺、浄妙寺をいいます。
「鎌倉五山」は鎌倉観光公式ガイドWebでも紹介され、「鎌倉の御朱印入門コース」とする御朱印ガイドもあります。
しかし、現時点(令和5年12月時点)で、この「鎌倉五山」の御朱印が揃わない可能性があります。
その理由は、第三位の壽福寺の御朱印を拝受できない可能性があるからです。
壽福寺の御朱印については、従前から拝受難易度の高さで知られていました。
ただし、「鎌倉五山」(御本尊)の御朱印については、比較的すんなりとお出しいただけた記憶があります。
ある時期から御朱印の授与自体を休止されているという情報があるものの、書置ながら拝受できるというWeb情報(リンク不可)もあり、実際、Web上でも新型コロナ禍以降の書置御朱印がいくつかUPされています。


【写真 上(左)】 壽福寺参道
【写真 下(右)】 御朱印休止中の掲示
しかし、先日(令和5年12月初旬)の参拝時には「御朱印休止中」の掲示が出ており御朱印は授与されていませんでした。
どうにも腑に落ちなかったので、鎌倉市観光協会に電話で尋ねてみました。
・壽福寺の御朱印は目下原則授与休止中となっているようだが、たまに授与所前で書置のものが授与されている場合があると聞く。
・複数の霊場札所を兼ねられているので、巡拝者の方から複数の問合せをいただいている。
・観光協会からも何度かお寺様に問合せしているが、電話がほとんど通じず状況がわからずに苦慮している。
・札所について、鎌倉十三佛については本年(令和5年)5月15日より第4番札所が壽福寺から報国寺に変更となっているが、他の霊場の札所変更の動きについては聞いていない。
・札所変更については関連の寺院様等でお決めになることなので、観光協会から働きかけることはできない。
回答された方の物腰ははなはだ恐縮モードで、それ以上問い詰めることもできず(笑)、お礼を述べて電話を切りました。
このやりとりは当山の山門前でしたのですが、その間にも「御朱印休止中」の掲示をみて、残念そうに引き返す方がおられました。
(まぁ、ふつうの人は(笑)観光協会まで電話して状況確認まではしないと思う。)
じっさい、鎌倉観光公式ガイドWebにも「しばらくの間、御朱印はお休みいたします※お電話によるお問い合わせはご遠慮ください」との記載があります。
現況からすると、このようにしか書き様がないかと思います。
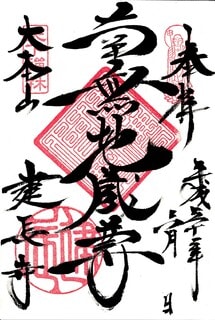

【写真 上(左)】 第一位 建長寺の御朱印
【写真 下(右)】 第一位 建長寺の扁額

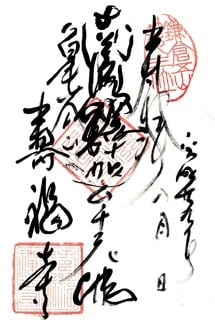
【写真 上(左)】 第二位 圓覚寺の御朱印
【写真 下(右)】 第三位 壽福寺の御朱印

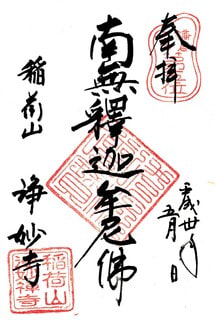
【写真 上(左)】 第四位 浄智寺の御朱印
【写真 下(右)】 第五位 浄妙寺の御朱印
2.鎌倉三十三観音霊場
鎌倉の名刹が参画される観音霊場で、新型コロナ禍では授与休止の札所もありましたが、現況、書置御朱印であればほとんど授与されている模様です。
ただし、こちらでも第24番札所の壽福寺が上記の状況でネックとなります。

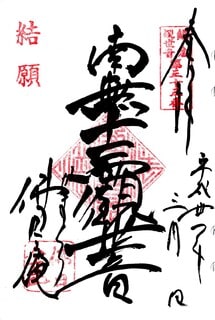
【写真 上(左)】 鎌倉三十三観音霊場第24番・壽福寺の御朱印
【写真 下(右)】 同 第33番・結願の御朱印(円覚寺佛日庵)
結願については事情をお話しすれば結願所で結願印をいただけるかもしれませんが、現況、御朱印コンプリートは難しいかもしれません。
3.鎌倉二十四地蔵霊場
鎌倉の名刹が参画される地蔵霊場で、新型コロナ禍では授与休止の札所もありましたが、現況、書置御朱印であればほとんど授与されている模様です。
ただし、こちらでも第18番札所の壽福寺が上記の状況でネックとなります。

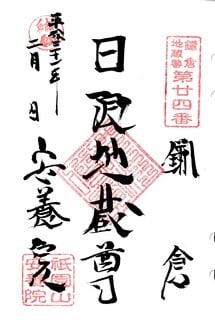
【写真 上(左)】 鎌倉二十四地蔵霊場第18番・壽福寺の御朱印
【写真 下(右)】 同 第24番・結願の御朱印(安養院)
こちらも観音霊場と同様で、御朱印コンプリートは難しいかもしれません。
4.鎌倉十三佛霊場
最近、霊場活動を活発化されている鎌倉の十三佛霊場で、令和5年5月15日より札所が以下のように変更となっています。
第4番札所(普賢菩薩) 壽福寺 → 報国寺
第8番札所(観世音菩薩) 報国寺 → 禅居院
現時点ではすべての札所で御朱印拝受できるので、御朱印コンプリート可能です。
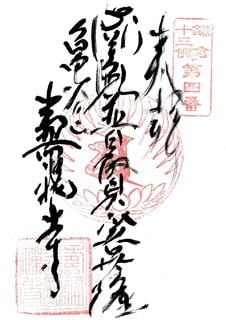
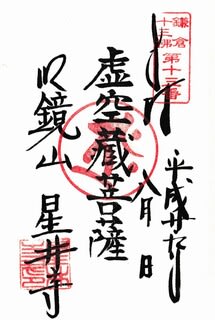
【写真 上(左)】 鎌倉十三佛霊場旧第4番・壽福寺の御朱印
【写真 下(右)】 同 第13番・結願寺の御朱印(星井寺)
5.相州二十一ヶ所霊場
知る人ぞ知る?、鎌倉の弘法大師霊場です。
もともと御朱印難易度が高い霊場ですが、メジャー寺院の札所では申告すれば(御朱印見本にはほぼ掲載されていない)おおむね拝受できます。
ただし、こちらでも第7番札所の壽福寺が上記の状況でネックとなります。
「書置あり」のWeb情報(リンク不可)でも、こちらの御朱印は授与されていないとの由。
また、第20番札所の感応院(藤沢市大鋸)もご不在気味で、郵送対応も不可なので、この霊場の御朱印コンプリートは現況かなり困難かもしれません。

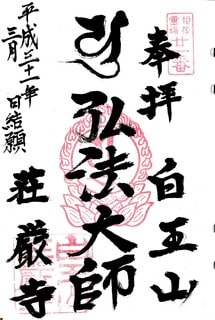
【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所霊場第7番・壽福寺の御朱印
【写真 下(右)】】 同 第21番・結願寺の御朱印(荘厳寺)
6.東国花の寺百ヶ寺霊場
「鎌倉」のエリアカテゴリーを置いているほど鎌倉の札所が多い霊場です。
令和3年5月17日に東慶寺(鎌倉第10番/通番99番)が退会となっており、現況この霊場の御朱印はいただけません。(鎌倉第10番は現在欠番。)
また、令和4年7月末時点の公式リーフレットでは鎌倉第6番(英勝寺)は「欠番」となっていますが、先日(令和5年12月初旬)参拝時には御朱印を拝受でき、公式Webでも鎌倉第6番は英勝寺となっています。

■ 令和4年7月末時点の公式リーフレット
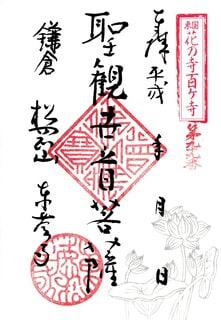
■ 東慶寺(鎌倉旧第10番/通番旧99番)の御朱印

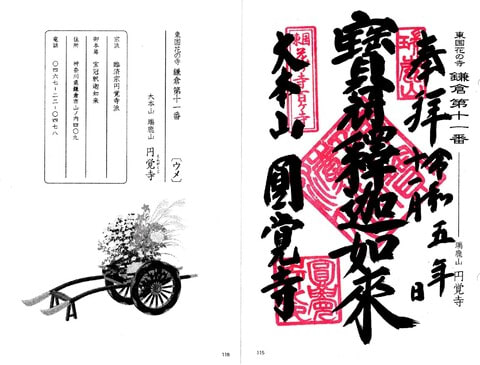
【写真 上(左)】 鎌倉第6番・英勝寺の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉の部結願第11番・圓覚寺の御朱印
-------------------------
なお、鎌倉の霊場(札所)は発願印の授与に厳格で、まっさらの御朱印の1頁目か、専用納経帳を購入しない限り授与いただけません。
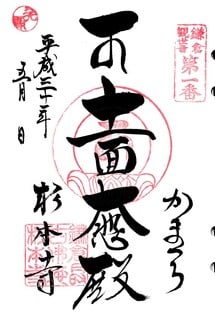
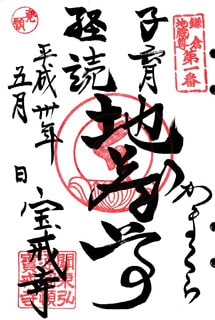
【写真 上(左)】 鎌倉三十三観音霊場 発願の御朱印(杉本寺)
【写真 下(右)】 鎌倉二十四地蔵霊場 発願の御朱印(宝戒寺)
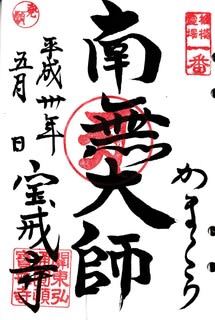

【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所霊場 発願の御朱印(宝戒寺)
【写真 下(右)】 鎌倉十三佛霊場 発願の御朱印(明王院)
【関連記事】
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編&全記事のリスト)
【 BGM 】
■ ヴィヴァルディ: 「四季」より冬
■ Ave Maria - 志方あきこ w / 葉加瀬太郎
■ 冬景色 - はいだしょうこ
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-19
Vol.-18からのつづきです。
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第55番 瑠璃光山 薬王寺 長久院
(ちょうきゅういん)
台東区谷中6-2-16
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第55番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第8番、弘法大師二十一ヶ寺第19番、閻魔三拾遺第4番、江戸・東京四十四閻魔参り第12番
第55番は谷中の長久院です。
第55番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに長久院で、第55番札所は開創当初から谷中の長久院であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
長久院は、慶長十六年(1611年)幕府より賜地を得て宥意上人が神田北寺町に開山、慶安十一年(1658年)幕府による寺地召上げを受け、代地として賜った谷中の現在地へ移転したといいます。
『下谷区史 〔本編〕』によると、神田北寺町での賜地および創建、谷中への移転の事由や時期は多寶院(第49番)、自性院(第53番)と同様とみられます。
江戸期の長久院は、本堂に御本尊の金剛界大日如来、弘法大師、興教大師、不動尊、愛染明王、薬師如来、歓喜天三躰、地蔵尊を奉安し、御府内霊場としての要件を満たしていたとみられます。
本堂とは別に閻魔法王石像(台石とも六尺)を奉安。
こちらは閻魔三拾遺第4番、江戸・東京四十四閻魔参り第12番の札所となっており、御府内でも著名な閻魔様であったことがわかります。
こちらの閻魔法王石像は右左にそれぞれ司命、司録像を配し「六十六部造立石造閻魔王坐像及び両脇侍像」として台東区登載文化財に指定されています。
なお、閻魔法王(大王)王冥界の王で、司命は閻魔王の判決を言い渡し、司録は判決内容を記録する従者であるとされます。
台座銘文に六十六部聖の光誉円心が享保十一年(1726年)に造立とあります。
六十六部聖とは、生前の罪障を滅し、死後の往生に近づくために法華経を六十六部写経し、全国の六十六箇所の霊場に一部ずつ奉納して回る聖のことをいいます。
六十六部聖は巡拝先に奉納経石塔を建立することが多いですが、石仏を奉納する例もみられます。
石仏は地蔵菩薩が多く、閻魔王像は極めて稀であるとされ、この稀少さもあって区登載文化財に指定されている模様です。
『寺社書上』には「飯縄不動安置」とあり、飯縄修験の流れが入っていた可能性があります。
同じく『寺社書上』にある「稲荷社」は、鎮守神かもしれません。
長久院は「弘法大師二十一ヶ寺」第19番の札所でもあります。
この霊場は、「弘法大師二十一ヶ寺御詠歌所附版木」が伝える弘法大師霊場で、この附版木は寛政二年(1790年)の開版ですからかなり古い来歴をもちます。
これとは別に「弘法大師 御府内二十一ヶ所」という霊場もあります。
「ニッポンの霊場」様によると、この霊場は元禄(1688年)から宝暦(1751年)の間に開創とされる古い霊場で、宝暦五年(1755年)頃の開創とされる御府内霊場より古い可能性があります。
二十一ヶ所霊場は、八十八ヶ所霊場のミニ版として開創され八十八ヶ所と札所が重複するケースもみられますが、「弘法大師二十一ヶ寺」「弘法大師 御府内二十一ヶ所」ともに御府内霊場(八十八ヶ所)との札所重複は多くありません。
「弘法大師二十一ヶ寺」はお大師さまのご縁日二十一日に因んでの開創なので合点がいきますが、「弘法大師 御府内二十一ヶ所」についてはナゾが残ります。
「弘法大師二十一ヶ寺」はなにかのWeb資料から札所情報を入手しましたが、いま検索してもヒットしません。ご参考までにリストします。
【弘法大師二十一ヶ寺】
1番 萬昌山 金剛幢院 圓満寺
真言宗御室派 文京区湯島1-6-2
2番 宝塔山 多寶院
真言宗豊山派 台東区谷中6-2-35
3番 五剣山 普門寺 大乗院
真言宗智山派 台東区元浅草4-5-16
4番 清光院 台東区下谷(廃寺)
5番 恵日山 延命寺 地蔵院
真言宗智山派 台東区元浅草1-15-8
6番 阿遮山 円満寺 不動院
真言宗智山派 台東区寿2-5-2
7番 峯松山 遮那院 仙蔵寺
真言宗智山派 台東区寿2-8-15
8番 高野山 金剛閣 大徳院
高野山真言宗 墨田区両国2-7-13
9番 青林山 最勝寺 龍福院
真言宗智山派 台東区元浅草3-17-2
10番 本覚山 宝光寺 自性院
新義真言宗 台東区谷中6-2-8
11番 摩尼山 隆全寺 吉祥院
真言宗智山派 台東区元浅草2-1-14
12番 神勝山 成就院
真言宗智山派 台東区元浅草4-8-12
13番 広幡山 観蔵院
真言宗智山派 台東区元浅草3-18-5
14番 望月山 般若寺 正福院
真言宗智山派 台東区元浅草4-7-21
15番 仏到山 無量寿院 西光寺
新義真言宗 台東区谷中6-2-20
16番 鶴亭山 隆全寺 威光院
真言宗智山派 台東区寿2-6-8
17番 十善山 蓮花寺 密蔵院
真言宗御室派 中野区沼袋2-33-4(移転)
18番 象頭山 観音寺 本智院
真言宗智山派 北区滝野川1-58-2
19番 瑠璃光山 薬王寺 長久院
真言宗豊山派 台東区谷中6-2-16
20番 玉龍山 弘憲寺 延命院
真言宗智山派 台東区元浅草4-5-2
21番 宝林山 大悲心院 霊雲寺
真言宗霊雲寺派 文京区湯島2-21-6
このうち、「御府内八十八ヶ所」「弘法大師二十一ヶ寺」「弘法大師 御府内二十一ヶ所」の3つの霊場すべての札所となっているのは、霊雲寺(第28番/湯島)、多寶院(第49番/谷中)、自性院(第53番/谷中)、長久院(第55番/谷中)の4箇寺しかなく、札所重複が少ないことを示しています。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
五十五番
谷中寺町
瑠璃光山 薬王寺 長久院
本所弥勒寺末 新義
本尊:阿弥陀如来 弘法大師 興教大師
■ 『寺社書上 [110] 谷中寺社書上 弐』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.97』
谷中不唱小名
新義真言宗 本所弥勒寺末
瑠璃光山薬師寺長久院
慶長十六年(1611年)二月、神田北寺町ニ●寺地拝領仕 其後慶安元年(1648年)右地所御用地ニ相成 同年十一月廿一日当所ニ●代地拝領仕候
開山宥意 寛永四年(1627年)正月三日寂
本堂
本尊金剛 大日如来木像
弘法大師 興教大師 不動尊
愛染明王木坐像 薬師如来木坐像 歓喜天三躰金佛厨子入 地蔵尊木立像
宝篋印塔
閻魔法王石像、臺石共六尺
稲荷社
飯縄不動安置
■ 『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)
長久院(谷中上三崎町一七番地)
本所彌勒寺末、瑠璃光山薬師寺と号す。本尊大日如来。当寺も亦多寶院、自性院等と同じく慶長十六年(1611年)二月、幕府より神田北寺町に地を給うて開創せられ、慶安元年(1648年)現地に移ったのである。開山は僧宥意。(寛永四年(1627年)一月三日寂)
境内に飯綱不動、石像閻魔等を安置する。

「長久院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
※『江戸切絵図』では「長久寺」となっています。
-------------------------
最寄りはJR「日暮里」駅で徒歩約10分。
東京メトロ千代田線「根津」駅からも歩けます。
三崎坂から南下して瑞輪寺よこを通り一乗寺に向かう路地沿いには、いくつかの寺院があってそのひとつ。
谷中寺町のほぼ中心部です。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 閉門時の山門
路地から少し引き込み、左右に築地塀と植栽をめぐらした山門の構えはなかなか風格があります。
山門は切妻屋根桟瓦葺の薬医門ないし高麗門で、見上げに院号扁額を掲げています。
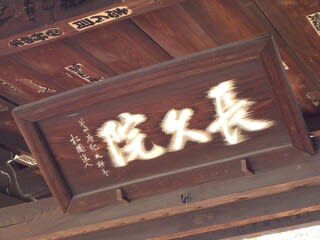

【写真 上(左)】 山門の扁額
【写真 下(右)】 山内
山門をくぐると左手に智拳印を結ばれる金剛界大日如来像。


【写真 上(左)】 大日如来像
【写真 下(右)】 本堂と大師堂
参道正面が庫裡で、その右手に本堂、さらにその右手前に直角に向きを変えて大師堂。
本堂は寄棟造桟瓦葺流れ向拝、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に本蟇股。
端正に整ったいい本堂です。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 閻魔様
本堂向かって右の堂前には、閻魔様、司命、司録が御座しています。
そばには「『笑いえんま』とよばれています。」という木板も掲げられていました。


【写真 上(左)】 大師堂
【写真 下(右)】 大師堂の扁額
大師堂は屋根に宝珠をおいた宝形造で流れ向拝。
向拝まわりの柱や虹梁はいずれも直線で、きっちりまとまった印象です。
御朱印は本堂向かって左の庫裡にて拝受しました。
なお、こちらは16:00閉門なので、時間に余裕をもった参拝をおすすめします。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
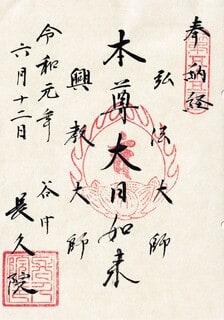

【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊大日如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「第五十五番」の札所印。左に院号の揮毫と寺院印が捺されています
■ 第56番 宝珠山 地蔵院 與楽寺
(よらくじ)
北区田端1-25-1
真言宗豊山派
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第56番、豊島八十八ヶ所第56番、武州江戸六阿弥陀霊場第4番、大東京百観音霊場第82番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第21番、九品仏霊場第3番(上品下生)、豊島六地蔵霊場第1番、滝野川寺院めぐり第1番
※本記事は「■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印」および「■ 滝野川寺院めぐり-1」から転載・追記したものです。
第56番は田端の與楽寺です。
第56番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに與楽寺で、第56番札所は開創当初から田端の與楽寺であったとみられます。
北区観光ホームページ、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
與楽寺は弘法大師の建立とも伝わる密寺で、慶安元年(1648年)に寺領二十石の御朱印状を拝領、京都仁和寺の関東末寺の取締役寺を務められ末寺20余を擁したとされる名刹です。
『滝野川寺院めぐり案内』には康歴三年(1381年)銘の石塔の存在が記され、開創は相当に古そうです。
弘法大師の御作とも伝わる御本尊の地蔵菩薩は「賊除け地蔵尊」と呼ばれ、つぎの逸話が伝わります。
昔、ある晩、盗賊が與楽寺に押し入ろうとした時、どこからともなく多数の僧侶が出てきて盗賊の侵入を防ぎ、遂にこれを追い返してしまいました。
翌朝、御本尊の地蔵菩薩の足に泥がついているのが発見され、地蔵菩薩が僧侶に姿を変えられて盗賊を追い出したのだと信じられるようになりました。
これより御本尊の地蔵菩薩は、賊除地蔵尊と称されるようになりました。
これが與楽寺の賊除け地蔵伝説です。
與楽寺は武州江戸六阿弥陀霊場第4番札所でもあります。
武州江戸六阿弥陀霊場(江戸六阿弥陀)は、行基菩薩が一夜の内に一本の木から刻み上げた六体の阿弥陀仏と、余り木で刻した阿弥陀仏、残り木(末木)で刻した聖観世音菩薩を巡拝する八箇寺からなる阿弥陀霊場で、女人成仏の阿弥陀仏として崇められ、江戸中期から大正時代にかけて、とくに春秋の彼岸の頃に女性を中心として盛んに巡拝されたといわれます。
開創年代については諸説あり錯綜していますが、札所は確定しています。
第1番目 三縁山 無量壽院 西福寺
北区豊島2-14-1 真言宗豊山派
第2番目 宮城山 円明院 恵明寺(旧小台村延命院)
足立区江北2-4-3 真言宗系単立
第3番目 佛寶山 西光院 無量寺
北区西ケ原1-34-8 真言宗豊山派
第4番目 宝珠山 地蔵院 與楽寺
北区田端1-25-1 真言宗豊山派
第5番目 福増山 常楽院
調布市西つつじヶ丘4-9-1(旧下谷(上野)広小路) 天台宗
第6番目 西帰山 常光寺
江東区亀戸4-48-3 曹洞宗
木余の弥陀 龍燈山 貞香院 性翁寺
足立区扇2-19-3 浄土宗
木残(末木)の観音 補陀山 昌林寺
北区西ケ原3-12-6 曹洞宗
※武州江戸六阿弥陀霊場についてはこちらをご覧ください。
境内には密教の思想を表した南北朝時代の四面に仏を浮彫りにした南北朝時代の石の仏塔(四面四仏石塔屋)や、江戸時代の巡拝塔、廻国供養塔などがあります。
近在有数の名刹ゆえ、複数の霊場の札所を兼ねられますが、とくに御府内霊場と武州江戸六阿弥陀の参拝者が多いのでは。
また、こちらは滝野川寺院めぐり第1番発願寺でもあります。
こちらのご住職は滝野川寺院めぐり開創当時の滝野川仏教会の会長で、そのことから札所1番発願寺を務められているものと思われます。
→滝野川寺院めぐりについては、こちらをご覧ください。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
五十六番
田ばた村
宝珠山 地蔵院 与楽寺
京都仁和寺宮 壇林所 新義
本尊:延命地蔵菩薩 不動明王 弘法大師
御朱印弐拾石 拾八ヶ寺本地
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
新義真言宗京都仁和寺末 寶珠山地蔵院ト号ス 慶安元年八月二十四日寺領二十石ノ御朱印を賜フ 本尊地蔵ハ弘法大師ノ作ナリ 昔当寺へ或夜賊押入シ時 イツク●ナク数多ノ僧出テ賊ヲ防キ遂ニ追退タリ 翌朝本尊ノ足泥ニ汚レアリシカハ 是ヨリ賊除ノ地蔵ト号スト傳フ 開山ヲ秀榮ト云
鐘樓 寶暦元年鑄造ノ鐘ヲカク
阿彌陀堂 本尊ハ行基ノ作ニテ六阿彌陀ノ第四番ナリ
九品佛堂 是モ近郷九品阿彌陀佛ノ内第三番ナリト云
稲荷社

「与楽寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはJR「田端」駅で徒歩約4分。
田端駅は北口こそそれなりに賑やかですが、南口は降り立ったそばからまったくの住宅街で、山手線の駅前とはとても思えないのどかな空気がただよっています。
ここから南に与楽寺坂を下っていくと、左手に與楽寺が見えてきます。

【絵図】 江戸時代後期の田端村(北区教育委員会の與楽寺前説明板より/出典『江戸名所図絵』)
この坂のそばにはかつて芥川龍之介など文人の居宅があり、いまでも落ち着いたたたずまいを見せています。
芥川龍之介は、あたりの風景を「田端はどこへ入っても黄白い木の葉ばかりだ。夜とほると秋の匂がする」と描写しています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 修行大師像と札所標
豊島郡有数の名刹の歴史を語るように、ゆったりとした間口を構えます。
山門は平成29年(2017年)建立で、切妻造本瓦葺の立派な四脚門。
山門左手には修行大師像と、御府内霊場第五十六番、六阿弥陀第四番の両札所標、それに上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所標「西國廿一番 丹波國阿のう寺写」があります。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 霊堂
参道を進むと左手に霊堂。宝形造唐破風向拝の少し変わった雰囲気のお堂です。
その先には鐘楼。さらに進んだ右手にも宝形造のお堂があって、伽藍は整っています。
境内はよく整備され、名刹特有の荘厳な空気がただよっています。


【写真 上(左)】 鐘楼
【写真 下(右)】 右手のお堂と客殿


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
参道正面に本堂。
入母屋造本瓦葺流れ向拝。降り棟、隅棟、稚児棟をきっちり備える堂々たる仏殿です。
水引虹梁両端に雲形木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁と雲形の手挟を伸ばし、中備に板蟇股を置いています。
正面桟唐戸の上に「與楽寺」の扁額。
向拝両脇の花頭窓と身舎欄間の菱格子が、引き締まった印象を与えます。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂向拝見上げ
本堂に御座す御本尊の地蔵菩薩は弘法大師の御作と伝わり、盗賊の侵入を追い返された「賊除地蔵」としても知られる秘仏です。
本堂右手が客殿。切妻造桟瓦葺唐破風付きの整った意匠は、本瓦葺の本堂とバランスのよい対比を見せています。
本堂右手脇にも上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所標がありますが、こちらは「西國弐拾九番」となっています。
第29番は東覚寺で、標中に「是」「道」の文字があるので、札所導標かもしれません。


【写真 上(左)】 客殿
【写真 下(右)】 阿弥陀堂
本堂向かって右手が阿弥陀堂で、こちらは武州江戸六阿弥陀第4番目の札所です。
「江戸六阿弥陀」と「滝野川寺院めぐり」とは複数の札所(第1番與楽寺、第9番無量寺、第10番昌林寺)が重複しています。
入母屋造桟瓦葺流れ向拝。水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。
正面板戸の上に「六阿弥陀 第四番」の扁額。
シンプルな虹梁と両脇の連子が効いて、シャープな印象の向拝です。
札所本尊の阿弥陀如来は行基作と伝わります。


【写真 上(左)】 阿弥陀堂の扁額
【写真 下(右)】 本堂と阿弥陀堂のあいだのナゾのお堂
阿弥陀堂の右手、本堂とのあいだにもうひとつ宝形造のナゾのお堂がありますが詳細不明。
お堂の手前に観音様の線刻碑があるので、観音堂かもしれません。
御朱印は本堂向かって右手の客殿で拝受します。ここは5回以上参拝していますが、いずれも揮毫御朱印をいただけました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

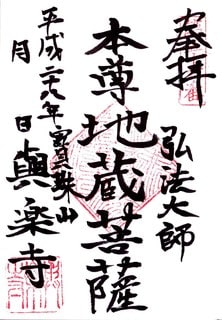
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 地蔵菩薩」「弘法大師」の揮毫と三寶印(蓮華座+宝珠)。
右に「第五十六番」の札所印。左に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

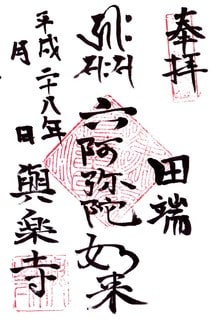
【写真 上(左)】 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 江戸六阿弥陀第4番目の御朱印
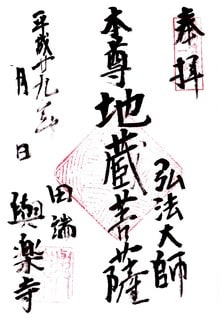
■ 滝野川寺院めぐりの御朱印
■ 第57番 天瑞山 観福寺 明王院
(みょうおういん)
台東区谷中5-4-2
真言宗豊山派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第57番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第5番
第57番は谷中の明王院です。
第57番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに明王院で、第57番札所は開創当初から谷中の明王院であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
明王院は、慶長十六年(1611年)二月、御水尾天皇の勅願により、幕府より神田北寺(小寺)町に寺地を給せられ、僧辨圓が創建。慶安元年(1648年)同所が幕府用地となつたため谷中に移ったといいます。
『下谷区史 〔本編〕』によると、神田北寺町での幕府からの賜地、谷中への移転の事由や時期は多寶院(第49番)、自性院(第53番)、長久院(第55番)と同様とみられますが、『ルートガイド』には慶安元年(1648年)に一旦谷中清水坂に遷ったあと、万治三年(1660年)に現地に移転とあります。
本堂には御本尊阿弥陀如来を奉安。
境内聖天堂には大聖歓喜天尊と本地十一面観世音菩薩、不動堂には不動尊、大師堂には弘法大師像を安置と伝わり、御府内霊場としての要件を満たしていたとみられます。
『寺社書上』にある「稲荷社」は、鎮守神かもしれません。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
五十七番
谷中三●●町
天瑞山 観福寺 明王院
本所弥勒寺末 新義
本尊:阿弥陀如来 弘法大師 興教大師
■ 『寺社書上 [111] 谷中寺社書上 三』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.101』
谷中不唱小名
新義真言宗 本所彌勒寺末
天瑞山歓福寺明王院
権現様御代慶長十六年(1611年) 開山辨圓法印代 於神田小寺町ニ拝領仕候
大猷院様御代慶安元年(1648年)中、右之寺地御用地ニ付被召上、谷中●代地拝領仕候
開山 辨圓法印 寛永五十月四日遷化
中興開基 朝誉法印、宝永三年(1706年)遷化
本堂
本尊 阿弥陀佛 丈一尺七寸立像
聖天宮 尊像金佛秘尊 本地十一面観音立像
不動堂 不動尊丈五寸座像
稲荷社 神躯幣束
■ 『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)
明王院(谷中初音町一丁目二三番地)
本所彌勒寺末、天瑞山觀福寺と号す。本尊三尊彌陀如来。
当寺も慶長十六年(1611年)二月、幕府より神田北寺町に於て寺地を給せられ、僧辨圓の建立する所で、慶安元年(1648年)同所は幕府用地となつたため現地に移つた。
境内聖天堂には大聖歓喜天像を安置し、大師堂には弘法大師像を安置する。

「明王院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは東京メトロ千代田線「千駄木」で徒歩約5分。
JR「日暮里」駅からも歩けます。
千駄木から谷中霊園へ向かう三崎坂をほぼ登り切ったところに道に面してあります。
このあたりも谷中寺町のほぼ中心部に当たります。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 院号標
山内入口の門柱は院号標を兼ねています。
参道左手に六地蔵、正面に大師堂がみえます。
大師堂前を斜め左に折れると、その正面が本堂です。
山内は手入れが行き届いてきもちがいいです。
大師堂右手前には、椅子式の牀座に坐される真如親王様の弘法大師像が刻まれた見事な宝篋印塔(納経塔?)があります。


【写真 上(左)】 六地蔵
【写真 下(右)】 宝篋印塔
当山は明治17年(1884年)の火災で堂宇を焼失し、本堂は昭和46年(1971年)、大師堂は平成7年(1995年)に再建されています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 天水鉢


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額
本堂は宝形造桟瓦葺流れ向拝で、屋根には火焔宝珠を置いています。
近代建築で向拝まわりはコンクリ造ですが、小壁に菱格子、向拝左右に花頭窓を置き引き締まった意匠です。
向拝見上げには山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 大師堂(手前)と本堂(奥)
【写真 下(右)】 大師堂
大師堂は宝形造本瓦葺で向拝柱はなく、屋根には宝珠を置いています。
大師堂前から拝むと、本堂の桟瓦と大師堂の本瓦、本堂の火焔宝珠と大師堂の宝珠が呼応して、見応えのある意匠となっています。
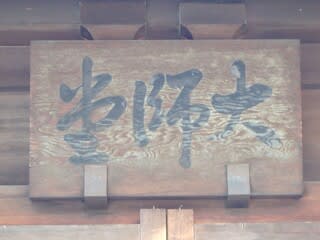

【写真 上(左)】 大師堂扁額
【写真 下(右)】 注意書き
山内には納経ないし読経を促す掲示があり、勤行式を貸し出しいただけます。
「大師堂のお大師さま、本堂の阿弥陀如来両方にお参り下さい。」とあるので、やはり御府内霊場(というか弘法大師霊場)の正式参拝はお大師さまと御本尊(ないし札所本尊)への参拝ということになるのでしょう。
御朱印は本堂向かって左手前の庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
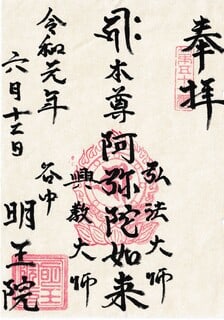
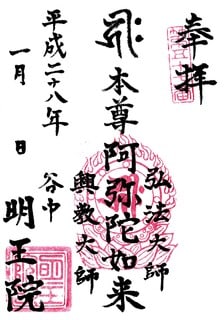
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に阿弥陀如来のお種子「キリーク」「本尊阿弥陀如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫と「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「第五十七番」の札所印。左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第58番 七星山 息災寺 光徳院
(こうとくいん)
公式Web
中野区上高田5-18-3
真言宗豊山派
御本尊:千手観世音菩薩
札所本尊:千手観世音菩薩
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第58番、山の手三十三観音霊場第22番、大東京百観音霊場第65番
第58番は中野・上高田の光徳院です。
第58番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに光徳院で、第58番札所は開創当初から光徳院であったとみられます。
公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
光徳院の創建年代等は不詳ながら、開山の亮珍和尚が寛永十八年(1641年)寂なのでそれ以前の創建とみられます。
開創は二番町(半蔵門)の地で、慶長十一年(1606年)、江戸城構築(拡張)の際に二番町(半蔵門)から市ヶ谷田町へ、寛永十二年(1635年)市ヶ谷柳町へ移転したともいいます。
さらに牛込柳町に遷った後、明治43年に中野・上高田の当地に移転しました。
なお、中野・上高田は御府内から移転した寺院で一種の寺町を形成しています。
寺宝の千手観世音菩薩は高さ三尺三寸の木像で、「子育観音」と呼ばれます。
第六〇代醍醐天皇の御代延喜元年(901年)に右大臣菅原道真公が筑紫・大宰府に左遷のみぎり、自刻され供養礼拝された尊像と伝わります。
久しく筑紫の千手坊に御座しましたが、縁あって中野宝仙寺の十四世秀雄法印に預けられ、秀雄法印が中野宝仙寺より光徳院に転住された際にこの尊像を守護され山内に一宇を建立、安置したとの由。
秀雄法印(寛永十九年(1642年)寂)は当山の中興とされています。
本堂に御本尊大日如来、弘法大師木座像、理源大師木座像を奉安。
観音堂には、菅原道真公自刻と伝わる千手観世音菩薩木立像が奉安され、『寺社書上』には「山ノ手廿二番 江戸五拾八番」とあります。
「山ノ手廿二番」は、山の手三十三観音霊場第22番を示すとみられます。
「江戸五拾八番」は、おそらく江戸八十八ヶ所霊場第58番を示し、「江戸八十八ヶ所霊場=御府内霊場」であった可能性を示唆しています。
観音堂には、菅原道真公との所縁をあらわす菅家像木立像も奉安。
地蔵堂堂宇本尊の地蔵尊石佛は「塩地蔵」と呼ばれていたようです。
鎮守社ともみられる稲荷社は、「妙見天満愛宕金毘羅相殿」とあります。
平成7年落成の五重塔は木造瓦葺きで、全国から仏塔愛好家が参拝に訪れるそうです。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
五十八番
市ヶ谷柳町
七星山 息災寺 光德院
音羽町護國寺末 新義
本尊:千手観世音菩薩 不動明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [111] 谷中寺社書上 三』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.46』
市ヶ谷柳町
新義真言宗 大塚護國寺宗
七星山息災寺光德院
起立慶長十一年(1606年)以前弐番丁住居仕候御用地ニ付市ヶ谷田町に替地 寛永十二年(1635年)御堀御普請ニ付当地拝領仕候
開山 亮珍 寛永十八年(1641年)寂
中興 秀雄 寛永十九年(1642年)寂
本堂
本尊 大日如来木座像
弘法大師木座像 理源大師木座像
観音堂
千手観音木立像 山ノ手廿二番 江戸五拾八番 以下尊像御縁起
菅家像木立像 馬頭観音唐銅座像 脇立六観音木立像 不動明王木立像
閻魔堂
閻魔王木座像三尺三寸
前立千手観音木立像
西國三拾三ヶ所観音木立像
十王
稲荷社 妙見天満愛宕金毘羅相殿
地蔵堂 地蔵尊石佛 塩地蔵と唱

「光德院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』市ヶ谷牛込絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは西武新宿線「新井薬師前」駅で徒歩約10分。
哲学堂公園の南にあり、周辺は妙正寺川沿いに公園や緑道がつづく緑ゆたかなところです。


【写真 上(左)】 院号標
【写真 下(右)】 石標
住宅街のなかにかなり広い山内を構えています。、
山内入口に院号標と御府内霊場札所標。そのよこには「天満宮御直作 千手観世音菩薩」の石標も建っています。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 山門と五重塔
山門は常閉のようで、切妻屋根本瓦葺。
山内側からの写真を撮り忘れたので断言できませんが、おそらく四脚門で、水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻を備えて風格があります。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 五重塔
伽藍配置をよく覚えていないのですが、五重塔、観音堂、本堂があります。
五重塔は均整のとれた意匠で、住宅街のなかにこのような立派な五重塔が聳え立つさまはある意味驚きがあります。


【写真 上(左)】 観音堂
【写真 下(右)】 観音堂扁額
観音堂は桟瓦葺の方形造とも思いますが、降り棟、稚児棟の意匠が複雑で断言できません。
向拝柱を構え、向拝見上げに「観音堂」の扁額を掲げています。
向拝柱掲出の古い札所板は「本尊千手観世音菩薩 ●●●(霊場名解読不能)第二十八番」と読めます。
こちらは山の手三十三観音霊場第22番の札所ですが、第28番札所に定められた別の観音霊場があったのかもしれません。


【写真 上(左)】 観音堂札所板
【写真 下(右)】 本堂
本堂はおそらく入母屋造銅板葺の妻入りで、妻部の千鳥破風の下に向拝を附設しています。
水引虹梁両端に獅子・貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股と両脇に二連の斗栱、その上に二軒の垂木という風格ある構えです。
向拝見上げには「大日閣」の扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に千手観世音菩薩のお種子「キリーク」「千手観世音」「弘法大師」の揮毫と「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「御府内第五十八番」の札所印とその下に五重塔の印。
左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-20)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ Just Be Yourself - 杏里
■ ヒカリヘ - miwa
far on the water - Kalafina
■ Sayonara Solitia - Yuki Kajiura
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第55番 瑠璃光山 薬王寺 長久院
(ちょうきゅういん)
台東区谷中6-2-16
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第55番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第8番、弘法大師二十一ヶ寺第19番、閻魔三拾遺第4番、江戸・東京四十四閻魔参り第12番
第55番は谷中の長久院です。
第55番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに長久院で、第55番札所は開創当初から谷中の長久院であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
長久院は、慶長十六年(1611年)幕府より賜地を得て宥意上人が神田北寺町に開山、慶安十一年(1658年)幕府による寺地召上げを受け、代地として賜った谷中の現在地へ移転したといいます。
『下谷区史 〔本編〕』によると、神田北寺町での賜地および創建、谷中への移転の事由や時期は多寶院(第49番)、自性院(第53番)と同様とみられます。
江戸期の長久院は、本堂に御本尊の金剛界大日如来、弘法大師、興教大師、不動尊、愛染明王、薬師如来、歓喜天三躰、地蔵尊を奉安し、御府内霊場としての要件を満たしていたとみられます。
本堂とは別に閻魔法王石像(台石とも六尺)を奉安。
こちらは閻魔三拾遺第4番、江戸・東京四十四閻魔参り第12番の札所となっており、御府内でも著名な閻魔様であったことがわかります。
こちらの閻魔法王石像は右左にそれぞれ司命、司録像を配し「六十六部造立石造閻魔王坐像及び両脇侍像」として台東区登載文化財に指定されています。
なお、閻魔法王(大王)王冥界の王で、司命は閻魔王の判決を言い渡し、司録は判決内容を記録する従者であるとされます。
台座銘文に六十六部聖の光誉円心が享保十一年(1726年)に造立とあります。
六十六部聖とは、生前の罪障を滅し、死後の往生に近づくために法華経を六十六部写経し、全国の六十六箇所の霊場に一部ずつ奉納して回る聖のことをいいます。
六十六部聖は巡拝先に奉納経石塔を建立することが多いですが、石仏を奉納する例もみられます。
石仏は地蔵菩薩が多く、閻魔王像は極めて稀であるとされ、この稀少さもあって区登載文化財に指定されている模様です。
『寺社書上』には「飯縄不動安置」とあり、飯縄修験の流れが入っていた可能性があります。
同じく『寺社書上』にある「稲荷社」は、鎮守神かもしれません。
長久院は「弘法大師二十一ヶ寺」第19番の札所でもあります。
この霊場は、「弘法大師二十一ヶ寺御詠歌所附版木」が伝える弘法大師霊場で、この附版木は寛政二年(1790年)の開版ですからかなり古い来歴をもちます。
これとは別に「弘法大師 御府内二十一ヶ所」という霊場もあります。
「ニッポンの霊場」様によると、この霊場は元禄(1688年)から宝暦(1751年)の間に開創とされる古い霊場で、宝暦五年(1755年)頃の開創とされる御府内霊場より古い可能性があります。
二十一ヶ所霊場は、八十八ヶ所霊場のミニ版として開創され八十八ヶ所と札所が重複するケースもみられますが、「弘法大師二十一ヶ寺」「弘法大師 御府内二十一ヶ所」ともに御府内霊場(八十八ヶ所)との札所重複は多くありません。
「弘法大師二十一ヶ寺」はお大師さまのご縁日二十一日に因んでの開創なので合点がいきますが、「弘法大師 御府内二十一ヶ所」についてはナゾが残ります。
「弘法大師二十一ヶ寺」はなにかのWeb資料から札所情報を入手しましたが、いま検索してもヒットしません。ご参考までにリストします。
【弘法大師二十一ヶ寺】
1番 萬昌山 金剛幢院 圓満寺
真言宗御室派 文京区湯島1-6-2
2番 宝塔山 多寶院
真言宗豊山派 台東区谷中6-2-35
3番 五剣山 普門寺 大乗院
真言宗智山派 台東区元浅草4-5-16
4番 清光院 台東区下谷(廃寺)
5番 恵日山 延命寺 地蔵院
真言宗智山派 台東区元浅草1-15-8
6番 阿遮山 円満寺 不動院
真言宗智山派 台東区寿2-5-2
7番 峯松山 遮那院 仙蔵寺
真言宗智山派 台東区寿2-8-15
8番 高野山 金剛閣 大徳院
高野山真言宗 墨田区両国2-7-13
9番 青林山 最勝寺 龍福院
真言宗智山派 台東区元浅草3-17-2
10番 本覚山 宝光寺 自性院
新義真言宗 台東区谷中6-2-8
11番 摩尼山 隆全寺 吉祥院
真言宗智山派 台東区元浅草2-1-14
12番 神勝山 成就院
真言宗智山派 台東区元浅草4-8-12
13番 広幡山 観蔵院
真言宗智山派 台東区元浅草3-18-5
14番 望月山 般若寺 正福院
真言宗智山派 台東区元浅草4-7-21
15番 仏到山 無量寿院 西光寺
新義真言宗 台東区谷中6-2-20
16番 鶴亭山 隆全寺 威光院
真言宗智山派 台東区寿2-6-8
17番 十善山 蓮花寺 密蔵院
真言宗御室派 中野区沼袋2-33-4(移転)
18番 象頭山 観音寺 本智院
真言宗智山派 北区滝野川1-58-2
19番 瑠璃光山 薬王寺 長久院
真言宗豊山派 台東区谷中6-2-16
20番 玉龍山 弘憲寺 延命院
真言宗智山派 台東区元浅草4-5-2
21番 宝林山 大悲心院 霊雲寺
真言宗霊雲寺派 文京区湯島2-21-6
このうち、「御府内八十八ヶ所」「弘法大師二十一ヶ寺」「弘法大師 御府内二十一ヶ所」の3つの霊場すべての札所となっているのは、霊雲寺(第28番/湯島)、多寶院(第49番/谷中)、自性院(第53番/谷中)、長久院(第55番/谷中)の4箇寺しかなく、札所重複が少ないことを示しています。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
五十五番
谷中寺町
瑠璃光山 薬王寺 長久院
本所弥勒寺末 新義
本尊:阿弥陀如来 弘法大師 興教大師
■ 『寺社書上 [110] 谷中寺社書上 弐』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.97』
谷中不唱小名
新義真言宗 本所弥勒寺末
瑠璃光山薬師寺長久院
慶長十六年(1611年)二月、神田北寺町ニ●寺地拝領仕 其後慶安元年(1648年)右地所御用地ニ相成 同年十一月廿一日当所ニ●代地拝領仕候
開山宥意 寛永四年(1627年)正月三日寂
本堂
本尊金剛 大日如来木像
弘法大師 興教大師 不動尊
愛染明王木坐像 薬師如来木坐像 歓喜天三躰金佛厨子入 地蔵尊木立像
宝篋印塔
閻魔法王石像、臺石共六尺
稲荷社
飯縄不動安置
■ 『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)
長久院(谷中上三崎町一七番地)
本所彌勒寺末、瑠璃光山薬師寺と号す。本尊大日如来。当寺も亦多寶院、自性院等と同じく慶長十六年(1611年)二月、幕府より神田北寺町に地を給うて開創せられ、慶安元年(1648年)現地に移ったのである。開山は僧宥意。(寛永四年(1627年)一月三日寂)
境内に飯綱不動、石像閻魔等を安置する。

「長久院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
※『江戸切絵図』では「長久寺」となっています。
-------------------------
最寄りはJR「日暮里」駅で徒歩約10分。
東京メトロ千代田線「根津」駅からも歩けます。
三崎坂から南下して瑞輪寺よこを通り一乗寺に向かう路地沿いには、いくつかの寺院があってそのひとつ。
谷中寺町のほぼ中心部です。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 閉門時の山門
路地から少し引き込み、左右に築地塀と植栽をめぐらした山門の構えはなかなか風格があります。
山門は切妻屋根桟瓦葺の薬医門ないし高麗門で、見上げに院号扁額を掲げています。
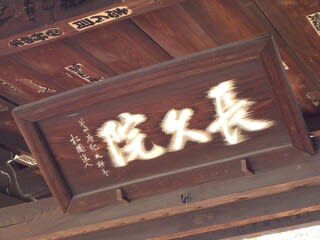

【写真 上(左)】 山門の扁額
【写真 下(右)】 山内
山門をくぐると左手に智拳印を結ばれる金剛界大日如来像。


【写真 上(左)】 大日如来像
【写真 下(右)】 本堂と大師堂
参道正面が庫裡で、その右手に本堂、さらにその右手前に直角に向きを変えて大師堂。
本堂は寄棟造桟瓦葺流れ向拝、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に本蟇股。
端正に整ったいい本堂です。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 閻魔様
本堂向かって右の堂前には、閻魔様、司命、司録が御座しています。
そばには「『笑いえんま』とよばれています。」という木板も掲げられていました。


【写真 上(左)】 大師堂
【写真 下(右)】 大師堂の扁額
大師堂は屋根に宝珠をおいた宝形造で流れ向拝。
向拝まわりの柱や虹梁はいずれも直線で、きっちりまとまった印象です。
御朱印は本堂向かって左の庫裡にて拝受しました。
なお、こちらは16:00閉門なので、時間に余裕をもった参拝をおすすめします。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
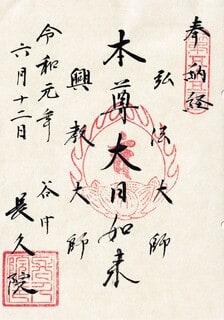

【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊大日如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「第五十五番」の札所印。左に院号の揮毫と寺院印が捺されています
■ 第56番 宝珠山 地蔵院 與楽寺
(よらくじ)
北区田端1-25-1
真言宗豊山派
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第56番、豊島八十八ヶ所第56番、武州江戸六阿弥陀霊場第4番、大東京百観音霊場第82番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第21番、九品仏霊場第3番(上品下生)、豊島六地蔵霊場第1番、滝野川寺院めぐり第1番
※本記事は「■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印」および「■ 滝野川寺院めぐり-1」から転載・追記したものです。
第56番は田端の與楽寺です。
第56番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに與楽寺で、第56番札所は開創当初から田端の與楽寺であったとみられます。
北区観光ホームページ、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
與楽寺は弘法大師の建立とも伝わる密寺で、慶安元年(1648年)に寺領二十石の御朱印状を拝領、京都仁和寺の関東末寺の取締役寺を務められ末寺20余を擁したとされる名刹です。
『滝野川寺院めぐり案内』には康歴三年(1381年)銘の石塔の存在が記され、開創は相当に古そうです。
弘法大師の御作とも伝わる御本尊の地蔵菩薩は「賊除け地蔵尊」と呼ばれ、つぎの逸話が伝わります。
昔、ある晩、盗賊が與楽寺に押し入ろうとした時、どこからともなく多数の僧侶が出てきて盗賊の侵入を防ぎ、遂にこれを追い返してしまいました。
翌朝、御本尊の地蔵菩薩の足に泥がついているのが発見され、地蔵菩薩が僧侶に姿を変えられて盗賊を追い出したのだと信じられるようになりました。
これより御本尊の地蔵菩薩は、賊除地蔵尊と称されるようになりました。
これが與楽寺の賊除け地蔵伝説です。
與楽寺は武州江戸六阿弥陀霊場第4番札所でもあります。
武州江戸六阿弥陀霊場(江戸六阿弥陀)は、行基菩薩が一夜の内に一本の木から刻み上げた六体の阿弥陀仏と、余り木で刻した阿弥陀仏、残り木(末木)で刻した聖観世音菩薩を巡拝する八箇寺からなる阿弥陀霊場で、女人成仏の阿弥陀仏として崇められ、江戸中期から大正時代にかけて、とくに春秋の彼岸の頃に女性を中心として盛んに巡拝されたといわれます。
開創年代については諸説あり錯綜していますが、札所は確定しています。
第1番目 三縁山 無量壽院 西福寺
北区豊島2-14-1 真言宗豊山派
第2番目 宮城山 円明院 恵明寺(旧小台村延命院)
足立区江北2-4-3 真言宗系単立
第3番目 佛寶山 西光院 無量寺
北区西ケ原1-34-8 真言宗豊山派
第4番目 宝珠山 地蔵院 與楽寺
北区田端1-25-1 真言宗豊山派
第5番目 福増山 常楽院
調布市西つつじヶ丘4-9-1(旧下谷(上野)広小路) 天台宗
第6番目 西帰山 常光寺
江東区亀戸4-48-3 曹洞宗
木余の弥陀 龍燈山 貞香院 性翁寺
足立区扇2-19-3 浄土宗
木残(末木)の観音 補陀山 昌林寺
北区西ケ原3-12-6 曹洞宗
※武州江戸六阿弥陀霊場についてはこちらをご覧ください。
境内には密教の思想を表した南北朝時代の四面に仏を浮彫りにした南北朝時代の石の仏塔(四面四仏石塔屋)や、江戸時代の巡拝塔、廻国供養塔などがあります。
近在有数の名刹ゆえ、複数の霊場の札所を兼ねられますが、とくに御府内霊場と武州江戸六阿弥陀の参拝者が多いのでは。
また、こちらは滝野川寺院めぐり第1番発願寺でもあります。
こちらのご住職は滝野川寺院めぐり開創当時の滝野川仏教会の会長で、そのことから札所1番発願寺を務められているものと思われます。
→滝野川寺院めぐりについては、こちらをご覧ください。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
五十六番
田ばた村
宝珠山 地蔵院 与楽寺
京都仁和寺宮 壇林所 新義
本尊:延命地蔵菩薩 不動明王 弘法大師
御朱印弐拾石 拾八ヶ寺本地
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
新義真言宗京都仁和寺末 寶珠山地蔵院ト号ス 慶安元年八月二十四日寺領二十石ノ御朱印を賜フ 本尊地蔵ハ弘法大師ノ作ナリ 昔当寺へ或夜賊押入シ時 イツク●ナク数多ノ僧出テ賊ヲ防キ遂ニ追退タリ 翌朝本尊ノ足泥ニ汚レアリシカハ 是ヨリ賊除ノ地蔵ト号スト傳フ 開山ヲ秀榮ト云
鐘樓 寶暦元年鑄造ノ鐘ヲカク
阿彌陀堂 本尊ハ行基ノ作ニテ六阿彌陀ノ第四番ナリ
九品佛堂 是モ近郷九品阿彌陀佛ノ内第三番ナリト云
稲荷社

「与楽寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはJR「田端」駅で徒歩約4分。
田端駅は北口こそそれなりに賑やかですが、南口は降り立ったそばからまったくの住宅街で、山手線の駅前とはとても思えないのどかな空気がただよっています。
ここから南に与楽寺坂を下っていくと、左手に與楽寺が見えてきます。

【絵図】 江戸時代後期の田端村(北区教育委員会の與楽寺前説明板より/出典『江戸名所図絵』)
この坂のそばにはかつて芥川龍之介など文人の居宅があり、いまでも落ち着いたたたずまいを見せています。
芥川龍之介は、あたりの風景を「田端はどこへ入っても黄白い木の葉ばかりだ。夜とほると秋の匂がする」と描写しています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 修行大師像と札所標
豊島郡有数の名刹の歴史を語るように、ゆったりとした間口を構えます。
山門は平成29年(2017年)建立で、切妻造本瓦葺の立派な四脚門。
山門左手には修行大師像と、御府内霊場第五十六番、六阿弥陀第四番の両札所標、それに上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所標「西國廿一番 丹波國阿のう寺写」があります。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 霊堂
参道を進むと左手に霊堂。宝形造唐破風向拝の少し変わった雰囲気のお堂です。
その先には鐘楼。さらに進んだ右手にも宝形造のお堂があって、伽藍は整っています。
境内はよく整備され、名刹特有の荘厳な空気がただよっています。


【写真 上(左)】 鐘楼
【写真 下(右)】 右手のお堂と客殿


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
参道正面に本堂。
入母屋造本瓦葺流れ向拝。降り棟、隅棟、稚児棟をきっちり備える堂々たる仏殿です。
水引虹梁両端に雲形木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁と雲形の手挟を伸ばし、中備に板蟇股を置いています。
正面桟唐戸の上に「與楽寺」の扁額。
向拝両脇の花頭窓と身舎欄間の菱格子が、引き締まった印象を与えます。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂向拝見上げ
本堂に御座す御本尊の地蔵菩薩は弘法大師の御作と伝わり、盗賊の侵入を追い返された「賊除地蔵」としても知られる秘仏です。
本堂右手が客殿。切妻造桟瓦葺唐破風付きの整った意匠は、本瓦葺の本堂とバランスのよい対比を見せています。
本堂右手脇にも上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所標がありますが、こちらは「西國弐拾九番」となっています。
第29番は東覚寺で、標中に「是」「道」の文字があるので、札所導標かもしれません。


【写真 上(左)】 客殿
【写真 下(右)】 阿弥陀堂
本堂向かって右手が阿弥陀堂で、こちらは武州江戸六阿弥陀第4番目の札所です。
「江戸六阿弥陀」と「滝野川寺院めぐり」とは複数の札所(第1番與楽寺、第9番無量寺、第10番昌林寺)が重複しています。
入母屋造桟瓦葺流れ向拝。水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。
正面板戸の上に「六阿弥陀 第四番」の扁額。
シンプルな虹梁と両脇の連子が効いて、シャープな印象の向拝です。
札所本尊の阿弥陀如来は行基作と伝わります。


【写真 上(左)】 阿弥陀堂の扁額
【写真 下(右)】 本堂と阿弥陀堂のあいだのナゾのお堂
阿弥陀堂の右手、本堂とのあいだにもうひとつ宝形造のナゾのお堂がありますが詳細不明。
お堂の手前に観音様の線刻碑があるので、観音堂かもしれません。
御朱印は本堂向かって右手の客殿で拝受します。ここは5回以上参拝していますが、いずれも揮毫御朱印をいただけました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

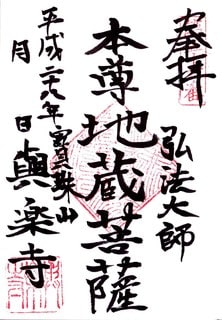
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 地蔵菩薩」「弘法大師」の揮毫と三寶印(蓮華座+宝珠)。
右に「第五十六番」の札所印。左に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

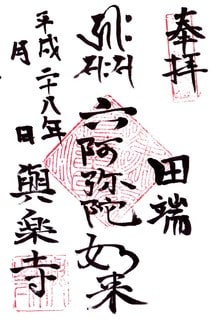
【写真 上(左)】 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 江戸六阿弥陀第4番目の御朱印
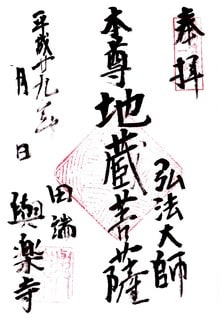
■ 滝野川寺院めぐりの御朱印
■ 第57番 天瑞山 観福寺 明王院
(みょうおういん)
台東区谷中5-4-2
真言宗豊山派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第57番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第5番
第57番は谷中の明王院です。
第57番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに明王院で、第57番札所は開創当初から谷中の明王院であったとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
明王院は、慶長十六年(1611年)二月、御水尾天皇の勅願により、幕府より神田北寺(小寺)町に寺地を給せられ、僧辨圓が創建。慶安元年(1648年)同所が幕府用地となつたため谷中に移ったといいます。
『下谷区史 〔本編〕』によると、神田北寺町での幕府からの賜地、谷中への移転の事由や時期は多寶院(第49番)、自性院(第53番)、長久院(第55番)と同様とみられますが、『ルートガイド』には慶安元年(1648年)に一旦谷中清水坂に遷ったあと、万治三年(1660年)に現地に移転とあります。
本堂には御本尊阿弥陀如来を奉安。
境内聖天堂には大聖歓喜天尊と本地十一面観世音菩薩、不動堂には不動尊、大師堂には弘法大師像を安置と伝わり、御府内霊場としての要件を満たしていたとみられます。
『寺社書上』にある「稲荷社」は、鎮守神かもしれません。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
五十七番
谷中三●●町
天瑞山 観福寺 明王院
本所弥勒寺末 新義
本尊:阿弥陀如来 弘法大師 興教大師
■ 『寺社書上 [111] 谷中寺社書上 三』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.101』
谷中不唱小名
新義真言宗 本所彌勒寺末
天瑞山歓福寺明王院
権現様御代慶長十六年(1611年) 開山辨圓法印代 於神田小寺町ニ拝領仕候
大猷院様御代慶安元年(1648年)中、右之寺地御用地ニ付被召上、谷中●代地拝領仕候
開山 辨圓法印 寛永五十月四日遷化
中興開基 朝誉法印、宝永三年(1706年)遷化
本堂
本尊 阿弥陀佛 丈一尺七寸立像
聖天宮 尊像金佛秘尊 本地十一面観音立像
不動堂 不動尊丈五寸座像
稲荷社 神躯幣束
■ 『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)
明王院(谷中初音町一丁目二三番地)
本所彌勒寺末、天瑞山觀福寺と号す。本尊三尊彌陀如来。
当寺も慶長十六年(1611年)二月、幕府より神田北寺町に於て寺地を給せられ、僧辨圓の建立する所で、慶安元年(1648年)同所は幕府用地となつたため現地に移つた。
境内聖天堂には大聖歓喜天像を安置し、大師堂には弘法大師像を安置する。

「明王院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは東京メトロ千代田線「千駄木」で徒歩約5分。
JR「日暮里」駅からも歩けます。
千駄木から谷中霊園へ向かう三崎坂をほぼ登り切ったところに道に面してあります。
このあたりも谷中寺町のほぼ中心部に当たります。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 院号標
山内入口の門柱は院号標を兼ねています。
参道左手に六地蔵、正面に大師堂がみえます。
大師堂前を斜め左に折れると、その正面が本堂です。
山内は手入れが行き届いてきもちがいいです。
大師堂右手前には、椅子式の牀座に坐される真如親王様の弘法大師像が刻まれた見事な宝篋印塔(納経塔?)があります。


【写真 上(左)】 六地蔵
【写真 下(右)】 宝篋印塔
当山は明治17年(1884年)の火災で堂宇を焼失し、本堂は昭和46年(1971年)、大師堂は平成7年(1995年)に再建されています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 天水鉢


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額
本堂は宝形造桟瓦葺流れ向拝で、屋根には火焔宝珠を置いています。
近代建築で向拝まわりはコンクリ造ですが、小壁に菱格子、向拝左右に花頭窓を置き引き締まった意匠です。
向拝見上げには山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 大師堂(手前)と本堂(奥)
【写真 下(右)】 大師堂
大師堂は宝形造本瓦葺で向拝柱はなく、屋根には宝珠を置いています。
大師堂前から拝むと、本堂の桟瓦と大師堂の本瓦、本堂の火焔宝珠と大師堂の宝珠が呼応して、見応えのある意匠となっています。
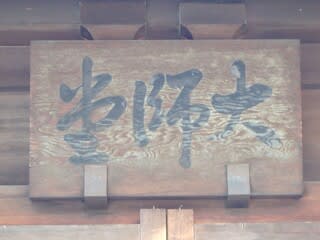

【写真 上(左)】 大師堂扁額
【写真 下(右)】 注意書き
山内には納経ないし読経を促す掲示があり、勤行式を貸し出しいただけます。
「大師堂のお大師さま、本堂の阿弥陀如来両方にお参り下さい。」とあるので、やはり御府内霊場(というか弘法大師霊場)の正式参拝はお大師さまと御本尊(ないし札所本尊)への参拝ということになるのでしょう。
御朱印は本堂向かって左手前の庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
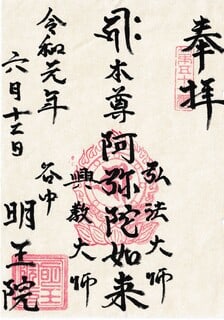
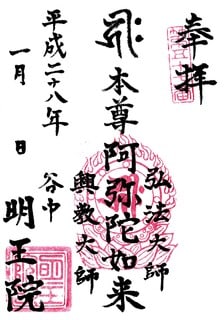
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に阿弥陀如来のお種子「キリーク」「本尊阿弥陀如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫と「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「第五十七番」の札所印。左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第58番 七星山 息災寺 光徳院
(こうとくいん)
公式Web
中野区上高田5-18-3
真言宗豊山派
御本尊:千手観世音菩薩
札所本尊:千手観世音菩薩
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第58番、山の手三十三観音霊場第22番、大東京百観音霊場第65番
第58番は中野・上高田の光徳院です。
第58番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに光徳院で、第58番札所は開創当初から光徳院であったとみられます。
公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
光徳院の創建年代等は不詳ながら、開山の亮珍和尚が寛永十八年(1641年)寂なのでそれ以前の創建とみられます。
開創は二番町(半蔵門)の地で、慶長十一年(1606年)、江戸城構築(拡張)の際に二番町(半蔵門)から市ヶ谷田町へ、寛永十二年(1635年)市ヶ谷柳町へ移転したともいいます。
さらに牛込柳町に遷った後、明治43年に中野・上高田の当地に移転しました。
なお、中野・上高田は御府内から移転した寺院で一種の寺町を形成しています。
寺宝の千手観世音菩薩は高さ三尺三寸の木像で、「子育観音」と呼ばれます。
第六〇代醍醐天皇の御代延喜元年(901年)に右大臣菅原道真公が筑紫・大宰府に左遷のみぎり、自刻され供養礼拝された尊像と伝わります。
久しく筑紫の千手坊に御座しましたが、縁あって中野宝仙寺の十四世秀雄法印に預けられ、秀雄法印が中野宝仙寺より光徳院に転住された際にこの尊像を守護され山内に一宇を建立、安置したとの由。
秀雄法印(寛永十九年(1642年)寂)は当山の中興とされています。
本堂に御本尊大日如来、弘法大師木座像、理源大師木座像を奉安。
観音堂には、菅原道真公自刻と伝わる千手観世音菩薩木立像が奉安され、『寺社書上』には「山ノ手廿二番 江戸五拾八番」とあります。
「山ノ手廿二番」は、山の手三十三観音霊場第22番を示すとみられます。
「江戸五拾八番」は、おそらく江戸八十八ヶ所霊場第58番を示し、「江戸八十八ヶ所霊場=御府内霊場」であった可能性を示唆しています。
観音堂には、菅原道真公との所縁をあらわす菅家像木立像も奉安。
地蔵堂堂宇本尊の地蔵尊石佛は「塩地蔵」と呼ばれていたようです。
鎮守社ともみられる稲荷社は、「妙見天満愛宕金毘羅相殿」とあります。
平成7年落成の五重塔は木造瓦葺きで、全国から仏塔愛好家が参拝に訪れるそうです。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
五十八番
市ヶ谷柳町
七星山 息災寺 光德院
音羽町護國寺末 新義
本尊:千手観世音菩薩 不動明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [111] 谷中寺社書上 三』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.46』
市ヶ谷柳町
新義真言宗 大塚護國寺宗
七星山息災寺光德院
起立慶長十一年(1606年)以前弐番丁住居仕候御用地ニ付市ヶ谷田町に替地 寛永十二年(1635年)御堀御普請ニ付当地拝領仕候
開山 亮珍 寛永十八年(1641年)寂
中興 秀雄 寛永十九年(1642年)寂
本堂
本尊 大日如来木座像
弘法大師木座像 理源大師木座像
観音堂
千手観音木立像 山ノ手廿二番 江戸五拾八番 以下尊像御縁起
菅家像木立像 馬頭観音唐銅座像 脇立六観音木立像 不動明王木立像
閻魔堂
閻魔王木座像三尺三寸
前立千手観音木立像
西國三拾三ヶ所観音木立像
十王
稲荷社 妙見天満愛宕金毘羅相殿
地蔵堂 地蔵尊石佛 塩地蔵と唱

「光德院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』市ヶ谷牛込絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは西武新宿線「新井薬師前」駅で徒歩約10分。
哲学堂公園の南にあり、周辺は妙正寺川沿いに公園や緑道がつづく緑ゆたかなところです。


【写真 上(左)】 院号標
【写真 下(右)】 石標
住宅街のなかにかなり広い山内を構えています。、
山内入口に院号標と御府内霊場札所標。そのよこには「天満宮御直作 千手観世音菩薩」の石標も建っています。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 山門と五重塔
山門は常閉のようで、切妻屋根本瓦葺。
山内側からの写真を撮り忘れたので断言できませんが、おそらく四脚門で、水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻を備えて風格があります。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 五重塔
伽藍配置をよく覚えていないのですが、五重塔、観音堂、本堂があります。
五重塔は均整のとれた意匠で、住宅街のなかにこのような立派な五重塔が聳え立つさまはある意味驚きがあります。


【写真 上(左)】 観音堂
【写真 下(右)】 観音堂扁額
観音堂は桟瓦葺の方形造とも思いますが、降り棟、稚児棟の意匠が複雑で断言できません。
向拝柱を構え、向拝見上げに「観音堂」の扁額を掲げています。
向拝柱掲出の古い札所板は「本尊千手観世音菩薩 ●●●(霊場名解読不能)第二十八番」と読めます。
こちらは山の手三十三観音霊場第22番の札所ですが、第28番札所に定められた別の観音霊場があったのかもしれません。


【写真 上(左)】 観音堂札所板
【写真 下(右)】 本堂
本堂はおそらく入母屋造銅板葺の妻入りで、妻部の千鳥破風の下に向拝を附設しています。
水引虹梁両端に獅子・貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股と両脇に二連の斗栱、その上に二軒の垂木という風格ある構えです。
向拝見上げには「大日閣」の扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に千手観世音菩薩のお種子「キリーク」「千手観世音」「弘法大師」の揮毫と「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「御府内第五十八番」の札所印とその下に五重塔の印。
左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-20)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ Just Be Yourself - 杏里
■ ヒカリヘ - miwa
far on the water - Kalafina
■ Sayonara Solitia - Yuki Kajiura
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-18
Vol.-17からのつづきです。
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第53番 本覚山 寶光寺 自性院
(じしょういん)
公式Web
台東区谷中6-2-8
新義真言宗
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第53番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第10番、弘法大師二十一ヶ寺第10番
第53番は「谷中愛染堂」とも呼ばれる谷中の自性院です。
第53番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに自性院で、第53番札所は開創当初から谷中の自性院であったとみられます。
公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
自性院は、慶長十六年(1611年)、道意上人により江戸神田北寺町(現・千代田区神田錦町)に開創、慶安元年(1648年)幕府用地となったため、谷中の現在地を賜り移転と伝わります。
中興開山は第9世貫海上人。
元文年間(1736-1741年)上人が境内の楠を切り彫刻された像高1メートルの像内には、上人が高野山参詣のとき奥之院路上で拾われた小さな愛染明王が納められているといいます。(公式Webによると、「近年修理をしたところ像内より胎内仏を確認」とのこと。)
当山は愛染堂安置の愛染明王像で知られ、文化文政の頃(1804-1830年)になると、その名は近在まで広がり「愛染寺」と呼ばれて親しまれたそうです。
愛染明王はとくに縁結び、家庭円満のご利益で信仰されます。
昭和12年(1937年)1月から翌年5月にかけ「婦人倶楽部」に連載された、文豪・川口松太郎の『愛染かつら』は、当山奉安の愛染明王の縁結びのご利益と本堂前のかつらの古木をモチーフとして書かれた作品といいます。(作品中では「永法寺」として描かれる。)
主人公ふたりは当山の愛染堂前のかつらの木に手をふれ、愛染明王に愛を誓約しました。恋人同士がこうして誓うと、将来かならず結ばれるという筋書きで、「愛染かつら」は昭和13年(1938年)松竹映画として、上原謙と田中絹代が共演して大ヒットとなりました。
また、映画の主題歌『旅の夜風』(昭和13年)を歌った霧島 昇と松原 操(ミス・コロムビア)が共演をきっかけに結ばれるというエピソードもあいまって、当山の愛染明王への参詣者は急増したといいます。
いまは谷中の奥まった一画で、御府内霊場巡拝者を迎える静かな寺院となっています。
当山は「弘法大師二十一ヶ寺」第10番の札所でもあります。
この霊場は、「弘法大師二十一ヶ寺御詠歌所附版木」が伝える弘法大師霊場で、この附版木は寛政二年(1790年)の開版ですからかなり古い来歴をもちます。
これとは別に「弘法大師 御府内二十一ヶ所」という霊場もあります。
「ニッポンの霊場」様によると、この霊場は元禄(1688年)から宝暦(1751年)の間に開創とされる古い霊場で、宝暦五年(1755年)頃の開創とされる御府内霊場より古い可能性があります。
二十一ヶ所霊場は、八十八ヶ所霊場のミニ版として開創され八十八ヶ所と札所が重複するケースもみられますが、「弘法大師二十一ヶ寺」「弘法大師 御府内二十一ヶ所」ともに御府内霊場(八十八ヶ所)との札所重複は多くありません。
「弘法大師二十一ヶ寺」はお大師さまのご縁日二十一日に因んでの開創なので合点がいきますが、「弘法大師 御府内二十一ヶ所」についてはナゾが残ります。
「弘法大師二十一ヶ寺」はなにかのWeb資料から札所情報を入手しましたが、いま検索してもヒットしません。ご参考までにリストします。
【弘法大師二十一ヶ寺】
1番 萬昌山 金剛幢院 圓満寺 真言宗御室派 文京区湯島1-6-2
2番 宝塔山 多寶院 真言宗豊山派 台東区谷中6-2-35
3番 五剣山 普門寺 大乗院 真言宗智山派 台東区元浅草4-5-16
4番 清光院 台東区下谷(廃寺)
5番 恵日山 延命寺 地蔵院 真言宗智山派 台東区元浅草1-15-8
6番 阿遮山 円満寺 不動院 真言宗智山派 台東区寿2-5-2
7番 峯松山 遮那院 仙蔵寺 真言宗智山派 台東区寿2-8-15
8番 高野山 金剛閣 大徳院 高野山真言宗 墨田区両国2-7-13
9番 青林山 最勝寺 龍福院 真言宗智山派 台東区元浅草3-17-2
10番 本覚山 宝光寺 自性院 新義真言宗 台東区谷中6-2-8
11番 摩尼山 隆全寺 吉祥院 真言宗智山派 台東区元浅草2-1-14
12番 神勝山 成就院 真言宗智山派 台東区元浅草4-8-12
13番 広幡山 観蔵院 真言宗智山派 台東区元浅草3-18-5
14番 望月山 般若寺 正福院 真言宗智山派 台東区元浅草4-7-21
15番 仏到山 無量寿院 西光寺 新義真言宗 台東区谷中6-2-20
16番 鶴亭山 隆全寺 威光院 真言宗智山派 台東区寿2-6-8
17番 十善山 蓮花寺 密蔵院 真言宗御室派 中野区沼袋2-33-4(移転)
18番 象頭山 観音寺 本智院 真言宗智山派 北区滝野川1-58-2
19番 瑠璃光山 薬王寺 長久院 真言宗豊山派 台東区谷中6-2-16
20番 玉龍山 弘憲寺 延命院 真言宗智山派 台東区元浅草4-5-2
21番 宝林山 大悲心院 霊雲寺 真言宗霊雲寺派 文京区湯島2-21-6
このうち、「御府内八十八ヶ所」「弘法大師二十一ヶ寺」「弘法大師 御府内二十一ヶ所」の3つの霊場すべての札所となっているのは、霊雲寺(第28番/湯島)、多寶院(第49番/谷中)、自性院(第53番/谷中)、長久院(第55番/谷中)の4箇寺しかなく、札所重複が少ないことを示しています。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
五十三番
谷中寺町
本覺山 寶光寺 自性院
本所弥勒寺末 新義
本尊:大日如来 弘法大師 興教大師
■ 『寺社書上 [110] 谷中寺社書上 弐』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.99』
本所彌勒寺末
谷中不唱小名
本覺山寶光寺自性院
新義真言宗
本所弥勒寺末 谷中不唱小名
慶長十六年(1611年)二月 神田北寺町ニ而拝領仕候処 其後慶安元年(1648年) 御用地ニ奉差上、於当所代地拝領仕候
開山 道意上人
本堂
本尊 金胎両部大日如来木像坐像 弘法大師木像 興教大師木像 不動尊木像 薬師如来木立像
宝篋印塔
地蔵堂 地蔵尊石像
中興開山 貫海上人
愛染堂 境内にあり 貫海上人の建立
愛染堂ハ今本堂と●●り 昔ハ別に本堂ありしと云
■ 『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)
自性院(谷中上三崎南町六番地)
本所彌勒寺末、本覺山寶光寺と号す。本尊金剛界大日如来、胎蔵界大日如来。慶長十六年(1611年)二月、幕府より神田北寺町に地を給うて開創せられ、慶安元年(1648年)現地に移ったのである。開山は僧道意。慶安元年(1648年)同所幕府の用地となり、現地に替地を給せられて移転した。

「自性院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋国立国会図書館DC(保護期間満了)
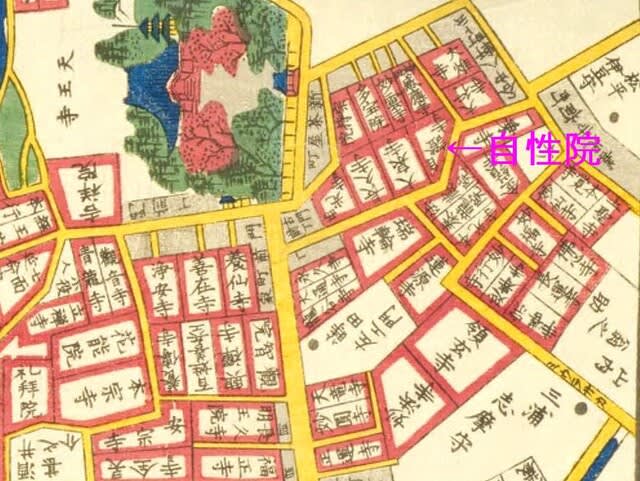
「自證寺(自性院)」/原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
※『江戸切絵図』では「自證寺」と記されています。
-------------------------
最寄りはJR「日暮里」駅で徒歩約7分。
東京メトロ千代田線「根津」駅からも歩けます。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 愛染明王安置碑
谷中六丁目のこのあたりは、ゆったりした区画の寺町で、落ち着いて参拝ができます。
路地に面した山内入口には愛染明王安置碑と『愛染かつらゆかりの地』の説明板。
左右の門柱は、それぞれ山号・寺号標と院号標となっています。


【写真 上(左)】 山号・寺号標
【写真 下(右)】 院号標
よく整備された山内。本堂前の大木が桂の木かどうかはうかつにも確認し忘れました。
参道が本堂前で右に折れる曲がり参道で、曲がった正面が本堂。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
入母屋造本瓦葺流れ向拝、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に本蟇股を備えた端正な本堂です。
向拝硝子格子扉のうえに「愛染寺」の扁額。
通称が扁額となるのはめずらしいと思います。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 慈母観世音菩薩
御朱印は本堂向かって左手の庫裡で拝受しましたが、現況は専用納経帳のみへの授与かもしれません。(直近の状況は未確認)
また、こちらは16:00に閉門となるので、時間に余裕をもった参拝をおすすめします。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
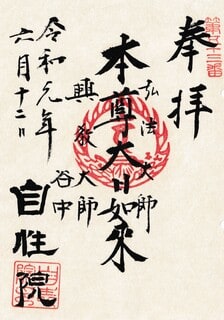
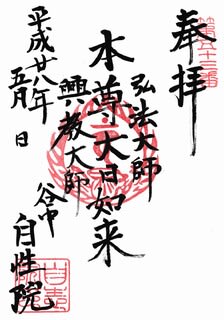
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊大日如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「第五十三番」の札所印。左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第54番 東豊山 浄瀧院 新長谷寺
(しんはせでら)
豊島区高田2-12-39
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:
〔新長谷寺〕
江戸八十八ヶ所霊場第54番、江戸五色不動(目白不動尊)、関東三十六不動霊場第14番、東京三十三観音霊場第23番、近世江戸三十三観音霊場[1] 第16番
〔金乗院〕
江戸八十八ヶ所霊場第38番、江戸三十三観音札所第14番、山の手三十三観音霊場第9番、近世江戸三十三観音霊場[1] 第14番
司元別当:此花咲耶姫社など
授与所:庫裡
第38番札所の金乗院は、第54番札所の目白不動堂(東豊山 浄滝院 新長谷寺)を合寺したので、現在、金乗院が第38番、第54番のふたつの札所の御朱印を授与されています。
第38番札所金乗院の記事で第54番札所目白不動堂(東豊山 浄滝院 新長谷寺)もとりあげたため、第54番ではこの記事を再掲します。
(なお、本記事は「江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 3.目白不動尊」から転載・追記したものです。)
第38番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに金乗院なので、御府内霊場開創時から一貫して下高田砂り場の金乗院であったとみられます。
下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』および『関東三十六不動霊場ガイドブック』などから縁起・沿革を追ってみます。
金乗院は天正年間(1573-1592年)、開山永順が御本尊の聖観世音菩薩を勧請して観音堂を建立したのが草創といいます。
当初は蓮花山 金乗院と号し中野寶仙寺の末寺でしたが、のちに神霊山 金乗院 慈眼寺と号を改め、音羽護国寺の末寺となりました。
御本尊は正観世音菩薩(伝・眦首羯摩作、運慶の作とも)。
山内に荒神を合殿する観音堂、御嶽社、辨天社、三峯社などを置き、江戸時代には旧砂利場村の此花咲耶姫社をはじめ社地三、四ヶ所の別当でしたが、昭和20年4月の戦災で本堂などの伽藍、水戸光圀公揮毫とされる此花咲耶姫の額などの宝物を焼失しました。
戦災で全焼した関口駒井町の新長谷寺(目白不動尊)を合併し、新長谷寺の札所も金乗院に移動しています。
明治初期の神仏分離を乗り切ったふたつの札所のうち一方が戦災で全焼して、一方に合寺されたという比較的めずらしい例です。
-------------------------
第54番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに新長谷寺(目白不動尊)なので、御府内霊場開創時から一貫して関口駒井町の新長谷寺(目白不動尊)であったとみられます。
下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』および『関東三十六不動霊場ガイドブック』などから縁起・沿革を追ってみます。
目白不動堂(東豊山 浄滝院 新長谷寺)は、元和四年(1618年)大和長谷寺代世小池坊秀算が中興し、関口駒井町(現・文京区関口、金乗院から東に約1㎞)にありました。
『江戸切絵図(小日向絵図)』をみると、江戸川橋から目白台にのぼる目白坂沿い北側に永泉寺、養国寺、八幡宮(正八幡神社)と並び、その南側神田川寄りに目白不動尊があったことがわかります。
目白不動堂奉安の不動尊は高さ八寸、「断臂不動明王」といい、弘法大師の御作と伝わります。
縁起によると、弘法大師が唐より御帰朝の後、出羽羽黒山に参籠されたとき大日如来が現れてたちまち不動明王のお姿に変じました。
大師に告げるには「此の地は諸仏内証秘密の浄土なれば、有為の穢火をきらえり、故に凡夫登山する事かたし、今汝に無漏の浄火をあたうべし」と。
不動尊は利剣をもってみずから左の御臂を切られると、霊火が盛んに燃え出でて仏身に満ちあふれました。
大師はこの御影を二体謹刻され、一体は出羽国の荒沢に安置され、もう一体は大師みずから護持されたと伝わります。
後年、野州足利の沙門某が大師護持の不動尊を奉持していましたが、武蔵国関口の松村氏が霊夢を得て足利よりお遷しし、領主の渡辺岩見守より関口台の一画に土地の寄進を受けて一宇を建立したのが本寺の濫觴(らんしょう/はじまりのこと)とされます。
元和四年(1618年)、大和長谷寺小池坊秀算僧正が中興、徳川2代将軍秀忠公の命により堂塔伽藍を建立。
大和長谷寺から御本尊と同木同作の十一面観世音菩薩像を御遷ししてその直末となり、東叡山 浄滝院 新長谷寺と号しました。
寛永年間(1624-1644年)、3代将軍家光公は当山の断臂不動明王に「目白」の号を贈り、江戸守護の江戸五色不動(青・黄・赤・白・黒)のひとつとして、また、江戸三不動の代一位として名を高め、人々の篤い信仰を受けました。
ことに護身、厄除け眼病治癒の不動尊として霊験あらたかとされます。
元禄年間(1688-1704年)には、5代将軍綱吉公とその母桂昌院が深く帰依してさらに伽藍を整え、寺容は壮麗を極めたと伝わります。
境内は堰口の流れを見下ろす高台の景勝地で、付近には茶肆、割烹などの店が出て、ことに月雪景の名所であったようです。
その佳景は、『東京名所四十八景 関口目しろ不動』 (慶應義塾大学メディアセンターDC)からも偲ぶことができます。
昭和20年5月の戦災で焼失したため金乗院に合併、御本尊の目白不動明王像は関口から金乗院に遷られました。
ふたつの名刹が合併した金乗院は今日も複数のメジャー霊場の札所であり、多くの参拝客を集めています。
また、当寺住職の小野塚幾澄大僧正は、平成20年から平成24年まで真言宗豊山派管長・長谷寺化主に就任されています。
-------------------------
【史料】
【金乗院関連】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
三十八番
砂り場
神霊山 金乗院
中野村宝仙寺末 新義
本尊:千手観音 興教大師 弘法大師
■『新編武蔵風土記稿 巻之12 豊島郡之4』(国立国会図書館)
(下高田村)金乗院
新義真言宗多磨郡中野村寶仙寺末、神靈山観音院ト號ス 本尊正観音長一寸八分眦首羯摩作 開山永順文禄三年(1594念)六月四日寂 御嶽社 辨天社 三峯社 観音堂/荒神ヲ合殿トス 観音ハ木ノ立像長三尺運慶ノ作ト云

「金乗院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

「宿坂関旧址 金乗院 観音堂」/原典:斎藤長秋 編 ほか『江戸名所図会』十二,博文館,1893.12.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』音羽絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
【新長谷寺関連】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
五十四番
関口駒井町
東豊山 海瀧院 新長谷寺
紀州初瀬小池坊末 新義
本尊:十一面観世音菩薩 本社目白不動明王 弘法大師
■『江戸名所図会. 十二』(国立国会図書館)
目白不動堂 同所東の方にありて堰口の涯に臨む真言宗にして東豊山新長谷寺と号す
長谷小池坊の宿寺とす
本尊不動明王の霊像は長八寸弘法大師の作 総門の額東豊山の三大字ハ南岳悦山の筆
縁起云弘法大師唐より帰朝の後 羽州湯殿山に参籠ありし時 大日如来忽然と不動明王の姿に変現し滝の下に現ハれ●● 大師に告て云く此地ハ諸佛内證秘密の浄土なれハ有為の穢土をきらえり 故に凡夫登山することかたし 今汝に無漏の上火をあたふべしと宣ひ持ちし●●●の利劍をもって左の御臂を切●●ハ、霊火盛に燃出でて佛身に充てり 依て大使面前に出現の像二躯を模刻し一躰ハ同國荒澤に安置し 一躰ハ大師自ら護持なしたまふ
その後野州足利に住せる沙門某之を感得し●奉持せしに一年 霊感あるを以て此地の住人松村氏某に●かりつひに一宇を開きて此本尊を移し安置なし奉ると
当寺元和四年和州長谷小池坊秀算僧正中興ありし頃 大将軍台徳公の厳命により堂塔坊舎御建立あり
また和州長谷寺の本尊と同木同作の十一面観世音の像をうつし新長谷寺と改む
大将軍大猷公目白の号を賜ひ 元禄の始にハ桂昌一位尼公御帰依浅からす諸堂修理を加へたまひ丈余●地蔵尊等を安置なさしめられたり
此地麓●●堰口の流を帯ひ 水流そうそうとして日夜不絶 早稲田の村落高田の森林を望む風光の地なり 境内貸食亭多く何れも涯に臨めり
また、『寺社書上(御府内備考). [61] 関口寺社書上』(国立国会図書館)および『御府内寺社書上P.134』
新義真言宗
和州長谷小池坊末
目白不動尊別当
東豊山 新長谷寺 海瀧院
本堂
本尊不動尊 弘法大師御作 秘佛
開帳佛不動 木立像
前立不動 木座像 四大明王ニ童附各立像
不動堂本殿 桂昌院御建立別堂
地蔵尊木立像
不動木立像 良弁僧都作
聖徳大師木立像
七曜佛木立像 運慶作
庚申佛木立像
疱瘡神木立像
愛染明王木像
大日如来木像 聖徳太子作
毘沙門木像
弁財天木像 竹生嶋写し
観音堂
本尊十一面木立像 行基菩薩作 開山秀算僧正勧請
前立観音木立像
与森天神木座像
興教大師木像
弘法大師木像 伊豫國延命寺写しニテ五十四番札所
開山秀算僧正木像
子安地蔵尊金立像
如意輪観音木像
弥陀木座像
聖天金像
末社
稲荷社、秋葉社、人丸社
唐金地蔵尊 濡佛
■『東京名所図会』(国立国会図書館)
目白不動堂は同所東の方にあり堰口の涯に臨む真言宗にして東豊山新長谷寺と號す 本尊不動明王は弘法大師の作なり 当寺は元和年間(1615-1624年)和州長谷の小池坊秀算僧正中興ありしより将軍家の厳命にて堂塔伽藍建立あり 後ち桂昌院尼公諸堂に修理を加えられ頗る荘厳を極めたり 境内眺望佳絶にして茶肆割烹店等多し 冬月雪景最も宜しと云ふ

「新長谷寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

「目白不動堂」/原典:斎藤長秋 編 ほか『江戸名所図会』十二,博文館,1893.12.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』小日向絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ・都電荒川線「雑司ヶ谷」駅か都電荒川線「学習院下」駅ですが、道行きの風情は「雑司ヶ谷」駅ルートの方があると思うので、こちらをご紹介。
メトロ・都電荒川線「雑司ヶ谷」駅3番出口から、目白通りを渡って宿坂通りに入ります。
目白通りは目白台の台地上を走り、ここから南側、神田川にかけては下り勾配となります。
宿坂(しゅくざか)もかなりの急坂ですが、この一本西側の「のぞき坂」は別名を「胸突(むなつき)坂」といい、「東京一急な坂」として知られています。
『江戸名所図会. 十二』(国会図書館DC)には以下のとおり「宿坂」と「金乗院」が記されています。
「宿坂関之旧跡 同北の方金乗院といへる密寺の寺前を四谷町の方へ上る坂口をいふ 同じ寺の裏門の辺にさらちの平地あり(中略)昔の奥州街道●●其頃関門のありて跡ありといへり」
現地掲示によると、この辺りは中世に「宿坂の宿」と呼ばれた関所があり、「立丁場」と呼ばれた金乗院裏門辺の平地が関所跡との伝承があります。
宿坂は「江戸時代には竹木が生い茂り、昼なお暗く、くらやみ坂と呼ばれ、狐や狸が出て通行人を化かしたという話」が伝わっているそうです。


【写真 上(左)】 宿坂
【写真 下(右)】 山門
宿坂をほぼ下りきった右手が金乗院の山門です。
二軒の垂木を備えた銅板葺のどっしりとした二脚門で、「神霊山」の山号扁額を掲げています。
右の門柱には、関東三十六不動霊場、左には江戸三十三観音札所の札所板。


【写真 上(左)】 関東三十六不動霊場の札所板
【写真 下(右)】 江戸三十三観音札所の札所板
約200年前の建立ですが昭和20年4月の戦災で屋根を焼失、昭和63年に檀徒の寄進により復元されています。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 山門前の不動尊
山門周辺に御府内霊場第38番および第54番の札所標、「目白」と刻まれた台座の上に石造坐像のお不動さま、江戸八十八ヶ所霊場第38番の札所標、「東豊山 新長谷寺」の寺号標などが建ち並び、当寺の歴史を物語っています。
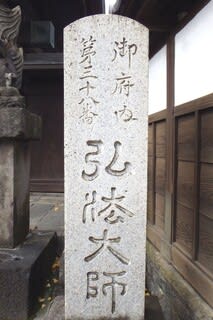

【写真 上(左)】 御府内霊場第38番の札所標
【写真 下(右)】 御府内霊場第54番の札所標
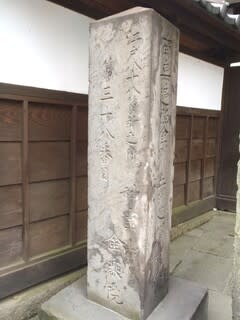

【写真 上(左)】 江戸八十八ヶ所の札所標
【写真 下(右)】 山の手三十三観音霊場の札所標
「江戸第拾六番 山之手第九番 本尊十一面観世音」の札所柱もありました。
「山之手第九番」は山の手三十三観音霊場第9番(新長谷寺)と思われますが、「江戸第拾六番」については霊場不明です。


【写真 上(左)】 金乗院の寺号標
【写真 下(右)】 新長谷寺の寺号標
石敷のすっきりとした境内。
山門正面が庫裡(納経所)、その左手に本堂、山門右手の高みが目白不動尊の不動堂です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂と不動堂
御府内霊場第38番、江戸三十三観音札所第14番は本堂、御府内霊場第54番、関東三十六不動霊場第14番は不動堂のお参りとなります。(御府内霊場は修行大師像も参拝)
(「本堂に『断臂不動明王』を安置」とする資料もありますが、『関東三十六不動霊場ガイドブック』には不動堂が参拝堂とあり、不動堂への参道に「目白不動尊参道」の案内掲示、不動堂の扁額も「目白不動堂」です。)
ちなみに御府内霊場のうち、一寺二札所、ふたつの御朱印をいただけるのはこちらのみです。


【写真 上(左)】 本堂(斜めから)
【写真 下(右)】 本堂向拝露天
本堂は昭和46年再建、平成15年の改修。
木造ではありませんが、入母屋造本瓦葺流れ向拝。
大棟、降り棟ともにやや細身ですが、隅棟、稚児棟まわりの鳥衾・熨斗瓦、掛瓦などのつくりが精緻で、屋根の照りもほどよく風格ある堂宇です。
水引虹梁に禅宗様の木鼻、中備えに蟇股、向拝正面は格子戸、その上に「神霊山」の扁額を掲げています。
御本尊は眦首羯摩作と伝わる高さ7㎝の聖観世音菩薩。金剛仏で秘仏です。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 修行大師像
本堂向かって左に端正な修行大師像が御座。
金乗院は江戸五色不動唯一の真言宗寺院で、江戸五色不動巡拝中に修行大師像のお参りができるのはこちらだけです。
本堂向かって右には「倶梨伽羅不動庚申」。
不動明王の法形である倶梨(利)伽羅剣と「見ざる、言わざる、聞かざる」の三猿が彫られた石像で、寛文六年(1660年)の建立です。
「人間を罪過から守る青面金剛の化身、三猿は天の神に人間の犯す罪を伝えない様子をあらわしている。」という現地掲示があります。


【写真 上(左)】 倶利伽羅不動庚申
【写真 下(右)】 不動堂参道
その横に宝塔。その後ろには立像の金仏(地蔵尊)。
その右横が墓地への参道で、その奥には慶安の変(由井正雪の乱、慶安四年7月(1651年))の首謀者の一人、丸橋忠弥の墓所があります。
さらに右手の山門寄りの高みのお堂が、目白不動尊の不動堂です。
確信はないですが、おそらく入母屋造銅板葺妻入り、妻側に付向拝の構成かと思われます。
棟部に経の巻獅子口、猪の目懸魚が見えます。


【写真 上(左)】 不動堂
【写真 下(右)】 不動堂向拝
水引虹梁部は向拝幕が張られているのでよくわかりませんが、身舎正面上部に「目白不動尊」の扁額。
格子戸越しに目白不動尊のおすがたが拝せます。
こちらの不動尊は御前立かと思われます。
整った面差しで、右手に剣、左臂に火焔を抱かれ、大盤石の上に御座される立像です。


【写真 上(左)】 不動堂扁額
【写真 下(右)】 鐔塚
境内にはこの他、寛政十二年(1800年)に建立の刀剣の供養塔、鐔塚(つばづか)などの見どころがあります。
なお、江戸名所図会で宿坂のかなり上方に描かれている観音堂(運慶作の観音像が奉られていたと伝わる)の現況については不明です。
御朱印は境内寺務所にて快く授与いただけます。
こちらは江戸五色不動のほか、御府内霊場(2札所)、江戸三十三観音札所、関東三十六不動霊場の札所も兼ねられ、いずれも御朱印を授与されています。
札所無申告の場合、目白不動尊、聖観世音菩薩いずれの御朱印になるかは不明ですが、おそらく先方からお尋ねになるのかと思います。
〔御府内霊場第54番(新長谷寺)の御朱印〕
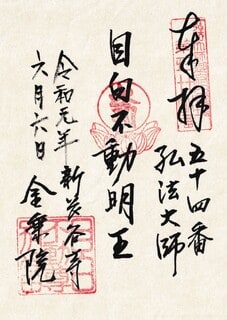
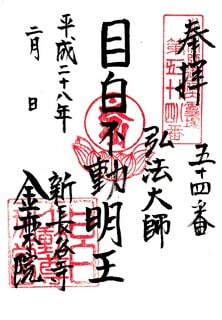
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「目白不動明王」「弘法大師」の揮毫と聖観世音菩薩のお種子「サ」の御寶印(蓮華座+宝珠)。
右上に「弘法大師御府内霊場第三十八 五十四番」の札所印。左下に寺号院号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔江戸五色不動尊の御朱印〕

・御朱印尊格:目白不動明王 関東三十六不動尊霊場第14番印判 師子光童子の印判 直書(筆書)
※ 関東三十六不動霊場の御朱印が授与されている模様です。
〔関東三十六不動尊霊場第14番の御朱印/専用納経帳〕

・御朱印尊格:目白不動明王 関東三十六不動尊霊場第14番印判 師子光童子の印判 筆書
〔江戸三十三観音札所第14番の御朱印〕
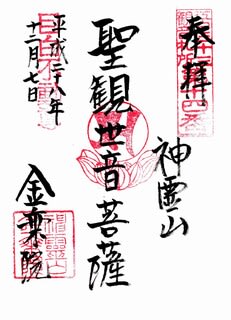
・御朱印尊格:聖観世音菩薩 江戸三十三観音札所第14番印判 目白不動尊の印判 直書(筆書)
〔 御府内霊場第38番(金乗院)の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「聖観世音菩薩」「弘法大師」の揮毫と聖観世音菩薩のお種子「サ」の御寶印(蓮華座+宝珠)。
右上に「弘法大師御府内霊場第三十八 五十四番」の札所印。左下に山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-19)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ 私達を信じていて - CINDY
■ Airport - 今井優子
■ far on the water - Kalafina
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第53番 本覚山 寶光寺 自性院
(じしょういん)
公式Web
台東区谷中6-2-8
新義真言宗
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第53番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第10番、弘法大師二十一ヶ寺第10番
第53番は「谷中愛染堂」とも呼ばれる谷中の自性院です。
第53番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに自性院で、第53番札所は開創当初から谷中の自性院であったとみられます。
公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
自性院は、慶長十六年(1611年)、道意上人により江戸神田北寺町(現・千代田区神田錦町)に開創、慶安元年(1648年)幕府用地となったため、谷中の現在地を賜り移転と伝わります。
中興開山は第9世貫海上人。
元文年間(1736-1741年)上人が境内の楠を切り彫刻された像高1メートルの像内には、上人が高野山参詣のとき奥之院路上で拾われた小さな愛染明王が納められているといいます。(公式Webによると、「近年修理をしたところ像内より胎内仏を確認」とのこと。)
当山は愛染堂安置の愛染明王像で知られ、文化文政の頃(1804-1830年)になると、その名は近在まで広がり「愛染寺」と呼ばれて親しまれたそうです。
愛染明王はとくに縁結び、家庭円満のご利益で信仰されます。
昭和12年(1937年)1月から翌年5月にかけ「婦人倶楽部」に連載された、文豪・川口松太郎の『愛染かつら』は、当山奉安の愛染明王の縁結びのご利益と本堂前のかつらの古木をモチーフとして書かれた作品といいます。(作品中では「永法寺」として描かれる。)
主人公ふたりは当山の愛染堂前のかつらの木に手をふれ、愛染明王に愛を誓約しました。恋人同士がこうして誓うと、将来かならず結ばれるという筋書きで、「愛染かつら」は昭和13年(1938年)松竹映画として、上原謙と田中絹代が共演して大ヒットとなりました。
また、映画の主題歌『旅の夜風』(昭和13年)を歌った霧島 昇と松原 操(ミス・コロムビア)が共演をきっかけに結ばれるというエピソードもあいまって、当山の愛染明王への参詣者は急増したといいます。
いまは谷中の奥まった一画で、御府内霊場巡拝者を迎える静かな寺院となっています。
当山は「弘法大師二十一ヶ寺」第10番の札所でもあります。
この霊場は、「弘法大師二十一ヶ寺御詠歌所附版木」が伝える弘法大師霊場で、この附版木は寛政二年(1790年)の開版ですからかなり古い来歴をもちます。
これとは別に「弘法大師 御府内二十一ヶ所」という霊場もあります。
「ニッポンの霊場」様によると、この霊場は元禄(1688年)から宝暦(1751年)の間に開創とされる古い霊場で、宝暦五年(1755年)頃の開創とされる御府内霊場より古い可能性があります。
二十一ヶ所霊場は、八十八ヶ所霊場のミニ版として開創され八十八ヶ所と札所が重複するケースもみられますが、「弘法大師二十一ヶ寺」「弘法大師 御府内二十一ヶ所」ともに御府内霊場(八十八ヶ所)との札所重複は多くありません。
「弘法大師二十一ヶ寺」はお大師さまのご縁日二十一日に因んでの開創なので合点がいきますが、「弘法大師 御府内二十一ヶ所」についてはナゾが残ります。
「弘法大師二十一ヶ寺」はなにかのWeb資料から札所情報を入手しましたが、いま検索してもヒットしません。ご参考までにリストします。
【弘法大師二十一ヶ寺】
1番 萬昌山 金剛幢院 圓満寺 真言宗御室派 文京区湯島1-6-2
2番 宝塔山 多寶院 真言宗豊山派 台東区谷中6-2-35
3番 五剣山 普門寺 大乗院 真言宗智山派 台東区元浅草4-5-16
4番 清光院 台東区下谷(廃寺)
5番 恵日山 延命寺 地蔵院 真言宗智山派 台東区元浅草1-15-8
6番 阿遮山 円満寺 不動院 真言宗智山派 台東区寿2-5-2
7番 峯松山 遮那院 仙蔵寺 真言宗智山派 台東区寿2-8-15
8番 高野山 金剛閣 大徳院 高野山真言宗 墨田区両国2-7-13
9番 青林山 最勝寺 龍福院 真言宗智山派 台東区元浅草3-17-2
10番 本覚山 宝光寺 自性院 新義真言宗 台東区谷中6-2-8
11番 摩尼山 隆全寺 吉祥院 真言宗智山派 台東区元浅草2-1-14
12番 神勝山 成就院 真言宗智山派 台東区元浅草4-8-12
13番 広幡山 観蔵院 真言宗智山派 台東区元浅草3-18-5
14番 望月山 般若寺 正福院 真言宗智山派 台東区元浅草4-7-21
15番 仏到山 無量寿院 西光寺 新義真言宗 台東区谷中6-2-20
16番 鶴亭山 隆全寺 威光院 真言宗智山派 台東区寿2-6-8
17番 十善山 蓮花寺 密蔵院 真言宗御室派 中野区沼袋2-33-4(移転)
18番 象頭山 観音寺 本智院 真言宗智山派 北区滝野川1-58-2
19番 瑠璃光山 薬王寺 長久院 真言宗豊山派 台東区谷中6-2-16
20番 玉龍山 弘憲寺 延命院 真言宗智山派 台東区元浅草4-5-2
21番 宝林山 大悲心院 霊雲寺 真言宗霊雲寺派 文京区湯島2-21-6
このうち、「御府内八十八ヶ所」「弘法大師二十一ヶ寺」「弘法大師 御府内二十一ヶ所」の3つの霊場すべての札所となっているのは、霊雲寺(第28番/湯島)、多寶院(第49番/谷中)、自性院(第53番/谷中)、長久院(第55番/谷中)の4箇寺しかなく、札所重複が少ないことを示しています。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
五十三番
谷中寺町
本覺山 寶光寺 自性院
本所弥勒寺末 新義
本尊:大日如来 弘法大師 興教大師
■ 『寺社書上 [110] 谷中寺社書上 弐』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.99』
本所彌勒寺末
谷中不唱小名
本覺山寶光寺自性院
新義真言宗
本所弥勒寺末 谷中不唱小名
慶長十六年(1611年)二月 神田北寺町ニ而拝領仕候処 其後慶安元年(1648年) 御用地ニ奉差上、於当所代地拝領仕候
開山 道意上人
本堂
本尊 金胎両部大日如来木像坐像 弘法大師木像 興教大師木像 不動尊木像 薬師如来木立像
宝篋印塔
地蔵堂 地蔵尊石像
中興開山 貫海上人
愛染堂 境内にあり 貫海上人の建立
愛染堂ハ今本堂と●●り 昔ハ別に本堂ありしと云
■ 『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)
自性院(谷中上三崎南町六番地)
本所彌勒寺末、本覺山寶光寺と号す。本尊金剛界大日如来、胎蔵界大日如来。慶長十六年(1611年)二月、幕府より神田北寺町に地を給うて開創せられ、慶安元年(1648年)現地に移ったのである。開山は僧道意。慶安元年(1648年)同所幕府の用地となり、現地に替地を給せられて移転した。

「自性院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋国立国会図書館DC(保護期間満了)
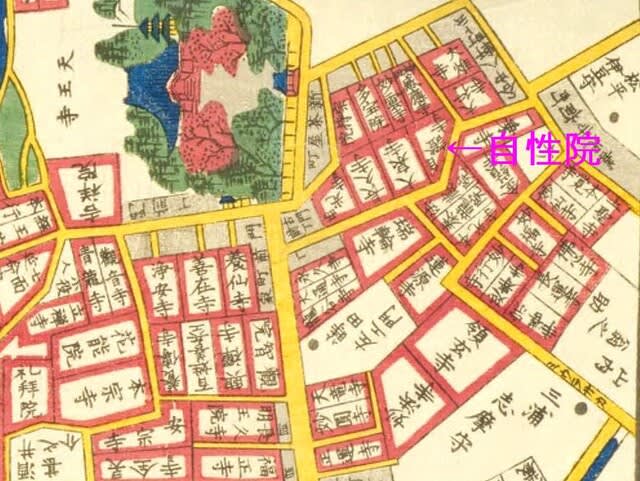
「自證寺(自性院)」/原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
※『江戸切絵図』では「自證寺」と記されています。
-------------------------
最寄りはJR「日暮里」駅で徒歩約7分。
東京メトロ千代田線「根津」駅からも歩けます。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 愛染明王安置碑
谷中六丁目のこのあたりは、ゆったりした区画の寺町で、落ち着いて参拝ができます。
路地に面した山内入口には愛染明王安置碑と『愛染かつらゆかりの地』の説明板。
左右の門柱は、それぞれ山号・寺号標と院号標となっています。


【写真 上(左)】 山号・寺号標
【写真 下(右)】 院号標
よく整備された山内。本堂前の大木が桂の木かどうかはうかつにも確認し忘れました。
参道が本堂前で右に折れる曲がり参道で、曲がった正面が本堂。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
入母屋造本瓦葺流れ向拝、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に本蟇股を備えた端正な本堂です。
向拝硝子格子扉のうえに「愛染寺」の扁額。
通称が扁額となるのはめずらしいと思います。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 慈母観世音菩薩
御朱印は本堂向かって左手の庫裡で拝受しましたが、現況は専用納経帳のみへの授与かもしれません。(直近の状況は未確認)
また、こちらは16:00に閉門となるので、時間に余裕をもった参拝をおすすめします。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
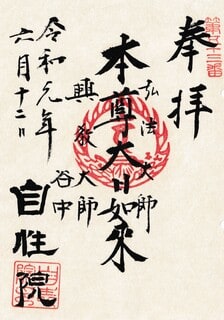
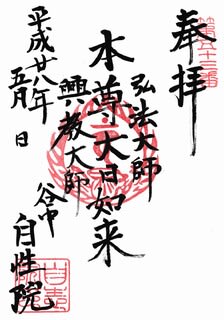
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊大日如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「第五十三番」の札所印。左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第54番 東豊山 浄瀧院 新長谷寺
(しんはせでら)
豊島区高田2-12-39
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:
〔新長谷寺〕
江戸八十八ヶ所霊場第54番、江戸五色不動(目白不動尊)、関東三十六不動霊場第14番、東京三十三観音霊場第23番、近世江戸三十三観音霊場[1] 第16番
〔金乗院〕
江戸八十八ヶ所霊場第38番、江戸三十三観音札所第14番、山の手三十三観音霊場第9番、近世江戸三十三観音霊場[1] 第14番
司元別当:此花咲耶姫社など
授与所:庫裡
第38番札所の金乗院は、第54番札所の目白不動堂(東豊山 浄滝院 新長谷寺)を合寺したので、現在、金乗院が第38番、第54番のふたつの札所の御朱印を授与されています。
第38番札所金乗院の記事で第54番札所目白不動堂(東豊山 浄滝院 新長谷寺)もとりあげたため、第54番ではこの記事を再掲します。
(なお、本記事は「江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 3.目白不動尊」から転載・追記したものです。)
第38番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに金乗院なので、御府内霊場開創時から一貫して下高田砂り場の金乗院であったとみられます。
下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』および『関東三十六不動霊場ガイドブック』などから縁起・沿革を追ってみます。
金乗院は天正年間(1573-1592年)、開山永順が御本尊の聖観世音菩薩を勧請して観音堂を建立したのが草創といいます。
当初は蓮花山 金乗院と号し中野寶仙寺の末寺でしたが、のちに神霊山 金乗院 慈眼寺と号を改め、音羽護国寺の末寺となりました。
御本尊は正観世音菩薩(伝・眦首羯摩作、運慶の作とも)。
山内に荒神を合殿する観音堂、御嶽社、辨天社、三峯社などを置き、江戸時代には旧砂利場村の此花咲耶姫社をはじめ社地三、四ヶ所の別当でしたが、昭和20年4月の戦災で本堂などの伽藍、水戸光圀公揮毫とされる此花咲耶姫の額などの宝物を焼失しました。
戦災で全焼した関口駒井町の新長谷寺(目白不動尊)を合併し、新長谷寺の札所も金乗院に移動しています。
明治初期の神仏分離を乗り切ったふたつの札所のうち一方が戦災で全焼して、一方に合寺されたという比較的めずらしい例です。
-------------------------
第54番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに新長谷寺(目白不動尊)なので、御府内霊場開創時から一貫して関口駒井町の新長谷寺(目白不動尊)であったとみられます。
下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』および『関東三十六不動霊場ガイドブック』などから縁起・沿革を追ってみます。
目白不動堂(東豊山 浄滝院 新長谷寺)は、元和四年(1618年)大和長谷寺代世小池坊秀算が中興し、関口駒井町(現・文京区関口、金乗院から東に約1㎞)にありました。
『江戸切絵図(小日向絵図)』をみると、江戸川橋から目白台にのぼる目白坂沿い北側に永泉寺、養国寺、八幡宮(正八幡神社)と並び、その南側神田川寄りに目白不動尊があったことがわかります。
目白不動堂奉安の不動尊は高さ八寸、「断臂不動明王」といい、弘法大師の御作と伝わります。
縁起によると、弘法大師が唐より御帰朝の後、出羽羽黒山に参籠されたとき大日如来が現れてたちまち不動明王のお姿に変じました。
大師に告げるには「此の地は諸仏内証秘密の浄土なれば、有為の穢火をきらえり、故に凡夫登山する事かたし、今汝に無漏の浄火をあたうべし」と。
不動尊は利剣をもってみずから左の御臂を切られると、霊火が盛んに燃え出でて仏身に満ちあふれました。
大師はこの御影を二体謹刻され、一体は出羽国の荒沢に安置され、もう一体は大師みずから護持されたと伝わります。
後年、野州足利の沙門某が大師護持の不動尊を奉持していましたが、武蔵国関口の松村氏が霊夢を得て足利よりお遷しし、領主の渡辺岩見守より関口台の一画に土地の寄進を受けて一宇を建立したのが本寺の濫觴(らんしょう/はじまりのこと)とされます。
元和四年(1618年)、大和長谷寺小池坊秀算僧正が中興、徳川2代将軍秀忠公の命により堂塔伽藍を建立。
大和長谷寺から御本尊と同木同作の十一面観世音菩薩像を御遷ししてその直末となり、東叡山 浄滝院 新長谷寺と号しました。
寛永年間(1624-1644年)、3代将軍家光公は当山の断臂不動明王に「目白」の号を贈り、江戸守護の江戸五色不動(青・黄・赤・白・黒)のひとつとして、また、江戸三不動の代一位として名を高め、人々の篤い信仰を受けました。
ことに護身、厄除け眼病治癒の不動尊として霊験あらたかとされます。
元禄年間(1688-1704年)には、5代将軍綱吉公とその母桂昌院が深く帰依してさらに伽藍を整え、寺容は壮麗を極めたと伝わります。
境内は堰口の流れを見下ろす高台の景勝地で、付近には茶肆、割烹などの店が出て、ことに月雪景の名所であったようです。
その佳景は、『東京名所四十八景 関口目しろ不動』 (慶應義塾大学メディアセンターDC)からも偲ぶことができます。
昭和20年5月の戦災で焼失したため金乗院に合併、御本尊の目白不動明王像は関口から金乗院に遷られました。
ふたつの名刹が合併した金乗院は今日も複数のメジャー霊場の札所であり、多くの参拝客を集めています。
また、当寺住職の小野塚幾澄大僧正は、平成20年から平成24年まで真言宗豊山派管長・長谷寺化主に就任されています。
-------------------------
【史料】
【金乗院関連】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
三十八番
砂り場
神霊山 金乗院
中野村宝仙寺末 新義
本尊:千手観音 興教大師 弘法大師
■『新編武蔵風土記稿 巻之12 豊島郡之4』(国立国会図書館)
(下高田村)金乗院
新義真言宗多磨郡中野村寶仙寺末、神靈山観音院ト號ス 本尊正観音長一寸八分眦首羯摩作 開山永順文禄三年(1594念)六月四日寂 御嶽社 辨天社 三峯社 観音堂/荒神ヲ合殿トス 観音ハ木ノ立像長三尺運慶ノ作ト云

「金乗院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

「宿坂関旧址 金乗院 観音堂」/原典:斎藤長秋 編 ほか『江戸名所図会』十二,博文館,1893.12.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』音羽絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
【新長谷寺関連】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
五十四番
関口駒井町
東豊山 海瀧院 新長谷寺
紀州初瀬小池坊末 新義
本尊:十一面観世音菩薩 本社目白不動明王 弘法大師
■『江戸名所図会. 十二』(国立国会図書館)
目白不動堂 同所東の方にありて堰口の涯に臨む真言宗にして東豊山新長谷寺と号す
長谷小池坊の宿寺とす
本尊不動明王の霊像は長八寸弘法大師の作 総門の額東豊山の三大字ハ南岳悦山の筆
縁起云弘法大師唐より帰朝の後 羽州湯殿山に参籠ありし時 大日如来忽然と不動明王の姿に変現し滝の下に現ハれ●● 大師に告て云く此地ハ諸佛内證秘密の浄土なれハ有為の穢土をきらえり 故に凡夫登山することかたし 今汝に無漏の上火をあたふべしと宣ひ持ちし●●●の利劍をもって左の御臂を切●●ハ、霊火盛に燃出でて佛身に充てり 依て大使面前に出現の像二躯を模刻し一躰ハ同國荒澤に安置し 一躰ハ大師自ら護持なしたまふ
その後野州足利に住せる沙門某之を感得し●奉持せしに一年 霊感あるを以て此地の住人松村氏某に●かりつひに一宇を開きて此本尊を移し安置なし奉ると
当寺元和四年和州長谷小池坊秀算僧正中興ありし頃 大将軍台徳公の厳命により堂塔坊舎御建立あり
また和州長谷寺の本尊と同木同作の十一面観世音の像をうつし新長谷寺と改む
大将軍大猷公目白の号を賜ひ 元禄の始にハ桂昌一位尼公御帰依浅からす諸堂修理を加へたまひ丈余●地蔵尊等を安置なさしめられたり
此地麓●●堰口の流を帯ひ 水流そうそうとして日夜不絶 早稲田の村落高田の森林を望む風光の地なり 境内貸食亭多く何れも涯に臨めり
また、『寺社書上(御府内備考). [61] 関口寺社書上』(国立国会図書館)および『御府内寺社書上P.134』
新義真言宗
和州長谷小池坊末
目白不動尊別当
東豊山 新長谷寺 海瀧院
本堂
本尊不動尊 弘法大師御作 秘佛
開帳佛不動 木立像
前立不動 木座像 四大明王ニ童附各立像
不動堂本殿 桂昌院御建立別堂
地蔵尊木立像
不動木立像 良弁僧都作
聖徳大師木立像
七曜佛木立像 運慶作
庚申佛木立像
疱瘡神木立像
愛染明王木像
大日如来木像 聖徳太子作
毘沙門木像
弁財天木像 竹生嶋写し
観音堂
本尊十一面木立像 行基菩薩作 開山秀算僧正勧請
前立観音木立像
与森天神木座像
興教大師木像
弘法大師木像 伊豫國延命寺写しニテ五十四番札所
開山秀算僧正木像
子安地蔵尊金立像
如意輪観音木像
弥陀木座像
聖天金像
末社
稲荷社、秋葉社、人丸社
唐金地蔵尊 濡佛
■『東京名所図会』(国立国会図書館)
目白不動堂は同所東の方にあり堰口の涯に臨む真言宗にして東豊山新長谷寺と號す 本尊不動明王は弘法大師の作なり 当寺は元和年間(1615-1624年)和州長谷の小池坊秀算僧正中興ありしより将軍家の厳命にて堂塔伽藍建立あり 後ち桂昌院尼公諸堂に修理を加えられ頗る荘厳を極めたり 境内眺望佳絶にして茶肆割烹店等多し 冬月雪景最も宜しと云ふ

「新長谷寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

「目白不動堂」/原典:斎藤長秋 編 ほか『江戸名所図会』十二,博文館,1893.12.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』小日向絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ・都電荒川線「雑司ヶ谷」駅か都電荒川線「学習院下」駅ですが、道行きの風情は「雑司ヶ谷」駅ルートの方があると思うので、こちらをご紹介。
メトロ・都電荒川線「雑司ヶ谷」駅3番出口から、目白通りを渡って宿坂通りに入ります。
目白通りは目白台の台地上を走り、ここから南側、神田川にかけては下り勾配となります。
宿坂(しゅくざか)もかなりの急坂ですが、この一本西側の「のぞき坂」は別名を「胸突(むなつき)坂」といい、「東京一急な坂」として知られています。
『江戸名所図会. 十二』(国会図書館DC)には以下のとおり「宿坂」と「金乗院」が記されています。
「宿坂関之旧跡 同北の方金乗院といへる密寺の寺前を四谷町の方へ上る坂口をいふ 同じ寺の裏門の辺にさらちの平地あり(中略)昔の奥州街道●●其頃関門のありて跡ありといへり」
現地掲示によると、この辺りは中世に「宿坂の宿」と呼ばれた関所があり、「立丁場」と呼ばれた金乗院裏門辺の平地が関所跡との伝承があります。
宿坂は「江戸時代には竹木が生い茂り、昼なお暗く、くらやみ坂と呼ばれ、狐や狸が出て通行人を化かしたという話」が伝わっているそうです。


【写真 上(左)】 宿坂
【写真 下(右)】 山門
宿坂をほぼ下りきった右手が金乗院の山門です。
二軒の垂木を備えた銅板葺のどっしりとした二脚門で、「神霊山」の山号扁額を掲げています。
右の門柱には、関東三十六不動霊場、左には江戸三十三観音札所の札所板。


【写真 上(左)】 関東三十六不動霊場の札所板
【写真 下(右)】 江戸三十三観音札所の札所板
約200年前の建立ですが昭和20年4月の戦災で屋根を焼失、昭和63年に檀徒の寄進により復元されています。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 山門前の不動尊
山門周辺に御府内霊場第38番および第54番の札所標、「目白」と刻まれた台座の上に石造坐像のお不動さま、江戸八十八ヶ所霊場第38番の札所標、「東豊山 新長谷寺」の寺号標などが建ち並び、当寺の歴史を物語っています。
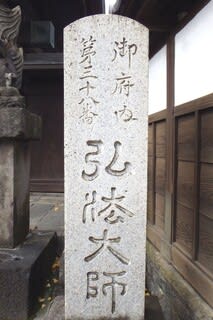

【写真 上(左)】 御府内霊場第38番の札所標
【写真 下(右)】 御府内霊場第54番の札所標
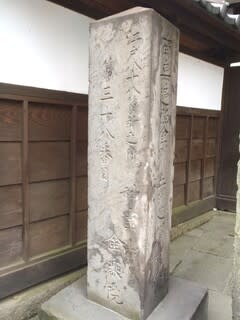

【写真 上(左)】 江戸八十八ヶ所の札所標
【写真 下(右)】 山の手三十三観音霊場の札所標
「江戸第拾六番 山之手第九番 本尊十一面観世音」の札所柱もありました。
「山之手第九番」は山の手三十三観音霊場第9番(新長谷寺)と思われますが、「江戸第拾六番」については霊場不明です。


【写真 上(左)】 金乗院の寺号標
【写真 下(右)】 新長谷寺の寺号標
石敷のすっきりとした境内。
山門正面が庫裡(納経所)、その左手に本堂、山門右手の高みが目白不動尊の不動堂です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂と不動堂
御府内霊場第38番、江戸三十三観音札所第14番は本堂、御府内霊場第54番、関東三十六不動霊場第14番は不動堂のお参りとなります。(御府内霊場は修行大師像も参拝)
(「本堂に『断臂不動明王』を安置」とする資料もありますが、『関東三十六不動霊場ガイドブック』には不動堂が参拝堂とあり、不動堂への参道に「目白不動尊参道」の案内掲示、不動堂の扁額も「目白不動堂」です。)
ちなみに御府内霊場のうち、一寺二札所、ふたつの御朱印をいただけるのはこちらのみです。


【写真 上(左)】 本堂(斜めから)
【写真 下(右)】 本堂向拝露天
本堂は昭和46年再建、平成15年の改修。
木造ではありませんが、入母屋造本瓦葺流れ向拝。
大棟、降り棟ともにやや細身ですが、隅棟、稚児棟まわりの鳥衾・熨斗瓦、掛瓦などのつくりが精緻で、屋根の照りもほどよく風格ある堂宇です。
水引虹梁に禅宗様の木鼻、中備えに蟇股、向拝正面は格子戸、その上に「神霊山」の扁額を掲げています。
御本尊は眦首羯摩作と伝わる高さ7㎝の聖観世音菩薩。金剛仏で秘仏です。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 修行大師像
本堂向かって左に端正な修行大師像が御座。
金乗院は江戸五色不動唯一の真言宗寺院で、江戸五色不動巡拝中に修行大師像のお参りができるのはこちらだけです。
本堂向かって右には「倶梨伽羅不動庚申」。
不動明王の法形である倶梨(利)伽羅剣と「見ざる、言わざる、聞かざる」の三猿が彫られた石像で、寛文六年(1660年)の建立です。
「人間を罪過から守る青面金剛の化身、三猿は天の神に人間の犯す罪を伝えない様子をあらわしている。」という現地掲示があります。


【写真 上(左)】 倶利伽羅不動庚申
【写真 下(右)】 不動堂参道
その横に宝塔。その後ろには立像の金仏(地蔵尊)。
その右横が墓地への参道で、その奥には慶安の変(由井正雪の乱、慶安四年7月(1651年))の首謀者の一人、丸橋忠弥の墓所があります。
さらに右手の山門寄りの高みのお堂が、目白不動尊の不動堂です。
確信はないですが、おそらく入母屋造銅板葺妻入り、妻側に付向拝の構成かと思われます。
棟部に経の巻獅子口、猪の目懸魚が見えます。


【写真 上(左)】 不動堂
【写真 下(右)】 不動堂向拝
水引虹梁部は向拝幕が張られているのでよくわかりませんが、身舎正面上部に「目白不動尊」の扁額。
格子戸越しに目白不動尊のおすがたが拝せます。
こちらの不動尊は御前立かと思われます。
整った面差しで、右手に剣、左臂に火焔を抱かれ、大盤石の上に御座される立像です。


【写真 上(左)】 不動堂扁額
【写真 下(右)】 鐔塚
境内にはこの他、寛政十二年(1800年)に建立の刀剣の供養塔、鐔塚(つばづか)などの見どころがあります。
なお、江戸名所図会で宿坂のかなり上方に描かれている観音堂(運慶作の観音像が奉られていたと伝わる)の現況については不明です。
御朱印は境内寺務所にて快く授与いただけます。
こちらは江戸五色不動のほか、御府内霊場(2札所)、江戸三十三観音札所、関東三十六不動霊場の札所も兼ねられ、いずれも御朱印を授与されています。
札所無申告の場合、目白不動尊、聖観世音菩薩いずれの御朱印になるかは不明ですが、おそらく先方からお尋ねになるのかと思います。
〔御府内霊場第54番(新長谷寺)の御朱印〕
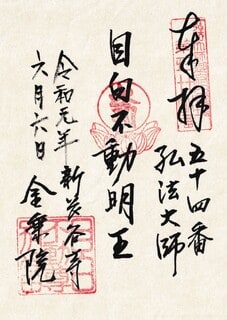
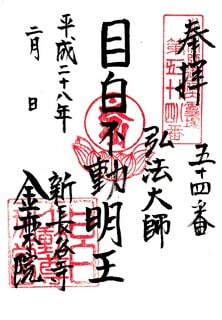
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「目白不動明王」「弘法大師」の揮毫と聖観世音菩薩のお種子「サ」の御寶印(蓮華座+宝珠)。
右上に「弘法大師御府内霊場第三十八 五十四番」の札所印。左下に寺号院号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔江戸五色不動尊の御朱印〕

・御朱印尊格:目白不動明王 関東三十六不動尊霊場第14番印判 師子光童子の印判 直書(筆書)
※ 関東三十六不動霊場の御朱印が授与されている模様です。
〔関東三十六不動尊霊場第14番の御朱印/専用納経帳〕

・御朱印尊格:目白不動明王 関東三十六不動尊霊場第14番印判 師子光童子の印判 筆書
〔江戸三十三観音札所第14番の御朱印〕
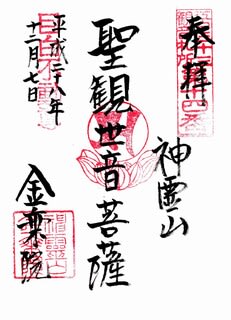
・御朱印尊格:聖観世音菩薩 江戸三十三観音札所第14番印判 目白不動尊の印判 直書(筆書)
〔 御府内霊場第38番(金乗院)の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「聖観世音菩薩」「弘法大師」の揮毫と聖観世音菩薩のお種子「サ」の御寶印(蓮華座+宝珠)。
右上に「弘法大師御府内霊場第三十八 五十四番」の札所印。左下に山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-19)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ 私達を信じていて - CINDY
■ Airport - 今井優子
■ far on the water - Kalafina
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-17
Vol.-16からのつづきです。
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第50番 高野山 金剛閣 大徳院
(だいとくいん)
墨田区両国2-7-13
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第46番、弘法大師二十一ヶ寺第8番、坂東写東都三十三観音霊場第7番、大東京百観音霊場33番
※院号は德川家(徳川家の正式表記)からとったとすると、「大德院」が正式名と思われますがここでは通称の「大徳院」を使います。
第50番は両国の大徳院です。
第46番弥勒寺の記事でも書きましたが、第50番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場では本所立川の弥勒寺(現御府内霊場・第46番札所)となっています。
よって、江戸時代に第46番札所の大徳院と第50番札所の弥勒寺とが入れ替わった可能性があります。
その経緯は不明ですが、大徳院は御府内霊場開創時からの札所であったとみられます。
下記史料、現地掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
大徳院は高野山金剛峯寺の江戸宿寺(宿寺居屋敷/江戸の拠点)で、寛永年間(1624-1644年)に拝領した神田紺屋町の屋敷地にありましたが、寛文六年(1666年)替地により本所猿江に移転、貞享元年(1684年)南本所元町(本所一ツ目)の現在地に二万廿坪余を拝領し移転したといいます。
神田紺屋町での建立 or 貞享元年(1684年)現在地に移転時の住職は本山中興の宥雅法印とされます。
江戸時代、高野山内の組織は学侶方・行人方・聖方の「高野三方(三派)」から成り立っていました。
聖方の頭寺院は蓮華(花)院(光徳院とも)で、弘法大師が悪魔降伏のため軍荼利明王の秘法を修し、結界を結ばれた草庵が草創とされます。
文禄三年(1594年)家康公が秀吉公に随従して高野山に参り蓮華院に止宿した際、家康公から大徳院の院号が与えられたといいます。
以降、徳川家との親交を深め、寛永年間(1624-1644年)大徳院の後山に東照宮(家康公)、台徳院殿(秀忠公)の御霊屋(徳川家霊台)が建立され、徳川家菩提所となりました。
「高野山霊宝館」公式Webには「徳川家霊台とは、徳川家康と秀忠をまつる東照宮をいいます。この場所は本来、聖派の代表寺院である大徳院の境内だったのですが、大徳院自体は明治になって他の寺院と合併して現存しませんので、霊台だけが残りました。大徳院は、代々徳川家との関係が深い寺院で、後に家康によって、それまで蓮華院と呼んでいたのを、『大徳院』と改められたともいわれています。造営に着工したのは寛永10年(1633)頃で、同16年には、正式に将軍家光より認可され、同20年に竣工」とあります。
「ぐるりん関西」には、蓮華(花)院の沿革や徳川家との関係が載っていますので抜粋引用します。
-------------------------(引用はじめ)
・蓮花院は、和歌山県高野山の小田原谷にある真言宗の準別格本山
・寺伝によると、弘法大師が悪魔降伏のため軍荼利明王の秘法を修し、結界を結んだ時の草庵が寺の起こりとされる。
・古くは聖方に属し、五之室谷の徳川家霊台の前に位置し、室町時代には光徳院、江戸時代は大徳院と号した。
・徳川将軍家の菩提寺として、歴代宗家の位牌と家康、秀忠の尊像が祀られている。
・水戸光圀の位牌や家康の念持仏といわれる薬師瑠璃光如来を奉安。
〔徳川家との関係〕
・永享十一年(1439年) 当院主が相模の藤沢寺(現・清浄光寺)に止宿し、家康公の祖先松平太郎左衛門親氏入道徳阿弥と師檀関係を結ぶ
・天文四年(1535年) 家康公の祖父松平清康公の遺骨が当院に納められ光徳院と改号
・文禄三年(1594年) 家康公が豊臣秀吉公に随従して高野山に参り、光徳院に止宿した際、家康公から大徳院の院号が与えられる
・寛永年間(1624-1644年) 大徳院の後山に東照宮(家康)、台徳院殿(秀忠)の御霊屋(徳川家霊台)が建立され、徳川家菩提所となる
・奥の院の松平秀康及び同母霊屋、徳川秀忠夫人崇源院供養塔は当院が管理している
-------------------------(引用おわり)
御府内霊場札所のなかでもとくに徳川将軍家とのかかわりが深い寺院で、『御府内八十八ケ所道しるべ』には「東照宮御本地」「寅の神」という記載があります。
江戸時代は高野山大徳院の江戸在番所(出張所)として宗務伝達所兼高野山諸末寺(聖方)総觸頭の地位にあり、江戸の弘法大師信仰あるいは「高野聖」(高野山を本拠とした遊行者)の活動の中心にあったともいいますが、明治18年にその機能を長寿寺(現・高野山東京別院)に移し現在に至っています。
御本尊の薬師瑠璃光如来は「本所一つ目寅薬師」と称され、とくに眼病治癒に霊験あらたかとされ信仰を集めています。
日光山輪王寺の公式Webによると、東照大権現の本地仏は薬師如来で、日光東照宮の本地堂(薬師堂)には薬師如来が奉安されています。
また、家康公は寅年、寅の日、寅の刻生まれともいわれ、家康公とゆかりのふかい寺院として、御本尊=寅薬師如来は自然に受け入れられたと思われます。
『御府内八十八ケ所道しるべ』に憚りなく「東照宮御本地」と書かれているので、おそらく公認されていたのでは。
このあたりは高野山の徳川家霊台を護持される、(高野山)大徳院の威光があったのかも。

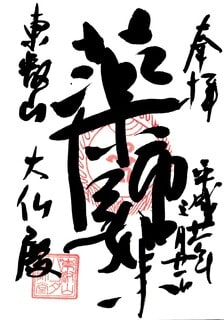
【写真 上(左)】 日光東照宮本地堂の御朱印
【写真 下(右)】 上野・パゴダ大仏殿の薬師如来の御朱印
なお、上野の東照宮境内にもしっかり本地堂(薬師堂)はありましたが、明治初期の神仏分離令により御本尊の薬師三尊は寛永寺に移管され、現在は「パゴダ大仏殿」内に奉安されています。
あるいは天台宗(比叡山)系の御本地(=東照宮本地堂)、真言宗(高野山)系の御本地(=大徳院)という色分けが意図的になされていたのかもしれません。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
五十番
本所一ッ目元町南
東照宮御本地 大德院
どくれい(独礼)せ● 古義
本尊:薬師如来 寅の神 弘法大師
■ 『寺社書上 [88] 本所寺社書上 壱』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.18』
御尊牌所
南本所 本所一ツ目
高野山金剛峯寺 大徳院宿寺
高野山聖方法国末寺 御尊牌所ニ候
古義真言宗高野山聖方諸国本寺惣触頭ニ候
●●年月不知
神田紺屋町辺● 宿寺居屋敷拝領仕●立
右●其所を諸人薬師堂前と呼び●●町の名となり
右之薬師(尊)像は弘法大師の作
寛文六年(1666年)右屋敷替地仰付 本所猿江に●●ひて寺地拝領仕
神田より猿江に引移り
貞享元年(1684年)南本所元町(本所一ツ目)にて●●の寺地二万廿坪余拝領仕候
開山 弘法大師
中興 宥雅法印 俗姓不知 寛文十四年(1673年?)寂
俗姓波多野●● ●永二年高野山●●●蓮花院(大徳院と御号)
任●●●寺代奉所
本堂
本尊 薬師如来座像 弘法大師作
脇立 日光菩薩立像 月光菩薩立像 十二神将立像
●雲院様(家光公とも)七回御忌御追福之● 竹千代君様(4代将軍家綱公)絵巻当御寄附(略)
有候薬師如来之尊像一体●●当院に奉納 是を寅薬師と称し御本地佛と崇敬して永く御武運長久を祈
台徳院様(2代将軍徳川秀忠公)御代、寛永年中(1624-1644年)、高野山より江戸神田の宿寺に右の尊像を移
弘法大師座像
同前佛座像
不動明王立像
社壇
稲荷立像
天満宮座像
高野四社明神繪像
辨財天座像 弘法大師作
寺寶
太政官符 嵯峨天皇より弘法大師●高野山を賜ふ御公御手判●
般若心経 弘法大師御真筆
大威徳明王像 弘法大師作
香合之内 愛染明王像一体 虚空蔵菩薩像一体 作人同前

「大德院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』本所絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはJR総武線「両国」駅で徒歩約5分。
都営大江戸線「両国」駅からも歩けます。
下町らしい低平な土地。オフィスと住宅の混在地にあります。
第23番、日本橋の薬研堀不動院とは隅田川を挟んで相対する立地で、すぐ北隣りは回向院です。


【写真 上(左)】 外観
【写真 下(右)】 札所標
平成25年に完成した地上5階地下1階建のビルで、一般的には「両国陵苑」のほうが通りがいいかもしれません。


【写真 上(左)】 延命地蔵尊
【写真 下(右)】 エントランス
エントランス前に延命地蔵菩薩が御座し、ビル前に札所碑、エントランスに唐破風を配しているので、近代的なビルながら寺院とすぐにわかります。
1階総合受付で参拝&御朱印の受付。
上層階の本堂のお参りもできますが、1階の弘法大師坐像も御府内霊場の拝所となっています。


【写真 上(左)】 1階弘法大師坐像横の札所札
【写真 下(右)】 1階弘法大師坐像
中段に弘法大師座像。
背後の壁面には智拳印を結ばれた金剛界大日如来の画像が掲げられています。
完璧なビル内参拝で、都会の霊場・御府内霊場らしい札所といえましょう。
御朱印は1階総合受付にて拝受しました。
いくつかの霊場札所を兼務されていますが、現況、御朱印を授与されているのは御府内霊場のみの模様です。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に薬師如来のお種子「バイ」「薬師如来」「弘法大師」の揮毫と「バイ」の御寶印(蓮華座+宝珠)。
右に「第五十番」の札所印。左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
専用集印帳の御朱印には「寅薬師」の揮毫もありました。
■ 第51番 玉龍山 弘憲寺 延命院
(えんめいいん)
台東区元浅草4-5-2
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第82番、弘法大師二十一ヶ寺第20番、弁財天百社参り第67番、江戸三十三ヶ所弁財天霊場第6番、奥の細道関東路三十三所霊場第3番
第51番は元浅草の延命院です。
御府内霊場には「延命院」を号する札所寺院がふたつ(第5番金剛山 延命院(南麻布)、第51番玉龍山 延命院(元浅草))ありますが、第5番の延命院を「麻布延命院」と呼んで区別しているようです。
第51番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに浅草鳥越の長樂寺となっています。
よって、第51番札所は明治以降に浅草鳥越の長樂寺から元浅草の延命院に変更されたとみられます。
まずは鳥越の長樂寺について、下記史料などから縁起・沿革を追ってみます。
長樂寺は鳥越に御鎮座の鳥越大明神(現・鳥越神社)の別当でした。
まずは、主に鳥越神社の境内掲示類から縁起・来歴を追ってみます。
鳥越大明神は白雉二年(651年)村人が日本武尊の遺徳を偲び、白鳥明神として鳥越山(白鳥山)に祀ったのが創祀と伝わる古社です。
往年のこの地は「鳥越(白鳥)の山」と呼ばれた小高い丘で、日本武尊が東夷御征伐の折に暫く御駐在された地といいます。
相殿の天児屋根命(あめのこやねのみこと)は、中臣(藤原)氏の祖神として祀られ、奈良時代に藤原氏が国司として武蔵に赴任した際、この地にお祀りされたといいます。
永承(1046-1053年)の頃、八幡太郎義家公の奥州征伐の折、この地で渡河に難儀しましたが、白い鳥に浅瀬を教えられて無事軍勢を進めることができました。
義家公はこれを白鳥大明神の御加護と称え、鳥越山(白鳥山)のお社を参拝され「鳥越大明神」の号を奉じられて、これより「鳥越」の地名が起こったとされます。
社地はすこぶる広く、三味線堀(姫が池)に熱田明神、森田町に第六天神(榊神社)が末社として御鎮座され「鳥越三所明神」と称していました。
徳川幕府による旗元・大名屋敷・御蔵地整備のため、鳥越山はとり崩されて埋め立てに使われました。
この際、熱田神社は三谷(現・今戸)へ、榊神社は堀田原(現・蔵前)へと御遷座され、鳥越大明神も御遷座を迫られましたが、第二代神主鏑木胤正の請願が容れられて元地に残られました。
別当・長樂寺は『寺社書上』によると、開山の法印の遷化が寛永二十年(1643年)なので、3代将軍家光公の治世(1623-1651年)までには創建とみられます。
鳥越山轉輪院長樂寺と号し、山号は本社から、院号は兼帯していた京都嵯峨轉輪院永院室から号したものとみられます。
本社・鳥越大明神の御本地馬頭観音、御本尊として不動明王を奉安していました。
弘法大師御像も奉安していたため、御府内霊場札所の要件はきっちり満たしていたとみられます。
鳥越大明神の神職鏑木氏は桓武平氏常将流と伝わり、鳥越神社の社紋として月星紋・九曜紋(千葉氏の紋)が使われているようです。
また、長樂寺に星供養曼荼羅が奉安されていたことからも、妙見信仰の千葉氏との関係がうかがわれます。
鳥越大明神と別当・長樂寺は源氏の棟梁・八幡太郎義家公、桓武平氏の代表姓・千葉氏いずれともゆかりをもつ、複雑な来歴をもたれているのかもしれません。
明治初期の神仏分離で別当の長樂寺は廃寺となり、以降は鳥越神社と号して郷社に列せられました。


【写真 上(左)】 鳥越神社
【写真 下(右)】 鳥越神社の御朱印
なお、相殿の東照宮の前身は、寛永十一年(1634年)、蔵前(南元町)の松平西福寺そばに江戸城の鬼門除けとして3代将軍家光公が祀られた松平神社(御祭神:徳川家康公)で、大正14年に鳥越神社の相殿に御遷座されました。

■ 松平西福寺(蔵前)
例大祭・鳥越祭は都内随一の重さを誇る「千貫神輿」の渡御と、夜に行われる荘厳な宮入で「鳥越の夜祭り」として広く知られています。
つぎに元浅草の延命院について、下記史料、現地掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
延命院は当初谷野(矢ノ蔵)に創建されたという新義真言宗寺院です。
東日本橋の矢之庫稲荷神社の由緒書には「当地に隣接する東日本橋1丁目あたりが谷野と呼ばれていた頃、幕府が米蔵を建て谷野蔵・矢之倉と称されていました。」とあるので、現在の東日本橋一丁目あたりとみられます。
『寺社書上』では開闢年代知不としながらも、奉安佛・水晶辨財天の縁起書に開山義観法師が文安年間(1444-1449年)に夢告を受け、武蔵国矢の蔵(倉)に一寺を建立して安置とあるので、その頃の創建とみられます。
現在の御本尊は大日如来ですが、寺院の草創は水晶辨財天の奉安によるものとあるので、当初の御本尊は辨財天だったのかもしれません。
当初は延寿院と号しましたが、元和年中(1615-1624年)頃、典薬頭延寿院道三と同号となったため、台徳尊公(徳川秀忠公)の上意により延命院と改めたといいます。
江戸時代は大塚の護持院末でありました。
『寺社書上』には「弘法大師 八十八所写第八十弐(?)番」とありますが、これは御府内霊場ではなく、おそらく荒川辺八十八ヶ所霊場を指すとみられます。
荒川辺八十八ヶ所霊場は天保九年(1838年)以前の開創とされる弘法大師霊場で、根岸・世尊寺から打ち始め、荒川、日暮里、尾久、船堀、豊島、江北、本木、千住、綾瀬、亀有、墨田、向島、亀戸、元浅草と回って根岸・千手院で結願となります。
→ 札所リスト(「ニッポンの霊場」様)
当山は第82番札所で、『寺社書上』の記載と符合します。
本堂に御座の御本尊大日如来、弘法大師御像が荒川辺霊場の拝所であったとみられます。
別に弘法大師の御作と伝わる水晶辨財天を奉安していました。
水晶辨財天は天長五年(828年)、弘法大師が琵琶湖の竹生島に参籠された折、二体の辨財天尊像を製作され、一体は竹生島の御本尊とし、一体はこの霊像と伝わります。
文安年間(1444-1449年)、讃岐國におられた開山義観法師の夢中にこの尊像があらわれ、お告げを受けた義観法師が東国へ下って武蔵国矢の蔵(倉)に一寺を建立してこの尊像を安置したのが当山草創とも伝わります。
竹生島辨財天は江ノ島・宮島と並ぶ「日本三弁才天」のひとつで、こちらの辨財天と同作の尊像とあれば、江戸庶民の信仰を集めたことは想像に難くありません。
実際、当山の水晶辨財天は弁財天百社参り第67番、江戸三十三ヶ所弁財天霊場第6番の札所となっていました。
当山の水晶辨財天は関東大震災、東京大空襲の災禍により消失し、現存はしていないとのこと。(出典:Wikipedia)
なお、弘法大師御作、義觀上人ゆかりとされる辨財天は鶴見の一至山 安養寺にも奉安され、こちらは鶴見七福神の一尊となっています。
(→ 安養寺公式Web)
明暦三年(1657年)火災(おそらく明暦の大火)に遭い、浅草新寺町(現・元浅草)に移転といいます。
鳥越神社は明治期に郷社に列格したほどの名社で、その別当・長樂寺が神仏分離で廃されたのは避けられない流れだったのかもしれません。
長樂寺は高野山金剛三昧院末の古義真言宗、延命院は大塚護持院末の新義真言宗で、宗派からすると御府内霊場札所(第51番)の承継はやや不自然な感じもします。
しかし第45番観蔵院と同様、荒川辺八十八ヶ所霊場の札所(第82番)で、あるいは弘法大師霊場札所寺院ということで定められたのかも。
荒川辺八十八ヶ所霊場は豊島八十八ヶ所霊場、荒綾八十八ヶ所霊場との札所重複は少なくないですが、御府内霊場との重複は亀戸東覚寺(第73番)、成増青蓮寺(第19番)、観蔵院(第45番)と延命院(当山)の4つしかありません。
しかし、下町の弘法大師霊場のうち蔵前・浅草辺に札所をもつのは荒川辺八十八ヶ所霊場だけなので、浅草鳥越に近い元浅草の札所から選ばれたのかもしれません。
-------------------------
【史料】
【長樂寺関連】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
五十一番
浅草鳥越明神 門前町あり
鳥越山 轉輪院 長樂寺
高野山金剛三昧院末 古義
本尊:不動明王 本社鳥越明神 弘法大師
■ 『寺社書上 [73] 浅草寺社書上 甲一』(国立国会図書館)
別当・長樂寺についてはこちらから記載されていますが、あまりに豪快な筆致につき解読不能が多いです。
抜粋引用します。
鳥越大明神 御本地馬頭観音
本尊 不動明王
弘法大師厨子入
金毘羅大権現
星供養曼荼羅厨子入
正観音像厨子入
●佛不動明王
●佛十一面観音厨子入
十三佛尊像厨子入
●大師像厨子入
聖天堂●●
聖天厨子入
銅佛十一面●殿入
別当 長樂寺
古義真言宗 本寺●●高野山金剛三昧院末
山号 鳥越山 ●●院
開山 法印(不明) 遷化之年月寛永廿年(1643年)四月十三日
中興開山 法印良長 遷化之年月●和二年
■ 『江戸名所図会 7巻 [16]』(国立国会図書館)
鳥越明神社
元鳥越町にあり此辺の産土神とす 祭神日本武尊 相殿天児屋根命なり 昔ハ第六天神 熱田明神を合わせて鳥越三所明神と号けし● 正保二年(1645年)此地公用の為に召上られ 三谷に●く替地を給ひけり 小社の地にかりを残さる その頃より熱田ハ三谷の地へうつし第六天ハ●田町へうつせりといへり
当社ハ最古跡なれとも 舊記等散失して勧請の年暦来由等詳ならすといへり
【延命院関連】
■ 『寺社書上 [80] 浅草寺社書上 甲五』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.59』
浅草新寺町
新義真言宗 大塚護持院末
玉龍山弘憲寺延命院
開闢年代知不●●
開山 義観法師 遷化ノ年月相不知申候
本堂
本尊 大日如来木坐像
弘法大師 八十八所写第八十弐(?)番
水晶●辨財天 弘法大師之作
聖天 但厨子入
地蔵尊石立像
稲荷社
拙寺往矢(?)野倉浜町ニ有(略)延寿院与申候処
元和年中(1615-1624年)頃典薬頭延寿院道三与同号ニ付 台徳尊公(徳川秀忠公)上意ヲ以延命ニ改
開山義観法師 生国讃岐差田村 遷化ノ年月相不知申候
水晶●辨財天縁起云 天長五年(828年)弘法大師江州竹生島に来●し 二体の尊像を製作し給ひ 一体ハ竹生島の本尊とし、一体ハ●●此霊像なり
文安年間(1444-1449年)讃岐國●●山●●●当院の開山義観法師の夢中●像●して(略)武蔵国矢の蔵(倉)●町に一寺建立して安置せり
明暦三年(1657年)火災に●●て今の浅草新寺町に移●ると云ふ

「長樂寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ銀座線「稲荷町」駅で徒歩約5分。
メトロ銀座線「田原町」駅からも歩けます。
住宅とオフィスビルが混在する立地。
元浅草から寿にかけては都内有数の寺院の密集地で、需要があるためか仏具・仏壇店が目立ちます。
都道463号浅草通り「松が谷一丁目」交差点から左右衛門橋通りを南に入ってひとつ目の信号を左(東)に入ったところです。
この界隈は田の字の区画で南参道の寺院はさほど多くはありませんが、延命院は完全な南参道南向きで、ビルの谷間ながらどことなく明るい雰囲気があります。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 院号札


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 参道
門柱に院号札、門柱手前には御府内霊場の札所標。
参道右手には赤地の御寶号幟を献ぜられた修行大師像が御座され、弘法大師御忌供養碑もあって御府内霊場札所の趣きゆたかです。
参道左寄り正面に本堂、その向かって左には延命地蔵尊。


【写真 上(左)】 修行大師像
【写真 下(右)】 延命地蔵尊


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に直線の繋ぎ虹梁、中備に板蟇股。
向拝硝子格子戸で扁額はなく、賽銭箱には丸に揚羽紋。
通りから引き込んでいるので、落ち着いて参拝ができます。
御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受しました。
辨財天についてお伺いしたところ、戦災に遭って失われ、代佛も御座されていないとの由。
また、御朱印は御府内霊場のみで、荒川辺八十八ヶ所霊場第82番などの御朱印は授与されていないとのことでした。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に金剛界大日如来のお種子「バン」「大日如来」「弘法大師」の揮毫と「バン」の御寶印(蓮華座+宝珠)。
右に「第五十一番」の札所印。左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第52番 慈雲山 蓮華院 観音寺
(かんのんじ)
新宿区西早稲田1-7-1
真言宗豊山派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:十一面観世音菩薩
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第52番、豊島八十八ヶ所霊場第52番、山の手三十三観音霊場第14番、近世江戸三十三観音霊場第15番
第52番は早稲田の観音寺です。
御府内霊場には「観音寺」を号する札所寺院が3つ(第42番蓮葉山 観音寺(谷中)、第52番慈雲山 観音寺(早稲田)、第85番大悲山 観音寺(高田馬場))あり、前2者をそれぞれ谷中観音寺、早稲田観音寺と呼んで区別されます。
第52番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに観音寺で、第52番札所は開創当初から早稲田の観音寺であったとみられます。
この寺院については史料がほとんど見当たらないので、『ルートガイド』をメインに縁起・沿革を追ってみます。
観音寺は寛文十三年(1673年)開山・賢栄和尚による創建といい、住民の発願により菩薩寺として建立とも伝わります。
御本尊の十一面観世音菩薩は智證大師円珍(814-891年)の御作といわれています。
円珍は入唐八家(最澄、空海、常暁、円行、円仁、恵運、円珍、宗叡)の一人で、讃岐国に豪族佐伯氏の一門として生誕され、弘法大師空海の甥(もしくは姪の息子)とも伝わります。
15歳で比叡山に登られ12年間の籠山行ののち、承和十二年(845年)には大峯、葛城、熊野諸山を巡礼し、修験道の発展にも寄与されたといいます。
仁寿三年(853年)入唐。天台山国清寺で求法され、斉衡二年(855年)には長安にて真言密教をも伝授されたといいます。
天安二年(858年)帰国。貞観十年(868年)比叡山延暦寺第5代座主となりました。
すでに貞観元年(859年)には大津の園城寺(三井寺)の長吏に補任。
園城寺は伝法灌頂の道場として隆盛し、寺門派(天台寺門宗)の拠点となりました。
円(法華経)、密(密教)、修験を極められ、天台宗の教義を広げられた傑僧として知られ、円珍を宗祖とする寺門派(天台寺門宗)はのちに円・密・禅・戒・修験の五法門をもって教義としています。
当山の縁起沿革については、寺伝類を焼失しているため詳細不明です。
よって、住民発願の真言密寺に寺門派(天台寺門宗)宗祖御作の御本尊が奉安された経緯についてもよくわかりません。
『ルートガイド』には「八十七番札所護国寺の隠居寺であったり、無住時代があったといわれています。」とあります。
護国寺の創建は天和元年(1681年)。当山創建は寛文十三年(1673年)で護国寺よりも早いですが、護国寺創建後に隠居寺となったのかもしれません。
御府内霊場の開創は宝暦五年(1755年)頃と伝わるので護国寺・当山創建の後になります。
観音寺は「護国寺の隠居寺」の流れから御府内霊場札所に定められたのではないでしょうか。
江戸期に複数の霊場札所に定められているので、相当の参詣者を集めたとみられますが、その様子は史料ではほとんど確認できませんでした。
貴重な史料である『御府内八十八ケ所道しるべ』の「本尊:十一面観世音菩薩 本社歓喜天宮」の記述が気になります。
歓喜天(大聖歓喜天)は強大なお力をもたれるとされる天部の尊格で、十一面観世音菩薩によって仏教の守護神となられたとされることから、十一面観世音菩薩とあわせて奉安されることが多く、ほとんどが秘佛です。
歓喜天の修法(聖天供(歓喜天供))は密教の奥義に属するとされるので、ここでは深くふれませんが、歓喜天(大聖歓喜天)を奉安する寺院の多くは霊験あらたかな祈願寺として知られ人々の信仰を集めています。
当山は早稲田大学の至近にあり、本堂も元早稲田大学の教授が設計されています。
早稲田大学周辺には寺院が多く、天台宗の宝泉寺は早稲田大学合格祈願寺として知られ、御朱印も授与されています。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
五十二番
下戸塚村
慈雲山 蓮華院 観音寺
牛込南蔵院末 新義
本尊:十一面観世音菩薩 本社歓喜天宮 弘法大師

「観音寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ東西線「早稲田」駅で徒歩約10分。
都電荒川線「早稲田」駅からも歩けます。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 寺号標
ほとんど早稲田大学の構内といえる立地にあり、あたりは学生であふれています。
本堂は斬新な近代建築で、手前の寺号標がなければとても寺院とは思えません。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 山内
山内入口に寺号標。側面には御府内霊場札所の旨が刻まれています。
その横には古色を帯びた御府内霊場の札所標。
参道右手には恵比寿さまと大黒さまが仲良く並んで御座されています。


【写真 上(左)】 恵比寿尊・大黒尊
【写真 下(右)】 庚申塔
その先右手に御座する舟形光背の地蔵尊石像は珍しい地蔵菩薩像を主尊とする庚申塔(寛文四年(1664年)の銘)で、新宿区の有形民族文化財に指定されています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 向拝前のお砂踏み場
【写真 下(右)】 扁額
2階建の本堂は建築家・石山修武氏による設計。
石山氏は「伊豆の長八美術館」(1985年)、日本建築学会賞受賞の「リアス・アーク美術館」(1995年)などの設計で知られ、平成26年まで早稲田大学の教授として教鞭をとられていました。
当本堂の竣工は平成8年(1996年)で30年近く経っていますが、いまでも斬新性を失っていません。
筆者は近代建築についてまったくのトーシロなので、詳細は→こちら(「建築とアートを巡る」様)をご覧くださいませ。
御朱印は本堂向かって右手に回り込んだ事務所にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「十一面観世音菩薩」「弘法大師」の揮毫と十一面観世音菩薩のお種子「キャ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「第五十二番」の札所印。左に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-18)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ 愛の季節 - アンジェラ・アキ
■ サイレント・イヴ - ClariS(Covered)
■ ebb and flow - LaLa(Covered)
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第50番 高野山 金剛閣 大徳院
(だいとくいん)
墨田区両国2-7-13
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第46番、弘法大師二十一ヶ寺第8番、坂東写東都三十三観音霊場第7番、大東京百観音霊場33番
※院号は德川家(徳川家の正式表記)からとったとすると、「大德院」が正式名と思われますがここでは通称の「大徳院」を使います。
第50番は両国の大徳院です。
第46番弥勒寺の記事でも書きましたが、第50番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場では本所立川の弥勒寺(現御府内霊場・第46番札所)となっています。
よって、江戸時代に第46番札所の大徳院と第50番札所の弥勒寺とが入れ替わった可能性があります。
その経緯は不明ですが、大徳院は御府内霊場開創時からの札所であったとみられます。
下記史料、現地掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
大徳院は高野山金剛峯寺の江戸宿寺(宿寺居屋敷/江戸の拠点)で、寛永年間(1624-1644年)に拝領した神田紺屋町の屋敷地にありましたが、寛文六年(1666年)替地により本所猿江に移転、貞享元年(1684年)南本所元町(本所一ツ目)の現在地に二万廿坪余を拝領し移転したといいます。
神田紺屋町での建立 or 貞享元年(1684年)現在地に移転時の住職は本山中興の宥雅法印とされます。
江戸時代、高野山内の組織は学侶方・行人方・聖方の「高野三方(三派)」から成り立っていました。
聖方の頭寺院は蓮華(花)院(光徳院とも)で、弘法大師が悪魔降伏のため軍荼利明王の秘法を修し、結界を結ばれた草庵が草創とされます。
文禄三年(1594年)家康公が秀吉公に随従して高野山に参り蓮華院に止宿した際、家康公から大徳院の院号が与えられたといいます。
以降、徳川家との親交を深め、寛永年間(1624-1644年)大徳院の後山に東照宮(家康公)、台徳院殿(秀忠公)の御霊屋(徳川家霊台)が建立され、徳川家菩提所となりました。
「高野山霊宝館」公式Webには「徳川家霊台とは、徳川家康と秀忠をまつる東照宮をいいます。この場所は本来、聖派の代表寺院である大徳院の境内だったのですが、大徳院自体は明治になって他の寺院と合併して現存しませんので、霊台だけが残りました。大徳院は、代々徳川家との関係が深い寺院で、後に家康によって、それまで蓮華院と呼んでいたのを、『大徳院』と改められたともいわれています。造営に着工したのは寛永10年(1633)頃で、同16年には、正式に将軍家光より認可され、同20年に竣工」とあります。
「ぐるりん関西」には、蓮華(花)院の沿革や徳川家との関係が載っていますので抜粋引用します。
-------------------------(引用はじめ)
・蓮花院は、和歌山県高野山の小田原谷にある真言宗の準別格本山
・寺伝によると、弘法大師が悪魔降伏のため軍荼利明王の秘法を修し、結界を結んだ時の草庵が寺の起こりとされる。
・古くは聖方に属し、五之室谷の徳川家霊台の前に位置し、室町時代には光徳院、江戸時代は大徳院と号した。
・徳川将軍家の菩提寺として、歴代宗家の位牌と家康、秀忠の尊像が祀られている。
・水戸光圀の位牌や家康の念持仏といわれる薬師瑠璃光如来を奉安。
〔徳川家との関係〕
・永享十一年(1439年) 当院主が相模の藤沢寺(現・清浄光寺)に止宿し、家康公の祖先松平太郎左衛門親氏入道徳阿弥と師檀関係を結ぶ
・天文四年(1535年) 家康公の祖父松平清康公の遺骨が当院に納められ光徳院と改号
・文禄三年(1594年) 家康公が豊臣秀吉公に随従して高野山に参り、光徳院に止宿した際、家康公から大徳院の院号が与えられる
・寛永年間(1624-1644年) 大徳院の後山に東照宮(家康)、台徳院殿(秀忠)の御霊屋(徳川家霊台)が建立され、徳川家菩提所となる
・奥の院の松平秀康及び同母霊屋、徳川秀忠夫人崇源院供養塔は当院が管理している
-------------------------(引用おわり)
御府内霊場札所のなかでもとくに徳川将軍家とのかかわりが深い寺院で、『御府内八十八ケ所道しるべ』には「東照宮御本地」「寅の神」という記載があります。
江戸時代は高野山大徳院の江戸在番所(出張所)として宗務伝達所兼高野山諸末寺(聖方)総觸頭の地位にあり、江戸の弘法大師信仰あるいは「高野聖」(高野山を本拠とした遊行者)の活動の中心にあったともいいますが、明治18年にその機能を長寿寺(現・高野山東京別院)に移し現在に至っています。
御本尊の薬師瑠璃光如来は「本所一つ目寅薬師」と称され、とくに眼病治癒に霊験あらたかとされ信仰を集めています。
日光山輪王寺の公式Webによると、東照大権現の本地仏は薬師如来で、日光東照宮の本地堂(薬師堂)には薬師如来が奉安されています。
また、家康公は寅年、寅の日、寅の刻生まれともいわれ、家康公とゆかりのふかい寺院として、御本尊=寅薬師如来は自然に受け入れられたと思われます。
『御府内八十八ケ所道しるべ』に憚りなく「東照宮御本地」と書かれているので、おそらく公認されていたのでは。
このあたりは高野山の徳川家霊台を護持される、(高野山)大徳院の威光があったのかも。

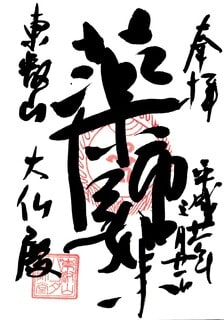
【写真 上(左)】 日光東照宮本地堂の御朱印
【写真 下(右)】 上野・パゴダ大仏殿の薬師如来の御朱印
なお、上野の東照宮境内にもしっかり本地堂(薬師堂)はありましたが、明治初期の神仏分離令により御本尊の薬師三尊は寛永寺に移管され、現在は「パゴダ大仏殿」内に奉安されています。
あるいは天台宗(比叡山)系の御本地(=東照宮本地堂)、真言宗(高野山)系の御本地(=大徳院)という色分けが意図的になされていたのかもしれません。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
五十番
本所一ッ目元町南
東照宮御本地 大德院
どくれい(独礼)せ● 古義
本尊:薬師如来 寅の神 弘法大師
■ 『寺社書上 [88] 本所寺社書上 壱』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.18』
御尊牌所
南本所 本所一ツ目
高野山金剛峯寺 大徳院宿寺
高野山聖方法国末寺 御尊牌所ニ候
古義真言宗高野山聖方諸国本寺惣触頭ニ候
●●年月不知
神田紺屋町辺● 宿寺居屋敷拝領仕●立
右●其所を諸人薬師堂前と呼び●●町の名となり
右之薬師(尊)像は弘法大師の作
寛文六年(1666年)右屋敷替地仰付 本所猿江に●●ひて寺地拝領仕
神田より猿江に引移り
貞享元年(1684年)南本所元町(本所一ツ目)にて●●の寺地二万廿坪余拝領仕候
開山 弘法大師
中興 宥雅法印 俗姓不知 寛文十四年(1673年?)寂
俗姓波多野●● ●永二年高野山●●●蓮花院(大徳院と御号)
任●●●寺代奉所
本堂
本尊 薬師如来座像 弘法大師作
脇立 日光菩薩立像 月光菩薩立像 十二神将立像
●雲院様(家光公とも)七回御忌御追福之● 竹千代君様(4代将軍家綱公)絵巻当御寄附(略)
有候薬師如来之尊像一体●●当院に奉納 是を寅薬師と称し御本地佛と崇敬して永く御武運長久を祈
台徳院様(2代将軍徳川秀忠公)御代、寛永年中(1624-1644年)、高野山より江戸神田の宿寺に右の尊像を移
弘法大師座像
同前佛座像
不動明王立像
社壇
稲荷立像
天満宮座像
高野四社明神繪像
辨財天座像 弘法大師作
寺寶
太政官符 嵯峨天皇より弘法大師●高野山を賜ふ御公御手判●
般若心経 弘法大師御真筆
大威徳明王像 弘法大師作
香合之内 愛染明王像一体 虚空蔵菩薩像一体 作人同前

「大德院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』本所絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはJR総武線「両国」駅で徒歩約5分。
都営大江戸線「両国」駅からも歩けます。
下町らしい低平な土地。オフィスと住宅の混在地にあります。
第23番、日本橋の薬研堀不動院とは隅田川を挟んで相対する立地で、すぐ北隣りは回向院です。


【写真 上(左)】 外観
【写真 下(右)】 札所標
平成25年に完成した地上5階地下1階建のビルで、一般的には「両国陵苑」のほうが通りがいいかもしれません。


【写真 上(左)】 延命地蔵尊
【写真 下(右)】 エントランス
エントランス前に延命地蔵菩薩が御座し、ビル前に札所碑、エントランスに唐破風を配しているので、近代的なビルながら寺院とすぐにわかります。
1階総合受付で参拝&御朱印の受付。
上層階の本堂のお参りもできますが、1階の弘法大師坐像も御府内霊場の拝所となっています。


【写真 上(左)】 1階弘法大師坐像横の札所札
【写真 下(右)】 1階弘法大師坐像
中段に弘法大師座像。
背後の壁面には智拳印を結ばれた金剛界大日如来の画像が掲げられています。
完璧なビル内参拝で、都会の霊場・御府内霊場らしい札所といえましょう。
御朱印は1階総合受付にて拝受しました。
いくつかの霊場札所を兼務されていますが、現況、御朱印を授与されているのは御府内霊場のみの模様です。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に薬師如来のお種子「バイ」「薬師如来」「弘法大師」の揮毫と「バイ」の御寶印(蓮華座+宝珠)。
右に「第五十番」の札所印。左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
専用集印帳の御朱印には「寅薬師」の揮毫もありました。
■ 第51番 玉龍山 弘憲寺 延命院
(えんめいいん)
台東区元浅草4-5-2
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第82番、弘法大師二十一ヶ寺第20番、弁財天百社参り第67番、江戸三十三ヶ所弁財天霊場第6番、奥の細道関東路三十三所霊場第3番
第51番は元浅草の延命院です。
御府内霊場には「延命院」を号する札所寺院がふたつ(第5番金剛山 延命院(南麻布)、第51番玉龍山 延命院(元浅草))ありますが、第5番の延命院を「麻布延命院」と呼んで区別しているようです。
第51番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに浅草鳥越の長樂寺となっています。
よって、第51番札所は明治以降に浅草鳥越の長樂寺から元浅草の延命院に変更されたとみられます。
まずは鳥越の長樂寺について、下記史料などから縁起・沿革を追ってみます。
長樂寺は鳥越に御鎮座の鳥越大明神(現・鳥越神社)の別当でした。
まずは、主に鳥越神社の境内掲示類から縁起・来歴を追ってみます。
鳥越大明神は白雉二年(651年)村人が日本武尊の遺徳を偲び、白鳥明神として鳥越山(白鳥山)に祀ったのが創祀と伝わる古社です。
往年のこの地は「鳥越(白鳥)の山」と呼ばれた小高い丘で、日本武尊が東夷御征伐の折に暫く御駐在された地といいます。
相殿の天児屋根命(あめのこやねのみこと)は、中臣(藤原)氏の祖神として祀られ、奈良時代に藤原氏が国司として武蔵に赴任した際、この地にお祀りされたといいます。
永承(1046-1053年)の頃、八幡太郎義家公の奥州征伐の折、この地で渡河に難儀しましたが、白い鳥に浅瀬を教えられて無事軍勢を進めることができました。
義家公はこれを白鳥大明神の御加護と称え、鳥越山(白鳥山)のお社を参拝され「鳥越大明神」の号を奉じられて、これより「鳥越」の地名が起こったとされます。
社地はすこぶる広く、三味線堀(姫が池)に熱田明神、森田町に第六天神(榊神社)が末社として御鎮座され「鳥越三所明神」と称していました。
徳川幕府による旗元・大名屋敷・御蔵地整備のため、鳥越山はとり崩されて埋め立てに使われました。
この際、熱田神社は三谷(現・今戸)へ、榊神社は堀田原(現・蔵前)へと御遷座され、鳥越大明神も御遷座を迫られましたが、第二代神主鏑木胤正の請願が容れられて元地に残られました。
別当・長樂寺は『寺社書上』によると、開山の法印の遷化が寛永二十年(1643年)なので、3代将軍家光公の治世(1623-1651年)までには創建とみられます。
鳥越山轉輪院長樂寺と号し、山号は本社から、院号は兼帯していた京都嵯峨轉輪院永院室から号したものとみられます。
本社・鳥越大明神の御本地馬頭観音、御本尊として不動明王を奉安していました。
弘法大師御像も奉安していたため、御府内霊場札所の要件はきっちり満たしていたとみられます。
鳥越大明神の神職鏑木氏は桓武平氏常将流と伝わり、鳥越神社の社紋として月星紋・九曜紋(千葉氏の紋)が使われているようです。
また、長樂寺に星供養曼荼羅が奉安されていたことからも、妙見信仰の千葉氏との関係がうかがわれます。
鳥越大明神と別当・長樂寺は源氏の棟梁・八幡太郎義家公、桓武平氏の代表姓・千葉氏いずれともゆかりをもつ、複雑な来歴をもたれているのかもしれません。
明治初期の神仏分離で別当の長樂寺は廃寺となり、以降は鳥越神社と号して郷社に列せられました。


【写真 上(左)】 鳥越神社
【写真 下(右)】 鳥越神社の御朱印
なお、相殿の東照宮の前身は、寛永十一年(1634年)、蔵前(南元町)の松平西福寺そばに江戸城の鬼門除けとして3代将軍家光公が祀られた松平神社(御祭神:徳川家康公)で、大正14年に鳥越神社の相殿に御遷座されました。

■ 松平西福寺(蔵前)
例大祭・鳥越祭は都内随一の重さを誇る「千貫神輿」の渡御と、夜に行われる荘厳な宮入で「鳥越の夜祭り」として広く知られています。
つぎに元浅草の延命院について、下記史料、現地掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
延命院は当初谷野(矢ノ蔵)に創建されたという新義真言宗寺院です。
東日本橋の矢之庫稲荷神社の由緒書には「当地に隣接する東日本橋1丁目あたりが谷野と呼ばれていた頃、幕府が米蔵を建て谷野蔵・矢之倉と称されていました。」とあるので、現在の東日本橋一丁目あたりとみられます。
『寺社書上』では開闢年代知不としながらも、奉安佛・水晶辨財天の縁起書に開山義観法師が文安年間(1444-1449年)に夢告を受け、武蔵国矢の蔵(倉)に一寺を建立して安置とあるので、その頃の創建とみられます。
現在の御本尊は大日如来ですが、寺院の草創は水晶辨財天の奉安によるものとあるので、当初の御本尊は辨財天だったのかもしれません。
当初は延寿院と号しましたが、元和年中(1615-1624年)頃、典薬頭延寿院道三と同号となったため、台徳尊公(徳川秀忠公)の上意により延命院と改めたといいます。
江戸時代は大塚の護持院末でありました。
『寺社書上』には「弘法大師 八十八所写第八十弐(?)番」とありますが、これは御府内霊場ではなく、おそらく荒川辺八十八ヶ所霊場を指すとみられます。
荒川辺八十八ヶ所霊場は天保九年(1838年)以前の開創とされる弘法大師霊場で、根岸・世尊寺から打ち始め、荒川、日暮里、尾久、船堀、豊島、江北、本木、千住、綾瀬、亀有、墨田、向島、亀戸、元浅草と回って根岸・千手院で結願となります。
→ 札所リスト(「ニッポンの霊場」様)
当山は第82番札所で、『寺社書上』の記載と符合します。
本堂に御座の御本尊大日如来、弘法大師御像が荒川辺霊場の拝所であったとみられます。
別に弘法大師の御作と伝わる水晶辨財天を奉安していました。
水晶辨財天は天長五年(828年)、弘法大師が琵琶湖の竹生島に参籠された折、二体の辨財天尊像を製作され、一体は竹生島の御本尊とし、一体はこの霊像と伝わります。
文安年間(1444-1449年)、讃岐國におられた開山義観法師の夢中にこの尊像があらわれ、お告げを受けた義観法師が東国へ下って武蔵国矢の蔵(倉)に一寺を建立してこの尊像を安置したのが当山草創とも伝わります。
竹生島辨財天は江ノ島・宮島と並ぶ「日本三弁才天」のひとつで、こちらの辨財天と同作の尊像とあれば、江戸庶民の信仰を集めたことは想像に難くありません。
実際、当山の水晶辨財天は弁財天百社参り第67番、江戸三十三ヶ所弁財天霊場第6番の札所となっていました。
当山の水晶辨財天は関東大震災、東京大空襲の災禍により消失し、現存はしていないとのこと。(出典:Wikipedia)
なお、弘法大師御作、義觀上人ゆかりとされる辨財天は鶴見の一至山 安養寺にも奉安され、こちらは鶴見七福神の一尊となっています。
(→ 安養寺公式Web)
明暦三年(1657年)火災(おそらく明暦の大火)に遭い、浅草新寺町(現・元浅草)に移転といいます。
鳥越神社は明治期に郷社に列格したほどの名社で、その別当・長樂寺が神仏分離で廃されたのは避けられない流れだったのかもしれません。
長樂寺は高野山金剛三昧院末の古義真言宗、延命院は大塚護持院末の新義真言宗で、宗派からすると御府内霊場札所(第51番)の承継はやや不自然な感じもします。
しかし第45番観蔵院と同様、荒川辺八十八ヶ所霊場の札所(第82番)で、あるいは弘法大師霊場札所寺院ということで定められたのかも。
荒川辺八十八ヶ所霊場は豊島八十八ヶ所霊場、荒綾八十八ヶ所霊場との札所重複は少なくないですが、御府内霊場との重複は亀戸東覚寺(第73番)、成増青蓮寺(第19番)、観蔵院(第45番)と延命院(当山)の4つしかありません。
しかし、下町の弘法大師霊場のうち蔵前・浅草辺に札所をもつのは荒川辺八十八ヶ所霊場だけなので、浅草鳥越に近い元浅草の札所から選ばれたのかもしれません。
-------------------------
【史料】
【長樂寺関連】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
五十一番
浅草鳥越明神 門前町あり
鳥越山 轉輪院 長樂寺
高野山金剛三昧院末 古義
本尊:不動明王 本社鳥越明神 弘法大師
■ 『寺社書上 [73] 浅草寺社書上 甲一』(国立国会図書館)
別当・長樂寺についてはこちらから記載されていますが、あまりに豪快な筆致につき解読不能が多いです。
抜粋引用します。
鳥越大明神 御本地馬頭観音
本尊 不動明王
弘法大師厨子入
金毘羅大権現
星供養曼荼羅厨子入
正観音像厨子入
●佛不動明王
●佛十一面観音厨子入
十三佛尊像厨子入
●大師像厨子入
聖天堂●●
聖天厨子入
銅佛十一面●殿入
別当 長樂寺
古義真言宗 本寺●●高野山金剛三昧院末
山号 鳥越山 ●●院
開山 法印(不明) 遷化之年月寛永廿年(1643年)四月十三日
中興開山 法印良長 遷化之年月●和二年
■ 『江戸名所図会 7巻 [16]』(国立国会図書館)
鳥越明神社
元鳥越町にあり此辺の産土神とす 祭神日本武尊 相殿天児屋根命なり 昔ハ第六天神 熱田明神を合わせて鳥越三所明神と号けし● 正保二年(1645年)此地公用の為に召上られ 三谷に●く替地を給ひけり 小社の地にかりを残さる その頃より熱田ハ三谷の地へうつし第六天ハ●田町へうつせりといへり
当社ハ最古跡なれとも 舊記等散失して勧請の年暦来由等詳ならすといへり
【延命院関連】
■ 『寺社書上 [80] 浅草寺社書上 甲五』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.59』
浅草新寺町
新義真言宗 大塚護持院末
玉龍山弘憲寺延命院
開闢年代知不●●
開山 義観法師 遷化ノ年月相不知申候
本堂
本尊 大日如来木坐像
弘法大師 八十八所写第八十弐(?)番
水晶●辨財天 弘法大師之作
聖天 但厨子入
地蔵尊石立像
稲荷社
拙寺往矢(?)野倉浜町ニ有(略)延寿院与申候処
元和年中(1615-1624年)頃典薬頭延寿院道三与同号ニ付 台徳尊公(徳川秀忠公)上意ヲ以延命ニ改
開山義観法師 生国讃岐差田村 遷化ノ年月相不知申候
水晶●辨財天縁起云 天長五年(828年)弘法大師江州竹生島に来●し 二体の尊像を製作し給ひ 一体ハ竹生島の本尊とし、一体ハ●●此霊像なり
文安年間(1444-1449年)讃岐國●●山●●●当院の開山義観法師の夢中●像●して(略)武蔵国矢の蔵(倉)●町に一寺建立して安置せり
明暦三年(1657年)火災に●●て今の浅草新寺町に移●ると云ふ

「長樂寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ銀座線「稲荷町」駅で徒歩約5分。
メトロ銀座線「田原町」駅からも歩けます。
住宅とオフィスビルが混在する立地。
元浅草から寿にかけては都内有数の寺院の密集地で、需要があるためか仏具・仏壇店が目立ちます。
都道463号浅草通り「松が谷一丁目」交差点から左右衛門橋通りを南に入ってひとつ目の信号を左(東)に入ったところです。
この界隈は田の字の区画で南参道の寺院はさほど多くはありませんが、延命院は完全な南参道南向きで、ビルの谷間ながらどことなく明るい雰囲気があります。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 院号札


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 参道
門柱に院号札、門柱手前には御府内霊場の札所標。
参道右手には赤地の御寶号幟を献ぜられた修行大師像が御座され、弘法大師御忌供養碑もあって御府内霊場札所の趣きゆたかです。
参道左寄り正面に本堂、その向かって左には延命地蔵尊。


【写真 上(左)】 修行大師像
【写真 下(右)】 延命地蔵尊


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に直線の繋ぎ虹梁、中備に板蟇股。
向拝硝子格子戸で扁額はなく、賽銭箱には丸に揚羽紋。
通りから引き込んでいるので、落ち着いて参拝ができます。
御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受しました。
辨財天についてお伺いしたところ、戦災に遭って失われ、代佛も御座されていないとの由。
また、御朱印は御府内霊場のみで、荒川辺八十八ヶ所霊場第82番などの御朱印は授与されていないとのことでした。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に金剛界大日如来のお種子「バン」「大日如来」「弘法大師」の揮毫と「バン」の御寶印(蓮華座+宝珠)。
右に「第五十一番」の札所印。左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第52番 慈雲山 蓮華院 観音寺
(かんのんじ)
新宿区西早稲田1-7-1
真言宗豊山派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:十一面観世音菩薩
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第52番、豊島八十八ヶ所霊場第52番、山の手三十三観音霊場第14番、近世江戸三十三観音霊場第15番
第52番は早稲田の観音寺です。
御府内霊場には「観音寺」を号する札所寺院が3つ(第42番蓮葉山 観音寺(谷中)、第52番慈雲山 観音寺(早稲田)、第85番大悲山 観音寺(高田馬場))あり、前2者をそれぞれ谷中観音寺、早稲田観音寺と呼んで区別されます。
第52番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに観音寺で、第52番札所は開創当初から早稲田の観音寺であったとみられます。
この寺院については史料がほとんど見当たらないので、『ルートガイド』をメインに縁起・沿革を追ってみます。
観音寺は寛文十三年(1673年)開山・賢栄和尚による創建といい、住民の発願により菩薩寺として建立とも伝わります。
御本尊の十一面観世音菩薩は智證大師円珍(814-891年)の御作といわれています。
円珍は入唐八家(最澄、空海、常暁、円行、円仁、恵運、円珍、宗叡)の一人で、讃岐国に豪族佐伯氏の一門として生誕され、弘法大師空海の甥(もしくは姪の息子)とも伝わります。
15歳で比叡山に登られ12年間の籠山行ののち、承和十二年(845年)には大峯、葛城、熊野諸山を巡礼し、修験道の発展にも寄与されたといいます。
仁寿三年(853年)入唐。天台山国清寺で求法され、斉衡二年(855年)には長安にて真言密教をも伝授されたといいます。
天安二年(858年)帰国。貞観十年(868年)比叡山延暦寺第5代座主となりました。
すでに貞観元年(859年)には大津の園城寺(三井寺)の長吏に補任。
園城寺は伝法灌頂の道場として隆盛し、寺門派(天台寺門宗)の拠点となりました。
円(法華経)、密(密教)、修験を極められ、天台宗の教義を広げられた傑僧として知られ、円珍を宗祖とする寺門派(天台寺門宗)はのちに円・密・禅・戒・修験の五法門をもって教義としています。
当山の縁起沿革については、寺伝類を焼失しているため詳細不明です。
よって、住民発願の真言密寺に寺門派(天台寺門宗)宗祖御作の御本尊が奉安された経緯についてもよくわかりません。
『ルートガイド』には「八十七番札所護国寺の隠居寺であったり、無住時代があったといわれています。」とあります。
護国寺の創建は天和元年(1681年)。当山創建は寛文十三年(1673年)で護国寺よりも早いですが、護国寺創建後に隠居寺となったのかもしれません。
御府内霊場の開創は宝暦五年(1755年)頃と伝わるので護国寺・当山創建の後になります。
観音寺は「護国寺の隠居寺」の流れから御府内霊場札所に定められたのではないでしょうか。
江戸期に複数の霊場札所に定められているので、相当の参詣者を集めたとみられますが、その様子は史料ではほとんど確認できませんでした。
貴重な史料である『御府内八十八ケ所道しるべ』の「本尊:十一面観世音菩薩 本社歓喜天宮」の記述が気になります。
歓喜天(大聖歓喜天)は強大なお力をもたれるとされる天部の尊格で、十一面観世音菩薩によって仏教の守護神となられたとされることから、十一面観世音菩薩とあわせて奉安されることが多く、ほとんどが秘佛です。
歓喜天の修法(聖天供(歓喜天供))は密教の奥義に属するとされるので、ここでは深くふれませんが、歓喜天(大聖歓喜天)を奉安する寺院の多くは霊験あらたかな祈願寺として知られ人々の信仰を集めています。
当山は早稲田大学の至近にあり、本堂も元早稲田大学の教授が設計されています。
早稲田大学周辺には寺院が多く、天台宗の宝泉寺は早稲田大学合格祈願寺として知られ、御朱印も授与されています。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
五十二番
下戸塚村
慈雲山 蓮華院 観音寺
牛込南蔵院末 新義
本尊:十一面観世音菩薩 本社歓喜天宮 弘法大師

「観音寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ東西線「早稲田」駅で徒歩約10分。
都電荒川線「早稲田」駅からも歩けます。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 寺号標
ほとんど早稲田大学の構内といえる立地にあり、あたりは学生であふれています。
本堂は斬新な近代建築で、手前の寺号標がなければとても寺院とは思えません。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 山内
山内入口に寺号標。側面には御府内霊場札所の旨が刻まれています。
その横には古色を帯びた御府内霊場の札所標。
参道右手には恵比寿さまと大黒さまが仲良く並んで御座されています。


【写真 上(左)】 恵比寿尊・大黒尊
【写真 下(右)】 庚申塔
その先右手に御座する舟形光背の地蔵尊石像は珍しい地蔵菩薩像を主尊とする庚申塔(寛文四年(1664年)の銘)で、新宿区の有形民族文化財に指定されています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 向拝前のお砂踏み場
【写真 下(右)】 扁額
2階建の本堂は建築家・石山修武氏による設計。
石山氏は「伊豆の長八美術館」(1985年)、日本建築学会賞受賞の「リアス・アーク美術館」(1995年)などの設計で知られ、平成26年まで早稲田大学の教授として教鞭をとられていました。
当本堂の竣工は平成8年(1996年)で30年近く経っていますが、いまでも斬新性を失っていません。
筆者は近代建築についてまったくのトーシロなので、詳細は→こちら(「建築とアートを巡る」様)をご覧くださいませ。
御朱印は本堂向かって右手に回り込んだ事務所にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「十一面観世音菩薩」「弘法大師」の揮毫と十一面観世音菩薩のお種子「キャ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「第五十二番」の札所印。左に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-18)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ 愛の季節 - アンジェラ・アキ
■ サイレント・イヴ - ClariS(Covered)
■ ebb and flow - LaLa(Covered)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-16
Vol.-15からのつづきです。
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第47番 平塚山 安楽院 城官寺
(じょうかんじ)
公式Web
北区上中里1-42-8
真言宗豊山派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
司元別当:(上中里村)平塚神社
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第47番、豊島八十八ヶ所霊場第47番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第6番、滝野川寺院巡り第8番
※この記事は■ 滝野川寺院めぐり-2をアレンジして仕上げています。
第47番はエリアを変えて上中里の城官寺です。
第47番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに城官寺となっています。
よって、第47番札所は御府内霊場開創時から一貫して上中里の城官寺であったとみられます。
公式Web、北区資料、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
城官寺は平塚神社(平塚明神)の元別当として知られています。(→平塚神社の公式Web)
城官寺は筑紫安楽寺の僧侶が諸国巡礼の折、当寺に宿泊した際に阿弥陀如来像を置き安楽院(安楽寺)と称し浄土宗の寺として創建といいます。
創建年代は不詳ですが、浄土宗開宗は承安五年(1175年)なので、それ以降の創建とみられます。
一方、『平塚明神并別当城官寺縁起絵巻』(北区指定有形文化財)は、平塚神社(平塚明神)の創祀について以下のように伝えています。
平安時代後期、このあたりに秩父平氏庶流の豊島太郎近義という人物が平塚城という城館を建て本拠としていました。
平塚城は源義家公が後三年の役(1083-1087年)で奥州に遠征した帰路の逗留地となり、豊島近義は心を尽くして饗応したため、義家公はこれに応じて、自らの鎧と守本尊の十一面観世音菩薩像を下賜しました。
近義は義家公の没後、平塚城鎮護のために拝領した鎧を埋め、その上に平たい塚(甲冑塚)を築き、義家公・義綱公・義光公の三人の木像を作り、そこに社を建てて安置したといいます。
創立は元永年中(1118-1120年)と伝わります。
これが平塚神社(平塚明神)の創祀で、”平塚”の地名の起こりともいわれ、当社は源家三兄弟にちなんで「平塚三所大明神」とも呼ばれて広く崇められました。
御祭神は八幡太郎 源義家命、賀茂次郎 源義綱命、新羅三郎 源義光命の源家三兄弟で、三兄弟を一社で祀る例はめずらしいかと思います。
以上より、平塚神社(平塚明神)創祀の後に城官寺が創建され、別当となったとみるのが妥当かと思われます。
豊島氏は秩父平氏の名族で、北区豊島が発祥の地、平塚城(豊島舘)を居城としたといいます。
前九年の役、後三年の役で戦功を挙げ、保元の乱では源義朝公の配下となり、治承四年(1180年)頼朝公の挙兵にも豊島清元(清光)・清重父子が馳せ参じて、豊島氏は有力御家人の地位を固めました。
鎌倉・室町時代の平塚城は領主・豊島氏代々の居城でしたが、文明十年(1478年)、太田道灌に攻められ落城しました。
その後の豊島氏宗家の動向は不明とされていますが、庶流は徳川幕府の旗本として幕末まで続いています。
清和源氏の守護神・八幡神の本地を阿弥陀如来とする説(例→兵庫県小野市Web記事)があり、清和源氏嫡流を祀る平塚明神の別当・城官寺の御本尊が阿弥陀如来であることは違和感なく受け入れられたのではないでしょうか。
また、豊島氏は王子神社や紀州神社の勧請創祀にかかわり、熊野信仰と深いつながりをもつとされます。
京都今熊野の新熊野神社の公式Webによると、熊野本宮大社の本地は阿弥陀如来で「この当時(平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて)の当時の熊野信仰を一言でいうと、本地垂迹説に基づく神仏習合信仰と浄土信仰が一体化した信仰ということになろう。」とあるので、豊島氏の信仰からみても城官寺の御本尊=阿弥陀如来は、自然な流れだったのかも。
さらに武州江戸六阿弥陀詣の縁起となる「足立姫伝説」の主人公も豊島氏(足立氏とも)とされ、豊島氏と阿弥陀如来のゆかりの深さを物語っています。
→ ■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印 ~ 足立姫伝説 ~
中世の城官寺の動静は史料が少なく不詳ですが、江戸時代、山川貞久(城官)という幕府仕えの鍼灸師が真言宗寺院として再興したと伝わります。
山川貞久(城官)は、三代将軍徳川家光公が病に倒れた時、平塚神社(平塚明神)に病の平癒を日夜祈りました。
その功徳もあってか家光公の病は快癒し、貞久(城官)は私財を投じて平塚明神を再建、さらに寛永十一年(1634年)には平塚神社の別当として当寺を再興したとされます。
寛永十七年(1640年)、家光公が鷹狩りで当地を訪れた際、平塚神社の社殿の豪華さに驚き、村長に造営者を尋ねたところ、貞久(城官)による家光公平癒祈願と社殿再建のくだりが説明されました。
これを聞いた家光公は貞久(城官)を呼び、平塚神社と当寺の所領として五十石、さらに貞久(城官)に知行地として二百石を与え、寺号を平塚山 城官寺 安楽院とすべく命じたとされます。
この病平癒の件もあってか、家光公は当地をたびたび参詣したといいます。
徳川家は源氏姓、新田氏流を名乗り、新田氏流(上野源氏)の祖は源義家公の三男義国公ですから、家光公が源家三兄弟をご祭神とする平塚神社を尊崇されたのも故あることかもしれません。


【写真 上(左)】 平塚神社の境内
【写真 下(右)】 平塚神社の御朱印
その後、真恵(享保三年(1718年)寂)を法流開基として現在に至ります。
御府内霊場の別当系札所寺院は明治初頭の神仏分離で廃絶となった例も多いですが、こちらは存続しています。
関係者のご尽力はもちろんですが、御府内から少し離れた郊外ということもあったのかもしれません。
山内には江戸幕府に奥医師として仕えた多紀・桂山一族の墓と山川貞久一族の墓があります。
奥医師には、典薬頭・奥医師・御番医師・寄合医師・小普請医師などが置かれ、奥医師は内科が多紀氏(丹波康頼の後裔とされる)、外科は桂川氏が世襲しました。
当寺再興の山川貞久(城官)も鍼灸師ですから、当山は医術とふかい所縁をもつことになります。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
四十七番
上中里村平塚別当
平塚山 安楽院 城官寺
音羽護国寺末 新義
本尊:阿弥陀如来 本社平塚大明神 弘法大師
本社 八幡太郎義家 加茂次郎義綱 新羅三郎義光
■ 『新編武蔵風土記稿 豊島郡之9』(国立国会図書館)
(平塚明神社別當城官寺)
新義真言宗大塚護国寺末 平塚山安楽院ト号ス 本尊阿彌陀ハ赤栴檀ニテ坐身長一尺許 毘首羯摩ノ作ト云 臺座ハ瑠璃ニテ造ル 是昔筑紫安楽寺ノ本尊ナリシカ 彼寺の僧回國ノ時當寺ニ旅宿シ 故有テ是ヲ附属セシヨリ安楽寺ト称ス 其頃迄ハ浄土宗ナリシカ 寛永十一年(1634年)社領修理アリシ時 金剛佛子ヲ請シテ別當タラシメシヨリ 今ノ宗門ニ改ムト云 同十七年(1640年)九月廿三日大猷院殿(3代将軍徳川家光公)社領ヘ渡ラセ給ヒテ 誰カ斯マテ造營セルヤト御尋アリシ頃 村長等山川城官ナルモノ公ノ御病悩ノ時 当社ハ己カ鎮守ナルヲ以テ御平癒アラン事ヲ祈誓セシニ 立所ニ験アリシユヘカクモノセシト御請マフセシカハ 御感ナヽメナラス 即城官ヲ御前ヘ召 社領五十石ヲ附ラセ賜ヒ 且忠賞トシテ城官ニ知行二百石ヲ賜ヒ 寺号ヲ改メ平塚山城官寺安楽院ト称スヘキノ台命アリシヨシ(略)
什物
假面一枚 義家手澤ノ物ト云伝フ
寺中光明院
十一面観音ヲ本尊トス コハ義家ノ守護佛行基の作ニテ 豊嶋近義ニ与フル所ノ像ナリト云 身長二尺
■ 『江戸名所図会 7巻 [15]』(国立国会図書館)
(平塚明神社)
平塚村にあり 当社縁起云往古八幡太郎義家兄弟 奥州前後十二年の戦終凱陣のみぎり此地に逗留あり ●主豊島氏某(或豊嶋太郎義近とも云)に鎧一領幷に守本尊十一面観音(長七寸行基菩薩の作也今城官寺に安置)を賜ふ 其後元永年中(1118-1120年)豊島氏●内清浄の地を択むて彼鎧を塚に築収め(塚の形高からさるを以て平塚と号●地名も亦これに因て称す)城の鎮守とす 且社城営むて三連枝の像●安し平塚三所明神と号す(八幡太郎義家 加茂次郎義綱 新羅三郎義光) 是義家兄弟の武功を欽崇且武運を祈らん為なりと云々 別当を平塚山城官寺といひ安楽院と号す 本地阿弥陀如来を安す 赤檀佛毘首羯摩天の作瑪瑙の玉座なり 昔筑紫安楽寺の僧回國修行の砌 此像をこヽに安置せしとそ

「城官寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
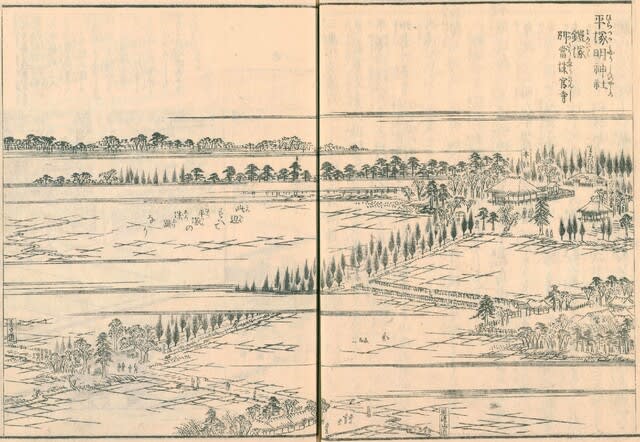
「平塚明神社 鎧塚 別当城官寺」/原典:松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[15],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836].国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』巣鴨絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはJR京浜東北線「上中里」駅で徒歩約3分。
「上中里」駅はかなり地味な駅でふつうは降り立つ機会がなかなかありません。
筆者も寺社巡りをはじめて、はじめて降りました。
Wikipediaには「2022年(令和4年)度の1日平均乗車人員は6,547人である。京浜東北線・根岸線の駅では最も乗車人員が少なく、東京23区のJR駅の中では越中島駅に次いで2番目に利用客数が少ない。」とあり、YouTubeなどで「都内の秘境駅」などと題されてしばしば紹介されます。
■【都会の過疎駅】京浜東北線 上中里駅を探検してみた Kami-Nakazato Station JR East Keihin Tohoku Line
メトロ南北線「西ヶ原」駅からも近いですが、こちらも乗降客の少なさで有名です。
乗降客が少ないということは付近に集客施設がないということで、この周辺は閑静な住宅街となっています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
「上中里」駅からの道行きはかなりの登り坂で、城官寺と平塚神社が田端台から飛鳥山にかけて南北に走る尾根上に位置していることがわかります。
人通りもまれな閑静な住宅地に、突如としてあらわれる立派な山門は桟瓦葺の四脚門。
「平塚山」の扁額は、当寺三百年を記念して書かれた当時の内閣総理大臣田中角栄氏の筆によるものとのこと。
山門前には御府内霊場第四十七番の札所標が建っています。


【写真 上(左)】 御府内霊場札所標
【写真 下(右)】 ???
全体に開放的であかるい雰囲気のお寺です。
正面に本堂。寄棟造平入りで起り屋根の向拝を付設しています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 向拝拝み部
水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
扁額は「城官寺」。格天井。扁額上の小壁に大瓶束と彫刻からなる笈形。
向拝屋根には経の巻獅子口と兎毛通を置く、存在感のある仏堂です。
御朱印は本堂向かって左手の庫裡にて拝受しました。
御府内霊場の他複数の霊場札所を兼務され、御朱印対応は手慣れておられます。
なお、上野王子駒込辺三十三観音霊場第6番の御朱印は、現在のところ授与されていないそうです。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
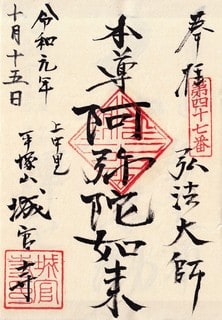
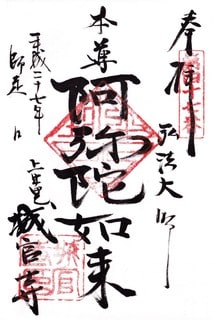
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 阿弥陀如来」「弘法大師」の揮毫。中央の印は山号印かもしれません。
右上に「第四十七番」の札所印。左下に山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。


【写真 上(左)】 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 滝野川寺院巡りの御朱印
■ 第48番 瑠璃光山 薬王寺 禅定院
(ぜんじょういん)
公式Web
中野区沼袋2-28-2
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
司元別当:
他札所:豊島八十八ヶ所霊場第48番
第48番はエリアを郊外に変えて沼袋の禅定院です。
第48番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに市ヶ谷の林松院となっています。
よって、第48番札所は御府内霊場開創時から江戸時代を通じて市ヶ谷の林松院であったとみられます。
公式Webに「明治16年、霊場巡拝の信仰の一つ、『御府内八十八カ所』の第48番霊場(林松院)の弘法大師像が奉安されたことから、第48番霊場となりました。」と明記されているので、第48番霊場は明治16年から禅定院となっています。
まずは、下記史料などから林松院の縁起・沿革を追ってみます。
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
四十八番
市ヶ谷袋町(市ヶ谷南寺町)
恵命山 圓満寺 松林院
大塚護持院末 新義
醍醐報恩いん(院)旅宿
本尊:不動明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [37] 市谷寺社書上 二』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.61』
市ヶ谷南寺町
恵命山 圓満寺 松林院
大塚護持院末 新義真言宗
旧号 宝珠院
林松院は市ヶ谷御門付近(あるいは四谷、市谷、牛込)に開創とみられますが、寛永十三年(1636年)の江戸城外堀普請に先立つ寛永十二年(1635年)、替地の市ヶ谷南寺町(市ヶ谷袋町)に移転しました。
開山は宝賢(正保三年(1646年)六月遷化)と伝わります。
江戸期は大塚護持院末の新義真言宗寺院でしたが、『御府内八十八ケ所道しるべ』には「醍醐報恩いん旅宿」とあります。
「京都ガイド」に「醍醐寺報恩院はかつて鎌倉時代前期に第35世座主・憲深僧正が上醍醐にあった極楽坊を活動拠点とし、報恩院と名付けたのが始まり」とあるので古義真言宗。
林松院が醍醐寺の江戸旅宿だったとすると、新義真言宗寺院が古義真言宗寺院の旅宿だったことになりますが詳細不明です。
御本尊は不動明王。
地蔵菩薩、弘法大師木像、大随求明王、歓喜天(秘佛)も奉安していたようです。
大随求明王はおそらく大随求菩薩とみられ、胎蔵曼荼羅の蓮華部院に在します。
観世音菩薩の変化身とされ、息災・滅罪、ことに求子の功能が説かれたようですが、作例は多くない模様です。
山内には、稲荷社、銀杏稲荷大明神、朝鮮五葉松などがありました。
つぎに公式Web、中野仏教会Web、下記史料などから禅定院の縁起・沿革を追ってみます。
禅定院は貞治元年(1362年)、法印恵尊を開基として新橋村(多摩郡野方領下沼袋村から枝分かれした村)に開創され、のちに現寺地に移転と伝わります。
開創時の御本尊は薬師瑠璃光如来で、山号・寺号は御本尊に由来するとも。
旧上沼袋村の伊藤一族の菩提寺として知られ、「伊藤寺」とも呼ばれていました。
明治16年、御府内霊場第48番札所であった林松院の弘法大師像が当山に奉安されたことから第48番札所となりました。
御本尊は不動明王立像で南北朝期(鎌倉時代後期?)の作といいます。
御内陣脇には薬師如来坐像が安置されています。
■ 『新編武蔵風土記稿』に御本尊は不動明王木立像とあるので、現御本尊はこの系譜をひく尊像と思われます。
同じく『新編武蔵風土記稿』には「薬師堂 木ノ立像長三尺九寸ナルヲ安ス 運慶ノ作ト云」とあります。
この薬師如来像は開創時の御本尊であった薬師如来であったかもしれず、現在の御内陣脇の薬師如来坐像もこの流れをひかれるかもしれません。
旧第48番の松林院、現第48番の禅定院ともに史料が少なく、沿革が辿りにくくなっています。
松林院は明治初頭の神仏分離の波は乗り越えたようですが現存せず、明治16年松林院の弘法大師像が禅定院に遷られたことから禅定院が第48番札所を承継しました。
このあたりの経緯も史料からは辿れず詳細不明です。
-------------------------
【史料】
【松林院関連】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
四十八番
市ヶ谷袋町(市ヶ谷南寺町)
恵命山 圓満寺 松林院
大塚護持院末 新義
醍醐報恩いん(院)旅宿
本尊:不動明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [37] 市谷寺社書上 二』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.61』
市ヶ谷南寺町
恵命山 圓満寺 松林院
大塚護持院末 新義真言宗
旧号 宝珠院
当寺開闢之代は往古市ヶ谷御門移し給ふ●● 寛永十二年(1635年)御門●(略)砌為替地只今之地也
拝領地寛永十二年(1635年)為替地賜
開山 宝賢 正保三年(1646年)六月遷化
本堂
本尊 不動明王木立像
地蔵尊木立像 弘法大師木像
大随求明王木坐像 歓喜天 秘佛
稲荷社
銀杏稲荷大明神
朝鮮五葉松
【禅定院関連】
■ 『新編武蔵風土記稿 多磨郡之35』(国立国会図書館)
(上沼袋村)禅定寺
村ノ東北ノ方小名内匠ニアリ 瑠璃光山薬王寺ト号ス 新義真言宗ニテ是モ寶仙寺末(略)
本尊不動木ノ立像ニテ長一尺五寸 開山詳ナラス
薬師堂 客殿ノ東ノ方ニアリ 木ノ立像長三尺九寸ナルヲ安ス 運慶ノ作ト云

「松林院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは西武新宿線「沼袋」駅。駅前の細い路地を歩くこと3分ほどで到着です。
第41番密蔵院のすぐそばです。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門の扁額
路地に面して築地塀。その奥に山門という二重の構え。
山門は切妻屋根本瓦葺でおそらく四脚門。
本瓦葺の屋根は照りがきいて格調高く、見上げに山号扁額を掲げています。
別に通用門?があって、こちらにも扁額が掲げられていました。

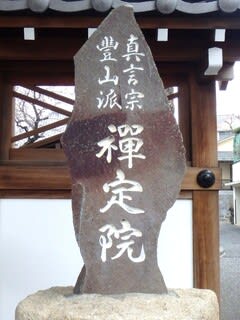
【写真 上(左)】 通用門?の扁額
【写真 下(右)】 院号標


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 山内
向かって右手に院号標、左手に御府内霊場の札所標を置いています。
駅そばとは思えないゆったりとした山内。
参道右手に六地蔵、左手に東屋、その先右手には樹齢600年以上ともいわれる銀杏の巨木があります。
本堂向かって右手には、修行大師像と聖観世音菩薩が御座します。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 修行大師像


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
正面の本堂は昭和45年の再建。
寄棟造本瓦葺で向拝柱はなく、比較的シンプルな構成です。
扉に掲げられた庵木瓜(いおりにもっこう)紋は、おそらく大旦那の伊藤家の家紋と思われます。


【写真 上(左)】 庵木瓜(いおりにもっこう)紋
【写真 下(右)】 弁天堂
向拝見上げに掲げられた扁額は五つの梵字から成りますが、筆者不勉強につき内容は不明です。
たしか本堂向かって左手の蓮池の向こうに弁天堂があり、弁財天・大黒天・毘沙門天の辨財天三尊を安置しています。
こちらは花の寺としても知られ、とくに牡丹が有名です。
御朱印は本堂向かって左手の庫裡にて拝受しました。
豊島八十八ヶ所霊場の札所も兼ね、対応は手慣れておられます。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳(専用用紙を貼付)
中央に「大聖不動」「弘法大師」の揮毫と不動明王のお種子「カン/カーン」の御寶印(火焔宝珠)。
右上に「御府内八十八所第四十八番札所」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
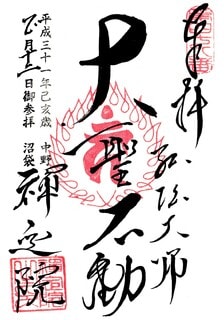
■ 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印
■ 第49番 寶塔山 龍門寺 多寶院
(たほういん)
台東区谷中6-2-35
真言宗豊山派
御本尊:多宝如来
札所本尊:多宝如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第49番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第9番、弘法大師二十一ヶ寺第2番
第49番は谷中の多寶院です。
第49番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに多寶院なので、御府内霊場開創時から一貫して谷中の多寶院であったとみられます。
下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
多寶院は、慶長十六年(1611年)幕府から神田北寺町に寺地を賜り建立されました。
開山は大僧都法印宥純(寛永五年(1628年)寂)、開基は不明です。
慶安元年(1648年)同所が幕府用地として召し上げとなり、現寺地に替地を得て移転しています。
湯島根生院の末寺の新義真言宗寺院で、御本尊は行基菩薩作と伝わる多宝如来です。
多宝如来は法華経に記され、東方・宝浄国の教主の如来です。
多宝如来は単独で奉安されることは少なく、御本尊の例もほとんどありません。
ただし、日蓮宗では法華経信仰に基づき釈迦如来とともに二体一組で信仰され重要なポジションです。
とくに、題目宝塔の両脇に釈迦如来と多宝如来を配した「一塔両尊」という安置形式は日蓮宗特有の御本尊として多くみられます。
密教では作例は少なく、札所本尊の例もほとんどないので当山の多宝如来は稀少です。
ちなみに、本四国八十八ヶ所に札所本尊が多宝如来の例はなく、他の弘法大師霊場でもみたことがありません。
当山は吉祥天の奉安でも知られています。
吉祥天はヒンドゥー教の女神・ラクシュミーが仏教にとり入れられたもので、仏教では母は鬼子母神、夫を毘沙門天とされます。
鬼子母神はとくに日蓮宗で信仰される尊格で、この点からも日蓮宗の影響が想起されますが当山は当初から純然たる密寺のようです。
この点は弘法大師霊場である御府内霊場の「御府内八十八ヶ所大意版木」が、多寶院が中心となって開版されたことからもわかります。
また、谷中エリアでの代表的な弘法大師霊場は、
1.御府内霊場(御府内八十八ヶ所霊場)
2.弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場
3.弘法大師二十一ヶ寺
の3つありますが、多寶院は3つの霊場すべての札所となっており、弘法大師巡拝に外せない寺院であったことがわかります。
(「御府内八十八ヶ所大意版木」、「弘法大師二十一ヶ寺御詠歌所附版木」ともに当山に収蔵。)
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
四十九番
谷中門外
寶塔山 龍門寺 多宝院
湯嶋根生院末 新義
本尊:多宝如来 弘法大師 興教大師
■ 『寺社書上 [110] 谷中寺社書上 弐』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.57』
湯島根生院末 谷中不唱小名
寶塔山龍門寺多宝院
慶長慶長十六年(1611年)二月十五日神田小寺町ニ寺地所拝領仕 其後慶安元年(1648年)御用地ニ●召上当時之地所拝領仕候
開山大僧都法印宥純(寛永五年(1628年)寂)
開基不分明
中興開山権大僧都法印澄正
本堂
本尊 多宝如来 行基菩薩作
聖天堂
聖天尊像
稲荷社
四国写八十八ヶ所碑三本 第四十九番目
石地蔵尊
■ 『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)
多寶院(谷中町三二番地)
湯島根生院末、寶塔山龍門寺と号す。本尊多寶如来、開山宥純(寛永五年(1628年)八月五日寂)。慶長十六年(1611年)二月、幕府より神田北寺町に地を給せられて建立した。慶安元年(1648年)同所が幕府の用地となるに及び現地に替地を給うて移転した。

「多宝院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』本郷湯島絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはJR「日暮里」駅で徒歩約8分。メトロ千代田線「千駄木」駅からも歩けます。
(→ 谷中マップ)
千駄木(団子坂下)から谷中に登る三崎坂(さんざきざか)が谷中霊園に月当たるところにあり、谷中界隈では比較的開けたところです。
門柱に札所札。門柱手前に吉祥天安置標。
門柱脇にも札所標がありますが、写真がうまく撮れていません。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 つつじの時期の門柱


【写真 上(左)】 門柱の院号札
【写真 下(右)】 吉祥天安置標
参道左手に六地蔵を含む地蔵尊、その先に慈母観音。
本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。
見上げに山号扁額を掲げています。
雰囲気のあるいい本堂で、落ち着いて参拝ができます。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝


【写真 上(左)】 斜めからの向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額
本堂向かって右手に谷中吉祥天のお堂。
堂前には幟がはためき、向拝見上げには「吉祥天」の扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 谷中吉祥天
【写真 下(右)】 谷中吉祥天の扁額
背後に円光(輪光)、胸部に瓔珞(ようらく)を帯び、右手は与願印、左手には宝珠を持たれる煌びやかな立像です。
吉祥天は仏教のなかでも屈指の美形の尊格として知られますが、こちらのお像も整った面立ちです。
御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受しました。
なお、「谷中吉祥天」の御朱印は不授与とのことです。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
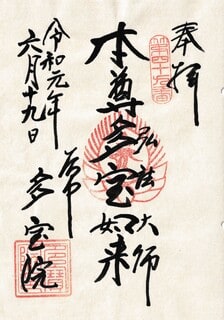

【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
【専用集印帳】
中央に「本尊多宝如来」「弘法大師」の揮毫とお種子の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「第四十九番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
多宝如来のお種子は「ア」とされますが、このお種子は「ア」ではないと思われます。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-17)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ ふたりでスプラッシュ - 今井美樹
■ Saikou no Kataomoi (最高の片想い) - Sachi Tainaka
■ Musunde Hiraku - kalafina
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第47番 平塚山 安楽院 城官寺
(じょうかんじ)
公式Web
北区上中里1-42-8
真言宗豊山派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
司元別当:(上中里村)平塚神社
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第47番、豊島八十八ヶ所霊場第47番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第6番、滝野川寺院巡り第8番
※この記事は■ 滝野川寺院めぐり-2をアレンジして仕上げています。
第47番はエリアを変えて上中里の城官寺です。
第47番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに城官寺となっています。
よって、第47番札所は御府内霊場開創時から一貫して上中里の城官寺であったとみられます。
公式Web、北区資料、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
城官寺は平塚神社(平塚明神)の元別当として知られています。(→平塚神社の公式Web)
城官寺は筑紫安楽寺の僧侶が諸国巡礼の折、当寺に宿泊した際に阿弥陀如来像を置き安楽院(安楽寺)と称し浄土宗の寺として創建といいます。
創建年代は不詳ですが、浄土宗開宗は承安五年(1175年)なので、それ以降の創建とみられます。
一方、『平塚明神并別当城官寺縁起絵巻』(北区指定有形文化財)は、平塚神社(平塚明神)の創祀について以下のように伝えています。
平安時代後期、このあたりに秩父平氏庶流の豊島太郎近義という人物が平塚城という城館を建て本拠としていました。
平塚城は源義家公が後三年の役(1083-1087年)で奥州に遠征した帰路の逗留地となり、豊島近義は心を尽くして饗応したため、義家公はこれに応じて、自らの鎧と守本尊の十一面観世音菩薩像を下賜しました。
近義は義家公の没後、平塚城鎮護のために拝領した鎧を埋め、その上に平たい塚(甲冑塚)を築き、義家公・義綱公・義光公の三人の木像を作り、そこに社を建てて安置したといいます。
創立は元永年中(1118-1120年)と伝わります。
これが平塚神社(平塚明神)の創祀で、”平塚”の地名の起こりともいわれ、当社は源家三兄弟にちなんで「平塚三所大明神」とも呼ばれて広く崇められました。
御祭神は八幡太郎 源義家命、賀茂次郎 源義綱命、新羅三郎 源義光命の源家三兄弟で、三兄弟を一社で祀る例はめずらしいかと思います。
以上より、平塚神社(平塚明神)創祀の後に城官寺が創建され、別当となったとみるのが妥当かと思われます。
豊島氏は秩父平氏の名族で、北区豊島が発祥の地、平塚城(豊島舘)を居城としたといいます。
前九年の役、後三年の役で戦功を挙げ、保元の乱では源義朝公の配下となり、治承四年(1180年)頼朝公の挙兵にも豊島清元(清光)・清重父子が馳せ参じて、豊島氏は有力御家人の地位を固めました。
鎌倉・室町時代の平塚城は領主・豊島氏代々の居城でしたが、文明十年(1478年)、太田道灌に攻められ落城しました。
その後の豊島氏宗家の動向は不明とされていますが、庶流は徳川幕府の旗本として幕末まで続いています。
清和源氏の守護神・八幡神の本地を阿弥陀如来とする説(例→兵庫県小野市Web記事)があり、清和源氏嫡流を祀る平塚明神の別当・城官寺の御本尊が阿弥陀如来であることは違和感なく受け入れられたのではないでしょうか。
また、豊島氏は王子神社や紀州神社の勧請創祀にかかわり、熊野信仰と深いつながりをもつとされます。
京都今熊野の新熊野神社の公式Webによると、熊野本宮大社の本地は阿弥陀如来で「この当時(平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて)の当時の熊野信仰を一言でいうと、本地垂迹説に基づく神仏習合信仰と浄土信仰が一体化した信仰ということになろう。」とあるので、豊島氏の信仰からみても城官寺の御本尊=阿弥陀如来は、自然な流れだったのかも。
さらに武州江戸六阿弥陀詣の縁起となる「足立姫伝説」の主人公も豊島氏(足立氏とも)とされ、豊島氏と阿弥陀如来のゆかりの深さを物語っています。
→ ■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印 ~ 足立姫伝説 ~
中世の城官寺の動静は史料が少なく不詳ですが、江戸時代、山川貞久(城官)という幕府仕えの鍼灸師が真言宗寺院として再興したと伝わります。
山川貞久(城官)は、三代将軍徳川家光公が病に倒れた時、平塚神社(平塚明神)に病の平癒を日夜祈りました。
その功徳もあってか家光公の病は快癒し、貞久(城官)は私財を投じて平塚明神を再建、さらに寛永十一年(1634年)には平塚神社の別当として当寺を再興したとされます。
寛永十七年(1640年)、家光公が鷹狩りで当地を訪れた際、平塚神社の社殿の豪華さに驚き、村長に造営者を尋ねたところ、貞久(城官)による家光公平癒祈願と社殿再建のくだりが説明されました。
これを聞いた家光公は貞久(城官)を呼び、平塚神社と当寺の所領として五十石、さらに貞久(城官)に知行地として二百石を与え、寺号を平塚山 城官寺 安楽院とすべく命じたとされます。
この病平癒の件もあってか、家光公は当地をたびたび参詣したといいます。
徳川家は源氏姓、新田氏流を名乗り、新田氏流(上野源氏)の祖は源義家公の三男義国公ですから、家光公が源家三兄弟をご祭神とする平塚神社を尊崇されたのも故あることかもしれません。


【写真 上(左)】 平塚神社の境内
【写真 下(右)】 平塚神社の御朱印
その後、真恵(享保三年(1718年)寂)を法流開基として現在に至ります。
御府内霊場の別当系札所寺院は明治初頭の神仏分離で廃絶となった例も多いですが、こちらは存続しています。
関係者のご尽力はもちろんですが、御府内から少し離れた郊外ということもあったのかもしれません。
山内には江戸幕府に奥医師として仕えた多紀・桂山一族の墓と山川貞久一族の墓があります。
奥医師には、典薬頭・奥医師・御番医師・寄合医師・小普請医師などが置かれ、奥医師は内科が多紀氏(丹波康頼の後裔とされる)、外科は桂川氏が世襲しました。
当寺再興の山川貞久(城官)も鍼灸師ですから、当山は医術とふかい所縁をもつことになります。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
四十七番
上中里村平塚別当
平塚山 安楽院 城官寺
音羽護国寺末 新義
本尊:阿弥陀如来 本社平塚大明神 弘法大師
本社 八幡太郎義家 加茂次郎義綱 新羅三郎義光
■ 『新編武蔵風土記稿 豊島郡之9』(国立国会図書館)
(平塚明神社別當城官寺)
新義真言宗大塚護国寺末 平塚山安楽院ト号ス 本尊阿彌陀ハ赤栴檀ニテ坐身長一尺許 毘首羯摩ノ作ト云 臺座ハ瑠璃ニテ造ル 是昔筑紫安楽寺ノ本尊ナリシカ 彼寺の僧回國ノ時當寺ニ旅宿シ 故有テ是ヲ附属セシヨリ安楽寺ト称ス 其頃迄ハ浄土宗ナリシカ 寛永十一年(1634年)社領修理アリシ時 金剛佛子ヲ請シテ別當タラシメシヨリ 今ノ宗門ニ改ムト云 同十七年(1640年)九月廿三日大猷院殿(3代将軍徳川家光公)社領ヘ渡ラセ給ヒテ 誰カ斯マテ造營セルヤト御尋アリシ頃 村長等山川城官ナルモノ公ノ御病悩ノ時 当社ハ己カ鎮守ナルヲ以テ御平癒アラン事ヲ祈誓セシニ 立所ニ験アリシユヘカクモノセシト御請マフセシカハ 御感ナヽメナラス 即城官ヲ御前ヘ召 社領五十石ヲ附ラセ賜ヒ 且忠賞トシテ城官ニ知行二百石ヲ賜ヒ 寺号ヲ改メ平塚山城官寺安楽院ト称スヘキノ台命アリシヨシ(略)
什物
假面一枚 義家手澤ノ物ト云伝フ
寺中光明院
十一面観音ヲ本尊トス コハ義家ノ守護佛行基の作ニテ 豊嶋近義ニ与フル所ノ像ナリト云 身長二尺
■ 『江戸名所図会 7巻 [15]』(国立国会図書館)
(平塚明神社)
平塚村にあり 当社縁起云往古八幡太郎義家兄弟 奥州前後十二年の戦終凱陣のみぎり此地に逗留あり ●主豊島氏某(或豊嶋太郎義近とも云)に鎧一領幷に守本尊十一面観音(長七寸行基菩薩の作也今城官寺に安置)を賜ふ 其後元永年中(1118-1120年)豊島氏●内清浄の地を択むて彼鎧を塚に築収め(塚の形高からさるを以て平塚と号●地名も亦これに因て称す)城の鎮守とす 且社城営むて三連枝の像●安し平塚三所明神と号す(八幡太郎義家 加茂次郎義綱 新羅三郎義光) 是義家兄弟の武功を欽崇且武運を祈らん為なりと云々 別当を平塚山城官寺といひ安楽院と号す 本地阿弥陀如来を安す 赤檀佛毘首羯摩天の作瑪瑙の玉座なり 昔筑紫安楽寺の僧回國修行の砌 此像をこヽに安置せしとそ

「城官寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
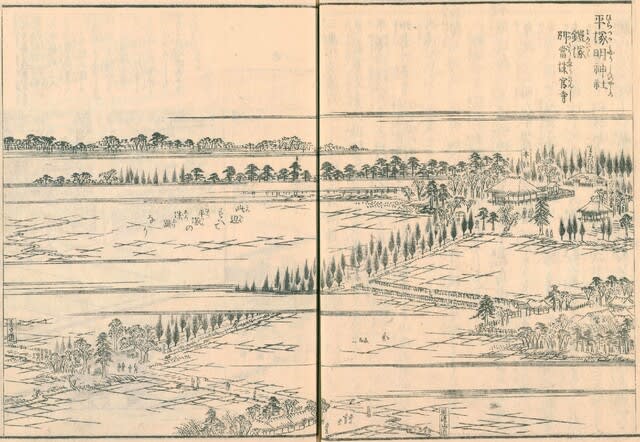
「平塚明神社 鎧塚 別当城官寺」/原典:松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[15],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836].国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』巣鴨絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはJR京浜東北線「上中里」駅で徒歩約3分。
「上中里」駅はかなり地味な駅でふつうは降り立つ機会がなかなかありません。
筆者も寺社巡りをはじめて、はじめて降りました。
Wikipediaには「2022年(令和4年)度の1日平均乗車人員は6,547人である。京浜東北線・根岸線の駅では最も乗車人員が少なく、東京23区のJR駅の中では越中島駅に次いで2番目に利用客数が少ない。」とあり、YouTubeなどで「都内の秘境駅」などと題されてしばしば紹介されます。
■【都会の過疎駅】京浜東北線 上中里駅を探検してみた Kami-Nakazato Station JR East Keihin Tohoku Line
メトロ南北線「西ヶ原」駅からも近いですが、こちらも乗降客の少なさで有名です。
乗降客が少ないということは付近に集客施設がないということで、この周辺は閑静な住宅街となっています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
「上中里」駅からの道行きはかなりの登り坂で、城官寺と平塚神社が田端台から飛鳥山にかけて南北に走る尾根上に位置していることがわかります。
人通りもまれな閑静な住宅地に、突如としてあらわれる立派な山門は桟瓦葺の四脚門。
「平塚山」の扁額は、当寺三百年を記念して書かれた当時の内閣総理大臣田中角栄氏の筆によるものとのこと。
山門前には御府内霊場第四十七番の札所標が建っています。


【写真 上(左)】 御府内霊場札所標
【写真 下(右)】 ???
全体に開放的であかるい雰囲気のお寺です。
正面に本堂。寄棟造平入りで起り屋根の向拝を付設しています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 向拝拝み部
水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
扁額は「城官寺」。格天井。扁額上の小壁に大瓶束と彫刻からなる笈形。
向拝屋根には経の巻獅子口と兎毛通を置く、存在感のある仏堂です。
御朱印は本堂向かって左手の庫裡にて拝受しました。
御府内霊場の他複数の霊場札所を兼務され、御朱印対応は手慣れておられます。
なお、上野王子駒込辺三十三観音霊場第6番の御朱印は、現在のところ授与されていないそうです。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
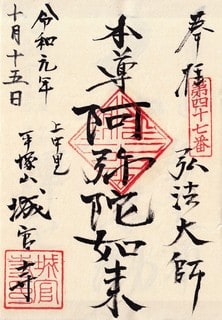
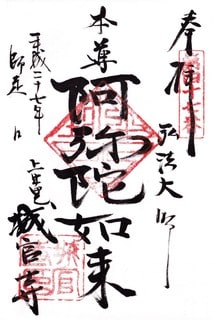
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 阿弥陀如来」「弘法大師」の揮毫。中央の印は山号印かもしれません。
右上に「第四十七番」の札所印。左下に山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。


【写真 上(左)】 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 滝野川寺院巡りの御朱印
■ 第48番 瑠璃光山 薬王寺 禅定院
(ぜんじょういん)
公式Web
中野区沼袋2-28-2
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
司元別当:
他札所:豊島八十八ヶ所霊場第48番
第48番はエリアを郊外に変えて沼袋の禅定院です。
第48番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに市ヶ谷の林松院となっています。
よって、第48番札所は御府内霊場開創時から江戸時代を通じて市ヶ谷の林松院であったとみられます。
公式Webに「明治16年、霊場巡拝の信仰の一つ、『御府内八十八カ所』の第48番霊場(林松院)の弘法大師像が奉安されたことから、第48番霊場となりました。」と明記されているので、第48番霊場は明治16年から禅定院となっています。
まずは、下記史料などから林松院の縁起・沿革を追ってみます。
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
四十八番
市ヶ谷袋町(市ヶ谷南寺町)
恵命山 圓満寺 松林院
大塚護持院末 新義
醍醐報恩いん(院)旅宿
本尊:不動明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [37] 市谷寺社書上 二』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.61』
市ヶ谷南寺町
恵命山 圓満寺 松林院
大塚護持院末 新義真言宗
旧号 宝珠院
林松院は市ヶ谷御門付近(あるいは四谷、市谷、牛込)に開創とみられますが、寛永十三年(1636年)の江戸城外堀普請に先立つ寛永十二年(1635年)、替地の市ヶ谷南寺町(市ヶ谷袋町)に移転しました。
開山は宝賢(正保三年(1646年)六月遷化)と伝わります。
江戸期は大塚護持院末の新義真言宗寺院でしたが、『御府内八十八ケ所道しるべ』には「醍醐報恩いん旅宿」とあります。
「京都ガイド」に「醍醐寺報恩院はかつて鎌倉時代前期に第35世座主・憲深僧正が上醍醐にあった極楽坊を活動拠点とし、報恩院と名付けたのが始まり」とあるので古義真言宗。
林松院が醍醐寺の江戸旅宿だったとすると、新義真言宗寺院が古義真言宗寺院の旅宿だったことになりますが詳細不明です。
御本尊は不動明王。
地蔵菩薩、弘法大師木像、大随求明王、歓喜天(秘佛)も奉安していたようです。
大随求明王はおそらく大随求菩薩とみられ、胎蔵曼荼羅の蓮華部院に在します。
観世音菩薩の変化身とされ、息災・滅罪、ことに求子の功能が説かれたようですが、作例は多くない模様です。
山内には、稲荷社、銀杏稲荷大明神、朝鮮五葉松などがありました。
つぎに公式Web、中野仏教会Web、下記史料などから禅定院の縁起・沿革を追ってみます。
禅定院は貞治元年(1362年)、法印恵尊を開基として新橋村(多摩郡野方領下沼袋村から枝分かれした村)に開創され、のちに現寺地に移転と伝わります。
開創時の御本尊は薬師瑠璃光如来で、山号・寺号は御本尊に由来するとも。
旧上沼袋村の伊藤一族の菩提寺として知られ、「伊藤寺」とも呼ばれていました。
明治16年、御府内霊場第48番札所であった林松院の弘法大師像が当山に奉安されたことから第48番札所となりました。
御本尊は不動明王立像で南北朝期(鎌倉時代後期?)の作といいます。
御内陣脇には薬師如来坐像が安置されています。
■ 『新編武蔵風土記稿』に御本尊は不動明王木立像とあるので、現御本尊はこの系譜をひく尊像と思われます。
同じく『新編武蔵風土記稿』には「薬師堂 木ノ立像長三尺九寸ナルヲ安ス 運慶ノ作ト云」とあります。
この薬師如来像は開創時の御本尊であった薬師如来であったかもしれず、現在の御内陣脇の薬師如来坐像もこの流れをひかれるかもしれません。
旧第48番の松林院、現第48番の禅定院ともに史料が少なく、沿革が辿りにくくなっています。
松林院は明治初頭の神仏分離の波は乗り越えたようですが現存せず、明治16年松林院の弘法大師像が禅定院に遷られたことから禅定院が第48番札所を承継しました。
このあたりの経緯も史料からは辿れず詳細不明です。
-------------------------
【史料】
【松林院関連】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
四十八番
市ヶ谷袋町(市ヶ谷南寺町)
恵命山 圓満寺 松林院
大塚護持院末 新義
醍醐報恩いん(院)旅宿
本尊:不動明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [37] 市谷寺社書上 二』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.61』
市ヶ谷南寺町
恵命山 圓満寺 松林院
大塚護持院末 新義真言宗
旧号 宝珠院
当寺開闢之代は往古市ヶ谷御門移し給ふ●● 寛永十二年(1635年)御門●(略)砌為替地只今之地也
拝領地寛永十二年(1635年)為替地賜
開山 宝賢 正保三年(1646年)六月遷化
本堂
本尊 不動明王木立像
地蔵尊木立像 弘法大師木像
大随求明王木坐像 歓喜天 秘佛
稲荷社
銀杏稲荷大明神
朝鮮五葉松
【禅定院関連】
■ 『新編武蔵風土記稿 多磨郡之35』(国立国会図書館)
(上沼袋村)禅定寺
村ノ東北ノ方小名内匠ニアリ 瑠璃光山薬王寺ト号ス 新義真言宗ニテ是モ寶仙寺末(略)
本尊不動木ノ立像ニテ長一尺五寸 開山詳ナラス
薬師堂 客殿ノ東ノ方ニアリ 木ノ立像長三尺九寸ナルヲ安ス 運慶ノ作ト云

「松林院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは西武新宿線「沼袋」駅。駅前の細い路地を歩くこと3分ほどで到着です。
第41番密蔵院のすぐそばです。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門の扁額
路地に面して築地塀。その奥に山門という二重の構え。
山門は切妻屋根本瓦葺でおそらく四脚門。
本瓦葺の屋根は照りがきいて格調高く、見上げに山号扁額を掲げています。
別に通用門?があって、こちらにも扁額が掲げられていました。

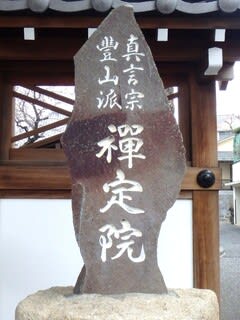
【写真 上(左)】 通用門?の扁額
【写真 下(右)】 院号標


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 山内
向かって右手に院号標、左手に御府内霊場の札所標を置いています。
駅そばとは思えないゆったりとした山内。
参道右手に六地蔵、左手に東屋、その先右手には樹齢600年以上ともいわれる銀杏の巨木があります。
本堂向かって右手には、修行大師像と聖観世音菩薩が御座します。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 修行大師像


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
正面の本堂は昭和45年の再建。
寄棟造本瓦葺で向拝柱はなく、比較的シンプルな構成です。
扉に掲げられた庵木瓜(いおりにもっこう)紋は、おそらく大旦那の伊藤家の家紋と思われます。


【写真 上(左)】 庵木瓜(いおりにもっこう)紋
【写真 下(右)】 弁天堂
向拝見上げに掲げられた扁額は五つの梵字から成りますが、筆者不勉強につき内容は不明です。
たしか本堂向かって左手の蓮池の向こうに弁天堂があり、弁財天・大黒天・毘沙門天の辨財天三尊を安置しています。
こちらは花の寺としても知られ、とくに牡丹が有名です。
御朱印は本堂向かって左手の庫裡にて拝受しました。
豊島八十八ヶ所霊場の札所も兼ね、対応は手慣れておられます。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳(専用用紙を貼付)
中央に「大聖不動」「弘法大師」の揮毫と不動明王のお種子「カン/カーン」の御寶印(火焔宝珠)。
右上に「御府内八十八所第四十八番札所」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
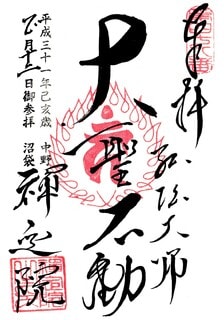
■ 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印
■ 第49番 寶塔山 龍門寺 多寶院
(たほういん)
台東区谷中6-2-35
真言宗豊山派
御本尊:多宝如来
札所本尊:多宝如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第49番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第9番、弘法大師二十一ヶ寺第2番
第49番は谷中の多寶院です。
第49番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに多寶院なので、御府内霊場開創時から一貫して谷中の多寶院であったとみられます。
下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
多寶院は、慶長十六年(1611年)幕府から神田北寺町に寺地を賜り建立されました。
開山は大僧都法印宥純(寛永五年(1628年)寂)、開基は不明です。
慶安元年(1648年)同所が幕府用地として召し上げとなり、現寺地に替地を得て移転しています。
湯島根生院の末寺の新義真言宗寺院で、御本尊は行基菩薩作と伝わる多宝如来です。
多宝如来は法華経に記され、東方・宝浄国の教主の如来です。
多宝如来は単独で奉安されることは少なく、御本尊の例もほとんどありません。
ただし、日蓮宗では法華経信仰に基づき釈迦如来とともに二体一組で信仰され重要なポジションです。
とくに、題目宝塔の両脇に釈迦如来と多宝如来を配した「一塔両尊」という安置形式は日蓮宗特有の御本尊として多くみられます。
密教では作例は少なく、札所本尊の例もほとんどないので当山の多宝如来は稀少です。
ちなみに、本四国八十八ヶ所に札所本尊が多宝如来の例はなく、他の弘法大師霊場でもみたことがありません。
当山は吉祥天の奉安でも知られています。
吉祥天はヒンドゥー教の女神・ラクシュミーが仏教にとり入れられたもので、仏教では母は鬼子母神、夫を毘沙門天とされます。
鬼子母神はとくに日蓮宗で信仰される尊格で、この点からも日蓮宗の影響が想起されますが当山は当初から純然たる密寺のようです。
この点は弘法大師霊場である御府内霊場の「御府内八十八ヶ所大意版木」が、多寶院が中心となって開版されたことからもわかります。
また、谷中エリアでの代表的な弘法大師霊場は、
1.御府内霊場(御府内八十八ヶ所霊場)
2.弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場
3.弘法大師二十一ヶ寺
の3つありますが、多寶院は3つの霊場すべての札所となっており、弘法大師巡拝に外せない寺院であったことがわかります。
(「御府内八十八ヶ所大意版木」、「弘法大師二十一ヶ寺御詠歌所附版木」ともに当山に収蔵。)
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
四十九番
谷中門外
寶塔山 龍門寺 多宝院
湯嶋根生院末 新義
本尊:多宝如来 弘法大師 興教大師
■ 『寺社書上 [110] 谷中寺社書上 弐』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.57』
湯島根生院末 谷中不唱小名
寶塔山龍門寺多宝院
慶長慶長十六年(1611年)二月十五日神田小寺町ニ寺地所拝領仕 其後慶安元年(1648年)御用地ニ●召上当時之地所拝領仕候
開山大僧都法印宥純(寛永五年(1628年)寂)
開基不分明
中興開山権大僧都法印澄正
本堂
本尊 多宝如来 行基菩薩作
聖天堂
聖天尊像
稲荷社
四国写八十八ヶ所碑三本 第四十九番目
石地蔵尊
■ 『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)
多寶院(谷中町三二番地)
湯島根生院末、寶塔山龍門寺と号す。本尊多寶如来、開山宥純(寛永五年(1628年)八月五日寂)。慶長十六年(1611年)二月、幕府より神田北寺町に地を給せられて建立した。慶安元年(1648年)同所が幕府の用地となるに及び現地に替地を給うて移転した。

「多宝院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』本郷湯島絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはJR「日暮里」駅で徒歩約8分。メトロ千代田線「千駄木」駅からも歩けます。
(→ 谷中マップ)
千駄木(団子坂下)から谷中に登る三崎坂(さんざきざか)が谷中霊園に月当たるところにあり、谷中界隈では比較的開けたところです。
門柱に札所札。門柱手前に吉祥天安置標。
門柱脇にも札所標がありますが、写真がうまく撮れていません。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 つつじの時期の門柱


【写真 上(左)】 門柱の院号札
【写真 下(右)】 吉祥天安置標
参道左手に六地蔵を含む地蔵尊、その先に慈母観音。
本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。
見上げに山号扁額を掲げています。
雰囲気のあるいい本堂で、落ち着いて参拝ができます。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝


【写真 上(左)】 斜めからの向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額
本堂向かって右手に谷中吉祥天のお堂。
堂前には幟がはためき、向拝見上げには「吉祥天」の扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 谷中吉祥天
【写真 下(右)】 谷中吉祥天の扁額
背後に円光(輪光)、胸部に瓔珞(ようらく)を帯び、右手は与願印、左手には宝珠を持たれる煌びやかな立像です。
吉祥天は仏教のなかでも屈指の美形の尊格として知られますが、こちらのお像も整った面立ちです。
御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受しました。
なお、「谷中吉祥天」の御朱印は不授与とのことです。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
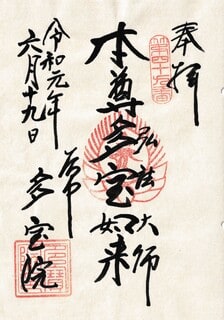

【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
【専用集印帳】
中央に「本尊多宝如来」「弘法大師」の揮毫とお種子の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「第四十九番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
多宝如来のお種子は「ア」とされますが、このお種子は「ア」ではないと思われます。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-17)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ ふたりでスプラッシュ - 今井美樹
■ Saikou no Kataomoi (最高の片想い) - Sachi Tainaka
■ Musunde Hiraku - kalafina
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-15
Vol.-14からのつづきです。
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第43番 神勝山 成就院
(じょうじゅいん)
台東区元浅草4-8-12
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第43番、弘法大師二十一ヶ寺第12番、江戸東方三十三観音霊場第24番(諸説あり)
第43番札所は元浅草の成就院です。
御府内霊場には成就院がふたつ(谷中の第43番、東上野の第78番)あり、第43番は百観音成就院、第78番は田中成就院と呼んで区別されます。
第43番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに成就院なので、御府内霊場開創時から一貫して成就院であったとみられます。
下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
成就院は、観宥法印(寛永五年(1628年)寂)が開山となり、矢の倉(現・浅草橋付近)に創建されたといいます。
「開山乗誉源印 寛永●(1624-1644年)起立 もと矢の倉に阿り万治(1658-1661年)の比当所へ移る」とする資料もあるようです。(『江戸志』)
史料によると御本尊は三尊阿弥陀如来、弘法大師坐像(大師巡拝江戸八十八ヶ所の内44番)興教大師坐像・三宝荒神坐像を奉じ、ほかに観音堂(百体観音・弘法大師)、石地蔵堂を有していたようですが、関東大震災や東京大空襲により諸堂は被災して現存していません。
「大師巡拝江戸八十八ヶ所(御府内霊場?)第44番」となっていますが、これは第43番と錯綜したのかもしれません。(第44番は当初から四ッ谷の顕性寺とみられる。)
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
四十三番
浅草寺町
神勝山 成就院
大塚護持院末 新義
本尊:観世音菩薩 不動明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [80] 浅草寺社書上 甲五』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.57』
江戸大塚護持院末 浅草新寺町
神勝山成就院
拙寺建立年代相知不申候
開山観宥、寛永五年6月15日遷化
本堂
本尊 三尊弥陀如来木立像
弘法大師木座像 大師巡拝江戸八十八ヵ所ノ内四十四番札所
興教大師木座像
三宝荒神木立像
大日如来木座像
観音堂
百体観音 弘法大師
石地蔵堂
開山乗誉源印寛永●(1624-1644年)起立 もと矢の倉に阿り万治(1658-1661年)の比当所へ移る(江戸志)

「成就院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
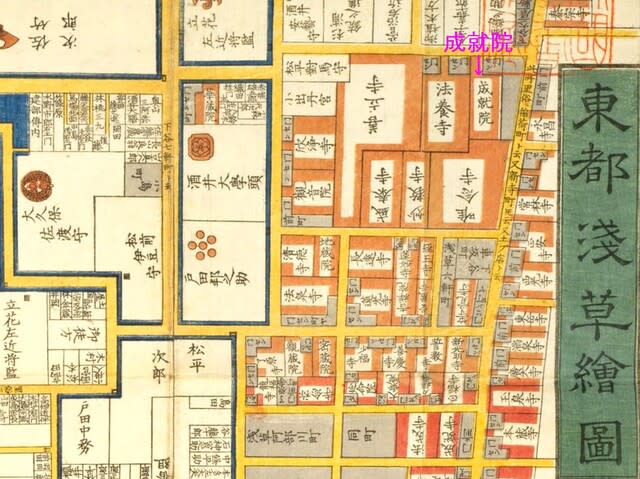
出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ銀座線「田原町」駅徒歩約5分。
御府内霊場札所が集中する元浅草・寿エリアの一画にあります。
都道463号浅草通り「元浅草四丁目」交差点から孫三通りを南に入ってすぐ。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 院号札
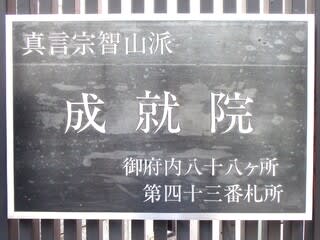

【写真 上(左)】 札所板-1
【写真 下(右)】 札所板-2
孫三通りに面して門柱。
門からだと民家風の事務所が目立ちますが、門柱の院号札と、本堂が一部見えるのでそれとわかります。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 本堂
本堂は2層の近代建築で、おそらく2階に鐘楼を置いていますが、こういうつくりの名称を筆者は知りません。
向拝柱はありませんが、見上げに山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 百観音
本堂向かって左手に百観音の尊像があり、背面には百観音の由来が記されています。
「当成就院は、古来通称百観音と云われてまいりました。百観音とは、西国三十三番、坂東三十三番、秩父三十四番観音霊場の総称であります。江戸時代には当境内にその百体の観音菩薩像がまつられていたと伝えられています、佛教信者にとって一生に一度は百観音霊場の巡拝を念願するものとされています。この度、特信者の寄進に依りその旧観を偲んで聖観音の尊像を像立し(略)」とありました。
御朱印は寺務所で拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
【専用集印帳】
中央に「本尊大日如来」「弘法大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「江戸御府内八十八ヶ所第四十三番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
【汎用御朱印帳】
中央に金剛界大日如来のお種子「バーンク」(五点具足/荘厳体)と弘法大師のお種子「ユ」の揮毫、御寶印(蓮華座+火焔宝珠)はおそらく金剛界大日如来のお種子「バン」。
右上に「江戸御府内八十八ヶ所第四十三番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第44番 金剛山 蓮華院 顕性寺
(けんしょうじ)
新宿区須賀町13-5
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第44番、山の手三十三観音霊場第26番
ようやっと中間の第44番までやってきました。
引きつづき同様の構成で進めます。
第44番札所は四ッ谷須賀町の顕性寺です。
第44番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに顕性寺なので、御府内霊場開創時から一貫して四ッ谷の顕性寺であったとみられます。
下記史料、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
顕性寺は慶長十六年(1611年)牛込御門外に起立。開山は賢秀法印(承應二年(1653年)寂)と伝わります。
江戸城外濠堀削のため寺地が召上げられ、寛永十一年(1634年)現在地に移転しました。
享保十年(1725年)2月青山の出火で焼失し、文政年間(1818年~1831年)に至ってもなお仮堂のままであったと伝わります。
元文三年(1738年)中野寶仙寺末。
中興開山は秀延法印(宝暦二年(1752年)寂)とあるので、秀延法印のときに寶仙寺末となったとみられます。
当寺は寺宝「俎大師(まないただいし)」で知られています。
これは弘法大師空海が土佐國高岡郡に巡錫された折、家に泊めてくれたお礼としてまな板に「南無阿弥陀仏」の文字を彫られたものといいます。
(『ルートガイド』には「長さ1メートルあまりの俎板に彫った、阿弥陀如来像」とあります。)
幕末に至り、弘法大師が泊まられた家の末裔が江戸に移住しました。
江戸(東京)で生活苦に陥り、「俎大師」を抵当として料亭「鳥八十」より借財し、そのまま「鳥八十」の所有となりました。
「鳥八十」のあるじの娘は、後に落語家の五代目古今亭今輔を生みましたが、昭和9年の弘法大師千百年遠忌に際して「俎大師」を当山に寄進、当山の寺宝となったといいます。
(以上「Wikipedia」(出所:『四谷南寺町界隈』(新宿区立図書館))より。)
「俎大師」とのゆかりは昭和に入ってからであり、宝暦の御府内霊場開創時にはすでに御府内霊場札所の資格を備えていたものとみられます。
当山は山の手三十三ヶ所観音霊場第26番札所ですが、この霊場は享保年間末(1736年)までには開創と目されるので、宝暦年間(1751-1764年)開創とされる御府内霊場より古い可能性があります。
山の手三十三ヶ所観音霊場の真言宗の札所の多くは御府内霊場の札所となっています。
(護国寺、新長谷寺、早稲田観音寺、放生寺、千手院→南蔵院、光徳院、顕性寺、真成院)
あるいは、顕性寺もこの流れで御府内霊場札所となったのかもしれません。
→ 札所リスト(「ニッポンの霊場」様)
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
四十四番
四ッ谷南寺町
金剛山 蓮華院 顕性寺
中の村宝仙寺末 新義
本尊:大日如来 不動明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [45] 四谷寺社書上 四』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.128』
中野寶仙寺末 四谷南寺町
金剛山蓮華院顕性寺
開闢起立之儀 慶長十六年(1611年)元地●●牛込●門外
中興開山 秀延法印 宝暦二年(1752年)寂
元寶仙寺門徒 元文三年(1738年)同寺末寺と相成候
客殿
本尊 金剛界大日如来木坐像
弘法大師 興教大師
観音堂
観世音木坐像 右山之手二拾六番札所
稲荷社 秋葉 八幡宮 相殿
石地蔵立像
開山 賢秀法印 承應二年(1653年)寂
■ 『四谷区史 [本編]』(国立国会図書館)
金剛山蓮花院顯性寺は中野村寶仙寺末の新義真言宗で、四谷南寺町にある。慶長十六年(1611年)牛込門外に起立し、外濠掘鑿の用地として公収されて、寛永十一年(1634年)此地に移転した。其後享保十年(1725年)二月の青山の出火に類焼して、文政(1818-1830年)当時は本建築に至らなかつたことが其書上に見える。
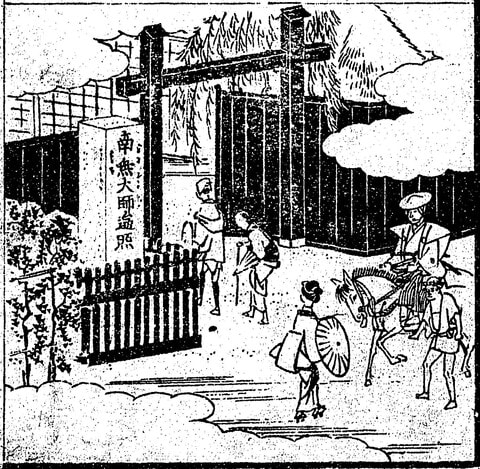
「顕性寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)
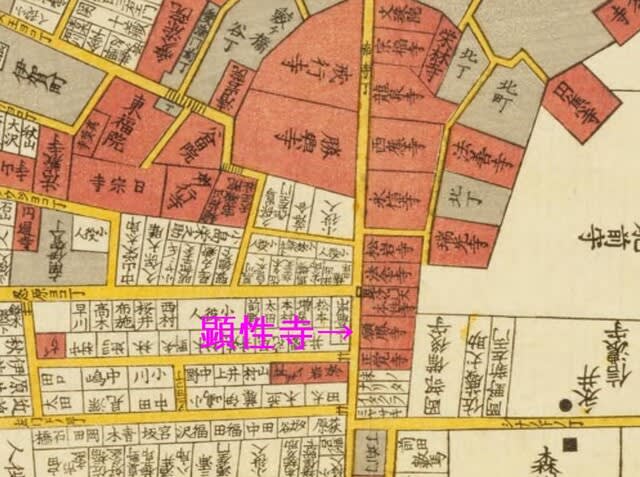
出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』四ツ谷絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」駅で徒歩約8分。
寺院が並ぶ四ッ谷寺町のまっただなかにあります。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 寺号標


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 本堂
山内入口に寺号標。右手に御府内霊場の札所標。
こぢんまりとした山内で、すぐ奥に本堂がみえます。
本堂は近代建築の2層。
向拝は2階で右手奥の階段でアプローチ。
向拝見上げには山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
『ルートガイド』によると本堂には御本尊・大日如来と俎大師が奉安されているそうです。
本堂は1階庫裡にて拝受できますが、筆者参拝時は2回ご不在があったので、事前TELがベターかもしれません。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

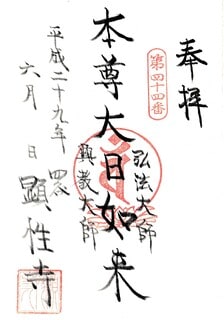
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊大日如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+宝珠)。
右上に「第四十四番」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第45番 廣幡山 隆源寺 観蔵院
(かんぞういん)
台東区元浅草3-18-5
真言宗智山派
御本尊:如意輪観世音菩薩
札所本尊:如意輪観世音菩薩
司元別当:
他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第83番、弘法大師二十一ヶ寺第13番
第45番札所は元浅草の観蔵院です。
第45番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに蔵前の雄徳山 神光寺 大護院なので、江戸期の御府内霊場第45番は蔵前の大護院であったとみられます。
『御府内八十八ケ所道しるべ』の札所異動表に第45番は大護院改め観蔵院とあるので、おそらく明治初期の神仏分離の際に札所異動があったとみられます。
まずは観蔵院について、下記史料、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
観蔵院は慶長十六年(1611年)澄(証)圓法印が開山となり中野屋鋪に創建、正保元年(1645年)現在地の元浅草に移転したと伝わります。
江戸大塚護国寺末の新義真言宗寺院です。
※『寺社書上』『御府内寺社備考』ともに長文の「舊記之写」を載せていますが、いずれも達筆すぎて筆者には解読不能につき、ここまでしかわかりません。
つぎに大護院について、藏前神社公式Web、下記史料などから縁起・沿革を追ってみます。
大護院の前身とみられる文殊院は蔵前にあって、高野山行人派觸頭の住院だったといいます。
『御府内八十八ケ所道しるべ』『江戸砂子温故名蹟誌』『江戸名所図会』ともに、もとは文殊院と号す高野山行人流の寺院で、行人派騒動の後、元禄五年(1692年)のころ石清水八幡宮を勧請された旨が記されています。
「行人派騒動」は、「元禄高野騒動」をさすと思われます。
「元禄高野騒動」とは寛永十五年(1638年)頃に端を発して50年ほどもつづき、元禄五年(1692年)幕府の裁定により決着した高野山の学侶方と行人方の争いです。
学侶方と行人方については、『元禄高野騒動と『高野春秋編年輯録』』(村上弘子氏・PDF)に、以下のとおり詳しくまとめられています。
「近世の高野山は、学侶方・行人方・聖方の「高野三方」と呼ばれる三つの組織から成り立っていた。学侶方とは法論談義や修法観念に専念する僧侶たちで、衆徒とも呼ばれる。青巌寺が頭寺院(略)行人方は興山寺を頭寺院とし、諸堂の管理や供花・給仕などの雑用に従事しており、堂衆・承仕とも呼ばれる(略)聖方は、弘法大師の入定信仰や高野山浄土信仰などを廻国唱導し(略)勧進活動を行なっていた中世の高野聖と呼ばれる僧たちが前身とされている。聖方頭寺院である大徳院は徳川氏と師檀関係を結んでおり、東照宮と二代将軍秀忠の台徳院御霊屋を祀っていた。」
行人方僧侶が堂上灌頂を受けることについて山内が紛糾し、江戸幕府も巻き込んで50年以上も争いがつづきました。
最終的には元禄五年(1692年)幕府の裁定により学侶方が勝利し、行人方の僧侶は600名以上も九州や隠岐に配流となり、行人方の多くの子院も取りつぶしとなりました。
この裁定について、『徳川実紀』(元禄五年九月四日条)は「こたび高野の事。査検のうへ仰下されし御旨もありしに。猶とかく愁訴やまず。いとひが事なれば。厳科にも處せらるべけれど。釋徒たるをもて助命せしめ山中を追放し。紀伊国の中にさしをき(略)増福院清雅はじめ八十二人は大隅国の島(略)八十人は隠岐国に遠流せしめ」と記しています。
高野山の内部機構の内紛にも係わらず、幕府は「厳科にも處せらるべけれ」とすこぶる強い姿勢でのぞみ、50年来の騒動に決着をつけたことがわかります。
「元禄高野騒動」の決着は元禄五年(1692年)9月、5代将軍綱吉公による山城國石清水八幡宮の勧請が元禄六年(1693年)8月5日(藏前神社公式Web)ですから史料類の時系列と符合します。
『御府内八十八ケ所道しるべ』の「昔ハ文殊院の八幡と称し高野山行人流の僧職ありしか 故あつて其地を改メられ石清水正八幡宮を勧請せり」の「故あつて」とは「元禄高野騒動」を示すものと思われます。
ここで気になったのは、御府内霊場札所と「高野三方」との関係です。
上記のとおり、近世の高野山は学侶方・行人方・聖方の「高野三方」と呼ばれる三つの組織から成り立っていました。
・学侶方 - 頭寺院は青巌寺、江戸の拠点は高輪の学侶方在番所
・行人方 - 頭寺院は興山寺、江戸の拠点は白金の高野山在番所行人方触頭
・聖方 - 頭寺院は(高野山)大徳院、江戸の拠点は高野山金剛峰寺諸国末寺総触頭(両国の大徳院)
これをもとに整理すると、
・学侶方 - 芝二本榎の学侶方在番所 → 高野山東京別院(第1番札所)
・行人方 - 白金の高野山在番所行人方触頭 → 文珠寺(第88番札所)
・聖方 - 高野山金剛峰寺諸国末寺総触頭 → 両国の大徳院(第50番札所)
となり、「高野三方」の江戸の拠点がそれぞれ御府内霊場の重要な札番を担っていたことになります。
御府内霊場折り返しの第45番・大護院(旧文珠寺?)が行人方触頭系寺院の系譜を曳くとなると、「高野三方」の関係からなんらかの意味合いがあったのかもしれません。
話が長くなりました。
ともあれ、文殊院跡地には元禄六年(1693年)8月5日5代将軍綱吉公が山城國男山の石清水八幡宮を勧請し、石清水正八幡宮と号しました。
なお、『御府内八十八ケ所道しるべ』には「昔ハ文殊院の八幡と称し」とあるので、綱吉公による石清水八幡宮勧請以前に八幡神の御鎮座があったのかもしれません。
ここからは主に藏前神社公式Webを参考に書き進めます。
上記のとおり、蔵前の石清水八幡宮は5代将軍綱吉公が元禄六年(1693年)に山城國男山の石清水八幡宮から勧請、御鎮座されました。
爾来、江戸城鬼門除守護神、徳川将軍家祈願所として篤く尊崇せられました。
藏前神社公式Webには以下のとおり記載があります。
「文政年間(1818-1830年)の『御府内備考続編』ならびに『寺社書上』には次のように記されています。『石清水八幡宮。御朱印社領200石。当社、石清水八幡宮境内、拝領の儀は 元禄6年5月27日、高野山興山寺上り屋敷拝領つかまつり、同年8月、八幡宮社頭建立の節、御金子300両拝領つかまつり、諸堂建立つかまつり候(略)」
「高野山興山寺上り屋敷」は旧文珠寺とみられ、文珠寺跡地が石清水八幡宮となったことを示しています。
享保十七年(1732年)類焼し、替地として浅草三嶋町に御遷りのところ、延享元年(1744年)寺社御奉行大岡越前守忠相が「三嶋町は御祈願所に不相応」とし、上意を得て蔵前の元地に還幸されました。
藏前神社公式Webには「江戸の北極星信仰」として、帯広市の真宗大谷派「順進寺」坂谷徹念住職による説が紹介されています。
要旨は以下のとおりです。
・北極星と北斗七星は古来より信仰の対象となり、仏教や神道にもとり入れられた。
・江戸の都市計画にも北極星、北斗七星の力が重用され、単に鬼門に神社仏閣を建立するだけでなく、神社仏閣の配置が北斗七星の形状となるように計画が練られた。
・江戸の都市計画をリードした天海は天台僧であり、神社だけで北斗七星を構成したとするには無理がある。
・北斗七星形成候補として考えられる朱印地30石以上の神社は上野東照宮、日枝神社、根津神社、藏前神社、氷川神社、愛宕神社、神田明神、白山神社の8社。
・うち根津神社は家宣公屋敷地に御遷座、白山神社は綱吉公の屋敷普請のため遷宮、氷川神社の御遷座は吉宗公の代で、江戸の都市計画(鬼門封じ)の色合いは薄く対象外とした。
・愛宕神社は防火・防災上極めて重要な神社、上野東照宮、日枝神社、石清水八幡宮(藏前神社)、神田明神はすべて江戸の守護神、祈願所として大切な神社であった。
・一方、朱印地が500石以上の大寺は寛永寺、増上寺、護国寺、浅草寺の4箇寺。
・増上寺は徳川家の菩提寺であり、寛永寺、護国寺、浅草寺はいずれも幕府の祈願寺として極めて大事な寺院であった。
・江戸の都市計画上の重要人物に、家光公側室で綱吉公生母の桂昌院がいる。
・延宝八年(1680年)5月実子綱吉公の将軍就任後ほどなく、桂昌院は綱吉公を動かし護国寺、藏前神社を創建して江戸守護のための北極星、北斗七星を完成させた。
・坂谷住職は以上から、増上寺、愛宕神社、日枝神社、神田明神、石清水八幡宮(藏前神社)、浅草寺、寛永寺(上野東照宮)が北斗七星、護国寺が北極星にあたると考えられた。
以上の説によると、元禄六年(1693年)8月5日、5代将軍綱吉公が文殊院跡地にみずから山城國男山の石清水八幡宮を勧請したことが符合し、また、享保十七年(1732年)の類焼で浅草三嶋町に御遷座の石清水八幡宮を、延享元年(1744年)寺社御奉行大岡越前守忠相が、「三嶋町は御祈願所に不相応」とし、上意を得て蔵前の元地に還幸された理由としても納得できます。
藏前神社公式Webにはさらに以下のとおりあります。
「当時は神仏習合思想に基づいて、全国の主要な神社には付属して別当寺が建立されていました。そして、当社石清水八幡宮の別当寺としては、雄徳山大護院(オトコヤマダイゴイン=新義真言宗)が営まれ、江戸の「切絵図」にも見られます。」
神社の公式Webで元別当が紹介される例は希とみられますが、こちらでは明記され、大護院の存在の大きさが伺えます。
石清水八幡宮は「藏前八幡」「東石清水宮」とも称され、崇敬者はなはだ多く関東の名社のひとつに数えられました。
天保十二年(1841年)には日本橋の「成田不動」(成田山御旅宿=ナリタサンオタビ)が、幕府の方針に基づき当社境内に遷されました。
『御府内八十八ケ所道しるべ』には「成田不動明王御旅所 江の嶋弁天御旅所 伊勢朝熊虚空蔵御旅所 御嶽山あり」とあり、石清水八幡宮(別当大護院)が神仏習合の一大拠点であったことが伺えます。
明治初頭の「神仏分離令」により別当・雄徳山大護院は廃寺(廃絶)となり、成田不動は明治2年深川に遷され、大施餓鬼塔も同3年練馬の東高野山に移されました。(藏前神社公式Web)
成田不動尊の江戸出開帳のほとんどは深川永代寺(富岡八幡宮)で催され、江戸の成田不動尊信仰の中心だったイメージがあります。
しかし、「成田不動信仰と市川團十郎」抄録(佛教大学大学院紀要)には、「元禄以降、江戸の成田不動信仰の拠点であった『成田山御旅宿』の経営にかかわっていた講中(略)」とあり、ふだんは日本橋の「成田山御旅宿」が江戸の成田不動信仰の拠点であったことを示唆しています。
この日本橋の「成田山御旅宿」が天保十二年(1841年)に蔵前の石清水八幡宮(別当大護院)に遷られ、その「成田不動は明治2年(1869年)深川に遷され」とあるので、1841年から1869年までの28年間は別当大護院が江戸の成田不動尊信仰の中心となった可能性があります。
話が飛んでばかりですみませぬ。
石清水八幡宮は明治6年8月郷社に列格、一時期「石清水神社」と改称するも復号し、昭和26年3月に社号を「藏前神社」と改めています。
なので戦前までの史料には「藏前神社」という神社は記載されていません。
大護院は「御室御所直院家」という真言宗仁和寺系の名刹なので、大護院廃絶後の御府内霊場札所は御室派系寺院が承継しそうですが、実際には智山派の観蔵院(元浅草)が承継しています。
観蔵院は荒川辺八十八ヶ所霊場第83番札所で、あるいは弘法大師霊場札所寺院ということで定められたのかも。
荒川辺八十八ヶ所霊場は天保九年(1838年)以前の開創とされる弘法大師霊場で、根岸・世尊寺から打ち始め、荒川、日暮里、尾久、船堀、豊島、江北、本木、千住、綾瀬、亀有、墨田、向島、亀戸、元浅草と回って根岸・千手院で結願となります。
→ 札所リスト(「ニッポンの霊場」様)
豊島八十八ヶ所霊場、荒綾八十八ヶ所霊場との札所重複は少なくないですが、御府内霊場との重複は亀戸東覚寺(第73番)、元浅草延命院(第51番)、成増青蓮寺(第19番)と観蔵院の4つしかありません。
しかし、下町の弘法大師霊場のうち蔵前・浅草辺に札所をもつのは荒川辺八十八ヶ所霊場だけなので、蔵前に近い元浅草の札所から選ばれたのかもしれません。
御室派系(大護院)から智山派系(観蔵院)への札所承継は、あるいは大護院が智山派系の成田不動尊の御旅所であったという縁によるものかもしれません。
-------------------------
【史料】
【観蔵院関連】
■ 『寺社書上 [80] 浅草寺社書上 甲五』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.58』
江戸大塚護国寺末 浅草新寺町
廣幡山隆源寺観蔵院
起立之年代舊記に無御座候得共 往古慶長十六年(1611年) 中野屋鋪●拝領仕罷●候処 御用地ニ付所替候 仰付正保元年(1645年)中当所に引移候由申伝候
開山 澄圓法印 寛永十年(1633年)入寂
本堂
本尊 如意輪観音坐像木佛
●● 弘法大師 興教大師
護摩堂
愛染明木像王 弘法大師作
※『寺社書上』『御府内寺社備考』ともに舊記之写を載せていますが、いずれも達筆すぎて筆者には解読不能です。
【大護院関連】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
四十五番
浅草御蔵前八幡 門前町あり
雄徳山 神光寺 大護院
御室御所直院家 新義
本尊:愛染明王 弘法大師
本社:石清水八幡宮
御本丸御祈願所
石清水正八幡宮 大倉前にあり
元禄五年(1692年)台命によって石清水正八幡宮勧請せり
昔ハ文殊院の八幡と称し高野山行人流の僧職ありしか
故あつて其地を改メられ石清水正八幡宮を勧請せり
別当大護院と号雄徳山と云
開山幸沼法印なり
護摩堂本尊ハ五大明王にして運慶作なり
成田不動明王御旅所江の嶋弁天御旅所
伊勢朝熊虚空蔵御旅所御嶽山あり
■ 『江戸砂子温故名蹟誌 6巻 [2]』(国立国会図書館)
八幡宮 御蔵前 社領二百石 別當雄徳山神光寺大護院 眞言
これを文殊院といふハ 以前文殊院といひて高野山行人派の觸かしら住院す 行人派騒動ありて後 元禄五年(1692年)のころ石清水八幡宮をうつさせられたり
■ 『江戸名所図会 7巻 [16]』(国立国会図書館)
八幡宮
御蔵前 社領二百石
雄徳山神光寺大護院 真言
これを文殊院の八幡といふハ以前文殊院といひて高野山行人流の觸かしら住院す
行人派騒動ありて後 元禄五年(1692年)のころ石清水八幡宮をうつさせられたり

「正覚寺 八幡宮」/原典:松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[16],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836].国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ銀座線「稲荷町」駅で徒歩約5分。
「稲荷町」は都内で育った人でもなかなか使わない駅ですが、御府内霊場札所密集エリアのアプローチになるので、御府内霊場巡拝時には重要な駅です。
都道463号浅草通り「松が谷一丁目」交差点から左右衛門橋通りを南に入り少し行った路地を左に回り込むとすぐにあります。


【写真 上(左)】 外観
【写真 下(右)】 院号札
路地にすぐ面して本堂があり、たたずまいは瀟洒な邸宅のようです。
確かベルを押して御朱印帳をお預けしてからの参拝でした。
本堂前左手に修行大師像、向かって右横には聖観世音菩薩の立像。
向拝上には真言宗智山派の宗紋・桔梗紋が染められた向拝幕を巡らし、見上げには豪快な筆致の山号扁額。
ここに来て俄然札所のイメージが高まります。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 札所幟
ご案内いただいた本堂内。
正面に御本尊の如意輪観世音菩薩坐像。
向かって右に胎蔵曼荼羅、左には金剛界曼荼羅が掲げられています。
御本尊まわりに愛染明王などの諸仏。
こちらの愛染明王は、大護院の御本尊であった愛染明王とのつながりも想起されますが、詳細不明です。
向かって右には弘法大師坐像、左には興教大師坐像が御座され、密寺らしい空間となっています。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
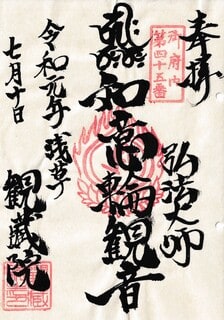
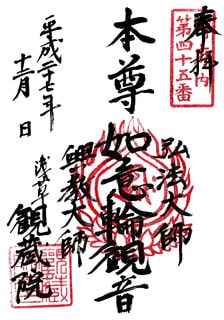
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に如意輪観世音菩薩のお種子「キリーク」と「如意輪観音」「弘法大師」の揮毫と「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内第四十五番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第46番 萬徳山 聖寶院 弥勒寺
(みろくじ)
墨田区立川1-4-13
真言宗豊山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第50番、御府内二十八不動霊場第20番、御府内十三仏霊場第6番(弥勒菩薩)、江戸十二薬師第6番
第46番は御府内霊場屈指の名刹です。
第46番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』で弥勒寺、江戸八十八ヶ所霊場では両国の大徳院(現御府内霊場・第50番札所)となっています。
よって、江戸時代に第50番札所の弥勒寺と第46番札所の大徳院が入れ替わった可能性があります。
その経緯は不明ですが、弥勒寺は御府内霊場開創時からの札所であったとみられます。
下記史料、すみだ観光サイト、現地掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
弥勒寺は、慶長十五年(1610年)宥鑁上人が小石川鷹匠町に創建(中興開山とも)、馬喰町上寺町、深川など幾度かの移転を経て元禄二年(1689年)本所に移転したと伝わります。
かつては京都醍醐寺三宝院末でしたが、のちに根来寺末となっています。
寺領百石の朱印状を拝領し、新義真言宗関東四箇寺のひとつとして触頭を勤めた名刹です。
触頭とは宗派内の寺院・僧侶を統括する寺院で、幕府との接触も多く江戸時代には極めて重要な役割を果たしました。
真言宗智山派総本山智積院の公式Webによると、「新義真言宗触頭」=「江戸四箇寺」で、発足当初は知足院・真福寺・円福寺・弥勒寺。
その後貞享四年(1687年)に知足院が将軍家の祈祷寺を理由に免除され、根生院が任じられています。
円福寺は明治2年に廃寺となっていますが、江戸時代には「江戸四箇寺」の寺院すべてが御府内霊場札所となっていました。
『御府内寺社備考』には、「元禄二年(1689年)賜此地 綱吉公命云彌勒根生二院者属小池房真福圓福二寺者属智積院住持亦各其山之僧可令居之云々 同年七月移寺院●本所造庫裡当」とあり、元禄二年(1689年)の本所移転時にはすでに「江戸四箇寺」に数えられていたことがわかります。
『新義真言宗触頭江戸四箇寺成立年次考』(宇高良哲氏/PDF)には「江戸四ヶ寺の成立年次であるが、従来の研究により元和五年以降同九年以前」とあり、智積院公式Webには「その後貞享四年(1687年)に知足院が将軍家の祈祷寺を理由に免除され、根生院が任じられています。」とあるので、元禄二年(1689年)に根生院が数えられている『御府内寺社備考』の記述と年次が符合します。
当初は弥勒菩薩を御本尊としたことから弥勒寺と号しましたが、後に薬師如来が御本尊となっています。
当山御本尊の薬師如来像は、徳川光圀公(1628-1701年)から寄進された尊像といいます。
この行基菩薩作と伝わるお薬師さまはもともと常陸国の真言宗寺院にあり、故あってこの寺の寺領を水戸光圀公が没収されたときにこの尊像を川(那珂川?)に流しました。
しかし不思議なことにこの尊像は下流に流されることなく、川上に向かって流されたといいます。
これを見た光圀公はこの尊像への尊崇を新たにし、川上に流れたことから「川上薬師」と呼ばれて以降人々の信仰を集めました。
光圀公はこの尊像を縁のあった弥勒寺に奉じ、以降当山の御本尊になったといいます。
弥勒寺の薬師如来は江戸十二薬師(十三薬師)第6番札所として知られていたようですが、その他の札所は概ね詳細不明のようです。
塔頭に法樹院、徳上院、正福院、寳珠院、正覺院、龍光院などがあり、多くの末寺を擁しました。
御府内霊場にも弥勒寺末の札所寺院がいくつかありました。
『御府内寺社備考』には、「権現様(徳川家康公) 台徳院様(2代将軍秀忠公) 大猷院様(3代将軍家光公) 右所三代之間御表御奥に御祈祷し●●献上仕御初穂等拝領仕候」とあり、徳川将軍家の祈祷所の役割を果たしていたことを示しています。
『御府内寺社備考』はまた、当山の大檀那が牧野備前守成貞であったことを記しています。
牧野成貞(1635-1712年)は三河牧野氏の流れで5代将軍綱吉公の側用人から下総関宿藩主。
三河牧野氏は東三河の土豪として松平氏(徳川氏)に仕え、江戸時代には門閥譜代として多くの大名・旗本家を輩出した名門です。
徳川光圀公とのゆかりといい、さすがに「触頭江戸四箇寺」にふさわしい沿革を伝えています。
山内には5代将軍綱吉公に鍼灸師として仕えた杉山和一(杉山検校)の墓所や鍼供養碑があります。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
四十六番
本所二ッ目林町
萬徳山 聖宝院 弥勒寺
院家長谷山方どくれいせ● 新義
本尊:薬師如来 弘法大師 興教大師
■ 『寺社書上 [88] 本所寺社書上 壱』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.75』
山城國醍醐三宝院末 本所二ッ目
萬徳山聖宝院弥勒寺
新義真言宗触頭
(以下抜粋)
開山宥鑁法印 聖寶院之住持也
初聖宝尊師作之不動尊幷行基作之彌勒菩薩以以為本尊故為院号
古ハ松梅山又松風山とも号
宥鑁後堀請武府拝領寺地於馬喰町建立院宇時蒙
鈞命為四箇寺職特是
慶長十五年(1610年)、御召ニ付江府●●寺地●仕 彌勒尊を本尊と●彌勒寺と号
触頭●
慶長十五年(1610年)鷹匠町に寺地を移し 元禄二年(1689年)●●拝領仕候在寺地東方に御●●
元和二年(1616年)鑁随醍醐山三寶院准三宮法務大僧正義演法流以為本寺
寛永十年(1689年)従水戸社務光明院移住以故水戸黄門君●遇
天和二年(1682年)罹災院宇為灰燼●是後転寺地 拝領深川俄造坊室
元禄二年(1689年)賜此地 綱吉公命云彌勒根生二院者属小池房真福圓福二寺もの属智積院住持亦各其山之僧可令居之云々 同年七月移寺院●本所造庫裡当
本堂
本尊 薬師如来木像 行基菩薩作
此尊像を●●常州筑波郡之内水戸殿御領内●る真言宗之寺(略)水戸黄門公右之寺を没収
し給ふとき本尊を谷川(那珂川とも)へ流し● 不思議なる●漲る●を川上へ流れし給ふ此奇特を以て黄門公より当寺八世(略)川上薬師●来と称
前立 薬師如来木像
日光月光菩薩
寺寶
常憲院様(5代将軍綱吉公)御画(筆) 鶴松之御画
不動尊画像 弘法大師五十二歳之時作画
千体不動尊画像
六臂辨財天像
弘法大師御影
鎮守八幡社
大日堂
本尊 大日如来 観音
権現様(徳川家康公) 台徳院様(2代将軍秀忠公) 大猷院様(3代将軍家光公)
右所三代之間御表御奥に御祈祷し●●献上仕御初穂等拝領仕候
■ 『江戸名所図絵 第4 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)
真言新義の触頭江戸四箇寺の一室なり。本尊は薬師如来、世に河上薬師と称せり。中興開山を、宥鑁上人と号す。総門の額に、彌勒寺と書せしは、朝鮮國雪月堂の筆跡なり。当寺舊柳原の地にありしを、天和二年(1682年)回禄の後、此地へ移されたり。毎月八日十二日を縁日として参詣多し。
■ 『東京名所図絵』(国立国会図書館)
萬徳山弥勒寺ハ天祖神社の北二丁余彌勒寺橋の北詰林町に在り 真言新義の触頭にして東京四ヶ寺の一なり 本尊ハ薬師如来なり 世に河上薬師と云ふ 中興開山ハ宥鑁上人なり 毎月八日十二日ハ縁日として参詣人多し

「弥勒寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』深川絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは都営新宿線・大江戸線「森下」駅で徒歩約5分。
住宅、オフィスビル、寺院が混在するエリアにひっそりとあります。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 門柱の寺号札


【写真 上(左)】 山内&本堂
【写真 下(右)】 杉山検校墓菩所
山内入口は門柱のみで、本堂もすぐそこに見えますが、どことなく風格を感じるのは触頭寺院の歴史でしょうか。
参道右手の観音聖像は、昭和20年3月10日の東京大空襲による犠牲者の冥福を祈る尊像です。この聖像のもとに多くの遺骨が収納されています。
「日本大百科全書(ニッポニカ)」によると2時間半の爆撃によって東京下町一帯は廃墟 (はいきょ)と化した。約2000トンの焼夷弾を装備した約300機のB-29の攻撃で下町エリアの40平方キロメートルが焼失、焼失家屋約27万戸、罹災者数は実に100万余人に達したといいます。
広くはない山内ということもあって、令和の今日でもなお戦禍の悲惨さが逼ってくるような感じがあります。
本堂は近代建築で、様式はよくわかりません。
向拝柱はなく、扉に置かれた真言宗豊山派の宗紋「輪違紋」がよく目立ちます。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 「筆供養」の碑
堂前向かって右手の「筆」と彫られた石碑は、「弥勒寺で書道の道場を開いていた昭和の書家、相沢春洋の命日にあたり、門下生がそれにちなんで使い古した毛筆に感謝を込めて供養する」「筆供養」の碑です。(すみだ経済新聞より)
本堂には表装をかけた千社札が掲げられていました。
御府内でも有数の名刹ゆえ、かつての堂宇には多くの千社札が貼られていたのでは。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 千社札
御朱印は本堂向かって左手奥の庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に薬師如来のお種子「バイ」と「薬師如来」の揮毫。別に左右に種子の揮毫がありますが、達筆すぎて読解できません。
中央の主印は三寶印。
右上に「御府内第四十六番」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-16)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ ノーサイド - 松任谷由実
■ thaw song - 中恵光城
■ LANI~HEAVENLY GARDEN~ - 杏里
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第43番 神勝山 成就院
(じょうじゅいん)
台東区元浅草4-8-12
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第43番、弘法大師二十一ヶ寺第12番、江戸東方三十三観音霊場第24番(諸説あり)
第43番札所は元浅草の成就院です。
御府内霊場には成就院がふたつ(谷中の第43番、東上野の第78番)あり、第43番は百観音成就院、第78番は田中成就院と呼んで区別されます。
第43番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに成就院なので、御府内霊場開創時から一貫して成就院であったとみられます。
下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
成就院は、観宥法印(寛永五年(1628年)寂)が開山となり、矢の倉(現・浅草橋付近)に創建されたといいます。
「開山乗誉源印 寛永●(1624-1644年)起立 もと矢の倉に阿り万治(1658-1661年)の比当所へ移る」とする資料もあるようです。(『江戸志』)
史料によると御本尊は三尊阿弥陀如来、弘法大師坐像(大師巡拝江戸八十八ヶ所の内44番)興教大師坐像・三宝荒神坐像を奉じ、ほかに観音堂(百体観音・弘法大師)、石地蔵堂を有していたようですが、関東大震災や東京大空襲により諸堂は被災して現存していません。
「大師巡拝江戸八十八ヶ所(御府内霊場?)第44番」となっていますが、これは第43番と錯綜したのかもしれません。(第44番は当初から四ッ谷の顕性寺とみられる。)
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
四十三番
浅草寺町
神勝山 成就院
大塚護持院末 新義
本尊:観世音菩薩 不動明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [80] 浅草寺社書上 甲五』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.57』
江戸大塚護持院末 浅草新寺町
神勝山成就院
拙寺建立年代相知不申候
開山観宥、寛永五年6月15日遷化
本堂
本尊 三尊弥陀如来木立像
弘法大師木座像 大師巡拝江戸八十八ヵ所ノ内四十四番札所
興教大師木座像
三宝荒神木立像
大日如来木座像
観音堂
百体観音 弘法大師
石地蔵堂
開山乗誉源印寛永●(1624-1644年)起立 もと矢の倉に阿り万治(1658-1661年)の比当所へ移る(江戸志)

「成就院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
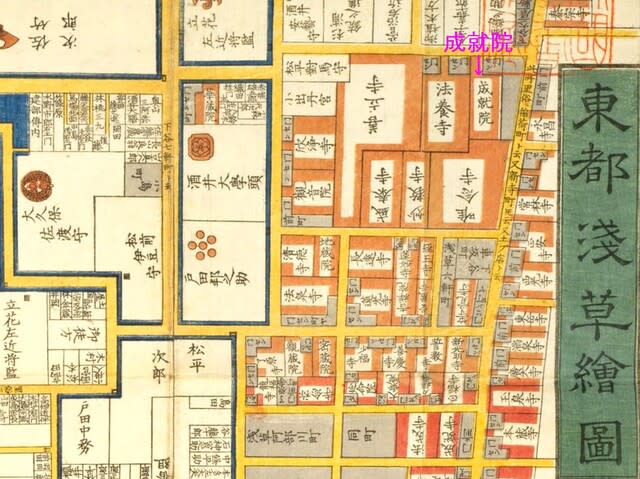
出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ銀座線「田原町」駅徒歩約5分。
御府内霊場札所が集中する元浅草・寿エリアの一画にあります。
都道463号浅草通り「元浅草四丁目」交差点から孫三通りを南に入ってすぐ。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 院号札
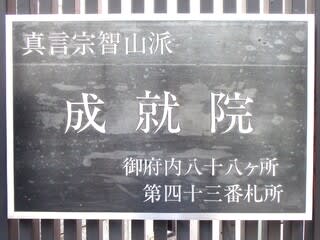

【写真 上(左)】 札所板-1
【写真 下(右)】 札所板-2
孫三通りに面して門柱。
門からだと民家風の事務所が目立ちますが、門柱の院号札と、本堂が一部見えるのでそれとわかります。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 本堂
本堂は2層の近代建築で、おそらく2階に鐘楼を置いていますが、こういうつくりの名称を筆者は知りません。
向拝柱はありませんが、見上げに山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 百観音
本堂向かって左手に百観音の尊像があり、背面には百観音の由来が記されています。
「当成就院は、古来通称百観音と云われてまいりました。百観音とは、西国三十三番、坂東三十三番、秩父三十四番観音霊場の総称であります。江戸時代には当境内にその百体の観音菩薩像がまつられていたと伝えられています、佛教信者にとって一生に一度は百観音霊場の巡拝を念願するものとされています。この度、特信者の寄進に依りその旧観を偲んで聖観音の尊像を像立し(略)」とありました。
御朱印は寺務所で拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
【専用集印帳】
中央に「本尊大日如来」「弘法大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「江戸御府内八十八ヶ所第四十三番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
【汎用御朱印帳】
中央に金剛界大日如来のお種子「バーンク」(五点具足/荘厳体)と弘法大師のお種子「ユ」の揮毫、御寶印(蓮華座+火焔宝珠)はおそらく金剛界大日如来のお種子「バン」。
右上に「江戸御府内八十八ヶ所第四十三番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第44番 金剛山 蓮華院 顕性寺
(けんしょうじ)
新宿区須賀町13-5
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第44番、山の手三十三観音霊場第26番
ようやっと中間の第44番までやってきました。
引きつづき同様の構成で進めます。
第44番札所は四ッ谷須賀町の顕性寺です。
第44番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに顕性寺なので、御府内霊場開創時から一貫して四ッ谷の顕性寺であったとみられます。
下記史料、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
顕性寺は慶長十六年(1611年)牛込御門外に起立。開山は賢秀法印(承應二年(1653年)寂)と伝わります。
江戸城外濠堀削のため寺地が召上げられ、寛永十一年(1634年)現在地に移転しました。
享保十年(1725年)2月青山の出火で焼失し、文政年間(1818年~1831年)に至ってもなお仮堂のままであったと伝わります。
元文三年(1738年)中野寶仙寺末。
中興開山は秀延法印(宝暦二年(1752年)寂)とあるので、秀延法印のときに寶仙寺末となったとみられます。
当寺は寺宝「俎大師(まないただいし)」で知られています。
これは弘法大師空海が土佐國高岡郡に巡錫された折、家に泊めてくれたお礼としてまな板に「南無阿弥陀仏」の文字を彫られたものといいます。
(『ルートガイド』には「長さ1メートルあまりの俎板に彫った、阿弥陀如来像」とあります。)
幕末に至り、弘法大師が泊まられた家の末裔が江戸に移住しました。
江戸(東京)で生活苦に陥り、「俎大師」を抵当として料亭「鳥八十」より借財し、そのまま「鳥八十」の所有となりました。
「鳥八十」のあるじの娘は、後に落語家の五代目古今亭今輔を生みましたが、昭和9年の弘法大師千百年遠忌に際して「俎大師」を当山に寄進、当山の寺宝となったといいます。
(以上「Wikipedia」(出所:『四谷南寺町界隈』(新宿区立図書館))より。)
「俎大師」とのゆかりは昭和に入ってからであり、宝暦の御府内霊場開創時にはすでに御府内霊場札所の資格を備えていたものとみられます。
当山は山の手三十三ヶ所観音霊場第26番札所ですが、この霊場は享保年間末(1736年)までには開創と目されるので、宝暦年間(1751-1764年)開創とされる御府内霊場より古い可能性があります。
山の手三十三ヶ所観音霊場の真言宗の札所の多くは御府内霊場の札所となっています。
(護国寺、新長谷寺、早稲田観音寺、放生寺、千手院→南蔵院、光徳院、顕性寺、真成院)
あるいは、顕性寺もこの流れで御府内霊場札所となったのかもしれません。
→ 札所リスト(「ニッポンの霊場」様)
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
四十四番
四ッ谷南寺町
金剛山 蓮華院 顕性寺
中の村宝仙寺末 新義
本尊:大日如来 不動明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [45] 四谷寺社書上 四』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.128』
中野寶仙寺末 四谷南寺町
金剛山蓮華院顕性寺
開闢起立之儀 慶長十六年(1611年)元地●●牛込●門外
中興開山 秀延法印 宝暦二年(1752年)寂
元寶仙寺門徒 元文三年(1738年)同寺末寺と相成候
客殿
本尊 金剛界大日如来木坐像
弘法大師 興教大師
観音堂
観世音木坐像 右山之手二拾六番札所
稲荷社 秋葉 八幡宮 相殿
石地蔵立像
開山 賢秀法印 承應二年(1653年)寂
■ 『四谷区史 [本編]』(国立国会図書館)
金剛山蓮花院顯性寺は中野村寶仙寺末の新義真言宗で、四谷南寺町にある。慶長十六年(1611年)牛込門外に起立し、外濠掘鑿の用地として公収されて、寛永十一年(1634年)此地に移転した。其後享保十年(1725年)二月の青山の出火に類焼して、文政(1818-1830年)当時は本建築に至らなかつたことが其書上に見える。
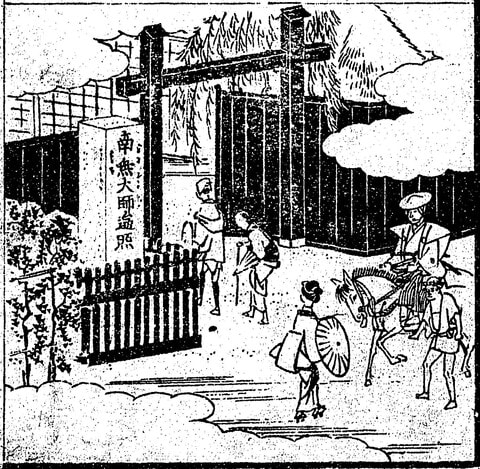
「顕性寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)
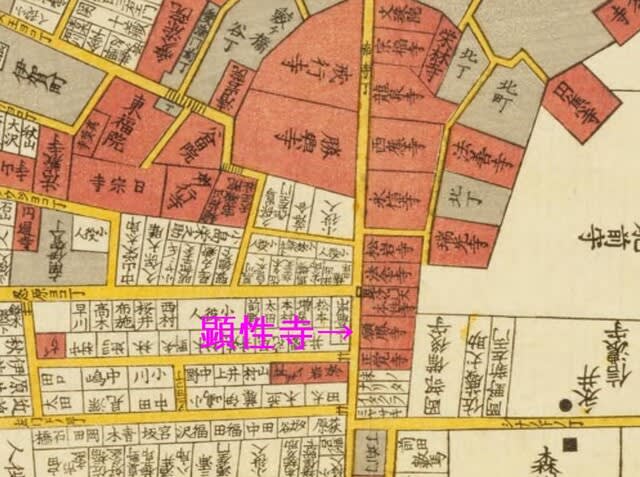
出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』四ツ谷絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」駅で徒歩約8分。
寺院が並ぶ四ッ谷寺町のまっただなかにあります。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 寺号標


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 本堂
山内入口に寺号標。右手に御府内霊場の札所標。
こぢんまりとした山内で、すぐ奥に本堂がみえます。
本堂は近代建築の2層。
向拝は2階で右手奥の階段でアプローチ。
向拝見上げには山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
『ルートガイド』によると本堂には御本尊・大日如来と俎大師が奉安されているそうです。
本堂は1階庫裡にて拝受できますが、筆者参拝時は2回ご不在があったので、事前TELがベターかもしれません。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

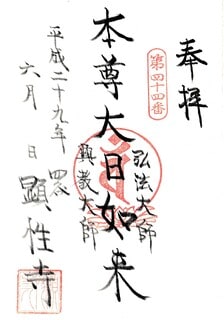
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊大日如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+宝珠)。
右上に「第四十四番」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第45番 廣幡山 隆源寺 観蔵院
(かんぞういん)
台東区元浅草3-18-5
真言宗智山派
御本尊:如意輪観世音菩薩
札所本尊:如意輪観世音菩薩
司元別当:
他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第83番、弘法大師二十一ヶ寺第13番
第45番札所は元浅草の観蔵院です。
第45番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに蔵前の雄徳山 神光寺 大護院なので、江戸期の御府内霊場第45番は蔵前の大護院であったとみられます。
『御府内八十八ケ所道しるべ』の札所異動表に第45番は大護院改め観蔵院とあるので、おそらく明治初期の神仏分離の際に札所異動があったとみられます。
まずは観蔵院について、下記史料、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
観蔵院は慶長十六年(1611年)澄(証)圓法印が開山となり中野屋鋪に創建、正保元年(1645年)現在地の元浅草に移転したと伝わります。
江戸大塚護国寺末の新義真言宗寺院です。
※『寺社書上』『御府内寺社備考』ともに長文の「舊記之写」を載せていますが、いずれも達筆すぎて筆者には解読不能につき、ここまでしかわかりません。
つぎに大護院について、藏前神社公式Web、下記史料などから縁起・沿革を追ってみます。
大護院の前身とみられる文殊院は蔵前にあって、高野山行人派觸頭の住院だったといいます。
『御府内八十八ケ所道しるべ』『江戸砂子温故名蹟誌』『江戸名所図会』ともに、もとは文殊院と号す高野山行人流の寺院で、行人派騒動の後、元禄五年(1692年)のころ石清水八幡宮を勧請された旨が記されています。
「行人派騒動」は、「元禄高野騒動」をさすと思われます。
「元禄高野騒動」とは寛永十五年(1638年)頃に端を発して50年ほどもつづき、元禄五年(1692年)幕府の裁定により決着した高野山の学侶方と行人方の争いです。
学侶方と行人方については、『元禄高野騒動と『高野春秋編年輯録』』(村上弘子氏・PDF)に、以下のとおり詳しくまとめられています。
「近世の高野山は、学侶方・行人方・聖方の「高野三方」と呼ばれる三つの組織から成り立っていた。学侶方とは法論談義や修法観念に専念する僧侶たちで、衆徒とも呼ばれる。青巌寺が頭寺院(略)行人方は興山寺を頭寺院とし、諸堂の管理や供花・給仕などの雑用に従事しており、堂衆・承仕とも呼ばれる(略)聖方は、弘法大師の入定信仰や高野山浄土信仰などを廻国唱導し(略)勧進活動を行なっていた中世の高野聖と呼ばれる僧たちが前身とされている。聖方頭寺院である大徳院は徳川氏と師檀関係を結んでおり、東照宮と二代将軍秀忠の台徳院御霊屋を祀っていた。」
行人方僧侶が堂上灌頂を受けることについて山内が紛糾し、江戸幕府も巻き込んで50年以上も争いがつづきました。
最終的には元禄五年(1692年)幕府の裁定により学侶方が勝利し、行人方の僧侶は600名以上も九州や隠岐に配流となり、行人方の多くの子院も取りつぶしとなりました。
この裁定について、『徳川実紀』(元禄五年九月四日条)は「こたび高野の事。査検のうへ仰下されし御旨もありしに。猶とかく愁訴やまず。いとひが事なれば。厳科にも處せらるべけれど。釋徒たるをもて助命せしめ山中を追放し。紀伊国の中にさしをき(略)増福院清雅はじめ八十二人は大隅国の島(略)八十人は隠岐国に遠流せしめ」と記しています。
高野山の内部機構の内紛にも係わらず、幕府は「厳科にも處せらるべけれ」とすこぶる強い姿勢でのぞみ、50年来の騒動に決着をつけたことがわかります。
「元禄高野騒動」の決着は元禄五年(1692年)9月、5代将軍綱吉公による山城國石清水八幡宮の勧請が元禄六年(1693年)8月5日(藏前神社公式Web)ですから史料類の時系列と符合します。
『御府内八十八ケ所道しるべ』の「昔ハ文殊院の八幡と称し高野山行人流の僧職ありしか 故あつて其地を改メられ石清水正八幡宮を勧請せり」の「故あつて」とは「元禄高野騒動」を示すものと思われます。
ここで気になったのは、御府内霊場札所と「高野三方」との関係です。
上記のとおり、近世の高野山は学侶方・行人方・聖方の「高野三方」と呼ばれる三つの組織から成り立っていました。
・学侶方 - 頭寺院は青巌寺、江戸の拠点は高輪の学侶方在番所
・行人方 - 頭寺院は興山寺、江戸の拠点は白金の高野山在番所行人方触頭
・聖方 - 頭寺院は(高野山)大徳院、江戸の拠点は高野山金剛峰寺諸国末寺総触頭(両国の大徳院)
これをもとに整理すると、
・学侶方 - 芝二本榎の学侶方在番所 → 高野山東京別院(第1番札所)
・行人方 - 白金の高野山在番所行人方触頭 → 文珠寺(第88番札所)
・聖方 - 高野山金剛峰寺諸国末寺総触頭 → 両国の大徳院(第50番札所)
となり、「高野三方」の江戸の拠点がそれぞれ御府内霊場の重要な札番を担っていたことになります。
御府内霊場折り返しの第45番・大護院(旧文珠寺?)が行人方触頭系寺院の系譜を曳くとなると、「高野三方」の関係からなんらかの意味合いがあったのかもしれません。
話が長くなりました。
ともあれ、文殊院跡地には元禄六年(1693年)8月5日5代将軍綱吉公が山城國男山の石清水八幡宮を勧請し、石清水正八幡宮と号しました。
なお、『御府内八十八ケ所道しるべ』には「昔ハ文殊院の八幡と称し」とあるので、綱吉公による石清水八幡宮勧請以前に八幡神の御鎮座があったのかもしれません。
ここからは主に藏前神社公式Webを参考に書き進めます。
上記のとおり、蔵前の石清水八幡宮は5代将軍綱吉公が元禄六年(1693年)に山城國男山の石清水八幡宮から勧請、御鎮座されました。
爾来、江戸城鬼門除守護神、徳川将軍家祈願所として篤く尊崇せられました。
藏前神社公式Webには以下のとおり記載があります。
「文政年間(1818-1830年)の『御府内備考続編』ならびに『寺社書上』には次のように記されています。『石清水八幡宮。御朱印社領200石。当社、石清水八幡宮境内、拝領の儀は 元禄6年5月27日、高野山興山寺上り屋敷拝領つかまつり、同年8月、八幡宮社頭建立の節、御金子300両拝領つかまつり、諸堂建立つかまつり候(略)」
「高野山興山寺上り屋敷」は旧文珠寺とみられ、文珠寺跡地が石清水八幡宮となったことを示しています。
享保十七年(1732年)類焼し、替地として浅草三嶋町に御遷りのところ、延享元年(1744年)寺社御奉行大岡越前守忠相が「三嶋町は御祈願所に不相応」とし、上意を得て蔵前の元地に還幸されました。
藏前神社公式Webには「江戸の北極星信仰」として、帯広市の真宗大谷派「順進寺」坂谷徹念住職による説が紹介されています。
要旨は以下のとおりです。
・北極星と北斗七星は古来より信仰の対象となり、仏教や神道にもとり入れられた。
・江戸の都市計画にも北極星、北斗七星の力が重用され、単に鬼門に神社仏閣を建立するだけでなく、神社仏閣の配置が北斗七星の形状となるように計画が練られた。
・江戸の都市計画をリードした天海は天台僧であり、神社だけで北斗七星を構成したとするには無理がある。
・北斗七星形成候補として考えられる朱印地30石以上の神社は上野東照宮、日枝神社、根津神社、藏前神社、氷川神社、愛宕神社、神田明神、白山神社の8社。
・うち根津神社は家宣公屋敷地に御遷座、白山神社は綱吉公の屋敷普請のため遷宮、氷川神社の御遷座は吉宗公の代で、江戸の都市計画(鬼門封じ)の色合いは薄く対象外とした。
・愛宕神社は防火・防災上極めて重要な神社、上野東照宮、日枝神社、石清水八幡宮(藏前神社)、神田明神はすべて江戸の守護神、祈願所として大切な神社であった。
・一方、朱印地が500石以上の大寺は寛永寺、増上寺、護国寺、浅草寺の4箇寺。
・増上寺は徳川家の菩提寺であり、寛永寺、護国寺、浅草寺はいずれも幕府の祈願寺として極めて大事な寺院であった。
・江戸の都市計画上の重要人物に、家光公側室で綱吉公生母の桂昌院がいる。
・延宝八年(1680年)5月実子綱吉公の将軍就任後ほどなく、桂昌院は綱吉公を動かし護国寺、藏前神社を創建して江戸守護のための北極星、北斗七星を完成させた。
・坂谷住職は以上から、増上寺、愛宕神社、日枝神社、神田明神、石清水八幡宮(藏前神社)、浅草寺、寛永寺(上野東照宮)が北斗七星、護国寺が北極星にあたると考えられた。
以上の説によると、元禄六年(1693年)8月5日、5代将軍綱吉公が文殊院跡地にみずから山城國男山の石清水八幡宮を勧請したことが符合し、また、享保十七年(1732年)の類焼で浅草三嶋町に御遷座の石清水八幡宮を、延享元年(1744年)寺社御奉行大岡越前守忠相が、「三嶋町は御祈願所に不相応」とし、上意を得て蔵前の元地に還幸された理由としても納得できます。
藏前神社公式Webにはさらに以下のとおりあります。
「当時は神仏習合思想に基づいて、全国の主要な神社には付属して別当寺が建立されていました。そして、当社石清水八幡宮の別当寺としては、雄徳山大護院(オトコヤマダイゴイン=新義真言宗)が営まれ、江戸の「切絵図」にも見られます。」
神社の公式Webで元別当が紹介される例は希とみられますが、こちらでは明記され、大護院の存在の大きさが伺えます。
石清水八幡宮は「藏前八幡」「東石清水宮」とも称され、崇敬者はなはだ多く関東の名社のひとつに数えられました。
天保十二年(1841年)には日本橋の「成田不動」(成田山御旅宿=ナリタサンオタビ)が、幕府の方針に基づき当社境内に遷されました。
『御府内八十八ケ所道しるべ』には「成田不動明王御旅所 江の嶋弁天御旅所 伊勢朝熊虚空蔵御旅所 御嶽山あり」とあり、石清水八幡宮(別当大護院)が神仏習合の一大拠点であったことが伺えます。
明治初頭の「神仏分離令」により別当・雄徳山大護院は廃寺(廃絶)となり、成田不動は明治2年深川に遷され、大施餓鬼塔も同3年練馬の東高野山に移されました。(藏前神社公式Web)
成田不動尊の江戸出開帳のほとんどは深川永代寺(富岡八幡宮)で催され、江戸の成田不動尊信仰の中心だったイメージがあります。
しかし、「成田不動信仰と市川團十郎」抄録(佛教大学大学院紀要)には、「元禄以降、江戸の成田不動信仰の拠点であった『成田山御旅宿』の経営にかかわっていた講中(略)」とあり、ふだんは日本橋の「成田山御旅宿」が江戸の成田不動信仰の拠点であったことを示唆しています。
この日本橋の「成田山御旅宿」が天保十二年(1841年)に蔵前の石清水八幡宮(別当大護院)に遷られ、その「成田不動は明治2年(1869年)深川に遷され」とあるので、1841年から1869年までの28年間は別当大護院が江戸の成田不動尊信仰の中心となった可能性があります。
話が飛んでばかりですみませぬ。
石清水八幡宮は明治6年8月郷社に列格、一時期「石清水神社」と改称するも復号し、昭和26年3月に社号を「藏前神社」と改めています。
なので戦前までの史料には「藏前神社」という神社は記載されていません。
大護院は「御室御所直院家」という真言宗仁和寺系の名刹なので、大護院廃絶後の御府内霊場札所は御室派系寺院が承継しそうですが、実際には智山派の観蔵院(元浅草)が承継しています。
観蔵院は荒川辺八十八ヶ所霊場第83番札所で、あるいは弘法大師霊場札所寺院ということで定められたのかも。
荒川辺八十八ヶ所霊場は天保九年(1838年)以前の開創とされる弘法大師霊場で、根岸・世尊寺から打ち始め、荒川、日暮里、尾久、船堀、豊島、江北、本木、千住、綾瀬、亀有、墨田、向島、亀戸、元浅草と回って根岸・千手院で結願となります。
→ 札所リスト(「ニッポンの霊場」様)
豊島八十八ヶ所霊場、荒綾八十八ヶ所霊場との札所重複は少なくないですが、御府内霊場との重複は亀戸東覚寺(第73番)、元浅草延命院(第51番)、成増青蓮寺(第19番)と観蔵院の4つしかありません。
しかし、下町の弘法大師霊場のうち蔵前・浅草辺に札所をもつのは荒川辺八十八ヶ所霊場だけなので、蔵前に近い元浅草の札所から選ばれたのかもしれません。
御室派系(大護院)から智山派系(観蔵院)への札所承継は、あるいは大護院が智山派系の成田不動尊の御旅所であったという縁によるものかもしれません。
-------------------------
【史料】
【観蔵院関連】
■ 『寺社書上 [80] 浅草寺社書上 甲五』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.58』
江戸大塚護国寺末 浅草新寺町
廣幡山隆源寺観蔵院
起立之年代舊記に無御座候得共 往古慶長十六年(1611年) 中野屋鋪●拝領仕罷●候処 御用地ニ付所替候 仰付正保元年(1645年)中当所に引移候由申伝候
開山 澄圓法印 寛永十年(1633年)入寂
本堂
本尊 如意輪観音坐像木佛
●● 弘法大師 興教大師
護摩堂
愛染明木像王 弘法大師作
※『寺社書上』『御府内寺社備考』ともに舊記之写を載せていますが、いずれも達筆すぎて筆者には解読不能です。
【大護院関連】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
四十五番
浅草御蔵前八幡 門前町あり
雄徳山 神光寺 大護院
御室御所直院家 新義
本尊:愛染明王 弘法大師
本社:石清水八幡宮
御本丸御祈願所
石清水正八幡宮 大倉前にあり
元禄五年(1692年)台命によって石清水正八幡宮勧請せり
昔ハ文殊院の八幡と称し高野山行人流の僧職ありしか
故あつて其地を改メられ石清水正八幡宮を勧請せり
別当大護院と号雄徳山と云
開山幸沼法印なり
護摩堂本尊ハ五大明王にして運慶作なり
成田不動明王御旅所江の嶋弁天御旅所
伊勢朝熊虚空蔵御旅所御嶽山あり
■ 『江戸砂子温故名蹟誌 6巻 [2]』(国立国会図書館)
八幡宮 御蔵前 社領二百石 別當雄徳山神光寺大護院 眞言
これを文殊院といふハ 以前文殊院といひて高野山行人派の觸かしら住院す 行人派騒動ありて後 元禄五年(1692年)のころ石清水八幡宮をうつさせられたり
■ 『江戸名所図会 7巻 [16]』(国立国会図書館)
八幡宮
御蔵前 社領二百石
雄徳山神光寺大護院 真言
これを文殊院の八幡といふハ以前文殊院といひて高野山行人流の觸かしら住院す
行人派騒動ありて後 元禄五年(1692年)のころ石清水八幡宮をうつさせられたり

「正覚寺 八幡宮」/原典:松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[16],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836].国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ銀座線「稲荷町」駅で徒歩約5分。
「稲荷町」は都内で育った人でもなかなか使わない駅ですが、御府内霊場札所密集エリアのアプローチになるので、御府内霊場巡拝時には重要な駅です。
都道463号浅草通り「松が谷一丁目」交差点から左右衛門橋通りを南に入り少し行った路地を左に回り込むとすぐにあります。


【写真 上(左)】 外観
【写真 下(右)】 院号札
路地にすぐ面して本堂があり、たたずまいは瀟洒な邸宅のようです。
確かベルを押して御朱印帳をお預けしてからの参拝でした。
本堂前左手に修行大師像、向かって右横には聖観世音菩薩の立像。
向拝上には真言宗智山派の宗紋・桔梗紋が染められた向拝幕を巡らし、見上げには豪快な筆致の山号扁額。
ここに来て俄然札所のイメージが高まります。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 札所幟
ご案内いただいた本堂内。
正面に御本尊の如意輪観世音菩薩坐像。
向かって右に胎蔵曼荼羅、左には金剛界曼荼羅が掲げられています。
御本尊まわりに愛染明王などの諸仏。
こちらの愛染明王は、大護院の御本尊であった愛染明王とのつながりも想起されますが、詳細不明です。
向かって右には弘法大師坐像、左には興教大師坐像が御座され、密寺らしい空間となっています。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
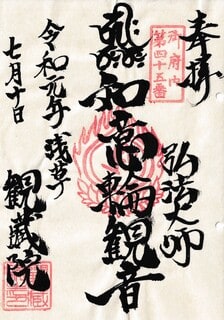
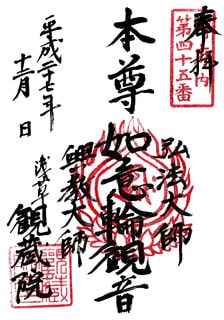
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に如意輪観世音菩薩のお種子「キリーク」と「如意輪観音」「弘法大師」の揮毫と「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内第四十五番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第46番 萬徳山 聖寶院 弥勒寺
(みろくじ)
墨田区立川1-4-13
真言宗豊山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第50番、御府内二十八不動霊場第20番、御府内十三仏霊場第6番(弥勒菩薩)、江戸十二薬師第6番
第46番は御府内霊場屈指の名刹です。
第46番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』で弥勒寺、江戸八十八ヶ所霊場では両国の大徳院(現御府内霊場・第50番札所)となっています。
よって、江戸時代に第50番札所の弥勒寺と第46番札所の大徳院が入れ替わった可能性があります。
その経緯は不明ですが、弥勒寺は御府内霊場開創時からの札所であったとみられます。
下記史料、すみだ観光サイト、現地掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
弥勒寺は、慶長十五年(1610年)宥鑁上人が小石川鷹匠町に創建(中興開山とも)、馬喰町上寺町、深川など幾度かの移転を経て元禄二年(1689年)本所に移転したと伝わります。
かつては京都醍醐寺三宝院末でしたが、のちに根来寺末となっています。
寺領百石の朱印状を拝領し、新義真言宗関東四箇寺のひとつとして触頭を勤めた名刹です。
触頭とは宗派内の寺院・僧侶を統括する寺院で、幕府との接触も多く江戸時代には極めて重要な役割を果たしました。
真言宗智山派総本山智積院の公式Webによると、「新義真言宗触頭」=「江戸四箇寺」で、発足当初は知足院・真福寺・円福寺・弥勒寺。
その後貞享四年(1687年)に知足院が将軍家の祈祷寺を理由に免除され、根生院が任じられています。
円福寺は明治2年に廃寺となっていますが、江戸時代には「江戸四箇寺」の寺院すべてが御府内霊場札所となっていました。
『御府内寺社備考』には、「元禄二年(1689年)賜此地 綱吉公命云彌勒根生二院者属小池房真福圓福二寺者属智積院住持亦各其山之僧可令居之云々 同年七月移寺院●本所造庫裡当」とあり、元禄二年(1689年)の本所移転時にはすでに「江戸四箇寺」に数えられていたことがわかります。
『新義真言宗触頭江戸四箇寺成立年次考』(宇高良哲氏/PDF)には「江戸四ヶ寺の成立年次であるが、従来の研究により元和五年以降同九年以前」とあり、智積院公式Webには「その後貞享四年(1687年)に知足院が将軍家の祈祷寺を理由に免除され、根生院が任じられています。」とあるので、元禄二年(1689年)に根生院が数えられている『御府内寺社備考』の記述と年次が符合します。
当初は弥勒菩薩を御本尊としたことから弥勒寺と号しましたが、後に薬師如来が御本尊となっています。
当山御本尊の薬師如来像は、徳川光圀公(1628-1701年)から寄進された尊像といいます。
この行基菩薩作と伝わるお薬師さまはもともと常陸国の真言宗寺院にあり、故あってこの寺の寺領を水戸光圀公が没収されたときにこの尊像を川(那珂川?)に流しました。
しかし不思議なことにこの尊像は下流に流されることなく、川上に向かって流されたといいます。
これを見た光圀公はこの尊像への尊崇を新たにし、川上に流れたことから「川上薬師」と呼ばれて以降人々の信仰を集めました。
光圀公はこの尊像を縁のあった弥勒寺に奉じ、以降当山の御本尊になったといいます。
弥勒寺の薬師如来は江戸十二薬師(十三薬師)第6番札所として知られていたようですが、その他の札所は概ね詳細不明のようです。
塔頭に法樹院、徳上院、正福院、寳珠院、正覺院、龍光院などがあり、多くの末寺を擁しました。
御府内霊場にも弥勒寺末の札所寺院がいくつかありました。
『御府内寺社備考』には、「権現様(徳川家康公) 台徳院様(2代将軍秀忠公) 大猷院様(3代将軍家光公) 右所三代之間御表御奥に御祈祷し●●献上仕御初穂等拝領仕候」とあり、徳川将軍家の祈祷所の役割を果たしていたことを示しています。
『御府内寺社備考』はまた、当山の大檀那が牧野備前守成貞であったことを記しています。
牧野成貞(1635-1712年)は三河牧野氏の流れで5代将軍綱吉公の側用人から下総関宿藩主。
三河牧野氏は東三河の土豪として松平氏(徳川氏)に仕え、江戸時代には門閥譜代として多くの大名・旗本家を輩出した名門です。
徳川光圀公とのゆかりといい、さすがに「触頭江戸四箇寺」にふさわしい沿革を伝えています。
山内には5代将軍綱吉公に鍼灸師として仕えた杉山和一(杉山検校)の墓所や鍼供養碑があります。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
四十六番
本所二ッ目林町
萬徳山 聖宝院 弥勒寺
院家長谷山方どくれいせ● 新義
本尊:薬師如来 弘法大師 興教大師
■ 『寺社書上 [88] 本所寺社書上 壱』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.75』
山城國醍醐三宝院末 本所二ッ目
萬徳山聖宝院弥勒寺
新義真言宗触頭
(以下抜粋)
開山宥鑁法印 聖寶院之住持也
初聖宝尊師作之不動尊幷行基作之彌勒菩薩以以為本尊故為院号
古ハ松梅山又松風山とも号
宥鑁後堀請武府拝領寺地於馬喰町建立院宇時蒙
鈞命為四箇寺職特是
慶長十五年(1610年)、御召ニ付江府●●寺地●仕 彌勒尊を本尊と●彌勒寺と号
触頭●
慶長十五年(1610年)鷹匠町に寺地を移し 元禄二年(1689年)●●拝領仕候在寺地東方に御●●
元和二年(1616年)鑁随醍醐山三寶院准三宮法務大僧正義演法流以為本寺
寛永十年(1689年)従水戸社務光明院移住以故水戸黄門君●遇
天和二年(1682年)罹災院宇為灰燼●是後転寺地 拝領深川俄造坊室
元禄二年(1689年)賜此地 綱吉公命云彌勒根生二院者属小池房真福圓福二寺もの属智積院住持亦各其山之僧可令居之云々 同年七月移寺院●本所造庫裡当
本堂
本尊 薬師如来木像 行基菩薩作
此尊像を●●常州筑波郡之内水戸殿御領内●る真言宗之寺(略)水戸黄門公右之寺を没収
し給ふとき本尊を谷川(那珂川とも)へ流し● 不思議なる●漲る●を川上へ流れし給ふ此奇特を以て黄門公より当寺八世(略)川上薬師●来と称
前立 薬師如来木像
日光月光菩薩
寺寶
常憲院様(5代将軍綱吉公)御画(筆) 鶴松之御画
不動尊画像 弘法大師五十二歳之時作画
千体不動尊画像
六臂辨財天像
弘法大師御影
鎮守八幡社
大日堂
本尊 大日如来 観音
権現様(徳川家康公) 台徳院様(2代将軍秀忠公) 大猷院様(3代将軍家光公)
右所三代之間御表御奥に御祈祷し●●献上仕御初穂等拝領仕候
■ 『江戸名所図絵 第4 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)
真言新義の触頭江戸四箇寺の一室なり。本尊は薬師如来、世に河上薬師と称せり。中興開山を、宥鑁上人と号す。総門の額に、彌勒寺と書せしは、朝鮮國雪月堂の筆跡なり。当寺舊柳原の地にありしを、天和二年(1682年)回禄の後、此地へ移されたり。毎月八日十二日を縁日として参詣多し。
■ 『東京名所図絵』(国立国会図書館)
萬徳山弥勒寺ハ天祖神社の北二丁余彌勒寺橋の北詰林町に在り 真言新義の触頭にして東京四ヶ寺の一なり 本尊ハ薬師如来なり 世に河上薬師と云ふ 中興開山ハ宥鑁上人なり 毎月八日十二日ハ縁日として参詣人多し

「弥勒寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』深川絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは都営新宿線・大江戸線「森下」駅で徒歩約5分。
住宅、オフィスビル、寺院が混在するエリアにひっそりとあります。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 門柱の寺号札


【写真 上(左)】 山内&本堂
【写真 下(右)】 杉山検校墓菩所
山内入口は門柱のみで、本堂もすぐそこに見えますが、どことなく風格を感じるのは触頭寺院の歴史でしょうか。
参道右手の観音聖像は、昭和20年3月10日の東京大空襲による犠牲者の冥福を祈る尊像です。この聖像のもとに多くの遺骨が収納されています。
「日本大百科全書(ニッポニカ)」によると2時間半の爆撃によって東京下町一帯は廃墟 (はいきょ)と化した。約2000トンの焼夷弾を装備した約300機のB-29の攻撃で下町エリアの40平方キロメートルが焼失、焼失家屋約27万戸、罹災者数は実に100万余人に達したといいます。
広くはない山内ということもあって、令和の今日でもなお戦禍の悲惨さが逼ってくるような感じがあります。
本堂は近代建築で、様式はよくわかりません。
向拝柱はなく、扉に置かれた真言宗豊山派の宗紋「輪違紋」がよく目立ちます。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 「筆供養」の碑
堂前向かって右手の「筆」と彫られた石碑は、「弥勒寺で書道の道場を開いていた昭和の書家、相沢春洋の命日にあたり、門下生がそれにちなんで使い古した毛筆に感謝を込めて供養する」「筆供養」の碑です。(すみだ経済新聞より)
本堂には表装をかけた千社札が掲げられていました。
御府内でも有数の名刹ゆえ、かつての堂宇には多くの千社札が貼られていたのでは。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 千社札
御朱印は本堂向かって左手奥の庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に薬師如来のお種子「バイ」と「薬師如来」の揮毫。別に左右に種子の揮毫がありますが、達筆すぎて読解できません。
中央の主印は三寶印。
右上に「御府内第四十六番」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-16)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ ノーサイド - 松任谷由実
■ thaw song - 中恵光城
■ LANI~HEAVENLY GARDEN~ - 杏里
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
冬の名曲10曲
寒くなってきたので、思いつくままにリストしてみました。
例によって女性ボーカル限定です。
メジャー曲は、カバーテイクをもってきました。
01. AYANE - 初雪 • HATSUYUKI (2022年)
02.ロッヂで待つクリスマス - Covered by ??? (1978年)
03.遠い街から - 今井美樹 (1992年)
04.サイレント・イヴ - Covered by ClariS (1991年)
05.フユラブ - Juliet (2009年)
06.ORION - Covered by 堀優衣 (2008年)
07.DEPARTURES - Covered by 華原朋美 (1996年)
08.雪の華 - Covered by 花たん(hanatan) (2003年)
09.メリクリ - Covered by 荒牧陽子 (2004年)
10.Over and Over - Every Little Thing (1999年)
-------------------------
■ シャ・ラ・ラ - サザンオールスターズ - 桑田 佳祐 & 原 由子 - (1980年)
ラストに初期サザンの名曲を入れてみました。
→ ■ 初期サザンとメガサザン(サザンオールスターズ、名曲の変遷)
例によって女性ボーカル限定です。
メジャー曲は、カバーテイクをもってきました。
01. AYANE - 初雪 • HATSUYUKI (2022年)
02.ロッヂで待つクリスマス - Covered by ??? (1978年)
03.遠い街から - 今井美樹 (1992年)
04.サイレント・イヴ - Covered by ClariS (1991年)
05.フユラブ - Juliet (2009年)
06.ORION - Covered by 堀優衣 (2008年)
07.DEPARTURES - Covered by 華原朋美 (1996年)
08.雪の華 - Covered by 花たん(hanatan) (2003年)
09.メリクリ - Covered by 荒牧陽子 (2004年)
10.Over and Over - Every Little Thing (1999年)
-------------------------
■ シャ・ラ・ラ - サザンオールスターズ - 桑田 佳祐 & 原 由子 - (1980年)
ラストに初期サザンの名曲を入れてみました。
→ ■ 初期サザンとメガサザン(サザンオールスターズ、名曲の変遷)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 2.目黒不動尊
写真を追加しました。
-------------------------
2023-11-18 UP
こちらからつづく
02.泰叡山 護國院 瀧泉寺〔目黒不動尊 / 江戸五色不動〕
目黒区下目黒3-20-26
天台宗
御本尊:不動明王(目黒不動尊)
札所:江戸五色不動(目黒不動尊)、関東三十六不動霊場第18番、江戸三十三観音札所第33番、山手七福神(恵比寿)、東京三十三所観世音霊場第3番、江都三十三観音霊場第33番、江戸三十三ヶ所弁財天霊場第22番、江戸・東京四十四閻魔参り第23番、弁財天百社参り第24番
境内掲示、公式Webの縁起、天台宗東京教区の公式Web、((一社)しながわ観光協会Web)、目黒区資料、『関東三十六不動霊場ガイドブック』などを参考に、縁起、変遷などをまとめてみます。
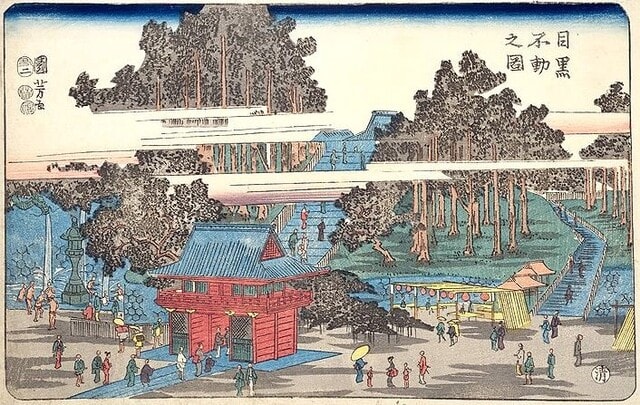
「目黒不動之図 / 源氏絵」 国芳
(国立国会図書館「錦絵で楽しむ江戸の名所」より利用規約にもとづき転載。)

「目黒不動堂 / 江戸名所図会. 七」
(国立国会図書館DCより利用規約にもとづき転載。)
大同三年(808年)、慈覚大師円仁が十五歳のとき、師の広智阿闍梨に伴われて故郷の下野国から比叡山の伝教大師最澄のもとに赴く途中、目黒の地に宿をとられました。
その夜のこと、夢の中に恐ろしい形相をした神人が現れ「我、この地に迹を垂れ、魔を伏し、国を鎮めんと思ふなり。来って我を渇仰せん者には、諸々の願ひを成就させん」と告げられました。
慈覚大師がその神人の尊容を像に刻して安置されたのが開創と伝わります。
承和五年(838年)、渡唐された大師が長安・青竜寺の不動明王を拝したところ、件の夢中の神人がまさにこの不動尊であると察せられ、御帰朝後の天安二年(858年)、像を安置した目黒の地に堂宇を建立されました。
堂宇の建立にあたり大師が法具の獨鈷を投じると、そこに霊泉が湧出し滝を落としました。
この滝は「獨鈷の瀧」と名づけられ、大師自ら「大聖不動明王心身安養呪願成就瀧泉長久」と棟牘に記されて、その由縁から「瀧泉寺」と号されたと伝わります。
貞観二年(860年)、清和天皇より「泰叡」の勅額を賜り「泰叡山」と号します。
弘治三年(1557年)堂塔の修理造営成ったものの、元和元年(1615年)火災により多くの伽藍を失いました。
このとき御本尊の不動明王はみずから猛火をなぎ払い、獨鈷の瀧の上に飛来して火災の難を逃れたと伝わります。
江戸時代の寛永年間(1624-1645年)、三代将軍家光公がこの地で鷹狩りを催した際、愛鷹が行方知れずになりました。
家光公みずから不動尊の前に額づき祈願を籠めると、愛鷹は本堂前の松(鷹居の松)に戻ってきたため家光公は不動尊の霊威を尊信、帰依しました。
寛永七年(1630年)、上野護国院の開祖・生順大僧正が当寺を管掌、堂宇再建を手掛けた際に家光公は寄進援助し、五十三棟にも及ぶ大伽藍の復興を成しました。
その壮大な伽藍は「目黒御殿」と称されるほどに華麗を極めたと伝わります。
承応三年(1654年)には御水尾天皇より「泰叡山」の勅額を、元禄六年(1693年)には御西天皇御宸筆の「不動明王」を拝戴して、開山以来、実に三度の勅額の下賜を受けています。
以降、徳川将軍家の保護もあって隆盛を極め、関東最古の不動霊場として、熊本の木原不動尊、千葉の成田不動尊と併せて「日本三大不動」のひとつに数えられます。
目黒は江戸御府内からほどよい距離の風光明媚の地(夕陽の紅葉で名高い行人坂上)で、目黒不動尊をはじめ蛸薬師と呼ばれる成就院や、弁財天霊場として知られる蟠龍寺もあったため江戸庶民の格好の参詣先となり、門前も市をなしてにぎわいました。
”江戸の三富”(当山、湯島天神、谷中感応寺)と呼ばれた名物の富くじも、目黒繁栄の一因といわれます。
明治に入っても諸人の尊崇篤く、西郷隆盛や東郷元帥などが祈願に訪れています。
西郷隆盛は主君島津斉彬公の当病平癒のために日参。
東郷元師は日本海海戦の勝利を立願し見事に成就したため、庶民の目黒不動尊信仰はますます隆昌を極めたといわれます。
なお、落語噺として有名な「目黒のさんま」は当然目黒の名物ではなく、江戸期には「目黒のたけのこ」と賞され、とくにたけのこ飯が名物だったようです。
~ 筍や 目黒の美人 ありやなし ~ 正岡子規
『江戸名所図会. 七』(国会図書館DC)には以下の記載があります。
「同所の西百歩あまり不動堂 泰叡山 龍泉寺と号す天台宗●●東叡山に属せし 開山ハ慈覚大師 中興慈海僧正なりと 本堂不動明王 慈覚大師作脇士ハ八大童子なり 本殿額泰叡山御西院御筆 楼門額泰叡山御水尾帝御筆 鳥井(ママ)額泰叡山日光御門主明王院宮御筆 経蔵 一代蔵経を安置本尊に釋迦阿難迦葉の像を置 八幡宮 早尾権現/祭神猿田彦大神或ハ素戔嗚尊ともいふ祭礼ハ五月十五日なり此堂社何れも本堂の左に並ぶ 恵比寿大黒祠 鐘楼 水神社 愛染明王 大行事権現/此地の地主神なり祭神高祖皇産霊尊なり五月十五日祭礼あり 石不動尊/何れも本堂の右にあり 稲荷祠 地蔵尊/掌善掌悪の二童子を置 聖観音 開山堂 聖徳太子 天照太神宮 本地大日如来/本堂の後峙●る山の腰を切割く安置を俗す奥の院と称す 吉祥天女祠 天満宮 鬼子母神 十羅刹女祠 虚空蔵堂 遮軍神祠 何れも本堂の後に並び建つ 結神祠 役小角/女坂の中程にあり銅像にして前鬼後鬼の像あり三佛堂/弥陀薬師釋迦等の三尊を安す 子安明神/鬼子母神あり 疱瘡神 粟島明神 石地蔵尊 秋葉権現 六所明神 荒神宮 何れも二(ママ)王門入て右の方にあり 辨財天祠/江島弁天の模なり 地蔵堂/堂内閻王脱衣婆等の像を安せり 観音堂/中尊ハ聖観音廻●●西國坂東秩父等の札所百番の観音を安置せり 勢至堂 稲荷祠 前不動/左右に十二天の像を安置す 何れも楼門の左の方にあり 楼門/左右に金剛密迹二王の像を置裏に使者犬の像を置り 獨鈷の瀧/(中略) 一年此滝水の涸たりしことありたる● 沙門某江島の弁天に祈請したてまつり再ひ元の如しとぞ故に今も年々当寺より江島の弁天へ衆僧をして参詣せしむる(中略) 鷹居の松/(中略) 」
明治23年刊の『東京名所図会』(国会図書館DC)には以下の記載があります。
「開山ハ慈覚大師なり 本尊不動明王ハ慈覚大師の作なり 本殿の額泰叡山は御西院天皇の御筆 楼門の額泰叡山ハ御水尾天皇の宸筆 鳥居の額泰叡山ハ日光御門主明王院宮の御筆なり 境内に神佛の堂社多くありて一々枚挙すべからぞ 獨鈷の瀧ハ常山の垢離場にして霊泉常に滔々と落下す 如何なる炎天干魃にも涸るヽ事なしと云ふ 往昔ハ三口に分れて湧出せしかど今ハニ流となれり 当寺ハ慈覚大師夢想に感得せし尊容を彫刻して露示の如く此地に安置せしなりとぞ 此地少しく都下を隔つと雖も諸人常に群参せり 殊に正五九の月にハ廿七廿八両日とも非常に賑へり 此門前五六町の間ハ左右酒店茶肆軒を連ねて参詣人の休憩所に充つ 殊に粟餅飴及び餅花等名物として之を商ふ家頗る多し 其繁昌推して知るべし」
参詣の土産として知られていたのが”粟餅”、”餅花”、”飴”でした。
「桐屋」の飴は人気だったらしく、『江戸名所図会』に「目黒飴」と題して挿絵が載せられています。

「目黒不動餅花 / 江戸自慢三十六興(書画五十三次) 絵師:広重, 豊国」
(錦絵で楽しむ江戸の名所(国会図書館DC)より利用規約にもとづき転載。)

「目黒飴 / 江戸名所図会. 七」
(国立国会図書館DCより利用規約にもとづき転載。)
公式Webでは、江戸五色不動につき以下のとおりとりあげています。引用します。
「江戸五色不動は、江戸時代には五眼不動といわれ、五方角(東・西・南・北・中央)を色で示すものです。その由来については諸説ありますが、各位置は江戸城(青)を中心として、それぞれ水戸街道(黄・最勝寺)、日光街道(黄・永久寺)、中山道(赤)、甲州街道(白)、東海道(黒)といった江戸府内を中心とした五街道沿い(又は近く)にあることから、徳川の時代に江戸城を守るために置かれたといわれています。」
************************
最寄り駅は「目黒」駅か東急線「不動前」駅ですが、どちらからも微妙に距離があります。
名勝・行人坂の往年の情景をしのぶには、目黒駅から歩いた方がいいかもしれません。
目黒駅から目黒川に向けて行人坂をくだっていきます。
江戸時代、紅葉夕景の名所「夕日の岡」として広く知られた急坂です。
江戸名所図会. 七(国会図書館DC)には「明王院の後の方西に向へる岡といへり古へハ楓樹数株梢を交へ晩秋の頃ハ紅葉夕日に映し奇観なりしと知らされと今ハ楓樹少く只名のみを存せり」とあります。

「夕日岡 行人坂 / 江戸名所図会. 七」
(国立国会図書館DCより利用規約にもとづき転載。)
目黒の高台から西側に下るこの坂は富士眺望の名所でもあり、数々の浮世絵が遺されています。
現・ホリプロのビルのあたりに富士の眺望で名を馳せた「富士見茶屋」があり、錦絵にも遺されています。


【写真 上(左)】 行人坂下り口
【写真 下(右)】 富士見茶屋跡地

「行人坂 / 江戸名勝図会 絵師:広重」
(錦絵で楽しむ江戸の名所(国会図書館DC)より利用規約にもとづき転載。)
※ 右手の冠木門が富士見茶屋

「目黒行人阪之図 / 広重東都坂尽 絵師:広重」
(錦絵で楽しむ江戸の名所(国会図書館DC)より利用規約にもとづき転載。)
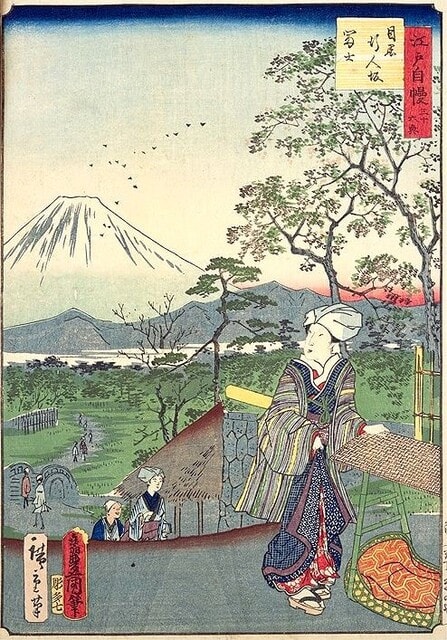
「目黒行人坂富士 / 江戸自慢三十六興 絵師:広重, 豊国」
(錦絵で楽しむ江戸の名所(国会図書館DC)より利用規約にもとづき転載。)
作家・杉本苑子先生の『東京の中の江戸名所図会』/文春文庫には、江戸時代のこのあたりの情景が叙情ゆたかに描写されています。引用します。
「もう、ここまでくると、いちめんの田園風景・・・・・・。春は梅が咲き桃が咲き、菜の花畑れんげ畑に野末がかすんで、ひばりの囀りが降るほどになるし、秋は百姓家の背戸に色づく柿の実、稲の垂れ穂に鳴子がひびいて、ごみごみした下町から抜け出してきた人々の耳目をたのしませてくれた。」


【写真 上(左)】 行人坂
【写真 下(右)】 行人坂の案内板


【写真 上(左)】 手前が目黒川架橋供養勢至菩薩、奥が大圓寺
【写真 下(右)】 大圓寺
坂の途中、左手に松林山 大圓寺。
出羽修験系の開創とされるこの天台宗寺院は、明和九年(1772年)の大火(行人坂火事)とかかわりを持ち、幕末に薩摩島津氏の菩提寺として再興されました。
山手七福神の大黒天で、数種の御朱印を授与されています。
さらに下ると雅叙園。
かつてここには松樹山 明王院という天台宗寺院がありました。
『江戸名所図会. 七』(国会図書館DC)には以下の記載があります。
「坂の側にあり天台宗●●東叡山に属す 本尊阿弥陀如来脇士観音勢至を安置せり 開山を栄運法師といふ常念佛の道場●●頗る殊勝なり 毎月四日報恩念佛百万遍修行あり 此常念佛ハ西運といふ沙門の発願なりとぞ」
雅叙園内のお七の井戸あたりが明王院跡とされ、八百屋お七の恋人吉三郎が出家して入り百万遍修行を経て西運上人となった寺と伝わります。
八百屋お七は、浮世草子『好色五人女』(貞享三年(1686年)刊)、浄瑠璃、歌舞伎などで広くとりあげられて江戸庶民の知名度が高く、また弁財天百社参り第25番の札所でもあったので、江戸期には参詣者を集めたとみられます。
明和九年(1772年)、行人坂火事で焼失した大圓寺は嘉永元年(1848年)まで再建を許されなかったので、その間はとくに行人坂と明王院の結びつきが強まったかもしれません。
明王院は明治13年(1880年)頃廃され、大圓寺に統合されました。
雅叙園先の太鼓橋で目黒川を渡ります。
雁歯橋とも呼ばれたこの橋も名所で、『江戸名所図会. 七』(国会図書館DC)には「同所坂下の小川に架せ●/目黒川といへり 桂を用ひて両岸より石を畳の如くして橋とす故に横面より是を望めハ太鼓の胴に彷彿せり故(略)」と記されています。
太鼓橋は1700年代初頭に木喰上人が造り始め(八百屋お七の恋人吉三郎が出家した西運上人とも)、後に江戸八丁堀の商人達が資材を出し合って宝暦十四年(1764年)から6年をかけて完成した江戸ではめずらしい太鼓状の石橋です。
初代の石橋は大正9年(1920年)の豪雨で崩壊し、当時の石材は大圓寺の境内に置かれています。
太鼓橋のシンボルツリーは椎の木だったようで、↓ の広重の「目黒太鼓橋夕日の岡」にも描かれ、目黒区の木に指定されています。

「太鼓橋 / 江戸名所図会. 七」
(国立国会図書館DCより利用規約にもとづき転載。)

「目黒太鼓橋夕日の岡 / 名所江戸百景 絵師:広重」
(錦絵で楽しむ江戸の名所(国会図書館DC)より利用規約にもとづき転載。)


【写真 上(左)】 行人坂上り口
【写真 下(右)】 太鼓橋
山手通りを越えると五百羅漢寺。羅漢会館の裏手が目黒不動尊への近道です。
五百羅漢寺でも数種の御朱印を授与されています。


【写真 上(左)】 五百羅漢寺
【写真 下(右)】 参道入口
東急目黒線「不動前」駅からのアプローチでも、臥龍山 安養院や不老山 成就院(蛸薬師)などの御朱印授与寺があります。(安養院の現在の授与は不明)
こちらは商店街づたいで、門前街としての風情はこちらの方があると思います。
----------------------------------------

それでは見どころ満載の山内に参ります。(→ 境内案内)
仁王門の門前に伏見稲荷社と芝居でおなじみの白井権八・小紫の比翼塚。
明暦元年(1655年)頃に生まれ波乱の生涯をおくった鳥取藩士平井(白井)権八は、歌舞伎『浮世柄比翼稲妻』、講談、浄瑠璃などでとりあげられ、新吉原の三浦屋の遊女・小紫との恋物語は、つとに知られています。
また、浮世絵見立て『役者見立 東海道五十三駅』(『役者東海道』)初版には「川崎駅 白井権八」(五代目岩井半四朗)が登場、こちらでも名を広めたとされます。
比翼塚とは相思相愛の男女を弔う塚で、こちらの比翼塚は白井権八・小紫の塚です。
目黒不動尊のそばに普化宗の東昌寺というお寺があり、権八は一時東昌寺に身を寄せたとされます。
東昌寺は『江戸名所図会. 七』(国会図書館DC)には「虚無僧寺」として記されていますが、明治初期に廃寺となり、比翼塚は東昌寺から当地に移されたそうです。
行人坂の明王院、太鼓橋、そして比翼塚など、歌舞伎、浄瑠璃、講談でなじみふかい人物ゆかりの名所があることも、目黒が行楽地として人気を集めた一因かもしれません。


【写真 上(左)】 伏見稲荷社
【写真 下(右)】 比翼塚


【写真 上(左)】 仁王門
【写真 下(右)】 仁王門と寺号標
仁王門の前に「目黒不動尊 瀧泉寺」の寺号標と一対の狛犬。
わたしのまわりにも、お寺と神社の区別がつかない人がけっこういたりします。
鳥居の有無、墓地の有無もありますが、やはり名称(●●寺、●●神社)で区別している人が多いようです。
●●寺、●●神社ならば問題ないですが、●●宮、●●尊となると?マークがついてくるようです。
こちらには鳥居も狛犬もあるし、「目黒不動尊」のみではお寺か神社かわからない人もいるのでは。
その点でこの「瀧泉寺」の寺号標は役立っているかもしれません。


【写真 上(左)】 仁王門扁額
【写真 下(右)】 参道
仁王門は三間一戸、瓦葺八脚の楼門で、二層中央に「泰叡山」の扁額を掲げ、さすがに名刹の風格があります。
左右に阿吽の仁王尊像、階上には韋駄天が祀られているそうです。


【写真 上(左)】 手水舎
【写真 下(右)】 山内
仁王門をくぐって右手に大ぶりな手水舎で、ここから山内が一望できます。
都内有数の名刹だけあって、さすがに広大な山内を構えます。


【写真 上(左)】 弁天堂(三福神)入口
【写真 下(右)】 金明湧水
仁王門から左手時計まわりにいくと、朱塗りの明神鳥居。そのよこの手水は金明湧水です。
この金明湧水のまわりは色濃く赤茶け、おそらく鉄分を含む湧水だと思います。
鳥居の先の三福神にお参りしてから、金明湧水で”福泉洗い”をするそうです。
これは、いわゆる”銭洗い弁天”を彷彿とさせますが、この一画は『江戸名所図会. 七』(国会図書館DC)で「辨財天祠/江島弁天の模なり」と記され、江戸三十三ヶ所弁財天霊場第22番、弁財天百社参り第24番の札所で、江戸期には弁天様の霊場としても知られたところではないでしょうか。


【写真 上(左)】 弁天堂(三福神)
【写真 下(右)】 恵比寿様
太鼓橋を渡って右手に折れると、正面が弁天堂(三福神)、向かって右手に豊川稲荷、左手に福珠稲荷大明神が御鎮座。
弁天堂はおそらく切妻造桟瓦葺。立派な降り棟を備えた整った堂宇で、向拝、水引虹梁まわりに木鼻、斗栱、蟇股、二軒の垂木を配しています。向拝正面は桟唐戸(閉扉)、見上げに「三福神」の扁額、左右に花灯窓を配しています。
桟唐戸の前には恵比寿様が鎮座され、こちらが「山手七福神」の一尊かと思います。(御前立かもしれぬ)
堂内の須弥壇上に奉られる「木造弁才天及び十五童子像」は目黒区の有形文化財(彫刻)に指定されています。
(→ 区資料)
制作年代は14世紀前半頃、南北朝時代と推測されています。
こちらは御開扉されることがあるようで、その際のWeb投稿写真によると、堂内には大黒天と七福神もお祀りされているようです。
単なる「弁天堂」ではないところが、瀧泉寺の信仰の複雑さを物語っています。
北向六地蔵尊、三界万霊塔と過ぎ、本堂の山裾に腰立不動尊、憂国の士北一輝の碑、作曲家本居長世の碑、勢至堂、青木昆陽(甘藷先生)碑、前不動堂、青龍大権現を祀る垢離堂と並び、本堂参道下左手が獨鈷の瀧です。


【写真 上(左)】 北向六地蔵尊
【写真 下(右)】 腰立不動尊
北向六地蔵尊は、切妻屋根銅板葺の立派な覆屋の下に御座。石造りの端正な立像です。
この前を通って左に向かうと、瀧泉寺墓地に至ります。
掲示によると「地蔵菩薩の浄土『迦羅陀山』は南方にあり、南を向いて地蔵菩薩を祈れば、直ちに浄土を発し我々のいる北に向かって救いに来てくださるので北を向いています。」とのこと。
腰立不動尊は、本堂の山裾にあり階段の参道です。
切妻造の堂宇の前に切妻の向拝を付設した複雑な構成。
向拝に掲げられた扁額には「山不動」とあり、御詠歌らしきものが記されていました。


【写真 上(左)】 勢至堂
【写真 下(右)】 前不動堂
勢至堂は「瀧泉寺勢至堂」として目黒区の有形文化財(建造物)に指定されています。
江戸時代中期の建築。瓦葺で一間の向拝を設けた整った意匠で、とくに絵様の一部は寛永中興期の瀧泉寺の面影を伝えるものとされます。
もとは前不動堂の手前にありましたが、昭和44年に現在地に移築されました。
青木昆陽(甘藷先生)碑は、当寺に青木昆陽の墓(国指定史跡)が
あることにちなむと思われ、毎年10月28日には先生の遺徳をしのんで甘藷祭りが催されています。
前不動堂は「滝泉寺前不動堂」として都の有形文化財(建造物)に指定されています。(→ 指定内容(都文化財情報DB))
江戸時代、将軍や大名の参拝持には庶民は本堂へは近づけず、その際の参詣者の便宜を図って建立したものとされます。
桁行三間梁間二間向拝一間、桟瓦葺の宝形造で、江戸時代中期の建築とされています。
堂内には木造不動明王三尊立像等を安置。
『江戸名所図会. 七』(国会図書館DC)には「前不動/左右に十二天の像を安置す」の記載があり、いまも十二天像が安置されているのかもしれません。
堂建立当時のものとされる扁額「前不動」は書家「佐玄龍書」の署名があり、附指定されています。
こちらは毎月28日の御縁日に内部公開とのこと。


【写真 上(左)】 前不動堂扁額
【写真 下(右)】 前不動堂下の湧水龍口
前不動堂の下には、湧水を吐き出す龍口があります。
目黒台と羅漢寺川(現在は暗渠化)を境するこのあたりは崖線となり、いわゆる「ハケの湧水」ポイントとみられます。
実際、こちら(「東京湧水巡礼」様)には「水を通しにくい東京層の地層が擁壁や石垣の裏側で露出し、その上から湧水が流れ出していると思われる。」とあります。(ただし、同記事によると、現在はすこし離れた浅井戸から送水しているらしい。)

「目黒不動尊(水垢離) / 東都名所 絵師:広重」
(錦絵で楽しむ江戸の名所(国会図書館DC)より利用規約にもとづき転載。)
本堂への参道階段左横に獨鈷の瀧。
慈覚大師が長安青竜寺の清滝を想起され法具の獨鈷を投じるとそこに霊泉が湧出し、滝をなしたので「獨鈷の瀧」と号します。
いまでも銅製の竜口から滝が注ぎ、不動講の水垢離場となっています。
数十日間の炎天旱魃が続いても涸れることがないそうです。
水垢離場上には石不動や講が奉安した倶利伽羅剣が奉られ、手前には水かけ不動明王が御座、垢離堂も配されて、不動霊場特有のパワスポ的雰囲気が感じられます。


【写真 上(左)】 獨鈷の瀧と水垢離場
【写真 下(右)】 参道方向から獨鈷の瀧


【写真 上(左)】 水かけ不動明王
【写真 下(右)】 水かけ不動明王の手水の龍
垢離堂の御本尊は青龍大権現で、5月の御縁日には青龍大権現大祭が営まれます。
青龍大権現は、法華経で説かれ仏法を守護するとされる八大竜王の一尊、娑伽羅(サーガラ)龍王の第三王女・善女(如)竜王と同一とされ、雨を司る尊格とされます。


【写真 上(左)】 倶利伽羅剣
【写真 下(右)】 垢離堂
善女龍王は、弘法大師が京の神泉苑で請雨修法を施された際に出現された尊格とされ、真言宗醍醐派総本山醍醐寺の守護女神ともされます。(清瀧大権現と呼称されます)
もともと西安の青龍寺の鎮守とされ、弘法大師が御帰朝ののち、京・高雄山麓の清滝に勧請されたと伝わります。
醍醐寺を開かれた聖宝の時代、昌泰三年(900年)頃に醍醐寺に御降臨。以来、醍醐寺の守護神として篤く祀られています。
『呪術宗教の世界』(速水 侑著)によると、聖宝の法系は平安中期の名僧、仁海に受け継がれ、ことに請雨の修法に優れて雨僧正とも称されました
仁海は東密(真言密教)小野流の祖とされ、小野流は独自の秘法として「請雨修法」を伝えました。
現在でも清瀧権現は真言宗寺院、とくに大寺で祀られ、川崎大師、成田山新勝寺、高尾山薬王院は、いずれもお祀りされています。
台密(天台密教)でも八大竜王を祀る例があり、目黒不動尊のそばの臥龍山 安養院(寝釈迦尊)には木食円空作八大龍王像が収蔵されています。
また、山梨県忍野村の天台宗寺院、忍草山 東円寺では稀少な娑伽羅龍王の御朱印を授与されています。


【写真 上(左)】 臥龍山 安養院の御朱印
【写真 下(右)】 忍草山 東円寺の娑伽羅龍王の御朱印
『江戸名所図会. 七』(国会図書館DC)には「獨鈷の瀧/一年此滝水の涸たりしことありたる● 沙門某江島の弁天に祈請したてまつり再ひ元の如しとぞ故に今も年々当寺より江島の弁天へ衆僧をして参詣せしむる」とあり、獨鈷の瀧は江島弁財天にゆかりがあったようです。


【写真 上(左)】 大本堂への参道(男坂)
【写真 下(右)】 鳥居工事中の男坂
水垢離場よこから大本堂への参道階段がはじまります。参道階段が男坂、右手の坂が女坂です。
階段右手には家光公ゆかりの「鷹居の松」(跡)、女坂途中には神変大菩薩(役ノ行者/役小角)のお堂があります。


【写真 上(左)】 女坂
【写真 下(右)】 神変大菩薩のお堂
堂内安置のお像は「銅造役の行者倚像」として目黒区の有形文化財(彫刻)に指定されています。(→ 区資料)
寛政八年(1796年)、太田駿河守藤原正義の作とされる銅造の倚像で、頭巾をかぶり、木の葉の肩衣をかけ、右手に錫杖、左手に巻子を持って腰掛けられています。
均整のとれた体躯、精緻な表現、品格ある表情などを備え、江戸時代の銅造彫刻の中でも優品とされています。
『江戸名所図会. 七』(国会図書館DC)には「役小角/女坂の中程にあり銅像にして前鬼後鬼の像あり」とあります。
前鬼・後鬼とは、元は生駒山地に住んでいた夫婦の鬼で、役小角は彼らを不動明王の秘法で捕縛して従者とされました。
堂内、役ノ行者の背後に安置されている二体のお像は、前鬼・後鬼かと思われます。


【写真 上(左)】 山王鳥居
【写真 下(右)】 鳥居の扁額
平成29年、男坂の参道途中に酉年本尊御開扉記念として石造の山王鳥居が建立されました。
現地掲示には「当山は往古より神仏習合の寺院でありました。江戸時代、天海大僧正が山王一実神道を創始され 当山にも山王鳥居が奉安。酉年復興いたしました。」とあります。
「護國院」の院号扁額が掲げられ、山王鳥居の合掌形と大本堂の千鳥破風が意匠的に呼応しています。


【写真 上(左)】 狛犬
【写真 下(右)】 手水舎の龍
階段を登り切ると大きな空間が広がります。
手前の狛犬はなかなかインパクトのある表情をしています。
手前左手に手水舎。水盤の龍がオーラを放っています。


【写真 上(左)】 大本堂
【写真 下(右)】 大本堂(斜めから)
正面の大本堂は石段の奥に朱塗りの堂々たる構え。
傾斜地ではないですが、舞台造(懸造)的な構成で、入母屋造本瓦葺正面千鳥破風とその先に設えた唐破風の下に三間の大がかりな向拝を張り出しています。
向拝水引虹梁は彩色で木鼻と中備えに蟇股。向拝中央に「目黒不動尊」の大提灯を掲げ、千鳥破風には猪ノ目懸魚を設えています。
慈覚大師の作と伝わる御本尊不動明王(目黒不動尊)が御座され、秘仏で十二年に一度、酉年のご開帳です。


【写真 上(左)】 大本堂向拝
【写真 下(右)】 意志不動尊
大本堂まわりには諸仏が御座します。
時計回りに辿ってみます。
大本堂向かって右手、玉垣に囲われて意志不動尊。
由緒は不明ですが、手前に眷属、制多迦童子と矜羯羅童子を配した石像の立像です。
そのお隣に微笑観世音菩薩。
穏やかな面差しの石造り立像の聖観世音菩薩です。


【写真 上(左)】 微笑観世音菩薩
【写真 下(右)】 愛染明王
大本堂向かって左手には愛染明王。
八角形の石敷の結界中央に、端正なおすがたの愛染明王の坐像露仏が御座。
こちらでは、良縁成就、縁結びを願掛けします。


【写真 上(左)】 子安延命地蔵尊
【写真 下(右)】 虚空蔵菩薩
大本堂右手には甘薯先生(青木昆陽)ゆかりと思われるサツマイモ畑があり、その前に子安延命地蔵尊。
左手に如意宝珠、右手に錫杖を持たれ、金色の輪光背を帯びて蓮華座に御座す坐像の金仏です。
サツマイモ畑の奥には虚空蔵菩薩。
頭上に宝冠を抱かれ蓮華座のうえに結跏趺坐される石仏で、あたらしいお像と思われます。
右手の石柱の上には牛の像が置かれています。
境内掲示の境内案内図には、諸仏諸堂に十二支が記されています。
大本堂には「うし、とら、うさぎ、たつ、へび、とり」、大本堂裏手の大日如来には「ひつじ、さる」、女坂下の観音堂には「ねずみ」、阿弥陀堂には「いぬ、いのしし」、勢至堂には「うま」。
このうち、こちらの虚空蔵菩薩に大本堂から「うし、とら」を分祀されたのでは?
なお、未確認ですが、この内容からすると大本堂に釈迦三尊(文殊菩薩/うさぎ、普賢菩薩/たつ、み(へび))が御座されているかもしれません。
子安延命地蔵尊の右には護衛不動尊。
石碑によると、開山一千二百年を記念して奉安された厄除けのお不動様で、儀軌に忠実なお像とみました。
お不動様に関することなので、少しく詳細に書いてみます。
『不動明王』(渡辺照宏著/朝日選書)によると、菅原道真の孫、淳祐が著した「不動尊道場観」のなかに不動尊の尊格や像容を記した「十九観」があり、うち第四~第十八の像容は次のとおりです。
この「十九観」は、のちの不動尊作像に大きな影響を与えたとみられています。
第四:童子形、第五:七莎髻(頭髪が七個の束になっていること)、第六:弁髪(左側に弁髪を垂らす)、第七:額の皺文、第八:一眼を閉じる(通常は左眼)、第九:下の犬歯が上唇を、上の犬歯が下唇を噛む、第十:その口を緘閉す、第十一:右手に剣を執る、第十二:左手に羂索を持つ、第十三:行人の残食を喫す、第十四:大盤石に座す、第十五:色醜くして青黒なり、第十六:奮迅忿怒す、第十七:遍身に迦楼羅炎、第十八:変じて倶利迦羅と成り
高々と迦楼羅焔を背負われ、盤石に御座すこの護衛不動尊は、「十九観」の特徴の多くを満たされています。


【写真 上(左)】 護衛不動尊
【写真 下(右)】 鐘楼
その右手に鐘楼、その奥は鬱蒼と木々が茂る八大童子の山。
八大童子の山の手前を奥に昇ると瀧泉寺墓地で、甘薯先生(青木昆陽)の墓所があります。


【写真 上(左)】 本堂裏手
【写真 下(右)】 大日如来
本堂裏手に回ると、覆屋の下に目黒区の有形文化財(彫刻)に指定されている銅造大日如来坐像。(→ 区資料)
現地掲示には「不動明王本地佛」とあります。
『江戸名所図会. 七』(国会図書館DC)には「本地大日如来/本堂の後峙●る山の腰を切割く安置を俗す奥の院と称す」とあります。
覆屋の屋根には二十八宿図が掲げられています。
これは天球を二十八のエリア(星宿)に分割した図で、東方青龍、北方玄武、西方白虎、南方朱雀の各七宿から成り立ち、風水思想と関連をもつという説があります。
なお、目黒不動尊は江戸城をはさんで上野寛永寺と鬼門・裏鬼門ラインのほぼ直線上に当たることから、目黒不動尊を江戸城の裏鬼門の鎮めとみる説もあります。
蓮華座に結跏趺座される高さ385㎝のお像は、宝髪、頭部、体躯など十数の部分に分けて鋳造して組み合わる”吹き寄せ”の技法で制作されています。
体躯に比べて頭部が大きいのがこの技法の特徴で、この像も同様とされます。
台座の刻銘によると、天和三年(1683年)、鋳物師横山半右衛門尉正重による造立。
法界定印を結ばれているので胎蔵(界)大日如来とみられ、回りを四天王(持国天・増長天・広目天・多聞天)が囲みます。
不動明王は大日如来の化身(教令輪身)とされますが、金剛界大日如来の化身とする説もあるようで、どうして胎蔵(界)大日如来が御座されるのかはわかりません。


【写真 上(左)】 覆屋屋根の二十八宿図
【写真 下(右)】 大行事権現
さらにその奥、神明鳥居を前に地主神・大行事権現が御鎮座です。
大行事権現は、大津坂本の日吉神社の山王二十一社の一社(中七社)で、山王一実神道とふかいかかわりをもつとされます。
『江戸名所図会. 七』(国会図書館DC)には「大行事権現/此地の地主神なり祭神高祖皇産霊尊なり」とあります。


【写真 上(左)】 本坊方面への案内
【写真 下(右)】 本坊への参道
男坂・女坂をくだって右手方向、阿弥陀堂への参道の左右に交通安全自動車祈祷殿、地蔵堂、精霊堂、観音堂、書院、阿弥陀堂(本坊・寺務所)と並びます。


【写真 上(左)】 地蔵堂
【写真 下(右)】 地蔵堂扁額


【写真 上(左)】 地蔵堂御内陣
【写真 下(右)】 精霊堂
地蔵堂は、入母屋造銅板葺平入りだと思いますが、すこし変わった感じの意匠です。
向拝柱はなく、見上げに「地蔵堂」の扁額を掲げています。
中央に地蔵菩薩坐像、向かって右に閻魔大王、左に奪衣婆が御座します。
毎月24日のお地蔵様ご縁日の午後の法要時には堂内に入れるようです。
瀧泉寺は江戸・東京四十四閻魔参り第23番の札所ですが、札所本尊はおそらくこちらの閻魔様とみられます。
地蔵堂と相対して交通安全祈願殿。御本尊は不動明王です。


【写真 上(左)】 交通安全祈願殿
【写真 下(右)】 幟
地蔵堂の横、精霊堂前には書道の大家西川春洞の碑。
精霊堂には地蔵菩薩坐像、六地蔵、閻魔大王、奪衣婆などが御座し、いずれも石仏です。


【写真 上(左)】 観音堂
【写真 下(右)】 観音堂扁額
観音堂は朱塗りの端正なお堂。
全容がよくわからないのですが、瓦葺で向拝側に千鳥破風を構えて流れ向拝。入母屋造妻入りかもしれません。
向拝柱や水引虹梁はなくシンプルな向拝で、見上げに「観音堂」の扁額。
向拝柱には観音霊場の札所板と御詠歌が掲げられています。
堂内には江戸三十三観音札所第33番結願の聖観世音菩薩のほか、千手観世音菩薩、十一面観世音菩薩も御座されるそうです。
第1番浅草浅草寺からはじまる江戸三十三観音は、府内各所を巡ってここ瀧泉寺で結願を迎えます。
現在の江戸三十三観音は、昭和51年(1976年)に改訂された「昭和新撰 江戸三十三観音霊場」ですが、江戸時代には享保二十年(1735年)版の『続江戸砂子』に収録された「江都三十三観音」(札所情報は→こちら(「日本を巡礼する」様))が、その前身として江戸庶民にさかんに廻られていたとみられます。
現在の江戸三十三観音とはことなる札所もありますが、発願の浅草寺と結願の瀧泉寺は変動なく、下町・浅草にはじまり、府内(都内)各所を巡って郊外の景勝地、目黒で結願するというコース設定に変わりはないということになります。
こちらの観音堂が江戸三十三観音札所第33番の結願所です。
東京三十三所観世音霊場第3番、江都三十三観音霊場第33番などの札所もおそらくこちらと思われます。


【写真 上(左)】 阿弥陀堂(本坊)-1
【写真 下(右)】 阿弥陀堂(本坊)-2
阿弥陀如来が御座す阿弥陀堂(本坊)の右手に御朱印授与所(寺務所)があります。
複数のメジャー霊場の札所を兼ね、ご親切で手慣れたご対応です。
〔江戸五色不動尊の御朱印〕
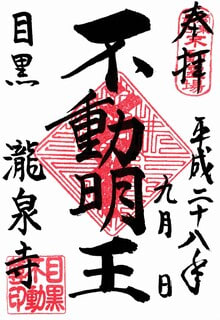
・御朱印尊格:不動明王 「関東最古不動霊場」の印判 直書(筆書)
〔関東三十六不動尊霊場第18番の御朱印/専用納経帳〕

・御朱印尊格:不動明王 関東三十六不動尊霊場第18番印判 書置(筆書)
〔関東三十六不動尊霊場第18番の御朱印/御朱印帳〕
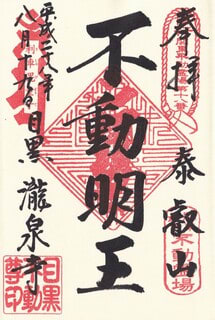
・御朱印尊格:不動明王 関東三十六不動尊霊場第18番印判 直書(筆書)
〔江戸三十三観音札所第33番の御朱印〕(通常御朱印)

・御朱印尊格:聖観世音 江戸三十三観音札所第33番印判 直書(筆書)
〔江戸三十三観音札所第33番の御朱印〕(結願御朱印)

・御朱印尊格:聖観世音 江戸三十三観音札所第33番印判 結願印 直書(筆書)
〔山手七福神(恵比寿神)の御朱印〕

・御朱印尊格:恵比寿神 山手七福神印判 直書(筆書)
(つづく) → こちら
-------------------------
2023-11-18 UP
こちらからつづく
02.泰叡山 護國院 瀧泉寺〔目黒不動尊 / 江戸五色不動〕
目黒区下目黒3-20-26
天台宗
御本尊:不動明王(目黒不動尊)
札所:江戸五色不動(目黒不動尊)、関東三十六不動霊場第18番、江戸三十三観音札所第33番、山手七福神(恵比寿)、東京三十三所観世音霊場第3番、江都三十三観音霊場第33番、江戸三十三ヶ所弁財天霊場第22番、江戸・東京四十四閻魔参り第23番、弁財天百社参り第24番
境内掲示、公式Webの縁起、天台宗東京教区の公式Web、((一社)しながわ観光協会Web)、目黒区資料、『関東三十六不動霊場ガイドブック』などを参考に、縁起、変遷などをまとめてみます。
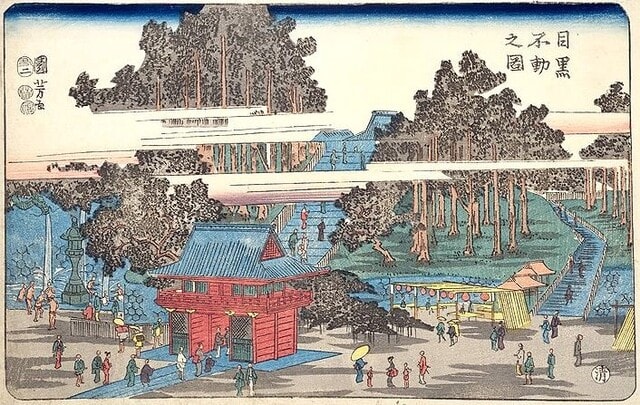
「目黒不動之図 / 源氏絵」 国芳
(国立国会図書館「錦絵で楽しむ江戸の名所」より利用規約にもとづき転載。)

「目黒不動堂 / 江戸名所図会. 七」
(国立国会図書館DCより利用規約にもとづき転載。)
大同三年(808年)、慈覚大師円仁が十五歳のとき、師の広智阿闍梨に伴われて故郷の下野国から比叡山の伝教大師最澄のもとに赴く途中、目黒の地に宿をとられました。
その夜のこと、夢の中に恐ろしい形相をした神人が現れ「我、この地に迹を垂れ、魔を伏し、国を鎮めんと思ふなり。来って我を渇仰せん者には、諸々の願ひを成就させん」と告げられました。
慈覚大師がその神人の尊容を像に刻して安置されたのが開創と伝わります。
承和五年(838年)、渡唐された大師が長安・青竜寺の不動明王を拝したところ、件の夢中の神人がまさにこの不動尊であると察せられ、御帰朝後の天安二年(858年)、像を安置した目黒の地に堂宇を建立されました。
堂宇の建立にあたり大師が法具の獨鈷を投じると、そこに霊泉が湧出し滝を落としました。
この滝は「獨鈷の瀧」と名づけられ、大師自ら「大聖不動明王心身安養呪願成就瀧泉長久」と棟牘に記されて、その由縁から「瀧泉寺」と号されたと伝わります。
貞観二年(860年)、清和天皇より「泰叡」の勅額を賜り「泰叡山」と号します。
弘治三年(1557年)堂塔の修理造営成ったものの、元和元年(1615年)火災により多くの伽藍を失いました。
このとき御本尊の不動明王はみずから猛火をなぎ払い、獨鈷の瀧の上に飛来して火災の難を逃れたと伝わります。
江戸時代の寛永年間(1624-1645年)、三代将軍家光公がこの地で鷹狩りを催した際、愛鷹が行方知れずになりました。
家光公みずから不動尊の前に額づき祈願を籠めると、愛鷹は本堂前の松(鷹居の松)に戻ってきたため家光公は不動尊の霊威を尊信、帰依しました。
寛永七年(1630年)、上野護国院の開祖・生順大僧正が当寺を管掌、堂宇再建を手掛けた際に家光公は寄進援助し、五十三棟にも及ぶ大伽藍の復興を成しました。
その壮大な伽藍は「目黒御殿」と称されるほどに華麗を極めたと伝わります。
承応三年(1654年)には御水尾天皇より「泰叡山」の勅額を、元禄六年(1693年)には御西天皇御宸筆の「不動明王」を拝戴して、開山以来、実に三度の勅額の下賜を受けています。
以降、徳川将軍家の保護もあって隆盛を極め、関東最古の不動霊場として、熊本の木原不動尊、千葉の成田不動尊と併せて「日本三大不動」のひとつに数えられます。
目黒は江戸御府内からほどよい距離の風光明媚の地(夕陽の紅葉で名高い行人坂上)で、目黒不動尊をはじめ蛸薬師と呼ばれる成就院や、弁財天霊場として知られる蟠龍寺もあったため江戸庶民の格好の参詣先となり、門前も市をなしてにぎわいました。
”江戸の三富”(当山、湯島天神、谷中感応寺)と呼ばれた名物の富くじも、目黒繁栄の一因といわれます。
明治に入っても諸人の尊崇篤く、西郷隆盛や東郷元帥などが祈願に訪れています。
西郷隆盛は主君島津斉彬公の当病平癒のために日参。
東郷元師は日本海海戦の勝利を立願し見事に成就したため、庶民の目黒不動尊信仰はますます隆昌を極めたといわれます。
なお、落語噺として有名な「目黒のさんま」は当然目黒の名物ではなく、江戸期には「目黒のたけのこ」と賞され、とくにたけのこ飯が名物だったようです。
~ 筍や 目黒の美人 ありやなし ~ 正岡子規
『江戸名所図会. 七』(国会図書館DC)には以下の記載があります。
「同所の西百歩あまり不動堂 泰叡山 龍泉寺と号す天台宗●●東叡山に属せし 開山ハ慈覚大師 中興慈海僧正なりと 本堂不動明王 慈覚大師作脇士ハ八大童子なり 本殿額泰叡山御西院御筆 楼門額泰叡山御水尾帝御筆 鳥井(ママ)額泰叡山日光御門主明王院宮御筆 経蔵 一代蔵経を安置本尊に釋迦阿難迦葉の像を置 八幡宮 早尾権現/祭神猿田彦大神或ハ素戔嗚尊ともいふ祭礼ハ五月十五日なり此堂社何れも本堂の左に並ぶ 恵比寿大黒祠 鐘楼 水神社 愛染明王 大行事権現/此地の地主神なり祭神高祖皇産霊尊なり五月十五日祭礼あり 石不動尊/何れも本堂の右にあり 稲荷祠 地蔵尊/掌善掌悪の二童子を置 聖観音 開山堂 聖徳太子 天照太神宮 本地大日如来/本堂の後峙●る山の腰を切割く安置を俗す奥の院と称す 吉祥天女祠 天満宮 鬼子母神 十羅刹女祠 虚空蔵堂 遮軍神祠 何れも本堂の後に並び建つ 結神祠 役小角/女坂の中程にあり銅像にして前鬼後鬼の像あり三佛堂/弥陀薬師釋迦等の三尊を安す 子安明神/鬼子母神あり 疱瘡神 粟島明神 石地蔵尊 秋葉権現 六所明神 荒神宮 何れも二(ママ)王門入て右の方にあり 辨財天祠/江島弁天の模なり 地蔵堂/堂内閻王脱衣婆等の像を安せり 観音堂/中尊ハ聖観音廻●●西國坂東秩父等の札所百番の観音を安置せり 勢至堂 稲荷祠 前不動/左右に十二天の像を安置す 何れも楼門の左の方にあり 楼門/左右に金剛密迹二王の像を置裏に使者犬の像を置り 獨鈷の瀧/(中略) 一年此滝水の涸たりしことありたる● 沙門某江島の弁天に祈請したてまつり再ひ元の如しとぞ故に今も年々当寺より江島の弁天へ衆僧をして参詣せしむる(中略) 鷹居の松/(中略) 」
明治23年刊の『東京名所図会』(国会図書館DC)には以下の記載があります。
「開山ハ慈覚大師なり 本尊不動明王ハ慈覚大師の作なり 本殿の額泰叡山は御西院天皇の御筆 楼門の額泰叡山ハ御水尾天皇の宸筆 鳥居の額泰叡山ハ日光御門主明王院宮の御筆なり 境内に神佛の堂社多くありて一々枚挙すべからぞ 獨鈷の瀧ハ常山の垢離場にして霊泉常に滔々と落下す 如何なる炎天干魃にも涸るヽ事なしと云ふ 往昔ハ三口に分れて湧出せしかど今ハニ流となれり 当寺ハ慈覚大師夢想に感得せし尊容を彫刻して露示の如く此地に安置せしなりとぞ 此地少しく都下を隔つと雖も諸人常に群参せり 殊に正五九の月にハ廿七廿八両日とも非常に賑へり 此門前五六町の間ハ左右酒店茶肆軒を連ねて参詣人の休憩所に充つ 殊に粟餅飴及び餅花等名物として之を商ふ家頗る多し 其繁昌推して知るべし」
参詣の土産として知られていたのが”粟餅”、”餅花”、”飴”でした。
「桐屋」の飴は人気だったらしく、『江戸名所図会』に「目黒飴」と題して挿絵が載せられています。

「目黒不動餅花 / 江戸自慢三十六興(書画五十三次) 絵師:広重, 豊国」
(錦絵で楽しむ江戸の名所(国会図書館DC)より利用規約にもとづき転載。)

「目黒飴 / 江戸名所図会. 七」
(国立国会図書館DCより利用規約にもとづき転載。)
公式Webでは、江戸五色不動につき以下のとおりとりあげています。引用します。
「江戸五色不動は、江戸時代には五眼不動といわれ、五方角(東・西・南・北・中央)を色で示すものです。その由来については諸説ありますが、各位置は江戸城(青)を中心として、それぞれ水戸街道(黄・最勝寺)、日光街道(黄・永久寺)、中山道(赤)、甲州街道(白)、東海道(黒)といった江戸府内を中心とした五街道沿い(又は近く)にあることから、徳川の時代に江戸城を守るために置かれたといわれています。」
************************
最寄り駅は「目黒」駅か東急線「不動前」駅ですが、どちらからも微妙に距離があります。
名勝・行人坂の往年の情景をしのぶには、目黒駅から歩いた方がいいかもしれません。
目黒駅から目黒川に向けて行人坂をくだっていきます。
江戸時代、紅葉夕景の名所「夕日の岡」として広く知られた急坂です。
江戸名所図会. 七(国会図書館DC)には「明王院の後の方西に向へる岡といへり古へハ楓樹数株梢を交へ晩秋の頃ハ紅葉夕日に映し奇観なりしと知らされと今ハ楓樹少く只名のみを存せり」とあります。

「夕日岡 行人坂 / 江戸名所図会. 七」
(国立国会図書館DCより利用規約にもとづき転載。)
目黒の高台から西側に下るこの坂は富士眺望の名所でもあり、数々の浮世絵が遺されています。
現・ホリプロのビルのあたりに富士の眺望で名を馳せた「富士見茶屋」があり、錦絵にも遺されています。


【写真 上(左)】 行人坂下り口
【写真 下(右)】 富士見茶屋跡地

「行人坂 / 江戸名勝図会 絵師:広重」
(錦絵で楽しむ江戸の名所(国会図書館DC)より利用規約にもとづき転載。)
※ 右手の冠木門が富士見茶屋

「目黒行人阪之図 / 広重東都坂尽 絵師:広重」
(錦絵で楽しむ江戸の名所(国会図書館DC)より利用規約にもとづき転載。)
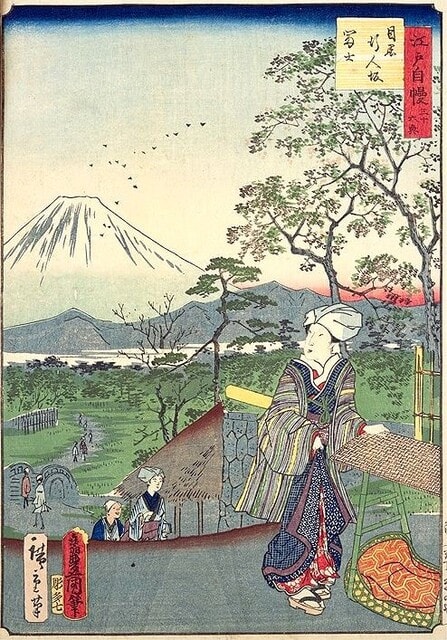
「目黒行人坂富士 / 江戸自慢三十六興 絵師:広重, 豊国」
(錦絵で楽しむ江戸の名所(国会図書館DC)より利用規約にもとづき転載。)
作家・杉本苑子先生の『東京の中の江戸名所図会』/文春文庫には、江戸時代のこのあたりの情景が叙情ゆたかに描写されています。引用します。
「もう、ここまでくると、いちめんの田園風景・・・・・・。春は梅が咲き桃が咲き、菜の花畑れんげ畑に野末がかすんで、ひばりの囀りが降るほどになるし、秋は百姓家の背戸に色づく柿の実、稲の垂れ穂に鳴子がひびいて、ごみごみした下町から抜け出してきた人々の耳目をたのしませてくれた。」


【写真 上(左)】 行人坂
【写真 下(右)】 行人坂の案内板


【写真 上(左)】 手前が目黒川架橋供養勢至菩薩、奥が大圓寺
【写真 下(右)】 大圓寺
坂の途中、左手に松林山 大圓寺。
出羽修験系の開創とされるこの天台宗寺院は、明和九年(1772年)の大火(行人坂火事)とかかわりを持ち、幕末に薩摩島津氏の菩提寺として再興されました。
山手七福神の大黒天で、数種の御朱印を授与されています。
さらに下ると雅叙園。
かつてここには松樹山 明王院という天台宗寺院がありました。
『江戸名所図会. 七』(国会図書館DC)には以下の記載があります。
「坂の側にあり天台宗●●東叡山に属す 本尊阿弥陀如来脇士観音勢至を安置せり 開山を栄運法師といふ常念佛の道場●●頗る殊勝なり 毎月四日報恩念佛百万遍修行あり 此常念佛ハ西運といふ沙門の発願なりとぞ」
雅叙園内のお七の井戸あたりが明王院跡とされ、八百屋お七の恋人吉三郎が出家して入り百万遍修行を経て西運上人となった寺と伝わります。
八百屋お七は、浮世草子『好色五人女』(貞享三年(1686年)刊)、浄瑠璃、歌舞伎などで広くとりあげられて江戸庶民の知名度が高く、また弁財天百社参り第25番の札所でもあったので、江戸期には参詣者を集めたとみられます。
明和九年(1772年)、行人坂火事で焼失した大圓寺は嘉永元年(1848年)まで再建を許されなかったので、その間はとくに行人坂と明王院の結びつきが強まったかもしれません。
明王院は明治13年(1880年)頃廃され、大圓寺に統合されました。
雅叙園先の太鼓橋で目黒川を渡ります。
雁歯橋とも呼ばれたこの橋も名所で、『江戸名所図会. 七』(国会図書館DC)には「同所坂下の小川に架せ●/目黒川といへり 桂を用ひて両岸より石を畳の如くして橋とす故に横面より是を望めハ太鼓の胴に彷彿せり故(略)」と記されています。
太鼓橋は1700年代初頭に木喰上人が造り始め(八百屋お七の恋人吉三郎が出家した西運上人とも)、後に江戸八丁堀の商人達が資材を出し合って宝暦十四年(1764年)から6年をかけて完成した江戸ではめずらしい太鼓状の石橋です。
初代の石橋は大正9年(1920年)の豪雨で崩壊し、当時の石材は大圓寺の境内に置かれています。
太鼓橋のシンボルツリーは椎の木だったようで、↓ の広重の「目黒太鼓橋夕日の岡」にも描かれ、目黒区の木に指定されています。

「太鼓橋 / 江戸名所図会. 七」
(国立国会図書館DCより利用規約にもとづき転載。)

「目黒太鼓橋夕日の岡 / 名所江戸百景 絵師:広重」
(錦絵で楽しむ江戸の名所(国会図書館DC)より利用規約にもとづき転載。)


【写真 上(左)】 行人坂上り口
【写真 下(右)】 太鼓橋
山手通りを越えると五百羅漢寺。羅漢会館の裏手が目黒不動尊への近道です。
五百羅漢寺でも数種の御朱印を授与されています。


【写真 上(左)】 五百羅漢寺
【写真 下(右)】 参道入口
東急目黒線「不動前」駅からのアプローチでも、臥龍山 安養院や不老山 成就院(蛸薬師)などの御朱印授与寺があります。(安養院の現在の授与は不明)
こちらは商店街づたいで、門前街としての風情はこちらの方があると思います。
----------------------------------------

それでは見どころ満載の山内に参ります。(→ 境内案内)
仁王門の門前に伏見稲荷社と芝居でおなじみの白井権八・小紫の比翼塚。
明暦元年(1655年)頃に生まれ波乱の生涯をおくった鳥取藩士平井(白井)権八は、歌舞伎『浮世柄比翼稲妻』、講談、浄瑠璃などでとりあげられ、新吉原の三浦屋の遊女・小紫との恋物語は、つとに知られています。
また、浮世絵見立て『役者見立 東海道五十三駅』(『役者東海道』)初版には「川崎駅 白井権八」(五代目岩井半四朗)が登場、こちらでも名を広めたとされます。
比翼塚とは相思相愛の男女を弔う塚で、こちらの比翼塚は白井権八・小紫の塚です。
目黒不動尊のそばに普化宗の東昌寺というお寺があり、権八は一時東昌寺に身を寄せたとされます。
東昌寺は『江戸名所図会. 七』(国会図書館DC)には「虚無僧寺」として記されていますが、明治初期に廃寺となり、比翼塚は東昌寺から当地に移されたそうです。
行人坂の明王院、太鼓橋、そして比翼塚など、歌舞伎、浄瑠璃、講談でなじみふかい人物ゆかりの名所があることも、目黒が行楽地として人気を集めた一因かもしれません。


【写真 上(左)】 伏見稲荷社
【写真 下(右)】 比翼塚


【写真 上(左)】 仁王門
【写真 下(右)】 仁王門と寺号標
仁王門の前に「目黒不動尊 瀧泉寺」の寺号標と一対の狛犬。
わたしのまわりにも、お寺と神社の区別がつかない人がけっこういたりします。
鳥居の有無、墓地の有無もありますが、やはり名称(●●寺、●●神社)で区別している人が多いようです。
●●寺、●●神社ならば問題ないですが、●●宮、●●尊となると?マークがついてくるようです。
こちらには鳥居も狛犬もあるし、「目黒不動尊」のみではお寺か神社かわからない人もいるのでは。
その点でこの「瀧泉寺」の寺号標は役立っているかもしれません。


【写真 上(左)】 仁王門扁額
【写真 下(右)】 参道
仁王門は三間一戸、瓦葺八脚の楼門で、二層中央に「泰叡山」の扁額を掲げ、さすがに名刹の風格があります。
左右に阿吽の仁王尊像、階上には韋駄天が祀られているそうです。


【写真 上(左)】 手水舎
【写真 下(右)】 山内
仁王門をくぐって右手に大ぶりな手水舎で、ここから山内が一望できます。
都内有数の名刹だけあって、さすがに広大な山内を構えます。


【写真 上(左)】 弁天堂(三福神)入口
【写真 下(右)】 金明湧水
仁王門から左手時計まわりにいくと、朱塗りの明神鳥居。そのよこの手水は金明湧水です。
この金明湧水のまわりは色濃く赤茶け、おそらく鉄分を含む湧水だと思います。
鳥居の先の三福神にお参りしてから、金明湧水で”福泉洗い”をするそうです。
これは、いわゆる”銭洗い弁天”を彷彿とさせますが、この一画は『江戸名所図会. 七』(国会図書館DC)で「辨財天祠/江島弁天の模なり」と記され、江戸三十三ヶ所弁財天霊場第22番、弁財天百社参り第24番の札所で、江戸期には弁天様の霊場としても知られたところではないでしょうか。


【写真 上(左)】 弁天堂(三福神)
【写真 下(右)】 恵比寿様
太鼓橋を渡って右手に折れると、正面が弁天堂(三福神)、向かって右手に豊川稲荷、左手に福珠稲荷大明神が御鎮座。
弁天堂はおそらく切妻造桟瓦葺。立派な降り棟を備えた整った堂宇で、向拝、水引虹梁まわりに木鼻、斗栱、蟇股、二軒の垂木を配しています。向拝正面は桟唐戸(閉扉)、見上げに「三福神」の扁額、左右に花灯窓を配しています。
桟唐戸の前には恵比寿様が鎮座され、こちらが「山手七福神」の一尊かと思います。(御前立かもしれぬ)
堂内の須弥壇上に奉られる「木造弁才天及び十五童子像」は目黒区の有形文化財(彫刻)に指定されています。
(→ 区資料)
制作年代は14世紀前半頃、南北朝時代と推測されています。
こちらは御開扉されることがあるようで、その際のWeb投稿写真によると、堂内には大黒天と七福神もお祀りされているようです。
単なる「弁天堂」ではないところが、瀧泉寺の信仰の複雑さを物語っています。
北向六地蔵尊、三界万霊塔と過ぎ、本堂の山裾に腰立不動尊、憂国の士北一輝の碑、作曲家本居長世の碑、勢至堂、青木昆陽(甘藷先生)碑、前不動堂、青龍大権現を祀る垢離堂と並び、本堂参道下左手が獨鈷の瀧です。


【写真 上(左)】 北向六地蔵尊
【写真 下(右)】 腰立不動尊
北向六地蔵尊は、切妻屋根銅板葺の立派な覆屋の下に御座。石造りの端正な立像です。
この前を通って左に向かうと、瀧泉寺墓地に至ります。
掲示によると「地蔵菩薩の浄土『迦羅陀山』は南方にあり、南を向いて地蔵菩薩を祈れば、直ちに浄土を発し我々のいる北に向かって救いに来てくださるので北を向いています。」とのこと。
腰立不動尊は、本堂の山裾にあり階段の参道です。
切妻造の堂宇の前に切妻の向拝を付設した複雑な構成。
向拝に掲げられた扁額には「山不動」とあり、御詠歌らしきものが記されていました。


【写真 上(左)】 勢至堂
【写真 下(右)】 前不動堂
勢至堂は「瀧泉寺勢至堂」として目黒区の有形文化財(建造物)に指定されています。
江戸時代中期の建築。瓦葺で一間の向拝を設けた整った意匠で、とくに絵様の一部は寛永中興期の瀧泉寺の面影を伝えるものとされます。
もとは前不動堂の手前にありましたが、昭和44年に現在地に移築されました。
青木昆陽(甘藷先生)碑は、当寺に青木昆陽の墓(国指定史跡)が
あることにちなむと思われ、毎年10月28日には先生の遺徳をしのんで甘藷祭りが催されています。
前不動堂は「滝泉寺前不動堂」として都の有形文化財(建造物)に指定されています。(→ 指定内容(都文化財情報DB))
江戸時代、将軍や大名の参拝持には庶民は本堂へは近づけず、その際の参詣者の便宜を図って建立したものとされます。
桁行三間梁間二間向拝一間、桟瓦葺の宝形造で、江戸時代中期の建築とされています。
堂内には木造不動明王三尊立像等を安置。
『江戸名所図会. 七』(国会図書館DC)には「前不動/左右に十二天の像を安置す」の記載があり、いまも十二天像が安置されているのかもしれません。
堂建立当時のものとされる扁額「前不動」は書家「佐玄龍書」の署名があり、附指定されています。
こちらは毎月28日の御縁日に内部公開とのこと。


【写真 上(左)】 前不動堂扁額
【写真 下(右)】 前不動堂下の湧水龍口
前不動堂の下には、湧水を吐き出す龍口があります。
目黒台と羅漢寺川(現在は暗渠化)を境するこのあたりは崖線となり、いわゆる「ハケの湧水」ポイントとみられます。
実際、こちら(「東京湧水巡礼」様)には「水を通しにくい東京層の地層が擁壁や石垣の裏側で露出し、その上から湧水が流れ出していると思われる。」とあります。(ただし、同記事によると、現在はすこし離れた浅井戸から送水しているらしい。)

「目黒不動尊(水垢離) / 東都名所 絵師:広重」
(錦絵で楽しむ江戸の名所(国会図書館DC)より利用規約にもとづき転載。)
本堂への参道階段左横に獨鈷の瀧。
慈覚大師が長安青竜寺の清滝を想起され法具の獨鈷を投じるとそこに霊泉が湧出し、滝をなしたので「獨鈷の瀧」と号します。
いまでも銅製の竜口から滝が注ぎ、不動講の水垢離場となっています。
数十日間の炎天旱魃が続いても涸れることがないそうです。
水垢離場上には石不動や講が奉安した倶利伽羅剣が奉られ、手前には水かけ不動明王が御座、垢離堂も配されて、不動霊場特有のパワスポ的雰囲気が感じられます。


【写真 上(左)】 獨鈷の瀧と水垢離場
【写真 下(右)】 参道方向から獨鈷の瀧


【写真 上(左)】 水かけ不動明王
【写真 下(右)】 水かけ不動明王の手水の龍
垢離堂の御本尊は青龍大権現で、5月の御縁日には青龍大権現大祭が営まれます。
青龍大権現は、法華経で説かれ仏法を守護するとされる八大竜王の一尊、娑伽羅(サーガラ)龍王の第三王女・善女(如)竜王と同一とされ、雨を司る尊格とされます。


【写真 上(左)】 倶利伽羅剣
【写真 下(右)】 垢離堂
善女龍王は、弘法大師が京の神泉苑で請雨修法を施された際に出現された尊格とされ、真言宗醍醐派総本山醍醐寺の守護女神ともされます。(清瀧大権現と呼称されます)
もともと西安の青龍寺の鎮守とされ、弘法大師が御帰朝ののち、京・高雄山麓の清滝に勧請されたと伝わります。
醍醐寺を開かれた聖宝の時代、昌泰三年(900年)頃に醍醐寺に御降臨。以来、醍醐寺の守護神として篤く祀られています。
『呪術宗教の世界』(速水 侑著)によると、聖宝の法系は平安中期の名僧、仁海に受け継がれ、ことに請雨の修法に優れて雨僧正とも称されました
仁海は東密(真言密教)小野流の祖とされ、小野流は独自の秘法として「請雨修法」を伝えました。
現在でも清瀧権現は真言宗寺院、とくに大寺で祀られ、川崎大師、成田山新勝寺、高尾山薬王院は、いずれもお祀りされています。
台密(天台密教)でも八大竜王を祀る例があり、目黒不動尊のそばの臥龍山 安養院(寝釈迦尊)には木食円空作八大龍王像が収蔵されています。
また、山梨県忍野村の天台宗寺院、忍草山 東円寺では稀少な娑伽羅龍王の御朱印を授与されています。


【写真 上(左)】 臥龍山 安養院の御朱印
【写真 下(右)】 忍草山 東円寺の娑伽羅龍王の御朱印
『江戸名所図会. 七』(国会図書館DC)には「獨鈷の瀧/一年此滝水の涸たりしことありたる● 沙門某江島の弁天に祈請したてまつり再ひ元の如しとぞ故に今も年々当寺より江島の弁天へ衆僧をして参詣せしむる」とあり、獨鈷の瀧は江島弁財天にゆかりがあったようです。


【写真 上(左)】 大本堂への参道(男坂)
【写真 下(右)】 鳥居工事中の男坂
水垢離場よこから大本堂への参道階段がはじまります。参道階段が男坂、右手の坂が女坂です。
階段右手には家光公ゆかりの「鷹居の松」(跡)、女坂途中には神変大菩薩(役ノ行者/役小角)のお堂があります。


【写真 上(左)】 女坂
【写真 下(右)】 神変大菩薩のお堂
堂内安置のお像は「銅造役の行者倚像」として目黒区の有形文化財(彫刻)に指定されています。(→ 区資料)
寛政八年(1796年)、太田駿河守藤原正義の作とされる銅造の倚像で、頭巾をかぶり、木の葉の肩衣をかけ、右手に錫杖、左手に巻子を持って腰掛けられています。
均整のとれた体躯、精緻な表現、品格ある表情などを備え、江戸時代の銅造彫刻の中でも優品とされています。
『江戸名所図会. 七』(国会図書館DC)には「役小角/女坂の中程にあり銅像にして前鬼後鬼の像あり」とあります。
前鬼・後鬼とは、元は生駒山地に住んでいた夫婦の鬼で、役小角は彼らを不動明王の秘法で捕縛して従者とされました。
堂内、役ノ行者の背後に安置されている二体のお像は、前鬼・後鬼かと思われます。


【写真 上(左)】 山王鳥居
【写真 下(右)】 鳥居の扁額
平成29年、男坂の参道途中に酉年本尊御開扉記念として石造の山王鳥居が建立されました。
現地掲示には「当山は往古より神仏習合の寺院でありました。江戸時代、天海大僧正が山王一実神道を創始され 当山にも山王鳥居が奉安。酉年復興いたしました。」とあります。
「護國院」の院号扁額が掲げられ、山王鳥居の合掌形と大本堂の千鳥破風が意匠的に呼応しています。


【写真 上(左)】 狛犬
【写真 下(右)】 手水舎の龍
階段を登り切ると大きな空間が広がります。
手前の狛犬はなかなかインパクトのある表情をしています。
手前左手に手水舎。水盤の龍がオーラを放っています。


【写真 上(左)】 大本堂
【写真 下(右)】 大本堂(斜めから)
正面の大本堂は石段の奥に朱塗りの堂々たる構え。
傾斜地ではないですが、舞台造(懸造)的な構成で、入母屋造本瓦葺正面千鳥破風とその先に設えた唐破風の下に三間の大がかりな向拝を張り出しています。
向拝水引虹梁は彩色で木鼻と中備えに蟇股。向拝中央に「目黒不動尊」の大提灯を掲げ、千鳥破風には猪ノ目懸魚を設えています。
慈覚大師の作と伝わる御本尊不動明王(目黒不動尊)が御座され、秘仏で十二年に一度、酉年のご開帳です。


【写真 上(左)】 大本堂向拝
【写真 下(右)】 意志不動尊
大本堂まわりには諸仏が御座します。
時計回りに辿ってみます。
大本堂向かって右手、玉垣に囲われて意志不動尊。
由緒は不明ですが、手前に眷属、制多迦童子と矜羯羅童子を配した石像の立像です。
そのお隣に微笑観世音菩薩。
穏やかな面差しの石造り立像の聖観世音菩薩です。


【写真 上(左)】 微笑観世音菩薩
【写真 下(右)】 愛染明王
大本堂向かって左手には愛染明王。
八角形の石敷の結界中央に、端正なおすがたの愛染明王の坐像露仏が御座。
こちらでは、良縁成就、縁結びを願掛けします。


【写真 上(左)】 子安延命地蔵尊
【写真 下(右)】 虚空蔵菩薩
大本堂右手には甘薯先生(青木昆陽)ゆかりと思われるサツマイモ畑があり、その前に子安延命地蔵尊。
左手に如意宝珠、右手に錫杖を持たれ、金色の輪光背を帯びて蓮華座に御座す坐像の金仏です。
サツマイモ畑の奥には虚空蔵菩薩。
頭上に宝冠を抱かれ蓮華座のうえに結跏趺坐される石仏で、あたらしいお像と思われます。
右手の石柱の上には牛の像が置かれています。
境内掲示の境内案内図には、諸仏諸堂に十二支が記されています。
大本堂には「うし、とら、うさぎ、たつ、へび、とり」、大本堂裏手の大日如来には「ひつじ、さる」、女坂下の観音堂には「ねずみ」、阿弥陀堂には「いぬ、いのしし」、勢至堂には「うま」。
このうち、こちらの虚空蔵菩薩に大本堂から「うし、とら」を分祀されたのでは?
なお、未確認ですが、この内容からすると大本堂に釈迦三尊(文殊菩薩/うさぎ、普賢菩薩/たつ、み(へび))が御座されているかもしれません。
子安延命地蔵尊の右には護衛不動尊。
石碑によると、開山一千二百年を記念して奉安された厄除けのお不動様で、儀軌に忠実なお像とみました。
お不動様に関することなので、少しく詳細に書いてみます。
『不動明王』(渡辺照宏著/朝日選書)によると、菅原道真の孫、淳祐が著した「不動尊道場観」のなかに不動尊の尊格や像容を記した「十九観」があり、うち第四~第十八の像容は次のとおりです。
この「十九観」は、のちの不動尊作像に大きな影響を与えたとみられています。
第四:童子形、第五:七莎髻(頭髪が七個の束になっていること)、第六:弁髪(左側に弁髪を垂らす)、第七:額の皺文、第八:一眼を閉じる(通常は左眼)、第九:下の犬歯が上唇を、上の犬歯が下唇を噛む、第十:その口を緘閉す、第十一:右手に剣を執る、第十二:左手に羂索を持つ、第十三:行人の残食を喫す、第十四:大盤石に座す、第十五:色醜くして青黒なり、第十六:奮迅忿怒す、第十七:遍身に迦楼羅炎、第十八:変じて倶利迦羅と成り
高々と迦楼羅焔を背負われ、盤石に御座すこの護衛不動尊は、「十九観」の特徴の多くを満たされています。


【写真 上(左)】 護衛不動尊
【写真 下(右)】 鐘楼
その右手に鐘楼、その奥は鬱蒼と木々が茂る八大童子の山。
八大童子の山の手前を奥に昇ると瀧泉寺墓地で、甘薯先生(青木昆陽)の墓所があります。


【写真 上(左)】 本堂裏手
【写真 下(右)】 大日如来
本堂裏手に回ると、覆屋の下に目黒区の有形文化財(彫刻)に指定されている銅造大日如来坐像。(→ 区資料)
現地掲示には「不動明王本地佛」とあります。
『江戸名所図会. 七』(国会図書館DC)には「本地大日如来/本堂の後峙●る山の腰を切割く安置を俗す奥の院と称す」とあります。
覆屋の屋根には二十八宿図が掲げられています。
これは天球を二十八のエリア(星宿)に分割した図で、東方青龍、北方玄武、西方白虎、南方朱雀の各七宿から成り立ち、風水思想と関連をもつという説があります。
なお、目黒不動尊は江戸城をはさんで上野寛永寺と鬼門・裏鬼門ラインのほぼ直線上に当たることから、目黒不動尊を江戸城の裏鬼門の鎮めとみる説もあります。
蓮華座に結跏趺座される高さ385㎝のお像は、宝髪、頭部、体躯など十数の部分に分けて鋳造して組み合わる”吹き寄せ”の技法で制作されています。
体躯に比べて頭部が大きいのがこの技法の特徴で、この像も同様とされます。
台座の刻銘によると、天和三年(1683年)、鋳物師横山半右衛門尉正重による造立。
法界定印を結ばれているので胎蔵(界)大日如来とみられ、回りを四天王(持国天・増長天・広目天・多聞天)が囲みます。
不動明王は大日如来の化身(教令輪身)とされますが、金剛界大日如来の化身とする説もあるようで、どうして胎蔵(界)大日如来が御座されるのかはわかりません。


【写真 上(左)】 覆屋屋根の二十八宿図
【写真 下(右)】 大行事権現
さらにその奥、神明鳥居を前に地主神・大行事権現が御鎮座です。
大行事権現は、大津坂本の日吉神社の山王二十一社の一社(中七社)で、山王一実神道とふかいかかわりをもつとされます。
『江戸名所図会. 七』(国会図書館DC)には「大行事権現/此地の地主神なり祭神高祖皇産霊尊なり」とあります。


【写真 上(左)】 本坊方面への案内
【写真 下(右)】 本坊への参道
男坂・女坂をくだって右手方向、阿弥陀堂への参道の左右に交通安全自動車祈祷殿、地蔵堂、精霊堂、観音堂、書院、阿弥陀堂(本坊・寺務所)と並びます。


【写真 上(左)】 地蔵堂
【写真 下(右)】 地蔵堂扁額


【写真 上(左)】 地蔵堂御内陣
【写真 下(右)】 精霊堂
地蔵堂は、入母屋造銅板葺平入りだと思いますが、すこし変わった感じの意匠です。
向拝柱はなく、見上げに「地蔵堂」の扁額を掲げています。
中央に地蔵菩薩坐像、向かって右に閻魔大王、左に奪衣婆が御座します。
毎月24日のお地蔵様ご縁日の午後の法要時には堂内に入れるようです。
瀧泉寺は江戸・東京四十四閻魔参り第23番の札所ですが、札所本尊はおそらくこちらの閻魔様とみられます。
地蔵堂と相対して交通安全祈願殿。御本尊は不動明王です。


【写真 上(左)】 交通安全祈願殿
【写真 下(右)】 幟
地蔵堂の横、精霊堂前には書道の大家西川春洞の碑。
精霊堂には地蔵菩薩坐像、六地蔵、閻魔大王、奪衣婆などが御座し、いずれも石仏です。


【写真 上(左)】 観音堂
【写真 下(右)】 観音堂扁額
観音堂は朱塗りの端正なお堂。
全容がよくわからないのですが、瓦葺で向拝側に千鳥破風を構えて流れ向拝。入母屋造妻入りかもしれません。
向拝柱や水引虹梁はなくシンプルな向拝で、見上げに「観音堂」の扁額。
向拝柱には観音霊場の札所板と御詠歌が掲げられています。
堂内には江戸三十三観音札所第33番結願の聖観世音菩薩のほか、千手観世音菩薩、十一面観世音菩薩も御座されるそうです。
第1番浅草浅草寺からはじまる江戸三十三観音は、府内各所を巡ってここ瀧泉寺で結願を迎えます。
現在の江戸三十三観音は、昭和51年(1976年)に改訂された「昭和新撰 江戸三十三観音霊場」ですが、江戸時代には享保二十年(1735年)版の『続江戸砂子』に収録された「江都三十三観音」(札所情報は→こちら(「日本を巡礼する」様))が、その前身として江戸庶民にさかんに廻られていたとみられます。
現在の江戸三十三観音とはことなる札所もありますが、発願の浅草寺と結願の瀧泉寺は変動なく、下町・浅草にはじまり、府内(都内)各所を巡って郊外の景勝地、目黒で結願するというコース設定に変わりはないということになります。
こちらの観音堂が江戸三十三観音札所第33番の結願所です。
東京三十三所観世音霊場第3番、江都三十三観音霊場第33番などの札所もおそらくこちらと思われます。


【写真 上(左)】 阿弥陀堂(本坊)-1
【写真 下(右)】 阿弥陀堂(本坊)-2
阿弥陀如来が御座す阿弥陀堂(本坊)の右手に御朱印授与所(寺務所)があります。
複数のメジャー霊場の札所を兼ね、ご親切で手慣れたご対応です。
〔江戸五色不動尊の御朱印〕
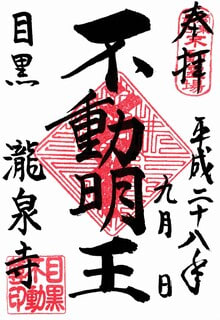
・御朱印尊格:不動明王 「関東最古不動霊場」の印判 直書(筆書)
〔関東三十六不動尊霊場第18番の御朱印/専用納経帳〕

・御朱印尊格:不動明王 関東三十六不動尊霊場第18番印判 書置(筆書)
〔関東三十六不動尊霊場第18番の御朱印/御朱印帳〕
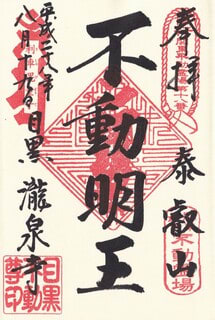
・御朱印尊格:不動明王 関東三十六不動尊霊場第18番印判 直書(筆書)
〔江戸三十三観音札所第33番の御朱印〕(通常御朱印)

・御朱印尊格:聖観世音 江戸三十三観音札所第33番印判 直書(筆書)
〔江戸三十三観音札所第33番の御朱印〕(結願御朱印)

・御朱印尊格:聖観世音 江戸三十三観音札所第33番印判 結願印 直書(筆書)
〔山手七福神(恵比寿神)の御朱印〕

・御朱印尊格:恵比寿神 山手七福神印判 直書(筆書)
(つづく) → こちら
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
| « 前ページ | 次ページ » |




