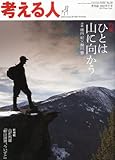Tarzan2015年6/11号「山がカラダに効く理由。」を、ちょっとdマガジンで覗いてみた。
『山=大自然のエンタメ型ジム!』『やっぱり凄い「歩く(トレッキング)」&「走る(トレラン)」の効果』と表紙に謳っている。中面では、いいこと書いている。少しだけ抜粋してみよう。
木々の緑、広がるパノラマ、吹き抜ける風。これらを五感で受け取りながら、歩いたり、走ったり。ココロは解放され、清々しい気分に浸かれることは間違いない。(中略)そして気持ちよさは運動の連続性に繋がる。5時間、6時間と歩くことができるし、終わった後も爽快感に包まれる。だから、山に入れば、1日でもかなりの運動量をこなせるのである。
そのとおり!だと思う。街中を長時間歩くのは、そもそもムリだ。平坦地で単調だからつまらなすぎる。誌面では、山歩きと街中のジョギングのイラストもついていて、その上に「週1回の山歩き」=「週7回のウォーキング」と書かれている。トレッキング程度の山歩きであれば、おそらく健康には非常にいい作用を及ぼすのだと思う。
でも何事もほどほどで中庸がいいといわれてるとおり、ほどほどの山歩きは健康にはいいだろうが、激しいのは当然健康に悪そうだよね。アップダウンの続くロングコースを10時間や12時間もかけてテントを背負って縦走するのは、明らかにカラダにムリを強いているから。そうじゃない、とおっしゃる鬼のような体力の持ち主もいるだろうけど、私は“そこそこ”、“ほどほど”で、健康を維持しながら山を楽しみたいものだ。
 | Tarzan (ターザン) 2015年 6月11日号 No.673 [雑誌] |
| クリエーター情報なし | |
| マガジンハウス |













 ナショナルジオグラフィック日本版2014年11月号
ナショナルジオグラフィック日本版2014年11月号