
標高 約280m 青森県
2008年9月16日(火) 快晴 
メンバー 山の神と私
コースタイム アクアグリーンビレッジANMON駐車場8:20--ぶな散策歩道--9:20暗門の滝第3の滝--9:50休憩10:00--10:27駐車場
6:00アクアグリーンビレッジANMONのテント場にて起床。朝食用に買っておいたパンをかじる。テント撤収後、観光案内所に移動し、暗門の滝のコースガイドをもらい、8:20ビレッジ内の駐車場から山の神とともに出発した。


左:ブナ以外にホオノキ、トチノキも生い茂る 右:おいしい水をいただく
コース起点には、「白神山地ブナ原生林の水 水飲場」があり、思わず引き寄せられる。ただの水飲場だったら、スルーしたかもしれないが、この名前だけに飲んでいかなければとなった。実際においしい水だった。
冒頭の巨大な標柱をフレームに入れて記念撮影し、山に分け入っていく。


左:鬱蒼としたブナの散策路を進む 右:河原に出た
木を伐りすぎじゃないのかというくらい広々とした道が続く。平日だけあって誰にも会わず、静かな道行となる。やがて河原に出た。


左:案内板 右:川沿いにつけられた遊歩道を行く
そこには案内板が設置されていて、暗門の滝第1の滝まで40分ほどであることがわかる。山の神と川沿いの遊歩道を進んだ。
9:20駐車場から1時間ほどでこぢんまりとした暗門の滝、第3の滝に到着した。マイナスイオンを全身に浴びながら山の神とパチリパチリと記念撮影していると、先ほどまでここにいた先行者が引き返してくる。なぜ?

暗門の滝、第3の滝
なんと第2の滝に向かう階段は鉄筋でがっちり通せんぼされていた。どうやら遊歩道が崩れてしまっていて通行不能のようだった。残念だが引き返すしかない。
9:50先ほど通過したブナ林散策道の分岐で休憩し、その後は渓谷の狭い場所を縫っていき、ちょっとした探検気分を味わった。


左:記念撮影 右:悲しいかな、通行止め
コース入口に戻ると、先ほどの水飲み場隣の休憩所には人がいて、森林環境整備を目的とした協力金を募っていた。300円を支払い、ブナの葉入りの協力証をいただいた(下の写真)。


森林環境整備協力者の証。裏にブナの葉
10:27アクアグリーンビレッジANMONの駐車場に戻った。
この暗門の滝をいま調べてみると、遊歩道は壊れてしまったようで(台風のせい?)、ガイドをつけて沢を詰めていくのが一般的なアプローチ方法になったようだ。誰もが容易に行けたところが、容赦ない自然の猛威で半ば閉ざされてしまった。環境保護という観点からはちょうどよかったのかもしれない。
楽チンコースで岩木山へにつづく
白神岳マテ山コースに戻る











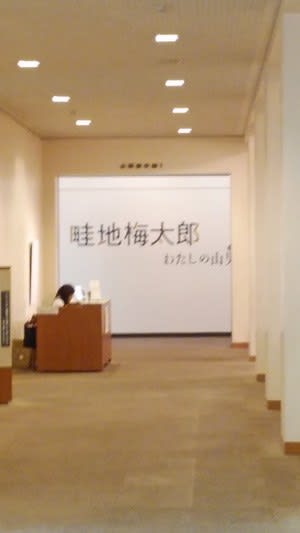
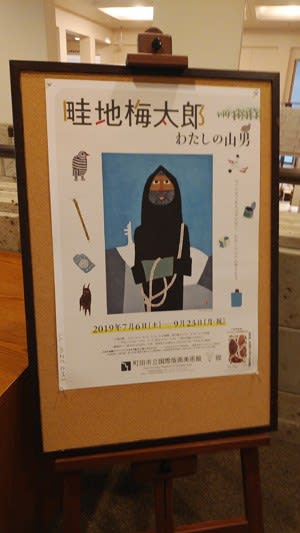
 1Fにはカフェがある。雨が降っていなければテラス席も
1Fにはカフェがある。雨が降っていなければテラス席も
 標高 1231.9m 青森県
標高 1231.9m 青森県













 十二湖リフレッシュ村キャンプ場
十二湖リフレッシュ村キャンプ場










