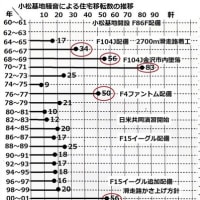19750900 書評『女性の歴史』(高群逸枝著)
1975年9月 金沢市田上公1にて
今、島田清次郎の論考「婦人参政権論者の幻滅―最近のパンカースト夫人」(1923年2月『婦人公論』)を読んでいる。この論考を理解するためには、高群逸枝の『女性の歴史』から学び直さねばならないと思い、約50年前の20歳代後半に書き殴った書評を引っ張り出した。
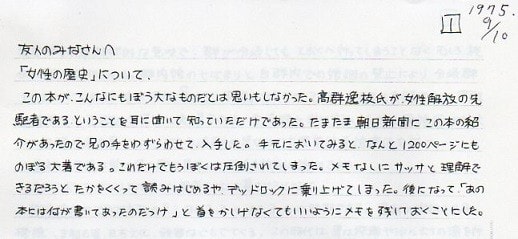

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
読後感想のまとめ
■ 明治の女平塚らいてうは「元始女性は太陽だった」と叫んだ。しかしその本当の理解は後の研究に待たねばならなかった。日本では、原始から古代に至るまで、母系氏族制が主だった。人間にとって自然が最も巨大な敵であった。まだその生産力は低く、分業として原始的な男と女による性的な分業であった。それぞれの分野で、それぞれが主人であり、とりわけて優劣はなかった。女性は共同体維持の中心となり、妊娠・出産・育児は共同体全体にとって神聖不可侵であった。女性は何ら不安なく出産・育児に心をかけることができた。女性にとって、孤立感を抱く必要はさらさらなかった。
■ 生産力の向上は農耕・牧畜からなされた。私有財産がここで生まれた。西欧では有史以前から始まり、男に富が集中した。ここから家父長制が生まれた。女性は奴隷化された。古代ギリシャに典型的に見られる。日本では、西欧と違い、私的所有は男女それぞれにあった。夫婦とはいえ、基本的に別居であり、別産であった。それぞれは別の経済単位=氏族共同体に属していた。だが、ここでも生産力の向上は新しい体制を求めていた。氏族間の戦争、下克上の力による富の獲得は肉体的差によって男を有力にした。次第に共同体内の富が男に集中しはじめた。そのことは女性の無産化をさらに無力化をもたらした。さらに女性の商品化・物化がなされ、妻の多少がその男の優劣を示すようにさえなった。ここに奴隷化が開始されるのである。家父長制への転回である。女性は一方では父系の純血を守るために夫のもとに閉鎖され、他の男との交通を断ち切り、子産み奴隷と化し、他方では自由な男女間の交通を拒絶された男のために、儀制恋愛のための公娼制が作られ、女性は売買される性的奴隷に転化した。
■ 江戸時代は、このような家父長的夫婦関係を固定化するために、ずいぶんと多くの「女訓書」「女大学」が出された。姦通は妻にとっては死を意味した。貞女であることが求められた。女性のための教育というよりは、男性の都合によって、勝手に書かれているようなものだった。
■ 明治維新はその性格から一時的、部分的に女性の解放に向けての政策がとられたが、次第に別な形で合理化され、良妻賢母型へと変形せられた。明治維新には「四民平等」のかけ声はあったが、それは天皇の下での赤子としての平民の平等でしかなかった。あくまでも部落差別身分はあり、女性の奴隷的身分は厳然として存した。維新はそもそも内外における徳川権力の崩壊的危機を迎えての、封建的支配層が一定の自己の階級の犠牲を我慢して、基本的に延命を計る方向での変革であった。これまで表面に出ていなかった天皇を担ぎ出しての江戸末期の封建領主階級防衛のための体制であった。
たとえば一旦発布された江藤新平による民法も、旧来の日本的家父長制・家族制と対立し、当時の学者間に喧々囂々の論争を巻き起こし、引っ込められた。結局あらためて江戸期の家族法、武家法と対立させない新民法を明治31年(1898)に発布したのである。ここでは女性の位置はあくまでも家父長権の下にあり、子女を売り飛ばそうと、殺そうと何らかまわないという状態下におかれた。
■ それでも開明的な官吏の子女や豪農の子女は西欧の家族制や女性のあり方に影響され、日本での女性解放闘争に立ち上がっていった。
■ 西欧では資本主義の発展自身が中世的な女性束縛を解き放していった。すなわち機械制生産の開始は女性の安価な労働力を迎え入れるのに熱心であり、これを阻む家族制を打ち壊さなければならなかった。資本主義の発達は女性の資本主義的自由=ブルジョワ的自由を拓いたのである。一方日本の資本主義の発達はそうではなく、逆に家父長制と深く結びついていたといえる。日本産業革命の花形繊維産業は寄宿舎制という囚人労働的労使関係の中で発展したのである。それは政府の農政と寄生地主制によって、とことん疲弊された小作・小自作の生きる道を家父長権による子女の売り飛ばし=繊維女工を不断に作り出したのである。ここに日本資本主義と家父長制の呼吸はぴったりと合うのである。
■ 第二次世界大戦は日本女性の社会的労働への進出を圧倒的に促進した。基幹労働力は前線へ送られ、女性がそのあとを補ったのである。これは画期的であった。もはや日本資本主義自体がその危機の故に女性を古い家庭に縛り付けておくことができず、社会に引きづり出したのである。このことは第2次世界大戦敗戦後の女性の圧倒的前進の基礎を形成したといえよう。敗戦を機として、女性解放のエネルギーはほとばしり出た。女子参政権―戦後第1回の選挙での39人の女性議員選出。売春防止法―公娼廃止のたたかい。労働組合での女性のたたかい。そして何よりもあらゆる職場への女性の進出である。
■ ここに女性にとっての最大の矛盾が待ち受けていたといえる。ここに家族制と女性の社会的進出の激突が現れ出たのである。旧来の家族制を打ち倒すか? それとも女性を家庭に戻すか?
■ まづ、資本の論理は貪欲にも労働力を男女を問わず労働力として要求することから現れてきた。すなわち母子問題を解決するのか、否かである。女性はたたかった。すでに資本主義は婦人労働力を社会的に要求していた。もはや後戻りはできない。資本主義は最小限において母体を社会の名において解決=保護しなければならなかった。さらに、「足手まとい」の子どものために、託児所や保育所の設置が必要となった。これらの施設も資本主義化されることによって、全婦人労働者の保護には遠くおよばず、常に社会問題化している。
■ さらに巨大な衝突は家族制と女性の社会化との正面衝突にある。今日においても結婚のことをよく「永久就職」という。結婚において女性に求められていることは家事労働である。男性は男性であるということだけから、家事労働から解放されている。女性が家の外で労働する必要のない時代には、問題は起こらなかった。共稼ぎの時代になって、すなわち女性が社会的に進出したときに、はじめて問題化したといえよう。共稼ぎの女性は外の労働と家事労働の二重の重圧を受けねばならなくなったのである。夫は帰宅しても翌日の労働のために十分にその力を回復することができる。しかし、女性にとっては外の労働を間に挟んで、その前には夫を送り出し、子どもを送り出さねばならない。そのあとには、夜中まで、くたくたになるまで家族のために働かねばならない。休日は体を休ませるどころか、平生できない家事労働に送らねばならない。ここにおいて女性は女性であるが故に、二重の重圧を受けねばならない。
■ では、何に解決を求めねばならないのか? ヒントは原始の母系制氏族制にあるだろう。夫婦単位の家族制こそその根源である。母系氏族制では財産、労働、個人はそれぞれの氏族に属していた。氏族共同体が統一的にその社会生活を運営していた。母性の保護の必要なときは産屋が作られた。子どもの養育は氏族共同体の責任でなされた。誰かに矛盾が集中することのないようになされた。あくまでも共同体的であった。原始共産制であった。
■ 著者は最後のページに近づくにしたがって革命の問題を曖昧化させている。いかにも革命が向こうから歩いてやってくるかのような表現をとっている。非常に残念だ。方法としては革命の必然性(女性問題から)を語り、女性解放はプロレタリア革命によってのみ貫徹されるとしながらも、生き生きとした革命への招待を提起していない。
~~~~~~~~~読書メモ~~~~~~~~~~~~~~~~
この本がこんなにも膨大なものだとは思いもしなかった。高群逸枝氏が女性解放の先駆者であるということを聞いて知っていただけであった。たまたま「朝日新聞」にこの本の紹介があったので、兄の手を煩わして入手した。手元に置いてみると、なんと1200ページにものぼる大著である。これだけでもう、僕は圧倒されてしまった。メモなしに、サッサと理解できるだろうとタカをくくって読み始めるや、デッドロックに乗り上げてしまった。あとになって、「あの本には何が書いてあったのだっけ」と首をかしげなくてもいいように、メモを残しておくことにした。
この著書全体にかける著者の意図は原始の母性我的な母権社会から男性の個人我による父権社会を経て、次に新しい社会を切り拓く現在および未来への歴史を述べることにある。
女性問題は単に女の性のみの問題ではなく、母・子問題としてとらえねばならない。今日の女性問題は常に母子問題として顕現してきているのもそれを示す。女性にとって性の問題が常に妊娠・出産・育児の問題として現れてきているからである。だから女性問題は女の問題に限られることなく、その社会全体の中で位置づけられねばならない。
第1章 「女性が中心となっていた時代」
まづ、女性が中心となっていた時代の展開が述べられている。
日本は遠い昔の母権性社会がどのようであったかを調べるのに非常に好都合な国である。有形無形の民族性・風俗・習俗・等に古い昔の名残がずいぶんと多く残されているのである。ユダヤ神話、インド神話と比べてみると、日本神話は年代的に最も新しいものであるが、内容的には最も原始的である。日本神話は明らかに母系・母権社会を反映しており、他の二つの神話は父系・父権社会のものであることは疑えない。日本神話はその中で女性=太陽としているし、他の国々においては男性=太陽となっているものが多い。インド神話もそうであり、ギリシャ神話のアポロン、中国周時代にはすでに夫=日、妻=月という観念が定着している。
では原始時代の社会を見ていこう。原始時代には家庭はなかった。
まづ縄文時代について
この時代は世界史的には新石器時代であるが、生産関係はきわめて低級で、旧石器もしくは中石器の時代の生活をしていたと考えられる。この時代の前期は定住しておらず、農耕も開始されてはいない。数十名が一群となって、あっちこっち放浪していたと考えられる。一群が大きくなると、二群に分かれ、二度と相まみえることもなかったであろう。婚姻の方式は群内婚であったと考えられる。だが次第に母子間の禁婚、さらには同母兄妹間の禁婚の傾向が進行するにしたがい、通婚圏が狭まっていく。あくまでも母を中心にした共同体であり、母性崇拝が普通にあったであろう。これが後に、母系氏族結成へと進化するのである。
縄文後期にいたって、定住し始め、集落を作り始める。だがまだ農耕は始められてはいない。定着化傾向は防衛的な意味で、群が分岐しても、遠くへ行ってしまうことなく、むしろ族的な結合がおこなわれる。群内婚の狭まりと自群内での婚姻の禁止により、分岐群との間での群婚が開始される。甲群の全男子が乙群の全女子と夫婦であり、甲群の全女子と乙群の全男子が夫婦である。分岐群が増加するに従い、通婚圏が拡大し、自群以外の男女とならどの分岐群の男女とでも連帯的通婚関係を持つ。
生まれた子どもは常に母の群に属す。母系制度の端緒である。ここにおいて二つ以上の群が集落をなして暮らすようになった。
弥生時代はどうであろうか?
BC2・3~AC3・4の時期である。農耕が開始され、機織り、磨製石器、巨石文化、鉄器なども出てくる。この時代は男性は狩猟や沖に出ての漁をおこない、女性は農作などをおこなっていたと見られる。女性は精神的にも物質的にも社会の背骨をなしている。母系氏族性が開始されるのである。となりの先進国周や漢(BC2)の影響を受けるようになる。だが日本はまだ国家的なものはなく、多数の氏族が存在していたに過ぎない。すなわち一区域の分岐群がたくさん集結して一大血縁圏をなしているのである。
婚姻関係はどうであろうか?
このころの住居は夫婦単位のものではない。生まれた子は原則として女性のところで成長したのであり、父は父の母系の一族と暮らし、子はこの母系の一族と生活したのである。妻問婚といわれるものである。古くは婿は夜だけ妻のもとに通っていたが、時によると「住み」といって、2,3日泊まり込んだり、もっと長く滞在したりするようになる。
氏族制は一定の組織を持ち、運営していかねばならないので、共同の核心としての祭祀というものが大きな役割を持つようになる。以前からの母性崇拝がいっそう際立ってきて、特定の母祖神崇拝となる。本家の群の姫と彦がその氏族の政治を司るようになる。
群や氏族にあっては総体として原始的環境は決して恵まれたものではなかった。しかし母子保障の面ではそれは恵まれていたといえる。群や氏族は連帯責任をもって母子たちを文句なしに保障したからである。そこには妊婦にとっては非常な安心感があり、だからこそそこには無痛分娩があり得たであろう。母系社会では母となる娘や母となった女性のために月経小屋や産屋の設備があり、女性たちがそのような共同小屋に入っている期間中は、その生活は氏族やその連合が保障する。生まれた子に対しては、その監護から扶育まで、これもすべて氏族やその連合の責任に帰していた。
一方後代の父権制社会においては月経や出産・育児における共同施設や共同保護はまったく見られない。
古墳時代(AC4~7)はどうであろうか?
各氏族は連合し、闘争し、侵略しあう。よって、族長の経営能力が氏族の盛衰に強くひびく。この時代の庶民の住居はまだ竪穴式である。婚姻関係は依然として妻問婚であり、夫婦は別居している。一生に一婿と決まっているわけでもない。このころになって母子小家族というものが若干はっきりしてきている。息子、娘が成長すれば、母の妻屋には常駐せず、息子は若者小屋へ、娘は別の妻屋へゆく。
このころの政治はどうか?
戦争の関係で、族長の能力が問われるや、男酋長の重要性が増してくる。しかし、一般の人民大衆はまだ女性の首長に執着しているといえる。男性の天皇が即位しても乱が治まらず、女性の天皇が即位すると治まるということがたびたび現れている。
卑弥呼のころはその弟を助力者として複式酋長制をとっていた。石器時代は姫中心の姫彦制、古墳時代には彦中心の姫彦制、古代天皇制の初期には姫彦交立の体制であった。
わが国の古代天皇制は男性君主独臨の形態としては開始されず、男女交立の形をとっている。推古女帝(592年~)から称徳女帝(~770年)までのほぼ2世紀の間は、なお姫彦交立という形態の上に姫彦制が投映されていた。姫彦制はすなわち女治制である。母権制ともいえる。
前に、「妊産婦が氏族制度そのものによって十分に保護されている」と書いた。では、今日の一夫一婦制の家庭ではどうであろうか? 妊婦を対象としての性交が要求され続けている事実がある。ここでは妊婦の性器がしばしば自然の機構から分離して解釈されねばならない現状におかれている。すでに受胎が完了しているにもかかわらず、その入口だけで受胎以前の行動がおこなわれている。これはなんとしても反自然的である。では一夫一婦制がいいか? 男女の数がほぼ同数であるからそれはまた反自然である。公娼制、私娼制がいいか? これは性の商品化であり、許すことはできない。正しい男と女の関係ではない。
原罪は何処にあるのか?
家庭制度にあるのである。「女が家庭制を超えて真の意味での雌としての色情に目覚めたとき、そしてその上さらに母としての愛をも兼ね持ったときにはじめて緩和されることであろう」と著者は答える。問題は提起されている。だがまだ決定的な回答は与えられていない。残された1000ページの中に展開されているのだろうか? きわめて楽しみな読書である。
第2章 「女性の地歩はどんな具合に後退したか」
『女性の歴史』ようやく第2章「女性の地歩はどんな具合に後退したか」を読み終えた。いよいよ複雑になり、日本史は中学校のころから嫌いだった僕にはずいぶんと骨の折れる仕事になってきた。
ここでは大化(BC7)ごろから鎌倉(BC13ごろ)時代の女性史を展開しており、母系制の崩壊しつつある姿を描き、家父長的私的所有の発生の端緒を述べている。
著者は世界史的な支店から未開社会の次に登場する文明社会(古代)に照準を合わせ、エンゲルスを引用しながら一般論を展開する。原始時代は一人の人間の生産力は一人の人間の消費量しかなく、共同生活で精一杯であり、貧富の差が生まれる余地はない。道具や技術の発展によって一人の人間の生産力が一人の人間の消費量を上回る物質を生産するようになる。他の者に働かせることによって自分の生活を保持できる者が出てくる。生産力の向上はその源泉である労働力をより多く求める傾向を生み出す。戦争は戦利品として労働力をもたらす。奴隷制の開始である。同時に剰余生産は商品交換をもたらす。交換の中に価値を見いだす。
これまでの血縁的人間関係(共同体的相互扶助関係)は破壊され、新たに富・利益を中心とした人間関係に入る。
奴隷の中で、特に女奴隷はどうであったであろうか? 男奴隷に比してきわめて性的傾向の強いものである。①普通に生産する奴隷として、②男の性欲を満たすための奴隷として、③奴隷を生産するための奴隷として、三重の奴隷の役割を果たした。
奴隷制の確立は自由な女の地位を低下させた.家庭に監禁されているという形で、身柄を拘束され、奴隷的地位に転落した。妻という形で「跡継ぎ」を生産するというだけの役割である。
次の時代の農奴制における女性は相変わらず父権・夫権の下に拘束されており、奴隷的境遇にあった。
その次の近代においてはどうか?
女性は一応身分的に自由になり、自由恋愛結婚も可能になった。他方では「自由」によって身の切り売りとしての私娼制が登場した。賃金奴隷としての夫が失業するや、その妻と子は路上に投げ出される。共稼ぎは妻に外での仕事と内での家事を二重に負わされ、常に女性に矛盾が集中するようになっている。
我々が普通に「古代」と呼んでいる大化~南北朝のころの期間は婚姻制や家族制は決して完全な「古代」のそれではない。むしろ半ば「原始」のそれ(原始的対偶婚・夫婦別居・別産制)を留めている(生産段階が原始の農耕段階にとどまっているからである)。わが国の婚姻制や家族制が古代ギリシャやローマのものと一致し、女性が「古代」的な奴隷の段階に入るのは室町時代以降においてである。「古代」において、日本の女性は男子同様に財産権を持ち、氏族に保障されていた対偶婚である(「岩波国語辞典」:対偶とは二つそろったもの、対、夫婦という意味)。氏族制は崩壊しつつあるとはいえ、崩壊したわけではない。
私有財産について
世界史的には私有財産は男性にのみ見られる。原始の分業は自然発生的で、両性間にのみ見られる。男は戦争、狩猟、漁労そしてそれらに必要な道具を作る。女は家事、衣食、紡織、裁縫。両者には優劣は見られず、各領域で主人であった。ところが男性が牧畜を発明し、最初の大きな社会的分業に発展する。次いで、牧草栽培そして穀物耕作を、やはり男が発明する。これらは労働力の多い方が有利性を持つ故、戦争による俘虜を奴隷化する。貧富の差が生まれ、二階級に発展する。
日本ではどうだったのか?
私有財産は男にも女にも発生したのである。自然物採取における男女間の分業は、男は狩猟、女は漁労(日本の海女などに典型的)。次いで農耕時代では、農神がすべて女性である。農業神事はすべて女性が司っているように、農業は女性が主体であった。女性が農業において主体であったことが女性を家内労働に専門化させなかった。織物部門=秦部(ハタベ)、服部(ハトリベ)、育児=託児所的な伴部(トモベ)がおかれたり、乳母・子守の制度があった。すなわち共同体内の家内労働を伴部によって充てる制度が生まれている。
室町以降になって、中国の思想の影響により「男は外、女は内」というのがはっきりしてきた。とはいえ、主として都会での官吏、武家、商人らの家でのことであり、農家には浸透せず。
世界史的には、男の飼う家畜が最初の貨幣となり、それは商業が主に男によって担われたことを示し、富は男に集中していった。そして、それが家父長制的私的所有の基礎をなすのである。
一方、日本では販女(ひさめ)、市女(いちめ)などと女性の商業活動が最初から見られる。だから当時の女は男と同じようにみずから財産を作り、親や他人から相続し、所有していたと見られる。太古から鎌倉末ごろまでは女性は男性とならんで直接生産者であり、かつ財産権を分有していたと思われる(氏族的共有制の枠内での分割的私有である)。
婚姻関係について
この期には嫁取り婚は現れず。婿通い、婿住みの招婿婚が支配的で、きわめて離婚が容易な不安定な夫婦関係であった(源氏物語などを思い出せばよい)。夫の氏族や家族の中に妻や妻が産んだ子が入り込み同居して暮らすことは原則的に禁忌されていた。
奴隷の所有について
氏族間の戦争は勝者が敗者を貢納隷民としての部民(べのたみ)に転化した。部民は儀制氏族として扱われ、勝者氏族の共有という形をとる。後になって私産現象が始まると、女性は男性と同じように所有者になることができた。部民は後に奴婢として本格的な奴隷になっていく。戸主に奴隷がなく、その母にのみあるということもたびたびあり、女性が奴婢を所有していることはきわめて普通であった。
土地の所有についても上記とあまり変わらない。
墓地について
室町中期ごろまでは、夫は夫の氏族の共同墓地に、妻は妻の氏族の共同墓地に引き裂かれて葬られた。このことは家族(夫婦)は生計の組織単位でないことを示す。夫婦で共同の財産を作るのではなく、それぞれの属する氏族に財産がおかれたのと同じ傾向である。
離婚について
夫婦が離婚しても、二人の間に生まれた子への権利・義務は基本的に母にあった。後の時代には、これが逆転し、子への権利は父が握り、後妻がその子の母となる。
氏族制と家族(夫婦)的結合は相容れないものである。氏族的結合の強いうちは、家族的結合はいつでも二分裂する要素を持つ。それ故婚姻制は対偶婚がとられる。生活組織としての氏族組織がしっかりしているので、離婚しても生活は安定している。
オヤについて
初期においては、「オヤ」とはその氏族内の年長者をさす。「コ」は少壮年齢者のことをさす。また一般成員も「コ」という。
上古の時代は母は「イロハ」と呼ばれる。息子は「イロセ」、娘は「イロモ」という。父を表す古語は現れていない。
大化前後からは、母子小家族が見られる。生計の単位も大家族(共同体)から小家族へ置き換える傾向にあり、このころの世帯主は母である。母=「オヤ」という現象が現れる。父をいうときは「母父」「父母」と並べていう。
平安ごろになって、父=「タラチネ」、母=「タラチメ」が定着してくる。以上のように父と母の関係・呼び方の中にも歴史が見られる。
最後に、
中国の律令制における女性の地位と日本古代天皇制のそれとの比較について、
①唐令では寡婦を除けば女性に班田しない。遺産の相続権も女子にはない。これは日本と違っている。
②唐律では兄妹婚は絞首刑、日本では父系の兄妹婚は許されている。
③中国は家父長制段階の嫁取り婚(一夫一婦、一夫多妻)、日本では氏族制段階の婿取り婚(対偶婚)、
④律令では結婚前の私通は禁、日本では当時恋愛こそすなわち結婚であった。
⑤律令には有夫の妻の姦通罪、日本では無意味であった。
⑥律令には離縁状をやって追放を規定、日本では無宣告の離婚。
以上のように律令制の女性観は隋唐的家父長段階の女性観の直輸入だったので、わが当時の俗とは根本的に相容れないものがあった。
平安女性の文学について
文学全体がいはゆる「もののあはれ」ともいうべき母性我的世界観によって作られている。あたたかな血縁的な見方で、人事や自然の一切のあり方を見ている。それは主観の極致をあらわし、冷徹な客観と一脈通通づるものがある。この意味の文学は平安をもって終わり、鎌倉で凋落した。この後、わが国の女性は二度とこんな高さに生きたことはない。
1975年9月 金沢市田上公1にて
今、島田清次郎の論考「婦人参政権論者の幻滅―最近のパンカースト夫人」(1923年2月『婦人公論』)を読んでいる。この論考を理解するためには、高群逸枝の『女性の歴史』から学び直さねばならないと思い、約50年前の20歳代後半に書き殴った書評を引っ張り出した。
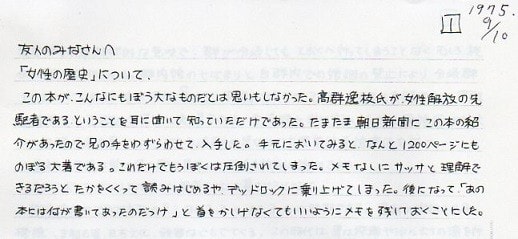

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
読後感想のまとめ
■ 明治の女平塚らいてうは「元始女性は太陽だった」と叫んだ。しかしその本当の理解は後の研究に待たねばならなかった。日本では、原始から古代に至るまで、母系氏族制が主だった。人間にとって自然が最も巨大な敵であった。まだその生産力は低く、分業として原始的な男と女による性的な分業であった。それぞれの分野で、それぞれが主人であり、とりわけて優劣はなかった。女性は共同体維持の中心となり、妊娠・出産・育児は共同体全体にとって神聖不可侵であった。女性は何ら不安なく出産・育児に心をかけることができた。女性にとって、孤立感を抱く必要はさらさらなかった。
■ 生産力の向上は農耕・牧畜からなされた。私有財産がここで生まれた。西欧では有史以前から始まり、男に富が集中した。ここから家父長制が生まれた。女性は奴隷化された。古代ギリシャに典型的に見られる。日本では、西欧と違い、私的所有は男女それぞれにあった。夫婦とはいえ、基本的に別居であり、別産であった。それぞれは別の経済単位=氏族共同体に属していた。だが、ここでも生産力の向上は新しい体制を求めていた。氏族間の戦争、下克上の力による富の獲得は肉体的差によって男を有力にした。次第に共同体内の富が男に集中しはじめた。そのことは女性の無産化をさらに無力化をもたらした。さらに女性の商品化・物化がなされ、妻の多少がその男の優劣を示すようにさえなった。ここに奴隷化が開始されるのである。家父長制への転回である。女性は一方では父系の純血を守るために夫のもとに閉鎖され、他の男との交通を断ち切り、子産み奴隷と化し、他方では自由な男女間の交通を拒絶された男のために、儀制恋愛のための公娼制が作られ、女性は売買される性的奴隷に転化した。
■ 江戸時代は、このような家父長的夫婦関係を固定化するために、ずいぶんと多くの「女訓書」「女大学」が出された。姦通は妻にとっては死を意味した。貞女であることが求められた。女性のための教育というよりは、男性の都合によって、勝手に書かれているようなものだった。
■ 明治維新はその性格から一時的、部分的に女性の解放に向けての政策がとられたが、次第に別な形で合理化され、良妻賢母型へと変形せられた。明治維新には「四民平等」のかけ声はあったが、それは天皇の下での赤子としての平民の平等でしかなかった。あくまでも部落差別身分はあり、女性の奴隷的身分は厳然として存した。維新はそもそも内外における徳川権力の崩壊的危機を迎えての、封建的支配層が一定の自己の階級の犠牲を我慢して、基本的に延命を計る方向での変革であった。これまで表面に出ていなかった天皇を担ぎ出しての江戸末期の封建領主階級防衛のための体制であった。
たとえば一旦発布された江藤新平による民法も、旧来の日本的家父長制・家族制と対立し、当時の学者間に喧々囂々の論争を巻き起こし、引っ込められた。結局あらためて江戸期の家族法、武家法と対立させない新民法を明治31年(1898)に発布したのである。ここでは女性の位置はあくまでも家父長権の下にあり、子女を売り飛ばそうと、殺そうと何らかまわないという状態下におかれた。
■ それでも開明的な官吏の子女や豪農の子女は西欧の家族制や女性のあり方に影響され、日本での女性解放闘争に立ち上がっていった。
■ 西欧では資本主義の発展自身が中世的な女性束縛を解き放していった。すなわち機械制生産の開始は女性の安価な労働力を迎え入れるのに熱心であり、これを阻む家族制を打ち壊さなければならなかった。資本主義の発達は女性の資本主義的自由=ブルジョワ的自由を拓いたのである。一方日本の資本主義の発達はそうではなく、逆に家父長制と深く結びついていたといえる。日本産業革命の花形繊維産業は寄宿舎制という囚人労働的労使関係の中で発展したのである。それは政府の農政と寄生地主制によって、とことん疲弊された小作・小自作の生きる道を家父長権による子女の売り飛ばし=繊維女工を不断に作り出したのである。ここに日本資本主義と家父長制の呼吸はぴったりと合うのである。
■ 第二次世界大戦は日本女性の社会的労働への進出を圧倒的に促進した。基幹労働力は前線へ送られ、女性がそのあとを補ったのである。これは画期的であった。もはや日本資本主義自体がその危機の故に女性を古い家庭に縛り付けておくことができず、社会に引きづり出したのである。このことは第2次世界大戦敗戦後の女性の圧倒的前進の基礎を形成したといえよう。敗戦を機として、女性解放のエネルギーはほとばしり出た。女子参政権―戦後第1回の選挙での39人の女性議員選出。売春防止法―公娼廃止のたたかい。労働組合での女性のたたかい。そして何よりもあらゆる職場への女性の進出である。
■ ここに女性にとっての最大の矛盾が待ち受けていたといえる。ここに家族制と女性の社会的進出の激突が現れ出たのである。旧来の家族制を打ち倒すか? それとも女性を家庭に戻すか?
■ まづ、資本の論理は貪欲にも労働力を男女を問わず労働力として要求することから現れてきた。すなわち母子問題を解決するのか、否かである。女性はたたかった。すでに資本主義は婦人労働力を社会的に要求していた。もはや後戻りはできない。資本主義は最小限において母体を社会の名において解決=保護しなければならなかった。さらに、「足手まとい」の子どものために、託児所や保育所の設置が必要となった。これらの施設も資本主義化されることによって、全婦人労働者の保護には遠くおよばず、常に社会問題化している。
■ さらに巨大な衝突は家族制と女性の社会化との正面衝突にある。今日においても結婚のことをよく「永久就職」という。結婚において女性に求められていることは家事労働である。男性は男性であるということだけから、家事労働から解放されている。女性が家の外で労働する必要のない時代には、問題は起こらなかった。共稼ぎの時代になって、すなわち女性が社会的に進出したときに、はじめて問題化したといえよう。共稼ぎの女性は外の労働と家事労働の二重の重圧を受けねばならなくなったのである。夫は帰宅しても翌日の労働のために十分にその力を回復することができる。しかし、女性にとっては外の労働を間に挟んで、その前には夫を送り出し、子どもを送り出さねばならない。そのあとには、夜中まで、くたくたになるまで家族のために働かねばならない。休日は体を休ませるどころか、平生できない家事労働に送らねばならない。ここにおいて女性は女性であるが故に、二重の重圧を受けねばならない。
■ では、何に解決を求めねばならないのか? ヒントは原始の母系制氏族制にあるだろう。夫婦単位の家族制こそその根源である。母系氏族制では財産、労働、個人はそれぞれの氏族に属していた。氏族共同体が統一的にその社会生活を運営していた。母性の保護の必要なときは産屋が作られた。子どもの養育は氏族共同体の責任でなされた。誰かに矛盾が集中することのないようになされた。あくまでも共同体的であった。原始共産制であった。
■ 著者は最後のページに近づくにしたがって革命の問題を曖昧化させている。いかにも革命が向こうから歩いてやってくるかのような表現をとっている。非常に残念だ。方法としては革命の必然性(女性問題から)を語り、女性解放はプロレタリア革命によってのみ貫徹されるとしながらも、生き生きとした革命への招待を提起していない。
~~~~~~~~~読書メモ~~~~~~~~~~~~~~~~
この本がこんなにも膨大なものだとは思いもしなかった。高群逸枝氏が女性解放の先駆者であるということを聞いて知っていただけであった。たまたま「朝日新聞」にこの本の紹介があったので、兄の手を煩わして入手した。手元に置いてみると、なんと1200ページにものぼる大著である。これだけでもう、僕は圧倒されてしまった。メモなしに、サッサと理解できるだろうとタカをくくって読み始めるや、デッドロックに乗り上げてしまった。あとになって、「あの本には何が書いてあったのだっけ」と首をかしげなくてもいいように、メモを残しておくことにした。
この著書全体にかける著者の意図は原始の母性我的な母権社会から男性の個人我による父権社会を経て、次に新しい社会を切り拓く現在および未来への歴史を述べることにある。
女性問題は単に女の性のみの問題ではなく、母・子問題としてとらえねばならない。今日の女性問題は常に母子問題として顕現してきているのもそれを示す。女性にとって性の問題が常に妊娠・出産・育児の問題として現れてきているからである。だから女性問題は女の問題に限られることなく、その社会全体の中で位置づけられねばならない。
第1章 「女性が中心となっていた時代」
まづ、女性が中心となっていた時代の展開が述べられている。
日本は遠い昔の母権性社会がどのようであったかを調べるのに非常に好都合な国である。有形無形の民族性・風俗・習俗・等に古い昔の名残がずいぶんと多く残されているのである。ユダヤ神話、インド神話と比べてみると、日本神話は年代的に最も新しいものであるが、内容的には最も原始的である。日本神話は明らかに母系・母権社会を反映しており、他の二つの神話は父系・父権社会のものであることは疑えない。日本神話はその中で女性=太陽としているし、他の国々においては男性=太陽となっているものが多い。インド神話もそうであり、ギリシャ神話のアポロン、中国周時代にはすでに夫=日、妻=月という観念が定着している。
では原始時代の社会を見ていこう。原始時代には家庭はなかった。
まづ縄文時代について
この時代は世界史的には新石器時代であるが、生産関係はきわめて低級で、旧石器もしくは中石器の時代の生活をしていたと考えられる。この時代の前期は定住しておらず、農耕も開始されてはいない。数十名が一群となって、あっちこっち放浪していたと考えられる。一群が大きくなると、二群に分かれ、二度と相まみえることもなかったであろう。婚姻の方式は群内婚であったと考えられる。だが次第に母子間の禁婚、さらには同母兄妹間の禁婚の傾向が進行するにしたがい、通婚圏が狭まっていく。あくまでも母を中心にした共同体であり、母性崇拝が普通にあったであろう。これが後に、母系氏族結成へと進化するのである。
縄文後期にいたって、定住し始め、集落を作り始める。だがまだ農耕は始められてはいない。定着化傾向は防衛的な意味で、群が分岐しても、遠くへ行ってしまうことなく、むしろ族的な結合がおこなわれる。群内婚の狭まりと自群内での婚姻の禁止により、分岐群との間での群婚が開始される。甲群の全男子が乙群の全女子と夫婦であり、甲群の全女子と乙群の全男子が夫婦である。分岐群が増加するに従い、通婚圏が拡大し、自群以外の男女とならどの分岐群の男女とでも連帯的通婚関係を持つ。
生まれた子どもは常に母の群に属す。母系制度の端緒である。ここにおいて二つ以上の群が集落をなして暮らすようになった。
弥生時代はどうであろうか?
BC2・3~AC3・4の時期である。農耕が開始され、機織り、磨製石器、巨石文化、鉄器なども出てくる。この時代は男性は狩猟や沖に出ての漁をおこない、女性は農作などをおこなっていたと見られる。女性は精神的にも物質的にも社会の背骨をなしている。母系氏族性が開始されるのである。となりの先進国周や漢(BC2)の影響を受けるようになる。だが日本はまだ国家的なものはなく、多数の氏族が存在していたに過ぎない。すなわち一区域の分岐群がたくさん集結して一大血縁圏をなしているのである。
婚姻関係はどうであろうか?
このころの住居は夫婦単位のものではない。生まれた子は原則として女性のところで成長したのであり、父は父の母系の一族と暮らし、子はこの母系の一族と生活したのである。妻問婚といわれるものである。古くは婿は夜だけ妻のもとに通っていたが、時によると「住み」といって、2,3日泊まり込んだり、もっと長く滞在したりするようになる。
氏族制は一定の組織を持ち、運営していかねばならないので、共同の核心としての祭祀というものが大きな役割を持つようになる。以前からの母性崇拝がいっそう際立ってきて、特定の母祖神崇拝となる。本家の群の姫と彦がその氏族の政治を司るようになる。
群や氏族にあっては総体として原始的環境は決して恵まれたものではなかった。しかし母子保障の面ではそれは恵まれていたといえる。群や氏族は連帯責任をもって母子たちを文句なしに保障したからである。そこには妊婦にとっては非常な安心感があり、だからこそそこには無痛分娩があり得たであろう。母系社会では母となる娘や母となった女性のために月経小屋や産屋の設備があり、女性たちがそのような共同小屋に入っている期間中は、その生活は氏族やその連合が保障する。生まれた子に対しては、その監護から扶育まで、これもすべて氏族やその連合の責任に帰していた。
一方後代の父権制社会においては月経や出産・育児における共同施設や共同保護はまったく見られない。
古墳時代(AC4~7)はどうであろうか?
各氏族は連合し、闘争し、侵略しあう。よって、族長の経営能力が氏族の盛衰に強くひびく。この時代の庶民の住居はまだ竪穴式である。婚姻関係は依然として妻問婚であり、夫婦は別居している。一生に一婿と決まっているわけでもない。このころになって母子小家族というものが若干はっきりしてきている。息子、娘が成長すれば、母の妻屋には常駐せず、息子は若者小屋へ、娘は別の妻屋へゆく。
このころの政治はどうか?
戦争の関係で、族長の能力が問われるや、男酋長の重要性が増してくる。しかし、一般の人民大衆はまだ女性の首長に執着しているといえる。男性の天皇が即位しても乱が治まらず、女性の天皇が即位すると治まるということがたびたび現れている。
卑弥呼のころはその弟を助力者として複式酋長制をとっていた。石器時代は姫中心の姫彦制、古墳時代には彦中心の姫彦制、古代天皇制の初期には姫彦交立の体制であった。
わが国の古代天皇制は男性君主独臨の形態としては開始されず、男女交立の形をとっている。推古女帝(592年~)から称徳女帝(~770年)までのほぼ2世紀の間は、なお姫彦交立という形態の上に姫彦制が投映されていた。姫彦制はすなわち女治制である。母権制ともいえる。
前に、「妊産婦が氏族制度そのものによって十分に保護されている」と書いた。では、今日の一夫一婦制の家庭ではどうであろうか? 妊婦を対象としての性交が要求され続けている事実がある。ここでは妊婦の性器がしばしば自然の機構から分離して解釈されねばならない現状におかれている。すでに受胎が完了しているにもかかわらず、その入口だけで受胎以前の行動がおこなわれている。これはなんとしても反自然的である。では一夫一婦制がいいか? 男女の数がほぼ同数であるからそれはまた反自然である。公娼制、私娼制がいいか? これは性の商品化であり、許すことはできない。正しい男と女の関係ではない。
原罪は何処にあるのか?
家庭制度にあるのである。「女が家庭制を超えて真の意味での雌としての色情に目覚めたとき、そしてその上さらに母としての愛をも兼ね持ったときにはじめて緩和されることであろう」と著者は答える。問題は提起されている。だがまだ決定的な回答は与えられていない。残された1000ページの中に展開されているのだろうか? きわめて楽しみな読書である。
第2章 「女性の地歩はどんな具合に後退したか」
『女性の歴史』ようやく第2章「女性の地歩はどんな具合に後退したか」を読み終えた。いよいよ複雑になり、日本史は中学校のころから嫌いだった僕にはずいぶんと骨の折れる仕事になってきた。
ここでは大化(BC7)ごろから鎌倉(BC13ごろ)時代の女性史を展開しており、母系制の崩壊しつつある姿を描き、家父長的私的所有の発生の端緒を述べている。
著者は世界史的な支店から未開社会の次に登場する文明社会(古代)に照準を合わせ、エンゲルスを引用しながら一般論を展開する。原始時代は一人の人間の生産力は一人の人間の消費量しかなく、共同生活で精一杯であり、貧富の差が生まれる余地はない。道具や技術の発展によって一人の人間の生産力が一人の人間の消費量を上回る物質を生産するようになる。他の者に働かせることによって自分の生活を保持できる者が出てくる。生産力の向上はその源泉である労働力をより多く求める傾向を生み出す。戦争は戦利品として労働力をもたらす。奴隷制の開始である。同時に剰余生産は商品交換をもたらす。交換の中に価値を見いだす。
これまでの血縁的人間関係(共同体的相互扶助関係)は破壊され、新たに富・利益を中心とした人間関係に入る。
奴隷の中で、特に女奴隷はどうであったであろうか? 男奴隷に比してきわめて性的傾向の強いものである。①普通に生産する奴隷として、②男の性欲を満たすための奴隷として、③奴隷を生産するための奴隷として、三重の奴隷の役割を果たした。
奴隷制の確立は自由な女の地位を低下させた.家庭に監禁されているという形で、身柄を拘束され、奴隷的地位に転落した。妻という形で「跡継ぎ」を生産するというだけの役割である。
次の時代の農奴制における女性は相変わらず父権・夫権の下に拘束されており、奴隷的境遇にあった。
その次の近代においてはどうか?
女性は一応身分的に自由になり、自由恋愛結婚も可能になった。他方では「自由」によって身の切り売りとしての私娼制が登場した。賃金奴隷としての夫が失業するや、その妻と子は路上に投げ出される。共稼ぎは妻に外での仕事と内での家事を二重に負わされ、常に女性に矛盾が集中するようになっている。
我々が普通に「古代」と呼んでいる大化~南北朝のころの期間は婚姻制や家族制は決して完全な「古代」のそれではない。むしろ半ば「原始」のそれ(原始的対偶婚・夫婦別居・別産制)を留めている(生産段階が原始の農耕段階にとどまっているからである)。わが国の婚姻制や家族制が古代ギリシャやローマのものと一致し、女性が「古代」的な奴隷の段階に入るのは室町時代以降においてである。「古代」において、日本の女性は男子同様に財産権を持ち、氏族に保障されていた対偶婚である(「岩波国語辞典」:対偶とは二つそろったもの、対、夫婦という意味)。氏族制は崩壊しつつあるとはいえ、崩壊したわけではない。
私有財産について
世界史的には私有財産は男性にのみ見られる。原始の分業は自然発生的で、両性間にのみ見られる。男は戦争、狩猟、漁労そしてそれらに必要な道具を作る。女は家事、衣食、紡織、裁縫。両者には優劣は見られず、各領域で主人であった。ところが男性が牧畜を発明し、最初の大きな社会的分業に発展する。次いで、牧草栽培そして穀物耕作を、やはり男が発明する。これらは労働力の多い方が有利性を持つ故、戦争による俘虜を奴隷化する。貧富の差が生まれ、二階級に発展する。
日本ではどうだったのか?
私有財産は男にも女にも発生したのである。自然物採取における男女間の分業は、男は狩猟、女は漁労(日本の海女などに典型的)。次いで農耕時代では、農神がすべて女性である。農業神事はすべて女性が司っているように、農業は女性が主体であった。女性が農業において主体であったことが女性を家内労働に専門化させなかった。織物部門=秦部(ハタベ)、服部(ハトリベ)、育児=託児所的な伴部(トモベ)がおかれたり、乳母・子守の制度があった。すなわち共同体内の家内労働を伴部によって充てる制度が生まれている。
室町以降になって、中国の思想の影響により「男は外、女は内」というのがはっきりしてきた。とはいえ、主として都会での官吏、武家、商人らの家でのことであり、農家には浸透せず。
世界史的には、男の飼う家畜が最初の貨幣となり、それは商業が主に男によって担われたことを示し、富は男に集中していった。そして、それが家父長制的私的所有の基礎をなすのである。
一方、日本では販女(ひさめ)、市女(いちめ)などと女性の商業活動が最初から見られる。だから当時の女は男と同じようにみずから財産を作り、親や他人から相続し、所有していたと見られる。太古から鎌倉末ごろまでは女性は男性とならんで直接生産者であり、かつ財産権を分有していたと思われる(氏族的共有制の枠内での分割的私有である)。
婚姻関係について
この期には嫁取り婚は現れず。婿通い、婿住みの招婿婚が支配的で、きわめて離婚が容易な不安定な夫婦関係であった(源氏物語などを思い出せばよい)。夫の氏族や家族の中に妻や妻が産んだ子が入り込み同居して暮らすことは原則的に禁忌されていた。
奴隷の所有について
氏族間の戦争は勝者が敗者を貢納隷民としての部民(べのたみ)に転化した。部民は儀制氏族として扱われ、勝者氏族の共有という形をとる。後になって私産現象が始まると、女性は男性と同じように所有者になることができた。部民は後に奴婢として本格的な奴隷になっていく。戸主に奴隷がなく、その母にのみあるということもたびたびあり、女性が奴婢を所有していることはきわめて普通であった。
土地の所有についても上記とあまり変わらない。
墓地について
室町中期ごろまでは、夫は夫の氏族の共同墓地に、妻は妻の氏族の共同墓地に引き裂かれて葬られた。このことは家族(夫婦)は生計の組織単位でないことを示す。夫婦で共同の財産を作るのではなく、それぞれの属する氏族に財産がおかれたのと同じ傾向である。
離婚について
夫婦が離婚しても、二人の間に生まれた子への権利・義務は基本的に母にあった。後の時代には、これが逆転し、子への権利は父が握り、後妻がその子の母となる。
氏族制と家族(夫婦)的結合は相容れないものである。氏族的結合の強いうちは、家族的結合はいつでも二分裂する要素を持つ。それ故婚姻制は対偶婚がとられる。生活組織としての氏族組織がしっかりしているので、離婚しても生活は安定している。
オヤについて
初期においては、「オヤ」とはその氏族内の年長者をさす。「コ」は少壮年齢者のことをさす。また一般成員も「コ」という。
上古の時代は母は「イロハ」と呼ばれる。息子は「イロセ」、娘は「イロモ」という。父を表す古語は現れていない。
大化前後からは、母子小家族が見られる。生計の単位も大家族(共同体)から小家族へ置き換える傾向にあり、このころの世帯主は母である。母=「オヤ」という現象が現れる。父をいうときは「母父」「父母」と並べていう。
平安ごろになって、父=「タラチネ」、母=「タラチメ」が定着してくる。以上のように父と母の関係・呼び方の中にも歴史が見られる。
最後に、
中国の律令制における女性の地位と日本古代天皇制のそれとの比較について、
①唐令では寡婦を除けば女性に班田しない。遺産の相続権も女子にはない。これは日本と違っている。
②唐律では兄妹婚は絞首刑、日本では父系の兄妹婚は許されている。
③中国は家父長制段階の嫁取り婚(一夫一婦、一夫多妻)、日本では氏族制段階の婿取り婚(対偶婚)、
④律令では結婚前の私通は禁、日本では当時恋愛こそすなわち結婚であった。
⑤律令には有夫の妻の姦通罪、日本では無意味であった。
⑥律令には離縁状をやって追放を規定、日本では無宣告の離婚。
以上のように律令制の女性観は隋唐的家父長段階の女性観の直輸入だったので、わが当時の俗とは根本的に相容れないものがあった。
平安女性の文学について
文学全体がいはゆる「もののあはれ」ともいうべき母性我的世界観によって作られている。あたたかな血縁的な見方で、人事や自然の一切のあり方を見ている。それは主観の極致をあらわし、冷徹な客観と一脈通通づるものがある。この意味の文学は平安をもって終わり、鎌倉で凋落した。この後、わが国の女性は二度とこんな高さに生きたことはない。