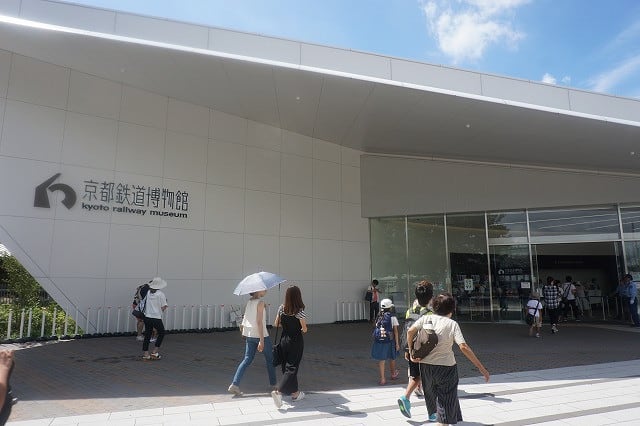京都鉄道博物館の本館に入りました。入ってまず出迎えてくれるのは500系、583系、489系です。博物館建造時にたまたま廃車になったことと車輪が8つ付いていることくらいしか共通点のない3者ですが、500系はともかく他の2台も何かしら功績を残しているんでしょう。
記念撮影には絶好の場所なので常に人だかりができています。まともに電車だけ撮影は不可能です。平日の閉館間際を狙いましょう。

あの3台は後で見るとして、まずはこれですよ、230形233号機。1902年製造開始の2-4-2配置の古典蒸気機関車です。
官設鉄道が汽車会社に発注して初めて国産化して量産化した蒸気機関車という肩書ですが、この頃はまだイギリスから輸入した蒸気機関車のパk・・・模倣でした。この頃の国産機関車あるあるです。これらの模倣、イギリスのメーカーの承諾は多分取ってないと思うんですけど、どうだったんでしょうね?

好ましい大きさで端正な造りの古典機です。好き。
よくぞ残っていたというところですが、幹線運用から退いた後、工場の入換機として生き延びていたところを価値が認められて保存となったようです。運が良かったのです。案外そんなものです。

みんな大好きネジ式連結器と緩衝器。これはブレーキ管が低い位置にあるのだなと。

シリンダー部。比較的単純な構造ですね。

動輪も2軸だしやっぱり単純。

後ろ。この時代の機体はライニングが良いのです。まだ蒸気機関車が珍しく1機1機が大事にされてたんだなと思わせます。

横から。弁天町から移される際に化粧直しされてきれいになりましたね。

ワット式複動蒸気機関の模型。ジェームス・ワットが発明した、蒸気機関の事実上の始祖と呼んでいい代物です。
蒸気機関自体はワット以前にもありましたが、ワット式はピストンの大幅な熱効率改善と円運動の発明が大きな特徴です。
ピストンと蒸気の冷却を別々に配置して熱効率を改善しました(ここらへんの構造は自分の中でよく噛み砕けてないのだが)。ピストンの熱効率が良いということは、エネルギーロスが少ないので低燃費であり石炭消費量は従来型の1/4になりました。
さらに、上下運動しかできないピストン運動をクランクシャフトを用いて円運動に変換することを可能にしました(発明当時クランクシャフトは特許技術だったので別の方法で代替したようだけど)。円運動が可能になったことで従来鉱山の排水用ポンプくらいにしか使い途のなかった蒸気機関は、紡績業を始めとした工業の動力や鉄道、蒸気船にその用途を拡大していき、まさに世界を変えていくことになるのです。また、これにより従来円運動を生むのに使っていた風車や水車は絶滅していくことになりました。
ロンドンの科学博物館にこれの実物大レプリカか本物があるはずなので、見てみたいものです。

ご存知ロコモーション号。世界で初めて乗客を乗せて走った蒸気機関車です。
シリンダーが垂直に配置されていて、それをあっちゃこちゃして車輪に伝えています。ボイラーの上は蜘蛛の足みたいな複雑さになっています。
これの実車は第一線から退いた後定置機関として使われてたんですが、保存されることが決まって復元されました。いまはどこかの博物館に保存されているはずです。

全国に19万人のファンを持つロケット号。世界初の鉄道人身事故の当該機として有名。
ロコモーション号と比較して、シリンダーの往復運動を連結棒で動輪に直接伝える方式にしました。これによりエネルギー効率が良くなりました。シリンダーもロコモーション号の垂直配置から斜めの配置になりました。ただしこれでは重心が高くて安定性に欠けるので、後に水平配置にして改善しています。
他にもボイラーにも改良が加えられてますが割愛(手抜き)
という風に以降の蒸気機関車設計の始祖となった機体なのです。
これもロンドンの科学博物館に保存されています。やっぱり行きたいですねぇ。

側鎖(マイルチェーン)という物差し。これ1つで20.1mで1チェーン。80チェーンで1マイル(1,600m)。明治時代の路線にはチェーンという単位が時々出てくるので覚えておいて損なし。

聖地新橋停車場。
ホームは1面2線ですが、左右に不自然な土地が有りにけり。これ、後々の拡張に対応していたのかしらね?この開業時の姿しか見たことないのでなんとも。
現在は跡地に新しく建て直された駅舎と線路数メートルが復元されています。よく汐留の再開発に飲み込まれずに済んだなと思います。

館内にもう1機いる古典蒸気機関車1800形1801号機。車輪配置は0-6-0で、これすなわち性能を牽引力に振った機関車です。
1880年官設鉄道大津~京都間開通の翌年にイギリスから輸入したもの。この区間にあった逢坂山隧道は急勾配でして、そのために用意されたのが1801号機でした。

動輪とか。
官設鉄道から引退後は高知鉄道、東レ滋賀工場の入換機として活躍。入換機には適した機体でした。東レから引退後に国鉄に寄贈されて戻ってきました。

みんな大好きネジ式連結器と緩衝器(2回目)。こっちは他の車両と連結状態ですね。

1801号機の後ろに連結されているのはマッチ箱客車の一部のレプリカ。たぶんハ1005。専門家いわくよく出来ているようだ。
こんなの今回の博物館に合わせて新しく造るはずないので(諦め)、交通科学博物館時代からの展示物だと思うんですが、うーん記憶にないですね・・・。

おおよそ全体の1/3の長さが再現されています。客室でいうと1区画と1/3。多扉車多コンパートメントというイギリス式の客車なのだということが分かります。
座面が畳敷きなのが日本らしく良いです。

ホコリを被っている線路。ちゃんと双頭レールなのか。

太湖汽船の第一太湖丸。官設鉄道の長浜駅と大津駅の間を結ぶ連絡船でした。

1928年製造の初の国産大型電気機関車のEF52形1号機。
国産化へ向けて機関車メーカー6社が一丸となって開発した機体です。東海道本線に投入されて、そこから退くと中央本線や阪和線などに転じて活躍しました。
というところで今日はここまで。