
2018年9月22日(土)7時43分
鹿児島県鹿児島市 HOTEL&RESIDENCE 南洲館
九州旅行4日目の朝です。旅館で朝ご飯を食べています。黒豚のしゃぶしゃぶや鶏飯などの郷土料理が提供されており、満足度が高いです。
今日は鹿児島市内の名所と桜島を回ろうと思います。

旅館を出て市電の通りまで出てきました。今日はいい天気ですね。

これから乗る観光周遊バスが来るまでの間、鹿児島市電(鹿児島市交通局)と路線バスを撮影します。
これは鹿児島市電1000形。

鹿児島交通のいすゞ・キュービック(#795) #7系統慈恩寺団地です。車体をよく見ると「民営」を強調していたり「赤字補填はありません 頑張ります!」と書かれていたり、なんだか異様なメッセージを出しています。なんだこれ。
鹿児島交通、というかいわさきコーポレーションについてはいい話が聞こえてこないですが、このブログでは深入りするのはやめときます。

鹿児島市営バスのふそう・MP38エアロスター(#1753) #11系統鴨池港。

第31走者:鹿児島市交通局カゴシマシティビュー(いすゞ・エルガ)天文館9:09→仙巌園9:49
鹿児島市内の観光名所を回る周遊バス「カゴシマシティビュー」に乗って仙巌園に行きます。奥の黄色いバス(LV290エルガ)の方です。

名所を回るのでさながらはとバスのようにバスに乗りながら観光地巡りができます。この建物は鹿児島市中央公民館です。
公民館には不釣り合いなただものじゃない威厳を感じ取れるこれは、1927(昭和2)年竣工の鹿児島市公会堂をルーツとする建築物なのです。昭和天皇のご成婚記念事業なんだとか(当時は大正13年なので皇太子)。片岡安の建築。
立派な近代建築である上にいまだ現役で使われている建物です。車窓からは他にもいくつかの近代建築が見え隠れしていて、鹿児島市ってもしかして近代建築物の宝庫なのでは?

これは”民営”の鹿児島交通が運行するまち巡りバス「せごどん号」です。日デ・スペースランナーRN+富士8E。よそ様向けのバスだからか、露骨な市営バス批判...もとい民営アピールはこれには書かれていないですね。
これもカゴシマシティビューと同じ観光地周遊路線バスです。運行経路もだいたい同じで、どちらも1日乗車券あり。ガチンコに競合しています。外から来た観光客にはややこしいんで一本化してほしいものですが、仲良くやる気はなさそうです。
使う人がどう動くかにもよりますが、カゴシマシティビューで使える1日乗車券だと他の市営バス路線と路面電車にも乗れます。なので私も市営バスの方を選びました。

バス停を降りてすぐに仙巌園に着きました。
仙巌園というのは1658(万治元)年に薩摩藩主の島津家が建てた別邸です。鹿児島湾と桜島を借景とした庭園が魅力。

園内に入るとまず石垣が目に入りますね。屋敷の跡か何かでしょうか。
庭園は後のお楽しみのようです。

屋敷じゃなくて反射炉の跡でした。1851(嘉永4)年に建造に着手したものです。
反射炉は、鉄を溶かして鋳造するための施設ですね。外国からの脅威に備えるための大砲、砲弾、船に鉄が必要になるので建てられたわけです。そういう国家防衛のための一連の事業および工場群が集成館というやつで、反射炉もその一部なわけです。

初めに建てた反射炉は崩れて失敗しちゃったので、続けて建てた2号炉が最初に実用化した物だそうな。1857(安政4)年のことでした。
明治時代に焼失してしまい、いまはこのように基礎だけ残っています。基礎だけだとあんまり構造がわからないですな。

正門です。1895(明治28)年築。大河ドラマ「篤姫」で登場。

まだまだ夏ですねー。

錫門、江戸時代の正門です。屋根は薩摩藩特産の錫の板になっています。島津家当主とその世継ぎしか通れなかったんですと。

磯御殿です。明治時代になると島津家はここに移り住むようになり、その居住地とした御殿です。

あれも磯御殿。二階建てだし窓ガラスがあるし、なんだかあそこだけ異空間。

んじゃ、上がらせてもらいましょうか。

廊下も畳敷きなのね。

壺です。間違い探しか何か?
ではなく、島津家当主がロシアのラストエンペラー、ニコライ2世の戴冠式の時に贈った壺の複製です。一対でひとつです。

ロシア皇帝の王冠の下にはニコライ2世の頭文字Hを象った模様。

縄の衣装がおしゃれだな~と思い写真に収めていました。
というところで今日はここまで。
その21へ→









































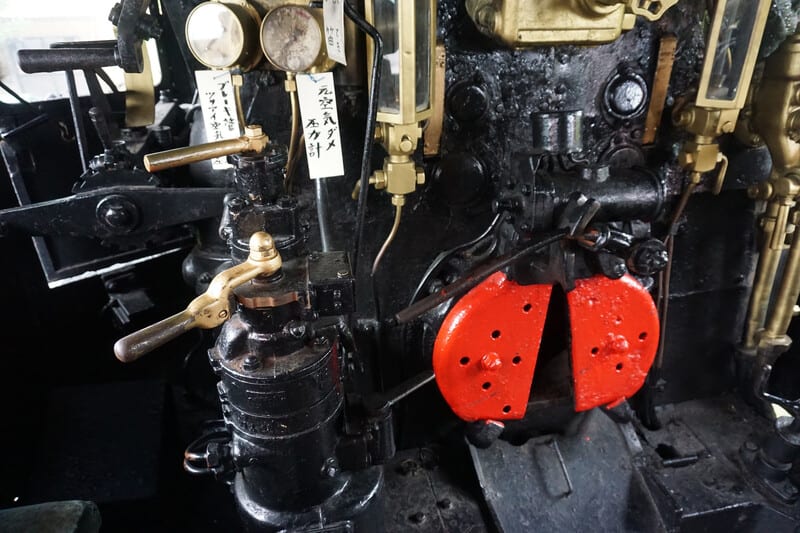






























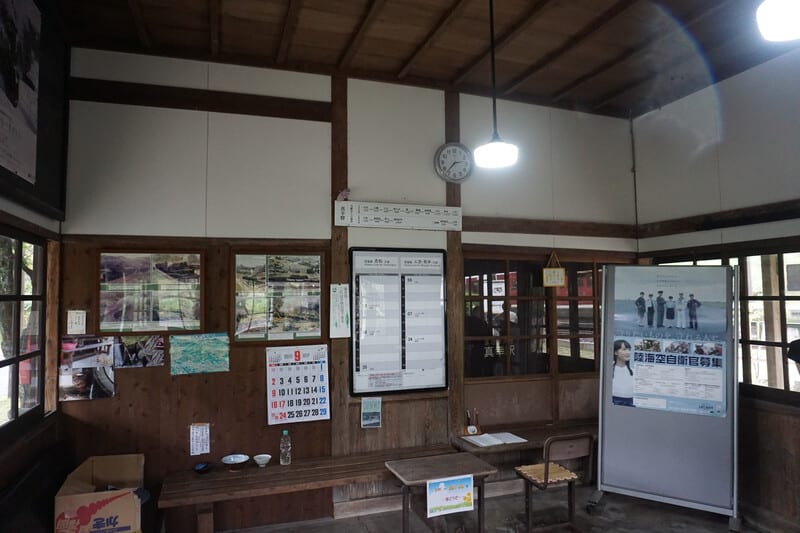






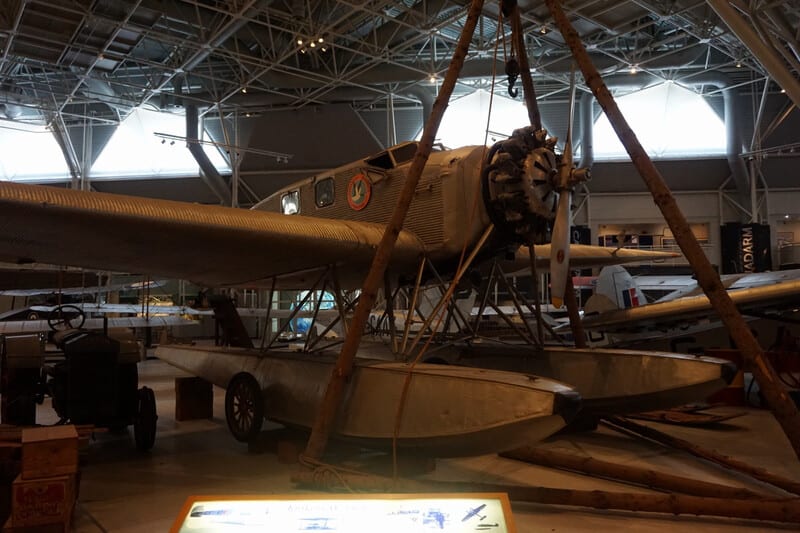








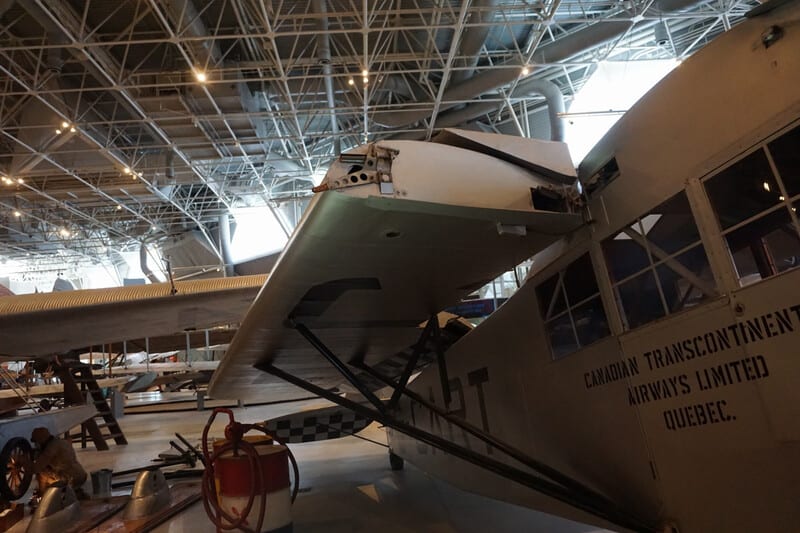




























![肥薩線 いさぶろう・しんぺい 人吉~吉松 往復 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/61AUqd2uEGL._SL160_.jpg)

![ayumi hamasaki 25th Anniversary LIVE(DVD)(スマプラ対応) [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/514YSkoWXdL._SL160_.jpg)
















































































