午後から、議員互助会主催の研修会。
テーマは「東日本大震災、緊急消防援助隊、大阪府隊として」
震災直後の3月13日から20日まで、岩手県釜石市・大槌町で救助・消火・救急活動に大阪の救援部隊の指揮をとられた堺市消防局の西川義久さんのお話をお聞きした。
赤や青・・・いろんな色の屋根が連なる「街」の風景が、ところどころに鉄筋の建物の残骸が残る一面土色の風景に変わる。
先日、ヘリコプターに乗って上空から見た、泉大津の町並みが重なって見える気がした。
一瞬にして、風景の「色」を塗り替えた津波の実相が、人々の声も入ったリアルな映像で映し出された。
「宮城県石巻市立大川小学校の全校児童108人のうち74人が死亡・行方不明」という悲劇。泉大津でもそうだが、学校は地域の避難所となっている。避難してきた市民と教員の間で議論しているうちに、移動開始が送れ、逃げ遅れたという。
また一方、岩手県釜石市では日頃の防災教育が生かされ、3000人近い小中学生のほとんどが無事に避難したのこと。校庭に出た子どもたちは、教師の支持を待たずに高台に向かって走りだし、中学生が小学生の手を引いて逃げた。
海に面し、沿岸部に近いところに小学校、中学校、保育所もある泉大津にとって、深い教訓としなければならないと思う。
防潮堤が、津波の被害を軽減させた効果もある一方、世界にも誇る「ギネス級の防潮堤」があることの安心感と、「3メートルの津波が来る」という情報とで「3メートルくらいの津波なら大丈夫」と、逃げ遅れた。これは「備えあれば憂いなし」の逆作用で「備え」がアダになってしまった。
一番の教訓は「地震が来たら高台へ。いち早く逃げること」を日頃から徹底しておくこと。そのことを、おとなも子どもも多くの市民の「常識」にすることだと思う。
きょうの研修会は、互助会役員会で私がテーマと「市民参加」ということも併せて提案し、ほとんどの会派の賛同があった。結果としてこれまでと同様、議員と幹部職員だけのものとなったが、多くの市民の皆さんに聞いて欲しい話、見て欲しい映像だった。
テーマは「東日本大震災、緊急消防援助隊、大阪府隊として」
震災直後の3月13日から20日まで、岩手県釜石市・大槌町で救助・消火・救急活動に大阪の救援部隊の指揮をとられた堺市消防局の西川義久さんのお話をお聞きした。
赤や青・・・いろんな色の屋根が連なる「街」の風景が、ところどころに鉄筋の建物の残骸が残る一面土色の風景に変わる。
先日、ヘリコプターに乗って上空から見た、泉大津の町並みが重なって見える気がした。
一瞬にして、風景の「色」を塗り替えた津波の実相が、人々の声も入ったリアルな映像で映し出された。
「宮城県石巻市立大川小学校の全校児童108人のうち74人が死亡・行方不明」という悲劇。泉大津でもそうだが、学校は地域の避難所となっている。避難してきた市民と教員の間で議論しているうちに、移動開始が送れ、逃げ遅れたという。
また一方、岩手県釜石市では日頃の防災教育が生かされ、3000人近い小中学生のほとんどが無事に避難したのこと。校庭に出た子どもたちは、教師の支持を待たずに高台に向かって走りだし、中学生が小学生の手を引いて逃げた。
海に面し、沿岸部に近いところに小学校、中学校、保育所もある泉大津にとって、深い教訓としなければならないと思う。
防潮堤が、津波の被害を軽減させた効果もある一方、世界にも誇る「ギネス級の防潮堤」があることの安心感と、「3メートルの津波が来る」という情報とで「3メートルくらいの津波なら大丈夫」と、逃げ遅れた。これは「備えあれば憂いなし」の逆作用で「備え」がアダになってしまった。
一番の教訓は「地震が来たら高台へ。いち早く逃げること」を日頃から徹底しておくこと。そのことを、おとなも子どもも多くの市民の「常識」にすることだと思う。
きょうの研修会は、互助会役員会で私がテーマと「市民参加」ということも併せて提案し、ほとんどの会派の賛同があった。結果としてこれまでと同様、議員と幹部職員だけのものとなったが、多くの市民の皆さんに聞いて欲しい話、見て欲しい映像だった。













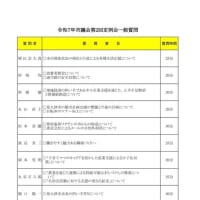





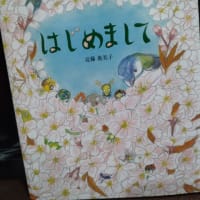






本当にそうですね。
それで普通だと思います。
私も7月に岩手に行ったとき、被災地を回っていて「もう見たくない」と思いました。
「自分の目で見ておかなければ」と思って行ったのに。
でも、今、やっぱり目をそむけずに見ることが、いつかやってくる「その日」に備えることになるのだと思います。
「目をそむけたくなる」その風景の、ただなかで暮らす岩手の方々が「大阪へ帰って少しでも、この現実を話してください」と言っておられたのも、忘れられません。