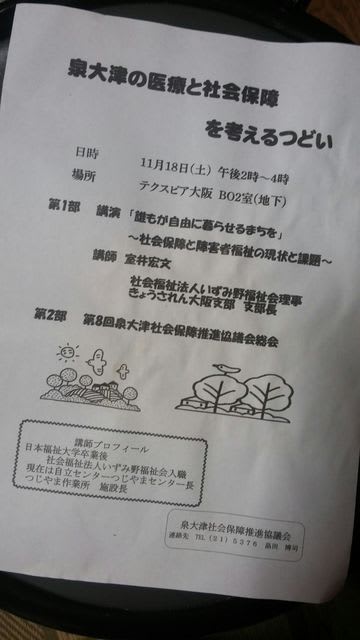要介護3以上でないと原則、特別養護老人ホームに入所できない。
現実には要介護2以下でも、在宅の暮らしが困難、不安な方はたくさんいる。
そんな中で、要支援認定に続いて、要介護1・2の在宅サービスを保険給付から外すことは論外。
開会中の議会に提出している意見書(案)。案文は以下の通りです。
要介護1・2の在宅サービスの「保険外し」中止、
介護保険制度の充実を求める意見書(案)
昨年5月に成立した「改正」介護保険法(地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律)の中で、「軽度」(要介護2以下)給付の総合事業への移行は、社会保障審議会の委員、事業者・職能団体などから強い批判の表明を受け見送られた。
しかし「次期以降の検討課題」と明記され、その後に示された財務省の財政制度審議会や内閣府の経済財政諮問会議の社会保障改革案では、介護保険の「要介護1・2」の240万人の在宅サービス(食事や入浴、排せつ、衣服の着脱などの日常生活の介助や、料理・選択などの生活援助)を保険給付から外す計画となっている。この計画どおりとなれば、要支援・要介護と認定されている人の実に65%が保険給付の枠外に置かれてしまうことになる。
これまでの社会保障制度審議会・介護保険部会でも、この問題に関して「要介護1・2の人を切り捨てることはできない。家族介護が必要となり、介護離職ゼロも達成できなくなる。」(日本医師会)、「給付削減は重度化を早め、介護財源を圧迫するだけだ」(認知症の人と家族の会)、「重度化を防いでいる軽度者の支援を止めるのは本末転倒だ。」(全国市長会)、「制度が維持されても、理念が失われてしまう。」(全国老人クラブ連合会)、など批判の声が集中している。
要介護2以下の認定であっても、独居高齢者、介護者の高齢化による老々介護など、在宅生活の継続が困難な場合が少なくない。特別養護老人ホームの入所条件も、原則要介護3以上とされているなかで、在宅サービスの保障さえ奪うことは、「介護を社会全体で支える」という介護保険制度創設の理念に背くものである。
よって、本市議会は政府に対し、要介護1・2以下の在宅サービスの「保険外し」をやめ、介護保険法第一条に謳われた「高齢者の尊厳の保持」を実現するよう、介護保険制度の充実を強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年3月 日
泉大津市議会
送付先 内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣
現実には要介護2以下でも、在宅の暮らしが困難、不安な方はたくさんいる。
そんな中で、要支援認定に続いて、要介護1・2の在宅サービスを保険給付から外すことは論外。
開会中の議会に提出している意見書(案)。案文は以下の通りです。
要介護1・2の在宅サービスの「保険外し」中止、
介護保険制度の充実を求める意見書(案)
昨年5月に成立した「改正」介護保険法(地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律)の中で、「軽度」(要介護2以下)給付の総合事業への移行は、社会保障審議会の委員、事業者・職能団体などから強い批判の表明を受け見送られた。
しかし「次期以降の検討課題」と明記され、その後に示された財務省の財政制度審議会や内閣府の経済財政諮問会議の社会保障改革案では、介護保険の「要介護1・2」の240万人の在宅サービス(食事や入浴、排せつ、衣服の着脱などの日常生活の介助や、料理・選択などの生活援助)を保険給付から外す計画となっている。この計画どおりとなれば、要支援・要介護と認定されている人の実に65%が保険給付の枠外に置かれてしまうことになる。
これまでの社会保障制度審議会・介護保険部会でも、この問題に関して「要介護1・2の人を切り捨てることはできない。家族介護が必要となり、介護離職ゼロも達成できなくなる。」(日本医師会)、「給付削減は重度化を早め、介護財源を圧迫するだけだ」(認知症の人と家族の会)、「重度化を防いでいる軽度者の支援を止めるのは本末転倒だ。」(全国市長会)、「制度が維持されても、理念が失われてしまう。」(全国老人クラブ連合会)、など批判の声が集中している。
要介護2以下の認定であっても、独居高齢者、介護者の高齢化による老々介護など、在宅生活の継続が困難な場合が少なくない。特別養護老人ホームの入所条件も、原則要介護3以上とされているなかで、在宅サービスの保障さえ奪うことは、「介護を社会全体で支える」という介護保険制度創設の理念に背くものである。
よって、本市議会は政府に対し、要介護1・2以下の在宅サービスの「保険外し」をやめ、介護保険法第一条に謳われた「高齢者の尊厳の保持」を実現するよう、介護保険制度の充実を強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年3月 日
泉大津市議会
送付先 内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣