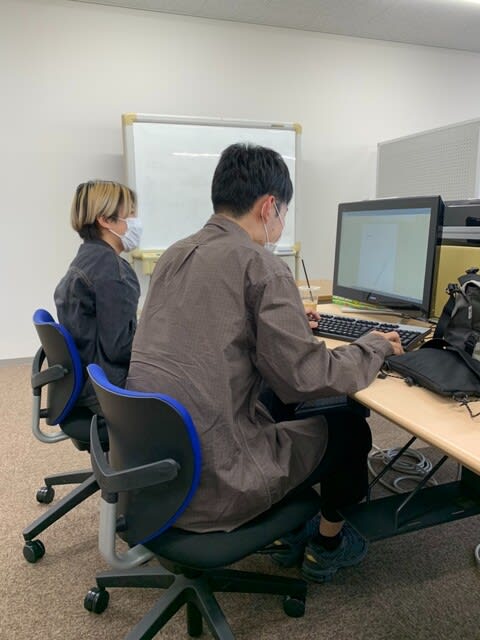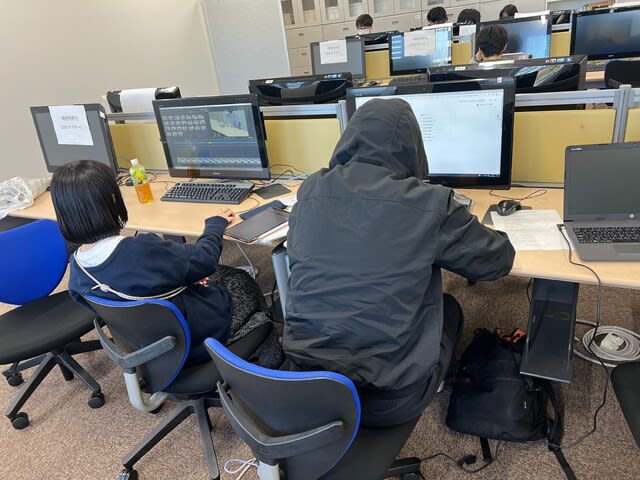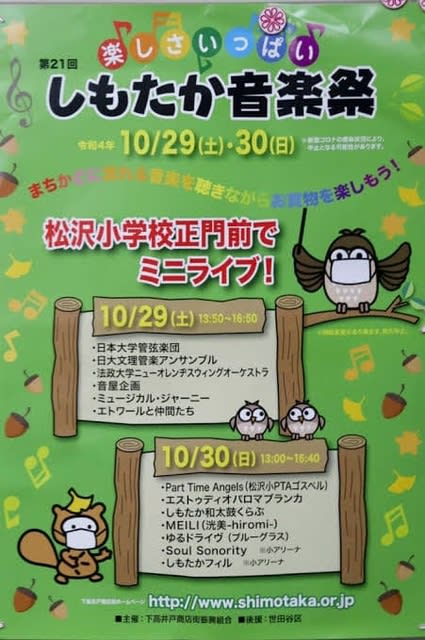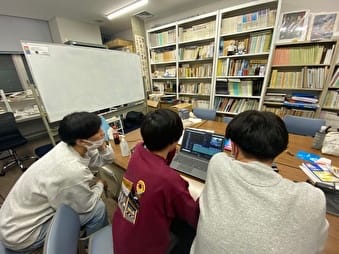こんにちは。
4年の荻野班です。
前回のゼミが行われてから、荻野班がどのような活動をしてきたのか。
ここから班員全員で分担してブログを書いていきます。
まずは荻野班のスケジュールを紹介します。
9月29日 13時‐14時30分 東京駅 【河西】
10月3日 16時‐17時 浅草地下街 【荻野】
10月4日 13時‐15時 ミーティング 【全員】
10月7日 14時‐15時30分 松屋銀座インタビュー 【大牧 鈴木】
16時‐17時 浅草地下街 【大牧】
10月15日 19時‐21時30分 浅草地下街(&ミーティング) 【荻野 大牧】
10月17日 14時‐ 銀座デザイン協議会インタビュー 【荻野 大牧 河西】
全員が集まる日は1日しかなかったものの、インタビューや調査のたびに連絡をとり、
報告や写真の確認をして、個別の活動にならないように気をつけながら動きました。
ここから、各活動日の報告をしていきます。
◇9月29日東京駅◇
【河西】
9月29日
有楽町から東京駅を繋ぐ地下道を歩いて
地下の様子などを何枚か写真撮ってきました。
有楽町から二重橋前までの区間は綺麗に整備されており地下の老朽化は見受けられず、
東京駅の地下に差し掛かったところから如実に老朽化と見られる箇所がとても多いように感じました。
ですので、次回からの写真に収める場所、区間を絞れたので、効率的に活動して行けたら良いと思いました。



◇10月3日浅草地下街◇
【荻野】
平日の昼間ということもあってか人はほとんどいませんでした。
いくつかの店主の方が掃除や開店の準備?などを行なっている程度。
5分おきくらいに通行人が通る
唯一入り口付近の立ち食い蕎麦屋さんのみお客さんが入っていました。


◇10月4日ミーティング◇
ここで、全員でのミーティングを行いました。
29日の河西、3日の荻野が撮ってきてくれた写真を見ながら計画を立てます。
その中で、私達は浅草地下街について知らないことが多すぎるという結論になり
まずは浅草地下街からフィールドワークを進めてていくことにしました。
また、大牧が松屋銀座と銀座のデザイン協議会にインタビューのアポをとりました。
日程調整をして、質問内容を考え、インタビューにそなえて準備を開始します。
メトロと旗艦店へのインタビューも予定していましたが、なかなかアポが取れず調整中です。
◇10月7日松屋銀座インタビュー◇
【鈴木 大牧】
松屋銀座の紀野様にインタビューをお願いしました。
紀野様は松屋銀座の150周年記念事業をご担当されており、私たちが写真に収めた松屋銀座の地下通路のリニューアルに携わられていた方です。
当日は、松屋銀座の地下通路にある1番の柱の前で待ち合わせをしました。
地下通路では主に2つの話を伺いました。
1つ目は、この数字の描かれた柱についてです。柱に数字があるこのデザインには、待ち合わせに使ってほしいという意図があるとのことでした。確かに待ち合わせしやすく感じました。

2つ目は、壁面タイルの遊び心に関してです。
この模様は一見全て同じ柄に見えますが、よく見ると左上にキツネのような柄があります。このような遊び心は、松屋銀座の地下通路のリニューアルを担当した佐藤卓さん考案のものだそうです。大人の遊び、余裕を表現しているようです。

その後松屋銀座の会議室で1時間程度、大きく以下8点のお話を伺いました。
①10→1
これは松屋銀座の地下通路の柱に関してのお話です。
松屋銀座の地下通路の柱には、上述したようにナンバリングがされていますが、
それは銀座駅→松屋銀座という導線に沿って、10→1にカウントダウンするように設計が為されてれているようです。
②佐藤卓さんの起用理由
佐藤卓さんは日本を代表するグラフィックデザイナーですが、松屋銀座の150周年記念で地下リニューアルを担当したのは以下3点の理由があるそうです。
①松屋と関わりの深いデザインコミッティーのメンバーである。
②松屋が佐藤さんをサポートしていた背景がある
③銀座とのつながりが最も深いでデザイナーである
③松屋銀座の地下通路の設計意図
以前は円柱型の柱に広告を多く載せていたようです。
しかし、リニューアル後は上述のように、ナンバリングがされています。これは、リニューアル前に比べた際に広告収入の減少という痛手はありますが、意匠性を高める意図があるようです。
④地下通路のタイル
松屋銀座の地下通路は、昔のお風呂のタイルのようなものが張られています。
普通の建物のタイル貼りは機会を用いて行うようですが、
リニューアルに際して、佐藤さんは手張りでタイルを張ることに決めたそうです。意図としては、綺麗なタイルではなく、ユラユラ揺れているようなタイルを採用することで、人が作ったというような何気な味を感じてもらいたいというところにあるようでした。
そのタイルも拘られていて、通常のように商社から値段を考慮しておろすのではなく、実際に佐藤さんと松屋の担当者が、現地に赴き決められたそうです。
⑤銀座のスローガン
銀座連合会という組合では、銀座憲章というまさに私たちがイメージする銀座を言語化した憲章が掲げられているそうです。
①銀座は創造性ひかる伝統の町
②銀座は品位と感性たかい文化の街
③銀座は国際性あふれる楽しい街
以上三点に関しての話を伺う中で、まさに銀座を象徴するワードが集約されていると感じました。
⑥松屋銀座の誇り
松屋銀座は、松屋と言えば銀座、銀座と言えば松屋というイメージや、実際の活動に誇りを持っており、
ビジネスにおいても、価値基準は松屋銀座らしいかどうか?という点が大きく考慮されているようです。
例えば、何かイベントを行い際、またはバイヤーが商品の選定をする際、重きを置かれる判断軸は、常に松屋銀座らしいかどうかという点にあるようです。地下通路もその松屋銀座らしさが象徴されているように感じます。
⑦銀座のつながり
銀座には深いつながりがあるようです。
例えば、銀座40歳未満の経営者が集まり、銀座や自分たちのビジネスをどのように盛り上げていくかという議論がなされているようです。
若い時から銀座のつながりを重要視し、他エリアと違い地域としてまとまりをもち銀座というブランドを創り上げているようでした。
⑧紀野さんの銀座の捉え方
銀座の街の特殊性、唯一性について多く言及されていました。
銀座には、最近、例えば、ユニクロや無印良品のような銀大衆向けブランドが進出しています。
既に自身の色と地位を確立しているような大手企業でも、銀座に進出する際は、
先ず、銀座に溶け込むことを重要視するようです。具体的には店舗の色や、雰囲気を銀座に合わせいているようです。
そんな街は、東京のほか他エリアでは見られない銀座の唯一性と言えるでしょう。
また、現在銀座は革新性や、先進性が求められているとのお話もありました。
銀座憲章とも重なる部分があり、銀座でビジネスを行う人にとっての共通認識を垣間見ることができたと感じました。
1時間程度お時間をいただきましたが、紀野さんからは、銀座への情熱と誇りを随所から感じることができました。
銀座は自身のブランドだけではなく、街に誇りを持てる独自性のある街という点や、銀座らしさという点について
再確認をすることができたと思います。
以上、松屋銀座の紀野さんへのインタビューのまとめでした。
◇10月7日浅草◇
【大牧】
この日は金曜日だったということもあり、荻野が訪れた日よりも人が多く感じました。
中でも1番賑わいを見せていたのが下の写真の忍者場NinjaBarです。

忍者の格好をした店員さんがおり、外国人向けなのかと思いきや日本人のお客さんが多くいました。
また、浅草地下街の上にあるのが松屋浅草です。

雨が強く外観はあまり見ることができなかったのですが、中の様子を見てみると下町らしさを感じました。
中で流れている音楽や、店員さんの声掛け、デザイン等、銀座とはかなり違うものとなっていて、松屋銀座でお話を伺ったあとだからこそ、この違いに気づくことができました。
◇10月15日浅草地下街◇
【荻野 大牧】
~DVD屋さんへのインタビュー内容~
20年前からこの地でお店をやっている
浅草地下街では印刷屋さんが1番古い
ここ5、6年で昔からのマスターが新しい人に店、場所を譲る(主な理由は高齢化、亡くなってしまった人も、、)
DVD屋さんの店主がこの浅草地下街を選んだ理由は駅が近い、家賃が割安などと、特に地下街などにこだわりはなく普通に店を出す上で総合的に判断して決めただけ
コロナになって人が少なくなった、客は今も戻らない
この土地について
代表者は特段いない
元々都の管理下、所有→台東区に委託?→浅草地下道株式会社が一括で管理(公共料金などなど)→各店舗?場所のオーナー(権利を持っている人)→店主が借りる


管理体制が特殊で、昔からの古い店や、忍者Barなどの比較的新しい店が入り混じる浅草地下街。
今後の調査では、ここに店を出した理由や、ここに居続ける理由、客層などを探っていきたいと思います。
また、私達は、銀座デザイン協議会の方におすすめしていただいた、
竹沢えり子著
『銀座にはなぜ超高層ビルがないのか』
を読み始めました。
まずは、【大牧】が読んで、印象に残ったフレーズをここに記しておきます。
(個人の感想であり、長くなりますので、飛ばしていただいても構いません。)
①入れ替わりが多く、みんな新参者で、そこに住む人はいない。人も建物も大きく変化しても「銀座らしい」ことを大事にする。
②伝統的なものを切り捨てて西洋のものを取り入れたわけではなく、伝統的なものを近代の中に潜り込ませることで、伝統も近代的なものも変容させてきた。
③ 守りに入らず新しいものを受け入れ、それを飲み込んで発展していくことこそが「銀座らしさ」なのである。
④ 銀座は多様な近代ビルの中に、古い暖簾を守る店やグローバル展開の海外ブランドや企業を両方抱える。一晩で数百万使える店もあれば3000円で気楽に飲める店もあり、入りにくそうだが、一度入ればあたたかくて親しみやすい店もある。どちらか一方になってしまっては銀座ではなくなるのだ。
⑤古いオフィスビルの階高が低く、地下に深いのは、1933年まで建物の高さは31mまでという決まりがあったためである。
⑥シャネルのリシャールコラスによると、銀座は目的無く水平的に回遊して楽しむ界隈空間であるからこそシャネルは出店するのだという。
⑦色やデザインは数値で決められないから、慣習的基準でやっていく、そして銀座は何も「決めない」ことに決めました。目に見えない「銀座フィルター」が銀座らしい町並みをつくってきたのだ。
⑧(銀座の)街に一人勝ちはない、街が栄えてこそ自分の店も栄えるのだ、一時的に自分だけが栄えたとしても、街全体が落ち込んでしまえばいずれ自分の店もだめになるだろう。
⑨「細かいルールなんて必要ない。「銀座はうるさい街だ」「あそこはうるさいよ」ということが皆にひろまれば、それでいいんですよ。最初から気をつけて中に入ってきてくれるから。それが大事なんだ」
⑩「銀座デザインルールは、協議の経験と事例の積み重ねによって熟成させて行くべきものであると同時に、ルール自体を新しいプロジェクトの提案に即して、常に見直し、再考していくべきもの」である。
この本を読んで、言葉で明確に表すことのできない「銀座らしさ」を感じ始めました。
今まで銀座という街に持っていたイメージは、高級感があって敷居が高く、おしゃれな街というものでした。
しかしこの本を読むと、人と人の繋がり、人と街の繋がり、そしてあたたかさを感じます。
規定や決まりではなく、人々の「銀座」の思いが、銀座の今を作り、未来へと繋がっていくのだと思います。
伝統を守りながらも、先端を受け入れていく。そして新しいものを率先して取り入れ、上手く融合し続けるのが伝統でもある。ということでしょうか。
長くなってしまいましたが、本の感想はここで終わりにします。
これをもとに、デザイン協議会へのインタビューに繋げていきます。
最後まで読んでいただき有難うございました。
文責 荻野哲平、大牧美衣奈、河西優介、鈴木悠佑(2022年度4年ゼミ生)