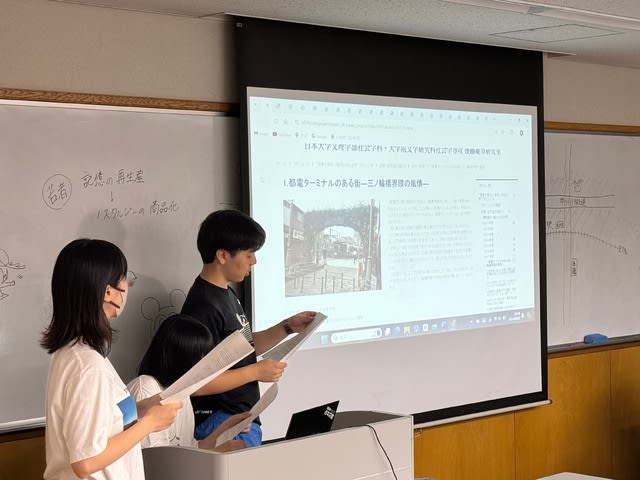先日1月16日に、後藤先生による日本大学社会学会特別講演会と3年生による「シモタカ・ジョースイ映像祭」が行われました。
まずは、後藤先生による『東京と東京人のビジュアル社会学』についての講演会からご紹介します。
プロジェクトの代表作と作品化の具体例を説明し、集合的写真観察法による作品化のプロセスのお話もされていました。
さらに、ゼミ生であれば何度も聞く「せめぎあいと紡ぎあい」という言葉にもふれ、学部生がどうすれば社会学的想像力を育てられるのか取り上げていました。

質疑応答の際には、「写真は偶発的にとられたものなのですか」という問いに対して、「学生がとった写真はプロではないため稚拙であるがよく見ると隠れた面白いものが眠っている。それを発見して分析をしていく。」と。写真の優劣にこだわらないからこそ毎年面白い考えさせられる写真が生み出されていくと感じました。

また、「学問の研究を行う大学の場では、学生をほめてばかりいてどうする。もっと問題点を指摘する、創意工夫をするためには何が足らないのかを指摘するということが大学教育では必要ではないか」といった学問を学ぶ場での環境に言及する場面もありました。
昨年はこの講演会はなかったですが、ゼミ生を含めてすべての方に意義がある時間であったと思います。ぜひ、来年も開いてほしいですね。
次に、3年生による『シモタカ・ジョースイ映像祭』についてです。

まずは篠原班。桜上水の八百屋清藤商店をピックアップしての映像です。動画内では、規格外に安い新鮮な商品と人とのつながりを重要視する店主さんが桜上水に新たな現象を巻き起こしている模様を収めていました。社会学だけではなく、私たちに若い起業家を応援する思いも感じさせてくれる作品であり、桜上水の方にどれだけ愛されているかもうかがうことができました。

次にイリヤ班。3年生は映像祭前、あまり班員が同じ方向への足踏みができなかったと語っていました。発表では、出だしから東京という街を大きく使った映像を使い下高井戸に焦点を絞る手法を用いていた点は過去作品でも例がないものだったのではないでしょうか。「ナナカマド」の店主さんの話を十分に使用した、下高井戸地域だけのロシア料理店を感じとることがができました。

二つの映像を鑑賞した後は、班長二名が登壇し質疑応答が行われていました。
少々堅苦しくなってしまいましたが、最後は全体写真とおそらく最後であろう4年生による自撮り集合写真で締めさせていただきます。


ここまで読んでくださりありがとうございました。