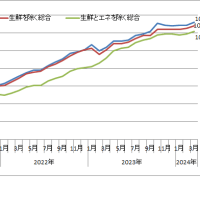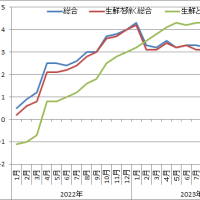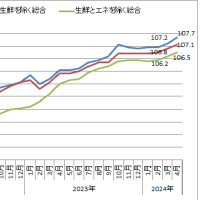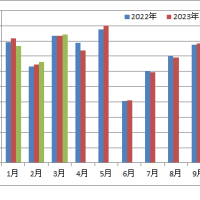11月3日「文化の日」は明治節の昔から「晴れの特異日」のようです。今日も朝から良く晴れて真っ青な空に太陽の素敵な秋晴れです。
ところが朝食の頃から北朝鮮からのミサイル騒ぎで大変です。一時間おきに3発のミサイルが発射され、その内の1発はICBMだそうで、どれがそうかは解りませんが、最初の1発は新潟、山形、宮城の3県の上を飛んだというJ・アラートが出たようです。
後から日本上空に来る前に「消失」したとのことで、日本の上空には来なかったようです。消失というのは忍者のようで、日本まで行かないように自爆させたのでしょうか。
折角の文化の日を朝からの騒ぎとは残念なことですが、これも「争いの文化」が主流の今の世界では致し方ないという事になるのでしょう。
何年か前の文化の日に「競いの文化」と「争いの文化」を書きましたが、このブログは、日本の伝統文化の根源は、縄文時代の争いのない1万余年の「平和共存」の文化で、基本的に「争いの文化」は持っていなかったと考えています。
「争いの文化」は弥生時代以降の大陸の文明「青銅器・鉄器」の導入、そしてそれに付随して入ってきた武器と戦争という文化で、つまりは外来の文化を学んだ結果の「文化の汚染」だったのだろうという見方です。
この外来の「争いの文化」は多分に刺激的で、日本はそれ以来「倭国大乱」に始まり、殆ど内戦の時代を過ごし、明治以降は1945年迄、外国との戦争に明け暮れました。
然しその結果の第二次世界大戦の敗戦をきっかけに「戦争を放棄」した「平和憲法」を持つ国となり、経済社会の大きな発展を経験し、日本の伝統文化である「競いの文化」に、まさに本卦返りして、精神的にも社会的にも極めて居心地のいい、住みやすい国を作ってきたのです。
この日本の、多様な人々が平和共存し、それぞれの文明の発展を競う事はあっても、争そうことはないという伝統文化は、縄文1万有余年の長きに亘る日本の自然環境に大きく関わるような気がしてきています。
氷河期が終わって海面が上がり日本列島が大陸と切り離されてから、自分達だけしかいない世界、自然災害はあるが、豊かな実りも齎すモンスーン地帯という環境の中で、自然と共存し、自分達も自然の一部と考えながら、自然を育てることが豊かさにつながる事を学んだ、その長い期間が、日本文化の原型になったのではないかと感じるのです。
然しユーラシア大陸全体を考えますと、ホモサピエンスが6万年前アフリカを出て、ユーラシア大陸から北米を通り南米南端まで広がった際、ヨーロッパには先住民であるネアンデルタール人(原人)が、居ました。
ネアンデルタール人は2万年ほど前に絶滅し、ヨーロッパはホモサピエンスの世界になりました、今年のノーベル賞受賞者にホモサピエンスとネアンデルタール人との交雑の研究者がいましたが、先住民との間に何があったのかは、長くタブーのようでした。
ユーラシア大陸東部には矢張り旧人のデニソワ人がいたのですが、今は絶滅しています。
同じ、ホモサピエンスどうしでも、ヨーロッパ人が、アメリカ大陸を発見してからの歴史を見れば、先住民と、より文明度の高い征服者の関係はおおよそ想像されるところです。
幸い、日本列島では、その特殊な環境条件で、「平和共存」、「争い」でない「競い」の文化が生まれたとすれば、これは人類の今後のために大切にしなければならないものではないかと考えるところです。
ところが朝食の頃から北朝鮮からのミサイル騒ぎで大変です。一時間おきに3発のミサイルが発射され、その内の1発はICBMだそうで、どれがそうかは解りませんが、最初の1発は新潟、山形、宮城の3県の上を飛んだというJ・アラートが出たようです。
後から日本上空に来る前に「消失」したとのことで、日本の上空には来なかったようです。消失というのは忍者のようで、日本まで行かないように自爆させたのでしょうか。
折角の文化の日を朝からの騒ぎとは残念なことですが、これも「争いの文化」が主流の今の世界では致し方ないという事になるのでしょう。
何年か前の文化の日に「競いの文化」と「争いの文化」を書きましたが、このブログは、日本の伝統文化の根源は、縄文時代の争いのない1万余年の「平和共存」の文化で、基本的に「争いの文化」は持っていなかったと考えています。
「争いの文化」は弥生時代以降の大陸の文明「青銅器・鉄器」の導入、そしてそれに付随して入ってきた武器と戦争という文化で、つまりは外来の文化を学んだ結果の「文化の汚染」だったのだろうという見方です。
この外来の「争いの文化」は多分に刺激的で、日本はそれ以来「倭国大乱」に始まり、殆ど内戦の時代を過ごし、明治以降は1945年迄、外国との戦争に明け暮れました。
然しその結果の第二次世界大戦の敗戦をきっかけに「戦争を放棄」した「平和憲法」を持つ国となり、経済社会の大きな発展を経験し、日本の伝統文化である「競いの文化」に、まさに本卦返りして、精神的にも社会的にも極めて居心地のいい、住みやすい国を作ってきたのです。
この日本の、多様な人々が平和共存し、それぞれの文明の発展を競う事はあっても、争そうことはないという伝統文化は、縄文1万有余年の長きに亘る日本の自然環境に大きく関わるような気がしてきています。
氷河期が終わって海面が上がり日本列島が大陸と切り離されてから、自分達だけしかいない世界、自然災害はあるが、豊かな実りも齎すモンスーン地帯という環境の中で、自然と共存し、自分達も自然の一部と考えながら、自然を育てることが豊かさにつながる事を学んだ、その長い期間が、日本文化の原型になったのではないかと感じるのです。
然しユーラシア大陸全体を考えますと、ホモサピエンスが6万年前アフリカを出て、ユーラシア大陸から北米を通り南米南端まで広がった際、ヨーロッパには先住民であるネアンデルタール人(原人)が、居ました。
ネアンデルタール人は2万年ほど前に絶滅し、ヨーロッパはホモサピエンスの世界になりました、今年のノーベル賞受賞者にホモサピエンスとネアンデルタール人との交雑の研究者がいましたが、先住民との間に何があったのかは、長くタブーのようでした。
ユーラシア大陸東部には矢張り旧人のデニソワ人がいたのですが、今は絶滅しています。
同じ、ホモサピエンスどうしでも、ヨーロッパ人が、アメリカ大陸を発見してからの歴史を見れば、先住民と、より文明度の高い征服者の関係はおおよそ想像されるところです。
幸い、日本列島では、その特殊な環境条件で、「平和共存」、「争い」でない「競い」の文化が生まれたとすれば、これは人類の今後のために大切にしなければならないものではないかと考えるところです。