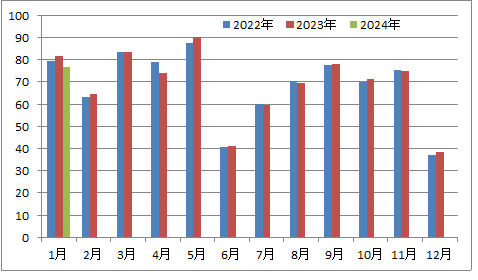日銀の新しい金融政策の方向が示されました。感想を言えば、適切な配慮をしつつ、解り易い表現で、的確にこれからの金融政策の方向を示したという点で、先ずは満点の内容という所ではないかと思っています。
先ず第一に挙げなければならないのは、マスコミの見出しのように、11年来のアベノミクス、異次元金融緩和からの明確な決別を明示した点です。政府は勿論、市中の金融機関も、企業経営者も、生活者としての一般家計も、みんな、これからの金融の在り方はこれまでと違うという意識変革の必要を感じたでしょう。
その上で、特筆すべきは、こんな金政策の大転換を発表したに関わらず、金融マーケットは全く平穏に推移しているという事です。
一部には、日銀が異次元金融緩和脱出の方向を明示し、一方でアメリカのFRBが金利引き下げの具体化を示唆するとなれば、為替レートは大幅円高、ダウ平均は上がるかもしれないが、日経平均は暴落というシナリオの現実化を予想した筋も多かったでしょう。
その危惧は既に3月7日の日経平均「寄り200円高、引け500円安」といった水鳥の羽音に驚いたミニ・ショックにも見られるところですが、それが現実となった昨日は、逆に円安、日経平均は2日連続大幅上昇という平穏を通り越し、マネーマーケットは絶好調といった状態です。
関連業界では、今回の日銀の発表はすでに「織り込み済み」という説明が用意されていたようですが、マスコミが巨大活字で扱う大変革と、それを全く気にしないようなマネーマーケットの活況はまだに対照の妙でしょう。
日銀発表の中身を見れば、日銀預金のマイナス金利は消えますが、0.1%の金利は変えず、市中銀行の金利は自主決定、ETFなどの購入は元々付加的な緩和政策ですから1年かけてやめますが「国債の買い入れ」は従来通り、しかし、基本方針は「BSの圧縮」という表現で示すといったものです。
政府は当面安心できると思うでしょうが、日銀は、決して無理はしないが、しかしやるべきこと確りやりますと内外に意思表示したものと理解すべきでしょう。
政府は当面安心しながらも、今迄のような国債を印刷すればバラマキが出来るという具合には行かなくなるだろうと自覚するでしょうし(少し甘いかな)、マネーマーケットもバブルの進展には気を付けるでしょう(これも甘いかな)。
今日のアメリカのFOMC の発表がどうなるかは微妙ですが、今年中に3回の金利引き下げの可能性がどの程度かも次第に明らかになるでしょう。
そうした、予測の難しい国際情勢の中で、日銀は、今のマネー経済面での活況を「→バブル→崩壊」ではなく、正常な範囲の活況で実体経済活動への潤滑剤にするような舵取りを目指すのではないでしょうか。植田総裁の腕に期待が懸るところです。
もう一つ付け加えれば、植田総裁が「金融改革は賃上げを見て」と繰り返されたことの意味を、日本の経営者も労働組合も(経団連も連合も)「日本経済における賃金決定の在り方の重要性」を労使に理解してもらうための発言と受け取り、「担当責任者」として、年々、誤りない「適正賃金の決定」に本気で取り組むという意識を確りと持って欲しいと思うところです。











 資料:日本銀行、総務省
資料:日本銀行、総務省