
「走る少女」
著:佐野久子 画:杉田比呂美
岩崎書店 初刊:2007年2月15日
同人誌「季節風」の幹部でいらっしゃる、佐野久子さんの作品である
主人公の比呂は中学一年生。
かつて中学生のときに陸上部に所属して、学校の伝説となった兄。その兄が比呂をバイクから救うため、一生走れない障害を負ってしまう。落ち込み、悩む比呂に対して、立ち直りと切り替えの早い兄の天真爛漫さがいい。その根底にはたくさんの葛藤はあるのだろう。それでも、起こったことを受け止め、忽然と前に進む強さに惹かれる。いつの世も、なにが待ち受けているか分からない。未曾有の大震災に見舞われることもある、今この時にも身に迫る題材でもあるのだ。
兄はストラディヴァリというヴァイオリンを産んだ街、イタリアのクレモナ公立音楽学院へ留学していく。ほどなくして、イタリアから陸上用のシューズが送られてきた。それがきっかけとなり、比呂は兄と同じ陸上部に入る
そこには、やはり幼い頃にオリンピック候補だった父を持つ季里子がいた。父と離れて暮らす季里子はやはり何かを抱えて生きている。そこに、面倒見のいい先輩である千秋、比呂が少しだけドキッと感じてしまう男の子、達也、妹にかまけている母のためつい意地悪な行動に出てしまうカオリなど一癖もふた癖もある部員たちとキャラクターは豊かで、万全だ。
比呂は胸に抱えたものを走るときにだけは前面に出していく。仲間たちとぶつかりあい、悪戦苦闘しながら、100mそして400mリレーへと進んでいく。はたして、それぞれが抱えた思いは前に進めることができるのか。一番やっかいで、切なくて、やりきれない大人になる前の中途半端な時期。それを乗り越えたとき、人はいつしか人生でいちばん愛おしいと思えるものに変容した、かけがえのない青春の宝物を得ることができるのだろう。
この兄貴のように達観した男になりたいもんだ
それにしても、比呂って名前、絵を描かれた杉田さんの名と同名。関係あるのかいなや。いま頃気付いた
その比呂や登場人物たちのひたむきに走る姿が、切ないほどエネルギッシュで爽やかな印象が心に残る作品である
「秋穂ゆれ 走る気持ちを わすれない」
海光
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
佐野さん、季節風108号に掲載の拙文への評論、ありがとうございました
筆者の表現したいものを怖いほどよくご洞察頂けているのだなあと、なによりもそれが嬉しい。
先輩たちの作品を評するのは、気が引けて温めていたのだけど・・・
一年前に書いた書評を掘り起こし、お礼方々、ブログに掲載させていただく。
拙い評ですみませぬ。
ヨチヨチですが、あっしも走り続けやす
佐野さんのご健筆を祈りつつ。。 2011年TOTAL RUN 1672.3km
2011年TOTAL RUN 1672.3km  10月20日現在
10月20日現在 




























 )にはある意味、女の子への幻想を打ち砕くお話
)にはある意味、女の子への幻想を打ち砕くお話










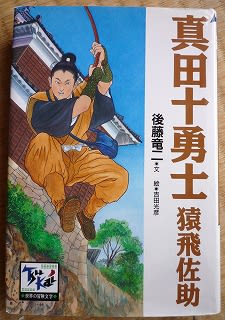
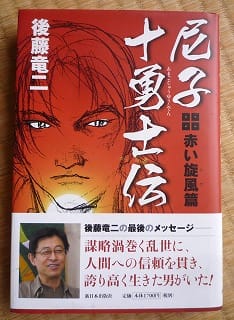
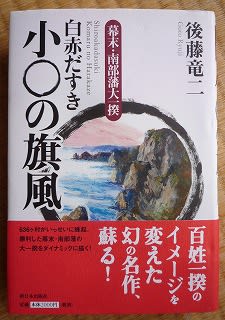
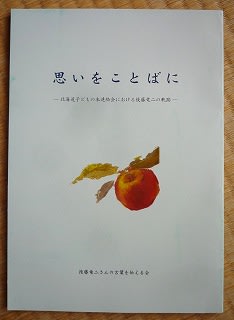






 )。
)。
 )
) 」
」 (おっと、児童文学の紹介でした)
(おっと、児童文学の紹介でした) 一葉通りの桜
一葉通りの桜 浅草寺 五重塔
浅草寺 五重塔 浅間神社の桜の木
浅間神社の桜の木
 蕾と空
蕾と空 刺身盛り
刺身盛り 味噌きゅうり
味噌きゅうり
 大いなる師の書斎
大いなる師の書斎






 師にも同人誌時代があった
師にも同人誌時代があった






 いまでも師ならペンを持つのか?
いまでも師ならペンを持つのか?



 ご存知芥川賞受賞作
ご存知芥川賞受賞作 玄関脇に
玄関脇に


 大映1958年の作品
大映1958年の作品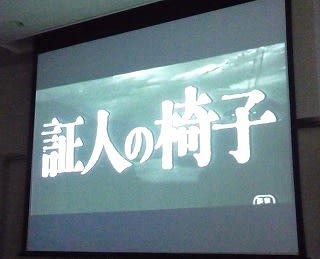
 1965年の作品
1965年の作品


 後楽園の新たな聖地JCBホール
後楽園の新たな聖地JCBホール




 同人誌「格闘公論」
同人誌「格闘公論」


 温和な印象に語り草もさすが現役アナ
温和な印象に語り草もさすが現役アナ 貴重なラジオドラマの脚本
貴重なラジオドラマの脚本


 代表作の一年一組シリーズのイラスト
代表作の一年一組シリーズのイラスト

 野間児童文学大賞時のことば
野間児童文学大賞時のことば 破綻した夕張市の学校で
破綻した夕張市の学校で 季節風の創刊号
季節風の創刊号