
宇宙空母ブルーノア
よみうりテレビ、アカデミー製作
(1979年)
昭和期の古典的作品を紹介する2回目です。本作は現時点で確認できる限り、軌道エレベーターを映像化した初の作品だと思われます。以前、「劇場版 仮面ライダーカブト」を、初めて軌道エレベーターが登場した実写作品と紹介しましたが、本作は実写・アニメ問わず、映像全般として初になります。今回はラストまでネタバレしますのでご注意下さい。
あらすじ 西暦2052年、異星人ゴドムの襲来により地球は壊滅寸前に追い詰められる。生き残った主人公たちは空母ブルーノアに乗り込み、ゴドムへの反撃を始める。
1. 本作に登場する軌道エレベーター
えー、軌道エレベーター初映像化作品、と強調しましたが、残念ながらその扱いは実に粗末なものでした。7話に登場し、次の回であっさり破壊。しかも建造したのは敵であるゴドムなんですよ。
ゴドムはいつの間にか、現在のキリバス領ギルバート諸島付近の赤道上に軌道エレベーターを完成させています。半透明のチューブみたいなピラーが上空へ伸びており、その中を昇降機らしきものが動いているのが外から見えます。

ゴドムは重水を主なエネルギー源としていて、この軌道エレベーターも海水から取り出した重水を宇宙に運んでいるらしいのですが、詳細は不明。直径500mで「耐レーザー装甲」を装備してるということ以外は、全長、材質、昇降機が有人なのか、動力源は何なのか、一切データがありません。説明できるのはこれだけ。重力を制御できるゴドムが、軌道エレベーターを必要とするのも説得力がありませんが、ようするに作中の役割は、縦向きのベルトコンベアーみたいなものでしょう。
で、ブルーノアは航海の途中でこの軌道エレベーターを発見。この時、
「おそらくこれは、軌道エレベーターです。
高度3万6000kmの静止衛星軌道まで、届いているものと思われます」
というセリフがあり、作中で「軌道エレベーター」と発言された初の映像作品ということにもなりますね。これを搭載兵器の反陽子砲により破壊します。軌道エレベーターの出番はこれだけで、その姿も、終始俯瞰した姿しか出てきません。
ゴドムに痛手を与えたんでしょうが、はっきり言って登場しなくても大差ない代物でした。本作は、日本の軌道エレベーター学普及の立役者でもあり、亡くなった金子隆一先生がSF監修をされていたのですが、軌道エレベーターに関しては「ちょっと出してみた」程度のものだったと思われます。
ちなみに反陽子砲ですから、軌道エレベーターの構成物質の陽子を対消滅させる原理だと思われますが、破壊後に完全消滅せずに若干物質が余ったらしく、砕けたガラスみたいなものが大気中を舞っていました。宇宙でもこのゴミが漂っており、ゴドムはそれを掃除機みたいな機械で吸い込んでいたのですが、真空の場所で掃除機使えんだろ。
こんなわけで、記念すべき軌道エレベーターの初映像化作品なわけですが、なんとも残念な描写でありました。
2. ストーリーについて
母星を失ったゴドム人は、デス・スターみたいな「ゴドム人工惑星」でやって来て地球周回軌道上に留まり、この人工惑星により地球上に大規模な災害が発生。さらに侵略を受けて人類は大打撃を受けます。学生だった主人公の日下真は、父親が亡くなる寸前、ブルーノアに至る鍵であるペンダントを受け取り、生き残った友人たちと乗艦、そのままクルーとなります。
この時点で、ブルーノアは飛行能力のない潜水空母であり、宇宙への進攻に必要な改修を受けるため、反重力エンジンが開発されているバミューダ諸島の基地へ向かいます。航海の過程でゴドムの艦隊と闘ったり、基地を破壊したりし、軌道エレベーターも破壊。反重力エンジンを装備後は宇宙に出てゴドム人工惑星を直接攻撃し、敵の内乱も重なって勝利します。
本作は「宇宙戦艦ヤマト」の成功にあやかろうとした二番煎じの作品で、人物配置や展開も非常に似通っていますが、「ヤマト」が放映後に人気が出て映画化や続編制作もされたのに対し、本作は尻すぼみに終わりました。
本作に限らず、昭和期のアニメは良くも悪くも型にはまっていてヒネリがなく、ツッコミどころも多すぎて、令和の視点で見ると退屈なのは否めません。正義感の強い熱血主人公やたおやめなヒロイン。ノリで闘う若者と、それを許す大人たち。勝利よりフェアプレー精神にこだわる敵味方。。。でもって作画のブレは日常茶飯事。本作もこれが当てはまります。
しかし本作の最大の問題点は、全24話中、20話までずーっと地球の海を航海して、タイトル通り宇宙空母になったのが最後の4話だけということでしょう。放送期間の短縮のせいもありますが、制作者の好みで海を舞台にしたともいわれます。
Wikipediaに海洋冒険ものとしては一定の評価があると書かれているものの、とにかく海の描写長すぎ。しかも主人公の真が乗る小型潜水艇「シイラ」の活躍が中心で、ブルーノアは待機していることが少なくなかった。
加えてラストが拍子抜けでして。。。本作ではゴドムの指導者ザイデル総統が地球侵略に妙に固執します。5ちゃんねる風に書くと、
総統 地球を侵略するで (`・ω・´)
軍人 ワイらの母星と重力値も違うし、ほかの星でええんちゃうか? (・ω・)
総統 あかん!何としてもブルーノアを倒して、大至急地球を奪うんや (`Д´)/
軍人 しゃあないなあ (´・ω・`) ……(なんでやろ?)
──みたいな状況だったのですが、実はゴドム人工惑星内では、軍人が知らないうちに民間人が死滅してしまっていたのでした。
んなアホな (´Д`)
居住区画が軍民で分断されてるらしいんですが、軍人だって民間人の家族とかいるだろうに、連絡とってないのか? つーか民間の後方支援なしで戦争が維持できるのか? ツッコミどころ満載ですが、総統はそれを隠して地球侵攻を急がせており(保管していた遺伝子を使って地球で人口を増やすつもりだった)、事実を知った軍人たちが総統を殺害して組織崩壊。残ったゴドム人は地球から去ることを決めます。
ゴドムの軍人でブルーノアの宿敵ユルゲンス(「ヤマト」のドメルみたいな立ち位置)は人工惑星に帰還せず、フレーゲル男爵みたいにブルーノアに艦対艦の一騎打ちを提案。すでに勝敗は着いていたのに、ブルーノアの土門艦長はあろうことかこれを受けます。本当にプロか。ブルーノアは僚艦(宇宙に出た後は、ブルーノアを旗艦として4隻で艦隊を編成していた)から離れ、単艦でユルゲンスに勝利します。ただし土門艦長は戦死。
ユルゲンスの犠牲にもかかわらず、ゴドム人工惑星は太陽に突っ込むという悲惨な結末。。。ちょっと後味も良くなかったのでした
。
3. ブルーノアの子孫
ストーリーはともかく、ブルーノアのデザインは非常にユニークでした。巨大な潜水艦が、浮上中は艦体の上半分が左右に割れるように展開して空母となり、断面が飛行甲板として機能するというものでした。
また艦首の喫水線から下の部分が小型潜水艦シイラとして分離、後部甲板の一部も分離変形して戦闘ヘリ・バイソンになるというのも、なかなか斬新で意欲的なアイデアだったと思います。ちなみに宇宙空母への改修の際には、シイラは(バイソンも)お役御免となり、ドッキングしていた艦首部分に反重力エンジンを搭載したのでした。

ですので、「宇宙戦艦ヤマト2199」みたいに、現代向けにヒネリを加えてリメイクしたら、意外と見応えあるんじゃないかなあ。最新のCGを駆使した作画で、リアルなデザインのブルーノアも見てみたい気もします。
かわりというわけではありませんが、「宇宙戦艦ヤマト 復活編」に新しくデザインされたブルーノアが登場し、こちらは主翼のような兵装コンテナが展開するというデザインでした。このほか未視聴ですが、「YAMATO2520」にも登場しているそうです。
制作から40年以上経つ本作を、私は10年くらい前に海外のamazonでスペイン語版DVDで購入し、実に久しぶりに視聴しました(だからスペイン語の字幕が出ちゃうんだよ)。
それがなんと、現在dアニメストアで視聴できるそうです。このコーナーで古典作品を扱おうと思ったのは、こうしたデジタル配信で見られる機会が増えてきた背景もあります。良い時代になったものです。ご興味のある方はそちらでご覧ください。










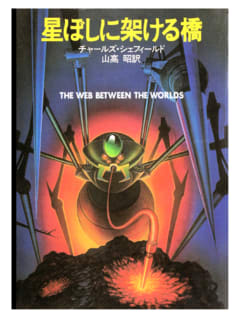






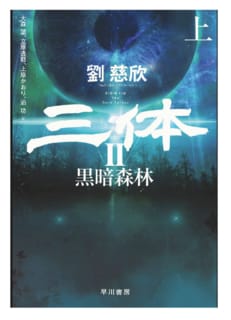



 iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。
iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。


