
第68回宇宙科学技術連合講演会に参加するため、兵庫県姫路市に来ております。
この半年近く、体調も気力もヨタヨタで当サイトの更新もままならない状態が続いていましたが徐々に復活して、年に1度の宇科連にはなんとか申し込みが間に合いました。今回はその報告です。軌道派としての本格的な活動は、ここから再スタートになればいいのですが。
会場は姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」。姫路駅から歩いて10分くらいの所にあります。
さて、今回の宇科連における、軌道エレベーターに直接関連する講演は次の通り(いずれもプログラム上のタイトル)。
落雷が宇宙エレベーターに与える影響の検討
宇宙エレベーター用CNTケーブルの耐環境性対策の地上照射試験評価
材料熱伸縮を考慮した宇宙エレベーターテザーの温度摂動に対する応答
全球雷活動分布から考察する宇宙エレベーター設置場所について
非赤道上宇宙エレベータにおける重力擾乱に対するねじれを含むテザー変形への影響
超小型衛星STARS-X搭載リール機構の耐宇宙環境を考慮したテザー伸展手法
天体表面でのケーブル敷設と宇宙エレベーター
宇宙エレベーター用クライマーのハイブリッド駆動ローラの機構と稼働特性について
宇宙エレベーター用クライマーの宇宙環境を模擬した高真空下における諸特性とその対応
富山市で開かれた前回宇科連でもいえたことですが、全体として、以前からの研究の続きの発表が多く、発表者の顔ぶれもやや固定化してきています。しかしその分、内容は回を追うごとに成熟していっているように感じます。
今回は雷の影響に関する発表が二つあり、両者を合わせて吟味することができたのが興味深かったです。
当然ながら高エネルギーの落雷は、軌道エレベーターのピラーを構成するテザー素材を傷める。一つの発表では落雷時の素材の温度変化などを伝えていて、もう一つはその落雷を理由として、地上基部をどこに造るかという点に着目。強力な落雷が発生するのは大陸上が多く、赤道上でそうした場所を避けるには、太平洋側の南米沖が適していると結論づけていました。
このほかに軌道派として興味深かったのは、赤道上を避けて地上基部を建造するモデルの検討で、ピラーのねじれの挙動解析でしょうか。
軌道エレベーターはものすごい長い構造体なので、色んな力を受けてぐにゃぐにゃ動く「摂動」を起こします。このうち主な要因が、昇降機の上下運動によるコリオリですが、今回の発表では地上基部を北緯20度に想定して、赤道上にない故に南北方向の力も加わりやすく、これらによるねじれに着目したのは新鮮でした。
また、軌道エレベーター研究にも波があり、今はお世辞にも盛んとはいえない時期にありますが、過去の隆盛期には赤道上にこだわらないモデルも注目されていました。
2012年の大林組の発表以降、このモデルを活用した研究が増えている中、今回のような非赤道型の軌道エレベーターの研究成果が出てきているのは、かつてを少し思い出してうれしかったです。次回以降の発展に期待をかけています。

余談。昨年から所属を「軌道エレベーター派」として登録・参加しておりまして、会場で受け取る名札にも所属先として明記されております。なんか特別感。
で、今回のうち8本の発表があった「宇宙テザーおよび宇宙エレベーター研究最前線」セッション、前回より会場がかなり狭くて椅子は25席。午前8時45分スタートで、1回の発表時間も前回より5分短い15分となり、質疑時間を除くと実質10分と、なんか「隅に追いやられた」感がハンパない。。。
上等だよ、異端とか傍流とかの方が性に合っとるわ! (ꐦ°᷄д°᷅)
宇科連に参加するのも、かれこれ10年くらいになりますかねー。今ではすっかり年1回の小旅行も兼ねたイベントとなり、同時に衣替えのタイミングにもなっています。持って行った下着などは旅先で着た後に捨てて、空いたスペースにお土産を入れて帰るというのが定番になりました。
昨年の宇科連では稚拙ながら「軌道エレベーター派」として発表をやりまして、今年続きをやる予定だったのが体調不振で断念しました。次回はぜひ、再チャレンジしたいものです。
ここまで読んで下さり、誠にありがとうございました。














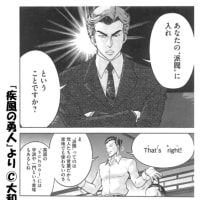






 iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。
iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。


