私がまだ小学5年生になる以前の頃、今のいなべ市の北部に住んでいたことがあり、ここに圧倒的存在感で私を魅了し続けた蒸気機関車が走る鉄道があった。 戦前に三重県から岐阜県に抜ける鉄道として作られ、「三岐鉄道」と名付けられた。しかし、三重県最北部の「西藤原駅」まで開通した状態で現在にいたっている。
鉄道は現在は電車が走っているが、全国的にも珍しいという「貨物専用の博物館」となっている。なお、当日は開館日でなかっために、中は見ることは出来なかった。(ボランティアによる運営のため、日曜日のみの開館なのである) 撮影:2013.03.29(金)
「貨物鉄道博物館」
三重県いなべ市大安町丹生川中 三岐鉄道三岐線丹生川駅に隣接

日本で唯一、鉄道貨物輸送を対象としている博物館である。貨車をはじめとして、機関車、コンテナが屋外展示されるほか、貨物関係の資料、貨車の部品等を収蔵している。各車両は静態保存によって博物館展示線と丹生川駅側線のほか、東藤原駅前でも展示されている。当博物館の建物の一部は、丹生川駅の旧貨物ホームが流用されている。
運営は鉄道事業者や行政ではなくボランティアによって行われており、費用は寄付によって賄われている。基本的に三岐鉄道は博物館建設のための基盤を整備・提供したにすぎず、中心的作業の車両搬入・展示・運営などの実務はボランティアにゆだねている。
日本で貨物鉄道が営業を開始した1873年(明治6年)9月15日にあわせ、2003年(平成15年)9月15日に開館した

「貨物鉄道博物館」のホームページ
「三岐鉄道」のホームページ

1898年(明治31年)イギリス製の機関車で、B4形39号として、東武鉄道で貨物列車牽引に使われていた。1966年(昭和41年)に現役引退し、昭和鉄道高校で保管されていたとある。
下の貨物車は、明治39年に新潟鉄工所で作られ、北越鉄道(現新潟本線)で使われていた。その後近江鉄道に移り、10トン積みに改造された。台枠から上は鋼製の柱に木製板張りで、引戸も木製であるとの事。

現在は電化され、下のような電車が走っている。

私がこの線路に耳を付けて、次第に大きくなり機関車が近づく迫力を感じていたのは、小学一年生の二学期から二年生の三学期一杯までであった。父が巡査駐在所勤務であったので、当時員弁郡と称したこの地を転々としていた時のことである。終戦もこの地で迎えている。
それはこの丹生川駅ではなく、ひとつ山に近い「石博駅(いしぐれ)」であった、その時一緒に機関車の響きを聞いた、近所で転校生の私と越して来たその日から仲良くしてくれた、2年先輩の伊藤さんはどうされているのだろうと、久々に思いだす。もう、六十数年も前の事だが明瞭に残っている・・・・・・・・・!。

「ヒマラヤユキノシタ」
「花写真館」はこちら http://mokunen.c.ooco.jp/h-p-syuu/01index/012frame.html
・・・・・と言っても、トップページしか出ないので、「ヒ」をクリック、次いで「ヒマラヤユキノシタ」をクリックいないと出ないのです。はい、・・・・・・・今の所・・・・?。

いなべ市の猪名部神社で行われる上馬神事を撮るための下見に出かけた際、時間があったので思い付きで寄ってみたのであったが、日曜日以外は休館日とは知らなかった。事前調査を怠った失敗であった。
追伸
ホームページ(表紙)のアドレスを変更しましたので、皆さまには大変お手数ですが変更の手続きをお願い致します。(メールについては個別に連絡してますが、もし必要な方はブログのコメント欄などで意思表示して戴けば連絡させて戴きます)
ホームページ表紙 アドレス http://mokunen.c.ooco.jp
なお、ブログへはこの”表紙”からも行けますが、変更はありません。
また、花図鑑は「花写真鑑」としてリニューアルしましたので、多少は見やすくなりましたので、機会がありましたら、見てやって下さい。













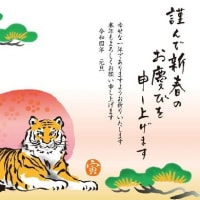






少年の頃は、誰しも、汽車とか電車とか、乗り物に憧れますよね。私も黒い煙を履いて、シュッシュと走る汽車が好きでした。トンネルを抜ける際には、大慌てで窓を閉めたりして。まだ、学生の内でしたね。バスも、ギヤをいちいち入れては、アクセルを踏んでいましたね。その動作にも憧れたものです。今では飛行機が一番好きです、見るのも、乗るのも、飛行機だけはドキドキします。
そうです。
蒸気機関車には特別の憧れと恐れがあったように思います。もう直ぐあのでかい鉄の塊が近ずくのに、線路に耳を付けていれば、見つかればこっぴどく叱られるでしょうから、機関車に敷かれる恐怖も入り混じりながらも、大好きな機関車にならどうなってもよいと言う感覚に陥って、子供心に、ドキドキしたあの興奮は忘れようとも忘れられない大きな出来事でした。この頃からすでに、好奇心は人一倍多かったようです。