ブログのネタ不足を補い、「花写真鑑」を充実させるためにと、再度「超マクロ撮影」シリ-ズを開始したのである。 なお過去に何回もの試行や実験を実施しているが、これは全て「ホームページ」の「ブログ索引」から見る事が出来る。
また、超マクロと私が言うのは、撮影倍率が1.0を越える場合を言うことにしている。
前回のブログでは、このシリーズを始めたきっかけを書いたが、今回は、今後の進め方の土台作りとして、現状把握を再度行って、今後の道筋を立てる資料にしたいと考えたのである。
1. 現状の撮影機材
今回使用した機材は下記である。

① リングストロボ(仮称) (上の写真最上段)
撮影倍率を上げると、少しのカメラブレも大きく影響するし、焦点距離が長くなるし、近接撮影になるから、当然焦点深度が浅くなり、ピントの合う範囲が一層小さくなる。 そこでその焦点深度を深くするために、絞りを最大にするために、シャッタースピードが極めて遅くなる。 それを補いシャッター速度を速めて、カメラブレの抑制のために、レンズ先端に付けるリング状のフラッシュであり、マクロ撮影には欠かせない機材。
② ステップアップ、ステップダウンリング (写真中央上から二段目)
使用するレンズにリングストロボを取り付けるためのサイズ調整リング。
③ ファインダーの拡大鏡 (左端、中央と下段)
私の視力が落ちているからだけではなく、よりシャープな映像とするために、ピントをより精密に合わすために必要なもの。
④ リモコンスイッチ (その右)
カメラの保持が頑丈でない場合は、手でシャッターを押すと、カメラブレを起こすので、遠隔操作をする。 セルフタイマー使用時はなくてはならないもの。 電池が消耗かと思い変えて見たが点灯しない。 故障かもしれず、現状はISO感度を上げて対応中。 昔のレリーズ式が本当は使いやすいのだが・・・・!。
⑤ テレコン (左から三列目の上下)
上が倍率1.4(レンズ側を上にして撮ったもの)、下は倍率2.0(カメラ側を上にして撮っている)。 今回の主役とも言える存在。
⑥ スライドレール (下段右端)
この上にカメラを取り付けて、カメラを前後左右に微調整するもの。 本機はプラスチック製の安物であるために頑丈でなく、またmm単位の移動にしか使えない。この先0.01mm単位の移動が必要になるので、買い増しの必要性が出ることは間違いなしと考える。
⑦ 頑丈な三脚 (写真はなし)
2. 現状レベルでの撮影結果
下は参考のため、現在標準的に使っている、18~300mmのレンズで撮ったもの。(焦点距離44mm)

レンズを180mmマクロレンズにして、最短距離(最大撮影倍率)で撮ったもの(テレコン不使用)。

180mmマクロレンズに、倍率2.0のテレコンを装着したもの。
かなり細部まで見るようになるが、花びらの根元などの詳細はまだよく見えていない。

不思議な形をした多肉植物であるが、昨年11月に購入して鉢植えとしたものから、一人栄えの新芽が出たので、これを別の鉢に植えて室内で育てたら、こんなに立派になったのである。 (標準レンズで撮影 焦点距離100mm)

かなりグロテスクであるが、下はその先端を、180mmマクロレンズに2.0倍のテレコンを付けて撮影した。 この被写体の場合はこれ以上の高倍率は、学者さんの領域と考え私は進まないこととする。
なお、先端についている“おわん”型のものは、蕾でも葉でも実でもなく、種を増やすための活動なのである。 これらが間もなく地面に落ち、次の世代が生まれる、繁殖のための営みである。 この恐ろしいほどの繁殖力をもって、「不死鳥」と言わせたのであった。

早くも鉢の地面に落ちたものから、あたかも“葉差し”をした如く、新しい世代が始まっている。 購入後半年余りで孫の世代が育とうとしている。 げに、恐ろしや!。


直経数ミリの花であるが、下はこれも同じく、180mmマクロレンズに2.0倍テレコン装着して撮ったもの。 花の中心部が詳細に知りたいところであるが、現状ではこれが限界と知る。

こでも同上の方法で撮影したもの。

またピンボケ写真、ピントが甘い写真を載せているとお叱りをうけそうではあるが、たしかに画面奥の方がボケている。 この撮影諸元は、絞りf/25、シャッタースピード1/60、ISO感度1250、35mm版換算の焦点距離270mm、ストロボ発光、露出補正+1.3・・・・・である。
被写体とレンズの距離を変えればもう少しよくする手はあるが、マクロ撮影では、それが極めて難しく、大変な手間を要するのだと、少々泣き言を・・・・。 マクロ撮影では、0.5~1mm前後の位置調整が必要である。前後左右は上記スライダーがあるが、実態はそんな単純なものでなく、立体的な調整はすべて手でやらねばならず、また、そのためには、無理な体勢で撮らねば成らないときもあり、ここにも腰痛が影響して来るので更なる改良を難しくしている。

この現状を踏まえて、次のステップは、どう撮影倍率を上げるかである。 顕微鏡の世界まで踏み込む積もりはないが、取り敢えず、撮影倍率10前後を目指し検討をしているが、長くなるのでひとまずここは閉めて、続きは次回にしたいと思う。
<< つづく >>













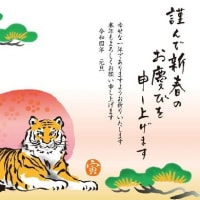






ピンぼけ写真と言ったのが恥ずかしいです。
然しこうした難しい手順・操作を踏み試行錯誤しながら徐々に目標に向かう過程が何より楽しいのでしょう。
苦心して満足した作品を完成した時の喜びは何物にも代えられません。
カメラも持っていない素人でもその満足感は解る気がします。静かに拝見しますので頑張って下さい。
例えば”ピントの合う範囲に被写体を持ってくる”という動作だけでも、超マクロの世界では簡単ではありません。 スライドレールが大切な役割になりますが、今のはX軸とY軸のみの移動でしかありません。 後は手で100%感で動かしますが、これが難しい、簡単ではありません。ならば、Z軸のあるものをつかえば?ということになるでしょうが、そんなものはあったとしても私にはとても買えません。
たきあんさんのストレートパンチは、かなり厳しいですが、それに反論したりはしてますが、私にはありがたい指摘と受け止め、常に念頭に置き、出来るものなら改善してゆきたいと、これはお世辞抜きでそう思っています。 その割には、少しもよくならないではないか!。との声も聞こえてきますが、残念ながら、努力しても出来ないことが多いのが悩みでもあります。
昔は、いろいろと改善アイデアが出てきて、そのすべてをやってみる体力、気力がありましたが、それが最近は極度に細くなってきて、ちょこっとやっては、ごろりと横になる癖が出てきて、困ったもんです。
でも、おっしゃる通り、満足の行ける写真が撮れたときは、大変に嬉しく、苦労もふっとび、A4サイズにして飾ったりしています。 友はそれを、その筋に投稿したらといいますが、残念ながらまだその域には達していません。 トホホ・・・!。