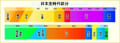最近フランスの小説を読んでるから、この機会にコレットを読もうと思った。フランスの女性作家で、今度キーラ・ナイトレイ主演で「コレット」という映画が公開される。改めて買うんじゃなくて、すでに何冊か持ってるからこの機会に読むかと思った。映画のチラシには「ココ・シャネルに愛され、オードリー・ヘプバーンを見いだした実在の小説家」って書いてある。オイオイいくら何でも「実在」はないだろうと思ったけど、コレットを検索すると「コレットは死ぬことにした」というコミックのことばかり出てくる。今ではフランスの小説家など知られてないんだろうなと思った。
 (シドニー=ガブリエル・コレット)
(シドニー=ガブリエル・コレット)
ホンモノのシドニー=ガブリエル・コレット(Sidonie-Gabrielle Colette、1873~1954)は、作品もすごいけど人生そのものがすごい人だった。晩年にはアカデミー・ゴンクール初の女性会員(にして初の女性総裁)に選ばれ、葬儀は女性として初めて国葬となった。そのときに離婚経験を理由にパリの大司教は協力を拒んだという。生涯に3回結婚し、その間には夫の連れ子と恋愛関係も生じたり、また同性愛者でもあるという自由な恋愛を生きた。生活のためミュージック・ホールの踊り子になったし、自作の舞台化では主役を務めるなど、小説以上に波乱の人生を送った人である。
コレットの父は元軍人で地方暮らしだったが破産して、コレットは20歳の時に14歳年上の男性(父の軍隊時代の友人の息子)と結婚してパリに出た。ジャーナリストだった夫は、妻の学生時代の話を小説化するように勧め、それはシリーズ化され大人気となった。しかしバイ・セクシャルの夫の恋愛関係に疲れて、自分も同性愛の女性のもとに身を寄せ、舞台にたって生活費を稼いだ。こういう風に最初からスキャンダラスな女性作家として売り出したのである。1913年に3歳年下の男性と再婚して男爵夫人となるも、義理の息子と恋愛関係になる。そして1935年に17歳年下の男性と結婚して、これが最後。
こうしてみると、単に恋愛スキャンダルが売りの「女流作家」に思われるかもしれない。昔は確かにそんな風な理解もあったようだが、今読むと先見的な身体性の作風に驚く。本人が自由に生きたように、その小説も物語も描写も時代を突き抜けて自由。まあセックス描写については、どうしても時代の制約を抜けられないが、生き生きとした心理描写が素晴らしい。小説はどうしても「視覚」的な描写が多くなるが、コレットの小説は触覚、嗅覚、聴覚などをフル回転させた「五感の文学」である。
僕が一番面白かったのが「牝猫」(岩波文庫、1933)で、現在品切れ中だが活字を大きくして再刊して欲しい。青年アランと新妻カミーユは仲良く暮らし始めるが、アランは実家に残してきた愛猫サアが忘れられない。実家に行くと寂しそうにしているので連れてゆくが、カミーユとサアは微妙な関係に…。多分書かれた当時は何だろうなという変な話に思われただろうが、今になると実によく判る先見的な物語。パリの風景や母親の心理も面白い。アランはいつも「サア、サア」って気にしていて、お前は福原愛かと突っ込みたくなる。新妻より猫が大事な男を1930年代に書いてたコレットはすごい。物語はどうなるのかと思ってたら、ラスト近くであっと驚く展開になった。(2019.5重版)

最高傑作とよく言われるのが、「シェリ」(1920)で、評判になって続編「シェリの最後」(1926)も書かれた。どっちも岩波文庫に収録されている。レアはフランス文学によく出てくる「高級娼婦」で有力者の愛人として生きてきて、経済感覚もあって豊かに暮らしている。友人が若い頃に産んだ息子シェリと関わるうちに彼はレアに惹かれてしまう。こうして10代後半からシェリは年上のレアと暮らして、男として磨かれていった。そして同じく仲間うちの美しい年下の娘と結婚することになる。キレイに別れるつもりの二人だったが…。という風に年上の女と若い男の関係が事細かに描かれる。実際にそういう関係を経験したコレットだけど、それは「シェリ」を書いた後で起こったことだそうだ。年増女の魅力と容色の衰えを心憎いほどに描きだしている。まさに五感の文学で傑作だと思う。

「シェリの最後」は無理矢理終わらせる感じの続編だけど、第一次大戦に従軍したシェリの変貌、そしてその間看護婦として社会体験を積んだ妻の自立などコレットの実際の体験も交えて描く。そしてシェリは悲劇の泥沼にはまり込んでゆく。日本でよく読まれたのは「青い麦」(1922)で、ウィキペディアを見ると11もの翻訳がある。今入手簡単なのは光文社古典新訳文庫で、ここには鹿島茂の傑作解説が付いている。高級娼婦レアと違い、今度は中間層の若い二人が夏のバカンスを同じ別荘で暮らす。パリの商工業者二人ががブルターニュの別荘を毎年借りているという設定。
一体フランスの有名小説(19世紀)は、大体「年上の人妻の姦通小説」だと鹿島茂が書いている。「赤と黒」も「ボヴァリー夫人」もバルザックやモーパッサンのたくさんの小説も。言われてみればその通りで、それには理由がある(鹿島茂解説に詳しい。)一方、20世紀になり、ようやく第三共和政の教育改革で「同じ階級の若者同士の恋愛」が可能になった。「青い麦」で16歳と15歳の若い二人が惹かれ合うが、しかしこの小説でもそこに「年上の女」が登場する。海辺の大自然の中で展開される幼い恋と年増女。僕はこの小説だけは若い頃に旺文社文庫で読んだ。興味本位で読んだんだけど、はっきり言ってしまえば三島由紀夫「潮騒」の方が興奮した。「青い麦」は心理描写が中心だから、五感文学のまだるっこしい描写が若い頃にはうっとうしい。今読む方が面白い。やはりすごい作家だなと思った。
 (シドニー=ガブリエル・コレット)
(シドニー=ガブリエル・コレット)ホンモノのシドニー=ガブリエル・コレット(Sidonie-Gabrielle Colette、1873~1954)は、作品もすごいけど人生そのものがすごい人だった。晩年にはアカデミー・ゴンクール初の女性会員(にして初の女性総裁)に選ばれ、葬儀は女性として初めて国葬となった。そのときに離婚経験を理由にパリの大司教は協力を拒んだという。生涯に3回結婚し、その間には夫の連れ子と恋愛関係も生じたり、また同性愛者でもあるという自由な恋愛を生きた。生活のためミュージック・ホールの踊り子になったし、自作の舞台化では主役を務めるなど、小説以上に波乱の人生を送った人である。
コレットの父は元軍人で地方暮らしだったが破産して、コレットは20歳の時に14歳年上の男性(父の軍隊時代の友人の息子)と結婚してパリに出た。ジャーナリストだった夫は、妻の学生時代の話を小説化するように勧め、それはシリーズ化され大人気となった。しかしバイ・セクシャルの夫の恋愛関係に疲れて、自分も同性愛の女性のもとに身を寄せ、舞台にたって生活費を稼いだ。こういう風に最初からスキャンダラスな女性作家として売り出したのである。1913年に3歳年下の男性と再婚して男爵夫人となるも、義理の息子と恋愛関係になる。そして1935年に17歳年下の男性と結婚して、これが最後。
こうしてみると、単に恋愛スキャンダルが売りの「女流作家」に思われるかもしれない。昔は確かにそんな風な理解もあったようだが、今読むと先見的な身体性の作風に驚く。本人が自由に生きたように、その小説も物語も描写も時代を突き抜けて自由。まあセックス描写については、どうしても時代の制約を抜けられないが、生き生きとした心理描写が素晴らしい。小説はどうしても「視覚」的な描写が多くなるが、コレットの小説は触覚、嗅覚、聴覚などをフル回転させた「五感の文学」である。
僕が一番面白かったのが「牝猫」(岩波文庫、1933)で、現在品切れ中だが活字を大きくして再刊して欲しい。青年アランと新妻カミーユは仲良く暮らし始めるが、アランは実家に残してきた愛猫サアが忘れられない。実家に行くと寂しそうにしているので連れてゆくが、カミーユとサアは微妙な関係に…。多分書かれた当時は何だろうなという変な話に思われただろうが、今になると実によく判る先見的な物語。パリの風景や母親の心理も面白い。アランはいつも「サア、サア」って気にしていて、お前は福原愛かと突っ込みたくなる。新妻より猫が大事な男を1930年代に書いてたコレットはすごい。物語はどうなるのかと思ってたら、ラスト近くであっと驚く展開になった。(2019.5重版)

最高傑作とよく言われるのが、「シェリ」(1920)で、評判になって続編「シェリの最後」(1926)も書かれた。どっちも岩波文庫に収録されている。レアはフランス文学によく出てくる「高級娼婦」で有力者の愛人として生きてきて、経済感覚もあって豊かに暮らしている。友人が若い頃に産んだ息子シェリと関わるうちに彼はレアに惹かれてしまう。こうして10代後半からシェリは年上のレアと暮らして、男として磨かれていった。そして同じく仲間うちの美しい年下の娘と結婚することになる。キレイに別れるつもりの二人だったが…。という風に年上の女と若い男の関係が事細かに描かれる。実際にそういう関係を経験したコレットだけど、それは「シェリ」を書いた後で起こったことだそうだ。年増女の魅力と容色の衰えを心憎いほどに描きだしている。まさに五感の文学で傑作だと思う。

「シェリの最後」は無理矢理終わらせる感じの続編だけど、第一次大戦に従軍したシェリの変貌、そしてその間看護婦として社会体験を積んだ妻の自立などコレットの実際の体験も交えて描く。そしてシェリは悲劇の泥沼にはまり込んでゆく。日本でよく読まれたのは「青い麦」(1922)で、ウィキペディアを見ると11もの翻訳がある。今入手簡単なのは光文社古典新訳文庫で、ここには鹿島茂の傑作解説が付いている。高級娼婦レアと違い、今度は中間層の若い二人が夏のバカンスを同じ別荘で暮らす。パリの商工業者二人ががブルターニュの別荘を毎年借りているという設定。
一体フランスの有名小説(19世紀)は、大体「年上の人妻の姦通小説」だと鹿島茂が書いている。「赤と黒」も「ボヴァリー夫人」もバルザックやモーパッサンのたくさんの小説も。言われてみればその通りで、それには理由がある(鹿島茂解説に詳しい。)一方、20世紀になり、ようやく第三共和政の教育改革で「同じ階級の若者同士の恋愛」が可能になった。「青い麦」で16歳と15歳の若い二人が惹かれ合うが、しかしこの小説でもそこに「年上の女」が登場する。海辺の大自然の中で展開される幼い恋と年増女。僕はこの小説だけは若い頃に旺文社文庫で読んだ。興味本位で読んだんだけど、はっきり言ってしまえば三島由紀夫「潮騒」の方が興奮した。「青い麦」は心理描写が中心だから、五感文学のまだるっこしい描写が若い頃にはうっとうしい。今読む方が面白い。やはりすごい作家だなと思った。