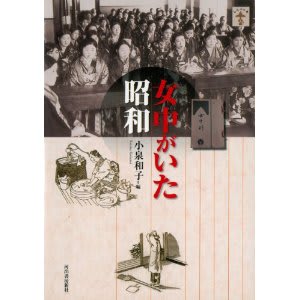 偉大なるオペラ作曲家、ジャコモ・プッチーニと聞いてもすぐにわからない方もいるだろう。しかし、映画『眺めのいい部屋』でも素晴らしく効果的に使用されていたのもプッチーニの「わたしのお父さん」だったように、有名なアリアは映画やCMに頻繁に登場するから、旋律にはなじみを覚える方も多いと思う。プッチーニほど、時代をこえて愛されるオペラをつくった作曲家はいないのではないだろうか。
偉大なるオペラ作曲家、ジャコモ・プッチーニと聞いてもすぐにわからない方もいるだろう。しかし、映画『眺めのいい部屋』でも素晴らしく効果的に使用されていたのもプッチーニの「わたしのお父さん」だったように、有名なアリアは映画やCMに頻繁に登場するから、旋律にはなじみを覚える方も多いと思う。プッチーニほど、時代をこえて愛されるオペラをつくった作曲家はいないのではないだろうか。さて、そのプッチーニだが、情熱は芸術分野だけでなく、妻以外の女性たちにも向けられて、新しい女ごとに情事をはずみに次々と傑作をうんだ。そんな中、プッチーニ家に雇われたメイドのドーリアが、嫉妬にかられた妻に今度のお相手として疑われて、厳しく追求されて追い詰められた果てに服毒自殺をするという事件が起こった。1909年当時、大スキャンダルとなった「ドーリア・マンフレード事件」をセンスよく描いたのが、『プッチーニの愛人』である。離れの家に監禁されたようなドーリアに、この頃のメイドは雇用主の所有物なのか、と社会におかれた彼女たちの立場がよくわかる。
ところで、プッチーニ家は成功した作家として大きな館を構えて複数の使用人をつかっていたが、戦前の日本の中流以上の家にも、メイドならぬ女中をおいたのが一般的だったそうだ。本書は、女中の成り手が多かった大正初期から女中が消えていく1960年頃までのリサーチから、今では差別用語として使用されていない”女中”を通して、昭和の一面が書かれている。先日、ほぼ同世代の女性に今読んでいる本ということでタイトルを伝えたら、「えっ、いやだ~・・・」と微笑されて終了・・・。
そ、そんな反応をしなくても、、、と思うのだが、女中に何か誤解を招く部分はあるのだろうか。その昔、石川達三が「幸福の限界」で”妻とは性生活の伴う女中”という今だったらユニークな名言を残してくれたが、そもそも”女中”という言葉に、人それぞれ微妙なニュアンスのイメージをもっているのかもしれないが、女中は、かっては40万~100万人程度までいて、戦前までの女工に並ぶ女性の二大職業のひとつであり身近な存在だったのだ。我家の平凡なる家族史をたどっても、確かにお嫁に行く前の花嫁修業として所謂”奉公”をしていたおばあさんもいる。本書は、半分以上の女性が大学に進学をする時代にあって関心をひかれるようなテーマではないかもしれないが、写真、資料、統計が豊富で眺めているだけでも楽しいのだが、実は社会学の講義を聞いているようなアカデミックな内容である。
かっての、家長制度のひとつの企業のような経営単位から核家族化への移行に伴い、生産から切り離された女性は経済的に夫に依存するようになり、主婦という言葉が登場するようになった。兎に角、昔の女性の家事は大変だった。私だってルンバが欲しい!と思っているが、炊事、洗濯、掃除、育児だけでなく、雨戸の開け閉め、洗い張り、半襟のつけかえ、お風呂をわかし、衣替え、蚊帳や雨具、夜具の手いれ、接客、毎日のルーティンワークから、季節、年ごとの仕事や行事が入り、高度な技術も求められたのが、この時代の家事だった。確かにひとりですべてをこなすのは厳しいことから、そこそこの家庭でも女中の需要はあったのだ。一方で、都会に憧れたり、口減らしなどで働きたい女性は大勢いた。多くの女中として働く女性対象の「女中訓」も出版され、守秘義務だけでなく、寸暇もおしんでしっかり働き、気働きまで求められ、よい女中はよい嫁にも通じるところが、結婚を控えた女性としても人気職種だったのだろう。
しかし、ご用心!誠実なご主人だったらよいけれど、プッチーニ家のスキャンダルのように、低い人権のもとに主人や若様にセクハラを受ける悲劇も珍しくなかった。第4章「女中と性」では、この時代におかれた女中の理不尽な立場まで、資料からほりおこしてしている。
プライバシーもないような日本的家屋の中での雇用関係で、家族ではない存在の女性。本書に掲載されている女中部屋の写真や間取り図は、彼女たちのおかれた立場を象徴しているようだ。編者の小泉和子さんは「昭和のくらし博物館」の館長だそうだが、隆盛期から女中が消えていくまでとてもよくまとまっている1冊だと思う。女性の生活史としても価値のある本である。









